以上、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」という前提のもとで、「地球の温度を低下させるしくみ」として考えられる、次の3つを説明した。
1.100%真空が実在していないので、物体の周囲の空気(分子)の熱伝導&対流によって、エネルギーが持ち去られ続けている。
2. 太陽から供給されるエネルギーの一部が、光合成や太陽光発電によって蓄えられる化学エネルギー、雲や風や海流として蓄えられる運動エネルギーや重力ポテンシャルエネルギーに変換される。
3.ある(外部)運動エネルギーと負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、その運動エネルギーを減少させるような仕事)のペアとして、互いに消滅してしまう。
これらによって、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」という前提のもとで、「地球の温度が上がり続けないこと」「放射冷却と呼ばれた現象」「黒体放射」について説明できるだけではない。
「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、「光合成、太陽光発電…」によって、あるいは、「雲、風海流」としてエネルギーを蓄え、“運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアが消滅するしくみ”として活用されうる(消費されうる)」からこそ、このダイナミックで多様な自然(nature)の運動が成立していることを説明できるのである。
このことは、単に、「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、すべて地球からの放射によって持ち去られ続けている」と考えるだけでは、説明できないのである。
※左側のバランスは、「熱放射がエネルギーを持ち去る」という前提で成立するものである。
これまで、多くの場所でこのように説明されてきた。 しかし、この左側のバランスでは、現実にある、ダイナミックで多様な自然(nature)の運動が成立していることや「石油や石炭などの化石燃料が存在すること」を説明できない。
右側のバランスは、「熱放射がエネルギーを持ち去らない」という前提で成立するものである。
この右側のバランスは、現実にある、ダイナミックで多様な自然(nature)の運動が成立していることや「石油や石炭などの化石燃料が存在すること」を説明できる。
|
|
なぜ、これまで、「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、すべて地球からの放射によって持ち去られ続けている」と、シンプルに説明され続けて来たのか?
それは、おそらく、(熱放射を含む)「エネルギー保存則」に他ならないと思われる。
すなわち、(証明されていない)経験則に過ぎなかった「エネルギー保存則」を守るために、作り上げられた説明が、「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、すべて地球からの放射によって持ち去られ続けている」というシンプルな説明だったのだと思われる。
このシンプルな説明は、(ダイナミックで多様な運動を持っている)豊かな自然(nature)から乖離しているように思われる。
ここにあるのは、『「エネルギー保存則」の呪縛』と呼べるものかもしれない。
※あのアインシュタインも、この『「エネルギー保存則」の呪縛』のせいで、(特に一般相対性理論において)矛盾(板挟み、行き詰まり…)に至ってしまったと言えるだろう。
※『
ヘリウムの方が重いので、星はつぶれようとするが、
水素の燃えかたをよくすることによって温度を上昇させ、より大きい圧力を発生させて、つぶれるのを防いでいる。』という苦し紛れの説明がこれまで見過ごされてきたことも、この『「エネルギー保存則」の呪縛』のせいだと言えるだろう。
※そもそも、量子物理学(→結果4)に登場する「ある短時間なら
エネルギー保存則を破って仮想粒子が生じることができる」という説明は、この『「エネルギー保存則」の呪縛』に対して風穴を開けているものの1つ(見直しを迫っているものの1つ)であると見なせるように思われる。
もう、そろそろ、『光子を含めて「エネルギー保存則」が成立しているはずだ』『「エネルギー保存則」に異を唱えることは、即、間違い(非科学)であることを意味している』『時空はどこまでも連続である』のような、これまでの物理学の常識(思い込み、ロックイン)から脱する必要があるのではないでしょうか── ということを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、示しているように思われる。
《光の反射と屈折》
◎ 光子の進行中に、鏡に遭遇すると、なんらかのしくみで原始ヒッグス場ユニットの方向がクルッと変化し、(入射角=反射角となるような)新たに共転回する相手を獲得して、その方向に進むのだろうか? 鏡の中の何か(原子核?)と衝突することによって(運動量保存則に基づいて)反射するのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
→光子の進行中に、鏡に遭遇すると、なんらかのしくみで原始ヒッグス場ユニットの方向がクルッと変化し、(入射角=反射角となるような)新たに共転回する相手を獲得して、その方向に進むのだろうと思われる。(鏡の中の何かと衝突することによって(運動量保存則に基づいて)反射するとは考えにくい。もしそうだとすると衝突することによって、光子の振動数が減り、色が変わるはずだからである) 詳細な検討は、今後の課題である。
結果4
《電子の定常状態と電子軌道》
◎大改訂
一方で、陽子に束縛された電子は、定常状態と言えど、円軌道や楕円軌道をとっている以上、“加速”や“減速”をしているはずである。
それなのに光子が放出されないのは、「電子の運動エネルギー順位Knが変化しない限り、光子を放出しない」からである。
例えば、電子軌道の「3s軌道、3p軌道、3d軌道」は、いずれも、電子の運動エネルギー順位K3の所産であり続けるので、(たとえ円軌道や楕円軌道をとっていても)いずれも、光子を放出しないことになる。
この「電子の運動エネルギー順位Knが変化しない限り、光子を放出しない」ことを考慮に入れることによって、“電子軌道”がどのように成立しているがわかる。
それを以下に示す。
◎ そして、エネルギー保存則は、経験則であるのに関わらず、これまで、物理学の根幹を成す、普遍的&絶対的な法則として君臨してきた。
→そして、エネルギー保存則は、証明されたわけではなく、経験則であるのに関わらず、これまで、物理学の根幹を成す、普遍的&絶対的な法則として君臨してきた。
◎追加
※なお、“熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去る”という前提よりも、“熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない”という前提の方が、シュテファン=ボルツマンの法則(『ある温度Tを持つ黒体は、熱輻射(=熱放射)として、I =ρT 4 [W/m2]のエネルギーを放出する』)と、よく調和している。 (参考『シュテファン=ボルツマンの法則』Wikipedia)
|
シュテファン=ボルツマンの法則が示す、式『I =ρT 4 [W/m2]』は、黒体から、1秒間に、1平方メートルあたり、熱放射(∈光子)として、放出されるエネルギーに相当する。([W]=[J/s])
“熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない”のであれば、この式の理解は容易である。 1秒
後であっても、2秒後であっても、温度が一定である限り、同じ熱放射(∈光子)は、エネルギーが放出され続けることになる。 もし、(伝導や対流によって)一切温度が変化しなければ、経過時間に比例した分だけ、熱放射(∈光子)のエネルギーが放出され続けることになる。
しかし、逆に、本当に“熱放射(∈光子)が、エネルギーを持ち去る”のならば、この式の意味の理解は、とたんに困難になる。
なぜなら、例えば、「0.1秒経過すると、熱放射(∈光子)によって、エネルギーが持ち去られる結果、温度が下がる。 0.2秒経過すると、先の0.1秒間の温度の低下に伴って、より小さなエネルギーだけが持ち去られて、より小さな温度だけ下がる。 0.3秒経過すると、先の0.2秒間の温度の低下に伴って、さらに小さなエネルギーだけが持ち去られて、より小さな温度だけ下がる。…」というように、熱放射(∈光子)によるエネルギーの持ち去りによって温度が下がることに伴い、時間経過とともに「熱放射(∈光子)のエネルギーの放出量」が減少し、1秒間に放出されるエネルギーである、『I =ρT 4 [W/m2]』が、何を意味しているのかわかならくなってしまうからである。
つまり、本当に“熱放射(∈光子)が、エネルギーを持ち去る”のならば── 一定の温度T[K]のまま、1秒が経過することは、不可能であるので、『I =ρT 4 [W/m2]』という数式が、意味不明なものになってしまうのである。
すなわち、“熱放射(∈光子)が、エネルギーを持ち去る”のならば、ある温度Tにおける、「熱放射(∈光子)のエネルギーの放出量」を、[W]=[J/s]を含む単位によって定義することは、無理のあることなのである。
“1秒間における&ある温度Tにおける”熱放射のエネルギー量が、『I =ρT 4 [W/m2]』であるということは、ありえないのである。
つまり、“熱放射(∈光子)が、エネルギーを持ち去る”という前提は、『I =ρT 4 [W/m2]』の式が、本当のところは、何を意味しているのかの理解を、とても困難にしてしまうのである。
|
◎さらには、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分やおよび、“自然な世界観(3Steps原理)”が、反証されたことを意味する
→さらには、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分や“自然な世界観(3Steps原理)”が、反証されたことを意味する
◎“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分やおよび、“自然な世界観(3Steps原理)”が、反証されなかったことを意味する。
→“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分や“自然な世界観(3Steps原理)”が、反証されなかったことを意味する。
◎この実験に対する動機付けが生まれるのである。
→この実験に対する動機付けを生むのである。
◎ 「熱放射(光子の総和)や重力波(重力子の総和)がエネルギーを持ち去らないこと」という予測──。
→ 「熱放射(光子の総和)や重力波(重力子の総和)がエネルギーを持ち去らない」という予測──。
◎大きな見直しがせまられることを意味する。
→大きな見直しをせまられることを意味する。
◎ところどころ見直しがせまられることを意味する
→ところどころ見直しをせまられることを意味する
2017年7月30日 2.14→2.14.1
◎上部リンク削除
《重力場の線形性について(詳細版)》
◎ 抽象的な数式のみならず、その解釈、すなわち、幾何的な構造を持つ実体像も重視する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、
→抽象的な数式のみならず、その解釈、すなわち、
具体的な幾何的実体像
(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)も重視する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、
◎ この結論は、“抽象的な数式”
のみを重視している限り、絶対にたどり着けない結論と言えるかもしれない。
なぜなら、『「E=mc
2が成り立つ」
ゆえに「あらゆるエネルギーは質量を持つ」
、そして「重力場は、エネルギーである」
ことにより、「重力場は、質量である」』という論理展開自体は、100%正し
いからである。
→ この結論は、“抽象的な数式”
の解釈を軽視している限り、絶対にたどり着けない結論と言えるかもしれない。
なぜなら、『「あらゆるエネルギーは質量を持つ」
→「重力場は、エネルギーである」
→「重力場は、質量である」』という論理
の流れ自体は、100%正し
くて非の打ち所がないからである。
◎ すなわち、
“抽象的な数式”の解釈を表面的に行う(軽視する)限り、(論理展開自体は100%正しいので)こういった考えの中にひそむ間違い(自然(nature)からの乖離)に気づくことはできないのだ。
→ すなわち、
「E=mc2」から導く「あらゆるエネルギーは質量を持つ」という解釈の部分を軽視している限り、(
その後の論理展開自体は100%正しいので)
「重力場は、質量である」という考えの中にひそむ間違い(自然(nature)からの乖離)に気づくことはできないのだ。
◎ しかし、「E=mc
2」という数式の持つ本当の意味、すなわち、その数式が意味する
幾何的な実体像を重視
してはじめて── 「あらゆるエネルギーは
、質量を持つ」「重力場がエネルギーを持つ
のは確かだから
、重力場も質量を持つ」「
“重力場のエネルギー”そのものを“質量”と見なし、新たな“時空の曲がり”の原因として方程式に代入するべきである」
という説明
が、自然(nature)から乖離していること
)に気づくことができる
のだ。
つまり、この“自然(nature)か乖離した説明”が存続するようになってしまったのは、抽象的な数式の解釈、すなわち、具体的な幾何的な実体像を軽視したからに他ならないのである。
→ しかし、「E=mc
2」という数式が持つ本当の意味、すなわち、その数式が意味する
具体的な幾何的実体像
(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)を重視すれば、「あらゆるエネルギーは質量を持つ」「重力場がエネルギーを持つので重力場も質量を持つ」「
“重力場のエネルギー”そのものを“質量”と見なし、新たな“時空の曲がり”の原因として方程式に代入するべきである」──いずれの説明も、自然(nature)から乖離していることに
明確に気づくことができる。
◎ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、
「重力場のエネルギーそのものが、(“物体(質量)”という大元の重力子の放出源のように)新たに重力子を放出する源として働き続ける能力を持つ(=新たに質量を持つ)」という意味での非線形性は、実在しないと、はっきり断言できる。 なぜなら、「重力場のエネルギー(=「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の通過点として蓄えられるものの総和)と 質量(=「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力)が、全く別物である」ことは明白だからである。
→ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、
「重力場のエネルギーそのものが(“物体(質量)”という大元の重力子の放出源のように)新たに重力子を放出する源として働き続ける能力を持つ(=新たに質量を持つ)」という意味での非線形性は実在しない、そうはっきり断言できる。 なぜなら、『重力場のエネルギーと質量が全く別物であること』(=『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の通過点として蓄えられるエネルギーの総和と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力が全く別物であること』)は明白だからである。
◎ ※「重力場が、新たな質量になる」「“物体(質量)
から生まれたにすぎない重力場”が新たな質量になり、
そこから、新たな重力場が生まれる」という── 非線形的なアイディアは、他ならぬ、アインシュタインの心の中から始まった。
→
※「重力場が、新たな質量になる」「“物体(質量)
が生んだ重力場”が新たな質量になり、
その新たな質量から、さらに新たな重力場が生まれる」という
と重力場の非線形
性」のアイディアは、他ならぬ、アインシュタインの心の中から始まった。
◎ その理由
の1つは、“E=mc
2”という抽象的な数式
について、「
あらゆるエネルギーは
、質量を持つ」という自然(nature)から乖離した解釈を、アインシュタインが導いた
からである。
→ その
根本理由は、“E=mc
2”という抽象的な数式
から、「エネルギーは質量を持つ」という自然(nature)から乖離した解釈を、アインシュタインが導いた
ことである。
◎「
あらゆるエネルギーは、質量を持つ」
ことを前提とすれば、「(エネルギーを持つ)重力場が、新たな質量になるのだ」という考えが、自然(nature)から乖離していることに気づくこと
はできないのは当然である。
→「エネルギーは質量を持つ」を前提とすれば、「(エネルギーを持つ)重力場が、新たな質量になるのだ」という考えが、自然(nature)から乖離していることに気づくこと
ができなくなるのは当然である。
◎
ミクロの自然(nature)についての、幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)を軽視している限り、このことに気づくことができないのである。
→
ミクロの自然(nature)についての具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)を軽視している限り、この乖離に気づくことができないのである。
◎ つまり、
この抽象的な数式(
この場合は“E=mc
2”)は、慎重に扱わないと、人を裏切りうるのである。
→
(つまり、抽象的な数式(
例えば、“E=mc
2”)は、慎重に扱わないと、人を裏切りうるのである。
(→考察2))
◎
E=mc2は、本来、決して「あらゆるエネルギーが、質量を持っていること」を示す式ではありえないのだ。
→ E=mc2は、本来、決して「あらゆるエネルギーが質量を持っていること」を示す式ではありえないのだ。
◎ 実際は、質量とエネルギーは、厳密には、100%等価ではないのだ。
→
実際は、質量とエネルギーは、100%等価ではないのだ。
◎ その理由
は、少なくとも、次の3つ挙げられる。
→ その理由
を整理すると、次のようになる。
◎
|
1.質量とは、「重力子の放出源として働き続ける能力」であり、 質量エネルギーE=mc2とは、運動エネルギー(内部&外部)に他ならない。
2.光子は、「エネルギーを持つけれども、質量を持たない」。 だからこそ、光速で進める。
つまり、「あらゆるエネルギーが、質量を持っている」という解釈や前提は、アインシュタイン自身が提唱した、光量子仮説の式E=hνと矛盾してしまっている。
3.電磁波のエネルギー(光子の総和のエネルギー)のみならず、“電荷エネルギー”、“磁極エネルギー”、電磁場のエネルギー(仮想光子の総和のエネルギー)、重力子&重力場のエネルギーも、それら自体は、“重力子の放出源”ではなく、質量を持っていない。
(Etotal =mc2 + aQc2 + bm1c2 +α」と表記できることは、すでに示した)
|
→
|
1.質量とは、「重力子の放出源として働き続ける能力」であり、 質量エネルギーE=mc2とは、「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」、すなわち、運動エネルギー(内部&外部)に他ならない。
つまり、質量と等価なのは、「エネルギー」ではなく、「運動エネルギー(内部&外部)」なのである。
2.エネルギーには、質量エネルギー(=運動エネルギー(内部&外部))の他に、少なくとも、電荷のエネルギー、磁極のエネルギー、光子のエネルギー、重力子のエネルギー、電磁波のエネルギー、重力波のエネルギー、電磁場のエネルギー、重力場のエネルギーがある。
これらの質量エネルギー(=運動エネルギー(内部&外部))以外のエネルギーは、いずれも“重力子の放出源として働き続ける能力”、すなわち、質量を持っていない。
3.エネルギーを持っている「光子や重力子、電磁波や重力波」は、光速で移動できるという意味においても、質量を持っていない。
したがって、「エネルギーが質量を持っている」という解釈や前提は、例えば、アインシュタイン自身が提唱した、光量子仮説の式E=hνとも矛盾してしまっているのである。
|
◎つまり、幾何的な実体像を重視する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「あらゆるエネルギーが、質量を持っている」という解釈は、自然(nature)と乖離していることが、はっきりわかるのである。
→ このように、具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)を重視する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「あらゆるエネルギーが質量を持っている」という解釈は、自然(nature)から乖離していることが、はっきりわかるのである。
◎ ※そういう意味で、mc2=E、あるいは、Em=mc2 が、誤解釈、誤用、濫用… を予防する表記と言えるのかも知れない。
→ ※そういう意味で、mc2=E、あるいは、Em=mc2 が、「誤解釈、誤用、濫用…」を予防する表記と言えるのかも知れない。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎ ※なお、例えば、光子によって対生成した電子や陽電子のペアは、質量を持つので、光子のエネルギーが“質量に変換される”ということはありうる。
→ ※なお、例えば、光子によって、電子や陽電子のペアが対生成したり、原子が(外部)運動エネルギーを獲得して熱を持ったりする過程は、新たな質量の生成を意味するので、光子のエネルギーが“質量に変換される”ということはありうる。
◎ また、ある物体が、重力ポテンシャルエネルギー(重力場のエネルギー)を利用して、運動エネルギーを獲得した場合も、ここにあるのは、“質量への変換”の例だと言える。
(質量エネルギーとは、静止質量エネルギーと運動エネルギーの和である)
→ また、例えば、ある物体が、重力ポテンシャルエネルギー(重力場のエネルギー)を利用して、(外部)運動エネルギーを獲得した場合も、新たな質量の生成を意味するので、重力場のエネルギーが“質量に変換される”ということもありうる。
(質量エネルギーとは、静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの和であった)
◎追加 ただし、光子や重力場は決して質量(重力子の放出源として働き続ける能力)を持っておらず、あくまで新たに獲得された(外部)運動エネルギーが質量(重力子の放出源として働き続ける能力)を持っているのである。
◎以下該当部分 運動エネルギー→(外部)運動エネルギー
◎ ※なお、“グルーオンの集積したひも”を構成するプレオン∴(→結果2)の運動エネルギーも、質量をもつ。
→ ※なお、“グルーオンの集積したひも”が、そのまま形を保ちながら運動できることを前提とするからこそ、“グルーオンの集積したひも”を構成するプレオン∴(→結果2)が、(外部)運動エネルギー、すなわち、質量を持つと考えられる。 もし、“グルーオンの集積したひも”はそのまま形を保ちながら運動できないのならば、クォークの運動エネルギー(内部&外部)のみが質量を担うと考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎ この「物質が存在しないときの重力場の方程式」は、下の一番左の図のものに相当すると考えられる。
→ この「物質が存在しないときの重力場の方程式」は、下の一番左の図のものに相当すると見なすことができる。
◎テーブル ※一番左の図が、「物質が存在しないときの重力場の方程式」に相当し、「1個の仮想的な質点によって、そのまわりにつくられた重力場」である。
→※一番左の図は、「物質が存在しないときの重力場の方程式」、すなわち、「1個の仮想的な質点によって、そのまわりにつくられた重力場」に相当すると見なすことができる。
◎テーブル ※右側の2つは、物質が存在するときの重力場を表している。
その、仮想質点と物質の“重力子の放出源として働き続ける能力”が全く等しいのなら、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、3つとも、全く等しくなる。
→ それに対して、右側の2つは、物質が存在するときの重力場を表していると見なすことができる。
仮想質点と物質の“重力子の放出源として働き続ける能力”が全く等しいので、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、3つとも、全く等しくなっているのだった。
◎
※一番左が、「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場、すなわち、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当し、
右側の2つは、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場、すなわち、物質が存在するときの重力場を表していると考えることができる。
その、仮想質点と物質の“重力子の放出源として働く能力”が全く等しいのなら、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、3つとも、全く等しくなる。
|
|
→
※一番左が、「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場、すなわち、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当していて、
右側の2つは、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場、すなわち、物質が存在するときの重力場に相当していると見なすことができる。
やはり、仮想質点と物質の“重力子の放出源として働く能力”が全く等しいので、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、3つとも全く等しくなっている。
|
|
◎それは、アインシュタイン方程式の原形(53)の左辺は、『「重力場のエネルギー成分tσμ」+「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場(時空の曲り)から、「重力場のエネルギー成分tσμ」がつくる重力場(時空の曲り)を引いたものであるということ── すなわち、アインシュタイン方程式の原形(53)の左辺は、単に、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場(時空の曲り)を表記する式に、相当することを意味するのである。
→それは、アインシュタイン方程式の原形(53)の左辺は、『「重力場のエネルギー成分tσμ」+「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場から、「重力場のエネルギー成分tσμ」がつくる重力場(時空の曲り)を引いたものであるということ── すなわち、アインシュタイン方程式の原形(53)の左辺は、単に、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場を表記する式に、相当することを意味するのである。
◎
(gσβΓαβμ),α =−κ[(tσμ+Tσμ)−δσμ(t+T)/2]
|
(52)
|
| (−g)1/2=1 |
『「重力場のエネルギー成分tσμ」+「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場(時空の曲り)
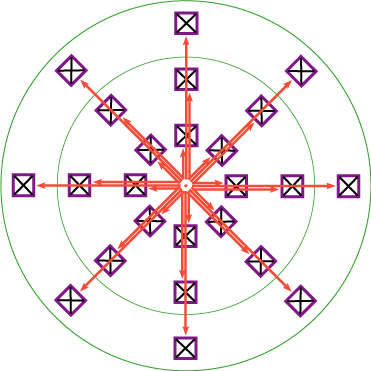 |
+ |
 |
|
− |
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
「重力場のエネルギー成分tσμ」がつくる重力場(時空の曲り)
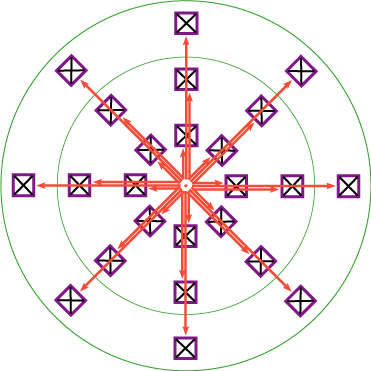
|
|
|
| = |
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場(時空の曲り)
|

|
→
(gσβΓαβμ),α =−κ[(tσμ+Tσμ)−δσμ(t+T)/2]
|
(52)
|
| (−g)1/2=1 |
『「重力場のエネルギー成分tσμ」+「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場
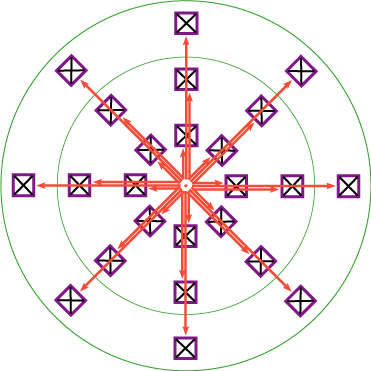 |
+ |
 |
|
− |
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
「重力場のエネルギー成分tσμ」がつくる重力場
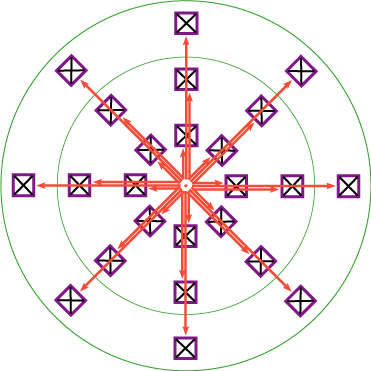
|
|
|
| = |
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場
|

|
◎中央の余計なテーブルを消去
物質が存在しない所での重力場の方程式
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =0
|
(47)
|
| (−g)1/2=1 |
や
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
が、意味するもの
|
|
物質が存在する所での重力場の方程式
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ)−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
が意味するもの
|
|
|
|
|
※左が、「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場、すなわち、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当し、
右は、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場、すなわち、物質が存在するときの重力場を表している。
|
|
|
→
物質が存在しない所での重力場の方程式
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =0
|
(47)
|
| (−g)1/2=1 |
や
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
が、意味するもの
|
物質が存在する所での重力場の方程式
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ)−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
が意味するもの
|
|
|
|
※左が、「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場、すなわち、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当し、
右は、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場、すなわち、物質が存在するときの重力場を表している。
|
|
|
◎ すると、 「この仮想質点の、重力子の放出源として働き続ける能力」=「太陽系のすべての天体の総和の、重力子の放出源として働き続ける能力」に等しいものと定義されることになる。
(ここに、(重力子の通過点である)重力場が持っているエネルギーが、「重力子の放出源として働き続ける能力」、すなわち、質量になるという考えが入り込む余地はどこにもない)
→ すると、 「この仮想質点の、重力子の放出源として働き続ける能力」=「太陽系のすべての天体の総和の、重力子の放出源として働き続ける能力」と定義されることになる。
(ここに、(重力子の通過点である)重力場が持っているエネルギーが、「重力子の放出源として働き続ける能力」、すなわち、質量になるという考えがどこにも入り込んでいない)
◎ ※だからこそ、 アインシュタイン方程式の右辺−kTμνの成分の近似値≒−(NM/π2n)×(1/r2)(≒−(NM/4πn)×(1/r2))は、この緑の部分であることを示すための項、(1/nr2)を含んでいると理解できることがわかる。
→ ※だからこそ、 アインシュタイン方程式の右辺−kTμνの成分の近似値≒−(NM/π2n)×(1/r2)(≒−(NM/4πn)×(1/r2))は、この緑の部分であることを示すための項、(1/nr2)を含んでいることがわかる。
◎ すなわち、一般相対性理論(アインシュタイン方程式)の意味内容を損なわずに、数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)を消すことに、アシュテカが成功したのだ。
→ つまり、一般相対性理論(アインシュタイン方程式)の意味内容を損なわずに、数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)を消すことに、アシュテカが成功したのだ。
◎ そもそも、アインシュタインは、やむを得なく、リーマン幾何学に頼ったことを思い出さなければならない。
→ そもそも、アインシュタインは、やむを得なく、リーマン幾何学に頼ったのだった。
◎ “時空の曲り”の幾何的な実体像を具体的にイメージできなかったからこそ、やむなく、抽象的で、時空が連続であることを前提とするリーマン幾何学に頼ることとなったのだ。
→ “時空の曲り”や“重力場”についての具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)をイメージできなかったからこそ、やむなく、抽象的で難解な(時空が連続であることを前提とする)リーマン幾何学に頼ることになったのだ。
◎ そして、このリーマン幾何学の体系の数学事情を反映して、アインシュタイン方程式の数式が、(計量gμνに関する)非線形性を持つものになってしまった。
→ そして、このリーマン幾何学の体系の数学事情を反映して、アインシュタイン方程式の数式が、(計量gμνに関する)非線形性を持つものになってしまったに過ぎないのだ。
◎ しかし、 その後、一般相対性理論(アインシュタイン方程式)の意味内容を損なわずに、数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)を消すことに、アシュテカが成功した。
→ その証拠に、 後に、一般相対性理論(アインシュタイン方程式)の意味内容を損なわずに、数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)を消すことに、アシュテカが成功した。
◎ したがって、この数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)は── 重力場そのものが非線形であることを、全く意味していないと断言できる。
→ 少なくともこのことから、この数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)は── 重力場そのものが非線形であることを、全く意味していないことがわかるのである。
◎テーブル、引用文中 そして最終的にき、よく用いる方程式のなかで以前説明したおなじみのGという因子が、あたかも2Gになってしまったかのようになるのである。
→そして最終的には、よく用いる方程式のなかで以前説明したおなじみのGという因子が、あたかも2Gになってしまったかのようになるのである。
◎テーブル (p.224-226 『新しい重力理論 ニュートンから重力波まで』 下線は、筆者による)
→ (p.224-226 『新しい重力理論 ニュートンから重力波まで』 アーサー・クライン著 竹内均訳 講談社ブルーバックス
下線は、筆者による)
◎ すなわち、このことは、質量M[kg]の物体が、自己の重力(重力ポテンシャルエネルギー)によって、コンパクト化していく場合── ニュートン力学にもとづいて考えた場合、質量M[kg]のままの対し、一般相対性理論によると、質量2M[kg]であるかのように、ふるまうということでもある。
→ この記述内容を単純に言い換えれば、「質量M[kg]の物体が、自己の重力(重力ポテンシャルエネルギー)によって、コンパクト化していく場合── ニュートン力学によれば、質量M[kg]のままなのに対し、一般相対性理論によると、質量2M[kg]であるかのように振る舞う」ということになる。
◎たかが、2倍といってあなどることはできない。
→たかが2倍といっても、あなどることはできない。
◎。なぜなら、質量が2倍になるということは、同時に、質量エネルギーMc2、時空の曲りも2倍になるということだからである。
→なぜなら、質量M[kg]が2倍になるということは、同時に、質量エネルギーMc2[J]や重力場(時空の曲り)も2倍になるということだからである。
◎
|
ニュートン力学
|
アインシュタインの一般相対性理論 |
|
『質量M、半径Rの単一物体の重力的自己エネルギー
あるいは結合エネルギー』
|
Eb=GM2/R
|
Eb=2GM2/R
|
|
重力ポテンシャルφ
|
φ=GM/R
|
φ=2GM/R
|
|
質量M
|
M
|
2M
|
|
質量エネルギーMc2
|
Mc2
|
2Mc2
|
|
時空の曲り
|
(≒−(NM/π2n)×(1/r2)
(≒−(NM/4πn)×(1/r2)))
|
(≒−(2NM/π2n)×(1/r2)
(≒−(2NM/4πn)×(1/r2)))
|
→
|
ニュートン力学
|
アインシュタインの一般相対性理論
|
|
『質量M[kg]、半径R[m]の単一物体の重力的自己エネルギー
あるいは結合エネルギー』[J]
|
Eb=GM2/R[J]
|
Eb=2GM2/R[J]
|
|
重力ポテンシャルφ[J]
|
φ=GM/R[J]
|
φ=2GM/R[J]
|
|
質量M[kg]
|
M[kg]
|
2M[kg]
|
|
質量エネルギーMc2[J]
|
Mc2[J]
|
2Mc2[J]
|
|
重力場[N/kg]
|
F=GM/R2[N/kg]
|
F=2GM/R2[N/kg]
|
|
時空の曲り[1/m2]
|
−(NM/π2n)×(1/r2)[1/m2]
(≒−(NM/4πn)×(1/r2))[1/m2])
|
−(2NM/π2n)×(1/r2)[1/m2]
(≒−(2NM/4πn)×(1/r2)[1/m2])
|
| ※なお、時空の曲りが2倍になるのは、(重力ポテンシャルエネルギーに比例する時空の曲り、すなわち、自由落下で消せる方の時空の曲りが2倍になるからである。 |
◎ これまでは、「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」ことは、一般相対性理論(重力)が非線形であることの根拠であると見なされてきた。
すなわち、Gが2Gになることは、上記のように、『実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”』が生じること、すなわち、重力場が、新たな質量になるという重力場が非線形性を持つという考えによって説明されてきた。
→ これまでは、「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」ことは、一般相対性理論(重力場)が非線形であることの根拠であると見なされてきた。 すなわち、Gが2Gになることは、上記のように、『実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”』が生じること、すなわち、「重力場が、新たな質量になる」という考えによって説明されてきた。
◎大改訂 『質量M、半径Rの単一物体の重力的自己エネルギーあるいは結合エネルギー』の値「Eb=GM2/R」は、その半径Rの物体をバラバラにして、無限遠方に移動させるのに必要なエネルギーに等しい。
この無限遠方に散らばった物体が再び、コンパクト化し、半径Rの単一の物体に戻ることを考えよう。
ニュートン力学によれば、元に戻った半径Rの単一の物体が持つ結合エネルギーは、「Eb=GM2/R」のままで変わらない。
これは、静止質量による結合エネルギー「Eb=GM2/R」[J]である。
※このエネルギーは、ポテンシャルエネルギーを利用して、獲得される(外部)運動エネルギー、すなわち、「Eb=GM2/R」[J]にぴったり等しいはずである。
アインシュタインの一般相対性理論によれば、元に戻った半径Rの単一の物体が持つ結合エネルギーは、「Eb=2GM2/R」と2倍なる。
それは、静止質量による結合エネルギー「Eb=GM2/R」[J]に、
「獲得される(外部)運動エネルギー」が持つ質量による結合エネルギー「Eb=GM2/R」[J]が加わるからであると考えられる。
「獲得される(外部)運動エネルギー」の分を新たな質量としてカウントするからこそ、時空の曲りも2倍、質量も2倍になったことと同じになるのである。
その結果、重力ポテンシャルの大きさは、ニュートン力学におけるφ=GM/Rの2倍の、 φ=2GM/Rとなるのである。
→
「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」ことについて、“重力線”を含む図で示すと次のようになる。
※無限遠方に散らばった静止質量M[kg]の物体が、重力によってコンパクト化する際の様子を示している。
左側がニュートン力学によるもので、右側が一般相対性理論によるものである。
左右での違いは、次の通りである。
〈1〉右の“重力線”の密度が、左の“重力線”の密度の2倍になっている。
(図では、2次元で2倍になるように示しているが、厳密に3次元で2倍になっているという意味である)
〈2〉右が、物体の半径が、2倍になっている。 左がR[m]だとすれば、右は、2R[m]である。
〈3〉下の段にくるにつれて、物体のコンパクト化が進んでいる。
(上図では、半径Rが1/3倍になっている。この1/3倍には、深い意味はない)
この図から、次のことがわかる。
右の“重力線”は、左の“重力線”の2倍になっているので、右の質量(エネルギー)は、左の質量(エネルギー)の2倍になっている。
「物体の表面」における“重力線”の球面密度は、左右で等しい。
したがって、物体の表面における重力(重力場)は、左右で等しい。
よって、物体の表面における、「重力ポテンシャルエネルギーに比例する時空の曲り」は、左右で等しい。
したがって、物体の表面における、「重力ポテンシャルエネルギー」は、左右で等しい。
|
なぜ、このようなことが起きるのか?
それは、一般相対性理論によると、物体が半径Rまで、コンパクト化するまでに獲得する(外部)運動エネルギーが新たな質量エネルギーとしてカウントされるからである。
その新たに獲得される質量エネルギー((外部)運動エネルギーK[J])は、ぴったりそこまで利用された重力ポテンシャルエネルギーの大きさGM/R[J]に等しい。
そして、物体表面での重力場は2倍なので、この新たに獲得される質量エネルギー((外部)運動エネルギーK[J])が、そのまま重力ポテンシャルエネルギーに寄与することになる。
※例えば、重心からR[m]、2R[m]の場所で、一般相対性理論にもとづく重力ポテンシャルエネルギーは、2倍になっていることが図示されている。
一般相対性理論にもとづく、重力ポテンシャルエネルギーのカーブは、各点で、ニュートン力学にもとづく場合の2倍となるのは、新たに獲得される運動エネルギーK=GM/R[J]が、そのまま重力ポテンシャルエネルギーに寄与する結果であると考えられる。 なぜなら、この関係があるおかげで、各点での重力(重力場)も2倍になるからである。
※物体の表面が、−GM/R[J]の重力ポテンシャルエネルギー(あるいは、GM/R2[N/kg]の重力(重力場))を持つために、ニュートン力学では、半径R[m]まで物体がコンパクト化する必要がある一方、一般相対性理論に理論では、半径2R[m]まで物体がコンパクト化すれば済むことも、この図から読み取れる。
※Gが2Gになるということは、この図のような関係があることを意味していることになる。
|
つまり、物体が獲得する運動エネルギーをカウントする結果、ニュートン力学で考えた時に物体の表面における重力ポテンシャルエネルギーU=−GM/R[J]は、一般相対性理論では、2倍の−2GM/R[J]となるのである。
そして、だからこそ、物体の表面における、「重力ポテンシャルエネルギー」や「重力(重力場)」、「自由落下で消せる時空の曲り」は、下図の左右で、等しくなるのである。
なお、『質量M[m]、半径R[m]の単一物体の重力的自己エネルギーあるいは結合エネルギー』[J]が、2倍になるのは、
「静止質量エネルギーによって生じる結合エネルギー」Eb=GM2/R[J]に、「物体が獲得する(外部)運動エネルギーによって生じる結合エネルギー」Eb=GM2/R[J]の分が、単純に加わる結果であると考えられる。
以上より、下表のすべてを説明できたことになる。
|
ニュートン力学
|
アインシュタインの一般相対性理論
|
|
『質量M[kg]、半径R[m]の単一物体の重力的自己エネルギー
あるいは結合エネルギー』[J]
|
Eb=GM2/R[J]
|
Eb=2GM2/R[J]
|
|
重力ポテンシャルエネルギーU[J]
|
U=−GM/R[J]
|
U=−2GM/R[J]
|
|
質量M[kg]
|
M[kg]
|
2M[kg]
|
|
質量エネルギーMc2[J]
|
Mc2[J]
|
2Mc2[J]
|
|
重力場[N/kg]
|
F=GM/R2[N/kg]
|
F=2GM/R2[N/kg]
|
|
時空の曲り[1/m2]
|
−(NM/π2n)×(1/r2)[1/m2]
(≒−(NM/4πn)×(1/r2))[1/m2])
|
−(2NM/π2n)×(1/r2)[1/m2]
(≒−(2NM/4πn)×(1/r2)[1/m2])
|
◎ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、質量になりうるのは、運動エネルギー(内部&外部)であり、重力場のエネルギーではないことを示している。
→ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、質量になりうるのは、重力場のエネルギーではなく、運動エネルギー(内部&外部)であることを示している。
◎削除 (当然、重力場が、新たな質量になるからでもないことも意味している)
◎“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、示しているのである。
→“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、はっきり示しているのである。
すなわち、Gという値が2倍になるのは、「物体が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した(外部)運動エネルギー」を、新たな質量としてカウントするからに他ならない。
◎削除 すなわち、Gという値が、2倍になるかならないかは、単に「物質が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した(外部)運動エネルギー」を、新たな質量をカウントするかカウントしないかの違いにすぎないことを意味しているのである。
◎ すなわち、重力場が非線形でないとは、「重力場のエネルギーそのものが質量になり、その質量がさらに新たな重力場を生み、またその新たな重力場のエネルギーそのものが、新たな質量になり… と限りなく繰り返すよう非線形性」がないということである。
→ ※「重力場のエネルギーそのものが質量にならない」ということは、当然、「重力場のエネルギーが質量になり、その質量がさらに新たな重力場を生み、またその新たな重力場のエネルギーそのものが、新たな質量になり… と限りなく繰り返すよう非線形性」もないということである。
◎
よって、「重力場が(外部)運動エネルギーという質量を生み、その(外部)運動エネルギーという質量がさらに新たな重力場を生み、またその新たな重力場が、新たな(外部)運動エネルギーという質量になり… と限りなく繰り返すよう非線形性」はあるとは、言えると思われる。
しかし、それでも、重力場そのものは、非線形ではないという結論はゆらがない。
「重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した(外部)運動エネルギーのみが新たな質量になる」からである。
しかも、重力場そのものは、非線形ではないという結論は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が調和振動子であり、重力場がそれらの総和として創発していると説明されていることとも調和している。
→ ※Gという値が2Gになるという関係が成立するのは、物体がシュバルツシルト半径までコンパクト化するまでの間だけである。
このことは、シュバルツシルト半径に至るまでは、(Gという値が2Gになるという関係が成立するので)「重力場が(外部)運動エネルギーという質量を生み、その(外部)運動エネルギーという質量がさらに新たな重力場を生み、またその新たな重力場が、新たな(外部)運動エネルギーという質量になり… と限りなく繰り返すような非線形性」が存在しないことを意味している。
仮に別の条件で、このような非線形性が存在していたとしても、「重力場そのものは非線形ではない」という結論はゆらがないと考えられる。
なぜなら、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が調和振動子であり、それらの総和として重力場が創発していることは変わらないと考えられるからである。
◎アインシュタインの右辺が、質量エネルギー(「静止質量エネルキー&き運動エネルギー」
→アインシュタインの右辺が、質量エネルギー(「静止質量エネルキー&(外部)運動エネルギー」
◎その全体積 Vだけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを説明しているものに過ぎない。 この場合は、全体積Vが小さくなると、それに反比例して、「物質の静止質量エネルギー&運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)の体積密度」が大きくなっているだけである。
→その全体積 V[m3]だけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを説明しているものに過ぎない。 この場合は、全体積V[m3]が小さくなると、それに反比例して、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)の密度」が大きくなっているだけである。
◎
→
◎テーブル ※この図は、「物体の質量エネルギー&運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件つきの図である。
この条件がついてはじめて、グリーンの部分の時空がすべて、同じになることができるのである。
→※この図は、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件つきの図である。
この条件がついてはじめて、グリーンの部分の時空がすべて、同じになることができるのである。
◎ しかし、「物体の質量エネルギー&運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件は、実は、現実的な条件ではなかったことになる。
すなわち、ふつう、物質は、それ自身の質量が生じる重力によって収縮する(コンパクト化する)ので、その際に「物質が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して、運動エネルギーを獲得し、それが新たな重力子の放出源になること」を考慮する方が現実的である。 それを考慮して図示すると、次のようになる。
→ しかし、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件は、実は、現実的な条件ではなかったことになる。
すなわち、ふつう、物体は、それ自身の質量が生じる重力によって収縮する(コンパクト化する)ので、その際に「物体が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して、運動エネルギーを獲得し、それが新たな重力子の放出源になること」を考慮する方が現実的である。 それを考慮して図示すると、次のようになる。
◎
|
物質が、(物質自身が持つ)重力によって収縮する(コンパクト化する)場合──
|
|
|
|
|
→
|
物体が、(物質自身が持つ)重力によって収縮する(コンパクト化する)場合──
|
|
|
→
|
|
◎
※「物質が重力によって収縮する(コンパクト化する)際に、物質が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した運動エネルギーが
新たな重力子の放出源になること」を考慮した図である。
この条件では、重力場は、徐々に大きくなり、最終的に2倍になることが示されている。
この2倍になることが、“Gから2Gまで変化すること”に他ならない。
※結果的に、これらの図は、アインシュタインの一般相対性理論に対応するものになっている。
なお、このような、“Gから2Gまでの変化”は、“重力場の非線形性”を意味しないのだった。
|
|
|
→
※「物体が重力によって収縮する(コンパクト化する)際に、物質が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した運動エネルギーが
新たな重力子の放出源になること」を考慮した図である。
※なお、2倍になるのは、無限遠方からコンパクト化させた場合である。この場合、一般相対性理論ではニュートン力学にもとづく値の2倍
になる。
しがって、上部のように、「途中から」コンパクトしただけでは、2倍には至らない。
※もし「無限遠方から」を考えた場合、下図のように、ニュートン力学の場合(上段)に比べて一般相対性理論の場合(下段)は、
シュバルツシルト半径に至るまでは常に2倍となっているはずである。
|
|
|
|
|
|
|
|
↓2倍
|
↓2倍
|
↓2倍
|
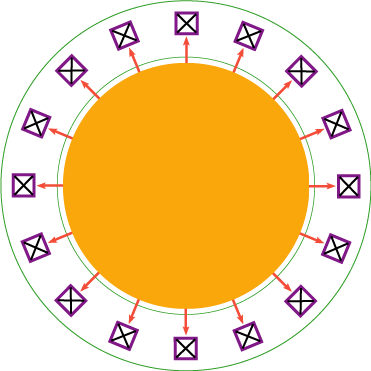 |
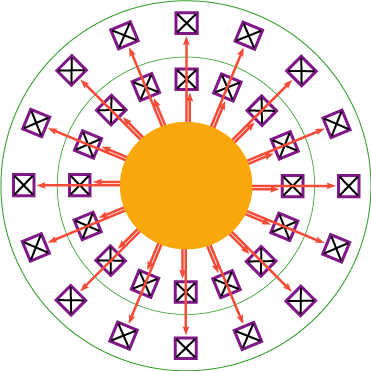 |
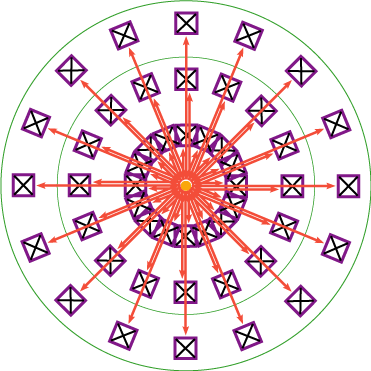 |
◎テーブルで追加 ※“4角形”(縮みきったバネ)が、規則正しく、交互に90度向きを変えているように図示しているが、実際は、様々な角度にランダムに向きを変えていると考えられる。
◎テーブル すなわち、この場合、事象の地平面において“4角形”(縮みきったバネ)が占める面積は、『(M/MG)2×(4LP2/π)』となる。
→したがって、物体がブラックホールになる場合、その事象の地平面において“4角形”(縮みきったバネ)が占める面積は、『(M/MG)2×(4LP2/π)』となるはずである。
◎ したがって、厚さ2LP[m]の球殻において『NM=(M/MG)』個の原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形していた、質量Mが、ブラックホールになることによって
→ つまり、厚さ2LP[m]の球殻において『NM=(M/MG)』個の原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形していた、質量M[kg]が、ブラックホールになることによって
◎ また、このことから、「重力場のエネルギーが新たな質量になる」という意味の非線形性ではないことも確かだと言える。
→ (また、このことから、ここにあるのは、「重力場のエネルギーが新たな質量になる」という意味の非線形性ではないことも確かである)
◎ したがって、ブラックホールに至ることによって、さらなる「運動エネルギーが増加するしくみ」があると考えられる。→(EMOES宇宙論1)
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ニュートン重力理論が(M/MG)×4LP2で説明できる一方、 ブラックホールが、(M/MG)×2×4LP2によっては説明できず、(M/MG)2×4LP2/πで、はじめて説明できることは、この根底に、何か重要なしくみ(からくり)が存在していることを示唆しているのである。 (→EMOES宇宙論1)
→ したがって、ブラックホールに至ることによって、さらなる「運動エネルギーが増加するしくみ」があると考えられる。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ニュートン重力理論が(M/MG)×4LP2で説明できる一方、 ブラックホールが、(M/MG)×2×4LP2によっては説明できず、(M/MG)2×4LP2/πで、はじめて説明できることは、この根底に、何か重要なしくみ(からくり)が存在していることを示唆しているのである。
◎ ※そのしくみ(からくり)とは、次のようなものだと考えれる。
→ そのしくみ(からくり)とは、次のようなものだと考えれる。
◎テーブル 重力ポテンシャルエネルギーエネルギーに等しい結果(K=Gm/R〔J〕)
→(シュバルツシルト半径以降の)重力ポテンシャルエネルギーエネルギーに等しい結果(K=Gm/R〔J〕)
◎テーブルで追加 より一般的に書くと、『質量m〔kg〕を持つプレオン∴2n[個]からなる質量2nm〔kg〕が、 ブラックホールに落ちると、22nm〔kg〕になる』ということになる。
数学的帰納法による証明は次のようになる。
命題『質量m〔kg〕を持つプレオン∴2n[個]からなる質量2nm〔kg〕が、 ブラックホールに落ちると、22nm〔kg〕になる』について──
n=1ときは、プレオン∴2個からなる2m〔kg〕は、ブラックホールに落ちると、4m〔kg〕となるので、成立する。
n=kのときに成立すると仮定すると、プレオン∴k個からなる2km〔kg〕が、ブラックホールに落ちると、22km[kg]になるはずである。
その仮定の上で、n=k+1のときを考えてみよう。
プレオン∴k+1個からなる 2k+1m〔kg〕は、ブラックホールに落ちると、n=kのときの質量、22km[kg]の4倍になるはずである。
なぜなら、質量の合計は、22km[kg]+22km[kg]+22km[kg](22kK[J]由来)+22km[kg](22kK[J]由来)となるからである。
つまり、プレオン∴k+1個からなる 2k+1m〔kg〕は、ブラックホールに落ちると、4×22km=22(k+1)m[kg]となるのである。
したがって、n=kのときに成立すると仮定するなら、n=k+1のときにも成立することが証明された。
以上の数学的帰納法により、任意の自然数nについて、命題『質量m〔kg〕を持つプレオン∴2n[個]からなる質量2nm〔kg〕が、 ブラックホールに落ちると、22nm〔kg〕になる』が成り立つという結論に至る。 |
|
◎テーブル したがって、
帰納的に次の結論を導くことができる。
→ プレオン∴の個数Nは、確かに、ぴったり「
2n[個]」
という形の数字だとは、限らないだろう。
しかし、大きなNについて、より一般化した、次のような結論を導くことは無理がないと思われる。
◎テーブル
結論1.10.4 一般に、質量m〔kg〕を持つプレオン∴が2n個(トータルの質量は、2nm〔kg〕)は、ブラックホールの中心に落下することによって、トータルで、2n倍の質量、すなわち(2n)2m〔kg〕=4n2m〔kg〕の質量を持つに至る。
→ 結論1.10.4 一般に、質量m〔kg〕を持つプレオン∴が2n個(トータルの質量は、2nm〔kg〕)は、ブラックホールの中心に落下することによって、トータルで、2n倍の質量、すなわち(2n)2m〔kg〕=22nm〔kg〕の質量を持つに至る。
◎ したがって、(真の)「事象の地平面の面積S」は、少なくとも、その効果の分を乗じたものに相当しなければならない。
すなわち、それは、『(M/M
G)×2×
(M/MG)×4L
P2〔m
2〕=(M/M
G)
2×2×4L
P2 〔m
2〕』
となる。
→ したがって、(真の)「事象の地平面の面積S
[m2]」は、少なくとも、
この効果の分を乗じたものに相当しなければならない。
そして、この効果の分を乗じた(真の)「事象の地平面の面積S[m]」に近いものとは、まさに、『(M/M
G)×2×
(M/MG)×4L
P2[m2]=(M/M
G)
2×2×4L
P2 [m
2]』
(=NM2×2×4LP2 [m2])に他ならない。
そして、この効果の分を乗じた(真の)「事象の地平面の面積S」に近いものとは、まさに、『(M/M
G)×2×
(M/MG)×4L
P2〔m
2〕=(M/M
G)
2×2×4L
P2 [m
2]』に他ならない。
◎テーブル
該当部分 〔m
2〕→[m
2]
◎なぜなら、プレオン∴の個数と、重力子質量の個数(M/M
G)は、単純に比例すると考えられるからである。
→なぜなら、プレオン∴の個数と、重力子質量の個数(M/M
G)
(=NM)は、単純に比例すると考えられるからである。
◎テーブル
なお、「1/2π倍」が何であっても、重力場は、獲得する運動エネルギーに比例して創発していることになるので、「重力場は線形である」という説明は、ゆらがない
ことになると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
→
そして、「1/2π倍」
の正体が何であっても、重力場は、
結局、獲得する運動エネルギーに比例して創発していること
は変わらないので、「重力場は線形である」という説明は、ゆらがない
のである。
◎
“調和振動子”であることを考えれば当然のことである。
→“調和振動子”であることを考えれば、やはり当然のことである。
◎ これらは、「(通過点である)重力場そのものから、いきなり、“新たな重力子が放出される”ことがありえない」おかげでもあるのだ。
→ これらは、「(重力子のエネルギーの通過点に過ぎない)重力場そのものが、いきなり、“新たな重力子の放出源として働く能力”、すなわち、新たな質量を獲得することがありえない」おかげでもあるのだ。
◎ 該当部分 〔J
〕→[J]
◎該当部分
〔kg〕→[kg]
◎
2016→
2016-2017



