◎大きな改訂
一方、この当量電荷QEは、ガウスの定理と調和している仮説(仮説1.9.1 ある電荷Q[C]が「厚さ2Lpの球殻内で&1秒間で変形させている“4面体”の個数」は、どの球殻でも同じである)により、r=2nLP に対応する他の球殻にも、一秒間にc/2LP[個]の「変形している“4面体”」を作る。
よって、次の結論に至る、
結論1.6.2 「当量電荷QEの中心からr=2nLp離れた場所にある厚さ2Lpの球殻が持っているエネルギーの総和の、1秒間での時間平均」は、
h/2×「その球殻内&1秒間で変形している“4面体”の個数」=h/2×(c/2LP[個/s])= hc/4Lp[J]と、n(≧20)によらず一定の値となる。
一般に、 Q[C]の電荷は、NQ[個]の当量電荷QE[C]から構成された電荷と見なして、Q=NQQE[C](NQ=(Q/QE))と表記できるので── Q[C]の電荷が、厚さ2LPの球殻が持つエネルギーの1秒間での時間平均は、NQ×hc/4Lp[J](NQ=(Q/QE))となる。
→ 『仮説1.9.1 ある電荷Q[C]は、いずれの「厚さ2Lp[m]の球殻」の中にも、(時間平均で)同じ大きさのエネルギーを蓄える結果、その空間平均として、クーロンの法則を担う電場(マクロの電場)を創発する』、および、『各「厚さ2LP〔m〕の球殻」に、1秒間の時間平均で、hc/4Lp〔J〕のエネルギーを蓄えるような電荷』という当量電荷QE[C]の定義により──
一般に、 Q[C]の電荷は、NQ[個]の当量電荷QE[C]から構成された電荷と見なすことができて、Q=NQQE[C](NQ=Q/QE[個])と表記できて、Q[C]の電荷が、各「厚さ2LP[C]の球殻」に蓄えさせられるエネルギーの1秒間での時間平均は、NQ×hc/4Lp[J](NQ=Q/QE[個])となる。
◎当量電荷QE[C]が生じるクーロン力を求めていくにあたり── →当量電荷QE[C]が生じる静電気力(電荷のクーロン力)を求めていくにあたり──
◎該当箇所 「変形した“4角形”」→「変形している“4面体”」
◎該当箇所 「変形した“4面体”」→「変形している“4面体”」
◎ r=2nLP離れた所にある厚さ2LPの球殻の中間にある球面の全面積は、およそ4πr2=16πn2LP2[m2]である。 厚さ2LP[m]でであるので、球殻の体積Vは、近似的に、V≒球面の全面積×厚さ=16πn2LP2[m2]×2LP[m](n≧20)とできる。
そのうち、1つの「変形している“4面体”」が占める球殻の中の体積は、8LP3[m3]×1[m2]とできる。(なお、近辺の原始ヒッグス場ユニットの位置は変わらないので、その変形によって、小さくなったことをここで考慮しなくてよい)
→ r=2nLP[m]離れた所にある厚さ2LP[m]の球殻の中間にある球面の全面積は、およそ4πr2=16πn2LP2[m2]である。 厚さ2LP[m]であるので、球殻の体積V[m3]は、近似的に、V≒球面の全面積×厚さ=16πn2LP2[m2]×2LP[m](n≧20)と表記できる。
そのうち、1つの「変形している“4面体”」が占める球殻の中の体積は、8LP3[m3]と表記できる。
(なお、各原始ヒッグス場ユニットの配置は変わらないので、ここでは、その変形によって“小さくなること”を考慮しなくてもよい)
◎ 一方、1つの「変形している“4面体”」の部分のエネルギーの1秒間での時間平均が「h/2」[J]であった。
→ 一方、1つの「変形している“4面体”」に蓄えられるエネルギーの1秒間での時間平均が「h/2」[J]であった。
◎ これらの値から、1つの「変形している“4面体”」の「球殻内での時間&空間平均」が計算できる。
→ これらの値から、「変形している“4面体”」1つあたりの「球殻全体に蓄えられるエネルギーの“時間&空間”平均」が計算できる。
◎1つの「変形している“4面体”」が蓄えるエネルギーの「球殻内での時間&空間平均」をE平均1〔J〕と書くことにすると
→ 「変形している“4面体”」1つあたりの「球殻全体に蓄えられるエネルギーの“時間&空間”平均」をE平均1〔J〕と書くことにすると
◎該当箇所 時間&空間平均→“時間&空間”平均
◎該当箇所 一秒→1秒
◎該当箇所 LP
→LP[m]
◎ 一秒間にc/2LP[個]の「変形している“4面体”」を作られることを考慮すると、
「当量電荷QEの中心からr=2nLP離れた所にある厚さ2Lpの球殻が蓄えるエネルギーの、一秒間での時間&空間平均」E平均QE〔J〕は、
→ 当量電荷QE[C]の周辺の厚さ2Lp[m]の各球殻(n≧20)において、1秒間にc/2LP[個]の「変形している“4面体”」が作られることを考慮すると、
「当量電荷QE[C]の中心からr=2nLP離れた所にある厚さ2Lp[m]の球殻が蓄えるエネルギーの“時間&空間”平均」E平均QE〔J〕は、
◎該当箇所 E平均1
→E平均1〔J〕
◎該当箇所 当量電荷QE
→当量電荷QE〔C〕
◎
→
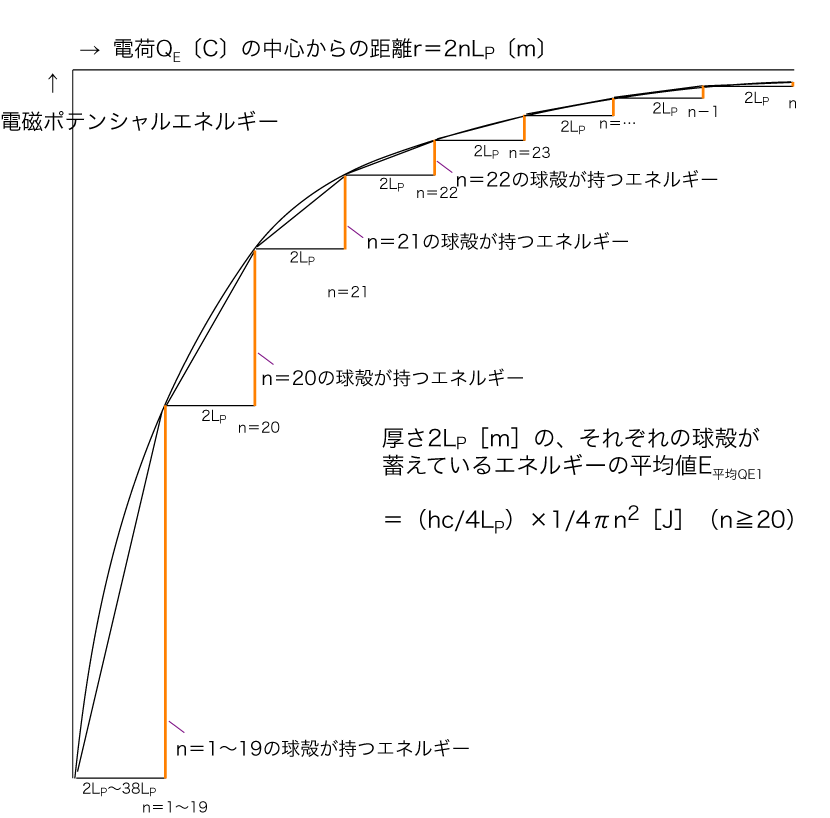 |
◎※やはり、厳密には、厚さ2LPの球殻”が持つエネルギーE平均QE1=(hc/4LP)×1/4πn2[J]は、n≧20 に限って成立する。
上では、1≦n≦19の範囲(2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]の仮想光子)について、便宜上、簡略化して図示している。
→※やはり、厳密には、厚さ2LP[m]の球殻”が持つエネルギーE平均QE1=(hc/4LP)×1/4πn2[J]は、少なくともn≧20 に限って成立する。
上図では、便宜上、1≦n≦19の範囲(2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]の仮想光子)についてのみを簡略化して図示している。
◎時空の中に新たに追加されることになるのは、重力の場合と似ている。→時空の中に新たに追加されることになることは、重力の場合と似ている。
◎追加 ※重力ポテンシャルエネルギーの計算を参考にすると、電荷が半径a=2mLP〔m〕の球体であると想定した場合、a=2mLP〔m〕の地点からr=2nLpの地点までの電磁ポテンシャルエネルギーの変化の大きさは、
(hc/4LP)×1/4π×(1/m−1/n)=(hc/16πLP)(1/m−1/n)〔J〕と計算できることがわかる。
よって、電荷が半径a=38LP〔m〕の球体であるならば、電磁ポテンシャルエネルギーの変化の大きさは、m=19を代入して、(hc/16πLP)(1/19−1/n)〔J〕と求まることになる。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎
E平均QE1(n≧20)を底辺2LP[m]で割れば、エネルギー勾配、つまり、 この上で、「r=2nLP[m]離れた厚さ2Lp[m]の球殻」で当量電荷QE[C]が作る電場E[N]が計算できる。
→ E平均QE1(n≧20)を底辺2LP[m]で割れば、エネルギー勾配、すなわち、「r=2nLP[m]離れた厚さ2Lp[m]の球殻」で当量電荷QE[C]が作る電場E[N]を計算できる。
◎ すなわち、次のようになる。
r=2nLP[m](n≧20)の場所での当量電荷QE[C]が作る電場E[N]=E平均QE1/2LP[N]= (hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)[N](n≧20) …(1)
→ つまり、
r=2nLP[m](n≧20)の場所での当量電荷QE[C]が作る電場E[N]は、E=E平均QE1/2LP[N]= (hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)[N](n≧20) …(1)
となる。
◎一方、電荷のクローンの法則の式から求まる、電場の式[N/C]を変形してみよう。
→ 一方、電荷のクーロンの法則の式から求まる、電荷Q[C]が作る電場の式E=kQ/r2[N/C]を変形することを考えてみよう。
◎該当部分 クローンの法則→クーロンの法則
◎ =kQE/r2
→ =kQE/r2[N/C]
◎ =(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(μ0/2LP)[N/C] …(2)
=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(μ0/2LP)[N/C]
=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/(2LP/μ0)}[N/C] …(2)
◎テーブルの中 当量電荷QEが作る電場E[N/C]=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(μ0/2LP)[N/C] …(2)
→当量電荷QEが作る電場E[N/C]=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/(2LP/μ0)}[N/C] …(2)
◎ 「QEc2 ∝ hc/4Lp」、「(μ0/2LP)∝ 1/QE」と考えればつじつまが合うことがわかる。
→ 「QEc2 ∝ hc/4Lp」、「(2LP/μ0)∝ QE」と考えればつじつまが合うことがわかる。
◎削除
|
(1)例えば、「1クーロン=1アンペア×1秒と電気量が決められている。」とのことである。 (参考 『物理学入門』p.133 実教出版株式会社)
つまりは、[C]=[A・s]であり、仮説が1.10が正しければ、[A]∝[kg/s]ということになる。
一方、「電流の強さI[A]は、次の式で表される。 I=nqvS 」とのことである。 (参考 『物理学入門』p.156 実教出版株式会社)
右辺の次元は、nqvS [1/m3・C・m/s・m2]∝[1/m3・kg・m/s・m2]=[kg/s]となり、矛盾していない。
(2)コンデンサーの電気容量C0[F]は、 C0=1/4πk・S/d=ε0S/d となる。(参考 『物理学入門』p.146 実教出版株式会社)
ε0S/d [C2/N・m2][m2][1/m]∝([kg]2/[kg・m/s2・m2])[m2][1/m]=[kg・s2/m2]
一方、1[F]=1[C/V]=1[C][C/J]∝1[kg][kg]/[kg・m2/s2]=[kg・s2/m2]となり、
やはり、矛盾していない。
(3)(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×(μ0/2Lp) …(2) の単位はどうなるか?
μ0=4π×10-7[N/A2]であるので──
[N/A2][1/m][J][1/m]∝([N]/[kg2/s2])・[kg・m2/s2][1/m2]=[N][1/kg]∝[N/C]=[E](電場)となり、やはり、矛盾していない。
|
クローンの単位[C]と[kg]は比例するという考えは、決して、的外れではないことが分かる。
◎すなわち、質量mがE=mc2 のエネルギーを持つように、電荷Qには、「E=aQc2[C・m2/s2] = hc/4Lp[J](=[kg・m2/s2])」というエネルギーがつまっているということである。
→すなわち、質量m[kg]がE=mc2[J]のエネルギーを持つように、電荷Q[C]には、「E=aQc2[kg/C][C・m2/s2] = hc/4Lp[J](=[kg・m2/s2])」というエネルギーがつまっているということである。
◎ 一方の、「(μ0/2LP)∝ 1/QE」、すなわち、「(2LP/μ0)∝ QE」に注目して単位を調べてみる。
まず、「(2LP/μ0)」の単位を調べてみると、
→ 一方の、「(2LP/μ0)∝ QE」に注目して単位を調べてみよう。
すると、「(2LP/μ0)」の単位は、
◎ よって、これらの逆数である(μ0/2aLP)の単位は、[1/C]となるので、1/QEの単位[1/C]とぴったり合致することが分かる。
→ つまり、a(2LP/μ0)の単位は[C]であり、QE[C]の単位とぴったり同じである。
◎ 「電荷のクローンの法則の式から求まる、当量電荷QEが作る電場E[N/C]」の式は、次のように変形できることがわかる。
=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(μ0/2LP)[N/C] …(2)
=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{(1/(2LP/μ0))}[N/C]
→ 「電荷のクーロンの法則の式から求まる、当量電荷QE[C]が作る電場E[N/C]」の式kQE/r2[N/C]を次のように変形することは、きわめて自然で合理的なことがわかる。
kQE/r2[N/C]
=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{(1/(2LP/μ0))}[N/C] …(1.4)
◎ 最後の変形は、結局、分母と分子にa[kg/C]を掛け合わせただけのものに相当している。
→ ※最後の変形は、結局、分母と分子にa[kg/C]を掛け合わせただけのものに相当しているが、それ以上の意味をもっている。
◎ 同様にして、一般的な、電荷のクーロンの法則F[N]= kQq/r2[N]の式は、次のように書き換えることができる。
→ 同様にして、一般的な、電荷のクーロンの法則F[N]= kQq/r2[N]の式を、次のように変形することができる。
◎ =(aQc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/a(2LP/μ0)}×q[N] …(3) (分母と分子に同じaを乗じてある)
→ =(aQc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/a(2LP/μ0)}×q[N] (分母と分子に同じaを乗じてある)
◎ よって、前に示した、「ニュートンの万有引力の式の“EMOES表記”と比較して予想される、クーロンの法則の“EMOES表記”の式」は、次のように変形できることになる。
→以上のような、分母と分子にa[kg/C]を掛け合わせる変形を行うことによって、前に示した「ニュートンの万有引力の式の“EMOES表記”と比較して予想される、クーロンの法則の“EMOES表記”の式」は、次のようにまとめなおすことができる。
◎ a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C] QE=(h/2μ0c)1/2[C]と、それぞれの値が計算で求めることができる。
→ a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C] QE=(h/2μ0c)1/2[C]と、それぞれの値を求めることができる。
◎上の計算によるの値QE[C]≒9.37×10-19[C]と合致する。
→上の計算によって求めた値QE[C]≒9.37×10-19[C]と合致する。
◎ 重力子質量MG[kg]が、陽子の質量の、およそ1019倍であるのに対して、当量電荷QEが電子の電荷のたった5.8倍であると言うことができる。
このことは、ミクロレベルで、電磁気力が、重力より、はるかに大きい理由を説明していると考えられる。
→ 重力子質量MG(=2×10-8/2π≒3.18×10-9)[kg]が、陽子の質量1.67×10-27[kg]のおよそ1.9×1018倍であるのに対して、当量電荷QE[C]は、電子の電荷1.60×10-19[C]のたったの5.8倍であると言うことができる。
このことは、ミクロレベルで、静電気力が、重力より、はるかに大きい理由を説明していると思われる。
◎追加 ※なお、r=2nLP[m]の位置にある球殻において、ある瞬間に(同時に)n個の共転回をする必要がある事情から、電子の振動数e〔回/s〕やプレオン∴の振動数ν∴〔回/s〕の分、ある瞬間に(同時に)共転回できる数が“増える(増幅する)”ことを考えたのだった。もしかしたら、当量電荷QE[C]が電子が持つエネルギーが大きいことは、それらの“増幅”の影響を反映しているだけなのかもしれない。詳細な検討は、今後の課題である。
◎この定数a[kg/C]が存在するのは、電荷[C]も、質量[kg]も、ともに、原始ヒッグス場抵抗を下げる能力をもつこと、
→この定数a[kg/C]が存在するのは、電荷[C]と質量[kg]は、ともに原始ヒッグス場抵抗を下げる能力をもつこと、
◎ =Q/QE・π/2×EP[J]=Q×1/(h/2μ0c)1/2・π/2×hc/2πLP[[J]
→ =Q/QE・π/2×EP[J]
◎そして、その理由は、「Q/QE」の項が“×1019”のオーダーで大きくなることに依存していることが数式から読み取れる。
「Q/QE」の項が大きくなる理由の1つは、1クーロンという単位の設定の仕方(「1m離して置いた時に、それらの間に働く力が9.0×109[N]となるような電気量を1クーロン(記号C)と決める。」(参考 『物理学入門))にある。 実際に、もし、ミクロレベル(プランクスケール)で、当量電荷QE[C]と重力子質量MG[kg]の同じ個数分ずつ存在するとして比較した場合は、
→そして、その理由は、「Q/QE」の項がおよそ“×1018”のオーダーで大きくなることに依存していることが数式から読み取れる。
「Q/QE」の項が大きくなる理由の1つは、1クーロンという単位の設定の仕方(『1mはなして置いた時に、それらの間に働く力が9.0×109[N]となるような電気量を1クーロン(記号C)と決める』(p.133 『物理学入門))にある。 実際に、もし、ミクロレベル(プランクスケール)で、当量電荷QE[C]と重力子質量MG[kg]が同じ個数分ずつ存在するとして比較した場合は、
◎しかし、「Q/QE」の項が大きくなる理由には、もう1つある。 上で述べたように、当量電荷QE[C]がおよそ電子の電荷の5.8個に相当するのに対して、重力子質量MG[kg]は陽子の質量のおよそ1019個分に相当することである。
→「Q/QE」の項が大きくなるもう1つ理由は、やはり、上で述べたように、当量電荷QE[C]がおよそ電子の電荷の5.8個に相当するのに対して、重力子質量MG[kg]は陽子の質量のおよそ1.9×1018個分に相当することである。
◎該当部分 電磁気力→静電気力
◎(典型的なのは、光合成のプロセスの中の“電子伝達系”である)
→(典型的な例は、光合成のプロセスの一部を担う“電子伝達系”である)
◎エネルギー問題解決の重要なカギの1つとなることを意味しているのかもしれない。
→エネルギー問題解決の重要なカギの1つとなることを意味しているように思われる。
◎一方、この“電子”の最もシンプルで取り扱いが便利な単体が、水素である。
→ 一方、この“電子”の「最もシンプルで、取り扱いが便利な単体」が、水素である。
◎ このことから、「電荷のエネルギーが質量を持っている」と考えることには、あまりに大きな桁外れな(1022倍もの)違い── すなわち、観測値と計算値の間の大きな矛盾があることがわかる。
つまり、この「電荷のエネルギーも、質量を持つ」という考えは、自然(nature)と乖離しているのである。
→ このことから、「電荷のエネルギーが質量を持っている」と考えることには、観測値と計算値の間における、あまりに大きな桁外れな(1022倍もの)ずれ(乖離)があることがわかる。
したがって、この「電荷のエネルギーも、質量を持つ」という考えは、自然(nature)と乖離しているのである。
◎ここにある値の大きなずれ(矛盾)の、根本の原因は
→ここにある値の大きなずれ(乖離)の、根本の原因は
◎「あらゆるエネルギーは、すべて質量を持つ」という意味に解釈したことにこそあることがわかる。
→「あらゆるエネルギーは質量である」という意味に解釈したことにこそあることがわかる。
◎そこに矛盾が生じてしまったのであり── この数式について、「質量は運動エネルギー(内部&外部)を持つ」、「質量はエネルギーの一種に過ぎない」という解釈をしていれば、「電荷のエネルギーも、質量を持つ」という考えも生じず、矛盾が、全く生じなかったことになるのだ。
→ここに自然(nature)からの乖離が生じてしまったのであり── この数式について、「質量は運動エネルギー(内部&外部)を持つ」、「質量はエネルギーの一種に過ぎない」という解釈をしていれば、「電荷のエネルギーも、質量を持つ」という考えも、観測値と計算値の間における大きなずれ(乖離)も、生じることはなかったのだ。
◎E=mc2という「抽象的な数式」そのものだけを重視しているだけでは、この「あらゆるエネルギーは、どれも質量を持つ」という解釈が自然(nature)から乖離していることは、気づくことが難しい。
→E=mc2という「抽象的な数式」そのものだけを重視しているだけでは、この「あらゆるエネルギーは質量である」という解釈が自然(nature)から乖離していることに気づくことは難しい。
◎自然(nature)からに乖離していることをはっきりわかるのだ
→自然(nature)から乖離していることに気づくことができるのだ
◎つまり、自然(nature)と調和しているか乖離しているか、に気づくためには、「抽象的な数式」の解釈、すなわち、自然(nature)についての、幾何的な実体像そのものを重視することが大切になるのである。
→つまり、「自然(nature)と調和しているかどうか、自然(nature)から乖離しているかどうか」に気づくためには、「抽象的な数式」の解釈、すなわち、自然(nature)についての具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)を重視することが大切になるのである。 (→考察2)
◎ よって、E=Mc2[J]の数式は、
→ よって、アインシュタインのE=Mc2[J]の数式は、
◎該当部分 質量M→質量M[kg]
◎該当部分 電荷Q→電荷Q[C]
◎該当部分 Etotal→Etotal[J]
◎(1/μ0=c2ε0を代入)→(r=2nLP、1/μ0=c2ε0を代入)
◎b(2LP/ε0)が、当量磁極mE[Wb]になればよい。
→b(2LP/ε0)[Wb]が、当量磁極mE[Wb]に等しければよい。
◎該当部分 当量磁極mE→当量磁極mE[Wb]
◎さらに、次のように変形できる。
磁極のクーロン力F[N]
→ 磁極のクーロン力F=m1m2/4πμ0r2[N]の式は、さらに、次のように変形できる。
磁極のクーロン力F(=m1m2/4πμ0r2)[N]
◎(なお、磁極も仮想光子の放出源として働き続ける能力てあるので、
→(なお、磁極も仮想光子の放出源として働き続ける能力であるので、
◎※mE=(h/2cε0)1/2[Nms/C]の単位、[Nms/C]は、
→※mE=(h/2cε0)1/2の単位、[Nms/C]は、
◎(モノポールが確認されていない以上、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によればモノポールが存在しないと予想できる以上
→(モノポールが確認されていない以上、そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によればモノポールが存在しないと予想できる以上
◎自然(nature)に存在する磁石(電子を含む)の持つエネルギーの目安を得ることができるだろう。
→自然(nature)に存在する磁石(電子を含む)が持つエネルギーの目安を得ることができるだろう。
◎ 果たして、電子のサイズは、どれくらいなのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
→ 果たして、電子のサイズは、どれくらいなのだろうか?
◎追加
結果2《磁力と、磁極の間に働く“引力と斥力”および“電子のスピン”について》によると、電子のサイズ(軸方向の幅)は、少なくとも、「プレオン∴のサイズ程度」、すなわち、LP〔m〕程度であることになる。
この値と1つの電子の磁気モーメント1.613565×10-30[Wb・m]の値を使うと、1つの電子の磁極[Wb]について、考えうる最大値が計算できる。
その値は、1.613565×10-30[Wb・m]/LP〔m〕≒1×105〔Wb〕である。(LP=1.616×1035〔m〕とした)
この値と1[Wb]が持つおおよそのエネルギー8.698×1024[J]を用いることによって、1つの電子の磁極が持つエネルギーの考えうる最大値が、およそ8.698×1024[J/Wb]×1×105〔Wb〕=8.698×1029[J]であると求まる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
|
◎ なお、電子のサイズがいくらであろうと、1[Wb]は、b×1×c
2[J]=9.6781×10
7×(2.9979×
108)
2≒8.698×10
24[J]のエネルギーを持
つことは変わらないので、電子が1つ磁極が持つエネルギーは、非常に大きいものになることが予想される。
→ なお、電子のサイズが
厳密にいくらであろうと、1[Wb]は、b×1×c
2[J]=9.6781×10
7×(2.9979×
108)
2≒8.698×10
24[J]のエネルギーを持
ち、1つの電子の磁気モーメントが1.613565×10-30[Wb・m]であることは変わらないので、電子1つ
が持つ磁極のエネルギーは、非常に大きいものになること
は確かである。
◎
以上をまとめると、電荷&磁荷のクーロンの法則の“EMOES表記”は、下のようになる。
→
以上をまとめると、電荷や磁極のクーロンの法則の“EMOES表記”は、下のようになる。
◎
|
a=(hμ0/8cLP2)1/2≒3.6460×1010[kg/C]
QE=プランク電荷qP/2≒9.3777295×10-19[C]
|
b=a×(ε0/μ0)1/2 ≒9.678×107[Cs/m2]
mE=(qP/2)×(μ0/ε0)1/2≒3.532874×10-16[Wb]
|
→
|
変換定数a=(hμ0/8cLP2)1/2≒3.6460×1010[kg/C]
当量電荷QE=プランク電荷qP/2≒9.3777295×10-19[C]
|
変換定数b=a×(ε0/μ0)1/2 ≒9.678×107[Cs/m2]
当量磁極mE=(qP/2)×(μ0/ε0)1/2≒3.532874×10-16[Wb]
|
◎それぞれのクーロン力がどのようにして生じるのかについての
大きな部分を説明している
→
電荷や磁極のクーロン力がどのようにして生じるのかについての
本質的な部分を説明している
◎
※なお、電気力や磁力には、引力や斥力が存在するので、まだ十分な説明ではない。
→
※なお、静電気力や磁力には、引力や斥力が存在するので、まだ十分な説明ではない。
◎ ここにあるのは、重力と電磁気力の統合の本質であると同時に、“重力場と電磁場の統合”の本質であると言える
だろう。
→ ここにあるのは、重力と電磁気力(静電気力&磁力)の統合の本質であると同時に、“重力場と電磁場(電場&磁場)の統合”の本質であると言える
のである。
◎これは、ミクロの自然(nature)そのものが、本来、シンプルだからである。
→ これは、ミクロ
(プランクスケール)の自然(nature)そのものが、本来、シンプルだからである。
◎
すなわち、このことは、自然な世界観(3Steps原理)の1つ、「ズームインするほど、よりシンプル一様化する」と調和している
からである。
→
つまり、このことは、自然な世界観(3Steps原理)の1つ、「ズームインするほど、よりシンプル一様化する」と調和している
のである。
◎ (なお、微分さえも用いていないのは、ミクロの自然(nature)においては、時空さえも、不連続である(飛び飛びである、微分できない)からである)
→ (なお、
(原則として)微分さえも用いていないのは、ミクロ(プランクスケール)の自然(nature)においては、時空さえも、不連続である(飛び飛びである、微分できない)ことを前提としているからである)
◎
まだ課題はあるものの、少なくとも、この方向性──
→
したがって、少なくとも、この方向性──
◎電磁気力(電気力&磁力)、および、重力を統合していくための大きなヒント
→電磁気力(
静電気力&磁力)、および、重力を統合していくための大きなヒント
◎マクロの世界を記述するための、近似式である
ことがわかる。
→マクロの世界を記述するための、近似式である
と言える。
◎したがって、
ネーターの定理は、連続な時空の対称性が成り立つときのみ、保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立つことを示すネーターの定理と── 時空が不連続であることを前提とする“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において、重力子や仮想光子がエネルギー非保存の所産であることは、調和しているのである。
→したがって、
「連続な時空の対称性が成り立つときのみ、保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立つことを示すネーターの定理
」と
「時空が不連続である
という前提で重力子や仮想光子がエネルギー非保存の所産であることを示す“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)」は、調和しているのである。
◎
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、質量を、より厳密に、次のように定義できる。
→“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)においては、質量を、より厳密に、次のように定義できる。
◎
このことは、ブラックホールから放出される大量の重力子がエントロピーを持ち去ることの根拠の1つとなる。
→
※実際は、このように雑然としていることは、ブラックホールから放出される大量の重力子がエントロピーを持ち去ることの根拠の1つとなる。
※
「厚さ2L
P[m]の球殻」輪切りにしたスペースに、8つずつ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」があるように図示されている。
◎
→
◎
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が持っているエネルギーの総和から創発するものに過ぎないものである。
→
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が持っているエネルギーの総和として創発するものに過ぎないものである。
◎
したがって、そうやって生み出された“重力場が持つエネルギー”自身が、新たな質量「(重力子を一定頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)」となることは、決してありえないことは、容易にわかる。
→
したがって、そうやって生み出された“重力場が持つエネルギー”自身が、新たな質量「(重力子を一定頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)」となることは、決してありえないのである。 ◎ ※重力場を創発する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、すべて、通過点に過ぎない。
→ ※重力場を創発する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、すべて、
エネルギーの通過点に過ぎない。
◎
すなわち、この物体(素粒子の総和)などの、大元の質量、すなわち、「運動エネルギー(内部&外部)を持つもの」こそが、“重力場の持つエネルギー”のすべてを供給し続けている源であり── やはり、重力場は、あくまで“エネルギーの通過点”に過ぎないのである。
→すなわち、この物体(素粒子の総和)などの、大元の質量、すなわち、「運動エネルギー(内部&外部)を持つもの」こそが、“重力場が持っているエネルギー”を供給し続けている源であり── やはり、重力場は、あくまで、これらの“エネルギーの通過点”に過ぎないのである。
◎(このことは、「一見、途中の“電線”からエネルギーが供給されるように見えても、実際は、すべてのエネルギーが、その源である発電所から供給されている」ということと似ていると思われる。
→(このことは、「一見、途中の“電線”から電気のエネルギーが供給されるように見えても、実際は、そのエネルギーは、その源である発電所から供給されている」ということと似ていると思われる。
◎以上の、「重力場のエネルギーは、質量を持っていない」という説明は、やはり、「あらゆるエネルギーが、質量を持つとは限らない」こと、「質量は、あくまで、エネルギーの1つのあり方にすぎない」ことをはっきり示しているものの一例でもある。
→
以上の「重力場のエネルギーは質量を持っていない」という説明は、やはり、「あらゆるエネルギーが質量を持つとは限らない」こと、すなわち、「質量は、あくまで、エネルギーの1つのあり方にすぎない」ことをはっきり示しているものの一例でもある。
◎
※エネルギーを持つが質量を持たないものの例として、次のものが挙げられる。
重力子、光子、仮想光子
「電磁波および電磁場」(光子や仮想光子の総和)
「重力波および重力場」(重力子の総和)
電荷や磁極(仮想光子を一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)
|
→
※エネルギーを持つが質量を持たないものの例をまとめると、次のようになる。
|
重力子、光子、仮想光子
「電磁波および電磁場」(光子や仮想光子の総和)
「重力波および重力場」(重力子の総和)
電荷や磁極(仮想光子を一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)
|
|
◎リレー(転送)し続けているだけの通過点であることを、はっきり示しているのである。
→
リレー(転送)し続けているだけの通過点に過ぎないことを、はっきり示しているのである。
◎ ※「あらゆる質量がエネルギーが持つ」という説明のみならず、「あらゆるエネルギーが質量を持つ」という説明を始めたのは、他ならぬ、E=mc2を発見したアインシュタインであったことは次の記述から読み取れる。
→ ※E=mc2という数式に対して、「質量がエネルギーが持つ」という解釈のみならず、「エネルギーが質量を持つ」という解釈を始めたのは、他ならぬ、E=mc2を発見したアインシュタインであったことは次の記述から読み取れる。
◎注意して読めば、次のいずれの「数式の解釈」も、実は、解釈の1つに過ぎないことが読み取れる。
→注意して考えれば、次のいずれの「数式の解釈」も、実は、解釈の1つに過ぎないことがわかる。
◎すなわち、いずれの数式に対しても、次のように、“ひっくり返して”解釈できるものであることがわかる。
→ すなわち、上のいずれの「数式の解釈」に対しても、次のように、“ひっくり返した”解釈が可能であることがわかる。
◎追加
| ※上の4つの文のみがアインシュタイン自身による解釈であり、ここからアインシュタインが「エネルギーは質量を持つ」と解釈していたことが読み取れる。 |
◎ 「その質量がその質量はL/9×1020 だけ変われば、エネルギーがLだけ変わる」
→ 「その質量がL/9×1020 だけ変われば、エネルギーがLだけ変わる」
◎追加
| ※4番目の『質量Mに属するエネルギーは質量に 光の莫大な速さの2乗を掛けたものに等しい』の文のみアインシュタイン自身による解釈である。ここから、アインシュタインが「質量がエネルギーを持つ」とも解釈していたことがわかる。 |
◎ つまりは、1つの抽象的な数式に対して、一見もっともな解釈が2つずつ存在するのだ。
→ つまりは、E=mc2という抽象的な数式に対して、本来、一見もっともな解釈が2つずつ存在するのだ。
◎アインシュタインは、「あらゆる質量は、エネルギーを持つ」と「あらゆるエネルギーは、質量を持つ」の両方の解釈を採用し、深く考えずに、どちらとも正しいと見なしたことが3番目の文章から読み取れる。
→そして、アインシュタインは、「質量はエネルギーを持つ」と「エネルギーは質量を持つ」の解釈の両方が正しいと見なしていたことが特に4番目の文のペア──『質量Mに属するエネルギーは質量に 光の莫大な速さの2乗を掛けたものに等しい』と『この関係をひっくり返して、エネルギーにおけるEだけの増加は質量におけるE/c2だけの増加を伴わなければならない』から読み取れる。
◎すなわち、アインシュタインにとっては、「あらゆる質量は、エネルギーを持つ」と「あらゆるエネルギーは、質量を持つ」は、大した違いがなかった。
→つまり、アインシュタインにとっては、「質量はエネルギーを持つ」と「エネルギーは質量を持つ」は、大した違いがなかったのである。
◎しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に照らすと、「あらゆる質量は、エネルギーを持つ」と「あらゆるエネルギーは、質量を持つ」という2つの解釈の間には、雲泥の差があることが、はっきりわかる。
→しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に照らすと、「質量はエネルギーを持つ」と「エネルギーは質量を持つ」という2つの解釈の間には、雲泥の差があることが、はっきりわかる。 なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「質量を持たないエネルギーが存在すること」や「運動エネルギー(内部&外部)こそが質量を持つこと」をはっきり示しているからである。
◎ すなわち、「あらゆる質量は、エネルギーを持つ」のみが自然(nature)と調和し、「あらゆるエネルギーは、質量を持つ」は、自然(nature)から乖離しているのである。
→ つまり、「あらゆる質量はエネルギーを持つ」のみが自然(nature)と調和し、「あらゆるエネルギーは質量を持つ」は、自然(nature)から乖離しているのである。
◎ たとえ偉大なアインシュタインであっても、「抽象的な数式」に裏切られうるのである。
→たとえ偉大なアインシュタインであっても、「抽象的な数式」に裏切られうるのである。(→考察2)
《アインシュタイン方程式(アインシュタインの“重力場の方程式”)》
◎追加 ※この数式は、確かに高校数学を越えている。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、この数式の意味──
具体的な“幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”)
をつかむべく、高校レベルの数学(計算)によって、可能な限り変形していく。 (→下記)
◎お粗末に設計された建物にぞらえて
→お粗末に設計された建物になぞらえて
◎「粗悪な材木」とまで言わしめたた方程式の右辺
→「粗悪な材木」とまで言わしめた方程式の右辺
◎右辺のテンソルTμνの成分の中の“圧力(力/面積=[kg・m/s2][1/m2])”は
→右辺のテンソルTμνの成分の一例である“圧力(力/面積=[kg・m/s2][1/m2])”は
◎該当部分 「静止質量エネルギー+運動エネルギー」
→「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」
◎時空の曲がり(曲率)に比例することを意味している式であることになる。
→時空の曲がり(曲率)に比例することを意味している式なのである。
◎ よって、「Tμν/EG」は、「Tμν/EG=(Mc2/EG)/V=NM/V[個/m3]」と変形できる。
→ よって、「Tμν/EG」の成分は、「Tμν/EGの成分」=(Mc2/EG)/V=NM/V[個/m3]と変形できる。
◎ したがって、「Tμν/EG=NM/V[個/m3]」は、「“重力子質量MG[kg]”数密度テンソル」あるいは、「“重力子放出数”密度テンソル」と呼べるものであることが分かる。
つまり、以上の書き換えは、アインシュタイン方程式の右辺が、“重力場の源”、すなわち、「重力子の放出源」であることを、より明確に示すものであることがわかる。
→ したがって、「Tμν/EGの成分」=NM/V[個/m3]は、「NM(重力子質量数(質量M[kg]が重力子質量MG[kg]の何個分かを示す数))の密度テンソル」あるいは、「“重力子放出数(厚さ2LP[m]の球殻に存在する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数)”密度テンソル」と呼べるものであることがわかる。
つまり、以上の言い換えは、アインシュタイン方程式の右辺が、“重力場の源”、すなわち、「重力子の放出源」であることを、より明確に示しているものであることがわかる。
◎ アインシュタイン方程式の右辺の成分の近似値は、次のように変型できる。
→ アインシュタイン方程式の右辺の成分の近似値は、次のように変形できる。
◎なお、(1/r2)[1/m2]の項は、半径r[m]の球面のガウス曲率Kに相当することがわかる。
なぜなら、半径r[1/m]の球面の曲率は、どこの場所においても、1/r [1/m]であり、ガウスの曲率Kは、K=1/ρ1ρ2=1/r2[1/m2]となるからである。
→ なお、(1/r2)[1/m2]の項は、「半径r[m]の球面」が持つガウス曲率K[1/m2]に相当することがわかる。
なぜなら、半径r[1/m]の球面の曲率は、どこの場所においても、1/r [1/m]であり、ガウスの曲率Kは、K=1/ρ1ρ2=1/r2[1/m2]と求まるからである。
◎ と変形でき、
−(NM/4πn)×(c2)∝−(NM/4nπ)×6 となるからである。
→ と変形できるので、
kTμνの成分≒−kMc2/V
= −(NM/4nπ)×6×(1/r2)
= (−GM/r)×6×(1/c2)×(1/r2)
となるからである。
◎ すなわち、下図のようなカーブが、重力ポテンシャルエネルギーに比例するところの“時空の曲り”なのである。
→つまり、下図のようなカーブと相似なものが、重力ポテンシャルエネルギーに比例するところの“時空の曲り”なのである。
◎自由落下によって消すことのできる“時空の曲り”に他ならない。
→自由落下運動によって消すことのできる“時空の曲り”に他ならない。
◎ 追加 c2で割ることにはどのような意味があるだろうか?
◎追加 そして、NMの方、すなわち、「Mc2がEGの何倍か?」の方が、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの合計」(=運動エネルギー(内部&外部))を、より考慮しやすいという意味もあると思われる。
(なお、同様に、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの合計」(運動エネルギー(内部&外部))を考慮しやすい重力の式は、(Mc2/EG)×(1/4πn2)であるということにもなるであろう。 (詳細な検討は、今後の課題である))
◎中心にあるM[kg]から放出される“重力子数”だけが、中心にあるM[kg]が作る“時空の曲がり”を計算するために必要である」という意味があると思われる。
→中心にある質量M[kg]から放出される“重力子数(厚さ2LP[m]の球殻に存在する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数)”を導く」という意味があると思われる。
◎ それでは、6をかける意味は何であろうか?
次に、上の《“時空の曲がり”&重力場の実体像》において、引用した次の記述を活用してみよう。
→
それでは、6をかける意味は何であろうか?
そこで、次に、上の《“時空の曲がり”&重力場の実体像》において引用した、次の記述を活用してみることにした。
◎追加 後者が正しいとすれば、6をかける意味は、「単なる誤差」なのだろうか?
◎ 4/πをかける意味は何であろうか?
もしかしたら、4/π≒1と考え、(NM/π2n)≒(NM/4πn)と見なした方が、意味がすっきりして理解しやすいということなのだろうか?
だとすれば、そそもそも、(V=2π2R3[m3]の代わりに)V=8πR3[m3]であればよいことになる。
→ それでは、4/πをかける意味は何であろうか?
考えた範囲では、その意味を見いだすことができなかった。
一方、4/πをかける意味も「単なる誤差」と考え、すなわち、4/π≒1と考え、(NM/π2n)≒(NM/4πn)と見なした方が、意味がすっきりして理解しやすいと思われた。
(だとすれば、最初から(V=2π2R3[m3]の代わりに)V=8πR3[m3]を用いればよかったことになる。ただし、後者の体積は、ふつうの球の体積V=4πr3/3[m3]のぴったり6倍に他ならない。これは、空間を6倍に膨張させるという意味を持つと考えてよいのだろうか? だとしたら、先に「単なる誤差」の可能性を考えた「6をかけること」の意味は、「空間を6倍に膨張させること」だったことになる。 また、だとしたら、なぜ6倍なのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である)
◎ いずれにせよ、曲率については、少なくとも、その方がより自然に近いと思われるので── 今後は、6をかける方(全体積を(V≒4πr3/3[m3]とする方)ではなく、4/πをかける方(全体積をV=2π2R3[m3]とする方)や1をかける方(全体積をV≒8πR3[m3]とする方)を採用していくこととする。
※一方、次のようなことも言える。
それは、単に「−GM/r=−(NMEG/4πn)×(1/MG)」よりも── この式の両辺に、1/c2をかけた「(−GM/r)×1/c2=−(NMEG/4πn)×(1/MGc2)=(Mc2/EG)×(1/4πn)=NM/4πn」の方が、より「時空の曲がりを生む重力ポテンシャルエネルギーの式」としてわかりやすいということである。 なぜなら、「Mc2がEGの何倍か?」の方が、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの合計」(=運動エネルギー(内部&外部))をより考慮しやすいからである。
(なお、同様に、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの合計」(運動エネルギー(内部&外部))を考慮しやすい重力の式は、(Mc2/EG)×(1/4πn2)であるということにもなるであろう。 (詳細な検討は、今後の課題である))
以上より、アインシュタイン方程式の右辺の成分における、−(Mc2/EG)×(1/π2n)(≒−(Mc2/EG)×(1/4πn))の項は、「自由落下運動によって、消すことができる時空の曲がり」を意味する項であり、(1/r2)の項は、「自由落下運動によって、消すことができない時空の曲がり」を意味する項であると解釈できることになる。
→ いずれにせよ、曲率については、少なくとも、その方がよりシンプルで自然に近いと思われるので── この重力ポテンシャルエネルギーに比例する項としては、−(NM/π2n)(≒−(NM/4πn))、すなわち、4/πをかける方(全体積をV=2π2R3[m3]とする方)(≒1をかける方(全体積をV≒8πR3[m3]とする方))を採用していくこととする。
アインシュタイン方程式の右辺の成分は、ガウスの曲率K=1/r2[1/m2]と重力ポテンシャルエネルギーU=−NMEG/4πn[J]に比例する項の積で示される。
そして、前者が、「自由落下運動によって、消すことができない時空の曲がり」を意味する項であり、後者が、「自由落下運動によって、消すことができる時空の曲がり」を意味する項である。
◎
|
−(Mc/EG)×(1/π2n)[無次元]
(≒−(Mc/EG)×(1/4πn)[無次元])
|
(1/r2)[cm-2]
(∝[1/m2])
|
→
|
−(Mc2/EG)×(1/π2n)[無次元]
(≒−(Mc2/EG)×(1/4πn)[無次元]
=重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG[無次元])
|
(1/r2)
[1/m2](∝[cm-2])
|
◎ 以上により、アインシュタイン方程式の右辺そのものが、すでに“曲率”に相当することを示せたことになる。
→ アインシュタイン方程式の右辺の成分そのものが、すでに“曲率”に相当するのである。
◎次の範囲をテーブルで囲む
左辺: Gμν= Rμν−gμνR/2 の中で、 −gμνR/2 の方をまず見てみよう。
〜
を意味する方程式(曲率の別表記(2種類の表記)をイコールで結んだ式)であることがわかる。
◎テーブル 上記で説明した右辺が意味するもの(重力ポテンシャルエネルギー×ガウス曲率K)と、おおよそ同等のものであると思われる。
→上記で説明した右辺が意味するもの(≒(重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG)×ガウス曲率K)と、おおよそ調和していることがわかる。
◎テーブル 右辺が意味するもの(重力ポテンシャルエネルギー×ガウス曲率K)と、おおよそ同等のものであることがわかる。
→右辺が意味するもの(≒(重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG)×ガウス曲率K)と、おおよそ調和していることがわかる。
◎テーブル やはり、アインシュタイン方程式は、本質的には、曲率=曲率”(すなわち、重力ポテンシャルエネルギー×ガウス曲率K=重力ポテンシャルエネルギー×ガウス曲率K)を意味する方程式(曲率の別表記(2種類の表記)をイコールで結んだ式)であることがわかる。
→ やはり、アインシュタイン方程式は、本質的には、“曲率=曲率”(すなわち、おおよそ「(重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG)×ガウス曲率K」を意味する2つの方程式(曲率の2種類の表記)をイコールで結んだ式)であることがわかる。
◎ Rμνは、どうだろうか?
→ 左辺の中の残りのRμνの方は、どうだろうか?
◎テーブル幅の修正
|
『 Rip=gkmRmikp=gipR1212/g (18.22)
R1212=〜=−a2sin2θ (18.26)
g=a4sin2θ 』(一部省略)
|
→
|
『 Rip=gkmRmikp=gipR1212/g (18.22)
R1212=〜=−a2sin2θ (18.26)
g=a4sin2θ 』(一部省略)
|
◎ これらを使うと Rip=gipR1212/g = gip×(1/a2) となり、やはり、右辺が意味するもの(重力ポテンシャルエネルギー×ガウス曲率K)と、おおよそ同等のもであることがわかる。
→ これらを使って単純な代入計算(高校数学レベルの計算)を行うと、Rip=gipR1212/g = gip×(1/a2) となり、やはり、右辺が意味するもの(重力ポテンシャルエネルギー×ガウス曲率K)とおおよそ同等のものであることがわかる。
◎※このことは、何を意味するのだろうか? 左辺は、無駄なのだろうか?
いや、無駄ではないだろう。 なぜなら、アインシュタイン方程式は、「重力場の源」の形が様々なものである場合、それらの「重力場の源」がどのような時空の曲りを生じるか、すなわち、(「単純な球形をした時空の曲がり」以外の)様々な“時空の曲がり”をも、普遍的に説明できる数式だからである。
一方、アインシュタイン方程式を厳密に解くことができるのは、“球形”のときであること(シュバルツシルト解…)、自然界に実在する多くの天体は、ほとんど球形と見なせるものであること、そして、アインシュタインが、リーマン幾何学を駆使して苦労して計算によって求めた、左辺の「“時空の曲がり”を意味するテンソル」 の意味の本質が、右辺が示すように「厚さ2LP[m]の球殻の時空(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)に生じる重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の所産として、シンプルに理解できることを考慮すると、球殻近似をした上のような右辺の表記にも、大きな意味があると考えられる。
→
このことは、何を意味するのだろうか?
「普遍的な数式なので、アインシュタイン方程式に無駄がない」という考えもありうるだろう。しかし、次の3つの理由で、無駄がある可能性がある。
|
〈1〉アインシュタイン方程式を厳密に解くことができるのは、“球形”のときであること(シュバルツシルト解…)
〈2〉自然界に実在する多くの天体は、ほとんど球形と見なせるものだけであること
〈3〉アインシュタインがリーマン幾何学を駆使して10年かけて苦労して計算によって導いた、アインシュタイン方程式の本質が── 質量『運動エネルギー(内部&外部)が持つ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働く能力』と重力場『厚さ2LP[m]の各球殻の時空(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)に生じる重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和』との関係として、シンプルに理解できること。
|
※なお、アインシュタイン方程式によって解くことができない系についても、もしかしたら、「重力子&原始ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、密度、分布(配置)…」の総和として、厳密に&シンプルに再定式化することによってなら解くことができる(理解が深まる)ということがあるかもしれない。
(詳細な検討は、今後の課題である)
|
◎ やはり、アインシュタイン方程式は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が生む「重力ポテンシャルエネルギー」、および、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の「球状の配置」が、“時空の曲がり(曲率)”を創発していることを示している式であると解釈できるのである。
すなわち、アインシュタインの一般相対性理論の抽象的な数式は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、密度、分布(配置)…」の総和をマクロ近似によって表現しているものであると解釈できるものなのである。
→ いずれにせよ、アインシュタイン方程式は、質量が生じる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として創発する「重力ポテンシャルエネルギー」、および、同じ質量が生じる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の「球状の配置」として創発している“時空の曲がり(曲率)”という自然(nature)を、「(想像できない)連続な時空における所産」として近似して示している式であると解釈できるのである。
すなわち、アインシュタインの一般相対性理論の抽象的な数式は、質量エネルギー(=運動エネルギー(内部&外部))が生じる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、密度、分布(配置)…」の総和を、連続時空における所産である見なすマクロ(粗視化)近似によって表現しているものであると解釈できるものなのである。
◎削除 ※もしかしたら、アインシュタイン方程式によって解くことができない系についても、「重力子&原始ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、密度、分布(配置)…」の総和として、厳密に&シンプルに再定式化することによって、解くことができる(理解が深まる)── ということがあるかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎ 以上の内容(アインシュタイン方程式の意味)を図示すると、おおよそ、下図のようになる。
→ 以上の内容(アインシュタイン方程式の意味)を整理して図示すると、おおよそ、下のようになる。
◎※オレンジで示した物質は、体積のみが同じであるが、物質の総質量(重力子の放出源となる能力、静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総和)
の密度が異なっている。
→※オレンジで示した物体は、体積のみが同じで、物質の総質量エネルギー(重力子の放出源となる能力、静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総和)
の密度は異なっている。
◎ ただし、その質量の密度がそれぞれ異なっているものを3パターンだけを示してある。
質量の密度が大きいほど、それに比例して、物質の周囲の、時空の曲がりは、大きくなると考えられる。
→ ただし、その質量エネルギーの密度がそれぞれ異なっているものを3パターンだけを示してある。
質量エネルギーの密度が大きいほど、それに比例して、物体の周囲の「時空の曲がり」は大きくなると考えられる。
◎「重力ポテンシャルエネルギー」による、“時空の曲り(=(NMEG/4πn)×c2/EG)の違いに
相当することになる。
→「重力ポテンシャルエネルギー」による“時空の曲り(−(NM/π2n)(≒−(NM/4πn)))の違いに
相当することになる。
◎ つぎに、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」の状況で、その中心(重心)に向けて、その全体積 Vだけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを考えてみよう。
全体積Vが小さくなると、それに反比例して、「物質の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)の体積密度」は、大きくなる。
→ つぎに、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」の状況で、その中心(重心)に向けて、その全体積 V[m3]だけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを考えてみよう。
全体積V[m3]が小さくなると、それに反比例して、「物質の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)の密度」は、大きくなる。
◎※これらの図においては、「球状の形」による時空の曲り(=1/r2、すなわち、ガウス曲率K)のみならず、
「重力ポテンシャルエネルギー」による時空の曲り(=(NMEG/4πn)×c2/EG)も関わっていることがわかる。
→※これらの図が示す系においては、(「球状の形」による時空の曲り(=1/r2[m-2]、すなわち、ガウス曲率K)のみならず)
「重力ポテンシャルエネルギー」による時空の曲り(−(NM/π2n)(≒−(NM/4πn)))が変化していることが、よりわかりやすい。
◎それを言い換えると、時空の中で、想像像上の、半径rの球面を考えた場合、
→それを言い換えると、時空の中で、想像上の、半径rの球面を考えた場合、
◎該当部分 「質量エネルギー&運動エネルギーの総和」
→「静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総和」
◎質量や運動エネルギーが、どのように分布していようとも
→静止質量エネルギーや(外部)運動エネルギーの分布がどのようになっていても
◎すなわち、仮想質点を考え、その“重心(=仮想質点)からの距離”を用いれば十分であることになるからである。
→すなわち、「仮想的な質点」を考えて、その「仮想的な質点」の中心からの距離”を用いれば十分であることになるからである。
◎追加 ※この「質点」と、ニュートンが考え出した質点は、本質的に同じものである。
◎※ただし、もし、物質の総質量自身の重力によってコンパクト化が進み、体積密度が高まる場合は、
→※ただし、もし、物体の総質量自身の重力によってコンパクト化が進み、質量密度が高まる場合は、
◎※ところで、「物質の質量エネルギー&運動エネルギーの総量(大きさ)が同一」の状況で、最高どれだけ、小さくなることができるだろうか?
→※ところで、物体の総質量自身の重力によってコンパクト化が進み、質量の密度が高まり続ける場合、実際には、最高どれだけ小さくなることができるだろうか?
◎それは、すなわち、最小の体積Vminは
→すなわち、最小の体積Vmin[m3]は
◎とても苦労する計算を10年かけて試行錯誤することによって、
→10年かけて、とても苦労する計算を進めることによって、
◎曲率を表す式((NM/nπ2)×(1/r2)[cm-2](∝[1/m2])が、とてもシンプルであることと、とても対照的である。
→曲率を表す式((NM/π2n)×(1/r2)(≒(NM/4πn)×(1/r2))[1/m2](∝[cm-2])が、とてもシンプルであることと対照的である。
◎(そこにあるのは、せいぜい、高校数学レベルである。
→(そこにあるのは、やはり、高校数学レベルである。
◎ ほとんど微分積分さえも必要なく、級数(数列の和)があるだけである。
→しかも、微分積分は基本的に使われず、その代わりには、割り算や級数(数列の和)を用いるだけである。
◎ なぜ、アインシュタインの方程式は、これほど、複雑で理解の難しいものになっているのか?
→ なぜ、アインシュタインの方程式は、これほど、複雑で難解なものになっているのか?
◎該当部分 「時空の曲がりが、どのようにして生じるのか?」
→ 「時空の曲がりが、どのようにして(なぜ)生じるのか?」
◎ 「時空の曲がり」の正体(実体像)を直感的(具体的に)につかむことが、どうしてもできず、その探求をあきらめたからこそ、やむを得なく、抽象的なリーマン幾何学に頼って、重力場を定式化するという、非常に、忍耐、執念、力技、離れ業… を要する困難な道を、アインシュタインは、突き進んだのだ。
→ 「時空の曲がり」についての、具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)をつかむことが、どうしてもできず、その探求をあきらめたからこそ、やむを得なく、抽象的なリーマン幾何学に頼って重力場を定式化するという「忍耐、執念、力技、離れ業…」を要する非常に困難な道を、10年もかけて、アインシュタインは突き進んだのだ。
◎ 自然(nature)そのものが、ズームインするとシンプル化する、という自然な世界観と調和しているからである。
→ 「自然(nature)そのものが、ズームインするほどシンプル化する」という自然な世界観と調和しているからである。
◎“幾何学的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”)”を重視するか(あきらめないか)否かなのである。
→幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)の探究を重視するかどうか(あきらめないかどうか)なのである。
◎アインシュタインは、一般相対性理論の定式化にあたり、具体的な“幾何学的な実体像”をあきらめ、
→アインシュタインは、一般相対性理論の定式化にあたり、具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)の探究をあきらめ、
◎具体的な“幾何学的な実体像”の探求を重視した(あきらめなかった)
→具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)の探求を重視した(あきらめなかった)
◎
→
◎ ※なお、時空が連続か不連続かどうかは、エネルギー保存則が成り立つかどうかと深い関係がある。
→ ※なお、時空が連続か不連続かどうかは、エネルギー保存則が成り立つかどうかと深い関係があるのだった。
◎ そして、どうにかこうにかやっとの思いで、作り上げたアインシュタイン方程式について不満を持ち続けていたのは、他ならぬ、アインシュタイン自身である。
→ そして、10年かけて、どうにかこうにかやっとの思いで作り上げたアインシュタイン方程式について、誰よりも不満を持ち続けていたのは、他ならぬ、アインシュタイン自身であった。
◎ このことは、明らかに、アインシュタイン方程式には、発展の余地、アップグレードすべき余地があったことを示している。
◎ これらのことは、明らかに、アインシュタイン方程式には、発展の余地、アップグレードできる(すべき)点があったことを示していると思われる。
◎ そして、実際、その後、次のような進展もある。
→ そして、実際、次のような進展もあった。
◎ 時空を連続と見なすか不連続と見なすかは、数式の難易度を決めるのみならず、エネルギー保存則が成り立つかどうかを決める。
アインシュタインは、時空を連続なものと見なし、エネルギー保存則が成立すると考えていた。
そして、その上で、他ならぬアインシュタイン自身が、一般相対性理論とエネルギーの関係について問題意識を持っていた。 そのことは次の記述からわかる。
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より p.170〜171 下線は、筆者による)
|
その問題は、『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』ほどの大きなものであった。
→
アインシュタインが、おそらく最も不満に思っていたことの1つは、一般相対性理論とエネルギーの関係についてであった。
そのことは次の記述から読み取れる。
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より p.170〜171 下線は、筆者による)
|
この問題は、『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』ほどの重大なものであった。
アインシュタインは、時空を連続なものと見なし、エネルギー保存則が成立すると考えていた。
それは、アインシュタインが、(連続な時空を前提とする)リーマン幾何学に依存していたので、当然のことであった。
しかし、だからこそ、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』が、問題になったのだ。
(すなわち、時空が不連続であることを前提にしていれば、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』は問題にならないのである)
◎ その一方、アインシュタインは、アインシュタイン方程式の導出にあたり、最終的には、相対性原理ではなく、「エネルギーおよび運動量保存則が成立すること」を最大の根拠としたことは、次の記述から読みとれる。
→ 一方で、アインシュタインは、アインシュタイン方程式の導出にあたり、最終的には、相対性原理ではなく、「エネルギーおよび運動量保存則が成立すること」を最大の根拠としていた。
そのことは、次の記述から読みとれる。
◎追加 しかし、やはり、だからこそ、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』が、問題になったのだ。
(すなわち、やはり、時空が不連続であることを前提にしていれば、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』は問題にならないのである)
◎ しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、重力場は、「エネルギー保存則を破って生じる重力子の総和」である。
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「エネルギーおよび運動量保存則が成立すること」を“最大の根拠”とすることはできないのは明白である。
→ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、重力場は、『エネルギー非保存の所産である「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和』として創発するものである。
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、少なくとも「エネルギー保存則が成立すること」を“最大の根拠”とすることはできないのは明白である。
◎また、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、“重力場のエネルギー”は、「重力子の放出源、すなわち質量ではなく、通過する重力子エネルギーの総和」にすぎないのであった。
→また、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、“重力場のエネルギー”は、質量(重力子の放出源として働き続ける能力)ではありえず、「通過する重力子エネルギーの総和」にすぎないのであった。
◎引用部分2カ所 他のどのような同じ形の→他のどのようなエネルギーとも同じ形の
◎ その理由の本質は、やはり、ひとえに、アインシュタインが、ミクロの幾何的な実体像をもっていなかったことだと言える。
すなわち、(時空が不連続とみなせる)「より深いレベルの階層」から説明しようとせずに、(時空が連続と見なせる)「浅いレベルの階層」から説明しようとし続けたからである。
→ その理由の本質は、やはり、ひとえに、アインシュタインが、具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)をもっていなかったことだと考えられる。
◎ だからこそ、1つは、「時空の曲がりの実体が、いったい何なのか?」「時空の曲がりが、どのようにして生じるのか?」を説明できないままにせざるをえなくなったのである。
そして、だからこそ、もう1つは、エネルギー保存則にしばられることになってしまったのである。 すなほち、“「エネルギーおよび運動量保存則が成立すること」(≒連続な時空では、エネルギー保存則、運動量保存則が成立しうることを示すネーターの定理)を最大の根拠とすることや、微分可能な連続な時空を前提としたリーマン幾何学に対して、明確な疑問を抱くことをできず、そこにしばられざるを得なかってしまったのである。
そして、だからこそ、“抽象的な数式”(E=mc2…)の意味を正しく解釈できなかったのである。
→ その結果、次のようになってしまったのである。
〈1〉「時空の曲がりの実体が、いったい何なのか?」「重力場が、どのようにして(なぜ)生じるのか?」を説明できないままにせざるをえなくなった。
〈2〉エネルギー保存則にしばられることになってしまった。
時空が連続であるという考えや(連続な時空を前提としている)リーマン幾何学に対して、疑問を抱くことができなくなってしまった。
〈3〉“抽象的な数式”(E=mc2…)の意味を正しく解釈できなかった。 重力場のエネルギー自体が、質量になりうると考えてしまった。
◎ つまり、アインシュタインは、ミクロの具体的な幾何的な実体像をもっていなかったからこそ── 「どのようにして、重力場が生ずるのか?」「重力場のエネルギーとは何なのか?」が、皆目見当つかなかったので、やむなく、やみくもに、“抽象的な数式”(E=mc2…)や抽象的な物理理論(エネルギー保存則、運動量保存則…)に頼るしかなかったのである。
→ つまり、アインシュタインは、「重力場、時空の曲り、重力子、重力波…」についての具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)を持っていなかったからこそ── やみくもに、“抽象的な数式”(リーマン幾何学、E=mc2…)や抽象的な物理理論(エネルギー保存則、運動量保存則、ネーターの定理…)に頼るしかなかったのである。
◎ しかも、『もう半分は「粗悪な材木」できているようなものだ』と自分自身でけなすほど、その数式に不満を抱いていた。
そして、様々な問題を生み、アインシュタインを迷走させたのだ。
→ そして、だからこそ、出来上がった数式は、『もう半分は「粗悪な材木」できているようなものだ』という不満を抱かせるほど不完全なものにならざるをえなかったのである。
そして、その不完全性に、誰よりもアインシュタインが気づいていたからこそ、アインシュタインは、生涯、不満を持ち続け、グレードアップを試み続けることとなったのである。
そして、アインシュタインを迷走させたのだ。
◎ ※なお、アインシュタインが提唱した“光子”(光量子)という発想さえも、実は、ミクロの幾何学的実体像をともなっていなかったことが次の記述から読み取れる。
『“すべての物理学者は光子が何であるか知っていると思っている”とアインシュタインは書き、さらに“私は光子とは何であるのかの問題に答を見いだすのに一生を費やしたが、いまだにわからない”と続けている』(p.10 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』)
→
※なお、アインシュタインが提唱した“光子”(光量子)という発想さえも、実は、具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)をともなっていなかったことが次の記述から読み取れる。
|
『“すべての物理学者は光子が何であるか知っていると思っている”とアインシュタインは書き、さらに“私は光子とは何であるのかの問題に答を見いだすのに一生を費やしたが、いまだにわからない”と続けている』(p.10 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』)
|
したがって、「いわんや、重力子をや」なのは明らかである。
◎誰より、アインシュタイン自身が、何かがおかしいことを感づいていた。 だからこそ、次のような文章を自ら紡ぐに至っているのである。(再掲する)
→ やはり、誰よりアインシュタイン自身が、何かがおかしいことに気づいていたからこそ、アインシュタインは、次のような文章を自ら紡ぐに至っていたのである。(再掲する)
◎ もし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が、「完成した量子論」と調和しているものであるならば、アインシュタインの、まさに、この記述と調和していることになる。
なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、確かに、「アインシュタインの重力理論」の部分的な修正を迫っているからである。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、アインシュタインの重力理論に、少なくとも、次の3つの部分的な修正を迫る。
→ このアインシュタインの『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』疑問を根底から解消しうるものの1つが“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)である。
そして、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、『量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』という記述と調和している。 なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、量子論の完成を助けるものであり(→結果4)、確かに、「アインシュタインの重力理論」の部分的な修正を迫っているからである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、アインシュタインの重力理論に、少なくとも、次の3つの部分的な修正を迫っている。
◎ アインシュタイン方程式の右辺を「粗悪な材木」から、強固な「高級大理石」に、アップグレードできる。
→ アインシュタイン方程式の右辺を、「粗悪な材木」から強固な「高級大理石」へとアップグレードできる。
◎ すなわち、アインシュタインが生前なしとげることのできなかった多くの問題を解決できる可能性が生まれるのである。
→ つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせまっている「アインシュタインの重力理論」の修正は、アインシュタインが生前なしとげることのできなかった多くの問題を解決できるのである。
◎むろん、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせんとすることは、
→むろん、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がしようとすることは、
◎ 例えば、時空が連続と見なせるようなレベルでの重力の働きについての記述は、一般相対性理論は、見事に自然(nature)と調和しているのであり── 今後とも有効な理論であり続けるのは確かである。 しかし、例えば、「時空が連続と見なせないようなミクロのレベルでの重力の働きを考える場面」や「エネルギーに関する場面(エネルギー保存則、重力場のエネルギー、重力波のエネルギー)」においては、注意して数式を解釈しないと、自然(nature)から乖離してしまうことを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は示してくれるのである。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、一般相対性理論を包含しつつ、一般相対性理論の適用条件を明確に示すものなのである。
→ 例えば、時空が連続と見なせるようなマクロのレベルでの重力についての記述としての一般相対性理論は、見事に自然(nature)と調和しているのであり── 今後とも有効な理論であり続けることが確かであることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は示している。 しかし一方で、例えば、「時空が連続と見なせないようなミクロのレベルでの重力を考える場面」や「エネルギーに関する場面(エネルギー保存則、重力場のエネルギー、重力波のエネルギー)」においては、一般相対性理論は、自然(nature)から乖離してしまっていることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は示している。
このように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、一般相対性理論の自然(nature)と調和する部分を包含しつつ、一般相対性理論の適用条件を示すものなのである。
◎テーブル −kTμν[cm-2]→−kTμν
◎テーブル (厚さ2LPの球殻に蓄えられるエネルギーの時間平均=NMEG=ΣMc2
= Σ(Mc2(≒M0c2+M0v2/2)
→ (厚さ2LP[m]の球殻に蓄えられるエネルギーの時間平均=NMEG=Mc2
(≒(低速では)Σ(M0c2+M0v2/2))
◎テーブル =「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」(運動エネルギー(内部&外部))
=「重力子の放出源として働き続ける能力、すなわち質量」としてのエネルギー)
→=「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」
(運動エネルギー(内部&外部))
=質量エネルギー(「重力子の放出源として働き続ける能力」))
◎テーブル ※nが大きくなると、ニュートンの万有引力の法則になる。
→ ※nが大きくなると、ニュートンの万有引力の法則の式になる。
◎ テーブル ≒(NM/π2n)×(1/r2) [1/m2]
(≒(NM/4πn)×(1/r2) [1/m2])
→ ≒(NM/π2n)×(1/r2)(≒(NM/4πn)×(1/r2))
◎ テーブル =自由落下で消せる時空の曲がり(∝重力ポテンシャルエネルギー)
×球状の配置による時空の曲り
→=自由落下で消せる時空の曲がり
(≒重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG)
×球状の配置による時空の曲り(=ガウスの曲率K[1/m2])
◎テーブル ※「質量エネルギーや運動エネルギー」の総和を源にして生じた、
→※「静止質量エネルギーや(外部)運動エネルギー」の総和を源にして生じた、
◎ テーブル 右辺kTμνの成分の近似値となる。
→ 右辺kTμνの成分の値に近づく。
◎テーブル 「時空は、連続で微分可能である」
ということを前提としている
→「時空は、どこまでも(プランクスケールでも)
連続で微分可能である」
ということを前提としている
◎テーブル エネルギー運動量保存則について→エネルギー保存則について
◎テーブル アインシュタインは、重力場のエネルギーや運動量についても
保存則が成り立つべきだと考えた。
すなわち、ネーターの定理により、
時間と場所によらず、物理法則は不変であるべきと考えた。
→アインシュタインは、重力場のエネルギーについても
エネルギー保存則が成り立つべきだと考えた。
◎テーブル ミクロのレベルでみれば、時空は不連続であり、
エネルギーや運動量の保存則は成り立っていない。
重力子&“4角形”(縮みきったバネ)は
エネルギー非保存の所産であり、その総和として創発するものが
「重力場」、「時空の曲がり」、「重力波」… である。
※ネーターの定理は、「連続な時空のときにエネルギーや運動量が保存すること」
(エネルギー保存則や運動量保存則が成り立たないときは時空が不連続であること)
を示してくれる定理であり、
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和している。
厚さ2LPの球殻に蓄えられるエネルギーの時間平均は、
どこでも、共通の、NMEG =Mc2 である
→ミクロのレベル(プランクスケール)において、時空は不連続であり、
少なくともエネルギー保存則は成り立っていない。
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は
エネルギー非保存の所産であり、その総和として創発する
「重力場、重力波…」も、エネルギー非保存の所産である。
厚さ2LP[m]の球殻に蓄えられるエネルギーの時間平均は、
どの球殻においても共通のNMEG =Mc2 [J]である。
◎テーブル追加
|
ネーターの定理について
|
アインシュタインは、ネーターの定理により、
時間と場所によらず、物理法則は不変であるべきと考えた。
ネーターの定理は、エネルギー保存則の根拠の1つ
|
※ネーターの定理は、「連続な時空のときにエネルギーや運動量が保存すること」
(エネルギー保存則や運動量保存則が成り立たないときは時空が不連続であること)
を示してくれる定理であり、このネーターの定理は、“EMOES”(素スピノール
からの創発モデル)と調和している。
|
◎テーブル 時空が連続で微粉可能であることを前提とする
→ (時空が連続で微分可能であることを前提とする)
◎「重力」や「時空の曲がり」(∝重力ポテンシャルエネルギー)を
→「重力」や「時空の曲がり」を
◎テーブル 「エネルギーや運動量」が直接、時空の曲がりを生むと説明
→質量エネルギーがあると、どのようなしくみで(なぜ)
時空の曲がりが生まれるのかは不明
◎テーブル 時間の流れが遅くなる)
→時間の流れがスローダウンする)
◎テーブル 重力波のみを考え、
重力子を考えなかった。
重力波も、エネルギー保存則に従う。
重力波は、力学的エネルギーE(=K+U)を減らす
(重力波がエネルギーを持ち去る)
→重力波のみを考え、重力子を考えなかった。
重力波も、エネルギー保存則に従うと考えた。
重力波は、力学的エネルギーE(=K+U)を減らす
(重力波がエネルギーを持ち去る)と考えた。
◎テーブル 重力波は、
「放出される重力子数の変化」
として創発しているものである。
→重力波は、「放出される重力子数の変化」として、
創発しているものである。(→下記《連星系パルサーと重力波について》)
◎
→
|
量子物理学
|
量子物理学との相性は悪い
|
究極の量子物理学である。
既存の量子物理学の自然(nature)と調和している部分を包含している
|
◎テーブル ニュートン力学と相対相対性理論、マクスウェルの電磁気学、量子論、
量子力学、素粒子物理学の標準模型(場の量子論)… を包含している
→ニュートン力学と相対相対性理論、マクスウェルの電磁気学、量子物理学、
素粒子物理学の標準模型… の自然(nature)と調和している部分を包含している。
◎テーブル 質量は、エネルギーである。
質量とエネルギーは、100%等価である
あらゆる質量がエネルギーを持つと同時に
あらゆるエネルギーは、すべて質量を持つ。
→質量はエネルギーである。そして、エネルギーは質量である。
質量とエネルギーは、100%等価である。
(あらゆる質量がエネルギーを持つと同時に
あらゆるエネルギーは質量を持つ)
◎テーブル 質量エネルギーは、エネルギーの一部に過ぎない。
→ 質量エネルギーは、エネルギーの一例に過ぎない。
◎テーブル該当部分 他にも読点の追加あり
2017年7月17日 2.13→2.13.1
結果1
《特殊相対性理論と光速不変の原理》
◎ それは、「空間を膨張させる方向、時間の流れを遅くさせる方向」に変化させているのである。
→ それは、「空間を膨張させる方向、時間の流れをスローダウンさせる方向」に変化させているのである。
◎この「空間を膨張させる、時間の流れを遅くさせる」という効果は
→この「空間を膨張させる、時間の流れをスローダウンさせる」という効果は
◎該当部分(《“時空の曲がり”&重力場の実体像》以下も同様)
時間の流れを遅くさせる→時間の流れをスローダウンさせる
◎「空間を収縮させる、時間の流れを早くさせる」という効果が、→「空間を収縮させる、時間の流れをスピードアップさせる」という効果が、
◎時間の流れが早くなり──
→時間の流れがスピードアップし──
◎時間の流れが遅くなる、ということになる。
→時間の流れがスローダウンする、ということになる。
◎空間が収縮し、時間が早く進む。
→空間が収縮し、時間の流れがスピードアップする。
(=時空が膨張(&スローダウン)する)
◎空間が膨張し、時間が遅く進む。
(=時空が膨張する)
→空間が膨張し、時間の流れがスローダウンする。
(=時空が膨張(&スローダウン)する)
◎時間の流れの遅れが生じる効果が存在するだけで十分であった。
→時間の流れのスローダウンが生じる効果が存在するだけで十分であった。
◎時間の流れの遅れがありさえすれば、光速不変が説明できることがわかる。
→時間の流れのスローダウンがありさえすれば、光速不変が説明できることがわかる。
◎時間の流れの早まり”が生じる効果があれば、十分であることがわかる。
→時間の流れのスピードアップ”が生じる効果があれば、十分であることがわかる。
◎時間の流れの早まりさえあれば、光速不変が説明できることがわかる。
→時間の流れのスピードアップさえあれば、光速不変が説明できることがわかる。
→
◎該当部分(以下も同様)
遅くなる。→スローダウンする。
◎該当部分(以下も同様)
早くなる。→スピードアップする。
◎
該当部分(以下も同様)
膨張(&遅延)
→
膨張(&スローダウン)
◎該当部分(以下も同様) 収縮(&早まり)
→収縮(&スピードアップ)
◎「空間の膨張と時間の
遅れ」をもたらすことになる。
→「空間の膨張と時間の流れの
スローダウン」をもたらすことになる。
◎該当部分(以下も同様) 遅れ→スローダウン
◎該当部分(以下も同様) 早まり→スピードアップ
◎
“剛体中で、時間の流れが遅くなること”も必要であった。
→
“剛体中で、時間の流れがスローダウンすること”も必要であった。
◎
「時間の流れを遅くさせている効果」が生まれるのか?
→「時間の流れをスローダウンさせている効果」が生まれるのか?
◎地球
が相対的に早く時間が進んでいるならば──
→地球
の時間の流れが相対的にスピードアップしているならば──
◎
※例えば、“地球に高速で降り注ぐミューオン”の寿命が延びることも、やはり、そこでも、高速で運動するミューオン自身が生じさせる“相対的に「運動方向の重力子の量が多くなる効果(&運動と反対方向の重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)
が、“ミューオンの中での素スピノールの“転回数の低下”を生じ、寿命が延びる── と説明できる
→
※例えば、“地球に高速で降り注ぐミューオン”の寿命が延びることも、やはり、そこでも、高速で運動するミューオン自身が生じさせる“相対的に「運動方向の重力子の量が多くなる効果(&運動と
は反対方向の重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)
が、“ミューオンの中での素スピノールの“転回数の低下”、すなわち、時間の流れのスローダウンを生じ、寿命が延びる── と説明できる
◎
すなわち、“測定機器(剛体)の運動”によって、「運動にともなって、運動方向に放出される重力子の量が多くなる効果(&運動と反対方向に放出される重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)が生じる結果、「剛体を収容する
空間が膨張し、そこでの時間の流れが遅くなる」ので、期待した“誤差”を100%観測できなくなるのは当然なのだ── と説明できるのである。
→ すなわち、“測定機器(剛体)の運動”によって、「運動にともなって、運動方向に放出される重力子の量が多くなる効果(&運動と
は反対方向に放出される重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)が生じる結果、「剛体を収容する
空間が膨張し、そこでの時間の流れがスローダウンする」ので、期待した“誤差”を100%観測できなくなるのは当然なのだ── と説明できるのである。
《“時空の曲がり”&重力場の実体像》
◎
アインシュタインは、一般相対性理論の中で、抽象的なリーマン幾何学を用いて導いたアインシュタイン方程式をもとに、重力は“時空の曲がり”によって生じる(重力場は“時空の曲がり”である)とエレガントに説明した。
→ アインシュタインは、一般相対性理論の中で、(連続な時空&微分可能性を前提にする)抽象的なリーマン幾何学を用いて導いたアインシュタイン方程式を根拠にして、重力は“時空の曲がり”によって生じる(重力場は“時空の曲がり”である)とエレガントに説明した。
◎ なぜなら、(“2D平面の曲がり”は、確かにイメージできるが)、“3D空間の曲がり”そのものを、直接、具体的にはっきりとイメージすることが困難だからである。
→ なぜなら、(連続な時空を前提にしながら“2D平面の曲がり”をイメージすることは、確かにできるが)、連続な時空を前提にしながら“3D空間の曲がり”そのものを、直接、具体的にはっきりとイメージすることは、困難だからである。
◎※アインシュタイン自身にとっても、“3D空間の曲がり”を具体的にイメージすることが困難であったことは次の記述から読みとれる。
→ ※アインシュタイン自身にとっても、連続な時空を前提にしながら“3D空間の曲がり”を具体的にイメージすることが困難であったことは次の記述から読みとれる。
◎抽象的な数学(数式)の力を借りて、それを表記しようとする努力をしたのだと考えられる。
→抽象的な数学(数式)の力を借りて、それを表記しようとする努力をしたのである。
◎※左側に比べ、右側は、質量とともに、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の存在数が、2倍になっている。
すなわち、この図より、質量の大きさに比例して、「重力ポテンシャルエネルギーの単位距離当たりの変化量」が大きくなること、すなわち、重力場が大きくなることが読み取れる。
→※左側に比べ、右側の質量が2倍になっているのにともなって、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の存在数が、2倍になっていることが示されている。
なお、質量の大きさに比例して、「重力ポテンシャルエネルギーの単位距離当たりの変化量」、すなわち、重力場が大きくなるのだった。(→《重力の実体像》)
◎実際は、雑然としており、
→実際は、下図のように雑然としており、
◎追加
|
|
|
 |
◎ その様子を頭の中に想像することは、難しくないだろう。
→ 不連続な時空を前提にしていれば、その様子を頭の中に想像することは、難しくないだろう。
◎途切れず限りなく広がっていく。→途切れず限りなく広がって存在している。
◎空間が収縮し、時間が速く進む。→空間が収縮し、時間の流れがスピードアップする。
(=時空が収縮する(&スピードアップする))
◎該当部分(以下も同様) 早まる→スピードアップする
◎空間が膨張し、時間が遅く進む。
(=時空が膨張する)
→空間が膨張し、時間の流れがスローダウンする。
(=時空が膨張する(&スローダウンする))
◎ つまり、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、位置(どの“2LP球殻”に位置するか、“2LP球殻”の中のどこに位置するか)に応じて、変化しているからこそ、“時空が曲がり”が存在しているのである。』が位置(「どの“2LP球殻”に位置するか」、「“2LP球殻”の中のどこに位置するか」)に応じて変化していることが、空間の膨張や時間の流れが変化していること、すなわち、“時空が曲がっている”ことに相当しているのだ。
→ つまり、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、位置(どの“2LP球殻”に位置するか、“2LP球殻”の中のどこに位置するか)に応じて、変化しているからこそ、“時空が曲がり”(=“空間”や“時間の流れ”が変化していること)が存在しているのである。
◎※「“2LP球殻”の中のどこに位置するか」というのは、下図のように、たとえ、たった1つの“2LP球殻”の中においても、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の密度が、変化しうると考えられるからである。
※たった1つの“2LP球殻”の中においても、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の密度が、変化しうることが図から読み取れる。 つまり、たった1つの“2LP球殻”の中においても、“時空の曲がり”が創発できるのである。
※なお、「どの“2LP球殻”に位置するか」を変化させることによって、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の密度が変化すること、すなわち、“時空の曲り”が創発できるのは自明なことである。 |
→ 「どの“2LP球殻”に位置するか」とは、下図からわかるものである。
すなわち、“2LP球殻”の位置の変化(r=2nLPにおけるnの変化)にともなって生じている時空の曲りである。
これは、自由落下運動によって、消すことができる時空の曲りに相当している。
一方の「“2LP球殻”の中のどこに位置するか」とは、下図からわかるものである。
すなわち、上図のように、たった1つの“2LP球殻”の中においても『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の密度が変化しうることにともなって生じている時空の曲りである。
これは、自由落下によって消せない、時空の曲りに相当する。
※なお、以上のことは、「地面に垂直な方向のみに重力が働き、地面に水平な方向には重力が働かない」理由を説明していると思われる。
◎ 時空の曲りの有無は、次のような性質から導かれるともいえる。
→いずれにしても、時空の曲りの有無は、次のような性質から導かれるとも言える。
◎ 削除 “3Dの球殻(厚さ2LP)”は、本来は、想像上のものに過ぎない。
たたじ、想像上のものと言えど、もし、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、位置(どの“2LP球殻”に位置するか、“2LP球殻”の中のどこに位置するか)に応じて、変化していれば、想像上の球殻の中心に、質量が存在していると考えられる。
逆に、もし、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、位置(どの“2LP球殻”に位置するか、“2LP球殻”の中のどこに位置するか)に応じて、変化していなければ、その想像上の球殻の中心に、質量が存在していないと考えられる。
※なお、以上のことは、「地面に垂直方向のみ重力が働き、地面に水平な方向には重力が働かない」理由を説明する。
◎2カ所 空間の膨張度&時間の流れが
→空間の膨張度&時間の流れのスピードが
◎ つまり、(原始ヒッグス場の上の)『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』は、重力場=“重位勾配”と、“時空の曲がり”=「空間の膨張度の変化&時間の流れの変化」の両方を創発しうるのだ。
→ つまり、(原始ヒッグス場の上の)『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』は、重力場=“重位勾配”のみならず、“時空の曲がり”=「空間の膨張度の変化&時間の流れのスピードの変化」も創発しうるのだ。
◎アインシュタインの驚異的な洞察を、理解するカギなのだ。→アインシュタインの驚異的な洞察を理解するカギなのだ。
◎ ※以上の説明によれば、“時空の曲がり”&重力場と解釈できるもの、3D空間における実体像を、(『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』として)頭の中に、しっかりイメージできる。
→ ※以上の説明によれば、重力場、および、“時空の曲がり”と解釈できるもの、3D空間における実体像を、(『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』として)頭の中に、しっかりイメージできる。
◎ 重力場(=“重位勾配”)と解釈できる『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』の働きのおかげで、地球は、太陽に引き寄せられ続け── 公転し続けていることになる。
→ 「太陽が作る重力場(=“重位勾配”)」と解釈できる『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』の働きのおかげで、地球は、太陽に引き寄せられ続け、「時空の流れるプール効果」と解釈できる地球の運動エネルギー相当する『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』の働きのおかげで(ほぼ)等速運動する結果、地球の公転が実現していることになる。
◎ 一方で、“時空の曲がり”とも解釈できる『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』のおかげで、“時間の流れる早さ”や“空間の膨張度”は変化する。
→ 一方で、“時空の曲がり”とも解釈できる『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』のおかげで、“時間の流れのスピード”や“空間の膨張度”は変化する。
◎ そして、重力場と“時空の曲がり”は、同一の実体によって担われているので── 「重力場とは、“時空の曲がり”である」という“短絡的な説明”も、ありえないこともないことになる。
→ そして、重力場と“時空の曲がり”は、同一の実体によって担われているので── 「重力場とは、“時空の曲がり”である」という“短絡的な説明”も、ありうることになる。
◎曖昧な(やや不正確な)ものだと言わざるをえないだろう。
→曖昧な(やや不正確な)ものだと言わざるをえないと思われる。
◎ なぜなら、「重力場とは、“時空の曲がり”である」という説明は、「カエルは、細胞の集合である。 人も、細胞の集合である。 だから、“カエルとは、人である”」というレベルものであるおそれがあるからである。 詳細な検討は、今後の課題である。
→ なぜなら、「重力場とは、“時空の曲がり”である」という説明は、「カエルは、細胞の集合である。 人も、細胞の集合である。 だから、“カエルとは、人である”」という説明と同様であると指摘されても仕方ないことを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)および3Steps理論が示しているからである。
◎ ※アインシュタインは、“時空の曲がり”についての明確で具体的な描像(“幾何的な実体像”)を持たないもまま、抽象的なリーマン幾何学の力を借りて、一般相対性理論、すなわち、アインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)を作り上げた。 その抽象的な数式は、実は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、分布(配置)の総和」を近似的に表現しているにすぎないと考えられる。
→ ※アインシュタインは、“時空の曲がり”についての明確で具体的な描像(“幾何的な実体像”)を持たないまま、抽象的なリーマン幾何学の力を借りて、一般相対性理論、すなわち、アインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)を作り上げた。 その抽象的な数式は、実は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、分布(配置)の総和」を近似的に表現しているものにすぎないと考えられる。
《重力場と“重力線”》
◎定義できる。→定義することができる。
◎あらゆる場所に“重位
勾配”が存在している。
→あらゆる場所に“重位勾配”が存在しうる。
◎ それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、本来は、雑然と放出されているからである。
→ それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、本来は、下図のように雑然と放出されているからでももある。
 |
|
 |
◎すなわち、“重力線”は、下図のように「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、整然と直線的に重力子が放出されていると仮定した図と、本質的に等しいものになると考えられる。
→ したがって、“重力線”は、下図のように「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、整然と直線的に重力子が放出されていると仮定した図と、本質的に等しいものになると考えられる。
したがって、“重力線”は、下図のように、便宜上、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、整然と(直線的に、対称的に)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されているように図示したものと、本質的に等しいと考えられる。
◎
※ 図のように、整然と、直線的、対称的に存在すると仮定して、図示しているものが、実は、“重力線”に相当するものに、本質的に等しいと考えられる。
実際は、雑然と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されており── 図のように、直線的に次々に重力子が放出されることはない。 本来は、『「厚さ2LPの球殻」に存在する存在する数は、常に、ほぼ一定である』という条件を満たしているだけである。
その雑然さが、まさに、「あらゆる場所に“重位勾配”が存在している」ことを支えると考えられる。
|
→
※左図のように、便宜上、整然と(直線的、対称的に)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されているように図示したものが、実は、右図の“重力線”と、本質的に同等であると考えられる。
※なお、「重力子の個数」と「“重力線”の本数」は比例しているはずだが、当然、「重力子の個数」と「“重力線”の本数」は等しくない。 よって、上図の数量関係は正確なものではない。
(→下記の計算によると、厚さ2LPの球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数をNM〔個〕とすると、“重力線”の本数は、NM×2c2LP[本](≒NM×2.9×10-18[本])ということになる)
|
◎ また、球面の面積は半径rの2乗に比例する(球面積S=4πr2)ので、物体から距離が大きくなるほど、距離の2乗に反比例して、“重力線の密度”が減ることになる。
よって、中心の物質に近づくほど、物体から距離の2乗に反比例して、“重力線の面密度”(∝「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度)が増えるので、“重位勾配”、つまりは重力も大きくなると考えられる。
この“重力線の密度”と“重位勾配”の関係は── ニュートンの万有引力の法則の式と合致する。
つまりは、“重力線の面密度”=“重位勾配”の大きさ=“重力の大きさ”=“重力場の強さ”=『「厚さ2LPの球殻が持つエネルギーの時間&空間平均の値」E平均=NMEG/4πn2』/2LP ∝「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度 ∝“時空の曲がりの強さ”ということになる。
※計算によると、質量Mが作る“重力線”の本数は、Mc2×2LP×1/MG=NMEG×2LP×1/MG=NMc2×2LP[本]となる。
半径rの球面における面密度を計算すると、NMEG×2LP×1/MG×(1/4πr2)=(NMEG/4πn2)×1/2LP×1/MG[N/kg]となり、ある他の質量[kg]に対する重力になる。
「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度= (4LP2NM/4πr2)である。
よって、「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度×EG×1/2LP=“重力線の面密度”=重力 となる。
→ 球面の面積は半径rの2乗に比例する(球面積S=4πr2)ので、物体からの距離が大きくなるほど、その距離の2乗に反比例して、“重力線の球面密度”(∝「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度)が減ることになり、重力(“重位勾配”)も小さくなる。 (逆に、物体の中心に近づくほど、物体の中心からの距離の2乗に反比例して、“重力線の球面密度”(∝「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度)が増えることになり、重力(“重位勾配”)も大きくなる。)
この“重力線の球面密度”と重力(“重位勾配”)の関係は── ニュートンの万有引力の法則の式とも調和している。
したがって、以上をまとめると、“重力線の面密度”=“重位勾配”の大きさ=“重力の大きさ”=“重力場の強さ”=『「厚さ2LPの球殻が持つエネルギーの時間&空間平均の値」E平均=NMEG/4πn2』/2LP ∝「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度 ∝“時空の曲がりの強さ”ということになる。
※半径r〔m〕の球面における“重力線”の球面密度は、ある他の質量[kg]に対する重力〔N/kg〕に相当する。
よって、質量Mが作る“重力線”の本数をn重力線とすると、 n重力線×(1/4πr2)=(NMEG/4πn2)×1/2LP×1/MG[N/kg]となるはずである。 (なお、r=2nLPである)
計算すると、質量Mが作る“重力線”の本数は、n重力線=NMEG×2LP×1/MG=NM×2c2LP[本]となる。
一方、厚さ2LPの球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数は、 NM〔個〕である。
したがって、厚さ2LPの球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数を、2c2LP(≒2.9×10-18)〔倍〕すると、“重力線”の本数になることになる。
このように“重力線”の本数と、厚さ2LPの球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数が比例定数で結ばれている事実は、“重力線”の図の理解を助ける。
◎ もし、同じ質量を持つ物体(天体を含む)の“サイズ(大きさ)”が変化すれば── 物体の周囲の、“重力線”の密度=重力場の大きさ=“重位勾配”の大きさ∝“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度∝“時空の曲がりの大きさ”も、変化する。
→ もし、同じ質量を持つ物体(天体を含む)の“サイズ(大きさ)”のみが変化すれば── 物体の周囲の、“重力線”の密度=重力場の大きさ=“重位勾配”の大きさ∝“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度∝“時空の曲がりの大きさ”も、変化する。
◎ 物体(天体を含む)のサイズが小さくなる(コンパクト化する)ほど、物体周囲の“重力線”の密度が高くなり、周辺の重力、“重位勾配”、“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度、時空の曲がり…が大きくなっていることが読み取れる。
しかし、物体が、同じ質量のままコンパクト化するほど── “重力線”の密度が高い領域が増えることが読み取れる。
→ 物体(天体を含む)のサイズが同じ質量のまま小さくなる(コンパクト化する)ほど、物体周辺(近辺)の“重力線”の密度が高くなり、物体周辺(近辺)の「重力、“重位勾配”、“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度、時空の曲がり…」が大きくなっていることが読み取れる。
しかも、物体が、同じ質量のまま小さくなる(コンパクト化する)ほど── 物体周辺において“重力線”の密度が高い領域が増えることも読み取れる。
(物体周辺において“重力線”の密度が高い領域が増えるということは、物体周辺において時空が膨張(&スローダウン)していると言うことに他ならない)
◎※なお、上の3つの図は、遠方(周囲)の“重力線”が、どれも同じになっており、これは“質量の大きさはどれも同じ”として、図示してある。
→※なお、上の3つの図は、物体周囲(遠方)の“重力線”が、どれも同じになっている。 これは物体が“同じ質量のまま”小さくなる(コンパクト化する)ときの様子を、図示してあるからである。
◎ 重力場に、非線形性は存在しない理由はではない理由をまとめると、次のようになる。
→ 重力場に、非線形性が存在しない理由をまとめると、次のようになる。
2017年7月14日 2.12→2.13
結果1
《等価原理》
◎ そして、大きな質量を持つ物体から放出される重力子による影響(重力)と、自由落下しながら進行方向に放出される重力子による影響(慣性力)は、ピッタリと打ち消し合う形となる。
→ そして、大きな質量を持つ物体から放出される重力子による効果(重力)と、(自由落下によって)加速運動しながら進行方向に新たに重力子が放出されるようになる効果(慣性力)は、ピッタリと打ち消し合う形となる。
◎追加
| ※「重力」と「加速運動」が等価なので、「重力」と「加速運動にともなう慣性力」は、大きさが等しく向きが逆となり、100%打ち消し合う。 |
◎ その結果、自由落下する物体は、見かけ上、“無重力状態”として観測される。
→その結果、物体が自由落下する系において、見かけ上、“無重力状態”が観測される。
◎ つまり、慣性力(加速運動に伴う)と重力が、ともに重力子の放出で説明できることが、アインシュタインの等価原理(この慣性力と重力(重力場)は全く等しい)を根底で支えていると言える。
→つまり、「加速運動(およびそれに伴う慣性力)」と「重力」が、ともに重力子の放出で説明できることが、アインシュタインの等価原理(この加速運動と重力(重力場)は全く等しい)を根底で支えていると言える。
◎ このことは、慣性質量と重力質量が、ともに『放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和を材料として創発するもの』として、統合的に説明できること、すなわち、本質的に、同等であることを示していると思われる、
→さらに、慣性質量と重力質量が、ともに『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」と関連して創発するもの』として統合的に説明できることも、慣性質量と重力質量が、本質的に、同等であることを支えていると思われる。
◎ ※ある静止質量Mの物体が、観測者の方に向かって速度vで等速運動している系を考える。
→ ※ある静止質量Mの物体が、観測者の方に向かって速さv〔m/s〕で等速運動している系を考える。
◎前項《重力子の働きと慣性》で述べたように、等速運動している物体からも重力子が放出されている。
等速運動している限り、その運動によって物体から放出される重力子の総和を材料にして、新たに“重位勾配”が生じることはないので、ある静止質量Mの物体が、観測者の方に向かって速さv〔m/s〕で等速運動している限り、“静止質量M”がもたらす重力より重力が大きくなることはないと考えられる。
→ 前項《重力子の働きと慣性》で述べたように、等速運動している物体からは、(静止質量エネルギーに相当する重力子のみならず)その等速運動に伴う運動エネルギーに相当する重力子が放出されている。
等速運動している限り、その運動エネルギーに相当する(放出される)重力子の総和は不変性であり新たに“重位勾配”が生じることがないので、ある静止質量M〔kg〕の物体が観測者の方に向かって速さv〔m/s〕で等速運動している限り、その等速運動している物体が観測者にもたらす重力が、(質量がより大きくなっているのに関わらず)“静止質量M〔kg〕”がもたらす重力より大きくなることはないと考えられる。
◎ しかし、もし、ある静止質量Mの物体が、観測者の方に向かって加速運動しているときには── “静止質量M”がもたらす重力よりも、大きな重力が生じると考えられる。
なぜなら、加速運動によって、新たに物体から放出される重力子の総和を材料として、新たな“重位勾配”が生じていると考えられるからである。
→ しかし、もし、ある静止質量M〔kg〕の物体が、観測者の方に向かって加速運動しているときには── “静止質量M〔kg〕”がもたらす重力よりも、大きな重力が生じると考えられる。
なぜなら、加速運動によって、新たに物体から放出される重力子の総和の変化によって、新たな“重位勾配”が生じていると考えられるからである。
《特殊相対性理論と光速不変の原理》
◎一見、“光速度不変の原理”を破ってしまうことを意味するように思われてしまうかしれない。
→一見、“光速度不変の原理”を破ってしまうように思われるかもしれない。
◎ すなわち、この“原始ヒッグス場”こそが、“光速度不変の原理”を破っているどころか、逆に根底で支えているのである。
→ すなわち、この“原始ヒッグス場”は、“光速度不変の原理”を破っているどころか、逆に根底で支えているのである。
◎ 光速c(km/s)=30万km/sであるとして話を進める。
簡単にするため、光源からちょうど30万kmはなれた観測者を考える。
→以下で、観測者も光源も、剛体であるとする。 なお、“剛体”というのは、特殊相対性理論の前提であった。
|
『ここから述べる理論は、すべての電気力学と同様に剛体の運動学にもとづいている。なぜならば、この種の理論のいうところの主張は、剛体(座標系)、時計、およびいろいろの電磁過程のあいだの関係について触れるものだからである』
(p.20 『アインシュタイン選集1』 [A1]運動している物体の電気力学について アインシュタイン)
|
光速c(km/s)=3×108〔m/s〕(秒速30万km)であるとして話を進める。
簡単にするため、光源からちょうど、3×108〔m〕(30万km)離れた観測者を考えてみよう。
◎ 次に、観測者が、(“原始ヒッグス場”に対して)速さv〔m/s〕で、光源の方に向けて等速運動しているとする。
→ 次に、観測者が、下図のように、(“原始ヒッグス場”に対して)速さv〔m/s〕で、光源の方に向けて等速運動しているとする。
◎ すると、自然に考えると(ガリレイ変換で考えると)── 「1秒間に光が、“原始ヒッグス場”の上で30万km進み、同じ1秒間に観測者は“原始ヒッグス場”の上でvメートル進むのだから、観測者から見て、光は、合わせて1秒間に、30万km+v(m)進むことになる── つまり、光速は、c+vとなり、観測者にとっての光速は、秒速30万kmを越えてしまうことになる」という結論に至ってしまうだろう。
→ すると、自然に考えると(ガリレイ変換で考えると)── 「1秒間に光が、“原始ヒッグス場”の上で30万km(3×108〔m/s〕)進み、同じ1秒間に観測者は“原始ヒッグス場”の上でvメートル進むのだから、観測者から見て、光は、合わせて1秒間に、3×108〔m〕+v(m)進むことになる── つまり、光速は、c+v〔m/s〕となり、観測者にとっての光速は、秒速30万kmを越えてしまうことになる」という結論に至ってしまうだろう。
◎ →
→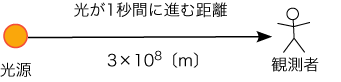
◎  →
→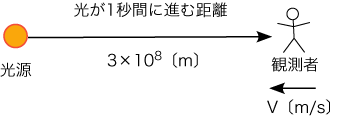
◎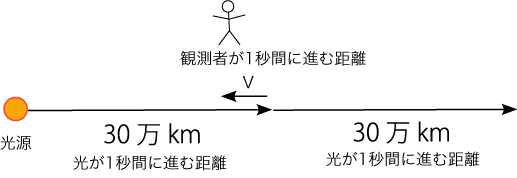 →
→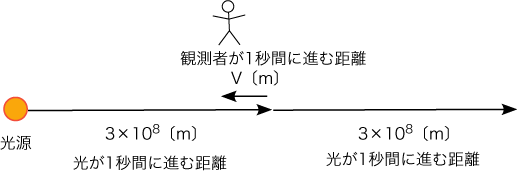
◎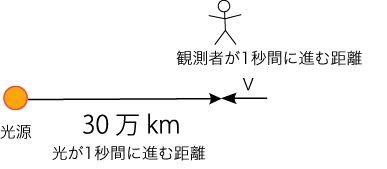 →
→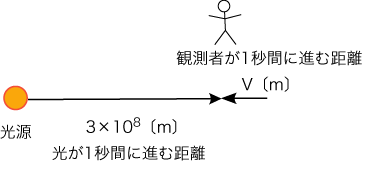
◎
※より厳密な図示の仕方があるかもしれないが、おおよその意味は読み取れると思われる。
※上側が、“静止した観測者の座標系”からみた“30万km”であるのに対し、下側は、“運動している観測者の座標系”からみた30万kmに相当する。
※上側が、「“静止した観測者の座標系”からみた、3×108〔m〕(30万km)」であるのに対し、下側は、「“運動している観測者の座標系”からみた3×108〔m〕(30万km)「に相当する。
|
→
※より厳密な図示の仕方があるかもしれないが、おおよその意味は読み取れると思われる。
※上側が、「“静止した観測者の座標系”からみた、3×108〔m〕(30万km)」であるのに対し、下側は、「“運動している観測者の座標系”からみた3×108〔m〕(30万km)」に相当する。
この図より、静止していた観測者にとっての「3×108〔m〕(30万km)」と、速さv〔m/s〕で運動していた観測者にとっての「3×108〔m〕(30万km)」とは、その実体が、異なるものになっているものであることがわかる。
|
◎ 静止した観測者と、vで等速運動している観測者の間で何かが決定的に違っているはずである。
→ 静止した観測者(剛体)と、速さv〔m/s〕で等速運動している観測者(剛体)の間で何かが決定的に違っているはずである。
◎ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、すでに繰り返し説明してきたように、“運動する物体(剛体)は、運動方向に重力子を放出していること”が、静止している状態と決定的に違うことを示す。
すなわち、物体(剛体)が慣性運動(等速運動)している間は、その運動方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されて続けており、それが「時空の流れるプール」の効果を生まれていることが、物体(剛体)が静止している状態とは、決定的に異なっているのである。
→ すでに繰り返し説明してきたように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、“運動する物体(剛体)は、運動方向に、(外部)運動エネルギーに相当する重力子を放出していること”が、静止している状態と決定的に違う。
すなわち、物体(剛体)が慣性運動(等速運動)している状態とは、その運動方向に((外部)運動エネルギーに相当する)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されて続けて「時空の流れるプール効果」が生み出され続けている状態であり、静止している状態とは、決定的に異なっているのである。
◎ よって、まさにその運動方向へ放出され続けている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が、運動方向の前方に存在する時空の性質を変化させている結果、上の例のような“光速度不変”が成立していると考えられるのである。
→ したがって、まさにその運動方向へ放出され続けている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が、運動方向の前方に存在する時空の性質を変化させている結果、上の例のような“光速度不変”が成立していると考えられるのである。
◎慣性運動(等速運動)は、「運動方向の前方に存在する時空」を、具体的に、どのように変化させているだろうか?
「空間を膨張させる方向、時間の流れを遅くさせる方向」に変化させているのである。
→ 上図のように光源に観測者が向かっていくような慣性運動(等速運動)は、「運動方向の前方に存在する時空」を、具体的に、どのように変化させているだろうか?
それは、「空間を膨張させる方向、時間の流れを遅くさせる方向」に変化させているのである。
◎(原始ヒッグス場の上での)速さv〔m/s〕の運動が持つ、
→(原始ヒッグス場の上での)速さv〔m/s〕の等速運動が持つ、
◎ それは、光源の方が等速運動して近づいていても、同様である。 すなわち、この場合、光源は、その運動する方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出し続けていて、それが運動方向の前方に存在する時空の性質を変化させている結果、“光速度不変”を成立させると考えられるのである。
→ それは、光源の方が速さv〔m/s〕の等速運動で観測者に向かって近づいていく場合も、同様である。 すなわち、この場合、ふつうに考えれば、光速がc+v〔m/s〕になりそうなものを、実際は、この光源は、その運動する方向に(その運動エネルギーに相当する)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出し続けていて、それらの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が運動方向の前方に存在する時空の性質を(「空間を膨張させる、時間の流れを遅くさせる」方向に)変化させている結果、観測者は、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測するのである。
◎ (静止質量エネルギーによって、もともと放出されている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」から、差っ引かれることになると考えられる)
→ (静止質量エネルギーによって、もともと放出されている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」から、差し引かれることになると考えられる)
◎ ※すなわち、“4面体”が、時空に占める割合が多くなるほど、空間が収集し、時間の流れが速くなり──
→ ※まとめると、“4面体”が、時空に占める割合が多くなるほど、空間が収縮し、時間の流れが早くなり──
◎空間が収縮し、時間が速く進む
→空間が収縮し、時間が早く進む
◎運動方向と逆方向への重力子の放出量が減っていたりする結果
→運動とは逆方向への重力子の放出量が減っていたりする結果
◎ 以上が、“光速度不変の原理”(を支持する現象&観測)が、 どのようなしくみで創発するのかについての説明である。
◎ 以上が、“光速度不変の原理”(を支持する現象&観測)が、 どのようなしくみで(なぜ)実現しているのかについての(創発的な)説明である。
◎ そして、なぜ“ローレンツ収縮”が(1−(v/c)2)1/2の割合で起こるかと言えば、「運動する物体(剛体)を収容する時空」、すなわち、「剛体の後端から前端の時空」が、“運動軸に沿って、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で、膨張しているからであると考えるとつじつまが合う。
すなわち、物体を内に含む時空が(運動方向に)膨張するからこそ、物体自体が逆に(運動方向に)収縮するように観測されるのである。 これが“ローレンツ収縮”がどのようなしくみで創発するかについての説明である。
→ そして、なぜ“ローレンツ収縮”が(1−(v/c)2)1/2の割合で起こるかと言えば、「等速運動する物体(剛体)を収容する空間」、すなわち、「等速運動する剛体の後端から前端の空間」が、“運動軸に沿って、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で、膨張しているからであると考えるとつじつまが合う。
すなわち、物体(剛体)を内に収容している空間が(運動方向に)膨張するからこそ、物体(剛体)自体が逆に(運動方向に)収縮するように、第三者によって外側から観測されるのである。
これが“ローレンツ収縮”がどのようなしくみで(なぜ)実現するのかについての(創発的な)説明である。
◎ それでは、そもそも、なぜ、「剛体の後端から前端の時空」が、“運動軸に沿って、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で、膨張しているのだろうか?
→ それでは、そもそも、なぜ、「剛体の後端から前端の空間」が、“運動軸に沿って、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で、膨張しているのだろうか?
◎時間の遅れが生じる効果が存在するだけで十分であった。
→時間の流れの遅れが生じる効果が存在するだけで十分であった。
◎時間の遅れがありさえすれば、光速不変が説明できることがわかる。
→時間の流れの遅れがありさえすれば、光速不変が説明できることがわかる。
◎ これは、観測者の運動の前方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増加することによって、生ずる効果である。
→ これは、観測者(剛体)の等速運動の方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増加することによって生ずる効果である。
◎“空間の収縮と、時間の進み”が生じる効果があれば、十分であることがわかる。
→“空間の収縮と、時間の流れの早まり”が生じる効果があれば、十分であることがわかる。
◎時間の進みがありさえすれば、光速不変が説明できることがわかる。
→時間の流れの早まりさえあれば、光速不変が説明できることがわかる。。
◎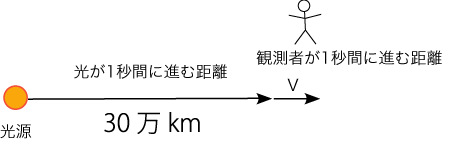 →
→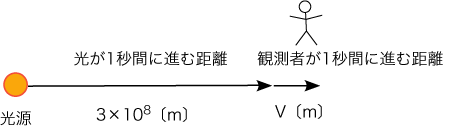
◎これは、観測者の運動の後方への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が、減少することによって、生ずる効果であると考えられる。
→これは、観測者(剛体)の運動とは逆方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が減少することによって生ずる効果であると考えられる。
◎
→
◎ つまり、ローレンツ収縮、および、ローレンツ変換が成立するのは、運動する剛体における、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の前方への効果と後方への効果の相乗平均の効果が働くからであると理解できるのだ。
→ つまり、ローレンツ収縮の効果を示す式から予想される、「(等速運動をする)剛体の後端から前端の時空(剛体を収容する時空)」が“運動軸に沿って膨張(&遅延)している割合『(1/(1−(v/c)2)1/2』は、この2つの効果の相乗平均にぴったり等しいのである。
以上のことは、まさに、「(等速運動をする)剛体の後端から前端の時空(剛体を収容する時空)」が、『(1/(1−(v/c)2)1/2』の割合で膨張(&遅延)する理由を説明していると思われる。
すなわち、剛体が等速運動すると、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出数の増減が生じることによって、「運動方向の時空の膨張(&遅延)の効果」と「運動とは逆方向の時空の収縮(&早まり)の効果」の両方が生じ、それらの両方の効果の相乗平均として膨張(&遅延)するのである。
そして、だからこそ、「(等速運動をする)剛体の後端から前端の空間(剛体を収容する空間)」が、『(1/(1−(v/c)2)1/2』の割合で膨張するのである。
◎削除 このことにより、特殊相対性理論で、なぜ、“剛体”が前提とされていたかが、よく理解できる。
(アインシュタイン選集1 p.20 『これから述べる理論は、すべて電気力学と同様に剛体の運動学にもとづいている。 なぜならば、この種の理論のいうところの主張は、剛体(座標系)、時計、およびいろいろの電磁過程のあいだの関係について触れるものだからである。』)
すなわち、剛体だからこそ、「空間の膨張と時間の遅れ」と「空間の収縮と時間の進み」の相乗平均の効果が生じるのである。 だからこそ、ローレンツ収縮や、ローレンツ変換が成り立つのである。
◎ (1/(1−(v/c)2)1/2の数式が示すように「空間の膨張と時間の遅れ」と「空間の収縮と時間の進み」の相乗平均の効果は、トータルで、剛体を収容する「空間の膨張と時間の遅れ」をもたらすことになる。
剛体を収容する空間が膨張する結果、剛体自体は、逆に収縮しているように観測されるのである。
以上が、ローレンツ収縮がどのようにして生じるか、そして、ローレンツ収縮を意味する数式が、どうして、(1−(v/c)2)1/2 となるのかについての説明である。
→
つまり、ローレンツ収縮は、等速運度をする剛体を収容する空間が膨張するからこそ、生じるのである。
すなわち、剛体を収容する空間が膨張する結果、剛体自体は、逆に収縮しているように観測されるのである。
以上が、ローレンツ収縮がどのようにして生じるか、そして、ローレンツ収縮を意味する数式が、どうして、(1−(v/c)2)1/2 となるのかについての説明である。
※(1/(1−(v/c)2)1/2の数式が示すように、厳密には、「空間の膨張と時間の流れの遅れ」と「空間の収縮と時間の流れの早まり」の相乗平均の効果は、トータルで、剛体を収容する「空間の膨張と時間の遅れ」をもたらすことになる。
そして、この理由で、「(等速運動をする)剛体の後端から前端の時空(剛体を収容する時空)」が膨張(&遅延)するからこそ、ローレンツ収縮のみならず、ローレンツ変換が成立するのである。
このことにより、特殊相対性理論で、なぜ、“剛体”が前提とされていたかが、よく理解できる。
|
『ここから述べる理論は、すべての電気力学と同様に剛体の運動学にもとづいている。なぜならば、この種の理論のいうところの主張は、剛体(座標系)、時計、およびいろいろの電磁過程のあいだの関係について触れるものだからである』
(p.20 『アインシュタイン選集1』 [A1]運動している物体の電気力学について アインシュタイン)
|
すなわち、剛体だからこそ、「空間の膨張と時間の流れの遅れ」と「空間の収縮と時間の流れの早まり」の両方の効果が生じうるのであり── その結果(それらの効果の相乗平均として)ローレンツ収縮やローレンツ変換が成立するからである。
◎ ※運動する剛体中の時空の変化は、“相乗平均”で計算できる一方、剛体の外の時空の変化は、単純に、それぞれの別々に求められることになる。
→ ※運動する剛体中の時空の変化は、“相乗平均”で計算できる一方、剛体の外の時空の変化は、単純に、それぞれ別々に求められることになる。
◎ ※そもそも、なぜ、等速運動にともなって運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増えると、その方向に空間が膨張するのか?
→ そもそも、なぜ、等速運動にともなって運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増えると、その方向に空間が膨張するのか?
◎ 逆に、等速運動にともなって運動の逆方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が減ると、その方向に空間が収縮するのは、単純に、「“4角形”(縮みきったバネ)が原始ヒッグス場ユニットの“4面体”になる分だけ“スペースが減る”からである」と考えられる。 (詳細な検討は、今後の課題である)
→ 逆に、等速運動にともなって運動とは逆方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が減ると、その方向に空間が収縮するのは、単純に、「“4角形”(縮みきったバネ)が原始ヒッグス場ユニットの“4面体”になる分だけ“スペースが減る”からである」と考えられる。
このような理由の説明は、次の仮説に基づいていると言える。
仮説1.8.2.1 原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)を構成する、素スピノールが“運動している空間そのもの”が、“空間そのもの”に相当し、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”は、その空間を減らす(収縮させる)ような働きをし、“4角形”(縮みきったバネ)は、逆にその空間を回復させる(膨張させる)働きをする。
◎ 剛体内で“光速度はcだ”の観測が成り立つためには、運動にともなって、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で“剛体中の空間が膨張すること”だけでなく、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で“剛体中で、時間の流れ(時計の歩み)が遅くなること”も必要である。
→ ところで、剛体内で“光速度はcだ”の観測が成り立つためには、速さv〔m/s〕の等速運動にともなって、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で“剛体中の空間が膨張すること”だけでなく、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で“剛体中で、時間の流れが遅くなること”も必要であった。
◎ それでは、なぜ、等速運動ともなって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増加すると、「時間の流れを遅くさせている効果」が生まれるのか?
それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、光子が転回する原始ヒッグス場の“4面体”の足場の比率を減らすことによって── 光子を構成する素スピノールが転回する過程を妨げ、「光子の振動数、すなわち、単位時間あたりの、光子を構成する素スピノールが共転回する回数を減らすから」と考えられる。
→ それでは、なぜ、等速運動にともなって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増加すると、「時間の流れを遅くさせている効果」が生まれるのか?
それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増えるほど、光子が共転回しずらくなるからであると考えられる。
すなわち、それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が増加するほど、光子が共転回できる素スピノールを持つ「原始ヒッグス場の“4面体”」という足場の比率が減少する形になる結果、光子を構成する素スピノールの共転回の過程が妨げられて「光子の振動数(=単位時間あたりの、光子を構成する素スピノールの共転回数)」が減るからであると考えられる。
◎ この理由は、「光子を構成する素スピノールの転回周期Tを大きくするから」とも言えるので、こういいった説明は次の仮説に基づいていると言える。
仮説1.8.2
→ このような理由の説明は、次の仮説に基づいていると言える。
仮説1.8.2.2
◎正しければ、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で時間の流れが遅くなる原因は── 「運動方向の重力子の量が多くなる効果(&運動と反対方向の重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)と、剛体中の光子の転回(=時の刻み)を減らす効果が割合で(比例して)生じることであることになる。
→この仮説が正しければ、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で時間の流れが遅くなる理由は、「運動方向の重力子の量が多くなる効果(&運動と反対方向の重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)と、剛体中の光子の転回(=時の刻み)を減らす効果が同じ割合で(比例して)生じるからである、と言うことになる。
◎“光速度不変の原理”を根底で支えていていると言える。
→“光速度不変の原理”を根底で支えていると言える。
◎原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和)であることになる。
→原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和)である、言うことになる。
◎ ※もし、仮説が正しく、“4つの力”のすべてが、根底で、素スピノールの転回を介して創発しているのならば── あらゆる現象(物理現象、化学現象、天体現象、人生の営み、生理現象、社会現象…)における“時の流れ”が、根底で、素スピノールの転回に基づいて創発していることになる。
→ ※もし、仮説1.8.2.2が正しく、“4つの力”のすべてが、根底で、素スピノールの転回を介して創発しているのならば── あらゆる現象(物理現象、化学現象、天体現象、人生の営み、生理現象、社会現象…)における“時間の流れの遅れや早まり”が、根底で、素スピノールの転回のしやすさの変化に基づいて創発していることになる。
◎ そして、実際、4つののすべてが、根底で、素スピノールの転回によって創発していると説明できる。(→結果2)
→ そして、実際、4つの力を含むすべての物理的な力が、根底で、素スピノールの転回によって創発していると説明できる。(→結果2)
◎時の流れが、より(相対的に)遅くなるだけだからである
→時間の流れが、より(相対的に)遅くなるだけだからである
◎すなわち、双子のうちで、どちらか一方だけが相対的に時の流れが遅くなるだけなので、もし、例えば、宇宙船が地球を出発して、光速近くで運動してきた後帰ってきたとき、地球が相対的に早く時間が進んでいるならば── 「宇宙船を基準にすると、地球の方が光速近くで運動することになるから、地球の時間の流れの方が遅くなる」ということは実在しないことになるので、パラドックスは消滅する。
→つまり、双子のうちで、どちらか一方だけが相対的に時間の流れが遅くなるだけなので、もし、例えば、宇宙船が地球を出発して、長期間、光速近くで運動してきた後に帰ってきたとき、地球が相対的に早く時間が進んでいるならば── 「宇宙船を基準にすると、地球の方が光速近くで運動することになるから、地球の時間の流れの方が遅くなる」ということは実在しないことになるので、パラドックスは根底から消滅するのである。
◎これが、「ブラックホールの外に光が出て行けなくなる」ことの背後に存在している実体であると考えられる。
→これが、「ブラックホールの外に光が出て行けなくなる」ことの背後に存在していることであると考えられる。
◎“ミューオンの中での素スピノールの“転回数の低下”を生じ、寿命が延ばす── と説明できる。 なお、ミューオンの寿命ののびが(1/(1−(v/c)2)1/2の式に合致するということは、ミューオンは、剛体の一種である(内部構造を持つ)ことを意味していることに他ならない。 (→結果3)
→“ミューオンの中での素スピノールの“転回数の低下”を生じ、寿命が延びる── と説明できる。 なお、ミューオンの寿命ののびが(1/(1−(v/c)2)1/2の式に合致するということは、ミューオンは、剛体の一種である(内部構造を持つ)ことを意味している。 (→結果3)
◎削除 ※特殊相対性理論は、剛体の運動が仮に光速度c近づくほど、 mc2(1−(v/c)2)−1/2の式により、質量エネルギー(=静止質量エネルギー+運動エネルギー、=運動エネルギー(内部&外部))が無限大に近づくので、実際はありえないと説明したのだった。 しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、剛体の運動が、仮に光速度cに近づいても、質量エネルギー(=静止質量エネルギー+運動エネルギー、=運動エネルギー(内部&外部))が無限大に近づくことはないのであった。
同様に、原始ヒッグス場ユニットがすべて100%“4角形”(縮みきったバネ)になったとしても、“時空の膨張”が無限大に至ることはないと考えられる。 すなわち、“時空の膨張”を示す「c/(c−v)」の式も、時空が連続であることを前提とした“近似式”に過ぎないことを示している考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎“四次元時空連続体”を支える実体でもあることになる。
→“四次元時空連続体”を支える実体でもある、と言える。
◎ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、時空が不連続であることを前提としていることを意識して、より厳密に書けば、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)は、『不連続な時空上にある「四次元時空連続体」』を支える実体であるということになる。
→ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が「時空が不連続であること」を前提としていることを意識して、より厳密に書けば、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)は、『不連続な時空上にある「四次元時空連続体」』を支える実体である、と言うことになる。
◎ 「これは、やはり、エーテルではないのか? エーテルは、かつて否定されたので、矛盾しているのではないか?」という疑問が、生じるかもしれない。
次の理由で問題ない。
→ それでも、「これは、やはり、エーテルではないのか? エーテルは、かつて否定されたはずなので、問題ではないか?」という疑問が、生じるかもしれない。
しかし、ここに問題はない。 その理由をまとめると次のようになる。
◎「剛体を収容する、空間が膨張し、そこでの時間の流れが遅くなる」ので
→「剛体を収容する空間が膨張し、そこでの時間の流れが遅くなる」ので
◎ この“原始ヒッグス場”を構成する原始ヒッグス場ユニットは、物質でない(物質未満である)し、それ自体は質量をもたず、原則として運動(移動)もしない。
すなわち、
→ この“原始ヒッグス場”を構成する原始ヒッグス場ユニットは、物質でないし(物質未満であるし)、それ自体は質量を持たず、原則として、場所を移動させるような運動はしない。
つまり、
《重力場の線形性について(詳細版)》
◎(シュバルツシルト半径(ブラックホール)に至ってから以降は、もはやクォークやレプトンが維持されず、プレオン∴に分解される(EMOES宇宙論1)ので、そのプレオン∴1つ1つが、重力子エネルギーEG(=MGc2〔J〕)に相当する運動エネルギーK〔J〕を持ちうるということが、カギを握っていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である)
→※そのしくみ(からくり)とは、次のようなものだと考えれる。
物体は、初めてシュバルツシルト半径までコンパクト化されるまでに、全質量は、2倍に至る。(G→2Gの変化に相当)
したがって、この効果によって生み出される(仮の)「事象の地平面の面積」は、『(M/MG)×2×4LP2』〔m2〕となる。
(そして、2倍となるのは、獲得する運動エネルギーを新たな質量として、カウントするからである。
その後、物体が、よりコンパクト化が進むと、もはやクォークやレプトンが維持されず、プレオン∴に分解される
(→EMOES宇宙論1)。
さらには、そのプレオン∴1つ1つは、重力子エネルギーEG(=MGc2〔J〕)に相当する運動エネルギーK〔J〕を獲得できるポテンシャルを持つ。 しかし、1つ1つのプレオン∴は、ブラックホールの中心に至るまでに、必ず重力子エネルギーEG(=MGc2〔J〕)を獲得するというものではなくて、やはり、(ブラックホールの中心に至るまでに放出される)「重力ポテンシャルエネルギー〔J〕」に比例した運動エネルギーK〔J〕を獲得するだけである。
ブラックホールの中心までコンパクト化が進むまでに、ある1つプレオン∴に運動エネルギーK〔J〕を与えるところの「重力ポテンシャルエネルギーE〔J〕」は、どうなるであろうか?
(それは、元の全質量(M〔kg〕)に比例しているはずであるという説明だけでは足りない。 なぜなら、それは、初めてシュバルツシルト半径までコンパクト化されるのと同様に、結局、全質量が単に2倍になるのに過ぎないからである。 単に、E=−GM/R〔J〕の式だけに基づいて、「トータルの質量が10倍になれば獲得する運度エネルギーは10倍、トータルの質量が100倍になれば獲得する運動エネルギーは100倍になる」という効果だけでは足りないのである。 したがって、もっと深いしくみがあるはずである)
質量m〔kg〕を持つ2つのプレオン∴が、それぞれブラックホールの中心へ落ちる場合を考えてみよう。この場合、「質量m〔kg〕を持つ2つのプレオン∴」が、さらに獲得する運動エネルギーK〔J〕は、重力ポテンシャルエネルギーエネルギーに等しい結果(K=Gm/R〔J〕)、この運動エネルギーK〔J〕は、m〔kg〕の質量の増加に相当することになるので、最終的に、質量はトータルで、m〔kg〕+m〔kg〕+m〔kg〕(K〔J〕由来)+m〔kg〕(K〔J〕由来)=4m〔kg〕となる。 つまり、この場合、2つのプレオン∴は、もともと2m〔kg〕の質量を持っていたが、ブラックホールの中心へ落下することによって、トータルで、2倍の4m〔kg〕の質量を持つに至ることになる。
さて、この系が2つ集合するとどうなるか?
別々であったなら、それぞれ、単に4m〔kg〕になるところが、「2つ合わさることによって、さらに獲得する運動エネルギー」は、それぞれ4K〔J〕になるはずである。4K〔J〕の運動エネルギーの増加は、4m〔kg〕の質量の増加に相当するので、合計で、4m〔kg〕+4m〔kg〕+4m〔kg〕(4K〔J〕由来)+4m〔kg〕(4K〔J〕由来)=16m〔kg〕の質量に至る。
つまり、4つのプレオン∴は、もともと4m〔kg〕の質量を持っていたが、ブラックホールの中心へ落下することによって、トータルで、4倍の16m〔kg〕の質量を持つに至ることになる。
さらに、この系が2つ集合するとどうなるか?
別々であったなら、それぞれ、16m〔kg〕になるところが、「2つ合わさることによって、さらに獲得する運動エネルギー」は、それぞれ16K〔J〕になるはずである。16K〔J〕の運動エネルギーの増加は、16m〔kg〕の質量の増加に相当するので、合計で、16m〔kg〕+16m〔kg〕+16m〔kg〕(16K〔J〕由来)+16m〔kg〕(16K〔J〕由来)=64m〔kg〕の質量に至る。
つまり、8つのプレオン∴は、もともと8m〔kg〕の質量を持っていたが、ブラックホールの中心へ落下することによって、トータールで、8倍の64m〔kg〕の質量を持つに至ることになる。
さらに、この系が2つ集合するとどうなるか?
別々であったなら、それぞれ、64m〔kg〕になるところが、「2つ合わさることによって、さらに獲得する運動エネルギー」は、それぞれ64K〔J〕になるはずである。64K〔J〕の運動エネルギーの増加は、64m〔kg〕の質量の増加に相当するので、合計で、64m〔kg〕+64m〔kg〕+64m〔kg〕(64K〔J〕由来)+64m〔kg〕(64K〔J〕由来)=256m〔kg〕の質量に至る。
つまり、16個のプレオン∴は、もともと16m〔kg〕の質量を持っていたが、ブラックホールの中心へ落下することによって、トータルで、16倍の256m〔kg〕の質量を持つに至ることになる。
…
以下同様である。
したがって、帰納的に次の結論を導くことができる。
結論1.10.4 一般に、質量m〔kg〕を持つプレオン∴が2n個(トータルの質量は、2nm〔kg〕)は、ブラックホールの中心に落下することによって、トータルで、2n倍の質量、すなわち(2n)2m〔kg〕=4n2m〔kg〕の質量を持つに至る。
したがって、(真の)「事象の地平面の面積S」は、少なくとも、その効果の分を乗じたものに相当しなければならない。
すなわち、それは、『(M/MG)×2×(M/MG)×4LP2〔m2〕=(M/MG)2×2×4LP2 〔m2〕』となる。
※4LP2 〔m2〕が乗じてある(真の)「事象の地平面の面積S」に対応するためには、単にM〔kg〕を乗じるのではなく、M〔kg〕を重力子質量MG〔kg〕あたりの個数に変換する必要がある。 なぜなら、プレオン∴の個数と、重力子質量の個数(M/MG)は、単純に比例すると考えられるからである。 詳細な個数については、今後の課題である。
そして、この『(M/MG)2×2×4LP2〔m2〕』の値が「1/2π倍」になりさえすれば、ブラックホールの(真の)「事象の地平面の面積S」=『(M/MG)2×4LP2/π〔m2〕』にぴったり一致する。
※「1/2π倍」は、おそらく、「回転」、あるいは、「結合エネルギー」を意味していると思われる。
プレオン∴は、回転運動(例えば、ペアを作った連星のような運動)をしながら運動エネルギーを獲得していると考えられるからである(→EMOES宇宙論1)。 詳細な検討は、今後の課題である。
なお、「1/2π倍」が何であっても、重力場は、獲得する運動エネルギーに比例して創発していることになるので、「重力場は線形である」という説明は、ゆらがないことになると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。 |
◎ もし、「 “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、後者、すなわち、たとえブラックホールに至ってからも 仮説1.11 重力場そのものは、線形である」が正しければ、「重力場も 電磁場も、ともに線形である」であるということになる。
→ このように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、たとえブラックホールに至ってからも『仮説1.11 重力場そのものは、線形である』が正しいことを示している。
このことは、つまり、「重力場も 電磁場も、ともに線形である」ということである。
◎ このことは、電磁場の世界も、重力場の世界も、ともに線形であるということは、電場や磁場の大きさ、重力場の大きさは、ともに単純な足し算&引き算で求められることを意味する。
そして、そのことはやはり、素スピノールの転回にともなう原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形が単振動であること── すなわち、「仮想光子&変形している“4面体”」も「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」も“調和振動子”であることによって支えられている。
→ このように電磁場の世界も、重力場の世界も、ともに線形であるということは、電場や磁場の大きさ、重力場の大きさは、ともに単純な足し算&引き算で求められることを意味する。
そして、そのことは、素スピノールの転回にともなう原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形が単振動であること、すなわち、「仮想光子&変形している“4面体”」も「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」も“調和振動子”であることを考えれば当然のことである。
《静電場(電荷のクーロンの法則)のEMOES表記と電荷エネルギー
(および、磁極のクーロンの法則と磁極のエネルギー)》
◎追加 この仮説により、「厚さ2Lpの球殻に、常に蓄えられているエネルギー」は、どの球殻でも(n (r=2nLp)の大きさに関わらず)、常に一定となることになる。
◎※また、1≦n≦19(2Lp[m]≦r≦38Lp[m])の球殻の中に生じる変形した“4面体”が蓄えるエネルギーE(=波長が、2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]が原始ヒッグス場ユニットの“4面体”を変形させるエネルギー)は、hc/38Lp≦E≦hc/2Lpであり、いずれも、重力子エネルギーEG=hc/(2π)2Lpよりは、大きくなっている。
したがって、波長が、2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]の仮想光子は、ふつうの仮想光子とは、異なった振る舞いをすると考えられる。
例えば、波長2Lp[m]の場合、19倍に増幅すると考えられる。(これが、「LP光子の集積したひも」に相当する)
そして、他にも波長4Lp[m]の場合、9倍に、波長8Lp[m]の場合、4倍に、波長16Lp[m]の場合、2倍というように増幅すると考えられる。 (なお、波長20Lp〜38Lp[m]の場合は、増幅しない)。
いずれにせよ、1≦n≦19の場合、その影響は、半径38Lp[m]の球面以内に限定されることになる。
したがって、厳密には、上の図にような「当量電荷QE[C]」の説明は、n≧20の場合、すなわち、半径40Lp[m]の球面の外側についてのみ、成立することになると考えられる。 (詳細な検討は、今後の課題である)
|
よって、以下では、「1≦n≦19の場合(2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]の仮想光子)も、便宜上、ふつうの仮想光子と同じ振る舞いをするものとして話を進めている」のか、「n≧20の場合、すなわち、半径40Lp[m]の球面の外側についてのみ成立する話をしている」のかを、適宜、説明していくこととする。
→※波長が、2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]が原始ヒッグス場ユニットの“4面体”を変形させるエネルギーは、hc/38Lp≦E≦hc/2Lpであり、いずれも、重力子エネルギーEG=hc/(2π)2Lpよりは、大きくなっている。
(r=λ/2であるので、2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]とは、Lp[m]≦r(=2nLp)≦19Lp[m]ということ、すなわち、0.5≦n≦9.5(1≦n≦9)の球殻の中に生じる変形している“4面体”が蓄えるエネルギーEが、重力子エネルギーEGよりも大きくなっている)
したがって、波長が、2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]の仮想光子は、ふつうの仮想光子とは、異なった振る舞いをすると考えられる。
例えば、波長2Lp[m]の場合、19倍に増幅すると考えられる。(これが、「LP光子の集積したひも」に相当する)
そして、他にも、例えば、波長4Lp[m]の場合9倍に、波長8Lp[m]の場合4倍に、波長14Lp〜19Lp[m]の場合2倍に、というように増幅すると考えられる。
なお、波長20Lp〜38Lp[m]の場合は、増幅しないので、これらはふつうの光子と同等にふるまうと考えられる。よって、ふつうの仮想光子とは異なった振る舞いをするもの、すなわち、「増幅する仮想光子」は、波長2Lp[m]〜19Lp[m]のものだけであることになる。
いずれにせよ、波長2Lp[m]の場合に19倍に増幅する以上、「(ふつうの仮想光子とは異なった振る舞いをする)増幅する仮想光子」の影響は、半径38Lp[m]の球面までおよぶことになる。
したがって、厳密には、上の図にような「当量電荷QE[C]」の説明は、n≧20の場合、すなわち、半径40Lp[m]の球面の外側についてのみ、成立することになると考えられる。 (詳細な検討は、今後の課題である)
|
よって、以下では、「1≦n≦9の場合(2Lp[m]≦λ≦38Lp[m]の仮想光子)も、便宜上、ふつうの仮想光子と同じ振る舞いをするもの(増幅しないもの)として話を進めている」のか、「n≧20の場合、すなわち、半径40Lp[m]の球面の外側についてのみ成立する話をしている」のかを、適宜、説明していくこととする。
◎すなわち、荷電プレオン17.4[個](≒5.8×3[個])分に相当することがわかる。 つまり、この荷電プレオンは、およそ(c/2LP)×1/17.4[回/s]≒5.388×1041[回/s]の頻度で、各球殻に存在する“4面体”を変形できることになることがわかる)
→すなわち、マイナスプレオン17.4[個](≒5.8×3[個])分に相当することがわかる。 つまり、このマイナスプレオンは、およそ(c/2LP)×1/17.4[回/s]≒5.388×1041[回/s]の頻度で、各球殻に存在する“4面体”を変形できることになる)
◎1秒間での時間平均は、NQ×hc/4Lp[J](NQ=(Q/QE))となることになる。
→1秒間での時間平均は、NQ×hc/4Lp[J](NQ=(Q/QE))となる。
EMOES宇宙論1
◎次のようものになる。
『一般相対性理論の数式が、“時空が連続である(微分可能である)ことを前提としている近似的で抽象的な数式”であるからである。
すなわち、それは、「より深いレベルの階層」の、ミクロの自然(nature)についての幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”)」の探求が欠けているからである』
→次のように要約できる。
『一般相対性理論の数式が、“時空が連続である(微分可能である)ことを前提としている近似的で抽象的な数式”だからである。
すなわち、それは、「より深いレベルの階層」の、ミクロの自然(nature)についての幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”)…」の探求が欠けているからである』
|
◎ 保存されるのではなく、増加すると考えられるのは、なぜか?
水星〜中性子星に至るまでにおては、重力ポテンシャルエネルギーによって、物質の“運動エネルギー”が増加する分、質量エネルギー、すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力が増加する結果、「Gが2Gになる」(「質量が2倍になる」)と考えられるのだった。(結果1)
→ 保存されるのではなく、増加すると考えられるのは、(重力ポテンシャルエネルギーを利用して)獲得された運動エネルギーが、新たな質量エネルギーになるはずだからである。
例えば、水星〜中性子星に至るまでにおいては、重力ポテンシャルエネルギーによって、物質の“運動エネルギー”が増加する分、質量エネルギー、すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力が増加する結果、「Gが2Gになる」(「質量が2倍になる」)と考えられるのだった。(結果1)
◎そして、ブラックホールに至ってからも、重力ポテンシャルエネルギーが利用され続けて、何らかのしくみで、質量(“運動エネルギー”)が増加し続けると考えられる。
なぜなら、NM(M/MG)の質量だけでは、「シュバルツシルト半径Rs(=2GM/c2)の球面積4πRs2」、すなわち、「事象の地平面の面積4πRs2」に存在する、原始ヒッグス場ユニット(PHU)のすべてを“4角形”(縮みきったバネ)に変化させ続けるには足りないからである。
(→結果1、考察3、下記)
→ そして、ブラックホールに至る過程で、重力ポテンシャルエネルギーが利用され続けて、質量(“運動エネルギー”)がさらに増加し続けると考えられる。
なぜなら、NM(M/MG)の質量だけでは、「シュバルツシルト半径Rs(=2GM/c2)の球面積4πRs2」、すなわち、「事象の地平面の面積4πRs2」に存在する、原始ヒッグス場ユニット(PHU)のすべてを“4角形”(縮みきったバネ)に変化させ続けるには足りず、質量は、ブラックホールに至る過程で、(2倍のみならず)NM/2π倍に増加する必要があるからである。 (→結果1《重力場の線形性について(詳細版)》)
ブラックホールに至る過程で、質量が、NM/2π倍に増加するしくみについては、結果1《重力場の線形性について(詳細版)》で述べた。
そのしくみの本質は、次の結論で要約できる。
『結論1.10.4 一般に、質量m〔kg〕を持つプレオン∴が2n個(トータルの質量は、2nm〔kg〕)は、ブラックホールの中心に落下することによって、トータルで、2n倍の質量、すなわち(2n)2m〔kg〕=4n2m〔kg〕の質量を持つに至る』
◎削除
質量M[kg]が作るブラックホールを考えて見よう。
このブラックホールの球の半径は、シュバルツシルト半径Rs=2GM/c2[m]である。
(G:重力定数、c[m/s]:光速)
すると、シュバルツシルト半径は、Rs=2GM/c2=4πcLP2M/h=M/M G×LP/π と変形できる。
(「G=2πc3LP2/h」、「M G=h/(2π)2cLP」(→結果1)を使用)
この式より導かれる「2πRs=M/M G×2LP」の式は、次のように解釈できる。
すなわち、『シュバルツシルト半径Rsの円周の長さ「2πRs」が、ちょうど、原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ“2LP”をM/M G個、円上に並べた長さ「M/M G×2LP」に等しい』と解釈できる。
このことは、(ブラックホールにいたる以前の“線形の重力(→結果1)”を説明する)「M/M G×4LP2」の式が意味する範囲だけでは、ブラックホールの事象の地平面のすべてをカバーすることができないこと、すなわち、「M/M G×4LP2」の式をそのまま、ブラックホールにあてはめることがゆるされないことを意味する。
ブラックホールの事象の地平面、すべてをカバーする式は、次のように求まる。
4πRs2=4π(M/M G×LP/π)2=(M/M G)2×4LP2/π
この式は、質量M[kg]の物体(NM〔個〕の重力子質量M G〔kg〕に相当)は、ブラックホールを構成するようになると、質量エネルギー(運動エネルギー(内部&外部))が、(2倍のみならず)NM/π倍に増加することを意味する。
|
つまり、「事象の地平面の面積4πRs2」のすべての原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にするためには、ブラックホールの質量(重力子の放出源として働き続ける能力)も、何らかのしくみによって、増加し続けなければつじつまが合わないのである。
◎ 一方、ブラックホールの形成過程で、クォークやレプトンから分解してできた、プレオン∴は、原則としては、素スピノールまで分解されることがないことがわかる。
→ 一方、ブラックホールの形成過程で、クォークやレプトンから分解してできた、プレオン∴は、原則としては、素スピノールまで分解されないことがわかる。
◎ ※「単独の素スピノール」の挙動は、電子と、電子ヒッグス場ユニットとの相互作用と似たものと考えられる。その振る舞いの中のどこにおいても、重力子を放出できる理由を見いだせない。
→※「単独の素スピノール」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)」との相互作用は、「電子」と「電子ヒッグス場ユニット(eHU)」との相互作用と似たものと考えられる。 したがって、その振る舞いの中のどこにおいても、重力子を放出できる理由を見いだせないことになる。
◎しかも、この獲得された運動エネルギーは、「NM個の重力子質量M Gは、ブラックホールを構成するようになると、質量がNM/π倍に増加する」という性質に調和していなければならない。
→ このようなしくみによって運動エネルギーが獲得されることは、「NM個の重力子質量M Gは、ブラックホールに至る過程で、質量がNM/2π倍に増加する(結果1《重力場の線形性について(詳細版)》)」という性質とも調和していると思われる。
◎削除 仮説C1.2 1つ1つの「スピン0の“4角形”(縮みきったバネ)」は、「スピン0の“4角形”(縮みきったバネ)」の存在数数に比例して、より大きな運動エネルギーを獲得する。
これらの仮説によって、「スピン0の“4角形”(縮みきったバネ)」が持つ運動エネルギーが、まさに、「NM個の重力子質量M Gは、ブラックホールを構成するようになると、質量がNM/π倍に増加する」を支えると考えるとつじつまが合う。
◎ これまでの説明をまとめると、次のように説明する。
→ これまでの説明をまとめると、次のようになる。
◎ その「スピン0の“4角形”(縮みきったバネ)」の数に比例して、個々の「スピン0の“4角形”(縮みきったバネ)」が獲得する運動エネルギー(重力子の放出源として働き続ける能力)も増加する。
(「利用される重力ポテンシャルエネルギー」が、まさに『「スピン0の“4角形”(縮みきったバネ)」の数』に比例にするからであると考えていいのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である)
→ その際には、 『結論1.10.4 一般に、質量m〔kg〕を持つプレオン∴が2n個(トータルの質量は、2nm〔kg〕)は、ブラックホールの中心に落下することによって、トータルで、2n倍の質量、すなわち(2n)2m〔kg〕=4n2m〔kg〕の質量を持つに至る』
というしくみが働く。(→結果1《重力場の線形性について(詳細版)》)
◎削除 ※このようにプレオン∴からなる『スピン0の“4角形”(縮みきったバネ)』の円軌道運動にともなう、各プレオン∴が獲得する運動エネルギーの増加が、質量エネルギーの増加につながっていると考えれば、ブラックホールにおいて質量、『「M/M G×4LP2」』から『(M/M G)2×4LP2/π』へと、『(M/M G)×1/π』倍に質量が増加するしくみを説明できる。
すなわち、このしくみにによって、質量M[kg]が作るブラックホールの事象の地平面にある原始ヒッグス場ユニット(PHU)のすべてを“4角形”(縮みきったバネ)に変化させることが可能になる。
◎削除
このあたりのことは、先に述べた、ブラックホールの地平面のすべてをカバーする式が、
4πRs2=4π(M/M G×LP/π)2=(M/M G)2×4LP2/π
のように求まり、この式が、NM個分の重力子質量M Gに相当する質量は、新しいブラックホールを構成するようになると、(NM/π)倍の質量、すなわち、重力子の放出源として働き続ける能力を持つことを意味していることと関連しているかもしれない。
なぜなら、質量が(NM/π)倍になる理由はおおよそ次のように説明できるが──
これは、ブラックホールによって、プレオン∴まで分解され、「プレオン∴×4の“4角形”(縮みきったバネ)」の集合に至り、コンパクト化が進むと、重力ポテンシャルエネルギーを利用した運動エネルギー増加に伴う質量の獲得の効果が強くなるからであると考えられる。
たしかに、トータルの質量が大きいほど、それに比例して「重力ポテンシャルエネルギーを利用した運動エネルギー増加」の効果が大きくなるので、正しそうに思われる。正しければ、このことは、ブラックホールに至る場合でも、“重力場は、結局は線形であり続けている”ことを意味する。
|
「なぜ、(NM/π)倍なのか」の厳密な理由を考える際には、プレオン∴×4の“4角形”(縮みきったバネ)は、ほとんど1カ所に集合する際、より具体的に、どのように配置するのか、が大きなカギを握っていると考えられるからである。 詳細な検討は、今後の課題である。
2017年7月8日 2.11→2.12
結果1
《質量の実体像》
◎ ※以後、こういった、すべての質量エネルギーの起源が運動エネルギーであることを明確に示すための表記としては、「運動エネルギー(外部&内部)」を使うこととする。
→ ※以後、こういった、すべての質量エネルギーの起源が運動エネルギーであることを明確に示すための表記としては、「運動エネルギー(内部&外部)」を使うこととする。
◎以下三カ所、同様に修正 運動エネルギー(外部&内部)→運動エネルギー(内部&外部)
◎追加
その様子は、おおよそ下図のように示せる。
※便宜上、各球殻の“切り口(平面)”上において、8つずつ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が存在しているように図示しているが、実際には、3次元の球殻の中に同数ずつ存在していると考えられる。
|
|
◎ ※時空が不連続であるという前提から導かれる、この仮説は、光速に近づくためには、「無限大の運動エネルギー」は不要であり、
1つの静止重力子質量(=MG[kg])あたり、重力子
エネルギーEG[J](=M
Gc2[J])に相当する運動エネルギーK
[J]を与えるだけで十分であること意味していると考えられる。(詳細な検討は、今後の課題である)
→ ※時空が不連続であるという前提から導かれる、この仮説は、光速に近づくためには、「無限大の運動エネルギー」は不要であり、
1つの粒子(2LP×2LPサイズ)あたり、重力子
エネルギーEG[J](=M
Gc2[J])に相当する運動エネルギーK
[J]を与えるだけで十分であること意味していると考えられる。(詳細な検討は、今後の課題である)
◎削除
なお、この性質は、重力ポテンシャルエネルギーによる結合エネルギーの大きさが、ニュートン力学においてGM2/rであるものが、一般相対性理論において2GM2/rとなることを説明するのを助ける。(→《重力場の線形性について(詳細版)》)
◎※静止重力子質量MG[kg]の物体に、外部からエネルギーを加えて、外部運動エネルギーを持たせる場合、それが光速に近づくためには、「無限大の運動エネルギー」は不要であり、1つの静止重力子質量(=MG[kg])あたり、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J]を与えるだけで十分であることは、静止重力子質量(=MG[kg])の構成によらないと考えられる。
|
時空が不連続であることを前提とすれば、外部から加えるエネルギーが、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に達すれば、最終的には(剛体から、完全流体に変わることによって)、ほぼ光速c〔m/s〕の等速直線運動に至ると同時に、c/2LP[回/s〕の頻度で、進行方向に重力子を放出するはずである。 そして、その加えるべきエネルギーの大きさ重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])は、いずれの構成であったとしても(陽子がおよそ1019個ほど集合したものであっても、「1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」であったとしても)変わらないと考えられる。
なぜなら、構成するそれぞれの質量に反比例して、それぞれの構成物を、ほぼ光速に近付けるために、外部から加えるべきエネルギーが減ると考えられるからである。 そして、(例えば、非常に高速で運動するニュートリノの重力子の放出頻度が少ないことからわかるように) 小さな質量を持つそれそれの構成要素は、たとえ光速近くで運動していても、それぞれの質量に見合った頻度でしか進行方向に重力子を放出しないと考えられるからである。 なお、その場合でも、当然、構成するそれぞれの質量による、重力子の放出数の合計は、c/2LP[回/s〕に至ることになる。 このことは、(ニュートリノを含めて)高速で運動している質量が、その中にびっしり(2プランク長(2LP〔m〕)置きに)存在するはずの原始ヒッグス場ユニット(PHU)のすべてと相互作用せずに、すり抜けていく(バイパスする、飛び越えていく)ようなしくみが存在していることを示唆していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
→ ※静止重力子質量MG[kg]の物体に、外部からエネルギーを加えて、外部運動エネルギーを持たせることを考えた場合、この物体の軌道運動の速さv〔m/s〕が光速c〔m/s〕に近づくためには、「無限大の運動エネルギー」は不要であり、1つの粒子(2LP×2LPサイズ)あたり、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J]を与えるだけで十分であることは、この投入すべきエネルギーの大きさが、静止重力子質量(=MG[kg]を構成する「粒子(2LP×2LPサイズ)の数」によって変わることを意味していると考えられる。
|
時空が不連続であることを前提とすれば、構成する「1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」あたりに、外部から加えるエネルギーが、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に達すれば、最終的には(剛体から完全流体に変わることによって)、ほぼ光速c〔m/s〕の等速運動に至ると考えられる。
そして、その加えるべきエネルギーの大きさの総計は、構成する「1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」の数に比例すると考えられる。
この粒子(2LP×2LPサイズ)の構成数が、1つなら、EG[J](=MGc2[J])、10個なら、10EG[J](=MGc2[J])、n個なら、nEG[J](=MGc2[J])とうように変わると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
《重力の実体像》
◎※やはり、簡略化した図である。
→※やはり、簡略化した、便宜上の図である。
◎追加
したがって、 厳密に見れば、切り口(平面)上の同心円であれば、外へ遠ざかるほど、“4角形”(縮みきったバネ)の密度は、減っているはずである。
つまり、上図は、本来3次元で示されるべき内容を、2次元で示している、便宜
上のものである、ということになる。
◎その方向へ運動する際に要する手間(=“原始ヒッグス場抵抗”)が減少しているので──
→その方向へ運動する際に要する手間(=“原始ヒッグス場抵抗”)が省かれていることになるので──
◎つまり、物体は、ただただ、「“原始ヒッグス場抵抗の小さい」方に動いているだけであり── その過程が、“重力という力によって引っぱられている”と観察されているに過ぎないと考えられるのである。
すなわち、重力は、「“原始ヒッグス場抵抗”が小さい方へと物体が運動しやすいという傾向」によって、そこに存在しているかのように見える力に過ぎないと考えられるのである。
→すなわち、物体は、ただただ、「“原始ヒッグス場抵抗の小さい」方に動いているだけであり── その過程が、“重力という力によって引っぱられている”と観察されているに過ぎないと考えられるのである。
つまり、重力は、「“原始ヒッグス場抵抗”が小さい方へと物体が運動しやすいという傾向」によって、そこに存在しているかのように見える力に過ぎないと考えられるのである。
◎追加 やはり、上図も、厳密に見れば、「本来3次元で示されるべき内容を、2次元で示している、便宜上のものである」ということになる。(以下、同様である)
◎ 重力子は、“厚さ2LPの球殻”の中に収まっている存在している。
→重力子が、すべて“厚さ2LPの球殻”の中に収まっている存在している場合の図である。
◎ ※上図は、重力子が2つの原始ヒッグス場ユニットに、“またがって”存在している場合を示している。
→ ※上図は、すべての重力子が2つの原始ヒッグス場ユニットに、“またがって”存在している場合を示している。
◎
→
◎そして、一方、各球殻に存在する数は、2倍となる。
→そして、一方、各球殻に存在する数は、(1つの球殻に収まっている場合に比べて、2つの球殻にまたがっている場合には)2倍となる。
◎
(しかも、アインシュタインのE=mc2[J]の右辺に相当するものがこの式に登場している。
→
(しかも、アインシュタインの式E=mc2[J]の右辺に相当するものがこの式に登場している。
◎ その力(=重力)[N]とは、単位距離当たりの「重力ポテンシャルエネルギーの変化量」のことに他ならないのだった。
→ その力(=重力)[N]とは、単位距離当たりの「重力ポテンシャルエネルギーの変化量」に他ならないのだった。
◎ 時空が連続で微分可能な世界であれば、連続である「重力ポテンシャルエネルギー」を単純に
偏微分すれば、重力を計算できる。
しかし、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、時空を不連続なもの(飛び飛びの値をとるもの)として考えているので、この
偏微分は使えない。
→ 時空が連続で微分可能な世界であれば、連続である「重力ポテンシャルエネルギー」を単純に
「質点からの距離」で微分すれば、重力を計算できる。
しかし、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、時空を不連続なもの(飛び飛びの値をとるもの)として考えているので、この
(質点から距離による)微分は使えない。
◎
重力子質量MG[kg]の1個分に相当するの質量m[kg]物体に対して、→
重力子質量MG[kg]の1個分に相当する質量を持つ物体に対して
◎「質量M[kg]物体(重力子質量M
G[kg]の
NM個分に相当)と、質量m[kg](重力子質量M
G[kg]の
Nm個分に相当)の間に働く重力は、
→「質量M[kg]
の物体(重力子質量M
G[kg]の
NM個分に相当)と、質量m[kg]
の物体(重力子質量M
G[kg]の
Nm個分に相当)の間に働く重力は、
◎
よって、すでに上の説明で導いた次の結論に至ることができる。
結論1.1.2 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」1つが持つエネルギーEGは、EG=EP/2π である。
→ よって、すでに上の説明で導いた次の結論に至ることができる。
結論1.1.2 重力子エネルギーEG[J]は、プランクエネルギーEP[J]を2πで割った値、すなわち、EP/2π[J]に等しい。
◎ これと、もう1つの
理論的に導出された「重力定数G=2πc3LP2/h」を比較することによって、
→これと、もう1つの
理論的に導出された「重力定数G=2πc3LP2/h」、および「プランクエネルギーEP=(hc5/2πG)1/2 =hc/2πLP 」を比較することによって、
◎ この「G=c
2L
P/2πM
G」の方には、ニュートンの万有引力の法則の“EMOES表記”との関わりを見ることによって、
「重力定数G=2πc3LP2/h」の意味を説明できる可能性があると思われる。
→この「G=c
2L
P/2πM
G」の方が、(ニュートンの万有引力の法則の“EMOES表記”との関連がつかみやすいので)
「重力定数G」の意味を、より説明しやすいと思われる。
◎
NMEG=Mc
2の関係式は、アインシュタインの式“E=mc
2”の意味を教えてくれる式と言うこともできると思われる。
→ NMEG=Mc
2の関係式は、アインシュタインの式“E=mc
2”の意味を教えてくれる式
であると言うこともできると思われる。
◎ すなわち、“mc
2”は、「重力子エネルギーEG[J]のNm[個]分に相当するエネルギー」であるということである。
→
すなわち、“mc
2”には、「重力子エネルギーEG[J]のNm[個]分に相当するエネルギー」という意味がある。
◎
しかも、Mc
2は、「“厚さ2
LPの球殻”がぞれぞれに持つエネルギー」でもある。
→
しかも、Mc
2には、「“厚さ2
LPの球殻”がぞれぞれに持つエネルギー」
という意味もある。
◎追加 すなわち、質量(「重力子の放出源として働き続ける能力」)によって放出され続ける「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」によって、質量の周囲に、重力ポテンシャルエネルギーの“勾配”(それは、“原始ヒッグス場抵抗”の勾配にも等しい)がもさらされ、周囲の質量が、その“勾配”にしたがって運動することが、「重力が生じている」と見なされていることを示しているのである。
◎すなわち、この
ニュートンの万有引力F[N]の“EMOES表記
”には、連続で微分可能な“距離r”が消失しており、プランク距離Lp[m]とそのn倍(整数倍)だけが長さと関連した量として含まれるようになっている。
このことは、(時空が連続であることを前提としている)ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2[N]と、(時空が不連続であることを前提としている)“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で求めた重力= (NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N] が、nが大きい極限で、一致することを意味する。
すなわち、このことは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で求めた重力= (NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N]の(nが大きくなったときの)近似式が、ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2[N]であったということにほかならない。
→ (すなわち、このニュートンの万有引力F[N]の“EMOES表記”には、連続で微分可能な“距離r”が消失しており、プランク距離Lp[m]とそのn倍(整数倍)だけが長さと関連した量として含まれるようになっている)
このことは、(時空が連続であることを前提としている)ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2[N]と、(時空が不連続であることを前提としている)“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で求めた重力= (NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N] が、nが大きい極限で、一致することを意味する。
言わば、それは“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で求めた重力= (NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N]の(nが大きくなったときの)近似式が、ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2[N]であったということに他ならない。
《「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の働きと運動の第1法則(慣性の法則)および運動の第2法則(F=ma)》
◎すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「どのようにして、“慣性”や“F=ma”が成立するのか」を説明できるのである。
→すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「どのようなしくみで(なぜ)、“慣性”や“F=ma”が成立するのか」を説明できるのである。
◎ “慣性の法則”や“F=ma”は、ニュートン力学の前提であり、おそらく、これまで誰も(かつての私自身も含め)
→ “慣性の法則”や“F=ma”は、ニュートン力学の前提であり、おそらく、これまで誰も
◎どのようにして生じるのか」を説明することの必要性を、ほとんど感じてこなかったと思われる。
→どのようなしくみで(なぜ)成立するのか」を説明することの必要性を、ほとんど感じてこなかったと思われる。
◎ しかし、よく考えてみると、例えば、質量を与える(光速を失わせる)“ヒッグス場”が真空を満たしている中で、どのように“慣性”(等速直線運動)が実現するのかについて説明することには、重要な意味があることがわかる。
→しかし、よく考えてみると、例えば、質量を与える(光速を失わせる)“ヒッグス場”が真空を満たしていると考えられている中で、“慣性”(等速運動)が実現していることは、(矛盾している言えるほど)不思議なことである。したがって、どのようなしくみで(なぜ)“慣性”(等速運動)が実現するのかについて説明することには、重要な意味があるのである。
◎ これができるようになったのは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が、「より深いレベルの階層」から説明しようとするものだからである。
→ これまで前提とするしかなかった「 “慣性の法則”や“F=ma”」を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「より深いレベルの階層」から説明しようとするのである。
◎ 以下にその説明を示す。
ニュートン力学が前提とする法則とは、次のようなものである。
→
ニュートン力学が前提とする法則とは、次のようなものであった。
◎※なお、以下では、「太陽の周囲を公転する地球」を含めて応用範囲を広げるために、等速直線運動の代わりに等速運動として説明を進めることとする。
◎ 静止していた物体は、力を加えない限り、ずっと、静止し続ける。(ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)の一例である)
静止している物体に力を加えると、物体は加速運動しながら(ニュートン力学の第2法則 F=maに従いながら)、運動エネルギー(外部)を増す。
→ 静止している物体は、力を加えない限り、ずっと静止し続ける。(ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)の一部である)
静止している物体に力を加えると、物体は加速運動することによって(ニュートン力学の第2法則 F=maに従いながら)、(外部)運動エネルギーを増す。
◎その加速の際、静止していた物体は、もとのように静止し続けようとして抵抗する。
→その加速の際、静止していた物体は、もとのままに静止し続けようとして抵抗する。
◎その“抵抗、動かしにくさ、慣性力…”の大きさが、“F=ma”の大きさに等しい。
→その“抵抗、動かしにくさ…”に相当する“慣性力”の大きさが、“F=ma”の大きさに等しい。
◎ そして、すでに加速しおえて、等速直線運動をしている物体は、力を加えない限り、ずっと、等速直線運動をし続ける。(ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)の一例である)
等速直線運動をしている物体に、(運動方向と逆向きの)力を加えると、物体は減速運動しながら(ニュートン力学の第2法則 F=maに従いながら)、運動エネルギー(外部)を減らす。
→ そして、すでに加速しおえて、等速運動をしている物体は、(摩擦力も含めて、運動方向に一切の)力を加えない限り、ずっと等速運動を続ける。(ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)の一部である)
等速運動をしている物体に(運動方向にマイナスの)力を加えると、物体は減速運動することによって(ニュートン力学の第2法則 F=maに従いながら)、(外部)運動エネルギーを減らす。
◎その減速の際は、等速直線運動していた物体は、もとのように等速直線運動し続けようとして抵抗する。
→その減速の際は、等速運動していた物体は、もとの等速運動を続けようとして抵抗する。
◎その“抵抗、勢い、はずみ、止めづらさ…”の大きさが、“F=ma”の大きさ等しい。
→その“抵抗、勢い、はずみ、止めづらさ…”に相当する“慣性力”の大きさが、“F=ma”の大きさ等しい。
◎ この(ニュートンが前提とするするしかなかった)「慣性の法則」がどのようなしくみで生ずるのかを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、説明できる。
→ この(ニュートンを含めて、これまで誰もが前提とするしかなかった)「慣性の法則」がどのようなしくみで(なぜ)生ずるのかを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、説明できる。
◎ そのことについて以下に説明する。
→
◎※アインシュタインの特殊相対性理論によれば、ある速度vで運動している物体は、運動エネルギー(外部)を獲得していると同時に── 質量エネルギー(=静止質量エネルギー+運動エネルギー、=運動エネルギー(内部&外部))が増加している。 (質量エネルギーは、(m0c2(1−v2/c2)-1/2で計算できる。v[m/s]<<光速c[m/s]の場合は、質量エネルギーは、(m0c2(1−v2/c2)-1/2≒(m0c2+m0v2/2と近似的に求まる)。
→※アインシュタインの特殊相対性理論によれば、速さv〔m/s〕で運動している物体は、(外部)運動エネルギーを獲得していると同時に── 質量エネルギー(=静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))が増加している。 (この質量エネルギーは、(m0c2(1−v2/c2)-1/2で計算できる。v[m/s]<<光速c[m/s]の場合は、質量エネルギーは、(m0c2(1−v2/c2)-1/2≒(m0c2+m0v2/2と近似的に求まるのだった)
◎現代物理学(標準模型)によると、→ 一方、現代物理学(標準模型)によると、
◎とても不思議なことである。→やはり、(矛盾しているといえるほど)とても不思議なことである。
◎ この(質量を与える)ヒッグス場は、いわば(光速を失わせる)抵抗として働くのであり、よく考えてみると、この抵抗の中を、ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)が示すように、等速直線運動を実現できるというのは、とても不思議なことである。
→この(質量を与える)ヒッグス場は、いわば(光速を失わせる)抵抗として働くのであり、よく考えてみると、この抵抗の中で、(ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)が示すような)等速直線運動を実現できるというのは、とても不思議なことである。
◎ 静止した物体を動かし始める際の“抵抗、動かしにくさ…”といった“慣性”が生じるのは、まさに、原始ヒッグス場の中を物体が進んでいく際、わざわざエネルギーを使って原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”を、“4角形”(縮みきったバネ)まで変形させる必要があるからと考えられる。
そして、“4角形”(縮みきったバネ)なった原始ヒッグス場ユニット(PHU)は、速やかに、「重力子」を、物体の運動方向に放出すると考えられる。
→ 静止した物体を動かし始める際の“抵抗、動かしにくさ…”という意味の“慣性(力)”が生じるのは、まさに、原始ヒッグス場の中を物体が進んでいく際、わざわざ各原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”を、“4角形”(縮みきったバネ)まで変形させる必要があるからである。
そして、“4角形”(縮みきったバネ)となった原始ヒッグス場ユニット(PHU)からは、速やかに、「重力子」が(物体の運動方向と同じ方向に)放出される。
◎ (当然、放出された「重力子」は、「重力子&新たな“4角形”(縮みきったバネ)」として、次々と原始ヒッグス場の上を、光速で飛び去っていくだろう)
→(当然、放出された1つ1つの「重力子」は、「重力子&新たな“4角形”(縮みきったバネ)」として、次々と原始ヒッグス場ユニット(PHU)を伝わりながら、原始ヒッグス場の上を、光速で飛び去っていくだろう)
◎「運動エネルギー(外部)を増すことによって、質量エネルギーを増す」ことに相当と考えられる。
→「(外部)運動エネルギーを増すことによって、質量エネルギーを増す」ことに相当すると考えられる。
◎ このように、加速運動によって、運動エネルギー(外部)が増加するしくみを、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として説明することは、 次の仮説にもとづいている。
仮説1.5.0 静止していた物体が加速し、運動エネルギー(外部)を獲得する際には── (元々の静止質量による「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出の他に)、新たに、運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が始まっている。
→したがって、加速運動によって(外部)運動エネルギーが増加するしくみを、運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出数の増加として説明することができる。
◎正しければ、この「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出源として働き続ける能力を増加させる過程が、静止していた物体が、もとのように静止し続けようとする“抵抗、動かしにくさ、慣性力…”の実体であると同時に── 運動エネルギー(外部)の増加の実体、すなわち、特殊相対性理論が説明する、運動エネルギー(外部)の増加とともに質量エネルギー(=静止質量エネルギー+運動エネルギー、=運動エネルギー(外部&内部))が増加することの実体であることになる。
→すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、この「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力を増加させる過程が── 静止している物体がそのまま静止し続けようとする“抵抗、動かしにくさ…”という意味の慣性(力)の実体であると同時に、(外部)運動エネルギーの増加の実体、すなわち、(特殊相対性理論が説明するところの)質量エネルギー(=静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(外部&内部))の増加の実体なのでる。
◎ 以下、v[m/s]<<光速c[m/s]とする
→ 以下、速さv[m/s]<<光速c[m/s]とする。
◎ その結果、物体が速度v[m/s]になったとすると、この物体は、mv2/2[J]の運動エネルギー(外部)を持つとする。
(これは、ニュートン力学の前提から求められることであるが、ここでは、ニュートン力学の前提がない中で、運動エネルギー(外部)がmv2/2[J]が求められたということとする)
→ その結果、この質量m[kg]の物体の速さが v[m/s]になった場合、この物体は、mv2/2[J]の(外部)運動エネルギーを持つ。
(これは、当然ニュートン力学の前提から求められることであるが、ニュートン力学の前提がない中で、(外部)運動エネルギーがmv2/2[J]に至ることを、別の方法で導くこともできることを後に示す)
◎ なお、この、mv2/2[J]の運動エネルギー(外部)は、上記で述べたように、新たな“重力子の放出源として働き続ける能力”(=新たに、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形できる能力)、すなわち、新たな質量に他ならない。
→ なお、この、mv2/2[J]の(外部)運動エネルギーは、上記で述べたように、新たな“重力子の放出源として働き続ける能力”(=新たに、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形できる能力)、すなわち、新たな質量エネルギーの一部に他ならない。
◎この「新たな“重力子の放出源として働き続ける能力”である運動エネルギー(外部)[J]」は、
→この「新たな“重力子の放出源として働き続ける能力”である(外部)運動エネルギー[J]」は、
◎ ここで、ある一定の大きさの力F[N]を加えたときの、加速度a [m/s2]が一定であると仮定する。
すると、力を加えた時間を t[s] とすると、v=at[m/s]、l=at2/2 [m]となる。
※高校物理である。
aは、一次関数の傾きに相当し、l は、その一次関数を積分したもの(オレンジの三角形の面積)に相当している。
※厳密には、このように、積分で計算できるのは、時空が連続と見なせるようなマクロのレベルのときだけである。
ただし、ニュートンの運動の第2法則を導く場面では問題はないと考えられる。
なお、時空が不連続と見なすミクロのレベルでは、グラフは直線にはならず、面積は、級数として求められると考えられる。詳細な検討は、今後の課題である。
|
これらを Fl = mv2/2 に代入すると、 F×at2/2 = m(at)2/2 よって、 F = ma すなわち、ニュートンの運動の第2法則が導れる。
→ ここで、Fl = mv2/2 [J]の両辺を、単純に時間で微分してみよう。
すると、力Fは、一定なので、 Fdl/dt=mvdv/dt(Fv=mva) すなわち、F=maが導かれる。
つまり、 Fl = mv2/2[J]の関係は、本質的に F=ma すなわち、ニュートンの運動の第2法則と同等の関係であることがわかる。
※厳密には、時空が不連続で微分できないが、上記のような場合は、(時空が連続であると)粗視化した上での近似計算として微分することに問題はないと思われる。詳細な検討は、今後の課題である。
◎ このことは、もし、運動エネルギー(外部)Kが(v[m/s]<<光速c[m/s]で)、例えば、K= mv2/2[J]であることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって導くことができさえすれば、それは同時に、少なくとも、ニュートンの運動の第2法則が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明できることを意味する。
(K= mv2/2[J]と導かれることは、後ほど示す)
→ このことは、もし、「(速さv[m/s]<<光速c[m/s]で)(外部)運動エネルギーKが、mv2/2[J]であること」と「ある一定の大きさの力F[N]を加えたときの、加速度a [m/s2]が一定であると」を“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって導きさえすれば、それは同時に、ニュートンの運動の第2法則(F=ma)が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって導かれたことになることを意味する。
(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、K= mv2/2[J]と導かれることは、後ほど示す)
◎さて、いったん加速しおえた物体は、力を加えるのを止めても、そのまま等速運動を続ける。 その際、一定の運動エネルギー(外部)を持っているということは、質量エネルギー(=静止質量エネルギー+運動エネルギー、=運動エネルギー(内部&外部))を保ち続けると言うことであり、それは、「重力子の放出源として働き続ける能力」を保ち続けることに他ならない。
→ さて、いったん加速しおえた物体は、力を加えるのを止めても、(摩擦を含めて運動方向に一切の力が働かない場合)そのまま等速運動を続ける。 このように等速運動を続けるということは、一定の(外部)運動エネルギーを持ち続けるということ、すなわち、質量エネルギー(=静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))を保ち続けると言うことであり、それは、「重力子の放出源として働き続ける能力」を保ち続けることに他ならない。
◎この『「重力子の放出源として働き続ける能力」をそのまま保ち続ける』という性質が、まさに、等速運動を可能にさせるカギであると考えられる。
→ この『「重力子の放出源として働き続ける能力」をそのまま保ち続ける』という性質が、まさに、(質量を与える)ヒッグス場の中での等速運動を可能にさせるカギであると考えられる。
◎ 仮説1.5.1 運動エネルギー(外部)を持って等速直線運動をしている物体は、物体の運動方向への「重力子の放出源として働き続ける能力」をそのまま保ち続けている。
この物体は、まさに、その物体の運動方向と同じ方向に放出し続ける「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が生んでいる“流れるプール”のような効果によって、
等速直線運動を実現している。
→ 仮説1.5.1 (外部)運動エネルギーを持って等速運動をしている物体は、(静止質量エネルギー(内部運動エネルギー)による重力子の放出源として働き続ける能力の他に)
「重力子の(物体の運動方向と同じ方向への)放出源として働き続ける能力」を保ち続けている。
この物体は、まさに、その物体の運動方向と同じ方向に放出し続ける「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が生んでいる“流れるプール”のような効果によって、
等速運動を実現している。
◎ 正しければ、等速直線運動をしている物体は、『物体の運動方向と同じ方向に生じ続ける「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和』のおかげで── たとえ新たな力を加えなくても、物体の進行方向に存在する、新たな「原始ヒッグス場の“4面体”」が、次から次へと「“4角形”(縮みきったバネ)」に変形され続けるしくみを持っていることになる。
→正しければ、等速運動をしている物体は、『物体の運動方向と同じ方向に生じ続ける「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和』のおかげで、たとえ新たな力を加えなくても、物体の進行方向に存在する、新たな「原始ヒッグス場の“4面体”」を、次から次へと「“4角形”(縮みきったバネ)」に変形させ続けることができる── というしくみを持っていることになる。
◎ そのようなことを可能にする“しくみ”は、どのようなものであろうか?
以下では、そのことについて説明する。
→ そのようなことを可能にする“しくみ”とは、どのようなものであろうか?
◎※なお、“剛体”というのは、特殊相対性理論の前提でもある。
→※なお、“剛体”というのは、特殊相対性理論の前提でもあった。
◎簡単のため、(運動エネルギー(内部)によって、重力子を放出し続けている)静止した素粒子○が多数集合して構成される、静止した剛体(トータルの静止質量は、m0[kg])を考える。
→簡単のため、((内部)運動エネルギーによって、重力子を放出し続けている)静止した粒子○が多数集合して構成される、静止した剛体(トータルの静止質量は、m0[kg])を考える。
◎この「静止した素粒子○が多数集合して構成される、静止した剛体」を、下のような単純化したモデルを使って表記する。
オレンジ色の○が、個々の素粒子である。
→この「静止した粒子○が多数集合して構成される、静止した剛体」を、例えば、下図のような単純化したモデルを使って表記できる。
オレンジ色の○が、個々の粒子である。
◎※静止質量m0[kg]の剛体によって、“4角形”(縮みきったバネ)が放出されている様子を示す。
→※静止質量m0[kg]の剛体によって“4角形”(縮みきったバネ)が放出されている様子が、モデル化されて示されている。
◎ ※静止質量エネルギー(=運動エネルギー(内部))による重力子の放出が放射状であることは、
下に述べる剛体の運動エネルギー(外部)による重力子の放出が、運動方向のみに平行であることと対照的である。
→※静止質量エネルギー(=(内部)運動エネルギー)による重力子の放出が放射状であることは、
下に述べる剛体の(外部)運動エネルギーによる重力子の放出が、運動方向のみに平行であることと対照的である。
◎ 物体が、たとえ(外から見て)静止していても、(○の中に多数存在する)各素粒子が持っている、運動エネルギー(内部)によって、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出し続けているので── その総和として物体から「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出され続けることになる。
この「内部運動エネルギー」こそが、静止質量エネルギーm0c2の実体に相当すると考えられることは、すでに述べた。
→ この「静止した粒子○が多数集合して構成される、静止した剛体」が、たとえ外から静止しているように見えても、(剛体の中に多数存在する)各粒子が持っている、静止質量エネルギー(=(内部)運動エネルギー)から「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出され続けているので── その総和として、この剛体の静止質量エネルギーm0c2[J]に相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出され続けることになる。
◎(光速よりずっと小さい)速度vで、等速運動をすることを考えてみよう。
→(光速よりずっと小さい)速さv[m/s]で、ある方向に等速運動をすることを考えてみよう。
◎ すると、もとからあった静止質量エネルギーm0c2[J](=静止した素粒子持つ運動エネルギー(内部)の総和) によって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放射状に放出される他に、運動エネルギー(外部)によって、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、運動方向に限定して放出されることになる。
→ すると、もとからあった静止質量エネルギーm0c2[J](=静止した粒子が持つ(内部)運動エネルギーの総和) によって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放射状に放出されるのに加え、(外部)運動エネルギーによって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が運動方向に限定して放出されることになる。
◎ 運動エネルギー(外部)の値は、特殊相対性理論によると、一般には「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」であるが、v[m/s]<<光速c[m/s]の場合なので、ニュートン力学の場合に一致し、m0v2/2[J]となる。
→(外部)運動エネルギーの値は、(特殊相対性理論によれば、「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」となるはずであるが)速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合なので、ニュートン力学の場合にほぼ一致し、m0v2/2[J]となるはずである。
◎そして、もし、運動エネルギー(外部)がm0v2/2になることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、説明できれば、運動の第2法則(F=ma)が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明できたことになるのだった)
→ そして、もし、(外部)運動エネルギーがm0v2/2になることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明できさえすれば、運動の第2法則(F=ma)が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明できたことになるのだった)
◎ この問題は、「なぜ、速度vの運動によって蓄えられる運動エネルギー(外部)が、単純にm0v2[J]ではなく、その1/2である、m0v2/2[J]になるのであろうか?」という問題に置き換えることができると思われる。
なぜなら、先に述べたように、重力子質量MG[kg]のエネルギーMGc2[J]に相当する、(外部)運動エネルギーK[J]を持つ仮想質点の移動速度は、ほとんど光速cになると考えられるからである。 すなわち、この理屈で考えると、質量m0が速度vの運動によって蓄えられる運動エネルギーは、単純にm0v2[J]になりそうなものだからである。
→この問題は、「なぜ、速さv〔m/s〕の運動によって蓄えられる(外部)運動エネルギーが、単純にm0v2[J]ではなく、その1/2である、m0v2/2[J]になるのであろうか?」という問題に置き換えることができる。
なぜなら、先に述べたように、静止重力子質量MG[kg]の物体の(内部)運動エネルギーを担うものが「1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」の場合は、MGc2[J]に相当する運動エネルギーK[J]を持ち、その移動の速さv〔m/s〕は、ほとんど光速c〔m/s〕になると考えられるからである。 すなわち、この理屈で考えると、質量m0が速さv〔m/s〕の運動によって蓄えられる運動エネルギーは、単純にm0v2[J]になりそうなものだからである。
◎ そこで、このことに関して、次の仮説を立てた。
仮説1.5.2 ある物体に蓄えられる運動エネルギー(外部)は、単独の「質点に近い素粒子」の場合m0v2[J]であっても、それらが複数集まった剛体となる場合m0v2/2[J]となる。
→ そこで、このことに関して、次の仮説を立てた。
仮説1.5.2 ある物体が「単独の粒子(2LP×2LPサイズ)」で構成されていて、その(外部)運動エネルギーがm0v2[J]となるならば、その「単独の粒子」が複数集まって、うまく構成された剛体が持つ(外部)運動エネルギーはm0v2/2[J]となる。
◎ ※なお、この仮説は、質点のみを前提とする系では、考えることができないものである。
→ ※なお、この仮説1.5.2は、(剛体ではなく)質点のみを前提とする系では、考えることができないものである。
◎ ※なお、ニュートン力学で運動エネルギー(外部)が、m0v2/2[J]となることが導かれたのは、質点という前提のみならず、F=maの前提があったからである。
→ ※なお、この仮説は、質点のみを前提とする系では、考えることができないものである。
(剛体ではなく)質点を前提とするニュートン力学で(外部)運動エネルギーがm0v2/2[J]となることが導かれたのは、あくまで、ニュートン力学がF=maの前提を持っていたからに他ならない。
◎追加 ※この仮説は、もし、(光速に比べて低速で運動する)物体の運動エネルギーがmv2/2[J]の式で示されるのならば、その物体は、剛体であり、内部構造を持つことを示唆している。
よって、例えば、(光速に比べて低速で運動する)電子の運動エネルギーは、mv2/2[J〕で示されているので、(光速に比べて低速で運動する)電子が剛体と見なせるのみならず、電子は内部構造を持つことになると考えられる。 (→結果2)
◎速度vの運動によって蓄えられる運動エネルギー(外部)が、単独の場合m0v2[J]となるような、「質点に近い素粒子」を考える。
この「粒子(2LP×2LPサイズ)」は、単独で運動する場合、速度m0v2の(外部)運動エネルギーに相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出できることになる。
→(下図のような方向に)速さv〔m/s〕の運動によって蓄えられる(外部)運動エネルギーが、単独の場合にm0v2[J]となるような、「粒子(2LP×2LPサイズ)」を考える。
◎
→
◎以下、該当部分
「質点に近い素粒子」→「粒子(2LP×2LPサイズ)」
運動エネルギー(外部)→(外部)運動エネルギー
◎ ※m0v2に相当する「(光速で進む)重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が運動方向にのみ放出される。
→ ※m0v2に相当する頻度で「(光速で進む)重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が運動方向にのみ放出される。
◎ 次に、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数集まった剛体として、運動する場合を考えて見よう。
すると、仮説1.5.2から、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数集合して塊(剛体)をなして、Σm素[kg]の質量をもって一緒に速度vで運動する場合は、(外部)運動エネルギーが1/2になるようなしくみが創発するはずであると予想される。
すなわち、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数集合してできた塊(剛体)を“仮想剛体”と呼ぶこととすると、この仮想剛体は、(Σm素[kg])v2/2の(外部)運動エネルギーに相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出すると予想されるのだ。
→ 次に、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数集まって、うまく構成されてできた剛体として、等速運動する場合を考えて見よう。
すると、仮説1.5.2から、この剛体は、Σm粒子[kg]の質量をもって一緒に速さv〔m/s〕で運動する場合、(外部)運動エネルギーが“1/2になる”しくみが創発するはずであると予想される。
すなわち、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数集まって、うまく構成されてできた剛体は、(Σm粒子[kg])v2/2の(外部)運動エネルギーに相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出すると予想されるのだ。
◎以下該当部分
m素→m粒子
素粒子→粒子
◎以下、該当する部分(テキスト&図) 仮想剛体→剛体
◎
|
「粒子(2LP×2LPサイズ)」
|
単独の場合
|
複数集合した場合
|
|
運動エネルギー
|
m0v2
|
(Σm0[kg])v2/2
|
→
|
「粒子(2LP×2LPサイズ)」
|
単独の場合
|
複数集まって、うまく構成
されてできた剛体の場合
|
|
(外部)運動エネルギー
|
m0v2
|
(Σm0[kg])v2/2
|
◎ 本当に、1/2になりうることは、次のように説明できる。
→ どのようなしくみで(なぜ)、(外部)運動エネルギーが“1/2になるのだろうか?
◎ 例えば、運動方向に平行に、9つの粒子が連なっている仮想剛体を考えてみよう。
→ 例えば、下図のような方向に、速さv〔m/s〕で等速運動している剛体、しかも、その運動方向に平行に「粒子(2LP×2LPサイズ)」が9つ連なっている剛体を考えてみよう。
◎ 以上の説明は、「各粒子が同一の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出する場合」ということを前提にしたものである。
→ 以上の説明は、『各粒子が同一の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出し続けると考えた場合』のものである。
◎ 剛体が運動する場合、実際は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する頻度は、どうなるであろうか?
「運動方向に平行に、いくつかの粒子が連なっている剛体」の中の各粒子は、実際は、どのような頻度で、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出するかは、次のように説明できる。
→ 一方、『それぞれの「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、様々な頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出し続けてよい場合』(実際の場合)は、どうなるであろうか?
すなわち、「運動方向に平行に、いくつかの粒子が連なっている剛体」の中のそれぞれの粒子(2LP×2LPサイズ)は、実際には、どのような頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出すると考えられるだろうか?
◎例えば、「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、単独で、速度vで運動する場合、n0[個/s]の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することを下図のように図示することとする。
→まず、「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、単独で、(下図のような方向に)速さv〔m/s〕で運動する場合、n0[個/s]の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することを考えてく見よう。 それを図示すると下のようになるとする。
◎この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数個(運動方向に並行に)1列につながってできた剛体を考える。
→ 次に、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数個(2つ、3つ、5つ、9つ)(運動方向に平行に)1列につながってできた剛体を考えていく。
◎ 単独の「粒子(2LP×2LPサイズ)」と比較して、剛体(2つ、3つ、5つ、9つ)が、速度vで進む場合、それぞれが、どれくらいの頻度で、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出するかを、下図のように考えることができる。
→ 単独の「粒子(2LP×2LPサイズ)」と比較して、(2つ、3つ、5つ、9つの「粒子(2LP×2LPサイズ)」で構成される)剛体が、(下図のような方向に)速さv〔m/s〕で進む場合、それぞれが、どれくらいの頻度で、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出するかを、下図をもとにして考えることができる。
◎
→
◎※緑で囲った部分は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が免除される部分、すなわち、実際は、放出されない部分に相当する。
→ ※左側半分が、各粒子が、同一頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出すると考えた場合、右側半分が、各粒子が、様々な頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出してよい場合、すなわち、実際にどうなるかを示したものである。(左側半分における)緑で囲った部分(数)は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が実際は(免除されて)放出されない部分に相当する。
◎(免除されるのは、剛体の後方から前方へ向けて放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、剛体の前方の「粒子(2LP×2LPサイズ)」が“4角形”(縮みきったバネ)へわざわざ変形させる手間を省いてくれる効果を持つからである)
→(免除されるのは、剛体の後方から前方へ向けて放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、『剛体の前方の「粒子(2LP×2LPサイズ)」が“4角形”(縮みきったバネ)へわざわざ変形させる手間を省いてくれる効果』を持つからである)
◎単独で、速度vで運動する場合→単独で、速さv〔m/s〕で運動する場合
◎剛体が速度vで等速運動する結果→ 剛体が(上図のような方向に)速さv〔m/s〕で等速運動する結果(速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合)
◎単独から、剛体に変化すると、剛体の後方から放出された「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」によって、剛体の前方から放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が免除される。
→単独から、剛体に変化すると、剛体の後方から放出された「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」によって、剛体の前方から放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が、ある程度ずつ、免除されるようになる。
◎その免除された部分が、図の“緑の線で囲まれた部分”に相当する。それは、「単独だったら放出しなればならなかったものが、剛体であるおかげで、実際には放出されない部分」とも言える。
→その免除される部分(数)が、上図の“緑の線で囲まれた部分”に相当する。それは、「単独だったら放出しなればならなかったものが、剛体であるおかげで、実際には放出されない部分(数)」とも言える。
◎ つまり、ある「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、わざわざ自分で、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省かれるということは、その「粒子(2LP×2LPサイズ)」自身が「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する頻度が減るということに他ならず── 逆に、ある「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、わざわざ自分で、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形しなければならないということは、その「粒子(2LP×2LPサイズ)」自身が「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する頻度が増えるということに他ならないのだ。
→ つまり、ある「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、わざわざ自分で、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省かれるということは、その「粒子(2LP×2LPサイズ)」自身が「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する頻度が(単独のときに比べて)減るということに他ならない。
(逆に、ある「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、わざわざ自分で“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省かれなくなるということは、その「粒子(2LP×2LPサイズ)」自身が「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する頻度が(剛体のときに比べて)増えるということに他ならない)
◎左の図と、右の図(上の図を90度回転させたもの)の中の緑の線で囲ってある部分の大きさが、ぴったり等しくなる。
→左の図と、右の図(上の図を90度回転させたもの)の中の緑の線で囲ってある部分の大きさ(数)が、ぴったり等しくなる。
◎※左の図と、右の図(上の図を90度回転させたもの)の中のピンクの線で囲ってある部分は、本質的に、同一のものである。
→※左の図と、右の図(上の図を90度回転させたもの)の中のピンクの線で囲ってある部分(数)は、本質的に、同一のものである。
◎ 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度は、(外部)運動エネルギーという名の質量(重力子の放出源として働き続ける能力)に比例するものである。
よって、放出頻度が1/2になるということは、(外部)運動エネルギーが、1/2になるということに他ならない。
→ 剛体として等速運動することにともなって、運動方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出される頻度は、(外部)運動エネルギーという名の質量(重力子の放出源として働き続ける能力)に比例するものである。
したがって、その放出頻度が1/2になるということは、(外部)運動エネルギーが、1/2になるということに他ならない。
◎以上より、『仮説1.5.2 ある物体に蓄えられる(外部)運動エネルギーは、単独の「粒子(2LP×2LPサイズ)」の場合m0v2[J]であっても、それらが複数集まった剛体となる場合m0v2/2[J]となる』の正しさが説明できたことになる。
ところで、単独の運動で獲得される運動がm0v2となる「粒子(2LP×2LPサイズ)」とは具体的に何か?
それは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、プレオン∴(結果2)に他ならない。
(なぜなら、素スピノールの運動エネルギーは、質量を持たず、プレオン∴(結果2)3つからなる電子の運動エネルギーは、mev2/2になるからである。(よって、電子は、剛体の一種と見なせることになる))
したがって、あらゆる「質量m[kg]を持つ物体(剛体)」は、プレオン∴の総和と見なせるので、あらゆる「質量m[kg]を持つ物体(剛体)」が獲得する運動エネルギーは、mv2/2となることになる。
→ 以上より、『仮説1.5.2 ある物体が「単独の粒子」で構成されていて、その(外部)運動エネルギーがm0v2[J]となるならば、その「単独の粒子」が複数集まって、うまく構成された剛体が持つ(外部)運動エネルギーはm0v2/2[J]となる』の正しさが説明できたことになる。
◎(なぜなら、素スピノールの運動エネルギーは、質量を持たず、プレオン∴(結果2)3つからなる電子の運動エネルギーは、mev2/2になるからである。(よって、電子は、剛体の一種と見なせることになる)
→(なぜなら、素スピノールの運動エネルギーは質量を持たないと同時に、プレオン∴の運動エネルギーは単独で質量を持ち、しかも、例えば「プレオン∴3つからなる電子」(結果2)は、その運動エネルギーが(速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合)mev2/2となり、剛体の一種と見なせるからである)
◎したがって、あらゆる「質量m[kg]を持つ物体(剛体)」は、プレオン∴の総和と見なせるので、あらゆる「質量m[kg]を持つ物体(剛体)」が獲得する運動エネルギーは、mv2/2となることになる。
→したがって、あらゆる「質量m[kg]を持つ物体(剛体)」は、プレオン∴の総和と見なせる(結果2)以上、あらゆる「質量m[kg]を持つ物体(剛体)」が獲得する運動エネルギーは、(速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合)mv2/2である、ということになる。
◎以上より、ニュートン力学の第2法則(F=ma)を前提とせずに、(速度vが光速cより小さい場合)
→以上より、ニュートン力学の第2法則(F=ma)を前提とせずに、(速さv〔m/s〕が光速c〔m/s〕より小さい場合)剛体の
◎ このことは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、ニュートン力学の運動の第2法則(F=ma)がなぜ成立するかを説明できたことを意味する。
→ このことは同時に、Fl=mv2/2[J]が、どのようなしくみで(なぜ)成立するか、つまりは、ニュートン力学の運動の第2法則(F=ma)が、どのようなしくみで(なぜ)成立するかを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明できたことを意味する。
◎ すなわち、ニュートン力学の運動の第2法則(F=ma)は、剛体と、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニットの総和)との相互作用、すなわち、剛体と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」で、説明できるのである。
→ すなわち、ニュートン力学の運動の第2法則(F=ma)は、剛体と、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニットの総和)との相互作用、および、その所産である「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」として説明できるのである。
◎※速度vが光速cに近い場合には、(外部)運動エネルギーが、mv2/2になることはない。 そのことに関しては、次のように説明できる。
→ ※なお、速さv〔m/s〕が光速c〔m/s〕に近い場合には、(外部)運動エネルギーが、mv2/2〔J〕になることはなく、より大きな値になる。
そのことに関しては、次のように説明できる。
◎ 剛体の速度vが光速cに近くなってくると、運動によって生じる「重力子の放出源として働く能力」、すなわち、(外部)運動エネルギーと言う名の質量エネルギーは、m0v2/2よりもはるかに大きくなり、「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」に従う大きさに近づくと考えられる。
→ 剛体の速さv〔m/s〕が光速c〔m/s〕に近づいていくと、運動方向に生じる「重力子の放出源として働く能力」、すなわち、(外部)運動エネルギーと言う名の質量エネルギーは、ある程度「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」に従いながら、m0v2/2よりもはるかに大きい値に近づくと考えられる。
◎ つまりは、上記で述べた(外部)運動エネルギーがぴったり1/2になるという関係は消失することになる。
この数式によると、物体が光速cに近づくと、(外部)運動エネルギーが無限大となることが示されるが──
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、原始ヒッグス場の抵抗が無限大になることがない以上、運動エネルギーが無限大になることも、ありえないことになる。
→ つまり、上記で述べた(外部)運動エネルギーがぴったり1/2になるという関係は消失することになる。
この数式「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」によると、物体が光速cに近づくと、(外部)運動エネルギーが無限大となることが示されるが──
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、原始ヒッグス場の抵抗が無限大になることがない以上、(外部)運動エネルギーが無限大になることも、ありえないことになる。
◎なぜなら、原始ヒッグス場の抵抗(原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形するのに必要なエネルギー)は、有限のものだからである。
→なぜなら、原始ヒッグス場抵抗、および、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形するのに必要なエネルギーが、有限のものだからである。
◎したがって、おそらく、1つの「重力子質量MG[kg]」あたりの(外部)運動エネルギーが、重力子質量エネルギーEG[J]に達すると、それ以上は、(外部)運動エネルギーが増加できなくなると考えられる。
→そのことを考慮に入れると、ある静止質量を持つ剛体は、「粒子(2LP×2LPサイズ)」(=プレオン∴)あたりの(外部)運動エネルギーの大きさが、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に達すると、それ以上は、(外部)運動エネルギーが増加できなくなると考えられる。 したがって、とりうる(外部)運動エネルギーの最大量は、構成する「粒子(2LP×2LPサイズ)」(=プレオン∴)の総数に比例することになる。
◎つまり、「物体を構成する重力子質量MG[kg]の個数NM[個]×重力子質量エネルギーEG[J]=Mc2[J]」が、理論上考えられる、剛体の(外部)運動エネルギーの最大値ということになる。
→したがって、『「物体の静止質量M〔kg〕を構成する「粒子(2LP×2LPサイズ)」(=プレオン∴)の総数N∴[個]」×「重力子エネルギーEG[J]」=MGc2[J]』が、理論上考えられる、剛体の(外部)運動エネルギーの最大値ということになるのである。
◎削除 つまり、質量M[kg]の剛体が獲得できる最大の(外部)運動エネルギーは、無限大ではなく、Mc2[J]であると考えられる。
(この結論は、ニュートン力学から一般相対性理論に変化する際に、Gが2Gとなるのを説明するに役立つ)
◎ この最大値をとるような極限では、「低速時に剛体が生んだ運動エネルギーが1/2になる効果」が完全に消失し、物体は、光速に近い速度で運動していることを意味する。
→ この最大値をとるような極限では、「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」の式からも予想されるように、「低速時に剛体が生んだ運動エネルギーが1/2になる効果」を完全に消失させながら、剛体は、光速c〔m/s〕に近い速さで運動していることになる。(このときは、“剛体”とはいうものの、実質上は、もはや、“完全流体”に至っていると見なしてよいと考えられる。詳細な検討は、今後の課題である)
◎ こういった違いが生まれるのは、「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」の数式の方が、時空が連続で不変であることを前提としているのに対して、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の方は、時空が不連続で可変であることを前提としているからである。
|
特殊相対性理論
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合
の運動エネルギー |
「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」
≒mv2/2
|
mv2/2
|
|
剛体が光速に近づく場合の運動エネルギー
|
「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」により、無限大
|
最大値は、Mc2[J]
|
|
時空
|
連続
|
不連続
|
|
→
特殊相対性理論と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を比較すると次のようになる。
|
特殊相対性理論
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合
の運動エネルギー
|
「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」
≒mv2/2
|
mv2/2
|
|
剛体が光速に近づく場合の運動エネルギー
|
「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」
により、無限大
|
最大値は、N ∴EG[J]
N∴[個]:「物体の静止質量M〔kg〕を構成する「粒子(2LP×2LPサイズ)」(=プレオン∴)の総数
EG[J]:「重力子エネルギー(=MGc2[J])」
|
|
時空
|
連続
不変
|
不連続
可変
|
|
◎“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)せんとすることは、決して、特殊相対性理論を否定することではない。 特殊相対性理論を包含しつつ、これが導く数式の適用範囲を示そうとすることが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせんとすることなのである。
→“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせんとすることは、決して、特殊相対性理論を否定することではない。 それは、特殊相対性理論を包含しつつ、これが導く数式の適用範囲を示そうとすることなのである。
◎※なお、例えば、静止質量Me[kg]の「剛体と見なせる電子」の場合を考えてみると次のようになる。
その「剛体と見なせる電子」が、獲得できる最大の運動エネルギーは、Mec2[J]となり、静止質量エネルギー、Mec2[J]と合計して、2Mec2[J]の質量エネルギーを持つこととなる。 すると、次の式より、その時の電子の速度ve[m/s]が求まることとなる。
Mec2(1−ve2/c2)-1/2=2Mec2[J]
よって、 ve=c×(31/2/2)[J]
「31/2(ルート3)」=1.732…なので、「剛体と見なせる電子」は、光速の86%ほどが最大の速度といことになる。
ところが、加速器で、実際には、電子は、光速の99.99…%という速さまで加速されうるのだった。
このことは、「光速の99.99…%」のように加速されている場合は、もはや、電子は、「剛体と見なせない別の状態のもの」になっていることを示唆していると考えられる。
(具体的には、プレオン∴(→結果3)の「完全流体と見なせる状態のもの」なっていると考えられる。
剛体の場合は、『1つの「重力子質量MG[kg]」あたりの(外部)運動エネルギーが、重力子質量エネルギーEG[J]』に達することが獲得する(外部)運動エネルギーの上限を決めるのに対して── プレオン∴(→結果2)の「完全流体とみなせる状態」の場合は、『1つの「プレオン∴」あたりの(外部)運動エネルギーが、重力子質量エネルギーEG[J]』に達することが獲得できる運動エネルギーの上限を決めるようになると考えられる。
詳細な検討は、今後の課題である)
→※なお、例えば、静止質量Me[kg]の電子を考えてみると次のようになる。
電子は、3つのプレオン∴からなるので(結果2)、電子が、獲得できる最大の(外部)運動エネルギーは、3×ME[J](=3×MGc2[J])となり、静止質量エネルギー、Mec2[J]と合計して、(Me+3MG)c2[J]の質量エネルギー(運動エネルギー(内部&外部))を持つこととなる。
すると、次の時空が連続であることを前提とする式を用いて、その時の電子のおおよその速さve[m/s]を計算すると次のようになる。
Mec2(1−ve2/c2)-1/2=(Me+3MG)c2[J]
式を変形すると、 ve=1−Me2/(Me+3MG)2)=c((Me+3MG)2−Me2)1/2/(Me+3MG)[J]となり、
MG≒2×10-8/2π[kg]に対して Me≒9.11×10-31[kg]はほとんど無視できる値なので、
ve=c×0.9999…[J]という値になる。(詳細な計算は、今後の課題である)
この計算は、少なくとも、加速器で、実際に、電子が光速の99.99…%という速さまで加速されうることと調和していると思われる。
ただし、この「時空が連続であることを前提とする式」によれば、さらに(外部)運動エネルギーを増加させることができるという結論に至る一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、それ以上(外部)運動エネルギーを増加させることはできないという結論に至るという違いがある。 しかも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、この最大値に達したとき、電子は、ほぼ光速に達してると考えられる。
※電子の(外部)運動エネルギーが、mev2/2[J]から、3×ME[J](=3×MGc2[J])に達する過程で、ほぼ剛体の状態から、ほぼ完全流体へと変化すると考えられる。 その変化についての詳細な検討は、今後の課題である。
◎以下該当部分 等速直線運動→等速運動
◎“時空の流れるプール”と呼ぶこととする。
→便宜上、“時空の流れるプール効果”と呼ぶこととする。
◎以下該当部分 “時空の流れるプール”→“時空の流れるプール効果”
◎ やはり、以下も、速度vは、光速cに比べて非常に小さいとして考える。
→ やはり、以下も、速さv〔m/s〕は、光速c〔m/s〕に比べて非常に小さいとして考える。
◎以下該当部分 速度v→速さv〔m/s〕
◎質量エネルギーの一種であると同時に
→質量エネルギーの一部であると同時に
◎原始ヒッグス場の中を運動する際の抵抗を、常に0にしてくれる結果→原始ヒッグス場の中を等速運動する際の抵抗を、常に0にしてくれる結果
◎“時空の流れるプール効果”のしくみによって、実現していることになる。
→“時空の流れるプール効果”の総和によって、実現していることになる。
◎“時空の曲がり”(“重位勾配”、重力場)のおかげであると言える。
→“時空の曲がり”(“重位勾配”、重力場)の効果のおかげであると言える。つまり、いずれも、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和によって創発していることになる。
◎(外部)運動エネルギーm0v2/2 あたりでは、(m0v2/2EG)×(c/2LP) =(m0/MG)×(v2/2c2)×(c/2LP)[個/s]の重力子を放出するであろう。
→(外部)運動エネルギーm0v2/2 あたりでは、単純に、(m0v2/2EG)×(c/2LP) =(m0/MG)×(v2/2c2)×(c/2LP)[個/s]の重力子を放出するであろう。
◎重力子の放出数は、かなり大きなものとなることができる。
→等速運動による重力子の放出数は、かなり大きなものとなることができる。
◎v2/2c2の値は── かりにvが秒速1mだとすると、1/(3×108)2≒0.555×10-17となるので、かなり小さいようにみえる。
しかし、m/MGや(c/2LP)の値がとても大きいので(例えば、100gの物体なら、m/MG=2π×100[g]/(2×10-5[g])=3.14×107となり、c/2LP≒0.927×1043[個/s]である)、 v2/c2の効果が打ち消されて、重力子の放出数は、かなり大きなものとなることができる。
よって、例えば、100gの物体が秒速1mで進む場合── 重力子の放出頻度≒3.14×107×0.55×10-17×0.92×1043 ≒1.58×1033[個/s]となる。
したがって、このことは、
→v2/2c2の値は── かりに速さがv=0.1〔m/s〕だとすると、(0.1)2/2(3×108)2≒0.555×10-19となるので、かなり小さいようにみえる。
しかし、m/MGや(c/2LP)の値がとても大きいので(例えば、1gの物体なら、m/MG=2π×1[g]/(2×10-5[g])=3.14×105となり、c/2LP≒0.927×1043[個/s]である)、 v2/c2の効果が打ち消されて、重力子の放出数は、かなり大きなものとなることができる。
よって、例えば、1gの物体が速さ0.1〔m/s〕で等速運動する場合── 重力子の放出頻度≒3.14×105×0.55×10-19×0.92×1043 ≒1.58×1029[個/s]となる。
このことは、
◎慣性運動(等速運動…)をし続けている可能性があるからである。
→慣性運動(等速運動…)を続けている可能性があるからである。
◎ それは、その静止している物体の周囲には、原始ヒッグス場の抵抗(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和)が均等に存在するので、運動する理由がなくなるからである。
→ それは、その静止している物体の周囲には、原始ヒッグス場抵抗(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和の所産)が均等に存在するので、運動する理由がなくなるからである。
◎ 3.“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の説明は、「双子のパラドックス」を根本的に解消するものである。
→ 3.“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の説明は、「双子のパラドックス」を根本的に解消するものである。
…
◎ このことは、ニュートンの運動の第1法則と第2法則を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)というアプローチによって統合的に説明できることを意味していると思われる。
詳細な検討は、今後の課題である。
→ このことは、ニュートンの運動の第1法則と第2法則を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)というアプローチによって統合的に説明できることを意味していると思われる。
◎ すなわち、加速によって、運動エネルギーが大きくなるということは、“時空の流れるプール”の効果が高まることを意味する。
→ すなわち、加速によって、運動エネルギーが大きくなるということは、「時空の流れるプール効果」が高まることを意味する。
◎ すなわち、減速によって、運動エネルギーが小さくなるということは、“時空の流れるプール”の効果が弱まることを意味する。
“止まりにくさ”に相当する慣性力とは、等速運動している物体が、進行方向に放出している「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が生んでいた“時空の流れるプール”の効果が解消される過程での“抵抗力”である。
→すなわち、減速によって、運動エネルギーが小さくなるということは、「時空の流れるプール効果」が弱まることを意味する。
“止まりにくさ”に相当する慣性力とは、等速運動している物体が、進行方向に放出している「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が生んでいた「時空の流れるプール効果」が解消される過程での“抵抗力”である。
◎ これは、「剛体」とは、正反対のものである。
→ これは、(特殊相対性理論で前提とされた)「剛体」とは、正反対のものである。
◎これらは、ともに重力子の放出源であり、重力場の源としてふさわしいことがわかる。
→これらは、ともに重力子の放出源(重力場の源)としてふさわしいことがわかる。
◎一方、重力子が関わる世界(「原始ヒッグス場ユニット(PHU)」に「質量を持つ物体(電子、クォーク…)」が作用するような世界)では成立していないように見える。
例えば、電子と原始ヒッグス場ユニット(PHU)が衝突して、重力子が放出されるような場合、
→一方、重力子が関わる世界(「原始ヒッグス場ユニット(PHU)」に「質量を持つ物体(電子、クォーク、プレオン∴(→結果2)…)」が作用するような世界)では成立していないように見える。
例えば、プレオン∴(→結果2)と原始ヒッグス場ユニット(PHU)が衝突して、重力子が放出されるような場合、
◎なお、このことは、エネルギー保存則と運動の第3法則(作用反作用の法則)は、別の問題として扱うべきことを示しているようにも思われる。
→なお、このことは、少なくとも「エネルギー保存則と運動の第3法則(作用反作用の法則)は別の問題として扱うべきこと」を示しているようにも思われる。
《重力場の線形性について(詳細版)》
◎ ニュートン力学によれば、元に戻った半径Rの単一の物体が持つ結合エネルギー(=元に戻るために放出すべきエネルギー)は、「Eb=GM2/R」のままで変わらない。
このエネルギーは、ポテンシャルエネルギーを利用して、獲得される(外部)運動エネルギー、すなわち、「Eb=GM2/R」[J]にぴったり等しいはずである。
→ ニュートン力学によれば、元に戻った半径Rの単一の物体が持つ結合エネルギーは、「Eb=GM2/R」のままで変わらない。
これは、静止質量による結合エネルギー「Eb=GM2/R」[J]である。
※このエネルギーは、ポテンシャルエネルギーを利用して、獲得される(外部)運動エネルギー、すなわち、「Eb=GM2/R」[J]にぴったり等しいはずである。
アインシュタインの一般相対性理論によれば、元に戻った半径Rの単一の物体が持つ結合エネルギーは、「Eb=2GM2/R」と2倍なる。
それは、静止質量による結合エネルギー「Eb=GM2/R」[J]に、
「獲得される(外部)運動エネルギー」が持つ質量による結合エネルギー「Eb=GM2/R」[J]が加わるからであると考えられる。
◎削除 一方、一般相対性理論によると、バラバラの物体が、自身の重力によってコンパクト化する際、重力ポテンシャルエネルギーを利用して増加した(外部)運動エネルギーは、新たな質量エネルギーとな
り、それによって活用できる重力ポテンシャルエネルギーを増加させることになる。
その増加した重力ポテンシャルエネルギーを利用して、(外部)運動エネルギーが増加する結果、さらに重力ポテンシャルエネルギーを増加させ
その増加した重力ポテンシャルエネルギーを利用して、(外部)運動エネルギーが増加する結果、さらに重力ポテンシャルエネルギーを増加させ
… というように果てしなく繰り返されることになる。
したがって、もし何らかの制限がなければ、(外部)運動エネルギーは果てしなく増加し続ける結果、無限大に近づくであろう。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、実際、そのようなことは起こらないことがわかる。
なぜなら、(外部)運動エネルギーには、その増加できる限界があるからである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、『質量M[kg]の剛体が獲得できる最大の(外部)運動エネルギーは、無限大ではなく、Mc2[J]である』と考えられるのだった。
(《「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の働きと運動の第1法則(慣性の法則)および運動の第2法則(F=ma)》)
つまり、質量M[kg]の物体(剛体)が、自己の重力(重力ポテンシャルエネルギー)によって、コンパクト化していく場合── その物体(剛体)が獲得する(外部)運動エネルギーは、決して無限大に近づくのではなく、Mc2[J]という最大値に近づくのである。
つまり、質量エネルギーは、静止質量エネルギーMc2[J]+(外部)運動エネルギーMc2[J]=2Mc2[J]に近づくことになる。
◎ゆえに、時空の曲りも2倍になり、質量も2倍になったことと同じになる。
その結果、重力ポテンシャルφ =GM/Rの大きさは2倍となる。そして、重力ポテンシャルφ =GM/Rの大きさは2倍となるからこそ、 『質量M、半径Rの単一物体の重力的自己エネルギー
あるいは結合エネルギー』 Eb=GM2/Rも2倍になる。
→ 「獲得される(外部)運動エネルギー」の分を新たな質量としてカウントするからこそ、時空の曲りも2倍、質量も2倍になったことと同じになるのである。
その結果、重力ポテンシャルの大きさは、ニュートン力学におけるφ=GM/Rの2倍の、 φ=2GM/Rとなるのである。
◎ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、質量になりうるのは、運動エネルギー(内部&外部)であり、重力場のエネルギーではない。
よって、『実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”』と考えられていたものは、「重力場のエネルギー」ではなく、実際は、『重力ポテンシャルエネルギーを利用して増加した(外部)運動エネルギーに相当する質量』であると考えると、つじつまが合うのである。
→ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、質量になりうるのは、運動エネルギー(内部&外部)であり、重力場のエネルギーではないことを示している。
すなわち、『実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”』と考えられていたものは、「重力場のエネルギー」ではなく、実際は、『重力ポテンシャルエネルギーを利用して増加した(外部)運動エネルギーに相当する質量』であることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、示しているのである。
◎ なお、シュバルツシルト半径(ブラックホール)に至ってから以降については、新たな説明が必要である。 なぜなら、ブラックホールに至ってから以降については、もはや、剛体ではなくなっているので『質量M[kg]の剛体が獲得できる最大の(外部)運動エネルギーは、無限大ではなく、Mc2[J]である』という考えがあてはまらなくなる結果、「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」という関係が、もはや成立しないと考えられるからである。
→ なお、シュバルツシルト半径(ブラックホール)に至ってから以降については、新たな説明が必要である。 なぜなら、「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」という関係が、もはや成立しないからである。
◎『NM2×(1/π)=(M/MG)2×(1/π)』個の原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形できるようになる。はずてあることがわかる
→『NM2×(1/π)=(M/MG)2×(1/π)』個の原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形できるようになるはずであることがわかる。
◎ (もはや剛体ではなくなり、プレオン∴(結果2)の総和であるので、そのプレオン∴の運動エネルギーが、カギを握ると考えられる)
→ (シュバルツシルト半径(ブラックホール)に至ってから以降は、もはやクォークやレプトンが維持されず、プレオン∴に分解される(EMOES宇宙論1)ので、そのプレオン∴1つ1つが、重力子エネルギーEG(=MGc2〔J〕)に相当する運動エネルギーK〔J〕を持ちうるということが、カギを握っていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である)
2017年7月3日 2.10.4→2.11
結果1
《質量の実体像》
◎重力子質量MG[kg](=プランク質量MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))をもつ物体が1つあるとする。
この重力子質量MG[kg]を持つ物体を、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出能力を一定に保ったままに圧縮することを考えてみよう。
すると、最終的に、“重力子質量MGを持つ仮想質点”に達する。
→静止重力子質量MG[kg](=プランク質量MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))をもつ物体が1つあるとする。
この静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の、(内部)運動エネルギーを担うものが、2LP×2LPサイズ(原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ)の1つの粒子であると想定してみよう。
◎この“重力子質量MGを持つ仮想質点”は、重力子エネルギーEG=MGc2[J]に相当する、(外部)運動エネルギーKのみを持つものとする。
この(外部)運動エネルギーK(=重力子エネルギーEG=MGc2[J])の大きさは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にする際に蓄えられるエネルギーに、ぴったり等しいのだった。
何が起こるであろうか?
→すると、この「静止重力子質量MG[kg]は、外から静止しているように見えても、2LP×2LPサイズ(原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ)の1つの粒子が、重力子エネルギーEG=MGc2[J]に相当する運動エネルギーK〔J〕を持って、運動を続けており、ある頻度nG[個/s]で重力子を放出し続けていることになる。
この2LP×2LPサイズの粒子の運動エネルギーK〔J〕が、(原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にして、1つの重力子を放出させるのに必要なエネルギーでもある)重力子エネルギーEGEG=MGc2[J]に、ぴったり等しい結果、何が起こるであろうか?
◎もし、エネルギー保存則が成立するのならば、この(外部)運動エネルギーKは、たった1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にするだけで、0になってしまう(消滅していまう)はずである。
→もし、エネルギー保存則が成立するのならば、この(内部)運動エネルギーK〔J〕は、たった1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にして、1つの重力子を放出させるだけで、0になってしまう(消滅していまう)はずである。
◎ すなわち、重力子質量MG[kg]を担う(外部)運動エネルギーKは、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力』をもっているはずだからである。
したがって、たとえ、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にしても、(外部)運動エネルギーKを持ち続けるはずである。
→ すなわち、静止重力子質量MG[kg]が持っている、重力子エネルギーEG(=MGc2)[J]に相当する(内部)運動エネルギーKは、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力』だからである。
したがって、たとえ、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にして、1つの重力子を放出したとしても、(内部)運動エネルギーK〔J〕を持ち続けるはずである。
◎ この結論に対して、「(物理学の根幹を担う)エネルギー保存則に反するから問題ではないのか?」という疑問がわくのも当然である。
→※この結論に対して、「(物理学の根幹を担う)エネルギー保存則に反するから問題ではないのか?」という疑問が湧くのも当然であろう。
◎ つまり、次の結論が導かれる。
→以上より、まず、重要な次の結論が導かれる。
◎ 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするエネルギー、すなわち、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する(外部)運動エネルギーK[J]を持つ仮想質点の移動速度は、どれくらいになるだろうか?
原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)は、「質量を与えるヒッグス場」にも相当するもので、本来、様々な素粒子に対して、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”を持つと考えられる。
原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするために必要なエネルギーに等しい(外部)運動エネルギー(K=MGc2[J])を持ち続ける仮想質点」は、“光速c[m/s]を失わせるはずの抵抗作用”に、やすやすと打ち勝つので、速やかに重力子を放出することになるだろう。しかも、この仮想質点にとって、時空は不連続なので、この過程によってエネルギーが失われることがないため、このブロセスはずっと続くだろう。
その結果、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”がほとんど働いていない状態に等しくなるので、ほぼ光速になると考えられる。
よって、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する(外部)運動エネルギーK[J])を持ち続ける仮想質点の移動速度について、次のような仮説を立てた。
仮説1.2.2 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするエネルギーEG[J]と等しい大きさの(外部)運動エネルギーK(=MGc2[J])を持ち続ける仮想質点は、ほぼ光速c[m/s]の速さで軌道運動(移動)を続けることができる。
→
『結論1.2.2 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、すべて、エネルギー非保存の所産に他ならない。』を踏まえた上で──
この「静止重力子質量MG[kg]の物体の(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」の運動エネルギーK〔J〕が、(原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にして、1つの重力子を放出させるのに必要なエネルギーである)重力子エネルギーEG(=MGc2)[J]に、ぴったり等しい結果、何が起こるかを考えよう。
そもそも、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)は、「質量を与えるヒッグス場」にも相当するもので、本来、様々な素粒子に対して、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”を持つと考えられるのだった。
したがって、「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするために必要なエネルギー重力子エネルギーEG(=MGc2)[J]に等しい運動エネルギーK〔J〕を持ち続ける粒子」は、“光速c[m/s]を失わせるはずの抵抗作用”に、やすやすと打ち勝ち続けながら、重力子の放出を続けることになるだろう。
その結果、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”がほとんど働いていない状態に等しくなるので、この「(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」は、ほぼ光速で運動すると考えられる。
よって、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J])を持ち続ける「(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」がどうなるかについて、次のような仮説を立てた。
仮説1.2.2 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を、“4角形”(縮みきったバネ)に変形して1つの重力子を放出させるのに必要なエネルギーEG(=MGc2)[J]と等しい大きさの運動エネルギーK[J]を持ち続ける「(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」は、ほぼ光速c[m/s]の速さで軌道運動(移動)を続けることができる。
※時空が不連続であるという前提から導かれる、この仮説は、光速に近づくためには、「無限大の運動エネルギー」は不要であり、1つの静止重力子質量(=MG[kg])あたり、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J]を与えるだけで十分であること意味していると考えられる。(詳細な検討は、今後の課題である)
このことは、アインシュタインの特殊相対性理論における数式「E= mc2/(1−(v/c)2)1/2」により、光速に近づくためには、無限の大きさの運動エネルギーが必要であると説明されてきたことは、実は、時空がどこまでも連続であるという前提に基づく説明に過ぎなかったことということを示していると思われる。
なお、この性質は、重力ポテンシャルエネルギーによる結合エネルギーの大きさが、ニュートン力学においてGM2/rであるものが、一般相対性理論において2GM2/rとなることを説明するのを助ける。(→《重力場の線形性について(詳細版)》)
(また、この性質は、運動エネルギーK[J]が、この重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])を越えさえすれば、光速cを越えうることを意味している。 これは、光速を越えて実現したかもしれない「ビッグバウンス〜インフレーション」の現象を支えるしくみなのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である)
◎ 一方、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”は、およそ、一辺が、2プランク長(2LP[m])の立方体のサイズごとにびっしりと存在すると考えられる。
→ 一方、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の配置について、次の仮説を立てることができる。
仮説1.2.3 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”は、あらゆる方向に、ほぼ2プランク長(2LP[m])の幅を占めながら、びっしりと存在している。
◎※それぞれの素スピノールは、一辺が1プランク長(1LP)の立方体の空間の中心にある。
→ ※それぞれの素スピノールは、一辺が1プランク長(1LP)の立方体の空間の中心にある。その結果、あらゆる方向に、ほぼ2プランク長(2LP[m])の幅を占めながら、びっしりと存在していると考えられる。 厳密な配置についての詳細な検討は、今後の課題である。
◎ このことにより、質量を持つ仮想質点は、2LP[m]移動するごとに、1回だけ原始ヒッグス場ユニット(PHU)と衝突すると考えられる。
以上より、“重力子質量MG[kg]を持つ仮想質点”は、ぼぼ速度c[m/s]で1秒間、運動する(1秒間にほぼ3×108[m]進む)間に、ほぼc/2LP= c/2LP[回]だけ、“4面体”と衝突できることになる。
衝突するたびに、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させることを、繰り返し続けると考えられる。 そうやって変形されて生じた1つ1つの“4角形”(縮みきったバネ)は、その後、それぞれ速やかに、1つずつの重力子を放出する。
つまり、この“重力子質量MGを持つ仮想質点”の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度nG は、nG ≒c/2LP[回/s]ということになる。
→この仮説により、上記で述べた、ほぼ光速で進む「(静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の)(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」は、2LP[m]移動するごとに1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”と衝突することになるので、1秒間に(ほぼc=3×108[m]進む間に)ほぼc/2LP[回]の頻度で、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”と衝突できると考えられる。
しかも、この「(静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の)(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」”は、“重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J])を持ち続けるので、衝突するたびに、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させ、速やかに、1つの重力子を放出させることを繰り返すことができる。
以上より、「(静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の)(内部)運動エネルギーを担う粒子(2LP×2LPサイズ)」の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度nG は、nG ≒c/2LP[回/s]ということになる。
◎ よって、この“重力子質量MG[kg]を持つ仮想質点”の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度nG は、まさに、当量質量ME[kg]の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度に、ほぼ等しかったことになる。
→よって、この「(静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の)(内部)運動エネルギーを担う粒子(2LP×2LPサイズ)」の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度nG は、まさに、当量質量ME[kg]の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度に、ほぼ等しかったことになる。
◎ところで、この“重力子質量MG[kg]を持つ仮想質点”は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出能力を一定に保ったままに圧縮した所産なのであった。
したがって、この“重力子質量MG[kg]を持つ仮想質点”が、仮に、陽子がおよそ1019個ほど集合してできた物体に変わったとしても、電子がおよそ1022個集合してできたものに変わったとしても、「1秒間にc/2LP[回]」の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することに変わりないことになる。
つまり、一般に、重力子質量MG[kg](=プランク質量MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))は、1秒間にc/2LP[回]の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することになる。
→ところで、この静止重力子質量MG[kg]を担うものは、“重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J])を持ち続ける「1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」でなければならないということはない。
例えば、陽子がおよそ1019個ほど集合したものでも担うことができる。
そして、静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の(内部)運動エネルギーを担うものが何であろうとも、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度nG は、変わらないはずである。
例えば、この『“重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J])を持ち続ける「1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」』が、仮に、『陽子がおよそ1019個ほど集合してできた物体』に変わったとしても「1秒間にほぼc/2LP[回]」の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することに変わりないはずである。
つまり、一般に、重力子質量MG[kg](=プランク質量/2π=MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))は、構成物が何であろうとも、1秒間にほぼc/2LP[回]の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することになる。
◎追加
※なお、静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の(内部)運動エネルギーを担うものの構成数が増えるほど、それぞれの構成物は、光速に比べてより遅くなっても構わないことになると考えられる。
|
例えば、構成物が2つになった場合、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさは、MGc2[J]/2で済む。
例えば、構成物が3つになった場合、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさは、MGc2[J]/3で済む。
例えば、構成物が100個になった場合、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさは、MGc2[J]/100で済む。
…
と言うように、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさが、構成数の数に反比例することによって、トータルの重力子の放出頻度は、c/2LP[回/s〕を維持できるであろう。そして、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさが小さくなるほど、その移動速度は遅くなると考えられる。(単峻な反比例ではなさそうである。詳細な検討は、今後の課題である)。
|
※静止重力子質量MG[kg]の物体に、外部からエネルギーを加えて、外部運動エネルギーを持たせる場合、それが光速に近づくためには、「無限大の運動エネルギー」は不要であり、1つの静止重力子質量(=MG[kg])あたり、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J]を与えるだけで十分であることは、静止重力子質量(=MG[kg])の構成によらないと考えられる。
|
時空が不連続であることを前提とすれば、外部から加えるエネルギーが、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に達すれば、最終的には(剛体から、完全流体に変わることによって)、ほぼ光速c〔m/s〕の等速直線運動に至ると同時に、c/2LP[回/s〕の頻度で、進行方向に重力子を放出するはずである。 そして、その加えるべきエネルギーの大きさ重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])は、いずれの構成であったとしても(陽子がおよそ1019個ほど集合したものであっても、「1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」であったとしても)変わらないと考えられる。
なぜなら、構成するそれぞれの質量に反比例して、それぞれの構成物を、ほぼ光速に近付けるために、外部から加えるべきエネルギーが減ると考えられるからである。 そして、(例えば、非常に高速で運動するニュートリノの重力子の放出頻度が少ないことからわかるように) 小さな質量を持つそれそれの構成要素は、たとえ光速近くで運動していても、それぞれの質量に見合った頻度でしか進行方向に重力子を放出しないと考えられるからである。 なお、その場合でも、当然、構成するそれぞれの質量による、重力子の放出数の合計は、c/2LP[回/s〕に至ることになる。 このことは、(ニュートリノを含めて)高速で運動している質量が、その中にびっしり(2プランク長(2LP〔m〕)置きに)存在するはずの原始ヒッグス場ユニット(PHU)のすべてと相互作用せずに、すり抜けていく(バイパスする、飛び越えていく)ようなしくみが存在していることを示唆していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
◎削除 ※なお、これまで、アインシュタインの特殊相対性理論をもとに、例えば、「電子を加速させ光速に近づければ、電子が持つ質量エネルギーが、「mec2(1−v2/c2)-1/2」の式よって、無限大に近づく」と説明されている。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による上の説明は、実際には、無限大に近づくことはないことを示しているようである。
なぜなら、もしも、電子の8LP3[m3](原始ヒッグス場ユニット(PHU)の体積)あたりの(外部)運動エネルギーが、重力子エネルギーEG[J]に達すれば、それ以上、(外部)運動エネルギーが上昇しようがなくなってしまうからである。 よって、特殊相対性理論で無限大が登場するのは、「時空が連続であること、時空が不変であること」を前提にしているからに過ぎないと考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎
※なお、実際は、「重力子の放出源として働き続ける能力」が、一定であることを満たしつつ、「2LP間隔の“球殻”」のそれぞれに上にほぼ同数ずつ、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、ランダムな位置に、分布しているのである。
→すなわち、実際は、「重力子の放出源として働き続ける能力」が、一定であることを満たしつつ、「2LP間隔の“球殻”」のそれぞれに上にほぼ同数ずつ、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、ランダムな位置に、分布しているのである。
結果2
《ウィークボソン質量、および、ウィークボソンと中間子の比較》
◎ そして、「LP光子の集積したひも」自体が、質量を持つとは、考えにくい。
→ そして、「LP光子の集積したひも」自体が質量を持つとも考えにくい。
◎したがって、観測されたと見なされるW−ボソンは、80Gevほどの質量エネルギー(=運動エネルギー)に達して
→したがって、観測されたと見なされるW−ボソンは、80GeVほどの質量エネルギー(=運動エネルギー)に達して
◎ つまり、中間子と、ウィークボソン(W−ボソン)には、ともに“二次的な力として生まれている”という意味で、似ているのである。
→つまり、中間子と、ウィークボソンには、ともに“二次的な力として生まれている”という意味で、似ているのである。
また、「π+、π−、π0、K+、K0、η…」のような多様な中間子(メソン)を、グルーオンによって統一的に説明できて、「W+、W−、Z0(e+-e−、u+-u−、d+-d−…)」のような多様なウイークボソンをLP光子によって統一的に説明できるという意味でも、似ている。
(このことに気づくと、多様なウィークボソンを、LP光子によって統一的に説明するというのは、とても自然な考えであるように思われてくる)
※なお、中間子とウィークボソンが似ているという考えは、次の記述とも調和していると思われる。
『湯川は、自然における到達距離の短い力が重い粒子の交換で説明できる、と考えた最初の人物である。実のところ、弱い力を伝えるものとして何年かのちにW粒子が提案されたのも、その着想のもととなったのは、湯川の中間子仮説であった』
(『アインシュタインを超える』 p.114 M・カク、J・トレイナー[著] 久志本克己[訳] 広瀬立成〔監修〕 講談社ブルーバックス)
|
2017年6月28日 2.10.3→2.10.4
結果1
《光子の波》
◎結論1.1 →結論1.0.0
◎追加 ※原始ヒッグス場ユニット(PHU)が、電磁場のみならず、重力場、質量を与えるヒッグス場、四次元時空連続体、時空の曲り、“新しいエーテル”… も担うということは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)が、宇宙(時空)をびっしりと占めていることを意味する。 そのことは、ある意味、時空が不連続であることを意味する。(“ある意味”とは、少なくとも「光子や重力子にとっては」という意味である)
◎この“連星のような動き”こそが、(運動量保存則によって(連続運動だからこそ運動量保存則が成立する))“場所を移動させない(位置を固定させる)”という重要な性質を創発すると考えられる。
→この“連星のような動き”こそが、(運動量保存則によって)“場所を移動させない(位置を固定させる)”という重要な性質を創発すると考えられる。 なお、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する素スピノールにとっては、時空は連続だからこそ、「素スピノールの運動量保存則」が成立すると考えられる。
◎結論1.2.1 →結論1.0.1
◎結論1.2.2 → 結論1.0.2
◎結論1.3 →結論1.0.3
◎“光子の運動量”を説明できることと調和している。 (詳細はのちほど)
→“光子の運動量”を説明できることと調和している。 (詳細はのちほど説明する)
◎2.このような電磁場(原始ヒッグス場)の説明は、「かつて、(古い)“エーテル”が否定されたこと」、すなわち、「マイケルソン-モーレーの観測結果」と矛盾していないのみならず── 他ならぬアインシュタインが一般相対性理論において(『アインシュタイン選集2』p.189〜A10 エーテルと相対性理論)、必要不可欠と考えていた(新しい)エーテルと調和するものである。 すなわち、こういった電磁場を創発できる原始ヒッグス場は、物質ではない(物質未満の実体である)とともに、重力場を説明するために必要不可欠なものなのである。
→ 2.このような電磁場(原始ヒッグス場から創発)の説明は、「マイケルソン-モーレーの観測結果」と矛盾していないのみならず── 他ならぬアインシュタインが一般相対性理論において(『アインシュタイン選集2』p.189〜A10 エーテルと相対性理論)、必要不可欠と考えていた(新しい)エーテルと調和するものである。(すなわち、こういった電磁場を創発できる原始ヒッグス場は、物質ではない(物質未満の実体である)とともに、重力場を説明できるものである)。 つまり、こういった説明には単に矛盾がないだけでなく、特殊相対性理論で「(古い)“エーテル”が否定されたこと」と、一般相対性理論で「エーテルが必要不可欠であると考えられていること」との間にある根本的な矛盾を解消するものなのである。
《重力子の波》
◎ 「(右巻き素スピノール+左巻き素スピノール)×2」(=光子×2)が、上のように配置することによってはじめて、“スピン2”となることができる。
→ 「(右巻き素スピノール+左巻き素スピノール)×2」(=光子×2)が、上のように配置することによってはじめて、(パウリの排他律に反せずに)“スピン2”となることができる。
◎理論上考えられる「最も短い波長」である。→理論上考えられる「最も短い“光子の波長”」である。
◎── 「“4角形”(縮みきったバネ)」と呼ぶこととする。
→を単純に「“4角形”(縮みきったバネ)」と呼ぶこととする。
◎(ブラックホールの中でどうなるかについて、詳細な検討は、今後の課題である)
→(ブラックホールの中でどうなっているかについての詳細な検討は、今後の課題である)
◎ ※重力子による原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形において、「軌道運動で近づく素スピノールのペアにおける共転回」と、「遠ざかる素スピノールのペアにおける共転回」の2種類の共転回が共存していることも読みとれる。 この2種類の共転回が同時に生じることによってはじめて、スピン2を保つことができる。
→ ※重力子による原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形において、「近づく素スピノールのペアにおける共転回」と、「遠ざかる素スピノールのペアにおける共転回」の2種類の共転回が共存していることも読みとれる。 この2種類の共転回が同時に生じることによってはじめて、(パウリの排他律に反せずに)スピン2を保つことができる。
◎「すぐとなりの“4面体”にまたがって達成される“デュアル共転回”」
→「2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”にまたがって達成される“デュアル共転回”」
◎「重力子&重力波」と「光子&電磁波」の関係は、実際は、どのようになっているのだろうか。かは重要なテーマである。 詳細な検討は、今後の課題である。
→「重力子&重力波」と「光子&電磁波」の関係は、実際は、どのようになっているのかは重要なテーマの1つである。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎(電磁波を構成する)光子が、様々な距離にある“4面体”の中の素スピノールと共転回しながら光速で移動するのに対して── 重力子は、「最も近くにある(1プランク長(LP)離れた)2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)をまたぐデュアル共転回」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中のデュアル共転回」を交互に繰り返しながら光速で移動することになる。
→(電磁波を構成する)光子は、その波長λに応じて決まる距離(r=λ/2)だけ離れた原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の中の素スピノールのペアが、次々と共転回しながら光速で移動するのに対して── 重力子は、「最も近くにある(1プランク長(LP)離れた)2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)をまたぐデュアル共転回」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中のデュアル共転回」を交互に繰り返しながら光速で移動することになる。
◎※重力子の波長、すなわち、重力子を構成する“LP光子”の波長は、これまで観測されてきている電磁波を構成する光子の波長──これまで観測されてきているX線やγ線を構成する光子の波長よりも、はるかに短い、2プランク長(2LP≒3.232×10-35m)[m]であることは、致命的なダメージを与えることはないのだろうか?
→重力子の波長、すなわち、重力子を構成する“LP光子”の波長は、これまで観測されてきている電磁波を構成する光子の波長──これまで観測されてきているX線やγ線を構成する光子の波長よりも、はるかに短い、2プランク長(2LP≒3.232×10-35m)[m]であることは、人体に致命的なダメージを与えることはないのだろうか?
◎(例えば、電子の中の素スピノールと、重力子の中の素スピノールが、いきなり“デュアル共転回”をすることは不可能であると考えられる。(電子の内部構造 →結果2))
したがって、重力子は、クォークやレプトンに直接作用せずに、生体を構成する原子(クォークや電子で構成される)の間を透過するだけなので、致命的なダメージを与えるとは考えにくい。
→つまり、重力子は、クォークやレプトンに直接作用できずに、生体を構成する原子(クォークや電子で構成される)の間を透過するだけなので、人体に致命的なダメージを与えるとは考えられないのである。 (例えば、電子の中の素スピノールと、重力子の中の素スピノールが、いきなり“デュアル共転回”をすることは不可能であると考えられる。(電子の内部構造 →結果2))
◎そのため、個々の重力子は、その観測さえも、極めて困難になると考えられる。
その一方で、『放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の変動の波(=“時空の曲がり”(重力場)の変動の波)』の方は、相対的に観測しやすいと思われる。
まさに、後者の『放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の変動の波(=“時空の曲がり”(重力場)の変動の波)』の方が、2016年2月に最初に発表された「LIGOによって観測された“重力波”」に相当する実体であると考えられる。
※『アインシュタイン選集2』の中の、重力波に関する部分をよく読み返してみると──
→そのため、波長2プランク長の個々の重力子は、(人体に致命的なダメージを与えていないことと矛盾していないのみならず)、その観測さえも、極めて困難になると考えられる。
※この個々の重力子と比べれば、『放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の変動の波(=“時空の曲がり”(重力場)の変動の波)』の方は、観測しやすいと言える。
この『放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の変動の波(=“時空の曲がり”(重力場)の変動の波)』の方が、2016年2月に最初に発表された「LIGOによって観測された“重力波”」に相当する実体であると考えられる。
『アインシュタイン選集2』の中の、重力波に関する部分をよく読み返してみると──
◎ 運動エネルギー順位Knの変化(→《ボーアの原子模型》)
でも電磁波は生じる(→スペクトル)。
→ 運動エネルギー順位Knの変化(→《ボーアの原子模型》)
によっても電磁波(スペクトル)は生じる。
◎ 光子の波長は、様々ありうる
電磁波の波長も、それに一致して様々ありうる
→電磁波の波長も、光子の波長も、様々ありうる
◎重力波の波長は、様々
重力子の波長は、一定の2プランク長(2LP[m])
→重力波の波長は、様々ありうる
重力子の波長は、一定の2プランク長(2LP[m])のみである
◎削除 ※重力子の観測はまだできていない。
◎ ※「電磁波の波長=光子の波長」ということは、放出される電磁波の振動数、および、放出される光子の振動数は、ともに「電荷の運動の周期」と密接に関連していることを意味する。
このことは、ある電荷が静電場を生じる際、その電荷の中の“カオス運動”に応じて(電荷の運動の周期が決定論的カオスによって変化し)、仮想光子が生じると考えられることと対照的であると同時に調和していると思われる。(→結果2) 詳細な検討は、今後の課題である。
→ ※「電磁波の波長=光子の波長」ということは、放出される電磁波の振動数、および、放出される光子の振動数は、ともに「電荷の運動の周期」と密接に関連していることを意味する。
(→《電気双極子の振動に伴う放射について》)
◎“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、以後、(アインシュタインが予言し、観測されたところの)“重力波”(「(光速で伝播する)重力場の変化の波」)は、個々の“重力子”の総和として創発していること── すなわち、「“重力波”≠個々の“重力子”」(「“重力波”=“重力子”の“総数の変化”として創発するもの」)であることを明確にした上で、以後、話を進めることとする。
→“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、以後、(アインシュタインが予言し、観測されたところの)“重力波”(「(光速で伝播する)重力場の変化の波」)は、個々の“重力子”の“総数の変化”として創発していること、すなわち、「“重力波”≠個々の“重力子”」であることを明確にした上で話を進めることとする。
◎※1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)に注目した場合── 「“4面体”の状態←→“4角形”(縮みきったバネ)の状態」と行ったりきたりするプロセスを、下のように説明できる。
→重力子は、その実体は、「並走するふたつの光子(厳密には、LP光子)」であるので、(光子の場合と同様に)一定のエネルギーを持っていると予想される。
すなわち、“4角形”(縮みきったバネ)を作っている状態のみならず、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)にまたいでいる状態を含めて、重力子のエネルギーの大きさは一定となっていると予想される。
確かめてみよう。
便宜上1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)に注目することによって、1つの重力子が通過するのに伴って、「“4面体”の状態→“4角形”(縮みきったバネ)の状態→“4面体”の状態」と変化する際の(エネルギーを含む)詳細を、下のように説明できる。
◎ ※この過程のおかけで、“4角形”(縮みきったバネ)の状態が一定時間持続することができる。
→ ※この過程のおかげで、“4角形”(縮みきったバネ)の状態が一定時間持続することができる。
◎重力子が、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)にまたがる場合のエネルギー変化を示すと次の図のようになる。
※重力子のデュアル共転回(2種類)にともなう、エネルギー変化を示す図である。
この図において、緑の縦線の部分が、開放されるエネルギーに相当し、ピンクの縦線の部分が新たに“4面体”に蓄えられる(吸収される)エネルギーに相当する。
コサインカーブの対称性により、エネルギーの放出量とエネルギーの吸収量が、“デュアル共転回”をする間、ずっと100%一致し続ける。 すなわち、重力子による“デュアル共転回”の間は、常に、総エネルギーが一定となる。
|
→
※この図は、重力子が、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)にまたがる場合、および“4角形”(縮みきったバネ)を作っている場合のエネルギー変化を示した図と見なすことができるものである。
この図において、緑の縦線の部分が、開放されるエネルギーに相当し、ピンクの縦線の部分が新たに“4面体”に蓄えられる(吸収される)エネルギーに相当している。
この図より、(コサインカーブの対称性によって)重力子が、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)にまたがる場合、および“4角形”(縮みきったバネ)を作っている場合のいずれにおいても、エネルギーの放出量とエネルギーの吸収量が、“デュアル共転回”をしている間、ずっと100%一致し続けることがわかる。
※なお、重力子の実体が「並走するふたつの光子(厳密には、LP光子)」だからこそ、コサインカーブとなる。 すなわち、数式を用いた説明については、本質的には、光子の場合と同様であると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。 |
◎この図は、1つの重力子が、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)の上を進行していく過程で── その間ずっと、「エネルギーの放出量とエネルギーを吸収量」が等しいまま推移し、トータルでエネルギーは、ずっと一定の大きさであることを意味する。
この一定である「1つの重力子が持つエネルギー」は、とても重要な意味を持つであろう。
→つまり、この説明から、1つの重力子が持っているエネルギーの大きさは、(原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)の上を光速で進んでいる間)常に一定となることを導くことができる。 (数式を用いたより厳密な説明については、今後の課題である)
よって、次の結論に至る。
結論1.1.1 1つの重力子が持っているエネルギー、すなわち、重力子を構成する4つの素スピノールを含む、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギー、あるいは、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの合計は、いずれも、常に一定である。
この「1つの重力子が持つエネルギー」は、とても重要な意味を持つであろう。
◎結論1.1.2 重力子エネルギーEGは、プランクエネルギーEP[J]を2πで割った値、すなわち、EP/2π に等しい。
→結論1.1.2 重力子エネルギーEG[J]は、プランクエネルギーEP[J]を2πで割った値、すなわち、EP/2π[J]に等しい。
◎ よって、重力子1つから、“LP光子”2つに分解されることは、非常に起こりにくいことであることがわかり、それは、この現実の宇宙と合致する。
→ よって、重力子1つから、“LP光子”2つに分解されることは、非常に起こりにくいことがわかり、それは、この現実の宇宙と合致する。
◎以上より、重力子は、非常に安定なものであることがわかると同時に、光子に比べて、“4角形”(縮みきったバネ)を作る過程が、非常に効率の良いものであることがわかる。
→以上より、重力子は、非常に安定なものであることがわかると同時に、光子よりも非常に効率の良く“4角形”(縮みきったバネ)を作れることがわかる。
◎「重力子エネルギー[J]に相当する質量エネルギー[J]を持つ質量[kg]」、すなわち、「プランク質量 MPを2πで割った値(MP/2π)[kg]」も重要な値であろう。
この値を重力子質量[kg]と呼び、MG[kg]と表記することとする。
→「重力子エネルギー[J]に相当する質量エネルギー[J]を持つ質量[kg]」、すなわち、「プランク質量 MPを2πで割った値(MP/2π)[kg]」、すなわち、重力子質量MG[kg]も重要な値である。
◎ ただし、重力子エネルギーEG[J]が質量を持っているわけではない。
すなわち、重力子質量MG[J]が、MGc2[J]のエネルギーを持っているのである。
→ ただし、重力子エネルギーEG[J]が質量を持っているとは限らない。
(例えば、重力子は、質量を持っていない)
すなわち、重力子質量MG[J]は、重力子エネルギーEG=MGc2[J]に相当するエネルギーを
持っているもの一例なのである。 (→下記 《質量の実体像》)
◎ ※なお、「重力子質量」呼ぶが、決して、重力子は、(光子と同様に)質量を持っているわけではない。
したがって、「重力子エネルギー当量質量」と呼ぶのが、より正確誤解を予防するかもむしれない。
→したがって、「重力子質量」と呼んでいるが、決して、重力子が(光子と同様に)質量を持っているという
意味はなはなく、「重力子エネルギー当量質量」の意味を持つ。
《重力子の波》
◎・例えば、“4角形”(縮みきったバネ)を放出することができるが、重力子の放出源としては働き続けないので、質量を持っていないと
判断できる。 “4角形”(縮みきったバネ)は、重力子の通過点に過ぎないのである。
→・例えば、“4角形”(縮みきったバネ)は、重力子を放出することができるが、重力子の放出源としては働き続けないので、
質量を持っていないと 判断できる。 “4角形”(縮みきったバネ)は、重力子の通過点に過ぎないのである。
このことにより、重力場も、質量を持っていないと判断できることになる。
◎※例えば、“運動エネルギー”は、質量を持っていると言える。
しかし、例えば、光子や重力子のエネルギー、電荷エネルギーや磁荷エネルギーが質量を持っているとは言えない。
→※例えば、“運動エネルギー”は、「「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力」に相当しているので、質量を持っていると言える。
しかし、例えば、光子や重力子のエネルギー、電荷エネルギーや磁荷エネルギーは、「「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力」に相当していないので、質量を持っているとは言えない。
◎E=mc2のみならず、あらゆるエネルギーが質量を持つという解釈は、アインシュタイン自身が起源であるらしい。
→なお、E=mc2のみならず、あらゆるエネルギーが質量を持つという解釈は、アインシュタイン自身が起源であるらしい。
◎例えば、もし、ある陽子が、外から見てわかるように運動していれば、その陽子が持っている(外部)運動エネルギーは、その大きさに相当する質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”に相当している。
この陽子は、たとえ、外から見て静止していたとしても、静止質量エネルギー、すなわち、(内部)運動エネルギーに相当する“重力子の放出源として働き続ける能力”を持つ。
→例えば、もし、ある陽子が、外から見てわかるように運動していれば、その陽子が持っている(外部)運動エネルギーは、その陽子が持っている「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」の一部に相当している。
この陽子は、たとえ、外から静止しているように見えたとしても、静止質量エネルギー、すなわち、(内部)運動エネルギーに相当する「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」を持つ。
◎それらのクォークの運動エネルギーは、その大きさに相当する質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”に相当している。 すなわち、陽子は、外から見て静止しているようにみえても、その内部で、クォークなどの素粒子が運動を続けているからこそ、静止質量エネルギーに相当する“重力子の放出源として働き続ける能力”を持っているのである。
なお、このクォークの運動エネルギーは、陽子の静止質量エネルギーのすべてではない。
→それらのクォークの(外部)運動エネルギーは、それらのクォーク子が持っている「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」の一部に相当している。 つまり、陽子は、外から静止しているように見えたとしても、その内部で、クォークなどが運動を続けているからこそ、静止質量エネルギーに相当する“重力子の放出源として働き続ける能力”を持っているのである。
なお、このクォークの(外部)運動エネルギーは、陽子の静止質量エネルギーのすべてではない。
◎他に、陽子の静止質量を担うと考えられるものの1つは、クォークの静止質量である。
外から見て静止しているクォークの内部では、3つのプレオン∴(→結果2)が運動をし続けており── それらのプレオン∴(→結果2)の運動エネルギーが、その大きさに相当する質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”に相当することとなる。 すなわち、クォークは、外から見て静止しているようにみえても、その内部で、クォークを構成するプレオン∴が運動を続けているからこそ、静止質量エネルギーに相当する“重力子の放出源として働き続ける能力”を持っているのである。
そして、もう一つ陽子の静止質量を生じると考えられるものは、クォークどうしを結びつける「グルーオンの集積したひも」(→結果2)を構成するプレオン∴(→結果2)の運動エネルギーである。
→他に、陽子の静止質量エネルギーを担うと考えられるものの1つは、クォークの静止質量エネルギー、すなわち、クォークの(内部)運動エネルギーに相当する「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」である。外から静止しているように見えるクォークの内部では、3つのプレオン∴(→結果2)が運動を続けており── それらのプレオン∴(→結果2)の(外部)運動エネルギーが、その大きさに相当する「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」の一部に相当していることとなる。 すなわち、クォークは、外から静止しているように見えたとしても、その内部で、クォークを構成するプレオン∴が運動を続けているからこそ、静止質量エネルギーに相当する“重力子の放出源として働き続ける能力”を持っているのである。
そして、陽子の静止質量エネルギーを担うと考えられるもう1つのものは、クォークどうしを結びつける「グルーオンの集積したひも」(→結果2)を構成するプレオン∴(→結果2)の外部運動エネルギーである。
◎このことが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において、質量の起源、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」の起源の実体が、運動エネルギーに集約されることの意味である。
|
1. 運動エネルギー(ふつうの意味での運動エネルギー)
(=外部運動エネルギー(external kinetic energy))
2. 静止質量エネルギー
(=内部運動エネルギー(internal kinetic energy))
|
→運動エネルギー
(外部運動エネルギー)
|
→このように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において、質量の起源、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」の起源の実体が、運動エネルギーに集約できるのである。
|
1. 運動エネルギー(ふつうの意味での運動エネルギー)
(=外部運動エネルギー(external kinetic energy))
2. 静止質量エネルギー
(=内部運動エネルギー(internal kinetic energy))
|
→運動エネルギー
|
◎ 結論1.2.1 あらゆる物体が“質量を持っている”ことの起源は── その物体を構成する素粒子が持っている、運動エネルギー(外部&内部)である。
→ 結論1.2.1 あらゆる物体が“質量を持っている”ことの起源は、その物体を構成するその物体を構成する素粒子(「プレオン∴以上に複雑な素粒子」)が持っている、運動エネルギー(外部&内部)である。
◎この場合、「LP光子の集積したひも」の長さをキープするところの、プレオン∴や、(例えば、W−ボソンの両端にある)電子や反電子ニュートリノの運動エネルギーだけが質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”担っていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である)
→ この場合、「LP光子の集積したひも」の長さをキープするところの、プレオン∴や、(例えば、W−ボソンの両端にある)電子や反電子ニュートリノの運動エネルギーだけが質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”を担っていると考えられる。
なお、同様に、『実は、「グルーオンの集積したひも」には質量がなくて、「グルーオンの集積したひも」の長さをキープするところのクォークの運動エネルギーだけが質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”を担っている』ということは、ありえないということで間違いないだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である)
◎質量m[kg]を持つ物体は、 すなわち、太陽も、地球も、人も、自動車も、電車も、自転車も、鉛筆も、本もノートも、消しゴムも、リンゴも、宇宙船も、ブラックホールも… 含めて、たとえ、外から見て静止しているように見えても── それらを構成する素粒子が、外から見えないレベルで運動し続けているおかげで、
→ある質量M[kg]を持つ物体は、すなわち、太陽も、地球も、人も、自動車も、電車も、自転車も、鉛筆も、本もノートも、消しゴムも、リンゴも、宇宙船も、ブラックホールも… 含めて、たとえ外から静止しているように見えたとしても、少なくとも、それらを構成する素粒子(「プレオン∴以上に複雑な素粒子」)が、外から見えないレベルで運動を続けているおかげで、
◎ すなわち、その静止質量が持っている『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力』に相当するエネルギー、すなわち、静止質量エネルギーmc2の実体は、素粒子が持つ運動エネルギー(外部&内部)の総和なのだ。
→すなわち、あらゆる静止質量が持っている『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力』に相当するエネルギー、すなわち、静止質量エネルギーmc2の実体は、素粒子(「プレオン∴以上に複雑な素粒子」)が持つ運動エネルギー(外部&内部)の総和なのだ。
◎ したがって、たとえ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」においてエネルギー保存則が成立していなくとも、時空が不連続である(時空が原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和である)ので、ここに問題がないことになるのである。
→ したがって、たとえ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」においてエネルギー保存則が成立していなくとも、少なくとも「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」にとっては、時空が不連続である(時空が原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和である)ので、ここに問題がないことになるのである。
◎「保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立ては、時空は連続である」→「保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立てば、時空は連続である」
◎ この記述は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)にとっても、やはり都合が良い。
→ この記述は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)にとって、やはり都合が良い。
◎「時空が不連続&エネルギー保存則が成立しない」にもとづいて、説明できると考えられる。→「時空が不連続&エネルギー保存則が成立しないこと」にもとづいて、説明できると考えられる。
◎すなわち、時空が不連続である(時空が原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和である)ので、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」において、エネルギー保存則が成立しないとも言えそうである。
→すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」にとって時空が不連続である(時空が原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和である)ので、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」において、エネルギー保存則が成立しないとも言えそうである。
◎ したがって、ここに物理学の根幹をゆるがす部分があるとすれば、その本質は、「時空が不連続である」ということであると考えられる。
→したがって、ここに物理学の根幹をゆるがす部分があるとすれば、その本質は、「時空が不連続であること」、すなわち、「時空が素スピノールから創発するということ」であると考えられる。
◎この記述からも、不連続な時空を前提とする“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)取り組んでいる内容は、これまで、物理学が十分に探求してこなかったことであることがわかる。
→この記述からも、不連続な時空を前提とする“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が取り組んでいる内容は、これまで、物理学が十分に探求してこなかったことであることがわかる。
◎どのようなしくみで成功(自然(nature)と調和し)し、→どのようなしくみで成功し(自然(nature)と調和し)、
◎(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、一般相対性理論における、エネルギーに関する問題を解消する。
(→《一般相対性理論とエネルギー保存則について》))
→例えば、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、一般相対性理論における、エネルギーに関する問題を解消する。
(→《一般相対性理論とエネルギー保存則について》)
◎追加 ※なお、重力子や光子にとっては、時空は不連続であっても、素スピノールにとっては、時空は連続であると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎重力子質量MG[kg]に相当する質量エネルギー(MGc2[J]=(外部)運動エネルギーK[J])を持つ仮想質点の移動速度は、どれくらいになるだろうか?
原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)は、本来、様々な素粒子に対して、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”を持つと言われている。
→原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするエネルギー、すなわち、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する(外部)運動エネルギーK[J]を持つ仮想質点の移動速度は、どれくらいになるだろうか?
原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)は、「質量を与えるヒッグス場」にも相当するもので、本来、様々な素粒子に対して、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”を持つと考えられる。
◎この質量エネルギー(MGc2[J]=(外部)運動エネルギーK[J])を持ち続ける仮想質点に対しては、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”がほとんど働かなくなるので、ほとんど光速に近くなると考えられる。
※しかし、厳密には、ぴったり光速c[m/s]であるというのは、ありえない。
なぜなら、そうだとすると、その仮想質点は、1つの重力子とともに移動できるということを意味し、「重力子の放出源として働き続ける能力」を持っていないこと、すなわち、質量0であることを意味するからである。 したがって、厳密には、光速未満でなければならない。
→原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするために必要なエネルギーに等しい運動エネルギーを持つ「質量エネルギー(MGc2[J]=(外部)運動エネルギーK[J])を持ち続ける仮想質点」は、“光速c[m/s]を失わせるはずの抵抗作用”にやすやすと打ち勝つので、速やかに重力子を放出することになるだろう。しかも、この仮想質点にとって、時空は不連続なので、この過程によってエネルギーが失われることがないため、このブロセスはずっと続くだろう。
その結果、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”がほとんど働いていない状態に等しくなるので、ほとんど光速に近くなると考えられる。
◎よって、重力子質量MG[kg]に相当する質量エネルギー(MGc2[J]=(外部)運動エネルギーK[J])を持つ仮想質点の移動速度について、次のような仮説を立てた。
仮説1.2.2 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするエネルギーEG[J]と等しい大きさの(外部)運動エネルギーK(=MGc2[J])を持ち続けるの仮想質点は、ほとんど、c[m/s]に近い速さで移動する。
→よって、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する(外部)運動エネルギーK[J])を持ち続ける仮想質点の移動速度について、次のような仮説を立てた。
仮説1.2.2 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするエネルギーEG[J]と等しい大きさの(外部)運動エネルギーK(=MGc2[J])を持ち続ける仮想質点は、ほぼ光速c[m/s]の速さで軌道運動(移動)を続けることができる。
※連続な時空を前提とした、アインシュタインの特殊相対性理論によれば、光速に近づくためには、無限の大きさの運動エネルギーが必要であった。
しかし、この仮説は、光速に近づくためには、無限の大きさの運動エネルギーは不要であり、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に等しい(外部)運動エネルギーK[J]だけで十分であること意味している。 言い換えれば、この重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])は、運動エネルギーがとりうる最大値を提供してくれているのである。
(もしこの仮想質点が、エネルギーEG[J](=MGc2[J])よりも大きな運動エネルギー(重力子の放出源として働き続ける能力)を獲得すれば、光速を超えてしまうことになる)
このことは、力ポテンシャルエネルギーによる結合エネルギーの大きさがニュートン力学におけるGM2/rが、一般相対性理論で2GM2/rになることを説明するのを助ける。(→《重力場の線形性について(詳細版)》)
《重力場の線形性について(詳細版)》
◎3.重力ポテンシャルエネルギーにの大きさが、「線形なニュートンの重力理論において、GM/r」であるのに対し、「一般相対性理論においては、2GM/r」になる。
→3.重力ポテンシャルエネルギーの大きさが、「線形なニュートンの重力理論において、GM/r」であるのに対し、「一般相対性理論においては、2GM/r」になる。
◎以上より、“重力子質量MG[kg]を持つ仮想質点”は、ぼぼ速度c[m/s]で1秒間、運動する(1秒間に3×108−1.616×10−35[m]進む)間に、ほぼc/2LP= c/2LP[回]だけ、“4面体”と衝突できることになる。
→以上より、“重力子質量MG[kg]を持つ仮想質点”は、ぼぼ速度c[m/s]で1秒間、運動する(1秒間にほぼ3×108[m]進む)間に、ほぼc/2LP= c/2LP[回]だけ、“4面体”と衝突できることになる。
2017年6月27日 2.10.2→2.10.3
結果1
◎“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、まさに、この困難さを解消し、これらの答えの獲得を助けようとするものである。
→“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、まさに、この困難さを解消するような、これらの疑問に対する答えを探究するものである。
◎ 簡略表記[→ 簡略表記
◎※“スピン1/2の右巻き素スピノール”と“スピン1/2の左巻き素スピノール”が結びついて、スピン1の光子ができている。
→※“スピン1/2の左巻き素スピノール”と“スピン1/2の右巻き素スピノール”が結びついて、スピン1の光子ができている。
◎※この光子の説明は、弦理論で「光子は、スピン1を持つ開いた弦である」と説明されていることと調和している。
→※この光子の説明は、弦理論において「光子は、スピン1を持つ開いた弦である」と説明されていることと調和している。
◎仮説1.1.2 間隔rが波長λの1/2の「素スピノールのペア」がスピン1を保ちながら
→間隔rが波長λの1/2であるような「素スピノールのペア」がスピン1を保ちながら
◎1波長進むことを意味する。
→1波長分の距離を進むことを意味する。
◎ ※なお、それぞの素スピノールは、下図のように、小さな円軌道を運動すると考えられる。
→ ※なお、それぞれの素スピノールは、下図のように、小さな円軌道を運動すると考えられる。
◎先の『振動数νの電磁波(光も、電波も、ガンマ線も…)は、→先に述べた『振動数νの電磁波(光も、電波も、ガンマ線も…)は、
→
◎ そこで、 z=nλ/2での場所での電場や磁場の変化を求めてみるために、k=2π/λ、z=nλ/2を代入すると──
→ そこで、 z=nλ/2での場所での電場や磁場の変化を求めてみるために、z=nλ/2、k=2π/λを代入すると──
◎『電気双極子の振動によって生じる電磁波』も説明できるだろうと思われる。 (詳細な検討は、今後の課題である)
→『電気双極子の振動によって生じる電磁波』も説明できるだろうと思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。(→《電気双極子の振動に伴う放射について》)
◎ “右巻き素スピノールのペアと
左巻きの素スピノールのペア”
対消滅してできている
→“左巻き素スピノールのペアと
右巻きの素スピノールのペア”
対消滅してできている
◎追加 ※なお、例えば、光子を構成している素スピノールとして、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成している素スピノールが共転回している間は、この“連星のような(連続)軌道運動”は、一時的にストップすると考えられる。
そして、その間、共転回していない方の“連星のような(連続)軌道運動”は、続いていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎光子を構成するそれぞれの素スピノールに相当する。→光子を構成するそれぞれの素スピノールに相当している。
◎ 上図の左側にあるピンクの素スピノールの転回は、蓄えたエネルギーを放出する過程を担い、
右側にあるブルーの素スピノールの転回は、新たにエネルギーを蓄える過程を担うことになる。
→ 上図の、上段の左側にあるピンクの素スピノールの転回は、蓄えたエネルギーを放出する過程を担い、
右側にあるブルーの素スピノールの転回は、新たにエネルギーを蓄える過程を担うことになる。
◎なぜなら、磁場のエネルギー密度は、μ0H2/2で求まるのに対し、原始ヒッグス場ユニット(PHU)が作るミクロの磁場も、sinθに比例するからである。
→なぜなら、磁場のエネルギー密度は、μ0H2/2で求まる一方で、原始ヒッグス場ユニット(PHU)が作るミクロの磁場も、sinθに比例するからである。
◎z=nλ/2での場所での磁場の変化を求めてみるために、k=2π/λ、z=nλ/2を代入すると──
→z=nλ/2での場所での磁場の変化を求めてみるために、z=nλ/2、k=2π/λを代入すると──
◎ ※なお、厳密には、1つの光子が生む「電場のエネルギーと磁場のエネルギー」の合計が、1つの光子が生むエネルギーに相当すると言うことになる。
→ ※なお、厳密には、1つの光子が持っている「電場のエネルギーと磁場のエネルギー」の合計が、1つの光子が持っているエネルギーに相当すると言うことになる。
◎ このように説明できる、たった1つの光子は、まさに、一定のエネルギーを光速で伝達するものであり、“量子波(quantum wave)”という言葉にふさわしいものである。
(こういった光子の総和が、どのように、電磁波(レーザー、電気双極子の振動にともなって発生する電磁波を含む)を創発するのかについては、詳細な検討は、今後の課題である)
→ このように説明できる、たった1つの光子は、まさに、一定のエネルギーを光速で伝達するものであり、“量子波(quantum wave)”という言葉にふさわしいものである。
◎ この仮説は、一見すると、既存の物理学をゆるがすような前提であるという印象を与えるかもしれない。
→ この仮説を共転回原理と呼ぶこととする。 この共転回原理は、一見すると、既存の物理学をゆるがすような前提であるという印象を与えるかもしれない。
◎に相当するものと見なせるのだ。→に相当するものと見なせるものなのだ。
(2017年6月26日 2.10.1→2.10.2
◎研究トップページの日付、バージョン修正
◎『“現代物理学”の危機を解消する手段』のページのバージョン修正)
2017年6月24日 2.10.1→2.10.2
◎考察の“リンクの言葉”の修正(該当部分)
1.数式と自然(nature)について──“法則や理論”が成立するための条件について
2.抽象的な数学(数式、群論…)と、具体的な数学(幾何、フラクタル…)について
→1.数学&観測と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)について
2.数式と自然(nature)について
考察1
◎そして、「アインシュタインの方程式」そのものへの評価が高まれば高まるほど──
→そして、「アインシュタイン方程式」そのものへの評価が高まれば高まるほど──
◎少しずつ、“自然(nature)”と解離し始めてきた。
→少しずつ、“自然(nature)”から解離し始めてきた。
◎ そして、自然(nature)と、ほとんど完全に乖離してしまい──
現代物理学は、もはや、行き詰まった。
→そして、自然(nature)から、ほとんど完全に乖離してしまい──
現代物理学は、もはや行き詰まり、危機に直面した。
◎そして、「(自然(nature)と調和している)パラダイムの多様性」の尊重が、結果的に、自然(nature)という真実にたどり着くためのカギになるのではないか?
→そして、「(自然(nature)と調和している)パラダイムの多様性」を尊重し続けることが、結果的に、「自然(nature)と100%調和している理論」という“真理”にたどり着くためのカギになるのではないか?
◎「数学」は、確かに重要であり、数々の成功をもたらしてきたし、これから必要不可欠であるのは確かである。
→「数学」は、確かに重要であり、数々の成功をもたらしてきたし、これからも必要不可欠であるのは確かである。
◎『プリンキピア』において、具体的な幾何をも使って説明していたではないか?
→『プリンキピア』において、具体的な幾何を駆使して説明していたではないか?
◎追加
※次の記述も、大いに参考になる。
『かつてアインシュタインは、相対性理論では宇宙のあらゆるところに別々の速さで時を刻む時計をおいていたけれども、実生活では時計を一つも置くつもりはない、と言ったことがある。
こういうアインシュタインの言葉の中に、大発見にいたる道への手がかりが示されている──彼はいつでも具体的な、物理的イメージで考えていたのだ。数学はどんなに抽象的で難解だろうと、どうせ後から登場するもので、主としてこういった物理的イメージを精密な言葉に翻訳するための道具なのだ。物理的なイメージは一般大衆にもわかるほど単純で簡潔なものだと、アインシュタインは確信していた。数学がいかに不明瞭だろうと、物理的イメージは常に本質をついているのだ。
…
アインシュタインは驚くほど鋭い洞察力によって、あらゆるものを単純な物理的イメージで見ていたので、他の人より先を読むことができたのである。アインシュタインを相対性理論に導いたのは、その絵画的な洞察力だった。三〇年にわたってアインシュタインが物理学界の巨峰だったのは、彼の物理的イメージが的確で、概念を考える能力が正確だったからである。』
(『アインシュタインを超える』 p.61-62 M・カク、J・トレイナー[著] 久志本克己[訳] 広瀬立成〔監修〕 講談社ブルーバックス ※アンダーラインは、筆者による。) |
◎という王道が、壊れてしまう結果となった。
→という王道から、ますます外れてしまうことが促される結果となった。
◎そして「マクスウェル〜アインシュタインが達成した場(field)物理革命」の頃から失われてきた
→そして「マクスウェル〜アインシュタインが達成した場(field)物理革命」の頃から失われ始めてきた
◎驚くほど深くて広い成果をもたらしてくれる、フルーツフルな科学スタイルなのである。
→驚くほど深くて広い成果をもたらしうるものとなったと考えられるのである。
◎“たった1つの力から4つの力が分岐した”、… “(抽象的な)数式上、矛盾していない”という理由だけで存続している理論たち──
→… “(抽象的な)数式上、矛盾していない”という理由だけで存続している理論たち──
◎ 二カ所 そのための根拠、よりどころが、なかったからである。
→そのための「根拠、よりどころ…」がなかったからである。
◎なぜなら、それは、「ズームインするほどシンプルになる」という自然な世界観と調和していないからである。
→なぜなら、それは、「ズームインするほどシンプルになる」という自然な世界観から乖離しているからである。
◎“自然な世界観”(3Steps原理)、すなわち、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が持っている科学スタイル」なのである。
→“自然な世界観”(3Steps原理)、および、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が持っている科学スタイル」なのである。
◎新たな「理論」や「数式」を探求することができるようになることを助けるのだ。
→新たな「理論」や「数式」を探求できるようになることを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が助けるのだ。
2017年6月21日 2.10→2.10.1
考察3 超弦理論〈Superstring Theory〉について
◎引用文の修正 理論を有限にする
鍵根本的な鍵は→理論を有限にする根本的な鍵は
◎追加
『量子力学と相対性理論を結びつけようとすると、多くの落とし穴──アノマリー、発散、タキオン(光より速い粒子)、幽霊(ゴースト、不の確率を持つ粒子)、その他さまざまな病変を集めた本物の地雷源──が出てくるので、それらを抹殺するには膨大な量の対称性が必要なのである。
単純に言うと、超弦モデルが「うまくいく」のは、今までの物理モデルの中で最大の対称性を持っているからである。点ではなく弦に基づいた理論を書き上げると自然に生じるこの対称性の大きな集合は、そのアノマリーや発散を充分に打ち消すことができる』
(『アインシュタインを超える』 p.276-277 M・カク、J・トレイナー[著] 久志本克己[訳] 広瀬立成〔監修〕 講談社ブルーバックス)
|
『多くの落とし穴──アノマリー、発散、タキオン(光より速い粒子)、幽霊(ゴースト、不の確率を持つ粒子)、その他さまざまな病変を集めた本物の地雷源』を解消するために生み出された対称性の1つが、「超対称性」であったことが読み取れる。
そもそも、「不完全な量子物理学」や「不完全な相対性理論」を結びつけようとしたからこそ、これらの問題が生じてしまったのではないだろうか? もし、「完全な量子物理学」や「完全な相対性理論」を結びつけようするのであれば、これらの問題は生じないのではないだろうか?
詳細な検討は、今後の課題である。 |
◎既存の物理学(量子論(量子力学、場の量子論)、大統一理論を含む)を最大限に尊重しながら育まれていること── すなわち、抽象的な数学(抽象的な数式(ハイゼンベルクの不確定性原理(不確定性関係))、抽象的な幾何学(ファインマン図…)、ゲージ原理…)に基づいて、育まれていることがわかる。
※「“超弦理論”が不完全な量子物理学を前提にして育まれている以上、“超弦理論”は、不完全にならざるをえない」と言うこともできると思われる。
→
既存の物理学(相対性理論、量子論(量子力学、場の量子論)、大統一理論を含む)を最大限に尊重しながら育まれていること── すなわち、抽象的な数学(抽象的な数式(ハイゼンベルクの不確定性原理(不確定性関係))、抽象的な幾何学(ファインマン図…)、ゲージ原理、対称性…)に基づいて、育まれていることがわかる。
※『“超弦理論”が「不完全な量子物理学」や「不完全な相対性理論」を前提にして育まれてしまった以上、“超弦理論”は、不完全にならざるをえない』と言うこともできると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎追加
|
相対性理論
|
完全である
|
不完全である
「時空の曲り、光速不変、エーテル…」を
「より深いレベルの階層」から説明し直す
|
◎ すなわち、不完全な量子物理学をそのまま尊重し続けるという“物理学の伝統”の結果──
→ すなわち、不完全な量子物理学や不完全な相対性理論をそのまま尊重し続けるという“物理学の伝統”の結果──
◎ただし、この考えにおいて、新たに追加された“コンパクトな新たな次元”(5次元目)とは、“新たな高次元空間”とは無縁のものである。 (詳細な検討は、今後の課題である)
→ただし、この考えにおいて、新たに追加された“コンパクトな新たな次元”(5次元目)とは、“新たな高次元空間”とは無縁のものである。
◎追加
なお、こういった“コンパクトな新たな次元”(5次元目)の説明は、次の記述と調和していると思われる。
『カルツアはすでに五つめの次元は円のように「丸まって」いるから他の四つの次元とはちがうのだと主張していた。宇宙がどう見ても四次元に見える理由を説明するのに、クラインの解答は、この円のサイズがあまりに小さいため直接観測することができないのだ、というものだった。
言い換えると、部屋に放出されたガス分子は確かにあらゆる空間次元を探し出しているのだが、分子は大きすぎるため、円形の第五次元には入っていけないのだ。その結果、ガス分子は五つの次元ではなく、四つの次元にしか充満しないのである。
クラインは第五のサイズがどのくらいになりうるのかも計算している。それはプランク長すなわち10-33センチメートル、言い換えると原子核の100億分のさらに100億分の一の大きさだ。』
(『アインシュタインを超える』 p.226-227 M・カク、J・トレイナー[著] 久志本克己[訳] 広瀬立成〔監修〕 講談社ブルーバックス)
|
| ※クラインによって計算されたサイズも、ほぼぴったりだと思われる。 なお、「プランク長すなわち10-33センチメートル」とは、LP〔m〕≒1.6×10-35〔m〕のことであった。 |
◎※もしかしたら、あらゆる余剰次元は、“高次元空間”によって、説明するのではなく、何かの実体の“自由度”で説明すれば、自然(nature)と調和し続けると言えるのかもしれない。
→※もしかしたら、あらゆる余剰次元は、得体の知れない“高次元空間”によって説明するのではなく、何かの実体の“自由度”で説明すれば、自然(nature)と調和し続けると言えるのかもしれない。
◎追加 ※この図の○は、プレオン∴に相当する
◎2カ所 物理史上最も大胆な→物理学史上最も大胆な
◎ 高次元空間が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していないことは、次の理由による。
→ 高次元空間が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していないことは、次の理由からわかる。
参考文献
◎追加 『アインシュタインを超える』 M・カク、J・トレイナー[著] 久志本克己[訳] 広瀬立成〔監修〕 講談社ブルーバックス
2017年6月14日 2.09→2.10
◎ページ追加 7.パラダイムと「科学の進歩」について
(
7.パラダイムと「科学の進歩」について)
◎次の6つについて考察する。→ 次の7つについて考察する。
◎追加 重力場(“時空の曲り”)の量子化を目指す一方で── 時空そのものは連続であり、エネルギー保存が成立すると説明している(or無限小を考えられるものとしている(微分可能であるとしている))。
◎(閉鎖系で)エネルギー保存則が成立すると説明している一方で── ミクロの世界では、不確定性原理が理由で、エネルギー保存則を破って仮想粒子が生じると説明し、その合計が無限大になると計算されている。(この根本的な矛盾を、根底から解消しようとしないままに、“繰り込み”という操作(数字合わせ)によって計算値と観測値が“10桁以上で”一致していることをもって、最高の成功の1つと見なしている。 このことは「only数字合わせ科学」を最も象徴している例の1つである)
→(閉鎖系で)エネルギー保存則が成立すると説明している一方で── ミクロの世界では、不確定性原理が理由で、エネルギー保存則を破って仮想粒子が生じると説明し、その合計が無限大(orある有限の値)になると計算されている。
各ページの修正
結果1
◎ その結果、アインシュタインは、どうしようもない板挟みにあった(どうしようもなく行き詰まった)のである。
→その結果、アインシュタインは、板挟みにあったのである。(『それにもかかわらず、このような減衰のない振動を考えられることができる。〜』以下のような無理のある考えをひねり出すほど、追いつめられたのである)
◎ すなわち、「連続な時空」と、重力子(「重力の量子化」)は、矛盾しているのである。
したがって、一般相対性理論が「連続な時空を前提とするリーマン幾何学」に依存していることが、重力の量子化を困難にしてきた最大の要因の1つであったことになる。
→すなわち、「連続な時空」と、重力子、および、「重力の量子化」(「重力場(時空の曲り)の量子化」)は、矛盾しているのである。
したがって、一般相対性理論が「連続な時空を前提とするリーマン幾何学」に依存していることが、重力の量子化(「重力場(時空の曲り)の量子化」)を困難にしてきた最大の要因の1つであったことになる。
◎追加
また、例えば、重力子(or その総和としての重力波)についても、計算値と観測値と一致は、(100%完全な真空が存在しないがゆえに)「単に真空と見なされた宇宙空間内に存在する分子との衝突を介する熱伝導&対流によって、エネルギーが失われていたに過ぎない」ということになるだろう。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wikipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
◎ つまり、実際は、楕円軌道とはならずに、互いに渦巻きを描いて近づいていくことは、理論上は、「重力波がエネルギーを持ち去る」と「重力波はエネルギーを持ち去らない」の両方で説明できるが── 力学的エネルギー保存則、アインシュタインの式(E=mc2=(m0c2/(1−(v/c)2)1/2 m0:静止質量)、ニュートンの万有引力F=GMm/r2[N]の式と矛盾していない(調和している)のは、後者のみである。
→
|
※なお、以上の説明(「重力波によってエネルギーが持ち去られない」と「重力波によってエネルギーが持ち去られる」の両方)においては、(100%完全な真空が存在しないがゆえに)「単に真空と見なされた宇宙空間内に存在する分子との衝突、すなわち、“うすい空気”の摩擦抵抗によって、エネルギーが失われる」という効果が、一切、考慮に入れられていない。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wikipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
それは、次のように大きく2つに分けて考えればよいと思われる。
1.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できない場合
2.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できる場合
1.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できない場合
例えば、地球が太陽の周囲を公転しているような場合、連星パルサーがきわめてゆっくり公転周期を小さくしている場合に相当すると考えられる。 その場合、重力波によって持ち去られていたと考えられていたエネルギーの大部分が、実際には、「“うすい空気”との摩擦」によって少しずつ失われていることになる。この場合、「重力波によって持ち去られると考えられるエネルギー」は、(上記で説明したように)「増加する運動エネルギーに相当するエネルギー」とは等しくはならず、部分的に「“うすい空気”との摩擦によって失われるエネルギー」によって相殺されると考えられる。 (厳密な計算を含め、詳細な検討は、今後の課題である)
2.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できる場合
連星パルサーや2つの巨大ブラックホールがらせんを描いて合体する直前等に、急激な「自由落下的な加速運動」をともないながら(重力波の振幅の増加を加速させながら)公転周期を小さくする場合に相当すると考えられる。
この場合、重力波によって持ち去られていたと考えられていたエネルギーの大部分が、「増加する運動エネルギーに相当するエネルギー」にほぼ等しくなる。 なぜなら、らせんを描いて衝突する直前においては、「増加する運動エネルギーに相当するエネルギー」が、とても大きくなるので、「“うすい空気”との摩擦」によって奪われるエネルギーを無視できると考えられるからである。
(厳密な計算を含め、詳細な検討は、今後の課題である)
|
つまり、実際は、楕円軌道とはならずに、互いに渦巻きを描いて近づいていくことは、理論上は、「重力波がエネルギーを持ち去る」と「重力波はエネルギーを持ち去らない」の両方で説明できることがわかる。
両者は、ともにネーターの定理と調和している。 しかし、運動エネルギーが増すと質量が増加すること(アインシュタインの式E=mc2=(m0c2/(1−(v/c)2)1/2 (m0:静止質量)が示しいること)、質量が増すと重力が大きくなること(ニュートンの万有引力F=GMm/r2[N]の式が示していること)、「“うすい空気”との摩擦」によってエネルギーが奪われることのいずれとも矛盾していない(調和している)のは、後者のみであると考えられる。(詳細な検討は、今後の課題である)
◎したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明は、次の成果を、決して否定するものではないことがわかる。
→“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明は、次の成果を、決して否定するものではない。
◎すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、この成果が、どのようなしくみで、成立しているか説明するものである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、この成果をゆるがし、否定するものでなく── 「より深いレベルの階層」から説明し、支持し、包含するものなのである。
→すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、この成果をくつがえす(否定する)ものでなく、「より深いレベルの階層」から説明して包含するものなのである。
結果4◎「人類が、どうあがいたって観測できない範囲の自然(nature)を含めて、合理的に探求する物理学」にも、存在意義があるのだ。
→「人類が、どうあがいたって観測できない範囲を含めて、自然(nature)を合理的に、そして、具体的に探求する物理学」にも、存在意義があるのだ。
◎「人類が、どうあがいたって観測できない、ミクロの自然(nature)を含めて、合理的に探求する物理学」の間には矛盾はなく、両者は、調和的に共存できるものなのだ。
→「人類が、どうあがいたって観測できないミクロのレベルを含めて、自然(nature)を合理的に、そして、具体的に探求する物理学」の間には矛盾はなく、両者は、調和的に共存できるものなのだ。
考察3
◎ すなわち、この『根本的な転』とは、→ すなわち、この『根本的な転換』とは、
考察6
◎“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分やおよび、“自然な世界観(3Steps原理)の根幹”が、反証されなかったことになると同時に
→◎“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分および“自然な世界観(3Steps原理)の根幹”が、反証されなかったことになると同時に
◎ また、例えば、重力子(or その総和としての重力波)についても、計算値と観測値と一致は、(100%完全な真空が存在しないがゆえに)「単に真空と見なされた宇宙空間内に存在する分子との衝突を介する熱伝導&対流によって、エネルギーが失われていたに過ぎない」ということになるだろう。
→ また、例えば、重力子(or その総和としての重力波)に関して、連星パルサー等が楕円軌道にならずにらせんを描いて近づくことは、重力子(or その総和としての重力波)によるエネルギーの持ち去りによるのではなく、(100%完全な真空が存在しないがゆえに)「単に真空と見なされた宇宙空間内に存在する分子との衝突を介する熱伝導&対流によって、エネルギーが失われていたことによる」という説明もありうることになるだろう。(詳細な検討は、今後の課題である)
◎追加
例えば、“新しい手段”は、「古い科学哲学
」(論理実証主義…)も、「新科学哲学」(『科学革命の構造』…)も、両方を尊重するべきであることを支持している。
◎追加 この論文で提案されている新たなパラダイムは、『新旧のパラダイムの急減な転換(科学革命)』を促しているものではなく、(自然(nature)調和している部分を持つ)既存のパラダイムの統合による、「パラダイムの進化」、すなわち、「科学の進歩」を促しているものなのである。
そして、そのことは、この研究が、科学哲学の「パラダイムの進化」── 「古い科学哲学」(論理実証主義…)と「新科学哲学」(『科学哲学の構造』…)の統合を促していることも意味しているのである。
付録
その他3
◎リンク修正2カ所 材料&手段(Material&Method)→ 材料&手段(Material&Method)
参考文献
◎『ビッグクエスチョンズ 物理 マイケル・ブルックス著 サイモン・ブラックバーン編 久保尚子訳 ディスカバリー』→『ビッグクエスチョンズ 物理』 マイケル・ブルックス著 サイモン・ブラックバーン編 久保尚子訳 ディスカバリー
◎『ファインマン物理学 電磁気学』 ファインマン 宮島龍興訳
→『ファインマン物理学 電磁気学』 ファインマン 宮島龍興訳 岩波書店
◎『聞かせて、弦理論 時空・ブレーン・世界の端』 スティーブン・S・ガブサー 吉田三知世訳
→『聞かせて、弦理論 時空・ブレーン・世界の端』 スティーブン・S・ガブサー 吉田三知世訳 岩波書店
◎ 『We Are the Weather Maker』 Tim Flannary
→ 『We Are the Weather Maker』 Tim Flannary PENGUIN BOOKS
◎『近代化学を超えて』 村上陽一郎 講談社学術文庫→『近代科学を超えて』 村上陽一郎 講談社学術文庫
◎追加 『改訂新版 細胞の社会 生命秩序の基本を探る』 岡田節人 講談社ブルーバックス
◎追加
『科学的発見のパターン』 N・R・ハンソン 村上陽一郎訳 講談社学術文庫
『パラダイムとは何か』 野家啓一(講談社学術文庫)
『科学の解釈学』 野家啓一(講談社学術文庫)
2017年5月28日
◎追加 重力場(“時空の曲り”)の量子化を目指す一方で── 時空そのものは連続であり、エネルギー保存が成立すると説明している(or無限小を考えられるものとしている(微分可能であるとしている))。
◎下記 2017年5月28日履歴にて追加 2.08→2.09
2017年5月28日 2.08→2.09
◎
要約〈Abstract(Summary)〉→
要約(Abstract)
◎該当部分
“現代物理学”が陥った行き詰まり、困難、迷走…
を解消する新しい手段の紹介
→“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介
◎上部&下部リンク 該当部分
4.自然な世界観(3Steps原理)
5.“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
→
4.論理の一貫性(無矛盾性)
5.自然な世界観(3Steps原理)
6.“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
◎該当部分
『“自然な世界観”(3Steps原理)と調和していること
→『“自然な世界観”(3Steps原理…)と調和していること』
◎
現代物理学は、精密な観測結果、そして、抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何、群論…)に基づいて発展してきた。
しかし、観測上の限界(ハイゼンベルグの不確定性原理、波と粒子の二重性、加速器の大きさの限界…)、理論上の限界(ゲーテルの不完全性定理…)にぶつかるともに、現代物理学において、“行き詰まり、困難、迷走…”が生じてしまった。
こういった現状を持つ現代物理学の世界を、「ズームインするほど自然(nature)はシンプル一様化するという原理(シンブル一様化原理)」(および「ズームアウトするほど自然(nature)は、複雑多様化するという原理(複雑多様化原理)」)や「フラクタル相似の原理」などの“自然な世界観”(3Steps原理)をもとに── 単純な、幾何構造の働きの総和として、説明することに取り組んだ。
→ 現代物理学は、精密な観測値と、抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何、群論…)による計算値を一致させることだけに基づいて発展してきた。
しかし、観測上の限界(ハイゼンベルグの不確定性原理、波と粒子の二重性、加速器の大きさの限界…)、理論上の限界(ゲーテルの不完全性定理…)にぶつかると同時に、予想された「陽子崩壊、超対称性粒子…」が観測されないという危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”に、現代物理学は陥った。
この現代物理学の危機は、まさに「only数字合わせ科学」の限界が生んだ危機に他ならない。
この「only数字合わせ科学」の限界を解消すべく、「ズームインするほど自然(nature)はシンプル一様化するという原理(シンブル一様化原理)」(および「ズームアウトするほど自然(nature)は、複雑多様化するという原理(複雑多様化原理)」)や「フラクタル相似の原理」などの“自然な世界観”(3Steps原理)を用いて── これまで説明しようしてきた自然界(natural world)を、単純な、幾何構造の働きの総和として、新たに説明することに取り組んだ。
◎これらの成果は、現代物理学における“迷走、行き詰まり、困難、閉塞感、不毛性、衝突&対立…”の主要な原因が、
→これらの成果は、現代物理学における危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、閉塞感、不毛性、衝突&対立…”の主要な原因が、
◎
現代物理学における“迷走、行き詰まり、困難、閉塞感、不毛性、衝突&対立…”に至ってしまった主な原因であったことを
→現代物理学における危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、閉塞感、不毛性、衝突&対立…”の主な原因であったことを
◎
現代物理学が、「迷走、行き詰まり、困難、閉塞感、不毛性、衝突&対立…」に至ってしまうのは、当然と言えば、当然のことだったのである。
→現代物理学が危機──「根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、閉塞感、不毛性、衝突&対立…」に至ってしまうのは、当然と言えば、当然のことだったのである。
◎
「限界ぎりぎりの観測」のみに依存してきてきた現代物理学における“迷走、行き詰まり、困難、閉塞感、不毛性、衝突&対立… を解消すると同時に
→「限界ぎりぎりの観測」のみに依存してきてきた現代物理学における危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、閉塞感、不毛性、衝突&対立…”を解消すると同時に
◎
(これらによって、現代物理学の行き詰まり、困難、迷走…を解消できるかどうか)
→(これらによって、現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”を解消できるかどうか)
◎
イントロ〈Intoduction〉→
イントロ(Intoduction)
◎
抽象的な数学(主に抽象的な数式)と、より精密な観測結果に依存しながら、大いに発展してきた。
その後の、目をみはる偉大な発展の数々が、相対性理論、量子論(量子力学、場の量子論)、素粒子物理学の標準模型… であるのは、疑いの余地がない。
→抽象的な数学(主に抽象的な数式)と、より精密な観測結果を一致させることだけに依存しながら、大いに発展してきた。
それは、いわば「only数字合わせ科学」と呼べるものであったが、その後の「相対性理論、量子論(量子力学、場の量子論)、素粒子物理学の標準模型…」を含む、目をみはる偉大な発展の数々を支えた。
◎
しかし、観測上の限界(ハイゼンベルグの不確定性原理、波と粒子の二重性、巨大加速器の大きさの限界…)、数学理論上の限界(ゲーテルの不完全性定理…)
に人類がぶつかってしまうとともに── その発展にブレーキがかかり減速することとなった。
→しかし、この「only数字合わせ科学」は、観測上の限界(ハイゼンベルグの不確定性原理、波と粒子の二重性、巨大加速器の大きさの限界…)、数学理論上の限界(ゲーテルの不完全性定理…)
にぶつかってしまうとともに── その発展にブレーキがかかり減速することとなった。
◎
数学的において全く矛盾がない(数式的には、正しい)のに関わらず──
観測による検証ができなかったり、“不自然で無理のある”前提を含んでいたり、対象がうやむやにされていたり… という問題を含む。 すなわち、これらの理論は、観測不能であったり、「自然(nature)から乖離した想像」が前提となって育まれていたり、(対象が不明確なので)やむをえず抽象的な数学に依存して育まれた理論であったりするのに関わらず、“数学的に矛盾がない”というだけの理由で、正当化され続けてきたという問題を持っていた。
このような問題が、物理学の分野における、“迷走、行き詰まり、困難、閉塞感、不毛性、衝突&対立…”を生じさせてきてしまったことは否定できない。
→ しかし、これらの理論は、数学的に全く矛盾がない(数式的に正しい、論理的に一貫している)のに関わらず── すでに観測されていいはずのもの(例えば、「陽子崩壊、超対称性粒子…」
)が観測されなかったり、
観測による検証が全く不可能であったり、“不自然で無理のある”前提を含んでいたり、対象がうやむやにされていたり… という問題を含んでいた。
すなわち、これらの理論は、予想が外れていたり、観測不能であったり、「自然(nature)から乖離した想像」が前提となって育まれていたり、(対象が不明確なので)やむをえず抽象的な数学に依存して育まれた理論であったり… するのに関わらず、「“数学的に矛盾していない”“数字が一致する”…」という理由だけで、正当化され続けてきたという問題を持っていた。
ここにあるのは、まさに現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、
閉塞感、不毛性…”である。
そして、こういった危機は、結局は、
「only数字合わせ科学」の限界によって生じているものに他ならないのである。
◎
こういった状況は、“観測上の限界”や“数学理論上の限界”があるのだから、やむを得ないことなのだろうか?
これは、“観測上の限界”や“数学理論上の限界”がある以上、人類にとって避けられないことなのだろうか?
「観測結果、抽象的な数学(抽象的な数式や抽象的な幾何…)、想像力」に頼る以外に、人類には、真実の探究に使える手段は、残されていないのだろうか?
→こういった状況は、“観測上の限界”や“数学理論上の限界”がある以上、人類にとって避けられないことなのだろうか?
本当に、「(限られた)観測結果」や「抽象的な数学(抽象的な数式や抽象的な幾何…)」、および、「想像力」や「数学的な一貫性(無矛盾性)」に頼る以外に、人類には、真実の探究に使える手段は、残されていないのだろうか?
◎ それは、次の3つの原理で示されるものである。
→ それは、少なくとも、次の3つの原理で示されるものである。
◎追加 ※なお、“自然な世界観(natural world-view)”には、例えば、“地動説(地球が太陽の周囲を公転している)”も含まれる。
◎そして想像力も含めて、可能な限り、あらゆる手段、ヒント、手がかりを重視していく。
→そして「想像力」や「論理の一貫性(無矛盾性)」も含めて、可能な限り、あらゆる手段、ヒント、手がかりを重視していく。
◎現在の理論物理学の分野での“迷走、行き詰まり、困難、閉塞感、不毛性、衝突&対立… を生じさせてしまった主要な原因が
→現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、閉塞感、不毛性、衝突&対立… を生じさせてしまった主要な原因が、
◎Method&Material(手段・道具&材料)→ 材料&手段(Material&Method)
◎ この研究を進めるために用いた「材料や道具・手段」は、次のものである。
→ この研究を進めるために用いた「材料や手段」は、次のものである。
◎ すなわち、この論文で提案する新たな手段(自然な世界観(3Steps原理)、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何))のみならず、自然(nature)と調和していると判断できる、これまでの科学的な成果のすべても、ここに含まれる。
→(テーブルの上から下に移動)すなわち、材料には、(自然(nature)と調和していると判断できる)これまでの科学的な成果のすべてが含まれ── 手段には、これまでの理論物理学の手段のみならず、この論文で提案する新たな手段(自然な世界観(3Steps原理)、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何)…)が含まれる。
◎リンク該当部分 手段・道具&材料→材料&手段
◎リンク該当部分 手段・道具&材料(Method&Material)→ 材料&手段(Material&Method)
◎
| (4)自然な世界観(“3Steps原理”) |
(5)“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)(by具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何))
|
→
| (4)論理の一貫性(無矛盾性) |
| (5)自然な世界観(“3Steps原理”…) |
(6)“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)(by具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何))
|
◎追加
単なる「数学的な一貫性(無矛盾性)」ではなく、(「数学的な一貫性(無矛盾性)」を一部に包含するところの)「論理の一貫性(無矛盾性)」を重視していく。
(この「論理の一貫性(無矛盾性)」も「自然との調和性」とともに、科学の必要条件である)
そして、この「論理の一貫性(無矛盾性)」を重視することによってはじめて── 現代物理学が“根本的な矛盾”をいくつも抱えていることに気づくことができ、そして、これらの“根本的な矛盾”の多くを解消していくことが動機づけられるのである。
(逆に言えば、単なる「数学的な一貫性(無矛盾性)」だけを重視しているからこそ── 現代物理学が“根本的な矛盾”を抱えていることに気づくことができなかったり、それらの“根本的な矛盾”を軽視、無視… してしまったりするのである)
※現代物理学が抱えている“根本的な矛盾”には、例えば、次のようなものがある。
特殊相対性理論において、エーテルは否定されたはずなのに── アインシュタインは、一般相対性理論において「エーテルが必要不可欠である」と述べている。
|
ヒッグス場は、光速を失わせるような“抵抗”を持っているはずなのに、その中で、「等速直線運動」が実現している。
|
もし、孤立系の中で、バラバラに(分散して)存在する多くの粒子が、重力によって、集中すればするほど(コンパクト化すればするほど)エントロピーは減るはずなのに── 孤立系でエントロピーが減らないことを主張する熱力学第2法則がある。
|
E=mc2により、「エネルギーは質量を持つ」と考えられている一方で── エネルギーを持つはずの「光子、重力子」は質量を持たず、光速で進むことができる。
|
質量同士は、重力子をやりとりして、引き合っていると考えられている一方で── この(あらゆる質量から放出されているはずの)重力子が、非常に大きな質量を持つブラックホールについては考慮されていない。
|
| (閉鎖系で)エネルギーが生成も消滅しないことを主張するエネルギー保存則(熱力学第1法則)が存在している一方で── 「光冷却の現象」、「ある運動エネルギーを持つ物体に対する“負の仕事”による減速」… において、エネルギーの一部が消滅している。 |
| (閉鎖系で)エネルギー保存則が成立すると説明している一方で── ミクロの世界では、不確定性原理が理由で、エネルギー保存則を破って仮想粒子が生じると説明し、その合計が無限大になると計算されている。(この根本的な矛盾を、根底から解消しようとしないままに、“繰り込み”という操作(数字合わせ)によって計算値と観測値が“10桁以上で”一致していることをもって、最高の成功の1つと見なしている。 このことは「only数字合わせ科学」を最も象徴している例の1つである) |
| 「陽子崩壊」や「超対称性粒子」が、(理論上)もうすでに観測されてよかったはずだったのに── 実際は、発見されてきていない。 |
| … |
◎
| (4)“3Steps原理”The principles of 3Steps |
→
| (5)自然な世界観(“3Steps原理”The principles of 3Steps…) |
◎想像力を駆使して、なおかつ、→「想像力」や「数学的な一貫性(無矛盾性)」を駆使して、
◎まさに、それを補う手段が、3Steps理論から見い出された、3Steps原理である。
→まさに、それを補う手段が、自然な世界観であり、その一例が、3Steps理論から見い出された、3Steps原理である。
※なお、例えば、地動説(“地動説(地球が太陽の周囲を公転している)も、自然な世界観の一例である。
もし、この地動説という名の「自然な世界観」がなかったならば、今だに「
(惑星運動を正確に予測できる)天動説」を却下することができなかったのである。
◎
| (5)“EMOES”(Emergent Model of Elementary Spinors、素スピノールからの創発モデル) |
→
| (6)“EMOES”(Emergent Model of Elementary Spinors、素スピノールからの創発モデル) |
◎
結果──Result→結果(Result)
結果1
◎ここにある“らせん軌道をとりながら自由落下する”系は、単純に、次のような“二ュートンの思考実験の世界”の延長上のものであると言うことは
できない。→
→ところで、ここにある“らせん軌道をとりながら自由落下する”系は、単純に、次のような“二ュートンの思考実験の世界”の延長上のものであると言うことはできない。
◎すなわち、次のような説明では不十分である。
『もし、遠心力と重力が釣り合っていれば、そのまま円運動を続ける。
しかし、わずかでも遠心力が重力を下回っていたら、自由落下の効果によって、加速しながら軌道を縮め、最終的に、自然に地上にたどり着くようになる。 その過程は、あくまで重力ポテンシャルエネルギーが原因である。 このような系は、まさに、“らせん軌道をとりながら自由落下する”系である。
少しでも、遠心力<重力となってしまった時点で、“らせん軌道をとりながらの自由落下”が始まり、それがそのまま続いていくのである。
そして、その後は、二度と遠心力と重力が釣り合うことがなくなるのである。
つまり、少しでも、遠心力<重力となってしまった時点で、“重力波によるエネルギーの持ち去り”は、全く不要になるのである。』
→すなわち、次のような説明では不十分である。
|
『もし、遠心力と重力が釣り合っていれば、そのまま円運動を続ける。
しかし、わずかでも遠心力が重力を下回っていたら、自由落下の効果によって、加速しながら軌道を縮め、最終的に、自然に地上にたどり着くようになる。 その過程は、あくまで重力ポテンシャルエネルギーが原因である。 このような系は、まさに、“らせん軌道をとりながら自由落下する”系である。
少しでも、遠心力<重力となってしまった時点で、“らせん軌道をとりながらの自由落下”が始まり、それがそのまま続いていくのである。
そして、その後は、二度と遠心力と重力が釣り合うことがなくなるのである。
つまり、少しでも、遠心力<重力となってしまった時点で、“重力波によるエネルギーの持ち去り”は、全く不要になるのである。』
|
◎一方、このことを、「重力波によってエネルギーの持ち去られない」ことによって説明すると次のようになる。
→ 一方、このことを、「重力波によってエネルギーが持ち去られない」ことによって説明すると次のようになる。
◎
|
※なお、一方で、(100%完全な真空が存在しないがゆえに)「単に真空と見なされた宇宙空間内に存在する分子との衝突を介する熱伝導&対流によって、エネルギーが失われる」結果、楕円軌道にならずに渦巻きを描いて互いに近づいてくるという説明もありうることに気づかれる。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wikipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
|
→
|
※なお、以上の説明(「重力波によってエネルギーが持ち去られない」と「重力波によってエネルギーが持ち去られる」の両方)においては、(100%完全な真空が存在しないがゆえに)「単に真空と見なされた宇宙空間内に存在する分子との衝突、すなわち、“うすい空気”の摩擦抵抗によって、エネルギーが失われる」という効果が、一切、考慮に入れられていない。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wikipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
それは、次のように大きく2つに分けて考えればよいと思われる。
1.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できない場合
2.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できる場合
1.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できない場合
例えば、地球が太陽の周囲を公転しているような場合、連星パルサーがきわめてゆっくり公転周期を小さくしている場合に相当すると考えられる。 その場合、重力波によって持ち去られていたと考えられていたエネルギーの大部分が、実際には、「“うすい空気”との摩擦」によって少しずつ失われている。この場合、「重力波によって持ち去られると考えられるエネルギー」は、ほぼ「“うすい空気”との摩擦によって失われるエネルギー」に等しくなるので、「運動エネルギーの増加と考えられるエネルギー」と等しくはならない。
2.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できる場合
連星パルサーや2つの巨大ブラックホールが合体する直前等の、加速的(自由落下的に)に公転周期を小さくする場合に相当すると考えられる。
この場合、主に「重力波によってエネルギーが持ち去られない」場合に説明した効果が、「“うすい空気”との摩擦」による効果をはるかに上回るっていることになる。 したがって、らせんを描いて衝突する現象は、主に「重力波によってエネルギーが持ち去られない」場合に説明した効果によって生じていると考えられる。この場合は、(「“うすい空気”との摩擦によって失われるエネルギー」が無視されるので)「重力波によって持ち去られると考えられたエネルギー」と「運動エネルギーの増加と考えられるエネルギー」が、ほぼ等しくなる。
|
◎つまり、実際は、楕円軌道とはならずに、互いに渦巻きを描いて近づいていくことは、「重力波がエネルギーを持ち去る」と「重力波はエネルギーを持ち去らない」の両方で説明できるということになる。 ただし、力学的エネルギー保存則、アインシュタインの式(E=mc2=(m0c2/(1−(v/c)2)1/2 m0:静止質量)、ニュートンの万有引力F=GMm/r2[N]の式と矛盾していない(調和している)のは、後者のみである。
→ つまり、実際は、楕円軌道とはならずに、互いに渦巻きを描いて近づいていくことは、理論上は、「重力波がエネルギーを持ち去る」と「重力波はエネルギーを持ち去らない」の両方で説明できるが── 力学的エネルギー保存則、アインシュタインの式(E=mc2=(m0c2/(1−(v/c)2)1/2 m0:静止質量)、ニュートンの万有引力F=GMm/r2[N]の式、「“うすい空気”との摩擦抵抗」と矛盾していない(調和している)のは、後者のみである。
結果4
◎4カ所「現代物理学の行き詰まり、困難、迷走…」→「現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”」
◎「観測や数式に基づいて生じた行き詰まり、困難、迷走…」
→「観測や数式だけに基づくことによって生じた危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”」
◎このことが、物理学に、行き詰まり、迷走、困難、混乱、停滞… をもたらしてしまう大きな原因の1つとなってしまったのである。
→このことが、現代物理学に、危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、混乱、停滞…”をもたらしてしまう大きな原因の1つとなってしまったのである。
◎テーブル内 物理学の迷走、行き詰まり、困難…の解消
→現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”の解消
◎このことも、物理学における、行き詰まり、迷走、困難、混乱、停滞… をもたらしてしまう原因の1つとなってきた恐れがあるのである。
→このことも、現代物理学に、危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、混乱、停滞…”をもたらしてしまう原因の1つとなってきた恐れがあるのである。
◎“現代物理学”が陥ってしまった行き詰まり、困難、迷走… を解消するべく、勇気を振り絞って、未踏の地を、合理的に探求していってもいいのではないだろうか?
→現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”を解消するべく、勇気を振り絞って、未踏の地を、合理的に探求していってもいいのではないだろうか?
結果6
◎行き詰まり、困難、迷走… に直面していると判断できるのである。
→危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”に直面していると判断できるのである。
◎ロックインしてきたことが、現代物理学の、行き詰まり、迷走、困難… にぶつかっている原因の1つである恐れがあるからである。
→ロックインしてきたことが、現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、迷走、困難…”にぶつかっている原因の1つである恐れがあるからである。
◎
考察〈Discussion〉→
考察(Discussion)
◎
次の5つについて考察する。→次の6つについて考察する。
考察1
◎実は、現代物理学の行き詰まり、迷走、困難、停滞… を解消させるカギがあったのだ。
→実は、現代物理学の
危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、迷走、困難、停滞…
”を解消させるカギがあったのだ。
◎
「観測できない世界」を探求した結果── 行き詰まり、困難に直面し、迷走し、不毛になってしまったという側面も、現代物理学は持つのである。→
→
「観測できない世界」を探求したからこそ、危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、不毛性…”に陥ってしまったという側面も、現代物理学は持つのである。
◎現代物理学における、行き詰まり、理論上の迷走、不毛性… を解消しようとしている営みの成果が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に他ならない。
→現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、不毛性…”を解消しようとしている営みの成果が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に他ならない。
考察2
◎すなわち、“抽象的な数式”は、必然的に、「自然(nature)と乖離した意味」を持ってしまうものなのである。
→ すなわち、“抽象的な数式”は、必然的に、「自然(nature)と乖離した意味」を持ってしま
いうるものなのである。
◎
そして、その結果、物理学に、行き詰まり、迷走、困難… をもたらしてしまいうるからである。
→
そして、その結果、現代物理学に、
危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、迷走、困難…
”をもたらしてしまいうるからである。
◎
ないがしろにしてきてしまった“つけ”、すなわち、弊害(困難、行き詰まり、迷走…)が生じていないかどうか、注意していく必要があるのである。
→ないがしろにしてきてしまった“つけ”、すなわち、危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”が生じていないかどうか、注意していく必要があるのである。
考察3
◎
『“観測&数式に基づいて発展してきた物理学”が陥った行き詰まり、困難、迷走…を解消する新しい手段の紹介』
→『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
考察6 検証実験とエネルギー保存則について(
6.検証実験とエネルギー保存則について)
◎※したがって、この実験は、
現代物理学が陥ってしまった、行き詰まり、困難、迷走…の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による解消が反証されるかどうかを確かめる実験でもある。
→ ※したがって、この実験は、
現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による解消が反証されるかどうかを確かめる実験でもある。
◎テーブル内 ・
現代物理学が陥ってしまった、行き詰まり、困難、迷走…の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による解消が、反証されるかどうか
→・
現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による解消が、反証されるかどうか
◎「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分が反証されるかどうか」(現代物理学が陥ってしまった、行き詰まり、困難、迷走…を解消できるかどうか)
→「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分が反証されるかどうか」(現代物理学の
危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…
”を解消できるかどうか)
◎これまで解決困難と言われてきた多くの問題を解消すると同時に、“現代物理学”が陥った行き詰まり、困難、迷走… を解消しうるのである。
→これまで解決困難と言われてきた多くの問題を解消すると同時に、“現代物理学”
の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…
”を解消しうるのである。
◎(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、物理学の行き詰まり、迷走、困難…が解消されるかどうか)
→(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、
現代物理学
の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、迷走、困難…
”が解消されるかどうか)
◎追加
※なお、次のような興味深い記述もある。
『神里 留保しておきたいのは、新エネルギーが本当に見つからないのかどうかです。 これに関しては、私は確信がもてません。というのも、現在の物理学はどうも「踊り場」が続いていて、新しくておもしろい発見があまりないように思われるからです。ノーベル賞も最近は小粒になったのではないか、といわれているんですね。
それは逆にいうと、踊り場のあとにはパラダイムの変換が起きると考えられるかもしれない。
菅野 つまり、いまは停滞しているだけで、そろそろエネルギーのパラダイムを変更するような大発見があってもおかしくないと?
神里 直感的にはそんな感じがしています。原理さえ見つかったら、実用化は早いと思いますよ。〜』
(『没落する文明』 p.158 萱野稔人 神里達博 集英社新書)
|
◎そして、既存の現代物理学が、ある意味、安泰となると同時に、行き詰まり、困難、迷走…が解消されなかったことになり
→そして、既存の現代物理学が、ある意味、安泰となると同時に、危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”が解消されなかったことになり
◎そして、物理学が(部分的に)ひっくり返ると同時に、行き詰まり、困難、迷走…が解消され、しかも、“エネルギー問題や気候変動問題”を解消するために役立ちうる、とても重要なヒントを得られることになる。
→そして、現代物理学が(部分的に)ひっくり返ると同時に、危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”が解消され、しかも、“エネルギー問題や気候変動問題”を解消するために役立ちうる、とても重要なヒントを得られることになる。
◎結果──Conclusion→結論〈Conclusion〉
◎そういった、抽象的な数学についての「自然から乖離した解釈」によって生じた、「現代物理学の迷走、困難、行き詰まり…」の解消を助ける。
→ そういった、抽象的な数学についての「自然から乖離した解釈」によって生じてしまった、「現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”」の解消を助ける。
◎(これらによって、現代物理学の行き詰まり、困難、迷走…を解消できるかどうか)のみならず
→(これらによって、現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”を解消できるかどうか)のみならず
◎付録──Appendix→付録〈Appendix〉
その他1『一般3Steps理論
&“素スピノール創発モデル”』
→『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
その他2『一般3Steps理論』
→『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
その他3 『“観測&数式に基づいて発展してきた物理学”が陥った
行き詰まり、困難、迷走…を解消する新しい手段の紹介』
『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
EMOES宇宙論1-3
『一般3Steps理論
&“素スピノール創発モデル”』→
『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
EMOES宇宙論1
◎追加
※このことは、次の記述と調和している。
『大部分の科学者たちが、ほとんどすべての時間を注いでいる通常科学の研究は、世界はいかなるものかを科学者集団はすでに知っているという仮定の上に立っている。うまくいっている研究というものは、たいてい、たとえかなり無理をしても、その科学者集団の仮定を護ろうとする志向から得られたものである』
(『科学革命の構造』 p.6 トーマス・クーン 中山茂訳 みすず書房 下線は、筆者による)
|
◎参考文献→参考文献〈Reference〉
◎一般3Steps理論と
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
→“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介
『 一般3Steps理論と
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)ver.2.00』
→『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
2017年5月1日
考察3 超弦理論について
◎追加 ※「“超弦理論”が不完全な量子物理学を前提にして育まれている以上、“超弦理論”は、不完全にならざるをえない」と言うこともできると思われる。
◎テーブルの中(2カ所) 自然(nature)と乖離している→自然(nature)から乖離している
◎ つまりは──
「ワインバーグ-サラム理論(電弱統一理論)→大統一→超大統一」という流れこそが正しいはずだという、「自然(nature)から乖離したビジョン」が生まれたのである。
→ つまりは、抽象的な数学(抽象的な数式、ゲージ原理、対称性、群論…)によって裏切られた結果──
「ワインバーグ-サラム理論(電弱統一理論)→大統一→超大統一」という流れこそが正しいはずだという、「自然(nature)から乖離したビジョン」が生まれてしまったのである。
◎という解釈の時点で、自然(nature)から乖離が始まっているのである。
→という解釈の時点で、自然(nature)からの乖離が始まっているのである。
◎そして、そういった「抽象的な数学」の重視(≒「抽象的な数式の解釈」の軽視)による自然(nature)からの乖離は── 必死に“伝統”を守ろうとした結果でもあった。
※その“物理学の伝統”とは、「観測」以外に、「抽象的な数学」のみを重視し、「抽象的な数式の解釈」の軽視する伝統、すなわち、ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)の探求を軽視する伝統である。
※なお、以上のことは、「観測数値と計算結果が一致しても十分ではない」ことを、はっきり示している。
すなわち、抽象的な数学(抽象的な数式…)を正しく“解釈”すること、すなわち、ミクロの世界の自然(nature)の真の姿、すなわち、“true picture at Planck scale”を正しく思い描こうすることも、気を抜かず、重視する必要があることを示している。
なぜなら、抽象的な数学(抽象的な数式…)の“解釈”が、新たな前提となるからである。
すなわち、もし抽象的な数学の“解釈”が、自然(nature)から乖離してしまえば、その解釈を前提とする、後に続く理論が、自然(nature)から乖離してしまう可能性が高まるからである。
※なお、以上のことは、「観測数値と計算結果が一致しても十分ではない」ことを、はっきり示している。
→ここにある自然(nature)からの乖離に気づくためには── 抽象的な数学(抽象的な数式…)を正しく“解釈”すること、すなわち、ミクロの世界の自然(nature)の真の姿、すなわち、“true picture at Planck scale”を正しく思い描こうすることが必要不可欠である。
なぜなら、抽象的な数学(抽象的な数式…)の“解釈”が、新たな前提となるからである。
すなわち、もし抽象的な数学の“解釈”が、自然(nature)から乖離すればするほど、その解釈を前提とする、後に続く理論が、自然(nature)から乖離してしまうからである。
こういった「抽象的な数学」の重視(≒「抽象的な数式の解釈」の軽視)による自然(nature)からの乖離は── 必死に“物理学の伝統”を守ろうとした結果であった。
すなわち、不完全な量子物理学をそのまま尊重し続けるという“物理学の伝統”の結果── 「抽象的な数式の解釈」の軽視する伝統は、ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)の探求が軽視され、自然(nature)からの乖離が進んだのである。
◎ 以上の説明は、“高次元空間”や“超対称性”は、ともに、抽象的な数学に裏切られた結果生まれた「自然(nature)から乖離した考え」であることを示唆している。
繰り返すが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせんとすることは、“超弦理論”を否定することではない。
“超弦理論”が、どのようなしくみで、うまくいき(成功し)、そして、どのようなしくみで、うまくいかなくなっているのか(失敗している)のかを、説明することである。
→以上の説明は、「観測数値と計算結果が一致しても十分ではない」ことを、はっきり示している。
すなわち、以上の説明は、ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)の探求する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していること(つまりは、3Steps原理と調和していること)も必要であることを、示しているのである。
そして、以上の説明は、“高次元空間”や“超対称性”は、ともに、抽象的な数学に裏切られ続けた結果(すなわち、不完全な量子物理学の伝統を必至に守ろうとし続けた結果)生まれた「自然(nature)から乖離した考え」である可能性が高いことを示唆している。
◎しかし、自然(nature)と乖離している部分については、却下しなければならない。
→しかし、自然(nature)から乖離している部分については、却下しなければならない。
◎したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、自然(nature)と乖離していると判断できる“超対称性”や“高次元空間”については、却下することとする。
すなわち、以後、原則として、“超弦理論”という言葉は使わず、弦理論(string theory)と表記して話を進めることとする。
→ したがって、自然(nature)から乖離していると判断できる“超対称性”や“高次元空間”については、却下される可能性が高いことがわかる。(詳細は下記で説明する)
よって、以後、原則として、“超弦理論”という言葉は使わず、弦理論(string theory)と表記して話を進めることとする。
◎ベッケンスタインが求めた、『同じ巨視的な状態を取る微視的状態の数』は、「(ブラックホールの中に存在しうる)エネルギーが最低の粒子の数」から、計算で求めたと言うことができる。
→ベッケンスタインやホークングが求めた、『同じ巨視的な状態を取る微視的状態の数』は、「(ブラックホールの中に存在しうる)エネルギーが最低の粒子の数」から、計算で求めたと言うことができる。
◎「ベッケンスタインが求めたブラックホールのエントロピー」→「ベッケンスタインやホーキングが求めたブラックホールのエントロピー」
◎※なお、「最大の波長の粒子」は、光子でも、同様にあてはまる。
(なお、ホーキング放射やブラックホールの蒸発においては、「ブラックホールに取り込まれた光子のエネルギーが、その分だけ、ブラックホールの質量エネルギーを減らす」という考え方がなされている。 もし本当にそうだとすれば、その取り込まれた“光子のエネルギー”の合計が、ブラックホールの質量に等しければ、ブラックホールの蒸発が完了することになるだろう)
しかし、光子は、質量を持たないので、本来は、ふさわしくない(自然(nature)から乖離している)と思われる。
→※なお、この計算は、「最大の波長の粒子」が“光子”であると考えても成り立つ。
(なお、ホーキング放射やブラックホールの蒸発においては、「ブラックホールに取り込まれた光子のエネルギーが、その分だけ、ブラックホールの質量エネルギーを減らす」という考え方がなされている。しかし、光子は質量を持たないので、その説明は、よりいっそう自然(nature)から乖離していると思われる)
バージョンアップ履歴
◎下記日付修正
2017年5月29日→ 2017年4月29日
2017年4月29日
考察
6検証実験とエネルギー保存則について(6.検証実験とエネルギー保存則について)
◎(“自然(nature)を説明できる&問題を解決できる”だけでなく──)
→(“自然(nature)を説明できる&問題を解決できる”だけでなく)
◎決定的に、既存の物理学がする予測とは異なる予測→決定的に、既存の物理学とは異なる予測
◎1.光子や重力子(および、それらの総和である電磁波や重力波)が、エネルギー非保存の所産である。(結果1)
→1.光子や重力子(および、それらの総和である電磁波や重力波)は、エネルギー非保存の所産であるので
エネルギーを持ち去らない。(結果1)
◎2の方は、エネルギー保存則の適用範囲(何を閉鎖系の中に含めるか)の問題に過ぎないのだった。
よって、検証に使うことが可能であるのは、1の「時空が不連続であること」を前提にしたものだけである。
→2の方は、エネルギー保存則の適用範囲(何を閉鎖系の中に含めるか)の問題に過ぎないのであった。
よって、検証に使うことが可能なのは、1の「時空が不連続であること」を前提にした予測だけである。
◎ したがって、以下では、1の「光子や重力子(および、それらの総和である電磁波や重力波)が、エネルギー非保存の所産である」ことに関する内容を中心にして考察していく。
→したがって、以下では、1の「光子や重力子(および、それらの総和である電磁波や重力波)が、エネルギー非保存の所産である」ことに関する予測を中心にして考察していく。
◎※したがって、この実験は、現代物理学が陥ってしまった、行き詰まり、困難、迷走…の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による解消が反証されるかどうかを確かめる実験である。
→※したがって、この実験は、現代物理学が陥ってしまった、行き詰まり、困難、迷走…の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による解消が反証されるかどうかを確かめる実験でもある。
◎「光子や重力子がエネルギーを持ち去らない」の方、すなわち、「光子や重力子は、エネルギー非保存の所産である」の方のみである。
→「光子や重力子は、エネルギー非保存の所産であるのでエネルギーを持ち去らない」の方のみである。
◎これから詳しく紹介する、『周囲が完全な真空に近付く中で、(浮かんでいる)高温の物体の温度が、どのように変化するかを調べる』という実験は、単に「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分が反証されるかどうか」(現代物理学が陥ってしまった、行き詰まり、困難、迷走…を解消できるかどうか)を確かめることができるので、物理学とっての大きな分岐点であるのみならず── 「エネルギー問題を解決するヒントを得られるかどうか」を確かめることができるので、人類にとっての、大きな分岐点なのであることがわかる。
→これから詳しく紹介する、『周囲が完全な真空に近付く中で、(浮かんでいる)高温の物体の温度が、どのように変化するかを調べる』という実験は、単に(「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根本部分が反証されるかどうか」(現代物理学が陥ってしまった、行き詰まり、困難、迷走…を解消できるかどうか)を確かめることができるので)物理学とっての大きな分岐点であるのみならず── (「エネルギー問題を解決するヒントを得られるかどうか」を確かめることができるので)人類にとっての、大きな分岐点であることがわかる。
◎「3.熱放射」の影響による変化のみを観察できるようになる。
→相対的に「3.熱放射」の影響による変化の方をメインにして観察できるようになる。
◎◎「重力子や光子、重力場や電磁場は、エネルギー保存則にしたがっている所産である」→「重力子や光子、重力場や電磁場は、エネルギー非保存の所産である」
→◎「重力場や電磁場は、エネルギー保存則にしたがっている所産である」→「重力場や電磁場は、エネルギー非保存の所産である」
2017年4月24日 2.07→2.08
考察
◎ページ追加
6検証実験とエネルギー保存則について
(6.検証実験とエネルギー保存則について)
◎考察2、4で、
『一般3Steps理論&“素スピノール創発モデル”』
→『“現代物理学”が陥った、行き詰まり、困難、迷走…を解消する新しい手段の紹介』
◎考察5.で削除 (一般3Steps理論&“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)ver.2.00)
結論
◎“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示す“新しい手段(自然な世界観(3Steps原理)、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何)”について、次のような少なくとも3つの結論に至ることができる。
→ 検証実験(考察6)の結果、反証されなかったと仮定すれば── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示す“新しい手段(自然な世界観(3Steps原理)、具体的な数学(具体的な数
式、具体的な幾何)”について、次のような少なくとも3つの結論に至ることができる。
◎追加
一方、この検証実験(考察6)の結果、反証されたと仮定すれば── 当然、「上記の結論の一部を含めて、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)や“自然な世界観”(3Steps原理)は、根本的な見直しを迫られることになる」と言わざるをえない。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)や“自然な世界観”(3Steps原理)が、机上の空論であるかどうかを判定できる検証実験が存在するということは、(ときに間違いを認めなければならないという意味において)厳しいことである。
しかし、それは同時に── (ときに不健康なロックインを解消(予防)できるという意味において)とても貴重で、ありがたいことであるとも言える。
この検証実験の結果は、『“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)や“自然な世界観”(3Steps原理)の根本」が反証されるかどうか(これらによって、現代物理学の行き詰まり、困難、迷走…を解消できるかどうか)のみならず、『エネルギー問題や気候変動問題を解消するための重要なヒントを得られるかどうか』をも決める。
したがって、この検証実験の結果は、人類にとって大きな分岐点であると言っても過言ではないのである。
要約
◎量子論(量子力学、場の量子論)で説明されてきた世界
→ 量子論(量子力学、場の量子論)で説明されてきた世界(不確定性原理(不確定性関係)、波と粒子の二重性…)
◎弦理論の世界(閉じたループ重力子、開いた弦(光子…)、ハドロンのひも理論、マルダセナの対応…)
→弦理論の世界(閉じたループ(スピン2の重力子)、開いた弦(スピン1の光子…)、ハドロンのひも理論、マルダセナの対応…)
◎ループ量子重力理論の世界(スピンネットワーク…)
プレオンモデルの世界
→ ループ量子重力理論の世界(スピンネットワーク、最小の面積や体積がある…)
プレオンモデルの世界(クォークやレプトンのそれぞれが、3つのプレオンから構成されている…)
◎
|
ニュートンの万有引力の法則
|
電荷のクーロンの法則
|
磁極のクーロンの法則
|
|
元の数式
|
F=GMm/r2[N]
|
F=kQq/r2=Qq/4πεr2[N]
|
F=m1m2/4πμ0r2[N]
|
|
“EMOES表記”
|
F=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nm[N]
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)×(1/MG)×m[N]
|
F=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq[N]
=(aQc2/4πn2)×(1/2LP)×(1/QE)×q[N](n≧20)
|
F=Nm1(hc/4LP)×1/4πn2×(1/2LP)×(Nm2)[N]
=(bm1c2/4πn2)×(1/2LP)×(1/mE)×m2[N](n≧20)
|
※c : 光速[m/s]、 h : プランク定数[J・s]、 LP : プランク距離[m]
M : 質量[kg]、 m : 質量[kg]
MG : 重力子質量[kg] ※MG=MP/2π
MP : プランク質量[kg] ※MP=h/2πcLP
EP : プランクエネルギー[J] ※EP=hc/2πLP
G : 重力定数 ※G[N・m2/kg2]=2πc3LP2/h=c2LP/MP[m3/s2kg]
r : 距離[m]
NM : 質量Mが重力子質量MGの何個分かを示す数NM=M/MG
Nm : 質量mが重力子質量MGの何個分かを示す数Nm=m/MG
n : 距離が2LP[m]の何個分かを示す数、中心からの距離をrとしたときr=2nLP[m]となる。
Q : 電荷[C]、 q : 電荷[C]
Q E: 当量電荷[C] QE=(h/2cμ0)1/2=e/2α1/2=qP/2[C]
(α : 微細構造定数1/137 μ0 : 真空の透磁率[N/A2] qP : プランク電荷[C])
『厚さ2LPの球殻に、常に「hc/4LP[J]」のエネルギー蓄えることのできる電荷』
NQ : 電荷Qが当量電荷QEの何個分かを示す数 ※NQ=Q/QE
Nq : 電荷Qが当量電荷QEの何個分かを示す数 ※Nq=q/QE
a : 変換定数 a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C]
これによって、Qc2[ C・m2/s2]の値を、[J]に変換できる。
すなわち、aQc2[ C・m2/s2][kg/C]=aQc2[ kg・m2/s2]=aQc2[J]となる
m1:磁極[Wb] m2:磁極[Wb] ※(仮想的な)“点磁極”である。
mE:当量磁極[Wb] mE=(h/2cε0)1/2=(qP/2)×(μ0/ε0)1/2[Wb]
(ε0 : 真空の誘電率[C2/N・m2] μ0 : 真空の透磁率[N/A2] qP : プランク電荷[C])
『厚さ2LPの球殻に、常に「hc/4LP[J]」のエネルギーを蓄えることのできる磁極』
Nm1 : 磁極m1が当量磁極mE[Wb]の何個分かを示す数 ※Nm1 =m1/mE
Nm2 : 磁極m2が当量磁極mE[Wb]の何個分かを示す数 ※Nm2 =m2/mE
b : 変換定数 b=(hε0/8cLP2)1/2[Cs/m2]
これによって、m1c2[ Wb・m2/s2]の値を、[J]に変換できる。
すなわち、bm1c2[Cs/m2][ Wb・m2/s2]=bm1c2[Cs/m2][Nms/C][m2/s2]
=bm1c2 [Nm]=bm1c2[J]となる。
|
|
→
|
ニュートンの万有引力の法則
|
電荷のクーロンの法則
|
磁極のクーロンの法則
|
|
元の数式
|
F=GMm/r2[N]
|
F=kQq/r2=Qq/4πε0r2[N]
|
F=m1m2/4πμ0r2[N]
|
|
“EMOES表記”
|
F=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nm[N]
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)×(1/MG)×m[N]
|
F=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq[N]
=(aQc2/4πn2)×(1/2LP)×(1/QE)×q[N](n≧20)
|
F=Nm1(hc/4LP)×1/4πn2×(1/2LP)×(Nm2)[N]
=(bm1c2/4πn2)×(1/2LP)×(1/mE)×m2[N](n≧20)
|
|
各項の説明
|
M : 質量[kg]、 m : 質量[kg]
G : 重力定数
※G[N・m2/kg2]
=2πc3LP2/h=c2LP/MP[m3/s2kg]
MG : 重力子質量[kg] ※MG=MP/2π
MP : プランク質量[kg] ※MP=h/2πcLP
EG : 重力子エネルギー[J] ※EG=MGc2=EP/2π
EP : プランクエネルギー[J] ※EP=hc/2πLP
NM : 質量Mが重力子質量MGの何個分かを示す数
NM=M/MG
Nm : 質量mが重力子質量MGの何個分かを示す数
Nm=m/MG
|
Q : 電荷[C]、 q : 電荷[C]
k :静電気力の定数(真空中)
ε0:真空の誘電率 ε0=1/4πk ※μ0ε0=1/c2
Q E: 当量電荷[C]─『厚さ2LPの球殻に、
常に「hc/4LP[J]」のエネルギー蓄えることのできる電荷』
QE=(h/2cμ0)1/2=e/2α1/2=qP/2[C]
(α : 微細構造定数1/137 μ0 : 真空の透磁率[N/A2]
qP : プランク電荷[C])
NQ : 電荷Qが当量電荷QEの何個分かを示す数
※NQ=Q/QE
Nq : 電荷Qが当量電荷QEの何個分かを示す数
※Nq=q/QE
a : 変換定数 a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C]
これを Qc2[ C・m2/s2]に乗ずることによって、
単位を[J]に変換できる。 すなわち、
aQc2[kg/C][ C・m2/s2]
=aQc2[ kg・m2/s2]=aQc2[J]となる
|
m1:磁極[Wb] m2:磁極[Wb] ※(仮想的な)“点磁極”である。
μ0:真空の透磁率 μ0=4π×10-7[N/A2] ※μ0ε0=1/c2
mE: 当量磁極[Wb]─『厚さ2LPの球殻に、常に「hc/4LP[J]」
のエネルギーを蓄えることのできる磁極』
mE=(h/2cε0)1/2=(qP/2)×(μ0/ε0)1/2[Wb]
(ε0 : 真空の誘電率[C2/N・m2] μ0 : 真空の透磁率[N/A2]
qP : プランク電荷[C])
Nm1 : 磁極m1が当量磁極mE[Wb]の何個分かを示す数
※Nm1 =m1/mE
Nm2 : 磁極m2が当量磁極mE[Wb]の何個分かを示す数
※Nm2 =m2/mE
b : 変換定数 b=(hε0/8cLP2)1/2[Cs/m2]
これを m1c2[ Wb・m2/s2]に乗ずることによって、
単位を[J]に変換できる。 すなわち、
bm1c2[Cs/m2][ Wb・m2/s2]
=bm1c2[Cs/m2][Nms/C][m2/s2]
=bm1c2 [Nm]=bm1c2[J]となる。
|
|
共通項
|
※c : 光速[m/s] h : プランク定数[J・s] LP : プランク距離[m] r : 距離[m] n : 距離rが2LP[m]の何個分かを示す数(中心からの距離をrとしたときr=2nLP[m]となる)
|
◎宇宙(時空)が加速膨張している原因は、重力ポテンシャルエネルギーにほかにならない。(→EMOES宇宙論3)
→宇宙(時空)が加速膨張している原因は、重力ポテンシャルエネルギーに他ならない。(→EMOES宇宙論3)
◎いずれは自然(nature)から乖離してしまうのである。 その結果
→いずれは自然(nature)からの乖離が増幅してしまいうるのである。 したがって
◎
追加 そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)や“自然な世界観”(3Steps原理)は、検証できる予測(testable prediction)を提供する。
この予測の検証実験の結果は、『“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)や“自然な世界観”(3Steps原理)の根本」が反証されるかどうか(現代物理学の行き詰まり、困難、迷走…を解消できるかどうか)のみならず、『エネルギー問題や気候変動問題を解消するための重要なヒントを得られるかどうか』を決めるので、人類にとって大きな分岐点であると言っても過言ではない。
Method&Material(手段・道具&材料)
◎なぜなら、「観測の理論負荷性」という考えが示しているように、“理論が何を観測するかを決める”からである。
→ なぜなら、『観測の理論負荷性』(ハンソン)や『理論が「事実」を造る』(村上陽一郎、『新しい科学論』 講談社ブルーバックス)という考えが示しているように、“理論が、何を観測するか(観測からどんな事実を見いだすか)を決める”からである。
※次の記述がとても参考になる。
『すなわち、ある状況のもとである理論を支えるために使われたデータが、別の状況のもとでは、別の(しかももとの理論に対立するような)理論を支えるために使われる、ということも十分あり得ることになり、データはきわめて理論依存的〈theory-dependent〉になるからである。』
(『近代科学を超えて』 村上陽一郎 講談社学術文庫 p51-52)
|
付録──Appendix
その他
◎リンク修正(該当ベージ) 3.一般3Steps理論と数式について
EMOES宇宙論1
◎ほぼ一カ所に集合したプレオン∴の“4角形”(縮みきったバネ)は、もしかしたら、このグルーボールと何らかの関係があるのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である)
→ほぼ一カ所に集合したプレオン∴の“4角形”(縮みきったバネ)は、もしかしたら、このグルーボールと何らかの関係があるのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である)
このあたりのことは、先に述べた、ブラックホールの地平面のすべてをカバーする式が、
4πRs2=4π(M/M G×LP/π)2=(M/M G)2×4LP2/π
のように求まり、この式が、NM個分の重力子質量M Gに相当する質量は、新しいブラックホールを構成するようになると、(NM/π)倍の質量、すなわち、重力子の放出源として働き続ける能力を持つことを意味していることと関連しているかもしれない。
なぜなら、質量が(NM/π)倍になる理由はおおよそ次のように説明できるが──
これは、ブラックホールによって、プレオン∴まで分解され、「プレオン∴×4の“4角形”(縮みきったバネ)」の集合に至り、コンパクト化が進むと、重力ポテンシャルエネルギーを利用した運動エネルギー増加に伴う質量の獲得の効果が強くなるからであると考えられる。
たしかに、トータルの質量が大きいほど、それに比例して「重力ポテンシャルエネルギーを利用した運動エネルギー増加」の効果が大きくなるので、正しそうに思われる。正しければ、このことは、ブラックホールに至る場合でも、“重力場は、結局は線形であり続けている”ことを意味する。
|
「なぜ、(NM/π)倍なのか」の厳密な理由を考える際には、プレオン∴×4の“4角形”(縮みきったバネ)は、ほとんど1カ所に集合する際、より具体的に、どのように配置するのか、が大きなカギを握っていると考えられるからである。 詳細な検討は、今後の課題である。
◎該当部 ペンローズ-ホークングの特異点定理→ペンローズ-ホーキングの特異点定理
◎追加 ※ホーキング氏は、「ホーキング-ペンローズの特異点定理」における無限大の問題を解消するために、大胆に、虚時間や無境界仮説を考え出し、“宇宙に始まりも終わりもない”と考えられた。 しかし、「無限大の問題」の解消と引き換えに、「特異点こそが宇宙の始まりである」と考えた学位論文のときのアイディアの方が犠牲になってしまったと言えるのかもしれない。 なぜなら、EMOES宇宙論は、「無限大の問題」を解消するともに、「特異点こそが宇宙の始まりである」というアイディアと調和している「新しいブラックホールの形成こそが、新しい宇宙の始まりの準備である」というアイディアを支持しているからである。
◎大量の重力子の放射が、エントロピーを持ち去るので、
→ブラックホールからは、大量の重力子が放射される。
このブラックホールから放射される大量の重力子が、
エントロピーを持ち去るので、
◎
♯この奇跡的な一致について、おおよそ次のように説明できるらしい。
質量M[kg]が作るブラックホールを考えて見よう。
このブラックホールの半径は、シュバルツシルト半径Rs=2GM/c2[m]である。
(G[N・m2/kg2]:重力定数、 c[m/s]:光速)
エネルギーが最低の粒子とは「最長の波長λmax[m]を持つ粒子」のことであり、上図のように、半波長(素スピノールの間隔)が、ブラックホールの直径に等しいものである。
この粒子が持つ最低エネルギーEminは、次のように計算できる。
Emin=hc/λmax=hc/4Rs=hc3/8GM[J]=h2/16πLP2M[J]
(λmax/2=2Rs(上図より)、Rs=2GM/c2[m]、「G=2πc3LP2/h」(→結果1)を使用)
(粒子の最低の運動量をpminとすると、pmin=h/λmax となり、この両辺に光速cをかけ合わせると、
Emin=cpmin=hc/λmaxとなる)
ところで、アインシュタインの式によると、全質量エネルギーは、E全質量=Mc2[J]である。
エネルギーが最低の粒子何個分が、この全質量エネルギーに相当するかを計算すると──
E全質量/Emin=Mc2[J]/(h2/16πLP2M)[J]=16πLP2c2M2/h2[個] …(1) となる。
一方、このブラックホールの球の表面積は、4πRs2[m2]である。この表面積の中に、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ、すなわち、縦と横が2LP[m]の正方形の面積(4LP2[m2])が、何個あるかを計算すると──
4πRs2[m2]/4LP2[m2]=π(2GM/c2)2/LP2=4πG2M2/c4LP2
=16π3LP2c2M2/h2 [個] …(2)
(1)と(2)は、おおよそ等しい。(π2だけずれているだけである)
(このπ2のずれは、何を意味しているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である)
※なお、「最大の波長の粒子」は、光子でも、同様にあてはまる。
(なお、ホーキング放射やブラックホールの蒸発においては、「ブラックホールに取り込まれた光子のエネルギーが、その分だけ、ブラックホールの質量エネルギーを減らす」という考え方がなされている。 もし本当にそうだとすれば、その取り込まれた“光子のエネルギー”の合計が、ブラックホールの質量に等しければ、ブラックホールの蒸発が完了することになるだろう)
しかし、光子は、質量を持たないので、本来は、ふさわしくない(自然(nature)から乖離している)と思われる。
※なお、シュバルツシルト半径は、Rs=2GM/c2=4πcLP2M/h=M/M G×LP/π と変形できる。
(「G=2πc3LP2/h」、「M G=h/(2π)2cLP」(→結果1)を使用)
なお、この式より導かれる「2πRs=M/M G×2LP」の式は、次のように解釈できる。
すなわち、『シュバルツシルト半径Rsの円周の長さ「2πRs」が、ちょうど、原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ“2LP”をM/M G個、円上に並べた長さ「M/M G×2LP」に等しい』と解釈できる。
このことは、(ブラックホールにいたる以前の“線形の重力(→結果1)”を説明する)「M/M G×4LP2」の式が意味する範囲だけでは、ブラックホールの地平面のすべてをカバーすることができないこと、すなわち、「M/M G×4LP2」の式をそのまま、ブラックホールにあてはめることがゆるされないことを意味する。
ブラックホールの地平面、すべてをカバーする式は、次のように求まる。
4πRs2=4π(M/M G×LP/π)2=(M/M G)2×4LP2/π
この式は、n個の重力子質量M Gは、ブラックホールを構成するようになると、n2に比例する重力子の放出源として働き続ける能力を持つことを意味する。
これは、ブラックホールによって、プレオン∴まで分解され、「プレオン∴×4の“4角形”(縮みきったバネ)」の集合に至り、コンパクト化が進むと、重力ポテンシャルエネルギーを利用した運動エネルギー増加に伴う質量の獲得の効果が強くなるからであると考えられる。
たしかに、トータルの質量が大きいほど、それに比例して「重力ポテンシャルエネルギーを利用した運動エネルギー増加」の効果が大きくなるので、正しそうに思われる。正しければ、このことは、ブラックホールにな至る場合でも、“重力場は、結局は線形であり続けている”ことを意味する。
詳細な検討は、今後の課題である。 |
→
♯この奇跡的な一致について、おおよそ次のように説明できるかもしれない。
質量M[kg]が作るブラックホールを考えて見よう。
このブラックホールの半径は、シュバルツシルト半径Rs=2GM/c2[m]である。
(G[N・m2/kg2]:重力定数、 c[m/s]:光速)
エネルギーが最低の粒子とは「最長の波長λmax[m]を持つ粒子」のことであり、上図のように、半波長(素スピノールの間隔)が、ブラックホールの直径に等しいものである。
この粒子が持つ最低エネルギーEminは、次のように計算できる。
Emin=hc/λmax=hc/4Rs=hc3/8GM[J]=h2/16πLP2M[J]
(λmax/2=2Rs(上図より)、Rs=2GM/c2[m]、「G=2πc3LP2/h」(→結果1)を使用)
(粒子の最低の運動量をpminとすると、pmin=h/λmax となり、この両辺に光速cをかけ合わせると、
Emin=cpmin=hc/λmaxとなる)
ところで、アインシュタインの式によると、全質量エネルギーは、E全質量=Mc2[J]である。
エネルギーが最低の粒子何個分が、この全質量エネルギーに相当するかを計算すると──
E全質量/Emin=Mc2[J]/(h2/16πLP2M)[J]=16πLP2c2M2/h2[個] …(1) となる。
一方、このブラックホールの球の表面積は、4πRs2[m2]である。この表面積の中に、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ、すなわち、縦と横が2LP[m]の正方形の面積(4LP2[m2])が、何個あるかを計算すると──
4πRs2[m2]/4LP2[m2]=π(2GM/c2)2/LP2=4πG2M2/c4LP2
=16π3LP2c2M2/h2 [個] …(2)
(1)と(2)は、おおよそ等しい。(π2だけずれているだけである)
(このπ2のずれは、何を意味しているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である)
※なお、「最大の波長の粒子」は、光子でも、同様にあてはまる。
(なお、ホーキング放射やブラックホールの蒸発においては、「ブラックホールに取り込まれた光子のエネルギーが、その分だけ、ブラックホールの質量エネルギーを減らす」という考え方がなされている。 もし本当にそうだとすれば、その取り込まれた“光子のエネルギー”の合計が、ブラックホールの質量に等しければ、ブラックホールの蒸発が完了することになるだろう)
しかし、光子は、質量を持たないので、本来は、ふさわしくない(自然(nature)から乖離している)と思われる。
|
なお、次の記述からは、ホーキング氏が、不完全な量子物理学の犠牲になったと言うこともできるかもしれない。
『量子論の不確定性原理によれば見かけ上、まったく何もない空間でも量子場は絶えず波動している。この量子の波動はエネルギー密度を無限大にする。理論上、無限大に発散する物理量を実測値で置き換えて、エネルギー密度を有限と捉える引き算が「繰り込み」である。これをしないことには、エネルギー密度は時空を針で突いたほどの点にまで圧縮するだろう。この引き算は、少なくとも局所的に、負のエネルギー期待値を残す。平坦な空間でエネルギーの総和が正であっても、局所的にエネルギー密度の期待値が負となる量子状態はあり得るということだ。
ならば、その負の期待値は時空を然るべき形にたわませるだろうか。どうやらそうに違いない。量子論の不確定性原理はブラックホールが粒子と熱を放出することを裏づける。それにより、ブラックホールは質量を失って徐々に蒸発する。ブラックホールの事象の地平の面積が減るためにはエネルギー密度が負で、隣り合った光線が離反する形で時空をたわめなくてはならない。エネルギー密度が常に正で、光線が近づく方向に時空を曲げるなら、ブラックホールの表面積は時間とともに拡大する』
(『ホーキング、自らを語る』 スティーヴン・ホーキング
池央あき(耳へんに火)訳 佐藤勝彦監修 あすなろ白書)
|
※この記述から、『量子論の不確定性原理』が、エネルギー密度が無限大になることの根拠になっていることがわかる。
さらに、ホーキング氏は、(無限大のエネルギー密度の問題を解消する)「繰り込み」に相当する『無限大に発散する物理量を実測値で置き換えて、エネルギー密度を有限と捉える引き算』を、『負のエネルギー期待値』の根拠、『局所的にエネルギー密度の期待値が負となる量子状態』の根拠としていることがわかる。そして、これらの『負のエネルギー期待値』(『局所的にエネルギー密度の期待値が負となる量子状態』)、『ブラックホールの事象の地平の面積が減る』ことの根拠にしていることがわかる。
一方、ホーキング氏は、『量子論の不確定性原理』を『ブラックホールが粒子と熱を放出すること』(ホーキング放射)の根拠としていることがわかる。
|
『量子論の不確定性原理』は、決して、ミクロの自然(nature)がどうふるまうべきかを示す原理ではないのだった。
それなのに、この(本来、人間の観測事情を示すにすぎない)『量子論の不確定性原理』が、ミクロの自然(nature)を記述するための原理として転用される結果、「無限大のエネルギー密度」「負のエネルギー期待値による引き算」『負のエネルギー期待値』(『局所的にエネルギー密度の期待値が負となる量子状態』)「ブラックホールの事象の地平の面積の減少」「ホーキング放射」が生まれてしまっているのである。
つまり、ホーキング氏は、(本来、人間の観測事情を示すにすぎないはずの)『量子論の不確定性原理』をミクロの自然(nature)を記述するための原理として転用していまうという「不完全な量子物理学の伝統」を、そのまま尊重してしまったことによる犠牲者になってしまったと言えるのである。
※そもそも、ホーキング氏は、はじめに「ブラックホールの事象の地平の面積が絶対に減らない」ということを証明したのだった。
それが、結果的には、後に、(不確定性原理にもとづく)ホーキング放射をもとに、ブラックホールの事象の地平の面積が減ると、考えを改めたことになる。
一方、ホーキング氏は、ブラックホールの特異点は宇宙の始まりに相当すると考えた学位論文を出したのだった。
しかし、後に、(不確定性原理にもとづいて)虚時間を導入して宇宙に始まりも終わりもないと説明する無境界仮説を提出した。
また、ホーキング氏は、最初、ブラックホールで情報が失われると考えた。
しかし、後に、(現代物理学者の猛反発に合い)情報は失われないと考えを変えた。
なぜ、こうなるのだろうか? なぜ、こうも一貫しないのだろうか?
確かに、ここには、ホーキング氏の、「間違えていると思ったら潔く間違いを認める」という“自己批判の精神”も併せ持つ「知を愛する探究者」としての偉大さが反映されているという見方もあるだろう。
しかし、決してそれだけではない。
ここには、現代物理学が抱えている根本的な欠陥が反映されているのである。
すなわち、現代物理学全体が、「抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせ」だけを重視しており── 抽象的な数学(抽象的な数式…)についての自然(nature)と調和している解釈に相当する、明確な具体的な「幾何的な実体像」の探究を軽視してしまっているという欠陥が、反映されているのである。
この欠陥は、「抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせ」が自然(nature)と調和しているどうかを判断するための根拠がない、という欠陥であるとも言える。 こういった現状を持つ現代物理学の伝統(特に不完全な量子物理学(不確定性原理の転用、連続な時空…))を痛々しいほど尊重しながら、ホーキング氏は、その才能や情熱を研究に注いだ。
その結果、ホーキング氏自身が自信を持てずに疑っていたとしても、あるいは、ホーキング氏自身が、たとえ自然(nature)から乖離した結論を導いてしまっていたとしても── (自然(nature)と調和しているかどうかを判断する根拠を持たないので)数字が一致しているというだけで、現代物理学を支持している大多数の研究者は、その研究成果を鵜呑みにして、高い評価を与えることになる。
つまり、 ホーキング氏は、『抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせだけを重視する現代物理学』の犠牲になった一方── 『抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせだけを重視する現代物理学』のおかげで、他の研究者によって、支持&賞賛されたのである。
ホーキング氏は、「『抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせだけを重視する現代物理学』を最大限に尊重するなら、こういうことになりますよ(なってしまいますよ)」というような知のフロンティア(極限)を勇敢に探究することによって、結果的に、『抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせだけを重視する現代物理学』にひそんでいる欠陥を、その“一貫性のなさ”を通じて提示していることになっているのだ。
すなわち、『(不確定性原理にもとづく)ホーキング放射』『(不確定性原理にもとづいて)虚時間』『(現代物理学者の猛反発に合い)』というように、ことごとく『現代物理学の伝統(特に不完全な量子物理学(不確定性原理の転用、連続な時空…))』に従うことによってもたらされているホーキング氏の第2の考えについて、自然(nature)と調和しているかどうかを判断するための根拠を、実は、『抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせだけを重視する現代物理学』は持っていない── ということが露呈されているのである。
つまり、せっかくホーキング氏が、「間違えていると思ったら潔く間違いを認める」という“自己批判の精神”も併せ持つ「知を愛する探究者」としての偉大さを持っていたとしても── 実は明確な根拠(具体的な「幾何的な実体像」)を持っていないという『抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせだけを重視する現代物理学』の不完全さのせいで、ホーキング氏の主張は、フラフラと変化せざるをえないことになるのだ。
例えば、「とてつもない重力を持つブラックホールから、大量の重力子が放射されていることが一切考慮されていない」という欠陥を持つ『現代物理学』にもとづいて、『(不確定性原理にもとづく)ホーキング放射』が登場したのであり、そして、それに対する、賞賛や高評価が成立してしまっているのである。 こういったことが起きてしまうのは、『現代物理学』が抽象的な数学(抽象的な数式…)を用いた数字合わせだけを重視し、明確な根拠(具体的な「幾何的な実体像」)を欠いているからに他ならない。
◎該当部分 ホーキング→ホーキング氏、ペンローズ→ペンローズ氏、サスキンド→サスキンド氏、トフーフト→トフーフト氏、ベッケンスタイン→ベッケンスタイン氏
結果1
《静電場(電荷のクーロンの法則)のEMOES表記と電荷エネルギー
(および、磁極のクーロンの法則と磁極のエネルギー)》
◎最後の変形は、結局、分母と分子にa[kg/C]を掛け合わせただけである。→最後の変形は、結局、分母と分子にa[kg/C]を掛け合わせただけのものに相当している。
《アインシュタイン方程式》
|
『上で述べたような物質のエネルギー・テンソルの導入の仕方は単に相対性の要請からでは正当化されないということに注意しなければならない。ここでは、われわれは、次のような要求を用いて、上の式を導いた。すなわち重力場のエネルギーは、他のどのような同じ形の、重力的作用をもつべきであるという要請である。しかし、ここに求められた方程式の正当性に対する最も強い根拠は、むしろこれらの式から導かれる次のような結果にある。すなわち、全エルネギー成分に対して、エネルギーおよび運動量保存則が成立することである。つまり全エネルギー成分に対して、(49)、(49・a)に相当する式が成立する。』
(アインシュタイン選集2(p98) 下線は、筆者による)
|
→
|
『上で述べたような物質のエネルギー・テンソルの導入の仕方は単に相対性の要請からでは正当化されないということに注意しなければならない。ここでは、われわれは、次のような要求を用いて、上の式を導いた。すなわち重力場のエネルギーは、他のどのような同じ形の、重力的作用をもつべきであるという要請である。しかし、ここに求められた方程式の正当性に対する最も強い根拠は、むしろこれらの式から導かれる次のような結果にある。すなわち、全エルネギー成分に対して、エネルギーおよび運動量保存則が成立することである。つまり全エネルギー成分に対して、(49)、(49・a)に相当する式が成立する。』
(アインシュタイン選集2(p98) 下線は、筆者による)
|
◎皆目検討つかなかったので→皆目見当つかなかったので
◎ しかし、例えば、エネルギーに関すること(エネルギー保存則、重力場のエネルギー、重力波のエネルギー)においては、注意して数式を解釈しないと、自然(nature)から乖離してしまうことを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は示してくれるのである。
→しかし、例えば、「時空が連続と見なせないようなミクロのレベルでの重力の働きを考える場面」や「エネルギーに関する場面(エネルギー保存則、重力場のエネルギー、重力波のエネルギー)」においては、注意して数式を解釈しないと、自然(nature)から乖離してしまうことを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は示してくれるのである。
《連星系パルサーと重力波について》
ここにある“らせん軌道をとりながら自由落下する”系は、次のような“二ュートンの思考実験の世界”の延長上のものであると言うこともできる。
|
『ニュートンは、主著『プリンキピア』とは別に『世界の体系について』という小冊子を書き残している。そのなかに、はじめての人工衛星の理論ともいえる次のような話がある。高い山から水平に物体を投げたとすると、投げる速さが速ければ速いほど遠くへ落下する。十分遠く投げれば(空気の抵抗はないとしたとき)、物体は地上に落下することもなく、地球を一周して再び山頂へ戻ってくるであろう。 もしも山よりも高いところから水平に物体を投げれば月と同じように地球の周りをまわり続けるにちがいない。』
(p.108 『物理入門コース1 力学』 戸田盛和著 岩波書店)
|
もし、遠心力と重力が釣り合っていれば、そのまま円運動を続ける。
しかし、わずかでも遠心力が重力を下回っていたら、自由落下の効果によって、加速しながら軌道を縮め、最終的に、自然に地上にたどり着くようになる。 その過程は、あくまで重力ポテンシャルエネルギーが原因である。 このような系は、まさに、“らせん軌道をとりながら自由落下する”系である。
この過程について、わざわざ、力学的エネルギー保存則(“E=U+K”が一定)を放棄してまで、「重力波がエネルギー持ち去り続けることによって、“軌道運動エネルギーが減少”し、軌道が縮んでいく」という解釈をしなければならない理由はない。
そもそも、少しでも、遠心力<重力となってしまった時点で、“らせん軌道をとりながらの自由落下”が始まり、それがそのまま続いていくのである。
そして、その後は、二度と遠心力と重力が釣り合うことがなくなるのである。
つまり、少しでも、遠心力<重力となってしまった時点で、“重力波によるエネルギーの持ち去り”は、全く不要になるのである。
これらの“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の成果を、決して否定するものではない。
→
ここにある“らせん軌道をとりながら自由落下する”系は、単純に、次のような“二ュートンの思考実験の世界”の延長上のものであると言うことはできない。
|
『ニュートンは、主著『プリンキピア』とは別に『世界の体系について』という小冊子を書き残している。そのなかに、はじめての人工衛星の理論ともいえる次のような話がある。高い山から水平に物体を投げたとすると、投げる速さが速ければ速いほど遠くへ落下する。十分遠く投げれば(空気の抵抗はないとしたとき)、物体は地上に落下することもなく、地球を一周して再び山頂へ戻ってくるであろう。 もしも山よりも高いところから水平に物体を投げれば月と同じように地球の周りをまわり続けるにちがいない。』
(p.108 『物理入門コース1 力学』 戸田盛和著 岩波書店)
|
すなわち、次のような説明では不十分である。
『もし、遠心力と重力が釣り合っていれば、そのまま円運動を続ける。
しかし、わずかでも遠心力が重力を下回っていたら、自由落下の効果によって、加速しながら軌道を縮め、最終的に、自然に地上にたどり着くようになる。 その過程は、あくまで重力ポテンシャルエネルギーが原因である。 このような系は、まさに、“らせん軌道をとりながら自由落下する”系である。
少しでも、遠心力<重力となってしまった時点で、“らせん軌道をとりながらの自由落下”が始まり、それがそのまま続いていくのである。
そして、その後は、二度と遠心力と重力が釣り合うことがなくなるのである。
つまり、少しでも、遠心力<重力となってしまった時点で、“重力波によるエネルギーの持ち去り”は、全く不要になるのである。』
なぜなら、次の記述からもわかるように、「渦巻きを描いて中心へ落ちていく軌道」にはならず「楕円軌道」になる、という主張がありうるからである。
|
『〜地上から地球の中心に落下する物体の軌道をめぐってフックと書簡の上で議論することになった。ニュートンは初め渦巻きを描いて中心へ落ちていく軌道を出したが、それに対してフックはその軌道は楕円になると主張した。ニュートンは自分の最初の解が誤りであったことは認めたが、楕円軌道にも反対し、より複雑な軌道を導出した。その過程で、ニュートンは万有引力の概念と、距離の自乗に反比例する力と楕円軌道との関係をつかむに至った。』
(『物理科学史 自然哲学から巨大科学まで』 橋本毅彦 放送大学教材 p.83 下線は、筆者による)
|
※ニュートンも、最終的には、
楕円軌道になると結論したようである。
ところが、実際は、連星バルサーにせよ、2つのブラックホールにせよ、楕円軌道とはならずに互いに渦巻きを描いて近づいていくことが観測されてきているのだった。
このことについて、これまでは、まさに“重力波によるエネルギーの持ち去り”を用いて、次のように説明されてきた。
|
『もし重力波によるエネルギーの持ち去りがなければ楕円軌道になるはずである。 しかし、実際、楕円軌道にならずに渦巻きを描いて互いに近づいてくることは重力波がエネルギーを持ち去ってくれるおかげである。 したがって、「楕円軌道とはならずに、互いに渦巻きを描いて近づいていくこと」は、重力波によるエネルギーの持ち去りが存在することの間接的な根拠になる』
|
一方、このことを、「重力波によってエネルギーの持ち去られない」ことによって説明すると次のようになる。
|
『物体は地上から地球の中心に落下すると同時に、運動エネルギーを増す(力学的エネルギー保存則)。 運動エネルギーが増せば、質量(重力子の放出源として働き続ける能力)が増加する(アインシュタインの式 E=mc2=(m0c2/(1−(v/c)2)1/2 m0:静止質量)。 質量が増加するということは、重力が増加するということに他ならない(ニュートンの万有引力F=GMm/r2[N])。 もしこの「運動エネルギーの増加(=質量の増加)に伴う重力の増加」がなければ、楕円軌道になるはずである。 しかし、しかし、実際、楕円軌道にならずに渦巻きを描いて互いに近づいてくることは、「運動エネルギーの増加(=質量の増加)に伴う重力の増加」があるおかげである。 したがって、「楕円軌道とはならずに、互いに渦巻きを描いて近づいていくこと」は、運動エネルギーの増加に伴う「重力子の放出源として働き続ける能力」アップが実在するということの、すなわち、「“放出される重力子の増加”」という形の「エネルギーを持ち去らない重力波」が放出されていることの間接的な根拠になる。』
|
つまり、実際は、楕円軌道とはならずに、互いに渦巻きを描いて近づいていくことは、「重力波がエネルギーを持ち去る」と「重力波はエネルギーを持ち去らない」の両方で説明できるということになる。 ただし、力学的エネルギー保存則、アインシュタインの式(E=mc2=(m0c2/(1−(v/c)2)1/2 m0:静止質量)、ニュートンの万有引力F=GMm/r2[N]の式と矛盾していない(調和している)のは、後者のみである。
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明は、次の成果を、決して否定するものではないことがわかる。
《熱放射について》
◎2カ所 原子どうしのランタムな衝突→原子どうしのランダムな衝突
◎なぜなら、定常状態に至る必要がないからである。→なぜなら、定常状態に至る必要がないからである(なお、原子模型において、スペクトルが飛び飛びとなるのは、定常状態となることを前提としているからこそのものであった)
◎ 「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるのなら、完全に断熱された黒体は、どんなに時間が経過しても温度が下がらないはずである。
「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるのなら、もし黒体の温度の低下が観測された場合は、その原因は、「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去り」ではなく、単に、“黒体”から周囲の空気への“熱伝導”や、周囲の空気の対流によって熱が持ち去られていることであることになる。
以上の考えを確かめる実験は、「光子が、エネルギーを持ち去らない」ということの検証、すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の検証実験の1つになると思われる。
『ある温度Tを持つ物体は、「真空中に、浮かばせた状態」等、“熱伝導を100%断った状態”で、(熱放射だけによって)本当に温度Tが低下するかどうか?』
という実験をすれば、判定できると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
なお、真空に浮かぶ太陽も、そういったことを確かめられる天然の系の1つに相当すると思われる。
すなわち、『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきている』という事実は── 「光子が、エネルギーを持ち去る」という前提ではなく、「光子が、エネルギーを持ち去らない」という前提によってこそ、上手く説明できると思われる。
なぜなら、やはり、もし本当に、光子がエネルギーを持ち去り続けているのだったら── 水素の核融合が進むほどに、燃料である水素が消費されて減少するにつれて(ヘリウムという不純物が増えるにつれて)、太陽の光度(太陽の温度)は低下し続けているはずだからである。
熱放射がエネルギーを持ち去らないのに加え、太陽の周囲が真空であるので、熱伝導・対流によって、熱(エネルギー)が一切持ち去られないからこそ、太陽の光度(太陽の温度)は、減らないのである。 それどころか、(水素の)静止質量エネルギー(内部運動エネルギー)の一部が、“外部運動エネルギー(すなわち、熱の運動エネルギー)”に転換されて蓄積する結果、太陽の光度(太陽の温度)が増すと考えられるのである。
→ 「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるのなら、「高温の物体」の周囲を完全に断熱することが可能になれば、どんなに時間が経過しても温度が下がらないはずである。
すなわち、(「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるならば)もし「高温の物体」の温度の低下が観測されたなら、その原因は、「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去り」ではありえず、単に、「高温の物体」を構成する分子に対する、周囲の空気の分子の衝突(熱伝導&対流)による“熱の持ち去り”であったということになる。
現在(2017年4月)、100%完全な真空を作り出す技術がない以上、その可能性はありうる。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wilipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
つまり、これまで100%完全な真空が作り出せていないということは── これまで“熱放射によるエネルギーの持ち去り”によると解釈された、温度の低下現象のすべては、実は、「高温の物体」を構成する分子に対する、周囲の空気の分子の衝突(熱伝導&対流)による“熱の持ち去り”によって生じていたと解釈されてもしかたないことを意味する。
すなわち、これまで100%完全な真空が作り出せていないということは── これまで“熱放射によるエネルギーの持ち去り”そのものは、実質上は、検証されてこなかったことを意味するのである。 そのことは、たとえ下記のような計算数値と観測値が一致していたとしても変わらない。
『(4)放射伝熱
T 1およびT 2 : 高温物体の表面および低温物体の表面の絶対温度[K]
面A 1およびA 2 : 高温物体および低温物体の表面積[m 4] とすると、放射によって低温物体から高温物に単位時間あたりに伝わる正味の熱量Qは次式で表される。
Q=σΦ12[T14−T24]A1= σΦ21[T14−T24]A2 [W] (1・7)
ここに、 σ=5.67×10-8W/(m2・K4): ステファン・ボルツマン定数
Φ12、Φ21 : 物体表面の性状と系の形状によって決まる定数 』
(『伝熱学の基礎』 吉田峻 理工学者 p.5)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、もし、「ある高温の物体は、100%完全な真空中に、浮かばせた状態」等、“周囲の分子との衝突を100%断った状態”を作ることができるのならば、(熱放射だけによって)温度が低下しないことを予測する。 (少なくとも思考実験では、低下しない)
この予測を確かめる実験は、「光子が、エネルギーを持ち去らない」ということの検証する実験であると同時に、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を検証する実験の1つになりうる。
その検証実験がうまくいくかどうかは、将来、“100%完全な真空”を人工的に作ることができるがどうかに、かかっている。
すなわち、もし、気体分子が1つも存在しないような“100%完全な真空”を人工的に作り出すことができるのであれば、「熱放射(∈光子)が、エネルギーを持ち去るのかどうか」、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が正しいのかどうかを検証できる。(すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が反証可能であることになる)
しかし、逆に1つでも、気体分子が残っているならば、検証できない(反証できない)ことになる。
すなわち、少なくとも、現在(2017年4月)の技術では、その検証が困難である。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wilipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
『外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在する』のであれば、「真空に浮かぶ太陽」も、実は、「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」ことを確かめられる天然の系の1つとしては、完全なものではなないことになる。
しかし、完全ではなくとも、ある程度は、役立つと思われる。
なぜなら、『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきている』という事実は── 「光子が、エネルギーを持ち去る」という前提ではなく、「光子が、エネルギーを持ち去らない」という前提によってこそ、上手く説明できるからである。
やはり、もし本当に、光子がエネルギーを持ち去り続けているのだったら── 水素の核融合が進むほどに、燃料である水素が消費されて減少するにつれて(ヘリウムという不純物が増えるにつれて)、太陽の光度(太陽の温度)は低下し続けているはずである。
逆に、熱放射(∈光子)がエネルギーを持ち去らないからこそ、(たとえ太陽の周囲にある、ごくわずかな気体分子による熱(エネルギー)の持ち去りがあったとしても)、太陽の光度(太陽の温度)は減らないと考えられるのである。 それどころか、(水素の)静止質量エネルギー(内部運動エネルギー)の一部が、“外部運動エネルギー(すなわち、熱の運動エネルギー)”に転換されて、ある程度蓄積する結果、太陽の光度(太陽の温度)が増すと考えられるのである。
◎ ※「黒体放射」や「放射冷却」やに関する現象についても→ ※「黒体放射」や「放射冷却」に関する現象についても
◎《黒体放射》において修正
もし「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」が前提として本当に正しければ、真空中に浮かんでいる物体(∋黒体)は、(たとえ、外部から放射熱を供給され続けていない中で、それ自自身が熱放射を続けているのに関わらず)どんなに時間が経過しても、温度が下がらないはずである。
すなわち、もし“物体(∋黒体)の温度の低下”が観測された場合は、その原因は、「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去り」ではなく、単に、(厳密な真空中に浮かんでいないことによる)「物体(∋黒体)から周囲の“空気や支柱等”への“熱伝導”(+周囲の空気の“対流”)による熱の持ち去り」であることになる。
このような「真空中に浮かんでいる物体(∋黒体)」の系の振る舞いを確かめる実験は、「光子が、エネルギーを持ち去らない」ということの検証、すなわち、現在の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が正しいかどうかの検証実験の1つになると思われる。
すなわち、『ある温度Tを持つ物体は、「真空中に、浮かばせた状態」等、“熱伝導や熱対流を100%断った状態”で、(熱放射だけによって)本当に温度Tが低下するかどうか?』を観測する実験をすれば、本当に、「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」ことを前提としてよいかどうか、判定できると思われる。
詳細な検討は、今後の課題である。
※「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」が前提として本当に正しければ── (外部から一切の熱放射等のエネルギーを受けとらない中で)「真空中に浮かんでいる物体(∋黒体)」の温度が下がらないままに、熱放射のエネルギーを放出し続けることになる。
つまり、このことは、もし「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」が前提として本当に正しく、なおかつ、「真空中に浮かんでいる物体(∋黒体)」のような系を実現できるのであれば、電磁波(光子の総和)のエネルギーとして、エネルギーを新たに産生し続けることが可能であることを意味する。
この新たに産生されたエネルギーを利用して、「発電、水の分解…」をすることが可能になれば── これは、エネルギー問題を解決するために役立つ技術の1つとなるかもしれない。
つまり、「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」が本当に正しければ── このことは、エネルギー問題を解決するためのヒントの1つになると思われる。
このような意味においても、上記の検証は、とても重要である。
(当然、検証の結果、もし「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」という前提が間違えていることが判明したのならば── これまで育まれた“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、大きな修正(これまでの「重力場、一般相対性理論、電磁場、電磁波…」に関する説明の大部分の却下)を余儀なくされることとなる)
※なお、真空に浮かぶ太陽も、こういったことを確かめられる天然の「真空中に浮かんでいる物体」の系の1つに相当すると思われる。
そして、『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきている』という事実は── やはり、「光子が、エネルギーを持ち去る」という前提ではなく、「光子が、エネルギーを持ち去らない」という前提によってこそ、上手く説明できると思われる。 なぜなら、前にも示したように── 水素どうしの核融合が進んでも、「太陽から放射される電磁波(光子の総和)がエネルギーを持ち去らない」ので、ランダムな熱運動に伴うエネルギー(太陽の中の(まだ核融合していない)水素や(核融合の結果生じた)ヘリウムの運動エネルギー)が増す一方となる結果、光度が増加し続けると説明できるからである。
逆に、もし、「太陽から放射される光子や電磁波が、本当にエネルギーを持ち去る」のだったら、その分、ランダムな熱運動に伴うエネルギー(太陽の中の(まだ核融合していない)水素や(核融合の結果生じた)ヘリウムの運動エネルギー)が減る一方となり、なおかつ、ヘリウムという不純物が増える一方なる結果、核融合の効率が低下してしまうので、太陽の光度は、減少し続けてしまうはずだ、と考えるのが自然であると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
→
一方、「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」が前提として本当に正しければ、100%完全な真空中に浮かんでいる高温の物体(∋黒体)は、(たとえ、外部から放射熱を供給され続けていない中で、それ自身が熱放射を続けているのに関わらず)どんなに時間が経過しても、温度が下がらないはずである。
すなわち、もし“高温の物体(∋黒体)の温度の低下”が観測された場合は、その原因は、「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去り」ではなく、単に、(
100%完全な真空中に浮かんでいないことによる)「高温の物体(∋黒体)から周囲の“空気や支柱等”への“熱伝導”(+周囲の空気の“対流”)による熱の持ち去り」であることになる。
現在(2017年4月)、100%の真空を作り出す技術がない以上、その可能性はありうるのだった。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wilipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
すなわち、現在(2017年4月)、100%完全な真空を作り出す技術がない以上── 高温の物体(∋黒体)から熱放射が熱を持ち去ることは、まだ実質的には検証されておらず、実は「高温の物体(∋黒体)から周囲の“空気や支柱等”への“熱伝導”(+周囲の空気の“対流”)による熱の持ち去り」による現象に過ぎないと解釈されてもしかたないのであった。 そのことは、たとえ下記のような数式による計算結果と観測結果が厳密に一致したとしても変わらない。
『黒体面間の放射伝熱
〜
面A 1から面A 2への正味の放射伝熱Qは、式(5・22)を面積A 1およびA 2にわたって積分すれば求まる。 すなわち、
Q=5.67[(T1/100)4−(T2/100)4]A1F12 [W]
〜
なお、再度注意しておくが、放射伝熱の場合には、電磁波の形でエネルギーが移動するので、前章までの熱伝導や対流伝熱とは異なって、高温の面から低温の面へエネルギーが伝えられるだけでなく、低温の面から高温の面へもエネルギーが伝えられる。 そして、上記のように、その正味として高温の面から低温の面へエネルギーが伝えられ、これが、結果的に伝熱量として求められるのである。』
(『伝熱学の基礎』 吉田峻 理工学者 p.130-131)
|
※なお、熱の実体とは、「ミクロの粒子(分子…)の運動エネルギー」に他ならないのだった。したがって、光子そのものも、“(光子の総和である)電磁波”そのものは、熱ではありえない。
また、本来、熱は高温の物体から低温の物体へ移動するのだった(熱力学の第二法則)。 したがって、「低温の面から高温の面へもエネルギーが伝えられる過程」を想定する上記の説明には、一貫性が欠けており、無理があるように思われる。
伝導や対流は、ミクロの粒子(分子…)の運動エネルギー」の移動そのものであるので、必ず“熱の持ち去り”を伴うと言える一方── 放射された光子、および(光子の総和である)電磁波”は、「ミクロの粒子(分子…)の運動エネルギー」の移動そのものではないので、熱放射(∈光子)は、必ずしも“熱の持ち去り”を伴わなくてもよいことがわかる。
熱について一貫性のある説明を維持していくためにも、「熱放射(∈光子)が熱を持ち去らない」という前提の方が、より自然であると思われる。
このような「100%完全な真空中に浮かんでいる高温の物体(∋黒体)」の系の振る舞いを確かめる実験、すなわち、『高温の物体(∋黒体)は、「100%完全な真空中に、浮かばせた状態」等、“熱伝導や熱対流を100%断った状態”で、(熱放射だけによって)本当に温度が低下するかどうか?』を観測する実験が達成できれば── その観測結果は、「光子が、エネルギーを持ち去るかどうか」、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が正しいかどうかの判断材料の1つになる。
その実験が達成できるかどうかは、本質的には、「100%完全な真空状態」を作り出す技術が生まれるかどうかにかかっていると思われる。
※もし、「100%完全な真空状態」を作り出せて、「その100%完全な真空の中に浮かんでいる高温の物体(∋黒体)」の温度が下がらなかったのなら、このことは、「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」こと(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が反証されなかったこと)が確かめられたことを意味するのみならず、 (外部から一切のエネルギーを受けとらないのに関わらず)「100%完全な真空中に浮かんでいる高温の物体(∋黒体)」が、熱放射(光子)のエネルギーを放出し続けることを意味する。
すなわち、このことは、熱放射(光子)のエネルギーとして、エネルギーを新たに産生し続けることが可能であることを意味する。
このことは、熱放射(光子)が関わる部分では、エネルギー保存則が破れていることが証明されたことを意味するのみならず(なお、このことは、エネルギー保存則を否定しているのではなく、エネルギー保存則の適用条件をより明確にしている)、この新たに産生されたエネルギーを上手に利用できれば(by 「発電、水の分解…」)、エネルギー問題を解決するために役立つ技術の1つとなるかもしれないことを意味する。
つまり、もし「100%完全な真空状態」を作り出せて、「100%完全な真空中に浮かんでいる高温の物体(∋黒体)」の温度が下がらなかったのなら── このことは、エネルギー問題を解決するような技術を得るためのヒントの1つになるかもしれないことを意味する。
以上の意味において、上記の“技術開発”および“検証実験”は、とても重要であることがわかる。
(当然、「100%完全な真空状態」を作り出せたのに関わらず、もし、「100%完全な真空中に浮かんでいる高温の物体(∋黒体)」の温度が下がったのなら、このことは、「熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない」や「時空が不連続である」という前提が間違えていることが判明したことになるのみならず── これまで育まれた“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)(特に、「重力場、一般相対性理論、電磁場、電磁波…」に関する説明の大部分)に重大な間違いがあり、大きな修正が必要であることを意味する。
しかし── もし、温度が下がらなかったのなら、既存の物理学の方が、様々な点で、ひっくりかえることになると思われる)
結果4
《不確定性原理(不確定性関係)と量子ゆらぎ(仮想粒子)の実体──(単振動振幅)確定性原理》
◎追加 ※なお、“観測事情”であることは、「(不確定性原理を導いた)ハイゼンベルグの思考実験」だけでなく、「(不確定性原理を導く)波束」とも関連していることは次の記述からもわかる。
|
『同じ長さΔxの波束に対して何回も観測を行うと、粒子の位置の測定値は平均値の回りでΔxのばらつきをもち、運動量の測定値もΔp=(h/2π)Δkのばらつきをもつ。波の性質により、この2つのぱらつき(不確定さ)の間に次の関係がある。
ΔxΔp ≧ h/4π (6.43)
これがハイゼンベルク(Heisenberg)が提唱した不確定性原理である』
(『振動と波動』 吉岡大二郎 p.179 東京大学出版 下線は、筆者による。 なお原文では、“エイチバー”で表示されていたのをプランク定数hを使って表示している。 また、≧(二重線+不等号)は、原文では、(一重線+不等号)であった。)
|
◎
“(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)
を記述しようとしているという“矛盾”が、ひそんでいる。
→(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)
を記述しようとしているという“矛盾”が、ひそんでいる。
◎
実質上は、“堂々とあきらめている”ことを意味しているのだ。→実質上、“堂々とあきらめている”ことを意味しているのだ。
◎ 実質的には、
何も説明していないに等しいのである。→実質的に
何も説明していないに等しいことを意味しているのである。
◎下記履歴3月7日《熱放射》での修正
この「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去り」を前提として説明されてきた、黒体の温度の変化は── 実は、単に、“黒体”から周囲の空気への“熱伝導”や、周囲の空気の対流によって熱が持ち去られていることを、反映しているということはないのだろうか?
→「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるのなら、完全に断熱された黒体は、どんなに時間が経過しても温度が下がらないはずである。
「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるのなら、もし黒体の温度の低下が観測された場合は、その原因は、「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去り」ではなく、単に、“黒体”から周囲の空気への“熱伝導”や、周囲の空気の対流によって熱が持ち去られていることであることになる。
参考文献 追加
《熱力学、エントロピー》
『わかりやすい熱力学 SI板』 一色尚次・北山直方 共著 森北出版株式会社
『伝熱学の基礎』 吉田峻 理工学社
『知っておきたい熱力学の法則と賢いエネルギーの選択』 リチャード・S・スタイン ジョセフ・パワーズ著 安倍明廣
《宇宙論、ブラックホール、ホーキング》
『ホーキング、自らを語る』 スティーヴン・ホーキング 池央耿訳 佐藤勝彦監修 あすなろ白書
『ホーキング 宇宙論のスーパー・ヒーロー』 キティ・ファーガスン著 栗原一郎訳 偕成社
科学哲学
『近代化学を超えて』 村上陽一郎 講談社学術文庫
2017年3月7日 2.06→2.07
要約
◎至ってしまうは、当然と言えば、当然のことだったのである。→至ってしまう
のは、当然と言えば、当然のことだったのである。
◎そして、この新た手段の根幹→そして、この新た
な手段の根幹
Method&Material(手段・道具&材料)
◎立方体の中心を占めるのようにふるまう。→立方体の中心を占める
かのようにふるまう。
◎その人差し指を右側(外側)にひねろうとする方向
がスピンするものが“右巻き”である
→その人差し指を右側(外側)にひねろうとする方向
にスピンするものが“右巻き”である
◎「総スピン
を一定のまま、ともに転回する」→「総スピン
が一定のまま、ともに転回する」
◎その結果、質量や電荷、重力場や電磁場、各種のヒッグス場、クォークやレプトン… を含め、あらゆる実体や現象を創発する。
→
このしくみによって、質量や電荷、重力場や電磁場、各種のヒッグス場、クォークやレプトン… を含め、あらゆる実体や現象が創発することを説明できる。
◎追加 なお、重力子を構成する4つの素スピノールは、総スピンが2のまま、共転回する。
◎位置を修正 ※なお、この共転回のしくみによって、様々な“量子もつれ(エンタングルメント)”をも説明できる。(→結果1、結果4))
◎この原始ヒッグス場の中で、重力子(重力場)や光子(電磁波)が創発する。(→結果1)
→この原始ヒッグス場の中で、
個々の「重力子や光子」、あるいは、それらの総和であるところの「重力場(or重力波)や電磁場(or電磁波)」が創発する。(→結果1)
◎ヒッグス場ユニットに必要な性質を獲得すると考えられる。
→
原始ヒッグス場ユニット
(PHU)にとって重要な性質を獲得すると考えられる。
◎原始ヒッグス場ユニットPHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和である原始ヒッグス場は
→原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)
)の総和である原始ヒッグス場は
◎追加 すなわち、原始ヒッグス場は、「重力場や電磁場、四次元時空連続体、“質量を与えるヒッグス場”、“(非物質的な)新しいエーテル”」を統合する実体でもある。
◎プレオン∴は、素スピノール
が3つから創発する。
→プレオン∴は、
3つの素スピノールから創発する。
◎このプレオン∴が、
さらに3つ結びつくことで、クォークやレプトン(電子、ニュートリノ)が創発する。
→このプレオン∴が、3つ結びつくこと
によって、クォークやレプトン(電子、ニュートリノ)が創発する。
◎クォークやレプトン(電子、ニュートリノ)の総スピン
は、1/2となる。
→クォークやレプトン(電子、ニュートリノ)の総スピン
も、1/2となる。
◎ 素スピノールどうしの間の距離には、1プランク長(1L
P[m])という、これ以上近付くことができない限界(最小の距離)があるということである。
→
これは、素スピノールどうしの間の距離には、1プランク長(1L
P[m])という、これ以上近付くことができない限界(最小の距離)がある
、ということである。
◎標準モデルの3世代までのクォークやレプトン、量子ゆらぎ、電荷、色荷、グルーオン、ウィークボソン、電子場(電子の波動性)、クォーク場、アンペールの法則、ファラデーの法則… も含め、あらゆる物理的な実体や、あらゆる物理的な現象(観測結果)を
、「複数の“素スピノール”の自己組織化によって創発するもの」として説明していこうとする。
→標準モデルの3世代までのクォークやレプトン、量子ゆらぎ、電荷、色荷、グルーオン、ウィークボソン、電子場(電子の波動性)、クォーク場、アンペールの法則、ファラデーの法則… も含め、あらゆる物理的な実体や、あらゆる物理的な現象(観測結果)を説明していこうとする。
結論
◎「不確定性原理(不確定性関係)が量子ゆらぎを生じ
する
→「不確定性原理(不確定性関係)が量子ゆらぎを生じる
◎改行解消 3つの結論に至ることができる。
◎下線の追加 『ネーターの定理』の抽象的な数学から導く(時空は連続なのだから)「すべてのエネルギーは保存する」
→『ネーターの定理』の抽象的な数学から導く(
時空は連続なのだから)「すべてのエネルギーは保存する」
◎『特集相対性理論』の抽象的な数学から導く
、「あらゆるエーテルは実在しない」
→『特集相対性理論』の抽象的な数学から導く「あらゆるエーテルは実在しない」
◎『一般相対性理論』の抽象的な数学から導く
、「重力子がエネルギーを持ち去る」
→『一般相対性理論』の抽象的な数学から導く「重力波がエネルギーを持ち去る」
◎「自然な世界観(3Steps原理)と調和すること
(すなわち、自然な世界観(3Steps原理)にもとづく、『ミクロの自然(nature)”についての、「幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”…)」
(by具体的な数学(具体的な幾何、具体的な数式))と調和していること)』」という、新たな必要条件を提示する。
→「自然な世界観(3Steps原理)と調和していること」という新たな必要条件を提示する。
◎2カ所 2.“新しい手段”は、
「より深いレベルの階層」から、既存の物理学を包含し、それらの適用条件を明確にする理論の構築を促しているという意味で、現代物理学の発展のために有効である。→2.“新しい手段”は、
『既存の物理学を包含しながら、それらの適用条件を明確にする理論』の構築を促しているという意味で、現代物理学の発展のために有効である。
◎
かといって、“新しい手段”によって育まれた“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、(「抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何)」にもとづく)既存の物理学、すなわち、一般相対性理論や量子論(不確定性原理(不確定性関係))… を否定するものではない。
→
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示す“新しい手段(自然な世界観(3Steps原理)、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何)は、(「抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何)」にもとづく)既存の物理学、すなわち、
一般相対性理論や量子物理学(不確定性原理(不確定性関係)…)… そのものを否定するものではない。
◎ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、既存の物理学を包含し、それらの適用条件を明確にする理論なのである。
→ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
が示しているように、“新しい手段”(自然な世界観(3Steps原理)、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何)は、『既存の物理学を包含しながら、それらの適用条件を明確にする理論』の構築を促しているのである。
◎ ※それは、アインシュタインの相対性理論が、ニュートン力学を否定したものではなく、ニュートン力学を包含したものであったこと、そして、ニュートン力学の適用条件を明確にしたものであったことと同様である。
→
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が『既存の物理学を包含しながら、それらの適用条件を明確にする理論』であることは、アインシュタインの相対性理論が、ニュートン力学を否定したものではなく、ニュートン力学を包含したものであったこと、そして、ニュートン力学の適用条件を明確にしたものであったことと同様である。
◎
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「より深いレベルの階層」から、既存の物理学がどのようにうまくいき(成功し)、どのように、うまくいかなくなっているか(自然(nature)から乖離しているか)を説明すると同時に、既存の物理学の適用条件を明確に示す理論なのである。
この“新しい手段”によって育まれた“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の成果は、驚くほどのものであった。
すなわち、この“新しい手段”
が生んだ“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“非常に抽象化が進み、視覚的な(幾何的な、直観的な)理解が難しいと思われてきた現代物理学”を、視覚的に(幾何的に、直観的に)、シンプルに理解することを可能にし── 一般相対性理論、量子論(量子力学、場の量子論)、ニュートン力学、電磁気学、素粒子理論〈標準モデル〉、プレオンモデル、弦理論、ループ量子重力理論、宇宙論… を包含して適用条件を明確にするのみならず、これらを統一的に説明できるものであった。
→ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示しているように、“新しい手段”の成果は、驚くほどのものであった。
すなわち、この“新しい手段”は、“非常に抽象化が進み、視覚的な(幾何的な、直観的な)理解が難しいと思われてきた現代物理学”を、視覚的に(幾何的に、直観的に)、シンプルに理解することを可能にし── 一般相対性理論、量子物理学(量子力学、場の量子論…)、ニュートン力学、電磁気学、素粒子理論〈標準モデル〉、プレオンモデル、弦理論、ループ量子重力理論、宇宙論… を包含して適用条件を明確にする理論の構築を促したのみならず、これらを「より深いレベルの階層」から統一的に説明することを可能にするものであった。
◎また、“新しい手段”によって育まれた“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の驚くほどの成果は── 「既存の物理理論を、やみくもに否定したり排除したりすること」によってではなく、「自然(nature)と調和している限り、既存の物理理論の多様性を尊重すること」によって、もたらされたものである。
このことからも、“新しい手段”は、 「二者択一、排他性 、唯一性…」ではなく、「自然(nature)と調和する科学の多様性の尊重」を支持していると見なしてよいと思われる。
→ “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の驚くほどの成果が示しているように、“新しい手段”は── 「既存の物理理論を、やみくもに否定したり排除したりすること」によってではなく、「自然(nature)と調和している限り、既存の物理理論の多様性を尊重すること」を支持している。
すなわち、“新しい手段”は、 「二者択一、排他性 、唯一性…」ではなく、「自然(nature)と調和する科学の多様性の尊重」を支持しているのである。
結果1
《質量の実体像》
◎一部テーブルの幅の修正
◎“重力子”は、放出され続けていることに問題はない。
→“重力子”が放出され続けていることに問題はない。
《ボーアの原子模型》
◎追加 (ヘリウムという不純物が増えるので)
《熱放射について》
1
◎“熱放射がエネルギーを持ち去らない”という前提で説明できるだろうか?
→“熱放射がエネルギーを持ち去らない”という前提でも説明できるだろうか?
◎原子や分子は、運動を始める。
→原子や分子は、ランダムな熱運動を始める。
◎追加 (光子の衝突によって、原子や分子の運動エネルギーが減少する一方)
◎吸収はほとんどしないかあるすいはまったく生じない
→吸収はほとんどしないかあるいはまったく生じない
◎そして、「最外殻電子の軌道運動」は、ランダムに逸脱する(外側の軌道に一時的に移る)ことが、広い周波数での熱放射となることをうまく説明できるからである。
→そして、ランダムに逸脱した(外側の軌道に一時的に移った)「最外殻電子の軌道運動」が、速やかに、元の基底状態に戻ることの総和が、広い周波数での熱放射となるというように、うまく説明できるからである。
◎(なお、このランダムな衝突の際には、エネルギーを吸収することはない。 すなわち、力学的エネルギーが保存しているままである。)
そして、すみやかに基底状態に戻る際には、光子を放出する。
(なお、この際に、放出される光子は、Km−Kn=hνに従う、エネルギー非保存の所産である。すなわち、この光子の放出によるエネルギーの持ち去りは存在しない)
以上より、“熱放射がエネルギーを持ち去らない”という前提でも、熱的平衡状態となることが説明できたことになる。
つまりは、「(静止している)原子や分子の運動エネルギーを増加させる光子の衝突と、(主に光源に近づく方向に運動する)原子や分子運動エネルギーを減少させる光子の衝突が釣り合う」ことになる結果、たとえ、“光子によるエネルギーの持ち去り”がなくとも、温度が上がり続けることはないのである。
こういった説明は、「光冷却」という現象を包含している説明である。
また、以上は、たとえ放射熱がエネルギーを持ち去らなくとも、地球がエネルギーを蓄え続けて灼熱地獄と化すことはないことを説明する候補の1つである。
→
なお、このランダムな衝突の際には、エネルギーを吸収することも、消失することもない。 すなわち、ランダムな衝突にともなって「最外殻電子の軌道運動」も、ランダムに逸脱する(外側の軌道に一時的にランダムに移る)際、力学的エネルギーが保存したままである。
そして、すみやかに基底状態に戻る際に放出する光子は、Km−Kn=hνに従う、エネルギー非保存の所産である。
よって、熱運動にともなって生じる、広い周波数での熱放射されるすべての過程で、力学的エネルギーが保存したままとなる。
このことは、“熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない”という前提であっても、「ある温度に達すると、熱的平衡状態となり、運動を開始する原子や分子の総数の増加は止まる」ことを意味する。
すなわち、「(静止している)原子や分子の運動エネルギーを増加させる光子の衝突と、(主に光源に近づく方向に運動する)原子や分子運動エネルギーを減少させる光子の衝突が釣り合う」ことになる結果、たとえ、“光子によるエネルギーの持ち去り”がなくとも、温度が上がり続けることはないのである。
以上より、“熱放射がエネルギーを持ち去らない”という前提でも、熱的平衡状態となることが説明できたことになる。
こういった説明は、「光冷却」という現象を包含している説明である。
また、以上の説明は、たとえ放射熱がエネルギーを持ち去らなくとも、地球がエネルギーを蓄え続けて灼熱地獄と化すことはないことを示している説明の1つである。
※なお、この“熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない”という前提は、シュテファン=ボルツマンの法則(『ある温度Tを持つ黒体は、熱輻射(=熱放射)として、I =ρT 4 [W/m2]のエネルギーを放出する』)と、よく調和している。 (参考『シュテファン=ボルツマンの法則』Wikipedia)
この場合、この式『I =ρT 4 [W/m2]』は、黒体から、1秒間に、1平方メートルあたり、熱放射(∈光子)として、放出されるエネルギーに相当する。
([W]=[J/s])
“熱放射(∈光子)は、エネルギーを持ち去らない”のであれば、この式の理解は容易である。 1秒後であっても、2秒後であっても、温度が一定である限り、同じ熱放射(∈光子)は、エネルギーが放出され続けることになる。 もし、(伝導や対流によって)一切温度が変化しなければ、経過時間に比例しただけ、熱放射(∈光子)のエネルギーが放出され続けることになる。
しかし、逆に、本当に“熱放射(∈光子)が、エネルギーを持ち去る”のならば、この式の意味の理解は、とたんに困難になる。
なぜなら、例えば、「1秒経過すると、熱放射(∈光子)によって、エネルギーが持ち去られる結果、温度が下がる。 2秒経過すると、先の1秒間の温度の低下に伴って、より小さなエネルギーだけが持ち去られて、より小さな温度だけ下がる。 3秒経過すると、先の2秒間の温度の低下に伴って、さらに小さなエネルギーだけが持ち去られて、より小さな温度だけ下がる。…」というように、熱放射(∈光子)によるエネルギーの持ち去りによって温度が下がることに伴い、温度の低下幅が小さくなり、時間経過とともに、『I =ρT 4 [W/m2]』の値の小さくなるからである。
同様に、本当に“熱放射(∈光子)が、エネルギーを持ち去る”のならば、「0.1秒後も、0.2秒後…」も、「0.01秒後、0.02秒後…」にも温度の低下が小さくなり、時間経過とともに、熱放射(∈光子)のエネルギーの放出量が減ってきているはずである。
だとすると、1秒間に放出されるエネルギーである、『I =ρT 4 [W/m2]』は、本当は、何を意味しているのかがあいまいになってしまう。
『I =ρT 4 [W/m2]』は、本当に、1秒間における「熱放射(∈光子)のエネルギーの放出量」の減少(温度Tの減少)を含意しているのだろうか?
だとすれば、ある温度Tにおける、「熱放射(∈光子)のエネルギーの放出量」に相当するとは言えなくなってしまう。
つまり、“熱放射(∈光子)が、エネルギーを持ち去る”という前提は、『I =ρT 4 [W/m2]』の式が、本当のところは、何を意味しているのかの理解を、とても困難にしてしまうのである。
「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるのなら、完全に断熱された黒体は、どんなに時間が経過しても温度が下がらないはずである。
「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるのなら、もし黒体の温度の低下が観測された場合は、その原因は、「熱放射(∈光子)による、エネルギーを持ち去り」ではなく、単に、“黒体”から周囲の空気への“熱伝導”や、周囲の空気の対流によって熱が持ち去られていることであることになる。
以上の考えを確かめる実験は、「光子が、エネルギーを持ち去らない」ということの検証、すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の検証実験の1つになると思われる。
『ある温度Tを持つ物体は、「真空中に、浮かばせた状態」等、“熱伝導を100%断った状態”で、(熱放射だけによって)本当に温度Tが低下するかどうか?』
という実験をすれば、判定できると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
なお、真空に浮かぶ太陽も、そういったことを確かめられる天然の系の1つに相当するかもしれない。
すなわち、『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきている』という事実も── 「光子が、エネルギーを持ち去らない」という前提で、上手く説明できるかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
2
◎(孤立系の外からの)負の仕事によって減る(消滅する)のである。
→(孤立系の外からの)負の仕事によってエネルギーは減る(消滅する)のである。
◎はるか上空から飛行機が落下してしまう危機を救う場面を考えてみよう。
→はるか上空から地上に向かって、飛行機が自由落下してしまう危機を救う場面を考えてみよう。
◎落下する飛行機が持っている大きな運動エネルギーは、
→落下とともに飛行機に蓄えられ続ける大きな運動エネルギーは
◎飛行機が持っていた大きな運動エネルギーの大部分が、スーパーマンによる「負の仕事」によって、消滅したのである。
(厳密には、一部の運動エネルギーは、音、小さな変形… などによって散逸する)
→ 落下とともに飛行機に蓄えられた大きな運動エネルギーの大部分が、スーパーマンによる「負の仕事」によって、消滅したのである。
(当然、厳密には、落下に伴って飛行機に蓄えられた運動エネルギーの一部だけは、音、小さな変形… などによって散逸するので、消滅しない)
◎「運動エネルギーと負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、運動エネルギーを減少させるような仕事)のペア」
「運動エネルギーの大部分と、負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、運動エネルギーを減少させるような仕事)のペア」
◎(ATPのもつ化学エネルギーから)変換された(負の)仕事と落下してくるリンゴの運動エネルギーのペアの大部分は消滅する。
→「(ATPのもつ化学エネルギーから)変換された(負の)仕事」と「落下してくるリンゴの運動エネルギーの大部分」のペアは消滅する。
◎この過程で、熱、空気との摩擦、音などの、あらゆる散逸するエネルギーを考慮しても、部分的には、エネルギーが完全に消滅している。
すなわち、「リンゴ、地球、人、空気」を含む孤立系において、エネルギーが減少しているのである。
つまり、この「リンゴ、地球、人、空気」を含む孤立系において、熱力学第一法則(エネルギー保存則)は成立し続けていないのである。
※「手でキャッチすることによって、リンゴは、結局、元の状態に戻ったのだから、散逸エネルギー以外のエネルギーが減っていない」、ということにもならない。
なぜなら、手の運動にともなって、ATPの化学エネルギーが減少しており(消費されており)、
「減少した(消費された)ATPの化学エネルギー」>「熱、空気との摩擦、音などの、あらゆる散逸するエネルギー」
となっているからである。
→
式を使って示そう。
リンゴを上に放出する際に、骨格筋がリンゴに加える仕事(リンゴにとって“正の仕事”に相当)を w骨格筋(放) とする。 リンゴを上に放出するため骨格筋が運動をする際に、骨格筋が熱として浪費したエネルギーを q骨格筋(放)とする。
この際に消費されたATPの化学エネルギーを、EATP(放)、空気等の摩擦によって奪われるエネルギーをq摩擦熱(放)とすれば、
EATP(放)= w骨格筋(放) + q骨格筋(放) + q摩擦熱(放) ・・・(1)
となる。
放り投げられたリンゴが、放物線を描き、落下する際、空気の摩擦熱として奪われるエネルギーをq空気摩擦熱
とすると、キャッチされる直前のリンゴが持つ運動エネルギーKリンゴは、 Kリンゴ =w骨格筋(放) − q空気摩擦熱 ・・・(2) となる
リンゴをキャッチする際に骨格筋がリンゴに加える仕事(リンゴにとっては“負の仕事”に相当)を w骨格筋(受) とする。 リンゴをキャッチするため骨格筋が運動をする際に、骨格筋が熱として浪費したエネルギーを q骨格筋(受)とする。
この際に消費されたATPの化学エネルギーをEATP受、運動する手と空気の摩擦等によって奪われるエネルギーをq摩擦熱(受)とすれば、
EATP(受)= w骨格筋(受) + q骨格筋(受) + q運動摩擦(受) ・・・(3)
となる。
リンゴをキャッチする際に生じる、音、摩擦…として散逸する熱をq音・摩擦擦(受)
とすると、 Kリンゴ =w骨格筋(受) + q音・摩擦擦(受) ・・・(4)
となる。
以上の過程で、散逸したエネルギーの総和は、E散逸=q骨格筋(放) + q摩擦熱(放) + q空気摩擦熱+ q骨格筋(受) + q運動摩擦(受) + q音・摩擦擦(受) ・・・(5)
である。
「運動エネルギーの大部分と、負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、運動エネルギーを減少させるような仕事)のペア」として消滅したエネルギーE消滅は、
E消滅=(運動エネルギーの大部分)+ 負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、運動エネルギーを減少させるような仕事)
=(Kリンゴ − q音・摩擦擦(受))+ w骨格筋(受) ((4)を使用)
=(Kリンゴ − q音・摩擦擦(受))+ (EATP(受)− q骨格筋(受) − q運動摩擦(受)) ((3)を使用)
=(w骨格筋(放) − q空気摩擦熱 − q音・摩擦擦(受)) + (EATP(受)− q骨格筋(受) − q運動摩擦(受)) ((2)を使用)
= (EATP(放)− q骨格筋(放) − q摩擦熱(放) − q空気摩擦熱− q音・摩擦擦(受)) + (EATP(受)− q骨格筋(受) − q運動摩擦(受))
((1)を使用)
= (EATP(放)+EATP(受)) −E散逸 ((5)を使用)
となる。
この式は、骨格筋の運動(放り上げる&受け止める)を引き起こすATPの化学エネルギーから、熱として散逸したすべてのエネルギーを除いた部分が、完全に消滅することを意味している。 (なお、このE消滅の値が正であることは、容易に確認できる)
すなわち、この式は、「手でキャッチすることによって、リンゴは、結局、元の状態に戻ったのだから、散逸エネルギー以外のエネルギーが減っていない」ということにもならないことを意味している。
なぜなら、手や腕(骨格筋)の運動にともなって、ATPの化学エネルギーが減少しており(消費されており)、
「減少した(消費された)ATPの化学エネルギー」>「熱、空気との摩擦、音などの、あらゆる散逸するエネルギー」
となっているからである。
ATPの化学エネルギーの起源は、そもそも、太陽光のエネルギーであった。
その太陽から得たエネルギーの一部は、熱とはならずに、完全に消滅するのである。
つまり、リンゴを上に放り上げて再びキャッチする過程で、熱、空気との摩擦、音などの、あらゆる散逸するエネルギーを考慮しても、部分的には、エネルギーが完全に消滅するのである。
すなわち、「リンゴ、地球、人、空気」を含む孤立系において、エネルギーが減少しているのである。
このことは、この「リンゴ、地球、人、空気」を含む孤立系において、熱力学第一法則(エネルギー保存則)は成立し続けていないことを意味している。
※なお、「リンゴ、地球、空気」を孤立系と見なし、「人」がリンゴに与える仕事を外力とみなせば、熱力学第一法則(エネルギー保存則)は成立し続けていると言える。
◎すなわち、これらの過程においても、ある運動エネルギーと「負の仕事」のペアが消滅することによって、エネルギーが減少しうる。
→すなわち、これらの自然現象における過程においても、ある運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアが消滅することによって、トータルのエネルギーが減少しうるのである。
◎ なぜなら、ある運動エネルギーと「負の仕事」のペアは、完全に消滅してしまうからである。
→ なぜなら、ある運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアは、完全に消滅してしまうからである。
◎以上のしくみは、地球が持つエネルギーが増加し続けて灼熱地獄と化すことはないことを説明しうる。
→以上のしくみは、地球が持つエネルギーが増加し続けて灼熱地獄と化すことはないことの説明の1つになりうる。
◎そして、それどころか、地球のエネルギー減り続けて、早々と寒冷化してしまいうることさえも示唆している。
→そして、それどころか、地球のエネルギーが減り続けて、早々と寒冷化してしまうことさえも示唆しうる。
◎エネルギーを供給され続けているからである。
→エネルギーが供給され続けているからである。
◎ある運動エネルギーと「負の仕事」のペアは、完全に消滅してしまっても
→ある運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアは、完全に消滅してしまっても
◎運動エネルギーと「負の仕事」のペアが消滅するしくみ
→運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアが消滅するしくみ
◎を支えているとも言える。
→を支えているとも言えるのである。
◎もし、本当に「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、熱放射によって持ち去られ続けている」と説明するならば── 運動エネルギーと「負の仕事」のペアが消滅するしくみによって、このダイナミックで、多様な自然が生じることが説明できなくなる。
→したがって、「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、放射熱として持ち去られておらず(消費されておらず)、“運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアが消滅するしくみ”として活用されうる(消費されうる)」からこそ、このダイナミックで多様な自然、ダイナミックな運動、活動… が成立していると言えるのである。
つまり、“熱放射がエネルギーを持ち去らない”ことは、実は、この地球上の、ダイナミックで多様な自然、ダイナミックな運動、活動… が成立するためにも必要なことだったのである。
そして、もし、本当に「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、放射によって持ち去られ続けている」と説明するならば── (運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアが消滅するしくみによって)このダイナミックで、多様な自然が生じることのみならず、「光合成、化石燃料、太陽光発電…」によって、実際に地球上にエネルギーが蓄えられてきていることも説明できなくなってしまう。
◎
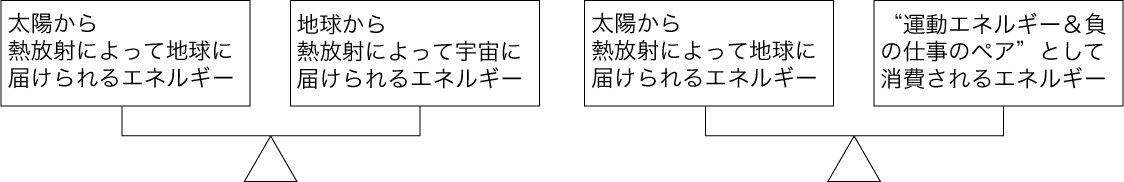
◎※「放射冷却」や「黒体放射」に関する現象ついても、「電磁波も、光子も、仮想光子も、エネルギー非保存の所産である」ことを前提に説明できると思われる。
※「黒体放射」や「放射冷却」やに関する現象についても、「電磁波も、光子も、仮想光子も、エネルギー非保存の所産である」ことを前提に説明できる。



