研究論文
『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
1.光子、重力子、相対性理論(光速不変、時空の曲がり…)、質量、運動法則、重力と電磁気力の量子化、プランク単位について
このページでは、次の項目について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による“説明”を記述する。 なぜなら、この“説明”は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって達成できた“結果”に相当するものと言える。
《光子の波》
光子とは、次のように説明されてきているものである。
|
『1905年、Einsteinは、振動数νの光はhνのエネルギーをもった粒子の流れのように振る舞うとする光量子仮説を唱えた. 〜 このような粒子は、後に光子(photon)と呼ばれるようになった』
(p.4 『8朝倉現代物理学講座 量子光学』 櫛田孝司著 朝倉書店) 下線は、筆者による
|
|
『アインシュタイン(1879〜1955、アメリカ)は、光を振動数ν[Hz]に比例するエネルギーhν[J]をもった粒子(光子または光量子という)の流れと見なし、光子1個が電子とぶつかって、そのエネルギー全部を電子に与えて消えてしまうと考えれば、光電効果が説明できることを示した(1905年)』
(p.236-237 『物理学入門』 実教出版) 下線は、筆者による
|
|
『光の振動数をν[Hz]で表すことにする。 光は
E=hν[J] h=6.63×10−34Js ……(5)
というエネルギーをもった多数の粒子の流れである。 この粒子を光子(光量子)という』
(p.308 『新しい物理学の教科書』 講談社ブルーバックス) 下線は、筆者による
|
|
『振動数νの光はエネルギーhνをもつ粒子のように振る舞う
hはプランク定数である。このように考えた光を光量子または光子という』
(p.344 『基礎教養 物理学』 廣川書店) 下線は、筆者による
|
|
『光子 光の粒子で、エネルギーをE=hνと、運動量p=h/λをもつ。ここで、νはその電磁放射の振動数、λは波長である』
(p.490 『量子革命』 用語集)
『電磁放射 電磁波には、運ぶエネルギーの大きさに応じてさまざまなタイプがある。 電磁波によって運ばれるエネルギーのことを電磁放射と言う。 振動数の低い波(たとえば電波)は、振動数の高い波(たとえばガンマ線)よりも電磁放射は少ない』
(p.493 『量子革命』 用語集) 下線は、筆者による
|
いずれの記述からも、“光子”について、ある程度の(ぼんやりとした)イメージを得ることができる。
そして、以上から、振動数νの電磁波(光も、電波も、ガンマ線も…)は、「“E=hνのエネルギー”を持つ光子」の総和として創発しているものであるらしいことがわかる。
しかし、いずれの説明からも、「光子は、いったいどういうしくみで流れる(移動する)のか?」、「どういうしくみでエネルギーを運ぶのか?」、「光子は、どういうしくみで、hνに相当するエネルギーをもつのか?」といったこと、すなわち、「光子とは、いったい何なのか?」についての、具体的な実体像を読み取ることは、困難である。
※その困難さに、アインシュタインは、しっかり気づいていた。 そのことは、次の記述から読み取れる。
|
『“すべての物理学者は光子が何であるか知っていると思っている”とアインシュタインは書き、さらに“私は光子とは何であるのかの問題に答を見いだすのに一生を費やしたが、いまだにわからない”と続けている』
(p.10 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』) 下線は、筆者による
|
|
『二〇世紀の始めから一九五五年にこの世を去るときまで、彼の念頭を離れなかったのがこの量子の問題だった。「量子問題については、私は一般相対論の一〇〇倍ぐらい頭を使っているよ」と彼は言っているが、そんなに考え続けても、どうにもらちがあかなかったのである。晩年になっても最初考えはじめたころと比べて少しの進歩もないどころか、いよいよもってわからなくなってきた感さえあった。「もう五〇年もの間必死で考え続けているというのに、いっこうに『光量子(クオンタ)とは何なのか?』という問題の解決に近づいてはしないのだ」とアインシュタインはぼやいている。「このごろは猫も杓子もこの答えがわかったなんぞと思っているらしいが、それは大まちがいというものだよ。」』
(p.60 『アインシュタインの部屋──[上]』 エド・レジス著 大貫昌子訳 工作社 下線は、筆者による。『(クオンタ)』はルビであった
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、まさに、この困難さを解消するような、これらの疑問に対する答えを探究するものである。
それは、抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何)によってではなく、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何)によってなされる。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、まさに、「光子は、いったいどういうしくみで流れる(移動する)のか?」、「どういうしくみでエネルギーを運ぶのか?」、「光子は、どういうしくみで、hνに相当するエネルギーをもつのか?」について、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何)を用いて、具体的な実体像を探求するものである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、1つ1つの“光子”は、どのような幾何学的な実体像を持っているかについて、次の仮説をたてる。
仮説1.1.1 光子は、下図のように、素スピノール2つから成り、スピン1を保ち続けるものである。
|
光子
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の表記
|
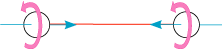 |
|
簡略表記
|
・・
|
|
スピン
|
1
|
| ※“スピン1/2の巻き左素スピノール”と“スピン1/2の右巻き素スピノール”が結びついて、スピン1の光子ができている。
※この光子の説明は、弦理論において、「光子は、スピン1を持つ開いた弦である」と説明されていることと調和している。
|
こういった光子が、空間(電磁場)を光速で移動するとは、どういうことであろうか?
次のような記述をヒントにしてみた。
|
『温度がゼロよりほんの少し高いとどうなるだろうか。この場合も基本はやはりすべてのスピンがそろった状態で、そこにときどきランダムに一個のスピンがひっくりかえることが起きる。そうすると、その隣のスピンがつき合ってやはり逆を向くこともあるだろう。ただ、二つが同時に逆を向くとエネルギーのロスが大きすぎるので、隣が逆を向いたら最初のは元に戻る。次はそのさらに隣が付き合って逆を向く……、という具合にスピンが格子上を伝わって移動していくこともありそうだ。まるで波のようではないか。そう、これは波だ。』
(『質量はどのように生まれるのか』 橋本省二 講談社ブルーバックス p160-162 鉄の強磁性に関しての説明文の一部)
|
この“スピンのひっくりかえりの伝播”が電磁場の上で(素スピノールのネットワーク上で)起きている場合── それがまさに、光子の創発に相当しているだろうと考えてみた。
よって、次の仮説を立てた。
仮説1.1.2 振動数ν、波長λ(=c/ν)の電磁波を構成する光子は、間隔rが波長λの1/2であるような「素スピノールのペア」がスピン1を保ちながら、180度、同時に転回する(共転回する)ことを、下図のように次々と繰り返しながら進むものに相当する。
※“素スピノールのペア”が、スピン1を保ちながら、同時に転回することを“共転回する”と呼ぶのだった。
(なお、1つの素スピノールが“ひっくり返る”ことを、“転回する”と呼ぶのだった)
この共転回の繰り返しの過程は、まさに、『隣が逆を向いたら最初のは元に戻る』ことの繰り返しの過程に相当していることが図から読み取れる。
※素スピノールのペアの間隔rが、波長λの1/2に相当するということは、光子は、180度の共転回を2回繰り返すことによって、1波長分の距離を進むことを意味する。
|
光子は、“素スピノールのペア”が“共転回”するからこそ、スピン1を保ち続けられることが、下図からわかる。
※素スピノールのペアが、共転回している最中の図である。
このように、Aがθだけ転回すると同時に、Bも同じθだけ転回するからこそ、総スピン1を保つことができることがわかる。
※なお、それぞれの素スピノールは、下図のように、小さな円軌道を運動すると考えられる。
これにより、光子の運動量、光電効果、コンプトン効果を説明できるようになる。 詳細はのちほど説明する。
|
この仮説によると、「このように、180度の共転回の繰り返しによって、スピンの1の光子が、次々と伝わっていくこと」こそが、まさに“光子の伝わり方”(光子の移動のし方)の実体に相当していることになる。
※これが、真空中を、光速という一定の速度で伝わるということは、「c=λν=2rν」(c:光速 ν:振動数 λ:波長 r:素スピノールのペアの間の距離)が成立することを意味する。
光子が1回振動する間に、180度の共転回は2回行われるので、単位時間あたりの“180度の共転回の頻度(共転回数)”は、「2ν」ということになる。
よって、「c=λν=2νr」の式から、単位時間あたりの“180度の共転回の頻度(共転回数)(=2ν[回/s])”が大きくなるほど、それに反比例して、光子の素スピノールの間の距離rが小さくなって(光の波長は短くなって)、逆に、単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”が少ないほど、それに反比例して、光子の素スピノールの間の距離が大きく(光の波長は長く)なることがわかる。
つまり、光子は、振動数ν[回/s]に反比例した波長λ[m]を持つと同時に── 「180度の共転回の振動数2ν[回/s]」に反比例した、「素スピノールの間の距離r[m]」を持つことになる。
※一方、アインシュタインの光量子仮説の式「E=hν」により、単位時間あたりの“180度の共転回の頻度(共転回数)(=2ν)”が多いほど、それに比例して、光子のエネルギーが大きくなり、単位時間あたりの“180度の共転回の頻度(共転回数)(=2ν)”が少ないほど、それに比例して、光子のエネルギーが小さくなることがわかる。
また、「E=hν」 であるということは、(ν=c/λ より)「E=hν=ch/λ=ch/2r」が成立するということなので、光子が持つエネルギー(E=hν)が大きいほど、それに反比例して、光子の波長λ、すなわち“足場”の間隔 r(=λ/2)は、逆に短くなることを意味する。
※「E=hν」の式は、ν=1/T(T:周期)より、「ET=h」と変形することもできる。 この周期Tは、「“180度の共転回”の周期の2倍」に相当し、「1つの素スピノール360度の転回周期」と見なすこともできる。 (「ET=h」の式は、不確定性原理(不確定性関係)とも関連する。→結果4)
※なお、このモデルは、“円偏光”についても、うまく説明できると思われる。 すなわち、転回する方向が、光の進行方向に平行な成分のみなら垂直偏光であるが、もし、光の進行方向と垂直な成分も合わせ持つならば、円偏光となるだろうと説明できる。
180度の共転回を2回繰り返すことによって、光子は、1波長分(λ=2r (r : 素スピノールのペアの間の距離))だけ進む。
(すなわち、180度の共転回を2回繰り返すこと(=共転回360度分)が、光子が1回振動することに相当する)
そして、このようなしくみで光子が光速cで移動し── この「光速cで移動する光子」の総和として、電磁波が創発する。
こういった描像により、次の結論が導かれる。
結論1.0.0 「E=hνのエネルギーのみならず、波の性質(振動数νや波長λ)も持つ光子」の総和として創発しているものが、振動数νの波長λの電磁波である
先に述べた『振動数νの電磁波(光も、電波も、ガンマ線も…)は、「E=hνのエネルギーを持つ光子」の総和として創発しているものであるらしい』では、個々の光子が、振動数νや波長λを持つかどうかについては、全く触れられていなかったので、この結論1.1には、「個々の光子が振動数νや波長λを持つ」という新しい意味(情報)が加わっている。
それぞれ1つ1つが「“E=hνのエネルギー”のみならず、振動数νや波長λを持つ」光子は、いわば、“光子の波”と呼べるものである。
以後、光子と言う場合── 「“E=hνのエネルギー”のみならず、振動数νや波長λを持つ光子」、すなわち、“光子の波”(=光の量子波)を意味しているものとする。
※この“光子の波”は、波ではあると同時に、「E=hνというエネルギーや、p=h/λという運動量を持つ“素スピノール(粒子)のペア”」であるので、光電効果や、コンプトン効果を説明できる。
(→あとで詳しく説明する。 《ボーアの原子模型》)
よって、このモデルにより、光が持つとされる“波と粒子の二重性”が生じる理由も、自然に、うまく説明できることになる。(→結果4)
こういった実体像を持つ光子、すなわち、“光子の波”は、「とびとびの波、デジタルな波、不連続な波…」であり、まさに“量子波”(quantum wave)とも呼べるものである。
こういった“光の量子波”の集合、すなわち、“振動数ν、波長λの光子の集まりの流れ”は、どのようにして、“振動数ν、波長λ(=c/ν)の電磁波”を創発するのであろうか?
まず、“1つの光子”の図に、電磁波の図を重ねてみよう。 すると次のようになる。
※「素スピノールのペア」の間隔rは、波長λの1/2になっているので──
図のように、おおよそ、電磁波の山と谷の部分に素スピノールが配置していると考えると、少なくとも振動数νと波長λの対応関係が説明できることが読み取れる。
※また、電場の向きと垂直な方向に、(同時に)磁場が生じていると考えると、おおよそ、うまく説明できることも読み取れる
|
上図からは──
さらに、 下図のように、“右巻きor 左巻きの素スピノールが転回する際に、どちらの方向に、どのような時間経過で電場や磁場が生じるか”という簡単なルールを決めることによって、光子の総和として、電磁波に一致する電場や磁場が創発することを、うまく説明できることが読みとれる。
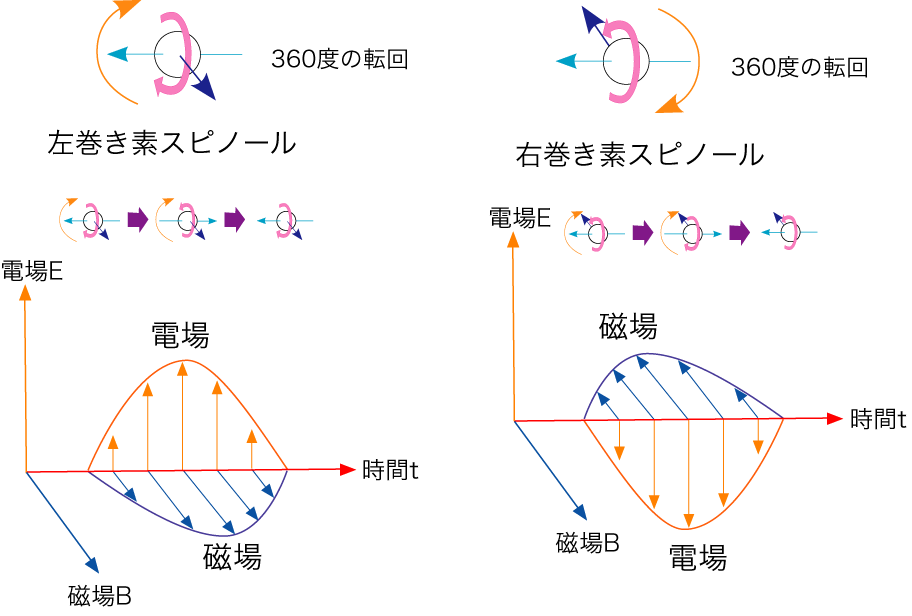 |
ルール1 左巻き素スピノールが転回する向きに対して、左ねじの方向に磁場が生じる。
右巻き素スピノールが転回する向きに対して、右ねじの方向に磁場が生じる。
ルール2 “左巻き素スピノール”が(小さな円)軌道運動していく向きと、同じ向きに電場が生じる。
“右巻き素スピノール”が(小さな円)軌道運動していく向きと、逆向きに電場が生じる。
|
※1つの素スピノールが360度転回する間に、電場や磁場のサインカーブは180度分しか変化しないことになる。
このことは、「スピノールは720度回ると元に戻る」と言われていることと関連しているかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
※このサインカーブ自体は、横軸が時間tになっているので、当然、電磁波のサインカーブとは異なるものである。
すなわち、これは、光子1つが(ある場所で)生じる電磁場の時間変化を示しているに過ぎない。
しかし、こういった性質を持つことは、マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式の解を満たすことがわかる。
マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式の解の1つである 「zの正の方向に進行する正弦波であらわされる電場や磁場」は、次の式で表されるるのだった。
|
Ex(z,t)=E0sin(kz−wt)
By(z,t)=(E0/v)sin(kz−wt)
(参考p.186 『物理学スーパーラーニングシリーズ 電磁気学 第2版』 佐川弘幸/本間道雄 著)
|
そこで、 z=nλ/2での場所での電場や磁場の変化を求めてみるために、z=nλ/2、k=2π/λを代入すると──
電場 Ex(z,t)= E0sin(2πz/λ−wt)=E0sin(πnλ/λ−wt)=E0sin(πn−wt)=±E0sin(wt)
磁場 By(z,t)= (E0/v)sin(2πz/λ−wt)=(E0/v)sin(πnλ/λ−wt)=(E0/v)sin(πn−wt)=±(E0/v)sin(wt)
と共に単純な正弦波となることがわかる。
このことは、「光子を構成する、とびとびの“素スピノール”」の1つ1つが単純な正弦波となる“電場や磁場の変化”を担いさえすれば、マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式を満たすことを意味する。
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、ミクロのレベルで、電場と磁場が、「「ミクロの“電場&磁場”」(左巻き)→「ミクロの“電場&磁場”」(右巻き)→「ミクロの“電場&磁場”」(左巻き)→…」のように、両方同時に生じていることになる。
それは、マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式の解の1つである 「zの正の方向に進行する正弦波であらわされる電場や磁場」は、次の式で表されることとも調和している。
|
Ex(z,t)=E0sin(kz−wt)
By(z,t)=(E0/v)sin(kz−wt)
(参考p.186 『物理学スーパーラーニングシリーズ 電磁気学 第2版』 佐川弘幸/本間道雄 著)
|
このことは、“電磁波は、「電場→磁場→電場→磁場→…」のようにして伝わる波である”と下図のように図示&説明されている文献があることと異なる。
この図は、「オリジナルは、ノーベル物理学賞者のボルンによって描かれたため、その後、多くの著者に取り上げられた」(『電磁波とは何か』 p194)とのことである。
しかし、この「電場→磁場→電場→磁場→…」と交互に伝わる波は、実際は、定在波にすぎず、進行する電磁波ではない。
『電界と磁界が交互にずれた位置で強くなるのは定在波であり、電磁波は進行しない。
〜電磁波が進むためには〜電界と磁界が同時に強くならなければならないのである』
(『電磁波とは何か』(後藤尚久 講談社ブルーバックス p194 下線、省略は筆者による) |
進行波が「電場と磁場が同時に強くなっている」ように図示され(p.327)、定在波は「電場と磁場が交互にずれた位置で強くなる」ように図示されている(p.352)文献がある。
(『基礎電磁気学 改訂版』(山口昌一郎 電気学会) |
『これは定在波を表していることに注意しなければならない』と記述され、『誤りの例』として、上のような図を提示している文献もある。
(『入門 電波応用 [第2版]』(藤本恭兵 共立出版)(p.17)) |
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示している次の図は、少なくとも、「進行する電磁波」を説明するものと調和している。
|
こういった個々の光子が複数集まると、どうなるであろうか。
このことに関連して、次のような記述がある。
|
『光子数の多い極限では、コヒーレント状態は振幅、位相ともに決まった波で表される古典的な状態と実質的に同じになる』
(p.163 『8朝倉現代物理学講座 量子光学』 櫛田孝司著 朝倉書店)
|
※コヒーレント状態とは、「位相がそろった状態」という意味である。
このことは、同じ振動数νを持つ光子(光の“量子波”)が多数、位相がそろった状態(=コヒーレント状態)で生み出されれば、古典的な電磁波の波(上図のサインカーブのような波)を創発しうることを示していると考えられる。
この説明は、「個々の光子は、マクスウェルの方程式から導かれた波動方程式を満たす」ことからも、無理のないことが分かる。
また、こういった、とびとびの光子(光の量子波)の総和として、創発するものが電磁波であるという描像は、『コヒーレントな光子の集団の典型的な例である、レーザー』はもちろん、『電磁波の腹と節の違いを観測したことに相当する「ヘルツの実験」』や『電気双極子の振動によって生じる電磁波』も説明できるだろうと思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。(→《電気双極子の振動に伴う放射について》)
すなわち、これらの既存の光に関する現象や観測結果は、光子の波(光の量子波)の総和として創発するものとして、再解釈することができると考えられるのである。
こういった光子および、そのエネルギーを伝える媒体は、どのようなものであろうか?
現在、電磁波は、「電磁場の上を伝わる」と説明されている。
(なお、マクスウェルは、エーテルの存在を前提として定式化したのだった。 そして、エーテルは、マイケルソン-モーレーの実験、アインシュタインの特殊相対性理論によって否定されたと言われている)
したがって、電磁波を構成する光子も、電磁場を媒体にし、その上を波として進むと考えるのが自然であろう。
それでは、“電磁場”の幾何的な実体像は、どのようなものであるだろうか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、次のような仮説を立てて説明する。
仮説1.1.3.1 下図のような、右巻き素スピノールのペアと左巻きの素スピノールのペア”が対消滅してできている、“原始ヒッグス場ユニット”(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))の挙動の総和として、電磁場が創発する。
|
“原始ヒッグス場ユニット”
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))
(=原始ヒッグス場の基本構造)
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の表記
|
|
←
→
|
|
|
構成
|
“左巻き素スピノールのペアと
右巻きの素スピノールのペア”
対消滅してできている
|
|
構造
|
“4面体”
|
|
エネルギー
|
“正4面体”のとき、
蓄えているエネルギーが最も小さい
|
|
スピン
|
0
|
光子は、この“原始ヒッグス場ユニット”(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))の“4面体”をバネ的な足場にして、光速で移動することになる。
この“原始ヒッグス場ユニット”(PHU)の総和が、原始ヒッグス場である。
電磁場は、この原始ヒッグス場の上で創発するものということになる。
※なぜ、電磁場ユニット((EU(=electromagnetic(field)Unit)))ではなく、わざわざ、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))と表記するか?
なぜなら、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニットの総和)は、電磁場のみならず、重力場、質量を与えるヒッグス場、四次元時空連続体、時空の曲り、“新しいエーテル”… も担うからである。(下記の説明)
なぜ、ヒッグス場(ユニット)ではなく、原始ヒッグス場(ユニット)と表記するか?
なぜなら、ヒッグス場には、質量を与えるヒッグス場以外にも、電子ヒッグス場、クォークヒッグス場、ニュートリノヒッグス場など、他のヒッグス場も存在すると考えられるからである。(→結果3)
※原始ヒッグス場ユニット(PHU)が、電磁場のみならず、重力場、質量を与えるヒッグス場、四次元時空連続体、時空の曲り、“新しいエーテル”… も担うということは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)が、宇宙(時空)をびっしりと占めていることを意味する。 そのことは、ある意味、時空が不連続であることを意味する。(“ある意味”とは、少なくとも「光子や重力子にとっては」という意味である)
※“原始ヒッグス場ユニット”(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)は、ゆるやかに結びつきながら特定の場所を占めている(自由に回転できると同時に場所を固定している)ものだと考えられる。(→下記、結果3、4)
※上図ではあたかも、とびとびで運動しているかのように図示されているが、凝縮のペア(黒い線で結ばれた、右巻きどうし、左巻きどうしのペア)は、ふだんは、それぞれに、連星のように、連続して、高速で回転運動をしていると考えられる。 この“連星のような動き”こそが、“場所を移動させない(位置を固定させる)”という重要な性質を創発すると考えられる。
※“連星のような(連続)軌道運動”を、わかりやすく図示すると、このようになる。
※なお、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する素スピノールにとっては、(連続な)回転対称性が成立するので(ネーターの定理によって)「素スピノールの角運動量保存則」が成立すると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※“高速”と書いたが、この素スピノールの軌道円運動の速さは、“光速に等しくなければならない”理由はないようである。 なぜなら、仮に、この素スピノールの軌道運動の速さが光速を越えていたとしても、“光速不変の原理”は成立し、特殊相対性理論と矛盾しないからである。
“光速不変の原理”が成立する理由(光速不変が、どのようなしくみで創発するか)については、下記で説明する。(→《特殊相対性理論と光速不変》)
※素スピノールの(連続)軌道円運動の“速度の大きさ”は、具体的にいくらになるのが自然(nature)と調和するのだろうか? それは、“場所を移動させない(位置を固定させる)”という重要な性質を創発することとも関連しているのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
※なお、「右巻き素スピノールのペア」と「左巻き素スピノールのペア」が同じ方向に(連星のような)回転運動しているということは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の、単なる(連星のような)回転運動については「時間が流れていない」と見なすべきであることを意味していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※なお、例えば、光子を構成している素スピノールとして、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成している素スピノールが共転回している間は、この“連星のような(連続)軌道運動”は、一時的にストップすると同時に、(「右巻き素スピノールのペア」と「左巻き素スピノールのペア」の運動の向きに差がでるからこそ)はじめて「時間が流れる」(時間が創発する)のだと考えられる。
よって、共転回の間、共転回していない方の“連星のような(連続)軌道運動”だけは続いているのだと考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
この原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和の上で“光子の流れ”が生ずることについて、次の仮説を立てた。
仮説1.1.3.2 原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”は、変形することによって、エネルギーを一時的に蓄えるバネのようなものとなり── 光子が持つエネルギー(E=hν)が大きいほど、それに比例して、“4面体”の変形の振幅、すなわち、“4面体”に蓄えられるエネルギーの振幅も大きくなる。 光子は、下図のように、この「原始ヒッグス場ユニット(PHU)のバネに一時的に蓄えられるエネルギーを、とびとびに伝えながら光速で進む。
※1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))の中の1つの素スピノールが、光子を構成するそれぞれの素スピノールに相当している。
※「バネのようにエネルギーを蓄えている、1つの“4面体”の変形」が解消されるとともに、新たな“4面体”の変形が生じることが図示されている。 すなわち、光子(素スピノールのペア)の移動とともに、エネルギーが移動することになる。
すなわち、共転回する素スピノールのペアの中で、ピンク色で示している素スピノールを含む“4面体”の方が、よりバネのようなエネルギーを蓄えており、その後“4面体”の変形を解消するとともに、そのエネルギーを次の“4面体”に新たに蓄えることを繰り返すことによって、エネルギーが光速で移動するのである。
なお、振動数νを持つ光子のエネルギー(2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの合計)は、常にぴったりE=hνとなる。(下で説明)
※時空をびっしり占める個々の“原始ヒッグス場ユニット(PHU)”の足場にはそれぞれ、必ず、右巻き素スピノール(相手に近づく方向に進むもの、遠ざかる方向に進むもの)、左巻き素スピノール(相手に近づく方向に進むもの、遠ざかる方向に進むもの)の4種類が存在するので、ある波長を持つ光子の進行に必要な素スピノールを、適宜選ぶことが可能となる。
|
光子は、その振動数νの違いに応じて、様々なエネルギー(E=hν)を持つことができる。
その光子の持つエネルギーの起源は、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)に蓄えられるエネルギーの合計である。
振動数νを持つ光子(光の量子波)のエネルギーの総和(原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの総和)は、常に一定のE=hνとなることは、次のように説明できる。
仮説1.1.3.2 により、1つの光子(2つの素スピノール)が1回だけ180度の共転回する間に── 一方の「変形している“4面体”」が、(蓄えた)エネルギーを放出するのと同時に、もう一方の“4面体”がエネルギーを新たに蓄えるように変化する。
まずは、その共転回の際の「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形」と「電場の変化」の様子を、下に示す。
※これからの180度の共転回において──
上図の、上段の左側にあるピンクの素スピノールの転回は、蓄えたエネルギーを放出する過程を担い、
右側にあるブルーの素スピノールの転回は、新たにエネルギーを蓄える過程を担うことになる。
|
上図のように、変形している原始ヒッグス場ユニット(PHU)の場所における「電場の変化」が単純な正弦波となることで、マクスウェル方程式から導かれる波動方程式を満たすようになるのだった。
この正弦波は、z=nλ/2の場所に存在する「変形している原始ヒッグス場ユニット(PHU)」が生じる「電場の変化」、すなわち、電場 Ex(z,t)=±E0sin(wt)という単純な正弦波に相当する。
位相がそろった(コヒーレントな)光子の集合が、トータルで古典的な電場となるので、光子1つによる電場の変化をE光子sin(wt) とし、その場所での、光子の個数をn光子とすると、z=nλ/2の場所での電場の変化は、単純に、電場 Ex(z,t)=±E0sin(wt)=±n光子E光子sin(wt) となる。
一方、一般に、電場Eの空間が持つエネルギー密度は、ε0E2/2 で求まるのだった。
よって、 z=nλ/2の場所にある1つの原始ヒッグス場ユニット(の“4面体”を含む立方体の体積((2LP)3=8LP3))が持つエネルギー密度EPHUを計算すると── 1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)が作る電場 は、±E光子sin(wt)なので、 エネルギー密度EPHU=ε0×(±E光子sin(wt))2/2=(ε0E光子2sin2wt)/2 となる。
ところで、 共転回している間の、原始ヒッグス場ユニット(PHU)が蓄えているエネルギー密度の変化は、エネルギーを放出する分と、エネルギーを吸収する分との間で、常に、ちょうど、位相がπ/2(90度)ずれている。
よって、共転回を担っている2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるのエネルギー密度の合計は、
ε0EP2sin2wt+ε0EP2sin2(wt±π/2)
=ε0EP2sin2wt+ε0EP2cos2wt
=ε0EP2
を1/2倍したもの、すなわち、一定の値として決まる。
※共転回を担っている2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるのエネルギー密度の合計が、一定の値となることは、次のように、図からも理解できる。
一般に、sin2θ=(1−cos2θ)/2 であるので、そのグラフは、次のような形になるのだった。
よって、θ=wt(=2πt/T)の場合を考えると、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”に蓄えられるエネルギー密度は、ε0E光子2sin2wt=ε0E光子2(1−cos2wt)/2 に比例したものとなるので、下図のグラフの形から、共転回の間、電場のエネルギーの総和は一定となることが読みとれる。
※共転回の開始と終了の時間経過をそろえて、図示されている。
※この図において、緑の縦線の部分が、放出されるエネルギーに相当し、
ピンクの縦線の部分が新たに蓄えられる(吸収される)エネルギーに相当する。
コサインカーブの対称性により、エネルギーの放出とエネルギーの吸収が、180度の共転回の間ずっと100%一致する。
したがって、共転回の間、電場のエネルギーの総和は一定となる。
※なお、当然、「右巻き素スピノールの転回に伴う電波のエネルギーの放出」から「左巻き素スピノールの転回に伴うのエネルギーの吸収」という“エネルギーの移動”も、同様に説明できる。
|
いずれにせよ、次の結論に至る。
結論1.0.1 180度の共転回に伴う電場のエネルギーの変化において、一方のエネルギーが減る分と、一方のエネルギーが増加する分が、常に、全く等しくなる。
すなわち、光子を構成する2つの素スピノールが共転回する間、2つのミクロ電場のエネルギーの合計(2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの合計)は、ぴったり一定となっているのである。
なお、ミクロ磁場のエネルギーについても、同様に考えることができる。
なぜなら、磁場のエネルギー密度は、μ0H2/2で求まる一方で、原始ヒッグス場ユニット(PHU)が作るミクロの磁場も、sinθに比例するからである。
|
z=nλ/2での場所での磁場の変化を求めてみるために、z=nλ/2、k=2π/λを代入すると── 磁場 Ey(z,t)= (E0/v)sin(2πz/λ−wt)=(E0/v)sin(πnλ/λ−wt)=(E0/v)sin(πn−wt)=±(E0/v)sin(wt)と単純な正弦波となることがわかる。
(参考 p.186 『物理学スーパーラーニングシリーズ 電磁気学 第2版』))
|
すなわち、磁場のエネルギー密度は、 sin2θ=(1−cos2θ)/2 に比例することになり、なおかつ、位相が常にπ/2(90度)ずれているので、電場の場合と同様にして、共転回の間、磁場のエルギーの総和も一定となることが説明できるのである。 よって、次の結論に至ることができる。
結論1.0.2 180度の共転回に伴う磁場のエネルギー変化において、一方のエネルギーが減る分と、一方のエネルギーが増加する分が、常に、全く等しくなる。
以上より、「左巻き素スピノールの転回が関与する“ミクロ電場とミクロ磁場”のエネルギー」と「左巻き素スピノールの転回が関与する“ミクロ電場とマイクロ磁場”のエネルギー」の合計は、常に一定となることがわかる。
よって、「共転回に関わる2つの“4面体”に蓄えられるエネルギーの合計」は、ずっと一定のままに、1つの光子は、光速で移動していくことになる。
この値、すなわち、1つの光子がもたらす一定な「共転回に関わる2つの“4面体”に蓄えられるエネルギーの合計」の値が、まさにアインシュタインの光量子仮説の式E=hν[J]の値、「光子1つが持つエネルギーの値」に相当すると考えるとつじつまが合う。
つまり、「光子1つが持つエネルギーは、常にE=hν」なのである。
よって、次の結論に至る。
結論1.0.3 光子を構成する2つの素スピノールを含む、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの合計は、常に、一定であり、その値が、E=hνである。
※エネルギーの合計が常に一定となるのは、「スピン1を保ちながら、同時に素スピノールのペアが転回できるから(共転回できるから)」に他ならない。
すなわち、共転回は、アインシュタインの光量子仮説も根底で支えていることになる。
※なお、厳密には、1つの光子が持っている「電場のエネルギーと磁場のエネルギー」の合計が、1つの光子が持っているエネルギーに相当すると言うことになる。
また、「E右巻き+E左巻き=hνで一定である」と言うこともできる。
※例えば、アインシュタインの光量子仮説の式、すなわち、光子が持つエネルギーEの式E=hν[J]は、「素スピノールの転回周期(=原始ヒッグス場ユニットが変形する周期)」をTとすると、ν=1/T であるので、E=hν=h/T[J] より、ET=h[J・s] という式を導くことができるのだった。
この「ET=h」の式は、(光子を構成する)素スピノールが360度の転回をする周期Tが短ければ短いほど── それに反比例して、その“4面体”の変形によって蓄えられるエネルギーの最大値(振幅)が大きくなることを意味していると解釈できる。
つまり、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”は、「素スピノールの転回によって変形させるスピードが速ければ速いほど── 蓄えるエネルギーの振幅がより大きくなる」という性質を持つと言える。 そして、原始ヒッグス場ユニット(PHU)がそのような性質を持つからこそ、ET=h[J・s]やE=hν[J]の式が成立すると言えるのである。
また、この「ET=h」の式は、ハイゼンベルグの不確定性原理の式「ΔE×Δt≧h」と似たものとなっているが、ハイゼンベルグの不確定性原理(不確定性関係)とは、根本的に異なる内容を意味している。
なぜなら、「ET=h」の式の方は、「光子の持つエネルギー」や「素スピノールの転回周期(=原始ヒッグス場ユニットが変形する周期)」が確定していることを意味しているからである。
この「ET=h」の式が、ミクロの自然(nature)そのものがどのようにふるまうかを示す式であるのに対し── ハイゼンベルグの不確定性原理の式「ΔE×Δt≧h」は、本来、人類の観測事情(ミクロとマクロの相互作用が持っている自然(nature))を示してくれる式であり、ミクロの自然(nature)そのものがどのようにふるまうかを示す式ではない。(→結果4)
※E=h/T にT=1を代入すると、E=h[J]となる。
プランク定数hの値の大きさの実体的な意味の1つは、“転回周期1秒で、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”のバネを変形させる際のエネルギー振幅である”ということになる。 (→下記《プランク定数、プランクエネルギー、プランク自然定数について》)
1つの“光子の量子波”と電磁波の関係について、やや詳しく図示すると次のようになる。
※上が電磁波(複数の光子の総和として創発)であり、下が電磁波を構成する“1つの光子”が生むミクロ電場やミクロ磁場を示す。
この図のポイントの1つは、電磁波の波長に比べて、“光子”を担うとされる「原始ヒッグス場の“4面体”」は、非常に小さい(せいぜい2プランク長(2LP[m])程度)と言うことである。
電磁波の波長には、例えば、10[km]に及ぶ長いもの(電波)から、3×10-12[m]ほどの短いもの(γ線)まで、観測されているが── いずれも、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)のサイズである、およそ2プランク長(2Lp[m])≒3.232×10-35[m]よりは、はるかに大きい。 ((電磁波を創発しない)LP光子は、ここで考えていない)
1つ1つの光子は、波長の半分(λ/2)の距離ずつ、とびとびに配置された、この小さな中継地点(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”)を土台にして進む。
個々の光子は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を変形するだけであるので、個々の光子によって生じる電場や磁場の変化は、実際は、2プランク長(2LP[m])程度の非常に狭い範囲に限られて生じていることになる。 (それらが、ミクロ電場&ミクロ磁場に他ならない。)
光子が波として伝わる様子、すなわち、“光の量子波”を、時間経過を詳しく図示すると次のようになる。
※緑の○で囲んだ部分は、“共転回”している過程の図に相当する。
※1つの光子が、とびとびに配置された、この小さな中継地点(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”)を土台にして進んでいく様子が読み取れる。
※この光子を伝えるとびとびの原始ヒッグス場ユニット(PHU)は、光子の波長の半分(λ/2)の距離ずつ離れて配置している。 |
このように説明できる、たった1つの光子は、まさに、一定のエネルギーを光速で伝達するものであり、“量子波(quantum wave)”という言葉にふさわしいものである。
ただし、このような“光の量子波(quantum wave)”の説明の根底には、重大な前提(仮定)が、含まれていることを見逃してはならない。
すなわち、様々な波長λを持つ光子(“光子の波”(=光の量子波))が存在するということは、「様々な距離(例えば、光子の半波長)はなれた2つの素スピノールのペアが同時に転回できること(共転回できること)」を意味し── このことの根底には、「光円錐を越えて、素スピノールのペアが作用し合うことが可能である」という前提が存在することを意味しているのだ。
※光子の2つの素スピノールのペアが共転回する様子を、光円錐に重ねて、図示してある。
光円錐とは、「光(光速)がたどりつける範囲」を示す。
共転回は、その定義により、「総スピンが一定のまま同時に転回すること」である。
したがって、共転回の開始時から終了の直前まで、2つの素スピノールのペアは、上図のように光円錐を超越して作用し合っていることになる。
共転回が終了すると、光円錐の外にあった素スピノールが、ちょうど光円錐に接するようになる。
この繰り返しによって、光子は、あくまで“光速”で進むことになる。
※なお、共転回を担う、1つ素スピノールの360度の転回周期をTとすると、時間T/2の間に、光速cで光子が進む距離が、素スピノールの間隔 r に等しいので、「cT/2=r」となる。 この式に、「波長λ=2r」の関係を代入すると、cT=λ、すなわち、c=λ/T=λν となるので、ここに矛盾はないことがわかる。
|
よって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、この重大な前提(仮定)を、仮説の1つに加える。
仮説1.0 素スピノールのペアは、光円錐を越えて、作用し合うことによって共転回する。
この仮説を「共転回原理」と呼ぶこととする。 この共転回原理は、一見すると、既存の物理学をゆるがすような前提であるという印象を与えるかもしれない。
しかし、よく考えてみると、必ずしも既存の物理学をゆるがさないことはすぐわかる。
例えば、共転回が完了するとともに、光円錐の外にあった素スピノールが光円錐に接するようになる結果、「光子の移動そのものは、光速である」ことは変わらないからである。
そして、既存の物理学をゆるがすどころか、以下の結果に示すように、この「光円錐を越えた素スピノールの相互作用の所産である共転回」は、光子のみならず、重力子、そして、光速度不変、特殊&一般相対性理論の世界、マクスウェルの方程式の世界、ニュートン力学の世界… の創発を根底で支えるものであることがわかるからである。
つまり、逆なのだ。
これまで、「“光速度不変の原理”や特殊相対性理論により、光円錐を越えた相互作用はありえない」と考えられてきたが── 「より深いレベルの階層」から見れば、実は、逆に、「光円錐を越えた素スピノールどうしの共転回」が、光子や重力子、“光速度不変の原理”や特殊相対性理論、一般相対性理論、マクスウェルの方程式の世界、ニュートン力学の世界… の成立を根底で支えていることがわかるのだ。
すなわち、「素スピノールの光円錐を越えた共転回」は、目立たぬ縁の下の力持ちのように、根底で既存のあらゆる物理学を支えているのだ。
そのことを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がはっきり示しているのだ。
“実験的な裏付けが全くない”と思われる方もおられるかもしれないが、それも、実は、すでにある。
それは、「ベルの不等式の破れ」を証明する数々の実験結果に他ならない。
それらは、すべて、素スピノールの共転回の実在性を裏づける、実験的な証拠であると解釈できるものである。
すなわち、それらの実験によって実在することが示されている“量子もつれ(エンタングルメント)”や“非局所性”は、“素スピノールの共転回”の実在性を裏付けていると解釈できるものなのだ。 (“量子もつれ”や“非局所性”が、どのようにして生じるかは、まさに“素スピノールの共転回”が、すっきりと説明できるものである)
つまり、これらの“量子もつれ”や“非局所性”を証明する実験結果は、“素スピノールの共転回”についての“観察の窓”なのだ。 (→結果4)
そして、“量子もつれ”や“非局所性”という、「一見、既存の物理学をゆるがしてしまうように思われる」という理由で、これまで、どちらかというと煙たがれる(見て見ぬされる)ことが比較的多かった現象は、実は、新たな“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を構築するための基礎、よりどころ、根拠… に相当するものと見なせるものなのだ。
“量子もつれ”や“非局所性”は、かつて、量子論や特殊相対性理論を生み出すためのよりどころとなった、2つの“暗雲”に続く── 新たな“暗雲”の1つに相当すると言えるだろう。
なぜなら、“量子もつれ”や“非局所性”という、新たな暗雲こそが、“光速不変の原理”や“量子仮説(量子原理)”に匹敵する原理と呼べる、“共転回原理”を支えているからである。
※2つの“暗雲”については次の文章を参考にした。
|
『今世紀初頭の1900年4月、イギリスの物理学会の長老ケルビン卿は、「熱と光の力学理論の頭上ある19世紀の雲」という象徴的な演題のもとに講演を行い、すでに完成されたと見なされていた古典物理学に内在する二つの深刻な困難を指摘した。
まず、熱輻射についての困難は、この講演の数ヶ月後に現れたプランクの量子仮説の提唱によって劇的な解決が見られることになったのであるが、1905年、アインシュタインはプランクの量子仮説を一歩進め、直裁、簡明な光量子論を提出して、光電効果の問題を解決した。 〜
〜
特殊相対性理論は、いうまでもなく、ケルビンのあげた、もう一つの光の伝播に関する困難を根本的に解決する〜ことになった。』
(『アインシュタイン選集1』 監修者のことば by湯川秀樹 i〜iiより引用 共立出版株式会社 一部省略)
|
※なお、この“共転回原理”にもとづく、光子の説明には、「光子がどのように移動するか」「光子がどのようにエネルギーを運ぶか」「どのようにしてE=hνという一定のエネルギーを持つか」を説明できるメリットがあるのみならず── 「光速不変がどのようなしくみで実現するか」(→下記)、「波と粒子の二重性がとのように実現しているか」、「マクスウェル-アンペールの法則やファラデーの法則… がどのようにして成立しているのか」(→結果2)を説明できるというメリットや「二重スリットの実験において、たとえ1つ1つの光子を独立にスクリーンにぶつけても、“縞模様”ができる理由」(→結果4)を自然に説明できるというメリットを含め様々なメリットがある。
そして、さらには── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、弦理論の中に登場する“弦”のすべて(1次〜3次)は、結局は(根底では)、「素スピノールどうしの共転回」をベースにして創発するものであると説明できる。(→考察3) すなわち、弦の実在性を支持するのもの(弦の実在性の根拠)が、実は、量子もつれ(エンタングルメント)、そして、共転回原理であったと言うことができるのである。
逆に見れば、“弦理論”(弦が存在することを前提にする理論)が、“一定のゆるぎない成果をあげていること”は、共転回原理の実在性を支持していると解釈できるのである。
※共転回の時間経過の詳細を図示すると、次のようになる。
この図の中の、共転回のペアの右側のブルーの素スピノールの動きに注目すると── “4面体”の中の、ある素スピノールが転回する際の、その素スピノールの(小さな円)軌道運動”そのもののおかげで、その運動する方向に、そのままバネが縮んだり伸びたりすると考えられることが読み取れる。
このことは、下図のように、“光子の運動量”を説明できることと調和している。 (詳細はのちほど説明する)
このように、「光子の媒体となる“電磁場”は、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)から創発するものである」という説明は、“エーテルの復活”を意味し、既存の物理学と矛盾しているように思われる方もおられるかもしれない。
しかし、後に詳しく説明するように、ここに矛盾はない。ここで簡単に説明すると、次のような理由になる。
|
1.このような電磁場(原始ヒッグス場から創発)は、“光速不変の原理”(なぜ、慣性系で光速一定が観測されるか、どのうようにして、マイケルソン-モーレーの観測結果が生じるか)を説明できるものである。(→下記の説明《等速運動と特殊相対性理論》)
2.このような電磁場(原始ヒッグス場から創発)の説明は、「マイケルソン-モーレーの観測結果」と矛盾していないのみならず── 他ならぬアインシュタインが一般相対性理論において(『アインシュタイン選集2』p.189〜A10 エーテルと相対性理論)、必要不可欠と考えていた(新しい)エーテルと調和するものである。(すなわち、こういった電磁場を創発できる原始ヒッグス場は、物質ではない(物質未満の実体である)とともに、重力場を説明できるものである)。 つまり、こういった説明には単に矛盾がないだけでなく、特殊相対性理論で「(古い)“エーテル”が否定されたこと」と、一般相対性理論で「エーテルが必要不可欠であると考えられていること」との間にある根本的な矛盾を解消するものなのである。
3.原始ヒッグス場は、電磁場や重力場(時空の曲り)のみならず、(質量を与える)ヒッグス場、等速直線運動、四次元時空連続体… も含めて、統一的に説明できるものである。 (詳細はのちほど説明する)
|
《重力子の波》
次に、重力子が、波として光速で移動することについて説明する。
重力子は、スピン2である。 よって、次の仮説を立てた。
仮説1.2.0 重力子は、スピン1の光子2つ分に相当し、4つの素スピノールから、次のように構成されている。
|
重力子(グラビトン)
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の表記)
|
|
|
簡略表記
|
: :
|
|
スピン
|
2
|
「(右巻き素スピノール+左巻き素スピノール)×2」(=光子×2)が、上のように配置することによってはじめて、(パウリの排他律に反せずに)“スピン2”となることができる。
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)における、このような重力子の説明は、弦理論における、「重力子は、スピン2の“閉じたひも”(ループ)である」という説明と調和している。 (→考察3)
さらに、「重力子がどのように移動するか」について、次の仮説を立てた。
仮説1.2.1 重力子は、「波長が2プランク長(2LP≒3.232×10-35m)の“LP光子”2つが並走するもの(=デュアルLP光子)」に相当し、2組の素スピノールのペア(間隔r=1プランク長(1LP≒1.616×10-35m))を、同時に並行して転回させながら(“デュアル共転回”させながら)、下図のように“原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)”の“4面体”の上を、次々と進む波に相当する。
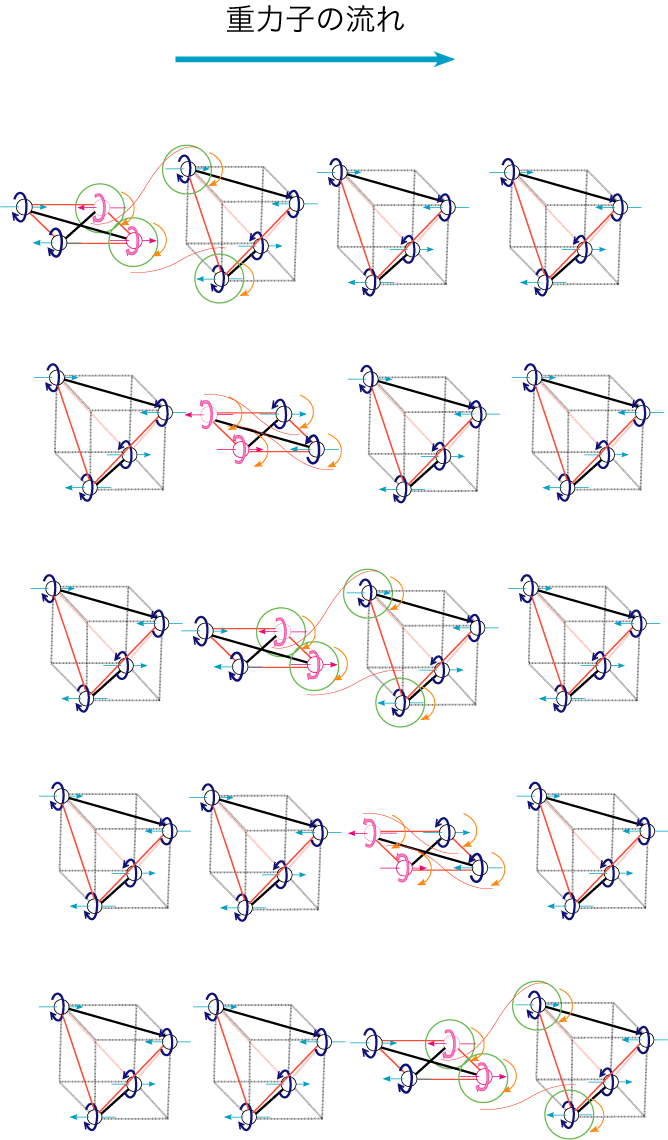 |
※“LP光子”とは、共転回する素スピノールのペアの間の距離rが、1プランク長(LP≒1.616×10-35m)である光子である。
このLP光子の波長λは、素スピノールの間隔rの2倍(λ=2r)に相当する「2プランク長(2LP≒3.232×10-35m)」となる。 このLP光子の波長2LP[m]は、理論上考えられる「最も短い“光子の波長”」である。
※上図で、重力子によって、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)のバネが、完全に縮みきっているのことが図示されている。
2つのLP光子によって、サンドイッチのように、上からと下からの両方からバネを縮める作用が働き、バネが縮みきっている“4角形”となっている様子が読みとれる。
このように、「重力子によって、完全に縮みきった状態になっている原始ヒッグス場ユニット(PHU)」を単純に「“4角形”(縮みきったバネ)」と呼ぶこととする。
1つの重力子があるところには、必ず、1つの「“4角形”(縮みきったバネ)」があることになる。
すなわち、少なくともブラックホールの外では、重力子と「“4角形”(縮みきったバネ)」は、1対1に対応していると言える。(ブラックホールの中でどうなっているかについての詳細な検討は、今後の課題である)
※重力子による原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形において、「近づく素スピノールのペアにおける共転回」と、「遠ざかる素スピノールのペアにおける共転回」の2種類の共転回が共存していることも読みとれる。 この2種類の共転回が同時に生じることによってはじめて、(パウリの排他律に反せずに)スピン2を保つことができる。
これらの2種類の共転回が同時に起こることを“デュアル共転回”と呼ぶこととする。
※「重力子を構成する素スピノールの間の距離」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)を構成する素スピノールの間の距離」は、ともに1LP[m]と等しくなるおかげで、デュアル共転回が、2種類生じることが、図から読み取れる。
すなわち、「2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”にまたがって達成される“デュアル共転回”」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の中で達成される“デュアル共転回」の2種類である。
この後者の「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の中で達成されるデュアル共転回」のおかげで、“4角形”(縮みきったバネ)の状態が一定の時間持続することができることになる。
このように、重力子のサイズと、原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)のサイズの間には、深い関係があるので、“より長い波長の重力子”は存在しえないと考えられる。
(なお、『アインシュタイン選集2』によれば、アインシュタインは「長い波長の重力波」というものを考えていたことがわかる。重力波は、「放出される重力子数の変動」として創発するものなので、より波長の長い重力波が存在すると考えることには、全く問題がないと思われる。
しかし、この「重力波は、放出される重力子数の変動として創発する」という説明は、一方の電磁波についての説明、「波長λの電磁波は、コヒーレントな波長λを持つ光子の総和として創発すると考えられる」ということと、微妙に異なっているように思われる。「重力子&重力波」と「光子&電磁波」の関係は、実際は、どのようになっているのかは重要なテーマの1つである。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
重力子は、上図のように、180度のデュアル共転回をするたびに、1プランク長(LP[m])進むことになる。 そして、これが、光速で移動することになる。
(電磁波を構成する)光子は、その波長λに応じて決まる距離(r=λ/2[m])だけ離れた原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の中の素スピノールのペアが、次々と共転回しながら光速で移動するのに対して── 重力子は、「最も近くにある(1プランク長(LP[m])離れた)2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)をまたぐデュアル共転回」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中のデュアル共転回」を交互に繰り返しながら光速で移動することになる。
重力子の波長、すなわち、重力子を構成する“LP光子”の波長は、これまで観測されてきている電磁波を構成する光子の波長──これまで観測されてきているX線やγ線を構成する光子の波長よりも、はるかに短い、2プランク長(2LP≒3.232×10-35[m])であることは、人体に致命的なダメージを与えることはないのだろうか?
しかし、その心配は不要であると考えられる。
なぜなら、重力子は、やはり、(スピン2の重力子が持つ構造上の理由から)“原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”上に存在する素スピノールとだけしか“デュアル共転回”を達成できないからである。
つまり、重力子は、クォークやレプトンに直接作用できずに、生体を構成する原子(クォークや電子で構成される)の間を透過するだけなので、人体に致命的なダメージを与えるとは考えられないのである。 (例えば、電子の中の素スピノールと、重力子の中の素スピノールが、いきなり“デュアル共転回”をすることは不可能であると考えられる。(電子の内部構造 →結果2))
さらには、単なる“シングルLP光子”ではなく、あくまで“デュアルLP光子”であるので、そこに、ふつうの光子が作る“電場”や“磁場”の延長上のもの(“激烈な電場”や“激烈な磁場”のようなもの)は、生じえないからである。 なぜなら、“ミクロ磁場”は、常に100%打ち消されており、かつ“ミクロ電場”は、常に“右素スピノールと左素スピノール”のペアによって同時に生じている結果、常に正負が打ち消し合っていることになるからである。
(マイナス電荷は、左巻き素スピノールのみからなり、プラス電荷は、右巻き素スピノールのみからなる。(→結果2)
“シングルLP光子”がどう振る舞うと考えられるかについては後ほど説明する)
そのため、波長2プランク長の個々の重力子は、(人体に致命的なダメージを与えていないことと矛盾していないのみならず)、その観測さえも、極めて困難になると考えられる。
※この個々の重力子と比べれば、『放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の変動の波(=“時空の曲がり”(重力場)の変動の波)』の方は、観測しやすいと言える。
この『放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の変動の波(=“時空の曲がり”(重力場)の変動の波)』の方が、2016年2月に最初に発表された「LIGOによって観測された“重力波”」に相当する実体であると考えられる。
『アインシュタイン選集2』の中の、重力波に関する部分をよく読み返してみると──
|
『重力場がどのように伝播するかという重大な問題』(p.159)
『(6)から重力場は光速度をもって伝播することがわかる』(p.161)
『もし力学系が終始、球対称の構造をもち続けるならば、これは重力波を放出できない』 (p.170)
|
という記述から、アインシュタインが予言した“重力波”とは、決して、「個々の重力子」のことではなく、「光速で伝播する重力場」の方、すなわち、『放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の変動の波(=“時空の曲がり”(重力場)の変動の波)』(=「放出される重力子数の変動の波」)の方であったことに気づかされる。
すなわち、「 個々の重力子 ≠ アインシュタインが予言した重力波 」であり、アインシュタインは、決して、個々の“重力子”について、予言してはいなかったことがわかる。
(それは、マクスウェルが個々の“光子”を予言していなかったことと同様である)
つまり、かつての論文(ver1.04)の中の記述、『その重力の強度(重力子の数)の増減の波自体は、決して、〜“重力波”ではないと考えられる』というのは、間違いであったことになる。 正しくは、『重力の強度(放出される重力子数)の増減(変動)の波は、アインシュタインが予言したところの“重力波”((光速で伝播する)重力場の変化の波)に相当すると考えられる』ということになる。
以上のことから、「電磁波と光子」の関係、「重力波と重力子」の関係を比較して整理すると次のようになる。
|
「電磁波と光子」
|
「重力波と重力子」
|
|
場の創発
|
電磁場は、原始ヒッグス場の上で
「光速で進む光子(or仮想光子)の総和」として創発している
|
重力場は、原始ヒッグス場の上で
「光速で進む重力子の総和」として創発している
|
|
源
|
電荷
|
質量
|
|
“場の変化”の波の予言
|
マクスウェルは、“電磁場の変化”にともなって生じる波が
光速で伝播することを予言
光子については予言していなかった。
|
アインシュタインは、“重力場の変化”にともなって生じる波が
光速で伝播することを予言。
重力子については予言していなかった。
|
|
“場の変化”の波の実体
|
波長λの“電磁波”(「(光速で伝播する)電磁場の変化の波」)は、
「波長λの“光子”(&変形した“4面体”)の波の
コヒーレントな集合」として創発している
|
波長λの“重力波”(「(光速で伝播する)重力場の変動の波」)は、
「波長2LP[m]の“重力子”&“4角形”(縮みきったバネ)の
数(密度)の変動の波」として創発している
|
|
振幅
|
電磁波の振幅は、光子の数に比例する
|
重力波の振幅は、重力子の数に比例する
|
|
“場の変化”の波の原因
|
電気双極子の周期的な加速運動
※電流の周期的な変化によっても、電磁波は生じる。
※原子の中の電子の“軌道の変更”に伴う
運動エネルギー順位K nの変化(→ 《ボーアの原子模型》)
によっても電磁波(スペクトル)は生じる。
|
“質量の周期的な加速運動”
※理論的には、人が手を振っても、風車が回っても、惑星が公転しても… “重力波”は生じる。
|
|
サイズ
|
電磁波の波長も、光子の波長も、様々ありうる
※例えば、レーザーの場合、電磁波を構成する光子の波長は1種類で
電磁波の波長=光子の波長となる。
例えば、電気双極子の振動によって生じる電磁波を構成する光子は、
「電磁波の波長=光子の波長」のものが最も多いが、他波長のものもある程度混ざっていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
重力波の波長は、様々ありうる
重力子の波長は、一定の2プランク長(2LP[m])のみである
※重力波の波長≠重力子の波長
|
|
観測
|
電磁波の観測、光子の観測は、ともに容易
※レンツの実験で電磁波を観測できた。
※二重スリットの実験で光子を観測できた。
|
重力波の観測、重力子の観測は、ともに困難
※しかし、重力波はLIGOにより、初めて観測できた。
(2016年2月に発表)
|
※「電磁波の波長=光子の波長」ということは、放出される電磁波の振動数、および、放出される光子の振動数は、ともに「電荷の運動の周期」と密接に関連していることを意味する。
(→《電気双極子の振動に伴う放射について》)
※「豆電球に与える電圧をゆっくり周期的に変化させて生じる、光の強度(光子の数)が増えたり減ったりを繰り返す波」の例は、(「光の強度(光子の数)の波の波長≠光子の波長」なので、(電磁波の波長=光子の波長であるところの)「“電磁波”」とは、(ともに光速で進むが)別物である。
しかし、この例は、(重力波の波長≠重力子の波長であるところの)“重力波”とは似ていると言えるかもしれない。
このことは、「(アインシュタインが予言した)重力波(「光速で伝播する重力場(の変動の波)」)と重力子」の関係と「(マクスウェルが予言した)電磁波(「光速で伝播する電磁場(の変動の波)」)と(アインシュタインが予言した)光子」の関係は、単純には類推し合えないことを意味していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、以後、(アインシュタインが予言し、観測されたところの)“重力波”(「(光速で伝播する)重力場の変化の波」)は、個々の“重力子”の“総数の変化”として創発していること、すなわち、「“重力波”≠個々の“重力子”」であることを明確にした上で話を進めることとする。
さて、重力子が、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)の上を、光速で波として移動するとき、“4角形”(縮みきったバネ)も、一緒に光速で移動していくことになる。 この“4角形”(縮みきったバネ)の動きを、次のように(簡略化して)表記できる。
※“4角形”(縮みきったバネ)が移動していくことだけが図示されている。
厳密にいえば、「“4角形”(縮みきったバネ)≠重力子」であるが── 1つの重力子につき、必ず1つの“4角形”(縮みきったバネ)が生じているので、便宜上、重力子の挙動を近似的に“4角形”(縮みきったバネ)の挙動として代用することが可能となる。
重力子は、その実体は、「並走するふたつの光子(厳密には、LP光子)」であるので、(光子の場合と同様に)一定のエネルギーを持っていると予想される。
すなわち、“4角形”(縮みきったバネ)を作っている状態のみならず、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)にまたいでいる状態を含めて、重力子のエネルギーの大きさは一定となっていると予想される。
確かめてみよう。
便宜上1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)に注目することによって、1つの重力子が通過するのに伴って、「“4面体”の状態→“4角形”(縮みきったバネ)の状態→“4面体”の状態」と変化する際の(エネルギーを含む)詳細を、下のように説明できる。
|
原始ヒッグス場ユニット(PHU)
由来の“4面体”
|
|
原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)
──その1
|
|
原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)
──その2
|
|
原始ヒッグス場の基本構造の“4面体”
|
|
|
→
|
|
→
|
|
→ |
|
|
※外部から来た重力子と、緑で囲ったペアが180度デュアル共転回しながら、“4角形”(縮みきったバネ)の配置に近づく。 その際、右巻きと左巻きの素スピノールの両方が、“4面体”のバネを縮める方向に運動する。(そのことが図から読み取れる) これによって、いわばサンドイッチのように上下からはさむように変形が進む。
なお、このエネルギーを蓄える過程は、下図の下側のピンクの縦線の部分に相当する。
|
|
|
※原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中で、デュアル共転回が進んでいる。
その際、下図のように、放出するエネルギー(緑の縦線)と、蓄えるエネルギー(ピンクの縦線)がぴったりと一致するので、スピン2を保ちながら、180度のデュアル共転回をする間、エネルギーの総和は、ずっと一定に保たれることになると考えられる。
※この過程のおかげで、“4角形”(縮みきったバネ)の状態が一定時間持続することができる。
|
|
|
※重力子がさらに進行し、外部の原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の素スピノールとデュアル共転回をするのにともない、上図の赤い素スピノールのペアのみが転回し、エネルギーが放出される。その過程は、下図の緑色の縦線の部分に相当する。
※エネルギーが放出されきるとともに、元の“4面体”の配置に戻る。 |
※この図は、重力子が、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)にまたがる場合、および“4角形”(縮みきったバネ)を作っている場合のエネルギー変化を示した図と見なすことができるものである。
この図において、緑の縦線の部分が、開放されるエネルギーに相当し、ピンクの縦線の部分が新たに“4面体”に蓄えられる(吸収される)エネルギーに相当している。
この図より、(コサインカーブの対称性によって)重力子が、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)にまたがる場合、および“4角形”(縮みきったバネ)を作っている場合のいずれにおいても、エネルギーの放出量とエネルギーの吸収量が、“デュアル共転回”をしている間、ずっと100%一致し続けることがわかる。
※なお、重力子の実体が「並走するふたつの光子(厳密には、LP光子)」だからこそ、コサインカーブとなる。 すなわち、数式を用いた説明については、本質的には、光子の場合と同様であると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。 |
つまり、この説明から、1つの重力子が持っているエネルギーの大きさは、(原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)の上を光速で進んでいる間)常に一定となることを導くことができる。
よって、次の結論に至る。
結論1.1.1 1つの重力子が持っているエネルギー、すなわち、重力子を構成する4つの素スピノールを含む、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギー、あるいは、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの合計は、いずれも、常に一定である。
この「1つの重力子が持つエネルギー」は、とても重要な意味を持つであろう。
具体的な値を、さっそく求めてみよう。
「重力子1つが持つエネルギー」の値を、EG[J](Gは、グラビトン(graviton)由来のものである)と表記し、重力子エネルギーと呼ぶこととする。
(このEG[J]は、「1つの重力子が持つ一定の“トータルエネルギー”」であると同時に、「1つの“4角形”(縮みきったバネ)が持つエネルギーの大きさ」でもある)
仮説により、重力子は、“波長が2プランク長(2LP[m])であるLP光子2個分”に相当するものなので、単純に、波長2LP[m]の光子が2つ分のエネルギーであると考えると、重力子エネルギーEG[J]の近似値を計算できる。 その値を“EG近似値[J]”と表記することにすると、その計算値は、次のように求まる。
EG近似値=2×hνG=2hc/λG=2hc/2LP=hc/LP[J]
(νG : 重力子の振動数(=波長2LP[m]の光子の振動数)=c/λG[回/s] λG : 重力子の波長(=波長2LP[m]の光子の波長)=2LP[m])
プランク長(LP≒1.616×10-35[m])、プランク定数h≒6.626×10-34[J・s]、光速c≒2.9979×108[m/s]として、
EG近似値=hc/LP
≒(6.626×10-34[J・s])×(2.9979×108[m/s])/(1.616×10-35[m])
≒1.22921×1010[J]
となる。
一方、プランクエネルギーEPの値は、 EP=1.9561×109[J]であった。
EG近似値(1.22921×1010[J])とプランクエネルギーEPの値(1.9561×109[J])は、確かに似ている。
ところで「プランク距離を求める式LP=(hG/2πc3)1/2[m]」を変形して得られる「G=2πc3LP2/h」を用いると、
EP=(hc5/2πG)1/2 =hc/2πLP[J]
が得られる。 したがって、
(1/2π)×EG近似値=(1/2π)×(hc/LP)=EP[J]
となることがわかる。 すなわち、EG近似値[J]を2πで割れば、プランクエネルギーEP[J]にぴったり等しい値になることがわかる。
果たして、プランクエネルギーEP[J]が、そのまま求めたかった重力子が持つエネルギーEG[J]に等しいのだろうか?
必ずしもそうとは限らないであろう。
したがって、重力子エネルギーEG[J]とプランクエネルギーEP[J]が共に単位が[J]であるので、βを無次元比例定数とし、EG[J]=βEP[J]と表記することとする。
今求めたいのは、この、無次元比例定数βの値である。 どうすれば、求まるだろうか?
それは、「重力を“EMOES”の理論で導く式」と「ニュートンの万有引力の法則を変形して導かれる式」を比較することで求まる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、r=2nLP[m]の場所での重力F[N]は、次のように求まる。
重力F[N]=(NMβEP/4πn2)×(1/2LP)[N]
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)×Nm [N] …(1.1)
|
1/4πn2 : r=2nLP[m]にある厚さ2LP[m]の球殻が持つエネルギーを平均化する項
1/2LP : エネルギー平均を厚さ2LP[m]で割り、傾き(力)を計算するための項
NMやNm : 質量M[kg]やm[kg]が重力子質量MG [kg]の何個分かを示す項
重力子質量MG :次の式を満たす質量 EG[J]=MGc2[J]、MG[kg]=βMP[kg](=β×プランク質量[kg])
※詳細は下記 《重力の実体像》にて説明する。
|
一方、ニュートンの万有引力の法則が示す重力F[N]=GMm/r2[N]は、次のように変形できる。
すなわち、「プランク距離を求める式LP=(hG/2πc3)1/2[m]」を変形して得られる「G=2πc3LP2/h」、r=2nLP[m] を代入することによって
重力F[N]=GMm/r2[N]
=(2πc3LP2/h)×(M/4LP2n2)×m [N]
=(2πcLP/h)×c2LP×(M/4LP2n2)×m [N]
=(Mc2/2n2)×(1/2LP)×(m/MP)[N] (プランク質量MP=h/2πcLP[kg]を利用)
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)×(2πm/MP)[N] …(1.2) (分母と分子に2πをかける)
のように変形できる。
(1.1)と(1.2)を比較すると、 (2πm/MP)=Nm=m/MGであることがわかる。
よって、両辺のmを消去して、MG(=βMP)=MP/2π という関係が導かれる。
つまり、これにより求めたかったβの値が、β=1/2π と決まったことになる。
したがって、EG[J]=βEP[J]より、重力子1つが持つエネルギー、すなわち重力子エネルギーEGは、プランクエネルギーEP[J]を2πで割ったものに等しいことになる。
結論1.1.2 重力子エネルギーEG[J]は、プランクエネルギーEP[J]を2πで割った値、すなわち、EP/2π[J]に等しい。
この重力子エネルギーEG[J]と、重力子エネルギーの近似値[J](EG近似値[J])との関係を考えると、重力子についての理解が次のように深まる。
(1/2π)×EG近似値=EP[J]であった。
よって、この重力子エネルギーEG(=EP/2π[J])は、EG近似値[J]、すなわち、「波長2LP[m]の“LP光子”2つ分が持つエネルギーch/LP[J]」を、(2π)2で割ったものに相当することになる。
この値EG(=EP/2π[J])を用いると、波長2LP[m]の“LP光子”2つが、1つの重力子になる際に放出する、“結合エネルギー”は、
「波長2LP[m]の“LP光子”2つ分が持つエネルギー[J]」−「重力子エネルギー[J]」
= ch/LP−ch/(2π)2LP ≒ (38.4/39.4)×ch/LP[J]と求められる。
したがって、その結合エネルギーは、1つの重力子が持つエネルギー(1/39.4)×ch/LP[J]のおよそ38.4倍であることがわかる。
よって、重力子1つから、“LP光子”2つに分解されることは、非常に起こりにくいことがわかり、それは、この現実の宇宙と合致する。
以上より、重力子は、非常に安定なものであることがわかると同時に、光子よりも非常に効率の良く“4角形”(縮みきったバネ)を作れることがわかる。
(まさに、「“サンドイッチのように上下はさみこむプロセス”が生む効率のよさであると考えられる)
プランクエネルギー[J]に相当する質量エネルギー[J]を持つ質量[kg]、プランク質量MP[kg]が重要であるように──
「重力子エネルギー[J]に相当する質量エネルギー[J]を持つ質量[kg]」、すなわち、「プランク質量 MP[kg]を2πで割った値(MP/2π)[kg]」、すなわち、重力子質量MG[kg]も重要な値である。 整理すると次のようになる。
|
プランクエネルギーEP[J]
=hc/2πLP[J]
|
→
×1//c2
|
プンランク質量MP[kg]
=EP/c2
=h/2πcLP[kg]
|
|
↓
×1/2π
|
|
↓
×1/2π
|
|
重力子エネルギーEG[J]
=EP/2π
=hc/(2π)2LP[J]
|
→
×1//c2
|
重力子質量MG[kg]
=MP/2π
=h/(2π)2cLP[kg]
|
※なお、EP=MPc2[J]と同様に、EG=MGc2[J]の関係がある。
ただし、重力子エネルギーEG[J]が質量を持っているとは限らない。
(例えば、重力子は、質量を持っていない)
すなわち、重力子質量MG[kg]は、重力子エネルギーEG=MGc2[J]に相当するエネルギーを
持っているものの一例なのである。 (→下記 《質量の実体像》)
したがって、「重力子質量」と呼んでいるが、決して、(光子と同様に)重力子が質量を持っているという
意味はなく、「重力子エネルギー当量質量」の意味を持つ。
|
※以上の考察から、光子(電磁波の構成要素)も重力子(重力波の構成要素)も、「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”を、“一時的にエネルギーを蓄えるバネ”のようなものとして活用し、伝わっていく波である」と言えることがわかる。
そのことは、光子の波も、重力子の波も、両方とも「原始ヒッグス場という共通の媒質の上を伝わる波である」と言えることを意味する。
以上の説明は、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のアプローチによって、“重力場と電磁場の統一”が可能であることを示唆している。
《質量の実体像》
質量とは何か?
アインシュタインは、E=mc2 の式により、「質量とは、エネルギーである」と説明した。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次のように定義する。
定義1.0 質量とは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力である。
この定義は、次の点で画期的なものである。
|
1. 「慣性質量」と「重力質量」を統合的に説明できる。
(すなわち、「慣性質量」と「重力質量」が、なぜ等しいかを説明できる定義である。 詳細は、下記の説明にて)
2. 質量とエネルギーの関係を明確にする。
すなわち、たとえ、エネルギーを持っていても、重力子を放出しなければ質量にはカウントされないことを明確に説明できる定義である。
・例えば、(電磁波を構成する)光子は、エネルギーを持っているが、重力子を放出しないので、質量としてにはカウントされない。
(これによって光速で進むことができる)
・また、質量エネルギーは、エネルギーの一種に過ぎないことを明確に説明できる定義である。
例えば、電子は、質量エネルギーの他に、電荷エネルギーや磁荷エネルギーを持つ。
(詳細は、下記《静電場(クーロンの法則)のEMOES表記と電荷エネルギー》)
・例えば、“4角形”(縮みきったバネ)は、重力子を放出することができるが、重力子の放出源としては働き続けないので、
質量を持っていないと 判断できる。 “4角形”(縮みきったバネ)は、重力子の通過点に過ぎないのである。
このことにより、重力場も、質量を持っていないと判断できることになる。
|
この定義は、アインシュタインのE=mc2 の式から導かれる「あらゆる質量は、エネルギーを持つ」という説明とは矛盾していない。
しかし、E=mc2 の式から導かれる「あらゆるエネルギーは、質量を持つ」という解釈とは、矛盾している。
すなわち、E=mc2 の式から導かれる「あらゆる質量は、エネルギーを持つ」という解釈は、正しい(=自然(nature)と調和している)が、
E=mc2 の式から導かれる「あらゆるエネルギーは、質量を持つ」という解釈は、正確ではない(=自然(nature)から乖離している)のである。
※例えば、“運動エネルギー”は、「「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力」に相当しているので、質量を持っていると言える。
しかし、例えば、光子や重力子のエネルギー、電荷エネルギーや磁荷エネルギーは、「「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力」に相当していないので、質量を持っているとは言えない。
したがって、「質量とは、エネルギーである」という質量の定義は、とても誤解を生みやすい定義であることになる。
(なぜなら、「あらゆるエネルギーは、質量を持つ」という自然(nature)と乖離している“解釈”を支持しうるからである。
なお、E=mc2のみならず、あらゆるエネルギーが質量を持つという解釈は、アインシュタイン自身が起源であるらしい。 →《重力場、エネルギー、質量》 )
それと比較すると、次の質量の定義は、誤解を生みにくいと言える。
定義1.0 質量とは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出し続ける放出源として働き続ける能力である。
あらゆる質量を持つ粒子(電子、クォーク、ニュートリノ、陽子、中性子…)は、周囲の原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)まで、変形させることによって、重力子を放出させ続ける能力を持っているのである。
アインシュタインの式、E=mc2=m0c2(1−v2/c2)-1/2≒m0c2+m0v2/2 (m0:静止質量)によると、質量エネルギーは、運動エネルギーと、静止質量エネルギーに分けられるのであった。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、質量の起源、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」の起源の実体は、1つに集約される。
|
1. 運動エネルギー(ふつうの意味での運動エネルギー)
(=外部運動エネルギー(external kinetic energy))
2. 静止質量エネルギー
(=内部運動エネルギー(internal kinetic energy))
|
→運動エネルギー |
※つまりは、あらゆる質量、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」は、実は、“運動エネルギー”として統一的に説明できることになる。 (→下記)
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、静止質量エネルギーm0c2も、その実体は、運動エネルギーであったということになる。
そして、だからこそ、運動エネルギーと静止質量エネルギーの両者は、その式の形が似ていると言えると思われる。
この考えによると、E=mc2 の式は、実は、厳密には、「運動エネルギーと質量エネルギーが等価であることを示す式である」と解釈すべきものであったことになる。
|
例えば、もし、ある陽子が、外から見てわかるように運動していれば、その陽子が持っている(外部)運動エネルギーは、その陽子が持っている「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」の一部に相当している。
この陽子は、たとえ、外から静止しているように見えたとしても、静止質量エネルギー、すなわち、(内部)運動エネルギーに相当する「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」を持つ。
すなわち、この外から見て静止している陽子の内部では、例えば、アップクォークu×2とダウンクォークd×1が運動を続けており── それらのクォークの(外部)運動エネルギーは、それらのクォーク子が持っている「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」の一部に相当している。 つまり、陽子は、外から静止しているように見えたとしても、その内部で、クォークなどが運動を続けているからこそ、静止質量エネルギーに相当する“重力子の放出源として働き続ける能力”を持っているのである。
なお、このクォークの(外部)運動エネルギーは、陽子の静止質量エネルギーのすべてではない。
他に、陽子の静止質量エネルギーを担うと考えられるものの1つは、クォークの静止質量エネルギー、すなわち、クォークの(内部)運動エネルギーに相当する「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」である。外から静止しているように見えるクォークの内部では、3つのプレオン∴(→結果2)が運動を続けており── それらのプレオン∴(→結果2)の(外部)運動エネルギーが、その大きさに相当する「質量エネルギー、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”」の一部に相当していることとなる。 すなわち、クォークは、外から静止しているように見えたとしても、その内部で、クォークを構成するプレオン∴が運動を続けているからこそ、静止質量エネルギーに相当する“重力子の放出源として働き続ける能力”を持っているのである。
※陽子の静止質量エネルギーを担うと考えられてきた「グルーオンの集積したひも」の質量(→結果2)の実体とは、クォークの外部運動エネルギーに他ならないと考えられる。クォークどうしを結びつける「グルーオンの集積したひも」(→結果2)は、運動しないと考えられるからである。(→結果2)
いずれにせよ、質量エネルギーのすべてが、最終的に、運動エネルギー(外部運動エネルギー)に、帰着することがわかる。
|
陽子の質量エネルギー
|
|
陽子の運動エネルギー
(=陽子の外部運動エネルギー(external kinetic energy))
|
陽子の静止質量エネルギー
(=陽子の内部運動エネルギー(internal kinetic energy))
|
|
クォークの外部運動エネルギー
※「グルーオンの集積したひも」の質量
と考えられてきたものに相当
|
クォークの静止質量エネルギー
(=クォークの内部運動エネルギー)
|
|
|
クォークを構成する
プレオン∴(→結果2)の外部運動エネルギー
|
※やはり、いずれも、(外部)運動エネルギーに帰着することがわかる。
※外部運動エネルギーか内部運動エネルギーかの違いは、見方によってかわる「相対的な違い」に過ぎないことがわかる。 |
このように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において、質量の起源、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」の起源の実体が、運動エネルギーに集約できるのである。
|
1. 運動エネルギー(ふつうの意味での運動エネルギー)
(=外部運動エネルギー(external kinetic energy))
2. 静止質量エネルギー
(=内部運動エネルギー(internal kinetic energy))
|
→運動エネルギー
|
※以後、こういった、すべての質量エネルギーの起源が運動エネルギーであることを明確に示すための表記としては、「運動エネルギー(内部&外部)」を使うこととする。
つまり、あらゆる素粒子の質量(重力子の放出源として働き続ける能力)は、その運動エネルギー(内部&外部)が持つ、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4面体”から“4角形”(縮みきったバネ)へ変形する、持続的な能力に相当することになる。
以上より、“物体が質量を持っている”ということについて、次の結論を得られる。
結論1.2.1 あらゆる物体が“質量を持っている”ことの起源は、その物体を構成する素粒子(「プレオン∴以上に複雑な素粒子」)が持っている、運動エネルギー(内部&外部)である。
※「LP光子の集積したひも」は、プレオン∴の運動エネルギーに応じた長さをキープし、プレオン∴の運動範囲を束縛する。
そして、「LP光子の集積したひも」(→結果2)は、運動せず、質量を持たないと考えられる。
このように、“LP光子の集積したひも”自体は質量を持たないことは、電子やクォークの静止質量エネルギー(=構成するプレオン∴の運動エネルギー)の値や、(構成する電子や反電子ニュートリノ、クォーク…の静止質量よりはるかに大きな)ウィークボソン(→結果2)の質量の値と調和している。
なぜなら、この場合、「LP光子の集積したひも」の長さをキープするところの、プレオン∴や、(例えば、W−ボソンの両端にある)電子や反電子ニュートリノの運動エネルギーだけが質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”を担っていると考えられるからである。
一方、「グルーオンの集積したひも」(→結果2)は、クォークの運動エネルギーに応じた長さをキープし、クォークの運動範囲を束縛する。
そして、「グルーオンの集積したひも」自体は、運動しないと考えられる。
したがって、『グルーオンの集積したひもの質量』と考えられてきたものは、クォークの外部運動エネルギーに由来するものであり、『裸のクォークの質量』と考えられてきたものは、クォークの静止質量に相当すると考えるとつじつまが合う。
そのことは、グルーオンが質量0であることとも調和している。
(すなわち、『1つ1つのグルーオンの質量が0であるはずなのに、グルーオンの集積したひもが質量を持つ』と説明するのは、矛盾しているということになる)
さらに、このように『「グルーオンの集積したひも」には質量がなくて、「グルーオンの集積したひも」の長さをキープするところのクォークの運動エネルギーだけが質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”を担っている』という説明は、『「LP光子の集積したひも」には質量がなくて、「LP光子の集積したひも」の長さをキープするところのプレオン∴や電子や反電子ニュートリノやクォーク… の運動エネルギーだけが質量、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”を担っている』という説明と、相似になっている。
以上の説明は、次の記述についての見直しを迫っていることを意味している。
『クォークの質量
このように閉じ込められてはいても、クォークやグルーオンの性質はいろいろわかりつつある。しかし前述したように、クォークの質量は直接に測定することはできない。ハドロンの質量などを考える場合には、クォークの質量にグルーオンの集積したひもの質量を加えたものが実質的な意味をもつ有効質量であると考えられる』
(『物質の究極を探る 現代の統一理論』 p.22 (1序論──素粒子像のあゆみ(大槻昭一郎)) 日本物理学会編 培風館 下線は、筆者による)
|
『
|
|
|
|
〜“mq”はハドロンに閉じ込められたクォークの有効質量(正確には構成質量)、
mqはいわば裸のクォークの質量(正確にはカレント質量)の、それぞれの推定値である』
|
(『物質の究極を探る 現代の統一理論』 p.11の表とその説明から一部抜粋 下線は筆者による)
|
※次のような対応関係にあると考えるとすっきりすると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
『クォークの質量』
『裸のクォークの質量(正確にはカレント質量)』 |
→クォークの静止質量 |
『グルーオンの集積したひもの質量を加えたもの』
『ハドロンに閉じ込められたクォークの有効質量(正確には構成質量)』 |
→クォークの静止質量
+クォークの外部運動エネルギー
|
|
このことは、例えば、『アップクォークとダウンクォークの質量エネルギーがそれぞれ3MeV、6MeVである』と同列に、『電子の質量エネルギーが0.5MeVである』と説明されるときの電子の質量エネルギーとは、「電子の静止質量」に他ならないことと調和していると思われる。
|
ある質量M[kg]を持つ物体は、すなわち、太陽も、地球も、人も、自動車も、電車も、自転車も、鉛筆も、本もノートも、消しゴムも、リンゴも、宇宙船も、ブラックホールも… 含めて、たとえ外から静止しているように見えたとしても、少なくとも、それらを構成する素粒子(「プレオン∴以上に複雑な素粒子」)が、外から見えないレベルで運動を続けているおかげで、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力』を持っていることになる。
すなわち、あらゆる静止質量が持っている『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力』に相当するエネルギー、すなわち、静止質量エネルギーmc2の実体は、素粒子(「プレオン∴以上に複雑な素粒子」)が持つ運動エネルギー(外部&内部)の総和なのだ。
※なお、マクロレベルで、物体が等速運動している場合は、上記の「静止質量に伴うあらゆる方向へ放出される重力子」に加えて、「その運動方向にのみに放出される重力子」も生じる。(→《重力子の働きと慣性》) また、マクロレベルで、加速運動すると、重力波が放出される。(→《連星系パルサーと重力波について》)
※なお、重力波は、「放出される重力子数の変化」として創発するものである。(→《連星系パルサーと重力波について》)
したがって、たとえ、下記の理由で、“重力波”が放出されていなくとも、“重力子”が放出され続けていることに問題はない。
|
『もし力学系が終始、球対称の構造をもち続けるならば、これは重力波を放出できない』
p.170 アインシュタイン選集2
|
つまり、球形であろうとどんな形であろうと関係なく、マクロレベルで見た運動状態にかかわらず(加速していても、等速運動していても、静止していても…)、太陽も、地球も、人も、自動車も、電車も、自転車も、鉛筆も、本もノートも、消しゴムも、リンゴも、宇宙船も、ブラックホールも… 含めて、質量を持つ物体は、常に重力子を放出し続けていることになる。
この性質は、後に述べていくように、重力と加速度が等価であるためにも、ニュートンの万有引力の法則に従った形で重力が働くためにも、必要不可欠である。
質量は、より厳密には、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を、ある一定の頻度で放出する源として働き続ける能力』と定義できる。
ある質量m[kg]は、果たして、どのくらいの頻度で、重力子を放出するであろうか?
それを考えるために、当量質量ME[kg]を導入する。
当量質量ME[kg]とは、下図のように、厚さ2LP[m]の球殻の中に必ず1つ「“4角形”(縮みきったバネ)」が存在するような頻度で、重力子を放出する質量のことである。
※中心の当量質量ME[kg]の物体から、“4角形”(縮みきったバネ)(紺色の台形で示した)が放出されている様子が図示されている。
厳密には“4角形”(縮みきったバネ)=重力子ではないが、1つの“4角形”(縮みきったバネ)には、必ず1つの重力子が対応しているので、“4角形”(縮みきったバネ)の数=重力子の数として話を進めることができる。
※図では、便宜上、平面上に、『“同心円”(厚さ2LP[m]』)の集まりを示し、この平面上にすべての“4角形”(縮みきったバネ)を示しているが── 実際は、『“同心球殻”(厚さ2LP[m])』の集まりが存在しており、3D空間のあらゆる方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されていると考えられる。 (また、1つ1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、当然、光速で無限遠方まで進んでいく)
以下、これと同様の図は、『“同心球殻”(厚さ2LP[m])』の集まり、そして、『3D空間のあらゆる方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出されていること』を意味しているものとする。
※「3D空間のあらゆる方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されている」ことは、本文で触れた「素スピノール3つで決定論的カオス」によるランダムな運動の作用もおおいに関連していると考えられる。 この作用が、ミクロの素粒子による、ランダムな方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出を可能にし、“長時間で均等にならされる”という“エルゴード性”が生じていると考えれば、つじつまが合う。
|
この当量質量ME[kg]が「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出するとは頻度とは、1秒間にc/2LP[個]の頻度、すなわち、c/2LP[個/s]に他ならない。
c/2LP[個/s]の頻度であればこそ、上図のように厚さ2LP[m]の球殻の中に必ず1つ「“4角形”(縮みきったバネ)」が存在することができるのである。
一方、重力子質量MG[kg](=プランク質量MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))が、単位時間(1秒)あたりに「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する頻度をnG [個/s]としてみよう。
具体的に、重力子質量MG[kg](=プランク質量MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))は、1秒間に何個の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出するのであろうか?(=上述のnGの値は何であろうか?)
これがわかれば、あらゆる物体について、その全質量がわかるだけで、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」のおおよその放出頻度が計算できることになる。
(m [kg]の質量は、「m/MG」個の、重力子質量MG[kg]を内在させていることになるので── 全質量m[kg]が単位時間当たりに放出する重力子の数Nmは、 Nm=nGm/MG[個/s]と計算で求まる)
思考実験をしてみよう。
静止重力子質量MG[kg](=プランク質量MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))をもつ物体が1つあるとする。
この静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の、(内部)運動エネルギーを担うものが、2LP×2LPサイズ(原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ)の1つの粒子であると想定してみよう。
すると、この「静止重力子質量MG[kg]は、外から静止しているように見えても、2LP×2LPサイズ(原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ)の1つの粒子が、重力子エネルギーEG=MGc2[J]に相当する運動エネルギーK[J]を持って、運動を続けており、ある頻度nG[個/s]で重力子を放出し続けていることになる。
この2LP×2LPサイズの粒子の運動エネルギーK[J]が、(原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にして、1つの重力子を放出させるのに必要なエネルギーでもある)重力子エネルギーEGEG=MGc2[J]に、ぴったり等しい結果、何が起こるであろうか?
もし、エネルギー保存則が成立するのならば、この(内部)運動エネルギーK[J]は、たった1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にして、1つの重力子を放出させるだけで、0になってしまう(消滅していまう)はずである。
しかし、実際は、そうはならない。
質量とは、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力』だからである。
すなわち、静止重力子質量MG[kg]が持っている、重力子エネルギーEG(=MGc2)[J]に相当する(内部)運動エネルギーKは、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力』だからである。
したがって、たとえ、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にして、1つの重力子を放出したとしても、(内部)運動エネルギーK[J]を持ち続けるはずである。
以上より、まず、重要な次の結論が導かれる。
結論1.2.2 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、すべて、エネルギー非保存の所産に他ならない。
※この結論に対して、「(物理学の根幹を担う)エネルギー保存則に反するから問題ではないのか?」という疑問が湧くのも当然であろう。
しかし、ここに問題はない。
なぜなら、この「結論1.2.2 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、すべて、エネルギー非保存の所産に他ならない」が、“ネーター定理”と調和しているからである。
|
結論1.2.2が、“ネーター定理”と調和している理由を以下の通りである。
そもそも、エネルギー保存則は、時空が連続であることを前提にしたときに成立するものだからである。
すなわち、対称性と保存則を結びつける“ネーターの定理”は、「時空が連続で微分可能である」という前提の上で保存則が成立することを示すものだからである。
|
『ネーターの定理は、系に連続的な対称性がある場合はそれに対応する保存則が存在する、と述べる定理である』
『ネーターの定理は、ラグラジアンの変数に対する連続的な変換が系の対称性になっている場合、対称性の下での作用の変分がある保存量の時間についての全微分になるという定理である』
(ウィキペディア『ネーターの定理』 下線は、筆者による)
『ネーターの定理は、物理法則の連続的対称性とそれにともなう保存則との関係を表している』
(p.123 『対称性 レーダーマンが語る量子から宇宙まで』 下線は、筆者による)
|
つまり、ネーターの定理は── 「 例えば、保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)は、実は、連続な時空(連続な時空の対称性(不変性))を前提として成立しているものに過ぎない」ということも教えてくれている定理でもあったのだ。
(ネーター定理の“対偶”をとれば── 「保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立たないのであれば、時空が不連続である」ということを教えてくれる定理である、ということもわかる)
したがって、たとえ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」においてエネルギー保存則が成立していなくとも、少なくとも「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」にとっては、時空が不連続である(時空が原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和である)ので、ここに問題がないことになるのである。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ネーターの定理と調和しているのである。
(※厳密には、ネーター定理の“逆”や“裏”、「保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立てば、時空は連続である」「時空が不連続であれは、保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立たない」は、論理上、正しいとは限らない。 しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、それらも正しいことを示しているようである。
すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」にとって時空が不連続である(時空が原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和である)ので、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」において、エネルギー保存則が成立しないとも言えそうである。
便宜上、以下そのように考えて説明していくこととする。 (詳細な検討は、今後の課題である))
一方、“ニュートリノ”が考えられていなかった時代についての、次のような記述も、おおいに参考になる。
|
『ベータ崩壊でのこの失われたエネルギーと運動量は、物理学者にとって長年の大きな謎であった。量子力学の創始者の一人であるニールス・ボーアは、この現象を説明するために、エネルギーと運動量の保存はその有効性に限界があって、ベータ崩壊の過程はこれらの保存則が実際に破られる最初の例を示してるのだという仮説を唱えた。 〜
ボーアの提案は、衝撃的な結果をもたらす可能性をはらんでいた。ボーアの仮説が正しいとすれば、ネーターの定理によって、ベータ崩壊に対してはなぜか空間と時間における連続的並進不変性と言う対称性が保たれないことになる。そうすると、空間と時間はある種の結晶格子を形成していることになり、結局は連続的並進対称性が空間(および時間)において成り立たないことになってしまう。これはまったく驚くべき発見である──われわれは宇宙に無限に広がる離散的なチェス盤に似たものになってしまうのだ。』
(p.135-136 『対称性 レーダーマンが語る量子から宇宙まで』 下線は筆者による)
|
この記述からも、「エネルギー&運動量の保存則が破られているなら、ネーターの定理によって、時空(空間と時間)が連続でない(離散的である)ことになる」と考えられることが読みとれる。 (この記述は、上記の“対偶”と同等である)
この記述は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)にとって、やはり都合が良い。
なぜなら、『空間と時間はある種の結晶格子を形成』『われわれは宇宙に無限に広がる離散的なチェス盤に似たもの』という説明は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による時空の説明、すなわち、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和であるという説明と、とても調和しているからである。
※なお、これまで不確定性原理(不確定性関係)によって説明されてきた、「エネルギー保存則を破って生じる仮想粒子の生成&消滅」も、“不連続な時空”にもとづく、エネルギー非保存の所産として(ネーターの定理と調和したものして)説明できると思われる。
すなわち、量子力学では、仮想粒子が、エネルギー保存則を破って生じる理由を“ハイゼンベルクの不確定性原理”にもとづいて説明してきているが── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、「時空が不連続&エネルギー保存則が成立しないこと」にもとづいて、説明できると考えられる。
詳細な検討は、今後の課題である。
※ここで見直さなければならないことの本質は、実は、「エネルギー保存則が成立する」という前提より、「時空が連続である」という前提の方であると思われる。
このことは、そもそも、アインシュタインの一般相対性理論においても、ニュートン力学においても、エネルギー保存則が成立するのは、ともに時空が連続であること(微分可能である)を前提にしているからこそに過ぎないことに気づかせてくれる。
また、このことは、アインシュタインの一般相対性理論も、ニュートン力学も、時空をなめらか(連続)とみなすような粗視化による所産であるという意味で、近似の理論に過ぎないということにも気づかせてくれる。
したがって、ここに物理学の根幹をゆるがす部分があるとすれば、その本質は、「時空が不連続であること」、すなわち、「時空が素スピノールから創発するということ」であると考えられる。
※なお、以上の説明は、次の記述とも関連すると思われる。
|
『目下のところ、物理学者は対称性に惚れ込んでおり、連続的な基礎物理学像しか探求していない』
(p.50 『万物理論』 J.D.パロー 林一訳 みすず書房 下線は、筆者による)
|
この記述からも、不連続な時空を前提とする“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が取り組んでいる内容は、これまで、物理学が十分に探求してこなかったことであることがわかる。
しかし、だからといって、時空が不連続であることを前提とする“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、連続な時空を前提とする「アインシュタインの一般相対性理論や、ニュートン力学といった、既存の物理学」を否定するものではなく、これらを包含するものである。
そして、より深いレベルの階層から、どのようなしくみで成功し(自然(nature)と調和し)、どのようなしくみでうまくいっていないか(自然(nature)から乖離しているのか)を説明するものである。
例えば、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、一般相対性理論における、エネルギーに関する問題を解消する。
(→《一般相対性理論とエネルギー保存則について》)
※なお、重力子や光子にとって時空は不連続であっても、素スピノールにとって時空は連続であると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
『結論1.2.2 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、すべて、エネルギー非保存の所産に他ならない。』を踏まえた上で──
この「静止重力子質量MG[kg]の物体の(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」の運動エネルギーK[J]が、(原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)にして、1つの重力子を放出させるのに必要なエネルギーである)重力子エネルギーEG(=MGc2)[J]に、ぴったり等しい結果、何が起こるかを考えよう。
そもそも、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)は、「質量を与えるヒッグス場」にも相当するもので、本来、様々な素粒子に対して、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”を持つと考えられるのだった。
したがって、「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするために必要なエネルギー重力子エネルギーEG(=MGc2)[J]に等しい運動エネルギーK[J]を持ち続ける粒子」は、“光速c[m/s]を失わせるはずの抵抗作用”に、やすやすと打ち勝ち続けながら、重力子の放出を続けることになるだろう。
その結果、“光速c[m/s]を失わせる抵抗作用”がほとんど働いていない状態に等しくなるので、この「(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」は、ほぼ光速で運動すると考えられる。
よって、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J])を持ち続ける「(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」がどうなるかについて、次のような仮説を立てた。
仮説1.2.2 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を、“4角形”(縮みきったバネ)に変形して1つの重力子を放出させるのに必要なエネルギーEG(=MGc2)[J]と等しい大きさの運動エネルギーK[J]を持ち続ける「(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」は、ほぼ光速c[m/s]の速さで軌道運動(移動)を続けることができる。
※時空が不連続であるという前提から導かれる、この仮説は、光速に近づくためには、「無限大の運動エネルギー」は不要であり、1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)あたり、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J]を与えるだけで十分であること意味していると考えられる。(詳細な検討は、今後の課題である)
このことは、アインシュタインの特殊相対性理論における数式「E= mc2/(1−(v/c)2)1/2」により、光速に近づくためには、無限の大きさの運動エネルギーが必要であると説明されてきたことは、実は、時空がどこまでも連続であるという前提に基づく説明に過ぎなかったことということを示していると思われる。
(また、この性質は、運動エネルギーK[J]が、この重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])を越えさえすれば、光速cを越えうることを意味している。 これは、光速を越えて実現したかもしれない「ビッグバウンス〜インフレーション」の現象を支えるしくみなのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である)
一方、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の配置について、次の仮説を立てることができる。
仮説1.2.3 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”は、あらゆる方向に、ほぼ2プランク長(2LP[m])の幅を占めながら、びっしりと存在している。
なぜなら、原始ヒッグス場ユニットを構成する、それぞれの素スピノールは、一辺が1プランク長(1LP)の立方体の空間の中心にあると考えられるからである(→考察4 ループ量子重力理論)。
※それぞれの素スピノールは、一辺が1プランク長(1LP[m])の立方体の空間の中心にある。その結果、あらゆる方向に、ほぼ2プランク長(2LP[m])の幅を占めながら、びっしりと存在していると考えられる。 厳密な配置についての詳細な検討は、今後の課題である。
|
この仮説により、上記で述べた、ほぼ光速で進む「(静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の)(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」は、2LP[m]移動するごとに1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”と衝突することになるので、1秒間に(ほぼc=3×108[m]進む間に)ほぼc/2LP[回]の頻度で、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”と衝突できると考えられる。
しかも、この「(静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の)(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」”は、“重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J])を持ち続けるので、衝突するたびに、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させ、速やかに、1つの重力子を放出させることを繰り返すことができる。
以上より、「(静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の)(内部)運動エネルギーを担う粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度nG は、nG ≒c/2LP[回/s]ということになる。
(nG の値は、c/2LP[回/s]≒(3×108m/s)/(2×1.616×10-35m)」≒9.28×1042[個/s]と非常に大きいものであることがわかる)
よって、この「(静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の)(内部)運動エネルギーを担う1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度nG は、まさに、当量質量ME[kg]の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度に、ほぼ等しかったことになる。
ところで、この静止重力子質量MG[kg]を担うものは、“重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J])を持ち続ける「1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」でなければならないということはない。
例えば、陽子がおよそ1019個ほど集合したものでも担うことができる。
そして、静止重力子質量MG[kg]を担うものが何であろうとも、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度nG は、変わらないはずである。
例えば、この『“重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J])を持ち続ける「1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」』が、仮に、『陽子がおよそ1019個ほど集合してできた物体』に変わったとしても「1秒間にほぼc/2LP[回]」の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することに変わりないはずである。
つまり、一般に、重力子質量MG[kg](=プランク質量/2π=MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))は、構成物が何であろうとも、1秒間にほぼc/2LP[回]の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することになる。
以上より、次の結論に至る。
結論1.2.2 “重力子質量MG[kg]”を持つ物質は、当量質量ME[kg]とほぼ等しい作用をし、ほぼc/2LP[回/s]の頻度で、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出し続ける。
※質量、すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力』は保存されているので、“一定の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出させ続ける”ことができる。
このことは、やはり、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、エネルギーの非保存の所産であることを意味している。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、不連続な時空を前提にしているので、ネーターの定理と調和しており、問題ないことはすでにのべた。
詳細は、《一般相対性理論とエネルギー保存則について》にて説明する。 なお、このことは、次の項目とも関連する。
《連星系パルサー》《重力場、エネルギー、質量、非線形性、電磁場の線形性との比較》《アインシュタイン方程式(アインシュタインの“重力場の方程式”)》)
※なお、静止重力子質量MG[kg]を持つ物体の(内部)運動エネルギーを担うものの構成数が増えるほど、それぞれの構成物は、光速に比べてより遅くなっても構わないことになると考えられる。
|
例えば、構成物が2つになった場合、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさは、MGc2[J]/2で済む。
例えば、構成物が3つになった場合、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさは、MGc2[J]/3で済む。
例えば、構成物が100個になった場合、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさは、MGc2[J]/100で済む。
…
と言うように、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさが、構成数の数に反比例することによって、トータルの重力子の放出頻度は、c/2LP[回/s〕を維持できるであろう。そして、それぞれの質量(すなわち、内部運動エネルギー)の大きさが小さくなるほど、その移動速度は遅くなると考えられる。(単峻な反比例ではなさそうである。詳細な検討は、今後の課題である)。
|
※静止重力子質量MG[kg]の物体に、外部からエネルギーを加えて、外部運動エネルギーを持たせることを考えた場合、この物体の軌道運動の速さv〔m/s〕が光速c〔m/s〕に近づくためには、「無限大の運動エネルギー」は不要であり、1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)あたり、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J]を与えるだけで十分であることは、この投入すべきエネルギーの大きさが、静止重力子質量(=MG[kg])を構成する「粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)の数」によって変わることを意味していると考えられる。
|
時空が不連続であることを前提とすれば、構成する「1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」あたりに、外部から加えるエネルギーが、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に達すれば、最終的には(剛体から、完全流体に変わることによって)、ほぼ光速c〔m/s〕の等速運動に至ると考えられる。
そして、その加えるべきエネルギーの大きさの総計は、構成する「1つの粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)」の数に比例すると考えられる。
この粒子(2LP[m]×2LP[m]サイズ)の構成数が、1つなら、EG[J](=MGc2[J])、10個なら、10EG[J](=MGc2[J])、n個なら、nEG[J](=MGc2[J])とうように変わると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
nGの値、nG=c/2LP[回/s]≒(3×108m/s)/(2×1.616×10-35m)」≒9.28×1042[個/s]を用いると、あらゆる物体について、その全質量がわかるだけで、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」のおおよその放出頻度が計算できることになる。
すなわち、一般に、m [kg]の質量は、「Nm=m/MG」個の、重力子質量MG[kg](=プランク質量MP/2π(≒約0.32×10-8[kg]))を内在させていることになるので(m[kg]=Nm×MG[kg](Nm=m/MG)と書き直せるので)、質量m[kg]が単位時間当たりの重力子の放出回数NG[回/s]は、
NG=nGNm=nGm/MG[回/s]=mc/2MGLP≒2.896×1051×m[回/s]で計算できる。
当然、電子やクォーク、陽子や中性子などの、重力子の放出頻度も、簡単な比例計算によって、計算で求めることができる。
|
電子ニュートリノ
|
電子
|
クォーク
|
陽子、中性子
|
W−ボソン
|
プランク質量MP
(≒2×10-8[kg])
|
重力子質量MG
=MP/2π(≒約0.32×10-8[kg])
|
|
静止質量エネルギーを
エネルギー[eV]で表記
|
<約2.5eV
|
約0.5MeV
(=0.0005GeV)
|
約3MeV
(アップクォーク)
約6MeV
(ダウンクォーク)
|
約1GeV
|
約80GeV
|
プランクエネルギーEP
=1.2209×1019[GeV]
|
重力子エネルギー
EG[J]
=0.194×1019
[GeV]
|
|
「重力子&“4角形”
(縮みきったバネ)」
を放出する頻度[回/s]
|
<約1.2×1016
[回/s]
|
約2.4×1021
[回/s]
|
(アップクォーク)
約1.4×1022
[回/s]
(ダウンクォーク)
約2.8×1022
[回/s]
|
約4.78×1024
[回/s]
|
約3.8×1026
[回/s]
|
“c/2LP”×2π
=約5.83×1043
[回/s]
|
“c/2LP”
≒9.28×1042
[個/s]
|
※1GeVあたりの、重力子の放出頻度が、(c/2LP)[回/s]×2π/EG[1/GeV]≒4.78×1024[回/(s・GeV)]であるとして、他の値を計算した。
※なお、nG=c/2LP[回/s]は、ちょうど、重力子の振動数c/2LP[回/s]にも等しいことになる。
※大きな質量M[kg]を持っている静止した物体が、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出している様子を、単純化したモデルで、次のように図示することができる。
※質量、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」が一定であるので、同心円上にある重力子の数は、同数となっている。
上図は、ある一定頻度で新たに生じている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の分布を理想化&簡略化して示していることになる。
すなわち、実際は、「重力子の放出源として働き続ける能力」が、一定であることを満たしつつ、「2LP[m]間隔の“球殻”」のそれぞれに上にほぼ同数ずつ、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、ランダムな位置に、分布しているのである。 その様子は、おおよそ下図のように示せる。
※便宜上、各球殻の“切り口(平面)”上において、8つずつ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が存在しているように図示しているが、実際には、3次元の球殻の中に同数ずつ存在していると考えられる。
|
|
|
《重力の実体像》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、重力(場)は、原始ヒッグス場(=「原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))から創発するものの1である。 すなわち、重力(場)は、原始ヒッグス場を構成する原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として創発するものである。
そのことを、以下で説明する。
ある質量を持つ物体は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が存在する方向へ進むためには、わざわざ、“4角形”(縮みきったバネ)に変形しながら、苦労して進む必要がある一方── すでに“4角形”(縮みきったバネ)となっている方向へ進む際には、その手間が省けるので、相対的に、楽に進むことが可能になる。
原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))
の“4面体”があると──

|
= |
運動の際、抵抗を受ける
(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間がかかる)
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」
(PHU由来)があると──

|
= |
(運動の際、抵抗を受けないので)
その方向に運動しやすい
(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省ける)
|
つまり、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の総和は、本来、物質の運動に対して抵抗する働きを持っていると考えられる。
この「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の総和が、物体の運動に対して与える抵抗」のことを、単純に“原始ヒッグス場抵抗”と呼ぶこととする。
すると、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が多いほど(=“4角形”(縮みきったバネ)の存在数の密度が小さいほど)、“原始ヒッグス場抵抗”は、大きくなり、物体はその中を進みにくくなり── 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が少ないほど(=“4角形”(縮みきったバネ)の存在数の密度が大きいほど)、 “原始ヒッグス場抵抗”は、小さくなり、物体はその中を進みやすくなることになる。
|
“4面体”(PHU由来)
|
多い
|
少ない
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」
(PHU由来)
|
少ない
|
多い
|
|
“原始ヒッグス場抵抗”
=物体が進む際に受ける抵抗
|
大きい
|
小さい
|
|
運動する物体
|
進みにくい |
進みやすい |
例えば、質量M[kg]を持つ物体Pが、次の図のように、一定の頻度で重力子を放出しているとする。
※やはり、簡略化した、便宜上の図である。
質量、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」が一定であるので、同心円上にある重力子の数は、同数となっている。
※実際は、「重力子の放出源として働き続ける能力」が一定であるという条件を満たしつつ、「2LP[m]間隔の“球殻”」のそれぞれに上にほぼ同数ずつ、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、ランダムな位置に分布している。
したがって、 厳密に見れば、切り口(平面)上の同心円であれば、外へ遠ざかるほど、“4角形”(縮みきったバネ)の密度は、減っているはずである。
つまり、上図は、本来3次元で示されるべき内容を、2次元で示している、便宜
上のものである、ということになる。 |
例えば、上図のようなO1、O2、O3の位置を決めると── ある周囲の質量を持つ物体Qは、O1の位置にあるときが一番、物体Pの方向へ運動しやすく(移動しやすく)、O3の位置にあるときが一番物体Pの方向へ運動しにくい(移動しにくい)と考えられる。
すなわち、周囲に存在する物体Qは、この物体Pに、より近い場所にあるほど、物体Pに近づく方向に運動しやすく(移動しやすく)なると考えられる。
なぜなら、周囲に存在する物体Qは、この物体Pに、より近い場所にあるほど──
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の空間に占める割合(存在数の密度)が高い場所にいる(=抵抗をもたらす“4面体”の密度が小さい場所にいる)ことになり、「“原始ヒッグス場抵抗”がより減少している」ことになるからである。
つまり、中心の物体Pに近いほど、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の空間に占める割合(存在数の密度)が、より高くなり、その方向へ運動する際に要する手間(=“原始ヒッグス場抵抗”)が省かれていることになるので── その方向へ進みやすくなると考えられるのである。
まさに、このたりに“重力の実体像”にせまるヒントがあると考えられる。
すなわち、物体は、ただただ、「“原始ヒッグス場抵抗の小さい」方に動いているだけであり── その過程が、“重力という力によって引っぱられている”と観察されているに過ぎないと考えられるのである。
つまり、重力は、「“原始ヒッグス場抵抗”が小さい方へと物体が運動しやすいという傾向」によって、そこに存在しているかのように見える力に過ぎないと考えられるのである。
以上をもとに、重力[N]を、理論的に計算で求めてみよう。
“4角形”(縮みきったバネ)の1つ1つは、重力子エネルギーEG[J]を蓄えているとする。
(この時点では、 上記で述べたように、EG=EP/2π[J]であることは、まだ不明であるとする。 なお、EP[J]は、プランクエネルギーである)
まず、質量M[kg]の中心から、r=2nLP[m]離れた所にある、“厚さ2LP[m]の球殻”を考える。(nは整数、LP[m]はプランク距離(1LP≒1.616×10-35[m])
|
ある質量Mを持つ物体を中心とする、半径 r の“厚さ2LP[m]の球殻”を考える。
※図の“4角形”は、半径rの“厚さ2LP[m]の球殻”の中にある「“4角形”(縮みきったバネ)」(PUH由来)を表す。
|
この、「厚さ2プランク距離(2LP[m])」には、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”や“4角形”(縮みきったバネ)のサイズ、重力子の波長、に相当するという意味がある。
下図のように、便宜上、“半径r=2nLP[m]の厚さ2LP[m]の球殻”の定義は、『半径r=2nLP[m]の球面の「LP[m]だけ外側の球面とLP[m]だけ内側の球面の間にある厚さ2LP[m]の球殻」』とする。
|
※話を簡単にするために、「1つの“4角形”(縮みきったバネ)は、すべて、ちょうど厚さに収まっている」と考えることとする。
(厳密には、“厚さ2LPの球殻”は、想像上の球殻にすぎいので、1つの“4角形”(縮みきったバネ)が、2つの球殻に“またがって”存在することも考えられ── 本来は、“凸凹なデジタル球面”を滑らかな球面として、近似的にとらえているにすぎないことになる。 詳細な検討は、今後の課題である)
※なお、たとえ“1cm”でも、r=2nLPの中のnの値は、n≒0.01[m]/2×(1.616×10-35)[m]≒0.309×1033と非常に大きなものとなる。
|
質量が重力子質量MG[kg]なら、ほぼ、2LPの球殻の1つ1つに、1ずつの「“4角形”(縮みきったバネ)」が存在するようなペースで、重力子が放出されると考えられるのであった。
※中心の重力子質量MG[kg]の物体からは、厚さ2LPの球殻に、最低1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が存在するような頻度で、重力子が放出される。
※便宜上、“同心円”の集まりとして図示してあるが、実際は、厚さ2LPの“同心球殻”の集まりに相当する。
そして、実際は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」がほぼ1つずつ、それぞれの「厚さ2LPの“球殻”」のランダムな位置に、分布している。
やはり、上図も、厳密に見れば、「本来3次元で示されるべき内容を、2次元で示している、便宜上のものである」ということになる。(以下、同様である) |
よって、もし、質量がM[kg]ならば、2LP[m]の球殻に、「NM=M/MG[個]」の「“4角形”(縮みきったバネ)」が存在するようなペースで、重力子が放出されていることになる。
すなわち、質量、すなわち、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出し続ける放出源として働き続ける能力』が一定であるならば、「質量M[kg]の中心から r=2nLP[m]離れた場所の、厚さ2LP[m]の球殻の中にある“4角形”(縮みきったバネ)の数NM[個]」は、nの大きさ(rの大きさ)に関わらず、どこでも一定であることになる。
よって、下の左図のような、すべての重力子が「厚さ2LP[m]の球殻」の中に収まっている場合を考えると── それぞれの厚さ2LP[m]の球殻は、nに関わらず、NM[個]の“4角形”(縮みきったバネ)を持ち、その1つ1つがEG[J]のエネルギーを持ち続けているので、それぞれの「厚さ2LP[m]の球殻」がもつエネルギーは、NMEG(=MEG/MG=Mc2[J])と一定の値に決まることになる。
|
※上図の“4角形”は、重力子質量MGから放出された重力子によって生じている、「“4角形”(縮みきったバネ)」を表す。
重力子が、すべて“厚さ2LP[m]の球殻”の中に収まっている存在している場合の図である。
※それぞれの“4角形”(縮みきったバネ)が持つエネルギーは、EG[J]である。
|
|
|
|
※上図は、すべての重力子が2つの原始ヒッグス場ユニットに、“またがって”存在している場合を示している。
この場合、2つの原始ヒッグス場ユニットにまたがってデュアル共転回が起きている。 なお、デュアル共転回している間、2つの原始ヒッグス場ユニットが持つエネルギーの和は、一定のEG[J]であることはすでに述べた。
|
|
一方、上の右図のように、すべての重力子が、2つの球殻にまたがって共転回している状態になっている場合も考えてみよう。
すると、その共転回している時間(T=LP/c[s])の間は、下図のようにエネルギーが経過し、それぞれの“4面体”が蓄えるエネルギーは一定ではないので──
“時間平均のエネルギー”を考える必要がある。 その“時間平均エネルギー”の値は、単純に最大エネルギー振幅を1/2すれば求まるので、EG/2[J]となる。 そして、一方、各球殻に存在する数は、(1つの球殻に収まっている場合に比べて、2つの球殻にまたがっている場合には)2倍となる。 したがって、「エネルギーの平均値がEG/2[J]である“4面体”の変形」は、各球殻に“2NM[個]”存在することになり── 結局は、それぞれの球殻が持つエネルギーの時間平均は、(EG/2)×2NM=NMEG[J] として、(上の左図の場合と同じ式で)計算できることになる。
したがって、実際は、1つの重力子が「1つの球殻内で、1つの“4角形”(縮みきったバネ)を作っている状態であるもの」と1つの重力子が「2つの球殻にまたがって、2つのヒッグス場ユニット(PHU)を変形させている状態のもの」が混在していたとしても──
計算上、「質量M[kg]の中心から r=2nLP[m]離れた場所の、厚さ2LP[m]の球殻が持つエネルギー」は、時間平均として、単純に、NMEG[J]と求まることになる。
|
(例えば、ある瞬間に、NM個のうちa個のみが“球殻のペアにまたがっている”というような系で、ある球殻が持つエネルギーの時間平均は、(NM−a)EG+2aEG/2=NMEG[J]と単純に計算できる。(2aとなるのは、ある球殻とその外側の球殻のペアと、ある球殻と内側の球殻のペアの、2種類のペアをカウントするために、aを2倍するからである) なお、時間が経過すると、NM個のうち(NM−a)個のみが“球殻のペアにまたがっている”というような系に変化することも考えられる。この場合も、ある球殻が持つエネルギーの時間平均は、aEG+2(NM−a)EG/2=NMEG[J]と単純に計算できる。より厳密な計算についての、詳細な検討は、今後の課題である)
|
以上が時間平均として計算したことをふまえた上で、さらに、半径r=2nLP[m]の厚さ2LP[m]の球殻が持つエネルギーの空間的な平均(空間平均)を計算してみよう。
r=2nLP[m]離れた所にある厚さ2LP[m]の球殻の中心の球面の全面積(すなわち、半径r=2nLP[m]の球面積)は、4πr2=16πn2LP2[m2]であり── そのうち、“4角形”(縮みきったバネ)が(NM−a)[個]、2つにまたがっている重力子によって変形している“4面体”がa[個]とすると、それらが占める面積は、それぞれ、およそ、(2LP)2×(NM−a)[m2]、(2LP)2×(2a)[m2]である。 全く変形していない“4面体”も、考量すると、「厚さ2LP[m]の球殻が蓄えるエネルギーの“時間&空間”平均」E平均[J]は、次のように計算できる。
「厚さ2LP[m]の球殻が蓄えるエネルギーの“時間&空間”平均」E平均
={(2LP)2×(NM−a)×(EG)+(2LP)2×2a×(EG/2)+ (4πr2−(2LP)2NM)×0}/4πr2
=NMEG/4πn2
=(M/MG)×EG/4πn2
=Mc2/4πn2[J] (EG=MGc2[J]を使った)
このことは、質量M[kg]の物体が、r=2nLP[m]離れた場所の“厚さ2LP[m]の球殻”という場所に、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として蓄えるエネルギーの“時間&空間”平均は、nの値だけで決まることを示している。
(しかも、アインシュタインの式E=mc2[J]の右辺に相当するものがこの式に登場している。
このことは、質量すなわち、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を一定の頻度で放出する源として働き続ける能力』が持っているエネルギーの大きさが、まさに、Mc2[J]であることを示唆している。 そして、しかも、Mc2[J]と同じ大きさのエネルギーを、質量M[kg]を取り巻く、“厚さ2LP[m]の球殻”に相当する時空のそれぞれが、等しく持つことを示している。 このことは、やはり、エネルギー保存則が明らかに大きく破れていることを意味している。 このことは、(不連続な時空を前提としているので)“ネーターの定理”と調和しており、問題ないのだった)
そして、しかも大小関係は、NMEG/(4π・12) > NMEG/(4π・22) > EG/(4π・32) > … > EG/4π(n−1)2 > EG/4πn2
となっている。
すなわち、このことは、質量のM[kg]の物体に中心に近づくほど、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として時空(球殻)に蓄えるエネルギー[J]』が大きくなり、同時に“原始ヒッグス場抵抗”がより減少することを意味し、このことは、重力場が持っていると予想される性質とぴったり合致する。
ここで、質量M[kg]の仮想質点を考えてみよう。
すると、次の仮説に至ることは、きわめて自然なこととなる。
仮説1.3.1 「厚さ2LP[m]の球殻が持つエネルギーの“時間&空間”平均」の値、E平均=NMEG/4πn2[J](=Mc2/4πn2[J]) を、(NMEG/4π)(1/12+1/22+1/32+…+1/(n−1)2)+1/n2)というように足しあげたものは、質量M[kg]の仮想質点が生む、r=2nLP[m]の地点での重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)に相当するものになる。
正しければ、重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)は、中心から遠ざかるにつれて階段状に増加する、下図のようなものとして、示すことができるようになる。
※質量M[kg]の仮想質点から2LP[m]だけ遠ざかるごとに、(r=2nLP[m]の距離の地点で)n番目の“2LP[m]幅の球殻”が持つエネルギーが、(その中心から遠ざかる方向に)時空の中に新たに追加されることになる。
そして、その総和が、重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)に相当していることが読みとれる。
※以上の説明は、“量子化された重力ポテンシャルエネルギー”について考える際のよりどころにもなる。
重力ポテンシャルエネルギーを数式でどのように表されるか”についての詳細な説明は、下記で行なう。(→《量子化された重力、重力場の計算》)
※このように、仮想質点を考え、n=1から足し上げることには、(質点を前提とする)ニュートン力学に対応するものである。
|
この図より、それぞれの「厚さ2LPの球殻が蓄えるエネルギー」は、それぞれの場所での「重力ポテンシャルエネルギーの変化量」に他ならないことがわかる。
今、求めたいのは、力(=重力)[N]である。
その力(=重力)[N]とは、単位距離当たりの「重力ポテンシャルエネルギーの変化量」に他ならないのだった。
時空が連続で微分可能な世界であれば、連続である「重力ポテンシャルエネルギー」を単純に「質点からの距離」で微分すれば、重力を計算できる。
しかし、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、時空を不連続なもの(飛び飛びの値をとるもの)として考えているので、この(質点からの距離による)微分は使えない。
すなわち、これは、単位距離当たりの「重力ポテンシャルエネルギー」の変化量を求めるための分母として“無限小(dx)”を使えないと言うことである。
それでは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、“無限小(dx)”の代わりに、“単位距離当たり”の「重力ポテンシャルエネルギー」の変化量を計算するための分母として、何を使えば良いだろうか?
それが、まさに“2LP”に他ならない。
| ※この図より、“無限小(dx)”の代わりに“2LP”を使えば、単位距離当たりの「重力ポテンシャルエネルギー」の変化量、すなわち、重力を“勾配”として計算できることが読みとれる。 |
つまり、厚さ“2LP”ごとの重力ポテンシャルエネルギーの変化量を、単に“2LP”で割れば、勾配として、重力[N]を計算で求められることになる。
※そのことは、例えば、仮に、下図に示されるような、ある仮想的な質量(重力子の放出源)が、nによらず、重力[N]の大きさが一定の重力場を生じるような場合── “2LP”でエネルギーの変化量を割れば、“勾配”として、重力が求まることからも理解できる。
“重力ポテンシャルエネルギーの変化量”とは、まさに、「厚さ2LP[m]の球殻が持つエネルギーの“時間&空間”平均の値」E平均=NMEG/4πn2に他ならないのであった。
よって、r=2nLP[m]の地点での単位距離当たりの変化量(=「単位距離当たりの“原始ヒッグス場抵抗”の減少量」)すなわち、重力[N]は、r=2nLP の厚さ2LPの球殻が持つエネルギーの平均値E平均=NMEG/4πn2[J]を、単純に、2LP[m]で割れば求まることになる。
※厚さ2LP[m]球殻が持つ平均エネルギーを、単純に、2LP[m]で割ることによって“勾配”が計算できる。
この重力ポテンシャルエネルギーの勾配(上図のピンクの斜線の傾き)を、(“電位勾配”に習って)“重位勾配”と呼ぶことにする。
この“重位勾配”が、この場所での“重力”にほかならない。 |
つまり、質量M[kg]物体が、r=2nLP[m]の地点で生じる重力[N]は、 F=(NMEG/4πn2)×(1/2LP) [N] となる。
なお、この段階では、まだ、何(どれほどの質量)に対する重力[N]が求まっているのかが明確でない。
次に、そのことを考えてみよう。
質量M[kg]物体は、重力子質量MG[kg]のNM個分に相当するのだった。
よって、もし、質量M[kg]が、重力子質量MG[kg]の1個分に相当する質量なら、重力[N]は、単純に F=(EG/4πn2)×(1/2LP) [N] となることになる。
このことは、先の「質量M[kg]物体が、r=2nLP[m]の地点で生じる重力[N]は、 F=(NMEG/4πn2)×(1/2LP) [N] となる」の厳密な意味は、
「重力子質量MG[kg]のNM個分に相当するの質量M[kg]物体が、r=2nLP[m]の地点で、重力子質量MG[kg]の1個分に相当する質量を持つ物体に対して、生じる重力[N]は、 F=(NMEG/4πn2)×(1/2LP) [N] となる」であることを示唆していると考えられる。
つまり、より一般的に言えば、「質量M[kg]の物体(重力子質量MG[kg]のNM個分に相当)と、質量m[kg]の物体(重力子質量MG[kg]のNm個分に相当)の間に働く重力は、
F=(NMEG/4πn2)×(1/2LP)×Nm [N] で計算できる」ということになる。
なお、この定式化により、式の中の分子のNM[個]&Nm[個]という単位と、分母のn2[個]2という単位が、ちょうど約分できるので、単位がぴったり合致していることがわかる。
以上より、次の結論がえられる。
結論1.3 質量M[kg]が、質量m[kg]の間に生じる重力[N]は、次の式で計算できる。
|
重力[N]
=(NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N]
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N]
|
※ NM[個]=M/M G[個]、 Nm[個]=m/M G[個]、E G=M Gc 2
これが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による、ニュートンの万有引力の法則の定式化である。
これをニュートンの万有引力の法則の“EMOES表記”と呼ぶこととする。
※なお、この“EMOES表記”は、ニュートンの重力定数Gを全く用いずに導かれたものである。
したがって、ここには、重力定数Gの理論的に導出法の1つが示されていることになると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
ここで、このニュートンの万有引力の法則の“EMOES表記” F=(NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)と、ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2とを比較してみよう。
ニュートンの万有引力F[N]は、次のように変形できる。
ニュートンの万有引力F[N]
=GMm/r2
=(2πc3LP2/h)×(Mm/4LP2n2) (GMm/r2に「重力定数G=2πc3LP2/h」と、「r=2nLP」を代入した結果である。
なお、重力定数G=2πc3LP2/hは、プランク定数h、光速c、重力定数Gを使った、プランク距離を求める式
「LP=(hG/2πc3)1/2」を変形して求まる)
=(2πcLP/h)×c2LP×(Mm/4LP2n2) (プランク質量MP=h/2πcLP」が代入できるように式を変形、
なお、「プランク質量MP=プランクエネルギーEP/c2=(hc/2πLP)×1/c2=h/2πcLP」である)
=(MP)×Mc2×(m/4LPn2) (分母と分子のLPを約分、「Mc2=EGNM」を代入できるように式を変形)
=(NMEG)×(1/2n2)×(1/2LP)×m/(1/MP)
=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×m/(1/(MP/2π))[N] (EMOESによる重力F=(NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)と比較しやすいように変形)
ここで、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による重力と、係数を比較してみよう。
ニュートンの万有引力F[N](=ニュートン理論の重力[N])
=(Mc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×m/(1/(MP/2π))[N]
=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×m/(1/(MP/2π))[N] |
EMOESによる重力F[N]
=(NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N]
=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(m/MG)
|
すると、この比較により、重力子質量が、MG=MP/2π であると一意に確定させることができる。
よって、すでに上の説明で導いた次の結論に至ることができる。
結論1.1.2 重力子エネルギーEG[J]は、プランクエネルギーEP[J]を2πで割った値、すなわち、EP/2π[J]に等しい。
まとめて表記すると次のようになる。
|
“ニュートンの万有引力F”
=GMm/r2[N]
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)×(m/MG)[N]
=(NMEG/4πn2)×(1/2LP)×Nm[N]
=NM{hc/(2π)2LP}×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nm[N]
=ニュートンの万有引力の法則の“EMOES”表記
|
※r=2nLpの地点での重力である。
※NMEGは、厚さ2LPの球殻が持つエネルギー、1/4πn2は、そのエネルギーの時間的&空間的な平均を求めるための項。 1/2LPは、“重位勾配”を求めるための項である。
※EGは、1つの重力子が持つエネルギーであり、EG=Ep/2πである。
※「NM=M/MG=2πM/Mp」、「Nm=m/MG=2πm/Mp」である。
それぞれの値は、それぞれの質量が、厚さ2LPの球殻の中に存在させることのできる重力子の数に相当する。
※なお、ニュートンの万有引力Fから計算される重力場[N/kg]が、
(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(1/MG)[N/kg]であることも理解できる。
すなわち、ここに、質量m[kg]を掛け合わせれば、ぴったり、ニュートンの万有引力F[N](=ニュートン理論の重力[N])となる。
※ニュートンの万有引力の法則の“EMOES表記”は
=(NMEG/4πn2)×(1/2LP)×Nm[N]
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)×(m/MG)[N]
=(c2LP/2πMG)×Mm/r2[N]
と変形できる。 よって、重力定数Gが、「G=c2LP/2πMG」と理論的に導かれたことになる。
これと、もう1つの理論的に導出された「重力定数G=2πc3LP2/h」、および「プランクエネルギーEP=(hc5/2πG)1/2 =hc/2πLP 」を比較することによって、EG=EP/2πが導かれたことになる。
この「G=c2LP/2πMG」の方が、(ニュートンの万有引力の法則の“EMOES表記”との関連がつかみやすいので)「重力定数G」の意味を、より説明しやすいと思われる。
詳細な検討は、今後の課題である。
※ニュートンの万有引力の法則の中にも、実は、すでに、アインシュタインの式“E=mc2”が内在していたことになる。
NMEG=Mc2の関係式は、アインシュタインの式“E=mc2”の意味を教えてくれる式であると言うこともできると思われる。
すなわち、“mc2”には、「重力子エネルギーEG[J]のNm[個]分に相当するエネルギー」という意味がある。
(このことからも、例えば、ふつうの電磁波を構成する光子のエネルギーhνは、“mc2”と全く関係ないということがわかる)
しかも、Mc2には、「“厚さ2LPの球殻”がぞれぞれに持つエネルギー」という意味もある。
(詳細は、下記→《重力場、エネルギー、質量》)
|
このニュートンの万有引力F[N]の“EMOES表記”は、「どのようにして重力が生じているか」を説明していると言える。
すなわち、質量(「重力子の放出源として働き続ける能力」)によって放出され続ける「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」によって、質量の周囲に、重力ポテンシャルエネルギーの“勾配”(それは、“原始ヒッグス場抵抗”の勾配にも等しい)がもさらされ、周囲の質量が、その“勾配”にしたがって運動することが、「重力が生じている」と見なされていることを示しているのである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で求めた重力F= (NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N]は、ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2[N]を量子化したものに相当する。
(すなわち、このニュートンの万有引力F[N]の“EMOES表記”には、連続で微分可能な“距離r”が消失しており、プランク距離Lp[m]とそのn倍(整数倍)だけが長さと関連した量として含まれるようになっている)
このことは、(時空が連続であることを前提としている)ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2[N]と、(時空が不連続であることを前提としている)“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で求めた重力= (NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N] が、nが大きい極限で、一致することを意味する。
言わば、それは“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で求めた重力= (NMEG/4πn2)×(1/2LP)×(Nm)[N]の(nが大きくなったときの)近似式が、ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2[N]であったということに他ならない。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の重力理論は、マクロのスケールから、プランクスケールというミクロのレベルまで適用できるものであり、少なくとも、ニュートンの万有引力の法則(ニュートンの重力理論)を包含するものであるといえる。
※(時空が連続であることを前提としている)もう一つの重力理論、アインシュタインの重力場の理論(アインシュタイン方程式)については、のちほど下記で説明する。
(→《アインシュタイン方程式(アインシュタインの“重力場の方程式”)》 )
ニュートンは、重力の働き方を数式化することに見事に成功したが、「どのようにして、重力が生じるか?」「重力の正体とは、何か?」については、何も述べていないに等しい説明に終始した。
以上の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明は、これらの基礎的な問いに、答えの1つを提示していると思われる。
一方、アインシュタインは、重力を“時空の曲がり”の所産であると見事に説明したしたが、そもそも「どのようにして、“時空の曲がり”が生じるか?」「“時空の曲がり”の正体とは何か?」については、ほとんど何も述べていないに等しい説明に終始した。 この“時空の曲がり”については、項をあらためて説明する。(→《“時空の曲がり”&重力場の実体像》)
《「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の働きと運動の第1法則(慣性の法則)および運動の第2法則(F=ma)》
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和は、重力場を創発するだけではなく、“慣性の法則”や“F=ma”が成立する世界も創発する。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「どのようなしくみで(なぜ)“慣性”や“F=ma”が成立するのか」を説明できるのである。
“慣性の法則”や“F=ma”は、ニュートン力学の前提であり、おそらく、これまで誰も(かつての私自身も含め)「このニュートン力学の前提、運動の第1法則(慣性の法則)および第2法則(F=ma)が、どのようなしくみで(なぜ)成立するのか」を説明することの必要性を、ほとんど感じてこなかったと思われる。
しかし、よく考えてみると、例えば、質量を与える(光速を失わせる)“ヒッグス場”が真空を満たしていると考えられている中で、“慣性”(等速運動)が実現していることは、(矛盾している言えるほど)不思議なことである。したがって、どのようなしくみで(なぜ)“慣性”(等速運動)が実現するのかについて説明することには、重要な意味があるのである。
これまで前提とするしかなかった「 “慣性の法則”や“F=ma”」を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「より深いレベルの階層」から説明しようとするのである。
ニュートン力学が前提とする法則とは、次のようなものであった。
|
『物体に外から力が働かないか、働いてもつり合っていれば、静止している物体はいつまでも静止を続け、運動している物体は、そのまま等速直線運動を続ける。 これを慣性の法則 または 運動の第一法則という』
( p.6 『基礎シリーズ 物理学入門』)
|
※なお、以下では、「太陽の周囲を公転する地球」を含めて応用範囲を広げるために、等速 直線運動の代わりに等速運動として説明を進めることとする。
|
『物体の外から力が働くと、力の向きに加速度を生じる。この加速度の大きさは力の大きさに比例し、物体の質量に反比例する。これを 運動の法則 または 運動の第二法則 という。』
( p.6 『基礎シリーズ 物理学入門』)
|
静止している物体は、力を加えない限り、ずっと静止し続ける。(ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)の一部である)
静止している物体に力を加えると、物体は加速運動することによって(ニュートン力学の第2法則 F=maに従いながら)、(外部)運動エネルギーを増す。
その加速の際、静止していた物体は、もとのままに静止し続けようとして抵抗する。 その“抵抗、動かしにくさ…”に相当する“慣性力”の大きさが、“F=ma”の大きさに等しい。
そして、すでに加速しおえて、等速運動をしている物体は、(摩擦力も含めて、運動方向に一切の)力を加えない限り、ずっと等速運動を続ける。(ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)の一部である)
等速運動をしている物体に(運動方向にマイナスの)力を加えると、物体は減速運動することによって(ニュートン力学の第2法則 F=maに従いながら)、(外部)運動エネルギーを減らす。
その減速の際は、等速運動していた物体は、もとの等速運動を続けようとして抵抗する。 その“抵抗、勢い、はずみ、止めづらさ…”に相当する“慣性力”の大きさが、“F=ma”の大きさ等しい。
※アインシュタインの特殊相対性理論によれば、ある速さv〔m/s〕で運動している物体は、(外部)運動エネルギーを獲得していると同時に── 質量エネルギー(=静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))が増加している。 (質量エネルギーは、(m0c2(1−v2/c2)-1/2で計算できる。v[m/s]<<光速c[m/s]の場合は、質量エネルギーは、(m0c2(1−v2/c2)-1/2≒(m0c2+m0v2/2と近似的に求まるのだった)
一方、現代物理学(標準模型)によると、時空は、(質量を与える)ヒッグス場に占められているのだった。
この(質量を与える)ヒッグス場は、いわば(光速を失わせる)抵抗として働くのであり、よく考えてみると、この抵抗の中で、(ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)が示すような)等速運動を実現できるというのは、やはり、とても不思議なことである。
この(ニュートンを含めて、これまで誰もが前提とするしかなかった)「慣性の法則」がどのようなしくみで(なぜ)生ずるのかを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、説明できる。
まずは、そのことについて以下に示す。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると──
静止した物体を動かし始める際の“抵抗、動かしにくさ…”という意味の“慣性(力)”が生じるのは、まさに、原始ヒッグス場の中を物体が進んでいく際、わざわざ各原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”を、“4角形”(縮みきったバネ)まで変形させる必要があるからである。
そして、“4角形”(縮みきったバネ)となった原始ヒッグス場ユニット(PHU)からは、速やかに、「重力子」が(物体の運動方向と同じ方向に)放出される。
(当然、放出された1つ1つの「重力子」は、「重力子&新たな“4角形”(縮みきったバネ)」として、次々と原始ヒッグス場ユニット(PHU)を伝わりながら、原始ヒッグス場の上を、光速で飛び去っていくだろう)
まさにこの過程は、「物体の加速運動によって“重力子の放出源として働き続ける能力がアップしている”こと」、すなわち、「(外部)運動エネルギーを増すことによって、質量エネルギーを増す」ことに相当すると考えられる。
したがって、加速運動によって(外部)運動エネルギーが増加するしくみを、運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出数の増加として説明することができる。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、この「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力を増加させる過程が── 静止している物体がそのまま静止し続けようとする“抵抗、動かしにくさ…”という意味の慣性(力)の実体であると同時に、(外部)運動エネルギーの増加の実体、すなわち、特殊相対性理論が説明するところの質量エネルギー(=静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(外部&内部))の増加の実体なのである。
以下、速さv[m/s]<<光速c[m/s]とする。
例えば、静止している質量m[kg]の物体に、ある一定の大きさの力F[N]を加えながら、距離 l[m]だけ移動したとする。
この物体に外から加えられるエネルギー(仕事)は、力×距離で、Fl[J]となる。
その結果、この質量m[kg]の物体の速さが v[m/s]になった場合、この物体は、mv2/2[J]の(外部)運動エネルギーを持つ。
(これは、当然ニュートン力学の前提から求められることであるが── ニュートン力学の前提がない中で、(外部)運動エネルギーがmv2/2[J]に至ることを、別の方法で導くこともできることを後に示す)
なお、この、mv2/2[J]の(外部)運動エネルギーは、上記で述べたように、新たな“重力子の放出源として働き続ける能力”(=新たに、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形できる能力)、すなわち、新たな質量エネルギーの一部に他ならない。
この「新たな“重力子の放出源として働き続ける能力”である(外部)運動エネルギー[J]」は、「外から加えられたエネルギー(仕事)Fl[J]」に等しいはずである。
つまり、 Fl = mv2/2 [J]となる。
ここで、Fl = mv2/2 [J]の両辺を、単純に時間で微分してみよう。
すると、力Fは、一定なので、 Fdl/dt=mvdv/dt(Fv=mva) すなわち、F=maが導かれる。
つまり、 Fl = mv2/2[J]の関係は、便宜上は(時空が連続であると見なした(粗視化した)場合は)、F=ma すなわち、ニュートンの運動の第2法則と同等の関係であることがわかる。
※そもそも「一定の加速度a」という概念は、時空が連続で、微分可能という前提にした概念である。 すなわち、厳密にば(プンクスケールで見ると)「一定の加速度」は、実在していない可能性があるのである。 したがって、上記のように「F=ma(ニュートンの運動の第2法則)」を導くために、便宜上、時空が連続であると見なした(粗視化した)上で、近似計算として微分することは、不可避であると思われる。 厳密には(プランクスケールで見れば) Fl = mv2/2[J]の関係のみが、自然(nature)と調和していることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
このことは、もし、「(速さv[m/s]<<光速c[m/s]で)(外部)運動エネルギーKが、mv2/2[J]であること」と「ある一定の大きさの力F[N]を加えたときの、加速度a [m/s2]が一定であると」を“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって導きさえすれば、それは同時に、ニュートンの運動の第2法則(F=ma)が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって導かれたことになることを意味する。
(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、K= mv2/2[J]と導かれることは、後ほど示す)
さて、いったん加速しおえた物体は、力を加えるのを止めても、(摩擦を含めて運動方向に一切の力が働かない場合)そのまま等速運動を続ける。 このように等速運動を続けるということは、一定の(外部)運動エネルギーを持ち続けるということ、すなわち、質量エネルギー(=静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))を保ち続けると言うことであり、それは、「重力子の放出源として働き続ける能力」を保ち続けることに他ならない。
この『「重力子の放出源として働き続ける能力」をそのまま保ち続ける』という性質が、まさに、(質量を与える)ヒッグス場の中での等速運動を可能にさせるカギであると考えられる。
よって、次の仮説を立てた。
仮説1.5.1 (外部)運動エネルギーを持って等速運動をしている物体は、(静止質量エネルギー(内部運動エネルギー)による重力子の放出源として働き続ける能力の他に)
重力子の(物体の運動方向と同じ方向への)放出源として働き続ける能力を保ち続けている。
この物体は、まさに、その物体の運動方向と同じ方向に放出し続ける「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が生んでいる“流れるプール”のような効果によって、
等速運動を実現している。
正しければ、等速運動をしている物体は、『物体の運動方向と同じ方向に生じ続ける「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和』のおかげで、たとえ新たな力を加えなくても、物体の進行方向に存在する、新たな「原始ヒッグス場の“4面体”」を、次から次へと「“4角形”(縮みきったバネ)」に変形させ続けることができる── というしくみを持っていることになる。
そのようなことを可能にする“しくみ”とは、どのようなものであろうか?
簡単のため、((内部)運動エネルギーによって、重力子を放出し続けている)静止した粒子○が多数集合して構成される、静止した剛体(トータルの静止質量は、m0[kg])を考える。
※なお、“剛体”というのは、特殊相対性理論の前提でもあった。
|
『ここから述べる理論は、すべての電気力学と同様に剛体の運動学にもとづいている。なぜならば、この種の理論のいうところの主張は、剛体(座標系)、時計、およびいろいろの電磁過程のあいだの関係について触れるものだからである』
(p.20 『アインシュタイン選集1』 [A1]運動している物体の電気力学について アインシュタイン)
|
この「静止した粒子○が多数集合して構成される、静止した剛体」を、例えば、下図のような単純化したモデルを使って表記できる。
オレンジ色の○が、個々の粒子である。
※静止質量m0[kg]の剛体によって“4角形”(縮みきったバネ)が放出されている様子が、dモデル化されて示されている。
当然、実際は、3Dのランダムな方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されている。
※静止質量エネルギー(=(内部)運動エネルギー)による重力子の放出が放射状であることは、
下に述べる剛体の(外部)運動エネルギーによる重力子の放出が、運動方向のみに平行であることと対照的である。
|
この「静止した粒子○が多数集合して構成される、静止した剛体」が、たとえ外から静止しているように見えても、(剛体の中に多数存在する)各粒子が持っている、静止質量エネルギー(=(内部)運動エネルギー)から「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出され続けているので── その総和として、この剛体の静止質量エネルギーm0c2[J]に相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出され続けることになる。
そして、この静止質量m0[kg] の剛体が、(光速よりずっと小さい)速さv[m/s]で、ある方向に等速運動をすることを考えてみよう。
すると、もとからあった静止質量エネルギーm0c2[J](=静止した粒子が持つ(内部)運動エネルギーの総和) によって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放射状に放出されるのに加え、(外部)運動エネルギーによって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が運動方向に限定して放出されることになる。
(外部)運動エネルギーの値は、(特殊相対性理論によれば、「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」となるはずであるが)速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合なので、ニュートン力学の場合にほぼ一致し、m0v2/2[J]となるはずである。
そもそも、この(外部)運動エネルギーは、なぜ、m0v2/2[J]なのか?
(当然、F=maの前提があれば導き出せるが、今は、その前提なしの状態で説明しようとしている。
そして、もし、(外部)運動エネルギーがm0v2/2になることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明できさえすれば、運動の第2法則(F=ma)が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明できたことになるのだった)
この問題は、「なぜ、速さv〔m/s〕の運動によって蓄えられる(外部)運動エネルギーが、単純にm0v2[J]ではなく、その1/2である、m0v2/2[J]になるのであろうか?」という問題に置き換えることができる。
なぜなら、先に述べたように、静止重力子質量MG[kg]の物体の(内部)運動エネルギーを担うものが「1つの粒子(2LP×2LPサイズ)」の場合は、MGc2[J]に相当する運動エネルギーK[J]を持ち、その移動の速さv〔m/s〕は、ほとんど光速c〔m/s〕になると考えられるからである。 すなわち、この理屈で考えると、質量m0が速さv〔m/s〕の運動によって蓄えられる運動エネルギーは、単純にm0v2[J]になりそうなものだからである。
そこで、このことに関して、次の仮説を立てた。
仮説1.5.2 ある物体が「単独の粒子(2LP×2LPサイズ)」で構成されていて、その(外部)運動エネルギーがm0v2[J]となるならば、その「単独の粒子」が複数集まって、うまく構成された剛体が持つ(外部)運動エネルギーはm0v2/2[J]となる。
※なお、この仮説1.5.2は、(剛体ではなく)質点のみを前提とする系では、考えることができないものである。
ニュートン力学で、(剛体ではなく)質点を前提とするのに(外部)運動エネルギーがm0v2/2[J]となることが導かれたのは、あくまで、ニュートン力学がF=maの前提を持っていたからに他ならない。
※この仮説は、もし、(光速に比べて低速で運動する)物体の運動エネルギーがmv2/2[J]の式で示されるのならば、その物体は、剛体であり、内部構造を持つことを示唆している。
よって、例えば、(光速に比べて低速で運動する)電子の運動エネルギーは、mv2/2[J〕で示されているので、(光速に比べて低速で運動する)電子が剛体と見なせるのみならず、電子は内部構造を持つことになると考えられる。 (→結果2)
(下図のような方向に)速さv〔m/s〕の運動によって蓄えられる(外部)運動エネルギーが、単独の場合にm0v2[J]となるような、「粒子(2LP×2LPサイズ)」を考える。
|
|
|
※この「粒子(2LP×2LPサイズ)」は、単独の場合、m0v2に相当する(外部)運動エネルギーを持つ。
※m0v2に相当する頻度で「(光速で進む)重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が運動方向にのみ放出される。 |
次に、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数集まって、うまく構成されてできた剛体として、等速運動する場合を考えて見よう。
すると、仮説1.5.2から、この剛体は、Σm粒子[kg]の質量をもって一緒に速さv〔m/s〕で運動する場合、(外部)運動エネルギーが“1/2になる”しくみが創発するはずであると予想される。
すなわち、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数集まって、うまく構成されてできた剛体は、(Σm粒子[kg])v2/2の(外部)運動エネルギーに相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出すると予想されるのだ。
それは、「粒子(2LP×2LPサイズ)」が単独で運動する場合、m0v2の(外部)運動エネルギーに相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出するのと対照的である。
|
「粒子(2LP×2LPサイズ)」
|
単独の場合
|
複数集まって、うまく構成
されてできた剛体の場合
|
|
(外部)運動エネルギー
|
m0v2
|
(Σm0[kg])v2/2
|
どのようなしくみで(なぜ)、(外部)運動エネルギーが“1/2になるのだろうか?
例えば、下図のような方向に、速さv〔m/s〕で等速運動している剛体、しかも、その運動方向に平行に「粒子(2LP×2LPサイズ)」が9つ連なっている剛体を考えてみよう。
|
|
|
※剛体の下に示した図は、剛体を構成する各粒子がそれぞれ、単位時間当たり同一の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出している様子を示している。
緑でかこった部分の面積は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が後方から前方へ向けて通過することによって、各粒子が、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”をわざわざ変形する手間が免除される効果の大きさに比例する。
例えば、一番、右はじの粒子は、最も多くの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が後方から前方へ向けて通過してくるので、わざわざ“4面体”を変形する手間がもっとも小さい。
逆に、左ばじの粒子は、後ろから通過してくる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が皆無なので、わざわざ“4面体”を変形する手間がもっとも大きい。
そのことは、仮に、下図のように「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の頻度が増したとしても、本質的に同様なことが言える。
|
つまり、この図から、“「粒子(2LP×2LPサイズ)」の各々が同一の頻度で重力子を放出する”と仮定した場合── 放出された「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が前方の粒子におよぼす効果が、剛体の進行方向の前方ほど重複して大きくなり、わざわざ“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にする手間が省かれることが読み取れる。
すなわち、各粒子が同一の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出する場合── 剛体中の位置と、“4面体”を変形する手間が省ける程度、すなわち、単位時間当たりの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の通過数は、下記のようになる。
|
|
|
※剛体の中の位置が、運動方向の先頭に近いほど、各「粒子(2LP×2LPサイズ)」は、わざわざ自分で、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省ける。
一方、運動方向の後方に近いほど、わざわざ自分で、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形しなければならない。 |
以上の説明は、『それぞれの「粒子(2LP×2LPサイズ)」が同一の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出し続けると考えた場合』のものである。
一方、『それぞれの「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、様々な頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出し続けてよい場合』(実際の場合)は、どうなるであろうか?
すなわち、「運動方向に平行に、いくつかの粒子が連なっている剛体」の中のそれぞれの粒子(2LP×2LPサイズ)は、実際には、どのような頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出すると考えられるだろうか?
まず、「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、単独で、(下図のような方向に)速さv〔m/s〕で運動する場合、n0[個/s]の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することを考えてく見よう。 それを図示すると下のようになるとする。
|
|
|
※単独の場合なので、やはり、m0v2に相当する運動エネルギーを持っている。
|
次に、この「粒子(2LP×2LPサイズ)」が複数個(2つ、3つ、5つ、9つ)(運動方向に平行に)1列につながってできた剛体を考えていく。
単独の「粒子(2LP×2LPサイズ)」と比較して、(2つ、3つ、5つ、9つの「粒子(2LP×2LPサイズ)」で構成される)剛体が、(下図のような方向に)速さv〔m/s〕で進む場合、それぞれが、どれくらいの頻度で、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出するかを、下図のように考えることができる。
※左側半分が、各粒子が、同一頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出すると考えた場合、右側半分が、各粒子が、様々な頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出してよい場合、すなわち、実際にどうなるかを示したものである。(左側半分における)緑で囲った部分(数)は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が実際は(免除されて)放出されない部分に相当する。(免除されるのは、剛体の後方から前方へ向けて放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、『剛体の前方の「粒子(2LP×2LPサイズ)」が“4角形”(縮みきったバネ)へわざわざ変形させる手間を省いてくれる効果』を持つからである)
その結果、剛体を構成する各「粒子(2LP×2LPサイズ)」は、実際は、右半分で示したような頻度で、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することになるのである。
剛体が(上図のような方向に)速さv〔m/s〕で等速運動する結果(速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合)、実際の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度が、右半分で示したようになるのである。
このことが、まさに、(外部)運動エネルギーが、(Σm粒子[kg])v2/2になることを説明していることになる。
※なお、次のように、剛体に厚みがあったとしても、同様に考えられることは、明らかである。
|
|
|
単独から、剛体に変化すると、剛体の後方から放出された「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」によって、剛体の前方から放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が、ある程度ずつ、免除されるようになる。
その免除される部分(数)が、上図の“緑の線で囲まれた部分”に相当する。 それは、「単独だったら放出しなればならなかったものが、剛体であるおかげで、実際には放出されない部分(数)」とも言える。 その免除の結果、実際は、右側のような頻度で、剛体を構成する各粒子から「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されると考えられる。
“免除される理由”は、上で説明したように、『剛体の中の位置が、運動方向の先頭に近いほど、各「粒子(2LP×2LPサイズ)」は、わざわざ自分で、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省かれ、運動方向の後方に近いほど、わざわざ自分で、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形しなければならない』という、効果が生まれるからに他ならない。
つまり、ある「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、わざわざ自分で、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省かれるということは、その「粒子(2LP×2LPサイズ)」自身が「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する頻度が(単独のときに比べて)減るということに他ならない。
(逆に、ある「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、わざわざ自分で“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省かれなくなるということは、その「粒子(2LP×2LPサイズ)」自身が「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する頻度が(剛体のときに比べて)増えるということに他ならない)
|
|
|
≒ |
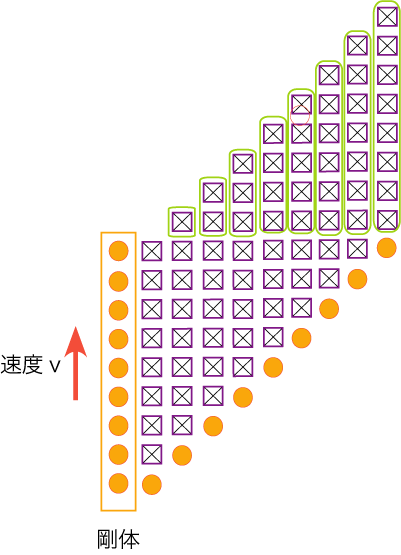 |
※左の図と、右の図(上の図を90度回転させたもの)の中の緑の線で囲ってある部分の大きさ(数)が、ぴったり等しくなる。
ともに、『各「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、わざわざ自分で“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省かれている(免除されている)程度』に相当している。
|
|
緑で囲ってある“免除される部分”は、免除がない場合の、ちょうど1/2であることが読みとれる。
一方、放出頻度の方も、下図のように、ちょうど1/2であることがわかる。
|
|
|
≒ |
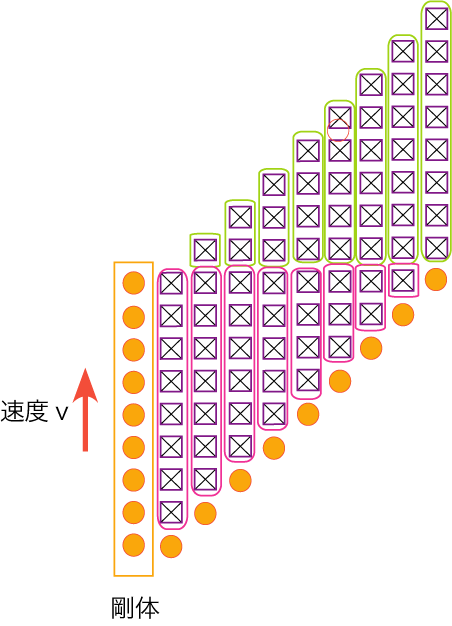 |
※左の図と、右の図(上の図を90度回転させたもの)の中のピンクの線で囲ってある部分は、本質的に、同一のものである。
ともに、『各「粒子(2LP×2LPサイズ)」が、わざわざ自分で“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形する程度』、すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度に相当している。
|
|
剛体として等速運動することにともなって、運動方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出される頻度は、(外部)運動エネルギーという名の質量(重力子の放出源として働き続ける能力)に比例するものである。
したがって、その放出頻度が1/2になるということは、(外部)運動エネルギーが、1/2になるということに他ならない。
以上より、『仮説1.5.2 ある物体が「単独の粒子」で構成されていて、その(外部)運動エネルギーがm0v2[J]となるならば、その「単独の粒子」が複数集まって、うまく構成された剛体が持つ(外部)運動エネルギーはm0v2/2[J]となる』の正しさが説明できたことになる。
ところで、単独の運動で獲得される運動がm0v2となる「粒子(2LP×2LPサイズ)」とは具体的に何か?
それは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、プレオン∴(結果2)に他ならない。
(なぜなら、素スピノールの運動エネルギーは質量を持たないと同時に、プレオン∴の運動エネルギーは単独で質量を持ち、しかも、例えば「プレオン∴3つからなる電子」(結果2)は、その運動エネルギーが(速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合)mev2/2となり、剛体の一種と見なせるからである)
したがって、あらゆる「質量m[kg]を持つ物体(剛体)」は、プレオン∴の総和と見なせる(結果2)以上、あらゆる「質量m[kg]を持つ物体(剛体)」が獲得する運動エネルギーは、(速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合)mv2/2である、ということになる。
以上より、ニュートン力学の第2法則(F=ma)を前提とせずに、(速さv〔m/s〕が光速c〔m/s〕より小さい場合)剛体の(外部)運動エネルギーが、mv2ではなく、mv2/2になることを説明できたことになる。
このことは同時に、Fl=mv2/2[J]が、どのようなしくみで(なぜ)成立するか、つまりは、ニュートン力学の運動の第2法則(F=ma)が、どのようなしくみで(なぜ)成立するかを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明できたことを意味する。
すなわち、ニュートン力学の運動の第2法則(F=ma)は、剛体と、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニットの総和)との相互作用、および、その所産である「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」として説明できるのである。
※なお、速さv〔m/s〕が光速c〔m/s〕に近い場合には、(外部)運動エネルギーが、mv2/2[J]になることはなく、より大きな値になる。
そのことに関しては、次のように説明できる。
剛体の速さv〔m/s〕が光速c〔m/s〕に近づいていくと、運動方向に生じる「重力子の放出源として働く能力」、すなわち、(外部)運動エネルギーと言う名の質量エネルギーは、ある程度「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」に従いながら、m0v2/2よりもはるかに大きい値に近づくと考えられる。
つまり、上記で述べた(外部)運動エネルギーがぴったり1/2になるという関係は消失することになる。
この数式「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」によると、物体が光速cに近づくと、(外部)運動エネルギーが無限大となることが示されるが── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、原始ヒッグス場の抵抗が無限大になることがない以上、運動エネルギーが無限大になることも、ありえないことになる。
なぜなら、原始ヒッグス場抵抗、および、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形するのに必要なエネルギーが、有限のものだからである。
そのことを考慮に入れると、ある静止質量を持つ剛体は、「粒子(2LP×2LPサイズ)」(=プレオン∴)あたりの(外部)運動エネルギーの大きさが、重力子エネルギーEG[J](=MGc2[J])に達すると、それ以上は、(外部)運動エネルギーが増加できなくなると考えられる。 したがって、とりうる(外部)運動エネルギーの最大量は、構成する「粒子(2LP×2LPサイズ)」(=プレオン∴)の総数に比例することになる。
したがって、『「物体の静止質量M[kg]を構成する「粒子(2LP×2LPサイズ)」(=プレオン∴)の総数N∴[個]」×「重力子エネルギーEG[J]」(=MGc2[J])』が、理論上考えられる、剛体の(外部)運動エネルギーの最大値ということになるのである。
この最大値をとるような極限では、「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」の式からも予想されるように、「低速時に剛体が生んだ運動エネルギーが1/2になる効果」を完全に消失させながら、“剛体”は、光速c〔m/s〕に近い速さで運動していることになる。(このときは、“剛体”とはいうものの、実質上は、もはや、“完全流体”に至っていると見なしてよいと考えられる。詳細な検討は、今後の課題である)
特殊相対性理論と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を比較すると次のようになる。
|
特殊相対性理論
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
速さv[m/s]<<光速c[m/s]の場合
の運動エネルギー
|
「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」
≒mv2/2
|
mv2/2
|
|
剛体が光速に近づく場合の運動エネルギー
|
「m0c2(1−v2/c2)-1/2−m0c2」
により、無限大
|
最大値は、N ∴EG[J]
N∴[個]:「物体の静止質量M[kg]を構成する「粒子(2LP×2LPサイズ)」(=プレオン∴)の総数
EG[J]:「重力子エネルギー(=MGc2[J])」
|
|
時空
|
連続
不変
|
不連続
可変
|
|
このことは、特殊相対性理論による、「m0c2(1−(v/c)2)−1/2」の式は、時空が連続であることを前提とした“近似式”に過ぎないことを示している考えられる。 “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせんとすることは、決して、特殊相対性理論を否定することではない。 それは、特殊相対性理論を包含しつつ、これが導く数式の適用範囲を示そうとすることなのである。
※なお、例えば、静止質量Me[kg]の電子を考えてみると次のようになる。
電子は、3つのプレオン∴からなるので(結果2)、電子が、獲得できる最大の(外部)運動エネルギーは、3×ME[J](=3×MGc2[J])となり、静止質量エネルギー、Mec2[J]と合計して、(Me+3MG)c2[J]の質量エネルギー(運動エネルギー(内部&外部))を持つこととなる。
すると、次の時空が連続であることを前提とする式を用いて、その時の電子のおおよその速さve[m/s]を計算すると次のようになる。
Mec2(1−ve2/c2)-1/2=(Me+3MG)c2[J]
式を変形すると、 ve=1−Me2/(Me+3MG)2)=c((Me+3MG)2−Me2)1/2/(Me+3MG)[J]となり、
MG≒2×10-8/2π[kg]に対して Me≒9.11×10-31[kg]はほとんど無視できる値なので、
ve=c×0.9999…[J]という値になる。(詳細な計算は、今後の課題である)
この計算は、少なくとも、加速器で、実際に、電子が光速の99.99…%という速さまで加速されうることと調和していると思われる。
ただし、この「時空が連続であることを前提とする式」によれば、さらに(外部)運動エネルギーを増加させることができるという結論に至る一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、それ以上(外部)運動エネルギーを増加させることはできないという結論に至るという違いがある。 しかも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、この最大値に達したとき、電子は、ほぼ光速に達してると考えられる。
※電子の(外部)運動エネルギーが、mev2/2[J]から、3×ME[J](=3×MGc2[J])に達する過程で、ほぼ剛体の状態から、ほぼ完全流体へと変化すると考えられる。 その変化についての詳細な検討は、今後の課題である。 |
一方のニュートン力学の第1法則(慣性の法則)は、次のようなものである。
|
『物体に外から力が働かないか、働いてもつり合っていれば、静止している物体はいつまでも静止を続け、運動している物体は、そのまま等速直線運動を続ける』
( p.6 『基礎シリーズ 物理学入門』 楠川絢一 高見郎 早川之助 /編集 実教出版)
|
このことは、どのように説明されるか、改めて整理してみよう。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、等速運動は、次のように説明される。
やはり、以下も、速さv〔m/s〕は、光速cに比べて非常に小さいとして考える。
剛体の“(外部)運動エネルギー”は、m0v2/2であり、それは、質量エネルギーの一部であると同時に、その運動方向に生じている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働く能力に他ならない。
そして、その運動方向に放出された「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が、原始ヒッグス場の中を等速運動する際の抵抗を、常に0にしてくれる結果、「流れるプール」のような現象、すなわち、慣性運動(等速運動)が実現する。
つまり、「m0v2/2の大きさを持つ剛体の“(外部)運動エネルギー”」という名の質量、すなわち、運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力こそが、慣性運動(等速運動)を支えていることになる。
すなわち、等速運動が実現している状態とは、つぎのようなものであると言える。
『質量m0の剛体が速さv〔m/s〕で慣性運動している
=m0v2/2の(外部)運動エネルギー(質量エネルギーの一部)に相当する頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を運動方向に放出し続けている
=原始ヒッグス場の中を進む際の、抵抗が0になり続けている。
=一切の力を新たに加えることなく(外から新たなエネルギー投入することなく)、「流れるプール」のような現象が生じ続けている。
=等速運動が実現している』
このような等速運動を実現させるしくみ、すなわち、運動方向に放出され続けている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和によって「流れるプール」のような現象を創発するしくみのことを“時空の流れるプール効果”と呼ぶこととする。
※『地球は、(赤道上で)およそ時速1666kmの速さで自転し、およそ秒速30kmの速さで太陽の回りを公転し、太陽系はおよそ秒速二百何十kmの速さで銀河系の中を進み──』というようなことが成立していることも、“時空の流れるプール効果”の総和によって、実現していることになる。
※いったん、あるスビードを持つに至った── 自動車(や自転車)、スーバーマーケットのカート、カーリングの石… アクセルを踏まなくても、ペダルをこがなくても、手を離しても… ほとんど、そのままの勢いで進み続けることも、この“時空の流れるプール効果”のおかげであることになる。
※なお、地球が太陽の回りを慣性運動で進み続けるのは、“時空の流れるプール効果”のおかげである一方、地球が太陽に引き寄せられ続けるのは、“時空の曲がり”(“重位勾配”、重力場)の効果のおかげであると言える。つまり、いずれも、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和によって創発していることになる。
※静止質量m0[kg]/sの物体が、速さv[m/s](v<<光速c)で等速運動するとき、その(外部)運動エネルギーm0v2/2により、具体的に、どれくらいの重力子を放出するだろうか?
重力子エネルギーEG あたり、(c/2LP)[個/s]の重力子 が放出されるので、(外部)運動エネルギーm0v2/2 あたりでは、単純に、(m0v2/2EG)×(c/2LP) =(m0/MG)×(v2/2c2)×(c/2LP)[個/s]の重力子を放出するであろう。
v2/2c2の値は── かりに速さがv=0.1〔m/s〕だとすると、(0.1)2/2(3×108)2≒0.555×10-19となるので、かなり小さいようにみえる。
しかし、m/MGや(c/2LP)の値がとても大きいので(例えば、1gの物体なら、m/MG=2π×1[g]/(2×10-5[g])=3.14×105となり、c/2LP≒0.927×1043[個/s]である)、 v2/c2の効果が打ち消されて、重力子の放出数は、かなり大きなものとなることができる。
よって、例えば、1gの物体が速さ0.1〔m/s〕で等速運動する場合── 重力子の放出頻度≒3.14×105×0.55×10-19×0.92×1043 ≒1.58×1029[個/s]となる。
このことは、例えば、宇宙空間の中の宇宙船の中で、「一人の人間」でも、「1本のペン」でも等運動(慣性運動)が可能であるという事実を説明するのに、“時空の流れるプール効果”のしくみを用いることは、的外れではないことを示していると思われる。
ニュートン力学の第1法則(慣性の法則)の残り── すなわち、『静止している物体はいつまでも静止を続け』る( p.6 『基礎シリーズ 物理学入門』)は、どのように説明されるだろうか。
ここで、生じる1つの問題は、「静止している物体は、いったい何に対して静止しているのか」ということである。
なぜなら、たとえ、一見、静止しているように見える物体も、『地球は、(赤道上で)およそ時速1666kmの速さで自転し、およそ秒速30kmの速さで太陽の回りを公転し、太陽系はおよそ秒速二百何十kmの速さで銀河系の中を進み──』というように、慣性運動(等速運動…)を続けている可能性があるからである。
したがって、厳密には、完全に静止している物体は、ほとんど実在しないと言えるだろう。
どんなに静止しているように見える物体でも、実は、ほとんどすべてが慣性運動(等速運動)をし続けているということになるだろう。
よって、『静止している物体はいつまでも静止を続け』るように見える現象の多くは、『運動している物体は、そのまま等速運動を続ける』現象として置き換えて説明できることになる。
もし、完全に静止している物体があるとすれば、その一例は、“原始ヒッグス場に対して静止しているもの”ということになるだろう。
(原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)は、場所を移動させないという性質を持つからである)
その“原始ヒッグス場に対して、静止しているもの”が、『物体に外から力が働かないか、力が働いていてもつり合っているかしている限り』、静止し続けるのは、なぜか?
それは、その静止している物体の周囲には、原始ヒッグス場抵抗(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和の所産)が均等に存在するので、運動する理由がなくなるからである。
※こういった説明は、“絶対空間やエーテルに近いもの”を復活させているように思われる。
一方、確かに、マイケルソン-モーレーの実験、アインシュタインの特殊相対性理論は、ニュートンが前提とした絶対空間、そして、エーテルを否定したと言われてきている。
しかし、やはり、ここに問題(矛盾)はない。 後に詳しく説明するが、ここでも、簡単に説明すると次の理由による。
|
1.“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、マイケルソン-モーレーの実験結果や光速不変、アインシュタインの特殊相対性理論を説明できる。(→下記説明)
2.アインシュタインは、一般相対性理論において、結局は、“(新しい)エーテル”が必要不可欠だと主張した。
3.“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の説明は、「双子のパラドックス」を根本的に解消するものである。
…
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ニュートン力学のみならず、マイケルソン-モーレーの実験結果、光速不変やアインシュタインの特殊相対性理論、一般相対性理論を含む観測や理論を、包括的、統合的に説明できる土台なのである。
以上より、ニュートンの運動の第1法則と第2法則が、どのようにして成り立つのかを、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として説明することができたことになる。
このことは、ニュートンの運動の第1法則と第2法則を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)というアプローチによって統合的に説明できることを意味していると思われる。
※“F=maの大きさ”を持つ、慣性力には、2種類ある。
静止している物体の動かしにくさに相当するものと、一度動き始めた物体の止まりにくさに相当するものの2つである。
ある静止している剛体を加速するときにも、慣性運動している剛体を減速するときにも、ともに、力(F=maの大きさを持つ)が必要になる。
静止している物体に力を加えて加速すると── 運動エネルギーが増えると同時に、運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力が増える。
すなわち、加速によって、運動エネルギーが大きくなるということは、「時空の流れるプール効果」が高まることを意味する。
“動かしにくさ”に相当する慣性力とは、ある質量を持つ物体が加速する際に、新たな重力子の“4角形”の放出が追加される過程での“抵抗力”である。
逆に、慣性運動(等速運動)している剛体に力を加えて減速すると── 運動エネルギーが減ると同時に、運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力が減る。
すなわち、減速によって、運動エネルギーが小さくなるということは、「時空の流れるプール効果」が弱まることを意味する。
“止まりにくさ”に相当する慣性力とは、等速運動している物体が、進行方向に放出している「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が生んでいた「時空の流れるプール効果」が解消される過程での“抵抗力”である。
このように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、慣性力による、“動かしにくさ”と“止まりにくさ”の両方を説明できる。
このことは、従来のヒッグス機構による質量獲得の説明においては、ヒッグス場が粘つく“納豆やアメ”に相当する働きをするという比喩があることからわかるように、慣性力の“動かしにくさ”の部分だけに焦点があてられていたようであることと対照的である。 “動かしにくさ”のみでなく、“止まりにくさ(勢いor はずみ)”も、説明できるので── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、従来のヒッグス場による質量獲得の説明を、より改善していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※なお、一般相対性理論で、重力場の源として、「エネルギー運動量テンソル」を導入しているが、これは、「完全流体」を前提として構築されている。
これは、(特殊相対性理論で前提とされた)「剛体」とは、正反対のものである。
このことは、「エネルギー運動量テンソル」の成分にあるものが、「mv2に相当するもののみで、mv2/2に相当する項がない」こととうまく対応していると思われる。 (なお、「エネルギー運動量テンソル」の成分の中で、圧力と解釈されているものは、その単位により、「運動エネルギー密度」と再解釈できる。 つまり、「エネルギー運動量テンソル」の成分は、「静止質量エネルギー密度」と「運動エネルギー密度」であると再解釈でき、これらは、ともに重力子の放出源であり、重力場の源としてふさわしいことがわかる。
詳細は下記にて説明する。→《アインシュタイン方程式(アインシュタインの“重力場の方程式”)》)
※なお、運動の第3法則(作用反作用の法則)についても、説明することも重要だと思われる。
光電効果のように、光子を構成する素スピノールと電子(を構成する素スピノール)が相互作用する場合では、運動の第3法則(作用反作用の法則)は、成立しているように見える。
この場合、「素スピノールどうしの間にも、運動の第3法則(作用反作用の法則)が成立するから」と説明するしかないように思われる。
一方、重力子が関わる世界(「原始ヒッグス場ユニット(PHU)」に「質量を持つ物体(電子、クォーク、プレオン∴(→結果2)…)」が作用するような世界)では成立していないように見える。
例えば、プレオン∴(→結果2)と原始ヒッグス場ユニット(PHU)が衝突して、重力子が放出されるような場合、(原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する)「近づく素スピノールと、遠ざかる素スピノール」が必ずペアとなっており打ち消し合うがために、見かけ上、運動の第3法則(作用反作用の法則)が成立していないように見えるに過ぎないという説明は可能だろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。なお、このことは、少なくとも「エネルギー保存則と運動の第3法則(作用反作用の法則)は別の問題として扱うべきこと」を示しているようにも思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
《等価原理》
アインシュタインの等価原理とは、「加速運動と重力が等価である」という原理である。
自由落下する物体を考える。
自由落下する場合には、(アインシュタインの等価原理により)、「加速運動にともなう慣性力」と重力は、完全に打ち消し合う。
自由落下する物体が、大きな質量を持つ物体に近づくほど重力──“重位勾配”──が大きくなり続ける。
それは、質量を持つ物体に近づくほど、大きな質量を持つ物体が放出する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が生む「厚さ2LPの球殻が蓄えるエネルギーの“時間&空間”平均」が大きくなるからである。
一方、その物質の方へ自由落下する物体は、加速運動をし続けるので、その加速運動に伴い原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変換させて、進行方向に重力子を放出させる頻度を増し続けながら落下する。
(物体が加速する際、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に、わざわざ新たに変形させる過程での抵抗力が、慣性力の実体であるのだった)
そして、大きな質量を持つ物体から放出される重力子による効果(重力)と、(自由落下によって)加速運動しながら進行方向に新たに重力子が放出されるようになる効果(慣性力)は、ピッタリと打ち消し合う形となる。 (これが、アインシュタインの“等価原理”の実体像であると考えられる)
| ※「重力」と「加速運動」が等価なので、「重力」と「加速運動にともなう慣性力」は、大きさが等しく向きが逆となり、100%打ち消し合う。 |
その結果、物体が自由落下する系において、見かけ上、“無重力状態”が観測される。
つまり、「加速運動(およびそれに伴う慣性力)」と「重力」が、ともに重力子の放出で説明できることが、アインシュタインの等価原理(この加速運動と重力(重力場)は全く等しい)を根底で支えていると言える。
さらに、慣性質量と重力質量が、ともに『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」と関連して創発するもの』として統合的に説明できることも、慣性質量と重力質量が、本質的に、同等であることを支えていると思われる。
※ある静止質量Mの物体が、観測者の方に向かって速さv〔m/s〕で等速運動している系を考える。
前項《重力子の働きと慣性》で述べたように、等速運動している物体からは、(静止質量エネルギーに相当する重力子のみならず)その等速運動に伴う運動エネルギーに相当する重力子が放出されている。
等速運動している限り、その運動エネルギーに相当する(放出される)重力子の総和は不変性であり新たに“重位勾配”が生じることはないので、ある静止質量M[kg]の物体が観測者の方に向かって速さv〔m/s〕で等速運動している限り、その等速運動している物体が観測者にもたらす重力が、(質量がより大きくなっているのに関わらず)“静止質量M[kg]”がもたらす重力より大きくなることはないと考えられる。
しかし、もし、ある静止質量M[kg]の物体が、観測者の方に向かって加速運動しているときには── “静止質量M[kg]”がもたらす重力よりも、大きな重力が生じると考えられる。
なぜなら、加速運動によって、新たに物体から放出される重力子の総和の変化によって、新たな“重位勾配”が生じていると考えられるからである。(それは、重力波の一種でもある)
このことも、“加速運動と重力が等価である”ことを示している例であると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
《特殊相対性理論と光速不変の原理》
特殊相対性理論は、2つの原理を仮定(前提)として成立している。
すなわち、“相対性原理”(あらゆる慣性系において、物理法則は等しく成り立つ)と、“光速度不変の原理”(あらゆる慣性系で観測する光の速度は一定であること)である。
「一見、常識に反するけれども、実験で裏打ちされている“光速度不変の原理”」は、あくまで、仮定(前提)に過ぎないものであった。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、この前提である“光速度不変の原理”を支持する現象が、 どのようなしくみで創発するのかを説明できるのである。
※なお、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、『光子とは、“原始ヒッグス場ユニット”のバネを利用して、素スピノールのペアが“共転回のリレー”を行いながら光速で移動するもの』であり、このことは、ある種の“新しいエーテル”の存在を認めることになるので、一見、“光速度不変の原理”を破ってしまうことを意味するように思われるかもしれない。
しかし、そもそも“原始ヒッグス場”は、かつての“古いエーテル”が想定していた“物質”とは異なる実体である。 そして、マイケルソン・モーレーの実験結果を説明できるものである。
すなわち、この“原始ヒッグス場”は、“光速度不変の原理”を破っているどころか、逆に根底で支えているのである。
以下に、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による、“光速度不変の原理”についての説明をする。
以下で、観測者も光源も、剛体であるとする。 なお、“剛体”というのは、特殊相対性理論の前提であった。
|
『ここから述べる理論は、すべての電気力学と同様に剛体の運動学にもとづいている。なぜならば、この種の理論のいうところの主張は、剛体(座標系)、時計、およびいろいろの電磁過程のあいだの関係について触れるものだからである』
(p.20 『アインシュタイン選集1』 [A1]運動している物体の電気力学について アインシュタイン)
|
光速c(km/s)=3×108〔m/s〕(秒速30万km)であるとして話を進める。
簡単にするため、光源からちょうど、3×108〔m〕(30万km)離れた観測者を考えてみよう。
すると、当然、光源から放出された光、つまり、光子は、1秒後に観測者にたどり着くことになる。
かりに、光源も観測者も、ともに“原始ヒッグス場”に対して完全に静止しているとすると── 当然、この観測者は、「光速は、秒速30万kmだ」という観測をする。
次に、観測者が、下図のように、(“原始ヒッグス場”に対して)速さv〔m/s〕で、光源の方に向けて等速運動しているとする。
すると、自然に考えると(ガリレイ変換で考えると)── 「1秒間に光が、“原始ヒッグス場”の上で30万km(3×108〔m/s〕)進み、同じ1秒間に観測者は“原始ヒッグス場”の上でvメートル進むのだから、観測者から見て、光は、合わせて1秒間に、3×108〔m〕+v(m)進むことになる── つまり、光速は、c+v〔m/s〕となり、観測者にとっての光速は、秒速30万kmを越えてしまうことになる」という結論に至ってしまうだろう。
ところが実際は違う。
実際には、観測者は、速さv〔m/s〕で運動していたとしても、静止していたときと同様に、「光速は、秒速30万kmだ(1秒間に光が進む距離は30万kmだ)」という観測する。
それこそが“光速度不変の原理”である。
※より厳密な図示の仕方があるかもしれないが、おおよその意味は読み取れると思われる。
※上側が、「“静止した観測者の座標系”からみた、3×108〔m〕(30万km)」であるのに対し、下側は、「“運動している観測者の座標系”からみた3×108〔m〕(30万km)」に相当する。
この図より、静止していた観測者にとっての「3×108〔m〕(30万km)」と、速さv〔m/s〕で運動していた観測者にとっての「3×108〔m〕(30万km)」とは、その実体が、異なるものになっているものであることがわかる。
|
何が起こっているのだろうか?
静止した観測者(剛体)と、速さv〔m/s〕で等速運動している観測者(剛体)の間で何かが決定的に違っているはずである。
何か?
すでに繰り返し説明してきたように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、“運動する物体(剛体)は、運動方向に、(外部)運動エネルギーに相当する重力子を放出していること”が、静止している状態と決定的に違う。
すなわち、物体(剛体)が慣性運動(等速運動)している状態とは、その運動方向に((外部)運動エネルギーに相当する)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されて続けて「時空の流れるプール効果」が生み出され続けている状態であり、静止している状態とは、決定的に異なっているのである。
したがって、まさにその運動方向へ放出され続けている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が、運動方向の前方に存在する時空の性質を変化させている結果、上の例のような“光速度不変”が成立していると考えられるのである。
上図のように光源に観測者が向かっていくような慣性運動(等速運動)は、「運動方向の前方に存在する時空」を、具体的に、どのように変化させているだろうか?
それは、「空間を膨張させる方向、時間の流れをスローダウンさせる方向」に変化させているのである。
この「空間を膨張させる、時間の流れをスローダウンさせる」という効果は、(原始ヒッグス場の上での)速さv〔m/s〕の等速運動が持つ、「光源との距離を短縮させている効果、光子が観測者にたどり着くまでの時間を短縮させている効果」をぴったりキャンセルしてしまうと考えられる。
そして、だからこそ、観測者は、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測するのである。
それは、光源の方が速さv〔m/s〕の等速運動で観測者に向かって近づいていく場合も、同様である。 すなわち、この場合、ふつうに考えれば、光速がc+v〔m/s〕になりそうなものを、実際は、この光源は、その運動する方向に(その運動エネルギーに相当する)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出し続けていて、それらの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が運動方向の前方に存在する時空の性質を(「空間を膨張させる、時間の流れをスローダウンさせる」方向に)変化させている結果、観測者は、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測するのである。
一方、遠ざかる場合は、どうか?
例えば、観測者が遠ざかる場合── その運動方向の後方の時空に放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、逆に(相対的に)減少するであろう。
(静止質量エネルギーによって、もともと放出されている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」から、差し引かれることになると考えられる)
その結果、逆に、「空間を収縮させる、時間の流れをスピードアップさせる」という効果が、光源と観測者の間の時空で生じ、その遠ざかる運動による「光源との距離を延長させている効果、光子が観測者にたどり着くまでの時間を延長させている効果」をぴったりキャンセルしてしまうだろう。
そして、つまりは、観測者は、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測するであろう。
それは、光源が遠ざかる場合も同様である。
※まとめると、“4面体”が、時空に占める割合が多くなるほど、空間が収縮し、時間の流れがスピードアップし──
逆に、“4角形”(縮みきったバネ)が、時空に占める割合が多くなるほど、空間が膨張し、時間の流れがスローダウンする、ということになる。
原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)
由来の“4面体”が多いほど──

|
→ |
空間が収縮し、時間の流れがスピードアップする。
(=時空が収縮(&スピードアップ)する)
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」
(PHU由来)が多いほど──

|
→ |
空間が膨張し、時間の流れがスローダウンする。
(=時空が膨張(&スローダウン)する)
|
※この性質は、光速不変のみならず、ローレンツ収縮や時空の曲りの創発も説明できる重要なものである。
つまりは、どの観測者が、どの光源が、どのような等速運動をしていようが関係なく、それぞれの等速運動に伴って、その運動方向への重力子の放出が増えていたり、運動とは逆方向への重力子の放出量が減っていたりする結果、運動方向の前後の時空の性質が変わっているので、観測者は、それぞれの時空(それぞれの慣性系)が持つ“時間と長さのものさし”で、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測するのである。
こういったしくみが、“光速度不変の原理”を支えているのだ。
以上が、“光速度不変の原理”(を支持する現象&観測)が、 どのようなしくみで(なぜ)実現しているのかについての(創発的な)説明である。
(第三者が外側から観測することによって)運動している物体が収縮しているように見える“ローレンツ収縮”は、運動方向の軸に沿ってのみ生じる。
このことは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が運動方向の軸に沿ってのみ増減することと調和している。
そして、なぜ“ローレンツ収縮”が(1−(v/c)2)1/2の割合で起こるかと言えば、「等速運動する物体(剛体)を収容する空間」、すなわち、「等速運動する剛体の後端から前端の空間」が、“運動軸に沿って、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で、膨張しているからであると考えるとつじつまが合う。
すなわち、物体(剛体)を内に収容している空間が(運動方向に)膨張するからこそ、物体(剛体)自体が逆に(運動方向に)収縮するように、第三者によって外側から観測されるのである。
これが“ローレンツ収縮”がどのようなしくみで(なぜ)実現するのかについての(創発的な)説明である。
それでは、そもそも、なぜ、「剛体の後端から前端の空間」が、“運動軸に沿って、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で、膨張しているのだろうか? それは、つぎのように説明できる。
|
まず、下図のような「観測者が光源へ近づく系」で、光速不変が成立するためには、c/(c−v)の空間の膨張と、時間の流れのスローダウンが生じる効果が存在するだけで十分であった。
※単純な比例計算で、c/(c−v)の空間の膨張と、時間の流れのスローダウンがありさえすれば、光速不変が説明できることがわかる。
|
これは、観測者(剛体)の等速運動の方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増加することによって生ずる効果である。
一方、下図のような「観測者が光源から遠ざかる系」で、光速不変が成り立つためには、次のようなc/(c+v)の“空間の収縮と、時間の流れのスピードアップ”が生じる効果があれば、十分であることがわかる。
| ※単純な比例計算で、c/(c+v)の空間の収縮と、時間の流れのスピードアップさえあれば、光速不変が説明できることがわかる。 |
これは、観測者(剛体)の運動とは逆方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が減少することによって生ずる効果であると考えられる。
次に、下図のように「剛体」が速さv〔m/s〕で運動するような系を考える。
この場合は、剛体を収容する時空について、下図のように、上の2つの効果が重なって生じることがわかる。
※ピンクの矢印は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増加する方向であり、この方向に空間が膨張し、時間の流れが遅くなる。 この効果は、剛体の後端から前方にかけて生じることが読みとれる。
緑の矢印は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が減少する方向であり、この方向に空間が収縮し、時間の流れがスピードアップする。 この効果は、剛体の前端から後方にかけて生じることが読みとれる。 |
これら2つの効果は、それぞれ、c/(c−v)と、c/(c+v)で表されるのであった。
単純に、これら2つの効果の相乗平均をとってみよう。
(c/(c−v)×c/(c+v))1/2 =(c2/(c2−v2))1/2 = (1/(1−(v/c)2)1/2
と、ぴったりローレンツ収縮の効果を示す式の逆数になる。(“ローレンツ変換”におけるかなめの式に相当するものでもある)
つまり、ローレンツ収縮の効果を示す式から予想される、「(等速運動をする)剛体の後端から前端の時空(剛体を収容する時空)」が“運動軸に沿って膨張(&スローダウン)している割合『(1/(1−(v/c)2)1/2』は、この2つの効果の相乗平均にぴったり等しいのである。
以上のことは、まさに、「(等速運動をする)剛体の後端から前端の時空(剛体を収容する時空)」が、『(1/(1−(v/c)2)1/2』の割合で膨張(&スローダウン)する理由を説明していると思われる。
すなわち、剛体が等速運動すると、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出数の増減が生じることによって、「運動方向の時空の膨張(&スローダウン)の効果」と「運動とは逆方向の時空の収縮(&スピードアップ)の効果」の両方が生じ、それらの両方の効果の相乗平均として膨張(&スローダウン)するのである。
そして、だからこそ、「(等速運動をする)剛体の後端から前端の空間(剛体を収容する空間)」が、『(1/(1−(v/c)2)1/2』の割合で膨張するのである。
|
つまり、ローレンツ収縮は、等速運度をする剛体を収容する空間が膨張するからこそ、生じるのである。
すなわち、剛体を収容する空間が膨張する結果、剛体自体は、逆に収縮しているように観測されるのである。
以上が、ローレンツ収縮がどのようにして生じるか、そして、ローレンツ収縮を意味する数式が、どうして、(1−(v/c)2)1/2 となるのかについての説明である。
※(1/(1−(v/c)2)1/2の数式が示すように、厳密には、「空間の膨張と時間の流れの遅れ」と「空間の収縮と時間の流れの早まり」の相乗平均の効果は、トータルで、剛体を収容する「空間の膨張と時間の流れのスローダウン」をもたらすことになる。
そして、この理由で、「(等速運動をする)剛体の後端から前端の時空(剛体を収容する時空)」が膨張(&スローダウン)するからこそ、ローレンツ収縮のみならず、ローレンツ変換が成立するのである。
このことにより、特殊相対性理論で、なぜ、“剛体”が前提とされていたかが、よく理解できる。
|
『ここから述べる理論は、すべての電気力学と同様に剛体の運動学にもとづいている。なぜならば、この種の理論のいうところの主張は、剛体(座標系)、時計、およびいろいろの電磁過程のあいだの関係について触れるものだからである』
(p.20 『アインシュタイン選集1』 [A1]運動している物体の電気力学について アインシュタイン)
|
すなわち、剛体だからこそ、「空間の膨張と時間の流れのスローダウン」と「空間の収縮と時間の流れのスピードアップ」の両方の効果が生じうるのであり── その結果(それらの効果の相乗平均として)ローレンツ収縮やローレンツ変換が成立するからである。
※運動する剛体中の時空の変化は、“相乗平均”で計算できる一方、剛体の外の時空の変化は、単純に、それぞれ別々に求められることになる。
すなわち、運動する剛体外の“前方の時空”の変化は、c/(c−v)=1/(1−(v/c))で、求められ、“後方の時空”の変化は、c/(c+v)=1/(1+(v/c))で求められる。
そもそも、なぜ、等速運動にともなって運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増えると、その方向に空間が膨張するのか?
それは、単純に、「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”が“4角形”(縮みきったバネ)になると、その分だけ“スペースが広がる”からである」と考えられる。
逆に、等速運動にともなって運動とは逆方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が減ると、その方向に空間が収縮するのは、単純に、「“4角形”(縮みきったバネ)が原始ヒッグス場ユニットの“4面体”になる分だけ“スペースが減る”からである」と考えられる。
このような理由の説明は、次の仮説に基づいていると言える。
仮説1.8.2.1 原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)を構成する、素スピノールが“運動している空間そのもの”が、“空間そのもの”に相当し、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”は、その空間を減らす(収縮させる)ような働きをし、“4角形”(縮みきったバネ)は、逆にその空間を回復させる(膨張させる)働きをする。
ところで、剛体内で“光速度はcだ”の観測が成り立つためには、速さv〔m/s〕の等速運動にともなって、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で“剛体中の空間が膨張すること”だけでなく、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で“剛体中で、時間の流れがスローダウンすること”も必要であった。
それでは、なぜ、等速運動にともなって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増加すると、「時間の流れをスローダウンさせている効果」が生まれるのか?
それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出が増えるほど、光子が共転回しずらくなるからであると考えられる。
すなわち、それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が増加するほど、光子が共転回できる素スピノールを持つ「原始ヒッグス場の“4面体”」という足場の比率が減少する形になる結果、光子を構成する素スピノールの共転回の過程が妨げられて「光子の振動数(すなわち、単位時間あたりの、光子を構成する素スピノールの共転回数)」が減るからであると考えられる。
このような理由の説明は、次の仮説に基づいていると言える。
仮説1.8.2.2 原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)を構成する、素スピノールの“転回そのもの”が、“時の刻み”に相当する。
この仮説が正しければ、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で時間の流れがスローダウンする理由は、「運動方向の重力子の量が多くなる効果(&運動と反対方向の重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)と、剛体中の光子の転回(=時の刻み)を減らす効果が同じ割合で(比例して)生じるからである、と言うことになる。
以上により、それぞれの慣性系が、それぞれ独自の“空間&時間”(時空)を獲得するしくみを持つことが、特殊相対性理論が示している“光速度不変の原理”を根底で支えていると言える。
そして、「それぞれの慣性系が、それぞれ独自の“空間&時間”(時空)を獲得するしくみ」を支える実体は、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和)である、と言うことになる。
※もし、仮説1.8.2.2が正しく、“4つの力”のすべてが、根底で、素スピノールの転回を介して創発しているのならば── あらゆる現象(物理現象、化学現象、天体現象、人生の営み、生理現象、社会現象…)における“時間の流れの遅れや早まり”が、根底で、素スピノールの転回のしやすさの変化に基づいて創発していることになる。
そして、実際、4つの力を含むすべての物理的な力が、根底で、素スピノールの転回によって創発していると説明できる。(→結果2)
すなわち、これにより、“ウラシマ効果”(光速近くで移動する宇宙船に乗ってでかけて帰ってくると地球上の時間が何十年も先に進んでいる等)が生じることを説明できる。
そして、同時に「双子のパラドックス」も解消できることになる。
なぜなら、あくまで、双子のうちで、相対的に「運動方向の重力子の量が多くなる効果(&運動と反対方向の重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)が大きい方のどらか一方だけが、時の流れが、より(相対的に)スローダウンするだけだからである。 つまり、双子のうちで、どちらか一方だけが相対的に時間の流れがスローダウンするだけなので、もし、例えば、宇宙船が地球を出発して、長期間、光速近くで運動してきた後に帰ってきたとき、地球の時間の流れが相対的にスピードアップしているならば── 「宇宙船を基準にすると、地球の方が光速近くで運動することになるから、地球の時間の流れの方がスローダウンする」ということは実在しないことになるので、パラドックスは根底から消滅するのである。
※この仮説は、一般相対性理論が示すように、「強い重力場であるほど、時間の進み方がスローダウンすること」とも合致する。
その理由は、やはり、強い重力場であるほど、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高くなるので、光子にとっての足場──原始ヒッグス場の“4面体”の足場が減り、転回しにくくなることである。
極端な話、もし、光子が転回できなくなっていれば、そこでは時間の流れが止まっていることになる。
例えば、ブラックホールの中の、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の足場が100%消失している場所では、光子は全く転回できなくなっているので、時間の流れが止まっていることになる。 当然、光子は、それ以上先へは進むことができなくる。 これが、「ブラックホールの外に光が出て行けなくなる」ことの背後に存在していることであると考えられる。
※ ※例えば、“地球に高速で降り注ぐミューオン”の寿命が延びることも、やはり、そこでも、高速で運動するミューオン自身が生じさせる“相対的に「運動方向の重力子の量が多くなる効果(&運動とは反対方向の重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)が、“ミューオンの中での素スピノールの“転回数の低下”、すなわち、時間の流れのスローダウンを生じ、寿命が延びる── と説明できる。 なお、ミューオンの寿命ののびが(1/(1−(v/c)2)1/2の式に合致するということは、ミューオンは、剛体の一種である(内部構造を持つ)ことを意味している。 (→結果3)
※ある時空の構造(=ある「重力子&縮みきったバネの“4角形”」の分布)をもたらしている運動が等速運動であれば── 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の比率は、その運動方向に沿った軸上で、どこでも一定となるので、その運動方向に沿った軸上で、“重位勾配”は、まったく生じない。 一方、加速運動なら、“重位勾配”を生じ、重力と似た効果をもたらすと考えられる。
※原始ヒッグス場ユニットがすべて100%“4角形”(縮みきったバネ)になった場合、時間の流れが止まるので“時空の膨張(&スローダウン)”が無限大に至ると考えていいのだろうか? それとも無限大に至ると考えるべきではないのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
※この説明は、“四次元時空連続体”という考え(時間と空間が切り離せず、かたく結びついているという考え)とも調和している。
すなわち、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和)は、“四次元時空連続体”を支える実体でもある、と言える。
なお、ここでの“連続”の意味は、“時間と空間が切り離せず、かたく結びついている”という意味である。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が「時空が不連続であること」を前提としていることを意識して、より厳密に書けば、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)は、『不連続な時空上にある「四次元時空連続体」』を支える実体である、と言うことになる。
『連続な時空を前提とする「四次元時空連続体」』は、『不連続な時空を前提とする「四次元時空連続体」』のマクロ近似である。 すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、『連続な時空を前提とする「四次元時空連続体」』による説明を包含するものである。
それでも、「これは、やはり、エーテルではないのか? エーテルは、かつて否定されたはずなので、問題ではないか?」という疑問が、生じるかもしれない。
しかし、ここに問題はない。 その理由をまとめると次のようになる。
|
1.この「原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和)」は、逆に“光速不変の原理”がどのようなしくみで成り立つかを説明してくれるものである。
よって、“光速不変の原理”の根拠の一つとなった、有名な「マイケルソン・モーレーの実験」の結果は、この「原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)」を、否定することができない。
そして、「マイケルソン・モーレーの実験」は、“新しいエーテル”を否定できないばかりか── 逆に、このこの「原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)」の存在を支持するものであると再解釈できるものである。
すなわち、“測定機器(剛体)の運動”によって、「運動にともなって、運動方向に放出される重力子の量が多くなる効果(&運動とは反対方向に放出される重力子の量が減少する効果)」(の相乗平均)が生じる結果、「剛体を収容する空間が膨張し、そこでの時間の流れがスローダウンする」ので、期待した“誤差”を100%観測できなくなるのは当然なのだ── と説明できるのである。
(“観測の理論負荷性”の一例である)
2.そもそも、アインシュタイン自身が、(特殊相対性理論で否定された形になったが、一般相対性理論に基づいて)、結局は、“エーテル”を必要不可欠と考えていた。
|
『すなわち一般相対性理論によれば、空間は物理的特性を与えられている。それゆえこの意味でエーテルは存在する。 一般相対性理論によればエーテルを伴わない空間を考えることはできないものである。なぜならば、そのような空間では光も伝播することができないし、また空間および時間の基準(すなわち物指と時計)も存在することができない。したがって物理学的に意味のある時間的、空間的距離というものも存在しえないことになる。しかしながらここに考えたエーテルが、質量をもったふつうの物質からできているとか、あるいはまた普通の媒質(水や空気のような)と同じような性質をもっていると考えることはできない。 たとえば、運動というような概念は、われわれのエーテルには適用できない』
([A10]『エーテルと相対性理論』(アインシュタイン選集2 p.189)の中の下記の記述から分かるように、 下線は、筆者による)
|
このアインシュタインが必要不可欠と考えていたエーテルを“新しいエーテル”と呼ぶこととする。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)」こそが、この“新しいエーテル”であることになる。
この“原始ヒッグス場”を構成する原始ヒッグス場ユニットは、物質でないし(物質未満であるし)、それ自体は質量を持たず、原則として、場所を移動させるような運動はしない。
つまり、「原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)」は、アインシュタインが考えた“新しいエーテル”が満たすべき条件も満たしている。
3.双子のパラドックスを根底から解消する。(上で説明した)
4.特殊相対性理論のもう一方の前提、“相対性原理”(あらゆる慣性系において、物理法則は等しく成り立つ)と調和している。
すなわち、ニュートン力学(→上記)や電磁気学(→結果2)を説明できる。
…
|
つまりは、「原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和)」は、「電磁場、重力場(時空の曲り→下記)、“新しいエーテル”、光速不変、“四次元時空連続体”、双子のパラドックス…」を統合的に説明できる幾何的な実体像なのである。
《“時空の曲がり”&重力場の実体像》
アインシュタインは、一般相対性理論の中で、抽象的なリーマン幾何学を用いて導いたアインシュタイン方程式をもとに、重力は“時空の曲がり”によって生じる(重力場は“時空の曲がり”である)とエレガントに説明した。
しかし、“時空の曲がり”という表現は、それだけでは、十分な表現ではない(or 比喩にすぎない)と思われる。
なぜなら、(連続な時空を前提にしながら“2D平面の曲がり”をイメージすることは、確かにできるが)、連続な時空を前提にしながら“3D空間の曲がり”そのものを、直接、具体的にはっきりとイメージすることは、困難だからである。
※アインシュタイン自身にとっても、連続な時空を前提にしながら“3D空間の曲がり”を具体的にイメージすることが困難であったことは次の記述から読みとれる。
|
『映画の上で私たちは、二次元のスクリーンの上で動いている二次元の人間を見慣れています。そこで私たちは、このような映像、つまりスクリーン上での役者が実際に生きていて、思考の力をもち彼ら自身の科学をつくることができると想像してみます。彼らにとっては二次元のスクリーンが幾何学的空間となっているのです。これらの人たちは、具体的に三次元の空間を想像することができません。それはあたかも私たちが四次元の世界を想像することができないことと同様です。彼らは直線を曲げることはでき、円がどんなものかを知っていますが、しかし、球をつくることはできません。球をつくるのにはその二次元のスクリーンの外に出なければならないからです。私たちもそれと似ていて、線や面を逸らせたり、曲げたりすることはできますが、三次元の空間を逸らせたり曲げたりするとどうなるかを考えようとすると、それは難しいのです。』
(p.97 『物理学はいかに創られたか 下巻』 アインシュタイン、インフェルト著 岩波新書 下線は筆者による)
|
一方、次の記述から、アインシュタインも、“時空の曲がり”について定式化する前に、頭の中に何らかの漠然とした「観念やアイデア」を持っていただろうことがわかる。
|
『彼(アインシュタイン)はよく「頭の中で考えるときに数式を用いる科学者は、一人もいませんよ……」といっていた。
実際、物理学者でも、計算をはじめる前にはまず、ある観念やアイデアを頭の中で思いうかべてみる。そして、これらの観念やアイデアはふつう、簡単な言葉で表現できるものなのである。計算や数式は、その後にでてくる操作なのである。』
(p.283 『アインシュタインの世界 物理学の革命』 L.インフェルト著、武谷光男、篠原正瑛訳 講談社ブルーバックス 「(アインシュタイン)」を補足)
|
ただし、アインシュタインが、数式化の際にもっていた「観念やアイデア」は、決して、“3D空間の曲がり”そのものではなかったことが、次の記述からはっきり読み取れる。
|
『この二次元の球面世界に対して三次元の類比物、つまりリーマンによって発見されている三次元の球状空間が存在する。その諸点もまたすべて同等である。それはその〈半径〉R によって決まる有限の体積(2π2R 3)を占める。 こういう球状空間というものを人は表象できるだろうか? ある空間を表象するというのは〈空間的〉経験、すなわち〈剛体〉の物体の動きによって得る経験の全体を表象することにほかならない。 この意味において、球状球面というものが表象できるのである。』
(p.141〜142 『特殊および「一般相対性理論」について』 A.アインシュタイン著 金子務 訳 白揚社)
|
すなわち、アインシュタインは、“3D空間の曲りのイメージ”を、「〈剛体〉の物体の動きによって得る経験の全体」に置き換えて、それを数式化しようとしたのである。
そして、“3D空間の曲り”そものものを、具体的にイメージすることが困難だっだからこそ、リーマン幾何学(計量テンソル、リーマン曲率テンソル、リッチ曲率テンソル…)という、抽象的な数学(数式)の力を借りて、それを表記しようとする努力をしたのだと考えられる。
※それは、マクスウェルが、電磁気学の世界を数式化する際、「空想上の渦や歯車」という形であったが、空間そのものを具体的にイメージしていたのとは対照的である。
|
『マクスウェル自身、巧みなエーテルの力学的なモデルを数学的に組み立て、それを通じてファラデーの場が作用すると想像した。これは空想上の渦と歯車による複雑な仕組みで、誘導された磁力による磁石の回転のような、観測される電気の効果が、機械的に生まれ、場を伝わる事情を具体例で示していた。 マクスウェルが初めて電磁波の存在を予想したのも、この数学的なエーテル・モデルをもとにしてのことで、この電磁波が、たまたま光の速さでエーテルを伝わる』
(p.258 『世界を数式で想像できれば アインシュタインが憧れた人々』 ロビン・アリアンロッド 松浦俊輔訳 青土社 下線は筆者による)
|
“幾何的な実体原理”や“シンプル一様化原理”(3つの3Steps原理の中の2つ)によると、重力という名の基本的な“自然(nature)”がイメージ不可能な実体からなりたっているとは、考えにくい。
すなわち、これらの原理は、“時空が曲がり”という表現(言葉)の背後に、“時空の曲がり”と表現できるような、なんらかの(具体的にイメージ可能な)シンプルな実体が、実在していることを示唆しているのである。
この“時空の曲がり”と表現(言葉に)できる重力場の幾何的な実体像、すなわち、アインシュタイン方程式についての解釈について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次のように説明する。
重力場の実体とは、原始ヒッグス場が担う、“4面体”と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和であった。
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」のみを、簡単に図示すると、次のようになる。
※左側に比べ、右側の質量が2倍になっているのにともなって、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の存在数が、2倍になっていることが示されている。
なお、質量の大きさに比例して、「重力ポテンシャルエネルギーの単位距離当たりの変化量」、すなわち、重力場が大きくなるのだった。(→《重力の実体像》)
※図は、理想化した“3Dの球殻”を輪切りにしたものに相当する。
整然と、直線的、対称的に図示しているが── 実際は、下図のように雑然としており、『「厚さ2LPの球殻」に存在する存在する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数は、(時間&空間)平均的に、常に、ほぼ一定である』という条件を満たしているだけである。
※「厚さ2LPの球殻」に存在する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数を便宜上、左側で8個、右側で16個ととして示してある。しかし、厳密には、上図のように輪切りにした部分(2次元)で同数になるのでなくて、球殻全体(3次元)で同数となっているはずである。
不連続な時空を前提にしていれば、その様子を頭の中に想像することは、難しくないだろう。
「タマネギ」や「打ち上げ花火の尺玉(あるいは、(立体としての)打ち上げ花火そのもの)」から発展させていけばよい。
※周辺で途切れているように図示されているが、当然、「実際は、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、途切れず限りなく広がって存在している。 また余白部分には、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が、びっしりしめている。
|
この図が、重力場に相当するという説明は、次のような性質から導かれるのだった。
原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)
の“4面体”が多いと──

|
= |
運動の際、抵抗を受けやすい
(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間がかかる)
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」
の密度が多いと──

|
= |
(運動の際、抵抗を受けにくいので)
その方向に運動しやすい
(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省ける)
|
一方、この『原始ヒッグス場上の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」』を、“時空の曲がり”であると説明(解釈)できるであろうか?
結論から言うと、“時空の曲がり”と解釈できる。
なぜなら、(上記の《特殊相対性理論と光速不変》で説明したように)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高いほど、「空間は膨張し、時間の流れがスローダウンする」という性質を原始ヒッグス場が持つからである。
原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)
由来の“4面体”が多いほど──

|
→ |
空間が収縮し、時間の流れがスピードアップする。
(=時空が収縮する(&スピードアップする))
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」
(PHU由来)が多いほど──

|
→ |
空間が膨張し、時間の流れがスローダウンする。
(=時空が膨張する(&スローダウンする))
|
つまり、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、位置(「どの“2LP球殻”に位置するか」、「“2LP球殻”の中のどこに位置するか」)に応じて、変化しているからこそ、“時空が曲がり”(=“空間”や“時間の流れ”が変化していること)が存在しているのである。
「どの“2LP球殻”に位置するか」とは、下図からわかるものである。
すなわち、“2LP球殻”の位置の変化(r=2nLPにおけるnの変化)にともなって生じている時空の曲りである。
これは、自由落下運動によって、消すことができる時空の曲りに相当している。
一方の「“2LP球殻”の中のどこに位置するか」とは、下図からわかるものである。
すなわち、上図のように、たった1つの“2LP球殻”の中においても『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の密度が変化しうることにともなって生じている時空の曲りである。
これは、自由落下によって消せない、時空の曲りに相当する。
※なお、以上のことは、「地面に垂直な方向のみに重力が働き、地面に水平な方向には重力が働かない」理由を説明していると思われる。
いずれにしても、時空の曲りの有無は、次のような性質から導かれるとも言える。
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、
位置に応じて変化しながら分布していると──
 |
& |
 |
|
= |
空間の膨張度&時間の流れのスピードが
位置に応じて変化する
(=時空が曲がっている)
|
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、
もし、位置に応じて変化せずに分布していると──
 |
& |
 |
|
= |
空間の膨張度&時間の流れのスピードが
位置に応じて変化しない
(=時空は曲がっていない)
|
※「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、位置(どの“2LP球殻”に位置するか、“2LP球殻”の中のどこに位置するか)に応じて、変化しているからこそ、“時空が曲がり”が存在しているのである。
すなわち、もし、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、位置(どの“3Dの球殻”(厚さ2LP)に位置するか)に応じて変化していなければ、“時空が曲がり”は、そこには存在していないのである。
|
つまり、(原始ヒッグス場の上の)『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』は、重力場=“重位勾配”のみならず、“時空の曲がり”=「空間の膨張度の変化&時間の流れのスピードの変化」も創発しうるのだ。
すなわち、重力場と“時空の曲がり”の関係を結びつけるミッシングリンク── それが、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』なのである。
この『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』こそが、重力場も“時空の曲がり”も、両方を説明できる、本質的な実体なのであり──
重力場=“時空の曲がり”というアインシュタインの驚異的な洞察を理解するカギなのだ。
(「重力場とかけて、“時空の曲がり”と解く。 その心は、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』である」ということになる)
※以上の説明によれば、重力場、および、“時空の曲がり”と解釈できるもの、3D空間における実体像を、(『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』として)頭の中に、しっかりイメージできる。
「太陽が作る重力場(=“重位勾配”)」と解釈できる『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』の働きのおかげで、地球は、太陽に引き寄せられ続け、「時空の流れるプール効果」と解釈できる地球の運動エネルギー相当する『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』の働きのおかげで(ほぼ)等速運動する結果、地球の公転が実現していることになる。 (なお、重力と垂直な方向には、密度の変化はないので、重力が働かない)
一方で、“時空の曲がり”とも解釈できる『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化』のおかげで、“時間の流れのスピード”や“空間の膨張度”は変化する。
そして、重力場と“時空の曲がり”は、同一の実体によって担われているので── 「重力場とは、“時空の曲がり”である」という“短絡的な説明”も、ありうることになる。
しかし、この「重力場とは、“時空の曲がり”である」という説明は、本質(実体像)を見失わせうる(誤解を招きうる)、曖昧な(やや不正確な)ものだと言わざるをえないと思われる。
なぜなら、「重力場とは、“時空の曲がり”である」という説明は、「カエルは、細胞の集合である。 人も、細胞の集合である。 だから、“カエルとは、人である”」という説明と同様であると指摘されても仕方ないことを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)および3Steps理論が示しているからである。
※アインシュタインは、“時空の曲がり”についての明確で具体的な描像(“幾何的な実体像”)を持たないまま、抽象的なリーマン幾何学の力を借りて、一般相対性理論、すなわち、アインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)を作り上げた。 その抽象的な数式は、実は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、分布(配置)の総和」を近似的に表現しているものにすぎないと考えられる。
(詳細は下記にて →《アインシュタイン方程式(アインシュタインの“重力場の方程式”)》)
《重力場と“重力線”》
重力場=“重位勾配の総和”(「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動の総和」の所産の一例)を、図で表現するために── 電気力線や磁力線に習い、“重力線”を考えることができる。 (なお、“重力線”は、新しいものではない。 (参考 『新しい重力理論』 アーサー・クライン 竹内均訳 講談社ブルーバックス))
電気力線の球面密度が静電気力に等しいように、“重力線”の球面密度は、重力に等しいというように定義することができる。
“重力線の球面密度”(すなわち、重力)と“2LP球殻における「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度”は、比例する。
なぜなら、“2LP球殻における「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度”に比例する『「厚さ2LP[m]の球殻が持つエネルギーの“時間&空間”平均の値」E平均=NMEG/4πn2』を2LP[m]で割ったものが重力だからである。
当然、“重力線”の上だけに“重位勾配”があるわけではなく、実際は、(あらゆる方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放射状に放出されているので)あらゆる場所に“重位勾配”が存在しうる。
それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、本来は、下図のように雑然と放出されているからでもある。
※『「厚さ2LPの球殻」に存在する存在する数は、常に、ほぼ一定である』という条件を満たしているだけであり、雑然と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されている。
その雑然さが、まさに、「あらゆる場所に“重位勾配”が存在している」ことを支えると考えられる。
|
したがって、“重力線”は、下図のように、便宜上、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、整然と(直線的に、対称的に)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されているように図示したものと、本質的に等しいと考えられる。
※左図のように、便宜上、整然と(直線的、対称的に)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されているように図示したものが、実は、右図の“重力線”と、本質的に同等であると考えられる。
※なお、「重力子の個数」と「“重力線”の本数」は比例しているはずだが、当然、「重力子の個数」と「“重力線”の本数」は等しくない。 よって、上図の数量関係は正確なものではない。
(→下記の計算によると、厚さ2LPの球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数をNM〔個〕とすると、“重力線”の本数は、NM×2c2LP[本](≒NM×2.9×10-18[本])ということになる)
|
球面の面積は半径rの2乗に比例する(球面積S=4πr2)ので、物体からの距離が大きくなるほど、その距離の2乗に反比例して、“重力線の球面密度”(∝「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度)が減ることになり、重力(“重位勾配”)も小さくなる。 (逆に、物体の中心に近づくほど、物体の中心からの距離の2乗に反比例して、“重力線の球面密度”(∝「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度)が増えることになり、重力(“重位勾配”)も大きくなる。)
この“重力線の球面密度”と重力(“重位勾配”)の関係は── ニュートンの万有引力の法則の式とも調和している。
したがって、以上をまとめると、“重力線の面密度”=“重位勾配”の大きさ=“重力の大きさ”=“重力場の強さ”=『「厚さ2LP[m]の球殻が持つエネルギーの“時間&空間”平均の値」E平均=NMEG/4πn2』/2LP ∝「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度 ∝“時空の曲がりの強さ”ということになる。
※半径r〔m〕の球面における“重力線”の球面密度は、ある他の質量[kg]に対する重力〔N/kg〕に相当する。
よって、質量M[kg]が作る“重力線”の本数をn重力線とすると、 n重力線×(1/4πr2)=(NMEG/4πn2)×1/2LP×1/MG[N/kg]となるはずである。 (なお、r=2nLPである)
計算すると、質量M[kg]が作る“重力線”の本数は、n重力線=NMEG×2LP×1/MG=NM×2c2LP[本]となる。
一方、厚さ2LP[m]の球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数は、 NM〔個〕である。
したがって、厚さ2LP[m]の球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数を、2c2LP(≒2.9×10-18)〔倍〕すると、“重力線”の本数になることになる。
このように“重力線”の本数と、厚さ2LP[m]の球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数が比例定数で結ばれている事実は、“重力線”の図の理解を助ける。
※“重力線の密度”が高いほど、“重位勾配”、重力、“時空の曲がり”… が大きくなることは── 電気力線や磁力線の面密度(単位面積あたりの本数)が高いほど、電気力や磁力が大きくなることと同様である。
“等電位面”と同様に── “等重位面”を考えることもできる。
※実際は3次元に放射されているので、 “等重位面”は、実際は球面である
※“等重位面”の間隔は、物体に近づくほど狭くなっている。
そのことは、物体に近づくほど、“重位勾配”=重力が大きくなることと合致する。
※“等重位面”とは、重力ポテンシャルエネルギーが等しい面であるとも言える。
|
※質量が小さいほど“重力”や重力場&“時空の曲がり”が小さくなるように── “重力線の面密度”(単位面積あたりの本数)も小さくなる。
逆に、質量が大きいほど“重力”や重力場&“時空の曲がり”が大きくなるように── “重力線の面密度”(単位面積あたりの本数)も大きくなる。
※“重力線”の面密度が高いほど、重位勾配”の大きさ=“重力の大きさ”=“重力場の強さ”∝物体から放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度∝“時空の曲がりの強さ”が、大きくなる。
もし、同じ質量を持つ物体(天体を含む)の“サイズ(大きさ)”のみが変化すれば── 物体の周囲の、“重力線”の密度=重力場の大きさ=“重位勾配”の大きさ∝“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度∝“時空の曲がりの大きさ”も、変化する。
物体(天体を含む)のサイズが同じ質量のまま小さくなる(コンパクト化する)ほど、物体周辺(近辺)の“重力線”の密度が高くなり、物体周辺(近辺)の「重力、“重位勾配”、“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度、時空の曲がり…」が大きくなっていることが読み取れる。
しかも、物体が、同じ質量のまま小さくなる(コンパクト化する)ほど── 物体周辺において“重力線”の密度が高い領域が増えることも読み取れる。
(物体周辺において“重力線”の密度が高い領域が増えるということは、物体周辺において時空が膨張(&スローダウン)していると言うことに他ならない)
※なお、上の3つの図は、物体周囲(遠方)の“重力線”が、どれも同じになっている。 これは物体が“同じ質量のまま”小さくなる(コンパクト化する)ときの様子を、図示してあるからである。
しかし、実際は、重力ポテンシャルエネルギーを利用してコンパクト化するのが自然であり── その場合は、コンパクト化に伴って、重力ポテンシャルエネルギーを利用して(外部)運動エネルギーが上昇し、重力子の放出源として働く能力がアップするので(質量エネルギーが増加することになるので)、“重力線”の密度も増加することになる。
下図は、重力によって、物体のサイズが小さくなる(コンパクト化する)場合の、“重力線”の変化を示した図である。
|
|
→
物体(質量)の、自身の重力による
コンパクト化
|
|
|
※この図の場合、質量が2倍になっていることがわかる。(“Gが2Gになる”という説明に対応する図でもある)
|
この現象は、「重力場が非線形である」という解釈を生む1つの要因だろうと思われる。
しかし、実際は、質量エネルギー(運動エネルギー(内部&外部)の総和)と重力場は比例し続けているので、重力場は線形であると言える。
重力場に、非線形性が存在しない理由をまとめると、次のようになる。
1.質量エネルギー(運動エネルギー(内部&外部)の総和)と重力場は比例し続けている
((外部)運動エネルギーの増加が、質量エネルギーの増加(重力子の放出源の増加)の実体である)
2.“重力場のエネルギー”そのものは、質量(重力子の放出源として働き続ける能力)を持っていない。
3.重力場は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和であり、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)は、
調和振動子(単振動する系)の一種である。
詳細は、下記にて説明する。 →《重力場の線形性について(詳細版)》
※このあたりは、実は、“宇宙(時空)の加速膨張”とも関連している。
(→“EMOES宇宙論3”)
《量子化された重力、重力場の計算》
上の《重力の実体像》で説明したように、「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”の減少量」=“重位勾配”=重力場は、次のように計算できる。
|
“質量M[kg]の中心からr=2nLP[m]の地点にできる重力場”
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)[N]
=(NMEG/4πn2)×(1/2LP) [N]
|
※重力子質量M G[kg]の NM個分の質量が生む重力場であり、重力子質量M G[kg]1つに対して働く重力[N]に相当するのだった。
これは、質量M[kg]の周辺に、厚さ2LP[m]の球殻を想定して求めたものであった。
半径2nLPの球殻が持つエネルギーの“時間&空間”平均値は、E平均=NMEG/4πn2 と求められるのだった。
よって、この質量M[kg]を持つ仮想質点を考えると、その仮想質点から2LP[m]だけ遠ざかるごとに、(NMEG/4π)×1/12、(NMEG/4π)×1/22、(NMEG/4π)×1/32、(NMEG/4π)×1/42、(NMEG/4π)×1/52… の大きさずつ、周囲の厚さ2LP[m]の球殻にれるエネルギーが蓄えられること、すなわち、中心から移動してきた重力子質量MG[kg]1つ分の質量に蓄えられる重力ポテンシャルエネルギー[J]が、(NMEG/4π)×1/12、(NMEG/4π)×1/22、(NMEG/4π)×1/32、(NMEG/4π)×1/42、(NMEG/4π)×1/52… の大きさずつ、増加(追加)すると考えられることも、前に述べた。
※質量M[kg]の仮想質点から2LP[m]だけ遠ざかるごとに、(NMEG/4π)×1/12、(NMEG/4π)×1/22、(NMEG/4π)×1/32、(NMEG/4π)×1/42、(NMEG/4π)×1/52 … (NMEG/4π)×1/(n−1)2、(NMEG/4π)×1/n2の大きさずつ、周囲の厚さ2LP[m]の球殻にれるエネルギーが蓄えられること、すなわち、中心から移動してきた重力子質量MG[kg]1つ分の質量に蓄えられる重力ポテンシャルエネルギー[J]が、(NMEG/4π)×1/12、(NMEG/4π)×1/22、(NMEG/4π)×1/32、(NMEG/4π)×1/42、(NMEG/4π)×1/52 … (NMEG/4π)×1/(n−1)2、(NMEG/4π)×1/n2の大きさずつ、増加(追加)していることが読み取れる。
※オレンジの高さの部分が、E平均=重力場×2LP=NMEG/4πn2 の値であり、それらを1からnの分まで足しあわせると、それがr=2nLPの地点での重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)に、等しくなることがわかる。
|
さて、この(質量M[kg]の仮想質点が生む)E平均=NMEG/4πn2の値を、1からnまで足し上げた値──
r=2nLPの地点での重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)を、実際に計算してみよう。
当然、(NMEG/4π)×(1/n2)の1からnまでを足しあわせるにあたって、最も大切な計算は、次の級数の計算である。
1+1/22+1/32+1/42+1/52+ … +1/(n−1)2+1/n2
一般に、nが自然数とき、次の不等式が成り立つことが、数学的な帰納法によって、証明できる。
(参考 『三訂版 高等学校 基礎解析』(昭和63年)の第3章『数列』の中の第2節 数学的帰納法の中の問題13(2))
|
1+1/22+1/32+……+1/n2 ≦ 2−1/n
|
この式は、このタイプの無限級数が発散しないという大事なことを示している。
しかし、よく考えると、この不等式の意味することは、「1/x2を積分した面積の方が、横1縦1/n2 の長方形の面積を足しあわせたものより大きい」という、おおざっぱで当たり前なことを意味しているにすぎないことがわかる。
※y=1/x2 を1からnまで積分によって求めた面積(右図のピンクの部分の面積)は、「1−1/n」である。
そこに「 1」(一番左側のオレンジの面積)を足しあわせた面積は、明らかに、左の図のオレンジの部分の総和より大きい。
|
より正確な値を求められないであろうか?
調べてみると、その値が『π2/6』に収束することが、オイラーによってすでに証明されていたことがわかった。
|
『1+1/22+1/32+… の無限級数は、π2/6に収束する』
(この無限級数の問題は、「バーゼル問題」と呼ばれていて、偉大な数学者オイラーが、10年もかけて証明したものであるとのことである)
(参考 『なるほど高校数学 数列の物語』p.170 宇野勝博 講談社ブルーバックス)
|
したがって、(2−1/n)において、nを無限大にした際、2に収束してしまうところを── π2/6に収束するように改善すればよいことがわかる。
すなわち、問題の級数は、近似的ではあるが、より正確に次のように計算できることがわかる。
|
1+1/22+1/32+……+1/n2 ≒ π2/6−1/n
|
※なお、このときの、「1/n」は、y=1/x2 をnから∞までの積分によって求めた面積(下図のピンクの部分の面積)に相当すると考えられる。
つまり、「1/n2 を1から∞まで足しあわせた面積π2/6」から、この「y=1/x2 をnから∞までの積分によって求めた面積1/n(ピンクの面積)」を引くことで、近似的に、「1+1/22+1/32+……+1/n2 」の面積(下図のオレンジの面積の総和)を計算していることになる。
※y=1/x2 をnから∞までの積分によって求める面積(ピンクの部分の面積)は、「1/n」である。
|
したがって、 「1/n2 を1から∞まで足しあわせた面積π2/6」から、“よけいに大きい値を引いている”ことになるので──
厳密には、「1+1/22+1/32+……+1/n2 ≧ π2/6−1/n」ということになる。
(つまり、トータルで 「2−1/n ≧ 1+1/22+1/32+……+1/n2 ≧ π2/6−1/n」ということになる。)
それでも、やはり、nが大きければ大きいほど誤差が小さくなる「π2/6−1/n」が、近似値として「2−1/n 」より、ずっとふさわしいと考えられる。
以上より、r=2nLPの場所での、重力ポテンシャルエネルギーは、
|
n
Σ (NMEG/4π)×(1/k2)
k=1
|
≒(NMEG/4π)×(π2/6−1/n)=πNMEG/24−NMEG/4πn=NMEP/48−NMEG/4πn |
|
※E G=E P/2πにより、一部、係数πを消すことができる。
というように近似的に計算できることになる。
※たとえ“1cm”でも、r=2nLPの中のnの値は、n≒0.01m/2×(1.616×10-35)m≒0.309×1033と非常に大きなものとなるので、われわれの日常的な距離で考えれば、かなり正確な値になっていると考えられる。
※当然、無限遠方のr=∞の地点での、重力ポテンシャルエネルギーの絶対値の大きさも、より簡単に正確に求められることになる。
より──
|
∞
Σ (NMEG/4π)×(1/k2)
k=1
|
=(NMEG/4π)×π2/6=NMEP/48 |
|
※やはり、E G=E P/2πにより、係数πを消すことができる。
となる。
いわゆる重力ポテンシャルエネルギーの式、−GM/r は、無限遠点の重力ポテンシャルエネルギーを0としたときの、相対的なものである一方── 先ほど求めたr=2nLpの地点での、重力ポテンシャルエネルギーの大きさ
|
n
Σ (NMEG/4π)×(1/k2)
k=1
|
≒NMEP/48−NMEG/4πn |
|
は、質量M[kg]の仮想質点における重力ポテンシャルエネルギー0としたときの、絶対的なものであると言える。
※この計算値は、あくまで仮想質点を考えた上でのものである。もし大きさを持った質量M[kg]の物体を考えた場合には、当然、若干の修正が必要になると考えられる。
簡単のため、質量M[kg]の物体を、半径a〔m〕の球体であると想定してみよう。
a=2mLP〔m〕とすると、a=2mLP〔m〕の地点からr=2nLpの地点までの重力ポテンシャルエネルギーの変化の大きさは、
(≒NMEP/48−NMEG/4πn)−(NMEP/48−NMEG/4πm)=NMEG/4π(1/m−1/n)と計算できると考えられる。
詳細な検討は、今後の課題である。
|
無限遠方のr=∞の地点での、重力ポテンシャルエネルギーの絶対値の大きさが、NMEp/48 であるということは、
「NMEp/48−NMEG/4πn」の中で、ニュートン力学の重力ポテンシャルエネルギー“−GM/r”に、相当する部分は、まさに、この式のマイナス項── 「 −NMEG/4πn 」であることを意味する。
このことは、ニュートンの重力ポテンシャルエネルギーの式が、次のように変形できることからも確かめられる。
−GM/r=−(Mc2/MP)×LP×(1/2nLP) (「プランク距離を求める式LP=(hG/2πc3)1/2」を変形して得られる、G=2πc3LP2/h=c2LP/MP を使用)
= −NMEG/4πn ×(2π/MP)
= −NMEG/4πn ×(1/MG)[J/kg]
以上より、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に基づいて量子化された重力場、重力ポテンシャルエネルギーの計算結果──
r=2nLPの地点での重力場=NMEG/4πn2×(1/2Lp)[N]
(質量M[kg]の仮想質点を想定した場合の)r=2nLpの地点での(絶対的な)重力ポテンシャルエネルギー =NMEP/48−NMEG/4πn[J]
は、ニュートンの万有引力の法則(ニュートンの重力理論)と調和していると言える。
|
ニュートンの万有引力の法則
(ニュートンの重力理論)
|
量子化された重力場や重力ポテンシャルエネルギー
(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の重力理論)
|
|
重力ポテンシャルエネルギー
|
−GM/r[J/kg]
※無限遠方を0としたときの
相対的なものである
|
NMEP/48−NMEG/4πn[J]
※物体が仮想質点であると想定し、
その質点の場所を0とした場合の絶対的なものである
※なお、物体が半径a=2mLp[m]の球体であると想定し、
物体の表面を0した場合の相対的なものは、次のようになる
NMEG/4π(1/m−1/n)[J]
|
|
重力場
|
GM/r2[N/kg]
|
NMEG/4πn2×(1/2Lp)[N]
|
※ニュートンの重力理論の方の単位は、[N/kg]や[J/kg]であり、1[kg]当たりのものである。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の重力理論の方の単位は、[N]や[J]であり、重力子質量MGの1[個]当たりのものである。 1/MG〔1/kg〕を掛け合わせれば、トータルの単位が〔N/kg〕や〔J/kg〕となり、ニュートンの重力理論の式と同等になる。
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の重力場は、NMEG/4πn2×(1/2Lp)[N]= NMEG/4πn×(1/2nLp)[N]=(NMEG/4πn)×(1/r)[N]と変形できる。 このことは、ニュートンの重力場が、 GM/r2[N/kg]= (GM/r)×1/r[N/kg]と変形できることと調和している。 なぜなら、NMEG/4πn[J]=GM/r[J]だからである。
|
以上のような“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に基づく「重力&重力ポテンシャルエネルギーの量子化」の理論においては、rが小さくなっても(n=1となっても)、重力の大きさ、重力ポテンシャルエネルギー、重力場が持つ総エネルギーについて、いずれにおいても、無限大は生じない。
しかし、以上の説明は、重力理論の量子化に成功していると言うには、十分ではない。
なぜなら、アインシュタインの重力理論、すなわち、一般相対性理論と調和していることを、まだ、示せていないからである。
アインシュタイン方程式との整合性を含め、アインシュタインの重力理論(一般相対性理論)についての、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明は下記で行なう。
(→《アインシュタイン方程式(アインシュタインの“重力場の方程式”)》)
《(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」を創発する仮想光子》
原始ヒッグス場は、重力場のみならず、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」も創発する。
重力場が、原始ヒッグス場の上の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として、創発する一方、電磁場は、原始ヒッグス場の上の「仮想光子&変形している“4面体”」の総和として創発する。
|
(万有引力の法則や一般相対性理論を担う)
重力場
|
(クーロンの法則を担う)
電場と磁場
|
|
どこで創発するか
|
ともに、
「原始ヒッグス場」の上で創発する
|
|
何によって創発するか
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」
の総和として
|
「仮想光子&変形している“4面体”」
の総和として
|
※「原始ヒッグス場」とは、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和のことである。
原始ヒッグス場の上で、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」を創発するものは、あくまで“仮想光子”の総和であり、“光子”の総和ではない。 “光子”の総和が創発するものは、電磁波である。
「電磁波を担う(構成する)“光子”」の中の素スピノールが転回する際に生じる「ミクロの電場やミクロの磁場」の向きは、下のようなルールに従っているのだった。
※左巻き素スピノールが転回する向きに対して、左ねじの方向に磁場が生じている。
右巻き素スピノールが転回する向きに対して、右ねじの方向に磁場が生じている。
※“左巻き素スピノールの軌道運動の方向”が転回していく向きと、同じ向きに電場が生じている。
“右巻き素スピノールの軌道運動の方向”が転回していく向きと、逆向きに電場が生じている。
※なお、光子が(上図のように)作る「ミクロの電場やミクロの磁場」は、あくまで電磁波を担っているものであり、クーロンの法則を担うことはない。
|
それに対して、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」の創発を支える1つ1つの“仮想光子”が生じるミクロの電場や、ミクロの磁場の振る舞いについては、次のような仮説を立てることができる。
仮説1.7 振動数ν、波長λ(=c/ν)の仮想光子は、電荷を構成する素スピノールと、電荷からλ/2の距離だけ離れた「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”」を構成する素スピノールのペアが、スピン1を保ちながら、180度共転回することによって進み、もう一度、共転回することによって元に戻るものに相当する。
※仮想光子の場合、ふつうの電磁波の光子と違い、“放出源に戻る”という性質を持つので、
仮想光子の進行方向が、 『 → ← 』のように途中で逆転している様子が図示されている。
※共転回した方向とは逆方向に共転回することを、逆転回と呼ぶこととする。
この逆転回は、上図の左側においてのみ生じている。 右側では、逆転回はしておらず、仮想光子の進行方向のみが逆転している。
※上図で示されているように、仮想光子の進行方向が前半と後半で逆転するとともに、ミクロの電場やミクロの磁場のどちらか一方も途中で逆転する。 よって、ミクロの電場やミクロの磁場が逆転していない方、すなわち、「左図の電場」や「右図の磁場」がそれぞれマクロの電場や、マクロの磁場の創発に役立つことになる。
※なお、これらのいずれの過程においても、やはり、仮想光子の進行方向について『右ネジの法則』が成立している。
|
|
『〜光の進行方向を表すベクトルと電気・磁気ベクトルは、たがいに「右ネジの法則」の関係にあることがわかっている。 〜電気ベクトルから磁気ベクトルに向けて右ネジをまわす(時計まわりにする)と、ネジの進む方向が光の進行方向(〜)に一致する。』
(『対称性から見た物質・素粒子・宇宙 鏡の不思議から超対称性へ』(広瀬立成 講談社ブルーバックス)p69-70より
(下線および一部省略は、筆者による))
|
以後、このように、光子や仮想光子が、プランクスケールで生ずる「ミクロの電場」と「ミクロの磁場」のことを、簡単に、ミクロ電場、ミクロ磁場と呼ぶこととする。
それに対して、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」は、厳密には「マクロの電場」や「マクロの磁場」と呼ぶべきものであり、必要に応じてそのように呼ぶこととする。 マクロの電場やマクロの磁場は、ミクロ電場やミクロ磁場の総和として創発する。
※ミクロ電場とミクロ磁場は、常に同時に生じていることになる。
この常に同時に生じているはずのミクロ電場とミクロ磁場が、複数(多数)、うまい具合に配置されたときにはじめて、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」(「マクロの電場」や「マクロの磁場」)が創発すると考えられる。
そういう意味では、マクロの電場が創発するか、マクロの磁場が創発するかは、“紙一重である”とも言える。
※以上のモデルは、電場と磁場が、常に互いに“直角に存在する”ことを、ピッタリと説明できる。
この電場と磁場が“直角に存在する”ことにより、例えば、アンペールの法則(電流の周りに磁場が生じる)や、ファラデーの法則(磁場の変化に伴い電場が生じる)も、うまく説明できる。(→結果2)
※「電荷を構成する素スピノール」という記述は、電荷が複数の素スピノールから創発するものであることによる。
(具体的には、「最も小さい“電荷”」とは、(3つの素スピノール(左巻きのみor右巻きのみ)から創発する)荷電プレオン∴である。(→結果2)
そして、この「最も小さい“電荷”」荷電プレオン∴の一種であるマイナスプレオン3つから電子が創発する。 (→結果2))
※この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)における仮想光子のモデルは、次のような記述で示される状況に対して、1つの答え(解決案)を提供していることになる。
|
『仮想光子は何らかの計測器で直接検出されることが期待されるが、その概念は定まっておらず、またその存在を証明するのはきわめて困難である。事実、仮想光子は、きわめて抽象的な状態にとどまり、いまだ確かになっていない理論の産物である』
(p.127 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』 Eugene Hecht著、尾崎義治・朝倉利光訳 丸善株式会社
下線は筆者による)
|
|
『“すべての物理学者は光子が何であるか知っていると思っている”とアインシュタインは書き、さらに“私は光子とは何であるのかの問題に答を見いだすのに一生を費やしたが、いまだにわからない”と続けている』
(p.10 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』)
|
ここで、仮想光子と光子を比較して整理すると、次のようになる。
|
仮想光子
|
光子
|
|
1つ1つが創発するもの
|
(どちらか一方は打ち消されてしまうような)
ミクロ電場、ミクロ磁場
|
(どちらも打ち消されないまま次々と移動していく)
ミクロ電場、ミクロ磁場
|
|
総和(集合)が創発するもの
|
マクロの電場やマクロの磁場
|
電磁波
|
|
進み方
|
電荷から放出されλ/2だけ進み、
λ/2引き返して、電荷に戻る。
|
λの1/2ずつ、
次から次へと遠方へ進み続ける
|
|
速さ
|
光速
|
|
しくみ
|
「電荷の中の素スピノール」と
「原始ヒッグス場ユニットの
中の素スピノール」のペアにおける
スピン1を保った共転回(or逆転回)
|
(2つの)「原始ヒッグス場ユニットの
中の素スピノール」のペアにおける
スピン1を保った共転回
|
厳密に言えば、「ミクロ電場」や「ミクロ磁場」は、決して、「個々の素スピノールのペア」だけから生じるわけではない。
すなわち、あくまで、「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”」の中の、特定の素スピノールが転回することによって生じる「変形している“4面体”」がミクロ電場やミクロ磁場を生むのである。
※ミクロ電場やミクロ磁場は、「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形」として創発するのである。
実際は、「変形し続けている“4面体”」によって、ミクロ電場やミクロ磁場が生じている。(すなわち、ミクロ電場、ミクロ磁場は、変化し続けている)
それらの「変形し続けている“4面体”」を、上図のような「変形中の直方体」で図示することとする。
こうすると、電場と磁場の関係がわかりやすくなるので便利である。(ミクロ電場とミクロ磁場が必ず直交するのでこのようなことができる)
なお、上の「変形中の直方体」の図の中の電場や磁場のベクトルは、当然、時間tを横軸にした図のような経過で“変化し続けている”ことになる。
だからこそ、 「仮想光子&変形した“4面体”」ではなく、「仮想光子&変形している“4面体”」と記述していることになる。
そして、「マクロの電場やマクロの磁場」は、「ミクロ電場&ミクロ磁場の総和」(=「変形している“4面体”」の総和)として、創発されるのである。
|
以上をふまえ、仮想光子において、ミクロ電場やミクロ磁場が、どのように創発するかを示す。
※「仮想光子の場合は、(電磁波を構成する光子と違い)“放出源に戻る”という性質を持つ」ということを反映している図が示されている。
※上図のように、電場や磁場のどちらか一方が、前半と後半で逆転することにより、仮想光子の進行方向についても『右ネジの法則』が保たれていることが、「仮想光子が持つ“放出源に戻る”という性質」を支えているのであった。
※上図の左側の「180度の転回&180度の逆転回」の方は、ミクロ磁場のみが時間経過とともに打ち消し合っている。よって、この「180度の転回&180度の逆転回」のタイプの「仮想光子&変形している“4面体”」が数的に優位になっている場合、マクロの電場が創発していることになる。
逆に、右側の「180度の転回×2」の方は、ミクロ電場のみが時間経過とともに打ち消し合っている。この「180度の転回×2」のタイプの「仮想光子&変形している“4面体”」が数的に優位になっている場合は、マクロの磁場が創発していることになる。 |
こういった仮想光子の所産であるミクロ電場やミクロ場を組み合わせることで── (クーロンの法則を担う)「電場や磁場」を含めて、様々な“マクロの電場”や“マクロの磁場”の創発を説明できる。
さらには、電荷が生む“仮想光子”についての仮説に加えて“電荷が運動すると仮想光子がどうなるか”を考慮することで、アンペール-マクスウェルの法則やファラデーの法則を説明できる。
(詳細は、結果2で説明する)
つまり、あらゆる「マクロの電場やマクロの磁場」は、「ミクロ電場&ミクロ場の総和」(=「仮想光子&変形している“4面体”」の総和)として創発すると説明できるのである。
※仮説1.7をより厳密に書けば、電子を構成する左巻き素スピノールと、(周囲の、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の中の)“右巻き素スピノール”は、ペアを作って共転回することで、仮想光子を生じる、ということになる。
(電子が左巻き素スピノールのみで構成されていることについての詳細は、結果2にて述べる。
要約して書けば、「電子は、“左巻き素スピノール3つから構成されるマイナスプレオン∴”が、3つ集まっているものである」ということになる。(→結果2))
《静電気力(電荷のクーロンの法則)のEMOES表記と電荷エネルギー
(および、磁力(磁極のクーロンの法則)のEMOES表記と磁極のエネルギー)》
ニュートンの万有引力の法則(F= F=GMm/r2[N])の“EMOES表記”が可能であったように、電荷や磁極のクーロンの法則(F=kQq/r2=Qq/4πε0r2[N]、 F=m1m2/4πμ0r2[N])についても“EMOES表記”が可能である。
以下では、まず、電荷のクーロンの法則にしぼって、説明を進める。
電荷のクーロンの法則を担う電場(厳密には、マクロの電場)は、「(静止している)電荷から放出&再吸収される仮想光子が、個々の原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)を変形させて、ミクロ電場を作ること」の総和として、原始ヒッグス場の上で創発すると考えられる。
※上記のように、原始ヒッグス場(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の変形によってミクロ電場が生じる。
このミクロ電場の総和として、電荷のクーロンの法則を担う電場(マクロの電場)が創発する。
なお、ミクロ磁場は、逆転しているので── マクロレベルで、電場のみが存在するかのように(磁場が全く存在しないかように)、観測される(自然(nature)がふるまう)ことになる。
|
一般的な仮想光子は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”を、(原則として)部分的に(途中まで)変形させているだけである。
※例えば、「波長が2LPの仮想光子」を考えるならば、例外的に、“4面体”を完全に変形させると言える。 ただし、その実体は、一般的な仮想光子と異なっている。 それを“LP光子”と呼ぶ。(→結果2)
この(一般的な)仮想光子が部分的に変形させ続けて生じている“4面体”、すなわち、“部分的に縮んでいるバネ”の方を、「変形している“4面体”」と呼ぶのであった。
それは、重力子が“4面体”を完全に変形させて生じているもの、すなわち、“完全に縮んでいるバネ”の方を、「“4角形”(縮みきったバネ)」と呼ぶのとは、対照的である。
重力子によって生じる“4角形”(縮みきったバネ)の方が、一定の時間、同じ状態を保つのに対して── 仮想光子による「変形している“4面体”」の方は、常に状態を変動させ続けることは、図から読み取れる。 そして、だからこそ、「変形した“4面体”」ではなく、「変形している“4面体”」と呼ぶのであった。
|
「“4角形”(縮みきったバネ)」
|
「変形している“4面体”」
|
|
何によって生じるか
|
重力子
|
仮想光子
|
|
“4面体”の変形
|
“4面体”を完全に変形
|
“4面体”を部分的に変形
|
|
状態の時間経過
|
一定の時間、同じ状態を保つ
|
常に状態を変動させ続ける
|
この仮想光子によって生じる「変形している“4面体”」の総和は、どのようにして(電荷のクーロンの法則を担う)電場(厳密には、マクロの電場)を創発するであろうか?
まず、(電荷のクーロンの法則を担う)電場(マクロの電場)の場合も、(重力場のときと同様に)“厚さ2Lp[m]の球殻”を考えてみよう。
※電荷についても、質量と同様に、上のように球殻の半径を定義できる。
やはり、話を簡単にするために、「変形している“4面体”は、すべて、ちょうど2LP[m]の厚さに収まっている」と考えることとする。
厳密には、やはり、本来は、“厚さ2LP[m]の球殻”は、想像上の球殻に過ぎず、“変形した“4角形”が、2つの球殻に“またがる”ことも考えられるので(位置が、球殻の枠からLP[m]程度ずれることも考えられるので)、このような考え方は、“凸凹なデジタル球面”を滑らかな球面として、近似的にとらえているものにすぎないことになる。 (詳細な検討は、今後の課題である)
|
次に、ある「厚さ2LP[m]の球殻」の中に存在する1つの「変形している“4面体”」が持っているエネルギーの平均値がどのような値になるかを考えてみよう。
一般に、共転回する素スピノールのペアの間の距離r[m]は、(仮想)光子の波長λ[m]を使って表記すると、r=λ/2[m]となるので── r=2nLP[m]にある原始ヒッグス場ユニットの“4面体”を変形する仮想光子の波長λは、λ/2=2nLP[m]より、λ=4nLP[m]と決まる。
よって、ある電荷から放出された仮想光子によって、その電荷の中心から r=2nLP[m]離れたところにある「厚さ2LP[m]の球殻」の中に存在する、1つの「変形している“4面体”」(部分的に縮んだバネ)が持つエネルギーは、最大値EmaxがEmax=hν=hc/λ=hc/4nLP[J]のサインカーブとなる。(c=λν[m/s]、λ=4nLP[m]を使った)
なお、その「“4面体”の変形」の周期(“変形周期”と呼ぶこととする)は、仮想光子を構成する素スピノールの“転回周期”、あるいは、光子(光の量子波)の振動周期と等しく、ET=hの関係を使うことによって、T=h/Emax=h×(4nLP/hc)=4nLP/c[s]と決まる。
したがって、1つの仮想光子が、その電荷の中心から r=2nLP[m]離れたところにある「厚さ2LP[m]の球殻」の中の1つの“4面体”にもたらす変形における「エネルギー変化の平均値」は、下図からわかるように(グラフの対称性によって)、単純に「“4面体”の変形に伴うエネルギーの最大値Emax」×1/2=hc/8nLP[J]と決まることになる。
※エネルギーの変化は、サインカーブであるので、赤い斜線部分のペアと、オレンジの斜線部分のペアが、それぞれ面積が全く等しい。
したがって、平均エネルギーは、「エネルギーの最大値」の1/2となる。 |
この「ある1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が蓄えるエネルギーの時間平均」の総和の空間的な平均として、“力”に寄与する“原始ヒッグス場抵抗”の減少、すなわち、クーロンの法則を担う電場(マクロの電場)が創発すると考えられる。
ところで、ある質量は、いずれの「厚さ2LP[m]の球殻」の中に、(時間平均で)同じ大きさのエネルギーを蓄えさせる結果、その空間平均として、重力場を創発するのであった。
よって、同様に、ある電荷は、いずれの「厚さ2LP[m]の球殻」の中にも(時間平均で)同じ大きさのエネルギーを蓄えさえすれば、その空間平均として、クーロン力を担う電場(マクロの電場)を創発することが予想される。
なぜなら、厚さ2LP[m]の各球殻が蓄えるエネルギーは「原始ヒッグス場抵抗の減少」を意味しているので、これが(重力と同様に)電気力(電荷のクーロン力)の実体に相当すると考えられるからである。
よって、次の仮説を仮説を立てた。
仮説1.9.1 ある電荷Q[C]は、いずれの「厚さ2LP[m]の球殻」の中にも、(時間平均で)同じ大きさのエネルギーを蓄える結果、その空間平均として、クーロンの法則を担う電場(マクロの電場)を創発する。
ところで、ある質量M[kg]からは、“重力線”が出ていると考えられ、“重力線”の密度(≒“重力線”の球面密度)は、重力の大きさに等しいのだった。
(すなわち、“重力線”の本数を球面積S=4πr2[m2]で割ると、重力になるのだった)
※“重力線”である
“重力線”の球面密度は、重力場の大きさ(重力の大きさ)に等しい。
※一方、厚さ2LP[m]の各球殻は、 r=2nLPの大きさに関わらず(時間平均で)どれも等しいエネルギーを持っている結果、その空間平均として、重力場が創発するのだった。
そして、その空間平均を計算する際の分母は、近似的に「球面積S×厚さ(2LP)」=4πr2×2LPであった。
したがって、“重力線”の本数と、「厚さ2LP[m]の各球殻が蓄えるエネルギーの時間平均」、すなわち、(各重力子が“2つの球殻にまたがって”おらず各球殻の中に収まっている場合の)厚さ2LP[m]の各球殻に存在する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数は、ほぼ比例することになる。
|
|
一方、ある電荷Q〔C〕からは、“電気力線”が出ていると考えられるのだった。(これは、力線の本家本元、ファラデーの成果に他ならない)
※電気力線である。
電気力線の球面密度は、静電場の大きさ(電気力の大きさ)に等しいのだった。
(すなわち、電気力線の本数を、球面積S=4πr2[m2]で割ると、静電気力(電荷のクーロン力)になるのだった)
一方、電荷Q〔C〕が「厚さ2LP[m]の各球殻に蓄えるエネルギーの時間平均」の空間平均が、静電場(電気力、電荷のクーロン力)の実体に相当すると考えられる。(原始ヒッグス場抵抗の減少をもたらすからである)
そして、その空間平均を計算する際の分母は、近似的に「球面積S×厚さ(2LP)」=4πr2×2LPである。(下記で説明する)
したがって、この電気力線の本数と「厚さ2LP[m]の各球殻が蓄えるエネルギーの時間平均」は、ほぼ比例していることになる。
|
|
そして、「電気力線の本数」と「厚さ2LP[m]の各球殻が蓄えるエネルギーの時間平均」は、ほぼ比例しており、しかも、どの「厚さ2LPの球殻」においても、貫く「電気力線の本数」は同じである。
このことは、「厚さ2LPの各球殻が蓄えるエネルギーの時間平均」は、電荷からの距離(r=2nLPの大きさ)に関わらず、ほぼ一定であるということに他ならない。
つまり、電気力線を考えることができるということは、『仮説1.9.1 ある電荷Q[C]は、いずれの「厚さ2LP[m]の球殻」の中にも、(時間平均で)同じ大きさのエネルギーを蓄える結果、その空間平均として、クーロンの法則を担う電場(マクロの電場)を創発する』と調和しているのである。
※電気力線を考えることができるということは、ある電荷Q[C]の中心からの任意の距離にある「厚さ2LPの球殻」において、同じ本数の電気力線が出ていることを意味する。
つまり、この仮説1.9.1は、電場のガウスの定理(マクスウェルの4つの方程式の1つ)とも調和しているのである。
ガウスの定理とは、次のようなものである。
|
『ある任意の閉曲面から外にでる電気力線の数は、その閉曲面の中の電荷の総和の1/ε0倍に等しい』
(p.11 電気磁気学 石井良博 コロナ社)
|
ところで、“重力線”の本数と、(各重力子が各球殻の中に収まっていると考えた場合の)厚さ2LPの球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数は、ほぼ比例しているのだった。
(この(各重力子が各球殻の中に収まっている場合の)厚さ2LPの球殻に存在する「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数をNM〔個〕とすると、“重力線”の本数は、NM×2c2LP[本](≒NM×2.9×10-18[本])となるのだった)
それでは、電気力線の本数と、厚さ2LP[m]の球殻に存在する「変形している“4面体”」の個数は、ほぼ比例しているのだろうか?。
すなわち、ある電荷Q[C]が「厚さ2LP[m]の球殻内で&1秒間で変形させている“4面体”の個数」は、どの球殻でも((r=2nLPにおける)nの大きさに関わらず)同じだろうか?
このことは、「ある電荷Q[C]を取り囲む厚さ2LP[m]の各球殻は、どのようなしくみで(なぜ)等しいエネルギーを蓄えるのか?」、「どのようなしくみで(なぜ)、(電場の)ガウスの定理が成り立つのか?」とも関連した重要なテーマである。
このテーマについての説明は、次のようになる。(「静電気力(電荷のクーロンの法則)のEMOES表記」の本流から外れたテーマなので別枠で示すこととする)
|
ある厚さ2LP[m]の球殻の中に存在する、ある1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”は、必ずしも、ずっと絶え間なく変形を繰り返しているわけではないこと、すなわち、変形している時間と変形していない時間があることを考慮しよう。 (以下、“4面体”とは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”のことを指すこととする)
そこで、まず、r=2nLP[m]の球殻の中に存在する、ある1つの“4面体”が、「1回だけ変形している間に蓄えるエネルギーの、1秒間での時間平均(平均値)」を求めてみよう。 それは、次の式によって求められる。
「 r=2nLP[m]の球殻の中に存在する、ある1つの“4面体”が、1秒間に1回だけ変形している間に蓄えるエネルギーの1秒間での時間平均(平均値)E」
= 「r=2nLP[m]にある、1つの“4面体”の1回の変形に伴うエネルギーの最大値Emax」×1/2」
ד4面体”が変形している時間(=転回周期)」/(「その“4面体”が変形している時間(転回周期)+“4面体”が変形していない時間)(=1秒)
+「0」×「“4面体”が変形していない時間」/(「その“4面体”が変形している時間(転回周期)+“4面体”が変形していない時間)(=1秒)
=(hc/8nLP)[J/回]×(4nLP/c)[s]×(1/1)[1/s]
=h/2 [J/回]
つまり、「ある1つの“4面体”が、1回だけ変形している間に、蓄えるエネルギーの変形周期の間での時間平均(平均値)」がたとえそれぞれ異なっていても── 「ある1つの“4面体”が、1回だけ変形している間に蓄えるエネルギーの、1秒間での時間平均」を考えると、それらは、どれもが等しくなるのである。
そのことは、例えば、下図からも読み取れる。 いずれも「1秒間の平均」を求めると等しくなることがわかる。
※4週類の、オレンジの長方形の高さは、「“4面体”に蓄えられるエネルギーの“転回周期の間(変形している時間内)”での時間平均」を表し、それぞれ異なっている。(それぞれの最大値の1/2である)
それに対し、「1秒間での“4面体”に蓄えられるエネルギーの時間平均」は、「変形していない時間」も考慮すると── すべて、一番下のオレンジの長方形の高さのように統一される。
※なお、オレンジの長方形の面積は、4種類とも、すべて等しく、h/2[J/回]に相当している。 |
以上の考察から、 次の結論に至る。
結論1.6.1「波長4nLPの1つの仮想光子が、r=2nLPの球殻の中の、ある1つの“4面体”を1回だけ変形する間に、その“4面体”に蓄えられるエネルギーE」の1秒間での時間平均は、nの値に関わらず一定の値 h/2[J/回]になる。
したがって、1秒間にν[個]の仮想光子が、ある厚さ2LP[m]の球殻中の“4面体”を、ν[回]変形する場合── 「厚さ2LP[m]の球殻全体」の中に蓄えられる“エネルギーEの1秒間での時間平均”は、それは、次のように計算され、nに関わらず一定であることになる。
ν×h/2 [J]
例えば、1秒間にν= 3 [回]の場合、下図のようになる。
※1秒間にν=3[回]の場合を図示した。
1秒間での時間平均は、それぞれ同じ値として求められるので、それらをν=3倍すれば、全体の時間平均が計算できることがわかる。
つまり、それは、3×h/2[J]である。
|
したがって、「ある電荷Q[C]の中心からr=2nLP[m]離れた場所にある厚さ2LP[m]の球殻全体が持っているエネルギーの総和の、1秒間での時間平均」は、やはり、h/2[J/回]×「その電荷Q[C]が、その球殻内で&1秒間で“4面体”を変形している回数ν[回]」、すなわち、h/2× ν[J]で求まるのである。
1秒間で、厚さ2LP[m]の球殻全体中で、どの“4面体”が、どのタイミングで変形するかは、ランダムであると考えられる。
(厳密には、決定論的カオスによって、ランダムになると考えられる。→結果4)
しかし、ν[回]が十分に大きい場合は、ある厚さ2LP[m]の球殻全体が持つエネルギーの1秒間での時間平均は、時刻によらず、一定だと見なせると考えられる。
以上より、1秒間で“4面体”を変形している回数ν[回]が十分に大きい場合、「ある電荷Q[C]が、厚さ2LPの球殻全体内で&1秒間で“4面体”を変形させている回数ν[回]」が、どの球殻でも同じでありさえすれば、「厚さ2LP[m]の球殻に、常に蓄えられているエネルギー」は、どの球殻でも((r=2nLP[m])におけるnの大きさに関わらず)、常に一定となることがわかる。
よって、次の結論に至る。
結論1.6.2 十分に大きい電荷Q[C]において、「厚さ2LP[m]の球殻内で&1秒間で“4面体”を変形させているの個数ν[個]」が、どの球殻においても((r=2nLP[m]における )nの大きさに関わらず)同じになるというしくみによって、厚さ2LP[m]の各球殻は、等しいエネルギーを持つ。
結論1.6.3 十分に大きい電荷Q[C]が作る電気力線の本数と、厚さ2LPの球殻に存在する「変形している“4面体”」の個数は、ほぼ比例している。
整理すると次のようになる。
|
荷量
|
質量M[kg]
|
十分に大きな電荷Q〔C〕
|
|
力線の本数
|
(各重力子が各球殻の中に収まっていると考えた場合の)
厚さ2LP[m]の球殻に存在する
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の
個数NM[個]と、ほぼ比例
NM×2c2LP[本]
(≒NM×2.9×10-18[本])
|
厚さ2LP[m]の球殻に存在する
「変形している“4面体”」の個数ν[個]と、ほぼ比例
|
|
厚さ2LP[m]の球殻が持つエネルギー
|
Mc2[J]=NMEG[J]
|
h/2× ν[J]
|
これらの結論は、「どのようなしくみで(なぜ)、厚さ2LP[m]の各球殻は、r=2nLp[m]におけるnの大きさに関わらず、どれも等しいエネルギーを持っているのか」のみならず、「どのようなしくみで(なぜ)、(電場の)ガウスの定理が成り立つのか」の説明の一部を担いうるものである。
そして、その説明は、次のようになるだろう。
電荷、すなわち、仮想光子の放出源として働く能力が保存され、どの球殻にも、1秒間に同じ数だけ「変形している“4面体”」を生じさせるからこそ、どの球殻にも、同じエネルギーを蓄えることができる。
そもそも「どの球殻にも、同数の「変形している“4面体”」を生じさせる」理由は、やはり、先にも触れたように、「“素電荷(荷電プレオン)および、それを構成する素スピノール”が持つ“決定論的カオスが生むランダムな運動”」と「仮想光子の波長λ[m]、エネルギーE[J]が、転回周期T[s](仮想光子の滞在時間(寿命))が、確定的に決まるという性質」の2つであると考えられる。
これらの理由から、自然に(必然的に)、ガウスの定理が成立するような“マクロの電場”を生じるのだ。
(詳細な検討は、今後の課題である)
|
|
さて、電荷のクーロン力を量子化するのに先立ち、重力の場合に「ある質量M[kg]が、重力子質量MG[kg]の何個分か」を考えたように── 電荷のクーロン力の場合にも、「ある電荷Q[C]が、ある基準となる電荷[C]の何個分か」を考えていく。
ある基準となる電荷として何がふさわしいか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、その基準となる電荷を、『各「厚さ2LP〔m〕の球殻」に、1秒間の時間平均で、hc/4LP[J]のエネルギーを蓄えるような電荷』と定義し、これを“当量電荷”と呼び、QE[C]と表記することとする。
この『hc/4LP[J]』のエネルギーは、(h/2)×(c/2LP)[J]の計算から導いたものである。
1秒間にc/2LP〔個〕の“4面体”を変形させるという頻度には、もし、「当量電荷QE[C]の大きさの電荷を持つ“仮想的な荷電粒子”」を考えれば、下図のように、n=1に相当する最も内側の球殻(r=2LPにある厚さLP[m]の球殻)に、絶え間なく、1つの“4面体”だけを変形させ続けることができる、という意味がある。
 |
※なお、実際は、例えば、最内殻を変形する、波長2LPの仮想光子は、LP光子に他にならず、ふつうの仮想光子とは、異なったふるまいをすると考えられる。(→結果2)
したがって、この図は、「当量電荷QE[C]」の意味を説明するためだけの仮想的な(便宜的な)図である。
以下、この図が、「当量電荷QE[C]」の意味を説明するためだけの仮想的な(便宜的な)図であることを前提とした上で、この図を説明していく。
※この図の中のオレンジ色の“4角形”は、「変形している“4面体”」を示している。
(一方、重力子が生む「“4角形”(縮みきったバネ)」は、紫色であった。 便宜上、この色の違いによって、両者を区別していくこととする)
なお、この図の場合も(重力子の場合と同様に)、実際は、3Dの球殻に存在するものを、便宜上、2Dの“円殻”の中に図示していることになる。
※ピンクの破線が中心からの距離が、r=2nLP [m]である位置を示す。
ピンクの破線の、LP[m]だけ内側の球面とLP[m]だけ外側の球面の間が、厚さ2LP[m]の球殻に相当する領域である。
r=2nLP のnの値が大きいほど、変形周期T=4nLP/c[s]、すなわち、「変形している“4面体”」の存続時間が長くなるので── ある時点(瞬間)での、「変形している“4面体”」の存在数は、nの大きさにおおよそ比例して多くなることになる。
その様子を示すと、下図のようになる。
※r=2nLPにおいて、n=1、2、3の場合を示している。 いずれも、c/2LP〔回/s〕の頻度で、“4面体”を変形させているだけなのに、エネルギーの合計幅(オレンジの長方形の幅)は、いずれも等しくなっており、『仮説1.9.1 ある電荷Q[C]は、いずれの「厚さ2LP[m]の球殻」の中にも、(時間平均で)同じ大きさのエネルギーを蓄える結果、その空間平均として、クーロンの法則を担う電場(マクロの電場)を創発する』と調和していることがわかる。
(このようなことが起こるのは、「c=λν=λ/T=4nLP/Tにもとづいてr=2nLPのnの値と周期Tが比例している」「ET=hにもとづいて、エネルギー振幅Eと周期Tが反比例している」という確定的な関係が存在するからである)
|
|
このような関係は、当然、n=30、50、70、100… でも、同様に成り立つと考えられる。
つまり、r=2nLP[m]にある厚さ2LP[m] の球殻において、例えば、n=1なら1[個]、n=2なら2[個]、n=3なら3[個]、n=30なら30[個]、n=100なら100[個]、n=300なら300個… というように比例して、ある瞬間に(同時に)「変形している“4面体”」の数が決まることになる。
このような関係があるからこそ、(『「厚さ2LP[m]の球殻内で&1秒間で“4面体”を変形させているの個数ν[個]」が、どの球殻においても((r=2nLP[m]における )nの大きさに関わらず)同じになる』&『(r=2nLP[m]における )nの大きさに反比例して、エネルギーが小さくなる』という条件においてさえ、)
厚さ2LP[m]の球殻で蓄えられるエネルギーは、どれも等しくなるのである。
※なお、上図は、もし、「当量電荷QE[C]を持つ荷電粒子」が半径LP[m]の球面の中におさまるほどよりもコンパクトであるという仮定のもとに図示されているという意味においても、「当量電荷QE[C]」の意味を説明するためだけの仮想的な(便宜的な)図であると言える。
すなわち、上図のような荷電粒子は、実際は、実在はしないと考えられる。 なぜなら、計算により、当量電荷QE[C]は、およそ電子5.8個分の電荷に相当するからである。(計算は、後の説明で示す)。 このことは、「当量電荷QE[C]を担う実体」は、実際は、半径LP[m]の球面より、ずっと大きいことを意味する。
※厳密には、上図のような「当量電荷QE[C]」の説明は、少なくともn≧20の場合、すなわち、少なくとも半径40LP[m]の球面の外側についてのみ、成立することになると考えられる。 それは、下の理由による。
波長 2LP[m]≦λ≦38LP[m]の光子が、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”を変形させるエネルギーは、hc/38LP≦E≦hc/2LPであり、いずれも、重力子エネルギーEG=hc/(2π)2LPよりは、大きくなっている。
(r=λ/2であるので、2LP[m]≦λ≦38LP[m]とは、LP[m]≦r(=2nLP)≦19LP[m]ということ、すなわち、0.5≦n≦9.5(1≦n≦9)の球殻の中に生じる変形している“4面体”が蓄えるエネルギーEが、重力子エネルギーEGよりも大きくなっている)
したがって、波長が、2LP[m]≦λ≦38LP[m]の仮想光子は、ふつうの仮想光子とは、異なった振る舞いをすると考えられる。
例えば、少なくとも、波長2LP[m]の場合、原始ヒッグス場ユニット(PHU)19個分に増幅すると考えられる。
(これが、「LP光子の集積したひも」に相当する。 →結果2)
そして、波長20LP〜38LP[m]の場合は、増幅せず、ふつうの仮想光子と同等にふるまうと考えられるが──
例えば、波長4LP[m]の場合、原始ヒッグス場ユニット(PHU)9個分、波長8LP[m]の場合原始ヒッグス場ユニット(PHU)4個分、波長14LP〜19LP[m]の場合原始ヒッグス場ユニット(PHU)個分というように増幅するかもしれない。(詳細な検討は、今後の課題である)
いずれにせよ、波長2LP[m]の場合に、原始ヒッグス場ユニット(PHU)19個分に増幅する以上、「(ふつうの仮想光子とは異なった振る舞いをする)増幅する仮想光子」の影響は、半径38LP[m]の球面までおよぶことになる。
したがって、もし、電子5.8個分(マイナスプレオン17.4個分)が、半径40LP[m]の球面の中に収まるのならば、上の図にような「当量電荷QE[C]」の説明は、n≧20の場合、すなわち、半径40LP[m]の球面の外側についてのみ、成立することになると考えられる。
もし、電子5.8個分(マイナスプレオン17.4個分)が、半径40LP[m]の球面の中に収まらないのならば、さらに大きな球面の外側でのみ成立することになると考えられる。 (詳細な検討は、今後の課題である)
|
|
よって、厳密には「少なくともn≧20の場合」というのが正確であるが、便宜上、以下で、「n≧20」と統一して表記していくことといる。
|
当量電荷QE[C]とは、(厚さの2LP[m]の)各球殻における原始ヒッグス場ユニット(PHU)を変形する頻度が、1秒間に“ν=c/2LP”[回]であるという電荷である。
ν=c/2LP≒3×108/2×1.6×10-35≒0.9375×1043[個]であるので、この頻度は、非常に大きい。
※なお、重力子質量MG[kg]とは、1秒間に“4面体”から“4角形”(縮みきったバネ)への変形を、c/2LP[回]の頻度で達成できる質量であった。
しかし、ある瞬間に(同時に)存在する「変形している“4面体”」の個数は、r=2nLPにある「厚さ2LP[m]の球殻」あたり、n[個]である。
すなわち、r=2nLPにある「厚さ2LP[m]の球殻」は、ある瞬間に(同時に)n個の「変形している“4面体”」を持っていることになる。
そうすると、例えば、1〔m〕の距離でも、1=2nLPより、n≒3.1×1034〔個〕も、同時に共転回する必要があるということになる。
※当量電荷QE[C]は、およそ電子5.8[個]分、すなわち、マイナスプレオン17.4[個](≒5.8×3[個])分に相当する。(→結果2)
そして、プレオン∴は、素スピノール3つでできているので(→結果2)、当量電荷QE[C]は、素スピノール52.2個(≒17.4×3[個])個に相当することになる。
「素スピノール52.2個」だけでは、例えば、0.001〔m〕(1ミリメートル)の距離の球殻に対して、ある瞬間に(同時に)共転回する必要がある個数、n≒3.1×1031〔個〕には、とても足りないのである。
したがって、(「素スピノール52.2個」で構成されている)当量電荷QE[C]は、ある瞬間に(同時に)、例えば、n≒3.1×1031〔個〕と、共転回できる何らかのしくみ(からくり)、各球殻に存在する“4面体”を変形できるしくみ(からくり)を持っているはずであることがわかる。
|
ある瞬間に(同時に)「変形している“4面体”」の個数が、r=2nLP[m]における球殻で、n[個]である一方、当量電荷QE[C]は、「素スピノール」たった52.2個だけで構成されていて、その絶対数が足りないという問題を解くしくみ(からくり)とは次のようなどのようなものだろうか?
そのしくみ(からくり)として最も有望なものの1つは、「電子」や「(電子を構成する)マイナスプレオン」は、それぞれ波動性を持ち、それぞれに電子ヒッグス場、プレオン∴ヒッグス場と相互作用していることである。(→結果3、4) なぜなら、電子やマイナスプレオンが、振動数νe〔回/s〕やν∴〔回/s〕の頻度で波動性を持つならば、同じ頻度で、次々と新しい電子やプレオン∴に切り替わることになるので、ある瞬間に(同時に)に共転回できる素スピノールの数が、格段に増える(増幅する)と考えられるからである。
(振動数νe〔回/s〕やν∴〔回/s〕の具体的な数値を含め、詳細な検討は、今後の課題である)
しかし、このしくみ(からくり)だけを考慮したとしても、ある瞬間に(同時に)多数の共転回を達成する能力には限界があるはずであり、その能力が直接に無限遠方まで働くことはあり得ないと思われる。
このことは、「電子ヒッグス場やプレオン∴ヒッグス場を介して、とびとびで遠方に作用していくことによって可能になっている」という新たなしくみ(からくり)を考えるべきことを示しているのだろうか? それとも、そもそも、「静電気力が作用できる範囲は実は有限であり、無限遠方ではない」と考えるべきことを示しているのだろうか?(なお、現実的には、無限遠方まで働く静電気力を観測することは不可能ある) それとも、他に考えるべきことがあることを示しているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
|
『仮説1.9.1 ある電荷Q[C]は、いずれの「厚さ2LP[m]の球殻」の中にも、(時間平均で)同じ大きさのエネルギーを蓄える結果、その空間平均として、クーロンの法則を担う電場(マクロの電場)を創発する』、および、『各「厚さ2LP〔m〕の球殻」に、1秒間の時間平均で、hc/4LP[J]のエネルギーを蓄えるような電荷』という当量電荷QE[C]の定義により──
一般に、 Q[C]の電荷は、NQ[個]の当量電荷QE[C]から構成された電荷と見なすことができて、Q=NQQE[C](NQ=Q/QE[個])と表記できて、Q[C]の電荷が、各「厚さ2LP[C]の球殻」に蓄えさせられるエネルギーの1秒間での時間平均は、NQ×hc/4LP[J](NQ=Q/QE[個])となる。
当量電荷QE[C]が生じる静電気力(電荷のクーロン力)を求めていくにあたり── 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が蓄えるエネルギー(=原始ヒッグス場抵抗の減少量)の時間での平均値のみならず、なおかつ、空間での平均値を求めなければならない。
なぜなら、1つ1つ“4面体”の変形は、厚さ2LP[m]の球殻の体積中における、およそ、8LP3[m3]の限られた範囲で生じているからである。
まず、当量電荷QE[C]の中心からr=2nLP[m]離れた場所にある「厚さ2LP[m]の球殻」の中の1つの「変形している“4面体”」が持っているエネルギーの、「球殻内での時間&空間平均」を計算してみる。
r=2nLP[m]離れた所にある厚さ2LP[m]の球殻の中間にある球面の全面積は、およそ4πr2=16πn2LP2[m2]である。 厚さ2LP[m]であるので、球殻の体積V[m3]は、近似的に、V≒球面の全面積×厚さ=16πn2LP2[m2]×2LP[m](n≧20)と表記できる。
そのうち、1つの「変形している“4面体”」が占める球殻の中の体積は、8LP3[m3]と表記できる。
(なお、各原始ヒッグス場ユニットの配置は変わらないので、ここでは、その変形によって“小さくなること”を考慮しなくてもよい)
一方、1つの「変形している“4面体”」に蓄えられるエネルギーの1秒間での時間平均が「h/2」[J]であった。
これらの値から、「変形している“4面体”」1つあたりの「球殻全体に蓄えられるエネルギーの“時間&空間”平均」が計算できる。
すなわち、 1つの「変形している“4面体”」の場所でのエネルギーの1秒間での時間平均が「h/2」[J]であり、それ以外の場所は変形していない“4面体”であり、そのエネルギーは、相対的に0であるので── 「変形している“4面体”」1つあたりの「球殻全体に蓄えられるエネルギーの“時間&空間”平均」をE平均1[J]と書くことにすると
E平均1={(2LP)3(h/2)×1 + (4πr2×2LP−(2LP)3×1)×0}/(4πr2×2LP)
=4LP2×(h/2)×(1/16πn2LP2) (2LP[m]で約分し、r=2nLP[m]を代入)
=(h/2)×1/4πn2[J] (n≧20) (4LP2[m2]で約分)
となる。
当量電荷QE[C]の周辺の厚さ2LP[m]の各球殻(n≧20)において、1秒間にc/2LP[個]の「変形している“4面体”」が作られることを考慮すると、
「当量電荷QE[C]の中心からr=2nLP[m]離れた所にある厚さ2LP[m]の球殻が蓄えるエネルギーの“時間&空間”平均」E平均QE[J]は、
E平均QE =(c/2LP)×E平均1=(hc/4LP)×1/4πn2[J](n≧20)
となる。
c/2LP(≒0.9375×1043[回/s])が非常に大きいので── この、時間平均かつ空間平均の値E平均QE [J]は、「常に、(中心からr=2nLP[m]を代離れた所にある厚さ2LP[m]を代の)球殻のすべての場所において、平等に」当量電荷QE〔C〕が蓄えさせているエネルギーであると見なすことができる。
“厚さ2LP〔m〕の球殻”が持つエネルギーE平均QE1=(hc/4LP)×1/4πn2[J](n≧20)の値は、電磁ポテンシャルエネルギーの変化量、すなわち、“電位差V”に相当すると見なすことができる。
すなわち、電磁ポテンシャルエネルギー(の絶対値)は、中心から遠ざかるにつれて階段状に増加する、おおよそ、下図のようなものとして、示すことができるようになる。
※やはり、厳密には、厚さ2LP[m]の球殻”が持つエネルギーE平均QE1=(hc/4LP)×1/4πn2[J]は、少なくともn≧20 に限って成立する。
上図では、便宜上、1≦n≦19の範囲(2LP[m]≦λ≦38LP[m]の仮想光子)についてのみを簡略化して図示している。
※電荷QE[C]の中心から2LP[m]だけ遠ざかるごとに、(r=2nLP[m]の距離の地点で)n番目の“2LP[m]幅の球殻”が持つエネルギーが、(その中心から遠ざかる方向に)時空の中に新たに追加されることになるのは、重力の場合と似ている。
そして、その総和が、電磁ポテンシャルエネルギー(の絶対値)に相当しうることが読みとれる。
※重力ポテンシャルエネルギーの計算を参考にすると、電荷が半径a=2mLP〔m〕の球体であると想定した場合、a=2mLP〔m〕の地点からr=2nLPの地点までの電磁ポテンシャルエネルギーの変化の大きさは、
(hc/4LP)×1/4π×(1/m−1/n)=(hc/16πLP)(1/m−1/n)[J]と計算できることがわかる。
よって、電荷が半径a=38LP〔m〕の球体であるならば、電磁ポテンシャルエネルギーの変化の大きさは、m=19を代入して、(hc/16πLP)(1/19−1/n)[J]と求まることになる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
したがって、重力の場合と同様に──
E平均QE1(n≧20)を底辺2LP[m]で割れば、エネルギー勾配、すなわち、「r=2nLP[m]離れた厚さ2LP[m]の球殻」で当量電荷QE[C]が作る電場E[N]を計算できる。
| ※この図より、“無限小(dx)”の代わりに“2LP[m]”を使えば、単位距離当たりの「電磁ポテンシャルエネルギー」の変化量、すなわち、電場を“勾配”として計算できることが読みとれる。 |
つまり、
r=2nLP[m](n≧20)の場所での当量電荷QE[C]が作る電場E[N]は、E=E平均QE1/2LP[N]= (hc/4LP)×(1/4πn2)×(
)[N](n≧20) …(1.3)
となる。
一方、電荷のクーロンの法則の式から求まる電荷Q[C]が作る電場E=kQ/r2[N/C]を変形することを考えてみよう。
例えば、当量電荷QE[C]が作る電場E[N/C]の場合は、次のように変形できる。
「電荷のクーロンの法則の式から求まる、当量電荷QE[C]が作る電場E[N/C]」
=kQE/r2[N/C] (k=1/4πε0 であるので──)
=QE/4πε0r2[N/C] (1/ε0=c2μ0 であるので──)
=c2μ0QE/4πr2[N/C] (この式に、1=(2LP)2 /(2LP)2 をかけて(=分母と分子の両方に(2LP)2 をかけて)──)
=c2μ0QE/4πr2×(2LP)2 /(2LP)2 [N/C] (この式に、r=2nLPを代入して、c2や(2LP)2 /(2LP)2 を移動すると──)
=(μ0/2LP)×(QEc2)×(4LP2/16πn2LP2)×(1/2LP)[N/C] (約分して、(μ0/2LP)を移動すると──)
=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(μ0/2LP)[N/C]
=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/(2LP/μ0)}[N/C] …(1.4)
ここで、(1)と(2)を比較してみよう。
| 当量電荷QEが作る電場E[N]=(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)[N](n≧20) …(1.3) |
by“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
| 当量電荷QEが作る電場E[N/C]=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/(2LP/μ0)}[N/C] …(1.4) |
by電荷のクーロンの法則の式
|
すると、
「QEc2 ∝ hc/4LP」、「(2LP/μ0)∝ QE」と考えればつじつまが合うことがわかる。(∝は、比例しているという記号)
なぜなら、ニュートンの万有引力の式の“EMOES表記”と比較すると、電荷のクーロンの法則の“EMOES表記”が、次のような形になると予想されるからである。
|
ニュートンの万有引力の法則
|
電荷のクーロンの法則
|
|
元々の数式
|
F=GMm/r2[N]
|
F=kQq/r2=Qq/4πε0r2=μ0c2Qq/4πr2[N]
|
|
“EMOES表記”
|
F=(Mc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(m/MG)[N]
=(NMMGc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(m/MG)[N]
=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nm[N]
※NM=M/MG、Nm=m/MG
|
F=(Qc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{q/(2LP/μ0)}[N]
=NQ(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{q/(2LP/μ0)}[N]
=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq[N]
※NQ=Q/QE、Nq=q/QE
|
本当にそのようなことが可能であろうか?
まず、「QEc2 ∝ hc/4Lp」に注目して、その単位を調べてみる。
右辺の「hc/4LP」の単位は、[J]=[kg・m2/s2]である。
一方、左辺の「QEc2」の単位は、[C・m2/s2]=[C・m2/s2]となる。
つまりは、クーロンCの単位について、[C]∝[kg]でありさえすれば、つじつまが合うことが予想される。 よって、次の仮説を立てた。
仮説1.10 クーロンの単位[C]は、質量の単位[kg]に比例する
※質量も電荷も、両方とも、「原始ヒッグス場の“4面体”を変形させる能力である」という意味で統一できるので、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)にもとづいて、考えれば、決して無理のある仮説ではない。
クーロンの単位[C]が、[kg]に比例することの意味の1つは、
クーロンの単位[C]を質量の単位[kg]に変換する比例定数a[kg/C]が存在するということである。
そして、「QEc2[C・m2/s2] ∝ hc/4LP[kg・m2/s2] 」の意味の1つは、『「E=aQEc2」が「アインシュタインの式E=mc2」の電荷版たりうる』ということである。
すなわち、質量m[kg]がE=mc2[J]のエネルギーを持つように、電荷Q[C]には、「E=aQc2[kg/C][C・m2/s2] = hc/4LP[J](=[kg・m2/s2])」というエネルギーがつまっているということである。
一方の、「(2LP/μ0)∝ QE」に注目して単位を調べてみよう。
すると、「(2LP/μ0)」の単位は、
[m]・1/[N/A2]=[m]・1/[kg・m/s2][C2/s2]=[C2/kg]であることが分かる。
したがって、先ほどの「クーロンの単位[C]を質量の単位[kg]に変える比例定数a[kg/C]」を(2LP/μ0)[C2/kg]にかけ合わせてできる「a(2LP/μ0)」の単位は、[kg/C][C2/kg]=[C] となることが分かる。
つまり、a(2LP/μ0)の単位は[C]であり、QE[C]の単位とぴったり同じである。
したがって、
「電荷のクーロンの法則の式から求まる、当量電荷QE[C]が作る電場E[N/C]」の式kQE/r2[N/C]を次のように変形することは、きわめて自然で合理的なことがわかる。
kQE/r2[N/C]
=(QEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/(2LP/μ0)}[N/C] …(1.4)
=(aQEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/a(2LP/μ0)}[N/C]
※最後の変形は、結局、分母と分子にa[kg/C]を掛け合わせただけのものに相当しているが、それ以上の意味を持っている。
同様にして、一般的な、電荷のクーロンの法則F[N]= kQq/r2[N]の式を、次のように変形することができる。
kQq/r2[N]
=(Qc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/(2LP/μ0)}×q[N]
=(aQc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/a(2LP/μ0)}×q[N] (分母と分子に同じaを乗じてある)
以上のような、分母と分子にa[kg/C]を掛け合わせる変形を行うことによって、前に示した「ニュートンの万有引力の式の“EMOES表記”と比較して予想される、クーロンの法則の“EMOES表記”の式」は、次のようにまとめなおすことができる。
|
ニュートンの万有引力の法則
|
電荷のクーロンの法則
|
|
元々の数式
|
F=GMm/r2[N]
|
F=kQq/r2=Qq/4πε0r2=μ0c2Qq/4πr2[N]
|
|
“EMOES表記”
|
F=(Mc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(m/MG)[N]
=(NMMGc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(m/MG)[N]
=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nm[N]
※NM=M/MG、Nm=m/MG
|
F=(aQc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{q/(2aLP/μ0)}[N]
=NQ(aQEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{q/(2aLP/μ0)}[N]
=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq[N]
※NQ=Q/QE、Nq=q/QE
|
『NQ(aQEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×{1/(2aLP/μ0)}×q[N]
=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq[N]』
の各項を比較することによって、次の2つの式が得られる。
aQEc2[J]=hc/4LP[J] …(1.5)
a(2LP/μ0)[C]=QE[C]…(1.6)
※(1.6)は、{1/(2aLP/μ0)}×q=Nq=q/QEより求まる。
(1.5)と(1.6)は、a[kg/C]とQE[C]の連立方程式である。
これを解くと、
a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C] QE=(h/2μ0c)1/2[C]と、それぞれの値を求めることができる。
結論1.7 「a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C]」が、電荷の単位クーロン「C」を質量の単位[kg]に変換できる比例定数である。
結論1.8 「QE=(h/2μ0c)1/2[C]」が、当量電荷である。
まとめて表記すると次のようになる。
|
“電荷のクーロン力F”
=kQq/r2=Qq/4πε0r2=μ0c2Qq/4πr2[N]
=(aQc2/4πn2)×(1/2LP)×(q/QE)[N]
=NQ(aQEc2)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(q/QE)[N]
=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq[N]
= 電荷のクーロンの法則の“EMOES”表記
(a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C]、QE=(h/2μ0c)1/2[C]」)
|
※r=2nLPの地点での電荷のクーロン力である。 なお、n≧20の範囲で成立すると考えられる。
|
ここで、当量電荷QE[C]の具体的な値を求めてみよう。
QE[C]=(h/2μ0c)1/2[C]≒(6.6256×10-34/8π×10-7×2.9979×108)1/2[C]≒9.37×10-19[C] という値になる。 これは、電子の電荷≒1.60×10-19[C]の約5.8倍である。
(h≒6.6256×10-34[J・s] c≒2.9979×108 [m/s]、μ0=4π×10-7 [N/A2] π≒3.14159 とした)
※なお、微細構造定数α(≒1/137)は、「 α=2πe2/4πε0hc= μ0c2e2/2hc = μ0ce2/2h 」と変形できる。(「1/ε0=c2μ0」を使用)
これと、「QE=(h/2cμ0)1/2」より、QE2=e2/4α となる。
つまり、この関係を使うと、QE≒e×(137)1/2/2 ≒5.8×e[C]のように、当量電荷QE[C]が、電子の電荷の約5.8倍であることが、より簡単に計算できることがわかる。
また、プランク電荷(Planck charge)qP=e/(α)1/2 [C]であるので♯、
QE=e/2(α)1/2=qP/2[C] である。 よって、プランク電荷qP=1.8755459×10-18[C]♯を2で割ることで、QE[C]の値が、より簡単に、そして、より正確に計算できる。
その値は、QE[C]≒9.3777295×10-19[C]となり、上の計算によって求めた値QE[C]≒9.37×10-19[C]と合致する。
(♯プランク電荷qP≒1.8755459×10-18[C]の値や「e/2(α)1/2=qP/2」の計算は英語版ウィキペディア/Wikipedia の『Planck charge』のページを参考にした)
重力子質量MG(=2×10-8/2π≒3.18×10-9)[kg]が、陽子の質量1.67×10-27[kg]のおよそ1.9×1018倍であるのに対して、当量電荷QE[C]は、電子の電荷1.60×10-19[C]のたったの5.8倍であると言うことができる。
このことは、ミクロレベルで、静電気力が、重力より、はるかに大きい理由を説明していると思われる。
※なお、r=2nLP[m]の位置にある球殻において、ある瞬間に(同時に)n個の共転回をする必要がある事情から、電子の振動数e〔回/s〕やプレオン∴の振動数ν∴〔回/s〕の分、ある瞬間に(同時に)共転回できる数が“増える(増幅する)”ことを考えたのだった。もしかしたら、当量電荷QE[C]が電子が持つエネルギーが大きいことは、それらの“増幅”の影響を反映しているだけなのかもしれない。詳細な検討は、今後の課題である。
一方、a[kg/C]の具体的な値は、「a=(hμ0/8cLP2)1/2」≒3.6460×1010[kg/C]となる。
(h≒6.6256×10-34[J・s] c≒2.9979×108 [m/s]、μ0=4π×10-7 [N/A2] π≒3.14159 LP≒1.616×10-35[m]とした)
電荷Q[C]に、この定数a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C]≒3.6460×1010[kg/C]をかけると[kg]の単位を持つ値に変換できることになる。
しかし、この定数a[kg/C]が存在することは、電荷[C]と質量[kg]が等しい物理的な全く同一な実体であることを意味していない。
なぜなら、電荷[C]は、仮想光子の放出源として働き続ける能力であり、質量[kg]は、重力子の放出源として働き続ける能力であるという、物理的な意味の厳然たる違いが存在し続けるからである。
この定数a[kg/C]が存在するのは、電荷[C]と質量[kg]は、ともに原始ヒッグス場抵抗を下げる能力をもつこと、すなわち、ともに(同一の)「原始ヒッグス場ユニット(PHU)」にエネルギーを蓄える能力を持つことに由来する。
したがって、この定数a[kg/C]は、電荷[C]を質量[kg]に変換する定数と言うよりも、Qc2[C・m2/s2]の値を“電荷エネルギーaQc2”[J]に変換し、質量エネルギーMc2[J]と対等に比較できるようにする定数であるという方がより正確であると考えられる。
ところで、 プランクエネルギーEPは、 EP=hc/2πLP[J] …(1.7)である。
一方、aQEc2[J]=hc/4cLP[J] …(1.8)である。
よって、(1.7)と(1.8)より、
aQEc2[J]=(π/2)×EP[J]
と、より単純に表せることがわかる。
Q[C]が持つエネルギーをEQ[J]とすると──
EQ[J]=aQc2[J]=NQaQEc2[J]=Q/QE・aQEc2[J]
(式(10)「aQEc2[J]=(π/2)×EP[J]」を用いて──)
=Q/QE・(π/2)×EP[J]
(QE=9.3757×10-19[C]、EP=1.9561×109[J]、π=3.14159として)
≒Q×3.2772×1027[J]
と求まる。
よって、例えば、1クーロンは、3.2772×1027[J]に相当する、(質量エネルギーならぬ)“電荷エネルギー”を持つことになる。
※EQ[J]=aQc2[J]により、1クローン(1[C])が持つ電荷エネルギー=ac2[J](≒3.2772×1027[J])は、(E[J]=Mc2[J]より導かれる)1キログラム(1[kg])が持っている質量エネルギー=c2[J]よりも、a(≒3.6460×1010[kg/C])倍大きいことになる。
その理由として、1クーロンという単位の設定の仕方(『1mはなして置いた時に、それらの間に働く力が9.0×109[N]となるような電気量を1クーロン(記号C)と決める』(p.133 『物理学入門))によって、「1[C]/QE[C]」の項がおよそ“1.06×1018”ほどと大きいことが挙げられる。
(それに対して、「1[kg]/MG[kg]」の項は、“3.14×108”ほどに過ぎない(MG[kg]≒2×10-8/2π[kg]を使用))
(もし、ミクロレベル(プランクスケール)で、当量電荷QE[C]と重力子質量MG[kg]が同じ個数分ずつ存在するとして比較した場合は、(当量電荷QE[C]1つが持つエネルギーが
(π/2)×EP[J]であるのに対して、重力子質量MG[J]1つが持つエネルギーがEP/2π[J]であるので)それらのエネルギーは“π2”程度しか違わないのである)
したがって、1.60210×10-19[C]の電荷を持つ1つの電子でも、5.2504×108[J]もの“電荷エネルギー”を持つことになる。
このことは、(重力子質量MG[kg]が陽子の質量のおよそ1.9×1018個分でまかなわれるのに対し)当量電荷QE[C]が電子の電荷のおよそ5.8個分だけでまかなわれることを説明している。
すなわち、陽子1つの質量が重力場を生じる場合より、電子1つの電荷が電場を生じる場合の方が、はるかに(およそ1018倍ほど)効率よく原始ヒッグス場を変形する(原始ヒッグス場にエネルギーを蓄える)のである。
(なお、陽子1つが持つ質量1.67×10-27[kg]は、およそ1.5×10-10[J]ほどの質量エネルギーを持ち、このおよそ1018倍が、電子1つの“電荷エネルギー”に近い値であることがわかる)
※たった1つの電子でも、5.2504×108[J]ものエネルギーを持つこと── ここに、電子の重要さが浮かび上がってくると思われる。
ただし、個々の電子から、5.2504×108[J]ものエネルギーを直接引き出すことは、(人類の観測事情や応用事情を示す)不確定性原理によって(or 不確定性原理のおかげで)、不可能であることがわかる。
しかし、人類は、すでに、“電気”(電流、電圧、エルクトロニクス技術、半導体、超伝導…)に依存する形で、この電子をフル活用してきている。
思い起こせば、光合成においても、生命は、この電子をフル活用している。(典型的な例は、光合成のプロセスの一部を担う“電子伝達系”である)
このことは、人工光合成(人工葉)、超伝導、レーザー、太陽光発電… その他の新しい技術を含め、“電子”の何らかの賢い有効活用が、エネルギー問題解決の重要なカギの1つとなることを意味しているように思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
一方、この“電子”の「最もシンプルで、取り扱いが便利な単体」が、水素である。
(電子と陽電子のペアは、すぐに対消滅してしまうので、シンプルであるが取り扱いが便利ではない)
このことは、燃料電池… その他の新しい技術を含め、“水素”を有効活用する技術も、エネルギー問題解決の重要なカギの1つとなることを意味しているのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
ところで、「この“電荷のエネルギー”も、エネルギーの一種なのだから、質量を持つはずだ」というのは、正しくない。
なぜなら、やはり、電荷[C]のエネルギーは、あくまで「仮想光子の放出源として働き続ける能力」を反映しているものである一方、質量[kg]のエネルギーは「重力子の放出源として働き続ける能力」を反映しているものであるという、物理的な意味の厳然たる違いが存在し続けるからである。
つまり、やはり、質量は、エネルギーの一種に過ぎないのである。
したがって、「アインシュタインのE=mc2の式によると、あらゆるエネルギーは質量なのだから、“電荷のエネルギー”も質量を持つはずだ」という説明は、自然(nature)から乖離しているのである。
具体的に、確認してみよう。
電子の電荷は、1.60210×10-19[C]であり、
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、電子の電荷が持つエネルギーは、aQec2≒5.2504×108[J]となるのであった。
もし、「電荷のエネルギーが質量を持っている」としたら、その質量は、aQe≒ 3.6460×1010[kg/C]×1.60210×10-19[C]≒5.84125×10-9[kg]である。
一方、電子の静止質量の測定&計算に基づく値は、me=9.10908×10-31[kg]であり、その静止質量エネルギーは、mec2≒8.1867×10-16[J]である。
|
電子が持つ荷量
|
電子の静止質量
me=9.10908×10-31[kg]
|
電子の電荷
Qe=1.60210×10-19[C]
|
|
エネルギー
|
mec2≒8.1867×10-16[J]
|
aQec2≒5.2504×108[J]
|
|
質量?
|
静止質量エネルギーmec2[J]が持つ質量は、
当然、me=9.10908×10-31[kg]
|
もし、電荷のエネルギーaQec2[J]が、質量を持っていたとしたら、
何[kg]に相当するか? aQe≒ 5.84125×10-9[kg] |
このことから、「電荷のエネルギーが質量を持っている」と考えることには、観測値と計算値の間における、あまりに大きな桁外れな(1022倍もの)ずれ(乖離)があることがわかる。
したがって、この「電荷のエネルギーも、質量を持つ」という考えは、自然(nature)と乖離しているのである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に基づいて、落ち着いて考えれば、ここにある値の大きなずれ(乖離)の、根本の原因は、「(質量だけでなく)電荷もエネルギーを持つ」と言うことにあるのではなく、E=mc2という抽象的な式を「あらゆるエネルギーは質量である」という意味に解釈したことにこそあることがわかる。
すなわち、E=mc2 の数式について「あらゆるエネルギーは質量である」という解釈をしたからこそ、ここに自然(nature)からの乖離が生じてしまったのであり── この数式について、「質量は運動エネルギー(内部&外部)を持つ」、「質量はエネルギーの一種に過ぎない」という解釈をしていれば、「電荷のエネルギーも、質量を持つ」という考えも、観測値と計算値の間における大きなずれ(乖離)も、生じることはなかったのだ。
E=mc2という「抽象的な数式」そのものだけを重視しているだけでは、この「あらゆるエネルギーは質量である」という解釈が自然(nature)から乖離していることに気づくことは難しい。
一方、E=mc2という「抽象的な数式」のみならず、その解釈(意味)、すなわち、幾何的な実体像そのものも重視するならば── 質量とは、「重力子の放出源として働き続ける能力」であり、電荷とは、「仮想光子の放出源として働き続ける能力」である、という本質的な違いに気づくことが容易であり、「電荷のエネルギーが、質量を持たない」ことは、明白なこととなる。
すなわち、幾何的な実体像そのものを重視する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)だからこそ、「質量がエネルギーを持つ一方で、電荷もエネルギーを持つ」ということ── そして、「あらゆるエネルギーは質量である」(「エネルギーと質量が完全に等価である」)というE=mc2の数式から導く解釈が、自然(nature)から乖離していることに気づくことができるのだ。
つまり、「自然(nature)と調和しているかどうか、自然(nature)から乖離しているかどうか」に気づくためには、「抽象的な数式」の解釈、すなわち、自然(nature)についての具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)を重視することが大切になるのである。 (→考察2)
よって、E=Mc2[J]の数式は、より正確に示せば、EM=Mc2[J](質量M[kg]が持っているエネルギーEM[J]が、Mc2[J]に等しいという意味)となる。
そして、一方で、EQ=aQc2[J] (電荷Q[C]が持っているエネルギーEQ[J]がaQc2[J]に等しいという意味を持つ)が成り立つ。
よって、総エネルギーをEtotal[J]とするならば、Etotal=Em+EQ+α=mc2+aQc2+α [J] ということになる。
ここでのα [J]とは、質量エネルギーや電荷エネルギー以外のエネルギーを意味する。
そして、質量や電荷と並んで、エネルギーを持つと考えられるものが、少なくとも、もう1つある。 それが、磁極のエネルギーである。
磁極のクーロンの法則について、次のような記述がある。
『点磁極を仮想すれば点電荷の場合と全く同様の関係が得られるはずであり、いま真空中に、磁極の強さm1、m2[Wb]なる二つの同性の点磁極が距離 r[m]を隔てて存在するとすれば、それらの磁極間には次の式で与えられる反発力Fが働くことになる。
F=m1m2/4πμ0r2[N] (11.93)
この式は磁界におけるクーロンの法則といわれる』
(p.311 『基礎電磁気学』 改訂版 山口 昌一郎 電気学会) |
|
この磁極のクーロンの法則についても、電荷とのクーロンの法則の場合と同様に考えてみることができる。 それは以下のようになる。
式を変形すると──
磁極のクーロン力F[N]
=m1m2/4πμ0r2[N]
=c2ε0m1×1/4πn2×(1/2LP)×(1/2LP)× m2 [N](r=2nLP、1/μ0=c2ε0を代入)
=bc2m1×1/4πn2×(1/2LP)× m2/{b(2LP/ε0)}[N](分母と分子に、定数bをかけて、式を変形)
b(2LP/ε0)[Wb]が、当量磁極mE[Wb]に等しければよい。 mE=b(2LP/ε0) …(1.9)
当量磁極mE[Wb]の定義は、当量電荷QE[C]と同様に、『厚さ2LP[m]の球殻に、常に「hc/4LP[J]」のエネルギー蓄えられる磁極』ということにすると、磁極のクーロン力F=m1m2/4πμ0r2[N]の式は、さらに、次のように変形できる。
磁極のクーロン力F(=m1m2/4πμ0r2)[N]
=bc2m1×1/4πn2×(1/2LP)× m2/{b(2LP/ε0)}[N]
=Nm1×bc2mE ×1/4πn2×(1/2LP)×m2/mE[N] (mE=b(2LP/ε0)…(1)、Nm1=m1/mE)
=Nm1×(hc/4LP)×1/4πn2×(1/2LP)×m2/mE[N] (bc2mE =(hc/4LP)…(1.10))
(なお、磁極も仮想光子の放出源として働き続ける能力であるので、電荷と同様に、やはり、n≧20という条件が適用されると考えられる)
(1.9)と(1.10)は、bとmEの連立方程式である。
mE=b(2LP/ε0)…(1.9) bmEc2 = (hc/4LP)…(1.10)
これを解くと──
b =(hε0/8cLP2)1/2 mE=(h/2cε0)1/2
と求まる。
つまり、磁極m1[Wb]は、bm1c2[J]のエネルギーを持つこととなる。
なお、定数b=(hε0/8cLP2)1/2[Cs/m2]は、磁極[Wb]([Nms/C]=[kg・m2/Cs])から導かれる、m1c2[Wb・m2/s2](=[kg・m4/Cs3])を、エネルギー[J](=[kg・m2/s2])に変換する定数である。
|
※mE=(h/2cε0)1/2[Nms/C]の単位、[Nms/C]は、[Nms/C]=[s・J/C]=[s・V]=[Wb]に相当し、
bc2mE =(hε0/8cLP2)1/2×c2×(h/2cε0)1/2=hc/4LP[J]となるので、単位も含めて矛盾していないことが確認できる。
※定数bを計算すると、b=(hε0/8cLP2)1/2[Cs/m2] ≒9.6781×107[Cs/m2]となる。
(h≒6.6256×10-34[J・s] c≒2.9979×108 [m/s]、ε0≒8.854185×10-12 LP≒1.616×10-35[m]とした)
※当量磁極mEの値を計算すると、mE=b(2LP/ε0)[Wb]=(h/2cε0)1/2[Wb] ≒3.5327×10-16[Wb] となる。
(b≒9.6781×107[Cs/m2] h≒6.6256×10-34[J・s] c≒2.9979×108 [m/s]、ε0≒8.854185×10-12 LP≒1.616×10-35[m]とした)
※なお、定数b=a×(ε0/μ0)1/2 である。ε0≒8.854185×10-12 [C2/Nm2] a≒3.6460×1010[kg/C] μ0=4π×10-7 [N/A2] π≒3.14159 として計算すると、b≒9.678×107[Cs/m2]となり、やはり、上の計算と一致する。 mE=b(2LP/ε0)[Wb]=(h/2cε0)1/2[Wb] と、微細構造定数α(≒1/137)= μ0ce2/2h より、mE2=e2/4α×(μ0/ε0)=QE2×(μ0/ε0)=(qP/2)2×(μ0/ε0)、すなわち、mE=(qP/2)×(μ0/ε0)1/2≒3.532874 ×10-16[Wb] となり、上の計算と、ほぼ合致する。
後者が、より単純に、より正確に求めた値であると言える。
(ε0≒8.854185×10-12、qP≒1.8755459×10-18[C]、μ0=4π×10-7 π≒3.14159 とした)
※なお、次のような記述があるように──
『棒状永久磁石は前にも述べたように、両端に必ず正負の磁極が一対となって現れるので、実際には正あるいは負の磁極を単独に取り出すことはできず、式(11.93)はあくまでも磁極が単独に存在すると仮想した場合に成立するものである』
( p.311 『基礎電磁気学』 改訂版 山口 昌一郎 電気学会)
|
|
上では、磁極を“点磁極”として設定しているので、(モノポールが確認されていない以上、そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によればモノポールが存在しないと予想できる以上(→結果2))、実際の自然とは、厳密には異なるので、上の数式は、あくまで、仮想的&近似的なものに過ぎないことになる。 ただし、S極とN極を持つ棒状の磁石は、S極とN極の点磁極を組み合わせたものと見なせるので、この仮想的&近似的な数式によって、自然(nature)に存在する磁石(電子を含む)が持つエネルギーの目安を得ることができるだろう。
1[Wb]は、b×1×c2[J]≒9.6781×107×(2.9979×108)2≒8.698×1024[J]ものエネルギーを持つことになる。
よって、1つの電子が持つおおよその“磁極”が求まれば、電子が持つ磁極が持つ、おおよそのエネルギーが計算できることになる。
1つの電子の磁気モーメントは、μe≒1.2840×10-24[Am2](=[J・T-1])である。(EB対応)
一方、真空の透磁率を、μ0≒1.2566706×10-6[H/m](=[Wb/Am])とすると、1つの電子の磁気モーメントは、μ0×μe≒1.2566706×10-6[Wb/Am]×1.2840×10-24[Am2]≒1.613565×10-30[Wb・m]とも表記できる。(EH対応) しかし、これでも、まだ、1つの電子が持つ磁極[Wb]ではない。 1つの電子が持つ磁極[Wb]を求めるためには、電子のサイズが必要となる。 電子のサイズが小さいほど、1つの電子が持つ磁極[Wb]、そしてその磁極が持つエネルギーは、大きくなる(電子のサイズと電子の磁極が反比例する)。
果たして、電子のサイズは、どれくらいなのだろうか?
結果2《磁力と、磁極の間に働く“引力と斥力”および“電子のスピン”について》によると、電子のサイズ(軸方向の幅)は、少なくとも、「プレオン∴のサイズ程度」、すなわち、LP〔m〕程度であることになる。
この値と1つの電子の磁気モーメント1.613565×10-30[Wb・m]の値を使うと、1つの電子の磁極[Wb]について、考えうる最大値が計算できる。
その値は、1.613565×10-30[Wb・m]/LP〔m〕≒1×105〔Wb〕である。(LP≒1.616×1035〔m〕とした)
この値と1[Wb]が持つおおよそのエネルギー8.698×1024[J]を用いることによって、1つの電子の磁極が持つエネルギーの考えうる最大値が、およそ8.698×1024[J/Wb]×1×105〔Wb〕=8.698×1029[J]であると求まる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
|
なお、電子のサイズが厳密にいくらであろうと、1[Wb]は、b×1×c2[J]=9.6781×107×(2.9979×108)2≒8.698×1024[J]のエネルギーを持ち、1つの電子の磁気モーメントが1.613565×10-30[Wb・m]であることは変わらないので、電子1つが持つ磁極のエネルギーは、非常に大きいものになることは確かである。
そして、電荷と同様に、大きいと予想される電子の磁極が持つエネルギーを、電子から直接引き出すことは── やはり、プレオン∴が閉じ込められていること(結果2)や(人類の観測事情や応用事情を示す)不確定性原理(結果4)によって、不可能である。
しかし、この例におていも、やはり、電子や水素、そして、永久磁石の有効活用が、エネルギー問題解決の重要なカギの1つとなることを意味していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
磁極m1[Wb]が、bm1c2[J](b=(hε0/8cLP2)1/2[Cs/m2])のエネルギーを持つということは──
つまりは、Etotal =mc2 + aQc2 + bm1c2 +α[J]と表記できることを意味する。
(ここでのα [J]とは、質量エネルギーや電荷エネルギー、磁極エネルギー以外のエネルギーを意味する)
すなわち、エネルギーには、質量エネルギーの他に、少なくとも、電荷エネルギーと、磁極エネルギーの2つがあることになる。
|
エネルギーE[J]
|
|
質量m[kg]が持つエネルギー
質量エネルギーEm[J]
|
電荷Q[C]が持つエネルギー
電荷エネルギーEQ[J]
|
磁極m1[Wb]が持つエネルギー
磁極エネルギーEm1[J]
|
|
mc2[J]
|
aQc2[J]
(a=(hμ0/8cLP2)1/2[kg/C])
|
bm1c2[J]
(b=(hε0/8cLP2)1/2[Cs/m2])
|
※これらの他にもあるのだろうか? すなわち、“さらなる+α”とは、あるだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
以上をまとめると、電荷や磁極のクーロンの法則の“EMOES表記”は、下のようになる。
|
電荷のクーロンの法則
|
磁極のクーロンの法則
|
|
元の数式
|
F(=kQq/r2)=Qq/4πεr2[N]
|
F=m1m2/4πμ0r2[N]
|
|
“EMOES表記”
|
F=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq
=NQ(aQEc2/4πn2)×(1/2LP)×(q/QE)
=(aQc2/4πn2)×(1/2LP)×(q/QE)[N]
|
F=Nm1(hc/4LP)×1/4πn2×(1/2LP)×Nm2
=Nm1(bmEc2/4πn2×(1/2LP)×(m2/mE)
=(bm1c2/4πn2)×(1/2LP)×(m2/mE)[N]
|
|
変換定数a=(hμ0/8cLP2)1/2≒3.6460×1010[kg/C]
当量電荷QE=プランク電荷qP/2≒9.3777295×10-19[C]
|
変換定数b=a×(ε0/μ0)1/2 ≒9.678×107[Cs/m2]
当量磁極mE=(qP/2)×(μ0/ε0)1/2≒3.532874×10-16[Wb]
|
※“EMOES表記”によって、電荷&磁極のクーロンの法則が、量子化されている。
|
これらの「電荷のクーロンの法則」や「磁極のクーロンの法則」の“EMOES表記”は、電荷や磁極のクーロン力がどのようにして生じるのかについての本質的な部分を説明している。 すなわち、これらの式の“EMOES表記”は、電荷Q[C]や磁極m1[Wb]から放出される仮想光子が作る電場や磁場(=“原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形の総和”)を介して生じていることを、はっきり示している。
※なお、静電気力や磁力には、引力や斥力が存在するので、まだ十分な説明ではない。
「引力&斥力がどのようにして生じるのか」については、結果2で説明する。
「ニュートンの万有引力の法則」、「電荷のクーロンの法則」、「磁極のクーロンの法則」を、並べて示すと次のようになる。
|
ニュートンの万有引力の法則
|
電荷のクーロンの法則
|
磁極のクーロンの法則
|
|
元の数式
|
F=GMm/r2[N]
|
F=kQq/r2=Qq/4πεr2[N]
|
F=m1m2/4πμ0r2[N]
|
|
“EMOES表記”
|
F=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nm
=(Mc2/4πn2)×(1/2LP)×(m/MG)[N]
|
F=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq
=(aQc2/4πn2)×(1/2LP)×(q/QE)[N]
|
F=Nm1(hc/4LP)×1/4πn2×(1/2LP)×(Nm2)
=(bm1c2/4πn2)×(1/2LP)×(m2/mE)[N]
|
※「ニュートンの万有引力の法則」、「電荷のクーロンの法則」、「磁極のクーロンの法則」の類似関係が、より明瞭になっている。
それぞれの“EMOES表記”は、それぞれの力を、量子化していると同時に、それぞれの力が、どのように生じるのかの本質を説明している。
すなわち、どの力も、「原始ヒッグス場の“4面体”の抵抗の減少の総和」に基づいて生じていることを示しているのである。
ここにあるのは、重力と電磁気力(静電気力&磁力)の統合の本質であると同時に、“重力場と電磁場(電場&磁場)の統合”の本質であると言えるのである。
確かに、ここにあるのは、単に、ニュートンの万有引力の法則と、クーロン力を統一したものに過ぎない。
しかし、ここにあるものは、かつてアインシュタインが(残りの生涯をかけて)完成をめざして達成できなかった“統一場理論”の答えの1部(or 少なくとも答えに至るためのヒント)であると言っても過言ではないと思われる。
なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ニュートン力学の世界はもちろん、特殊相対性理論の世界(光速不変、ローレンツ変換…)も、電磁気学の世界(マクスウェルの4つの方程式の世界)(→結果2)も、一般相対性理論の世界(時空の曲り、アインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)、曲率、線形or非線形…)も、包含するものだからである。
(一般相対性理論の詳細については、下記の、《アインシュタイン方程式(アインシュタインの“重力場の方程式”)》、《重力場の線形性について(詳細版)》で説明する)。
しかも、それらは、非常にシンプルで具体的な数学(数式や幾何、数列、級数…)によって示されている。
これは、ミクロ(プランクスケール)の自然(nature)そのものが、本来、シンプルだからである。
つまり、このことは、自然な世界観(3Steps原理)の1つ、「ズームインするほど、よりシンプル一様化する」と調和しているのである。
(なお、(原則として)微分さえも用いていないのは、ミクロ(プランクスケール)の自然(nature)においては、時空さえも、不連続である(飛び飛びである、微分できない)ことを前提としているからである)
したがって、少なくとも、この方向性── 原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)の上で、電場や磁場、そして、重力場が創発していると説明し、「原始ヒッグス場抵抗の減少」として、それらの力の本質を説明するという方向性は、電磁気力(静電気力&磁力)、および、重力を統合していくための大きなヒント(ガイド、きっかけ、足がかり、ステップ…)になるのは確かだろうと思われる。
※なお、nが大きくなると、元の式(ニュートンの万有引力の法則の式、クーロンの法則の式)に近づく。
このことは、“対応原理”が成り立っていることを意味する。
すなわち、元の式(「ニュートンの万有引力の法則」と「電荷のクーロンの法則」、「磁極のクーロンの法則」の式)は、マクロの世界を記述するための、近似式であると言える。
3つの荷量について、まとめると次のようになる。
|
荷量
|
質量M[kg]
|
電荷Q[C]
|
磁極m1[Wb]
|
|
定義
|
「重力子の放出源として働き続ける能力」 |
「“仮想光子”の放出源として働き続ける能力」 |
「“仮想光子”の放出源として働き続ける能力」
|
|
荷量が持つエネルギー
|
E=Mc2[J]
=NMEG=NMEP/2π[J]
|
E=aQc2[J]
=NQEP×π/2(=NQ(ch/4LP))[J]
|
E=bm1c2[J]
=Nm1EP×π/2(=Nm1(ch/4LP))[J]
|
|
厚さ2LP[m]の各球殻が
持つエネルギー
|
同上
|
同上
|
同上
|
それは、時空の厚さ2LP[m]の球殻には、すべての1枚1枚のそれぞれに、それぞれの荷量が持つエネルギーと全く同じ大きさのエネルギーが蓄えられていることを意味している。
すなわち、荷量のエネルギーと全く同じ大きさのエネルギーを持つ「厚さ2LP[m]の球殻」という“皮”が、周辺の時空に、タマネギの皮のように、何層にも渡って重なって存在していることになる。
ここでも、明らかに「エネルギー保存則」が成り立っていないことがわかる。
しかし、やはり、ここに問題はない。
なぜなら、やはり、“ネーターの定理”は、時空が連続であるときに限って、保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立つこと示しているからである。
|
『ネーターの定理は、系に連続的な対称性がある場合はそれに対応する保存則が存在する、と述べる定理である』
(ウィキペディア『ネーターの定理』 下線は、筆者による)
『ネーターの定理は、物理法則の連続的対称性とそれにともなう保存則との関係を表している』
(p.123 『対称性 レーダーマンが語る量子から宇宙まで』 下線は、筆者による)
|
したがって、「連続な時空の対称性が成り立つときのみ、保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成り立つことを示すネーターの定理」と「時空が不連続であるという前提で重力子や仮想光子がエネルギー非保存の所産であることを示す“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)」は、調和しているのである。
《重力場、エネルギー、質量》
重力子は、確かにエネルギーを持つが、それ自体は質量を持たない。 (だからこそ、光速で無限遠方まで移動できる)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)においては、質量を、より厳密に、次のように定義できる。
『質量とは、 重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を、一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力である』
この定義であれば、(誤解を招きにくく)自然(nature)と調和していると思われる。
※なお、「質量とは、運動エネルギー(内部&外部)である」という定義も、(誤解を招きにくく)自然(nature)と調和していると思われる。
一方、『質量とは、エネルギーである』という定義は、採用しない。
なぜなら、「あらゆるエネルギーは質量である」という誤解を招くからである。 「電荷エネルギーや磁極エネルギーが、質量を持たない」ことからわかるように、「あらゆるエネルギーは質量である」というのは、自然(nature)から乖離しているのである。
この『質量とは、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を、一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力である』という定義によれば、
『重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の通過点として働く能力』のみを持つ、原始ヒッグス場ユニットの“4角形”(縮みきったバネ)自体は、質量を持たないことは明らかである。
※中心部に“質量”──『重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を、一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力』を持つ物体があり、周囲部に、『重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の通過点として働く能力』のみを持つ原始ヒッグス場ユニットがあること示す図である。
※整然と図示してあるが、厚さ2LP[m]の球殻に同数の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が存在するという条件のみを見たしながらも、その1つの球殻内での配置は、実際は、下図のように、それぞれ雑然としていると考えられる。
※実際は、このように雑然としていることは、ブラックホールから放出される大量の重力子がエントロピーを持ち去ることの根拠の1つとなる。
※「厚さ2LP[m]の球殻」輪切りにしたスペースに、8つずつ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」があるように図示されている。
|
重力子は、本来、物体(“素粒子の総和”)が持つ質量(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を、一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力」)が原因となって、放出されるものである。
質量が保存されているということは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力」、すなわち、運動エネルギー(内部&外部)が保存されていることに他ならない。
※この定義によれば、当然、(電磁波を構成する)光子も、(電磁場を創発する)仮想光子も、電荷エネルギーや磁極エネルギーも、(エネルギーを持っているが)質量を持っていないことがはっきりわかる。
例えば、電子は、質量エネルギーのほかに、電荷エネルギーや磁極エネルギーを持つ。 電荷のエネルギーや磁極のエネルギーは、あくまで“仮想光子を繰り返し放出する源として働き続ける能力”に相当するものであり、“重力子を繰り返し放出する源として働き続ける能力”に相当しないので、それらのエネルギーは質量を持っていないことになる。
“ある素粒子が質量を獲得する”過程とは、「一定の頻度で重力子を繰り返し放出する源として働き続ける能力」、すなわち、運動エネルギー(内部&外部)を獲得する過程そのものであり── 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を、「“4面体”→“4角形”(縮みきったバネ)」のように、繰り返し変形させ続けられる能力を獲得する過程そのものと言える。
※例えば、外から見える(外部)運動エネルギーが増加し、等速運動が実現する過程は、まさに、「一定の頻度で重力子を繰り返し放出する源として働き続ける能力」が増加する過程の1つである。
『質量とは、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を一定の頻度で繰り返し放出し続ける源として働く能力である』ということは、一定時間内にどれくらいの頻度で、「“4面体”から“4角形”(縮みきったバネ)へ」と原始ヒッグス場ユニットのを繰り返し変形させることができるかは、まさに、質量の大きさに比例することを意味する。
|
|
|
質量が小さいほど、それに比例して
生じる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」
の放出頻度が少ない。 |
質量が大きいほど、それに比例して
生じる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」
の放出頻度が多い。
|
|
電荷でも磁極でもなく、“質量”こそが、重力子の放出源である。
その「質量」によって生み出された重力場は、確かにエネルギーを持つといえる。
しかし、その“重力場が持つエネルギー”は、あくまで、その大元の源が持つ「質量(重力子を一定頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)」によって放出されて移動(通過)する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が持っているエネルギーの総和として創発するものに過ぎないものである。 つまり、重力場が持っているエネルギーは、「質量」という放出源から放出されたところの、“通過する重力子エネルギーの総和”の所産にすぎない。
したがって、そうやって生み出された“重力場が持つエネルギー”自身が、新たな質量「(重力子を一定頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)」となることは、決してありえないのである。
※重力場を創発する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、すべて、エネルギーの通過点に過ぎない。
つまり、質量(=重力子を一定頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)は、“エネルギーが通過するところである重力場”にあるのではなく、物体(素粒子の総和)などの「運動エネルギー(内部&外部)を持つもの」にこそあるのだ。
すなわち、この物体(素粒子の総和)などの、大元の質量、すなわち、「運動エネルギー(内部&外部)を持つもの」こそが、“重力場が持っているエネルギー”を供給し続けている源であり── やはり、重力場は、あくまで、これらの“エネルギーの通過点”に過ぎないのである。
(このことは、「一見、途中の“電線”から電気のエネルギーが供給されるように見えても、実際は、そのエネルギーは、その源である発電所から供給されている」ということと似ていると思われる。 やはり、途中の電線は、決して、エネルギーの源なのではなく、エネルギーの通過点に過ぎないのである)
以上の「重力場のエネルギーは質量を持っていない」という説明は、やはり、「あらゆるエネルギーが質量を持つとは限らない」こと、「質量は、あくまで、エネルギーの1つのあり方にすぎない」ことをはっきり示しているものの一例でもある。
※この図は、質量(=重力子を一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)があれば、必ずエネルギーがあるが──
エネルギーがあるからといって必ず質量(=重力子を一定の頻度で繰り返し放出し続ける源として働く能力)があるとは限らないことを示している。
「質量→エネルギー」○(真) 「エネルギー→質量」×(偽) という関係があることがわかる。
つまり、エネルギーは質量の必要条件であるが十分条件ではないのである。
※エネルギーを持つが質量を持たないものの例をまとめると、次のようになる。
|
重力子、光子、仮想光子
「電磁波および電磁場」(光子や仮想光子の総和)
「重力波および重力場」(重力子の総和)
電荷や磁極(仮想光子を一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)
|
|
したがって、重力場は確かにエネルギーを持つが、質量(=重力子を一定の頻度で繰り返し放出する源として働き続ける能力)は持たないのであり── 「重力場が新たな質量となる」と考えることも、「重力場が、新たな“重力子の放出源”となる」と考えることも、「 “重力場のエネルギー”そのものを、E=mc2の式にあてはめて、“重力場の質量”を計算で求められる」と考えることもナンセンスだと言うことになる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は── 重力場は、大元の重力子の放出源(質量)から届いてくる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」をリレー(転送)し続けているだけの通過点に過ぎないことを、はっきり示しているのである。
※E=mc2という数式に対して、「質量がエネルギーが持つ」という解釈のみならず、「エネルギーが質量を持つ」という解釈を始めたのは、他ならぬ、E=mc2を発見したアインシュタインであったことは次の記述から読み取れる。
|
『〜 K0−K1=Lv2/2c2 とおくことができる。
この数式から、直ちに次の結論が導かれる。
もし物体が輻射の形でエネルギーをL を放出すると、その質量はL/c2だけ減少する。
物体から取り去られたエネルギーは輻射になるという事実は明らかであるから、さらに次のようなもっと一般的な結論が導かれる。
物体の質量はその保有するエネルギー量の目安である。もしエネルギーがLだけ変わると、その質量は同じくL/9×1020 だけ変わる。ここでエネルギーはエルグで、質量はグラムで測ったものとする』
(『アインシュタイン選集1』 p.50 下線は、筆者による)
|
|
『 M '−M=E/c2 この式は、エネルギーと質量の等価性を表す。エネルギーの増加E に対して質量の増加E /c2が伴う』
(『アインシュタイン選集1』p. 53 下線は、筆者による)
|
|
『質量とエネルギーの等価性を表すには、E=M c2という式を使うのが普通である。ここでcは光の速度で、約1186000マイル/秒である。E は一定の物体のなかに含まれるエネルギーで、M はその質量である。質量Mに属するエネルギーは質量に 光の莫大な速さの2乗を掛けたものに等しい。〜。
ところでこの関係をひっくり返して、エネルギーにおけるEだけの増加は質量におけるE/c2だけの増加を伴わなければならないということができる。』
(『アインシュタイン選集1』 p.56 下線は、筆者による)
|
注意して考えれば、次のいずれの「数式の解釈」も、実は、解釈の1つに過ぎないことがわかる。
|
『物体が輻射の形でエネルギーをL を放出すると、その質量はL/c2だけ減少する』
『もしエネルギーがLだけ変わると、その質量は同じくL/9×1020 だけ変わる』
『エネルギーの増加E に対して質量の増加E /c2が伴う』
『この関係をひっくり返して、エネルギーにおけるEだけの増加は質量におけるE/c2だけの増加を伴わなければならない』
「エネルギーが変化すれば、質量も変化する」
「あらゆるエネルギーは、質量を持つ」
|
| ※上の4つの文のみがアインシュタイン自身による解釈であり、ここからアインシュタインが「エネルギーは質量を持つ」と解釈していたことが読み取れる。 |
すなわち、上のいずれの「数式の解釈」に対しても、次のように、“ひっくり返した”解釈が可能であることがわかる。
|
「質量はL/c2だけ減少すれば、物体が輻射の形でエネルギーをL を放出する」
「その質量がL/9×1020 だけ変われば、エネルギーがLだけ変わる」
「質量の増加Mに対して、エネルギーの増加E=M c2 が伴う」
『質量Mに属するエネルギーは質量に 光の莫大な速さの2乗を掛けたものに等しい』
「質量が変化すれば、エネルギーも変化する」
「あらゆる質量は、エネルギーを持つ」
|
| ※4番目の『質量Mに属するエネルギーは質量に 光の莫大な速さの2乗を掛けたものに等しい』の文のみアインシュタイン自身による解釈である。ここから、アインシュタインが「質量がエネルギーを持つ」とも解釈していたことがわかる。 |
つまりは、E=mc2という抽象的な数式に対しては、本来、一見もっともな解釈が2つずつ存在するのだ。
そして、アインシュタインは、「質量はエネルギーを持つ」と「エネルギーは質量を持つ」の解釈の両方が正しいと見なしていたことが特に4番目の文のペア──『質量Mに属するエネルギーは質量に 光の莫大な速さの2乗を掛けたものに等しい』と『この関係をひっくり返して、エネルギーにおけるEだけの増加は質量におけるE/c2だけの増加を伴わなければならない』から読み取れる。
つまり、アインシュタインにとっては、「質量はエネルギーを持つ」と「エネルギーは質量を持つ」は、大した違いがなかったのである。
アインシュタインにとって、まさに、エネルギーと質量は、100%等価だったのである。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に照らすと、「質量はエネルギーを持つ」と「エネルギーは質量を持つ」という2つの解釈の間には、雲泥の差があることが、はっきりわかる。 なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「質量を持たないエネルギーが存在すること」や「運動エネルギー(内部&外部)こそが質量を持つこと」をはっきり示しているからである。
つまり、「あらゆる質量はエネルギーを持つ」のみが自然(nature)と調和し、「あらゆるエネルギーは質量を持つ」は、自然(nature)から乖離しているのである。
「抽象的な数式」のみを重視し、その解釈、すなわち、「ミクロの自然(nature)の幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」を軽視している限り、そのことに気づくことができない。
たとえ偉大なアインシュタインであっても、「抽象的な数式」に裏切られうるのである。(→考察2)
そして、このことが、後に、(ますます抽象的な数学に依存する)一般相対性理論やその応用(重力波…)において、アインシュタインを迷走、混乱… させる原因の1つとなってしまったのだ。 (→下記)
《アインシュタイン方程式(アインシュタインの“重力場の方程式”)》
アインシュタイン方程式は、アインシュタインが、(連続(なめらか)で微分可能な世界を前提としている)リーマン幾何学を駆使して構築した、次のような「重力場についての方程式」である。
※アインシュタインの重力場の方程式である。 宇宙項は省いてある。
アインシュタインの重力定数 : k= 8πG/c4
アインシュタイン・テンソル : Gμν= Rμν−gμνR/2
であるので、 Gμν = 8πG/c4 Tμν と表記することもできる。
(参考 『アインシュタイン選集2』および、ウィキペディア『アインシュタイン方程式』…)
※この数式は、確かに高校数学を越えている。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、この数式の意味──
具体的な“幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)
をつかむべく、高校レベルの数学(計算)によって、可能な限り変形していく。 (→下記) |
既存の物理学においては、アインシュタイン方程式の左辺のテンソル 「Rμν−gμνR/2」は、「“時空の曲がり”(曲率)を意味するテンソル」であり、右辺のテンソル「Tμν」は「時空を曲げる原因(重力場の源)であるエネルギー運動量テンソル」であると説明されている。
アインシュタイン自身は、実は、この式に、終生、満足していなかった。
次は、この式についてのアインシュタイン自身による評価に関する興味深い記述である。
|
『一九二一年までには、著名な人物のなかでこの理論にまだ不満を抱いているのはアインシュタイン本人だけとなっていた。この理論全体が一貫して対称性を持つようにと望んでいた彼の厳しい目からすれば、この方程式の左辺については、これは時空の幾何学によって表現されており、堅固なものと言ってよかったが、右辺のほうは、そうとはいえなかったのだ。 彼は、この方程式のことを、お粗末に設計された建物になぞらえて、半分は「高級大理石」でできているのに、もう半分は「粗悪な材木」でできているようなものだとけなしたことまであった。不満を抱えた彼は、残りの生涯のほとんどを、この建物を修繕するという無駄な努力に費やす。三〇年以上かけてこの修繕作業を続けたのに関わらず、彼はそれに成功することはなかった。』
(『世界でもっとも美しい10の物理方程式』p.329 下線は、筆者による)
|
アインシュタイン自身が、とりわけ不満を持ち続け、「粗悪な材木」とまで言わしめた方程式の右辺(−kTμν= −(8πG/c4) Tμν)について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、どのように説明するのであろうか?
まず、1つ言えるのは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、右辺の「時空を曲げる原因」として、“重力場のエネルギー”を入れるのはナンセンスであるということである。 なぜなら、上でも説明したように、“重力場のエネルギー”は、通過点にすぎず、源ではないからである。
すなわち、“重力場のエネルギー”は、「時空を曲げる原因」ではなく、時空を曲げる原因(重力子の放出源)によって生じた“結果”(通過する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和の所産)に過ぎないのだ。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、右辺の重力場の源は、(「重力子の通過点」ではなく)あくまで、「重力子の放出源」でなければならない。
それでは、右辺のテンソルTμνの成分──「物質のエネルギー密度や圧力(力/面積)」は、本当に、重力子の放出源になっているだろうか?
そういう目で見ると、右辺のテンソルTμνの成分の一例である“圧力(力/面積=[kg・m/s2][1/m2])”は、運動エネルギー(内部&外部)の密度(力×距離/体積=[kg・m/s2][m][1/m3]=[kg・m2/s2][1/m3]=質量×速度2/体積))と解釈することも可能であることに気づかれる。
(参考 『ひとりで学べる一般相対性理論』 p.186〜187 9 物質のエネルギー・運動量テンソル 唐木田健一 講談社)
このことは、右辺のエネルギー運動量テンソルTμνの成分は、「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」(=運動エネルギー(内部&外部))の密度であると解釈することが可能であることを意味する。 このことは、EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で、すでに「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギー」(=運動エネルギー(内部&外部))は、ともに重力子の放出源として働く能力を持つ」と説明してきた内容とうまく調和している。
つまり、右辺のエネルギー運動量テンソルTμνの成分は、やはり、まさに重力子の放出源を意味していると言えるのだ。
右辺のエネルギー運動量テンソルTμνの成分である、「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」(=運動エネルギー(内部&外部))の密度を、近似的に、Vを総体積として、 Mc2/V[J/m3]と表記することとする。
なぜなら、(この中のMc2[J] は、一見、静止質量エネルギーしか考慮していないようにも見えるが──) この質量M[kg]が、特殊相対性理論によって定まる、M=M0(1−v2/c2)-1/2[kg]であると考えることにより、静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの両方を含むもの(=運動エネルギー(内部&外部))であると理解できるからである。
(M0を静止質量とすると、v≪c なら、Mc2≒M0c2+M0v2/2[J] となるのだった。
なお、エネルギー運動量テンソルTμνの中の「運動エネルギー(内部&外部)の密度」と解釈できる成分には、それぞれ係数1/2がかかっていない。 これは、(特殊相対性理論が“剛体であること”を前提にしているのに対し)一般相対性理論では、“完全流体であること”を前提としているからだと考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である)
アインシュタイン方程式は、この「運動エネルギー(内部&外部)の密度 Mc2/V[J/m3]」 が、時空の曲がり(曲率)に比例することを意味している式なのである。
さっそく、この比例定数、アインシュタインの重力定数k=8πG/c4 をニュートンの重力定数Gの別表記G=2πc3LP2/h を使って書き換えてみよう。
すると── 単純に、 k=4LP/EG となることがわかる。 (EG=EP/2π=ch/(2π)2LPを使用)
(EG[J]は、重力子エネルギーであり、1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が持っているエネルギーである。 なお、プランクエネルギーEP[J]を使うと、EG=EP/2π[J]と表記できるのであった)
これを使うと、アインシュタイン方程式の右辺は、−kTμν=−4LPTμν/EG となる。
エネルギー運動量テンソルTμνの成分は、Mc2/V[J/m3]であるとしたのだった。 よって、「Tμν/EGの成分」は、「Tμν/EGの成分」=(Mc2/EG)/V=NM/V[個/m3]と変形できる。
NMは、ある質量M[kg]が、重力子質量MG[kg]の何個部分に相当するかを示す数であった。 重力子質量MG[kg]1つとは、厚さ2LP[m]の球殻に、常に、1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を存在させる質量であり、NM(=M/MG)[個]とは、厚さ2LP[m]の球殻に、常に存在する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数に相当するのだった(例えば、この体積の中にある、物体の「静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギー」(=運動エネルギー(内部&外部))が、EG[J](MG[kg])の100個分に相当するならば、NM=100[個]であり、周辺の「厚さ2LP[m]の各球殻」の中には常に、100個分の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が存在することになる)。
したがって、「Tμν/EGの成分」=NM/V[個/m3]は、「NM(重力子質量数(質量M[kg]が重力子質量MG[kg]の何個分かを示す数))の密度テンソル」あるいは、「“重力子放出数(厚さ2LP[m]の球殻に存在する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数)”密度テンソル」と呼べるものであることがわかる。
つまり、以上の言い換えは、アインシュタイン方程式の右辺が、“重力場の源”、すなわち、「重力子の放出源」であることを、より明確に示しているものであることがわかる。
ここで、まずは、総体積V[m3]を、ふつうに考えて、半径r[m]の球であると近似してみよう。 すると、V=4πr3/3[m3] であるので、
アインシュタイン方程式の右辺の成分の近似値は、次のように変形できる。
kTμνの成分≒−kMc2/V
=−3kMc2/4πr3
=−(3kMc2/4πr)×(1/r2)
= −(12LPNM/4πr)×(1/r2) (k=4LP/EG Mc2/EG=NM を使用)
= −(3LPNM/πr)×(1/r2)
= −(NM/4nπ)×6×(1/r2) (一部に r=2nLP を使用)
アインシュタイン方程式の右辺−kTμνの成分≒−(3NM/2nπ)×(1/r2) の単位は、[1/m2]であるので、左辺の“曲率”の単位と調和している。
|
『左辺(“曲率”)は単位cm-2をもつ』
(p427 『重力理論 Gravitation─古典力学から相対性理論まで、時空の幾何学から宇宙の構造へ』 Charles W.MISNER Kip S. THORNE John Archibald WHEELER 若野省己[訳] 丸善出版)
|
なお、(1/r2)[1/m2]の項は、「半径r[m]の球面」が持つガウス曲率K[1/m2]に相当することがわかる。
なぜなら、半径r[1/m]の球面の曲率は、どこの場所においても、1/r [1/m]であり、ガウスの曲率Kは、K=1/ρ1ρ2=1/r2[1/m2]と求まるからである。
そして、(NM/4nπ)×6の項は、ニュートンの重力ポテンシャルエネルギーと比例するものであることがわかる。
なぜなら、(無限遠点でのエネルギーを0としたときの)重力ポテンシャルエネルギーは、
−GM/r
=−NMEG/4πn×(1/MG)
=−(NM/4πn)×(c2)(EG=MGc2 を使用)
と変形できるので、
kTμνの成分≒−kMc2/V
= −(NM/4nπ)×6×(1/r2)
= (−GM/r)×6×(1/c2)×(1/r2)
となるからである。
したがって、重力ポテンシャルエネルギーの方を、c2で割り、そこに6をかけると、“ある種の時空の曲り”が求まることになる。
この重力ポテンシャルエネルギーに比例する“時空の曲り”とは何か?
それは、まさに、“重力ポテンシャルエネルギーのカーブ”と相似であるところの“時空の曲り”である。
つまり、下図のようなカーブと相似なものが、重力ポテンシャルエネルギーに比例するところの“時空の曲り”なのである。
※このカーブが、重力ポテンシャルエネルギーに比例するところの“時空の曲り”に相当する。
そして、この「重力ポテンシャルエネルギーに比例するところの“時空の曲り”」は、自由落下運動によって消すことのできる“時空の曲り”に他ならない。 |
c2で割ることにはどのような意味があるだろうか?
重力ポテンシャルエネルギー=−GM/r[J/kg]=−NMEG/4πn×(1/MG)[J/kg](=−(NM/4πn)×(c2)[J/kg])を、c2で割ることには、「EGや1/MGの項を消去し(or重力ポテンシャルエネルギー[J/kg]=[m2/s2]の単位を消去し、無次元化し)、中心にある質量M[kg]から放出される“重力子数(厚さ2LP[m]の球殻に存在する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数)”を導く」という意味があると思われる。
そして、NMの方、すなわち、「Mc2がEGの何倍か?」の方が、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの合計」(=運動エネルギー(内部&外部))を、より考慮しやすいという意味もあると思われる。
(なお、同様に、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの合計」(運動エネルギー(内部&外部))を考慮しやすい重力の式は、(Mc2/EG)×(1/4πn2)であるということにもなるであろう。 (詳細な検討は、今後の課題である))
それでは、6をかける意味は何であろうか?
そこで、次に、上の《“時空の曲がり”&重力場の実体像》において引用した、次の記述を活用してみることにした。
|
『この二次元の球面世界に対して三次元の類比物、つまりリーマンによって発見されている三次元の球状空間が存在する。その諸点もまたすべて同等である。それはその〈半径〉R によって決まる有限の体積(2π2R3)を占める。』
(p.141〜142 『特殊および「一般相対性理論」について』 A.アインシュタイン著 金子務 訳 白揚社 下線は、筆者による)
|
このV=2π2R3[m3]を用いて、(V=4πr3/3[m3]の代わりに)さっそく、アインシュタイン方程式の右辺を書き換えてみよう。
すると、次のように比較的シンプルになる。
−kTμνの成分≒−kMc2/V
=−kMc2/2π2R3
=−(4LP/EG)×(Mc2/4π2nLP)×(1/R2)
(k=4LP/EG 一部に r=2nLP を使用 Mc2/EG=NM を使用)
=−(NM/π2n)×(1/R2)
=(−GM/r)×(4/π)×(1/c2)×(1/R2) (−GM/r=−(NM/4πn)×(c2)を使用)
c2で割るのは前と同じである。 しかし、今度は、“6”をかける代わりに、4/π≒1.27 だけをかければ済むことになる。
後者が正しいとすれば、6をかける意味は、「単なる誤差」なのだろうか?
それでは、4/πをかける意味は何であろうか?
考えた範囲では、その意味を見いだすことができなかった。
一方、4/πをかける意味も「単なる誤差」と考え、すなわち、4/π≒1と考え、(NM/π2n)≒(NM/4πn)と見なした方が、意味がすっきりして理解しやすいと思われた。
(だとすれば、最初から(V=2π2R3[m3]の代わりに)V=8πR3[m3]を用いればよかったことになる。ただし、後者の体積は、ふつうの球の体積V=4πr3/3[m3]のぴったり6倍に他ならない。これは、空間を6倍に膨張させるという意味を持つと考えてよいのだろうか? だとしたら、先に「単なる誤差」の可能性を考えた「6をかけること」の意味は、「空間を6倍に膨張させること」だったことになる。 また、だとしたら、なぜ6倍なのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である)
いずれにせよ、曲率については、少なくとも、その方がよりシンプルで自然に近いと思われるので── この重力ポテンシャルエネルギーに比例する項としては、−(NM/π2n)(≒−(NM/4πn))、すなわち、4/πをかける方(全体積をV=2π2R3[m3]とする方)(≒1をかける方(全体積をV≒8πR3[m3]とする方))を採用していくこととする。
アインシュタイン方程式の右辺の成分は、ガウスの曲率K=1/r2[1/m2]と重力ポテンシャルエネルギーU=−NMEG/4πn[J]に比例する項(≒U/EG)の積で示される。
そして、前者が、「自由落下運動によって、消すことができない時空の曲がり」を意味する項であり、後者が、「自由落下運動によって、消すことができる時空の曲がり」を意味する項である。
比較して整理すると、次のようになる。
|
アインシュタイン方程式の右辺−kTμνの成分
≒−(NM/π2n)×(1/r2)(≒−(NM/4πn)×(1/r2))
|
|
右辺kTμνの中の各項
|
−(Mc2/EG)×(1/π2n)[無次元]
(≒−(Mc2/EG)×(1/4πn)[無次元]
=重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG[無次元])
|
(1/r2)
[1/m2](∝[cm-2])
|
|
各項の意味
|
「自由落下運動によって、消すことができる時空の曲がり」
[重力ポテンシャルエネルギーのカーブに比例する“時空の曲り”]
|
「自由落下運動によって、消すことができない時空の曲がり」
「半径rの球面のガウスの曲率K(スカラー曲率R)に相当する“時空の曲り”」
|
|
「時空の曲がり」を生じる原因
|
「重力ポテンシャルエネルギー」の変化のカーブそのもの
=『質量エネルギー(静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの和
すなわち、運動エネルギー(内部&外部))が放出する
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が創発するものの1つ』)
|
「球状の形」
=『質量エネルギー(静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの和
すなわち、運動エネルギー(内部&外部))が放出する
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が創発するものの1つ』)
|
|
その他
|
等価原理、計量gμν、潮汐力の一部と関連
|
「自由落下する2つの物体が互いに近づく現象」(潮汐力の一部)と関連
|
アインシュタイン方程式の右辺の成分そのものが、すでに“曲率”に相当するのである。
一方、左辺のテンソルの成分も、曲率を意味するのだった。
つまり、アインシュタイン方程式は、“曲率=曲率”を意味する方程式(曲率の別表記(2種類の表記)をイコールで結んだ式)であったことになる。
|
左辺: Gμν= Rμν−gμνR/2 の中で、 −gμνR/2 の方をまず見てみよう。
ガウスの曲率Kと、 スカラー曲率Rの間には、次の関係がある。 K=−R/2 (『一般相対性理論』(p 115 Torsten Flieβbach著 共立出版))
そして、計量gμνは、重力ポテンシャルエネルギーに関係すると言われている量である。
つまり、 −gμνR/2=gμνK は、上記で説明した右辺が意味するもの(≒(重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG)×ガウス曲率K)と、おおよそ調和していることがわかる。
左辺の中の残りのRμνの方は、どうだろうか?
『一般相対性理論』(p 115 Torsten Flieβbach著 共立出版)の中に、半径aの球面を例として考えた、次の3つの数式がある。
|
『 Rip=gkmRmikp=gipR1212/g (18.22)
R1212=〜=−a2sin2θ (18.26)
g=a4sin2θ 』(一部省略)
|
これらを使って単純な代入計算(高校数学レベルの計算)を行うと Rip=gipR1212/g = gip×(1/a2) となり、やはり、右辺が意味するもの(≒(重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG)×ガウス曲率K)と、おおよそ調和していることがわかる。
やはり、アインシュタイン方程式は、本質的には、“曲率=曲率”(すなわち、おおよそ「(重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG)×ガウス曲率K」を意味する2つの方程式(曲率の2種類の表記)をイコールで結んだ式)であることがわかる。
|
このことは、何を意味するのだろうか?
「普遍的な数式なので、アインシュタイン方程式に無駄がない」という考えもありうるだろう。しかし、次の3つの理由で、無駄がある可能性がある。
|
〈1〉アインシュタイン方程式を厳密に解くことができるのは、“球形”のときであること(シュバルツシルト解…)
〈2〉自然界に実在する多くの天体は、ほとんど球形と見なせるものだけであること
〈3〉アインシュタインがリーマン幾何学を駆使して10年かけて苦労して計算によって導いた、アインシュタイン方程式の本質が── 質量『運動エネルギー(内部&外部)が持つ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働く能力』と重力場『厚さ2LP[m]の各球殻の時空(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)に生じる重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和』との関係として、シンプルに理解できること。
|
※なお、アインシュタイン方程式によって解くことができない系についても、もしかしたら、「重力子&原始ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、密度、分布(配置)…」の総和として、厳密に&シンプルに再定式化することによってなら解くことができる(理解が深まる)ということがあるかもしれない。
(詳細な検討は、今後の課題である)
|
いずれにせよ、アインシュタイン方程式は、質量が生じる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として創発する「重力ポテンシャルエネルギー」、および、同じ質量が生じる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の「球状の配置」として創発している“時空の曲がり(曲率)”という自然(nature)を、「(想像できない)連続な時空における所産」として近似して示している式であると解釈できるのである。
すなわち、アインシュタインの一般相対性理論の抽象的な数式は、質量エネルギー(=運動エネルギー(内部&外部))が生じる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動、密度、分布(配置)…」の総和を、連続時空における所産である見なすマクロ(粗視化)近似によって表現しているものであると解釈できるものなのである。
以上の内容(アインシュタイン方程式の意味)を整理して図示すると、おおよそ、下のようになる。
すなわち、仮に「物質の体積が同じであっても、静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(すなわち、運動エネルギー(内部&外部)の総量)」が大きくなるのに比例して、周囲の“時空の曲がり”(曲率)も大きくなっている。
|
|
|
|
※オレンジで示した物体は、体積のみが同じで、物質の総質量エネルギー(重力子の放出源となる能力、静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総和)
の密度は異なっている。
ただし、その質量エネルギーの密度がそれぞれ異なっているものを3パターンだけを示してある。
質量エネルギーの密度が大きいほど、それに比例して、物体の周囲の「時空の曲がり」は大きくなると考えられる。
※時空の曲がりは、2種類の効果(原因)から生まれるのだった。
(2種類の効果(原因)とは、「重力ポテンシャルエネルギー」(=「各“厚さ2LP[m]の球殻に存在する重力子の球面密度”の合計」)と
「“厚さ2LP[m]の球殻が持つ“球状の形”」の2つである)
上の図の3つのパターンにおいては、「球状の形」による時空の曲り(=1/r2、すなわち、ガウス曲率K)は、どれも共通である。
したがって、これら、3つのパターンの違いは、「重力ポテンシャルエネルギー」による“時空の曲り(−(NM/π2n)(≒−(NM/4πn)))の違いに
相当することになる。
|
|
|
つぎに、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」の状況で、その中心(重心)に向けて、その全体積 V[m3]だけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを考えてみよう。
全体積V[m3]が小さくなると、それに反比例して、「物質の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)の密度」は、大きくなる。
|
|
|
|
※オレンジで示した物質の総質量(重力子の放出源となる能力、静止質量エネルギー&運動エネルギーの総和)の大きさと、重心はどれも同じである。
ただし、その総質量の体積密度のみがそれぞれ異なっているものを3パターンだけを示してある。
左に行くほど、質量の密度が大きくなり、物体がコンパクト化していると同時に、その周囲の“時空の曲がり”も大きくなっているのが読みとれる。
※これらの図が示す系においては、(「球状の形」による時空の曲り(=1/r2[m-2]、すなわち、ガウス曲率K)のみならず)
「重力ポテンシャルエネルギー」による時空の曲り(−(NM/π2n)(≒−(NM/4πn)))が変化していることが、よりわかりやすい。
|
|
|
ここで、重要な性質が浮かび上がってくる。
それは、「静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総和」の大きさと重心が一定である限り── たとえ総体積(すなわち密度)が異なったとしても、
例えば、上の共通する図の“2重の緑の間”の場所での“時空の曲がり”は、どれも全く同一のままになっているという性質である。
それを言い換えると、時空の中で、想像上の半径rの球面を考えた場合、その内側で、「静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総和」の大きさと重心が一定である限り、静止質量エネルギーや(外部)運動エネルギーの分布がどのようになっていても、その想像上の球面の外側の重力場は全く変化しないという性質である。
よって、次の結論に至る。
結論1.9 ある想像上の半径rの球面の外側の時空の曲がりは、外部との物質的なやりとりがなく、「静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総和」の大きさと重心が一定である限り、(その球面の内部での状態(分布…)がどうであろうと関係なく)、全く同一となる。
この性質を使うと、便利である。
ある系によって生じる、ある場所での重力場を求めるためには、「ある系を取り囲み、ある場所に接する球面」を考え、「静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総和」の大きさと重心が一定のまま、重心へ向けて可能な限り小さくしたもの、すなわち、「仮想的な質点」を考えて、その「仮想的な質点」からの距離”を用いれば十分であることになるからである。
※この「仮想的な質点」と、ニュートンが考え出した質点は、本質的に同じものである。
※ただし、もし、物体の総質量自身の重力によってコンパクト化が進み、質量密度が高まる場合は、「重力ポテンシャルエネルギーの減少&(外部)運動エネルギーの増加」(by 力学的エネルギー保存則)によって、重力子の放出源として働き続ける能力、すなわち、質量、すなわち、「質量エネルギー&運動エネルギーの総和」が、大きくなることを考慮しなければならない。
なお、この過程は、「重力は、非線形である」という解釈を誘いうる現象の根底に起きていることであると言える。
しかし、実際は、重力場は線形であると考えられる。(→《重力場の線形性について(詳細版)》 )
※ところで、物体の総質量自身の重力によってコンパクト化が進み、質量の密度が高まり続ける場合、実際には、最高どれだけ小さくなることができるだろうか?
ペンローズ&ホーキングの特異点定理によれば、“大きさを持たない点”ということになる。 しかし、それは「時空が、連続で微分可能であること」を前提として生まれた結論に過ぎない。
時空を、不連続で微分不可能であることを前提とする“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、異なった結論に至る。
すなわち、最小の体積Vmin[m3]は、ある一定以上の値となると考えられる。(→結果6、付録『EMOES宇宙論』)
アインシュタインは、連続(なめらか)で微分可能であることを前提とする、抽象的なリーマン幾何学にもとづき、10年かけて、とても苦労する計算を進めることによって、重力場についての方程式、すなわち、アインシュタイン方程式の構築にたどり着いた。
アインシュタイン方程式が、とても複雑難解なものであることは、次のような記述からも読みとれる。
|
『ガウスやリーマンの非ユーリッド幾何学と、重力を関連づけたその方程式の背後にある理論は美しい──物理学者が好む言いまわしでは「エレガントな」──ものの、その細部は乱雑に見えなくもない。 実際には、時空の幾何学を表す一〇の関数を持つ一〇の方程式が書かれていて、すべて非線形でお互いに絡まり合っているため、一般的に関数をひとつずつ解いていくことはできない。』
(p.44 『パーフェクト・セオリー 一般相対性理論に挑む天才たちの100年』 ペドロ・G・フェレイラ 高橋則明 訳 NHK出版 下線は、筆者による)
|
|
『一般相対論は、他のアインシュタインの業績に比べて、いろいろな点で異なっている。これ以前の論文では、あまり難しい数式は使われていない。アインシュタイン自身、高等数学の計算はそれほど得意ではなかったことが窺える。難しい計算を行なうよりも前に、本質を浮かび上がらせるような思考実験を行なって結論を先取りしてしまうのだ。計算は、結論の確認と細部の詰めに使われる程度だった。ところが、一般相対論は、研究者泣かせと言えるほど数式が難しい。物理的なイメージだけでは話を進められず、計算を遂行してはじめて何が起きるかが判明することも少なくない。
物理学の理論的な研究において数式の扱いが主要部分を占めるようになる傾向は、すでにマクスウェルの電磁気学やボルツマンの統計力学の頃から現れていたが、アインシュタインの一般相対論によって、決定的なものになった。世界は数学的な秩序に従っている。だが、この数学的秩序は、初等幾何学や代数計算で示されるほど簡単なものではない。最先端の物理学を理解するためには、まず、大学院レベルの高等数学をマスターしなければならない。難解な数式と格闘した末、何とか導き出した命題を実験や観測デーと比較して、ようやく理論の検証が可能になる。そこには、直観的なイメージを利用できる余地など、大して残されていないのである。こうした方法論の変革が、イメージ優先の思考実験を得意とするアインシュタインによってもたらされたとは、何とも皮肉なことである。
数式を使わなければ一般相対論から有用な命題を導けない──このことは、アインシュタインにとっても厄介の種となった。自分が作り上げた最も輝かしい理論が、自分にも理解しにくいものになってしまったのである。』
(p.101『思考の飛躍 アインシュタインの頭脳 吉田伸夫 新潮社』
|
それは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による重力場を示す式(−NMEG/4πn×(1/MG)[N/kg])、曲率を表す式((NM/π2n)×(1/r2)(≒(NM/4πn)×(1/r2))[1/m2](∝[cm-2])が、とてもシンプルであることと対照的である。
(そこにあるのは、やはり、ほぼ高校数学レベルである。 しかも、微分積分は基本的に使われず、その代わりには、割り算や級数(数列の和)を用いるだけである。 それでいて、ミクロの量子化した重力も、マクロの重力も説明できる。)
|
アインシュタインの一般相対性理論
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による
重力場、重力、時空の曲り… の説明
|
| 数学 |
複雑、難解、抽象的
「一〇の方程式が書かれていて、
すべて非線形でお互いに絡まり合っている」
「研究者泣かせと言えるほど数式が難しい」
「大学院レベルの高等数学をマスターしなければならない」
「直観的なイメージを利用できる余地など、
大して残されていない」
|
具体的、シンプル
具体的な幾何、具体的な数式
(ほとんど、せいぜい高校数学レベル)
理解が比較的容易
「直感的なイメージを利用できる」
|
なぜ、アインシュタインの方程式は、これほど、複雑で難解なものになっているのか?
1つは、やはり、アインシュタイン自身が、「時空の曲がりの実体が、いったい何なのか?」「時空の曲がりが、どのようにして(なぜ)生じるのか?」がよくわかっていなかった(具体的にイメージできなかった)からに他ならないだろう。
「時空の曲がり」についての、具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)をつかむことが、どうしてもできず、その探求をあきらめたからこそ、やむを得なく、抽象的なリーマン幾何学に頼って重力場を定式化するという「忍耐、執念、力技、離れ業…」を要する非常に困難な道を、10年もかけて、アインシュタインは突き進んだのだ。
その結果、「本来、不連続で微分不可能な時空として、創発している、ミクロの自然(nature)」を、 連続(なめらか)で微分可能性を前提とする、抽象的なリーマン幾何学を駆使して表現しようとすることに、多大な“無理”が生じ、本来シンプルになりうる数式が、とても複雑になってしまったと考えられるのである。
逆に、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による数式が、これほど、シンプルでわかりやすいのはなぜか?
「自然(nature)そのものが、ズームインするほどシンプル化する」という自然な世界観と調和しているからである。
そして、「時空の曲がりの実体が、いったい何なのか?」「時空の曲がりが、どのようにして(なぜ)生じるのか?」についての幾何的な実体像を、具体的にイメージできているからであると言えるだろう。
つまり、アインシュタインのアプローチと“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のアプローチの違いの本質は、具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)の探究を重視するかどうか(あきらめないかどうか)なのである。
アインシュタインは、一般相対性理論の定式化にあたり、具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)の探究をあきらめ、やむを得なく、抽象的な幾何(リーマン幾何学)、抽象的な数式… をのみを重視するようになった。 その結果、その数学は複雑で抽象的なもので、理解が困難なものとなった。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、重力場についても、具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)の探求を重視した(あきらめなかった)。 その結果、その数学(数式、幾何…)は、シンプルで具体的なもので、理解が比較的容易なものとなっているのである。
|
アインシュタインの一般相対性理論のアプローチ |
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のアプローチ |
|
具体的な
“幾何学的な実体像”
の探求
|
あきらめた
|
あきらめない
|
|
数学
(数式、幾何…)
|
抽象的
(リーマン幾何学、テンソル…)
複雑、難解
|
具体的
(具体的な幾何、具体的な数式)
シンプル
|
|
時空
|
連続
|
不連続
|
|
エネルギー保存則
|
成り立つ
|
成り立たない
(重力子は、エネルギー非保存の所産である)
|
※なお、時空が連続か不連続かどうかは、エネルギー保存則が成り立つかどうかと深い関係があるのだった。
そして、10年かけて、どうにかこうにかやっとの思いで作り上げたアインシュタイン方程式について、誰よりも不満を持ち続けていたのは、他ならぬ、アインシュタイン自身であった。
|
『一九二一年までには、著名な人物のなかでこの理論にまだ不満を抱いているのはアインシュタイン本人だけとなっていた。この理論全体が一貫して対称性を持つようにと望んでいた彼の厳しい目からすれば、この方程式の左辺については、これは時空の幾何学によって表現されており、堅固なものと言ってよかったが。右辺のほうは、そうとはいえなかったのだ。 彼は、この方程式のことを、お粗末に設計された建物にぞらえて、半分は「高級大理石」でできているのに、もう半分は「粗悪な材木」できているようなものだとけなしたことまであった。不満を抱えた彼は、残りの生涯のほとんどを、この建物を修繕するという無駄な努力に費やす。三〇年以上かけてこの修繕作業を続けたのに関わらず、彼はそれに成功することはなかった。』
(『世界でもっとも美しい10の物理方程式』p.329 下線は、筆者による)
|
アインシュタインは、実際、アインシュタイン方程式に宇宙項を追加しては、それを間違いであると悔やんだり──
|
『一般相対論的重力場の理論の概念と方法を拡張することによって、電磁場も含めた統一理論を得ること』
(アインシュタイン選集2 B7 p.323)
|
を探求したりもした。
これらのことは、明らかに、アインシュタイン方程式には、発展の余地、アップグレードできる(すべき)点があったことを示していると思われる。
※そして、実際、次のような進展もあった。
|
『(アシュテカは)アインシュタインの重力場の方程式を解く巧妙な方法を思いつき、方程式を書き直すことで最悪の非線形性の大半を消して、一般相対性理論をはるかに単純に見えるようにした。』
(p.268『パーフェクト・セオリー 一般相対性理論に挑む天才たちの100年』(ペドロ・G・フェレイラ 高橋則明 訳 NHK出版
“(アシュテカは)”は、筆者による補足である。 下線は、筆者による)
|
|
『〜、Einstein理論に対する新たな正準理論はAshtekar 理論と呼ばれる. Ashtekar 理論はいくつかの優れた特徴を持っている. その第1は、理論に現れる諸式が基本変数の簡単な微分多項式となっていることである. 第6章で展開した計量を基礎とする正準理論(ADM理論)では拘束関数が計量の複雑な非線形式(実は分数式)となっていたことを思い起こすと,これは大幅な進歩である.』
(『岩波講座 現代の物理学6 一般相対性理論』 p.215 佐藤文隆・児玉英雄著 岩波書店 一部省略、下線は、筆者による)
|
※さらには、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示す、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギー」(=運動エネルギー(内部&外部))こそが重力子の放出源であるという描像、そして、自由落下運動で消せる「重力ポテンシャルエネルギーによる時空の曲り」と、自由落下運動で消せない「球面の配置による時空の曲り」の積が、右辺に相当するという説明は、『「粗悪な材木」できているようなもの』と自己評価が低かった、アインシュタイン方程式の右辺を、強固な『「高級大理石」』と評価できるものまでグレードアップするために役立つ可能性があると思われる。
(詳細な検討は、今後の課題である)
アインシュタインが、おそらく最も不満に思っていたことの1つは、一般相対性理論とエネルギーの関係についてであった。
そのことは次の記述から読み取れる。
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より p.170〜171 下線は、筆者による)
|
この問題は、『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』ほどの重大なものであった。
アインシュタインは、時空を連続なものと見なし、エネルギー保存則が成立すると考えていた。
それは、アインシュタインが、(連続な時空を前提とする)リーマン幾何学に依存していたので、当然のことであった。
しかし、だからこそ、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』が、問題になったのだ。
(すなわち、時空が不連続であることを前提にしていれば、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』は問題にならないのである)
一方で、アインシュタインは、アインシュタイン方程式の導出にあたり、最終的には、相対性原理ではなく、「エネルギーおよび運動量保存則が成立すること」を最大の根拠としていた。
そのことは、次の記述から読みとれる。
|
『そこで一般相対性理論でも、物質のエネルギー・テンソルTσμ を考えよう。 〜。
このエネルギー・テンソル(これはポアッソン方程式のρに対応する)が重力場の方程式のなかにどんな具合に挿入されなければならないかは、(51)式が教えてくれる。すなわち、いま一つの完全な系(たとえば太陽系)を考えよう。 この物理系の全質量、したがってまたその全重力的作用は、この物理系の全エネルギー、つまり物質によるエネルギーと、重力場のエネルギーの総和に依存する。この事情は、(51)において、重力場のエネルギー成分tσμのかわりに、物質および重力場の両方のエネルギー成分の和tσμ+Tσμ を導入することによって表現される』
(アインシュタイン選集2(p97) 下線は、筆者による)
|
|
『上で述べたような物質のエネルギー・テンソルの導入の仕方は単に相対性の要請からでは正当化されないということに注意しなければならない。ここでは、われわれは、次のような要求を用いて、上の式を導いた。すなわち重力場のエネルギーは、他のどのようなエネルギーとも同じ形の、重力的作用をもつべきであるという要請である。しかし、ここに求められた方程式の正当性に対する最も強い根拠は、むしろこれらの式から導かれる次のような結果にある。すなわち、全エルネギー成分に対して、エネルギーおよび運動量保存則が成立することである。つまり全エネルギー成分に対して、(49)、(49・a)に相当する式が成立する。』
(アインシュタイン選集2(p98) 下線は、筆者による)
|
しかし、やはり、だからこそ、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』が、問題になったのだ。
(すなわち、やはり、時空が不連続であることを前提にしていれば、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』は問題にならないのである)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、重力場は、『エネルギー非保存の所産である「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和』として創発するものである。
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、少なくとも「エネルギー保存則が成立すること」を“最大の根拠”とすることはできないのは明白である。
また、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、“重力場のエネルギー”は、質量(重力子の放出源として働き続ける能力)ではありえず、「通過する重力子エネルギーの総和」にすぎないのであった。 したがって、『この物理系の全質量、したがってまたその全重力的作用は、この物理系の全エネルギー、つまり物質によるエネルギーと、重力場のエネルギーの総和に依存する』や『すなわち重力場のエネルギーは、他のどのようなエネルギーとも同じ形の、重力的作用をもつべきであるという要請である』という記述は、自然(nature)から乖離していることになる。
なぜ、アインシュタインは、このような、“考え違い”をしてしまったのか?
その理由の本質は、やはり、ひとえに、アインシュタインが、具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)をもっていなかったことだと考えられる。
その結果、次のようになってしまったのである。
〈1〉「時空の曲がりの実体が、いったい何なのか?」「重力場が、どのようにして(なぜ)生じるのか?」を説明できないままにせざるをえなくなった。
〈2〉エネルギー保存則にしばられることになってしまった。
時空が連続であるという考えや(連続な時空を前提としている)リーマン幾何学に対して、疑問を抱くことができなくなってしまった。
〈3〉“抽象的な数式”(E=mc2…)の意味を正しく解釈できなかった。 重力場のエネルギー自体が、質量になりうると考えてしまった。
つまり、アインシュタインは、「重力場、時空の曲り、重力子、重力波…」についての具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)を持っていなかったからこそ── やみくもに、“抽象的な数式”(リーマン幾何学、E=mc2…)や抽象的な物理理論(エネルギー保存則、運動量保存則、ネーターの定理…)に頼るしかなかったのである。
そして、その結果、その数学が、「研究者泣かせと言えるほど」難解なものとならざるをえなかったのである。
そして、だからこそ、出来上がった数式は、『もう半分は「粗悪な材木」できているようなものだ』という不満を抱かせるほど不完全なものにならざるをえなかったのである。
そして、その不完全性に、誰よりもアインシュタインが気づいていたからこそ、アインシュタインは、生涯、不満を持ち続け、グレードアップを試み続けることとなったのである。
そして、アインシュタインを迷走させたのだ。
※なお、アインシュタインが提唱した“光子”(光量子)という発想さえも、実は、具体的な幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)をともなっていなかったことが次の記述から読み取れる。
|
『“すべての物理学者は光子が何であるか知っていると思っている”とアインシュタインは書き、さらに“私は光子とは何であるのかの問題に答を見いだすのに一生を費やしたが、いまだにわからない”と続けている』(p.10 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』)
|
したがって、「いわんや、重力子をや」なのは明らかである。
やはり、誰よりアインシュタイン自身が、何かがおかしいことに気づいていたからこそ、アインシュタインは、次のような文章を自ら紡ぐに至っていたのである。(再掲する)
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より p.170〜171 下線は、筆者による)
|
このアインシュタインの『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』疑問を根底から解消しうるものの1つが“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)である。
そして、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、『量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』という記述と調和している。 なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、量子論の完成を助けるものであり(→結果4)、確かに、「アインシュタインの重力理論」の部分的な修正を迫っているからである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、アインシュタインの重力理論に、少なくとも、次の3つの部分的な修正を迫っている。
|
1.時空は連続である
|
→ |
時空は不連続である。
|
|
2.重力場は、エネルギー保存則にしたがう。
(重力場のエネルギーを含む全エネルギーは、
エネルギー保存則に従う)
|
→ |
重力場は、エネルギー非保存の所産である。
(重力場は、「エネルギー非保存の所産である
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和」
として創発している)
|
|
3.重力場は、非線形である
|
→ |
重力場は、線形である。
(重力場のエネルギーそのもそのが、
直接そのまま、質量になりえない)
|
そして、この「アインシュタインの重力理論」の修正により──
重力場を量子化できる。
重力場と電磁場を統合できる。
アインシュタイン方程式の右辺を、「粗悪な材木」から強固な「高級大理石」へとアップグレードできる。
…
というメリットが生まれることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示している。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせまっている「アインシュタインの重力理論」の修正は、アインシュタインが生前なしとげることのできなかった多くの問題を解決できるのである。
むろん、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせんとすることは、アインシュタインの一般相対性理論を否定することではなく── 「より深いレベルの階層」から、これがどのようにして成功し、どのようにしてうまくいかなくなっているのかを説明することである。
例えば、時空が連続と見なせるようなマクロのdレベルでの重力についての記述としての一般相対性理論は、見事に自然(nature)と調和しているのであり── 今後とも有効な理論であり続けることが確かであることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は示している。 しかし一方で、例えば、「時空が連続と見なせないようなミクロのレベルでの重力を考える場面」や「エネルギーに関する場面(エネルギー保存則、重力場のエネルギー、重力波のエネルギー)」においては、一般相対性理論は、自然(nature)から乖離してしまっていることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は示している。
このように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、一般相対性理論の自然(nature)と調和する部分を包含しつつ、一般相対性理論の適用条件を示すものなのである。
アインシュタイン方程式(一般相対性理論)と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の比較をまとめた。
|
アインシュタイン方程式
一般相対性理論
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
方程式
|
アインシュタインの“重力場の方程式”
Rμν−gμνR/2 =−kTμν
曲率テンソル=エネルギー運動量テンソル
※エネルギーや運動量が、時空の曲がりを生むと説明
時空の曲がりが、エネルギーや運動を生むと説明
|
重力場
=(NMEG)×(1/4πn2)×(1/2LP)×(1/MG) [N/kg]
(厚さ2LP[m]の球殻に蓄えられるエネルギーの時間平均=NMEG=Mc2
(≒(低速では)Σ(M0c2+M0v2/2))
=「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」
(運動エネルギー(内部&外部))
=質量エネルギー(「重力子の放出源として働き続ける能力」))
※nが大きくなると、ニュートンの万有引力の法則の式になる。
アインシュタイン方程式の右辺−kTμνの成分
≒(NM/π2n)×(1/r2)(≒(NM/4πn)×(1/r2))
=自由落下で消せる時空の曲がり
(≒重力ポテンシャルエネルギーU/重力子エネルギーEG)
×球状の配置による時空の曲り(=ガウスの曲率K[1/m2])
※「静止質量エネルギーや(外部)運動エネルギー」の総和を源にして生じた、
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が
重力場や時空の曲りを創発すると説明
※nが大きくなると、アインシュタイン方程式の
右辺kTμνの成分の値に近づく。
|
|
時空についての前提
|
「時空は、どこまでも(プランクスケールでも)
連続で微分可能である」
ということを前提としている。
|
「時空が不連続(離散的、とびとび…)で、微分不可能である」
ということを前提としている。
|
|
エネルギー保存則について
|
アインシュタインは、重力場のエネルギーについても
エネルギー保存則が成り立つべきだと考えた。
|
ミクロのレベル(プランクスケール)において、時空は不連続であり、
少なくともエネルギー保存則は成り立っていない。
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は
エネルギー非保存の所産であり、その総和として創発する
「重力場、重力波…」も、エネルギー非保存の所産である。
厚さ2LP[m]の球殻に蓄えられるエネルギーの時間平均は、
どの球殻においても共通のNMEG =Mc2 [J]である。
|
|
ネーターの定理について
|
アインシュタインは、ネーターの定理により、
時間と場所によらず、物理法則は不変であるべきと考えた。
ネーターの定理は、エネルギー保存則の根拠の1つ
|
※ネーターの定理は、「連続な時空のときにエネルギーや運動量が保存すること」
(エネルギー保存則や運動量保存則が成り立たないときは時空が不連続であること)
を示してくれる定理であり、このネーターの定理は、“EMOES”(素スピノール
からの創発モデル)と調和している。
|
|
どのような数学による説明か
|
「重力」や「時空の曲がり」を、
(時空が連続で微分可能であることを前提とする)
抽象的な「リーマン幾何学、テンソル…」を用いて説明
|
「重力」や「時空の曲がり」を
具体的な数式、具体的な幾何、数列や級数… を用いて説明
|
|
“時空の曲がり”について
|
質量エネルギーがあると、どのようなしくみで(なぜ)
時空の曲がりが生まれるのかは不明
|
「静止質量エネルギーや運動エネルギー」
(=運動エネルギー(内部&外部))を源として放出される
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が
(重力場のみならず)“時空の曲がり”を担うと説明
(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の存在数の密度が
高いほど空間は膨張し、時間の流れがスローダウンする)
|
|
重力波&重力子について
|
重力波のみを考え、重力子を考えなかった。
重力波も、エネルギー保存則に従うと考えた。
重力波は、力学的エネルギーE(=K+U)を減らす
(重力波はエネルギーを持ち去る)と考えた。
|
重力波は、「放出される重力子数の変化」として、
創発しているものである。(→下記 《連星系パルサーと重力波について》)
個々の重力子も、重力波(「放出される重力子数の変化」)も、
エネルギー 非保存にもとづいて生じるものである。
したがって、重力波は、力学的エネルギーE=K+Uを減らさない
重力波が生じても、力学的エネルギーE=K+Uは保存される。
(重力波は、エネルギーを持ち去らない) |
|
量子物理学
|
量子物理学との相性は悪い。
|
究極の量子物理学である。
既存の量子物理学の自然(nature)と調和している部分を包含している。
|
|
包含するもの
|
ニュートン力学を包含している。
|
ニュートン力学と相対相対性理論、マクスウェルの電磁気学、量子物理学
素粒子物理学の標準模型… の自然(nature)と調和している部分を包含している。
|
|
E=mc2の解釈
|
質量はエネルギーである。そしてエネルギーは質量である。
質量とエネルギーは、100%等価である。
(あらゆる質量がエネルギーを持つと同時に
あらゆるエネルギーは質量を持つ)
|
質量エネルギーとは、運動エネルギー(内部&外部)である。
質量エネルギーは、エネルギーの一部に過ぎない。
(質量を持たないエネルギーもある。
重力子、重力場、重力波、電磁波(光子の総和)、
仮想光子、電磁場、電荷エネルギーや磁極エネルギーなど)
|
|
線形? 非線形?
|
重力(場)は、非線形である。
|
重力(場)も線形である。
|
《重力場の線形性について(詳細版)》
上でも述べた、『アインシュタインの一般相対性理論によると、重力場が非線形であると説明されるのに対し── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、重力場が線形であると説明されること』について、詳しく説明する。
すなわち、これは、次の仮説を、詳しく検討することでもある。
仮説1.11 重力場そのものは、線形である。
アインシュタインの一般相対性理論において、“重力場が非線形である”と考えられてきた理由は、少なくとも、大きく3つあるようである。
1.アインシュタイン方程式が、「重力場のエネルギーは、新たな質量、すなわち、新たな重力子の放出源として働き続ける能力(=新たな“時空の曲がり”の原因)である」という考えを用いて導出されている。
2.アインシュタイン方程式の中の曲率そのものが、計量gμνの非線形な式となっている。
3.重力ポテンシャルエネルギーによる結合エネルギーの大きさが、「線形なニュートンの重力理論において、GM2/r」であるのに対し、「一般相対性理論においては、2GM2/r」になる。
1.アインシュタイン方程式が、「重力場のエネルギーは、新たな質量、すなわち、新たな重力子の放出源として働き続ける能力(=新たな“時空の曲がり”の原因)である」という考えを用いて導出されている。
再三述べていることであるが──
抽象的な数式のみならず、その解釈、すなわち、具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)も重視する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「“重力場のエネルギー”は、新たな質量、すなわち、新たな重力子の放出源として働き続ける能力(=新たな“時空の曲がり”の原因)である」という考えは、自然(nature)から乖離しているという結論に至る。
この結論は、“抽象的な数式”の解釈を軽視している限り、絶対にたどり着けない結論と言えるかもしれない。
なぜなら、『「あらゆるエネルギーは質量を持つ」→「重力場は、エネルギーである」→「重力場は、質量である」』という論理の流れ自体は、100%正しくて非の打ち所がないからである。
すなわち、「E=mc2」から導く「あらゆるエネルギーは質量を持つ」という解釈の部分を軽視している限り、(その後の論理展開自体は100%正しいので)「重力場は、質量である」という考えの中にひそむ間違い(自然(nature)からの乖離)に気づくことはできないのだ。
しかし、「E=mc2」という数式が持つ本当の意味、すなわち、その数式が意味する具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)を重視すれば、「あらゆるエネルギーは質量を持つ」「重力場がエネルギーを持つので重力場も質量を持つ」「“重力場のエネルギー”そのものを“質量”と見なし、新たな“時空の曲がり”の原因として方程式に代入するべきである」──いずれの説明も、自然(nature)から乖離していること)に明確に気づくことができる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「重力場のエネルギーそのものが(“物体(質量)”という大元の重力子の放出源のように)新たに重力子を放出する源として働き続ける能力を持つ(=新たに質量を持つ)」という意味での非線形性は実在しない、そうはっきり断言できる。 なぜなら、『重力場のエネルギーと質量が全く別物であること』(=『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の通過点として蓄えられるエネルギーの総和と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力が全く別物であること』)は明白だからである。
したがって、やはり、少なくとも「重力場のエネルギー(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の通過点として蓄えられるものの総和)=質量(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力)」という意味での非線形性は、自然(nature)の中には、実在しないのだ。
※「重力場が、新たな質量になる」「“物体(質量)が生んだ重力場”が新たな質量になり、その新たな質量から、さらに新たな重力場が生まれる」という「重力場の非線形性」のアイデアはアイデアは、他ならぬ、アインシュタインの心の中から始まった。
その根本理由は、“E=mc2”という抽象的な数式から、「エネルギーは質量を持つ」という自然(nature)から乖離した解釈を、アインシュタインが導いたことである。
「エネルギーは質量を持つ」を前提とすれば、「(エネルギーを持つ)重力場が、新たな質量になるのだ」という考えが、自然(nature)から乖離していることに気づくことができなくなるのは当然である。 すなわち、「 E=mc2」という抽象的な数式だけを重視し、その解釈、すなわち、ミクロの自然(nature)についての具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)を軽視している限り、この乖離に気づくことができないのである。
(つまり、抽象的な数式(例えば、“E=mc2”)は、慎重に扱わないと、人を裏切りうるのである。 (→考察2))
E=mc2は、本来、決して「あらゆるエネルギーが質量を持っていること」を示す式ではありえないのだ。
実際は、質量とエネルギーは、100%等価ではないのだ。
その理由を整理すると、次のようになる。
|
1.質量とは、「重力子の放出源として働き続ける能力」であり、 質量エネルギーE=mc2とは、「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」、すなわち、運動エネルギー(内部&外部)に他ならない。
つまり、質量と等価なのは、「エネルギー」ではなく、「運動エネルギー(内部&外部)」なのである。
2.エネルギーには、質量エネルギー(=運動エネルギー(内部&外部))の他に、少なくとも、電荷のエネルギー、磁極のエネルギー、光子のエネルギー、重力子のエネルギー、電磁波のエネルギー、重力波のエネルギー、電磁場のエネルギー、重力場のエネルギーがある。
これらの質量エネルギー(=運動エネルギー(内部&外部))以外のエネルギーは、いずれも“重力子の放出源として働き続ける能力”、すなわち、質量を持っていない。
3.エネルギーを持っている「光子や重力子、電磁波や重力波」は、光速で移動できるという意味においても、質量を持っていない。
したがって、「エネルギーが質量を持っている」という解釈や前提は、例えば、アインシュタイン自身が提唱した、光量子仮説の式E=hνとも矛盾してしまっているのである。
|
このように、具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)を重視する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「あらゆるエネルギーが、質量を持っている」という解釈は、自然(nature)と乖離していることが、はっきりわかるのである。
※そういう意味で、mc2=E、あるいは、Em=mc2 が、「誤解釈、誤用、濫用…」を予防する表記と言えるのかも知れない。 詳細な検討は、今後の課題である。
※なお、例えば、光子によって、電子や陽電子のペアが対生成したり、原子が(外部)運動エネルギーを獲得して熱を持ったりする過程は、新たな質量の生成を意味するので、光子のエネルギーが“質量に変換される”ということはありうる。
また、例えば、ある物体が、重力ポテンシャルエネルギー(重力場のエネルギー)を利用して、(外部)運動エネルギーを獲得した場合も、新たな質量の生成を意味するので、重力場のエネルギーが“質量に変換される”ということもありうる。
(質量エネルギーとは、静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの和であった)
ただし、光子や重力場は決して質量(重力子の放出源として働き続ける能力)を持っておらず、あくまで新たに獲得された(外部)運動エネルギーが質量(重力子の放出源として働き続ける能力)を持っているのである。
※なお、“グルーオンの集積したひも”はそのまま形を保ちながら運動できないと考えられるので、クォークの運動エネルギー(内部&外部)のみが質量を担うと考えられる。
詳細な検討は、今後の課題である。
それでは、「重力場のエネルギーが質量となるという」考えを盛り込んで導出されたアインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)は、間違いなのだろうか?
そのことを検討してみよう。
『アインシュタイン選集2』の「物質が存在しないときの重力場の方程式」(p92〜)の項目に次のように書かれている。
|
『たとえば1個の質点によって、そのまわりにつくられた重力場を考えてみよう。この重力場はどんな座標系を採用しても、それを消し去ることはできない。すなわち、gμνを質点のまわりで至る所, 定数のgμνに変換することはできない(訳者注:質点のまわりでは物質は存在しないが、重力場は存在する。 〜)。
そこで、物質が不在の場合の重力場の方程式として、テンソルBσμστから導かれた対象テンソルBμνを0とおくことは、きわめて自然な要求であろう。こうして、10個の量gμνに対して10個の方程式が得られたわけである。 これらの式は、Bσμστがすべて0のときには、もちろん満足される。これらの式は、われわれに好都合な座標系では、(44)を考慮に入れて
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =0
|
(47)
|
| (−g)1/2=1 |
となる。 これが物質が存在しない所での重力場の方程式である。
〜
一般相対性の要求から、まったく数学的な方法で導かれたこれらの場の方程式は、一方質点の運動方程式(46)といっしょになって、第一近似ではニュートンの引力の法則を与える。また第二近似まで考えると、ルヴェリエ(Leverrier)によって発見された水星の近日点の移動(他の惑星による摂動に由来する修正を行なったあとに残る移動量)を説明することができる。これらの事実は、ここに展開された理論が物理的に正当である証拠であると見なしてよいと思う』
(p.93〜94 『アインシュタイン選集2』 一部省略。 下線は筆者による。 数式は、入力の都合上、表記法を変えてあるが、その内容は元の数式と同等のものである)
|
この「物質が存在しないときの重力場の方程式」は、下の一番左の図のものに相当すると見なすことができる。
|
|
|
|
※一番左の図は、「物質が存在しないときの重力場の方程式」、すなわち、「1個の仮想的な質点によって、そのまわりにつくられた重力場」に相当すると見なすことができる。
それに対して、右側の2つは、物質が存在するときの重力場を表していると見なすことができる。
仮想質点と物質の“重力子の放出源として働き続ける能力”が全く等しいので、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、3つとも、全く等しくなっているのだった。
|
|
|
このことは、「物質がないときの重力場」(=「1個の仮想的な質点によって、そのまわりにつくられた重力場」)と「物質があるときの重力場」は、“密度の違い”があるだけで、重力場を作る能力は、本質的には同じと見なすことができることを意味する。
つまり、このことは、「物質が存在しないときの重力場の方程式」、すなわち、「(物質が存在せず)質点のみがあるとときの重力場の方程式」として、考え出された(47)の式だけで、本質的には、もう十分であることを示しているのである。
現に、それだけで、少なくとも、ニュートンの引力の法則も、水星の近日点移動も説明できている。
ところが、物質が存在しない所での重力場の方程式である式(47)──
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =0
|
(47)
|
| (−g)1/2=1 |
をもとにして導かれた、式(47)の“第3の形”── 式(51)
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
をもとに、上記の「“重力場のエネルギー”が新たな質量となる」という意味の、非線形的な考え方が盛り込まれた上で、アインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)の原型であるところの、式(53)ができていている。
|
『そこで一般相対性理論でも、物質のエネルギー・テンソルTσμ を考えよう。 〜。
このエネルギー・テンソル(これはポアッソン方程式のρに対応する)が重力場の方程式のなかにどんな具合に挿入されなければならないかは、(51)式が教えてくれる。すなわち、いま一つの完全な系(たとえば太陽系)を考えよう。 この物理系の全質量、したがってまたその全重力的作用は、この物理系の全エネルギー、つまり物質によるエネルギーと、重力場のエネルギーの総和に依存する。この事情は、(51)において、重力場のエネルギー成分tσμのかわりに、物質および重力場の両方のエネルギー成分の和tσμ+Tσμ を導入することによって表現される。 したがって、(51)のかわりにテンソル式
(gσβΓαβμ),α =−κ[(tσμ+Tσμ)−δσμ(t+T)/2]
|
(52)
|
| (−g)1/2=1 |
が求められる。T =Tμμである(ラウエのスカラー)。これはわれわれが求めていた一般の場合(すなわち、物質が存在するときに)における重力場の方程式の混合テンソル形式に書かれたものである。この式から逆に(47)に対応して
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
が出てくる。』
(アインシュタイン選集2(p97) 一部省略。 下線は、筆者による。)
|
「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場は、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当し、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場が、「物質があるときの重力場」に相当する。
ここで、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)と「物質があるときの重力場」は、“密度の違い”があるだけで、重力場を作る能力は、部分的には、本質的には同じと見なすことができることを思い出そう。
|
|
|
|
※一番左が、「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場、すなわち、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当していて、
右側の2つは、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場、すなわち、物質が存在するときの重力場に相当していると見なすことができる。
やはり、仮想質点と物質の“重力子の放出源として働く能力”が全く等しいので、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、3つとも全く等しくなっている。
|
|
|
「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場と、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場が、部分的に同等であると見なせるということは、何を意味するか?
それは、アインシュタイン方程式の原形(53)の左辺は、『「重力場のエネルギー成分tσμ」+「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場(時空の曲り)から、「重力場のエネルギー成分tσμ」がつくる重力場(時空の曲り)を引いたものであるということ── すなわち、アインシュタイン方程式の原形(53)の左辺は、単に、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場(時空の曲り)を表記する式に、相当することを意味するのである。
(gσβΓαβμ),α =−κ[(tσμ+Tσμ)−δσμ(t+T)/2]
|
(52)
|
| (−g)1/2=1 |
『「重力場のエネルギー成分tσμ」+「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場
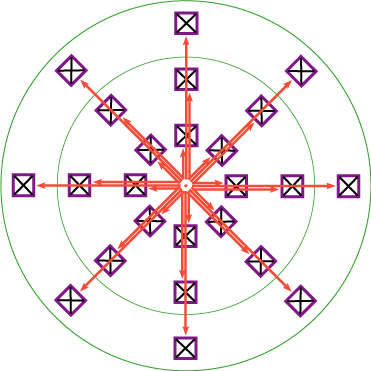 |
+ |
 |
|
− |
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
「重力場のエネルギー成分tσμ」がつくる重力場
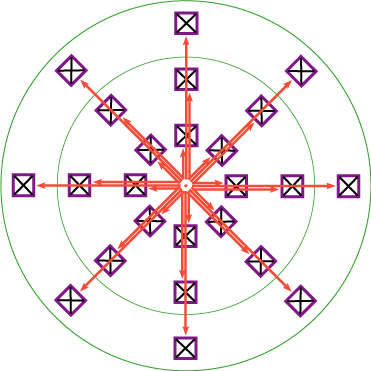
|
|
|
| = |
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場
|

|
このようにして、アインシュタイン方程式自体は、「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形的な考え方が盛り込まれた上で導出されているが、その最終的には、「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形性を持っていない式となっているのである。
すなわち、アインシュタイン方程式は、右辺が、質量エネルギー(静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))によって、生じた重力場(時空の曲り)を意味し、左辺も、質量エネルギー(静止質量エネルギー&(外部)と運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))によって生じる重力場(時空の曲り)を意味しているだけであり── 「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形性が式から消えてしまっているのである。
つまり、「重力場のエネルギーが質量となる」という自然(nature)から乖離した考えを用いて導出されたのに関わらず、アインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)自体は、結果的に自然(nature)と調和したもの(「重力場のエネルギーが質量となる」という考えが反映されていない式)となっているのである。
よって、次の結論に至ることができる。
結論1.10.1 アインシュタイン方程式が、「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形的な考え方を用いて導出されていることは、重力場が非線形であるという根拠にならない。
※整理すると、次のようになる。
物質が存在しない所での重力場の方程式
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =0
|
(47)
|
| (−g)1/2=1 |
や
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
が、意味するもの
|
物質が存在する所での重力場の方程式
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ)−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
が意味するもの
|
|
|
|
※左が、「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場、すなわち、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当し、
右は、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場、すなわち、物質が存在するときの重力場を表している。
|
|
|
この対応関係は、式(47)も式(53)も、本質的には、部分的には、同等なものであることを意味する。
どちらも、「ニュートンの引力の法則」や「水星の近日点移動」を説明できる。
(そして、さらには、重力波(重力波は“線形近似”によって導かれている)、光が曲がること、ブラックホール(シュバルツシルトの解)… も説明できるであろう。 詳細な検討は、今後の課題である。)
※例えば、太陽系を考えてみよう。 全体の重心に仮想的な質点を考え、太陽系のあらゆる重力子の放出源としての働きを、この仮想的な質点1だけが担うと仮定しよう。
すなわち、“仮想的質点M”は、太陽系に含まれる「物質のエネルギー・テンソルTσμ 」が持つ重力子の放出源としての働き続ける能力をそのままにしながら、想像上、重心点まで圧縮したものである。
すると、 「この仮想質点の、重力子の放出源として働き続ける能力」=「太陽系のすべての天体の総和の、重力子の放出源として働き続ける能力」と定義されることになる。
(ここに、(重力子の通過点である)重力場が持っているエネルギーが、「重力子の放出源として働き続ける能力」、すなわち、質量になるという考えがどこにも入り込んでいない)
このことは、仮想的質点の質量をM仮として、太陽系に存在する各天体の質量エネルギー(静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))をMc2とすると(その静止質量をM0、速度をvとすると)、
M仮c2 =ΣMc2(=ΣM0c2(1−v2/c2)−1/2)
と表記できることを意味する。
すると、太陽系のまわりの重力場は、結局、「この仮想質点のみがあるときの重力場の方程式」(=「物質が存在しないときの重力場の方程式」)の一部分(例えば、下の2重の緑で囲まれた所)で表現されることになる。
|
|
|
|
※左が、「仮想的質点と、そのまわりにつくられた重力場」であり、右は、太陽系のすべての物質を取り囲む球面と、そのまわりの重力場を表しているとする。
その、定義により、仮想的質点と太陽系の全物質の、“重力子の放出能力”が全く等しいので── 例えば、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、両方とも、全く等しくなる。
|
|
|
※だからこそ、 アインシュタイン方程式の右辺−kTμνの成分の近似値≒−(NM/π2n)×(1/r2)(≒−(NM/4πn)×(1/r2))は、この緑の部分であることを示すための項、(1/nr2)を含んでいることがわかる。
2.アインシュタイン方程式の中の曲率そのものが、計量gμνの非線形な式として表記されている。
アインシュタイン方程式の中には、リッチ曲率テンソルRμνが含まれている。
例えば、「物質が存在していない場合の重力場の方程式」は、次のようになり── この式は「リッチ曲率テンソルRμν=0」を意味している。
| Γαμν,α−Γαμα,ν+ΓαμρΓρνα−ΓαμνΓρνρ=0 |
|
| (−g)1/2≠1 |
※アインシュタイン選集2 p.98の訳者注を参考にした。
※『Γαμν,α−Γαμα,ν+ΓαμρΓρνα−ΓαμνΓρνρ』が、リッチ曲率テンソルRμν
である。
※この物質が存在していない場合の重力場の方程式は、(−g)1/2=1 という条件を付けない場合、すなわち、任意の座標系を用いたときのものである。 |
そして、この「リッチ曲率テンソルRμν=0」、すなわち、『Γαμν,α−Γαμα,ν+ΓαμρΓρνα−ΓαμνΓρνρ=0』という数式は、“計量gμνの非線形な式”に相当する。
果たして、このことは、重力場そのもそのが非線形であることの根拠になるであろうか?
そのことに関連して、やはり、次の記述が参考になる。
|
『(アシュテカは)アインシュタインの重力場の方程式を解く巧妙な方法を思いつき、方程式を書き直すことで最悪の非線形性の大半を消して、一般相対性理論をはるかに単純に見えるようにした。』
(p.268『パーフェクト・セオリー 一般相対性理論に挑む天才たちの100年』(ペドロ・G・フェレイラ 高橋則明 訳 NHK出版 下線は、筆者による)
|
|
『以上で導いた、Einstein理論に対する新たな正準理論はAshtekar 理論と呼ばれる. Ashtekar 理論はいくつかの優れた特徴を持っている. その第1は、理論に現れる諸式が基本変数の簡単な微分多項式となっていることである. 第6章で展開した計量を基礎とする正準理論(ADM理論)では拘束関数が計量の複雑な非線形式(実は分数式)となっていたことを思い起こすと,これは大幅な進歩である.』
(『岩波講座 現代の物理学6 一般相対性理論』 p.215 佐藤文隆・児玉英雄著 岩波書店 下線は、筆者による)
|
つまり、一般相対性理論(アインシュタイン方程式)の意味内容を損なわずに、数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)を消すことに、アシュテカが成功したのだ。
このことは、一般相対性理論の数式が持っている非線形性は、決して必要不可欠なものではなく、リーマン幾何学という数学上(数式上)事情を反映したものに過ぎず、物理学的な意味は、乏しいものであることを意味しているのだ。
そもそも、アインシュタインは、やむを得なく、リーマン幾何学に頼ったのだった。
“時空の曲り”や“重力場”についての具体的な幾何的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)をイメージできなかったからこそ、やむなく、抽象的で難解な(時空が連続であることを前提とする)リーマン幾何学に頼ることになったのだ。
そして、このリーマン幾何学の体系の数学事情を反映して、アインシュタイン方程式の数式が、(計量gμνに関する)非線形性を持つものになってしまったに過ぎないのだ。
その証拠に、 後に、一般相対性理論(アインシュタイン方程式)の意味内容を損なわずに、数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)を消すことに、アシュテカが成功した。
少なくともこのことから、この数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)は── 重力場そのものが非線形であることを、全く意味していないことがわかるのである。
よって、次の結論に至ることができる。
結論1.10.2 アインシュタイン方程式の中に、(計量gμνに関する)非線形性があることは、“重力場が非線形である”ということの根拠にはなりえない。
3.重力ポテンシャルエネルギーの大きさが、「線形なニュートンの重力理論において、GM/r」であるのに対し、「一般相対性理論においては、2GM/r」になる。
このことに関連して、次のような記述がある。
『簡単に言えば、重力の非線形性は、Eb(封じられた結合エネルギー)を急激に大きくする。なぜなら、重力的な力は、残りの質量があたかも最後には2という値にまで上昇する因子だけ大きいかのように作用するからである。
この非線形的な補足は、実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”と考えることができる(〜)。収縮が進むにつれて、質量は増加して行くようにみえる。そして最終的には、よく用いる方程式のなかで以前説明したおなじみのGという因子が、あたかも2Gになってしまったかのようになるのである。
このようにして質量M、半径Rの単一物体の重力的自己エネルギーあるいは結合エネルギーに対する「相対論的」な方程式は、そのもっとも簡単な形、Eb=2GM2/Rとなる。
同様にして、重力の強さが弱いところで物体を取り扱う場合には、重力ポテンシャルφに対する方程式は、Φ=GM/Rであるが、重力の強さが非常に強い場合、物体は、あたかも、Φ=2GM/Rであるかのようにふるまう。』
(p.224-226 『新しい重力理論 ニュートンから重力波まで』 アーサー・クライン著 竹内均訳 講談社ブルーバックス
下線は、筆者による)
|
この記述内容を単純に言い換えれば、「質量M[kg]の物体が、自己の重力(重力ポテンシャルエネルギー)によって、コンパクト化していく場合── ニュートン力学によれば、質量M[kg]のままなのに対し、一般相対性理論によると、質量2M[kg]であるかのように振る舞う」ということになる。
たかが2倍といっても、あなどることはできない。なぜなら、質量M[kg]が2倍になるということは、同時に、質量エネルギーMc2[J]や重力場(時空の曲り)も2倍になるということだからである。
|
ニュートン力学
|
アインシュタインの一般相対性理論
|
|
『質量M[kg]、半径R[m]の単一物体の重力的自己エネルギー
あるいは結合エネルギー』[J]
|
Eb=GM2/R[J]
|
Eb=2GM2/R[J]
|
|
重力ポテンシャルエネルギーU[J]
|
U=−GM/R[J]
|
U=−2GM/R[J]
|
|
質量M[kg]
|
M[kg]
|
2M[kg]
|
|
質量エネルギーMc2[J]
|
Mc2[J]
|
2Mc2[J]
|
|
重力場[N/kg]
|
F=GM/R2[N/kg]
|
F=2GM/R2[N/kg]
|
|
時空の曲り[1/m2]
|
−(NM/π2n)×(1/r2)[1/m2]
(≒−(NM/4πn)×(1/r2))[1/m2])
|
−(2NM/π2n)×(1/r2)[1/m2]
(≒−(2NM/4πn)×(1/r2)[1/m2])
|
| ※なお、時空の曲りが2倍になるのは、(重力ポテンシャルエネルギーに比例する時空の曲り、すなわち、自由落下で消せる方の時空の曲りが2倍になるからである。 |
これまでは、「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」ことは、一般相対性理論(重力場)が非線形であることの根拠であると見なされてきた。 すなわち、Gが2Gになることは、上記のように、『実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”』が生じること、すなわち、「重力場が、新たな質量になる」という考えによって説明されてきた。
それでは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」ということは、どのように説明されるであろうか?
それは、次のようになる。
「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」ことについて、“重力線”を含む図で示すと次のようになる。
※無限遠方に散らばった静止質量M[kg]の物体が、重力によってコンパクト化する際の様子を示している。
左側がニュートン力学によるもので、右側が一般相対性理論によるものである。
左右での違いは、次の通りである。
〈1〉右の“重力線”の密度が、左の“重力線”の密度の2倍になっている。
(図では、2次元で2倍になるように示しているが、厳密に3次元で2倍になっているという意味である)
〈2〉右が、物体の半径が、2倍になっている。 左がR[m]だとすれば、右は、2R[m]である。
〈3〉下の段にくるにつれて、物体のコンパクト化が進んでいる。
(上図では、半径Rが1/3倍になっている。この1/3倍には、深い意味はない)
この図から、次のことがわかる。
右の“重力線”は、左の“重力線”の2倍になっているので、右の質量(エネルギー)は、左の質量(エネルギー)の2倍になっている。
「物体の表面」における“重力線”の球面密度は、左右で等しい。
したがって、物体の表面における重力(重力場)は、左右で等しい。
よって、物体の表面における、「重力ポテンシャルエネルギーに比例する時空の曲り」は、左右で等しい。
したがって、物体の表面における、「重力ポテンシャルエネルギー」は、左右で等しい。
|
なぜ、このようなことが起きるのか?
それは、一般相対性理論によると、物体が半径Rまで、コンパクト化するまでに獲得する(外部)運動エネルギーが新たな質量エネルギーとしてカウントされるからである。
その新たに獲得される質量エネルギー((外部)運動エネルギーK[J])は、ぴったりそこまで利用された重力ポテンシャルエネルギーの大きさGM/R[J]に等しい。
そして、物体表面での重力場は2倍なので、この新たに獲得される質量エネルギー((外部)運動エネルギーK[J])が、そのまま重力ポテンシャルエネルギーに寄与することになる。
※例えば、重心からR[m]、2R[m]の場所で、一般相対性理論にもとづく重力ポテンシャルエネルギーは、2倍になっていることが図示されている。
一般相対性理論にもとづく、重力ポテンシャルエネルギーのカーブは、各点で、ニュートン力学にもとづく場合の2倍となるのは、新たに獲得される運動エネルギーK=GM/R[J]が、そのまま重力ポテンシャルエネルギーに寄与する結果であると考えられる。 なぜなら、この関係があるおかげで、各点での重力(重力場)も2倍になるからである。
※物体の表面が、−GM/R[J]の重力ポテンシャルエネルギー(あるいは、GM/R2[N/kg]の重力(重力場))を持つために、ニュートン力学では、半径R[m]まで物体がコンパクト化する必要がある一方、一般相対性理論に理論では、半径2R[m]まで物体がコンパクト化すれば済むことも、この図から読み取れる。
※Gが2Gになるということは、この図のような関係があることを意味していることになる。
|
つまり、物体が獲得する運動エネルギーをカウントする結果、ニュートン力学で考えた時に物体の表面における重力ポテンシャルエネルギーU=−GM/R[J]は、一般相対性理論では、2倍の−2GM/R[J]となるのである。
そして、だからこそ、物体の表面における、「重力ポテンシャルエネルギー」や「重力(重力場)」、「自由落下で消せる時空の曲り」は、下図の左右で、等しくなるのである。
なお、『質量M[m]、半径R[m]の単一物体の重力的自己エネルギーあるいは結合エネルギー』[J]が、2倍になるのは、
「静止質量エネルギーによって生じる結合エネルギー」Eb=GM2/R[J]に、「物体が獲得する(外部)運動エネルギーによって生じる結合エネルギー」Eb=GM2/R[J]の分が、単純に加わる結果であると考えられる。
以上より、下表のすべてを説明できたことになる。
|
ニュートン力学
|
アインシュタインの一般相対性理論
|
|
『質量M[kg]、半径R[m]の単一物体の重力的自己エネルギー
あるいは結合エネルギー』[J]
|
Eb=GM2/R[J]
|
Eb=2GM2/R[J]
|
|
重力ポテンシャルエネルギーU[J]
|
U=−GM/R[J]
|
U=−2GM/R[J]
|
|
質量M[kg]
|
M[kg]
|
2M[kg]
|
|
質量エネルギーMc2[J]
|
Mc2[J]
|
2Mc2[J]
|
|
重力場[N/kg]
|
F=GM/R2[N/kg]
|
F=2GM/R2[N/kg]
|
|
時空の曲り[1/m2]
|
−(NM/π2n)×(1/r2)[1/m2]
(≒−(NM/4πn)×(1/r2))[1/m2])
|
−(2NM/π2n)×(1/r2)[1/m2]
(≒−(2NM/4πn)×(1/r2)[1/m2])
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、新たな質量になりうるのは、重力場のエネルギーではなく、運動エネルギー(内部&外部)であることを示している。
すなわち、『実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”』と考えられていたものは、「重力場のエネルギー」ではなく、実際は、『重力ポテンシャルエネルギーを利用して増加した(外部)運動エネルギーに相当する質量』であることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、はっきり示しているのである。
すなわち、Gという値が2倍になるのは、「物体が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した(外部)運動エネルギー」を、新たな質量としてカウントするからに他ならない。
このことは、ある天体が自身の重力によってコンパクト化すると、(線形な)ニュートンの重力理論での、Gという値が、2倍になる(2Gになる)のは── 重力場が非線形であるからではないことを意味している。
つまりは、「質量の大きさ(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力)に比例した大きさの重力場が創発する」ことは変わりがないので、重力場そのものは、線形であるという説明は、ゆるがないことになるのである。
(すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が重力場に相当し続けるので線形であると言えるのである。
もし、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和以上が、重力場となるならば、非線形と言えるが、実際はそうではない)
(線形な)ニュートンの重力理論での、Gという値が、2倍になる(2Gになる)ことは、重力場が非線形であるという誤解を生む、原因の1つとなってきた。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の結論に至る。
結論1.10.3 (線形な)ニュートンの重力理論での、Gという値が、2倍の2Gになることは、“重力場が非線形である”ということの根拠にはなりえない。
※「重力場のエネルギーそのものが質量にならない」ということは、当然、「重力場のエネルギーが質量になり、その質量がさらに新たな重力場を生み、またその新たな重力場のエネルギーそのものが、新たな質量になり… と限りなく繰り返すよう非線形性」もないということである。
※Gという値が2Gになるという関係が成立するのは、物体がシュバルツシルト半径までコンパクト化するまでの間だけである。
このことは、シュバルツシルト半径に至るまでは、(Gという値が2Gになるという関係が成立するので)「重力場が(外部)運動エネルギーという質量を生み、その(外部)運動エネルギーという質量がさらに新たな重力場を生み、またその新たな重力場が、新たな(外部)運動エネルギーという質量になり… と限りなく繰り返すような非線形性」が存在しないことを意味している。
仮に別の条件で、このような非線形性が存在していたとしても、「重力場そのものは非線形ではない」という結論はゆらがないと考えられる。
なぜなら、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が調和振動子であり、それらの総和として重力場が創発していることは変わらないと考えられるからである。
なお、「重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した(外部)運動エネルギーのみが新たな質量になる」という説明は、アインシュタインの右辺が、質量エネルギー(「静止質量エネルキー&き運動エネルギー」=運動エネルギー(内部&外部))であるという説明とも調和している。
(このことは、この「アインシュタインの右辺が、質量エネルギー(「静止質量エネルキー&(外部)運動エネルギー」=運動エネルギー(内部&外部))であるという説明」が、アインシュタイン方程式の右辺を「粗悪な材木」から、強固な「高級大理石」に、アップグレードしうるという考えを支持するものである)
※以上の説明のような、「物質が重力によって収縮する(コンパクト化する)際に、物体(質量)が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して、運動エネルギーを獲得し、それが新たな重力子の放出源になること」を考慮すると、下図の説明について補足する必要が生まれることがわかる。
すなわち、下図は、やはり、あくまで「物体の静止質量エネルギー&運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件のもとで、その中心(重心)に向けて、その全体積 Vだけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを説明しているものに過ぎない。 その全体積 V[m3]だけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを説明しているものに過ぎない。 この場合は、全体積V[m3]が小さくなると、それに反比例して、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)の密度」が大きくなっているだけである。
|
|
|
|
※この図は、「物体の質量エネルギー&運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件つきの図である。
この条件がついてはじめて、グリーンの部分の時空がすべて、同じになることができるのである。
※結果的に、質量のみを考えているところの“ニュートンの重力理論”に相当するものになっている。
|
|
|
しかし、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件は、実は、現実的な条件ではなかったことになる。
すなわち、ふつう、物質は、それ自身の質量が生じる重力によって収縮する(コンパクト化する)ので、その際に「物質が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して、運動エネルギーを獲得し、それが新たな重力子の放出源になること」を考慮する方が現実的である。 それを考慮して図示すると、次のようになる。
|
物体が、(物質自身が持つ)重力によって収縮する(コンパクト化する)場合──
|
|
|
→
|
|
|
|
|
|
|
|
※「物体が重力によって収縮する(コンパクト化する)際に、物質が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した運動エネルギーが
新たな重力子の放出源になること」を考慮した図である。
※なお、2倍になるのは、無限遠方からコンパクト化させた場合である。この場合、一般相対性理論ではニュートン力学にもとづく値の2倍
になる。
しがって、上部のように、「途中から」コンパクトしただけでは、2倍には至らない。
※もし「無限遠方から」を考えた場合、下図のように、ニュートン力学の場合(上段)に比べて一般相対性理論の場合(下段)は、
シュバルツシルト半径に至るまでは常に2倍となっているはずである。
|
|
|
|
|
|
|
|
↓2倍
|
↓2倍
|
↓2倍
|
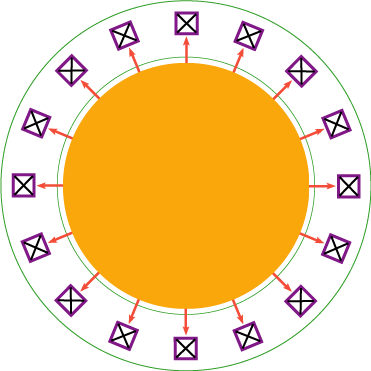 |
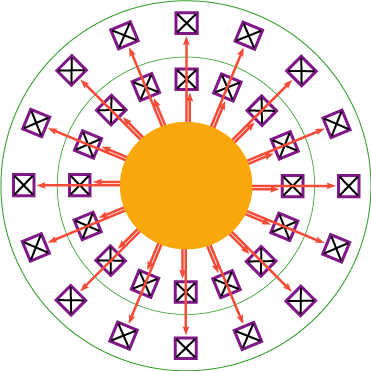 |
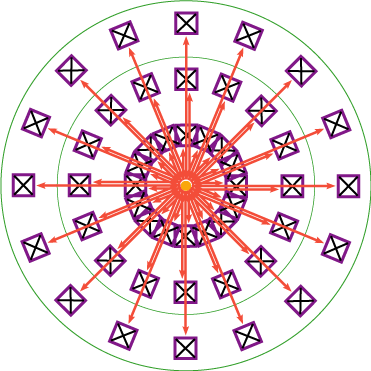 |
以上の3つの結果、すなわち、
結論1.10.1 アインシュタイン方程式が、「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形的な考え方を用いて導出されていることは、重力場が非線形であるという根拠にならない。
結論1.10.2 リッチテンソルの数式が非線形性を持つことは、“重力場が非線形である”ということの根拠にはなりえない。
結論1.10.3 (線形な)ニュートンの重力理論での、Gという値が、2倍の2Gになることは、“重力場が非線形である”ということの根拠にはなりえない。
は、いずれも、少なくとも、物体のコンパクト化が、シュバルツシルト半径に至るまでは、「仮説1.11 重力場そのものは、線形である」が成立することを支持するものである。
なお、シュバルツシルト半径(ブラックホール)に至ってから以降については、新たな説明が必要である。 なぜなら、「(線形な)ニュートン力学でのGという値が、一般相対性理論によると、2倍になる(2Gになる)」という関係が、もはや成立しないからである。
このことについて、下のテーブル内で説明する。
シュバルツシルト半径Rsに対応する事象の地平面の面積Sは、S=4πRs2[m2]である。
一方、シュバルツシルト半径Rs=2GM/c2=M×(4πcLP2/h)=M×(4π2cLP/h)×LP/π=(M/MG)×(LP/π)である。
(重力定数「G=2πc3LP2/h」、重力子質量「MG=h/(2π)2cLP[kg]」を使った)
よって、S=4πRs2=(M/MG)2×(4LP2/π)[m2] となる。
つまり、(ニュートン重力理論やアインシュタイン重力理論の一部を説明できた)『(M/MG)×4LP2』だけでは、事象の地平面のすべてを“4角形”(縮みきったバネ)にするためには、とても足りないのである。 (そして、その2倍でも足りない)
すなわち、『(M/MG)×4LP2』がカバーできる範囲は、せいぜい、半径Rsの幅2LP[m]の円周分だけにすぎない。 なぜなら、シュバルツシルト半径Rs=M/MG×LP/πから導かれる、『2πRs=M/MG×2LP』という式が『シュバルツシルト半径Rsの円周の長さ「2πRs」が、ちょうど、原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ“2LP[m]”をM/M G[個]、円上に並べた長さ「M/M G×2LP」に等しい』と解釈できるからである。
※“4角形”(縮みきったバネ)が、規則正しく、交互に90度向きを変えているように図示しているが、実際は、様々な角度にランダムに向きを変えていると考えられる。
『(M/MG)×4LP2』とは、(ニュートンの重力理論やアインシュタイン重力理論の一部を説明できた)厚さ2LP[m]の球殻において、質量M[kg]が生じる“4角形”(縮みきったバネ)が占める面積であった。
一方、質量M[kg]の物体がブラックホールになると、事象の地平面において、すべての原始ヒッグス場ユニット(PHU)が“4角形”(縮みきったバネ)になると考えられる(そのことにより、光子がブラックホールの内部から外部へ進めなくなると考えられる)。 したがって、物体がブラックホールになる場合、その事象の地平面において“4角形”(縮みきったバネ)が占める面積は、『(M/MG)2×(4LP2/π)』となるはずである。
つまり、厚さ2LP[m]の球殻において『NM=(M/MG)』個の原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形していた、質量M[kg]が、ブラックホールになることによって、『NM2×(1/π)=(M/MG)2×(1/π)』個の原始ヒッグス場ユニット(PHU)を“4角形”(縮みきったバネ)に変形できるようになるはずであることがわかる。
このことは、ある質量M[kg]は、ブラックホールになることによって、その質量が、『NM×(1/π)』倍に増加すると解釈できることを意味する。 (これは、“2倍”になるどころの話ではない)
|
なぜだろうか?
やはり、“重力は、非線形だ”ということなのだろうか?
それとも、その「重力子の放出源として働き続ける能力の増加」が『NM×(1/π)』倍になるように何かの運動エネルギーが増加するしくみが存在するに過ぎず── “重力場の線形性は保たれている”と見なせるのだろうか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、後者、すなわち、たとえブラックホールに至ってからも 仮説1.11 重力場そのものは、線形である。
が成立することを支持しているようである。
なぜなら、重力場は、結局、「(“デュアルLP光子”からなる)重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として創発しているからである。
すなわち、それは、重力場は、結局、“個々の原始ヒッグス場ユニットの単振動(調和振動子)の総和”に過ぎないのだから、“当然といえば当然のことだ”ということになる。
(また、このことから、ここにあるのは、「重力場のエネルギーが新たな質量になる」という意味の非線形性ではないことも確かである)
したがって、ブラックホールに至ることによって、さらなる「運動エネルギーが増加するしくみ」があると考えられる。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ニュートン重力理論が(M/MG)×4LP2で説明できる一方、 ブラックホールが、(M/MG)×2×4LP2によっては説明できず、(M/MG)2×4LP2/πで、はじめて説明できることは、この根底に、何か重要なしくみ(からくり)が存在していることを示唆しているのである。
そのしくみ(からくり)とは、次のようなものだと考えれる。
物体は、初めてシュバルツシルト半径までコンパクト化されるまでに、全質量は、2倍に至る。(G→2Gの変化に相当)
したがって、この効果によって生み出される(仮の)「事象の地平面の面積」は、『(M/MG)×2×4LP2』[m2]となる。
(そして、2倍となるのは、獲得する運動エネルギーを新たな質量として、カウントするからである。
その後、物体が、よりコンパクト化が進むと、もはやクォークやレプトンが維持されず、プレオン∴に分解される
(→EMOES宇宙論1)。
さらには、そのプレオン∴1つ1つは、重力子エネルギーEG(=MGc2[J])に相当する運動エネルギーK[J]を獲得できるポテンシャルを持つ。 しかし、1つ1つのプレオン∴は、ブラックホールの中心に至るまでに、必ず重力子エネルギーEG(=MGc2[J])を獲得するというものではなくて、やはり、(ブラックホールの中心に至るまでに放出される)「重力ポテンシャルエネルギー[J]」に比例した運動エネルギーK[J]を獲得するだけである。
ブラックホールの中心までコンパクト化が進むまでに、ある1つプレオン∴に運動エネルギーK〕を与えるところの「重力ポテンシャルエネルギーE[J]」は、どうなるであろうか?
(それは、元の全質量(M[kg])に比例しているはずであるという説明だけでは足りない。 なぜなら、それは、初めてシュバルツシルト半径までコンパクト化されるのと同様に、結局、全質量が単に2倍になるのに過ぎないからである。 単に、E=−GM/R[J]の式だけに基づいて、「トータルの質量が10倍になれば獲得する運度エネルギーは10倍、トータルの質量が100倍になれば獲得する運動エネルギーは100倍になる」という効果だけでは足りないのである。 したがって、もっと深いしくみがあるはずである)
質量m[kg]を持つ2つのプレオン∴が、それぞれブラックホールの中心へ落ちる場合を考えてみよう。この場合、「質量m[kg]を持つ2つのプレオン∴」が、さらに獲得する運動エネルギーK[J]は、(シュバルツシルト半径以降の)重力ポテンシャルエネルギーエネルギーに等しい結果(K=Gm/R[J])、この運動エネルギーK[J]は、m[kg]の質量の増加に相当することになるので、最終的に、質量はトータルで、m[kg]+m[kg]+m[kg](K[J]由来)+m[kg](K[J]由来)=4m[kg]となる。 つまり、この場合、2つのプレオン∴は、もともと2m[kg]の質量を持っていたが、ブラックホールの中心へ落下することによって、トータルで、2倍の4m[kg]の質量を持つに至ることになる。
さて、この系が2つ集合するとどうなるか?
別々であったなら、それぞれ、単に4m[kg]になるところが、「2つ合わさることによって、さらに獲得する運動エネルギー」は、それぞれ4K[J]になるはずである。4K[J]の運動エネルギーの増加は、4m[kg]の質量の増加に相当するので、合計で、4m[kg]+4m[kg]+4m[kg](4K[J]由来)+4m[kg](4K[J]由来)=16m[kg]の質量に至る。
つまり、4つのプレオン∴は、もともと4m[kg]の質量を持っていたが、ブラックホールの中心へ落下することによって、トータルで、4倍の16m[kg]の質量を持つに至ることになる。
さらに、この系が2つ集合するとどうなるか?
別々であったなら、それぞれ、16m[kg]になるところが、「2つ合わさることによって、さらに獲得する運動エネルギー」は、それぞれ16K[J]になるはずである。16K[J]の運動エネルギーの増加は、16m[kg]の質量の増加に相当するので、合計で、16m[kg]+16m[kg]+16m[kg](16K[J]由来)+16m[kg](16K[J]由来)=64m[kg]の質量に至る。
つまり、8つのプレオン∴は、もともと8m[kg]の質量を持っていたが、ブラックホールの中心へ落下することによって、トータールで、8倍の64m[kg]の質量を持つに至ることになる。
さらに、この系が2つ集合するとどうなるか?
別々であったなら、それぞれ、64m[kg]になるところが、「2つ合わさることによって、さらに獲得する運動エネルギー」は、それぞれ64K[J]になるはずである。64K[J]の運動エネルギーの増加は、64m[kg]の質量の増加に相当するので、合計で、64m[kg]+64m[kg]+64m[kg](64K[J]由来)+64m[kg](64K[J]由来)=256m[kg]の質量に至る。
つまり、16個のプレオン∴は、もともと16m[kg]の質量を持っていたが、ブラックホールの中心へ落下することによって、トータルで、16倍の256m[kg]の質量を持つに至ることになる。
…
以下同様である。
より一般的に書くと、『質量m[kg]を持つプレオン∴2n[個]からなる質量2nm[kg]が、 ブラックホールに落ちると、22nm[kg]になる』ということになる。
数学的帰納法による証明は次のようになる。
命題『質量m[kg]を持つプレオン∴2n[個]からなる質量2nm[kg]が、 ブラックホールに落ちると、22nm[kg]になる』について──
n=1ときは、プレオン∴2個からなる2m[kg]は、ブラックホールに落ちると、4m[kg]となるので、成立する。
n=kのときに成立すると仮定すると、プレオン∴k個からなる2km[kg]が、ブラックホールに落ちると、22km[kg]になるはずである。
その仮定の上で、n=k+1のときを考えてみよう。
プレオン∴k+1個からなる 2k+1m[kg]は、ブラックホールに落ちると、n=kのときの質量、22km[kg]の4倍になるはずである。
なぜなら、質量の合計は、22km[kg]+22km[kg]+22km[kg](22kK[J]由来)+22km[kg](22kK[J]由来)となるからである。
つまり、プレオン∴k+1個からなる 2k+1m[kg]は、ブラックホールに落ちると、4×22km=22(k+1)m[kg]となるのである。
したがって、n=kのときに成立すると仮定するなら、n=k+1のときにも成立することが証明された。
以上の数学的帰納法により、任意の自然数nについて、命題『質量m[kg]を持つプレオン∴2n[個]からなる質量2nm[kg]が、 ブラックホールに落ちると、22nm[kg]になる』が成り立つという結論に至る。 |
|
プレオン∴の個数Nは、確かに、ぴったり「2n[個]」という形の数字だとは、限らないだろう。
しかし、大きなNについて、より一般化した、次のような結論を導くことは無理がないと思われる。
結論1.10.4 Nが大きい数の場合、一般に、質量m[kg]を持つプレオン∴N個(トータルの質量は、Nm[kg])は、ブラックホールの中心に落下することによって、トータルで、およそN倍の質量、すなわち、およそN2m[kg]の質量を持つに至る。
したがって、(真の)「事象の地平面の面積S[m2]」は、少なくとも、この効果の分を乗じたものに相当しなければならない。
そして、この効果の分を乗じた(真の)「事象の地平面の面積S[m2]」に近いものとは、まさに、『(M/MG)×2×(M/MG)×4LP2〔m2〕=(M/MG)2×2×4LP2 [m2]』(=NM2×2×4LP2 [m2])に他ならない。
※4LP2 〔m2〕が乗じてある(真の)「事象の地平面の面積S」に対応するためには、単にM[kg]を乗じるのではなく、M[kg]を重力子質量MG[kg]あたりの個数に変換する必要がある。 なぜなら、プレオン∴の個数と、重力子質量の個数(M/MG)(=NM)は、単純に比例すると考えられるからである。 詳細な個数については、今後の課題である。
そして、この『(M/MG)2×2×4LP2[m2]』の値が「1/2π倍」になりさえすれば、ブラックホールの(真の)「事象の地平面の面積S」=『(M/MG)2×4LP2/π[m2]』にぴったり一致する。
※「1/2π倍」は、おそらく、「回転」、あるいは、「結合エネルギー」を意味していると思われる。
プレオン∴は、回転運動(例えば、ペアを作った連星のような運動)をしながら(外部)運動エネルギーを獲得していると考えられるからである(→EMOES宇宙論1)。 詳細な検討は、今後の課題である。
そして、「1/2π倍」の正体が何であっても、重力場は、結局、獲得する運動エネルギーに比例して創発していることは変わらないので、「重力場は線形である」という説明は、ゆらがないのである。
|
このように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、たとえブラックホールに至ってからも『仮説1.11 重力場そのものは、線形である』が正しいことを示している。
このことは、つまり、「重力場も 電磁場も、ともに線形である」ということである。
このように電磁場の世界も、重力場の世界も、ともに線形であるということは、電場や磁場の大きさ、重力場の大きさは、ともに単純な足し算&引き算で求められることを意味する。
そして、そのことは、素スピノールの転回にともなう原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形が単振動であること、すなわち、「仮想光子&変形している“4面体”」も「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」も“調和振動子”であることを考えれば、やはり当然のことである。
(すなわち、仮想光子や重力子が変形させている原始ヒッグス場ユニットの“4面体”が調和振動子であるからこそ、その総和である電子場も重力場も、ともに線形なのである)
その一方で、(重力子の通過点である)重力場そのものから、いきなり、新たな重力子を生じるようなことは起こりえないので、少なくとも、“重力場が質量になる”というような非線形性が決して生じえないのは確かであろう。
だからこそ、静止質量の大きさに比例して、重力が増加するというニュートンの万有引力の数式も成り立つのだ。
そして、だからこそ、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギー」の総和(=運動エネルギー(内部&外部)の総和)、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”に比例して、Gが2Gになる程度に、重力が増加するというアインシュタインの重力理論も成り立つのだ。
これらは、「(重力子のエネルギーの通過点に過ぎない)重力場そのものが、いきなり、“新たな重力子の放出源として働く能力”、すなわち、新たな質量を獲得することがありえない」おかげでもあるのだ。
《連星系パルサーと重力波について》
連星パルサーの研究成果に関連して、次のような記述がある。
|
『伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいることが発見され、この重力波の存在が間接的に示された』
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』 J.M.ワイズバーグ、J.H.テイラー、L.A.ファウラー)
|
『アインシュタインは、1915年に発表した一般対性理論の中で加速運動している物体は、重力波の形でエネルギーを放出すると予言した』
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』) |
これらの「間接的な重力波の観測」も「アインシュタインの予言」も── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明、すなわち、『(重力波は「放出される重力子数の変化」として創発する(→下記説明))』という説明や『質量を持つ物体が加速運動する(=物質の運動エネルギーが増す)ことによって、重力子の放出源として働き続ける能力が増す(→上記説明)』という説明と、おおよそ調和している。
しかし、次の記述は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の説明とは、180度逆である。
『連星系パルサーからの重力放射に必要なエネルギーの源は、軌道運動エネルギーである。だから、重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら、軌道エネルギーはしだいに減少し、このために、パルサーとその伴星が渦巻き状に互いに近づきあい、軌道周期も減少するはずである』
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』 下線は、筆者による) |
すなわち、この従来の物理学における“重力波がエネルギーを持ち去る”という説明は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の説明とは、180度逆である。
なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、「重力波は、“放出される重力子数の変化”であり、重力子は、エネルギー非保存の所産である」ので、“重力波(=「放出される重力子数の変化」)がエネルギーを持ち去らない”のは明白だからである。
両者を比較すると次のようになる。
|
従来の物理学
(『連星系パルサーからの重力波
サイエンス1981年12月号』…)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
連星系パルサーから放出する
重力波(重力子の総和)による
“エネルギーの持ち去り”
|
ある
|
ない
|
|
重力波
(重力子の総和)
|
エネルギー保存則の所産
|
エネルギー非保存の所産
|
|
重力波のエネルギーを含めたエネルギー保存則
|
成り立つ
|
成り立たない
|
|
力学的エネルギーの保存
(運動エネルギーK[J]
+重力ポテンシャルエネルギーU[J]が一定)
|
成り立たない
|
成り立つ
(ゆえに、ΔK=−ΔU)
|
|
重力波の解釈
|
『この重力波は、“エネルギーの持ち去り”分に相当する』
|
『この重力波は、“重力子の放出源として働き続ける能力”アップ分に相当する』
|
|
重力と遠心力の関係
|
重力=遠心力
(ゆえに、GMm/r2=mv2/r より、−U/2=K)
|
重力>遠心力
|
|
『P =(32GΩ6/5c5)×ε2I 2
回転している質量分布からの放射パワー』の解釈
|
重力波によってよって持ち去られる
エネルギー
|
「加速運動にともなって“重力子の放出源として働き続ける能力がアップしている部分”」 |
|
根拠となる数式
|
−dE/dt=dK/dt=−1/2dU/dt=P
(軌道半径は、r[m])
|
dK/dt=−dU/dt= P
(軌道半径は、2r[m])
|
※参考 『一般相対性理論』 Torsten Flieβbach著 共立出版
※なお、次の記述からも、アインシュタイン自身も、“重力波のエネルギーを含めたエネルギー保存則が成り立つこと”を前提として、重力波が“エネルギーの持ち去る”と考えていたことがわかる。
『重力波を放出している物質系は、エネルギーを外に向かって放出するはずである。したがってエネルギー保存則を考えると、この反作用として物質系の運動は減衰することとなる』
(『アインシュタイン選集2』(p.180) 下線は、筆者による) |
アインシュタインは、一般相対性理論を、エネルギー保存則(by連続な時空)を前提にして作り上げたので、当然と言えば、当然のことである。
そもそも、連星系において、重力波によってエネルギーが持ち去られると考えられた理由は何だったのだろうか?
その理由の1つは、「重力=遠心力」を保ちながら(楕円軌道とならずに)『渦巻き状に互いに近づき』合うためには、重力ポテンシャルエネルギーU[J]を消費することによって獲得される(外部)運動エネルギーK[J]が、本来の値(力学的エネルギーが保存する場合の値)の1/2にならなければならないと考えられたからであると思われる。
|
系の全エネルギーをE[J]とする。
重力波による持ち去りがなければ、系の全エネルギーE[J]は、全力学的エネルギーにほかならず、E=K+U[J]という式が成り立つ。
(K[J] : 系の全運動エネルギー U[J] : 系の全ポテンシャルエネルギー)
もし重力波による持ち去りがなければ、少しでも「重力>遠心力」となれば、自由落下運動も始まるので、重力ポテンシャルエネルギーU[J]が消費されて、運動エネルギーK[J]が増加する。
すなわち、力学的エネルギー保存則により、E=U+Kが、一定なので、 −ΔU=ΔKとなる。
そして、この大きな運動エネルギーによって、「楕円軌道となって飛び去ってしまうだろう」と考えられた。
そして、「楕円軌道となって飛び去らない」ためには、「重力=遠心力」を保ちながら、少しずつ『渦巻き状に互いに近づき』合わなければならないと考えた。
「重力=遠心力」を保つということは、GMm/r2=mv2/r より、GMm/2r=mv2/2、つまりは、−U/2=K すなわち、−ΔK=ΔU/2の関係を保つということに他ならない。
(K[J] : 系の全運動エネルギー U[J] : 系の全ポテンシャルエネルギー)
つまり、先ほどの自由落下ときに獲得した運動エネルギーΔK(=−ΔU)の1/2にならなければ、「重力=遠心力」を保つことができないということである。
その結果、この余分な運動エネルギーを重力波が持ち去っていると考えれば、つじつまが合う── と考えられたのだと思われる。
|
しかし、「獲得された新たな運動エネルギーが新たな質量になること」を思い出すならば、必ずしも、1/2になる必要がないことがわかる。
なぜなら、下図からわかるように、(重力ポテンシャルエネルギーを利用して)獲得された新たな運動エネルギーが新たな質量になる効果によって、重力場も(およそ)2倍になるはずだからである。
※この図では、半径R[m]の地点で、ニュートン力学にもとづけば、重力ポテンシャルエネルギーが−GM/R[J]となるところが、一般相対性理論にもとづけば、重力ポテンシャルエネルギーが、(およそ)2倍の−2GM/R[J]となることが読み取れる。
※なお、この図は、ある等しい重力ポテンシャルエネルギー−GM/R[J]を得るためには、ニュートン力学にもとづく軌道半径R[m]が、一般相対性理論にもとづけば、2倍の2R[m]で済むと解釈もできる。
|
つまり、「楕円軌道となって飛び去らない」ためにと考えられた条件であるΔK/2の2倍、ΔKの運動エネルギーを獲得したとしても、重力場がおよそ2倍になる結果、楕円軌道となって飛び去らないと考えられるのである。
※「およそ2倍」というのは、重力場(or軌道半径)が完全な2倍になるためには、厳密には無限遠方から近づく必要があるからである。
なお、無限遠方から物体同士が近づかなくとも、重力場が強くなればなるほど(軌道半径が小さくなればなるほど)、誤差の比率が小さくなり、より(正確な)「2倍」に近づいていくと考えられる。
※無限遠方からの自由落下ではなく、「途中から」自由落下している場合の図である。
オレンジ色の2本線の幅、ブルーの2本線の幅が、「無限遠方から」との誤差に相当する。 コンパクト化が進めば進むほど、これら誤差の比率が低下すると考えられる。
|
これまでは、連星パルサーにせよ、2つのブラックホールにせよ、楕円軌道とはならずに互いに渦巻きを描いて近づいていくことが観測されてきていることについて、これまでは、まさに“重力波によるエネルギーの持ち去り”を用いて、次のように説明されてきた。
|
『もし重力波によるエネルギーの持ち去りがなければ楕円軌道になるはずである。 しかし、実際、楕円軌道にならずに渦巻きを描いて互いに近づいてくるのは重力波がエネルギーを持ち去ってくれるおかげである。』
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると次のように説明できることになる。
|
『「獲得された新たな運動エネルギーが新たな質量になる」がなければ、楕円軌道になるはずである。 しかし、実際、楕円軌道にならずに渦巻きを描いて互いに近づいてくるのは「獲得された新たな運動エネルギーが新たな質量になる」効果(「運動エネルギーの増加(=質量の増加)に伴う重力場の増加」の効果)があるおかげである。』
|
つまり、重力波によるエネルギーの持ち去りを考えなくとも、(楕円軌道とならずに)『渦巻き状に互いに近づき』合うことを説明できるのである。
しかも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の場合、「重力>遠心力」を前提にしているので、『渦巻き状に互いに近づき』合うことを、より自然に説明できる。
※一方、重力波によるエネルギーの持ち去りを考える場合、(連星系パルサーにおいて)そもそも「重力=遠心力」が成立していることが不思議なことであることが次の記述からわかる。
|
『連星中性子星が形成されるためには、2度の超新星爆発を経る必要がある. 超新星爆発では、爆発で放出され質量が大幅に減る。これが連星で起きると、連星が解体する可能性がある.〜. 2つの星が、別々の方向に飛んでいってしまうのである. 〜 爆発が非対称的に起こって、軌道運動とはまったく関係のない方向に新たに誕生した中性子星が飛び出し、運良くもう一方の中性子星の飛んでいった方向に向かえば、連星のまま保たれることもあり得るが、確率は低い. だから、連星中性子性は大変珍しい天体なのである.』
(『一般相対論の世界を探る 重力波と数値相対論』 柴田大 著 東京大学出版会 p21-23より一部抜粋 下線は、筆者による)
|
“連星系パルサーの形成はまれなことであり、超新星系爆発の直後の運動の方向が、たまたま連星系パルサーの形成のためにふさわしい方向のときに限って、形成されるものである”ことが読み取れる。(なお、『超新星爆発後に残った中性子星がパルサーの正体である』と考えられている。(参考 Wikipedia『パルサー』)) したがって、はじめから、ぴったり遠心力=重力となっている可能性が限りなく低いことがわかる。(すなわち、はじめから「重力>遠心力」である可能性が高いことがわかる)
『そもそも「重力=遠心力」が成立しているのはなぜか?』が説明しにくい理由は、他にもある。それは、厳密には100%完全な真空が存在しないことである。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wikipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
「不完全な真空内に存在する分子との衝突、すなわち、“うすい空気”の摩擦抵抗」が存在すれば、それによって、エネルギーが失われることになるので、すみやかに、(重力波以前に)「重力>遠心力」となるはずであり、「重力=遠心力」を保ち続けることは、本来、不可能なことなのだと思われる。 したがって、(連星系パルサーにおいて)そもそも「重力=遠心力」という前提は、自然(nature)から乖離していると考えられるのである。 詳細な検討は、今後の課題である。
そもそも、観測されているものは、あくまで、「公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいること」だけであった。
(“連星系パルサーの軌道運動エネルギーの減少”は、解釈にすぎず、決して実際に観測されされたものではない。 現に、この記事にも『重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら』と書かれてある。)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のパラダイムでは、“連星系パルサーの軌道周期の減少”と重力波の関係を、次のように説明する。
連星パルサーは、互いの重力によって、系の重心に向かってらせんを描きながら、自由落下しているだけである。
特定の観測点での、重力子の放出数[個/s]の変化の振幅は、下図のように増加するであろう。
実際は、重力ポテンシャルエネルギーを利用して加速する連星は、(軌道)運動エネルギーが増加し続ける。
もし、“らせん軌道をとりながらの自由落下”をする物質の「運動エネルギーの増加に相当する“放出される重力子の変動”」を考えるならば、その変化は、次のようになるであろう。
重力ポテンシャルエネルギーを利用した自由落下&加速によって生じた「(外部)運動エネルギーの増加」(すなわち、速度の増加)および、軌道そのものの減少(コンパクト化)にともなって、“連星系パルサーの軌道周期の減少”も生じる。
そして、その“連星系パルサーの軌道周期の減少”は、「エネルギーが保存し重力波がエネルギーを持ち去る」と前提にしたものとぴったり一致することになる。
なぜなら、『巻き込み時間』および“連星系パルサーの軌道周期の減少”は、同等と言える「−1/2dU/dt=P(軌道半径r[m])」と「−dU/dt=P(軌道半径2r[m])」の式やケプラー則の式(『T 2∝r 3』)を利用して計算されるものだからである。
(参考 『一般相対性理論』 p242〜244 Torsten Flieβbach著 共立出版)
|
従来の物理学
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』…)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
根拠となる数式
|
−dE/dt=dK/dt=−1/2dU/dt=P
(軌道半径は、r[m])
|
dK/dt=−dU/dt= P
(軌道半径は、2r[m])
|
※ 『 P =(32G Ω6/5c 5)×ε 2I 2 回転している質量分布からの放射パワー』
(『一般相対性理論』 p241 Torsten Flieβbach著 共立出版)
従来の物理学では、重力波がエネルギーを持ち去る結果、軌道収縮ともなって獲得される運動エネルギーは、(重力ポテンシャルエネルギー−ΔU[J]を利用した)本来の運動エネルギーの増加ΔK[J]の、1/2になるのであった。
従来の物理学では、重力=遠心力の前提により、−U/2=Kの関係がある。また、これにより、全力学的エネルギーE[J]について、E=U+K=−K=U/2[J]の関係が導かれる。
そして、P=−dE/dt(=dK/dt=−1/2dU/dt)の式を用いて、重力波によるエネルギーの持ち去りを説明し、『巻き込み時間』および“連星系パルサーの軌道周期の減少”を導いたのだった。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、(重力ポテンシャルエネルギー−ΔUを利用した)本来の運動エネルギーの増加ΔKに伴う「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出数の増加が、重力波に相当すると説明する。
このΔK=−ΔUの単位時間あたりの変化、dK/dt=−dU/dt が、放射パワーP をに等しいということは、軌道半径が、持ち去りを前提にした場合のr[m]の2倍、2r[m]になっていればよいことを意味する。 なぜなら、重力ポテンシャルエネルギーの式「U=−GM/r」より、軌道半径rが2倍になれば、重力ポテンシャルエネルギーUが、1/2になるからである。
すなわち、軌道半径が2倍になる(2r[m]になる)という前提(仮定)のもとに、次の関係を導くことができるのである。
dK/dt=−dU/dt= P (軌道半径2r[m])
この数式は、重力波によるエネルギーの持ち去りを前提にした場合の計算式、−1/2dU/dt=P(軌道半径r[m])と全く等しいものであるる。
『巻き込み時間』および“連星系パルサーの軌道周期の減少”は、「−1/2dU/dt=P(軌道半径r[m])」の式やケプラー則の式(『T 2∝r 3』)を利用して計算されるのであった。(参考 『一般相対性理論』 p242〜244 Torsten Flieβbach著 共立出版)
したがって、−1/2dU/dt=P(軌道半径r[m])と全く等しい数式(dK/dt=)−dU/dt= P (軌道半径2r[m])を用いることになるので、「重力波がエネルギーを持ち去らないこと」を前提にする(運動エネルギーの増加ΔKに伴う「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出数の増加としての重力波を説明する)“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において導かれる、『巻き込み時間』および“連星系パルサーの軌道周期の減少”は、「重力波によるエネルギーの持ち去り」を前提にしたものと、ぴったり一致することになるのである。
※このように、“重力波がエネルギーを持ち去る”と前提して導いた数字(計算結果)と“重力波がエネルギーを持ち去らない”と前提して導いた数字(計算結果)は、ぴったり一致することは、「数字の一致は必要条件に過ぎないこと」および「観測の理論負荷性」を示す例であると言える。
※「軌道半径が2倍であること」は、これまで観測と矛盾していないだろうか?
そのことに関して、次の記述がとても参考になる。
『では、ハルスとテイラーが発見した連星パルサーPSR B1913+16の観測結果から、重力波の存在がどのように検証されたのか、そのプロセスをもう少しくわしく見ていきましょう。
図3-2は、連星パルスの電波パルスの周期変化から、連星パルサーの視線方向(地球と連星パルサーを結ぶ線の方向)における速度を求めた結果を示しています。この図から、軌道についての特徴を見いだすことができます。
…
… 軌道の大きさは、a sini=1.00R◎。a は、軌道長半径、R◎は太陽の半径、i は軌道傾斜角(軌道面に垂直な線と地球からの視線方向との間の角度)を表しています。残念ながら視線方向速度の観測結果だけからは、軌道半径と軌道傾斜角を分離して求めることはできないのですが、よほど極端なケースを考えなければ、軌道半径はほぼ太陽半径と同等か、せいぜいその数倍程度と推定できます。』
(p.81-82 『重力波とはなにか』 安東正樹 講談社ブルーバックス 下線は、筆者による。
なお、『◎』で示した記号は、原文では、『◯&その中の点・』の記号であった) |
|
この記述から、軌道半径はこれまで正確に観測されて来なかったこと、これまでの軌道半径の推定値には数倍の誤差が生じうることがわかる。 つまり、このことから、現在のところ、「軌道半径が2倍であること」は、これまで観測と矛盾していないと言ってよいと思われる。詳細な検討は、今後の課題である。
|
このことは、下の記述の修正を促していると思われる。
『われわれの見積もり(36.33)は, この効果のオーダーをよく表している. 観測結果の綿密な解析によって, 観測された減衰は相対誤差1%で理論的な計算と一致することが明らかになった. このほかにも考えられる効果があり, それらの議論を経て, 重力波放射が軌道の減衰に対する唯一の可能な説明であるという結論になった. このことから, この観測は重力波放射の間接的な証拠と見なされる』
(『一般相対性理論』 p244 Torsten Flieβbach著 共立出版 下線は、筆者による) |
すなわち、「重力波放射によるエネルギーの持ち去り」が、『軌道の減衰に対する唯一の可能な説明』ではないのである。
『軌道の減衰』には、少なくとも2つの可能な説明があるのだ。
〈1〉「重力波放射によるエネルギーの持ち去り」によって、重力=遠心力を保ちながら、軌道が減衰する。
〈2〉重力>遠心力による自由落下によって、軌道が減衰する。
重力波とは、自由落下に伴う重力ポテンシャルエネルギーを利用した(外部)運動エネルギーが増加する過程での、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出数の増加そのものに相当するのである。 |
果たして、どちらが、自然(nature)と調和しているのだろうか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、明らかに後者〈2〉を支持している。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、ある質量を持つ物体が加速運動をすれば、運動エネルギーが増加して(その加速運動の方向への)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の放出源として働き続ける能力」が増加するとともに、質量が増加する。
(この性質が、加速しおえた物体のその後の等速運動(慣性運動)(“流れるプール効果”)を支え、運動が光速に近づくほど質量が増加することを支え、光速不変を支え(マイケルソンモーレーの実験結果を支え)、そして、アインシュタイン方程式の右辺を支え、一般相対性理論が持っている矛盾(「エネルギー保存則」と「熱運動による正のエネルギーの放射」の間の矛盾)の解消を支えることは、これまでの説明で述べたとおりである)
ある質量を持つ物体が減速運動をすれば、運動エネルギーが減少して(その減速運動とは逆の方向への)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の放出源として働き続ける能力」が減少するとともに、質量が減少する。
この質量の加速運動(や減速運動)にともなう『放出された「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数の変化』として創発するものが、重力波である。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、重力波がエネルギーを持ち去らないのは明白である。
個々の重力子が、エネルギー非保存(by不連続な時空)の所産である以上、
重力波(放出される重力子数の変化)も、エネルギー非保存(by不連続な時空)の所産なのである。
そして、重力波(放出される重力子数の変化)がエネルギー非保存の所産である以上、
エネルギー保存則を根拠に、重力波がエネルギーを持ち去ると考えることに意味がなくなるのである。
そもそも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、加速していようが、静止していようが関係なく── 重力子は、地球からも、太陽からも、月からも、人からも、りんごからも、自動車からも、鉛筆からも、消しゴムからも、水素からも、電子からも、クォークからも、宇宙船からも、ブラックホールからも… あらゆる物体(質量)から、常にある頻度で放出され続けており、どの重力子も「エネルギーを持ち去る」ということをしていないのである。
(仮に、もし、“重力子がエネルギーを持ち去る”ことが本当に起こっているならば── 電子も、クォークも… 含め、あらゆる物体が持つ質量が、(重力子1つあたりおよそ3.2×10−9[kg]ずつのペースで)減り続けることになってしまうので、今、目の前に存在している自然(nature)の姿と、全く異なってしまっているだろう。(万有引力の法則も成立しないであろう) つまり、こう言った単純な思考実験からも、“重力子がエネルギーを持ち去る”という説明が、自然(nature)から乖離しているらしいことがわかるのである)
なぜなら、どの重力子も、エネルギー非保存(by不連続な時空)の所産だからである。
もし、運動エネルギー(内部&外部)が増せば、“重力子の放出源として働き続ける能力”が増すので、放出される重力子の数も増すし──
もし、運動エネルギー(内部&外部)が減れば、“重力子の放出源として働き続ける能力”が減るので、放出される重力子の数も減る。
(参考 《重力子の働きと慣性》)
そして、その運動エネルギー(内部&外部)の変化に伴う“放出される重力子数の変化”のことを、重力波と呼んでいる、ただそれだけのことなのだ。
したがって、やはり、個々の重力子が“エネルギー非保存”の所産であり“エネルギーの持ち去り”に関係しない以上、これらの“放出される重力子数の変化”、すなわち、重力波も、“エネルギー非保存”の所産であり、“エネルギーの持ち去り”に全く関与しないのである。
重力波は、『加速中 or 減速中の「放出される重力子数の変化」の部分を取り上げて見ているだけのものに過ぎない』とも言える。
例えば、2つの同じ質量M[kg]の物体が、互いに反対向きに単振動しているような系で重力波が放出される様子は、次のように示される。
※図のピンク色の斜線の部分が、運動エネルギーの変化ΔK、すなわち、「放出される重力子数の変化」に相当し、これらが重力波に相当する。
やはり、この図でも、重力波による“エネルギーの持ち去り”は、存在しないことがわかる。
※静止質量がM0[kg]の剛体は、物体の運動方向へは、c/(c−v)に相当する膨張の効果、物体の運動と反対の方向へは、c/(c+v)に相当する収縮の効果をもたらす結果、この剛体の質量エネルギーMc2[J]は、Mc2=M0c2/(1−v2/c2)1/2≒M0c2+M0v2/2 [J]((c>>v)[m/s])となるのだった。
緑の線で示した効果は、「静止質量エネルギーによる重力子の放出が減る効果」に相当する。
赤の線で示した効果は、「この“静止質量エネルギーによって重力子の放出が減った分”を帳消しにする効果」と「運動エネルギーによって重力子の放出が増える効果」の和に相当する。
「静止質量エネルギーによる重力子の放出が減る効果」と「この“静止質量エネルギーによって重力子の放出が減った分”を帳消しにする効果」の和により、静止質量エネルギーM0c2は一定となり、「運動エネルギーによって重力子の放出が増える効果」により、M0v2/2 [J]が生ずる。
(この運動エネルギーM0v2/2 [J]が、時空の流れるプール効果を生ずるのだった)
このことを、互いに、反対向きに単振動する2つの剛体にあてはめると、次の図ようになる。
すると、観測点では、緑の線で示される「静止質量エネルギーによる重力子の放出が減る効果」と、赤の線の効果の一部である「この“静止質量エネルギーによって重力子の放出が減った分”を帳消しにする効果」が、ちょうど打ち消し合うことになる。
その結果、運動線上の上のような観測点では、ちょうど、運動エネルギーK≒M0v2/2[J]の変動に相当する、「放出される重力子数の変化」、すなわち、重力波を観測することになるのである。
つまり、上図の観測地点で観測する「放出される重力子数の変化(重力波)」は、結局は、「M0v2/2」[J]の変動とぴったり同じになるのである。
|
例えば、単に、1つの物体が、加速a[m/s2]で加速したり、減速したりするだけでも「放出される重力子数の変化」が生ずるので、重力波が生じることになる。
それを図で示すと次のようになる。
※図の紫の部分が、加速中の「重力子の放出頻度の変化」(「放出される重力子数の変化」)に相当し、ピンクの部分が、減速中の「重力子の放出頻度の変化」(「放出される重力子数の変化」)であり、これらが重力波に相当する。
やはり、この図でも、重力波による“エネルギーの持ち去り”は、存在しないことがわかる。
※このカーブは、v=at、運動エネルギーK=mv2/2=ma2t2/2より、2次関数(放物線)に相当するカーブである。
※厳密には、上図における重力波(重力子の放出頻度の変化)とは、単独の物体(剛体)の内部において、観測することができる重力波(重力子の放出頻度の変化)ということになる。 なぜなら、厳密には、物体(剛体)の内部においてのみ、運動エネルギーK≒M0v2/2[J]の変動を観測できるからである。
厳密には、物体(剛体)の外部では、単独の物体(剛体)が運動する場合、運動エネルギーK≒M0v2/2[J]の変動に相当する重力波(重力子の放出数の変化)を観測することができないが、剛体の運動の速さv[m/s]が光速c[m/s]より、十分小さいときは、外部での観測結果を、運動エネルギーK≒M0v2/2[J]の変動に相当する重力波(重力子の放出数の変化)の近似値と見なしても問題ないと思われる。詳細な検討は、今後の課題である。
|
※他にも、例えば、物体が、他の物体に向かって、自由落下する場合には、ラセン軌道をとろうがとるまいが関係なく、重力波(重力子の放出数の変化)が生じると考えられる。
※左図の紫の部分が、(ラセン軌道をとらない)自由落下に伴う加速(運動エネルギーの増加)による、「放出される重力子数の変化」)であり、重力波の一種である。
右図が、ラセン軌道をとる自由落下による、「放出される重力子数の変化」)であり、これも、重力波の一種である。
やはり、いずれも、重力波による“エネルギーの持ち去り”は、存在しない。
※このカーブは、何に相当するカーブなのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
|
よって、もし、“連星系パルサーの軌道運動エネルギーが減少”するだけであれば、本来は、“重力子を生じる能力”が減り、放出される重力子の量(頻度)が減るだけのことである。
(なお、その後、重力ポテンシャルエネルギーを利用して加速し、“重力子を生じる能力”が増え、放出される重力子の量(頻度)が増えることは考えられる)
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── 連星系パルサーについて、“重力波(“重力子の放出数の変化”(結局は、重力子の総和))がエネルギーを持ち去る”という現象を、どこにも見い出すことはできない。
重力波は、エネルギー非保存の所産であるので、力学的エネルギー保存則に従っていないのである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、(摩擦がない限り)、全エネルギーEは、減少しないと考えられるのである。
重力波は、「運動エネルギーの変動」、「重力子の放出源として働き続ける能力の変動」、「質量の変動」のを反映したものなのである。
※こういった重力波の説明は── 他の説明、すなわち、『特殊相対性理論の前提(光速不変…)やそれが導く結論(ローレンツ収縮、加速による質量の増加…)』や『アインシュタイン方程式の右辺を「高級大理石」とする考え』『Gが2Gになること』についての説明とも調和している。
※また、「重力>遠心力」、「“うすい空気”との摩擦」によってエネルギーが奪われること」とも調和している。
|
※「重力波によってエネルギーが持ち去られる」が、「重力=遠心力」を前提としている一方、「重力波によってエネルギーが持ち去られない」は、「重力>遠心力」を前提としている。
したがって、(100%完全な真空が存在しないがゆえに)「単に真空と見なされた宇宙空間内に存在する分子との衝突、すなわち、“うすい空気”の摩擦抵抗によって、エネルギーが失われる」という効果と調和しているのは、「重力波によってエネルギーが持ち去られない」の方だけである。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wikipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
それは、次のように大きく2つに分けて考えればよいと思われる。
1.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できない場合
2.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できる場合
1.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できない場合
例えば、地球が太陽の周囲を公転しているような場合、連星パルサーがきわめてゆっくり公転周期を小さくしている場合に相当すると考えられる。 その場合、重力波によって持ち去られていたと考えられていたエネルギーの大部分が、実際には、「“うすい空気”との摩擦」によって少しずつ失われていることになる。この場合、「獲得される運動エネルギーに相当するエネルギーΔK[J]」は、「利用される重力ポテンシャルエネルギー−ΔU[J]」とは等しくはならず、部分的に「“うすい空気”との摩擦によって失われるエネルギー」によって相殺されると考えられる。 この“うすい空気”との摩擦抵抗による効果が、獲得された運動エネルギーによって重力ポテンシャルエネルギーが「およそ2倍」になることからの誤差、すなわち、厳密には無限遠方から近づかないことによる誤差を増加させてしまっていると考えられる。
(厳密な計算を含め、詳細な検討は、今後の課題である)
2.“うすい空気”との摩擦抵抗が無視できる場合
連星パルサーや2つの巨大ブラックホールがらせんを描いて合体する直前等に、急激な「自由落下的な加速運動」をともないながら(重力波の振幅の増加を加速させながら)公転周期を小さくする場合には、“うすい空気”との摩擦抵抗によって奪われるエネルギーを無視できると考えられる。なぜなら、らせんを描いて衝突する直前においては、「獲得する運動エネルギーに相当するエネルギーΔK[J]」が、相対的に、とても大きくなるからである。
この場合、厳密には無限遠方から近づかないことによる誤差を増加させてしまう効果も無視できるようになり、獲得された運動エネルギーによって重力ポテンシャルエネルギーが「2倍」に近づいていく効果がメインになると考えられる。
(厳密な計算を含め、詳細な検討は、今後の課題である)
|
「重力波がエネルギーを持ち去る」ことに関連して、大きな問題(矛盾)が生ずることに、アインシュタインは気づいていた。
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』 p.170〜171 下線は、筆者による)
|
そして、この『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』ほどの、大きな問題(矛盾)を解消しようとアインシュタインは必死だった。
|
『重力波を放出している物質系は、エネルギーを外に向かって放出するはずである。したがってエネルギー保存則を考えると、この反作用として物質系の運動は減衰することとなる。 それにもかかわらず、このような減衰のない振動を考えることができる。たとえば、物質系から波が外に向かって放射されるとともに、他方で中心に向かって集まってくる第2の波動場が存在する場合である。しかもこの第2の波は、第1の波によってもち去られたエネルギーと同じ量のエネルギーを、物質系に運び入れる場合である。〜』
(『アインシュタイン選集2──A9重力波について』(p.180-181) 下線は、筆者による)
|
なぜ『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』が『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』のかと言えば、その理由は、やはり、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』が、(エネルギー保存則にもとづくと)「重力波による“エネルギーの持ち去り”によって、系全体の質量が減少する」という奇妙な予測を導くからだと思われる。
そこにある大きな問題(矛盾)に、誰よりも一番アインシュタイン自身が気づいていたからこそ、アインシュタインは、必死だったのである。
だからこそ、アインシュタインは、『それにもかかわらず、このような減衰のない振動を考えることができる。〜』以下のような、系全体のエネルギーが減少しなくなるようなしくみを、ひねりだしたのだのだと思われる。 (たしかに『考えることができる』かもしれないが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)から見ると、かなり無理のある(自然(nature)から乖離している可能性が高い)説明であるように思われる。なぜなら、なにゆえに『第1の波によってもち去られたエネルギーと同じ量のエネルギー』が『物質系に運び入れ』られなければならないのかが説明つかないからである)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、この問題を解決するためにまず何より修正すべきだったのは、「重力波によって“エネルギーの持ち去り”が生じるという」と説明、つまりは、その前提であるところの「時空は連続なので、エネルギー保存則が成り立つ」という考えの方だったことになる。
なぜなら、時空が不連続であることを前提とする“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── 『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』には、どこにも問題が生じないからである。
しかし、アインシュタインは、この「連続な時空&エネルギー保存則が成り立つ」という前提を守るべく、必死にもがいたのである。
なぜなら、アインシュタインの偉大な成果、アインシュタイン方程式(一般相対性理論)は、「連続な時空&エネルギー保存則が成り立つ」を前提に生まれていたからである。
「連続な時空&エネルギー保存則が成り立つ」という前提を守ることは、一般相対性理論(byリーマン幾何学)を守ることであった。
したがって、アインシュタインには、「連続な時空」や「エネルギー保存則」(byネーターの定理)を尊重するしか選択肢がなかったのである。
そのアインシュタインにしてみれば、重力波〈放出される重力子数の変化〉が、エネルギー非保存の所産であると考えることなど、ナンセンスでしかなかった。
当然、「負にならない全放射エネルギーが、重力波によるエネルギーの持ち去りを意味する」と解釈するしかなかった。
その結果、アインシュタインは、板挟みにあったのである。
そして、必死に、(『それにもかかわらず、このような減衰のない振動を考えられることができる。〜』以下のような)無理のある考えをひねり出すほど、追いつめられたのである。
アインシュタインは、重力波というテーマに至って、「エネルギー保存則(連続な時空)を前提とする 一般相対性理論」が、根本的な矛盾を抱えていることに、はっきり気づいたのだ。
(だからこそ、『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』だったのだと思われる)
しかも、その矛盾は、一般相対性理論が「連続な時空を前提とするリーマン幾何学」に頼っている以上、アインシュタインにとって、どうしても根底から解消することができないものであった。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、この矛盾(板挟み、行き詰まり…)を根底から解消するものである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、重力子、重力波、重力場はいずれも、「不連続な時空」&「エネルギー非保存の所産」である。
「どんな方向に対しても負にならない全放射エネルギー」の実体は、不連続な時空の中で、エネルギー保存則を破って生じている重力子の総和、数の変化… であり、それは、結局は、エネルギー非保存の所産であることを、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、はっきり示している。
(→ 《一般相対性理論とエネルギー保存則について》)
しかも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、時空の量子化を含むところの── いわば、“究極の量子論”といえるものであり、量子論の完成をも助けるものである。 (→結果2、4) すなわち、このことは、次のアインシュタインの期待(予想)と調和している。
|
『量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』 p.170〜171 下線は、筆者による)
|
しかも、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、特殊相対性理論(光速不変、ローレンツ収縮、運動エネルギーが増すと質量が増加すること(アインシュタインの式E=mc2=(m0c2/(1−(v/c)2)1/2 (m0:静止質量)が示していること)…)や一般相対性理論(時空の曲り、獲得した運動エネルギーが新たな質量となること…)、ニュートン力学(慣性の法則、万有引力の法則)、電磁気学(クーロンの法則…)… を、「より深い階層のレベル」から根底から説明し、これらを包含するものである。
※逆に「重力波によるエネルギー持ち去り」という考えは、たとえエネルギー保存則と調和していたとしても、特殊相対性理論とも、一般相対性理論とも、ニュートン力学とも、矛盾してしまうことを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は示している。(例えば、質量が減少し続ける結果、万有引力法則が成立しなくなるだろう。また、等速運動が実現しなくなるだろう…)
つまり、「エネルギー保存則にしがみついている限り、重力は、量子化することはできない」のだと思われる。
すなわち、「連続な時空」や「エネルギー保存則」と、重力子や「重力の量子化」(「重力場(時空の曲り)の量子化」)は、矛盾しているのである。
したがって、一般相対性理論の成功をもたらした「連続な時空を前提とするリーマン幾何学」そのものが、重力の量子化(「重力場(時空の曲り)の量子化」)を困難にしてきた最大の要因の1つであったということになるだろう。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の成果を、決して否定するものではない。
|
『伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいることが発見され、この重力波の存在が間接的に示された』
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』 J.M.ワイズバーグ、J.H.テイラー、L.A.ファウラー)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、この成果が、どのようなしくみで成立しているかを、説明するものである。
この成果には、大きく、次の2つの解釈(説明)があることになる。
|
従来の物理学
(『連星系パルサーからの重力波
サイエンス1981年12月号』…)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
連星系パルサーから放出する
重力波(重力子の総和)による
“エネルギーの持ち去り”
|
ある
|
ない
|
|
重力波
(重力子の総和)
|
エネルギー保存則の所産
|
エネルギー非保存の所産
|
|
重力波のエネルギーを含めたエネルギー保存則
|
成り立つ
|
成り立たない
|
|
力学的エネルギーの保存
(運動エネルギーK[J]
+重力ポテンシャルエネルギーU[J]が一定)
|
成り立たない
|
成り立つ
(ゆえに、ΔK=−ΔU)
|
|
重力波の解釈
|
『この重力波は、“エネルギーの持ち去り”分に相当する』
|
『この重力波は、“重力子の放出源として働き続ける能力”アップ分に相当する』
|
|
重力と遠心力の関係
|
重力=遠心力
(ゆえに、GMm/r2=mv2/r より、−U/2=K)
|
重力>遠心力
|
|
『P =(32GΩ6/5c5)×ε2I 2
回転している質量分布からの放射パワー』の解釈
|
重力波によってよって持ち去られる
エネルギー
|
「加速運動にともなって“重力子の放出源として働き続ける能力がアップしている部分”」 |
|
根拠となる数式
|
−dE/dt=dK/dt=−1/2dU/dt=P
(軌道半径r[m])
|
dK/dt=−dU/dt= P
(軌道半径2r[m])
|
|
『巻き込み時間t spir』および
“連星系パルサーの軌道周期の減少dT/dt”
|
等しい
(いずれも同等な次の式から計算される。
(「−1/2dU/dt=P」(軌道半径r[m]、「−dU/dt= P」(軌道半径2r[m]) )
|
※参考 『一般相対性理論』 Torsten Flieβbach著 共立出版
たとえ数値計算の結果がぴったり一致していても、この成果についての解釈(説明)は、180度逆である。
一方は、「重力=遠心力」や「エネルギー保存則(連続な時空)」を前提にして“重力波がエネルギーを持ち去る”と解釈(説明)し──
一方は、「重力>遠心力」や「エネルギー非保存(不連続な時空)」を前提にして“らせん軌道をとりながらの自由落下(運動エネルギーの増加)”にともなう「放出される重力子数の変化」が重力波である”と解釈(説明)している。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、後者こそが自然(nature)と調和しているらしいことを示している。
連星パルサーと重力波について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の結論を導く。
結論1.11.1 連星パルサーから放出される重力波は、エネルギーを持ち去っていない(エネルギー非保存の所産である)。
結論1.11.2 連星パルサーは、それぞれ、らせん軌道を描く自由落下によって、(重力ポテンシャルエネルギーを利用して)運動エネルギーを増加させる(=連星の重力子の放出源として働き続ける能力を増加させる)過程によって、重力波(=放出される重力子数の変化)を生んでいる。
結論1.11.3 連星パルサーの巻き込み時間t spir、“連星系パルサーの軌道周期の減少dT/dt”の計算数値は、「重力波がエネルギーを持ち去ること」を前提にして導いても、「重力波が、らせん軌道を描く自由落下、および、重力ポテンシャルエネルギーを利用した、運動エネルギーの増加(=連星の重力子の放出源として働き続ける能力の増加)によって生み出されていること」を前提として導いても、ぴったり等しくなる。
※「重力波はエネルギーを持ち去らない」という前提を持つ“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、(2016年2月に最初に発表された)「LIGOが“重力波”を直接、観測した」という偉大な成果を決して否定するものではない。
しかし、「LIGOによって観測された“重力波”」(LIGOが得た観測データ(重力波の波形))についての“解釈”については、
「重力波はエネルギーを持ち去る」(重力波を含めてエネルギー保存則が成立する(連続な時空))を前提とする、これまでの物理学のものと、
「重力波はエネルギーを持ち去らない」(重力波はエネルギー非保存の所産である(不連続な時空))を前提とする、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のものとの間で、
180度の違いがあると予想される。
例えば、これまでの物理学では、『太陽の約35倍と約29倍の質量のブラックホールが、合体後、太陽の約62倍の質量のブラックホールになった結果、太陽の約3倍のエネルギーが重力波として持ち去られた』という“解釈”をしてきた。
※なお、これらの質量の数値は、決して直接観測されたものではなく、LIGOの観測データ(重力波の波形)をもとに、アインシュタインの一般相対性理論(エネルギー保存則(連続な時空)、「重力波によるエネルギーを持ち去り」)を前提とするモデルやシミュレーションを駆使して得られた“見積もり計算”の所産に過ぎない。
(参考 『Observasion of Gravitayional Waves from a Binary Black Hole Merger』(PHYSICAL REVIEW LETTERS B.P.Abbot et al.(特に『VI.SOURCE DISCUSSION』の部分))
『重力波とは何か』(p.173-175 講談社ブルーバックス 安東正樹))
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の前提(不連続な時空、「重力波はエネルギーを持ち去らない」)によれば、LIGOの観測データ(重力波の波形)から、180度逆の説明を与える。 それは、次のようなものである。
|
2つのブラックホールが「インスパイラル期、合体、リングダウン期」を経る過程で、重力波の振幅が大きくなったり小さくなったりしている一方で、重力波の振動数は一貫して増加し続けている。
このことは、『2つブラックホールが、「インスパイラル期、合体、リングダウン期」のようにコンパクト化し続けるのに伴い、角運動量保存則に従って、回転数がアップし続けていることを意味している』と解釈できる。 (アイススケートのスピンにおいて、両腕を縮こませると回転数がアップするの同じ理由である)
2つのブラックホールのコンパクト化に伴い回転数が増加する際、(角運動量の大きさが一定であるのに対して)運動エネルギーは増加し続けるので、当然、質量エネルギーも増加し続けることになる。
(角運動量の大きさL=mvr=mr2ω(v=rω(ω:角振動数))が一定になる結果、運動エネルギーK=mv2/2=mv2/2=mr2ω2/2は増加し続ける)
コンパクト化が進んで球体に近づくほどに、重力波(重力子の放出数の変化)は消失していくが、この運動エネルギー増加に伴う、質量エネルギーの増加により、重力子の放出数は増え続けていることになる。
つまり、『重力波の振動数は一貫して増加し続けている』という観測結果(重力波の波形)は、この過程で一貫して質量が増加し続けていることを示していると解釈できるのである。
そして、まさに、この解釈(説明)は、重力波はエネルギーが持ち去らないという前提とぴったり調和している。
|
このように、(連星パルサーのとき同様に)「重力波はエネルギーを持ち去らない」という前提でも「LIGOによって観測された“重力波”」(LIGOが得た観測データ(重力波の波形))の“解釈”は可能である。 これが正しければ、「LIGOによって観測された“重力波”」(LIGOが得た観測データ(重力波の波形))は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を支持する証拠の1つである、と再解釈できることになる。 (まさに、これは、「観測の理論負荷性」の一例であると言えるだろう)
両者を整理すると次のようになる。
|
|
これまでの物理学
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
重力波を直接観測した成果
|
○
|
○
|
|
アインシュタインの一般相対性理論
|
すべて正しい
|
一部(特にエネルギーと関連する部分)は、
修正を要する。
|
|
重力波を含むエネルギー保存則
|
○
成立する
(時空は、どこまでも連続)
ゆえに、重力波はエネルギーを
持ち去るはずである。
|
×
成立しない
※重力波はエネルギー非保存の所産である。
((プランクスケールで)時空は不連続)
ゆえに、重力波はエネルギーを
持ち去らないはずである。
|
|
インスパイラル期〜リングダウン期における
2つのブラックホールの質量
|
一貫して
減るはずである
|
一貫して
増えるはずである。
|
|
観測結果(重力波の波形)の解釈
|
『太陽の約35倍と約29倍の質量のブラックホールが、合体後、太陽の約62倍の質量のブラックホールになった結果、太陽の約3倍のエネルギーが重力波として持ち去られた』 |
『(重力波の振幅が大きくなったり小さくなったりしている一方で)重力波の振動数は一貫して増加し続けている』以上、合計の質量は増加し続けている。
※単純に、太陽の約3倍の質量エネルギー(運動エネルギー)が増加したと考えていいのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。 |
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、アインシュタインの重力理論に、少なくとも、次の3つの部分的な修正を迫っているのだった。
|
1.時空は連続である
|
→ |
時空は不連続である。
|
|
2.重力場は、エネルギー保存則にしたがう。
(重力場のエネルギーを含む全エネルギーは、
エネルギー保存則に従う)
|
→ |
重力場は、エネルギー非保存の所産である。
(重力場は、「エネルギー非保存の所産である
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和」
として創発している)
|
|
3.重力場は、非線形である
|
→ |
重力場は、線形である。
(重力場のエネルギーそのもそのが、
直接そのまま、質量になりえない)
|
| ※「重力波がエネルギーを持ち去る(重力波もエネルギー保存則に従う)」→「重力波がエネルギーを持ち去らない(重力波はエネルギー非保存の所産である)」という修正は、本質的に、2.の修正と同類であると考えられる。 |
※「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提にもとづく、『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という一見、もっともに思われる解釈(説明)には、根本的な矛盾があることに気づいた。それは、次のようなものである。
|
1つは、『たとえ「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提の上であっても、連星ブラックホールの質量が最終的に減るとは考えにくい』ことから生まれる矛盾である。
まず、連星ブラックホールのインスパイラル期について、考えてみよう。
この説明は、「連星パルサー(連星中性子星)」についての説明と同じである。
「重力波がエネルギーを持ち去らない」場合、ブラックホール連星は、重力ポテンシャルエネルギーU[J]の減少分(−ΔU[J])のすべてを利用して、運動エネルギーK[J]を増加させる。(すなわち、ΔK=−ΔUである。なお、このことは、力学的エネルギーが保存していることを意味している)
それに対して、「重力波がエネルギーを持ち去る」場合、この重力ポテンシャルエネルギーU[J]の減少分(−ΔU[J])の1/2だけが重力波として持ち去られ、その残りの1/2だけが、運動エネルギーK[J]の増加に使われると考えられる。
(すなわち、ΔK=−ΔU/2である。これが成立するのは、「遠心力=重力」(「mv2/r=GMm/r2」)、すなわち、「U=−K/2」の関係が保たれるからである。 なお、「U=−K/2」と「E=U+K」より、「E=−K」が導かれるのだった)
つまり、インスパイラル期において、たとえ「重力波がエネルギーを持ち去る」としても、連星ブラックホールは、その運動エネルギーを増加させる結果、その質量エネルギー(すなわち、質量)を増加させることになるのである。
それは、連星ブラックホールの合体〜リングダウン期についても、基本的に同様に考えて説明するのが自然であろう。
すなわち──
『連星ブラックホールが合体して球状に至るのは、重力の働きがあるから、すなわち、重力ポテンシャルエネルギーU[J]が利用されるからに他ならない。 「重力波がエネルギーを持ち去る」場合、連星ブラックホールが合体して球状に至る過程においても、重力波として持ち去られるのは、重力ポテンシャルエネルギーU[J]の一部だけであり、残りは、合体したブラックホールの運動エネルギーの増加、すなわち、質量エネルギーの増加に利用される。(かりに、重力ポテンシャルエネルギーU[J]の100%が重力波として持ち去られるとしても、合体したブラックホールの質量が減ることはない)』と説明するのが自然であると思われる。
したがって、インスパイラル期〜合体〜リングダウン期のいずれにおいても、『たとえ「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提の上であっても、連星ブラックホールの質量が減るとは考えにくい』のである。
その理由は、『重力波がエネルギーを持ち去る結果、連星ブラックホールの質量が減る』という解釈(説明)は、『新たに獲得された運動エネルギーが、新たな質量エネルギー(すなわち、質量)になる』という相対性理論の説明と矛盾しているからである、と要約できるだろう。
※より簡単に言えば、『もし、本当に「重力波がエネルギーを持ち去ることによって質量が減るしくみ」があるのならば、これまでの(運動エネルギー=質量エネルギーが増加し続けていることに依存している)連星パルサーについての説明が成立しなくなってしまう』となる。
つまり、「LIGOによる重力波を直接観測したことについての説明」と、「M.ワイズバーグ、J.H.テイラー、L.A.ファウラーによる重力波を間接的に観測したことについての説明」は、ともに「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提であるのに関わらず、互いに矛盾し合っているのである。
以上を踏まえると、「連星ブラックホールの質量が減る」と説明された理由は、「重力波を含めてエネルギー保存則が成り立たなければならない」という前提以外に、どこにもないことに気づくことができる。
つまり、『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という一見、もっともな解釈(説明)は、「重力波を含めてエネルギー保存則が成り立たなければならない」という制約の中で無理してひねり出されたものに過ぎない可能性が高いのである。
※なお、「リングダウン期に限って、何らかの未知なるしくみがあって、本当に、重力波によるエネルギーの持ち去りによってブラックホールの質量が減る」と考え続けるのであれば、(アインシュタインがかつて遭遇した)『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』ほどの重大な問題に直面することになる。
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より p.170〜171 下線は、筆者による)
|
つまり、『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という解釈(説明)は、実は、一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるような解釈(説明)でもあるのである。
「直接観測された重力波(波形)」そのものは、もともと、一般相対性理論を正当化するものであるはずだったのに、その解釈(説明)が一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるものになってしまっている── それが、もう1つの矛盾である。
|
《重力場と電磁場の比較》
重力場と電磁場は、ともに線形である点で似ているが、やはり違いもある。
これら間の違いを比較してみよう。
そこにある大きな違いの1つは、(クーロンの法則を担う)マクロの電場やマクロの磁場を生むのは、仮想光子であり、「ふつうの“電磁波”を構成する光子」ではない一方──
重力場を生む重力子は、(ふつうの“電磁波”を構成する光子と似ている“波長2LP[m]の光子”が並走する)「デュアルLP光子」であるということである。
|
場
|
電磁場
(クーロンの法則を担う
マクロの電場&マクロの磁場)
|
重力場
|
|
荷量
|
電荷、磁極
|
質量
|
|
荷量の定義
|
仮想光子の放出源として働き続ける能力
|
重力子の放出源として働き続ける能力
|
|
創発を支えるもの
|
仮想光子
(波長は、様々)
|
重力子
(波長は一定(2LP[m])
“デュアルLP光子”である
|
|
場の創発
|
(仮想光子が生む)
「変形している“4面体”」
(ミクロ電場やミクロ磁場)の総和として創発
|
(重力子が生む)
「“4角形”(縮みきったバネ)」
の総和として創発
|
|
場のエネルギー
|
エネルギー非保存の所産
(仮想光子、電磁波、光子も同様)
|
エネルギー非保存の所産
(重力波、重力子も同様)
|
|
厚さ2LP[m]の球殻に蓄えられる
エネルギーの大きさ
|
aQc2[J]
|
Mc2[J]
|
|
仮想光子や重力子が
どこへ行くか
|
ふつう、その電荷に再吸収される
(無限遠方まで進んでいかない)
※ある電荷が加速すると、放出された仮想光子は、
その電荷に再吸収されず、
ふつうの光子として無限遠方まで進む。
(そして、別の電荷に吸収されることはありうる)
|
無限遠方まで進み続ける
(質量に再吸収されることは
ありえない。物質はデュアル共転回
できる構造を持たないからである)
|
|
荷量(電荷や質量)が
静止(等速運動)している間の振る舞い
|
仮想光子の放出&再吸収を繰り返し続け、
電場や磁場を創発する。
|
(運動方向にも)重力子の放出を繰り返し続け、
重力場を創発している
|
|
荷量が加速運動をすると
|
光子が放出される
|
重力子の放出数がアップする
|
|
主な加速(or減速)の原因
|
電磁場のポテンシャルエネルギー
※重力場のポテンシャルエネルギーが
加速(or減速)の原因になることもありうる。
|
重力場のポテンシャルエネルギー
※電磁場のポテンシャルエネルギーが
加速(or減速)の原因になることもありうる。
|
|
荷量が周期的な振動をすると
|
電磁波が放射される
|
重力波が放射される
|
|
波の創発
|
電磁波は、光子の総和として創発
(光子の放出数が電磁波の振幅に相当)
|
重力波は、重力子の放出数の変化として創発
(重力子の放出数が重力波の振幅に相当)
|
静止電荷(or等速運動する電荷)は、仮想光子を放出したり、再吸収したりを繰り返すことによって、電磁場(マクロの電場やマクロの磁場)を創発する。
もし、仮想光子が存在せず、「ふつうの“電磁波を構成する光子”」のみが存在するとしたらどうなるか?
そうだとしたら、「ふつうの“電磁波を構成する光子”」は、ミクロ電場やミクロ磁場の正負を交互に逆転し続けながら進行するものなので── (クーロンの法則を担う)マクロの電場やマクロの磁場を創発することができなくなってしまうと考えられる。
したがって、(クーロンの法則を担う)マクロの静電場やマクロの磁場が創発するためには、その構成要素は、(放出と再吸収を繰り返す)“仮想光子”でなければならない。
(この説明は、電荷の起源── 電荷の幾何学的な実体像を追求するためにも役立つ。(→結果2))
一方、重力子は、いったん質量から放出されると、次から次へと原始ヒッグス場ユニット(PHU)を変形させながら、無限遠方まで進み続ける。
1つ1つの重力子&“4角形”(縮みきったバネ)は、無限遠方まで進み続ける過程で、突然、増幅したり減衰したりすることは、考えられない。
単に、質量の重心からの距離の2乗に反比例して、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)が、厚さ2LP[m]の球殻上に蓄えるエネルギーの“時間&空間”平均を厚さ2LP[m]で割ったもの──すなわち“重位勾配”)が減るだけである。
そして、この性質が、ニュートンの万有引力の法則や一般相対性理論を支えているのは、言うまでもない。
※ネーターの定理は、時空が連続である時に限って、保存則(エネルギー保存則、運動量保存則)が成立することを示している。
時空が不連続であることを前提にしている“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において、重力子や光子(仮想光子)、そして、それらの集合である、重力波や電磁波が、エネルギー非保存則の所産であると説明されていることは、ネーターの定理と調和している。 →《一般相対性理論とエネルギー保存則について》)
※「(仮想光子と同様に)光子も電磁波(光子の総和として創発)も、エネルギーを持ち去らない(エネルギー非保存の所産である)」ことにもとづくと、『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきている』という事実を、より自然に説明しなおすことができるように思われる。
水素の核融合が進んでも、「太陽から放射される光子や電磁波がエネルギーを持ち去らない」ので、熱エネルギー(水素やヘリウムの運動エネルギー)が増す一方となる結果、光度が増加すると考えられるからである。
もし太陽から放射される光子や電磁波が本当にエネルギーを持ち去るのだったら、『熱エネルギー(水素やヘリウムの運動エネルギー)が減る一方となる(&ヘリウムという不純物が増える一方となる)結果、核融合の効率が低下するので、光度は減少してしまうはずである』と考えるのが、本来は自然であるように思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
《ボーアの原子模型》
ボーアの原子模型は、ラザフォードの原子模型(『正に帯電した原子核の周囲の、電子が回っている』(p.247『物理学入門』))が持っている下記のような「重大な難点」を解消するために生み出されたモデルである。
|
『ラザフォードは、この場合の電子の運動を、原子核との間に働く静電気力を向心力とする円運動と考えた(1911年)。これを、ラザフォードの原子模型という(…)。しかし、この模型には、重大な難点があった。一般に、荷電粒子が加速度をもって運動をすると電磁波を出し、そのエネルギーはしだいに減ってくる。したがって、電子が原子核の周囲を円運動していると、電子はしだいにエネルギーを失って速さが弱まり、ついには原子核に落ち込んでしまうことになる。結局は、そのような模型は、安定に存在できないということになる』
(p.247 『物理学入門』 下線は、筆者による)
|
そして、ラザフォードの原子模型が抱える「重大な難点」のみならず、ボーアの原子模型の成功も、“重力波によるエネルギーの持ち去り”という説明がアインシュタインをはじめ、多くの物理学者の心の中に育った理由の1つとして考えられる。
なぜなら、ボーアの原子模型も、ラザフォードの原子模型と同様に、“光子によるエネルギーの持ち去り”、すなわち、「光子のエネルギーを含む全エネルギー保存則」を前提とするものだからである。
(まさに、そういった想定を反映したものが、例えば、数式、En−Em=hνの式や、下のような図である。)
※ボーアの原子模型では、図のような、“光子によるエネルギーの持ち去り”が想定されている。
Em[J]やEn[J]が、それぞれ全エネルギーであり、その差が光子のエネルギーhν[J]に等しいのは(すなわち、En−Em=hν[J]が成り立つのは)、「光子のエネルギーを含めたエネルギー保存則」が成立することが前提となっているからである。
※「?」となっているのは、次の記述のような奇妙な事情があるからである。
『ボーアは、電子の量子飛躍には、非常に奇妙な性質があることに気づいた。飛躍している時の電子の所在については、何も言えないということだ。軌道間の飛躍──エネルギー順位間の遷移──は、瞬間的に起こらなければならない。さもないと、軌道から軌道へ移動する間に、電子はエネルギーを放出してしまうからだ。ボーアの原子の内部では、電子は軌道と軌道のあいだの空間には存在することができない。電子はまるで魔法のように、ある軌道上から消えた瞬間、別の軌道に姿を表すのだ』(p.146 『量子革命』 下線は、筆者による)
|
|
つまり、ラザフォードの原子模型やボーアの原子模型が前提とする「光子を含む全エネルギー保存則(“光子によるエネルギーの持ち去り”)」からの類推が、「重力波を含む全エネルギー保存則(“重力波によるエネルギーの持ち去り”)」のアイデアを(アインシュタインをはじめとして)多くの物理学者が支持する根拠の1つとなったと考えられるのである。
ところが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「重力波を含む全エネルギー保存則(“重力波によるエネルギーの持ち去り”)」は、自然(nature)から乖離していることをはっきり示している。
そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、仮想光子や重力子と同様に、光子もエネルギー非保存の所産であることを示している。
(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、時空が不連続であることが前提とされているので、ここに問題はない)
このことは、「光子を含む全エネルギー保存則(“光子によるエネルギーの持ち去り”)」を前提としている“ボーアの原子模型”の説明が、自然(nature)から乖離していないかどうかについて検討を要求しているように思われる。
果たして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、(ほぼあらゆる教科書に載っている)“ボーアの原子模型”の説明についても修正を迫っているであろうか?
すなわち、「光子がエネルギーを持ち去らない」という前提で、「原子のスペクトル」や「原子が安定に存在すること」を説明しなおすことができるであろうか?
結論を先に言うと、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、明からに修正を迫っているようである。
そして、「光子がエネルギーを持ち去らない」という前提で、「原子のスペクトル」や「原子が安定に存在すること」を説明しなおすことができるようである。
以下で、その説明をしていくことになる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が展開している「光子がエネルギーを持ち去らない」ということを前提にしている原子模型を「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」と呼ぶこととする。
まず、この「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」と、ボーアの原子模型 (従来の物理学)の両者の比較を概観すると次のようになる。
|
ボーアの原子模型
(従来の物理学)
|
「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の原子模型」
|
|
原子のスペクトルにおける
“光子によるエネルギーの持ち去り”
|
ある
|
ない
|
|
光子のエネルギーを含めた
エネルギー
|
保存する
(ゆえに、E(=K+U)+hν[J]が保存する)
|
保存しない
( 光子は、エネルギーを持ち去らない)
|
|
電子の力学的エネルギー
(運動エネルギーK[J]
+電磁場のポテンシャルエネルギーU[J])
|
保存しない
( 光子が、エネルギーを持ち去ってしまう)
|
保存する
(E=K+U[J]が保存する。
ゆえに、ΔK=−ΔU[J])
|
|
光子の解釈
|
『この光子は、電子の全エネルギー順位En[J]の低下分
に相当する“エネルギーを持ち去る”』
|
『この光子は、電子の加速運動(運動エネルギー順位Kn[J]の上昇)に伴う
「剥ぎ取られた仮想光子」である』
仮想光子がエネルギー非保存の所産である以上
この光子はエネルギーを持ち去らない
|
|
(電子に働く)
静電気力と遠心力の関係
|
常に、静電気力=遠心力
(ゆえに、ke2/r2=mv2/r[N]より、−U/2=K[J])
|
原則として
静電気力>遠心力
(ke2/r2[N]>mv2/r[N])
電子にエネルギーが加えられると
「静電気力」<「遠心力」ともなりうる。
→その結果、楕円軌道も生じうる。
|
|
「電子が、より内側の殻へと
落ちていきやすい傾向」
「電子が、最内殻から順に
うまっていく傾向」
|
説明できない
|
説明できる
|
|
中心に据えるもの
|
電子の「エネルギー順位」
(電子の力学的エネルギーE=K+U[J])
En=−2π2k2me4/h2・1/n2[J]
|
電子の「運動エネルギー順位」
Kn=2π2k2me4/h2・1/n2[J]
|
|
根拠となる数式
|
hν=En−Em(n>m)=Km−Kn(n>m)[J]
=Un/2−Um/2(n>m)[J]
(Kn=2π2k2me4/h2・1/n2[J])
(Un=−4π2k2me4/h2・1/n2[J])
(Kn=−Un/2[J])
|
hν=Km−Kn(n>m)[J]
=Un−Um(n>m)[J]
(Kn=2π2k2me4/h2・1/n2)[J]
(Un=−2π2k2me4/h2・1/n2[J])
(Kn=E−Un[J])
|
|
半径rn[m]
|
rn=h2n2/4π2kme2[m]
|
rn=h2n2/2π2kme2[m]
|
|
水素原子の半径[m]
|
ボーア半径(≒0.53Å[m])
|
ボーア半径の2倍(≒1.06Å[m])
※水素原子のファンデルワールス半径は、1.2Å[m]
|
|
光子が放出される
しくみ(原因)
|
電子の「エネルギー順位」が変化する原因は、
あいまい。
|
電子の「運動エネルギー順位 Kn」の上昇
(by電磁場のポテンシャルエネルギー)
|
|
リュードベリー定数R
|
ともに、導出できる
|
|
統合性、一貫性
|
低い
|
高い
(放射光を含め)一般に、“電荷の加速”に伴って
光子が放出されることと統合できる
仮想光子や重力子がエネルギー非保存の所産であること
(エネルギーを持ち去らないこと)と統合できる
|
次に、それぞれの原子模型について、別々に説明していく。
1.ボーアの原子模型
2.「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」
1.ボーアの原子模型
ボーアの原子模型の前提を、次のようにまとめることができる。
|
〈1〉原子の中の電子の軌道角運動量mvr は、h/2πの整数倍をとるときだけ、定常状態となり、光子を放出しない。
(ボーアの原子模型は、円軌道の場合を考えており、定常状態の条件は、「mvr =nh/2π」ということであり── それは、「mv=h/λ(ド・ブロイの物質波の式)&2πr=nλ」と等価である。
なお、この円軌道の半径r[m]は、「rn=n2h2/4π2kme2[m]」のように量子化されている)
〈2〉電子は、(電子に対して働く力)「静電気力=遠心力」によって、円運動している。
(それは、「K=−U/2」と等価である。 K:運動エネルギー U:ポテンシャルエネルギー)
〈3〉光子は、エネルギーを持ち去る。
光子を含む全エネルギー(「力学的エネルギー(E=K+U)+光子のエネルギーhν」)が保存する。
|
〈1〉と〈2〉の前提から、水素原子の定常状態のエネルギー、すなわち、「エネルギー順位 En=−2π2k2me4/h2・1/n2」が導出される。
そして、〈3〉の前提から、「hν=En−Em(n>m)」が導かれる。
図で示すと、やはり、次のようになる。
※光子がエネルギーを持ち去り、その分だけ、エネルギー順位の値が小さくなっていると説明される。
※エネルギー順位 En=−2π2k2me4/h2・1/n2 は、「力学的エネルギー(E=K+U)」から求められるものである。“光子がエネルギーを持ち去る”ということは、「力学的エネルギー(E=K+U)」の保存則は、成立していないことを意味する。
※この説明では、(電子に対して働く力が)「静電気力=遠心力」であるという条件の中で、「どのようなしくみで、エネルギー順位が変わるのか」、「光子が、どのようなしくみで放出されるのか」がはっきりしない。 すなわち、「光子の放出」と「エネルギー順位を変えること」のどちらが原因で、どちらが結果なのかがはっきりしない。
※図のように『?』が示されているのは、やはり、下のような記述で示される奇妙な事情があるからである。
『ボーアは、電子の量子飛躍には、非常に奇妙な性質があることに気づいた。飛躍している時の電子の所在については、何も言えないということだ。軌道間の飛躍──エネルギー順位間の遷移──は、瞬間的に起こらなければならない。さもないと、軌道から軌道へ移動する間に、電子はエネルギーを放出してしまうからだ。ボーアの原子の内部では、電子は軌道と軌道のあいだの空間には存在することができない。電子はまるで魔法のように、ある軌道上から消えた瞬間、別の軌道に姿を表すのだ』(p.146 『量子革命』 下線は、筆者による)
|
|
以上の、(電子に対して働く力)「静電気力=遠心力」(すなわち、ke2/r2=mv2/r[N]より、「K=−U/2[J]」)という前提と「全エネルギー保存」という前提から導かれる「光子によるエネルギー持ち去り現象」を、電磁場のポテンシャルエネルギー順位Un[J]を考えて説明(解釈)すると次のようになる。
もし、電子が電磁場のポテンシャルエネルギー順位が、Un[J]からUm[J]へと変わる場合、電子は、Un−Um[J]の電磁場のポテンシャルエネルギーを利用することによって、本来は(力学的エネルギー保存則にしたがって)、運動エネルギーKは、Un−Um[J]だけ、増加するはずである。
ところが、そのエネルギーの半分が、光子のエネルギーhν[J]として持ち去られるので、運動エネルギーKは、その半分の(Un−Um)/2[J]しか増加できない。
すなわち、運動エネルギー順位Kn[J]を考えれば、Kn[J]からKm[J]へと運動エネルギー順位が変化した場合の、運動エネルギーの増加分は、Km−Kn=(Un−Um)/2[J]ということになる。
この場合は、残りの半分の(Un−Um)/2[J]が、持ちさられた光子のエネルギーhν[J]に等しいので、hν=(Un−Um)/2[J]となる。
以上から、Km−Kn=(Un−Um)/2=hν[J]となることがわかる。
|
| ※この図は、説明(解釈)を理解するための便宜上の図であり、「ボーアの原子模型」の正確な図ではない。 |
この「(ボーアの原子模型における)電子の運動エネルギー順位Kn[J]」は、具体的に、どのような値をとっているかを調べてみよう。
(電子に対して働く力)「静電気力=電子の遠心力」(ke2/r2=mv2/r[N])の前提から、「Kn=−Un/2[J]」が直ちに導かれる。
すると、En=Kn+Un[J]に代入すると、「En=Kn+Un=Kn+(−2Kn)=−Kn[J]」、つまり、「Kn=−En[J]」が成立していることが導かれる。
したがって、「(ボーアの原子模型における)電子の運動エネルギー順位」は、次のような値となる。
「(ボーアの原子模型における)運動エネルギー順位 Kn=2π2k2me4/n2h2[J]」
※この「(ボーアの原子模型における)運動エネルギー順位Kn」は、単に、エネルギー順位Enの符号を変えただけのものに過ぎない。
この式は、“電子の運動エネルギー”が、とびとびの値をとることを意味している。
ただし、この場合、『光子を含む全エネルギー(「力学的エネルギー(E=K+U)+光子のエネルギー」)が保存する』という前提は変わらないので、この「hν=Km−Kn(n>m)」の式を、「電子の運動エネルギー順位Knの増加(by電子の加速)に伴って、光子が放出されることを意味している」と解釈することはできない。
また、電子に働く力について「静電気力=遠心力」という条件も変わらないので、「どのようなしくみで電子の運動エネルギー順位Knが変わるのか」もはっきりしないままである。
※なお、この“電子の運動エネルギー順位Knの式”用いても、リュードベリー定数Rを導くことができる。
(1/λ=(Km−Kn)/hc=2π2k2me4×1/hc3×(1/m2−1/n2)より、R=2π2k2me4/hc3)。
2.「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」
「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」の前提は、次の3つである。
|
〈1〉電子は、 一定の運動エネルギー順位Kn=2π2k2me4/n2h2をとっている限り、定常状態となり、光子を放出しない。
(これにより、リュードベリ定数Rの導出可能性が保たれる。
すなわち、hν(=hc/λ)=(Km−Kn)より、
1/λ=(Km−Kn)/hc=2π2k2me4×1/hc3×(1/m2−1/n2)より、R=2π2k2me4/hc3 と求まる。
※この前提は、電子が「原子核が作る電磁場」の中に束縛されて円運動しているときに、よくあてまる。
〈2〉原則として、(電子に対して働く力は)「静電気力<遠心力」となっており、電子は、本来、常に、内側へ内側へと遷移して行こうとする傾向を持つ。 (それは、「K<−U/2」と等価である。 K:運動エネルギー U:ポテンシャルエネルギー)
〈3〉光子はエネルギーを持ち去らず、「力学的エネルギー(E=K+U)」のみが保存する。
※このことは、例えば、楕円軌道(p軌道、d軌道)の場合に、運動エネルギー順位Kn=2π2k2me4/n2h2が変化して光子を放出したとしても、
問題がないことを意味する。
|
これらの前提から、 『hν=Km−Kn(n>m)』(Kn 、Km : 電子の運動エネルギー順位)の式について、「光子は、運動エネルギー順位Knの変化(電子の加速)に伴って、(エネルギー非保存の所産として)生じる」という説明(解釈)が可能になる。
そして、電磁場のポテンシャルエネルギー順位Un[J]を交えて、次のように説明(解釈)できる。
光子がhν[J]のエネルギーが持ち去ることはない。
したがって、もし電子が電磁場のポテンシャルエネルギー順位が、Un[J]からUm[J]へと変化する場合、電子は、Un−Um[J]の電磁場のポテンシャルエネルギーを利用することによって、力学的エネルギー保存則にしたがって、電子の運動エネルギーが、そのまま、Un−Um[J]だけ増加する。
この運動エネルギーの増加分、すなわち、運動エネルギー順位が、Kn[J]からKm[J]へと変化する場合の運動エネルギーの増加分(Km−Kn)[J]は、E=Kn+Un[J](E[J]は一定)により、 (Km−Kn)=(Un−Um)となるのである。
よって、『hν=Km−Kn(n>m)』の式は、『hν=Km−Kn(n>m)=(Un−Um)(n>m)』という意味を持つことになる。
(それは、ボーアの原子模型では、『hν=En−Em(n>m)』の式が、『hν=En−Em(n>m)=Km−Kn(n>m)=(Un−Um)/2(n>m)』という意味を持っていたことと対照的である。(1/2倍の違いがある))
|
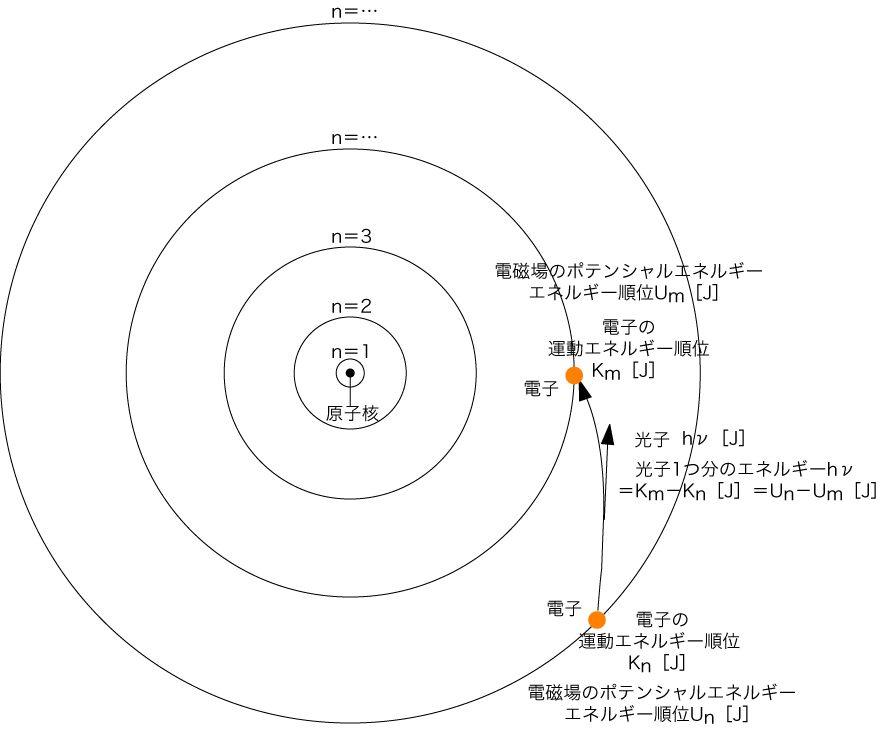 |
※内側の電子ほど、大きな運動エネルギー順位を持つので、Km−Kn>0 となる。
(電子に対して働く力が)「静電気力>遠心力」であるという前提なので、「どのようなしくみで、電子の運動エネルギー順位が変わるのか」も説明できる。すなわち、電磁場のポテンシャルエネルギーを利用して電子が加速することによって、運動エネルギー順位が変わるのであり、その際の、電子の加速運動によって、仮想光子が剥ぎ取られる結果、(エネルギー非保存の所産として)光子が放出されると説明できるのである。
※「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」の場合、(電磁場のポテンシャルエネルギーは、Un=定数−ke2/rn[J]の形を取ることから)電子の円軌道の半径rは、「rn=n2h2/2π2kme2[m]」のように量子化されていることがわかる。この値は、ボーアの原子模型のときの2倍である。したがって、図の同心円のサイズは、ボーアの原子模型のときの2倍となっている。
これにより、『ボーアの原子模型では、(Un−Um)/2[J]が、光子のエネルギーhν[J]に相当するのに対し、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」は、(Un−Um)[J]が、光子のエネルギーhν[J]に相当する』というように、つじつまが合う。
(このように電子の円軌道の半径rがボーアの原子模型のときの2倍となっていることに問題は生じないだろうか?
1つは、「ボーア半径」は、そもそも単なる理論的な計算値に過ぎず、観測値ではなかったので、このように2倍になっても問題は生じないと思われる。
そして、問題がないどころか、逆に、「ボーア半径」が「水素原子のファンデルワールス半径」の1/2に過ぎないという問題の解消を助けているように思われる。すなわち、(理論計算から導かれた)「ボーア半径」(ボーアの原子模型でn=1の場合における、水素の原子の半径≒0.53Å)の2倍(≒1.06Å)は、(観測&計算から導かれた)水素原子のファンデルワールス半径(≒1.2Å)に近いという意味において、より自然(nature)と調和しているように思われる。 詳細な検討は、今後の課題である)
※図のように、電子が軌道を変える際の「接線方向」へ、光子が放射されると考えられる。
それは、放射光や電磁放射についての下記の記述と調和していると思われる。
(放射光について)『この光は、ほぼ光速で走る高エネルギーの電子が円運動や蛇行運動をするときに、その接線方向に放出するもので』(p.1 渡辺誠・佐藤繁編 東北大学出版会 下線は、筆者による)
|
|
(電磁放射について)『エネルギーは、それを生じさせるもとである加速度に垂直な方向に一番強く放射される』(p.95 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─』(Eugene Hecht著、尾崎義治・朝倉利光訳 丸善株式会社)
|
|
詳細な検討は、今後の課題である。
※ある円軌道から、その内側の円軌道に移動する場合、「楕円軌道とはならないのはなぜか?」という疑問がわく。
それは、重力波のときと同様に考えることができる。すなわち、その獲得した運動エネルギー(Km−Kn)=(Un−Um)[J]が、新たな質量となり、(電子の静止質量エネルギーが生む重力場よりはるかに大きい)新たな重力場を生じるおかげで、円軌道を保つと考えることができる。つまり、静電気力と重力の両方が働くおかげで、楕円軌道とはならずに、円軌道を保つと考えられるのである。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」の前提により、原則として(電子に働く力について)「静電気力」>「電子の遠心力」であるので、原子の中の電子は、より内側の殻へ内側の殻へと落ちていきやすい傾向を持つことになる。
この「電子が、原則として、より内側の殻へと落ちていきやすい傾向」があるからこそ、「電子が最内殻から順にうまっていく傾向」が生まれるのであり、実在するような(より原子番号の大きな)様々な原子が、安定的に創発できると考えられる。
なお、それでも、完全に落ちていかないのは、パウリの排他律をはじめ、ほかの理由があるからである。(→結果3、4 電子の波動性が生じるしくみ)。
“原則として”とあるのは、もし、電子にエネルギーが加えられた場合(例えば、水素原子が加熱された場合)は、(電子に働く力について)「静電気力」<「電子の遠心力」となりうるからである。 その場合は、電子は楕円軌道をとると考えられる。(その楕円軌道に相当するものがp軌道やd軌道である。なお、円軌道に相当するものがs軌道である)
このようにして楕円軌道をとる場合、運動エネルギー順位Knの変動を伴う加速運動によって、光子が放出されることなると考えられる。
しかし、「たとえ運動エネルギー順位Knが変化して、電子から光子が放出されたとしても、その光子は、エネルギーを持ち去らない(エネルギー非保存の所産である)」ので問題ないと考えられる。
|
円運動の場合
|
楕円運動の場合
|
|
(たとえ円運動に伴って加速していても)
運動エネルギー順位Knが増加していないので、
電子から光子が放出されることはない。
(前提〈1〉)
|
運動エネルギー順位Knの増加が生じるので、
電子から光子が放出されても、その光子は
エネルギーを持ち去らないので問題ない。
(前提〈3〉)
|
すなわち、例えば、(加熱された)水素原子の中で電子が、3p軌道、3d軌道とっている場合、たとえ光子を放出していても安定的に存在できることになると考えられるのである。
そして、それらの光子は、まさに、水素原子のスペクトルの一部として観測されると考えられる。
以上より、次の結論に至る。
結論1.12 「光子がエネルギーを持ち去らない」という前提でも、「原子のスペクトル」や「原子が安定に存在すること」を説明できる。
単に「原子のスペクトル」や「原子が安定に存在すること」を説明できるだけではない。
「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」には、他にも、いくつかのメリットがある。 整理すると次のようになる。
|
〈1〉ボーアの原子模型が持っている、あいまいさや奇妙さの一部を解消できる。
例えば、(電子に対して働く力が)「静電気力=遠心力」であるという条件の中で、「どのようなしくみで、エネルギー順位が変わるのか」、「光子が、どのようなしくみで放出されるのか」がはっきりしないこと、すなわち、「光子の放出」と「エネルギー順位を変えること」のどちらが原因で、どちらが結果なのかがはっきりしないことを解消できる。
すなわち、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」によれば──
原則として(電子に働く力について)「静電気力」>「電子の遠心力」
→電磁場のポテンシャルエネルギーを利用した電子の加速(「運動エネルギー順位の上昇」)
→「その電子の加速に応じた一部(特定の振動数の)の仮想光子の剥ぎ取り」
→「(特定の振動数の)光子の放出」
のように 「光子が放出されるしくみ」が、比較的はっきりと説明できる。
つまり、少なくとも、次のような記述が示しているボーアの原子模型の奇妙さを解消できる。
『ボーアは、電子の量子飛躍には、非常に奇妙な性質があることに気づいた。飛躍している時の電子の所在については、何も言えないということだ。軌道間の飛躍──エネルギー順位間の遷移──は、瞬間的に起こらなければならない。さもないと、軌道から軌道へ移動する間に、電子はエネルギーを放出してしまうからだ。ボーアの原子の内部では、電子は軌道と軌道のあいだの空間には存在することができない。電子はまるで魔法のように、ある軌道上から消えた瞬間、別の軌道に姿を表すのだ』(p.146 『量子革命』 下線は、筆者による)
|
〈2〉統合性が高まる。
原子核の中の電子のみならず、原子核の外にある自由電子にも応用できる。
すなわち、「原子による光放射」のみならず、電磁波の「加速される電荷による放射(シンクロトロン放射…)」の説明を含めて、応用範囲が広い。
このことは、原子核にとらわれていても、いなくても(自由粒子であっても)、電子は、ある程度“運動エネルギー順位Kn[J]”を持ち続けていることを示唆しているように思われる。(ある程度、光速に近づくと“運動エネルギー順位Kn[J]”を失うと考えられる。詳細な検討は、今後の課題である)
※なお、「仮想光子の剥ぎ取り」に注目すれば、より広い範囲を統合的に説明できる。
電磁波(光子の総和として創発)が放出されるしくみとして、少なくとも次のものがあるのだった。
|
1.『加速される電荷による放射(シンクロトロン放射…)』
2.『電気双極子放射』
3.『原子による光放射』
(参考 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─』(Eugene Hecht著、尾崎義治・朝倉利光訳 丸善株式会社)
の電磁放射についてのページ(p92-103))
|
1.『加速される電荷による放射(シンクロトロン放射…)』と、3.『原子による光放射』は、ともに、「“電荷の加速”(例えば“電子の運動エネルギー順位Kn[J]の上昇”)に伴う仮想光子の剥ぎ取りによる、電磁波(光子の総和)が放出」として説明できる。
そして、2.『電気双極子放射』についても、結局は、「仮想光子の剥ぎ取り」で説明できる。 (→《電気双極子の振動に伴う放射について》)
つまり、これら3つすべては、「仮想光子の剥ぎ取り」によって説明できることになる。
なお、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」における「電子の加速運動によって放出され電磁波(光子の総和)は、エネルギーを持ち去らない」という説明は、「質量の加速運動によって放出される重力波(重力子の総和)がエネルギーを持ち去らない」という説明と統合できるものである。
〈3〉自然(nature)との調和性が高まる。
「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」における水素原子の半径は、ボーア半径の2倍であることは、(観測&計算から導かれた)水素原子のファンデルワールス半径(≒1.2Å)により近いという意味において、より自然(nature)と調和していることを示しているように思われる。(詳細な検討は、今後の課題である)
|
このように、“電子の運動エネルギー順位Kn[J]”を主役に据えて「電荷の加速に伴って光子が放出される(仮想光子が剥ぎ取られる)」「光子はエネルギーを持ち去らない(光子はエネルギー非保存の所産である)」と考える「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」には、大きな矛盾がないだけでなく── 例えば、『「静電気力」>「遠心力」により、電子は、最内殻から順にうまっていく傾向があること説明できる』というメリットや、統合性や一貫性が高い(重力波、仮想光子… と調和している)ことを含め、様々なメリットがある。
ボーアの原子模型(従来の物理学)と「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」を比較整理すると次のようになる。
|
ボーアの原子模型
(従来の物理学)
|
「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の原子模型」
|
|
原子のスペクトルにおける
“光子によるエネルギーの持ち去り”
|
ある
|
ない
|
|
光子のエネルギーを含めた
エネルギー
|
保存する
(ゆえに、E(=K+U)+hν[J]が保存する)
|
保存しない
( 光子は、エネルギーを持ち去らない)
|
|
電子の力学的エネルギー
(運動エネルギーK[J]
+電磁場のポテンシャルエネルギーU[J])
|
保存しない
( 光子が、エネルギーを持ち去ってしまう)
|
保存する
(E=K+U[J]が保存する。
ゆえに、ΔK=−ΔU[J])
|
|
光子の解釈
|
『この光子は、電子の全エネルギー順位En[J]の低下分
に相当する“エネルギーを持ち去る”』
|
『この光子は、電子の加速運動(運動エネルギー順位Kn[J]の上昇)に伴う
「剥ぎ取られた仮想光子」である』
仮想光子がエネルギー非保存の所産である以上
この光子はエネルギーを持ち去らない
|
|
(電子に働く)
静電気力と遠心力の関係
|
常に、静電気力=遠心力
(ゆえに、ke2/r2=mv2/r[N]より、−U/2=K[J])
|
原則として
静電気力>遠心力
(ke2/r2[N]>mv2/r[N])
電子にエネルギーが加えられると
「静電気力」<「遠心力」ともなりうる。
→その結果、楕円軌道も生じうる。
|
|
「電子が、より内側の殻へと
落ちていきやすい傾向」
「電子が、最内殻から順に
うまっていく傾向」
|
説明できない
|
説明できる
|
|
中心に据えるもの
|
電子の「エネルギー順位」
(電子の力学的エネルギーE=K+U[J])
En=−2π2k2me4/h2・1/n2[J]
|
電子の「運動エネルギー順位」
Kn=2π2k2me4/h2・1/n2[J]
|
|
根拠となる数式
|
hν=En−Em(n>m)=Km−Kn(n>m)[J]
=Un/2−Um/2(n>m)[J]
(Kn=2π2k2me4/h2・1/n2[J])
(Un=−4π2k2me4/h2・1/n2[J])
(Kn=−Un/2[J])
|
hν=Km−Kn(n>m)[J]
=Un−Um(n>m)[J]
(Kn=2π2k2me4/h2・1/n2)[J]
(Un=−2π2k2me4/h2・1/n2[J])
(Kn=E−Un[J])
|
|
半径rn[m]
|
rn=h2n2/4π2kme2[m]
|
rn=h2n2/2π2kme2[m]
|
|
水素原子の半径[m]
|
ボーア半径(≒0.53Å[m])
|
ボーア半径の2倍(≒1.06Å[m])
※水素原子のファンデルワールス半径は、1.2Å[m]
|
|
光子が放出される
しくみ(原因)
|
電子の「エネルギー順位」が変化する原因は、
あいまい。
|
電子の「運動エネルギー順位 Kn」の上昇
(by電磁場のポテンシャルエネルギー)
|
|
リュードベリー定数R
|
ともに、導出できる
|
|
統合性、一貫性
|
低い
|
高い
(放射光を含め)一般に、“電荷の加速”に伴って
光子が放出されることと統合できる
仮想光子や重力子がエネルギー非保存の所産であること
(エネルギーを持ち去らないこと)と統合できる
|
※「“電荷の運動エネルギー順位の上昇”に伴う“電荷の加速”」によって光子の放出(「仮想光子の剥ぎ取り」)が起こるように、「“電荷の運動エネルギー順位の低下”に伴う“電荷の減速”」によって、光子の放出(「仮想光子の剥ぎ取り」)は起こらないのだろうか? 仮に起こったとしても観測と矛盾していないという可能性はないだろうか? (あるいは、もし起こらないとすれば、加速する時だけ「仮想光子の剥ぎ取り」が起きるのは、どのようなしくみによるのだろうか?) 詳細な検討は、今後の課題である。
また、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型」の前提は、「光子の吸収」について次のように説明する。 ただし、課題も多いようである。
『(仮想光子は電子に再吸収されるが、いったん剥ぎ取られて生じた、ふつうの)光子は、本来、電子と完全弾性衝突するだけである。
光子との衝突は、ときに(内側の軌道を進んでいた)電子を外側の軌道へと変化させる。その際、電子は、蓄えられる電磁場のポテンシャルエネルギー順位Umを上げると同時に、減速して運動エネルギー順位Kmを下げる。「電子の力学的エネルギーE(=Km+Um)は保存される(一定となる)」からである。この過程で、光子は電子の軌道を変化させることしかしていない。この過程では、光子は、エネルギーを与えていない(減らしていない)ので、同じエネルギーhν[J]を持ったまま、飛び去るであろう。つまり、この過程では、「光子の吸収」は存在していない。
外側の軌道に移った電子は、ふつう、その後、速やかに、hν[J]のエネルギーを持つ光子を放出しながら(自然放出しながら)内側の軌道に戻ってくる。(この光子は、エネルギー非保存の所産であり、やはり、エネルギーを持ち去っていない)
(以上だけなら、ここで起きている現象は、トータルで見ると「誘導放出」と似たような現象であることになる。本来、「誘導放出」は、外側に軌道にある電子に、光子が衝突して、新たに1つの光子が放出される現象であるが、ここでは、逆に、内側の軌道にある電子に光子が衝突して、新たに1つの光子が放出されている。
ただし、もし、“電荷の減速”によっても光子が放出されるのならば、内側の軌道にある電子に光子が衝突することによって、新たに2つの光子が放出さることになる。 そのようなことはありうるのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である)
電子と光子との衝突は、ときに、光子のエネルギーを失わせ(光子の振動数を減らし)、電子の運動エネルギーを増加させる。これが、コンプトン効果である。(→《コンプトン効果について》)この過程では、光子のエネルギーの一部が、電子に吸収されたと見なすことができる。
もし、光子のエネルギーhν[J]の値が十分大きければ、電子は、原子核の束縛を完全に逃れ、外に飛び出すであろう。
まさに、その現象が、「Kmax=hν−W」の式で示される“光電効果”に相当すると考えられる。
一方、原子吸光分析は、「(その振動数の)光子が吸収された」ことを観測していると言うよりも、「(その振動数の)光子だけが散乱されてしまった(or一部のエネルギーを失ってしまった)」ことをを観測していると言う方が正確なように思われる。(詳細な検討は、今後の課題である)』
|
《コンプトン効果について》
光子と電子が衝突する過程は、「光電効果」や 「コンプトン効果」を支える。
この光子と電子が衝突する過程ついて、コンプトン効果を例にして、下で説明する。
コンプトン効果とは、『X線を物体に照射したとき、散乱X線の波長が入射X線の波長より長くなる現象』のことである。
(参考、ウィキペディア 『コンプトン効果』)
波長の変化Δλは、『 Δλ=λ'−λ=(h/mec)×(1−cosφ)』の数式で示される。
(λ' : 長くなった波長、λ:入射X線の波長 φ:散乱される方向を示す角度)
この『コンプトン効果』を説明する数式は、光子を粒子とみなし、エネルギー保存則と運動量保存則を用いて導かれている。
そして、この数式は、実験結果と合致する。
ここで、「光子の運動量の実体は、何か?」について、次の仮説を立てた。
仮説1.12 光子の運動量の実体は、下図のような光子を構成する素スピノールの“転回に伴う円に近い軌道運動”である。
※1つの“ヒッグス場ユニットの中の素スピノール”に注目して、その素スピノールの転回に伴う“円に近い軌道運動”を、拡大して(強調して)図示している。
※光子の進行方向が正とすると、素スピノールが、180度転回した瞬間が、転回に伴う運動量が最大になり──
素スピノールが、転回を始める寸前(0度の転回時に相当)と、転回を終えた瞬間(360度の転回時に相当)が、転回に伴う運動量pが最小になる。
※この描像によって、「ふつうの電磁波を構成する光子のみが、光電効果やコンプトン効果を引き起こし、仮想光子は、引き起こさない」ことが自然に説明できる。
※共転回している間、2つの原始ヒッグス場ユニットにまたがっている光子の運動量の合計は、常に一定となる。 |
この仮説によると、光子の運動量とは、次のように、とびとびに伝わって行くものであることになる。
この「光子の運動量」の描像をふまえて、コンプトン効果についての次の記述を読んでみる。
|
『1923年にコンプトンは(A.H.Compton)は、物質によって散乱されたX線には、入射波と同じ波長λのもののほかに、λより長い波長λ'をもつものがあることを発見した』
(p.6 『基礎物理シリーズ5 量子力学』 原康夫 岩波書店 下線は筆者による)
|
この記述からもわかるように、コンプトンによる実験結果を示す図を見ると── 確かに 観測される散乱X線には、「入射波と同じ波長を持つもの」と、「波長がのびたもの」の2種類の山があることがわかる。
「入射波と同じ波長を持つもの」の山の方は、鏡の反射と同じで、同じ波長の光子が反射(→下記《光の反射と屈折》)したと説明できる。
もう一方の、「波長がのびたもの」は、光子と電子が衝突して、光子の波長が伸びたと説明できる。
光子(光子を構成する素スピノール1つ)と電子(厳密には電子を構成する素スピノール1つ?(詳細な検討は、今後の課題である))が衝突することによって互いに運動量を変化させる瞬間に移動できる範囲では(原始ヒッグス場ユニット(PHU)よりも小さい移動範囲では)“時空が連続である”ので、ネーターの定理により、衝突の前後で、運動量保存則もエネルギー保存則も成立すると考えられる。
したがって、運動量保存則により、運動量h/λの光子が、静止した電子に衝突したとすると、次の式が成立する。
「h/λ'cosφ+mv cosθ=h/λ h/λ' sinφ=mv sinθ」 …(1) となる。
(新たな電子の運動量:mv、放出された光子の運動量:h/λ')
一方、エネルギー保存則より、「hν=Ke+hν'」 …(2) が成立する。
(1)と(2)より、コンプトン効果を意味する数式、『 Δλ=λ'−λ=(h/mec)×(1−cosφ)』を導くことができる。
光電効果において光子と電子が衝突する際も、同様なしくみが成立していると考えられる。
《熱放射について》
熱放射とは、3種類の「熱移動」の中の1つである。
「熱移動」によって、温度が変化する。
そもそも、温度の実体を担うものは、「粒子(分子、原子…)の運動エネルギー」であった。
この温度(その実体は「粒子(分子、原子…)の運動エネルギー」)が、『1.熱伝導 2.対流』という「熱移動」によって変化することについては、比較的容易に理解(イメージ)できる。
『3.放射熱』という「熱移動」によって、温度(その実体は「粒子(分子、原子…)の運動エネルギー」)が変化するとはどういうことなのだろうか?
これまでの説明は、次のようなものであった。
|
『物体が電磁波の形でエネルギーを放出したり吸収したりする現象を一般に放射(または、ふく射、radiation)といい、特にこれが物体の温度だけで定まるものを熱放射(または、熱ふく射、thermal radiation)という。その温度に応じて物体が放射線を放出する際には、物体の内部エネルギーが放射のエネルギーに変換され、一方、放射線が物体に入射して吸収されると、放射のエネルギーは物体の内部エネルギーに変換される。したがって、熱放射は結果的に熱エネルギーの移動とみなしてよい。熱放射の波長範囲は、赤外部および可視部と紫外部の一部を含む0.1〜100μmである』
(『伝熱学の基礎』 吉田峻 理工学者 p.125 下線は、筆者による)
|
※ここに、温度(=「分子の運動エネルギーの平均」)と、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)が全く異なる実体であるのに関わらず、熱放射という「熱移動」が成立するしくみが説明されている。
|
すなわち、これまでは、『物体が持っている温度(その実体は「粒子(分子、原子…)の運動エネルギー」)の一部が、熱放射のエネルギーに変換されて持ち去られて、その熱放射のエネルギーが、他の物体に供給される際に、新たな温度(その実体は「粒子(分子、原子…)の運動エネルギー」)の一部に変換される』ことによって、「熱移動」が成立すると考えられて来たのである。
つまり、以上の熱放射による「熱移動」の説明は、『熱放射が、エネルギーを持ち去ること』と『熱放射が、エネルギーを供給すること』の両方を前提とするものなのである。
そして、『熱放射が、エネルギーを持ち去る』と考えられた根拠は、「光子のエネルギーを含めて、エネルギー保存則が成立する(時空は連続である)」という前提であったと考えるのが自然であろう。
※なお、次の数値計算も、『熱放射がエネルギーを持ち去るはずだ』、「光子のエネルギーを含めて、エネルギー保存則が成立する(時空は連続である)」という前提にもとづくものに過ぎなかったことになる。
『(4)放射伝熱
T 1およびT 2 : 高温物体の表面および低温物体の表面の絶対温度[K]
面A 1およびA 2 : 高温物体および低温物体の表面積[m 4] とすると、 放射によって高温物体から低温物に単位時間あたりに伝わる正味の熱量Qは次式で表される。
Q=σΦ12[T14−T24]A1= σΦ21[T14−T24]A2 [W] (1・7)
ここに、 σ=5.67×10-8W/(m2・K4): ステファン・ボルツマン定数
Φ12、Φ21 : 物体表面の性状と系の形状によって決まる定数 』
(『伝熱学の基礎』 吉田峻 理工学者 p.5 下線は、筆者による)
|
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)おいても、熱放射はエネルギーを供給する。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において、熱放射は、電磁波(光子の総和)の一種(0.1〜100μmの波長の電磁波)である以上、エネルギーを持ち去らないはずである。その根拠は、「光子はエネルギー非保存の所産である(時空は不連続である)」という前提である。
ここには、既存の物理学と、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)との、決定的な違いがある。
整理すると次のようになる。
|
これまでの物理学
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
熱放射によるエネルギーの供給
|
○
|
○
|
|
熱放射によるエネルギーの持ち去り
|
○
|
×
|
|
時空
|
連続である
|
不連続である
|
|
光子を含めたエネルギー保存則
|
成り立つ
|
成り立たない
|
|
※そもそも、『熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)がエネルギーを持ち去るはずだ』という考えが生まれた理由は、「光子のエネルギーを含めて、エネルギー保存則が成立する」(「時空は連続である」)という前提があったからに過ぎないと考えられる。なぜなら、100%の真空が存在しない(人工的に作り出せない)以上、そのことを証明できないからである。(→下記にて詳しく説明する)
※なお、アインシュタインは、「重力波のエネルギーを含めて、エネルギー保存則が成立する」という前提を持っていたからこそ、物体の熱運動によって放出される重力波がエネルギーを持ち去るはずだと考えた。 そして、まさに、この考えに、『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』ほどの大きな問題が内在していることに、アインシュタイン自身が気づいたのだった。
このことは、「光子のエネルギーを含めて、エネルギー保存則が成立する(時空は連続である」)という前提を根拠にして、安易に『熱放射(電磁波の一種)がエネルギーを持ち去るはずだ』と考えてはいけないことを示唆しているように思われる。
※そもそも、熱運動が、エネルギー非保存の所産として、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)を生み出し続けることは、次のように説明できる。
次の記述から、熱放射において、「最外殻電子の軌道運動」の変化が最も重要であることがわかる。
『原子の集団を考えた場合、低温では多くの原子は基底状態にあるが、徐々に温度が高くなると、原子間の衝突によって徐々により多くの原子が励起状態になっていく。このような機構は、比較的穏やかな励起と分類され、グロー放電、炎、火花などで生じ、最も外側にある対になっていない価電子のみにエネルギーを与える。可視光とその近くの赤外線や紫外線の光の放出をもたらす、このような外側の電子の推移に、まずは注目していこう』
(p101 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』 下線は、筆者による) |
|
そして、さらに、次の記述は、固体(例えば、黒体)を構成する、原子や分子の熱運動に伴うランダムな衝突が、広い周波数範囲での熱放射を生んでいることがわかる。
『一つの原子、あるいは原子間にほとんど相互作用のない低圧ガスからの放出光のスペクトルは、何本かの鋭い線、すなわち、原子に固有の周波数特性でできている。もっとも、原子の運動や衝突などからの放射による、ある程度の周波数広がりは常にあり、各線は、厳密には単色ではない。しかし一般に、一つのレベルから他のレベルへの原子の遷移は、明確な狭い周波数範囲の光放出で特徴づけられる。一方、原子どうしが互いに相互作用している固体や液体からの放射光スペクトルは、広い周波数帯になっている。二つの原子が接近すると、互いに影響し合って、それぞれがもっている離散的なエネルギーが少しずつ変化する。固体中では、互いに相互作用している多数の原子は、膨大な数の変化したレベルを生み出し、実効的にもとのレベルを広げて連続的な帯構造を生成する。このような性質を持つ物質は、広い周波数範囲で放出・吸収を行う』
(p103 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』 下線は、筆者による) |
|
熱運動、すなわち、原子や分子どうしがランダムに衝突(相互作用)することによって、「最外殻電子の軌道運動」も、ランダムに逸脱する(外側の軌道に一時的にランダムに移る)だろう。 なぜなら、定常状態に至る必要がないからである(なお、原子模型において、スペクトルが飛び飛びとなるのは、定常状態となることを前提としているからこそのものであった)。 そして、ランダムに逸脱した(外側の軌道に一時的に移った)「最外殻電子の軌道運動」が、速やかに、元の基底状態に戻ることの総和が、広い周波数での熱放射、すなわち、「0.1〜100μmの波長の電磁波」を生じると考えられる。
なお、このランダムな衝突の際には、エネルギーを吸収することも、消失することもない。すなわち、ランダムな衝突にともなって「最外殻電子の軌道運動」も、ランダムに逸脱する(外側の軌道に一時的にランダムに移る)際は、力学的エネルギー(運動エネルギーK+ポテンシャルエネルギーU)が保存したままである。
そして、すみやかに基底状態に戻る際に放出する光子は、Km−Kn=hνに従う、エネルギー非保存の所産である。
したがって、熱運動にともなって、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)が生み出されるすべての過程で、力学的エネルギー(運動エネルギーK+ポテンシャルエネルギーU)が保存したままとなっていることになる。
このようにして、熱運動は、エネルギー非保存の所産として、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)を生み出し続けるのである。
|
例えば、「太陽光によって、地球の温度が上がり続けないこと」や「放射冷却と呼ばれた現象」は、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」という前提でも、説明できるであろうか?
できる。 それを以下に示す。
まず、「太陽光によって、地球の温度が上がり続けないこと」を中心に考えていく。
地球は、太陽から放出される熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)の形でエネルギーが供給されることによって、温まる(温度が上がる)。
太陽から、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)としてエネルギーを供給される続けている中で、地球の温度が、ある一定の温度に保たれているのは、(太陽からの熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)としてエネルギーを供給される続けることによる)『地球の温度を上げる効果』と、何らかのしくみによる『地球の温度を下げる効果』が釣り合っているからに他ならない。
これまでは、『地球の温度を下げる効果』は、まさに、地球から放出される熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)がエネルギーを持ち去ることによってもたらされると説明されてきた。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、地球から放出される熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らないので、『地球の温度を下げる効果』をもたらさないのであった。
それなのに、地球の温度が、ある一定の温度に保たれているのは、『地球の温度を下げる効果』をもたらす、他のしくみがあるからに他ならない。
それは、具体的にどんなしくみだろうか?
|
これまでの物理学
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
温度の上昇
|
熱放射によるエネルギーの供給
|
熱放射によるエネルギーの供給
|
|
温度の低下
|
熱放射によるエネルギーの持ち去り
|
?
|
温度を低下させるしくみとして考えられるものには、少なくとも、次の3つがある。
1.100%真空が実在していないので、物体の周囲の空気(分子)の熱伝導&対流によって、エネルギーが持ち去られ続けている。
2. 太陽から供給されるエネルギーの一部が、光合成や太陽光発電によって蓄えられる化学エネルギー、雲や風や海流として蓄えられる運動エネルギーや重力ポテンシャルエネルギーに変換される。
3.ある(外部)運動エネルギーと負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、その運動エネルギーを減少させるような仕事)のペアとして、互いに消滅してしまう。
1.100%真空が実在していないので、物体の周囲の空気(分子)の熱伝導&対流によって、エネルギーが持ち去られ続けている。
実は、少なくとも地球上に100%完全な真空は実在しない。
そして、現在(2017年4月)、100%完全な真空を作り出す技術もない。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wilipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
このことは、“熱放射によるエネルギーの持ち去り”による温度の低下現象は、これまで、証明されてこなかったことを意味する。
すなわち、「地球上にも、銀河と銀河の間にも、100%の真空が存在しないこと」、そして、「これまで100%完全な真空を作り出せていないこと」は── これまで“熱放射がエネルギーを持ち去ること”は、実際には、決して証明されてこなかったことを意味するのである。
したがって、次のような数式による説明も
『(4)放射伝熱
T 1およびT 2 : 高温物体の表面および低温物体の表面の絶対温度[K]
面A 1およびA 2 : 高温物体および低温物体の表面積[m 4] とすると、 放射によって高温物体から低温物に単位時間あたりに伝わる正味の熱量Qは次式で表される。
Q=σΦ12[T14−T24]A1= σΦ21[T14−T24]A2 [W] (1・7)
ここに、 σ=5.67×10-8W/(m2・K4): ステファン・ボルツマン定数
Φ12、Φ21 : 物体表面の性状と系の形状によって決まる定数 』
(『伝熱学の基礎』 吉田峻 理工学者 p.5 下線は、筆者による)
|
“熱放射によるエネルギーの持ち去り”による放射冷却の説明も、証明されたもの(確定したもの)ではないのである。
なぜなら、温度の低下は、すべて、物体の周囲の空気(分子)の熱伝導&対流によって、宇宙空間に熱が持ち去られてきた結果であると説明できるからである。
つまり、100%完全な真空が実在しないということは、「熱放射によって持ち去られたと考えられた熱エネルギー」は、物体の周囲の空気の分子の衝突(熱伝導&対流)によって、持ち去られているいると説明できることを意味しているのである。
この説明は、そもそも、温度の正体が「分子の運動エネルギーの平均」であることとも調和している。
例えば、地球の周囲は、100%完全な真空ではなく、空気(分子)に満たされ続けている。
※地球は、少なくとも地上三万キロメートルまで「大気」で覆われていることは次の記述からわかる。
『大気 地球表面に密着し、地球と共に回転している気体の総称。大気の上限はせいぜい三万キロで、対流圏(約10キロ)、成層圏(約50キロ)、中間圏(約80キロ)、熱圏(約600キロ)、外気圏(約700キロ以上)に分類される』
(『Imidas1992』 p686) |
|
高度
|
気温
|
|
外気圏
|
約700km以上
|
-
|
|
熱圏
|
約600km
|
『1000℃になることもある』
|
|
中間圏
|
約80km
|
『氷点下90℃』
|
|
成層圏
|
約50km
|
『上空に行くほど高温になる』
|
|
対流圏
|
約10km
|
『高度100mごとに0.65℃下がる』
|
| ※気温については、『地球を殺そうとしている私たち』 ティム・フラナリー著 椿正春訳 ヴィレッジブックス (『We Are The Wether Makers』の翻訳書)を参考にした。 |
そして、銀河と銀河の間にさえも気体分子が存在する以上、大気の外にも気体分子が存在していることになるので、熱伝導&対流によって地球の外へと熱エネルギーを移動させることで、地球の温度を下げることが可能であることがわかる。
つまり、周囲の空気の分子の衝突(熱伝導&対流)によって地球はエネルギーの一部を失い続ける結果、地球の温度が下がる効果が生まれるので、太陽から放出される熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)によって、エネルギーを供給され続けている中で、地球の温度が上がり続けないと説明できるのである。
※「温室効果」という言葉があるけれども、地球の周囲に、たとえ雲や二酸化炭素の層が存在していたとしも、決して、本当の温室のようにガラスやビニールによって完全に空気の出入りが遮断されているわけではない。 したがって、(秒速30kmで公転運動をし続けている)地球からは、熱伝導や対流によって、熱を外部へ排出し続けることが可能なのである。
日なたで(窓を閉めっぱなしの)温室や車中の温度が、外気温よりも非常に高くなるのはなぜか? 日なたでいったん外気温よりも高くなった(窓を閉めっぱなしの)温室や車中の温度が、日陰に入ったとしても、その高温を長時間維持するのはなぜか? それは、ガラスやビニールによって空気の流れが遮断されているからに他ならない(熱放射によって、より高い運動エネルギーを持つようになった気体分子が閉じ込められ続けているからである)。 その証拠に、ドアや窓を全開すれば、速やかに気温は、外気温とぼぼ等しくなる。
なお、より大きな運動エネルギーを持つようになった気体分子から放出される熱放射が本当に、エネルギーを持ち去るのであれば、そもそも、(窓を閉めっぱなしの)温室や車内が、外気温よりも非常に高温になる理由が説明しにくくなると思われる。なぜなら、その熱放射が、ビニールやガラスを通り抜けて外へ移動し続けてしまうはずであり、それは、外気温が成立する条件とほぼ同じ条件になるはずだからである。
放射冷却についても、基本的に同様に説明できる。
《放射冷却》
放射冷却については、これまでは、例えば、次のように説明されてきた。
『地表面や大気が長波放射(赤外放射)によって熱を失い冷える現象。 また、これによって地表面に接する大気の気温が下がることを放射冷却ということもある。 この放射冷却によって熱を奪われるため地表の温度が上昇し続けることはない。よく晴れた夜間には強く冷えこみ晩霜などが降りやすい』
(『Imidas1992』 p686 下線は、筆者による) |
|
すなわち、これまでは、放射冷却は、『長波放射(赤外放射)』によるエネルギーの持ち去りによって説明されてきた。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、『長波放射(赤外放射)』といえもども、エネルギーを持ち去らない。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が導く「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)はエネルギーを持ち去らない」という前提は、『地表面や大気が長波放射(赤外放射)によって熱を失い冷える』ことが実在しないことを示している。
それでは、放射冷却で説明されてきた現象そのもの── 『地表面や大気が熱を失い冷える現象』『地表の温度が上昇し続けることはない』『よく晴れた夜間には強く冷えこみ晩霜などが降りやすい』は、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」という前提でどのように説明できるだろうか?
『地表の温度が上昇し続けることはない』や『地表面や大気が熱を失い冷える現象』については、単に、『“地表”から周囲の空気等への“熱伝導”や、周囲の空気の“対流”によって熱が持ち去られていること』が原因であると説明できる。
『よく晴れた夜間には強く冷えこみ晩霜などが降りやすい』については── 『“地表”から周囲の空気等への“熱伝導”や、周囲の空気の“対流”によって熱が持ち去られていること』と『「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)」という形で、雲から地表へ供給されるエネルギーがなくなること』が原因であると説明できる。
なお、冷たい空気ほど重いので地表近くに下がり、暖かい空気ほど軽いので上に上昇すという性質も、放射冷却で説明されてきた現象の説明を助けると思われる。
|
また、「黒体放射」に関する現象についても、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)はエネルギーを持ち去らない」という前提で説明できる。
《黒体放射》
黒体放射は、シュテファン=ボルツマンの法則で説明されてきた。
このシュテファン=ボルツマンの法則(『ある温度Tを持つ黒体は、熱輻射(=熱放射)として、I =ρT 4 [W/m2]のエネルギーを放出する』 (参考『シュテファン=ボルツマンの法則』Wikipedia))は、“熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない”という前提と、ある意味、よく調和している。
すなわち、この場合、この式『I =ρT 4 [W/m2]』は、黒体から、1秒間に、1平方メートルあたり、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)として、放出されるエネルギーに相当する。 (※なお、[W]=[J/s])
“熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない”のであれば、この式の理解は容易である。 1秒後であっても、2秒後であっても、温度が一定である限り、同じ熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーが放出され続けることになる。 もし、(伝導や対流によって)一切温度が変化しなければ、経過時間に比例した分だけ、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)のエネルギーが放出され続けることになる。
※しかし、逆に、“熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)が、エネルギーを持ち去る”という前提は、『I =ρT 4 [W/m2]』の式が、本当のところは、何を意味しているのかの理解を、とても困難にしてしまう。
なぜなら、例えば、「0.1秒経過すると、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)によって、エネルギーが持ち去られる結果、温度が下がる。 0.2秒経過すると、先の0.1秒間の温度の低下に伴って、より小さなエネルギーだけが持ち去られて、より小さな温度だけ下がる。 0.3秒経過すると、先の0.2秒間の温度の低下に伴って、さらに小さなエネルギーだけが持ち去られて、より小さな温度だけ下がる。…」というように、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)によるエネルギーの持ち去りによって温度が下がることに伴い、時間経過とともに「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)のエネルギーの放出量」が減少し、1秒間に放出されるエネルギーである、『I =ρT 4 [W/m2]』が、何を意味しているのかわかならくなってしまうからである。
つまり、本当に“熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)が、エネルギーを持ち去る”のならば── 一定の温度T[K]のまま、1秒が経過することは、不可能であるので(“ある温度Tにおいて(Tのままに)、1秒間に放射される”エネルギー量が、『I =ρT 4 [W/m2]』であるということは、厳密に見れば、ありえないので)、『I =ρT 4 [W/m2]』という数式が、意味不明なものになってしまうのである。
少なくとも、このことから、(シュテファン=ボルツマンの法則で説明されてきた)黒体放射についても、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」という前提で説明する方がむしろ自然であることがわかる。
一方、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」が前提として本当に正しければ、100%完全な真空中に浮かんでいる高温の物体(∋黒体)は、(たとえ、外部から放射熱を供給され続けていない中で、それ自身が熱放射を続けているのに関わらず)どんなに時間が経過しても、温度が下がらないはずである。(→考察6)
しかし、実際は、現在(2017年4月)、100%の真空を作り出す技術がない以上──
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wilipedia 『真空』 下線は、筆者による)
|
観測された“高温の物体(∋黒体)の温度の低下”の原因は、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)による、エネルギーを持ち去り」であると証明できないのであった。
なぜなら、単に、「高温の物体(∋黒体)から周囲の“空気や支柱等”への“熱伝導”(+周囲の空気の“対流”)による熱の持ち去り」であると説明できてしまうからである。
そのことは、たとえ下記のような数式による計算結果と観測結果が厳密に一致したとしても変わらない。
『黒体面間の放射伝熱
〜
面A 1から面A 2への正味の放射伝熱Qは、式(5・22)を面積A 1およびA 2にわたって積分すれば求まる。 すなわち、
Q=5.67[(T1/100)4−(T2/100)4]A1F12 [W]
〜
なお、再度注意しておくが、放射伝熱の場合には、電磁波の形でエネルギーが移動するので、前章までの熱伝導や対流伝熱とは異なって、高温の面から低温の面へエネルギーが伝えられるだけでなく、低温の面から高温の面へもエネルギーが伝えられる。 そして、上記のように、その正味として高温の面から低温の面へエネルギーが伝えられ、これが、結果的に伝熱量として求められるのである。』
(『伝熱学の基礎』 吉田峻 理工学者 p.130-131 一部省略 下線は、筆者による)
|
なお、本来、熱は高温の物体から低温の物体へ移動するのだった(熱力学の第二法則)。
したがって、計算の途中で、「低温の面から高温の面へとエネルギーが伝えられる過程」をも想定してしまっている上記の説明には、一貫性が欠けており、無理があるように思われる。
また、温度を担う実体とは、「ミクロの粒子(分子、原子…)の運動エネルギー」に他ならず、熱伝導や対流を担うものは、「ミクロの粒子(分子、原子…)の運動エネルギー」の移動そのものであるので、熱伝導や対流は、必ず“熱の持ち去り”を伴うと言える。
一方、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、温度を担う実体である「ミクロの粒子(分子、原子…)の運動エネルギー」とは全く異なる実体であるので、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)が、必ず“熱の持ち去り”を伴うべき理由はないと言える。
このように、熱や温度について一貫性のある説明を維持していくためにも、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)が熱を持ち去らない」という前提の方が、より自然であると思われる。
|
また、太陽の光度の変化(『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきていること』)も、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)はエネルギーを持ち去らない」という前提で説明できる。
|
《太陽の光度の変化(『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきていること』)》
これまでの物理学の常識によれば、次のような説明がなされてきた。
|
『太陽は、中心で水素が燃え、輝いている。中心は高温、高圧状態で、水素の原子核どうし融合する反応が起こるからである。このエネルギーが宇宙空間に放出され、太陽光となる。
地球が誕生し、太陽系が誕生したのは、今から約四十六億年前といわれているが、いまとくらべると、その頃の太陽は燃料である水素が多く、燃えかすであるヘリウムはすくない。しかし太陽が燃え続けていると水素は減り、ヘリウムは増える。ヘリウムの方が重いので、星はつぶれようとするが、水素の燃えかたをよくすることによって温度を上昇させ、より大きい圧力を発生させて、つぶれるのを防いでいる。したがって、時間経過と共に太陽の内部温度はますます上昇していき、太陽の輝き方は時間と共に明るくなっていくことが理論的にも予想されるし、実際に観測からも確かめられている。』
(p.96 『サイエンス・パラダイムの潮流 複雑系の基底を探る』 黒崎政男編 丸善ライブラリー
『第三章 地球誕生のパラダイム 松井孝典』 下線は、筆者による)
|
※この説明は、松井孝典氏個人による説明というよりも、これまでの物理学の常識(「光子を含むエネルギー保存則」)が導いてきた説明であると言うべきものだと思われる。
|
この説明は、「光子のエネルギーを含むエネルギー保存則が成立すること」、「光子がエネルギーを持ち去ること」を前提として導かれた説明である。
なぜなら、この説明の中の『ヘリウムの方が重いので、星はつぶれようとするが、水素の燃えかたをよくすることによって温度を上昇させ、より大きい圧力を発生させて、つぶれるのを防いでいる。』の部分については、(「光子がエネルギーを持ち去らないこと」を前提とする)“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明と決定的に異なるからである。 (なお、その他の部分は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明と同じである)
その部分の説明は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、次のようになる。
『太陽からの熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)がエネルギーを持ち去らないので、(たとえ太陽の周囲にある、ごくわずかな気体分子による熱(エネルギー)の持ち去りがあったとしても)、水素どうしの核融合が進むことによって、ランダムな熱運動に伴うエネルギー(太陽の中の(まだ核融合していない)水素や(核融合の結果生じた)ヘリウムの運動エネルギー)、すなわち、温度が増す一方となる。』
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、太陽からの熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)がエネルギーを持ち去らないので、系の温度が上昇し続けることになり、その結果── 時間と共に、太陽の光度(太陽の温度)は光度が増加し続けると、シンブルに説明できるのである。
もし、太陽からの熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)が、本当にエネルギーを持ち去り続けているのだったら── その分、ランダムな熱運動に伴うエネルギー(太陽の中の(まだ核融合していない)水素や(核融合の結果生じた)ヘリウムの運動エネルギー)が減る一方となり、なおかつ、水素の核融合が進むほどに燃料である水素が消費されて減少しヘリウムという不純物が増えるにつれて、核融合の効率が低下してしまう結果、太陽の光度(太陽の温度)は低下し続けてしまうはずであり、本来は『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきている』という事実が説明しにくくなるはずである。
それでは、これまでの物理学の常識が導いてきた『ヘリウムの方が重いので、星はつぶれようとするが、水素の燃えかたをよくすることによって温度を上昇させ、より大きい圧力を発生させて、つぶれるのを防いでいる。』という説明は、一体、どのように解釈するべきなのだろうか?
これは、「(光子を含む)エネルギー保存則」という、これまでの物理学の常識の1つを守るために非常に無理してひねり出された説明だと思われる。
なぜなら、そもそも、「水素4つ」と「ヘリウム1つ」の重さを比べたら、本来、「水素4つ」の方が重いというのが、物理学のもう1つの常識だからである。
すなわち、「ヘリウムの方が重いので、星はつぶれようとするが」という説明は、(なんとしても)「水素の燃えかたをよくすることによって温度を上昇させ」るという説明を成立させる必要があったために無理してひねり出された言い訳に過ぎないと見なされてもしかたないような、自然(nature)から乖離したものだからである。
こういった苦し紛れの説明が見過ごされてきた理由は、何か?
それは、やはり、「(光子を含む)エネルギー保存則」が成立するはずである(光子がエネルギーが持ち去るはずである)」という前提、すなわち、これまでの物理学の常識の1つを守ることを最優先したこと、これにつきるのではないだろうか?
逆に、「太陽からの熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)がエネルギーを持ち去らない」という前提であれば、(たとえ太陽の周囲にある、ごくわずかな気体分子による熱(エネルギー)の持ち去りがあったとしても)水素どうしの核融合が進んでも、ランダムな熱運動に伴うエネルギー(太陽の中の(まだ核融合していない)水素や(核融合の結果生じた)ヘリウムの運動エネルギー)が増す一方となり、その結果、太陽の光度(太陽の温度)は増加し続けると説明しやすい。
つまり、(水素の)静止質量エネルギー(内部運動エネルギー)の一部が“外部運動エネルギー”に転換されて生じた熱エネルギーが、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)として持ち去られないおかげで(ある程度)蓄積し続ける結果、太陽の光度(太陽の温度)が増すという考えの方が、『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきている』という事実を説明しやすいのである。
したがって、『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきている』という事実は、「光子はエネルギーを持ち去る」という前提ではなく、「光子はエネルギーを持ち去らない」という前提を支持していると解釈できるものなのである。
※なお、太陽からは、熱運動に伴って熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)以外の電磁波や、重力波(重力子の放出数の変化)も放出されていると考えられる。
もし、これらの電磁波や重力波もエネルギーを持ち去っているとしたら、太陽の電荷や質量が猛烈な勢いで減少する等、おかしなことになるはずである。
よって、これらの電磁波や重力波は、エネルギーを持ち去らないと考えられる。
しかし、そうだとすれば、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)だけがエネルギーを持ち去る理由を、説明できなくなってしまうと思われる。
|
※なお、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)がエネルギーを持ち去らない」が正しい前提であるのなら、もし、ある「高温の物体」の周囲を完全に断熱すること、すなわち、100%の真空状態を作出すことが実現できれば、どんなに時間が経過しても温度が下がらないはずである。(→考察6)
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、もし、「ある高温の物体は、100%完全な真空中に、浮かばせた状態」等、“周囲の分子との衝突を100%断った状態”を作ることができるのならば、(熱放射だけによって)温度が低下しないことを予測する。(少なくとも思考実験では、低下しない)
確かに、現在、100%の真空の実現は困難であるが、こういった系における「熱平衡状態に至る時間」を観測する等の工夫をすることで、「光子が、エネルギーを持ち去らない」ということの検証できるかもしれない。(→考察6)
なお、『外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在する』ので、「真空に浮かぶ太陽」も、実は、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」ことを確かめられる天然の系の1つとしては、完全ではないことになる。
2. 太陽から供給されるエネルギーの一部が、光合成や太陽光発電によって蓄えられる化学エネルギー、雲や風や海流として蓄えられる運動エネルギーや重力ポテンシャルエネルギーに変換される。
太陽から供給される熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)のエネルギーが、光合成や太陽光発電によって蓄えられる化学エネルギーや、雲や風や海流として蓄えられる運動エネルギーや重力ポテンシャルエネルギーとして変換されることは、『地球の温度を下げる効果』をもたらすと考えられる。
なぜなら、太陽から、熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)として供給される続けているエネルギーが、単に、熱、すなわち、「地球の温度を上げる効果」として利用される代わりに、別のエネルギーに変換されていることになるからである。
※なお、風の起源は「空気の温度差」、海流の起源は「海水の温度差」、雲の起源は「(温度の上がった)水(海水…)からうばわれる蒸発熱)」であった。
そして、(こうした起源から生まれたれた)風のエネルギー、海流のエネルギー、雲のエネルギーは、それぞれ、風力発電、海流発電、水力発電にも利用できるのであった。
この説明は、これまでの「太陽から供給され続けている熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)のエネルギーが、単に、そのまま地球から放出され続けている熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)のエネルギーに等しい」という説明が無視してきた対象を包含しているという意味で、より自然(nature)と調和していると思われる。
すなわち、太陽光が供給するエネルギーは、単に、熱放射として宇宙に還っていくのではなく── 地球の自然(nature)の中で観察される、ダイナックな多様な自然(nature)の運動(光合成の所産を利用した動物たちの運動、化石燃料を利用した人類が引き起こしている運動、「風、海流、降雨、降雪、台風…」といった気象現象としての運動…)が生まれることを支えているという事実を、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)がエネルギーを持ち去らない」という前提の方が、説明しやすいのである。
※なお、この説明は、化石燃料(石油、石炭…)に蓄えられているエネルギーの源が、太陽から供給され続けている熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)のエネルギーであったこととも調和している。
3.ある(外部)運動エネルギーと負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、その運動エネルギーを減少させるような仕事)のペアは、互いに消滅する。
「ある(外部)運動エネルギーと負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、その運動エネルギーを減少させるような仕事)のペアは、互いに消滅する」というしくみは、『地球の温度を下げる効果』をもたらすと考えられる。
なぜなら、このしくみは、光合成や太陽光発電によって蓄えられた化学エネルギーや、雲や風や海流として蓄えられた運動エネルギーや重力ポテンシャルエネルギーは、最終的に、すべてが熱(「地球の温度を上げる効果」)になるのではなく、一部が、最終的に、完全に消滅することを支えるからである。
この説明も、地球上に実在している、ダイナミックで多様な自然(nature)の運動と調和している。
その詳細を、以下に示す。
熱力学の第一法則は、ΔU=q+wで記述される。
(ΔU:系の内部エネルギーの変化、q:系に加えられた熱、w:系に加えられた仕事)
この『ΔU=q+w』において、q=0 w=0 ならば、当然、ΔU=0 となる。
このことは、ある系について、外界と物質や熱qのみならず、仕事wのやりとりが一切ない場合、エネルギーの総量が変化しないことを意味する。
すなわち、『孤立系では、エネルギーの総量が変化しない』(ウィキペディア『エネルギーの保存』)のである。
※『孤立系は、外界とものもエネルギーも交換できない系である』(p.53『アトキンス物理化学要覧』 P.W.ATKINS著 千原秀昭・稲葉章訳)
これが、エネルギー保存則に他ならない。
つまり、エネルギー保存則(『ΔU=q+w』において、q=0 w=0 ならば、ΔU=0)は、熱力学の第一法則(ΔU=q+w)の特殊な例に過ぎないのである。
すなわち、エネルギー保存則は、孤立系でのみ成立するのである。
したがって、孤立系でなければ、エネルギーは、増加したり、減少したり(消滅したり)しうるのである。
例えば、ある系は、(外からの)正の仕事によって、エネルギーは増える一方、(外からの)負の仕事によってエネルギーは減る(消滅する)のである。
このことは、より一般的な、熱力学の第一法則(ΔU=q+w)が示していることである。
例えば、スーパーマンが、はるか上空から地上に向かって、飛行機が自由落下してしまう危機を救う場面を考えてみよう。(参考 映画『スーパーマンリターンズ』)
もし、スーパーマンがいなかったら、落下とともに飛行機に蓄えられ続ける大きな(外部)運動エネルギーは、地上に落下したとたん、大きな「飛行機を変形する仕事、熱、音…」に変換され、ガソリンの化学エネルギーの放出も加わって、大惨事となってしまっていただろう。
そして、その後の振る舞いは、(「落下する飛行機と、大気、地球」を「孤立系」と見なすことにより)基本的にエネルギー保存則に従っていると言えるだろう。
(なお、当然、厳密には地球は孤立系ではない)
ところが、映画の中では、スーバーマンが登場し、スーパーマンは(飛行機の運動に対して)「負の仕事」をし、落下する飛行機を減速させた。 そして、そっと優しく、飛行機を地上におろし、大惨事がまぬがれた。
このとき、何が起こっていたか? 落下する飛行機が蓄え続けていた大きな運動エネルギーは、どこへいってしまったか?
その「落下する飛行機が蓄え続けていた大きな運動エネルギー」の大部分が、スーパーマンによる「負の仕事」によって、消滅したのである。
(当然、厳密には、落下に伴って飛行機に蓄えられ続けていた運動エネルギーの一部だけは、「音、小さな変形、空気との摩擦…」などによって散逸するので、消滅しない)
「落下する飛行機と、大気、地球」が“ある系”であり、スーパーマンが外界から負の仕事を加えたと考えると、このことは、「ある系の外界から、仕事が働けばエネルギーは変化する」ということに相当し、熱力学第一法則に従っていると言える。
しかし、もし、「落下する飛行機と、大気、地球、スーパーマン」を含む系を孤立系と見なすならば、どうなるであろうか?
この場合は、明らかに、「孤立系では、エネルギーが変化しない」という説明が、成立していないように思われる。
なぜなら、このスーパーマンを含む孤立系において、「運動エネルギーの大部分と、負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、運動エネルギーを減少させるような仕事)のペア」が消滅する結果、「孤立系のエネルギーが減少している」からである。
このことは、『孤立系では、エネルギーの総量が変化しない』(ウィキペディア『エネルギーの保存』)に対する反例の1つに相当すると言えないだろうか?
(この「エネルギー保存則」については、「(証明されておらず)経験則にすぎないが、今まで反例が見つかったことがない」と、しばしば言われてきた)
このような「孤立系の中におけるエネルギーの減少」が生じる状況は、映画に限らず、実は、様々な場面に存在することに気づかれる。
例えば、リンゴを手で上に放り投げて、ふたたび手でキャッチする系を考えてみよう。
(便宜上、「リンゴ、地球、人、空気」を含む系を「孤立系」と見なしてみよう。当然、厳密には地球は孤立系ではない)
リンゴが上に飛び上がるのは、身体(手、腕…)が、リンゴに対して、仕事をするからである。 その仕事は、筋肉の収縮によって行われる。筋肉の収縮のエネルギー源は、ATPが持つ化学エネルギー(ミクロのポテンシャルエネルギー)であり、そのエネルギーは、もとはといえば、太陽光のエネルギーに他ならなかった。(すなわち、ATPは、光合成を通じて作られたのだった)
リンゴを手で上に放り投げる場合、このATPが持つ化学エネルギーは、一部(50%〜70%)は、(正の)仕事に変換され、一部(50%〜30%)は、熱として捨てられる。
『骨格筋は、非常に効率よく化学エネルギーを機械的な仕事に変換する。自動車のエンジンはガソリンから得るエネルギーの80%〜90%までも熱にして浪費しているのに、骨格筋では熱にしているものは30〜50%にすぎない。
筋収縮のエネルギーはATPの加水分解によって得られる〜』(『細胞の分子生物学 第2版』 p618) |
|
この場合、リンゴを上に放り投げたあとに何もしなければ、基本的にエネルギーは保存され続けるだろう。
すなわち、(ATPの化学エネルギーを利用した筋肉の収縮によって仕事されて)運動エネルギーを獲得したリンゴは、基本的には、力学的エネルギー保存則を満たしながら(重力ポテンシャルエネルギーU+運動エネルギーKが一定となりながら)運動を続け、ボールは、運動中、空気の抵抗(摩擦)によって、エネルギーを散逸し続け、最終的には、地面に落下する直前に持っていた運動エネルギーは、すべて「リンゴを変形するための仕事、音や熱…」に変換される。 (骨格筋の運動に伴って放出された熱も含めて)あらゆる散逸したエネルギーを考え合わせれば、エネルギーの合計は一定となり、基本的にエネルギーが保存されて続けているだろう。
しかし、リンゴを上に放り投げた位置あたりで、その落下するリンゴを手で優しくキャッチする場合(リンゴに対して負の仕事をする場合)を考えてみよう。
下に落ちてくるリンゴが持っている運動エネルギーは、上に投げるときにリンゴに蓄えられる運動エネルギーとほぼ等しいはずである。
(なお、厳密には、リンゴの運動中、空気の抵抗(摩擦)によって、エネルギーが、わずかに散逸する)
手でキャッチする場合にも、ATPが蓄える化学エネルギーは、一部(50%〜70%)は、(負の)仕事に変換され、一部(50%〜30%)は、熱として捨てられる。
この手でキャッチする過程において、「(ATPのもつ化学エネルギーから)変換された(負の)仕事」と「落下してくるリンゴの運動エネルギーの大部分」のペアは消滅する。
(厳密には、一部のリンゴの運動エネルギーは、手でキャッチする際に、音、熱… などによって散逸する)
式を使って示そう。
リンゴを上に放り投げる際に、骨格筋がリンゴに加える仕事(リンゴにとって“正の仕事”に相当)を w骨格筋(放)[J] とする。 リンゴを上に放り投げるため骨格筋が運動をする際に、骨格筋が熱として浪費したエネルギーを q骨格筋(放)[J]とする。
この際に消費されたATPの化学エネルギーを、EATP(放)[J]、空気等の摩擦によって奪われるエネルギーをq摩擦熱(放)[J]とすれば、
EATP(放)= w骨格筋(放) + q骨格筋(放) + q摩擦熱(放)[J] ・・・(1.11)
となる。
放り投げられたリンゴが、放物線を描き、落下する際、空気の摩擦熱として奪われるエネルギーをq空気摩擦熱[J]
とすると、キャッチされる直前のリンゴが持つ運動エネルギーKリンゴは、 Kリンゴ =w骨格筋(放) − q空気摩擦熱[J] ・・・(1.12) となる
リンゴをキャッチする際に骨格筋がリンゴに加える仕事(リンゴにとっては“負の仕事”に相当)を w骨格筋(受)[J]とする。 リンゴをキャッチするため骨格筋が運動をする際に、骨格筋が熱として浪費したエネルギーを q骨格筋(受)[J]とする。
この際に消費されたATPの化学エネルギーをEATP受[J]、運動する手と空気の摩擦等によって奪われるエネルギーをq摩擦熱(受)[J]とすれば、
EATP(受)= w骨格筋(受) + q骨格筋(受) + q運動摩擦(受)[J] ・・・(1.13)
となる。
リンゴをキャッチする際に生じる、音、摩擦…として散逸する熱をq音・摩擦擦(受)
とすると、 Kリンゴ =w骨格筋(受) + q音・摩擦擦(受)[J] ・・・(1.14)
となる。
以上の過程で、散逸したエネルギーの総和は、E散逸=q骨格筋(放) + q摩擦熱(放) + q空気摩擦熱+ q骨格筋(受) + q運動摩擦(受) + q音・摩擦擦(受)[J] ・・・(1.15)
である。
「運動エネルギーの大部分と、負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、運動エネルギーを減少させるような仕事)のペア」として消滅したエネルギーE消滅[J]は、
E消滅=(運動エネルギーの大部分)+ 負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、運動エネルギーを減少させるような仕事)[J]
=(Kリンゴ − q音・摩擦擦(受))+ w骨格筋(受)[J] ((1.14)を使用)
=(Kリンゴ − q音・摩擦擦(受))+ (EATP(受)− q骨格筋(受) − q運動摩擦(受))[J] ((1.13)を使用)
=(w骨格筋(放) − q空気摩擦熱 − q音・摩擦擦(受)) + (EATP(受) − q骨格筋(受) − q運動摩擦(受))[J] ((1.12)を使用)
=(EATP(放)− q骨格筋(放) − q摩擦熱(放) − q空気摩擦熱 − q音・摩擦擦(受)) + (EATP(受)− q骨格筋(受) − q運動摩擦(受))[J]
((1.11)を使用)
= (EATP(放)+EATP(受)) −E散逸 [J] ((1.15)を使用)
となる。
この式は、骨格筋の運動(放り上げる&受け止める)を引き起こすATPの化学エネルギーから、熱として散逸したすべてのエネルギーを除いた部分が、完全に消滅することを意味している。 (なお、このE消滅[J]の値が正であることは、容易に確認できる)
すなわち、この式は、「手でキャッチすることによって、リンゴは、結局、元の状態に戻っていても、散逸エネルギー以外のエネルギーが減っている」ことを意味している。
なぜなら、手や腕(骨格筋)の運動にともなって、ATPの化学エネルギーが減少しており(消費されており)、
「減少した(消費された)ATPの化学エネルギー」>「熱、空気との摩擦、音などの、あらゆる散逸するエネルギー」
となっているからである。
ATPの化学エネルギーの起源は、そもそも、太陽光のエネルギー(太陽からの熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)のエネルギー)であった。
その太陽から得たエネルギーの一部は、熱とはならずに、完全に消滅するのである。
つまり、リンゴを上に放り上げて再びキャッチする過程で、熱、空気との摩擦、音などの、あらゆる散逸するエネルギーを考慮しても、部分的には、エネルギーが完全に消滅するのである。
すなわち、「リンゴ、地球、人、空気」を含む「孤立系」において、エネルギーが減少しているのである。
このことは、この「リンゴ、地球、人、空気」を含む「孤立系」において、エネルギー保存則は成立し続けていないことを意味している。
※なお、「リンゴ、地球、空気」を“ある系”と見なし、「人」がリンゴに与える仕事を外力とみなせば、熱力学第一法則が成立し続けていると言える。
他にも、「孤立系」の中で── 例えば、「反復横跳びをする。できるだけ静かにキャッチボールする。その場でジャンプし静かに着地する。手を振る。走って往復する(シャトルランをする)。歩いて往復する。…」ということがあると、いずれも、ある運動エネルギーと、それに対する“負の仕事”の作用によって、エネルギーは部分的に完全に消滅するのである。
この部分的なエネルギーの消滅は、当然、人や動物が関わらない、様々な自然現象の過程においても起きうる。
例えば、風によって木の枝や葉っぱがゆれる過程、波によって砂粒等が往復する過程、風向きがめまぐるしく変わる過程、水流がめまぐるしく変わる過程、乱流、台風… において部分的なエネルギーの消滅が起きうる。 すなわち、これらの自然現象における過程においても、ある運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアが消滅することによって、トータルのエネルギーが減少しうるのである。
つまり、すべてのエネルギーは、最終的に、全て熱になるとは、限らないのである。
なぜなら、ある運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアは、完全に消滅してしまうからである。
以上のような「負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、その運動エネルギーを減少させるような仕事)のペアは、互いに消滅する」というしくみは、『地球の温度を下げる効果』をもたらすと考えられる。
そして、それどころか、地球のエネルギーが減り続けて、早々と寒冷化してしまうことさえも示唆しうる。
しかし、実際は、そうなっていない。
なぜなら、実際は、「リンゴ、地球、人、空気」は、決して、孤立系ではなく、太陽光を浴び続けることによって、エネルギーが供給され続けているからである。
運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアが消滅するしくみは、『地球の温度を下げる効果』を説明するのみならず── 「風によって木の枝や葉っぱがゆれる過程、波によって砂粒等が往復する過程、風向きがめまぐるしく変わる過程、水流がめまぐるしく変わる過程、乱流、台風… というダイナミックで多様な自然現象や、人間を含む動物による多彩な運動」、すなわち、「人類を含む地球上の自然(nature)が生む、あらゆるダイナミックでバラエティに富んだ運動、活動…」を支えているとも言えるのである。
|
以上、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」という前提のもとで、「地球の温度を低下させるしくみ」として考えられる、次の3つを説明した。
1.100%真空が実在していないので、物体の周囲の空気(分子)の熱伝導&対流によって、エネルギーが持ち去られ続けている。
2. 太陽から供給されるエネルギーの一部が、光合成や太陽光発電によって蓄えられる化学エネルギー、雲や風や海流として蓄えられる運動エネルギーや重力ポテンシャルエネルギーに変換される。
3.ある(外部)運動エネルギーと負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、その運動エネルギーを減少させるような仕事)のペアとして、互いに消滅してしまう。
これらによって、「熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)は、エネルギーを持ち去らない」という前提のもとで、「地球の温度が上がり続けないこと」「放射冷却と呼ばれた現象」「黒体放射」について説明できるだけではない。
「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、「光合成、太陽光発電…」によって、あるいは、「雲、風海流」としてエネルギーを蓄え、“運動エネルギーの大部分と「負の仕事」のペアが消滅するしくみ”として活用されうる(消費されうる)」からこそ、このダイナミックで多様な自然(nature)の運動が成立していることを説明できるのである。
このことは、単に、「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、すべて地球からの放射によって持ち去られ続けている」と考えるだけでは、説明できないのである。
※左側のバランスは、「熱放射がエネルギーを持ち去る」という前提で成立するものである。
これまで、多くの場所でこのように説明されてきた。 しかし、この左側のバランスでは、現実にある、ダイナミックで多様な自然(nature)の運動が成立していることや「石油や石炭などの化石燃料が存在すること」を説明できない。
右側のバランスは、「熱放射がエネルギーを持ち去らない」という前提で成立するものである。
この右側のバランスは、現実にある、ダイナミックで多様な自然(nature)の運動が成立していることや「石油や石炭などの化石燃料が存在すること」を説明できる。
|
|
なぜ、これまで、「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、すべて地球からの放射によって持ち去られ続けている」と、シンプルに説明され続けて来たのか?
それは、おそらく、(熱放射を含む)「エネルギー保存則」に他ならないと思われる。
すなわち、(証明されていない)経験則に過ぎなかった「エネルギー保存則」を守るために、作り上げられた説明が、「太陽からの熱放射によって地球に届けられたエネルギーが、すべて地球からの放射によって持ち去られ続けている」というシンプルな説明だったのだと思われる。
このシンプルな説明は、(ダイナミックで多様な運動を持っている)豊かな自然(nature)から乖離しているように思われる。
ここにあるのは、『「エネルギー保存則」の呪縛』と呼べるものかもしれない。
※あのアインシュタインも、この『「エネルギー保存則」の呪縛』のせいで、(特に一般相対性理論において)矛盾(板挟み、行き詰まり…)に至ってしまったと言えるだろう。
※『ヘリウムの方が重いので、星はつぶれようとするが、水素の燃えかたをよくすることによって温度を上昇させ、より大きい圧力を発生させて、つぶれるのを防いでいる。』という苦し紛れの説明がこれまで見過ごされてきたことも、この『「エネルギー保存則」の呪縛』のせいだと言えるだろう。
※重力波の直接の観測結果(重力波の波形)から、『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という解釈(説明)が無理してひねり出されたことも、この『「エネルギー保存則」の呪縛』のせいだと言えるだろう。
※そもそも、量子物理学(→結果4)に登場する「ある短時間ならエネルギー保存則を破って仮想粒子が生じることができる」という説明は、この『「エネルギー保存則」の呪縛』に対して風穴を開けているものの1つ(見直しを迫っているものの1つ)であると見なせるように思われる。
もう、そろそろ、『光子を含めて「エネルギー保存則」が成立しているはずだ』『「エネルギー保存則」に異を唱えることは、即、間違い(非科学)であることを意味している』『時空はどこまでも連続である』のような、これまでの物理学の常識(思い込み、ロックイン)から脱する必要があるのではないでしょうか── ということを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、示しているように思われる。
《電気双極子の振動に伴う放射について》
電気の双極子が振動することによって電磁波を放出するしくみについては、これまで、電場(電気力線)の図を用いてなされてきた。
電気双極子の振動に伴う放射のしくみについて、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、どのように説明できるだろうか。
それは、おおよそ、次のようになる。 (なお、詳細な検討は、今後の課題である)
正と負の電気(電荷)の双極子が、周期T[s]で、お互いに単振動する系を考えてみよう。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、正と負の電荷のそれぞれは、様々な振動数を持つ仮想光子を放出しては、再吸収することを繰り返しているのだった。
そういった状況の中で、正と負の電気(電荷)の双極子が、それぞれ、t=0で共転回を開始し、その後、t=T/2[s]だけ時間が経過するとどうなるか?
この図から、時間がt=T/2[s]時間経過すると、180度の共転回が終了する。 そして、新たに共転回する相手を探すと、戻ろうとする方向には、正負が逆である電荷が存在する。 光子は、必ず、右巻きと左巻きのペアで構成されているので── この場合、仮想光子は、もはや、元の電荷に戻っていくことができないことになる。
そこで、下図のように、新たな共転回の相手を「(電荷のある方向と)反対の方向にある原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の素スピノール」に求めるしかなくなる。
そして、上図のピンクの素スピノールを含む原始ヒッグス場ユニット(PHU)にはエネルギーが蓄えられているので、この後、ふつうの(電磁波を構成する)光子として、光速で飛び去っていってしまうことになる。
以上の説明から、様々な振動数を持つ仮想光子の中で、最も再吸収されずに(電磁波を構成する)光子として放出されるものは、(新たな共転回の相手をさがす際に、電荷の正負の位置が、(位相180度分)ぴったり逆転してしまっているところの)まさに“振動数ν(=1/T)の仮想光子”であると考えるのが自然であることがわかる。
※あくまで、最も再吸収されにくい仮想光子が、振動数ν(=1/T)の仮想光子であるというだけで、これと前後する振動数を持つ光子も、ある程度、放出されると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
一方、例えば、下図のように「単振動の位相が約30度の位置」に対応する素スピノールで構成される仮想光子についても、最も再吸収されずに(電磁波を構成する)光子として放出される(飛び去る)ものは、“振動数ν(=1/T)の仮想光子”であると考えられる。
なぜなら、“振動数ν(=1/T)の仮想光子”は、共転回の相手を探す際に、電荷の正負の位置が、(位相180度分)ぴったり逆転してしまっているからである。
一方、「再吸収されずに、光子として放出される数が、振幅に比例する」ならば、(光子の総和である)電磁波の性質と調和すると考えられる。
すなわち、このような単振動の場合は、下図のように、単振動の周期Tが一定の場合、“振幅”に比例して、生じる“共転回のペア”の数が多くなると考えられる。
※右側の振幅が、左側の2倍になっているのに伴い、共転回のペアの数も2倍になっている。
※緑の線は、いずれも、新たな共転回を開始する時点の位置に相当している。
そして、いずれの共転回も、半周期(t=T/2)経過すると、電荷の正負が(位相180度分)ぴったり逆転する。
※「新たな共転回を開始する時点の位置」がどこであっても、半周期(t=T/2)で、正負がぴったり逆転する仮想光子の振動数νは一定であるので、(c=νλにより)最も再吸収されない仮想光子の波長λ(=2r(r:共転回する素スピノールどうしの距離))も一定になる。
|
|
おおよそ、以上のようなしくみで、振動数νで、単振動する電気双極子が、「(振動の振幅に比例する個数を持つ)“振動数νの光子”で構成される電磁波」を放出すると考えられる。 厳密な数式化を含めて、詳細な検討は、今後の課題である。
※もし、電気双極子の振動が、1直線上で繰り広げられているのならば、「電荷の正負の位置が(位相180度分)ぴったり逆転してしまう」ことによって仮想光子が放出されることの他に、電荷の加速(「運動エネルギー順位 Kn=2π2k2me4/n2h2」の変化)によって、「hν=Km−Kn(m>n)」に従う光子を放出することも考えられる。
一方、もし、電気双極子の振動が、下図のような円運動によって繰り広げられているならば、「運動エネルギー順位 Kn=2π2k2me4/n2h2」が変化しないので、「hν=Km−Kn(m>n)」に従う光子の放出はなくなると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
《光の反射と屈折》
光は、例えば、鏡によって反射する。
そのとき、ふつう、振動数も波長も変わらない。
その際、原始ヒッグス場ユニットの変形に伴って蓄えられるエネルギーが一定のまま、方向だけが変化することになる。(入射角=反射角)
この過程は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、どのように説明されるだろうか?
光子の進行中に、鏡に遭遇すると、なんらかのしくみで原始ヒッグス場ユニットの方向がクルッと変化し、(入射角=反射角となるような)新たに共転回する相手を獲得して、その方向に進むのだろうと思われる。(鏡の中の何かと衝突することによって(運動量保存則に基づいて)反射するとは考えにくい。もしそうならば衝突することによって、光子の振動数が減り、色が変わるはずだからである) 詳細な検討は、今後の課題である。
一方、例えば、真空中から水中に光が進行するときに屈折する。
水の真空に対する屈折率をn(>1)とすると──
ふつう振動数νは変わらない(→光を構成する光子のエネルギーE=hνは変わらない)一方で、波長λ'は短くなるので、c'=νλ'=νλ/n=c/nにより、光の速さが遅くなるように観測されると考えられる。
これは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で、次のように説明できる。
|
『単なる真空より、水が存在している方が、その水の質量の分、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高く存在している。
そのことによって、“単なる真空”を収容する時空より“水”を収容する時空の方が、「空間が膨張し、時間の流れがスローダウンするように」が変化している。
その結果、いったん水中に入った光自身は、常に光速で進んでいるつもりになっているのに── 外から見れば、波長が短くなって、ゆっくり進んでいるように見える。
なお、“単なる真空”を収容する時空から、“水”を収容する時空へと移る場合、すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度」が変化するときに限って、光子は、進行方向を変える。
いったん水の中に入った光子は、“水”を収容する時空が持っている「空間が膨張し、時間の流れがスローダウンする」変化の程度(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度)が一定なので直進することになる。』
|
屈折についてのこの説明は、「光が、大きな重力を持つ天体の周囲を進む際に、そのルートを曲げること」についても同様に(統合的に)説明できるものである。
正しければ、光子は、時空の「空間が膨張し、時間の流れがスローダウンする」変化の程度(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の存在数の密度の変化の程度)に応じて、進行方向を変えるという性質を持っていることになる。
例えば、光子が、真空中から水中へと進んでいく場合、光子が進行方向を変えるのは、「真空中の原始ヒッグス場ユニットの中の素スピノール」と「水中の原始ヒッグス場ユニットの素スピノール」が共転回を開始する際だけであると考えられる。(なぜなら、その前後においては、直進しているからである)
例えば、「光が、大きな重力を持つ天体の周囲を進む際に、そのルートを曲げる」場合は、新たな共転回を開始するたびに、進行方向を変えると考えられる。
このことは、光子は、その進行方向について、新たな共転回をはじめようとする際に、全体的な「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の分布全体を反映できる仕組みを持っていることを意味しているように思われる。 このような仕組みは本当に可能なのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
《プランク定数、プランクエネルギー、プランク自然定数について》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、プランク定数h[J・s]とは、
「1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”が変形することによって蓄えるエネルギーの振幅E[J]」と「その原始ヒッグス場ユニット(PHU)が変形する周期(=(その原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する素スピノールの転回周期)T[s]」の積である。
つまり、ET=h[J・s]が成り立つ。
この ET=h[J・s]にT=1[s]を代入すると、E×1[J・s]=h[J・s] 、すなわち、E[J]=h[J] が導かれる。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── プランク定数h[J・s] に等しい大きさのエネルギーh[J]の大きさは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を変形周期T=1[s](=1秒)の時間をかけて単振動させた場合のエネルギー振幅E[J]の大きさに等しいと言えるのである。
したがって、プランク定数h[J・s]の大きさは、“1秒”と深い関係がある量であるという見方が成立するのである。
そもそも、1秒とは、「およそ“地球が自転する時間”の24分の1の60分の1の60分の1」のようにして、“地球が自転する時間”から決まってきた時間に過ぎないのであった。
したがって、実際は、「周期T=1秒よりも長い時間をかけて共転回する光子」も存在していると考えられる(例えば、周期T=3秒でやっと1回、共転回できる光子、あるいは、周期T=60秒で1回単振動する原始ヒッグス場ユニットの“4面体”も存在していると考えられる)。
そのことは、例えば、プランク定数h[J・s] に等しい大きさのエネルギーh[J]の1/3や1/60というエネルギーも、宇宙には実在するはずであることを意味する。
すなわち、例えば、“1秒”と深い関係を持つh[J]というエネルギーの大きさがあるように、3秒と深い関係があるh/3[J]というエネルギーの大きさ、1/60秒と深い関係があるh/60[J]というエネルギーの大きさも存在するのである。
( ET=h[J・s]にT=1[s]を代入すると、E×1[J・s]=h[J・s] 、すなわち、E[J]=h[J] が導かれるように──
ET=h[J・s]にT=3[s]を代入すると、E×3[J・s]=h[J・s] 、すなわち、E[J]=h/3[J] 、
ET=h[J・s]にT=60[s]を代入すると、E×60[J・s]=h[J・s] 、すなわち、E[J]=h/60[J] が導かれる)
つまり、プランク定数h[J・s]自体は、実際は、「宇宙のエネルギーの最小単位」ではないことになる。
※もしかしたら、エネルギーについての普遍的で一定な基準値としては、例えば、重力子エネルギーEG(=EP/2π)の方が、よりふさわしいのかもしれない。
なぜなら、例えば、「1つの原始ヒッグス場ユニットが“4角形”(縮みきったバネ)に変形するときに蓄えられるエネルギー」は、(どのような時間の単位が使われていようが関係なく存在する)普遍的な実体であると考えられるからである。
プランク定数h[J・s]が持っている意味の1つは、「宇宙のエネルギーの最小単位」ではなく、「反比例定数」なのである。
すなわち、プランク定数h[J・s]は、「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形周期(構成する素スピノールの転回周期)」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が蓄えるエネルギー振幅」を結びつける“反比例定数”という、とても便利で重要な意味を持つものなのである。
そして、一方で、プランク定数h[J・s]には、それを2πで割ったもの(h/2π[J・s]=h/2π[kg・m/s][m])が、「素スピノールが持つ、スピン角運動量に相当する」という重要な意味もある。
※なお、当然、素スピノールのスピン角運動量に相当しているのみならず、「電子、クォーク…」のスピン角運動量に相当しているとも言える。
このプランク定数h[J・s]以外の、様々な定数についても、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に基づいて、その意味(実体像)をつかむことができる。
それらを整理して示すと次のようになる。
|
プランク定数
|
h≒6.626×10-34[J・s] |
◎「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形周期[s](構成する素スピノールの転回周期[s])」と
「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が蓄えるエネルギー振幅E[J]」を結びつける“反比例定数”
◎2πで割ったもの(h/2π[J・s]=h/2π[kg・m/s][m])が、
「素スピノールが持つ、スピン角運動量に相当する」 |
|
プランク距離
|
LP≒1.616×10-35[m] |
◎素スピノールのペアの間の最短距離 |
|
プランク時間
|
TP=LP/c
≒5.4×10-44[s] |
◎素スピノールが1回180度転回するためにかかる最短時間 |
|
光速
|
LP/TP≒3×108[m/s] |
◎光子や重力子が進む速さ(1秒間に進む距離)
◎「nLPだけ距離の離れた素スピノールのペアが、nTPの時間を費やして生じる“共転回”」が移動する速さ |
|
重力子エネルギー
|
EG=hc/(2π)2LP[J]
(=EP/2π[J]) |
◎1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の系が持っているエネルギー”
◎波長2LP[m]の2つの“LP光子”が持つエネルギーを(2π)2で、割ったもの |
|
重力子質量
|
MG=EG/c2≒2×10-8/2π[kg] |
◎重力子エネルギーEGに相当する質量(=プランク質量/2π)
◎重力子振動数νG=c/2LP[個/s]で、重力子を放出できる質量の大きさ
|
|
重力子振動数νG
|
νG=c/2LP[個/s]
c/2LP≒0.927×1043[個/s] |
◎重力子の振動数
◎重力子質量MG[kg]が1秒間に重力子を放出する頻度
※M[kg]の質量が1秒間に何個の重力子を放出できる頻度は(M/MG)×(c/2LP)[個/s]で計算できる
|
|
プランクエネルギー
|
EP =hc/2πLP[J]
≒1.9561×109[J]
≒1.2×1019[GeV] |
◎2πで割ったものが、「重力子1つ(=素スピノール4つ分の転回運動)の系が持つエネルギー」や
「1つの原始ヒッグス場ユニットの“4角形”(縮みきったバネ)が持つエネルギー”」に相当する。
(◎波長2LP[m]の2つの“LP光子”が持つエネルギーを(2π)で、割ったもの) |
|
プランク質量
|
MP=EP/c2≒2×10-8[kg] |
◎プランクエネルギーEP[J]に相当する質量
◎2πで割ったものが、重力子質量MG[kg]に相当する。
|
もう1つのプランクエネルギーを求める式「EP=(hc5/2πG)1/2」 と、上記の式「EP=(h/π)×c/2LP」
をイコールでつなぐ(「hc/2πLP =(hc5/2πG)1/2」とする)ことによっても、重力定数Gを計算でき、「G=2πc3LP2/h」と求まる。
※この計算結果は、(次元解析から計算された)プランク距離を求める式 LP=(hG/2πc3)1/2の変形から導かれるGと合致する。
このことは、重力子の振動数や波長の大きさについての説明(重力子が波長2LPの光子2つ分が結合エネルギーを放出して結びついているものであるという説明)が、自然(nature)と調和していることを示していると思われる。
この重力定数「G=2πc3LP2/h」を用いて、各物理量を書き換えてみると、よりシンプルになる。
それは、「重力定数Gを LP[m]で置き換えた表現である」と言える。
|
これまでの表現
(次元解析から計算されたもの)
|
“重力定数Gを、LP[m]を用いた式で置き換えた表現”
(Gに、G=2πc3LP2/h を代入した表現)
|
|
プランク距離
|
LP=(hG/2πc3)1/2[m]
|
LP[m]
(素スピノールの間の最小距離)
|
|
プランク時間
|
TP=(hG/2πc5)1/2[s]
|
LP/c[s]
(素スピノールが180度転回する最小時間)
|
|
プランクエネルギー
|
EP=(hc5/2πG)1/2 [J]
|
hc/2πLP[J]
(=2πEG[J])
|
(※“これまでの表現”の部分はウィキペディアを参考にした)
※なお、プランク定数h[J・s]を、プランクエネルギーEP[J]や プランク時間 TP[s]を用いて置き換えて表すと次のようになる。
|
これまでの表現
|
重力定数Gを LP[m]でを用いた式で置き換え、
さらにプランク定数h[J・s]をEP[J]や TP[s]を用いた式で置き換えた表現
|
|
プランク定数
|
h[J・s]
|
(EP=hc/2πLP[J]より)
h[J・s]=2πEPLP/c
=2πEPTP[J・s]
=πEP×2TP[J・s]
(=(hc/2LP)×2TP[J・s])
=「波長2LP[m]の光子が原始ヒッグス場ユニットに蓄えるエネルギー振幅」
×「波長2LP[m]の光子を構成する素スピノールの360度の転回周期」
|
※h=πEP×2TP[J・s](=(hc/2LP)×2TP[J・s])は、やはり、「エネルギー振幅」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形周期」の反比例関係を示す式、ET=hを満たしていることがわかる。
※例えば、もし、プランク時間TP[s]を1単位にしている星があれば、そこでの、プランク定数は、H=h/TP[J・TPs]=πEP×2×TP/TP[J・TPs]=πEP×2[J・TPs]となるだろう。
地球上のように、1秒を1単位にしている“われらの宇宙観”では、プランク定数Hは、そのままH=h[J・s](=πEP×2TP[J・s])となる。
もし、われわれにとっての“0.1秒分”を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=10h[J・s/10](=πEP×20TP[J・s/10])となるであろう。
もし、われわれにとっての“3秒分”を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=h/3[J・3s](=πEP×2TP/3[J・3s])となるであろう。
もし、われわれにとっての60秒分を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=h/60[J・60s](=πEP×2TP/60[J・60s])となるであろう。
そして、いずれの時間を単位にする星においても、H=ETは、成立する。
(なぜなら、Eは、いずれも、E=πEP[J]で、Tは、いずれも、その実体が等しく、T=2[J・TPs]=2TP[J・s]=20TP[J・s/10]=2TP/3[3s]=2TP/60[60s]が成立しているからである)
つまり、H=ETは、どこの星でも(どのような時間を1単位とする星でも)なりたつ普遍的な原理であるということなのである。
(そして、その関係は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”がもつ性質として、創発されてきたと考えられるのである)
|
※一方、h[J・s]=2πEPTP[J・s]
=(2π)2EGTP[J・s]
と変形できる。よって、
h/2π2
=EG×2TP[J・s]
=「1つの“波長2LPの重力子”が原始ヒッグス場ユニットに蓄えるエネルギーの振幅EG[J]」×「重力子を構成する波長2LP[m]の光子の素スピノールの転回周期[s]」
となる。 この数式は、重力子による原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形についての反比例関係に相当するものである。
つまり、光子の場合の反比例定数がh[J・s]であるのに対し、重力子の場合の反比例定数は、h/2π2[J・s]であるということになる。
この反比例定数は、ディラック定数 h/2π[J・s]をπで割った値に相当している。
|
プランク定数
|
h[J・s]
|
=2πEPTP[J・s]
=πEP×2TP
=(hc/2LP)×2TP[J・s]
=「1つの波長2LP[m]の光子のエネルギー」
×「“4面体”の変形周期(=素スピノールの転回周期)」[J・s]
|
|
ディラック定数
|
h/2π[J・s]
|
=EPTP[J・s]
=πEG×2TP[J・s]
|
|
ディラック定数/π
|
h/2π2[J・s]
|
=EG×2TP[J・s]
=(hc/(2π)2LP)×2TP[J・s]
=1/(2π)2×{(hc/2LP)×2}×2TP[J・s]
=「並走する2つの光子のエネルギーを(結合エネルギーを放出させて)
1つの重力子のエネルギーにするための係数」
×「2つの波長2LP[m]の光子のエネルギー」
×「“4面体”の変形周期(=素スピノールの転回周期)」[J・s]
|
※重力子の場合の反比例定数は、h/2π2[J・s]であることが示されている。
ただし、光子の場合は、h=ETにおいて、E[J]やT[s]は、様々な値を取りうるのに対し、
重力子の場合は、h/2π2=ETにおいて、E=EG[J]、T=2TP[s]という値だけを取ると考えられる。
そういう意味で、「重力子の場合の反比例定数」という言い方は、適当ではないのかもしれない。詳細な検討は、今後の課題である。
|
※さらに、c=LP/TP[m/s]、h=2πTPEP[J・s]を用いて、重力定数Gを、変形してみると次のようになる。
G=2πc3LP2/h
= 2π(LP/TP)3×(LP2/2πTPEP)
=(LP/TP)3×(LP2/TPEP)
=LP5/TP4EP
=LP5/2πTP4EG
(=LPc4/2πEG)
果たして、重力定数は、一定であるだろうか?
確かに、プランク距離LP[m]やプランクエネルギーEP[J](重力子エネルギーEG[J])は、一定である。
しかし、プランク時間TP[s](素スピノールが1回180度転回するためにかかる最短時間)や光速c[m/s]は、それぞれの時空で変化する。
なぜなら、相対性理論が示すように、時間の流れが、それぞれの時空で異なりうるからである。
したがって、プランク時間TP[s]も、光速c[m/s]も、実は、それぞれの時空で変化しうるのである。 そういう意味では、重力定数の意味は、実質的には、それぞれの時空で異なりうることになる。
しかし、たとえ、そうだとしても、それぞれの時空で「光速はcだ」を観測するように、それぞれの時空で「重力定数はGだ」を観測することになる(だからこそ、ウラシマ効果も生じる)。
そうだとすると、それぞれの時空で重力定数Gを測定して、それらを比較することによっては、(時空によって)重力定数Gが実質的に変化していることの証明が難しくなるように思われる。
ところが、例えば、光が、真空から屈折率nの水中に進む場合、光速cが、光速c/nになることは、観測されているのだった。 同様に、真空中の重力定数と、水中の重力定数を比較することは、可能ではないだろうか?(G=LPc4/2πEGにより、水中の重力定数は、G=LPc4/2πn4EG(n>1)のように小さくなる(したがって、重力は、1/n4の割合で小さくなる)と予想される)。 また、あるいは、そもそも、ウラシマ効果が存在しているということが、実は、(時空によって)重力定数Gが実質的に変化していることを証明している、と説明できないだろうか?
詳細な検討は、今後の課題である。 (→付録 EMOES宇宙論2)
|