研究論文
『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
4.量子論〈Quantum theory〉について
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、いわば、“究極の量子化”を、その根底に内在させているモデルである。
それは、“これまでの量子論が間違っている”と否定するモデルではなく── これまでの量子論が、どのようなしくみでうまくいっているのかを含め、「より深いレベルの階層」から、包括的&統合的に、ミクロ&マクロの自然(nature)を説明しようとするモデルである。
そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、プランクの“エネルギーの量子”の発見からスタートして育まれてきた「“量子”物理革命」を完成に近付けるために、おおいに役立つツールなのである。
このページでは、次のような項目に整理して説明していく。
《量子論と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の概論》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は── “素スピノール”という“最も基本的な量子(究極の量子)”が実在することを前提にして、“すべて”の物理現象(観測結果)や既存の主要な物理理論(古典力学、電磁気学、相対性理論、量子論、素粒子物理学の標準模型、弦理論、ループ量子重力理論…)を、包括的に、そして、統合的に説明しようとするモデルである。
例えば、量子論については──
「どのようなしくみで、量子ゆらぎが生じるのか? どのようなしくみで、二重スリットの縞模様が生じるのか? どのようなしくみで、不確定性原理が成り立つような観測事情が生まれるのか? どのようにして、粒子と波の二重性が認められるようになるのか? どのようなしくみで、確率としてしか計算できなくなるという事情が生じるのか? どのようなしくみで、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)が有効になるのか? …」といった、これまで、“抽象的な数学”でうやむやにするしかなかった根本的な問題を含めて── 「より深いレベルの階層」から、包括的&統合的に、そして、“具体的&調和的、シンプル”に説明しようとするものが“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)なのである。
この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、(量子論の本質と見なされてきた)『「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」や「ハイゼンベルグの不確定性原理」』による(観測上&応用上の)成功の陰で、これまで、あきらめられてきた部分(思考停止になってしまった部分、切り捨てられてきた部分、“うやむや”にされてきた部分…)にも焦点をあて、それらをも根底から説明しようとするモデルなのである。
これまでの量子論においては、基本的に“あきらめ”が内在している。
すなわち、これまでの量子論(量子力学、場の量子論)の根底には、結局は、「ミクロの自然(nature)について、なぜ、そうなのか、どのようなしくみでそうなるのかを理解すること、すなわち、幾何学的な実体像(視覚的な描像、true picture at Planck scale、ミクロの自然が持つ究極の構造…)をつかむことは不可能だ、その探求は無意味だからおやめなさい、抽象的で正確な数式(法則、規則、ルール…)に慣れることで我慢しなさい、という“あきらめ”」が、ひそんでいるのである。
量子論において、“あきらめ”が蔓延していることを知ることのできる例は、多数ある。
例えば、次のようなファインマンの言葉がある。
『ところが、量子力学となると、これを本当に理解できている人はいない。こういってまずまちがいないと私は思っております。〜
できることならの話ですが、 「どんなからくりでそうなるのだろう」と考えこむのはおやめください。 泥沼にはまってしまうからです。 それは袋小路です。いまだかつて出口を探り当てた人はいない。どんな仕掛けで自然がそんな振る舞うのか、だれにも分かっていないのであります』
(『物理法則はいかに生まれたか』 ダイヤモンド社 R.P.ファインマン著 江沢洋 訳 p167 下線は筆者による)
|
『つまり、電子は本当は粒子と電子のどちらにも似ていないのである。こんな具合なので、もうあきらめて、電子はそれらのどっちにも似ていないものであるというより仕方のないものである』 (『ファインマン物理学』V 量子力学 砂川重信[訳] p.1 下線は筆者による)
|
例えば、次のようなディラックの言葉がある。
『第1の批判に答えて、物理学のような科学のおもな目的は像を描き出すことではなくて、現象を支配している法則を定式化し、それらの法則を応用して新しい現象を発見することにあるという点を注意しておこう。もしも像が描ければそれにこしたことはないけれども、像が描けるか描けないかは二の次の問題にすぎない。原子に関する現象の場合には普通の‘像’とうことばの意味での像を描けることは期待できない。普通このことばは、本来古典論的な働きを営む模型をさしているからである。 しかし、‘像’ということばの意味を広げて、基本法則が内部に矛盾を含まないことを明らかにするような見方はどんなものでもこれに含まれるという解釈をすることもできる。このように意味を広げておけば、量子論の法則に慣れてくるにつれてだんだんと原子に関する現象の像が描けるようになってくる』
(p.13 『ディラック 量子力学 原書第四版』 岩波書店 イタリック体での下線は、ディラックによる下線である。 他の下線は筆者による)
|
『すなわちそこにはまったく新しい考え方が含まれているのであって、この考えに慣れてしまうことが必要なのであり、そしてまたこの考えを用いて正確な数学的理論を作り上げなければならないのである。そして立入った古典論的な像を描くことはやめにするのである』
(p.16 『ディラック 量子力学 原書第四版』 岩波書店 重ね合わせについてのコメントである。 下線は、筆者による)
|
例えば、次のような、古澤明氏の言葉もある。
『「量子力学がわかったと思う人がいたら、その人は量子力学がわかっていないのだ」と言った有名な物理学者もいたぐらいだから、わからなくても一向に悲観することはない。 というか、そもそもわかっている人はいないのである。 量子力学は自然現象を記述する、現在知られている最良の「言語」である。 〜。
〜 例えば、日本語において、「私は」の「は」は何故「わ」と書かないかはルールであって、疑問の対象ではない。量子力学という「言語」にも、この類のルールが存在する。代表例は、後で述べる「波束の収縮」というルールである(〜)。これは、ルールであって疑問の対象ではないのであるが、量子力学をわからなくさせている元凶である。
ただ、このルールが量子力学を量子力学たらしめているのであり、こうするとすべての自然現象を矛盾なく記述できるというだけなので認めるしかない。つまり、繰り返しになるが我々が量子力学をのすべてを直感的に理解するのはそもそも不可能なのである。 しかし、そこさえ我慢すれば、あとは「パラダイス」である。』
(『量子もつれとはなにか 』(p.16-17 古澤明 講談社ブルーバックス 一部省略、下線は、筆者による。)
|
例えば、次のような、記述もある。
『スーパーストリングの横顔を見てみよう。 長さ10-33センチメートル 〜 という短さである。 〜 この長さは、「プランクの長さ」ともいい、いわば長さの単位素量である。いいかえるなら、これ以上小さなスケールの世界ではハイゼンベルグの不確定性原理が圧倒的に威力を発揮して、因果性に基づく物理的に意味のある議論が不可能になってしまう、そんな長さである』
(『最新 素粒子論 「究極の理論=Theory of Everything」を求めて』p74 学研) (※下線は筆者による)
|
…
多くの文献から、量子論の根底には、“あきらめ”が内在していることが読み取れる。
これが大多数派なのである。
このような、量子論に対する“あきらめ”の姿勢──「ミクロの自然(nature)についての視覚的な描像(true picture at Planck scale)の探求をあきらめて、切り捨てる姿勢」が、現在の物理学の世界に蔓延しているのは、なぜか?
いろいろ考えられる。
その答えの1つは、先ほどの古澤明氏の言葉の中からも読みとれる。
すなわち、“量子論のルール”が、観測上&応用上、とても成功しているからである。
その量子論のルールの根本とは、「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」であり、「ハイゼンベルグの不確定性原理」にほかならない。
この「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」と「ハイゼンベルグの不確定性原理」が、観測上&応用上、とても成功しているからこそ── ますます、あきらめるのである。
しかし、一方で── 最初から、決して、あきらめなかった物理学者もいた。
その最も主要な物理学者は、アインシュタインである。
ほとんどの物理学者が、あきらめていた中で、アインシュタインは、決して最初から最後まであきらめなかった。
アインシュタインは、「完成された量子論(完全なる量子論)」を待ち望み続けていたのだ。
それは、次の記述から読みとれる。
『一九四九年という最晩年になって、〜、アインシュタインは、「今日の量子論のもつ本質的に統計的な性質は、この理論が物理系について不完全な記述をしているせいで生じていると固く信じています」と述べた。
〜。一九五四年には、彼ははっきりと次のように述べている。「今日の量子力学の全体的構造に関する基本的な考え方を変えることなく、単に何かを付け加えることによって、この理論の統計的な性質を取り除くことはできない」。彼は、ミクロな量子の世界で古典物理学の概念に立ち返るのではなく、何かもっと過激なことが必要だと確信するようになっていた。もしも量子力学が、真実の一部しか捉えることのできない不完全な理論ならば、完全な理論がきっと存在して、発見されるのを待っているに違いないと彼は考えていたのだ』
(p.462 『量子革命』 下線は筆者による)
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』 下線は、筆者による)
|
『二〇世紀の始めから一九五五年にこの世を去るときまで、彼の念頭を離れなかったのがこの量子の問題だった。「量子問題については、私は一般相対論の一〇〇倍ぐらい頭を使っているよ」と彼は言っているが、そんなに考え続けても、どうにもらちがあかなかったのである。晩年になっても最初考えはじめたころと比べて少しの進歩もないどころか、いよいよもってわからなくなってきた感さえあった。「もう五〇年もの間必死で考え続けているというのに、いっこうに『光量子(クオンタ)とは何なのか?』という問題の解決に近づいてはしないのだ」とアインシュタインはぼやいている。「このごろは猫も杓子もこの答えがわかったなんぞと思っているらしいが、それは大まちがいというものだよ。」』
(p.60 『アインシュタインの部屋──[上]』 エド・レジス著 大貫昌子訳 工作社 下線は、筆者による)
|
そして、近年にも、あきらめずに、「完成された量子論(完全な量子論)」を探求している理論物理者がいることは、確かだろうと思われる。
例えば、次のような記述から読み取れる。
『未解決の概念問題──測定問題や、量子的な世界はどこで終わり、古典的な日常世界はどこから始まるのかがはっきりしないことなど──のために、しだいに多くの物理学者が、量子力学より深い理論を探すようになっている。 オランダのノーベル賞受賞者で理論物理学者のヘラルト・トホーフトは、「『たぶん』をつけて答えるような理論は、不正確な理論と見なすべきだ」と述べた。彼は、宇宙は決定論的だと考えており、奇妙で直観に反する量子力学の特徴をすべて説明するようなより基本的な理論を探しているところだ。そのほかにも、エンタングルメントの分野をリードする実験物理学者のニコラス・ギシンは、「量子力学が不完全だと考えることには、なんの抵抗もない」と述べている。
ほかにも解釈が登場し、量子力学は完全だという主張が本格的に疑問視されるようになって、アインシュタイン=ボーア論争ではアインシュタインが敗北したという、従来の判定が見直しを受けている。数学者で物理学者でもあるイギリスのサー・ロジャー・ペンローズは次のように述べた。 「アインシュタインは、ボーアの追従者なら言うであろうように、何か重要なところで深く『間違っていた』のだろうか? わたしはそうは思わない。わたし自身は、微視的なレベルよりもさらに下層の世界が実在し、今日の量子力学は根本的に不完全だというアインシュタインの確信を強く支持している」』
(p.466-467 『量子革命』 下線は筆者による)
|
『17.3 21世紀の宇宙の数学とは何か
では、宇宙を理解するうえでの今日的問題を解くために我々が開発すべき21世紀の宇宙の数学とは何であろうか。筆者は、これは量子論であると考える。〜。 なぜいまさら量子論なのか。
それには2つの理由がある。1つは、素粒子物理学の基本言語である場の量子論が数学的に定式化されておらず、そのためには新しい数学が必要であると考えられていること。もう1つは、場の量子論、さらには量子論と一般相対論を統合する理論が、初期宇宙の謎を解くために重要になってきたことである。』
(p258-259 『素粒子論のランドスケープ』 大栗博司著 数学書房 下線は、筆者による)
|
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、まさに、「微視的なレベルよりもさらに下層の世界が実在」することを前提として生まれており、「量子力学より深い理論」「奇妙で直観に反する量子力学の特徴をすべて説明するようなより基本的な理論」「場の量子論、さらには量子論と一般相対論を統合する理論」の候補の1つであると思われる。
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のせんとすること
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のせんとすることは、決して、これまで量子力学の本質と見なされてきた「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」と「ハイゼンベルグの不確定性原理」を、否定&批判することではない。
「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」が「なぜ、うまくいくのか」、「ハイゼンベルグの不確定性原理」が「どのようなしくみで、成立しているのか」を説明することである。
それらの成功を根底で支えているところの“幾何的な実体像”を示すことである。
すなわち、これまで、「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」と「ハイゼンベルグの不確定性原理」で、あいまいに、うやむやに説明されてきたところの、ミクロの自然(nature)を包括的&統合的に、そして、“具体的&調和的、シンプル”に説明することである。
そして、「量子論の完成」を強力にサポートすることである。
たしかに、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、『素スピノールは「プランクの長さ」より小さく、因果性に基づいた振る舞いをする(=3Stepsを持つ)』と考えることを含め、「量子論が、なぜそうなのかを理解すること、すなわち、そのミクロの世界の幾何学的な実体像(視覚的な描像、true picture at Planck scale…)の探求することを、あきらめていない」ので── 明らかに、「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」や「ハイゼンベルグの不確定性原理」の姿勢と真っ向から対立しうると言える。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の科学スタイルと、ボーアやハイゼンベルグの科学スタイルの間には、互いに正反対のところがある。
|
ボーアやハイゼンベルグの科学スタイル
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル) |
| 対象 |
「“観測できるもの”だけに制限する」
|
「“観測できないないもの”も含む」
|
しかし、両方に存在意義がある。
すなわち、当然、ボーアやハイゼンベルグらが理想とした、「対象を、“観測できるもの”だけに制限する物理学」には、ゆるぎない存在意義がある。
なぜなら── そのおかげで、「人類にとっての、観測上&応用上(実用上)の限界および安全性」を知ることができるからである。
つまり、「対象を、“観測できるもの”だけに制限する物理学」には、「人類にとっての、観測上&応用上(実用上)の限界および安全性」という「自然(nature)が持っているゆるぎない一面」を示してくれるという存在意義があるのである。
これは、決して皮肉ではない。
なぜなら、この「人類にとっての、観測上&応用上(実用上)の限界および安全性」を示してくれる「対象を“観測できるもの”だけに制限する物理学」のおかげで、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のような究極のズームインした世界についての研究を、思う存分、繰り広げることができる、と言えるからである。
このことは、「自然(nature)と調和している限り、科学スタイルの多様性は、尊重されるべきである」ということと同じくらい(or それ以上に)、重要なことである。
一方、果たして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)にも、本当に、存在意義があるだろうか?
人類にとって、観測も応用もできないことを探求することに何の意味もないのではないか?
観測上、応用上(実用上)だけにおいて成功すれば、十分ではないか?
十分ではない。
なぜなら、(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が持っている)「対象を“観測できるもの”だけに制限しない物理学」という方向性を持つアプローチによってこそ、はじめて「現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”」を解消できるからである。
すなわち、「対象を“観測できるもの”だけに制限する物理学」だったからこそ、「(観測できない)ミクロの自然(nature)」についての探求をあきらめたからこそ、「現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”」が生じたからである。
そして── 「現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”」が生じているせいで、貴重な人類の頭脳、マンパワー、資源、時間… が浪費されているおそれがあるからである。
それは、いわば「間接的な貢献」である。
それは、「より大事な方面の研究に、人類のエネルギーが優先的に注がれることを促す」という貢献である。
それは、「研究の方向性を示す」という貢献である。
それは、「人類の優秀な頭脳を浪費させない」という貢献であり、人類が持っている、限られた“貴重な時間や資源”を浪費させない」という貢献でもある。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)には、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)なりの、存在意義があるのだ。
実用性と結びついた、「人間が観測&応用できる範囲の自然(nature)を厳密に、正確に記述する物理学」に存在意義がある一方で──
「人類が、どうあがいたって観測できない範囲を含めて、自然(nature)を合理的に、そして、具体的に探求する物理学」にも、存在意義があるのだ。
やはり、自然(nature)と調和している限り、科学スタイルの多様性は、尊重されるべきなのだ。
※そもそも、科学スタイルの多様性が尊重されてきたおかげで、これまで、科学は、存続&進化してこられたのであり、これからも、そうであるはずなのだ。
「人間が観測&応用できる範囲の自然(nature)を厳密に、正確に記述する物理学」と「人類が、どうあがいたって観測できないミクロのレベルを含めて、自然(nature)を合理的に、そして、具体的に探求する物理学」の間には矛盾はなく、両者は、調和的に共存できるものなのだ。
※ときとして、「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」や「ハイゼンベルグの不確定性原理」のサイドが、我が身の存在意義を死守せんとすべく、悲しいことほどに、排他的、独善的、教義的… になってしまったことがあったように見受けられるが── そもそも、そのようにしなければならい理由、必要性… はどこにもなかったのだ。 なぜなら、そのままで、ある種の大切な真実を示してくれているのであり、もう十分に存在意義があるからである。 これまでも、これからも──。
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が持っている姿勢──科学スタイル
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“人類に観測できない、ミクロの自然(nature)”について、「視覚的な描像を得ることを、決してあきらめない」という姿勢(科学スタイル)を持ち続けることによって、育まれているモデルである。
この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)という「人類が、どうあがいたって観測できない、ミクロの自然(nature)を、合理的に探求する物理学」を、「ハイゼンベルグの不確定性原理」自体は、本来は、決して禁止していない。
なぜなら、この不確定性原理は、本来は、「人類の観測&応用事情」を示す原理、すなわち、ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)が、どういう関係にあるかという自然(nature)を示してくれる原理であり── (人類を含まないところの、“人類の観測”と言うノイズのない)ミクロの自然(nature)そのものがどうなっているかを示す原理ではないからである。
不確定性原理に禁止されるどころか、逆に、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、この不確定性原理が、どのようにして成り立つのか、すなわち、ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合いが、どのようにして成立しているかを、「より深いレベルの階層」から、包括的に説明することができるものである。
たしかに、「実在しない確率の波の重ね合わせが先に存在し、観測とともに波が一点に収束する」という「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」には、確かに、「どうあがいたって人類には視覚化できない、得体の知れないものがそこにある」という“あきらめ感”をもたらしうるかもしれない。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、根底にある実体像の視覚化を決してあきらめないことによって、逆に、「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」が、なぜ、これほど有効に機能するか(成功しているか)を説明できるものなのである。
こういったことが可能となるなのは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が、「想像力と理論の力」によって、“人類にとって、どうあがいても観測できない、ミクロの自然(nature)”について、視覚的な描像(true picture at Planck scale)の探求し続ける」という姿勢を持っているからこそなのだ。
こういった“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が持っている姿勢(科学スタイル)は、本来は、物理学の発展において、きわめてメジャーなものであった。
なぜなら、そもそも、「地動説」が最初に唱えられた当時は、「地球が回っていること」そのこと自体は、決して直接に観測できないことだったからである。
(すなわち、「地球が回っている」は、最初は、「想像力と理論の力」の産物に他ならなかったのだ)
そして、同様に、「原子も、クォークも、中間子も、重力波も、重力子も…」も、少なくとも最初は、観測できなかった中で考え出された「想像力と理論の力」の産物だったからである。
※「原子も、クォークも、中間子も、重力波も、重力子も…」の中には、考え出された当時は全く観測できなかったものの、後に、“ある限度(限界)内で”、観測できるようになったものがある。 なお、その観測における“限度(限界)”を示しているものが、不確定性原理にほかならない。 よって、この観測上の“限度(限界)”を越えた観測は、今後とも不可能であり続けることになる。 そのことが、「人類にとって、どうあがいても観測できない、ミクロの自然(nature)」が存在する理由の1つである。
つまり、「(観測できない)自然(nature)を、想像力と理論の力を使って探求する」というのは、本来、科学──“真実の探求”の王道の一部であったはずなのだ。
したがって、「人類が、どうあがいても観測できないこと」を認めた上で── 「(人類の観測というノイズのない)純粋なミクロの世界の自然(nature)そのものだけ」、すなわち、「本来、人類の有無に関係なく実在しているはずの、さらにズームインしたところのミクロの自然(nature)そのものだけ」の実体像(内部構造)を、想像力と理論の力(合理的な自然な世界観(3Steps原理))を持って、探求していこうとしている“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の科学スタイルは、本来は、決して、物理の王道から外れたものではないのだ。
ところが、「人間が観測&応用できる世界についての自然(nature)を厳密に、正確に記述する物理学」という科学スタイルの応用上の成功は── いつしか、「観測できないミクロの世界の自然(nature)についての探求は、あきらめるべきだ、意味がない、すべきではない…」という姿勢を、物理学の世界に蔓延させることとなった。
その“あきらめる姿勢”は、「量子論の完成(完全な量子論)」から、人々を遠ざけた。
そして、「現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”」をもたらす大きな原因の1つとなった──。
ここで対照的な2つの「科学スタイル(姿勢)」を整理しておく。
|
「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」
「ハイゼンベルグの不確定性原理」
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
人類が観測できないミクロの世界
の探求についての考え方
|
視覚的な描像(true picture at Planck scale)の探求をあきらめよう。
観測できない以上、それは無意味なのだ。
|
視覚的な描像(true picture at Planck scale)の探求をあきらめない。
それにも意味がある。 |
|
重視するもの
|
「観測値&応用」と
主に抽象的な数式
|
「観測値&応用」と
主に具体的な図形(モデル)&具体的な数式
そして、想像力(思考実験、思考観測…)と
理論の力(合理的な自然な世界観(3Steps原理))
|
|
数式
|
抽象的
ときに複雑難解、ときにあいまい
|
具体的
シンプル、明確
|
|
間違えるリスク
|
小さい
※ しかし、“抽象性にともなう間違えるリスクの低減”と
引き換えに“失うもの”がある。
|
大きい
※しかし、“具体性にともなう間違うリスクの高さ”と
引き換えに“得るもの”がある。
|
|
よりズームインした
ミクロの自然(nature)について
の具体的な描像の探求について
|
“あきらめ”や“思考停止”を促している
|
探求を促す
|
|
視覚的な描像
|
「視覚的な描像」を持てるということは、
間違いであることを意味する。
|
「視覚的な描像」こそ、探求すべきもの
なぜなら、「視覚的な描像」があることによって
“どのようなしくみで、そうなってるのか”
を明確に説明&理解できるからである。
|
|
間違いについて
|
間違えてはいけない。
※間違いに対する過度の恐れによって
(or間違いに気づこうとしないことによって
or間違いに気づきにくいことによって)
物理学を停滞させてしまっている可能性がある。
|
間違えられる分、進化できる。
※間違いは、気づいて活用できるのであれば、
物理学が進化できるチャンスである。
|
|
数式について
|
数式に慣れることを促す
(つべこべいわずに慣れればよいのだ)
|
“100数式”は、“1図”にしかず
|
|
他の理論に対する姿勢
|
ときとして
排他的、独善的、教義的
|
包括的(包含的)、サポート的、網羅的
「自然(nature)と調和している限り、科学スタイルの多様性は、尊重されるべきである」
|
|
“波と粒子の二重性”
|
(幾何的な実体像の)視覚化は不可能
得体の知れないもの
相補性原理の根拠
|
(幾何的な実体像の)視覚化は可能
シンプルな実体として統一的に説明できる。
“光子や電子”等のモデル化の根拠
|
|
波動関数ψの意味
|
「実在とは無縁の“確率を意味する波”」
|
「実在する“消滅と生成の波”」
(→下記説明)
|
|
因果律
|
“波の収束”については、ない
|
常に、ある
(決定論的カオス、“消滅と生成の波”…)
|
|
根拠・原理
|
ボーアの哲学(相補性原理)、ハイゼンベルグの哲学
(不確定性原理、ΔEΔT〜h、ΔpΔx〜h))
|
自然な世界観(3Steps原理)
(“(単振動振幅)確定性原理”、ET=h、pλ=h)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)」と「ハイゼンベルグの不確定性原理」で支えられている量子論を、否定するものではななく、それらを包含しつつ、量子論の完成を助けんとするものである。
|
「量子論の完成」を助ける“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は──
これまで、不確定性原理、コペンハーゲン解釈(確率)、相補性原理、多世界解釈… によって、うやむやに説明されてきた“量子論の世界”、すなわち、《量子ゆらぎ、対生成&対消滅を繰り返す真空、非局所性(量子もつれの現象)、粒子と波の二重性、二重スリットの実験での縞模様…》を含む“量子論の世界”を、各ミクロのレベルの自己組織化が積み重なって“創発してきている”ものとして説明するものである。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── 量子論の世界は、一見“どんなに奇妙に見える”ふるまいであっても、「より深いレベルの階層」に存在する単純な要素(素スピノール)から、自己組織化によって生まれてきた創発現象にすぎないものなのである。
※核子やレプトンの生成レベルのところで、電子やクォークの波動性の生成が創発することが示されている。
つまりは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、量子論の世界(様々な観察結果、その奇妙に見える現象…)を、因果的&実在論的に説明できることを示しているのである。
このように「量子論の世界を“因果律にしたがう実体から創発される現象”として説明することが可能である」ということは── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、(「これまで、量子論がどのようなしくみで成功してきたか」を説明するのみならず)、アインシュタインが待ち望んでいた「量子論の完成」を、おおいに助けるものであることを意味しているのである。
《電子の波動性と波動関数ψ──シュレーディンガー方程式》
そもそも、シュレーディンガー方程式は、「ド・ブロイの物質波」の理論を取り入れて生まれたものであった。
すなわち、波動関数ψは、本来、「空間を伝わる電子波」を表すはずのものであった。
※『量子は空間を伝わるときには波動として伝わり, 物質と衝突するときには粒子として振舞う. 空間を伝わる電子波を表す, 時刻t と座標x, y, zの関数ψ(x, y, z, t)を波動関
数と呼ぶ. 〜 電子波の伝わり方を表す法則, すなわち, 波動関数を決める方程式は、1926年にシュレーディンガーが発見したシュレーディンガー方程式である. 』
(p.40 裳華房テキストシリーズ-物理学 『現代物理学』 原康夫著 裳華房 下線は筆者による)
しかし、シュレーディンガー自身、出来上がったシュレーディンガー方程式の中の波動関数ψについての解釈に苦労した。
|
『虚数 i を含む複素数がそこに入ってくることにシュレーディンガーは気づいた。彼は、自分の波動理論に複素数が出てくるのに頭を痛め、なんとか排除しようとがんばった。しかし、そうはできなかった。彼が頭を痛めたのは、複素数には二つの部分──実部と虚部──があり、虚部があるということは、波動関数には、直接観察できない位相があるということを意味していたからだ。位相とは、アナログ時計の針の角度のように周期的に変化する量で、位相に虚部があるということは、そこには直接測定できない部分があるということだった。位相の虚部は、時間の経過に従って振動しているのに、外部からはそれを見ることができない、つまり、それを「リアリティー」として見ることはできないということだった。 シュレーディンガー方程式は、多次元の「配位空間」の中で「波打って」いる何かを描いているのだった。』 (p356 『世界でもっも美しい10の物理方程式』 ロバート・P・クリス 吉田三知世・訳 日経BP 一部省略 下線は筆者による)』
|
そして、シュレーディンガー方程式についての、シュレーディンガー自身による解釈(「波動一元論」&波束、「重み関数」)は、失敗に終わった。
(参考 p.85〜87『光の場、電子の海 量子場理論への道』新潮社)
以下に示すように、現在の物理学界では、「波動関数ψは、実在する物理的何かに対応するのではなく、ψの“絶対値の2乗”が存在確率を意味すると解釈する」というのが主流となっている。
|
『時刻tに場所(x, y, z)電子を検出しようとする場合に, 電子を発見する確率は │ψ(x, y, z, t)│2に比例する』(p.40 裳華房テキストシリーズ-物理学 『現代物理学』 原康夫著 裳華房)
『現在では、波動方程式の解となるψそのものが物理的に存在していると考える物理学者はほとんどいない。ψは確かに何かを表しているのだが、それが何なのかを確信することができないのだ。
波動関数ψについての最も実用的な解釈は、1926年にマックス・ボルン(1882〜1970)によって与えられた。それによると、ψの波形を持った何かが実在するのではない。 ψはある事象が起きる確率を表すというのである。〜 この解釈は、「電子とは何か」といった根源的な謎を不問に付しているものの、実際に波動関数を使って計算する際には最も便利で破錠のない解釈なので、現在でも通用している。』
(p.89『光の場、電子の海 量子場理論への道』新潮社 太線の下線部は、原文では、傍点であった。 他の下線は、筆者による)
『その二、三ヶ月後、こんどはヴォルフガング・パウリが、波動方程式の解釈を一歩進めた。〜 ボルンはψを状態の確率と解釈したが、ここにきてパウリは、ψは粒子の確率だと主張した。つまり、ψ2は、一個の電子がある位置に存在する確率を表していると言うのだ。 パウリのこの立場は、ψ関数からリアリティーを完全に剥ぎ取ったものであり、したがってシュレーディンガーの解釈からは一層遠く離れたものだった』
(『世界でもっとも美しい10の物理方程式』 ロバート・P・クリース 吉田三知世・訳 日系BP 下線は、筆者による)
…
|
つまり、現在の物理学界では── 波動関数ψそのものは、『何かの“物理的な実体”に対応していると解釈することはできるものではなく、 ψの「絶対値の2二乗」が“存在確率”を表すと解釈できるものである』としているのである。
以上のような状況について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、何か貢献できるだろうか?
できる。 それは、次の3点においてである。
1.『波動関数ψそのそものが、何なのか? 波動関数ψが意味する、幾何学的な実体像(物理的な実体)とは、どのようなものか?』を、
ずばりと示す。
2.『どうして、ψの「絶対値の2二乗」は、存在確率を表すと解釈できるのか?』を説明する。
3. シュレーディンガー方程式の価値を取り戻す。
|
1. 波動関数ψそのそものが、何なのか?
波動関数ψが意味する、幾何学的な実体像(物理的な実体)とは、どのようなものか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次のように説明する。
電子は、電子ヒッグス場(電子ヒッグス場ユニットの総和)の中を進む際に、消滅と生成を交互に繰り返す。
この「電子の消滅と生成の繰り返し」は、波に相当する。
すなわち、“電子ヒッグス場(=電子ヒッグス場ユニットの総和)”と電子の相互作用が、電子の波としての振る舞いを創発するのだ。(→結果3)
まさに、この「電子ヒッグス場(電子ヒッグス場ユニットの総和)の中で生じる、電子の“消滅と生成の繰り返し”の波」こそが、波動関数ψの意味である。
※この波が創発する過程は、電子が質量を獲得する過程ではないことは、前に述べた。
すなわち、電子の運動エネルギーも、電子ヒッグス場ユニットに蓄えるエネルギーの和も、常に一定となる。
(→結果3 《「電子の運動エネルギー&電子ヒッグス場ユニット」による、電子の質量の獲得》)
電子が消滅と生成を繰り返す様子を簡単に図示すると次のようになる。
左巻き電子が運動してきて、電子ヒッグス場ユニットに近づく。
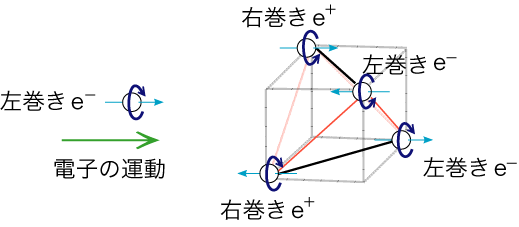
|
→ |
左巻き電子がで電子ヒッグス場ユニット(eHU)の中の
右巻き陽電子と結びつくことによって消滅する。
と同時に、新たな四極子が生成する。
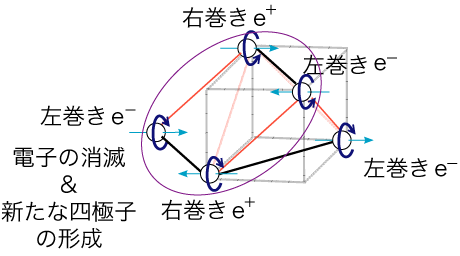
※紫の楕円で囲んだ4つの素スピノールが新たな四極子である
|
|
↑
|
|
↓
|
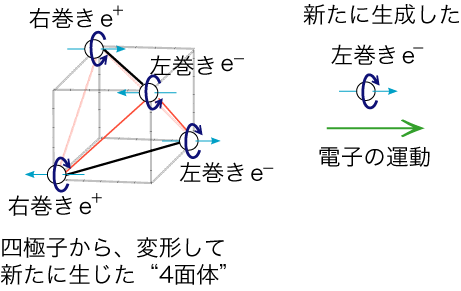
| ※四極子が“4面体”に変形する過程で、新たな電子が生成する。 |
|
※結果3で、『電子ヒッグス場ユニットと電子の相互作用の詳細』を説明する際に示した図を簡略化したものである。
ある運動エネルギーを持つ電子が、ある電子ヒッグス粒子ユニットの中の陽電子とペアを作り消滅しては、新たに電子が生成する。
新たに生成した電子は、その後、別の新たな電子ヒッグス場ユニットの“4面体”まで運動し、再び、消滅する。
そして、新たに生成しては、また消滅する。…
電子は、消滅と生成を繰り返しながら、運動を続ける。
この電子ヒッグス場の中での「電子の消滅と生成の繰り返し」の全過程は、まさに、“波”と見なすことができるものである。
そして、「電子の消滅と生成の繰り返し」こそが、(ド・ブロイが考えた)“電子の物質波”(電子の波動性)の実体であると考えられる。
つまりは、「電子の消滅と生成の繰り返し」こそが、「ド・ブロイの物質波」の理論を取り入れて生まれたシュレーディンガー方程式の解である波動関数ψが、意味する幾何的な実体像に他ならないのである。
しかも、この 「電子の消滅と生成の繰り返しの波」は、“電子の存在度”(電子の存在確率)が周期的に変化している波と解釈できるもにほかならないので、つじつまがあっている。
※なお、この「電子の消滅と生成の繰り返しの波」にともなって電子の存在度が変化する結果── 電子が持つ重力子の放出源として働き続ける能力(=電子の質量)の方も周期的に変化することとなる。
すなわち、定常状態において、電子は、その軌道運動の速さv[m/s]を変化させないのに関わらず、電子の存在度、すなわち、質量エネルギー(静止質量エネルギー+運動エネルギー(=m0c2(1−v2/c2)-1/2(m0:静止質量)、低速の場合≒m0c2+m0v2/2)が波打つのである。
そのことは、『仮説3.4 クォークやレプトンの粒子と反粒子(例えば、「電子e−と陽電子e+」、「アップクォークuと反アップクォークu」、「ダウンクォークdと反ダウンクォークd」)が対消滅する場合は、 これらを構成するプラスプレオンとマイナスプレオンがペアになることによって、プレオン∴ヒッグス場ユニットと相互作用できなくなるので、そのプレオン∴の物質波(生成と消滅の波)が消滅する。』によって説明できる。
それは、次のようになる。
この仮説により、静止質量(m0[kg])が波打つことを説明できる。
すなわち、電子が消滅する際は、電子が持っているスピン(プレオン∴ヒッグス場ユニットとの相互作用)が失われる結果、静止質量エネルギーが失われ、逆に、電子が生成する際は、電子が持っているスピン(プレオン∴ヒッグス場ユニットとの相互作用)が復活する結果、静止質量エネルギーが増加すると説明できる。
そして、静止が波打つのに伴い、質量エネルギー(静止質量エネルギー+運動エネルギー(=m0c2(1−v2/c2)-1/2(m0:静止質量)、低速の場合≒m0c2+m0v2/2)も一緒に波打つこととなる。
(なお、定常状態の場合、1つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)に蓄えられるエネルギーは、もう1つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)から開放されたエネルギーに等し
い。このしくみにより、軌道運動する1つの電子には、軌道運動の方向に働く力が0になり(=電子は、軌道運動の方向に、加速や減速が生じなくなり)、等速で運動し続けるのだった)
以上の説明、すなわち、「電子の消滅と生成の繰り返し」の波こそが、(ド・ブロイが考えた)“電子の物質波”(電子の波動性)の実体であり、電子についてのシュレーディンガー方程式が表記している“波動関数ψ”が意味する物理的な実体であるという説明にもとづき── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次のような定義をする。
定義4.1 波動関数ψの実体は、(電子等の)「消滅と生成」の繰り返しの波である。
※この定義は、シュレーディンガー方程式についての次の記述とも調和している。
『虚数 i を含む複素数がそこに入ってくることにシュレーディンガーは気づいた。彼は、自分の波動理論に複素数が出てくるのに頭を痛め、なんとか排除しようとがんばった。しかし、そうはできなかった。彼が頭を痛めたのは、複素数には二つの部分──実部と虚部──があり、虚部があるということは、波動関数には、直接観察できない位相があるということを意味していたからだ。 位相とは、アナログ時計の針の角度のように周期的に変化する量で、位相に虚部があるということは、そこには直接測定できない部分があるということだった。位相の虚部は、時間の経過に従って振動しているのに、外部からはそれを見ることができない、つまり、それを「リアリティー」として見ることはできないということだった。 シュレーディンガー方程式は、多次元の「配位空間」の中で「波打って」いる何かを描いているのだった。』
(p356 『世界でもっも美しい10の物理方程式』 ロバート・P・クリス 吉田三知世・訳 日経BP 一部省略、下線は筆者による)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれぱ、「「波打って」いる何か」とは、「(電子等の)「消滅と生成」の繰り返しの波」に他ならない。
すなわち、シュレーディンガー方程式の解、波動関数ψは、「(電子等の)「消滅と生成」の繰り返しの波」を描いているのである。
※上記のような「複数の電子が協力してできる“消滅と生成の波”の創発」が可能なのは、どの電子も100%同じことに依存している。 「どの電子も100%同じ」であることは、各種の原子に“同位体”といった多様性があることと対照的である。(このことは、シンプル一様化原理と合致する)
このような「“消滅と生成の波”の創発」を支えるしくみ、すなわち、「どの電子も100%同じであること」は、「トンネル効果」とも、関連があると思われる。(詳細な検討は、今後の課題である)
2. どうして、ψの「絶対値の2二乗」は、存在確率を表すと解釈できるのか?
波動関数ψは、実数ではなく複素数である。 すなわち、波動関数ψは、実部と虚部からできており、位相θを用いて、単純に表記すると次のようになる。
ψ=cosθ+isinθ θ=2π(1/T−1/λ)
※ψ=cosθ+isinθ=eiθとなるが、“eiθ”の項は、省くこととする
ここで、複素平面(ガウス平面)を思い出そう。
『実数x を数直線(x軸)上の点と1対1対応させられるように、複素数z=x+iyをxy平面上の点と1対1対応させられる(図〜). この平面を複素平面あるいはガウス平面という. 極座標r、θを導入すると、複素数の実数部xと虚数部yは
x=cosθ y=isinθ (2.25) と表される.』
(p.29『岩波基礎物理シリーズ5 量子力学』 原康夫 岩波書店 一部省略。 下線は筆者による)
|
複素数の一種である「波動関数ψ=cosθ+isinθ」を、この複素平面(ガウス平面)上で示すと次のようになる。
※「波動関数ψ=cosθ+isinθ」という複素数を、複素平面(ガウス平面)の上の点(上図のピンクの点)として、1対1に対応させて示すことができる。
※位相θが変化すると、オレンジ色で示した円上を、波動関数ψの値に1対1で対応する点(ピンクの点)が移動することになる。 |
ここで、波動関数ψの中の実数部分(実数軸x=cosθ)は、観測できる部分、すなわち、“生成度”を意味し、虚数部分(虚数軸y=sinθ)は、観測できない部分、すなわち、“消滅度”を意味すると考えてみよう。
※波動関数ψの中の実数部分(実数軸x=cosθ)は、観測できる部分、すなわち、“生成度”を意味し、虚数部分(虚数軸y=sinθ)は、観測できない部分、すなわち、“消滅度”を意味すると考えると──
位相θが変化に伴って、オレンジ色で示した円上を、波動関数ψの複素数に対応する点が移動する様子は、消滅と生成の繰り返しを意味していることが読み取れる。
位相がπ/2変化するごとに、消滅→生成→消滅→生成… が繰り返されていることもわかる。 |
生成度を示す「実数軸のx=cosθ」を生成波と呼び、消滅度を示す「虚数軸のy=sinθ」を消滅波と呼ぶことにしよう。
すると、「波動関数ψ=cosθ+isinθ」は、実質的には、「生成波と消滅波の和である」と解釈できることを意味する。
電子の“物質波”にしぼって、図示すると次のようになる。
※オレンジのcosθの波が、“生成度”を意味する生成波である。 グリーンのsinθの波が、“消滅度”を意味する消滅波である。
※電子が電子ヒッグス場ユニット(eHU)から離れているほど(電子ヒッグス場ユニット(eHU)の中間地点に近いほど)、オレンジのcosθの波、すなわち、生成波の山や谷が大きいことが読み取れる。
逆に電子が電子ヒッグス場ユニット(eHU)に近づいているほど(電子ヒッグス場ユニット(eHU)の地点に近いほど)、グリーンのsinθの波、すなわち、消滅波の山や谷が大きいことが読み取れる。
すなわち、電子ヒッグス場ユニット(eHU)の間隔の中央が、最も電子の生成度が高く、 オレンジで示したcosカーブが相当する。 一方、電子ヒッグス場ユニット(eHU)の場所そのものが、最も“消滅度”が高く、グリーンで示したsinカーブが相当することが読み取れる。
※生成波と消滅波は、互いに位相がπ/2だけずれている。
(だからこそ、位相がπ/2ごとに、生成と消滅を繰り返す)
※生成波は、“プラスの存在度”を意味する存在波と呼べるものである。
消滅波は、“マイナスの存在度”を意味する非存在波と呼べるものである。
※オレンジのcosカーブが“電子場”に相当すると言える一方、が、グリーンのsinカーブが“電子ヒッグス場”に相当するとも言える。
※ 電子ヒッグス場ユニットと電子ヒッグス場ユニットの間の間隔は、電子の物質波の波長の半分(λe/2)である。
|
上図は、“自由電子”(ポテンシャルエネルギーV=0)の片道の物質波を意味する波動関数ψ=cosθ+isinθが示す幾何的な実体像であると言えるものである。
定常状態(定在波の状態)になると、いわば、“往路と復路”が重ね合わさることになる。
すると、次のようになる。
※定常状態(定在波の状態)の場合、オレンジのcosθの生成波が、増幅するのに対し、グリーンのsinθの消滅波が打ち消し合うことになることが読み取れる。
つまり、定常状態(定在波の状態)の場合は、波動関数ψの総和は、ψ=2cosθ と実数部分だけになると考えられる。
このことは、井戸型ポテンシャル、調和振動子、水素原子といった系におけるシュレーディンガー方程式の解が、実数部分からなる理由を示していると思われる。
すなわち、この理由は、「定常状態(定在波の状態)の場合では、波動関数ψの往路と復路の合計において、虚数部分がキャンセルされ、実数部分だけになるからである」と説明できる。
※生成波と消滅波は、π/2(90度)分だけ位相がずれており、その際、進行方向に対して、消滅波の方が必ず先行している。 だからこそ、定常波の場合(定常状態の場合)── 消滅波のみが、打ち消し合うことになると考えられる。
|
つまり、定常状態(定在波の状態)では、“生成波”(実数軸のx=cosθ)だけを考えればよいことになる。
すなわち、「井戸型ポテンシャル、調和振動子、水素原子…」といった定常状態(定在波の状態)において── 波動関数ψは、実数部分のみ、すなわち、“生成度”を意味する生成波に比例する部分のみで構成されるようになるのである。
このことは、波動関数の絶対値の二乗が“存在確率”に比例する量と解釈されていることと調和している。
すなわち、「井戸型ポテンシャル、調和振動子、水素原子…」といった定常状態(定在波の状態)における、“生成度”を意味する生成波に比例する部分のみで構成される波動関数ψの“絶対値の二乗”は、まさに、“存在度”に対応するものに相当するからである。
(合計が1になるように、計算によって“規格化”すれば、存在確率になるのは当然である)
※定常状態(定在波の状態)でない場合は、シュレーディンガーの波動方程式を解くことが困難になるのみならず── 波動関数の絶対値の二乗が“存在確率”に比例する量にならないと考えられる。
なぜなら、定常状態(定在波の状態)でない場合は、例えば、波動関数「波動関数ψ=cosθ+isinθ」の絶対値の二乗は、ψ*ψ=(cosθ+isinθ)×(cosθ−isinθ)=cos2θ+sin2θ=1 と、位相に関わらず一定値となるからである。(逆に、定常状態(定在波の状態)の場合は、波動関数が、波動関数ψ=(cosθ+isinθ)+(cosθ−isinθ)=2cosθとなり、その絶対値の二乗は、“存在確率”に比例する量になる)
波動関数の絶対値の二乗が“存在確率”に比例する量でなくなる理由は、波動関数ψの中に、虚数部分の消滅波の成分が残っているからに他ならない。
だとすると、定常状態(定在波の状態)であることと、波動関数の絶対値の二乗が“存在確率”に比例する量になることには、きってもきれない関係があることになる。 すなわち、波動関数ψの絶対値の二乗が“存在確率”に比例する量になるための必要条件が、「定常状態である」ということなのだと考えられる。
※なお、「「波動関数ψ=cosθ+isinθ」の絶対値の二乗は、ψ*ψ=(cosθ+isinθ)×(cosθ−isinθ)=cos2θ+sin2θ=1 と、位相に関わらず一定値となる」ということは、「電子は、たとえ消滅しているように観測されていても、実は、完全には消滅していない(単に陽電子とペアを組んだり、陽電子とのペアを解消したりしているだけである)。 すなわち、生成しているように観察されていようが、たとえ消滅しているように観測されていようが関係なく、実は、電子は、常に実在している」と解釈できることを意味しているのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
また、虚数部分の消滅波「i sinθ」の方は、単に二乗すると「−sin2θ」となることから、“消滅度”、“非存在度(マイナスの存在度)”すなわち、“消滅確率(非存在確率)”に比例する量と言えるのかもしれない。 すなわち、波動関数ψの中に、虚数iが存在する理由は、電子の消滅度を意味する消滅波を表記するためであった、ということになるかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
※存在確率に比例すると考えられるcos2θの変化と、“消滅確率(非存在確率)”に比例すると考えられるsin2θの変化を、重ね合わせて図示すると次のようになる。
※波動関数の絶対値二乗ψ*ψの中のcos2θ、sin2θの変化のグラフを合わせて図示している。
※cos2θ、sin2θは、ともに二乗なので、常に正の値になっていることがわかる。
当然、cos2θ変化と、sin2θの変化の合計は、1であり、常に一定となる。
※なお、この図は、“ニュートリノ振動”における、例えば、電子ニュートリノの割合と、ミューニュートリノの割合の関係を示す図と相似なものとなっている。
このことは、大きな2つのことを示唆しているのかもしれない。
1つは、『「電子の生成←→電子の消滅」の波は、実は、「電子の生成←→ミューオンの生成」の波と、本質的に、同じものであると見なすことができるものかもしれない』ということである。
なぜなら、電子ヒッグス場ユニットの中の陽電子と電子が、対消滅したあとの“残り”は、ミューオンの組成と同じものに他ならないからである。
もし、電子のエネルギーが十分に大きければ(高エネルギーの電子の場合)、「電子←→ミューオン」のように振動すると予想される。 しかし、p=h/λ により、電子のエネルギーが大きいほど、電子波の波長は、短くなる。 したがって、「電子←→ミューオン」となるような高エネルギーの電子波の波長は、水素原子の最内殻の電子の波長よりも短いものであろう。 この辺りが「電子←→ミューオン」の波の観測を難しくしているのかもしれない。(詳細な検討は、今後の課題である)
(正しければ、“電子の消滅”は、実は、“ミューオンの生成”に他ならなかったということになる)
もう1つは、『ニュートリノの振動の実体は、ニュートリノと、ニュートリノヒッグス場ユニット(νeHU)の相互作用であるかもしれない』ということである。 なぜなら、抽象的な数学(量子力学(実在しない確率の波の“重ね合わせ”)…)を駆使して予想され、実際に観測された“ニュートリノ振動”の幾何的な実体は、『ニュートリノと、ニュートリノヒッグス場ユニット(νeHU)の相互作用である』と考えるとつじつまが合うように思われるからである。
例えば、「電子ニュートリノ←→ミューニュートリノ」の振動は、「電子←→ミューオン」の振動よりも、低いエネルギーで生じるからこそ、観測しやすいのだと考えられる。
(詳細な検討は、今後の課題である)
|
以上からも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、シュレーディンガーの波動方程式の中の虚数 i が示唆する“観測できない部分を含む波動”、すなわち、波動関数ψの正体についての定義──、 「定義4.1 波動関数ψの実体は、(電子等の)「消滅と生成」の繰り返しの波である。」は、的外れではないことがわかる。
電子は、“消滅と生成”を繰り返しながら、電子ヒッグス場(=電子ヒッグス場ユニット(eHU)の総和)の中を移動し続けている。
その電子の「“消滅と生成”を繰り返し」、すなわち、「“電子の存在度”が変化する様子」をシュレーディンガーの波動方程式が表記している。
シュレーディンガーが解くことができるのは、定常状態(定在波の状態)の場合であり── その場合、波動関数ψは、実数部分、すなわち、生成波のみで構成されているので、その絶対値の二乗は、存在度、すなわち、「ある場所に電子が存在する確率」ときってきれないものとなるのである。
3. シュレーディンガー方程式の価値を取り戻す。
以上のような説明を可能にするという意味からも、シュレーディンガー方程式は、(ハイゼンベルグの行列力学にはない)非常に高い価値を持っていることがわかる。
確かに、シュレーディンガー方程式と、ハイゼンベルグの行列力学は、数学的には、等価であると言えるのかもしれない。
しかし、そのイメージ喚起性、すなわち、「ダイナミックに生き生きと電子の振る舞いを示してくれる」ことを含め、物理的には、等価ではないのである。
シュレーディンガー方程式についてのシュレーディンガー自身による解釈は、失敗してしまったが── そのことは、“シュレーディンガー方程式”自体の価値を低める理由であってはならない。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、このシュレーディンガー方程式と調和している。
シュレーディンガー方程式は、「“電子ヒッグス場(=電子ヒッグス場ユニット(eHU)の総和)”と電子の相互作用」というミクロの自然(nature)の本質を、ダイナミックに生き生きと、そして、厳密に示してくれる式なのである。
《電子の定常状態と電子軌道》
“定常状態”(運動エネルギー順位Knが一定)において、電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)は、“単振動”的に相互作用する。
そうすると、一見、「単振動に伴い、電子が加速or減速していることになので、電子の“運動エネルギー、速度、波長”が変化することになってしまうので、矛盾している」ように思われる。
しかし、ここに問題はない。 その理由を以下で説明する。
“定常状態”(運動エネルギー順位が一定)において、電子に作用する、「電子ヒッグス場ユニットが生じるポテンシャルエネルギー」は、次のように変化すると考えられる。
※各電子ヒッグス場ユニットが生じるポテンシャルエネルギーが、色別に示してある。
運動している電子には、常に、“2つのポテンシャルエネルギー”が作用していることが読み取れる。
そして、“2つのポテンシャルエネルギー”が作用することによって生まれる力は、合計が常に0になることが図から読み取れる。
なぜなら、“2つのポテンシャルエネルギー”は、上下逆転しているだけで、同じ形だからである。
(なお、電子に作用するポテンシャルエネルギーを位置で微分したものが、電子に作用する“力”に相当するのであった)
※一方のポテンシャルエネルギーの減少分が、もう一方のポテンシャルエネルギーの増加分に常に等しいことが読み取れる。すなわち、ポテンシャルエネルギーの合計は、常に一定であることが読み取れる。 |
定常状態(運動エネルギー順位が一定)においては、電子に作用する力の合計が0であるということは、定常状態における電子は、軌道運動の方向においては、全く加速していない(等速運動している)ことを意味する。
つまり、定常状態(運動エネルギー順位Knが一定)では、「“生成&消滅の単振動に伴う加速&減速”によって電子の速度や波長が変化してしまう」という問題は、はじめから存在してないことになるのである。
このように、「電子の運動エネルギー順位Knが変化しない限り、光子を放出しない」という説明は、電子が円軌道を取っているときによくあてはまる。
一方、陽子に束縛された電子が、楕円軌道をとっている場合は、電子の運動エネルギー順位Knが変化する以上、光子が放出される。
その際に放出される光子は、まさに原子のスペクトルとして観測されるので問題ないのだった。(→結果1《ボーアの原子模型》)
電子の「1s軌道」、「2s軌道、2p軌道」、「3s軌道、3p軌道、3d軌道」までを簡単に図示すると次のようになる。
※四角は、電子ヒッグス場ユニット(eHU)に相当する。
※2p軌道、3p軌道は、8の字を描くような軌道である。
※3d軌道は、「8の字を描くような軌道」2つ分ではなく、あくまで、「一筆書き」をするような軌道である。
だから、図のようにつぶれていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。 |
例えば、電子軌道の「1s軌道」、「3s軌道」、「3d軌道」の詳細は、次のように図示できる。
|
1s軌道
|
|
|
3s軌道
|
|
| 3d軌道 |
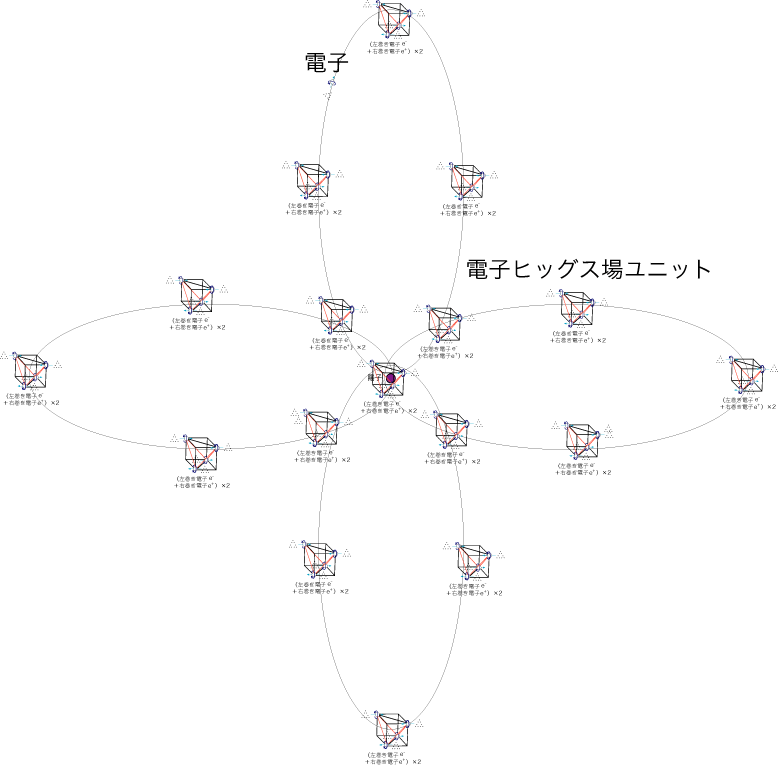 |
|
円軌道であれば、1s軌道は、2s軌道は、3s軌道は、「運動エネルギー順位Kn」が一定なので、光子が放出しない。
一方、2p軌道、3p軌道、3d軌道は、「運動エネルギー順位Kn」を変化させてしまう結果、光子を放出してしまうことになる。 しかし、光子は、エネルギー非保存の所産なので問題ない。
そして、それらの光子は、観測される原子のスペクトルと調和していると考えられる。
|
※つまりは、この「“電子ヒッグス場(=電子ヒッグス場ユニット(eHU)の総和)”と電子の相互作用」は、少なくとも3つを支えることになる。
1.「電子の定常状態(原子内の電子軌道)の獲得のプロセス」
2.「電子の波動性(電子の物質波、電子の波動関数ψ)」
3.「“量子ゆらぎ”」
|
《“電子の軌道運動”とコペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)》
この「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)との相互作用」による「消滅と生成の繰り返し」こそが、電子についての「“ド・ブロイの物質波”、“シュレーディンガー方程式の解である波動関数差ψ”、“波と粒子の二重性”…」の幾何的な実体像である。
この説明は、1つの電子は、生成と消滅をを繰り返しながら、あくまで、たった1つの軌道を運動し続けていることを意味する。
しかし、この「たった1つの軌道を運動し続ける」という描像によって── 「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)が、どのようなしくみで成功しているか」、すなわち、「コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)で説明される世界が、どのように創発するか」をどのように説明できるのであろうか?
以下では、その説明を示す。
例えば、下図のように、1つの陽子の回りを、1つの電子が、(2つの電子ヒッグス場ユニットと関わり)消滅と生成を繰り返しながら、1つの軌道運動している系を考える。
※上の図では、(2つの電子ヒッグス場ユニットから成り立つ)1つの電子軌道を示している。“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”の間の“電子の軌道運動の距離”は、およそ、電子の波長λeの1/2である。
※この配置は、電子軌道の「1s軌道、2s軌道、3s軌道…」の配置と、相似である。
(「1s軌道、2s軌道、3s軌道…」のサイズは、それぞれ異なる)
|
運動エネルギー順位がKn=2π2k2me4/n2h2と定義された電子は、 速さ「vn=2πke2/nh」を持つのだった。(→結果1 《“ボーアの原子モデル”》)
よって、軌道電子のおよその速さvは、vn=2πke2/nh≒3.48×105/n[m/s]と求まる。
(h≒6.6256×10-34[J・s]、静電気力の定数(真空中)k=8.99×109[N・m2/C2] π≒3.14 電子の電荷e≒1.602×10-19[C]とした)
こうして求めた電子の速さは、光の速さの約1/1370ほどであり、およそ秒速2190/n[km]という、かなりの高速であることがわかる。
ただし、1つの電子は、上図のように“特定の2つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)だけ”を、ずっと軌道運動し続けているとは考えにくい。
すなわち、1つの電子と1つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)は、トータルで、3つ以上の自由度(厳密には、電子3つと陽電子2つの“5つの自由度”)を持つので、ここには、決定論的カオスが生じ、電子が相互作用する電子ヒッグス場ユニット(eHU)の相手が、その都度変化し、それにともなって、正確な円から外れた軌道運動をし続けると考えられる。
よって、次の仮説を立てた。
仮説4.1.1 1s軌道、2s軌道、3s軌道… の電子は、それぞれの電子殻の中にある“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”を、くまなく行き渡るように軌道運動することによって、“球状”の電子雲を創発する。
※電子の持つおよそ2.2×106/n[m/s]という速さは、特定の電子殻の中の電子ヒッグス場ユニットをまんべんなく均等に行き渡るのに十分な速さであると思われる。
p軌道、d軌道の電子の場合は、電子が相互作用する、相手の電子ヒッグス場ユニット(eHU)が、ある程度決まっているとしても、やはり、決定論的カオスにより、正確な“八の字”から外れた軌道運動をし続けると考えられる。
よって、次の仮説を立てた。
仮説4.1.2 p軌道、d軌道の電子は、「ある程度、決まった“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”」と相互作用し、なおかつ、その条件の中で、くまなく行き渡るように軌道運動することによって、それぞれの“(回転対称性を持つ)棍棒状”の電子雲を創発する。
s軌道、p軌道、d軌道、いずれにしても、決定論的カオスが、関わっていることになる。
すなわち、1つの電子が、“電子ヒッグス場ユニット”を経て、次に、放出された新たな電子がどのような軌道運動をするかは、電子&陽電子の挙動の総和(より厳密に言えば、“素スピノールの挙動の総和”)として、(確率ではなく)因果律に従って決定されることになるのである。
(すなわち、全く「ランダムな“サイコロが振り”」によって、電子の軌道が決まるのではない)
この、いわば「決定論的な“サイコロが振り”」によって、電子の軌道運動の長時間平均の分布(ある軌道を通過する頻度)は、均等なものとなり── 「s軌道、p軌道、d軌道」が創発するのである。
そして、これらの「s軌道、p軌道、d軌道」は、いずれも定常状態なので、このときの波動関数ψの絶対値の二乗の値は、やはり、“電子の存在度”すなわち、存在確率に比例するものとなる。
つまり、「決定論的な“サイコロが振り”」(決定論的カオス、因果律)に基づいて、電子が軌道運動する結果── その統計的な総和は、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)が生む所の「電子の存在確率」として理解できるものと等価になるのである。
この説明は、まさに、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)がしているところの、『“シュレーディンガー波動関数の絶対値の二乗は、「電子が存在する確率を表している」という解釈』が、なぜ成功しているのかを説明していることを意味する。
(すなわち、このあたりに、「なぜ、コペンハーゲン解釈がうまく機能するか?」の答えがある)
※なお、「電子の存在度=電荷の存在度」であるので、上記の視覚的な描像は、シュレーディンガー自身による「シュレーディンガー方程式について」の解釈── 「電荷&質量密度」であるという解釈とも、結果的に調和すると思われる。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)の間には、大きな違いがある。
その違いは、次のようになる。
|
コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)解釈
|
|
波と粒子の二重性
|
「実在しない波の重ねあわせが先に存在し、
観測とともに波が一点に収束する」
|
(観測に関係なく)「実在する1つの電子は、1つの軌道を進みながら、
消滅したり生成したりを繰り返す波を形成している」
(電子の波は、常に実在している)
|
|
実在性
|
×
(観測するまで実在しない)
|
○
(観測する前から実在している)
|
|
確率
|
「シュレーディンガーの波動方程式の解である
“波動関数ψの絶対値の二乗”は、
電子の存在する確率を意味する」
|
「シュレーディンガーの波動方程式の解である波動関数ψ」は、
定常状態(定在波の状態)においては、
電子の“生成波”のみに相当するものである。
電子の軌道運動は「決定論的カオス」に従うので、
この「電子の“生成波”」は、まんべんなく分散する
ことによって、電子雲を創発できる。
「電子の“生成波”」の二乗の統計的な総和は、
その“電子の存在度”、すなわち、
「電子が存在する確率」に比例するものに相当する。
(計算によって“規格化”すれば、確率になる)
|
|
因果律
|
(波の収束は確率によって決まるので)
保たれていない。
|
電子の挙動は「決定論的カオス」に
従うものであるので、因果律は保たれている。
|
|
自然(nature)像
|
「ランダムネスに支配されたサイコロ」が
振られている。
|
「決定論的なサイコロ」が
振られている。
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「実在しない波の重ねあわせが先に存在し、観測とともに波が一点に収束する」のではなく── はじめから、1つの電子は、1つの軌道を、およそv=3.48×105/n[m/s]で、あくまで、因果律に従い決定論的に軌道運動し続けているだけである。
そして、もし、その統計を取り、平均値を求め、規格化すれば(総和が1になるように調整すれば)── 「結果として、それは確率になる」ということに過ぎないのである。
ミクロの自然(nature)そのものにおいては、“ランダムなサイコロ”が振られているわけではない。
いわば、“決定論的なサイコロ”がふられているのだ。
すなわち、一瞬一瞬で電子がどこへ進むかは、因果律によって確定しているのだ。
つまりは、“ランダムなサイコロ”か“決定論的なサイコロ”かの間には── “因果律があるかないか”という大きな違いが内在しているのである。
ただし、その統計的な平均は、均等にならされるので── 観測結果は、確率によって予想されるもの、すなわち、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)に予想されるものと全く同じになる。
すなわち、電子の軌道運動は、「決定論的カオス」(≒“決定論的なサイコロ”)に依存するがために、長時間平均がまんべんなく均等なものになり(エルゴード的になり)、その電子は、ある場所で、“ある確率で”観測されるようになるのだ。
※「エルゴード的」の意味は、次の記述から理解できる。
|
『例えば、さいころで1の目のでる確率が6分の1だったら、さいころをずっと投げていけば、1の目のでる割合が6分の1に近づく. その確率の方が位相平均で、たくさん投げたときに、1の目のでる割合が時間平均』
(p.1 『エルゴード理論とフラクタル』釜江哲郎・高橋智 シュプリンガー・フェラーク東京)
『長時間平均
統計的、事象的、観察結果
位相平均
計算論的、収束するもの、あるいは一定のサイクルにおさめることの出来るもの、全事象等確率的として推察できるもの
上記の2つの平均が同じような値(あるいは関数)を得られるものについて、エルゴード的ということが出来る』
(ウィキペディア 『エルゴード理論』)
|
※『一般3Steps理論と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)ver1.04』までの論文の中においては、「サイコロが振られていない」というスタンスがとられていた。 その後、その姿勢は、より正確に言えば、「“ランダムネスに支配されたサイコロ”が振られていない」という意味に過ぎないことに気づいた。
そのことに気づかせてくれたのは、『カオス的世界像 神はサイコロ遊びをするか?/ DOES GOD PLAY DICE?』(イアン・スチュアート著 須田不二夫・三村和男訳 白揚社)の中の「サイコロと決定論」(p.360〜)の部分である。 この部分には、「実際の“サイコロ振り、コイン投げ”も、厳密に見れば、決定論にしたがっている(のだから、もし100%の観測が可能ならば、結果の予測も可能になる)」という意味のことが書かれている。
|
『要するに、大切なのは神がサイコロ遊びをするかどうかではなく、どのようなやり方でサイコロ遊びをするかということなのである』
(p.361 『カオス的世界像 神はサイコロ遊びをするか?/ DOES GOD PLAY DICE?』
本文中で“傍点”で示されている部分を太線で表記した)
|
さらには、次のような記述もある。
|
『何らかの新解釈を施された量子力学が、波動関数の確率的な性質を、決定論的でかつカオス的であるようなものに置き換えてしまう可能性が残されている』
(p.361 『カオス的世界像 神はサイコロ遊びをするか?/ DOES GOD PLAY DICE?』 下線は筆者による)
|
この記述は、量子論に「決定論的カオス」を結びつける“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の説明と調和している。 すなわち、この「波動関数の確率的な性質を、決定論的でかつカオス的であるようなものに置き換えてしまう」ような「何らかの新解釈を施された量子力学」に、まさに、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が相当している可能性がある。 (詳細な検討は、今後の課題である)
以上では、電子雲を創発する際に働く、電子が電子ヒッグス場ユニット(eHU)と相互作用するしくみを説明した。
当然、“電子雲”が創発されるためには、中心の陽子が創発するところの“電磁場(電磁気力(by仮想光子))”も必要不可欠である。
※この“電磁場”が、電子が「おおよその“円状、楕円状”の軌道運動すること」を支えることになる。
シュレーディンガー方程式にも、電磁場のポテンシャルエネルギーの項が含まれているのだった。
そして、電子が相互作用する相手は、実は、電子ヒッグス場ユニット(eHU)や電磁場(電磁気力(by仮想光子))だけではない。
他にも、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)とも相互作用をする。 その相互作用の具体的な中身には、電磁波(光子の総和)による散乱、光子の放出(運動エネルギー順位の変化)、重力子の放出(質量の獲得)、重力場(重力子の総和)、弱い力(LP光子を介する“原始的な力”)が含まれる。
これらの相互作用のどれもが“電子の振る舞い”に影響する。
つまり、ある1つの電子の振る舞いは、実際は、非常に多くの相互作用が関係して生じていると言える。
|
電子と相互作用する場
|
電子の振る舞い
|
|
電子ヒッグス場との相互作用
|
電子ヒッグス場の作用→量子ゆらぎ、消滅と生成を繰り返す波動性 |
|
原始ヒッグス場との相互作用
|
電磁場の作用(by仮想光子)による運動(=電磁気力の作用) |
重力場の作用(by重力子)による運動(=重力の作用)
電子の運動エネルギーによる質量(重力子の放出源ととして働き続ける能力)獲得の(→重力場の創発)
|
光子(電磁波)の作用による散乱、
(運動)エネルギーの増加(by運動エネルギー順位の変化)による光子の放出 |
| 弱い力による作用(=LP光子を介する“原始的な力”の作用)(→結果2) |
以上のような“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明は、「確率のみに頼ってきた、これまでの“量子力学”による説明」を、ある意味、一変させる。
なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明は、1つの電子は、その通り道で遭遇する、“時空の基本構造の社会”(素スピノールのネットワーク)の様々な相互作用のすべて── つまり、「電子ヒッグス場、および、原始ヒッグス場などとの相互作用のすべて」を、もし100%把握できれば、そのふるまいを100%予測できることを意味しているからである。
よって次の結論を得られる。
結論4.1 1つの電子のあらゆる振る舞いは── ランダムな確率に従って生じるのではなく、しっかりとした因果律に従って生じている。
よって、「原理的に1つの電子のふるまいの予測が不可能」なのではなく── 実際は、「根底にある現象の“100%の把握(観測)”が困難であることだけが理由で、1つの電子のふるまいの予測が困難」であるに過ぎないことになる。
“100%の把握(観測)”が困難である結果、確率に頼るしかない── という現状になっているだけであり、自然(nature)そのもの、現象そのものが確率(ランダムネス)に支配されているわけではないのだ。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“アインシュタインが求めていた因果律”を取り戻しつつ、なおかつ、“コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)が、どのようなしくみでうまくいくか”を説明するモデルなのである。
一見、矛盾している両者を結びつける(調和させる)キーコンセプトは、「決定論的カオス」である。
※『科学的思索における直観と抽象』(湯川秀樹著作集2 p151)の中には、次のような文章がある。
『量子力学において抽象的な数学の記号で記述されるところを、直観的に忠実に表現するような物質と光の新しい描像を作り上げることは、極度に困難であることが分かってきました。 英国のすぐれた天文学者であり物理学者であったエディントンが一時、波動と粒子の二重性をもった対象に“WAVICLE”という新語を使いましたが、これは大して役に立ちませんでした。 この粒子とか波動とかいった直観的概念が無力なため、物理学者は、確率の概念に頼ることになりました。 確率と言うのは、物理学者にとって、何も真新しい概念ではありませんが、これまでは、問題にしている事物が極端に複雑で、それについての知識が不完全である、と考えられた時にだけ導入されてきたものです』
(下線は筆者による)
|
この記述は、「粒子とか波動とかいった直観的概念」を回復し、量子論に「決定論的カオス」を結びつけることによって、(原理的には(理論上は))確率の概念に頼らなくて済むと考える“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和している。
ただし、やはり、(統計熱力学のように、人類の観測事情のせいで)、現実的には(観測上、応用上)は、確率の概念に頼らざるをえない。 だからこそ、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)が役立つのである。
「3Steps理論と確率的解釈の関係の一般化」
上の引用の一部、『この粒子とか波動とかいった直観的概念が無力なため、物理学者は、確率の概念に頼ることになりました。』
(『科学的思索における直観と抽象』(湯川秀樹著作集2 p151) 下線は筆者による)
という記述から、(具体的な幾何学的実体像という)直観的概念が有力な“完全な量子論”を探究しようとしている“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において、「確率の概念に頼る必要」がなくなっていることが自然であることがわかる。
このことは、一般に、「直観的概念が有力な“完全な説明”があれば、確率に頼らなくて済む」ことを示唆していると思われる。
「直観的概念が有力な“完全な説明”があれば、確率に頼らなくて済む」ということは、“3Steps理論”と確率の関係は、一般に、どのように理解されるべきものなのかのヒントになる。
それを以下に説明する。
例えば、【素粒子の挙動レベル】と、3Steps理論的に相似であるものの一例である【人生レベル】について説明してみる。
例えば、“ゴールデンウィーク or 夏休みの計画──”
といった、頭の中で、あれこれ想像するような場面を考えてみる。
山に行く、海に行く、森に行く、川に行く、動物園に行く、水族館に行く、博物館に行く、映画を見る、家で本を読む、文章を書く… 様々な可能性が存在し、それぞれを思い浮かべることが可能である。
それぞれの可能性が実現する確率の合計は、1以下であり── その中のどれかが実現したとたん、それ以外の可能性は0になる。
誕生日プレゼントの中身の計画──
帰り道の道路の選択──
食事内容の計画──
将来の夢──
…
いずれの場面についても同様に、「ある瞬間、瞬間のそれぞれの人生に様々な可能性があり、それぞれの可能性が実現する確率の合計は、いついかなる時も、“1”以下である。 実現したとたん、その可能性の幅は、一点に絞り込まれる」と説明できる。
一見、人生のふるまいは、確率的な解釈でも十分に説明可能なように見える。
しかし、実際は、人生は、サイコロふりのようなランダムな“確率”だけによって成り立っていることは決してない。
実際には── 【人生レベル】とは、感情、体調、イメージ、連想、言葉活動、思考、意欲、意志、知覚、情報との接し方、知恵、くせ、習慣、個性、性格、人格、アイデア、ひらめき、感性、価値観、社会の見方、周囲の人の言動に対する見方… を含む【細胞の社会レベル】(および、他の人の【人生レベル】の所産)が関わって、創発されるものである。
つまり、自他の“【細胞の社会レベル】の総和”が関わることによって生じる、非確率的な、因果関係のある絞り込みの所産が、【人生レベル】なのである。
つまり、“サイコロ振りで決めよう”“あみだくじで決めよう”“じゃんけんで決めよう”… というような人生のあり方も含め、人生における選択ひとつひとつに、厳然たる、なんらかの因果関係がひそんでいるはずなのである。
結論4.2 【人生レベル】の3Stepsは、たとえ確率的にも解釈できたとしても── 実際は、非確率的な、因果関係を持つ絞り込みによって成り立っている。
※“サイコロを振りながら人生を決めよう”“確率的に生きよう”という意志を燃やすような人生を含め──
もし【細胞の社会レベル】のすべてを100%把握できたとすれば、人生のふるまいを、ある意味100%予測できる。
すなわち、「直観的概念が有力な“完全な説明”があれば、確率に頼らなくて済む」のである。
しかし、実際は、その“100%の把握”が困難であるせいで── 人生のふるまいの予測は困難になる。
すなわち、「直観的概念が有力な“完全な説明”がないので、確率に頼らざるをえなくなる」のである。
かえり見て、電子や光子を含む【素粒子の挙動レベル】はどうか。
ある瞬間、瞬間のそれぞれの電子や光子に様々な可能性があり、それぞれの可能性が実現する確率の合計は、いついかなる時も、“1”以下である。 実際に観察されたとたん、その可能性の幅は、一点に絞り込まれる。
一見、ランダムなサイコロふり──確率によって、支配されているように見える。
しかし、実際は── 【素粒子の挙動レベル】とは、電子や光子などが、通り道において遭遇する各種のヒッグス場をはじめとする“【時空の基本構造の社会レベル】の総和”(それぞれの場、他の素粒子の存在に伴う場… )が関わるものである。 しかも、そこに、“決定論的なカオス”が関わることもあると考えられる。
つまり、自他の“【時空の基本構造の社会レベル】の総和”が関わることによって生じる非確率的な、因果関係のある絞り込みの所産が、【素粒子の挙動レベル】なのである。
すなわち、素粒子のふるまいのひとつひとつに、厳然たる、なんらかの因果関係がひそんでいるはずなのである。
それは、個々の素粒子は、“様々な場の作用を受けながら、特定のルートをたどる”という意味での“個性”を持つという理解に基づいた説明である。
したがって、次の結論を得る。
結論4.3 【素粒子の挙動レベル】の3Stepsは、たとえ確率的に解釈できても── 実際は、非確率的な、因果関係を持つ絞り込みによって成り立っている。
※もし、非確率的な、因果関係を持つ絞り込みを生み出す「“時空の基本構造の社会(素スピノールのネットワーク)”の働きの総和」を100%知ることができれば、すなわち、もし、あらゆる素スピノールの挙動、あらゆる光子、あらゆる重力子の挙動、あらゆるヒッグス場との相互作用… を見る目があれば── “1つ1つの光子や電子がスリットを通って、ある場所にたどり着くこと”を含め、素粒子のふるまいについて、確率の所産としてではなく、因果律の結果として、(決定論カオスが関わることを含めても)100%の予測ができるはずある。
すなわち、「直観的概念が有力な“完全な説明”があれば、確率に頼らなくて済む」のである。
しかし、実際は、その“100%の把握”が困難であるせいで── 1つ1つの光子や電子のふるまいの予測は困難になる。
すなわち、「直観的概念が有力な“完全な説明”がないので、確率に頼らざるをえなくなる」のである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、量子(電子、光子)の1つ1つがスリットを通り、ある1点が発光するという過程は── それぞれ「そのルートで、どのような場と遭遇し、どのように相互作用するか」といった1つの軌道を進む結果として生まれているもの、しっかりとした因果関係(理由)があって起きているものである。
たとえ、観測上の制限により、確率の概念に頼り続ける必要性があったとしても(確率の概念に頼るのが便利であっても)── 決して、ミクロの自然(nature)そのもの自体が、原理的に“確率に支配されている”ことはない。
すなわち、ミクロの自然(nature)においては、やはり、「ランダムなサイコロ」が振られているのではなく、「決定論的なサイコロ」が振られているのである。
【人生レベル】を確率的に説明できるということは── 決して、人生の実体が100%ランダムなサイコロ振りであることを意味しない。
同様に、【素粒子の挙動レベル】(量子論)を確率的に説明できるということは── 量子論の世界の実体が、100%ランダムなサイコロ振りであることを意味しない。
ある1つの人生が奇妙なふるまいをするように見えるのは── 実在する、自他の“細胞の社会の働き”から受ける影響の総和を見ていないからである。
同様に、ある素粒子が奇妙なふるまいをするように見えるのは── 実在する、自他の“時空の基本構造の社会(素スピノールのネットワーク)の働き”から受ける影響の総和を見ていないからである。
3Stepsと確率の関係についての結論は、さらに次のように一般化できる。
結論4.3.2 3Stepsは、どのレベルも確率的に解釈しようと思えばできるが── 実際には、どのレベルも“非確率的な、因果律による絞り込み”によって成立している。
(なお、例えば、各種の量子の振る舞い等、観測上の制限によって、“確率に頼らざるをえない”という状況が生じることは、当然ありうる)
|
※アインシュタインが「サイコロは振られていない」と主張したことの真意は、まさに、「自然(nature)そのもの、現象そのものが確率(ランダムネス)に支配されていることはなく、そこには、因果律があるはずだ。」といったことであった。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、たしかに“因果律”を取り戻しているので、アインシュタインが信じていたところの“完全な量子論(量子力学…)”の理想像に近づいているものであると思われる。
なお、次のような記述もある。
『アインシュタインの物理学の核心にあったものは、観測されるかどうかによらず、「そこ」にある実在へのゆるぎない確信であった。〜アインシュタインのいう実在とは、因果律にのっとった法則に支配される、局所的な宇宙だった。〜アインシュタインは、実在論、因果律、局所性を信じていた。』
( p.458 『量子革命』(マンジット・クマール[著] 青木薫[訳] 新潮社) 下線は、筆者による)
|
つまり、アインシュタインが理想とする“完全な量子論(量子力学…)”は、“実在論と因果性と、局所性”の3つの条件を満たすものであったことがうかがえる。
この3つの条件の中の、“実在論と因果性”の2つについては、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、満たしていることになる。
(“局所性”については、下記の《非局所性(量子もつれ)と重ね合わせの原理についてで説明する)
《電子の波動性と、電子の質量(重力子の放出源として働く能力)──ディラック方程式》
電子が重力子を放出する理由、すなわち、電子の質量エネルギーの起源は、大きく、次の2つにわけられるのだった。
1.電子の静止質量エネルギーによるもの(=電子の内部運動エネルギーによるもの)
2.電子の外部運動エネルギーによるもの
電子の速度v[m/s]、光速c[m/s]において、c[m/s]>>v[m/s]の場合、次のようになる。
|
1.電子の静止質量エネルギーによるもの
(=電子の内部運動エネルギーによるもの)
|
2.電子の外部運動エネルギーによるもの
|
|
創発のしくみ
|
電子のスピンによって創発
(=“(電子を構成する)マイナスプレオンの軌道運動”が、直接、
原始ヒッグス場ユニット(PHU))を変形することによって創発) |
“電子の軌道運動”が、直接、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を変形することによって創発 |
|
エネルギー
|
m0c2≒8.2×10−14[J]
|
m0v2/2≒5.5×10−20/n2[J]
(運動エネルギー順位がKnである電子)
|
※静止質量m0=9.11×10−31[kg]として計算した。
※運動エネルギー順位がKnである電子は、およそv=3.48×105/n[m/s]の速さで、軌道運動する。
※相対論的には、電子の質量エネルギーmc2は、mc2=m0c2(1−v2/c2)−1/2で計算され、c>>vの場合、mc2≒m0c2+m0v2/2 となるのだった。
|
このように、“質量エネルギー”を考慮した「電子と電子ヒッグス場ユニットの相互作用」は、まさに、「相対論的な波動方程式、ディラック方程式」と関連しているテーマである。 (なお、シュレーディンガー方程式は、非相対論的な波動方程式である)
ディラック方程式は、「4成分の量」に対する(連立)波動方程式である。(「4つの波動関数」についての方程式である)。
(参考 『ディラック方程式』 日笠健一著 サイエンス社)
このことは、ディラック方程式は、4つの成分で構成されている“ヒッグス場ユニット”と深い関係がありそうであることがわかる。
ただし、ディラック場は、右巻き粒子、左巻き粒子、右巻き反粒子、左巻き反粒子によって構成されるとのことである。
もし、この“4つ”、すなわち、“右巻き粒子、左巻き粒子、右巻き反粒子、左巻き反粒子”を忠実に反映したもので構成される“電子ヒッグス場ユニット”を考えるならば、それは、次の図のようになる。
※「左巻き電子、右巻き電子、右巻き陽電子、左巻き陽電子」の4種で構成されている。
|
しかし、上図のような“電子ヒッグス場ユニット”は、実在性が乏しいと判断できる。
なぜなら、実在する電子は、すべて“左巻き素スピノール”で構成されており、本来は、左巻きだからである。
(β崩壊で生まれる電子は、本来は、すべて左巻きである。 “右巻き電子”は、観測上(電子を上回る速度で運動する観測系において)、存在すると見なされているものに過ぎず、実際、その量も、左巻き電子より少ない)
(なお、実在する陽電子は、すべて“右巻き素スピノール”で構成されており、本来は、右巻きである)
一方で、次のような記述もある。
|
『ヴァイル場は、ディラック場の自由度を半分にした場である。実粒子の標準理論においては、物質粒子であるクォーク・レプトンは(電子も含めて)すべてヴァイル場として、ラグラジアンに現れる』
(p.83 『ディラック方程式』 日笠健一 サイエンス社 下線は、筆者による)
|
この記述は、実際の自然(nature)において実在する“電子ヒッグス場ユニット”は、上図のような“4種類”から構成されるものではなく、下図のような“2種類”から構成されるものであることを示唆していると思われる。
※「左巻き電子と右巻き陽電子」の2種のみで構成されているので、 「ディラック場の自由度を半分にした」ものに相当している。
これが、“ヴァイル場”の幾何的な実体像であると考えられる。
※「左巻き粒子と右巻き反粒子」から構成されているので、“左巻きのヴァイル場”ということになる。
|
これは、これまで、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で説明してきた電子ヒッグス場ユニット(eHU)そのものである。
そして、『実粒子の標準理論においては、物質粒子であるクォーク・レプトンは(電子も含めて)すべてヴァイル場として、ラグラジアンに現れる』という記述は、「ヴァイル場」と調和した、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の電子ヒッグス場ユニット(eHU)の方が、「ディラック場」と調和した「“右巻き粒子、左巻き粒子、右巻き反粒子、左巻き反粒子”の4つで構成された“電子ヒッグス場ユニット”」より実在性が高いことを示している。
よって、次の仮説を立てた。
仮説4.2 実在するのは、ディラック方程式の解の1つである 『“4成分を持つディラック場”(4成分のディラックスピノルよりなる)の自由度を半分にした、ヴァイル場(2成分のワイルスピノルよりなる)』であり、これが「電子ヒッグス場ユニット(eHU)」に相当する。
正しければ、シュレーディンガー方程式のみならず、ディラック方程式が意味する幾何学的実体像が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で示してきた「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)の相互作用」であることになる。
この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示している「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)の相互作用」という幾何的な実体像は、抽象的な数式(ディラック方程式)の解釈の“解釈(意味)”に相当するものということになる。
ディラックは、抽象的なディラック方程式から、苦労して(“負エネルギーの電子”や“電子の海”を考える“空孔理論”を経て)陽電子を予言するに至った。
※ディラックは、後に「解釈を手に入れることは、ただ単に方程式を作るよりずっと難しいことがわかった」とも述べた。(p.466『量子革命』)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示している「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)の相互作用」という幾何的な実体像には、この“陽電子”が、自然な形で、含まれている。
そして、電子が生成するともに、陽電子も生成することも自然に説明できる。
(量子力学と特殊相対性理論を結びつけて育てられてきている)「場の量子論」は、抽象的な数式(ディラック方程式)、行列、各種の演算子(生成演算子、消滅演算子…)、ファインマン図、不確定性原理… などを用い、自然現象を、抽象的に厳密に記述しようとしているものである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「場の量子論」を否定するものではなく── 「場の量子論」がどのようなしくみで成立しているのか説明したり、その抽象的に表記された世界に対し、実際に何が起こっているかについての具体的な“幾何的な実体像”を提供したりすることによって、その理解や発展を助けるものである。
例えば、その抽象的な表記によって、生じてしまう“発散”の問題が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が提供する具体的な“幾何的な実体像”を組み合わせることで、解消される(繰り込み不要となる)可能性があるかもしれない。
また、例えば、電磁気力は、「実際には、“光子のキャッチボール”によっては生じていない」という提案をすることによって、理解を深めるかもしれない。
また、例えば、その抽象的で、複雑難解な記述を、よりシンプル化させ、具体化させる可能性があるかもしれない。
また、(ミクロの世界とマクロの世界をつなぐことによって人類の観測事情を教えてくれる)不確定性原理ではなく、(ミクロの世界そのものの振る舞いを教えてくれる)単振動振幅確定原理を使うことによって、理論が、よりミクロの自然と調和し、より厳密になることを助けるかもしれない。
…
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、より根源的なモデルであり、「場の量子論」を包含し、「場の量子論」と調和しているのみならず── 「場の量子論」の発展、完成をサポートする可能性を持つものなのである。
※運動エネルギー順位がKnの電子の速度がvn=2.2×106/n[m/s]で示される一方で── 電子は、人工的に(加速器によって)、光速3×108[m/s]の99.99…%という速さまで加速されうる。
このことは、「電子の速度vn=2.2×106/n[m/s]」が意味するものは、「電子が電子ヒッグス場ユニットと相互作用する際の速度」であることを示しているのだと思われる。 だとすれば、このことは、“n=1”の場合の v1=3.48×105[m/s]よりも、電子が速く軌道運動する場合は── 電子ヒッグス場ユニット(eHU)とは相互作用せず、原始ヒッグス場ユニット(PHU)のみと相互作用すること、すなわち、“電子の波動性”(電子の物質波)が消失することを示唆していると考えていいのだろうか? すなわち、「v1=3.48×105[m/s]よりも、電子が速く軌道運動する場合は、“電子の波動性”(電子の物質波)が消失する」は、反証可能性を持つ予測だと言えるだろうか?
あるいは、「電子→ミューオン→電子→ミューオン→…」という振動の創発が関わることはないのだろうか? あるとすれば、それは、どのように関わるのだろうか?
詳細な検討は、今後の課題である。
(なお、いずれにせよ、電子の質量については、特殊相対性理論と調和し続けていると考えられる。 なぜなら、質量エネルギーの創発は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)との関わりの中でのみ生じるものであり── 電子ヒッグス場ユニット(eHU)は質量エネルギーの創発とは関係ないからである)
《量子論(量子力学)の哲学と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)──軌道解釈(先導波理論)》
理論物理学の世界で、“コペンハーゲン解釈”が支配的であった中においても、果敢に、いくつかの量子論(量子力学)の“解釈”が生み出されてきている。
多世界解釈(by エヴェレット…)、軌道解釈(先導波理論)(byド・ブロイ、ボーム)、時間対称的な解釈…
『量子力学の哲学』(森田邦久 講談社現代新書)の中に、次のような記述がある。
|
『本書では、量子力学のさまざまな解釈を紹介していく。これらはいずれも「解釈」であるから、量子力学が経験的に正しいこと(実験事実をうまく予測したり説明したりすること)を認める。つまり、実験的に確かめられることについては、どの解釈も一致しているのだ。 それゆえ、どの解釈が正しいのかを実験的に確かめることは、いまのところできない。 だから、これは「科学」ではなく「哲学」なのである』
(p.7〜 『量子力学の哲学』 森田邦久 講談社現代新書 下線は、筆者による)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が探求している、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の“幾何的な実体像”は── まさに、量子力学の “解釈”の一種とも見なしうる。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「観測や数式だけに基づくことによって生じた危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”」を解消すべく、自然な世界観(3Steps原理)に基づいて育まれている、「科学」である。
(『だから、これは「科学」ではなく「哲学」なのである』の部分は、『だから、これは、いまのところ「科学」ではなく「哲学」なのである』が、より正確だと思われる)
したがって、自然な世界観(3Steps原理)、および、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、 こういった『どの解釈が正しいのかを実験的に確かめることは、いまのところできない』という状況を、打破し、“絞り込み”や“グレードアップ”に貢献するできる可能性があるのだ。
さまざまな“解釈”と、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を比較してみた。
|
|
コペンハーゲン解釈 |
多世界解釈 |
時間対称的な解釈 |
軌道解釈(先導波理論)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル) |
|
実在論
|
×
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
因果律
|
×
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
非局所性
|
○
|
×
|
×
|
○
|
○
|
| ※実在論とは、『観測者とは無関係な世界が存在するという哲学的世界観。実在論者にとっては、月は、誰も見ていなくてもそこに存在している』(p.491『量子革命』の用語集)というようなものである。 |
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による視覚的描像は、既存の“解釈”の中では、「軌道解釈(先導波理論)」に最も近いことがわかる。
「軌道解釈(先導波理論)」と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による“電子の振る舞い”の説明には、確かに共通点が多い。
しかし、違いも多くある。
例えば、「軌道解釈」は、「相対性理論との相性が悪い」という欠点を持つと言われている。
一方の、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「相対性理論との相性が悪い」どころか、結果1で示したように、相対性理論(光速不変、空間の膨張&時間のおくれ≒時空の曲がり、重力場…)が、なぜ生じるか(どのようなしくみで生じるのか)を説明できるものである。
両者の違いを、まとめてみた。(便宜上、“電子のふるまい”にしぼって記述する)
|
軌道解釈(先導波理論)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
波について
|
電子が、先導波(パイロット波、ガイド波)
&先導方程式にしたがって運動する。
|
電子ヒッグス場(電子ビッグス場ユニットの総和)
との相互作用による、電子の「消滅と生成の波」に相当する
|
|
シュレーディンガーの
波動方程式
|
系の完全な記述ではない。
先導方程式を用いる。
|
電子ヒッグス場(電子ビッグス場ユニットの総和)
との相互作用による、電子の「消滅と生成の波」を記述する
|
|
予測
|
位置と運動量がわかれば、
位置と運動量を正確に予測できる。
|
仮に、位置と運動量がわかっても
「決定論的なカオス」によって、予測が難しくなる。
|
|
運動
|
電子が上下に波打つ運動をする。
|
電子は、上下に波打つ運動はしない。
円や楕円、直線などの軌道運動をする。
|
|
相対性理論との相性
|
悪い
|
よい
|
|
非局所性の内容
|
状況が変わると、
すべてのガイド波が瞬間的にいっせいに変わる。
|
「共転回原理」に従って生じる。(→結果1)
光子(電磁波)、仮想光子(電磁場)、重力子(慣性運動、運動の第二法則、光速不変、重力場、時空の曲がり)… を創発する土台である
|
「軌道解釈(先導波理論)」において欠点みなされることの多い「非局所性」は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)においては、必要不可欠で根本的な「共転回原理」によって生じる性質と説明される。
少なくとも、相対性理論との相性が良いので、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「軌道解釈(先導波理論)」を改善した理論であると言えると思われる。
※一方、「軌道解釈(先導波理論)」の「 状況が変わると、すべてのガイド波が瞬間的にいっせいに変わる」という説明は、 もしかしたら、なにかしらのヒントを与えてくれているのだろうか? 「軌道解釈(先導波理論)」が示す先導方程式と、「電子の消滅と生成を示す波」は何か関係があるだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
※アインシュタインは、ボームの「軌道解釈(先導波理論)」を、“チープすぎる”と評価した。 もしアインシュタインが生きていたら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)については、どのように評価するであろうか?
アインシュタインは、重力と電磁気力の統一することによって、量子力学を改善することを目指していた。
よって、相対性理論を説明できるのみならず、重力と電磁気力の統一をも可能にしうる“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に対する評価は、もしかしたら、それほど悪くないのかもしれない。 (しかし、実際どうかはわからない)
なお、ボームの軌道解釈(先導波理論)に関連して、次のような記述があることも、大いに参考になる。
|
『ボームは、そのふたつの論文の中で、量子論のコペンハーゲンとは別の解釈を示し、「このような解釈が可能だというだけでも、個々の系を量子レベルで、正確に、合理的に、そして、客観的に記述するという望みを捨てる必要はないことがわかる」と述べた。ボームが提案した解釈は、量子力学による予測とまったく同じ予測をし、数学的な観点からは、ルイ・ド・ブロイの先導波を洗練させ、矛盾を取り除いたバージョンとみることができる。』
(p.437『量子革命』。 下線は、筆者による)
『ボームは、通常の量子力学に取って代わる理論を真剣に目指していた訳ではなく、単に隠れた変数理論が不可能でないことを示しただけだった。そしてそれが、現在の量子力学を超える新しい発想や実験につながることを期待していた。』
(ウィキペディア 『隠れた変数理論』 下線は、筆者による)
『ベルは、ボームの二篇の論文を読むなり、「不可能であるはずのことができてしまった、と思った」という。ベルもまた、ほとんどすべの人たちと同じく、ボームが考え出したようなコペンハーゲン解釈の代替案は、不可能だとしてすでに除外されたものと思い込んでいたのだ。 先導波理論のことを、なぜ誰も教えてくれなかったのだろう、とベルは自問した。「なぜ先導波のアイデアは、教科書のどこにも紹介されていないのだろう? 先導波の考え方は、それが唯一可能な案だからというのではなく、広く行き渡っている自己満足への解毒剤として、むしろ積極的に教えるべきではないだろうか? 量子の世界は、あいまいだとか、主観的だとか、非決定論的だとかいうのは、それが実験事実だからではなく、意図的に選びとった思想として押し付けられているのだということを明らかにするだけのためにも、先導波理論を教えるべきなのではないだろうか?」。 それなのになぜ、誰も教えてくれなかったのだろう? その答えの一部は、ハンガリー生まれの伝説の数学者、ジョン・フォン・ノイマンにあった。』
(『量子革命』 p.437 下線は筆者による)
『〜。ほとんどすべての物理学者が、フォン・ノイマンの証明は、隠れた変数理論は、それがどんなものであれ、量子力学と同じようには実験結果を再現できないことを意味すると思い込んだのである。
ボームは、フォン・ノイマンの証明を詳しく調べて、何かがおかしいと確信したが、具体的に間違いを突き止めることはできなかった。しかしアインシュタインとの議論に力づけられたボームは、不可能であるはずの隠れた変数理論をじっさいに作ってみたのである。 フォン・ノイマンが用いた仮説のなかに、必ずしも正しいという保証のないものがひとつ含まれていること、それゆえ、彼の「不可能性」の証明は正しくないことを明らかにしたのが、ベルだった。』
(『量子革命』 p.440〜 下線は筆者による)
|
ボーム自身は、彼の軌道解釈(先導波理論)が完全だとは決して思っておらず、“叩き台”を提示してくれた。
そして、その「ボームの軌道解釈(先導波理論)」は、ベルを勇気づけた。
そして、ベル(ベルの定理)は、「量子力学が、非局所性にもとづくことの証明」、すなわち、「量子もつれ(エンタングルメント)が実在することを証明する観測」を生み出すきっかけとなった。
そして、今── ボームも、(そのボームに勇気づけられた)ベルも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を勇気づけている。
なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“共転回原理”(「非局所性、量子もつれ(エンタングルメント)」と関連)にもとづいていると同時に、結果的に、(“叩き台”であった)「ボームの軌道解釈(先導波理論)」を、より『洗練させ、矛盾を取り除いたバージョン』に相当しているからである。
《隠れた変数理論とベルの定理について》
ベルによって切り開かれた「非局所性」について説明する前に、「隠れた変数理論」について説明しなければならない。
それは──
『ベルの定理が意味するのは、量子力学と同じ予測をする隠れた変数理論はすべて、非局所的でなければならないということだ』(p.460 『量子革命』 下線は、筆者による) という事情があるからである。
「隠れた変数」とは、次のように説明されているものである。
『 隠れた変数 量子力学は不完全であり、量子の世界について付加的な情報を含む、基礎的な実在が存在するという信念に基づく量子力学解釈。 ここでいう「付加的な情報」は、目には見えないけれども実在する、「隠れた変数」という物理量として与えられる。〜。隠れた変数の支持者は、そのような変数があれば、コペンハーゲン解釈によって否定された観測とは無関係な実在を取り戻すことができると考える』
(用語集 p.488 『量子革命』 一部省略 下線は筆者による)
|
ここから、「隠れた変数(理論)」と「実在(論)」の間には、深い関係があること、すなわち、両者は、ほとんど同義であることが読み取れる。
※実在論とは、『観測者とは無関係な世界が存在するという哲学的世界観。実在論者にとっては、月は、誰も見ていなくてもそこに存在している』(p.491『量子革命』の用語集)というようなものである。
この「隠れた変数理論(hidden variable theory)」と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の関係はどうなっているのだろうか?
このことを考えるにあたり、『量子革命』(p439〜)の中の、次の記述が、きわめて参考になる。
|
『隠れた変数のアプローチには、長い歴史がある。 十七世紀以来、ロバート・ボイルをはじめとする科学者たちが、圧力、体積、温度を変えた多ときに気体が示す性質を調べて、気体の従う法則を明らかにしてきた。 〜
気体の法則がきちんと物理的に説明されたのは、十九世紀にルートヴィヒ・ボルツマンとジェームズ・クラーク・マクスウェルが気体分子運動論を作り上げたときのことだった。 〜。 たえず動き回る気体分子が、お互い同士や容器の壁とランダムに衝突することにより、圧力、温度、体積のあいだに成り立つ関係、すなわち気体の法則を成り立たせているのだ。 気体分子は、観測されることのない微視的な「隠れた変数」であり、観測されている巨視的な気体の性質は、その隠れた変数によって説明されると考えることができる。
アインシュタインが一九〇五年に説明したブラウン運動では、花粉分子が浮かぶ液体中の分子を「隠れた変数」と見なすことができる。 花粉分子のランダムな運動をみんなが不思議に思っていたが、その基礎には、目には見えない液体分子のランダムな運動が存在するとアインシュタインが指摘すると、突如としてすべての謎が解けた。
量子力学にも隠れた変数のアプローチが可能なのではないかとの発想は、アインシュタインが、量子力学は不完全だと主張したのを発端として生まれた。 アインシュタインのいう不完全性の背後には、何かもっと基礎的な階層が存在するのではないだろうか? 隠れた変数──隠れた粒子、隠れた力、あるいはまったく新しい何か──を考えれば、観測者とは関係ない、客観的な実在を取り戻せるかもしれない。 あるレベルでは確率的に見える現象が、隠れた変数を考えることにより、実は決定論的であることが明らかになるのでは? もうそうなら、粒子はつねに確定した速度と位置をもつだろう、というのが、量子力学における隠れた変数の考え方である。』
(『量子革命』(p439〜) 下線は筆者による)
|
整理すると次のようになる。
|
気体の法則
|
ブラウン運動
|
量子力学
|
|
説明する対象
|
気体、圧力、温度
|
花粉
|
量子
|
|
隠れた変数
(≒実在している何か)
|
気体分子
|
花粉分子が浮かぶ
液体中の分子
|
「隠れた粒子、隠れた力、あるいはまったく新しい何か」
|
以上より、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、量子力学における「隠れた変数理論」の1つであることが理解できる。
なぜなら、まさに──
|
『アインシュタインのいう不完全性の背後には、何かもっと基礎的な階層が存在するのではないだろうか? 隠れた変数──隠れた粒子、隠れた力、あるいはまったく新しい何か──を考えれば、観測者とは関係ない、客観的な実在を取り戻せるかもしれない。 あるレベルでは確率的に見える現象が、隠れた変数を考えることにより、実は決定論的であることが明らかになるのでは? もうそうなら、粒子はつねに確定した速度と位置をもつだろう』
(『量子革命』(p439〜) 下線は筆者による)
|
という記述に、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が、ぴったり調和しているからである。
例えば、“電子の挙動”においては、「電子ヒッグス場ユニット(eHU)、プレオン∴ヒッグス場ユニット(∴HU)、原始ヒッグス場ユニット(PHU)、および、素スピノール」が、主要な「隠れた変数」、すなわち、『何かもっと基礎的な階層』『観測者とは関係ない、客観的な実在』そのものに相当すると考えられられる。 そして、例えば、「“電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)”の相互作用」によって、電子の『確率的に見える現象』を、『決定論的であること』として理解することができる。
つまりは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「隠れた変数理論(hidden variable theory)」の一種なのである。
さらに、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「共転回原理」という非局所性を内在していることを考え合わせると、次のように結論をまとめることができる。
結論4.4 “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「非局所的な隠れた変数理論」の一種である。
※電子を説明する“隠れた変数”(≒実在する何か)と、その働き(創発するもの)をまとめると次のようになる。
|
電子を説明する“隠れた変数”
(≒実在する何か)
|
働き(創発するもの)
|
|
電子ヒッグス場ユニット(eHU)
|
電子の波動性
|
|
プレオン∴ヒッグス場ユニット(∴HU)
|
電子のスピン
|
|
プレオン∴
|
電子のスピン
|
|
原始ヒッグス場ユニット(PHU)
|
電子の質量エネルギー
((内部&外部)運動エネルギー)
電子を構成するプレオン∴
を閉じ込める
「LP光子の集積したひも」
|
|
素スピノール
|
仮想光子の放出&吸収(電荷)
|
《非局所性(量子もつれ、絡み合い、エンタングルメント)と重ね合わせの原理について》
非局所性(量子もつれ、絡み合い、エンタングルメント)とは、次のようなものである。
|
『非局所性 二つの系(または二つの粒子)のあいだで、瞬間的に影響が伝わるという性質。影響が伝わる速さは光の速さよりも大きく、遠くの場所で起こった出来事の影響が、瞬時に別の場所に及ぶ』
(用語集 p.496 『量子革命』)
|
もともとは、この非局所性とは逆の“局所性”こそが、アインシュタインが持っていた“常識的な前提”の1つであった。
そもそも、EPR論文における主張も、「もし、量子論が正しければ、非局所性というおかしな性質を持ってしまうことになる。 だから、量子論は、不完全である」という論理のものだったのだ。
アインシュタインが持っていた“常識的な前提”は、この“局所性”と、そして、“実在論”(≒隠れた変数理論)であった。
|
アインシュタインにとっての
“常識的な前提”
|
|
局所性
|
非局所性
|
実在論
(≒隠れた変数理論)
|
|
○
|
×
|
○
|
しかし、実際は、この非局所性(量子もつれ、絡み合い、エンタングルメント)が存在していることが証明されたのだ。
すなわち、「“ベルの不等式”が破れている」ことが観測されたのである。
ベルの不等式とは、“局所性と実在論”という前提において、成り立つべき不等式である。
|
ベルの不等式の“前提”
|
|
局所性
|
非局所性
|
実在論
(≒隠れた変数理論)
|
|
○
|
×
|
○
|
したがって、「“ベルの不等式”が破れ」の観測は、(アインシュタインが信じていた)「局所性を持つ実在論(≒“隠れた変数理論”)」の否定を証明したことになるのである。 すなわち、それは、非局所性(量子もつれ、絡み合い、エンタングルメント)の方こそが、ミクロの自然(nature)が持っている本来の性質であることを証明したことになるのだ。
|
ベルの不等式の破れが証明したこと
|
|
局所性
|
非局所性
|
実在論
(≒隠れた変数理論)
|
|
×
|
○
|
○
|
次は、そのことは、次の記述からもわかる。
|
『この不等式が成り立たなかったとしよう。ベルの定理によれば、この結果は「非局所性」の証拠となる。つまり一方の粒子に何かが起こると、もう一方の粒子に何かが起こると、もう一方の粒子がどんなに離れていようがそれに瞬間的に影響が及ぶ』
(『量子の絡み合う宇宙』アミール・D・アクゼル 水谷淳・訳 p,146 早川書房 下線は筆者による)
『クローザー=アリードマンの実験は、量子力学が本来非局所的であることを示す確たる証拠となった』
(『量子の絡み合う宇宙』アミール・D・アクゼル 水谷淳・訳 p,169 早川書房 下線は筆者による)
『アスペの実験によって絡み合いの実在が完全に立証され、絡み合いの現象の研究は大きく進展した』
(『量子の絡み合う宇宙』 p,188 早川書房 下線は筆者による)
|
※なお、“ベルの定理”については、次の記述から理解できる。
|
『もし量子論が正しければ局所性は成り立たない。もし局所性にこだわるのなら、微小の世界を記述する理論としての量子論は間違っていることになる。ベルはこの結論を、特別な不等式を含む純粋な数学的定理として表現した。 もし実験によってこの不等式が否定されれば、量子力学が正しくアインシュタインによる常識的な局所的現実性の仮定が間違っていることの証拠となる。逆にもしこの不等式が成り立てば、量子力学は誤っており局所性が正しいことが証明される。』
(『量子の絡み合う宇宙』 p,188 早川書房 下線は筆者による)
『ベルの定理が意味するのは、量子力学と同じ予測をする隠れた変数理論はすべて、非局所的でなければならないということだ』
(p.460 『量子革命』 下線は、筆者による)
|
つまり、「ベルの不等式の破れ」が観測されたので──
量子論は正しく、なおかつ、ミクロの自然(nature)の中には、非局所性(量子もつれ、絡み合い、エンタングルメント)が存在していることが、証明されたのである。
したがって、「ベルの不等式の破れ」の観測結果によって否定されたのは、「アインシュタインによる常識的な局所的現実性の仮定」の方、すなわち、「局所性を持つ“隠れた変数理論”(≒実在論)」だけであり── 「非局所性を持つ“隠れた変数理論”(≒実在論)」ではないということになる。
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)も、「ベルの不等式の破れ」によって否定されないことになる。
ここで、3つの立場を整理しておく。
|
量子論(量子力学)
|
局所的な実在論
「局所性を持つ“隠れた変数理論”」
|
非局所的な実在論
(「非局所性を持つ“隠れた変数理論”」)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
「ベルの不等式の破れ」の観測結果
との調和性
|
○
(否定されない)
|
×
(否定される)
|
○
(否定されない)
|
|
非局所性
(量子もつれ、絡み合い、エンタングルメント)
|
○
|
×
|
○
|
|
実在論
|
×
(コペンハーゲン解釈は、
実在論を否定している)
|
○
|
○
|
つまり、「量子力学」と「量子力学の予測と合致するような“隠れた変数理論”(≒実在論)」は、両方ともに、「ベルの不等式の破れ」によって── “否定されなかった”と同時に、“非局所性を持っていることが証明された”ことになるのである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、この「非局所性(量子もつれ)」と(コペンハーゲン解釈を支える)「重ね合わせの原理」とは、実は深い関係があることがわかる。 そのことを以下で説明する。
例えば、次のような例を考えてみよう。
『電子Aと電子Bが、“量子もつれ”の状態にあるとき、電子AとBが、どんなに遠くに離れていても、「電子Aが上向きならば、電子Bは必ず下向き」であり、「電子Aが下向きならば、電子Bは必ず上向き」であるという関係が成り立つ。
観測される前は、これらの二つの状態が、(同時に)重ね合わさっており、その状態は、(上向き電子A+下向き電子B)+(下向き電子A+上向き電子B) と表記できる。』
こういった例を持つ「非局所性(量子もつれ)」や「重ね合わせの原理」は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、どのように説明できるであろうか?
次の仮説を立てた。
仮説4.3.1 「非局所性(量子もつれ)」の一切は、“素スピノールどうしの共転回”によって生じている、
仮説4.3.2 「同時に存在している各状態の重ね合わせ(同時多状態)」によって説明されてきた現象はすべて、「“時間差”を持って存在している各状態(一時一状態)の総和」として創発している。
上記の電子Aと電子Bの例については、この仮説で説明すると、次のようになる。
『電子Aと、電子Bの中の素スピノールが共転回することにより、どんなに遠くに離れていても、「電子Aが上向きならば、電子Bは必ず下向き」であり、「電子Aが下向きならば、電子Bは必ず上向き」であるという関係が成り立つ。
観測される前は、共転回する度に、これらの二つの状態の間を、(同時にではなく)時間をかけて行ったり来たりしている。 その様子は、(上向き電子A+下向き電子B)←→(下向き電子A+上向き電子B) と表記できる。』
これらの仮説が正しいなら、観測される前にも後にも、電子のペアは、常に実在していることになる。(→実在論○)
なお、一方の「同時に存在する複数の状態の重ね合わせ(同時多状態)」の方は、観測されるまでは実在していないことになる。(→実在論×)
|
量子力学
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
原理
|
「重ね合わせの原理」
|
「共転回原理」
|
| 表記の例 |
(上向き電子A+下向き電子B)+(下向き電子A+上向き電子B) |
(上向き電子A+下向き電子B)←→(下向き電子A+上向き電子B) |
|
時間
|
同時に存在してると仮定
|
時間をかけて行ったり来たりしていると仮定
|
|
実在論
|
×
(観測されるまで実在しない)
|
○
(観測に関係なく実在している)
|
これらの仮説──
仮説4.3.1 「非局所性(量子もつれ)」の一切は、“素スピノールどうしの共転回”によって生じている、
仮説4.3.2 「同時に存在している各状態の重ね合わせ(同時多状態)」によって説明されてきた現象はすべて、「“時間差”を持って存在している各状態(一時一状態)の総和」として創発している。
によって、「2つの電子のスピンの量子もつれ」のみならず、「2つの光子の量子もつれ」を含め、あらゆる、「ベルの不等式の破れ」を示す観測結果を説明できることがわかる。
すなわち、「ベルの不等式の破れ」を示す実験結果はすべて、「素スピノールどうしの共転回(共転回原理)が成立していることを支持する観測結果である」と解釈できるのである。(「観察の理論負荷性」の一例に相当すると思われる。 詳細な検討は今後の課題である)
※「二重スリットの実験で生じる縞模様」は、これまで、「重ね合わせの原理」&「波の干渉」によって説明されている現象の1つであるが── 「“時間差”を持って存在している各状態(一時一状態)の総和」によって説明できる。 (→《電子の二重スリット実験の解釈》)
※仮説4.3.2 は、「1つの電子は、1つの軌道を運動し続けている」という“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の説明とも調和している。
このように、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の根幹を支えている、「共転回原理」が、「非局所性(量子もつれ)の一切の現象」を支えていると理解したら、さまざまな、つじつまが合うのである。
当然、(結果1でも説明したように)、この共転回の法則が持つ“同時に”転回するという性質は、“光円錐”を超越して初めて成り立つものである。
※光子の2つの素スピノールのペアが共転回する様子を、光円錐に重ねて、図示してある。
共転回は、総スピンが一定のまま同時に転回することである。
したがって、共転回の開始時から終了の直前まで、2つの素スピノールのペアは、上図のように光円錐を超越して作用し合っていることになる。
共転回が終る瞬間、光円錐の外にあった素スピノールが、ちょうど光円錐に接する。
この繰り返しによって、“光子”は、あくまで、“光速”で進むことに相当する。
※なお、共転回の周期をTとすると、時間T/2の間に、光速cで光子が進む距離が、素スピノールの間隔rになるので、cT/2=r となる。 この式に、「波長λ=2r」の関係を代入すると、cT=λ、すなわち、c=λ/T=λν となるので、ここに矛盾はない。 |
光速を超えた“同時”の“素スピノールどうしの相互作用”── それが共転回である。
そして、この共転回のおかげで、非局所性(量子もつれ)の現象を説明できるのみならず── 光子や重力子の現象、すなわち、光子(電磁波)、仮想光子(電磁場、電磁気力、ファラデーの法則、アンペール-マクスウェルの法則…)、重力子(慣性運動、運動の第二法則、光速不変、重力場、時空の曲がり…)といった現象を説明できるのだ。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“素スピノールどうしの共転回”こそが、マクスウェルの電磁気学、ニュートン力学、アインシュタインの相対性理論、量子論(量子力学、場の量子論)(「非局所性(量子もつれ)」の現象や「重ね合わせ」で説明されてきた現象を含む)… を根底で支えるしくみであることを示しているのである。
既存の物理学のパラダイムに照らすと、確かに、“非局所性(量子もつれ)”の現象には、奇妙に&気味悪く思われてしまうところがある。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に照らすと、それは、全く逆転する。
なぜなら、まさに“共転回原理”が、“非局所性(量子もつれ)”の困難を解消すると同時に、“共転回原理”こそが「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)」を育てる土壌となっているからである。
すなわち、『「素スピノールどうしの共転回」は、実は、ありふれた根本的なしくみとして、自然(nature)をくまなく支え── 例えば、光子(電磁波)も、仮想光子(電磁場、ファラデーの法則、マクスウェル・アンペールの法則)も、重力子(重力場、慣性の法則、F=ma、光速不変…)も、電荷も、電子も、電子ヒッグス場(電子ヒッグス場ユニットの総和)も、電子の波動性も、色荷も、グルーオンも、ニュートン力学も… 創発させている』と説明できるからである。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、『“非局所性(量子もつれ)”を示す現象こそは、量子論や相対論が育つ土壌となった「第1、第2の暗雲」に続く、「第3の暗雲」に匹敵する、きわめて重要な現象なのだ』ということになる。
※“第1、第2の暗雲”については、やはり次の記述が参考になる。
|
『今世紀初頭の1900年4月、イギリスの物理学会の長老ケルビン卿は、「熱と光の力学理論の頭上ある19世紀の雲」という象徴的な演題のもとに講演を行い、すでに完成されたと見なされていた古典物理学に内在する二つの深刻な困難を指摘した。
まず、熱輻射についての困難は、この講演の数ヶ月後に現れたプランクの量子仮説の提唱によって劇的な解決が見られることになったのであるが、1905年、アインシュタインはプランクの量子仮説を一歩進め、直裁、簡明な光量子論を提出して、光電効果の問題を解決した。 〜
〜
特殊相対性理論は、いうまでもなく、ケルビンのあげた、もう一つの光の伝播に関する困難を根本的に解決する〜ことになった。』
(『アインシュタイン選集1』 監修者のことば by湯川秀樹 i〜iiより引用 共立出版株式会社 一部省略 下線は、筆者による』
|
そして、非局所性(≒「共転回原理」)は、まさに、次の記述の中の「何かもっと過激なこと」にも相当していると思われる。
|
『一九四九年という最晩年になって、〜、アインシュタインは、「今日の量子論のもつ本質的に統計的な性質は、この理論が物理系について不完全な記述をしているせいで生じていると固く信じています」と述べた。
〜。一九五四年には、彼ははっきりと次のように述べている。「今日の量子力学の全体的構造に関する基本的な考え方を変えることなく、単に何かを付け加えることによって、この理論の統計的な性質を取り除くことはできない」。 彼は、ミクロな量子の世界で古典物理学の概念に立ち返るのではなく、何かもっと過激なことが必要だと確信するようになっていた。もしも量子力学が、真実の一部しか捉えることのできない不完全な理論ならば、完全な理論がきっと存在して、発見されるのを待っているに違いないと彼は考えていたのだ』(p.462 『量子革命』 下線は筆者による)
|
光円錐を越えて生じる“共転回”は、「特殊相対性理論に反するからおかしい」という批判は、的外れなものである。
逆だからである。
この“共転回”こそが、逆に、「特殊相対性理論」(光速不変、運動エネルギーとともに質量が大きくなること…)の成立を根底で支えているのだ。
すなわち、この“共転回”が存在しなければ、実は、「特殊相対性理論」(光速不変、運動エネルギーとともに質量が大きくなること…)は成り立たないことになってしまうのだ。
つまりは、「非局所性と“特殊相対性理論”」は、矛盾していないどころか、非局所性が“特殊相対性理論”を支えているのである。
光円錐を越えて生じる“共転回”は、「“遠隔作用”の一種であり、電磁場や重力場の理論(電磁気学や一般相対性理論)に反するからおかしい」という批判も、的外れなものである。
逆だからである。
この“共転回”こそが、逆に、電磁場や重力場の理論(電磁気学や一般相対性理論)の成立を根底で支えているのだ。
すなわち、この“共転回”が存在しなければ、実は、電磁場や重力場の理論(電磁気学や一般相対性理論)は成り立たないことになってしまうのだ。
つまりは、「非局所性と電磁場や重力場の理論(電磁気学や一般相対性理論)」は、矛盾していないどころか、非局所性が電磁場や重力場の理論(電磁気学や一般相対性理論)を支えているのである。
そして、それは、「特殊相対性理論」や「電磁場や重力場の理論(電磁気学や一般相対性理論)」のみならず、「二ュートン力学」も、量子論(量子力学、量子もつれ…)も、素粒子物理学の標準模型も… 同様のことである。
すなわち、このように“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が、ニュートン力学(慣性の法則、運動の第2法則F=ma、万有引力の法則)、特殊相対性理論(光速不変の原理…)、一般相対性理論(時空の曲がり、重力場…)、マクスウェルの4つの方程式(電磁気力、ファラデーの法則、アンペールマクスウェルの法則)、量子力学、「非局所性(量子もつれ)」の現象や「重ね合わせ」で説明されてきた現象、素粒子物理学の標準模型、弦理論(→考察3)… を説明できるということは、「非局所性と“物理法則の成立”」が矛盾していないことどころか、非局所性が“物理法則の成立”を支えていることを意味しているのである。
つまり、非局所性(≒「共転回原理」) は、既存の物理学を否定するものではなく── 既存の物理学と調和しているのみならず、既存の物理学を根底で支えているものなのだ。
そのことを“究極の量子論”である“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がはっきり示しているのである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば──
非局所性(量子もつれ)が実在することを示す「ベルの不等式の破れ」を示す現象は、たまたま、この“共転回”の性質がはっきりと前面に現れた現象であるに過ぎない。
すなわち、“共転回”という現象は、本来は、自然界をくまなく、根底で支えてくれるありふれた現象だったのだ。
そして、この一見奇妙に思える「ベルの不等式の破れ」を示す現象は、実は、ふつうは隠されていて認識できない“共転回”という現象をかいま見させてくれる、貴重な“窓”と言えるものなのである。
すなわち、非局所性(量子もつれ)が実在することを意味する「ベルの不等式の破れ」を示す観測結果はすべて、まさに、“共転回”の実在性を支持する重要な観測結果であると解釈できるものなのである。 (やはり、「観察の理論負荷性」の一種であろうと思われる)
つまりは、既存の物理学の世界で、比較的、“やっかいもの”あつかいされたり、見て見ぬふりされたりする傾向の多い、「非局所性」(量子もつれ)の存在証明は── 実は、物理学を根底で支える重要な性質(共転回原理)の存在証明だったと言うことになるのである。
※アインシュタインが、 生前に、ベルの定理や「ベルの不等式の破れ」を知っていればどのように対応したであろうか?
おそらく、いさぎよく、(局所性を信じていたことの)間違いを認め、非局所性を受け入れたであろうと推測できる。
なぜなら、1つは、アインシュタインは、大切にしていた“実在論、因果律、局所性”の中で、実在論こそを最も重視していたからである。
そのことは、『量子革命』の中の以下のような記述からも読みとれる。
|
『「神はサイコロを振らない」という印象的な言葉を、アインシュタインは一度ならず口にした。〜「神は……」は、コペンハーゲン解釈ではダメだということを印象づけるフレーズであって、彼の科学的世界観の基礎ではなかった。〜
〜 「アインシュタインの意見がわれわれと異なるのは、“決定論”かどうかではなく、“実在論”かどうかという点なのです」とパウリはボルンに言った。〜驚いたことに、アインシュタインとは長い付き合いだったにもかかわらず、ボルンは、アインシュタインが真に問題視していたのは神がサイコロを振るかどうかではなく、コペンハーゲン解釈が「観測者とは独立した実在を説明することを断念した」ことだという点を、ついに十分に理解することはなかった。』 (p.458 『量子革命』 下線は、筆者による)
『アインシュタインは1950年に書いた量子力学についての文章の中で、「問題の核心は、因果律にあるのではなく、実在論にあるのです」と述べた。「実在を描き出すという望みを捨てることなく、量子のパズルを解くことはできる」と、彼はずっと思っていたのだ。 そしてその実在は、相対性理論を発見した人間にとってみれば、光より速く伝わる影響には居場所のない、局所的なものでなければならなかった。 ベルの不等式が破られたということは、アインシュタインが観測者とは独立した量子の世界を求めるのであれば、捨てるべきは局所性であるということを意味していた。』 (p.460 『量子革命』 下線は、筆者による)
|
そして、非局所性をいさぎよく受け入れたであろう、もう1つの理由は、アインシュタインが、ハッブルによる宇宙膨張を示唆する観測結果を知ったとき、それまで持っていた「宇宙は静的である」という考えの間違い、すなわち、“宇宙項”の間違いをいさぎよく認めたことから分かるように(おそらく、その後、加速膨張の観測結果を知れば、“宇宙項が間違いだったと見なしたこと”が間違いだったことを潔く認めるであろう)── アインシュタインは、“特定の理論(考え)”を守ろうとし続けた人ではなく、あくまで、真実を探求しようと続けた人だからである。
“自分が間違えたかどうか”よりも何よりも、あくまで「それが自然(nature)という名の真実に近いかどうか」にこだわり続けた、真の科学者だったからである。
※“晩年のアインシュタイン”について、多くの文献で、「(量子力学などの)新しい考えに順応できなかった、おいぼれ頑固科学者」というレッテルが貼られているようである。 しかし、少なくとも私には、アインシュタインは、最後の最後まで、「間違いに気づいていこう」という態度を貫き、「真実の探求」をあきらめようとしなかった、真の科学者にしか見えない。
もう一度、引用する。
|
『二〇世紀の始めから一九五五年にこの世を去るときまで、彼の念頭を離れなかったのがこの量子の問題だった。「量子問題については、私は一般相対論の一〇〇倍ぐらい頭を使っているよ」と彼は言っているが、そんなに考え続けても、どうにもらちがあかなかったのである。晩年になっても最初考えはじめたころと比べて少しの進歩もないどころか、いよいよもってわからなくなってきた感さえあった。「もう五〇年もの間必死で考え続けているというのに、いっこうに『光量子(クオンタ)とは何なのか?』という問題の解決に近づいてはしないのだ」とアインシュタインはぼやいている。「このごろは猫も杓子もこの答えがわかったなんぞと思っているらしいが、それは大まちがいというものだよ。」』
(p.60 『アインシュタインの部屋──[上]』 エド・レジス著 大貫昌子訳 工作社 下線は筆者による)
|
※『量子革命』の翻訳者 青木薫氏自身の次の、胸を打つ言葉もある。
|
『もしもあの世のアインシュタインに会いに行き、ベルの不等式のことを説明して、クラウザーやアスペらの新世代の物理学者による実験結果を伝えたならば、アインシュタインはちょっと遠くを見やるような目をして、「ああ、そうか、そういうことだったのか」と言うのではないだろうか。そして彼は、非局所相関のある宇宙像を受け入れ、実在論は堅持するに違いない。』
(p.510 『量子革命』あとがき)
|
※ペンローズ氏の言葉を、もう一度引用する。
|
『「わたし自身は、微視的なレベルよりもさらに下層の世界が実在し、今日の量子力学は根本的に不完全というアインシュタインの確信を強く支持している」』
(p.467 『量子革命』の中の引用文)
|
※「EPR論文」は、結果的に、量子論についての新たな真実にたどりつくための、かけがえなのないヒントを提供したのである。
|
『ベルは、アインシュタインとポドルスキーとローゼン(EPR)が三〇年前に書いた論文を、かつて読んだことがあった。ボーアらはこの論文に反論した。そのため誰もが、間違っているのはアインシュタインであり、この問題はすでに解決したと信じていた。しかしベルはそうは考えなかった。
ジョン・ベルは、かつてEPRがくりひろげた主張には大きな真実が隠されていることに気づいた。彼は、正しかったのは実はアインシュタインだったと悟った。誰もが「EPRのパラドックス」と呼んでいたのは、実はパラドックスではなかった。アインシュタインが発見した現象は宇宙の仕組みを理解するうえで極めて重要なものだったのだ』
(『量子の絡み合う宇宙』 p,142〜143 早川書房 下線は筆者による)
|
※なお、『不完全性・非局所性・実在主義 量子力学の哲学序説』(マイケル・レッドヘッド 石垣郎 みすず書房)の結論は、次のようになっている。
|
『よって、やはりこうなる──ある種の遠隔反応、あるいは(概念的には異なる)分離不能性が、実在の量子論的な見方を理解するどの合理的な試みにも組み入れられるように思われる。ポパーが注意したように、われわれの理論は、「世界を把握するためにわれわれが考案した網」である。量子力学がかなり奇妙な魚を捕らえてしまった事実を直視すべきであろう。』
(p.186 『不完全性・非局所性・実在主義 量子力学の哲学序説』 下線は、筆者による)
|
《電子の二重スリット実験の解釈》
「量子の奇妙に見える振る舞い」について、例えば、次のような二重スリットの実験結果(&解釈)にもとづいて、しばしば説明されてきた。
「“二重スリットを、電子を1つずつ通過させて、ある1点を発光させる”という過程を繰り返すと── 1つ1つの電子が、時間をずらして、投入されているのに関わらず、なぜか、波の干渉が起きて、スクリーンに縞模様ができる」
こういった奇妙さは、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)(「(分割しない)1つの電子は、波として両方のスリットを通過するのだ」)、多世界解釈… 等々を含む、奇妙な解釈が正当化されてきた理由の1つとなってきた。
この「二重スリットの実験」によって観察される“量子の奇妙に見える振る舞い”を“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、どのように説明するだろうか?
それは、次のようになる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、電子は、(v1=2πke2/h≒2.2×106[m/s]以下の速度で軌道運動する場合)、消滅と生成を繰り返す波を創発している。
スクリーンに到着したとき、ちょうど消滅のタイミング(位相)だったら発光しないし、ちょうど生成しているタイミング(位相)だったら、発光する。
1つ1つの電子の物質波の波長λeは(投入される電子の運動エネルギーおよび“運動量の大きさ”が一定である限り)どれも一定であると考えられる一方── (電子の進行方向が決定論的カオスに基づき、微妙な方向転換はありうるとは言えども、投入された電子が、スリットを通過した後に、極端な方向転換をするとは考えにくいので)、“おおよそ直線”に近くなり── 「軌道運動する電子の分布」も「相互作用する電子ヒッグス場ユニットの分布」も、おおよそ、同心半円の上に分布すると考えられる。
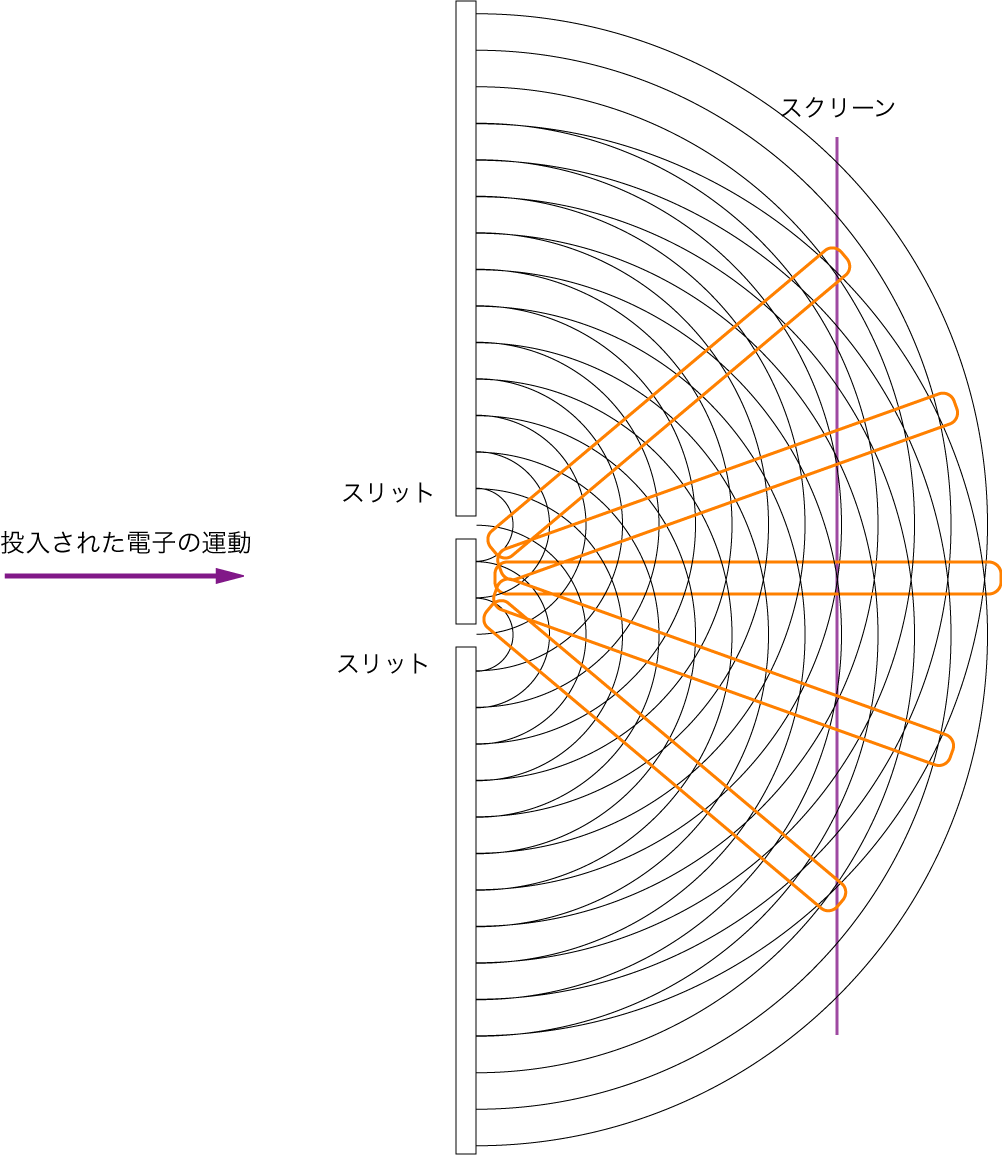
この図においては、半円を描く線上の部分が、「(生成度が最大の)電子」が分布するところに相当し── 半円と半円の間の中央の部分は、「電子と相互作用する電子ヒッグス場ユニット((消滅度が最大の)電子)」が分布するところに相当すると考えることができる。(その様子を詳しい図で下に示した)
さて、次の図に戻ると──
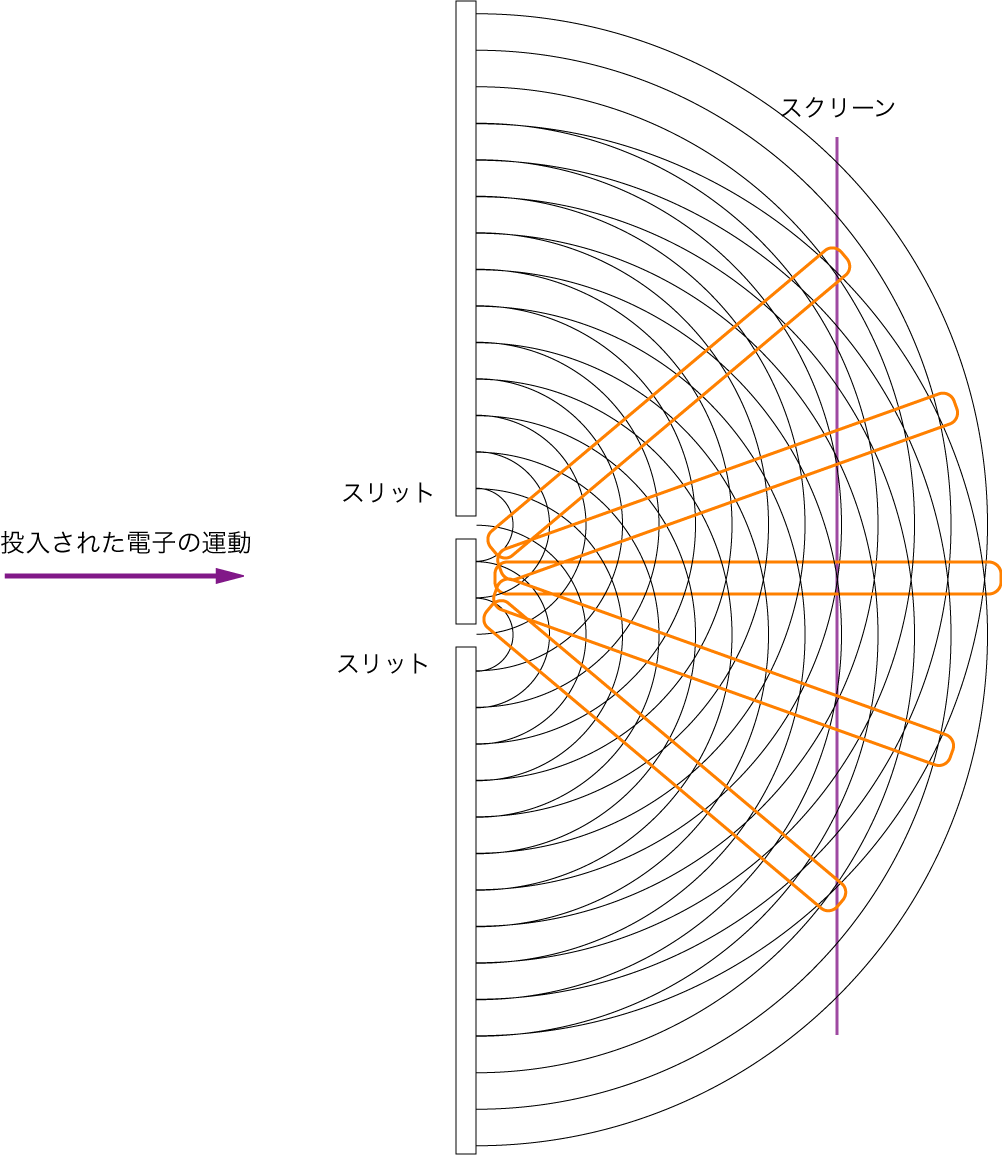
この同心半円が、二つ重なるところ(オレンジで囲ってある所)は、ともに、電子の生成度が最大になっている場所である。
ちょうどスクリーン上で、ちょうどこの同心半円が重なる場所では電子による発光が最も大きくなり── 周辺の重ならない場所では、相対的に電子による発光が小さくなる。 このことが、結果として、“縞模様”として観測されると考えられる。
『量子力学を見る 電子線ホログラフィーの挑戦』(外村彰 著 岩波科学ライブラリー28)には、
『大変不思議な結果が得られました。一個一個の電子を送ったのにもかかわらず、干渉縞が観測されたのです』
『量子力学を見る 電子線ホログラフィーの挑戦』(外村彰 著 岩波科学ライブラリー28) |
という記述(p.56、下線は筆者による)と、その観測結果を示す美しい写真(p.54-55)が載っている。
この写真をよくみると、“電子の存在数のピークの間にも、けっこうな数の電子が存在する”のがわかる。 このことは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による上のような説明と調和していると思われる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明の最大のメリットの1つは、「たとえ、1つ1つの電子が、時間をずらして投入されても、スクリーンに縞模様ができる」ことを自然に説明できることである。
すなわち、1つ1つの電子は、どちらか一方のスリットを通ってスクリーンに到達しているだけである。 ただし、それぞれの電子は、生成と消滅の波をもって、おおよそ直線でスクリーンに到達する。 それを繰り返すと、スリット上で、生成度の高い電子が多数やって来る場所もできれば、少数しか来ない場所(電子が電子ヒッグス場ユニット(eHU)と相互作用して消滅していることの多い場所)もできる。
すなわち、ただ、1回1回の投入を繰り返すだけで、電子の数が相対的に多い場所と、少ない場所の濃淡── すなわち、“縞模様”できるのである。
※したがって、厳密に言えば、ここにあるのは、“干渉縞”ではなく、ただの“縞模様”に過ぎないということになる。
なぜなら、もし“干渉”であるなら“強め合い”のみならず、“打ち消し合い”があるはずだが── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明においては、“打ち消し合い”が存在しないからである。
「縞模様が観測された(スクリーンに、単に縞模様ができた)」と「干渉縞が観測された(波の干渉が起きて、スクリーンに縞模様ができた」の間にある違いは、「観察の理論負荷性」を反映したものに他ならない。
このような単純な説明には── 「(分割しないはずの)1つの電子が、確率の波として同時に2つのスリットを通過して、干渉するのだ」という、“きわめて奇妙な説明”(“きわめて不自然で無理のある説明”)が不要になるという大きなメリットがある。
もしかしたら、「たとえ1つ1つの電子が、時間をずらして別々に投入されたとしても、スクリーンに縞模様ができる」という観測結果は、(「干渉によって縞模様が生じる」という説明に対する反証するものであり)、より単純なしくみで縞模様が生じること、すなわち、「“電子の消滅と生成の波”が実在し、それらの合計が縞模様を生んでいる」という単純な説明を支持するもの(反証しないもの)であると解釈できるのかもしれない。
(やはり、“観測の理論負荷性”の一種であると思われる)
※なお、スリットを1つにしてみると次のようになるだろう。
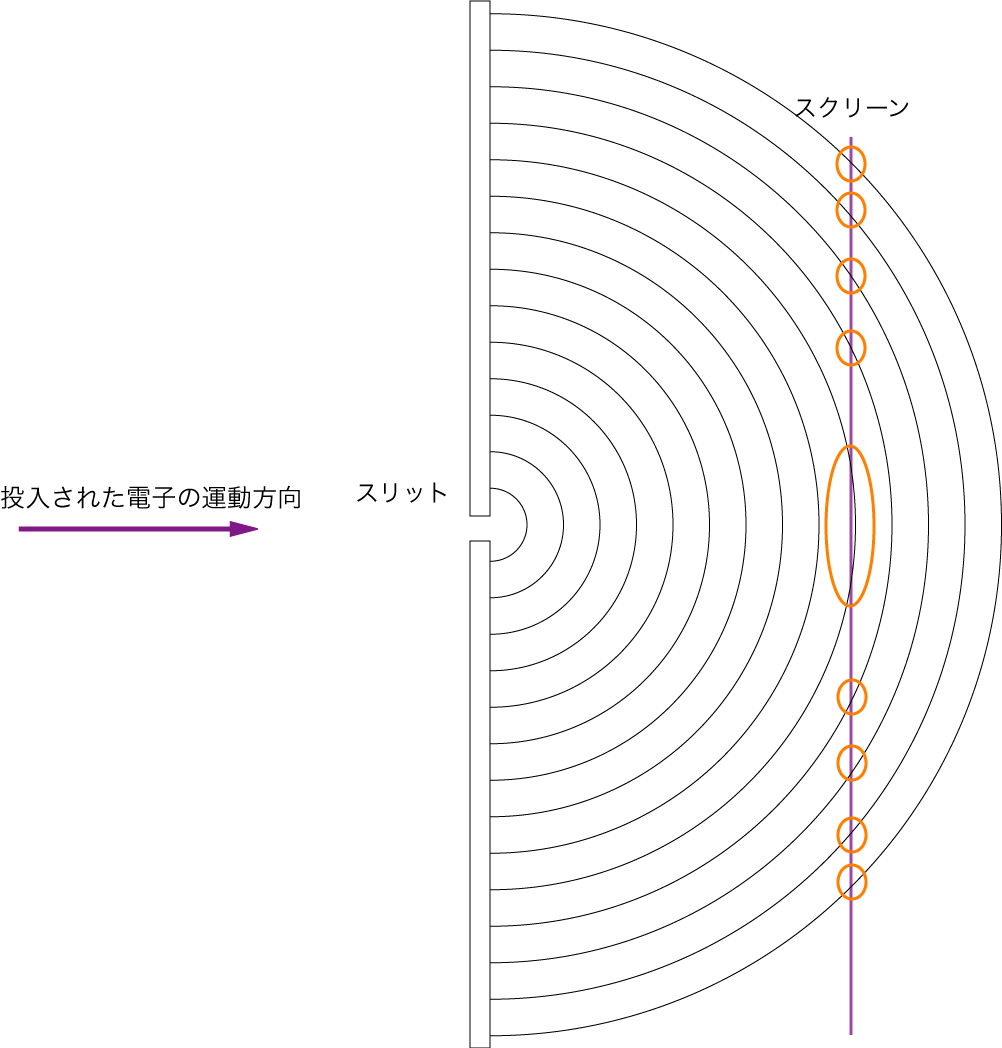
図のオレンジで囲った部分で、(相対的に生成度の高い電子が多くなるので)、電子による発光数が多くなると考えられる。 これは、“回折縞”が生じる理由を説明していると思われる。 すなわち、「スリットが1つの場合に、電子によって回折縞が現れる」という観測結果についても、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、説明できることになると思われる。
詳細な検討は、今後の課題である。
|
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)においては、
「1つの電子から生じた“両方のスリットを同時に通る、確率の波”が干渉しあって…」という、無理のある(奇妙な、不思議な…)説明は、不要となるのである。
1つ1つの(実在する)電子は、やはり、それぞれ、たった1つの軌道を、因果律に従って、進んでいるだけである。
これらの電子の到着ポイントを、複数(ある時間差の中で)足し合わせてみると、多く存在する部分、少ししか存在しない部分の濃淡、すなわち、縞模様が現れてくる。 これは、“波”に見える。 ただし、この“波”は、因果律に従う“実在する電子”の軌道運動を集計した結果、すなわち、“統計的な分布”にほかならない。
そして、この“電子の生成度”を集計したものは、「電子の“存在度”の分布」、あるいは、「電子の存在確率」であると見なしても、つじつまが合うであろう。
(すなわち、観測結果が、コペンハーゲン解釈で求めた計算結果とおおよそ一致するであろう。 詳細な検討は、今後の課題である)
(たとえ、コペンハーゲン解釈と結果がおおよそ一致しているとしても──)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明には、「両方のスリットを同時に通るような、(実在しない)確率の波の干渉」による説明が不要になるという大きなメリットがある。
よって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の予測をする。
予測4.1 「1つの電子が、両方のスリットを同時に通る」ことによって生じる“波の干渉”は、実在しない。
電子の場合と同様にして、光子の場合の“2重スリットの実験”を説明できる。
すなわち、「“光子を1つずつ、二重スリットを通過させて、ある1点を発光させる”という過程を繰り返すと、1つ1つの光子は、時間をずらして投入されているのに関わらず、スクリーンに縞模様ができる」ということも同様に説明できる。
そして、光子の場合においても、電子の場合と同様に、“1つの光子が、同時に両方のスリットを通過する結果生じる、波の干渉”によって「スクリーン上に縞模様ができる」という奇妙な説明は、不要となることがわかる。
その説明は、次のようになる。
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)においては、
光子についても、「1つの光子から生まれ“両方のスリットを同時に通る、確率の波”が干渉しあって…」という、無理のある(奇妙な、不思議な…)説明は、不要となるのである。
1つ1つの(実在する)光子は、やはり、それぞれ、たった1つの進路を、因果律に従って、進んでいるだけである。
これらの量子の到着ポイントを、複数(ある時間差の中で)足し合わせてみると、多く存在する部分、少ししか存在しない部分の濃淡、すなわち、縞模様が現れてくる。 これは、“波”に見える。 ただし、この“波”は、因果律に従う“実在する光子”の到達を集計した結果、すなわち、“統計的な分布”にほかならない。
そして、この“光子の到達”を集計したものは、「光子の“存在度”の分布」、あるいは、「光子の存在確率」と解釈しても、つじつまが合うであろう。
(すなわち、観測結果が、コペンハーゲン解釈で求めた計算結果とおおよそ一致するであろう。 詳細な検討は、今後の課題である)
(たとえ、コペンハーゲン解釈と結果がおおよそ一致しているとしても──)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明には、「両方のスリットを同時に通るような、(実在しない)確率の波の干渉」による説明が不要になるという大きなメリットがある。
よって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の予測をする。
予測4.2 「1つの光子が、両方のスリットを同時に通る」ことによって生じる波の干渉は、実在しない。
『「二重スリットの実験」は、電子、光子、いずれにおいても── 1つ1つの(実在する)量子のそれぞれが、因果律に従うたった1つの軌道・ルートを進んでいるだけで、それらの量子の振る舞いの総和によって、スクリーンに縞模様が創発するのである』というように、「電子や光子を1つずつ投入したとしても、スクリーンに縞模様ができる」ということを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、無理せず、自然に説明できるのである。
正しければ、「たとえ、1つ1つの光子や電子が、時間をずらして投入されても、スクリーンに縞模様ができる」ことが観測された時点で、『この縞模様は、「ふつうの波の干渉」とは、全く異なったしくみで生じている。 そもそもそ、干渉縞ではないのかもしれない』と考えるべきであったということになる。
そもそも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、二重スリットで生じる縞模様を説明できるのは── “量子波”の実体を 「滑らかに進む連続な古典的な波」と考えず、「デジタルな量子的な(とびとびの)波」と考えたおかげである。
(逆に“古典的な連続な波”のイメージにとらわれたせいで、「同時に両方のスリットを通っているのだ」という、強引できわめて奇妙な説明が生まれたとも考えられる)
このことは、量子論の世界に存在する波、すなわち、量子波は、「滑らかに進む連続な古典的な波」ではなく、「デジタルな(とびとびの)波」であると説明することは、さほど突拍子もないことではなく、むしろ自然な発想であることを示していると思われる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── 「二重スリットの実験」で、スクリーンに生じる縞模様は、「滑らかに進む連続な波の“干渉”によって生じているもの)」ではなく、「デジタルな(とびとびの)波の総和(合計)」として創発したものである。
電子&光子の「二重スリットの実験」の観測結果は、こういった“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明を支持するものであると解釈しなおすことが可能であると思われる。 (やはり、「観察の理論負荷性」の一例である)
※それでも、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)に基づく計算は、実用上は、(観測値の確率的な予想&説明のために)役立ち続けると思われる。
なぜなら、「観測上の限界(人類の観測事情)」、および、「決定論的カオス」が存在するからである。 詳細な検討は、今後の課題である。
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、「二重スリットの実験」を説明するために、少なくとも、「1つの量子が、不思議なしくみで同時に両方のスリットを通っているのだ」という奇妙な説明が不要になる以上、無理して“多世界解釈”することも、不要となると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※ところで、つぎのような記述がある。
|
『量子力学は, 粒子と波動の両方の性質をもつ電子のしたがう力学である. 原子核, 陽子, 中性子なども量子力学にしたがう』
(p.40 裳華房テキストシリーズ-物理学 『現代物理学』 原康夫著 裳華房)
|
『原子核, 陽子, 中性子なども量子力学にしたがう』ことは、「中性子ヒッグス場ユニット」や「陽子ヒッグス場ユニット」が、存在することを示唆しているのだろうか? それとも、アップクォークヒッグス場ユニット(uHU)、ダウンクォークヒッグス場ユニット(dHU)だけで、 “原子核, 陽子, 中性子”の波動性を説明できることを示唆しているのだろうか?
ここで、“C60の分子さえも縞模様を作る”(参考 『量子コンピュータ』 竹内繁樹 講談社ブルーバックス)ことを思い出してみる。
この“C60の分子さえも縞模様を作る”ことは── (さすがに、「C60ヒッグス場ユニット」は、実在しないと思われるので)「中性子ヒッグス場ユニット」や「陽子ヒッグス場ユニット」が不要であり、アップクォークヒッグス場ユニット(uHU)、ダウンクォークヒッグス場ユニット(dHU)だけで、 “原子核, 陽子, 中性子”の波動性を説明できることを示しているように思われる。
そして、「アップクォークヒッグス場ユニット(uHU)、ダウンクォークヒッグス場ユニット(dHU)だけで、 “原子核, 陽子, 中性子”の波動性を説明できる」ならば、結局は、クォークヒッグス場ユニット(uHU)、ダウンクォークヒッグス場ユニット(dHU)までだけで、“C60の分子さえも縞模様を作ること”を説明できるを示しているように思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※当然、「EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の説明で、“観測結果との矛盾がないか?」の検討が必要である。
また、「“連続な波の干渉”によるのではなく、あくまで、個々の光子や電子の“デジタルな(とびとびの)量子波の集計”によって、縞模様が生じていること」を、はっきりと検証できる何らかの「実験&観測」をデザインすることが必要かもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
(例えば、電子や光子を1つ1つ投入する二重スリットの実験で、スリットを通らないで(orスリットを通ったあとに) 壁を跳ね返ってくる電子や光子をもしっかりカウントするような観測も役立つのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である)
《不確定性原理(不確定性関係)と量子ゆらぎ(仮想粒子)の実体──(単振動振幅)確定性原理》
不確定性原理とは、次のようなものである。
|
不確定性原理 一九二七年に、ヴェルナー・ハイゼンベルクの発見した原理。これにより、ある種の観測可能量のペア(たとえば位置と運動量、エネルギーと時間など)は、プランク定数により課される限界を超えて、同時に正確に測定することはできないことが示された。 (『量子革命』 用語集 p.496 下線は筆者による)
|
この記述からもわかるように──
不確定性原理は、本来、人類の観測事情(=測定事情)── すなわち、(マクロの自然(nature)である)人類が、ミクロの自然(nature)を観測しようとする(=測定しようとする)際に生じる事情を示す原理である。
つまり、不確定性原理は、“ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合い”を説明してくれる原理であり── 本来は、“ミクロの自然(nature)”自体がどうふるまうかを説明している原理ではないのである。
※なお、“不確定性原理”の代わりに“不確定性関係”という表記もあるが、後者も、人類の観測事情(=測定事情)を示しているという意味で、本質的に同じである。
以下では、不確定性原理(不確定性関係)と表記していくこととする。
※なお、“観測事情”であることは、「(不確定性原理を導いた)ハイゼンベルグの思考実験」だけでなく、「(不確定性原理を導く)波束」とも関連していることは次の記述からもわかる。
|
『同じ長さΔxの波束に対して何回も観測を行うと、粒子の位置の測定値は平均値の回りでΔxのばらつきをもち、運動量の測定値もΔp=(h/2π)Δkのばらつきをもつ。波の性質により、この2つのぱらつき(不確定さ)の間に次の関係がある。
ΔxΔp ≧ h/4π (6.43)
これがハイゼンベルク(Heisenberg)が提唱した不確定性原理である』
(『振動と波動』 吉岡大二郎 p.179 東京大学出版 下線は、筆者による。 なお原文では、“エイチバー”で表示されていたのをプランク定数hを使って表示している。 また、≧(二重線+不等号)は、原文では、(一重線+不等号)であった。)
|
「“人類の観測事情(=測定事情)”、すなちわ、“ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合い”を記述するものとしての、本来の不確定性原理(不確定性関係)」は、それ自体は、全く正しい。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「“人類の観測事情(=測定事情)”を記述する、本来の不確定性原理(不確定性関係)」で説明されてきた自然(nature)そのものが、どのようにして創発しているかを説明しようとする。
一方、この不確定性原理(不確定性関係)は、しばしば、「ミクロの自然(nature)の説明手段」として“転用”された。
|
本来の
不確定性原理(不確定性関係)
|
「不確定性原理(不確定性関係)の、
ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」
|
|
“ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合い”
を示す。
=“人類の観測事情(=測定事情)”を示す。
|
“ミクロの自然(nature)のみ”を
説明しようとする。
|
その転用は、ときに成功をもたらした。
※例えば、湯川秀樹による中間子の質量の導出は、こういった「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」によってもたらさられた成功の1つと言える。
しかし、ときには、迷走も、もたらした。
※例えば、場の量子論において生じた“発散の問題”&“繰り込み理論による解決”は、こういった「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」によってもたらさられた迷走の1つだと考えられる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」を、あたまごなしに全否定するものではない。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」が、なぜ、ときに成功をもたらし、そして、なぜ、ときに失敗や迷走をもたらしてしまったのか(うまくいかなかったのか)を説明しようとする。
以下に、これらの説明を示す。
不確定性原理(不確定性関係)は、その定式化からして、おおざっぱ&あいまいである。 そのことは、次の記述から、よく読み取れる。
『 Δx・Δp 〜 h (6.3)
が導かれる。
これハイゼンベルグの不確定性原理として有名な式である。〜。 おおざっぱには、両者の不確定の積はh 程度であり、書物によってはh/2、h/2π であったり、h/4πと書かれているものもある。
これらのうちどれが正しいのか、といわれても、Δxの定義が人によって必ずしも一致していないのだから仕方ない』
|
(『なっとくする量子力学』(p.200 都筑卓司 講談社) 一部省略。 下線は、筆者による。
入力できなかったので、ディラック定数(エイチ・バー、ディラック・エイチ)は用いずに、“プランク定数h”のみを使って統一して表記した)
( 便宜上、この論文では、不確定性原理(不確定性関係)の式は 以後、「ΔX ・ΔP ≧ h/4π(ΔE・Δt ≧ h/4π)」と記述して、話を進めていくこととする) |
このように、不確定性原理(不確定性関係)の式が、おおざっぱ&あいまいになっている理由は、ミクロの自然(nature)の幾何的な実体像が、欠けているからに他ならない。
なぜなら、ミクロの自然(nature)を探求する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)における式は、「ET=h、pλ=h」のように、明確なものとなるからである。
なぜ、ミクロの自然(nature)の幾何的な実体像が欠けているのだろうか?
それは、ハイゼンベルクが、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の幾何的な実体像」の探求は、無意味であると主張したからである(実質上、禁止したからである)。
つまり、不確定性原理(不確定性関係)は、“(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の探求をあきらめるべき、観測できるものだけを扱うべき”というハイゼンベルクの哲学の元に生み出されたものだからこそ、おおざっぱ、あいまいなのである。
不確定性原理(不確定性関係)は、“人類の観測事情”を記述すると同時に、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の探求」を徹底的にあきらめさせる原理でもあるのである。
(実際、多くの物理学者は、この原理のおかげで、胸を張って堂々とあきらめることとなった。 あきらめるからこそ、不確定性原理(不確定性関係)の式の、おおざっぱ&あいまいさは、よりいっそう正当化された。 そういう意味で、不確定性原理は、“自己保存的な原理”であると言える)
※なお、不確定性原理(不確定性関係)を生んだハイゼンベルクが、“(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)そのそものの探求をあきらめるべき”という哲学を持っていたことは、少なくとも、次の記述から読み取れる。
『量子的粒子は本性をはっきりさせようとしない。あいいれない描像を生じさせてしまう。それはハイゼンベルクが懸命に取り組んでいた謎だった。量子力学の隠された秘密を強引に暴き出し、量子の世界で何が起こっているのかを教えてくれる手だてを見つけることができるだろうか?
できるはずがない! ある日の夕方、物思いに耽りながら思い足取りで公園を歩き回っていたハイゼンベルクの頭にひらめいた答えがこれだった。 ヘルゴランド島で量子ジャンプを古典物理学の連続的な言葉で言い表すことはどうしてもできないと気づいたのとまったく同じように、今度も同様の考えが彼の目をさらに大きく開かせた。量子力学の系をどう扱っても、古典物理学で明確な意味をもたらすことはできないのだ。』
(p166〜167 『そして世界に不確定性がもたらされた ハイゼンベルクの物理学革命』 デイヴィド・リンドリー著 阪本芳久訳 早川書房 下線は、筆者による)
次は、ハイゼンベルク自身の言葉である。
『量子論の統計的性格はあらゆる知覚の不正確さと結びついているのだから、知覚された統計的な世界の背後にはなお、因果律の成り立つ「真の」世界が隠れているのではないかという憶測に心をそそられるかもしれない。 だがこのような思惑は、とくに強調するのであるが、非生産的であり無意味であると思われる』
(『アインシュタインvs.量子力学』p.260 下線は筆者による)
次は、ハイゼンベルクが(不確定性原理(不確定性関係)を生む前に)生んだ“行列力学”に関する記述である。
『その視覚化不能性──行列力学は原子領域の力学について描像を提供するのを意図的に回避したという事実──と、その基本的な表現形態である行列は、厳密に言えば何の意味も持たず、単なる形式的な記号でしかないということに嫌悪感を抱いた者も少なくなかった』
(『世界でもっとも美しい10の物理方程式』p.393 太線は、傍点であった。 下線は筆者による) |
例えば、“量子ゆらぎ(仮想粒子)”というミクロの自然(nature)を考えてみよう。
“量子ゆらぎ(仮想粒子)”は、これまでは、不確定性原理(不確定性関係)によって、説明されてきた。
実際、場の量子論(or 場の量子論を基礎理論とする素粒子物理学)の多くの教科書には、“量子ゆらぎ(仮想粒子)”が生じる原因が“不確定性原理であるかのような”記述が多く見受けられる。 すなわち、例えば、『不確定性原理(不確定性関係)によると、Δt程度の短い時間なら、エネルギー保存則を破って粒子が出現することがゆるされる』というような説明である。
しかし、ここには、本来、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の探求のあきらめ」を促している不確定性原理(不確定性関係)の転用によって、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)を記述しようとしているという“矛盾”が、ひそんでいる。
すなわち、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の探求をあきらめた結果、生まれている不確定性原理」が、なぜか、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)のふるまいを決める、“原因”にすりかえられているという矛盾である。
不確定性原理(不確定性関係)は、本来、ミクロの自然(nature)のふるまいを記述するものではないし、ミクロの自然(nature)のふるまいの“原因”ではありえないのだ。
それなのに、この(本来、ミクロの自然(nature)のふるまいの“原因”ではありえないはずの)不確定性原理(不確定性関係)が、ミクロの自然(nature)のふるまいの“原因”になりかわっていることは、何を意味しているか?
それは、“量子ゆらぎ(仮想粒子)”という(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)が、どのようなしくみで創発しているのかについての探求を、実質上、“堂々とあきらめている”ことを意味しているのだ。
すなわち、『不確定性原理(不確定性関係)によると、Δt程度の短い時間なら、エネルギー保存則を破って粒子が出現することがゆるされる』という説明は、どのようなしくみで、“量子ゆらぎ(仮想粒子)”が創発するのかについては、 実質的に何も説明していないに等しいことを意味しているのである。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の探求を、あきらめないのだった。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、“量子ゆらぎ(仮想粒子)”の実体は、「光子と原始ヒッグス場ユニット(PHU)」「重力子と原始ヒッグス場ユニット(PHU)」「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)」「クォークとクォークヒッグス場ユニット(uHU、dHU)」「グルーオンとプレオン∴ヒッグス場ユニット(∴HU)」などの相互作用から生じる“単振動”に他ならないのだった。
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“量子ゆらぎ(仮想粒子)”ついて、次のように説明していることになる。
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による
“量子ゆらぎ(仮想粒子)”の説明
|
0.エネルギー非保存の所産である。
(不連続な時空にもとづいており、ネーターの定理と調和している)
1. 実在のものである。
(摂動計算のために考えられたものに過ぎないと見なさない)
2.因果律に従う。
(“不確定性原理”が原因なのではない。 すなわち、(パウリの排他律などの)ミクロの自然(nature)そのものが持っている原因によって生じる。)
3. エネルギー的に単振動しながら生成&消滅するものである。
(“(単振動振幅)確定性原理”に従っている。 調和振動子に相当するものと言える)
|
この説明によると、仮想光子、LP光子、グルーオン、中間子のみならず──
(電磁波を構成する)光子、 重力子、そして、(波動性を持つ)電子も仮想粒子であると見なせることになる。
※なお、この説明によれば、例えば、光子による電子(電子&陽電子)の対生成は、“量子ゆらぎ(仮想粒子)”に含まれないことになる。 なぜなら、光子によって電子(電子&陽電子)が対生成する過程は、エネルギー保存則に従っているからである。
以下では、次の3つの系の量子ゆらぎ(仮想粒子)について、詳しく説明する。
|
1.「光子と原始ヒッグス場ユニット(PHU)」
2.「重力子と原始ヒッグス場ユニット(PHU)」
3.「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)」
|
1.「光子と原始ヒッグス場ユニット(PHU)」
それを説明するために、まず、例として、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の中で、“1つの素スピノールが転回する系”に注目してみる。
これは、光子の進行に伴う原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の単振動に相当する系である。
| ※上図の緑で囲まれた部分が、単振動の1周期分すべてを図示している。 1つの素スピノールが180度転回すると、“4面体”が変形し(“4面体”のバネが一部縮み)エネルギーが蓄えられ、再び、同じ素スピノールが180度転回すると、エネルギーが放出され、“4面体”に戻ることを示している。 |
この「1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の1つの素スピノールが360度転回する間のエネルギーの変化」は、「“4面体”←→変形した“4面体”(部分的に縮まったバネ)という単振動」におけるエネルギーの変化に他ならない。
そして、光子とは、「この原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”に蓄えられる単振動のエネルギーが、次から次へと、光速で伝わっていくもの」として創発したものということができる。
一方、光子1つのエネルギーは、E=hνであった。(アインシュタインの光量子仮説の式である。 h : プランク定数[J・s]、ν: 光の振動数[回/s])
ν=1/Tであるので、(T : 光の振動周期[T]) E=hν=h/T と変形できる。 したがって、 ET=h[J・s]という式が導かれる。
この「ET=h[J・s]」という式が、「光子によって、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの最大値E」と「光子を構成する素スピノールの転回周期T」の関係を示している式である。
(この式は、「光子の振動周期ν1/ν=T」は、「光子を構成する素スピノールの転回周期T」に等しいという重大な意味を含んでいることになる。
この式は、光子を創発する「1つ1つの“原始ヒッグス場ユニット(PHU)&素スピノール”」の振る舞いを決める“式”に相当すると言える)
この ET=h[J・s]の式は、「光子を構成する1つの素スピノールが360度転回する間に原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”に蓄えられるエネルギー振幅E[J]と、同じ素スピノールが360度転回する周期T[s]の積が、常に、プランク定数hに等しいことを意味している」と解釈できる。
(例えば、周期がT=1[s]なら、“4面体”に蓄えられるエネルギー振幅Eは、h[J]になる。 もし、周期がT=3[s]なら、“4面体”に蓄えられるエネルギー振幅E[J]は、h/3[J]になる。 周期がT=0.1[s]なら、“4面体”に蓄えられるエネルギー振幅E[J]は、10h[J]になる。…)
このET=h[J・s]という式は、「転回周期T[s]とエネルギー振幅E[J]の関係が、確定している」ことを意味している。
※1つの光子について成り立つ、ET=h[J・s]の関係は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の性質として、創発したものであると考えられる。
※1つの光子は、「2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”にまたがって存在する“2つの素スピノールの共転回”」として創発するのだった。
そして、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の蓄えられるエネルギーの合計は、常に、E=hνと一定になるのだった。(結果1)
この性質のおかげで、1つ1つの光子について、E=hν の式が成り立っていると言えることになる。
すなわち、このE=hνの式が示す実体的な意味は、もともと「光の振動数νが大きければ大きいほど、光子のエネルギーEが大きくなること」であるが── その根底に、光子を構成する素スピノールの転回周期T[s]と(その素スピノールを含む)原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギー振幅E[J]の間に、ET=h[J・s]の関係が存在していたということになる。
※このET=h[J・s]の関係のおかげで、光子は、そのエネルギーの大きさが変化しない限り、たとえ重力場が変化しても(≒波長λが変化しても)一定の振動数νのままに、真空中を進んでいくことができることになる。
一方、光子の運動量pは、p=E/c=h/λ[J・s/m](=[kg・m/s])と定義される。
よって、pλ=h[J・s]が導かれる。
この式は、「ある光子(≒2つの素スピノールの共転回)が運動量p(=E/c)を持っている場合、そのときの光子が持っている波長λ(すなわち、光子を構成する2つの素スピノールどうしの距離r=λ/2)が確定している」ことを意味している。
すなわち、 この式は、ある光子が持っている運動量p[kg・m/s]と波長λ[m]の関係が、確定していることを意味しているのである。
この1つの光子について成り立つ、pλ=h[J・s]の関係も、原始ヒッグス場ユニット(PUU)の“4面体”(および、構成する素スピノール)の性質として、創発されたものであると考えられる。
そもそも、“光子の運動量”とは、何なのか? “光子の運動量”の幾何的な実体像とは、どのようなものなのか?
については、結果1にて、次の仮説を立てたのだった。
仮説1.12 光子の運動量の実体は、下図のような光子を構成する素スピノールの“転回に伴う円に近い軌道運動”である。
※1つの“ヒッグス場ユニットの中の素スピノール”に注目して、その素スピノールの転回に伴う“円に近い軌道運動”を、拡大して(強調して)図示している。
※素スピノールが、180度転回したときが、転回に伴う運動量が最大になる。
素スピノールが、0度転回したときと、360度転回したときが、転回に伴う運動量pが最小になる。 |
光子は、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の素スピノールにまたがって存在しているので── 当然、運動量も、2つの素スピノールにまたがって存在していることになる。 2つの運動量は、それぞれ単振動(サインカーブ)的に変化すると考えられる。
(なぜなら、“2つ原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギー”がそれぞれ単振動(サインカーブ)的に変化し、運動量が式“p=E/c”で求まるからである)
そして、その2つの運動量の合計は、常に一定となる。
※共転回の開始と終了の時間経過をそろえて、図示されている。
※この図において、緑の縦線の部分が、1つの素スピノールの運動量の減少分に相当し、
ピンクの縦線の部分が、もう1つの素スピノールの運動量の増加分に相当する。
コサインカーブの対称性により、エネルギーの放出とエネルギーの吸収が、180度の共転回の間ずっと100%一致する。
つまり、共転回の間、素スピノールの転回に伴う運動量の総和は一定となる。
※この図は、“2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギー合計が一定になることを示した図”と同様の図である。
|
まさに、その合計の運動量が、pλ=h[J・s]の中のpであると考えられる。
つまり、「ある光子が持っている運動量p」とは、2つの“原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の素スピノール”が持つ運動量の(一定の)合計値であるということになる。
このpの値は、「光子によって、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられる運動量の最大値(振幅)」と理解することができる。
すなわち、この「pλ=h[J・s]」という式は、「光子によって、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられる運動量の最大値p」と「光子の波長λ(=光子を構成する素スピノールの(素スピノールの間隔r×2)」の関係を示しているのである。
※“光子の運動量p”も、“光子のエネルギーE”も、2つの“原始ヒッグス場ユニットの中の素スピノール”の共転回によって、とびとびで光速で伝わっていくものであるということになる。
※光子の流れにともなって、光子の運動量pやエネルギーEが、とびとびで移動していく様子を示している。
※図は、共転回の直後(or直前)の時点を示しているので、変形している原始ヒッグス場ユニット(PHU)は、1つだけになっている。
まさに、この時点で、1つ素スピノールが持つ運動量、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)が持つエネルギーは、それぞれ最大値をとっている。
|
光子のエネルギーと運動量は、似ている。 光子のエネルギーと運動量を比較し示すと次のようになる。
|
光子のエネルギー
|
光子の運動量
|
|
実体
|
“原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるもの
|
“原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の
素スピノール”の“円に近い軌道運動”
|
|
伝わるしくみ
|
2つの“原始ヒッグス場ユニット(PHU)”の中の
素スピノールの共転回によって、光速で伝わる
|
|
“2つ”にまたがる
エネルギー(or 運動量)の合計
|
E=hν(=h/T)
常に一定。
|
p=h/λ(=E/c)
常に一定。
|
|
変化
|
単振動(サインカーブ)
|
|
光子のエネルギー(or運動量)
の振幅
|
確定している。
(ET=h)
|
確定している。
(pλ=h)
|
2.「重力子と原始ヒッグス場ユニット(PHU)」
重力子についてはどうか?
原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)が持つエネルギーが重力子エネルギーEG[J](=EP/2π EP : プランクエネルギー)であり、
重力子の振動数がc/2LP[回/s]であるので、重力子の転回周期TG[s]は、2LP/c[s]である。 (結果1)
よって、 EGTG=EG×(2LP/c)=(EP/2π)×(2LP/c)=(hc/2πLP)×(1/2π)×(2LP/c)=h/2π2[J・s] となる。
重力子の場合は、光子と違い、転回周期TG[s]も、重力子エネルギーEG[J]も1つの値だけをとる。
以上のことは、この式は重力子の転回周期TG[s]とエネルギー振幅EG[J]が、確定していることを意味している。
※1つの重力子について成り立つ「EGTG=h/2π2」の関係は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の性質として、創発されたものであると考えられる。
|
「光子や重力子を構成する(360度の)素スピノールの転回周期」(=光子や重力子が振動する周期)と
「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”に蓄えられるエネルギー振幅」の関係
|
|
光子の場合
by 2つの素スピノールの転回(1つの共転回)
|
ET=h[J・s]
|
|
重力子の場合
by 4つの素スピノールの転回(2つの共転回)
|
EGTG=h/2π2[J・s]
(=EPTG=h/π[J・s])
|
なお、重力子の運動量pGを pG=EG/cと定義するのなら── 重力子の運動量pG(=EG/c)と重力子の波長λGの関係は、pGλG=h/2π2[J・s]と計算できる。
(h/2π2=EGTG=EG×(2LP/c)=(EG/c)×2LP=pG×2LP=pGλG[J・s])
するとやはり、この式は、重力子が持っている、運動量pG[kg・m/s]と波長λG(=2LP)[m]の関係が、確定していることを示している。
※やはり、1つの重力子について成り立つ、pGλG=h/2π2[J・s]の関係は、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の性質として、創発されたものであると考えられる。
|
「運動量」と「波長」の関係
|
|
光子の場合
|
pλ=h[J・s]
|
|
重力子の場合
|
pGλG=h/2π2[J・s]
|
これらの単振動の様子を示す式は、光子、重力子、あるいは、「エネルギー&転回周期、運動量&波長」に関わらず、単振動の振幅が確定していることを示している。
3.「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)」
電子の場合はどうなるか。
ド・ブロイの物質波の式により pe=h/λe となるのだった。(pe : 電子の運動量、λe : 電子の波長)
よって、peλe=h という関係が導かれる。
原子の周囲を軌道運動する電子に限定すると── その運動エネルギーは、Kn=2π2k2me4/n2h2と定義され、
この定義は、「vn=2πke2/nh」(by Kn=mvn2/2)、「λn=h/mv=nh2/2πmke2」(by mvn=pe=h/λn)と、等価なのであった。(→結果1)
よって、電子の振動周期Tnは、Tn=λn/vn=nh2/2πmke2×(nh/2πke2)=n2h3/4π2mk2e4 となる。
電子の振動周期Tnと電子の運動エネルギーKnの積をとると──
KnTn=2π2k2me4/n2h2×n2h3/4π2mk2e4=h/2 となる。
これは、KeTe=h/2 という関係が導かれたことを意味する。(Ke : 電子の運動エネルギー、Te : 電子の振動周期)
|
「電子の運動量の最大値(振幅)」と「電子の波長」の関係
|
「電子の運動エネルギーの最大値(振幅)」
と「電子の振動周期Te」の関係
|
|
電子の場合
|
peλe=h[J・s]
|
KeTe=h/2
|
電子の運動量pe=mvnも、運動エネルギーKe=Kn=2π2k2me4/n2h2も単振動(サインカーブ)的に変化する。
なぜなら、電子の消滅&生成により、電子の質量mが単振動(サインカーブ)的に変化するからである。
(すなわち、シュレーディンガー方程式の定常状態の解である波動関数ψが“サインカーブ”となるからである)
※なお、1つの「電子ヒッグス場ユニット(eHU)に蓄えられるポテンシャルエネルギー」も、単振動(サインカーブ)的に変化する。
そして、2つの「電子ヒッグス場ユニット(eHU)に蓄えられるポテンシャルエネルギー」の合計は、常に一定Eとなる。
このEは、1つの「電子ヒッグス場ユニット(eHU)に蓄えられるポテンシャルエネルギーの最大値(振幅)」に相当する。
このEと電子の運動エネルギーKeは、どのような関係を持っているのだろうか?(単純に等しいのだろうか?) 詳細な検討は、今後の課題である。
いずれにせよ「peλe=h」と「KeTe=h/2」の式は、電子の単振動(サインカーブ)的な変化の振幅、すなわち、「電子のエネルギーKe&振動周期Te」と「電子の運動量pe&波長λe」が確定していることを示している。
すなわち、電子(スピノールの一種)と電子ヒッグス場ユニットの相互作用によるゆらぎ(=電子の消滅と生成の波)の単振動も、振幅が確定しているのである。
以上より、光子、重力子、電子いずれも単振動にもとづいており、その単振動の振幅が確定していることがわかる。
※ 「単振動=調和振動(=線形振動)」である。
次のような記述もある。
『単振動を行なう系を調和振動子(harmonic oscillator)とよび』
(『岩波基礎物理シリーズ5 量子力学』(原康夫 岩波書店 p56)
|
この「単振動を行なう系である“調和振動子(harmonic oscillator)”」の例として、光子や重力子、電子も挙げられることになる。
単振動の振幅が確定していることを示す式をまとめると、次のようになる。
|
「運動量」と「波長」の関係
|
「振動周期」と「エネルギー振幅」の関係
|
|
光子の場合
|
pλ=h[J・s]
|
ET=h[J・s]
|
|
重力子の場合
|
pGλG=h/2π2[J・s]
|
EGTG=h/2π2[J・s]
(=EPTG=h/π[J・s])
|
|
電子の場合
|
peλe=h[J・s]
|
KeTe=h/2[J・s]
|
※このように単振動の振幅が確定していることは、“仮想光子”や“LP光子”についても、同様に成り立つことは自明のことである。
そして、クォーク、グルーオン、中間子… についても、同様に、単振動の振幅が確定していると考えるのは自然なことである。
一方、次の不確定性原理(不確定性関係)の式は、次のようになる。
ΔX・ΔP ≧ h/4π ΔE・Δt ≧ h/4π
この不確定性原理(不確定性関係)の式の構造は、一目見て、先の単振動の振幅が確定していることを示す式の構造(例えば、pλ=h[J・s]、ET=h[J・s])に、とても似ていることがわかる。
※まさに、このことが、「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)を探求するための道具としての転用」が、ときに、うまくいっている理由の本質であると考えられる。
すなわち、例えば、湯川秀樹による、中間子の質量の導出が成功したのは、不確定性原理(不確定性関係)の式の中の誤差ΔEと、“(確定している)単振動の振幅E”がちょうど合致したからでであることになる。
つまりは、「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)を探求するための道具としての転用」が成功するのは、“誤差Δ”が、“(確定している)単振動の振幅”に等しいときに限られると予想される。 詳細な検討は、今後の課題である。
このように式の構造が似ていることは、不確定性原理(不確定性関係)の式が説明しているところの“量子ゆらぎ(仮想粒子)”を支える実体は── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が説明しているところのミクロの自然(nature)、すなわち、「各種の“粒子とヒッグス場ユニット”の相互作用によって創発している、(振幅が確定している)単振動」と、本質的に同一のもであることを強く示唆していると思われる。
一方、不確定性原理の式の導出過程(ハイゼンベルグの思考実験)に関する文献を読むと── 不確定性原理の式は、結局は、「Δx ≧ λsinν、 Δp 〜 h/λsinν」 (λ: 光の波長、p : 光子の運動量(p=h/λ))という、2つの式を掛け合わせることによって導かれており(参考p.191〜194 『観測の理論 2 微視的現象の観測』 湯川秀樹著作集3)、不確定性原理の式の導出は、広がりを持った“光の波長λ”に、強く依存していることがわかる。 そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、“光の波長λ”とは、“光子の波長λ”、すなわち、“光子を構成する素スピノールの間隔の2倍に等しい”のだった。
つまり、以上より、(ハイゼンベルグによる)不確定性原理の式の導出は、結局は、光子が持っている“単振動の振幅”が確定しているという土台の上で達成されていると説明できることがわかる。
よって、一般化して、次の仮説を立てた。
仮説4.5.1 不確定性原理(不確定性関係)は、「あらゆる“量子とヒッグス場ユニットの相互作用”が、調和振動子(単振動を行う系)であり、その単振動の“振幅”が、因果律&実在論に従いながら100%確定している」という土台の上で、2次的に成立しているものである。
この仮説によれば──
『ミクロの世界においては、「光子、重力子、電子、クォーク、グルーオン、プレオン∴、素スピノール…」といった量子が「各種のヒッグス場ユニット」と相互作用する系は、調和振動子(単振動を行う系)であり、その“単振動の振幅”、すなわち、「エネルギーと周期」や「運動量と波長」は、それぞれ、因果律(決定論)&実在論に従いながら、100%確定している』ということになる。
このように、「エネルギーと周期」や「運動量と波長」といった、“単振動の振幅”が、因果律(決定論)&実在論に従いながら、100%確定していることを
“(単振動振幅)確定性原理”と呼ぶこととする。
この“(単振動振幅)確定性原理”は、「不確定性原理(不確定性関係)」と数式上は似ているが、その意味は、大きく異なるものである。
|
不確定性原理(不確定性関係)
|
(単振動振幅)確定性原理
|
|
「ミクロの世界の自然(nature)とマクロの世界の自然(nature)の
両方のふるまいの関係を説明してくれる原理」
(=“人類の観測事情”を記述)
|
「“ミクロの自然(nature)のふるまい”を説明する原理」
|
|
「エネルギーと観測時間」や「運動量と位置」といった
物理量は、観測上、確定せることができない。
(一方を観測によって確定させると、一方の誤差が無限大になる)
|
「エネルギーと振動周期」や「運動量と波長」といった
“単振動の振幅”は、ともに100%確定している。
(一方を理論によって確定させると、一方も理論によって確定する)
|
|
人類の観測には限界がある
|
人類の想像力には限界がない。
|
|
因果律× 実在論×
|
因果律○ 実在論○
|
|
ΔX・ΔP ≧ h/4π ΔE・Δt ≧ h/4π
|
|
pλ=h[J・s]
|
ET=h[J・s]
|
|
pGλG=h/2π2[J・s]
|
EGTG=h/2π2[J・s]
|
|
peλe=h[J・s]
|
KeTe=h/2[J・s]
|
|
不確定性原理(不確定性関係)とは──
『“(単振動振幅)確定性原理”に従っているミクロの自然(nature)を、マクロの自然(nature)の一部である人類が“各種の素粒子”を用いて実際に観測(測定)しようとすると、(まさに、その観測に使う“各種の素粒子”が持っている「100%確定している振幅を持つ“単振動”」が原因となって)どうしても誤差がでてしまう』というような 「ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合い」を反映した「人類の観測事情(測定事情)」を記述しているものなのである。
このように、結局は、「人類の観測事情(測定事情)」を示している原理である以上──
不確定性原(不確定性関係)は、やはり、本来は、「ミクロの世界の自然(nature)そのものが、どうふるまうか」や「人類が観測(測定)ではきない世界(プランクスケールほどのミクロの自然(nature))が、実際どうなっているか(どのうようなしくみで創発しているか)」について説明してくれる原理ではないのである。
つまり、不確定性原理(不確定性関係)を理由にして、“ミクロの自然(nature)のふるまい”、すなわち、“量子ゆらぎ”“仮想粒子の出現”… を説明しようとする試みは、本来は、やはり、無理のあることなのである。
そのように無理があるのは── 不確定性原理(不確定性関係)が、そもそも、“(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の探求をあきらめるべき”というハイゼンベルクの哲学の元に、生み出されたものなのであるので、当然といえば、当然のことである。
《 「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」が招いた損失》
確かに、「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」が、ときには成功をもたらした。
しかし、それは、本来は、例外的なことなことだった。
※その例外的な成功の一例が、湯川秀樹による、中間子の質量の導出である。 この中間子の質量の導出が成功したのは、不確定性原理(不確定性関係)の式の中の誤差ΔEと、“(確定している)単振動の振幅E”が、たまたま、ちょうど合致したからであると考えられることは、すでに述べた。
つまり、例外的な成功の理由は何かと言えば、不確定性原理と(単振動振幅)確定性原理の式の構造が、とても似た構造を持っていたことである。 すなわち、数式の構造が、とても似たものだったので、計算結果が、ときに、ミクロの自然(nature)と調和したものとなったのである。
「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」は、大きな損失も生んだのである。
その大きな損失とは、次の2つである。
1.ミクロの自然(nature)の探求をあきらめさせつつ、ミクロの自然(nature)像を“ただならぬもの”にしてしまった。
→その結果、例えば、「場の量子論」や「弦理論」を迷走させた。
2.シュレーディンガー方程式の価値・評価を低めさて、解釈をゆがめさせた。
→その結果、科学の多様性が損なわれた。
1.ミクロの自然(nature)の探求をあきらめさせつつ、ミクロの自然(nature)像を“ただならぬもの”にしてしまった。
その損失の1つは、(科学者のみならず哲学者を含め)多くの人が、『ミクロの自然(nature)は、“確率やランダムネス”に従うのだ。因果律が失われ、実在論(≒隠れた変数理論)も成立しないのだ。 ミクロの世界の視覚化は、絶対無理で、無意味なのだ』と考えるようになってしまったことである。
※例えば、次の記述は、典型的である。
|
『スーパーストリングの横顔を見てみよう。 長さ10-33センチメートル 〜 という短さである。 〜 この長さは、「プランクの長さ」ともいい、いわば長さの単位素
量である。いいかえるなら、これ以上小さなスケールの世界ではハイゼンベルグの不確定性原理が圧倒的に威力を発揮して、因果性に基づく物理的に意味のある議論が不可能になってしまう、そんな長さである』
(『最新 素粒子論 「究極の理論=Theory of Everything」を求めて』p74 学研) (※下線は筆者による)
|
つまり、本来は、「人類の観測(測定)事情」を示してくれる原理に過ぎなかったはずの不確定性原理(不確定性関係)を、ミクロの「自然(nature)の仕組み(振る舞い)」の説明手段として転用(濫用、誤用…)してしまうことによって、多くの物理学者が、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)についての、“ただならぬ描像”を持ってしまったのである。
その結果、不確定性原理(不確定性関係)は、「人類には、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)は、絶対想像もできないのだ(人類が視覚的描像を得るのは不可能なのだ)という、人類の想像(視覚化)不可能性」の根拠を示す原理として見なされ── そして、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)を合理的に探求すること」にブレーキがかかることになってしまったのである。
すなわち、この「“不確定性原理(不確定性関係)”の、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」は、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の探求の放棄」や「視覚化不可能」という哲学を正当化し、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の探求」や「視覚化可能」という方向性を持つ研究の誕生を妨げたのである。
そして、まさに、このことが、現代物理学に、危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、混乱、停滞…”をもたらしてしまう大きな原因の1つとなってしまったのである。
例えば、「場の量子論」や「弦理論」を迷走させた理由の1つは、以上のような「“不確定性原理(不確定性関係)”の、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」が生んだ損失であるおそれがある。 すなわち、
「場の量子論」において、「発散」という問題が生じ、「繰り込み理論」という解決法がとられたことも──
「弦理論」(→考察3)において、「光が質量を持ってしまう」問題が生じ、「10次元(or26次元)」という解決法がとられたことも──
「“不確定性原理(不確定性関係)”の、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」が生んだ損失が理由の1つとなって生じた“迷走”であるおそれがあるのである。
(なぜなら、「場の量子論」も 「弦理論」(→考察3)も、「“不確定性原理(不確定性関係)”の、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」を基礎の1つにおいて育まれているからである)
※例えば── 「人間の観測事情にすぎなかった不確定性原理(不確定性関係)を、(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)のふるまいを説明する原理であるかのように転用してしまった」からこそ、“発散”という重大な問題が生じてしまったおそれがあるのである。
そして、もしかしたら、その発散という重大問題を解消するためにひねり出された「繰り込み理論」は、そういった発散を生じてしまう“場の量子論”を存続させるための“周天円”のような無理のある理論にすぎなかったおそれがあるのである。 詳細な検討は、今後の課題である。
(かつての“天動説&周天円”の理論も、観測値と正確に合致していたことを思いおこすならば── 観測値との正確な合致だけでは十分ではなく、やはり、自然(nature)そのものとの合致こそをめざすべきだということなのだと思われる。 すなわち、数字の一致は、必要条件で十分条件ではないということなのだと思われる。 →考察2)
なお、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、あらゆる量子と各種のヒッグス場ユニットの相互作用は、“(単振動振幅)確定性原理”にしたがって、単振動しており(線形であり)、因果律に従い、振幅が100%確定しているものなので(“有限のサイズをもって、決められたふるまい”をするものなので)、「発散問題」は生じず、繰り込みも不要になると考えられる。
※発散についての次の記述も参考になる。
|
『なぜ発散するのであろうか? 量子的な場は空間の1点1点は量子力学的自由度を持つので、無限の自由度を持つ。これらの自由度は基本的に全てが量子効果の中間状態に寄与できるため、寄与を足し上げると無限大になってしまうのである。たとえば空間を有限の自由度しか持たない格子で近似すると、摂動論高次の寄与も発散しない。格子間隔を小さくして連続理論に近付けるとこれらの寄与は一般に発散する』
(p.96『素粒子物理学』 原康夫・稲見武夫 青木健一郎 著 朝倉書店 下線は筆者による)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に登場する、各種のヒッグス場ユニットが、まさに、「(“(単振動振幅)確定性原理”に従う)有限の自由度しか持たない格子」に相当すると考えられるものなので、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)において発散は生じないと考えられる。それは、重力場も、電磁場も同じである。
2.シュレーディンガー方程式の価値・評価を低めさせ、解釈をゆがめさせた。
「“不確定性原理(不確定性関係)”のミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」が生んだ、もう1つの損失は「シュレーディンガー方程式」の価値・評価が低められ、そして、解釈がゆがめられてしまったことである。
「シュレーディンガー方程式」と「行列力学」は、数学的(数式的)には、等価であるとよく言われている。
しかし、その“イメージ喚起性”を含め、物理学的には、等価ではない。
| ハイゼベルグの行列力学 |
シュレーディンガーの波動方程式 |
|
視覚化不可能
|
視覚化可能
|
|
観察可能なものだけに
物理学を制限する
|
観察可能なものだけに
物理学を制限しない
|
|
抽象的
|
具体的
|
※参考 『世界でもっとも美しい10の方程式』
ところが、「“不確定性原理(不確定性関係)”のミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」は、「シュレーディンガー方程式」を価値・評価を低めさせて、解釈をゆがめさせると同時に、「行列力学」(および、「コペンハーゲン解釈」)の主張を正当化させる── という効果を持っていた。
その結果、科学の多様性が損なわれてしまったのである。
損なわれた科学スタイルとは、「(観測不可能なものも含めた)ミクロの自然(nature)の視覚化を探求する」というシュレーディンガーの波動方程式が持っていた科学スタイルである。
優位となった科学スタイルとは、「観察可能なものだけを、対象にすべきである。 (観測できない)ミクロの自然(nature)の視覚化の探求はあきらめるべきである」というハイゼンベルクの行列力学が持ていた科学スタイルである。
「ハイゼベルグの行列力学」と「シュレーディンガーの波動方程式」の“対立”に関して、次のような記述がある。
|
『ゲッチンゲン陣営側の物理学者たちの反応はまるで喧嘩腰だった。 ハイゼンベルクは、「うまくできすぎていて、正しいとは思えない」と言い、ディラックは「敵意」ある反応を示し、パウリは「ばかげている」と言った。 だが、たちまちのうちに、彼らの多くが波動力学に魅せられてしまった。 パウリは、水素スペクトルの理論を行列力学を使ってたいへんな苦労の末に作り上げた挙句に、波動力学を使えば同じことがはるかに簡単にできることに気づいた』
(『世界でもっとも美しい10の方程式』 p.394 下線は筆者による)
『この対立は、手法の科学的価値を巡る先ほどの対立よりも、はるかに勝負がつきにくく、しかもはるかに感情的なものであった。というのも、これは激論を交わしている物理学者たちの個々人が、物理学とはいったい何なのか、世界とは何かという意識、そして、人類と世界の基本的な関係をどのように捉えるかということを反映する問題だったのである』 (『世界でもっとも美しい10の方程式』 p.397 下線は筆者による)
『ハイゼンベルクの反論は、少なくとも痛烈さの点ではまったく引けを取らなかった。 彼は波動関数を「虫唾が走る」ような「ゴミ」だと言った。視覚化可能な限りは導関数は間違いだと主張した。 行列力学を使う物理学者は、そんな甚だしい思い違いはしないし、それゆに自然のさらに深い奥を見抜くことができると述べた』
(『世界でもっとも美しい10の方程式』 p399 下線は筆者による)
|
つまり、不確定性原理(不確定性関係)が育まれる背景にあったのは、合理的な科学的な営み(真実探求の営み)と言うより── 自己の理論の生き残りをかけた“排他的・独善的な感情”だったのである。
たった、それだけの動機がきっかけとなって── 貴重な“科学の多様性”が損なわれてしまったのだ。
すなわち、(このような背景で生まれた)不確定性原理(不確定性関係)が、ミクロの自然(nature)の説明手段として転用された結果── 「たちまちのうちに、彼らの多くが波動力学に魅せられてしまった」「波動力学を使えば同じことがはるかに簡単にできる」という、もともと、「シュレーディンガーの波動方程式」が圧倒的に有利で、「ハイゼベルグの行列力学」が不利だった形勢を、すっかり、ひっくりかえしてしまったのである。
※なお、本来の、(人類の観測事情を示す)“不確定性原理(不確定性関係)”には、ひっくり返す力はない。「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」にこそ、その力があったのである。
「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」は、多くの物理学者に共有されたことはハイゼンベルクらにとって都合が良かった。
なぜなら、シュレーディンガー方程式の価値・評価を低下させ、自らの理論(行列力学、不確定性原理(不確定性関係))の優位性のアピールに必死だったハイゼンベルクらにとって、追い風となったからである。
そもそも、ここにあったのは、厳密に言えば、合理的な真実探求の問題ではなく── (大した根拠のない)哲学の選択の問題、すなわち、「物理学とはいったい何なのか、世界とは何かという意識、そして、人類と世界の基本的な関係をどのように捉えるかということを反映する問題」であった。 それにも関わらず── シュレーディンガー自身による、シュレーディンガーの波動方程式の解釈が失敗した(自然(nature)と乖離したものだった)ことも追い風となり、「“不確定性原理(不確定性関係)”のミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」は、圧倒的に優位となった。
そして、「“不確定性原理(不確定性関係)”のミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」が持っている、自然(nature)からの乖離性は、物理学を迷走させる原因の1つとなった──。
やはり── 自然(nature)と調和する限り、科学スタイルの多様性は尊重されなければならない。
ハイゼンベルクの科学スタイルも、シュレーディンガーの科学スタイルも、自然(nature)と調和する限り、ともに尊重されなければならない。
どちらかが、不当に(大した根拠もなく、排他的・独善的な感情によって)、ゆがめられたり軽視されたりすることは、物理学にとっての損失である。
なぜなら、“自然(nature)と調和している科学の多様性”が損なわれるということは── 自然(nature)により近づくための、ヒント、チャンス… がせばめられてしまうことを意味しているからである。
《ハイゼンベルクの科学スタイルと“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の科学スタイル》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ハイゼンベルクの科学スタイルも、シュレーディンガーの科学スタイルも、それぞれに、かけがえのないよさ&存在意義を持っていることを示している。
確かに、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、シュレーディンガーの科学スタイルを包含していると言えるほど、シュレーディンガーの科学スタイルを支持し、そして、シュレーディンガー方程式の価値・評価を回復するものである。
しかし、そうだからといって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ハイゼンベルグの科学スタイルを全否定するものではない。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ハイゼンベルグが生んだ、本来の不確定性原理(不確定性関係)── すなわち、人類の観測事情(応用事情)、すなわち、「ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合いを教えてくれる」という不確定性原理(不確定性関係)にも、重大な存在意義があることを、はっきりと認めている。
|
その存在意義の1つは、人類の観測(測定)上の限界、応用上の限界を示してくれるおかげで、ある種の安全性を保証してくれることである。 すなわち、たった1つの電子に働きかけ、電子が持っている電荷のエネルギーや磁荷のエネルギーを引き出すことは不可能であることをはっきり教えてくれることである。
もう1つ存在意義は、ハイゼンベルグの不確定性原理が、人類が観測(測定)できること、人類が応用できることの限界を示してくれたおかげで── 早々と“量子論の応用(実用)に専念できたことである。 そのおかげで、エレクトロニクス、電化製品、コンピュータ… といった多くの恩恵が得られたのである。
|
ここで、ハイゼンベルクの科学スタイルと、(シュレーディンガーの科学スタイルを包含するところの)“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の科学スタイルの違いを整理しておく。
|
ハイゼンベルクの科学スタイル
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の科学スタイル
|
|
観測
|
観測できるもののみを対象にしよう
|
観測できないものを含めて
想像力&理論の力で、探求しよう
|
|
主な対象
|
ミクロの自然(nature)と
マクロの自然(nature)の関わり合い
|
ミクロの自然(nature)の中の相互作用
|
|
存在意義
|
人類の観測(測定)上の限界、
応用上の限界を示してくれる
→安全性の保証、応用への専念。
|
自然(nature)と調和している
“研究の方向性”を示してくれる。
→現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”の解消
|
|
包括性
|
量子論
(量子力学、場の量子論)
を包括する
|
ニュートン力学、相対性理論、電磁気学、
不確定性原理(不確定性関係)、量子論、
素粒子物理学の標準模型… を包括する。
|
|
量子の世界で
何が起こっているのか
を見つけること
|
「できるはずがない!」
|
「できる!」
|
|
量子ゆらぎや仮想粒子
を説明する原理
|
(本来、人間の観測事情を示すはずの)
不確定性原理(不確定性関係)の、
ミクロの自然(nature)の
説明手段としての転用。
|
ミクロの世界の自然(nature)が
どうなっているかを示す原理である
“(単振動振幅)確確定性原理”
|
|
発散
|
生じる
|
生じない
|
|
波動関数ψ
|
コペンハーゲン解釈
(重ね合わせの原理&確率解釈)を支持
※確率解釈は、行列力学と調和
|
“粒子の生成と消滅の波”を意味する
|
|
ミクロの自然(nature)
についての描像
|
ミクロの自然(nature)は、
ランダムさに従う。
常に「ランダムなサイコロ」が振られている
|
ミクロの自然(nature)は、
(単振動振幅)確定性原理に従う。
ときに「決定論的なサイコロ」が振られている
|
|
因果律
|
×
因果律に全く従わない
|
○
ときに、決定論的カオスに従う
|
|
実在論
(隠れた変数理論)
|
×
|
○
|
|
背後に「因果律の成り立つ
「真の」世界が隠れている」
という発想
|
「非生産的であり無意味である」
|
フルーツフルである(生産的である)
意味がある。
|
※グレーで示したのは、自然(nature)から乖離していると考えられる部分である。
やはり、自然(nature)と調和している限りは、多様な科学スタイルは、尊重されるべきである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ハイゼンベルクの科学スタイルも、シュレーディンガーの科学スタイルも、ともに、自然(nature)と調和する限り、尊重しているものである。
不確定性原理(不確定性関係)の抽象的な数式、それ自体は正しい。
ただし、それは、本来、「人間の観測(測定)事情」を示している(“ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合い”を説明している)── という意味において言えることである。
しかし、もし、この不確定性原理(不確定性関係)の抽象的な数式を、ミクロの自然(nature)の説明手段として転用し、例えば、「“ミクロの自然そのものが、ランダムネスに従う”ことを示している」「ミクロの自然(nature)そのものの探求は、非生産的であり無意味である」と解釈するのならば── そこにあるのは、自然(nature)からの乖離なのである。
もしも、仮にミクロの世界の自然(nature)そのものが、本当に、“確率やランダムネス”に従って、“(単振動振幅)確定性原理”が成立していなかったとしたらどうなるか?
光子の波長や運動量も、振動数やエネルギーも、光速も、不規則に変化しまくってしまうだろう。
重力子の波長や運動量も、振動数やエネルギーも、光速も、不規則に変化しまくるので、重力子として存続できなくなってしまうだろう。
電子やクォークの波長や速度、質量(運動エネルギー+静止質量エネルギー)も、不規則に変動しまくってしまうだろう。
電子やクォークは、プレオン∴に分解しまくってしまうだろう。
…
「ミクロの自然そのものが、“確率やランダムネス”によって支配されている」という考えは、明らかに、実態とかけ離れているのである。
※このように、抽象的な数式の解釈は慎重にやらないと、自然(nature)と乖離してしまいうるのである。(→考察2)
同様な例として、 E=mc2 が挙げられる。 (→結果1)
ハイゼンベルグの不確定性原理(不確定性関係)の数式そのものは正しいが、本来、やはり、あくまで「人類の観測(測定)事情」を示している原理に過ぎない。
そして、決して、ミクロの自然(nature)の振る舞い方を示している原理ではないのだ。
そのことを、他ならぬハイゼンベルク自身も気づいていたはずである。 なぜなら、ハイゼンベルグ自身が、『初期条件を知ることができればその後の粒子の軌跡を予測できることは認めている』からである。 (『アインシュタインvs.量子力学』p.260、一部省略。傍点を太線に変えた。下線は筆者による)
それなのに、なぜ、「“不確定性原理(不確定性関係)”の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」を黙認したのだろうか?
それほど、シュレーディンガーの波動方程式に対抗するために、生き残りをかけて必死だったからなのだろうか?
いずれにせよ── ハイゼンベルクの(自然(nature)と調和している)科学スタイルが持っている“重大な存在意義”は、ゆらがないのであろう。
確かに、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)」を探求することには── 観測によって初期条件を知り得ない以上、未来が“予測”ができなくなるという意味では、観測上や応用上、存在意義がなくなる。
しかし、その中で、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の真の姿(true picture at Planck scale)」を探求することの存在意義は何であろう。
1つは、「(正確に観測できないけれど、実在しているはずの)ミクロの自然(nature)」がどうなっているかを、“自然な世界観”を持ちながら合理的に探求し続けることにも、「観測上&応用上の限界を見極める」という意味があるからである。
例えば、「(正確にor全く観測できない)ミクロの自然(nature)の真の姿(true picture at Planck scale)」の探求により、『「絶対に発見(観測)できない“何か”」を観測しようとするために、巨額の資金、多くのマンパワーが浪費されてしまうことを防ぎ、より有意義な分野に資金やマンパワーを振り向けることができる』といった意義が生まれうるのだ。
そして、もう1つは、(正確にor全く観測できない)「実在しているはずの自然(nature)」を合理的に探究することには、「理論上&真実の探求上の限界を見極める」という意味もあるからである。
例えば、『「絶対に完成できない“理論”」を完成させようとするために、貴重な優秀な頭脳が浪費されてしまうことを防ぎ、より有意義な分野にその能力を振り向けることができる』といった意義が生まれうるのだ。
(例えば、理論物理学界において、「“超弦理論”が主流である」という状況は、貴重なマンパワー、頭脳、資源… の浪費である可能性があることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、示しているようである。 →考察3.超弦理論〈Super String Theory)について)
つまり、「(正確にor全く観測できない)実在しているはずのミクロの自然(nature)」を“自然な世界観”を持ちながら合理的な探求することには、“研究の方向性を示してくれる”という意味がありうるのだ。
※貴重なマンパワー、頭脳、資源… を投入していくべき大事な研究、すなわち、現代社会において「優先すべき科学的な課題」「優先すべき大事な研究のフィールド」には、具体的には、次のようなものがあると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
例えば、 人工光合成(人工葉)などによって太陽光を有効に活用する研究、
例えば、水素や電子を有効活用するための研究
例えば、「異なった文化を持つ人どうしが、どうしたら、互いを尊重しながら、調和的に生きていけるか?」についての研究
例えば、気候変動をマイルドに保つ方法についての研究
例えば、人や社会、生態系に優しい研究とは何かについての研究
…
|
そして、そういった「観測不能なミクロの自然(nature)」を合理的に探求しようとする営みの一例として、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)があるのだ。
確かに、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「抽象的であいまいな“不確定性原理”」に基づいて探求する営みに比べて、より具体的であいまい性が少ない分、相対的に“間違い”(≒自然(nature)との乖離)が発見されるリスクが大きくなるであろう。
しかし、“間違い”が発見されやすいということは、“間違い”に“気づきやすい”ということに他ならない。
「抽象的であいまいな不確定性原理(不確定性関係)」による探求よりも、「具体的なあいまい性の少ない“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)」による探求の方が、“間違い”(≒自然(nature)との乖離)に気づきやすいということは、何を意味するのか?
それは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の方が、その“間違い”に気づきやすい分── (その間違いを解消していくことによって)進化させ続けることが、より容易であることを意味するのだ。
“科学が進化する”とは、“自然(nature)に、より近づいていく”ということに他ならない。
そして、自然(nature)と、より調和・合致したものへ進化することこそが、本来、科学の営みの主流だったはずなのだ。
確かに、これまでの科学は、そのようにして進化してきた。
※『アリストテレス、プトレマイオス→コペルニクス→ケプラー、ガリレオ→ニュートン
→ファラデー、マクスウェル→アインシュタイン
→プランク、(アインシュタイン)、ボーア、ハイゼンベルク、シュレーディンガー…』
間違いに気づくことができること(間違いを指摘できること≒ “反証可能性を持つこと”)が、科学が進化できること、すなわち、「“自然(nature)に、より近づいていける”科学スタイル」の条件の1つであると言える。
逆に、間違いに気づきにくい(間違いを指摘しにくい)性質を持つ、「抽象的であいまいな不確定性原理(不確定性関係)」による探求は、「“自然(nature)に近づく”ことが、より困難な科学スタイル」である恐れがある。
すなわち、「抽象的であいまいな不確定性原理(不確定性関係)」による探求は、相対的に“間違い”を発見されるリスクが小さいこと(“間違い”を発見できチャンスが小さいこと)が裏目となり、「“自然(nature)に、より近づいていく”という科学の進化」を停滞させうる恐れがあるのである。
|
ハイゼンベルクの科学スタイル
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の科学スタイル
|
|
抽象度、あいまいさ
|
抽象的、あいまい
|
具体的、明確
|
|
間違い
(≒自然(nature)との乖離)
|
“間違い”を発見されるリスクが小さい
→間違いを解消しにくい。
=科学が進化しづらい
|
“間違い”を発見するチャンスが大きい
→改善によって間違いを解消しやすい。
=科学が進化しやすい
|
※グレーで示したのは、結果的に、自然(nature)からの乖離につながると考えられるからである。
※「抽象的であいまいである」という科学スタイルが持っている、否定されくい(批判されにくい、反証されにくい)という性質は、実は、同時に、進化しにくくなる(真実を探求しにくくなる、自然(nature)を探求しにくくなる)というマイナスの性質でもあると思われる。 |
そして、実際に、このことも、現代物理学に、危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走、混乱、停滞…”をもたらしてしまう原因の1つとなってきた恐れがあるのである。
(詳細な検討は、今後の課題である)
《ハイゼンベルクの封印》
“不確定性原理”は、本来、「人類の観測事情」(ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合い)を教えてくれる原理であり── “ミクロの自然(nature)そのものが、どのようにふるまうかを説明する原理ではない。
したがって、例えば、この“不確定性原理”をよりどころにして、“ミクロの自然(nature)は、ランダムネスに従う、不確定な存在である”などとは、決して言うことはできない話なのだ。
やはり、『(決定論的で因果関係を持つ)“(単振動振幅)確定性原理”にしたがって、ミクロの自然(nature)が実在しており、そのミクロの自然(nature)をマクロの人間が観測しようとする際には、誤差が生じざるをえなくなる』ということを不確定性原理(不確定性関係)が教えてくれる、ということなのだ。
そして、ハイゼンベルグによる「非生産的であり無意味であると思われる」という主張の根底にあったのは、決して明確な根拠や原理ではなく── ハイゼンベルグの哲学(姿勢、価値観、好み(taste)、ひらめき(直観)、こだわり、社会的な事情…)、すなわち、1つの科学スタイルに過ぎないのであった。
しかも、ハイゼンベルグ自身は、『初期条件を知ることができればその後の粒子の軌跡を予測できる』ことを認めていたのだ。
もう、そろそろ、『ハイゼンベルグの封印──不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用、あきらめ宣言、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)のやみくもな推奨、シュレーディンガーの波動方程式に対する低評価…』を解消して、「より“自然(nature)に近づく”科学」としての進化を再開してもいいのではないだろうか?
もう、そろそろ、現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、困難、迷走…”を解消するべく、勇気を振り絞って、未踏の地を、合理的に探求していってもいいのではないだろうか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ミクロの自然(nature)の各種の実体は、“(単振動振幅)確定性原理”に従うこと、すなわち、「各種の量子と各種のヒッグス場ユニットの相互作用によって創発する単振動」の振幅が100%確定していることを示している。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“各種の粒子&ヒッグス場ユニット”の単振動を念頭に置くことによって── 「たとえ直接の観測は不可能でも、誤差0の思考実験(思考観測)はできること」、「理論上はすべてを把握できて、確率に頼らなくてすむこと」… を示している。
そこに、“限界につきあたった感”(あきらめ感)はない。
《素スピノール》
結果1にて、素スピノールが転回している最中のエネルギーの変化を、「sin2θ=(1−cos2θ)/2」のカーブで示した。 よって、単振動中の、ある瞬間にどんな値をとるかさえも、理論上計算できるようになると考えられる。
《電子》
“(単振動振幅)確定性原理”によって、例えば、電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)との相互作用に伴う「消滅と生成の単振動」の過程で、ある瞬間に、運動量pや波長λ、運動エネルギーKや振動周期Tが、どんな値をとるかについて、理論上計算できると考えられる。
(いわゆる“先導方程式”とは、関係あるのだろうか? 詳細な検討は今後の課題である)
《光子》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、光子は、2つの素スピノールから構成されており、広がりを持っているものである。
したがって── 光子の位置を、例えばΔx=0の測定精度で(“光子は広がりのない点である”ということを前提として)、観測しようとすることに、そもそも無理がある(意味がない)と考えられる。
すなわち、もし、光子を“2つの素スピノールの位置”として、全体的に把握できれば── 運動量も、同時に(理論的に計算できるのみならず)正確に把握できると考えられる。 (同様に── もし転回周期Tの時間をかければ、エネルギー振幅も、同時に、正確に把握できる、ということになると考えられる)
|
つまり、“広がりのある幾何学的な実体像”を前提として、(観測ではなく)想像上で把握しようとする分には、“不確定性”はどこにも生じないと言える。
よって、確かに観測技術的には難しいとしても、位置と運動量、時間とエネルギーの両方を同時に決めることは“原理的には(理論上は)可能”であることになる。
すなわち、“(単振動振幅)確定性原理”に基づけば、理論的には両者を計算によって同時に導出できることになる。
「量子ゆらぎ(仮想粒子の生成&消滅)」を担う実体は、「各種の“量子&ヒッグス場ユニット”」であり、それらは、調和振動子(単振動をする系)である。
これらの挙動は、各種のヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギー振幅や、各種の量子の振動周期、各種の量子の運動エネルギーの振幅や運動量の振幅、波長… といった“単振動の振幅”を確定してくれる式── “(単振動振幅)確定性原理の式”、および、“サインカーブ”に相当する式という、シンプルな(不確定性のない)式で、理論上(想像上)、明確に記述することができる。
「量子ゆらぎ(仮想粒子の生成&消滅)」は、実在する「各種の“量子&ヒッグス場ユニット”」の、実在論&因果律に従う(確定的な)ふるまいの総和として創発してきており── 不確定性原理(不確定性関係)は、その創発してきたミクロの自然(nature)を、マクロの人類が観測(測定)する際に生じる事情を示している。
以上が、「量子ゆらぎ(仮想粒子の生成&消滅)」の幾何学的な実体像と、不確定性原理(不確定性関係)についての“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明である。
※湯川秀樹の中間子の理論(「電子の約200倍の質量を持つ中間子を予言」)も── この“(単振動振幅)確定性原理”によって、より正確に導くことができると考えられる。 なお、「不確定性原理の“不確定性関係”としての転用が成功する」のは、誤差Δが、ちょうど単振動の振幅に等しいときに限られると思われることは、すでに述べた。
※「ある固体の中で、整然と並んだな原子or分子の振動エネルギーも、hνの整数倍となる」とのことである。
この振動についても、“(単振動振幅)確定性原理”の式によって説明できることを示していると思われる。 詳細は今後の課題である。
※なお、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次のような記述とも調和している。
『 隠れた変数は、普通の変数とは違って測定することができず、それゆえ不確定性原理の支配を受けない。フォン・ノイマンは、こう論じた』
(p.438 『量子革命』)
|
例えば、を観測できない個々の素スピノールは、不確定性原理の支配を受けるものではないということになる。
※なお、不確定性原理は、ボーアの相補性原理によって、説明できると言われている。
ハイゼンベルグの哲学の形成に対して、上司であるボーアの哲学(相補性原理)が影響したことも考えられる。
《電子が原子核に落ち込まないこと》
「電子が原子核に落ち込まないこと」も、これまで、不確定性原理(不確定性関係)で説明されてきたことの1つである。
すなわち、「不確定性原理(不確定性関係)によると“電子の位置が確定するほど、運動量が無限大にゆらぐので、原子の中で電子が原子核の方に落ち込むことはない」と説明されてきた。
しかし、この説明は、次の記述とと矛盾している。
『中性子星は大きな圧力によって、電子が原子核内に押し込められ、すべての粒子が中性子となってしまった星です』
(p. 140『宇宙の事典』 脇屋奈々代、沼澤茂美 ナツメ社) |
すなわち、「“電子の位置が確定するほど、運動量が無限大にゆらぐ」ことと「ある種の恒星が超新星爆発を経て、“中性子星”ができうること」と矛盾しているのである。
仮に、不確定性原理(不確定性関係)が原因で、原子の中で電子が原子核の方に落ち込むことはないしくみがあるのなら── 中性子星が、生じることは不可能である。
なぜなら、たとえどんなに強い重力であっても“無限大”の運動量をもつ電子を押し込むことが不可能になるはずだからである。
しかし、中性子星が実在することが、観測されている。
このことは、「不確定性原理(不確定性関係)が原因で、原子の中で電子が原子核の方に落ち込むことはないしくみ」の方が、実在しないことを示唆している。
つまり、「原子の中で電子が原子核の方に落ち込まないこと」を説明するための、「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」は、失敗(自然(nature)から乖離)しているのである。
この矛盾を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、解消できる。
なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)においては、不確定性原理(不確定性関係)を用いないで、“原子の中で電子が原子核の方に落ち込んでいかない理由”を説明できるからである。
電子は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、不確定性原理(不確定性関係)に従うものではなく、あくまで、(単振動振幅)確定性原理に従って、電子ヒッグス場ユニット(eHU)と相互作用し続けているものである。 したがって、電子は、いきなり原子核の中の陽子と相互作用して消滅するよりも── はるかに、電子ヒッグス場ユニット(eHU)の中の“陽電子”と相互作用しながら定常状態でありやすくなる。
だから、「原子の中で電子が原子核の方に落ち込まない」のである。
※やはり、“量子ゆらぎ(仮想粒子の生成&消滅)”や“電子の原子核への落ち込みの防止”の“原因”は、不確定性原理(不確定性関係)そのものではない。
それらの原因は── 具体的には、「“パウリの排他律”よって駆動される共転回」、((単振動振幅)確確定性原理に従う)「光子や重力子によって駆動される“原始ヒッグス場ユニットの単振動」、そして、((単振動振幅)確確定性原理)に従う「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)が生む単振動」である。
つまり、ミクロの自然(nature)の中にこそ、“量子ゆらぎ(仮想粒子の生成&消滅)”や“電子が原子核への落ち込むことの防止”といったミクロの自然(nature)の振る舞いの原因があるのである。
それは、光子も、仮想光子も、重力子も、色荷を持つグルーオンも、中間子も、(波動性を持つ)電子も… 同様のことでである。
そして、このようにして創発したミクロの自然(nature)を、マクロの自然(nature)の一部である人類が観測しようとする際に限って── 不確定性原理(不確定性関係)で説明されるような“事情”が生じる、ということなのだ。
《ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)》
ゼロ点エネルギーも、これまで、不確定性原理(不確定性関係)で説明されてきた。
それは、次のような記述から読み取れる。
『これは、結局は不確定性原理のせいである。Δq・Δp≒hであり、単振動している固体原子は、かなり狭い空間に押し込められている。 つまりΔqは小さい。とすると、相当大きい運動量Δpが期待され、そのため
E=(Δp)2/2m (6.40)
のエネルギーが、どんなに冷たい物質の中にでも、不確定なために存在するわけである。 (6.40)がなぜ hν/2になるかは、直接には導き得ない。 しかし、量子論においてはこのように、未決定部分があるために、ゼロ点エネルギーというものが存在する。 ある物質から、熱などの形で全部エネルギーを抜き去っても、なおかつミクロな意味で物質はエネルギーを所持し続けるのである。』
(p.224 『なっとくする量子力学』 都筑卓司 講談社 下線は筆者による。)
|
『(6.40)がなぜ hν/2になるかは、直接には導き得ない。』という部分には、“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)”を不確定性原理(不確定性関係)によって説明してはいるが── “ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)”の幾何的な実体像が不明であることが示されていると思われる。
この“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)hν/2”についても、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、やはり、不確定性原理(不確定性関係)では説明しない。
なぜなら、不確定性原理(不確定性関係)は、やはり、本来、人類の観測事情(ミクロの自然(nature)とマクロの自然(nature)の関わり合い)を示す原理であり、ミクロの自然(nature)がどのようにふるまうかを示す原理ではないからである。
それでは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、の“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)hν/2”を、どのように説明するであろうか?
“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)”の幾何学的な実体像とは、何か?
ヒントは、『単振動している固体原子は、かなり狭い空間に押し込められている』『(6.40)がなぜ hν/2になるかは、直接には導き得ない。』『ある物質から、熱などの形で全部エネルギーを抜き去っても、なおかつミクロな意味で物質はエネルギーを所持し続けるのである』にあると思われた。
まず、電子の零点エネルギーについて、考えてみよう。
こりまで、電子について説明した中で、最もエネルギーが低く、最も狭い空間に押し込められた状態は、1s軌道である。
それは、下図のようになる。
※1s軌道の場合、電子の波長は、λ1である。
2πr=λ1より 、1波長進むことによって、円を一周することになる。
2つの電子ヒッグス場ユニットの間を電子が移動し続けている状態である。
※たった1つの円だけを軌道運動し続けるわけではない。 決定論的なカオスにより、軌道を変化させながら、軌道運動するために、球状の空間を網羅することになる。 これが、1s軌道が生む電子雲が創発するしくみである。
|
ボーアの原子模型では、これ以上小さな軌道を考えることはできない。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の原子模型では、さらに小さい軌道を考えることができる。
それは、すなわち、2πr=λ1/2 となるものであり、それは下図のようなものである。
※関わる電子ヒッグス場ユニットは1つだけとなっている。
2πr=λ1/2 より 、このλ1/2が1つ分で、円を一周することになる。
1つの電子ヒッグス場ユニットの中(orごく近辺)で電子が移動し続けている状態である。
※やはり、たった1つの円だけを軌道運動し続けるわけではない。決定論的なカオスにより、軌道を変化させながら、軌道運動し続けるために、球状の空間を網羅することになる。 これが、“0s軌道”が生む電子雲が創発するしくみであると考えられる。
したがって、下図のように円周が、1つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)を完全に取り囲んでいるように図示した方が、より正確かもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
|
|
これは、電子を構成するマイナスプレオンのもっとも小さな軌道、スピン角運動量がh/4πとなるときの条件と似ている。
(結果2 《磁力と、磁極の間に働く“引力と斥力”について》)
このことは、電子におけるこの「2πr=λ1/2」という条件こそが、最も小さな軌道であり、“スピン”に似た性質を持ち、軌道運動によって移動しない(熱運動をしない)状態に相当していることを示唆しているように思われる。
そして、このことは、『単振動している固体原子は、かなり狭い空間に押し込められている』『ある物質から、熱などの形で全部エネルギーを抜き去っても、なおかつミクロな意味で物質はエネルギーを所持し続けるのである』というようなゼロ点エネルギーがもつ性質と調和していると思われる。
すなわち、(軌道を一周するために)電子が相互作用する“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”が、たった1つである点が── 1s、2s、2p、3s、3p、3d… という軌道において、電子が相互作用する“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”が、2つであることと決定的に異なっているために、これだけ半整数のE=hν/2となると考えられるのである。
よって、電子のゼロ点エネルギー(零点エネルギー)について、次の仮説を立てた。
仮説4.6.1 たった1つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)と相互作用し合いながら、単振動を繰り返している状態が、電子の“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)E=hν/2”に対応するものの幾何的な実体像である。
そうすると、電子の“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)”に相当する幾何学的な実体像とは、たった1つ電子ヒッグス場ユニット(eHU)を取り囲み、“スピン運動に近い状態”が持続している状態であるということである。
“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)”が“スピン(自転)運動に近い状態”に相当するということは── 場所を移動しないこと(軌道運動(公転運動)をしないこと)を意味しており、“熱運動”とも関係なくなることになる。 すなわち、“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)”は、絶対0度でも、存在し続けることになる。
つまり、これは、やはり、『単振動している固体原子は、かなり狭い空間に押し込められている』『ある物質から、熱などの形で全部エネルギーを抜き去っても、なおかつミクロな意味で物質はエネルギーを所持し続けるのである』という性質と調和している。
しかも、不確定性原理(不確定性関係)を全く用いない説明である。
(すなわち、「不確定性原理(不確定性関係)の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」が存在しない説明である)
そして、電子についてのみならず、プレオン∴、クォークやニュートリノについても同様に、“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)E=hν/2”を考えることができる。
※ただし、光子や重力子に関する“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)E=hν/2”は、考えにくいようである。
なぜなら、たった1つの原始ヒッグス場ユニットとだけ相互作用し続ける光子や重力子の幾何的な実体像を考えることができないからである。
これは、何を意味しているのであろうか? もしかしたら、“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)E=hν/2”を持つものは、スピン1/2のフェルミオンに限るということ、すなわち、光子や重力子の“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)は、実在しないということなのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
※なお、“電子のスピン”は、実は、マイナスプレオンの“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)E=hν/2”の総和に相当するものだったことになる。 (結果2)
つまりは、「軌道角運動量が、h/2πの整数倍であるのに対して、スピン角得運動量が、h/2πの半整数倍であること」と、「“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)”でのみ、エネルギーが(E=hνの)1/2となること」は、関連していたことになる。
《“波と粒子の二重性”と相補性原理》
波と粒子の二重性について、次のような記述がある。確ではない。 なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると── 電子や光子などの量子は、(実験に関わらず)常に、波と粒子の性質を同時に持っている(波と粒子の両方の振る舞いを同時に行っている)からである。 したがって、“どんな実験を行うかによって、波としての振舞いを観測できることもあれば、粒子としての振舞いを観測できることもある”という記述が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していることになる。
後者の、「 電子や光子などの量子が、(実験に関わらず)常に、波と粒子の性質を同時に持っている(波と粒子の両方の振る舞いを同時に行っている)」という意味での“波と粒子の二重性”を、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の“波と粒子の二重性”」と呼ぶこととする。
まずは、この「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の“波と粒子の二重性”」について、光子と電子を例にして、以下で説明する。
《光子における「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の“波と粒子の二重性”」》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、個々の“光子”そのものは、波動性と粒子性の両方の性質を同時に持っている。
すなわち、光子とは── (原始ヒッグス場ユニットの“4面体”をバネのような土台とした、総スピン1の)“素スピノールのペア”の共転回の伝播である。
ふつうの古典的な波のように、ある一点で、連続な波が通過する頻度が、振動数に相当するのではなく── 時空内における、とびとびの“共転回の頻度”が、光子の振動数に相当する。
この“光子”を“波と見ることも、粒子と見ることも”両方とも自然にできる。
《電子における「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の“波と粒子の二重性”」》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、個々の電子は── 電子ヒッグス場ユニット(eHU)と相互作用することによって、消滅と生成の繰り返しの波を創発する。
この“電子”を“波と見ることも、粒子と見ることも”両方とも自然にできる。
こういった「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の“波と粒子の二重性”」が示す、光子や電子の描像、すなわち「幾何学的な実体像」は── いずれも、粒子と見ることも波と見ることも、自然にできるものである。
それは、例えば、「円柱」という3次元の実体が、(2次元の)「長方形」と見ることも、(2次元の)「円」と見ることも、自然にできるものであることと似ている。
(参考 『アインシュタインvs.量子力学』 p135-136)
つまり、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の“波と粒子の二重性”」が示している幾何学的な実体像は、波動性と粒子性の説明を同時にしているものであり── まさに、「長方形」と「円」の説明を同時にできる『「円柱」という3次元の実体』に相当しているものであると言える。
一方、ボーアは、粒子と波の二重性について、“相補性原理”によって、説明しようとした。
相補性とは、次のように記述されているものである。
『相補性
光と物質には、波としての性質と、粒子としての性質があり、これら二つの性質は互いに補い合いつつ、排他的であるとする考え方で、ニールス・ボーアにより唱導された。光と物質がもつこれら二つの側面は、同じコインの裏と表のように、一度に両面を見ることはできない。光の波としての性質、または粒子としての性質の、どちらか一方を見るように実験を計画することはできるが、同時に両方を得るための実験を行うことはできない』
(p.492『量子革命』用語集より 下線は、筆者による) |
ボーアは、この「(波と粒子の)二つの性質は互いに補い合いつつ、排他的である」という“相補性原理”によって、光子や、電子などの量子が、波と粒子の二重性を持つことを説明しようとしたのである。
しかし、この“相補性原理”は、上の『相補性』の引用文を読めばわかるように、「波と粒子という性質は、互いに相容れないものであり(≒排他的であり)、どうしたって統一できないものである」と宣言してしまっている原理である。
そして、残念ながら、実質的には、“何も解決していない”に等しい原理である。
そのことに関連する、次のような記述もある。
『相補性概念に対する否定的な評価
しかし、アインシュタイン自身は、一九四九年の時点でも、「相補性に費やした多くの努力にもかかわらず、私はその原理を明確に定式化することができなかった」と述べている。シュレーディンガーは、相補性概念について「ボーアはすべての困難を相補性で片づけようとしている」と語っている。また、ディラックは「私は相補性が好きではない。 ……相補性はなんら新しい解決法をもたらさない。……波と粒子についてまだ最終的な答えは出ていないと私は信じている」と発言している。
〜。
たしかに、結局のところ、相補性という概念を持ち出したところで何がどう解決したことになるのかよくわからないというのは私も同じ感想である』
(p.134〜135 『アインシュタインvs.量子力学』 。一部省略。 下線は筆者による) |
筆者も同感である。
さらに、次のような記述もある。
『位置を媒体として自然を表現することも、運動量を媒体として自然を表現することもできます。 いずれも可能なのですが、両方を同時におこなうことはできません。 一言で言うと、両者は相補的なのです。
〜
ボーアは、晩年になって、「二者択一でお互いに排他的」な記述の仕方の意義を検討し、大哲学原理へと高めようとしました。それは、同時に起こりえないたくさんのものについて適用されるものです。生物学と物理学の関係──この、いつも当惑させられる問題を例にとりましょう。
確かに、生体系には物理的な要素があります。しかし、生物学(や人類学)が、込み入って入るけれども物理学から派生した分野だと考えて喜ぶためには、徹頭徹尾還元論者(複雑な要素から成り立っているものを、過度に単元化する主義の者)にならなければなりません。私たちが困惑していると、ボーアはすぐに手を差し伸べてくれます。
もし生体系をその成分の原子に分裂させてしまうと、その系を殺すではないか──こう、彼は、指摘します。つまり、生命と原子物の間には、相補性原理が働いているわけです!
〜。相補性は、お互いに同時には成立しないものを取り扱っています。〜。 そして、相補性原理は、演繹的な原理であるというよりも、むしろ、説明上の標語となる危険性に直面します。
〜。 生物学と物理学の真の関係がどのようなものであろうとも、両者の関係は微妙な意味合いを持っており、相補性などとという一言で包んでしまうことはできないのです。』
(p.143-145 『量子力学の考え方』 JCポーキングホーン=著 宮崎忠=訳、一部省略。下線は筆者による。太線部分は、元々、傍点であった。) |
この文章は、『生物学と物理学の真の関係』は、本来、もっと深い仕組みがあり探求の余地があるはずなのに── “相補性”の一言には、『「説明上の標語」として、「思考停止」や「真実探求の放棄」を促してしまう危険性がある』ことを指摘している。
私も同感である。
なぜなら、『生物学と物理学の真の関係』──物質(分子)と生命の関係は、明らかに、単に「相補性原理」で片付けるよりも、まさに「3Steps原理」によって把握しようとする方が、より深い理解に達しやすく、はるかに、実り多いと思われるからである。 (→『3Steps理論とその応用について』)
そして、それは、「波と粒子の二重性」についても同じである。
なぜなら、3Steps原理および“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に照らせば── 「波と粒子の二重性」について、“相補性”の一言ですまそうとすることにも、『「説明上の標語」として、「思考停止」や「真実探求の放棄」を促してしまう危険性がある』ことが、わかるからである。
すなわち、相補性原理ではなく「3Steps原理」によって、ミクロの自然(nature)を探求し、把握しようとする方が、より深い理解に達しやすく、はるかに実り多いことを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示しているからである。
相補性原理は、『生物学と物理学の真の関係』や『波と粒子の二重性の真の関係』の探求に対する、早々とした“あきらめ”を促す危険性のある原理である。
すなわち、この相補性原理は、実質上、『(互いに排他的な)「円」と「長方形」は、統合的に、同時に「円柱」としてとらえることは不可能であり、「円」か「長方形」かの、どちらか一方だけずつしか把握できないのだ』と主張するのに似た、「あきらめ宣言」にすぎないものなのである。
そして、「円柱」を探求することは、不可能なのだと高らかに宣言することによって── 自然(nature)の探求を“あきらめ(思考停止、放棄…)”させてしまいうる原理なのである。
一方、3Steps原理は、『生物学と物理学の真の関係』や『波と粒子の二重性の真の関係』の探求を促す原理である。
すなわち、この3Steps原理は、実質上、『(互いに排他的に見える)「円」と「長方形」は、統合的に、同時に「円柱」としてとらえることも、可能なはずだ』と主張するのに似た、「ネバーギブアップ宣言」に相当するのである。
そして、「円柱」を探求することも、可能なはずであるとさりげなく宣言することによって── 自然(nature)の探求を促進させうる原理なのである。
さらには、関連する、次のような記述もある。
『アインシュタインは、光の量子論と、光の波動論のどちらか一方ではなく、「それらふたつの概念を統合しなければなりません」と主張した。〜。アインシュタインは、「統合」を待望していたのに対し、ボーアは相補性を導入し、波と粒子の性質を、互いに相容れないものとして分離しようとしていた。』(p.365『量子革命』 下線は、筆者による)
|
※アインシュタインの科学スタイルと、ボーア(相補性原理)の科学スタイルは、対照的であることが示されている。
そして、3Steps原理の科学スタイルは、アインシュタインの科学スタイルと調和している(アインシュタインの科学スタイルを包含している)ことがわかる。
ここで、「相補性原理」の科学スタイルと「3Steps原理」の科学スタイル(アインシュタインの科学スタイルを包含)の違いをまとめると、次のようになる。
|
相補性原理
|
3Steps原理
|
|
排他的に見えるものを
分離させたままにする。
|
排他的に見えるものの
統合(統一)をめざす。
|
|
「円か長方形かどちら一方ずつしか
とらえることができない」という
あきらめを促す。
|
“円柱”のまるごとをとらえようとする
円と長方形の説明を
同時にしようとすることを促す。
|
|
思考停止をもたらす標語
|
さらなる思考を促すコンパス
|
|
さらなる真実の探求を
あきらめさせる
|
さらなる真実の探求を
促す(サポートする)
|
|
うやむやにする
|
明確化する
|
|
空虚である
実質的な意味が乏しい
不毛である
|
実がある
意味がある(ミーニングフル)
フルーツフル
|
|
何も解決していない
|
様々なものを解決できる
|
|
…
|
…
|
だからといって、相補性原理には、全く存在意義がないのであろうか?
そのようなことはない。 相補性原理にも、当然、存在意義がある。
それは、不確定性原理(不確定性関係)やコペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)を支持することによる貢献、いわば、“間接的な貢献”である。
相補性原理が、不確定性原理(不確定性関係)を支持していることは、例えば、次の記述から読みとれる。
『ボーアは、波と粒子の二重性は相補性という枠組みの中でしか説明できないと主張した。また、不確定性原理は、自然に本来備わっている特徴であり、古典的概念に適用限界があることを明らかにするものだが、その基礎は相補性にあると述べた』
(p.365『量子革命』 下線は、筆者による)
|
※なお、不確定性原理(不確定性関係)は、「“ミクロの自然(nature)”だけに本来備わっている特徴」ではなく、「“ミクロの自然(nature)とマクロ自然(nature)の関わり合い”(ミクロとマクロの関わり合いという自然(nature))に本来備わっている特徴」である。 すなわち、やはり、あくまで「人類の観測事情」を示すものに過ぎない。
一方、不確定性原理(不確定性関係)は、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)を支持しているのだった。
つまり、相補性原理は、不確定性原理(不確定性関係)を支持し── その不確定性原理(不確定性関係)は、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)を支持していることになる。
したがって、不確定性原理(不確定性関係)やコペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)に存在意義がある以上、相補性原理にも存在意義があると言えるのである。
人類にとって、観測や応用の場面では、結局は、確率の概念に頼らざるをえないのであった。
そして、それこそが、実際の現場で、「不確定性原理」や「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)という道具が、有効に機能した理由なのであった。
そして、その便利な道具のおかげで「量子力学の応用」に専念でき、コンピュータ、電化製品、IT… といった様々なエレクトロニクス技術の発展がこれまで達成できたのだった。
すなわち、「量子力学の基礎」についての研究を後回しにして、「量子力学の応用」にエネルギーを注ぐことを促したという点で、「不確定性原理」や「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)には、大きな存在意義があったのだった。
さらには、「不確定性原理」や「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)には、人類にとっての「観測上&応用上の限界」を示してくれる(ある種の安全性を保証してくれる)という点でも、大きな存在意義を持つのであった。
つまりは、相補性原理には、『このような大きな存在意義を持つ「不確定性原理」や「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)を支持する』という、存在意義があるのだ。
|
やはり、確かに、科学スタイルは、自然(nature)と、調和している限り、尊重されなければならない。
しかし、一方で、「現代物理学」が行き詰まってしまった現状においては── どうしても「量子力学の基礎」についての研究は、必要不可欠である。 すなわち、『相補性原理に支えられた「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)と不確定性原理』の科学スタイルとは異なる、新たな科学スタイルによって、自然(nature)を探求する必要がある。
なぜなら、物理学界の大部分が『相補性原理に支えられた「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)&不確定性原理』の科学スタイルに、長らく、ロックインしてきたことが、現代物理学の危機──“根本的な矛盾、行き詰まり、迷走、困難…”にぶつかっている原因の1つである恐れがあるからである。
それでは、そもそも、なぜ、物理学界は、『相補性原理に支えられた「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)&不確定性原理』の科学スタイルに、長らくロックインしてきたのだろうか? そのことを見つめることは、ロックインから脱するためにも、重要な意味があると思われる。
その1つの理由は、観測面や応用面で、成功をもたらしたことであることは間違いないだろう。(それが、存在意義の1つであった)
しかし、実は、他にも、大きな理由があったのだ。
次は、その理由に関連する記述である。
『アインシュタインの影響力が弱まるにつれ、ボーアのそれは強まった。 ハイゼンベルグやパウリのような伝道師たちがその福音を述べ伝えているうちに、コペンハーゲン解釈は、量子力学の同義語となっていた。 ジョン・クラウザーは、まだ大学生だった一九六〇年代に、アインシュタインとシュレーディンガーは「年寄り」で、このふたりが量子について語ることは信用できないと言われるのをしばしば耳にしたという。 「こういうゴシップを、一流の研究機関の著名な物理学者がみんなしてわたしに話してきかせたのだった」。 クラウザーがそう語ったのは、一九七二年に初めてベルの不等式を検証してから長い年月を経たのちのことだった。 対するボーアは、ほとんど超自然的な論証力と直観もつかのように語られた。 ほかの人たちは計算をしなければならないが、ボーアは計算する必要がなかったと言われることもあった。 クラウザーが語ったところによれば、彼が学生だった頃、コペンハーゲン解釈には答えられないような、「量子力学に関する疑問や問題点を公に口にすることは、さまざまな宗教的烙印と社会的圧力によって、事実上禁じられていた。それらが力を合わせて、量子力学に反対する思想を打ち倒そうとする十字軍のようなものになっていた」』
(p.464 『量子革命』 下線は筆者による) |
『アメリカのノーベル賞受賞者マレー・ゲルマンは、そうなった理由のひとつは、「ニールス・ボーアが一世代の物理学者をまるごと洗脳して、問題はすでに解決したかのように思い込ませたことだ」と述べた。』 (p.466 『量子革命』)
|
ボーアらは、いつしか、「自然界そのものについての“真実の探求”」を放棄して、「自分が作り上げた理想上の“哲学(教義)の普及”」をするようになってしまったのだ。
そして、ボーアらは、いつしか「自分らだけこそが絶対に正しい」「自分らを批判する方こそが間違えている」と“信じる姿勢”、すなわち、“独善性”&“排他性”を持ち続けるようになってしまったのだ。
すなわち、疑問をはさむものは、異端視し(おかしいと見なし)、ことごとく排除したのである。
(ド・ブロイしかり、ボームしかり、アインシュタインしかり…)
その結果、多くの物理学者は、同調せざるをえなくなった。
特に(駆け出しの、実績の乏しい)若い物理学者にとっては、「同調しなければ、大学に残れない(科学者として食べていけない)というプレッシャー」は相当なものであったろうことは、容易に想像がつく。
一方、アインシュタインは、「自然界そのものについての“真実の探求”」こそをし続けた。
そして、「間違いに気づいていこう」という“疑う姿勢”を懸命に持ち続けた。
アインシュタインは、「量子論が、まだ完全ではない」ことを確信し、「量子論の本当の意味での完成」を望み続けた。
『アインシュタインは、量子力学が正しいという点においては意義を唱えなかった。彼はただ、量子力学は、量子レベルの物理的実在を、完全には描き出していないと言ったのである』
(p.448 『量子革命』 下線は、筆者による) |
そして、他の物理学者にも「量子論が、まだ不完全である」ことに気づいてもらいたいと思ったアインシュタインは、「局所的実在論」を前提とした上で、EPR論文を発表した。
確かに、「局所的実在論」自体は、「ベルの不等式の破れ」の観測結果によって否定された。 しかし、このEPR論文は、結果的に、「非局所性(量子もつれ)」という、自然(nature)により近づくためのドア(扉)を開く大きなきっかけとなった。
※アインシュタインは、「ベルの不等式の破れ」の観測結果を知っていれば、「観測者と独立した量子の世界」すなわち、実在論を最も重視し、「局所性」を疑い、そして、「非局所性(量子もつれ)」を受け入ていただろう── と考えられることは、すでに述べた。
なお、下記を、もう一度引用する。
『もしもあの世のアインシュタインに会いに行き、ベルの不等式のことを説明して、クラウザーやアスペらの新世代の物理学者による実験結果を伝えたならば、アインシュタインはちょっと遠くを見やるような目をして、「ああ、そうか、そういうことだったのか」と言うのではないだろうか。そして彼は、非局所相関のある宇宙像を受け入れ、実在論は堅持するに違いない。』
(p.510 『量子革命』あとがき) |
そして、今、この「非局所性(量子もつれ)」は、“共転回原理”という形で、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を根底で支えている。
そして、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「非局所的な“隠れた変数理論(実在論)”で因果律を持つ」(「量子レベルの物理的実在を、完全には描き出して」いる理論の候補の1つである)と同時に、『相補性原理に支えられた「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)&不確定性原理』がどのようにして成立しているのか(成功しているのか)を説明できるものである。
そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、今も、進化し続けている──。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、『相補性原理に支えられた「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)&不確定性原理』の哲学(教義)を持ち続けていれば、決して生まれなかったものである。
このことは、もしかしたら、『相補性原理に支えられた「コペンハーゲン解釈」(重ね合わせの原理&確率解釈)&不確定性原理』の“哲学(教義)に多くの物理学者がロックインしてしまったことによって── (コペルニクスが天動説を示して以来、“真実の探求の営み”として、多いに進化してきた)科学が、いつしか、“哲学(教義)を普及する営み”として、進化を止めてしまってきたことを、象徴的に示唆しているのかもしれない。
※科学は、少なくとも、『アリストテレス、プトレマイオス→コペルニクス→ケプラー、ガリレオ→ニュートン→ファラデー、マクスウェル→アインシュタイン→プランク、(アインシュタイン)、ボーア、ハイゼンベルク…』のように進化してきたのだった。
ボーアらと、アインシュタインを比較すると、次のようになる。
|
ボーアら
|
アインシュタイン
|
|
自分たちが作った「量子力学は、完全だ」
と信じ続けた。
|
「量子力学は、まだ完全ではない」と
疑い続けた。
|
|
疑問に思うことを禁じた。
|
自ら疑問に思い続けた。
|
| 「“間違いなどどこにもない”という態度」を貫いた。 |
「“間違いに気づいていこう”とする態度」を貫いた。 |
|
もうすでに完全だと信じていたので、
新たな考えに対して
排他的、独善的に対応した。
|
実在論、因果律にもとづいて
統一的な説明を可能にする
新たな考えを熱望していた。
|
| 「自然界そのものについての“真実の探求”」を放棄して、いつしか、本来「進化しうる科学」を、特定の“哲学(教義)を普及する営み”に、すり替えてしまった。 |
「自然界そのものについての“真実の探求”」の営みとしての、本来「進化しうる科学」を、最後の最後まで、守り続けようとした。 |
アインシュタインの“新たな偉大さ”が、浮かび上がる。
アインシュタインは、決して、“流行、時流、批判…”に流されなかった。
アインシュタインは、文字通り(“Einstein”の名の通り)“1つの大きな岩”のごとく、身体を張って、最後の最後まで、「本物(本来)の科学の営み」を守りぬこうとし続けたのだ。
アインシュタインは、真の科学者であり続けたのである。
科学の営みは、本来、特定の「哲学(教義)の普及」のための“信じる営み”ではなく、「真実の探求」のための“疑う営み”である。
すなわち、科学は、本来、“やみくもに完全だと信じ込む営み”ではなく、“不完全かもしれないと徹底的に疑う営み”なのだ。
そして、疑っては、間違い気づき、疑っては、間違い気づくことを繰り返し、改善し続ける中で── 真実、すなわち、自然(nature)そのものに、より近づいていくべく、進化を重ねる営みなのだ。
そうして、どんなに、どんなに疑っても、びくともしないもの── それが、本物の真実の候補、すなわち、自然(nature)そのものを説明する真実の候補となるのだ。
※なお、以上のことは、例えば、理論物理学界において、(“不完全な量子論”に依存して育ってきている)「“超弦理論”が主流である」という状況は、見直す必要がある、ということをも示唆しているのかもしれない。
そして、少なくとも、“超弦理論”の営みが、(ボーアらと同じような)「哲学(教義)の普及」の営みにすり替わっていないかどうか── (アインシュタインが守り抜こうとしたところの)「真実の探求」の営みに相当しているかどうかを見直すことは、有意義だろうと思われる。 (→考察3)
《完成した量子論(完全な量子論)の探求》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、究極の量子化── すなわち、「素スピノールという量子を用いた、時空の量子化」を含む、“究極の量子論”と呼べるものである。
したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「完成した量子論(完全な量子論)の探求」を強力にサポートするものであると考えられる。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、「完成した量子論(完全な量子論)の探求」は、より実り多いものになると考えられる。
物理学は、いくつかの革命を経ながら、進化してきているものである。
物理学の最初の革命は、ニュートンによって、ほぼ完成した。
すなわち、その革命とは、「アリストテレス、プトレマイオス→コペルニクス→ケプラー、ガリレオ→ニュートン」という科学の進化によって、達成されたものである。
これを、力学(dynamics)物理革命と呼ぶこととしよう。
次の物理学の革命は、アインシュタインによって、ほぼ完成した。
すなわち、その革命とは、「二ュートン(遠隔作用)→ファラデー&マクスウェル(電磁場、近接作用)→アインシュタイン(一般相対性理論、重力場)」という科学の進化によって、達成されたものである。
これを、場(field)物理革命と呼ぶこととしよう。
しかし、次の物理学の革命は、まだ完成していない。
すなわち、その革命とは、「二ュートン&アインシュタイン(連続)→プランク(不連続)→アインシュタイン(光量子論)、ボーア、ハイゼンベルク、パウリ、ディラック、ベル…」という科学の進化によって、進行中のものである。
これを、量子(quantum)物理革命と呼ぶこととしよう。
よって、物理学は、次のように進化してきていると見ることができることになる。
この量子(quantum)物理革命が完成した暁には、同時に、力学(dynamics)物理革命や場(field)物理革命も、本当の意味で完成したと言えるであろう。
(すなわち、重力理論(一般相対性理論、万有引力の法則)も、ニュートン力学(運動方程式、慣性の法則…)も、電磁気学も、素粒子の標準模型(場の量子論)… も同時に完成したと言えるであろう)
つまり、量子(quantum)物理革命が完成すれば、物理学は真に統合され、物理学が完成するのである。
この「量子(quantum)物理革命」の完成、すなわち、物理学の完成を強力に助けるものの1つが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に他ならない。
そして、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって物理学が完成するならば、その物理学は、「自己組織化系(創発系、複雑系…)」の一部に相当することになる。 (そのことを、自然な世界観(3Steps原理)および一般3Steps理論は、はっきり示している)
つまりは、このような「物理学の完成」を通じて── 物理学は、ライフ(生化学、分子生物学、細胞学、生理学、人生、生態系…)と統合されることになるのである。
(→考察5)
《“強力な重力”による、ミクロの自然(nature)の変化》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、ミクロの自然(nature)は、すべて、「“単純な要素”の振る舞い」の総和として生じた“創発現象”に過ぎない。
このことは、少なくとも“強い重力”という条件が、「ミクロの自然(nature)── 例えば、量子ゆらぎ(仮想粒子の生成&消滅)、電子やクォークの波動性(生成&消滅の波)、光子の進み方等」を変化させうることを示唆していると思われる。
例えば、“強い重力”の条件下で存在する中性子星は、「巨大な原子核」と言えるものであり、「中性子星の内部」では、「“強い重力”によって、電子が原子核(の中の陽子)に取り込まれてしまっている」と考えられるので、電子と電子ヒッグス場(電子ヒッグス場ユニット(eHU)の総和)の相互作用、「電子の波動性」「電子が関わる量子ゆらぎは、消失してしまうと考えられる。
※なお、『 「中性子星」が実在していることは、不確定性原理が破れていることを意味する』とは、言えない。
なぜなら、そもそも、不確定性原理のおかげで、電子が落ち込み、原子核の中の陽子に取り込まれるのを防がれているのではないからである。
(不確定性原理は、あくまで、人類の観測事情示す原理(ミクロとマクロの相互作用という自然(nature)を示す原理)にすぎない)
もし、不確定性原理が原因で、電子の落ち込みが防がれているとするなら、「有限の重力によって、無限大の運動量を取り込まなければならない」という矛盾が生ずる。
※なお、中性子星やクォーク星の段階では、もはや、【多様な物質の生成レベル】や、強い力(by中間子)は、消失していることになる。
さらに強い重力を持つ、新しいブラックホールができる際には、何が起こるであろうか?
まず考えられるのは、もはや、物質の反物質に対する優位性が消失してしまう(物質と反物質が対消滅してしまう)ことである。
すなわち、この段階では、【核子やレプトンの生成レベル】も消失してしまうのである。
さらには、ブラックホールは、クォーク星より小さいので、その重力は、もはやクォーク星を構成していたアップクォークやダウンクォークを、プレオン∴まで分解してしまうほどの強いものであると考えられる。
したがって、これほど強い重力は、もはや、対消滅していた、電子ヒッグス場ユニットやクォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニットさえも、消失してしまうと考えられる。
※具体的には、プレオン∴3つからなるフェルミオンはすべて消失し、プレオン∴からなるボソン、すなわち、「プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)というボソン」になると考えられる。 →EMOES宇宙論『新しいブラックホールの中で起こること、エントロピーについて』
その際は、「原始ヒッグス場ユニット(PHU)を介さずに、LP光子が直接、プレオン∴どうしを結びつけるような“原始的な力”」が作用すると考えられる。
※この段階では、当然、電子の波動性や、クォークの波動性、ニュートリノの波動性も消失していることになる。
また、この段階では、強い力(byグルーオン)や弱い力(byウィークボソン)も消失していることになる。
※一方、新しいブラックホールの内部の強い重力場では、原始ヒッグス場ユニット(PHU)のすべてが、“4角形”(縮みきったバネ)の状態へと変化すると考えられる。
その結果、1つは、原始ヒッグス場の“4面体”の足場が消失する結果、光子が前進できなくなると考えられる。
(そのせいで、光子(電磁波)はブラックホールの外へ出て行けなくなると考えられることは、これまで度々述べた)
もう1つは、仮想光子も、生じることができなくなる結果、電磁場、すなわち、電磁気力も消失すると考えられる。
つまり、新しいブラックホールができているができる際には、光子、仮想光子、電子、クォーク、ニュートリノ、ウィークボソン… も、もはや存在できなくなると考えられる以上── 3つの力(電磁気力、弱い力(byウィークボソン)、強い力(by中間子やグルーオン))が消失するのである。
すわなち、新しいブラックホールが生まれる過程では、重力と「(原始ヒッグス場ユニット(PHU)を介さない、ダイレクトな)“原始的な力”」以外の力が存続できなくなるのである。
つまり、新しいブラックホールにおいては、3Steps理論における【多様な物質の生成レベル】や【核子やレプトンの生成レベル】が消失すると同時に、クォークヒッグス場ユニット、電子ヒッグス場ユニットも、ニュートリノヒッグス場ユニット、3つの力(電磁気力、弱い力(byウィークボソン)、強い力(by中間子やグルーオン))も消失する。
それを図示すると次のようになる。
|
現在の宇宙
|
|
|
|
※【多様な物質の生成レベル】や【核子やレプトンの生成レベル】が存在しているのにともない、電子やクォーク、ニュートリノの波動性が存在している。
同時に、3つの力(電磁気力、弱い力(byウィークボソン)や強い力(by中間子やグルーオン))も存在している。
|
|
↓
|
|
|
新しいブラックホール
|
|
|
|
※【多様な物質の生成レベル】のみならず【核子やレプトンの生成レベル】が消失しているのにともない、電子やクォーク、ニュートリノの波動性のみならず、クォークヒッグス場ユニット、電子ヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニットも消失している。
同時に、3つの力(電磁気力、弱い力(byウィークボソン)や強い力(by中間子やグルーオン))も消失している。
|
【核子やレプトンの生成レベル】までもが消失するということは、電子、クォーク、ニュートリノ、ウィークボソン、光子… の波動性、“量子ゆらぎ”のみならず── 量子力学の世界における現象の大部分──《対生成&対消滅を繰り返す真空、トンネル効果、物質と粒子の二重性、二重スリットの実験での量子の奇妙に見える振る舞い…》も消失することを意味している。
つまりは、量子論(量子力学、場の量子論)で説明される自然(nature)の大部分は、【核子やレプトンの生成レベル】として創発しているものに過ぎないのである。
※なお、たとえ【核子やレプトンの生成レベル】が消失していても、例えば、非局所性(量子もつれ)の現象が“素スピノールの共転回”の形で残ったり、“パウリの排他律”が“電荷の保存”の形で残ったりすると考えられる。
したがって、【核子やレプトンの生成レベル】が消失したとしても、量子論で説明される自然(nature)の100%が消失する、ということにはならない。
重力が非常に強くなり(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が非常に高くなり)、【核子やレプトンの生成レベル】までもが消失している世界においても── 当然、重力子は光速で移動し続けていると考えられる。
そして、重力子の単振動の振幅は、常に一定値である。
(転回周期T=2LP/c[s](=2TP[s](2プランク時間))、エネルギー振幅EG[J]=EP/2π[J](=hc/4π2LP[J])(EP[J]:プランクエネルギー)
重力子の波長λG=2LP[m]、重力子の運動量pG=h/4π2LP[kg・m/s])
このことは、たとえミクロの自然(nature)であっても、(“(単振動振幅)確定性原理”にもとづく)圧倒的な“量子的な秩序”によって支配されることがありうることを示唆している。
すなわち、新しいブラックホールの中心部近辺(あるいは、宇宙が始まる直前)といった重力が極めて強い世界(重力子の密度がきわめて高い世界)に存在するのは、“量子的無秩序、ランダムさ…”ではなく、あくまで“量子的な秩序”であるということになる。
※以上の説明は、重力の性質が特異的なものであること明白に示していると同時に── 重力が(主に【核子やレプトンの生成レベル】にもとづいている)“標準モデル”に組み込まれにくかった理由の1つと言えると思われる。
|