研究論文
『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
3.ヒッグス場とエネルギー、および3つの世代について
これまで、結果1、結果2において、少なくとも、次の5種類の“ヒッグス場ユニット”が登場した。
|
ヒッグス場ユニット
|
創発するもの(関連するもの)
|
|
原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))
|
電磁場(電場、磁場)、電磁気力
質量、重力場、慣性、光速不変、時空の曲り、重力
光子&電磁波、重力子&重力波
LP色荷“原始的な力”、LP光子&「LP光子の集積したひも」
|
|
プレオン∴ヒッグス場ユニット
(∴HU(=preon∴ Higgs(field)Unit))
|
強い相互作用(強い力)
グルーオン&「グルーオンの集積したひも」、
電子のスピン(マイナスプレオンの軌道運動)
|
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU(=electron Higgs(field)Unit))
|
弱アイソスピン、弱い相互作用
|
|
クォークヒッグス場ユニット
(厳密には、アップクォークヒッグス場ユニット&
ダウンクォークヒッグス場ユニット
uHU(=up quark Higgs(field)Unit)&
dHU(=down quark Higgs(field)Unit))
|
弱アイソスピン、弱い相互作用
中間子、核力
|
|
ニュートリノヒッグス場ユニット
(厳密には、電子ニュートリノヒッグス場ユニット
νeHU(=electron-neutrino Higgs(field)Unit))
|
弱アイソスピン、弱い相互作用
|
※∴HU、eHU、uHU…のように略記できることとした。
これらの各種の「ヒッグス場ユニットの総和」として創発するものが、各種のヒッグス場(ヒッグス場、プレオン∴ヒッグス場、電子ヒッグス場、クォーク場…)である。
ヒッグス場とは、もともと、素粒子物理学の標準模型の中で、各種の素粒子に“質量を与える場”として(ヒッグス機構を支えるものとして)考え出されたものであった。
そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、各種のヒッグス場(各種のヒッグス場ユニットの総和)は、質量を与えること以外にも── 重力場、電磁場、光子、重力子、光速不変、時空の曲り、弱いアイソスピン、4つの力… を含め様々なものを説明するのに役立つことは、結果1、結果2で示してきた通りである。
このページでは、さらに、“標準模型の3つの世代”、物質波(素粒子の持つ波動性)、エネルギー、インフラトン、階層性問題… を含め、様々なものを説明するために、ヒッグス場(ヒッグス場ユニットの総和)が役立つことを示す。
『記憶に新しいニュース「“ヒッグス粒子”(スピン0)の存在を高い確率で支持する観測結果を、大型加速器LHCによって得られた」の中の、“ヒッグス粒子”とは何か?』を含め、このページでは、次のポイントについて説明していく。
《ヒッグス場と各種の場》
ヒッグス場ユニットの総和として、創発するものが、ヒッグス場である。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、少なくとも、5種類のヒッグス場ユニットが考えられるので── 少なくとも、次の5種類のヒッグス場を考えることができる。
ヒッグス場ユニットは、これらのヒッグス場の構成単位なのである。
|
ヒッグス場
|
ヒッグス場ユニット(=“ヒッグス場”の構成単位)
|
|
原始ヒッグス場
|
原始ヒッグス場ユニット
PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)
|
|
プレオン∴ヒッグス場
|
プレオン∴ヒッグス場ユニット
(∴HU(=preon∴ Higgs(field)Unit))
|
|
電子ヒッグス場
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU(=electron Higgs(field)Unit))
|
|
|
クォークヒッグス場
|
クォークヒッグス場ユニット
(具体的には、アップクォークヒッグス場ユニット&
ダウンクォークヒッグス場ユニット
uHU(=up quark Higgs(field)Unit)&
dHU(=down quark Higgs(field)Unit))
|
|
|
ニュートリノヒッグス場
|
ニュートリノヒッグス場ユニット
(具体的には、電子ニュートリノヒッグス場ユニット
νeHU(=electron-neutrino Higgs(field)Unit))
|
|
※どのヒッグス場ユニットも、基本形は、“4面体”である。 そして、どれも変形しうる。
※「原始ヒッグス場ユニット」の構成要素は、素スピノール・、「プレオン∴ヒッグス場ユニット」の構成要素は、プレオン∴、そして、「電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニット」の構成要素は、クォーク(orレプトン)∴×3であるので、“×3”のタイプのフラクタルであることがわかる。
すなわち、このことは、“フラクタル相似の原理”と調和していることを意味する。
※ヒッグス場ユニットのサイズの大小関係は、『原始ヒッグス場ユニット<プレオン∴ヒッグス場ユニット<電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニット』のようになっていることが図示されている。
ただし、その大小関係は、厳密なものでははい。 詳細な検討は、今後の課題である。
※ヒッグス場ユニットのスピンは、基本的には、どれも0である。 変形に伴って、スピンが変化することがある。
(例…原始ヒッグス場ユニットが“4角形”(縮みきったバネ)になることで、スピン2になる)
※なお、各種のヒッグス場ユニットは、「“粒子のペア”と“反粒子のペア”の対消滅」に生まれていると言うことができる。
このモデルは、『ヒッグス場は、自発的対称性の破れ、すなわち、「粒子と反粒子のペアの凝縮(沈殿)」によって生まれる』という説明とも調和していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。 |
そして、これらの5つのヒッグス場が組み合わさったり、各種の粒子が作用したりすることで、“各種の場”が創発する。
“各種の場”が、どのように創発するかについて下にまとめた。
|
創発する“各種の場”
|
重力場
電磁場
“原始的な力”の場
|
グルーオン場
(強い力の場)
|
電子場
|
クォーク場
中間子場
|
ニュートリノ場
|
ウィークボソン場
(弱い相互作用の場)
|
|
関わるヒッグス場
|
原始ヒッグス場
|
“プレオン∴ヒッグス場”
原始ヒッグス場
|
電子ヒッグス場
原始ヒッグス場
|
クォークヒッグス場
プレオン∴ヒッグス場
原始ヒッグス場
|
ニュートリノヒッグス場
原始ヒッグス場
|
ニュートリノヒッグス場
電子ヒッグス場
(クォークヒッグス場)
原始ヒッグス場
|
|
作用する粒子
|
重力子
光子
LP光子
|
グルーオン
( LP光子)
|
電子
( LP光子)
|
クォーク
グルーオン
( LP光子)
|
ニュートリノ
( LP光子)
|
電子、ニュートリノ
(クォーク)
LP光子
|
|
関係
|
粒子の場=ヒッグス場
|
粒子の場≠ヒッグス場
|
※原始ヒッグス場が変形したものが、電磁場や重力場、LP光子の場そのものであるように── グルーオンヒッグス場が変形したものがグルーオン場そのもそのである。
つまり、ここには、「粒子の場=ヒッグス場」の関係がある。
※一方、例えば、電子ヒッグス場が変形したものそのものは、“電子場”ではない。
すなわち、電子場とは、“電子の分布(存在度)そのもの”に注目している“電子の場”なのである。
逆に、電子ヒッグス場とは、“電子のふるまい(波動性、消滅度(→結果4)…)”を決める“電子の周囲の場”に過ぎない。
つまり、ここには、「電子ヒッグス場≠電子場」の関係がある。
それは、「“クォークヒッグス場”と“クォーク場”の関係」や「“ニュートリノヒッグス場”と“ニュートリノ場”の関係」についても同様である。
つまり、ここにあるのは、「クォークヒッグス場≠クォーク場」、「ニュートリノヒッグス場≠ニュートリノ場」という関係である。
※なお、原始ヒッグス場は、重力場や電磁場のみならず、他のすべての場を根底で支えている。
なぜなら、原始ヒッグス場は、「LP光子を介する“原始的な力”の場」として、クォークやレプトン、ウィークボソン、グルーオンの創発を支えているからである。
|
つまり、あらゆる“ヒッグス場”は、“ヒッグス場ユニットの総和として創発している”と同時に、“各種の場の創発を担う実体である”ということになる。
《ヒッグス場ユニット(=ヒッグス場の構成単位)とエネルギー》
5種類のヒッグス場ユニットは、それぞれ、エネルギーと深い関係を持っている。
|
ヒッグス場ユニット(=ヒッグス場の構成単位)
|
|
原始ヒッグス場ユニット
PHU
|
プレオン∴ヒッグス場ユニット
∴HU
|
電子ヒッグス場ユニット
eHU
|
クォークヒッグス場ユニット
uHU、dHU
|
電子ニュートリノヒッグス場ユニット
νeHU
|
|
|
|
 |
|
|
このヒッグス場ユニットとエネルギーの一般的な関係について、次の仮説を立てた。
仮説3.1 ヒッグス場ユニットは、“正4面体”のときにエネルギーが最低となり、変形することによってエネルギーを蓄えることができる。
そのときのエネルギー密度の変化の様子は、下図のようになっている。
※“正4面体”の状態が最もエネルギーが低くなっていることが図示されている。
※“4角形”(縮みきったバネ)の方は、これ以上エネルギーを蓄えられない限度がはっきりしているのに対して、“4角形”(四極子)の方は、さらにエネルギーを吸収して、バラバラになる(対生成する)りうるので、エネルギー密度が、より高くなることができる。
この“ワインボトルの底”の形状を示す図は、まさに、素粒子物理学の標準模型のヒッグス機構に登場する図と調和している。
※この図は、一般化して示してあるものであり、この図のようなエネルギー的な関係は、すべてのヒッグス場ユニット、すなわち、原始ヒッグス場ユニット(PHU)、プレオン∴ヒッグス場ユニット(∴HU)、電子ヒッグス場ユニット(eHU)… いずれにおいても、おおよそ、あてはまりうる。
※なお、上図における“エネルギー密度の大きさ”は、厳密なものではない。 詳細な検討は、今後の課題である。
※なお、上図のヒッグス場ユニットの“正4面体”の図は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)やプレオン∴ヒッグス場ユニットに相当する図である。
|
なぜ、ヒッグス場ユニットは、“正4面体”のときにエネルギーが最低であると考えられるのだろうか?
以下に、原始ヒッグス場ユニットPHU(=Primordial Higgs(field)Unit)を例にして、説明する。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は── ペンローズの“スピンネットワーク”の考え方を踏襲しており、素スピノールどうしは、ネットワークを作り、素スピノール同士が互いにリンクし合っていると考える。
すなわち、素スピノールの1つ1つが、“理想気体のように、まったくバラパラに存在している”ということはないと考えるのである。
一方、現在の「地球の周辺の宇宙(時空)」は、どの方向においても、おおむね性質が均等である(おおよそ対称性が保たれている)ので、素スピノールが、“びっしり整然と結びついて、1つの結晶構造を作っている”とも考えにくい。
したがって、次の仮説を立てるのは、自然なことであろうと思われる。
仮説3.2 “素スピノールのネットワーク”は、小さな“構成単位”(基本ユニット)をなし、それぞれが(原則として)ある場所に固定され続ける性質を持つと同時に、それぞれが、ゆるやかに結びつく(その場で自由に回転できる性質を持つ)ことによって、マクロの時空を創発する。
正しいとすれば、現在の宇宙に相当する素スピノールのネットワークは── 少なくとも、“単原子分子を想定する理想気体”のようなものでも、“ダイヤモンドなどの結晶”のようなものでもないことになる。 そして、しいて表現するなら、“金属原子のようにある場所に固定されている”と同時に、“液体の水の中の水分子のように自由に向きを変えることができる”ようなものということになる。
時空が持ちうる、最も基本的な“分子に似たような基本ユニット”として、どのようなものが考えられるだろうか?
この“基本ユニット”は、“(おおよそ対称性が保たれている)空間全体を満たす”ので── その構造は、原則として、正多面体構造に近いと考えられる。
そして、正多面体から遠ざかるほど、マクロの時空にストレスがかがり(ひずみが加わり)、エネルギーが高くなると予想される。
正多面体構造は、5つある。(正4面体、正6面体(立方体)、正8面体、正12面体、正20面体)
これらの中で最もエネルギーが低いのはどれであろうか?
それは、構成要素(頂点)の数が最少の正4面体である。
|
|
正4面体
|
正6面体
(立方体)
|
正8面体
|
正12面体
|
正20面体
|
|
構成要素(頂点)の数
|
4
|
8
|
6
|
20
|
12
|
(※ 正4面体が4つの構成要素(頂点)からなることは、例えば 4つのビー玉を使っても確かめることができる)
|
なぜなら、当然、構成要素(頂点)の数が多ければ多いほど、エネルギーが大きくなるからである。
つまり、5つある正多面体構造の中で、最もシンプルな正4面体の構造が最もエネルギーが小さいのである。
※なお、「時空の構成要素として可能性が高いのは、正6面体(立方体)、正8面体、正12面体、正20面体の方よりも、最もシンプルな正4面体の方である」と考えることは、シンプル一様化原理とも調和していると思われる。
一方、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“正4面体”は、やはり、“素スピノール”の組み合わせから創発するものである。
化学の世界(水素原子2つがバラバラに存在するより、ペアを組み水素分子1つになった方がエネルギーが低くなる等)から類推されるように── 素スピノールは、単独でバラバラに存在するよりも、“素スピノールのペア・・”を作って存在した方が、エネルギーレベルが低くなると考えられる。 すなわち、“素スピノールのペア・・は、離れれば離れるほど、エネルギーレベルが高くなると考えられる。
そして、さらに、1つの“素スピノールのペア・・”と1つの“素スピノールのペア・・”どうしは、それぞれ単独でバラバラに存在するよりも、“・・&・・”のように組み合わさった方がさらにエネルギーレベルが低くなると考えられる。 すなわち、“正4面体”の中の「“素スピノールのペア・・”×2」は、“素スピノールのペア・・”と“素スピノールのペア・・”の間の距離が離れれば離れるほど、エネルギーレベルが高くなると考えられる。
そして、一方で、“正4面体”は、つぶれる方向に変形すればするほど、正多面体の状態から遠ざかると同時に、密度が高まるので、エネルギーが高くなると考えられる。
つまり、つぶれる方向でも、分離する方向でも、“正4面体”の構造から離れれば離れるほど、エネルギーレベルが高くなると考えられる。
すなわち、おおよそ、仮説の図のようにエネルギーレベルが変化すると考えられる。
したがって、次の仮説は、的外れではない(自然(nature)と調和している)と言える。
仮説3.1 ヒッグス場ユニットは、“正4面体”のときにエネルギーが最低となり、変形することによってエネルギーを蓄えることができる。
そのときのエネルギー密度の変化の様子は、下図のようになっている。
※より厳密な説明は、今後の課題である。
|
このように、“正4面体”のときに最もエネルギーが低くく、変形することによって、エネルギーを蓄えることができると考えられることの他にも──
全く幾何学的な事実として、2つの線分“−”&“−”は、それらをうまく配置させることによって、容易に(線分の両端を頂点とする)“4面体”を作ることができること
“4面体”は、“4角形”(縮みきったバネ)に変形することにより、“重力子”(スピン2)を伝えることを説明できること(結果1)
“4面体”が途中まで変形することで、光子(スピン1)を伝えることを説明できること
…
を考え合わせると、やはり、結果1からすでに登場してきている、“原始ヒッグス場ユニットPHU(=Primordial Higgs(field)Unit)”と呼ぶところの、4つの素スピノールからなる下図のような“4面体”が、構成単位として、最もふさわしいことが理解できる。
|
原始ヒッグス場ユニット
PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)
|
|
|
他の4種類のヒッグス場ユニットについても、おおよそ同様にして、“4面体”が構成単位として、最もふさわしいことが理解できると思われる。
(それが“フラクタル相似の原理”と調和していることはすでに述べた)
5種類のヒッグス場ユニットは、それぞれの総和として、それぞれのヒッグス場を創発するのだった。
そして、その5つのヒッグス場の総和の中で、基本的には、最もエネルギーが低い状態のものが“真空”に相当すると考えられる。
すなわち、“真空”とは── 基本的には、5種類のヒッグス場ユニットのそれぞれにおける、最もエネルギーが低い状態である“正4面体”の総和として創発するものだということになる。
※ただし、「最もエネルギーが低い状態である“正4面体”の総和として創発するものが“真空”である」という説明だと── 厳密に考えれば、例えば、質量の周囲の“時空の曲り”が存在するところは、(重力子が存在し続けるので)、真空とは、呼べないことになってしまう。 同様に、例えば、電子ヒッグス場ユニットの中の“電子”を創発する“LP光子”が存在するところも、同様に真空と呼べないことになる。
よって、真空とは、「原始ヒッグス場ユニット以外のヒッグス場ユニットにおいて、最もエネルギーが低い状態である“正4面体”の総和として創発するものが“真空”である」ということでよいのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
ヒッグス場ユニット(および、その総和であるヒッグス場)とエネルギーの間には、やはり、きってもきれない関係がある。
|
“4角形”(縮みきったバネ)
|
|
“正4面体”
|
|
“4角形”(四極子)
|
|
|
エネルギーの放出
→
←
エネルギーの吸収
|
|
エネルギーの放出
←
→
エネルギーの吸収
|
|
|
※上下方向に縮まることによって生じている。
|
|
※凝縮のペア(黒い線で結ばれる)が
2つ組み合わさってできている。
※最もエネルギーが低い状態に相当する。
|
|
※四極子に相当する。
※各粒子間の距離(黒&赤)を保ちながら、ねじれることで“4面体”に至ることができる。
|
※ヒッグス場ユニットの構造の変化に応じて、エネルギーを蓄えたり、放出したりできる。
そして、ヒッグス場ユニット(および、その総和であるヒッグス場)とエネルギーの関係から、“真空”の他にも、様々なことを説明するためのヒントを得ることができる。
ヒッグス場の上をエネルギーが伝わる過程として、光子や重力子が創発すること(その集合として電磁波や重力波が創発すること)→結果1
エネルギーを蓄えたヒッグス場ユニットの総和として、重力場や電磁場が創発すること。→結果1
LP光子、グルーオン、ウィークボソンの作用、すなわち、“原始的な力”、強い力、弱い力が創発すること。 →結果2
静止の質量の獲得のしくみ(マイナスプレオンとプレオン∴ヒッグス場との相互作用から生まれる“電子のスピン”) →結果2
「LP光子の集積したひも」「グルーオンの集積したひも」が創発するしくみ →結果2
「運動エネルギー&ヒッグス場ユニット」による質量の獲得→下記の説明
自発的対称性の破れ、“ヒッグス場の相転移”や“インフラトン”→下記の説明
(宇宙開闢後、各種の素粒子が質量を獲得する過程で、ヒッグス場が生まれるとき、エネルギーが放出される)
高エネルギー状態が、四極子の状態、そして、“3つの世代”を生むこと。 →下記の説明
物質(電子、クォーク、ニュートリノ…)の波動性 →下記の説明、結果4
対生成&対消滅 →下記の説明
“量子ゆらぎ”の実体は、ヒッグス場ユニットにおける「“4面体”←→“4角形”(四極子)」の単振動であること。 →下記の説明、結果4
…
以下の項目で、ヒッグス場(および、その総和であるヒッグス場)とエネルギーの関係について、より詳しく説明していく。
《各種のヒッグス場と質量の関係》
そもそも“ヒッグス場”は、素粒子物理学の標準模型の中で、素粒子の質量獲得を説明するために考えだされたものであった。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、ヒッグス場は5種類考えられて、どれもエネルギーと深い関係を持つ。 しかし、質量は、エネルギーの一種に過ぎないのだった。 このことは、5種類のヒッグス場がすべて質量と関係があるとは限らないことを意味する。
それでは、この「素粒子の質量獲得を説明するために考えだされたヒッグス場」、すなわち、「質量を与えるヒッグス場」とは、5種のヒッグス場の中のどれに相当するのだろうか?
それは、「原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)」に他ならない。
そのことは、素粒子の質量獲得を説明する“ヒッグス場”についての、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による次の説明からわかる。
『もし、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が存在しない場合は(=すべてが“4角形”(縮みきったバネ)である場合は)、素粒子は、わざわざ“4面体”からに“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省かれるので、質量0(重力子の放出源として働き続ける能力が0)となり、ほぼ光速で運動できる。
しかし、実際は、宇宙開闢後の時空の相転移により、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”が、多くを占めるようになったので── その中において、その素粒子が運動し続けるために、常に、ある一定の頻度で、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)へと新たに変形させ続けるようになる。 まさに、その過程で、素粒子が、質量、すなわち、重力子の放出源として働き続ける能力を獲得したように観察されると同時に、光速を大きく失ったように観察される。』
つまり、「質量を与えるヒッグス場」とは、(5つあるヒッグス場の中の1つである)「原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)」に他ならないのである。
アインシュタインの式「E=mc2=m0c2(1−v2/c2)-1/2≒m0c2+m0v2/2(m0:静止質量)」によると、素粒子が持っている質量(すなわち、重力子の放出源として働き続ける能力)の起源は、大きくわけて、2つ考えられた。 すなわち、静止質量(m0c2)と運動エネルギー(m0v2/2に相当)の2つである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、質量の起源、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」の起源の実体は、1つに集約されるのだった。(→結果1)
|
1. 運動エネルギー(ふつうの意味での運動エネルギー)
(=外部運動エネルギー(external kinetic energy))
2. 静止質量エネルギー
(=内部運動エネルギー(internal kinetic energy))
|
→運動エネルギー |
※つまりは、あらゆる質量、すなわち、「重力子の放出源として働き続ける能力」は、実は、“運動エネルギー”として統一的に説明できることになる。
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、この静止質量エネルギーm0c2も、その実体は、運動エネルギーであったということになる。
例えば、電子の静止質量は、電子を構成する「プレオン∴の運動エネルギー」であり、プレオン∴の軌道運動が電子の「スピン運動」を担うのだった。(結果2)
|
|
|
※1つのマイナスプレオンにつき、1つのみのプレオン∴ヒッグス場ユニットが対応している。 |
「プレオン∴の運動エネルギー」も、「電子の運動エネルギー」も、いずれも、粒子(プレオン∴や電子)の軌道運動にともなって、(完成した)原始ヒッグス場(びっしりつまった原始ヒッグス場ユニットの総和)の中を、わざわざ、“4角形”(縮みきったバネ)に変形させながら進むことによって獲得する質量である。
したがって、原始ヒッグス場ユニット(PHU)は、もし、その位置を固定させていなければ、“質量”を創発させることができない。
なぜなら、位置を固定させていなければ、様々な物質の運動に伴い、“よける(逃げる)”ように移動してしまうので、物質に対する“見かけ上の光速を失わせる抵抗”として機能できなくなると同時に重力子の放出に至らないことになってしまうからである。
原始ヒッグス場ユニット(PHU)について── (運動方向が逆向きの)右巻き素スピノールのペア、(運動方向が逆向きの)左巻き素スピノールのペアのそれぞれは、“連星”のように、互いにクルクルと回りあい続けているおかげで“場所を固定する”という性質を獲得すると考えられることは、前にも述べた。(結果1)
|
“原始ヒッグス場ユニット
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の表記
|
|
※「 (運動方向が逆向きの)右巻き素スピノールのペア、(運動方向が逆向きの)左巻き素スピノールのペアのそれぞれは、“連星”のように、互いにクルクルと回りあい続けている」ことが、角運動量保存の法則によって説明できるということは、「原始ヒッグス場ユニットの中の素スピノールにとって、(連座な)回転対称性が成立し続けている」からであると考えてよいと思われる。(なお、ネーターの定理によると、(連続な空間において)回転対称性があるからこそ、角運動量保存則が成り立つとのことである) 詳細な検討は、今後の課題である。
プレオン∴ヒッグス場ユニット、電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニットは、質量を創発するものではないとすれば、必ずしも、その位置を固定させていなければならないということはないことになる。
よって、 原始ヒッグス場ユニット以外の“ヒッグス場ユニット”の一般的な性質について、次の仮説を立てることとする。
仮説3.3 “個々の「プレオン∴ヒッグス場ユニット、電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニット」、は、ある程度、向きを自由に変えられると同時に、全体の中で、それぞれの位置を、ある程度、固定させる。
※なお、この性質により、ニュートリノ振動をも説明できるようになる。(→下記)
原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)だけが質量を与える働きをする一方で── 「プレオン∴ヒッグス場、電子ヒッグス場、二ュートリノヒッグス場、クォークヒッグス場」は、質量を与える働きをしないとすれば、何をするのだろうか?
それは、“素粒子の存在度”(および、質量)を波のように変動させるのである。(→下記、結果4)
そのことによって、プレオン∴や電子やニュートリノやクォークの波動性を創発するのである。(→下記、結果4)
素粒子と、これらのヒッグス場の構成する各種のヒッグス場ユニット(プレオン∴ヒッグス場ユニット、電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニット)と相互作用する過程において、総エネルギー、すなわち、「素粒子の質量エネルギー(静止質量エネルギー+運動エネルギー)」と「各種のヒッグス場ユニットが蓄えるポテンシャルエネルギー」の和は、常に一定となる。 これらのヒッグス場は、質量エネルギーを一時的に蓄え、再び同じ大きさのエネルギーを質量エネルギーに返すという働きをするだけである。
なお、「プレオン∴ヒッグス場、電子ヒッグス場、二ュートリノヒッグス場、クォークヒッグス場」は、素粒子の速度を変化させないので、運動エネルギー、すなわち、“運動エネルギー順位”も変化させないことになる。。→結果4《電子の量子論的な振る舞いと、因果律──シュレーディンガー方程式》)
各種の粒子の質量について、まとめると次のようになる。
|
粒子
|
電子
|
ニュートリノ
|
クォーク
|
ウィークボソン
|
中間子、陽子、中性子
|
|
質量を与える
ヒッグス場
|
原始ヒッグス場
(=PHUの総和)
|
原始ヒッグス場
(=PHUの総和)
|
原始ヒッグス場
(=PHUの総和)
|
原始ヒッグス場
(=PHUの総和)
|
原始ヒッグス場
(=PHUの総和)
|
|
質量の起源
|
|
静止質量エネルギー
(=内部運動エネルギー)
|
《電子、ニュートリノ、クォークの場合》
(構成する)プレオン∴の外部運動エネルギー
《ウィークボソンの場合》
(構成する)電子、ニュートリノ、クォークの外部運動エネルギー
|
|
外部運動エネルギー
|
電子、ニュートリノ、クォーク、ウイィークボソンの
「軌道運動による質量獲得」
|
|
|
静止質量エネルギー
(=内部運動エネルギー)
|
(構成する)クォークの
静止質量エネルギー&外部運動エネルギー
|
|
外部運動エネルギー
|
中間子、陽子、中性子の
「軌道運動による質量獲得」
|
|
|
静止質量エネルギー
|
<0.5MeV
(電子)
|
電子ニュートリノ<2.5eV
ミューニュートリノ<170keV
タウニュートリノ<18MeV
|
<3MeV
(〜4.2MeV)
(アップクォーク)
<6MeV
(〜7.5MeV)
(ダウンクォーク)
|
<80GeV
(W−ボソン、W+ボソン)
<91.2GeV
(Z0ボソン)
|
<約350MeV
(中間子)
約1GeV(陽子、中性子)
|
※数値については、『物質の究極を探る 現代の統一理論』(日本物理学会 培風館)『宇宙と素粒子のしくみ』(京極一樹著 アスキー・メディアワークス)等を参考にした。
※なお、陽子の静止質量の2%を生むクォークの静止質量エネルギー(3MeV、6MeV)は、「クォークを構成するプレオン∴の外部運動エネルギー」由来で生じ、陽子の残りの98%の静止質量の大部分を「クォークの外部運動エネルギー」が担うと考えると、つじつまが合うと思われる。
さらに、『π中間子の質量、約350MeVは、「(「グルーオンの集積したひも」の両端の)2つのクォークの静止質量エネルギー&運動エネルギー」の和である』ことを考え合わせると、陽子と中性子の質量(約1GeV)が、中間子の質量(約350MeV)3つ分(350MeV×3=1050MeV)と比べて、(クォークの静止質量3つ分よりもずっと)小さくなっていることをスムーズに説明できると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※一方、この「グルーオンの集積したひも」を創発する材料である「プレオン∴ヒッグス場ユニット」は、“4面体”のときには、その「プレオン∴の軌道運動」のおかげで、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の放出源として働き続ける能力」、すなわち、質量を持つと考えられる。
まさに、これが、ダークマターの大部分を担うと考えると、つじつまが合いそうである。(→EMOES宇宙論)
“物質の質量”(クォークの外部運動エネルギー…)が、多く存在するほど、その分、「プレオン∴ヒッグス場ユニット」(主要なダークマター)は、「グルーオンの集積したひも」に転化することによって、その質量を失う。
すなわち、“物質の質量”(クォークの外部運動エネルギー…)と、(主要なダークマターと考えられる)「プレオン∴ヒッグス場ユニット」の質量の和は、おおよそ一定となると考えられる。
それは、「ダークマターが消費されて、物質が生まれている」という説明、および、観測結果と調和していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※ヒッグス場ユニットの“4面体”は、おそらくは“フラクタルな分布”をしていると予想される。 詳細な検討は、今後の課題である。
《電子と“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”との相互作用》
電子の質量エネルギーは、静止質量エネルギーと、運動エネルギーの和であり、ともに、重力子の放出源として働き続ける能力を持っている。
電子の軌道運動は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)と、電子ヒッグス場ユニット(eHU(=electron Higgs(field)Unit))の両方と、深い関わりがある。
まず、原始ヒッグス場ユニットと電子ヒッグス場ユニットを、比較して図示すると下のようになる。
|
原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU=electron Higgs(field)Unit)
|
|
ヒッグス場ユニットの構造
|
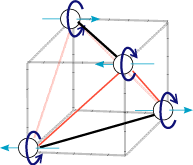
「左巻き素スピノール2つ」のペア
&「右巻き素スピノール2つ」のペア
|
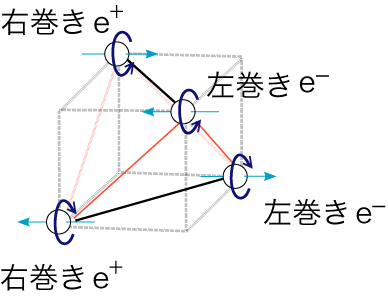
「左巻き電子と右巻き陽電子」のペア×2
|
|
基本構造の
おおよそのサイズ
|
3.232×10-35[m]
(2プランク長(2LP[m]))
|
<10-10[m]
(少なくとも水素原子の大きさよりは小さい)
詳細な検討は、今後の課題である。
|
|
“電子の軌道運動”
との関わり
|
運動エネルギーに等しい
質量エネルギーを創発する
|
消滅させたり、生成させたりする。
電子の波動性を創発する。
(→詳細は、結果4 シュレーディンガー方程式)
|
電子の軌道運動は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)に作用すると、それらを直接変形させることによって、重力子を放出させ続ける。
まさに、それが、運動エネルギーという名の質量エネルギーの一種である。
一方、電子の軌道運動は、電子ヒッグス場ユニット(eHU(=electron Higgs(field)Unit))に作用すると、電子の消滅の生成の波を創発する。
まさに、これは、電子の物質波に相当するものである。(→詳細は、結果4 シュレーディンガー方程式)
「電子の物資波(消滅と生成の波)」についての概要を示すと次のようになる。
定常状態において、電子は、決まった波長λe[m]を持つ。
この波長λe[m]を持つ、定常状態の電子は、λe/2[m]の間隔の電子ヒッグス場ユニットの相互作用しながら、軌道運動をする。
この電子の“定常状態”において、電子に作用する、「電子ヒッグス場ユニットが生じるポテンシャルエネルギー」は、次のようになると考えられる。(→結果4)
※各電子ヒッグス場ユニットが生じるポテンシャルエネルギーが、色別に示してある。
運動している電子には、常に、“2つのポテンシャルエネルギー”が作用していることが読み取れる。
そして、“2つのポテンシャルエネルギー”が作用することによって生まれる力は、合計が常に0になることが図から読み取れる。
なぜなら、“2つのポテンシャルエネルギー”は、上下逆転しているだけで、同じ形だからである。
(なお、電子に作用するポテンシャルエネルギーを位置で微分したものが、電子に作用する“力”に相当する)
※一方のポテンシャルエネルギーの減少分が、もう一方のポテンシャルエネルギーの増加分に常に等しいことが読み取れる。 すなわち、ポテンシャルエネルギーの合計が常に一定であることが読み取れる。 |
このようなしくみにより、定常状態の電子は、一定の速度ve 一定の波長λe ── つまりは、“決まった運動エネルギー順位Kn”を保ち続けることになる。
(電子は、加速or減速しない(運動エネルギー順位を変えない)ので、この電子は、光子を放出しないことになる)
このときの、電子ヒッグス場ユニットと電子の相互作用の詳細は、次のようになる。
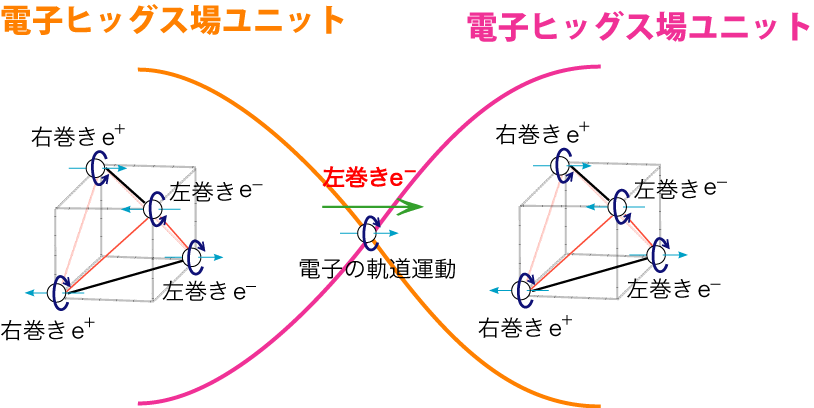
※左巻き電子が軌道運動し、ある電子ヒッグス場ユニットから離れると同時に、別の電子ヒッグス場ユニットに近づいていることが示されている。
※“定常状態で、軌道運動している電子”は、この図からわかるように、常に「離れている1つの電子ヒッグス場ユニット」と、「近づいている1つの電子ヒッグス場ユニット」の両方から、同時に、力を受けている。
そして、定常状態の場合、このように、働いている力の合計が常に0であることがわかる。
(“ポテンシャルエネルギーの変化(傾き)”である、2つの力の大きさが互いに等しくて、その向きが逆であるからである) つまり、定常状態の電子は、加速も減速もしておらず、常に等速運動をしているのである。
※したがって、このことは、「どのようなしくみで電子の定常状態が生じるか、どうして電子の定常状態において光子が放出されないのか」の理由の一部を説明していることになる。 (ボーアが仮定(前提)とするしかなかったことの一部を説明していることになる) (→結果4) |
|
|
↓
|
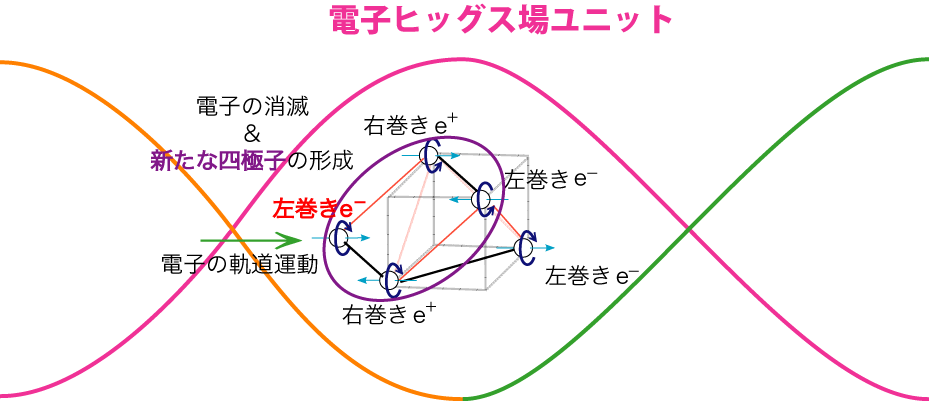
※軌道運動してきている左巻き電子が、原始ヒッグス場ユニットの中の右巻き陽電子と結びつくことによって“消滅”すると同時に、新たな四極子が生成している。
この電子ヒッグス場ユニットは、運動してきた左巻き電子が持っていた、「電子ヒッグス場ユニット由来の“ポテンシャルエネルギー”」に等しい大きさのエネルギーを蓄えることになる。
※この過程で、左巻き電子は、一定の速度vで運動し続けているのに関わらず、消滅もしている。 この消滅(=静止質量m0の消失)の度合いに比例して、運動エネルギー(m0v2/2)も、減少することになる。
この「静止質量エネルギー&運動エネルギー」の減少分が、電子ヒッグス場ユニットに蓄えられることになる。
※電子ヒッグス場ユニットの“4面体”が、新たな四極子を生成している間も、左巻き電子は、運動し続ける。
すなわち、“できあがる四極子の構造”は、常に変化し続けると考えられる。 また、その変化の様子自体も、蓄えるエネルギーの大きさの違いに応じて、微妙に異なるものになると予想される。 詳細な検討は、今後の課題である。 |
|
|
↓
|
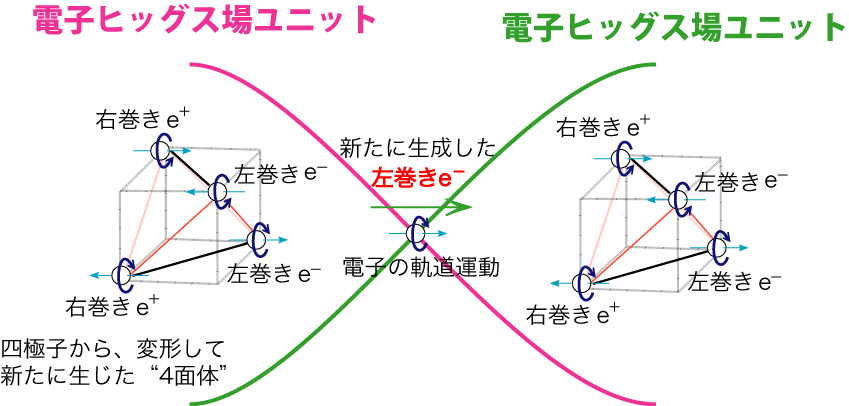
※電子ヒッグス場ユニットに蓄えられたポテンシャルエネルギーを利用して、「四極子を構成していなかった残りの左巻き電子」が新たに放出される。
この過程で、電子ヒッグス場ユニットの中の四極子が消滅すると同時に、元の“4面体”に戻る。
この新たに生じた左巻き電子の起源が、「電子ヒッグス場ユニットを構成していて、四極子になり損ねた左巻き電子」であるということは、厳密には、新たに生じた左巻き電子は、元の左巻き電子とは、異なるものであることを意味する。 しかし、両者は、全く区別がつかない。
※電子ヒッグス場ユニットに蓄えられたポテンシャルエネルギーが開放されていると同時に、電子ヒッグス場ユニットにポテンシャルエネルギーが蓄えられている。
電子ヒッグス場ユニットのポテンシャルエネルギーに由来する力と、電子ヒッグス場ユニットのポテンシャルエネルギーに由来する力は、ぴったり打ち消しあっている。
つまり、この新たに左巻き電子が放出される過程においても、やはり、“左巻き電子の加速”は生じない。(等速運動を続ける) よって、光子が放出されることはない。
※この過程で、「電子の質量エネルギー(運動エネルギー+静止質量エネルギー)」も、「2つの電子ヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギーの合計」も、常に一定となる。
|
|
|
↓
…
|
この全過程を、まさに、“波”と見なすことができる。
つまり、これこそが“電子の波動性”、すなわち、“電子の物質波”の創発を支える実体であると考えられる。(→結果4)
それは、いわば、電子ヒッグス場ユニットの“4面体”を“バネ”として利用しながら、電子が、電子ヒッグス場の中を、その質量エネルギー(静止質量エネルギー+運動エネルギー)を周期的に変動させながら、波動的に移動していることに相当する。
しかも、この“電子の物質波”を支える実体は、「電子が、消滅と生成を繰り返すところの波」を支える実体、すなわち、「“電子の存在度”が周期的に変化する波」を支える実体であるとも言える。
(なお、「“電子の存在度”の周期的な変化の波」のサインカーブと、上記の「電子ヒッグス場ユニットのポテンシャルエネルギーの変化」のサインカーブは、異なっている(→結果4))
そして、この“電子の存在度”の変動の波は、まさに、“電子の存在確率”の変動の波と関連あるものに他ならない。
つまり、いわゆる“電子の存在確率”を創発する実体、すなわち、波動関数の絶対値の二乗ψ*ψの意味するものの実体は、この“電子の存在度”の変化の波と関連したものであると考えると、ぴったりつじつま合うのである。 (→結果4)
※電子と陽子よりも、電子と陽電子(電子と電子ヒッグス場ユニット)の方が、より相互作用しやすいがために、電子は、原子核の所に落ちていかないで済むと考えることができると思われる。
詳細な検討は、今後の課題である。
※電子の定常状態において、電子ヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギーの最大値と、電子の運動エネルギー順位Kn (運動エネルギーの最大値)、速度ve 波長λe にの間には、決まった関係があるであろう。 詳細な検討は、今後の課題である。
※「質量エネルギー(運動エネルギー+静止質量エネルギー)」と「電子ヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギー」(重力子を放出しないエネルギー)の和は、常に一定となる。
つまり、電子の定常状態における、この全過程で、トータルのエネルギーの増減は生じず、エネルギーが保存されている。
なお、電子の定常状態においては、“加速や減速”は存在しないので、光子が放出されることはない。
電子ヒッグス場ユニットのみならず、プレオン∴ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニットも、その本質は、プレオン∴、電子、クォーク、ニュートリノの“存在度を変動させる”だけであり、新たに質量を生み出すということはない。
なぜなら、 「質量エネルギー(運動エネルギー+静止質量エネルギー)」と「電子ヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギー」が、互いに転化しているだけだからである。
したがって、この各種の粒子と、各種の「ヒッグス場ユニット」の間の相互作用においては、“質量獲得”は、存在しないことになる。
つまり、重要な結論を導き出せる。
結論3.1 各種の粒子に“質量を与える”働きを持つものは、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニットの総和)だけである。
このことは、いわゆる、「カイラル対称性の破れにともなう質量獲得」と言われる過程について、見直しを迫っていると思われる。
「カイラル対称性の破れにともなう質量獲得」とは、例えば、電子は、「左巻き電子→右巻き電子→左巻き電子→右巻き電子…」と変化することを繰り返す過程によって、(マクロレベルでの見かけ上の)光速を失い、質量を獲得することである。(参考 『質量はどのように生まれるのか 素粒子物理最大のミステリーに迫る』(橋本省二 講談社ブルーバックス))
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、このような「カイラル対称性の破れにともなう質量獲得」というしくみは、自然界に実在しないことを示している。
1つの理由は、電子は、本質的に、左巻きであるからである。 すなわち、“右巻き電子”は、「電子が光速を失うことにより、観測しうるもの」にすぎず、本来、右巻き電子と左巻き電子は、対称的に存在するものではないからである。(実際、観測される量は、左巻き電子>>右巻き電子となっている)
つまり、カイラル対称性は、「電子は、本質的に、左巻きである」という意味で、元々から破れているのである。
そこで、実在するとすれば、「左巻き電子→右巻き陽電子→左巻き電子→右巻き陽電子…」 のようなしくみである。
しかし、このしくみを含む(内在している)と見なせる、定常状態の電子と電子ヒッグス場ユニットの相互作用においては、「質量エネルギー(運動エネルギー+静止質量エネルギー)」と「電子ヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギー」が、互いに転化しているだけであり、“質量の新たな獲得”はどこにも存在していない。
質量獲得は、単に電子ヒッグス場ユニットと相互作用するだけでは達成されず、完成した「原始ヒッグス場」との相互作用があってはじめて、達成されるのである。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、少なくとも、『例えば、電子は、左巻き電子→右巻き電子→左巻き電子→右巻き電子… と変化することを繰り返す過程によって、(マクロレベルでの見かけ上の)光速を失い、質量を獲得する』という意味での「カイラル対称性の破れにともなう質量獲得」は、実在しないことを示しているのである。
詳細な検討は、今後の課題である。
|
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、対消滅した状態、すなわち、例えば、電子ヒッグス場ユニットやクォークヒッグス場ユニットの“正4面体”が形成されている状態では、重力子の放出がほぼなくなることを予想している。
なぜなら、かつて、1対10億の比率で物質が優位になり、残りの物質と反物質のペアが対消滅した所産が各種のヒッグス場ユニット(電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット…)と考えられるわけであるが、実際、ダークマターの比率は、せいぜい物質数%に対して、ダークマターが数十%の比率であるからである。
(すなわち、もし、例えば、電子ヒッグス場ユニットやクォークヒッグス場ユニットの“正4面体”が質量を持ち続け、重力子の放出を続けているのならば、ダークマターの比率は、物質数%に対して、ダークマターが数億%になってしまいかねないからである)
しかし、このことにより、「粒子と反粒子のペア(プラスの電荷とマイナス電荷のペア)が近くに存在すると、重力子の放出も消失する」と説明することはできない。
なぜなら、少なくとも次の3つの理由があるからである。
1.(電子2つと陽電子1つで構成されていると考えられる)ミューオンが、1つの電子よりはるかに大きな質量を持っている。
2.新しいブラックホールができる際に生ずると考えられる(マイナスプレオン2つとプラスプレオン2つで構成されている、スピン0の)“4角形”(縮みきったバネ)が、重力子を放出し続けると考えられる。(→結果1、結果2)
3.(マイナスプレオン2つとプラスプレオン2つで構成されている)プレオン∴ヒッグス場ユニットが質量を持ち続け、それがダークマターの候補であると考えられる。(→EMOES宇宙論)
|
以上のことは、例えば、電子ヒッグス場ユニットの“正4面体”を構成する、電子や陽電子は、ほとんど運動していない((外部)運動エネルギーを持っていないのみならず、スピンも消失しているので静止質量エネルギーも持っていない)ことを示唆しているように思われた。
よって、次の仮説を立てた。
仮説3.4 クォークやレプトンの粒子と反粒子(例えば、「電子e−と陽電子e+」、「アップクォークuと反アップクォークu」、「ダウンクォークdと反ダウンクォークd」)が対消滅する場合は、 これらを構成するプラスプレオンとマイナスプレオンがペアになることによって、プレオン∴ヒッグス場ユニットと相互作用できなくなるので、そのプレオン∴の物質波(生成と消滅の波)が消滅する。
この仮説により、例えば、「電子e−と陽電子e+」が対消滅する場合は、それぞれ、電子のスピン、陽電子のスピンが消失するのにともない、電子や陽電子の「静止質量エネルギー」(内部運動エネルギー)が消失することを説明できる。
一方、連星のような軌道運動にともなって獲得される質量エネルギーは、電磁場のポテンシャルエネルギーを利用して獲得される外部運動エネルギーに相当する分だけ生じると考えられる。
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU=electron Higgs(field)Unit)
|
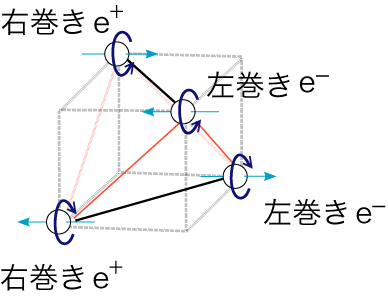
「左巻き電子と右巻き陽電子」のペア×2
|
※電子と陽電子がペアを組んで連星のような軌道運動をしているのは、それが、電磁場のポテンシャルエネルギーを利用して獲得される外部運動エネルギーにもとづいて生じているからである。
対照的に、プレオン∴ヒッグス場ユニットが、マイナスプレオンどうし、プラスプレオンどうしがペアを組んで連星のような軌道運動しているのは、それが、重力場のポテンシャルエネルギーを利用して獲得される外部運動エネルギーをもとづいて生じているからである。
|
それは、電子ヒッグス場ユニットのみならず、クォークヒッグス場ユニットについても同様に考えられる。
そして、「これらが獲得する質量が、(プレオン∴ヒッグス場とともに)ダークマターの一部を担いうると同時に、その大きさが十分に小さい」のであれば、『物質数%に対して、ダークマターが数十%の比率である』ことと、つじつまが合うと思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
《素粒子物理学の標準模型における“3つの世代”》
素粒子物理学の標準模型における“3つの世代”とは、次のようなものである。
|
電子から始まる3つの世代
|
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
|
電子e−
|
ミューオンμ−
|
タウオンτ−
|
|
スピン1/2
|
スピン1/2
|
スピン1/2
|
|
|
|
ニュートリノから始まる3つの世代
|
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
|
電子ニュートリノνe
|
ミューニュートリノνμ
|
タウニュートリノντ
|
|
スピン1/2
|
スピン1/2
|
スピン1/2
|
|
|
|
|
|
ダウンクォークから始まる3つの世代
|
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
|
ダウンクォークd−1/3
|
ストレンジクォークs−1/3
|
ボトムクォークb−1/3
|
|
スピン1/2
|
スピン1/2
|
スピン1/2
|
|
|
|
アップクォークから始まる3つの世代
|
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
|
アップクォークu+2/3
|
チャームクォークc+2/3
|
トップクォークt+2/3
|
|
スピン1/2
|
スピン1/2
|
スピン1/2
|
|
それぞれの“3つの世代”は、「質量のみが異なり、スピンや電荷など他の性質は、全く同じ」という関係を持っている。
なぜ、このような“3つの世代”が存在しているのか、どのようにして、このような“3つの世代”が生まれたのか、これまでの理論物理学は、まだ全く解明していないとのことであった。
素粒子物理学の標準模型における“3つの世代”について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明すると次のようになる。
標準模型における、それぞれの“3つの世代”は、いずれもスピン1/2のフェルミオンである。
これらは、“フラクタル相似の原理”により、何らかのフラクタルの関係を持っていると予想した。
もし、“×偶数タイプ(例えば、×2)”のフラクタルであるとすると、スピンが、1となったり、2になったりしてしまい、つじつまが合わない。
したがって、“×奇数タイプ(例えば、×3)”の何らかのフラクタルな関係を持つと予想される。
よって、次の仮説を立てた。
仮説3.5.1 標準模型における、それぞれの“3つの世代”は、“×3タイプ”フラクタルの関係にある。
※×奇数タイプの中で、×3を選択したということは、最も単純な奇数タイプを選んだことになる。 こことは、シンプル一様化原理と調和していると思われる。
この仮説をもとにすると、それぞれの“3つの世代”の具体的な構造は、次のように説明できる。
例えば、ミューオンμ−(第2世代)は、電子e−(第1世代)の何らかの組み合わせで生じると考えられる。
一方、総スピンや総電荷は、ミューオンμ−(第2世代)と電子e−(第1世代)の間で、一切違いがない。(違うのは質量のみである)
よって、 仮説3.2.1を考慮に入れて、最もシンプルな組み合わせを考えると── ミューオンμ-(第2世代)は、「電子e−(第1世代)2つと、陽電子e+(第1世代)1つ」との組み合わせとして創発するという描像が、自然に導かれる。
図示すると、例えば、次のようなミューオンの構造を考えられる。
※電子は左巻き、陽電子は右巻きになっており── トータルで、ミューオンは左巻きとなっている。
※“打ち消し”があるので── トータルのスピンは1/2であり、トータルの電荷が電子1つ分に相当することが読み取れる。
※このミューオンの中の「ある電子と陽電子のペア」に着目すると、“対消滅のペア”((連星のような軌道運動をする)電子ヒッグス場ユニットの半分)に、相当するように見えなくもない。
しかし、このペアは、「(連星のような軌道運動をする)電子ヒッグス場ユニットの半分」ではない。 なぜなら、(決定論的カオスにより)より激しく運動することによって、ミューオンの質量106MeVを生んでいると考えられるからである。
なお、その激しい運動をするミューオン中の電子と電子は、「LP光子の集積したひも」を介する“原始的な力”で結びつけられていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※トータルの磁気モーメントも、電子1つ分に相当すると考えられる。
詳細な検討は、今後の課題である。 |
これなら、スピンや電荷を一切変化させずに、“ミューオン”に相当するものの創発を説明できる。
より一般化することによって、次の仮説を立てることができる。
仮説3.5.2 次の世代は、「1つ前の世代の“粒子2つと、反粒子1つ”の組み合わせ」として創発するものである。
これによると、例えば、ミューニュートリノとは、「ニュートリノ2つと反ニュートリノ1つの組み合わせ」として創発するものであることになる。
すなわち、次のようなミュー二ュートリノの構造を考えることができる。
※電子ニュートリノが左巻き、反電子ニュートリノが右巻きになっており── トータルで、ミューニュートリノは、左巻きになっている。
※“打ち消し”があるので── トータルのスピンは1/2であり、トータルの電荷は、電子ニュートリノ1つ分に相当することが読み取れる。
※このミューニュートリノの中の「ある電子ニュートリノと反電子ニュートリノのペア」に着目すると、“対消滅のペア”((連星のような軌道運動をする)ニュートリノヒッグス場ユニットの半分)に、相当するように見えなくもない。
しかし、このペアは、「(連星のような軌道運動をする)ニュートリノヒッグス場ユニットの半分」ではない。 (決定論的カオスにより)より激しく運動することによって、ミューニュートリノの質量0.2keV以下を生んでいると考えられるからである。
なお、その激しい運動をするミューニュートリノ中の電子ニュートリノと電子ニュートリノは、「LP光子の集積したひも」を介する“原始的な力”で結びつけられていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
組成だけを見ると、ミューオンは、電子ヒッグス場ユニットの“4面体”から、1つだけ陽電子を取り除いたものに相当し──
ミューニュートリノは、電子ニュートリノヒッグス場ユニットの“4面体”から1つだけ反電子ニュートリノを取り除いたものに、相当することがわかる。
|
|
→
1つだけ陽電子を
取り除くと──
|
|
|
|
|
|
|
→
1つだけ右巻き反電子ニュートリノを取り除くと──
|
|
しかし、電子ヒッグス場ユニットの質量(運動エネルギー)よりもミューオンの質量(運動エネルギー)方が、
ニュートリノヒッグス場ユニットの質量(運動エネルギー)よりもミューニュートリノの質量(運動エネルギー)が、はるかに、大きいと考えられるのだった。
よって次の仮説を立てた。
仮説3.5.3 高エネルギー状態のときに限って、ある粒子(電子やニュートリノ、クォーク…)の“ヒッグス場の“4面体”から1つ取り除かれることによって、ある粒子の次の世代のものができる。
※高世代が生じるのは、高エネルギーのとき限定であるということは、
ヒッグス場ユニットの4面体”が励起して生じた“四極子”から1つを取り除くと考える方が、よりしっくりくると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
|
→
励起 |
|
→
1つだけ陽電子
(緑で囲んだもの)を
取り除くと──
|
|
|
|
|
|
|
|
|
→
励起
|
|
→
1つだけ右巻き反電子ニュートリノ(緑で囲んだもの)を取り除くと──
|
|
以上の説明について、既存の観測結果を用いた、簡単な検証を試みる。
ミューオンμ−については、ミューニュートリノνμ、電子e−、反電子ニュートリノνeに崩壊する現象が観測されている。
この崩壊過程は、おおよそ、次のような“反応式”として説明できる。
| 、 |
|
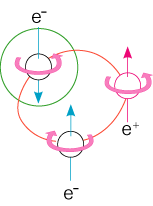 |
+ |
|
|
ミューオンμ−
|
|
ニュートリノヒッグス場ユニットが
励起して生じた“四極子”
|
|
| → |
|
|
|
W−ボソン
(→速やかに電子と反電子ニュートリノに分解)
|
|
|
+
|
|
|
|
|
ミューニュートリノνμ
|
|
|
+
|
|
|
|
|
速やかに対消滅する“電子と陽電子”のペア
|
|
弱い相互作用の過程で、「ミューオンの中の1つの電子(例えば、緑で囲んだもの)」と「ニュートリノヒッグス場ユニットが励起して生じた“四極子”の中の1つの右巻きニュートリノ(例えば、緑で囲んだもの)」からW−ボソンが生まれて放出されると──
|
1.(そのW−ボソンは)その後、速やかに
電子と反電子ニュートリノに分解される。
2.ニュートリノヒッグス場の“四極子”側の残りは、
そのままミューニュートリノになる。
3.ミューオン側の残りは、電子と陽電子のペアとして
速やかに対消滅する。(電子ヒッグス場ユニット
の半分に相当) |
例えば、パイ中間子−(ダウンクォーク+反アップクォーク)から、ミューオンと反ミューニュートリノができるという現象が観測されている。
この変化は、おおよそ、次のような“反応式”として説明できる。
|
パイ中間子π−
|
|
(弱い相互作用により)W−ボソンが生じる
そのW−ボソンは、速やかに分解して、
電子と反電子ニュートリノとなり──
|
|
励起して生じた“各種の四極子”の中の
陽電子やニュートリノと一緒に
対消滅すると──
|
|
ミューオンμ−と
反ミューニュートリノνμができる。 |
|
|
→ |
|
+
|
|
→ |
|
|
ダウンクォーク
+
反アップクォーク
|
|
W−ボソン
→電子+反電子ニュートリノ
|
|
1.「W−ボソンの分解で生じた電子」と「電子ヒッグス場ユニット由来の“四極子”の中の“陽電子”(緑で囲んだもの)」は、対消滅する。
2.「W−ボソンの分解で生じた反電子ニュートリノ」と「ニュートリノヒッグス場ユニット由来の“四極子”の中の“ニュートリノ”(緑で囲んだもの)」は、対消滅する。
|
もし、高エネルギー状態でなかったら、W−ボソンは、単に、電子と反電子ニュートリノに分解するだけである。
(ある高エネルギー状態に限定して、ミューオンや反ミューニュートリノが生成する)
よって、 パイ中間子π−からW−ボソンに変化する過程で生じるエネルギーが、高エネルギー状態、すなわち、電子ヒッグスユニットとニュートリノヒッグス場ユニットが励起した状態を生む結果── ミューオンと反ミューニュートリノが生じるようになるのだと考えられる。
低エネルギー状態の場合は、W−ボソンの分解で生じた電子と反電子ニュートリノは、電子ヒッグス場ユニットと、ニュートリノヒッグス場ユニットと相互作用することで、それぞれ、“物質波”を創発するだけとなる。
しかし、高いエネルギー状態ならば、ミューオンやミューニュートリノを生じることになる。
(そのことは、高世代が生じるのは、実際は、高エネルギーのとき限定であると考えられることと調和している。
つまりは、“物質波”が創発するか、高世代が創発するかは、エネルギーの大きさ次第ということになる。
※物質波と高世代の創発は、確かに、似ている(重なっている)ところがある。
すなわち、例えば、“ミューオンの組成”そのものは、電子ヒッグス場の“4面体”から、1つだけ陽電子を取り除いたものに相当するので── 上で説明した“電子の波動性の図”は、“ミューオンの創発の可能性を示す図”と見なすこともできる。
※上で説明した、電子の波動性を示す図である。 「新たな四極子」と「新たな電子」を読み取れる。
※上と全く同じ実体像を、「対消滅しうる電子と陽電子のペア」と『ミューオンになりうる「電子×2+陽電子×1」』と見なすことができることが読み取れる。
この図は、「ミューオンの創発」や「電子と陽電子の対消滅」を示しているわけではないが── “ミューオンの創発の可能性を示す図”であると言える。
すなわち、もし、エネルギーが十分に高ければ、それだけのことで、ミューオンが創発していまうことを示しているのである。
|
同様に、ミューニュートリノの組成は、電子ニュートリノヒッグス場の“4面体”から、1つだけ反電子ニュートリノを取り除いたものに相当するので── “電子ニュートリノの波動性を示す図”は、“ミューニュートリノの創発の可能性を示す図”と見なすこともできる。
(“電子の波動性を示すエネルギーの変化の図”と、“ニュートリノ振動を示す図”は、相似である)
このことは、ニュートリノのエネルギーが十分に高ければ、それだけのことで、ミューニュートリノが創発してしまうことを意味している。
※このあたりのことは、“ニュートリノ振動”(ニュートリノ→ミューニュートリノ→ニュートリノ→ミューニュートリノ→…)と関連しているのかもしれない。
すなわち、(これまで、抽象的な数学(波動間関数の重ね合わせ)によって、説明されてきた)“ニュートリノ振動”の幾何的な実体像を、このようなしくみを応用することによって説明できるかもしれない。
例えば、ニュートリノは、「ミューニュートリノの創発させるほど十分にエネルギーが高いと同時に── ミューニュートリノが、(弱い相互作用によって)すぐに分解してしまわないほど十分にエネルギー低い」という条件を満たせば、“ニュートリノ振動”を創発できる、と説明できるかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
あるいは、“ニュートリノ振動”の観測結果は、こういったしくみが実在することを証明してくれるものであると解釈できるかもしれない。
(正しければ、「観察の理論負荷性」の一種ということになる) 詳細な検討は、今後の課題である。
あるいは、そもそも、「“電子の波動性”を示す図は、実は、そのままで、“電子→ミューオン→電子→ミューオン…”という“電子振動”の一種に相当する。 ミューオンは、分解されない限り、観測されないものに過ぎない」と言える可能性はないだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
以上のようにして、
「仮説3.5.2 次の世代は、「1つ前の世代の“粒子2つと、反粒子1つ”の組み合わせ」として創発するものである。」
「仮説3.5.3 高エネルギー状態のときに限って、ある粒子(電子やニュートリノ、クォーク…)の“ヒッグス場の“4面体”から1つ取り除かれることによって、ある粒子の次の世代のものができる。」という仮説は、既存の観測結果をもとに簡単に検証できて、自然(nature)と調和的であることが確かめられる。
(“ニュートリノ振動”を含めて── 当然、さらなる厳密な検証は、今後の課題である)
一方、例えば、第3世代のタウオンについても、「仮説3.2.2 次の世代は、1つ前の世代の“粒子2つと、反粒子1つ”を組み合わせてできたものである。」をあてはめると──
「タウオンとは、ミューオン2つと反ミューオン1つを組み合わせてできたものである」ということになる。
すると、電子から始まる、第1世代から第3世代までの構造は、すべて、次のように、フラクタルによって説明できることになる。
|
電子から始まる第3世代までのフラクタル(×3)
|
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
|
電子e−
|
ミューオンμ−
|
タウオンτ−
|
|
e−
|
e+ e−
e−
|
μ+ μ−
μ−
|
|
(∴×3)
厳密には、
(−∴)×3
|
(∴×3×3)
厳密には──
(−∴)×3×2&(+∴)×3×1
|
(∴×3×3×3)
厳密には──
(−∴)×3×5&(+∴)×3×4
|
※−∴は、マイナスプレオン、+∴は、 プラスプレオンのことである。
同様に、この仮説によって、ニュートリノの3つの世代(電子ニュートリノ、μニュートリノ、τニュートリノ)、クォークの3つの世代(アップクォーク、チャームクォーク、トップクォーク/ダウンクォーク、ストレンジクォーク、ボトムクォーク)の関係も説明できる。
|
ニュートリノから始まる第3世代までのフラクタル(×3)
|
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
|
電子ニュートリノνe
|
ミューニュートリノνμ
|
タウニュートリノντ
|
|
νe
|
νe νe
νe
|
νμ νμ
νμ
|
※反粒子を便宜上、アンダーバーで示している
|
ダウンクォークから始まる第3世代までのフラクタル(×3)
|
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
|
ダウンクォークd−1/3
|
ストレンジクォークs−1/3
|
ボトムクォークb−1/3
|
|
d−1/3
|
d−1/3 d+1/3
d−1/3
|
s−1/3 s+1/3
s−1/3
|
| ※なお、K0=ds、K0=ds (便宜上、反粒子をアンダーバーで示している)の反応について、この組成をあてはめて検証してみても、矛盾がない。 |
|
アップクォークから始まる第3世代までのフラクタル(×3)
|
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
|
アップクォークu+2/3
|
チャームクォークc+2/3
|
トップクォークt+2/3
|
|
u+2/3
|
u+2/3 u−2/3
u+2/3
|
c+2/3 c−2/3
c+2/3
|
以上のように、「仮説3.2.2 次の世代は、1つ前の世代の“粒子2つと、反粒子1つ”を組み合わせてできたものである。」をあてはめるだけで、確かに、すべておいて「総電荷や総スピンを保存しつつ、質量だけが異なるもの」を構成できることがわかる。
正しければ、高世代は、(高いエネルギー状態における)低世代の自己組織化によって創発するものであることになる。
そして、世代が上がるほど質量が大きいので、次の予測を立てられる。
予測3.1 エネルギーが高い環境であるほど、より高い世代の素粒子が創発しやすい。
※もし、エネルギーが十分であれば、(同様な規則で)第4世代、第5世代… ができうるだろうか?
|
第1世代
|
第2世代
|
第3世代
|
第4世代? |
第5世代? |
… |
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
… |
|
a
|
a a
a
|
b b
b
|
c c
c
|
d d
d
|
… |
※反粒子を便宜上、アンダーバーで示している
しかし、“第4世代”は、「最もエネルギーが小さいニュートリノから始まる“第4世代”」でさえ観測されていない以上── なんらかの制限(理由)があるために、3世代までが限界である可能性もあるだろう。 ただし、「最もエネルギーが小さいニュートリノから始まる“第4世代”」が観測されていないのは、「その観測が“Z0の崩壊”を利用しているからに過ぎない」という可能性もあるかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
※ヒッグス場ユニットも、“3つの世代がある”と見なすことができないこともないが、それぞれ1次ヒッグス場ユニット、2次ヒッグス場ユニット、3次ヒッグス場ユニットと呼ぶこととする。
(“クォーク&レプトンの3世代”との混乱をさけるためである)
|
ヒッグス場ユニット(=ヒッグス場の構成単位)
|
|
1次ヒッグス場ユニット
|
2次ヒッグス場ユニット
|
3次ヒッグス場ユニット
|
|
原始ヒッグス場ユニット
PHU
|
プレオン∴ヒッグス場ユニット
∴HU
|
電子ヒッグス場ユニット
eHU
|
クォークヒッグス場ユニット
uHU、dHU
|
電子ニュートリノヒッグス場ユニット
νeHU
|
|
|
|
|
|
|
《ヒッグス場ユニットとヒッグス粒子》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、ヒッグス場とは、「(自発的対称性の破れにともなって生じた)各種のヒッグス場ユニットの“4面体”がびっしりとつまってできた場」である。
そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「各種の素粒子に質量を与える“ヒッグス粒子”」とは、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primal Higgs(field)Unit)であると考えるとつじつまが合う。
なぜなら、電子やクォーク、ニュートリノ… に質量を与えるのは、あくまで、原始ヒッグス場、すなわち、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和であり── プレオン∴ヒッグス場ユニット(∴HU)、電子ヒッグス場ユニット(eHU)、クォークヒッグス場ユニット(uHU、dHU)、ニュートリノヒッグス場ユニット(νeHU)ではないからである。
|
原始ヒッグス場ユニット
(PHU)
|
プレオン∴ヒッグス場ユニット
(∴HU)
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU)
|
クォークヒッグス場ユニット
(uHU&dHU)
|
ニュートリノヒッグス場ユニット
(νeHU)
|
|
「各種の素粒子に質量を与える
“ヒッグス粒子”」
|
「各種の素粒子に質量を与えない
“ヒッグス粒子”」
|
※すなわち、次の記述の中に登場しているヒッグス粒子と、調和しているヒッグス粒子は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)に他ならない。
|
・『ヒッグス粒子とは、1964年にピーター・ヒッグスが提唱したヒッグス機構において要請される素粒子である』
・『ヒッグス機構は、質量の起源について合理的な説明を与えることができる』
・『ヒッグス粒子はスピン0・電荷0のボース粒子である』
(『ヒッグス粒子』(ウィキペディア))
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、ヒッグス粒子とは、少なくとも5種類ある“ヒッグス場ユニット”という複合粒子に他ならない。
そして、その5種類のヒッグス粒子(=ヒッグス場ユニット)の中で、「質量を与える“ヒッグス粒子”」は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)だけである。
一方で、ヒッグス粒子が観測されたと発表されている。
「ヒッグス粒子の観測はどこまで進んだのか?」について、ウィキペディアの『ヒッグス粒子』のページを参考にして、整理してみよう。
|
・『2008年より稼働したCERNのLHCでの発見が期待されていた。
その実験はたやすいものでなく、LHCを用いた衝突実験ても、理論計算によるとおよそ10兆回に1回しか生成されないとされている』
・『2011年12月のこと、「ヒッグス粒子」が「垣間みられた」と発表され、そのニュースが世界を駆け巡った』
・『2012年7月4日、同施設で「新たな粒子を発見した」と発表された。質量はCMS:125.3GeV/c2、ATLAS:126.0GeV/c2である。
だが、この「新しい粒子」が、捜し求めていたヒッグス粒子であるのかそうではないのか、ということについては確定的には表現されず、
さらに精度を高めて確かめるために実験が続けられる、とされた』
・『2013年3月14日にCERNは、2012年7月31日の時より2.5倍も多いデータを分析した結果、新たな粒子はヒッグス粒子である事を
強く示唆していると発表した。例えば、ヒッグス粒子は理論的にスピン角運動量が0であるとされているが、データ解析の結果それと
一致することが確かめられた』
|
この観測されたと発表されている“ヒッグス粒子”(スピン0、質量125.3〜126GeV)とは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)における何に相当しているのだろうか?
(単純に、原始ヒッグス場ユニット(PHU)のことであると見なしてよいのだろうか?)
この「観測されている“ヒッグス粒子”」について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、まず、次の仮説を立てた。
仮説3.6 「観測されている“ヒッグス粒子”(スピン0)」とは、ある種のヒッグス場ユニット(スピン0)1つ分を、“何らかの形で”、スピン0のままに単独で叩き出した複合粒子に相当する。
「観測されている“ヒッグス粒子”」は、どのような状態のヒッグス場ユニットであるだろうか?
「スピン0の“4面体”」や「スピン0の“4角形”(縮みきったバネ)」の状態のヒッグス場ユニットは、却下される。
なぜなら、これらは、速やかに崩壊しないからである。
一方、“ヒッグス粒子”は、スピン0であるので── スピン2の“4角形”(縮みきったバネ)も、当然、却下される。
よって、「観測されている“ヒッグス粒子”」の候補として残るのは、「スピン0の四極子」だけとなる。
つまり、「観測されている“ヒッグス粒子”」とは、ヒッグス場ユニットの“4面体”でも、“4角形”(縮みきったバネ)(スピン2やスピン0)でもなく── 「スピン0の“四極子”」の状態のものに他ならないのである。
結論3.2 「観測されている“ヒッグス粒子”」とは、ある種の、ヒッグス場ユニット(スピン0)1つ分を、「スピン0の四極子」の形で、スピン0のままに単独で叩き出した複合粒子に相当する。
観測された「スピン0の四極子」は、5種類のヒッグス場ユニットの中のどれに由来するものであろうか?
|
原始ヒッグス場ユニット
(PHU)
|
プレオン∴ヒッグス場ユニット
(∴HU)
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU)
|
クォークヒッグス場ユニット
(uHU&dHU)
|
ニュートリノヒッグス場ユニット
(νeHU)
|
|
|
|
|
|
|
まず、プレオン∴ヒッグス場ユニット(∴HU(=preon∴ Higgs(field)Unit))は、却下される。
なぜなら、プレオン∴が閉じ込められているからである。
プレオン∴ヒッグス場ユニット(∴HU)が四極子として、叩き出され、速やかに、プレオン∴1つ1つに分解するとは考えられない。
したがって、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)も、却下される。
なぜなら、素スピノールは、“プレオン∴以上に”強固に閉じ込められているからである。
原始ヒッグス場ユニット(PHU)が四極子として、叩き出され、速やかに、素スピノール1つ1つに分解するとも考えられない。
※つまり、「観測されているヒッグス粒子」と「質量を与えるヒッグス粒子」が別物であることになる。
また、クォークヒッグス場ユニット(uHU(=up quark Higgs(field)Unit)、dHU(=down quark Higgs(field)Unit))も、却下される。
なぜなら、クォークは、強い相互作用によって、閉じ込められているからである。
クォークヒッグス場ユニット(uHU)が四極子として、叩き出され、速やかに、クオーク1つ1つに分解するとも考えられない。
※例えば、アップクォークuヒッグス場ユニット(uHU)の四極子二つから、アップクォークuと、反アップクォークuのペアが放出されて、チャームクォークcと反チャームクォークcのペアに変化するという過程は、考えられる。 ただし、それは、期待される、すみやかな「ヒッグス粒子の分解」ではないと思われる。 1つの理由は、その過程は、3GeV程のエネルギーで生じるものだからである。 詳細な検討は、今後の課題である。
残る候補は、電子ヒッグス場ユニット(eHU(=electron Higgs(field)Unit))と、ニュートリノヒッグス場ユニット(νeHU(=electron-neutrino Higgs(field)Unit))だけであることになる。
ここで、“ヒッグス粒子”の探求のための加速器による実験での生成物には、光子のみならず、グルーオンやウィークボソン、第2世代、第3世代といった多様な粒子があることを思い出そう。
そして、ニュートリノは、ほとんど何とも相互作用せず、“すりぬけてしまう”とという性質を持つことも思い出そう。
『ニュートリノは強い相互作用や電磁相互作用がなく、弱い相互作用と重力相互作用でしか反応しない。ただ、質量が非常に小さいため、重力相互作用もほとんど反応せず、このため他の素粒子との反応がわずかで、透過性が非常に高い』(ウィキペディア 『ニュートリノ』)
すなわち、ニュートリノは、スーパーカミオカンデのようなおおがかりな装置ではじめて、観測されるものである。
よって、このように透過性のニュートリノが、原因で、多様な粒子が生まれるとは考えにくい。
しったがって、「観測されているヒッグス粒子」が、ニュートリノヒッグス場ユニット(νeHU)が四極子として、叩き出され、速やかに、1つ1つに分解している結果生じているとは考えにくい。
よって、次の結論を得られる。
結論3.3 「観測されているヒッグス粒子」は、電子ヒッグス場ユニット由来の四極子である。
|
観測されているヒッグス粒子
|
観測されているヒッグス粒子の由来
|
|
電子ヒッグス場ユニット(eHU)由来の四極子
|
電子ヒッグス場ユニット(eHU)
|
|
|
|
※ともに、スピン0である。
ここで、Z0ボソンの質量エネルギー91.2GeVであることを思い出してみる。
この91.2GeVという値は、「観測されているヒッグス粒子」の質量エネルギー(質量125.3〜126GeV)に近いといえば近い。
何か関連があるだろうか?
ここで、次の電子と陽電子で構成されたZ0ボソンを考える。
|
Z0ボソン
|
|
|
|
電荷0、 スピン1/2
|
|
左巻き電子+右巻き陽電子
|
Z0ボソンも、速やかに分解してしまうという性質を持つのだった。
|
『Wボソンは陽子の約80倍、Zボソンは約90倍と他の素粒子に比べて大きな質量を持ち、ごく短時間のうちに別の粒子に分解されてしまうという特徴を持つ』
(ウィキペディア 『ウィークボソン』)
|
すなわち、W±ボソンと同様に、Z0ボソン(電子&陽電子)も、電子と陽電子に分解されてはじめて、観測されるものであると考えられる。(“分解される”からこそ観測される。(分解→観測))
したがって、Z0ボソン(電子&陽電子)の質量エネルギー91.2GeVは、“電子と陽電子”に分解するのに必要なエネルギー、すなわち、ウィークボソンZ0(e−とe+ )が分解される直前に、「電子e−」と「陽電子e+」に蓄えられていた外部運動エネルギーと見なすことができる。
※電子ヒッグス場ユニットを構成する電子と陽電子のペアが引き離される際、分解される直前まで、「電子e−」と「陽電子e+」に蓄えられる外部運動エネルギーが高まり続ける。 だからこそ、分解されると同時に観測が達成されるのであり、観測される質量エネルギー(主に『電子と陽電子』の外部運動エネルギー)と、分解の際に必要なエネルギーが等しくなるのだと考えられる。
※Z0ボソンは、4種類ある。
その中で、「電子と陽電子で構成されたZ0」を考えるのは── それが、91.2GeVのエネルギーを持つと観測されたからである。
|
『Z0粒子は、電子・陽電子対(Z0→e+e−)またはミュー粒子対(Z0→μ+μ−)への崩壊モードを検出した。これらの事象のレプトン対の質量分布のピークより、約90GeVと測定された.』
(p.41-42 『素粒子物理学』 高エネルギー加速器研究機構[監修] [著]堺井義秀 山田憲和 野尻美保子 共立出版)
|
このZ0ボソン(電子&陽電子)は、具体的に、何に由来して生じるのだろうか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、このZ0ボソン(電子&陽電子)は、やはり、(完全な無から生じるのではなく)“電子ヒッグス場ユニット”から生じると考えるのが自然である。
そこで、1つの“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”から、1つのZ0ボソン(電子&陽電子)が生じるのに、必要なエネルギーが、91.2GeVであると考えてみよう。
一方、1つの「観測されているヒッグス粒子」が生じるのに、必要なエネルギーが、125.3〜126GeVである。
この125.3〜126GeVのエネルギーを使って、1つの“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”の分解により、電子2つと、陽電子2つが生じると考えてみよう。
ここで、「観測されているZ0ボソン(電子1つ&陽電子1つ)」と「観測されているヒッグス粒子(電子2つ&陽電子2つ)」が、それぞれ「電子ヒッグス場ユニット(eHU)由来の四極子の中の“どこが切れることによって生じるか”」を図示すると次のようになる。
|
「観測されているZ0ボソン(電子1つ&陽電子1つ)」
|
「観測されているヒッグス粒子(電子2つ&陽電子2つ)」
|
|
|
|
※ピンクの丸で囲った部分が、切れる場所を示している。
「観測されているZ0ボソン(電子1つ&陽電子1つ)」の場合、3カ所切れる必要があるのに対し──「観測されているヒッグス粒子(電子2つ&陽電子2つ)」の場合、4カ所切れる必要があることがわかる。
|
このことにより──
“電子と陽電子”の結合を切るのに必要なエネルギーは、単純に、125.3〜126GeV−91.2GeV=34.1〜34.8GeVと計算できることがわかる。
そうすると、“電子と電子”(or“陽電子と陽電子”)の結合を切るのに必要なエネルギーは、(91.2GeV−34.1〜34.8GeV)/2=28.55〜28.2GeVと計算できることになる。
「電子と陽電子の結合を切るのに必要なエネルギー(34.1〜34.8GeV)」が、「電子と電子(陽電子と陽電子)を切るのに必要なエネルギー(28.2〜28.55GeV)」よりも大きいことは、“電磁ポテンシャルエネルギー”の働き方と調和している。
すなわち、正と負の電荷を引き離す方が、負と負(or 正と正)の電荷を引き離すよりも、より大きなエネルギーが必要になることと、上の計算結果は、調和している。
※なお、結合を切るのに必要なエネルギーは、やはり、それぞれの結合が切れる直前に、各粒子に蓄えられる外部運動エネルギーに相当すると考えられる。
※「電子と陽電子の結合を切るのに必要なエネルギー(34.1〜34.8GeV)」が、「電子と電子(陽電子と陽電子)を切るのに必要なエネルギー(28.2〜28.55GeV)」の差、5.9〜6.25GeVを1/2した、が、2.95〜3.125GeVが、“電磁気力によるポテンシャルエネルギー”による結合エネルギーの変動に寄与する値である。
この“電磁気力によるポテンシャルエネルギー”による結合エネルギーが、2.95〜3.125GeVという値が、『基底状態にある水素原子をイオン化するのに必要なエネルギー(イオン化エネルギー)』13.6eV(p.251 『物理学入門』)よりも、はるかに大きいことは、“電子と陽子”の結びつきよりも、“電子と陽電子”と結びつきの方が、はるかに強固であることを意味する。
(詳細な検討は、今後の課題である)
以上の説明は、「Z0ボソン(電子1つ&陽電子1つ)の観測」と、「ヒッグス粒子(電子2つ&陽電子2つ)の観測」は、非常に似ているもの(本質的には同一なもの)であることを示している。
すなわち、両者の違いは、(1つの“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”から)、1つの“電子&陽電子”の分解を生じるか、2つの“電子&陽電子”の分解を生じるか、という違いに過ぎなかったということになる。 よって、だからこそ、両者のエネルギーは、微妙に似たものだったと言えることになる。
以上のことは、“ヒッグス粒子の分解”、すなわち、“電子ヒッグス場ユニット(eHU)”の分解そのもそのから直接に生じるものは、「電子と陽電子のみ」であり、観測の際に生じる他のものは、副産物であることを示している。
すなわち、“ヒッグス粒子”の探求のために用いられた加速器(LHC)によって生じる“電子や陽電子”以外の生成物、すなわち、「光子、グルーオン、クォーク、ウィークボソン(W±ボソン)、第2世代(チャームクォーク反チャームクォーク(c+2/3c−2/3)、ストレンジクォーク反ストレンジクォーク(s−1/3s+1/3)、ミューオン反ミューオン(μ−μ+)…)、第3世代の素粒子(ボトムクォーク反ボトムクォーク(b−1/3b+1/3))…」は、“ヒッグス粒子の分解”の副産物ということになる。
|
・光子は、「電子&陽電子」等の“対消滅”の過程で生ずると考えられる。
・グルーオンやクォークは、“陽子と反陽子”(クォーク&グールオンの総和)を衝突させたさせたことによって生じる副産物である。
・第2世代は、“高エネルギー”の副産物として、クォークヒッグス場ユニット(uHU、dHU)、電子ヒッグス場ユニット(eHU)由来の四極子から生じると考えられる。
チャームクォーク反チャームクォーク(c+2/3c−2/3)やストレンジクォーク反ストレンジクォーク(s−1/3s+1/3)は、1つの“クォークヒッグス場ユニット(uHU、dHU)”由来の四極子あたり、1つの クォーク(uやu、dやd)が取り除かれることで生ずる。 まさに、その“取り除き”の結果、生じたものが、W−ボソン(or W+ボソン)であると考えられる 。
(d&uの取り除きとともに生じたものが、W-ボソンであり、 u&dの取り除きとともに生じたものが、W+ボソンである)
ミューオン反ミューオン(μ−μ+)は、2つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)由来の四極子の、それぞれからe−やe+が取り除かれることによって生ずるであろう。その取り除きの際、「他のe−とe+」との対消滅が起きるだろう。
・第3世代は、やはり、“高エネルギー”の副産物として、第2世代の集合から、生ずると考えられる。
すなわち、ボトムクォーク反ボトムクォーク(b−1/3b+1/3)は、ストレンジクォーク反ストレンジクォーク(s−1/3s+1/3)から、2つの四極子ができた上で、1つの四極子あたり1つのs−1/3やs+1/3が取り除かれることによって、生成するであろう。 その取り除きの際、「他のs−1/3とs+1/3」との対消滅が起きるだろう。
|
一方、 『質量の起源』(広瀬立成 講談社ブルーバックス)に、次のような記述(および図)がある。
『局所ゲージ不変性が成り立っているとき、ゲージ粒子の質量はゼロである。そこで対称性の自発的破れを要求すると、質量もつゲージ粒子以外に、質量ゼロでスピン・ゼロの「ゴールドストン・ボソン」、および、スピンはゼロであるが質量を持つ「ヒッグス粒子」が現れる』 (p.194 『質量の起源』)
『(対称性の自発的破れによって)四つのヒッグス場のうち三つがゴールドストン・ボソンになるが、それはゲージ粒子に食べられウィークボソンの質量に変わっている』 (p.200 『質量の起源』)
『ゲージ対称性が成り立っているとき、ゲージ粒子(W+、Z0、W-)は質量ゼロであった。対称性の破れによって、W+、Z0、W-は、ヒッグス粒子を食べて質量を獲得した。残された4番目のヒッグス粒子(斜線で示すH0)はそのまま質量ある粒子として観測が待たれている』
(p.201 図6-9およびその解説 『質量の起源』 “斜線”を“オレンジ色”に変えて図示している)
|
以上の記述と、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を比較すると──
「ゴールドストン・ボソン」、すなわち、「食べられてしまったヒッグス粒子」に、おおよそ相当するものが、「質量を与えるヒッグス粒子」、すなわち、「原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))の“4面体”」であると考えるとつじつまが合いそうである。 “食べて”、というのは、「ウィークボソン(W+、Z0、W−)を構成する電子やニュートリノ、クォークの運動エネルギーが、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形し続ける形で消費すること」に相当すると考えられるからである。(なお、ウィークボソン(W+、Z0、W−)を構成する電子やニュートリノ、クォークの運動エネルギーが、ウィークボソン(W+、Z0、W−)の大きな質量の起源に相当すると考えられる)
一方、『質量ある粒子として観測が待たれている』『残された4番目のヒッグス粒子』とは、電子ヒッグス場ユニット(eHU(=electron Higgs(field)Unit))由来のものに相当すると考えるとつじつまが合いそうである。
なぜなら、これが、まさに、『電子ヒッグス場ユニット由来の四極子』(125.3〜126GeV)として、すでに観測されたものに相当すると考えられるからである。
しかも、電子ヒッグス場ユニット(eHU)は、スピン0で、質量を持つと考えられる。
(電子ヒッグス場ユニット(eHU)も重力子の放出源となると考えられる。 電子&陽電子の対消滅によって、質量の放出量は減るけれども、100%、0にはならないと考えられるのだった)
そして、ここに、『電子ヒッグス場ユニットを構成する電子や陽電子は、LP光子で結びついている。 ウィークボソン(W+、Z0、W−)は、「LP光子の集積したひも」で、結びついている。』という意味での“対称性”が存在しているように見える。 このことが、まさに、電弱統一理論(ワインバーグ・サラム理論)を根底で支えていると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
《質量を与えるヒッグス粒子とウィークボソン》
前の項目で、「観測されているヒッグス粒子」とは、「質量を与えるヒッグス粒子」ではなく、 電子ヒッグス場ユニット(eHU)(由来の四極子)ことを示した。
また、「質量を与えるヒッグス粒子」とは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)に他ならないのだった。
|
「質量を与えるヒッグス粒子」
|
「観測されているヒッグス粒子」
|
|
原始ヒッグス場ユニット(PHU)
|
電子ヒッグス場ユニット(eHU)
(由来の四極子)
|
そして、『素粒子物理学の標準模型において、「素粒子(とくにウィークボソン)が質量獲得するしくみ」を説明するために考えだされたヒッグス場』とは、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニットの総和)に他ならないのだった。
※この原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニットの総和)は、各種の素粒子(電子、クォーク、ニュートリノ、プレオン∴、ウィークボソン(W±ボソン、Z0ボソン)に質量を与えうるのみならず、2次ヒッグス場ユニット(=プレオン∴ヒッグス場ユニット(=∴HU))にも、質量を与えうる。
よって、「自発的対称性の破れによる、時空の相転移によって、ウィークボソン(W±ボソン、Z0ボソン)が質量を持つようになった」という説明を根底で支えるものは、「原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニットの総和)の相転移」に他ならない。
この「原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニットの総和)の相転移」とは、宇宙開闢後、物体が分散すると同時に、多くの「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”」が創発する結果、達成されたと考えられる。 (“4角形”(縮みきったバネ)の一時的なキャンセルにもとづくと考えられる(→EMOES宇宙論2、3))
ところで、そもそも、電子や反ニュートリノ、クォークが存在しているということは、完成した原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の総和)および“原始的な力”が、すでに存在していればこそである。
(もし、すべての原始ヒッグス場ユニットが“4角形”(縮みきったバネ)となっている場合、質量0となるかもしれないが“時間が流れない”ので、“原始的な力”も、弱い力も、電子も反ニュートリノもクォークも、そもそも創発できないことになる)
したがって、少なくとも電子やニュートリノやクォークは、それらが創発する同時に、実は、質量を獲得していることになるのである。
よって、「(電子やニュートリノやクォークで構成される)ウィークボソンが、質量0で光速で運動すること」は、そもそもありえないことになる。 すなわち、「光速で移動できるウィークボソン」は、実在しないことになる。
つまり、ウィークボソンは、「(原始ヒッグス場の完成のおかげで)創発していると同時に、質量を獲得しているのである」のである。
《対生成&対消滅とエネルギー》
一般に、「真空は、エネルギーを得ると、粒子と反粒子のペアを対生成し── 逆に対消滅する際は、光子(γ線)という形で、エネルギーを放出する」と説明されている。
そのことは、“真空”とは、完全な無ではなく── 真空には“何か”が存在し続けることを示唆している。
その“何か”とは何か?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、その“何か”とは、「各種の最もエネルギーが低いヒッグス場ユニットの“正4面体”」に他ならない。
それは、真空とは、“エネルギーが最低の状態である”と定義されていることと調和している。
※ただし、「各種の最もエネルギーが低いヒッグス場ユニットの“正4面体”」は、質量を全く持たない(重力子の放出源として働き続けない)ということはないと思われる。
なぜなら、それらが、ダークマターに相当すると考えられるからである。(→EMOES宇宙論)
真空から“粒子と反粒子のペア”の対生成する過程は、まさに、“4面体”から“4角形”(四極子)へと変形する過程を経て達成されると考えれば、つじつまが合う。
すなわち、“4面体”←→“4角形”(四極子)の相互に変化する過程(緑で囲った部分に相当)は、対生成や対消滅の過程の一部に相当するものである。
その「対生成や対消滅の過程の一部」を、図示すると次のようになる。
|
“4面体”
|
|
“4角形”(四極子)
|
|
|
“対生成の過程”
の一部
→
←
“対消滅の過程”
の一部
|
|
|
※対生成の前の状態でもありうるし、
対消滅の後の状態でもありうる。
|
|
※対消滅に至る前の状態でもありうるし、
対生成に近づく途中の状態でもありうる。
|
※“4角形”(四極子)の状態を経て、粒子・反粒子が完全にバラバラになってはじめて対生成が完結すると言えるので、あくまで“過程の一部”であり、対生成、対消滅のすべての過程ではないと言える。
※プレオン∴ヒッグス場ユニット、電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニットいずれも共通である。
※原始ヒッグス場における“対生成”に相当するものが実在するかどうかは、不明である。
もし、素スピノールが単独で、原始ヒッグス場ユニットを励起することがあれば、原始ヒッグス場ユニット由来の四極子も実在すると予想できる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※“4角形”(四極子)から“4面体”への変化は、時空の相転移 or “自発的対称性の破れ”の一部にも相当する。
(対消滅は、時空の相転移 or “自発的対称性の破れ”の一部に相当すると言える)
※「対消滅する際は、光子(γ線)という形で、エネルギーを放出する」ということについては、一般に「光子がエネルギーを持ち去る」と説明されている。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、単に、ポテンシャルエネルギーを利用して対消滅が起きているだけで、その際の「電荷の運動エネルギー順位の上昇(→結果1)」によって、光子が放出されていると説明できる。(すなわち、この光子は、エネルギー非保存の所産ということになる) 詳細な検討は、今後の課題である。
|
《量子ゆらぎのエネルギー》
エネルギーのゆらぎ、すなわち、“量子ゆらぎ”の効果は、まさに、“4面体”←→“4角形(四極子)or“4角形”(縮みきったバネ)(or 変形した“4面体”(途中まで縮んだバネ))の変化の総和として創発すると考えると、様々な、つじつまが合う。(→結果4)
それは、すなわち、次の仮説を立てると、うまく説明ができるということである。
仮説3.7 “4面体”のエネルギーの放出&吸収こそが、“量子のゆらぎのエネルギー”の実体である。
“量子ゆらぎのエネルギー”の変化の様子を図示すると次のようになる。
| ※“4面体”←→“4角形”(四極子)の変化は、“量子ゆらぎ”のみならず、“粒子が持つ波動性”とも関連する。 (→上記、結果4) |
なお、不確定性原理が、量子ゆらぎの原因(理由、起源…)なのではない。
(不確定性原理は、本来、人類の観測事情を教えてくれる原理(ミクロとマクロが関係する自然(nature)が持っている性質を教えてくれる原理)に過ぎず、決して、ミクロの自然(nature)そのそものだけが持っている性質(ミクロの自然(nature)そのものがどうふるまうか)を教えてくれるものではない。(→結果4))
すなわち、このゆらぎのエネルギーは、決して、無から生じたものではないし、また、決してどこからともなく理由もなくやってきたわけでもないことになる。
「仮想粒子は、エネルギー保存則を破って生じるものである」と言われるが、全く無秩序なエネルギーを持つのではなく、あくまで、「ET= h、pλ= h 」等にしたがって(単振動の振幅が確定して)生じているものである。(→結果1、4)
“量子ゆらぎ”の原因(理由、起源…)として挙げられるのは、大きく、次の3つである。
1.原始ヒッグス場ユニット(1次ヒッグス場ユニット)と光子(LP光子、仮想光子、電磁波を構成する光子)や重力子の相互作用
2.プレオン∴ヒッグス場ユニット(2次ヒッグス場ユニット)とプレオン∴やグルーオンの相互作用
3.各種の3次ヒッグス場ユニットと各粒子の相互作用
|
|
量子ゆらぎの原因(理由、起源…)
|
|
1.原始ヒッグス場と光子や重力子の相互作用
|
2.プレオン∴ヒッグス場とプレオン∴やグルーオンの相互作用
|
3.各種の3次ヒッグス場と各粒子の相互作用
|
|
光子による量子ゆらぎ
(byLP光子、仮想光子、電磁波を構成する光子と
原始ヒッグス場の相互作用)
重力子による量子ゆらぎ
(by重力子と原始ヒッグス場の相互作用)
|
グルーオンによる量子ゆらぎ
(byプレオン∴やグルーオンと
プレオン∴ヒッグス場ユニットとの相互作用)
|
電子による量子ゆらぎ
(by電子と電子ヒッグス場ユニットの相互作用)
クォークによる量子ゆらぎ
(byクォークとクォークヒッグス場ユニット
の相互作用)
ニュートリノの量子ゆらぎ
(byニュートリノとニュートリノヒッグス場ユニット
の相互作用)
LP光子
|
|
“原始的な力”、プレオン∴の閉じ込め(漸近自由)
質量(=重力子の放出源として働き続ける能力)や
電荷(=仮想光子の放出源として働き続ける能力)と関連
(ダークエネルギーとも関連(→EMOES宇宙論))
|
電子のスピン、
強い力、クォークの閉じ込め(漸近自由)
(ダークマターとも関連(→EMOES宇宙論))
|
「電子やクォーク、ニュートリノ」の波動性と関連
(ダークマターとも関連(→EMOES宇宙論))
|
いずれも、光子や重力子、プレオン∴、グルーオン、電子、クォーク、ニュートリノ… といった各粒子と、各種のヒッグス場ユニットの相互作用という、はっきりした原因があって、量子ゆらぎが創発する。
このことは、逆に、もし、各粒子とヒッグス場ユニットの相互作用が、何らかの理由で消失すれば、量子ゆらぎも存在しなくなることになることを意味する。(→結果4)
例えば、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット総和)については、ブラックホールほどに重力が非常に強くなると、4角形”(縮みきったバネ)のみになるので、光子(LP光子、仮想光子、電磁波を構成する光子)が進行できなくなると同時に、素スピノールが転回できなくなるので時間の流れが止まる。
このことは、ブラックホールほどに重力が非常に強くなると、“光子による量子ゆらぎ”が消失するとともに、重力子、グルーオンやウィークボソンによる量子ゆらぎが消失することを意味する。
また、例えば、ブラックホールほどに重力が非常に強くなると、2次ヒッグス場ユニット(=∴HU)と各種の3次ヒッグス場ユニット(=eHU、dHU、uHU、νeHU)も消失する。 その結果、各種の粒子(プレオン∴、電子、クォーク、電子ニュートリノ)による量子ゆらぎ”も消失することになる。 この際、いわゆる、E=hν/2が対応する“ゼロ点エネルギー(零点エネルギー)(→結果4)”さえも、消失する。
つまり、量子ゆらぎの原因は、不確定性原理(不確定性関係)の中にあるのではなく、ミクロの自然(nature)の中にあるのである。
《インフレーションをもたらすエネルギー(インフラトン)》
“インフレーション”や“ビッグバン”は、宇宙の始まりに存在していたと考えられている現象である。
“インフラトン”とは、“インフレーションをもたらすエネルギー”として考えられているものである。
このインフラトンの正体は、いったい何なのだろうか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、この“インフラトン”について、次のような仮説を立てて説明する。
仮説3.8.1 「ある種のヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)が、とてつもなく高密度に凝縮した状態」が、指数関数的に解放される(分散する)と同時に、“4面体”へと相転移しながらエネルギーが放出される。 この過程が、インフレーション、およびビッグバンに相当する。 つまり、インフラトンを担う実体とは、この“4角形”(縮みきったバネ)として蓄えられたエネルギーの総和である。
ある種のヒッグス場ユニット由来の「“4角形”(縮みきったバネ)」は、ボソンである。
(スピンは、2か0かは、まだ明確ではないが── いずれにせよ、ボソンであることは確かである)
したがって、フェルミオンとは違ってボソンには同じ物理状態で多数存在できる性質があるので、“4角形”(縮みきったバネ)は、高密度に凝縮することができる。
※なお、この「高密度に凝縮」は、アインシュタイン・ボース凝縮と関連すると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
その(高密度に凝縮した)“4角形”(縮みきったバネ)とは、具体的に、どのヒッグス場ユニット由来のものだろうか?
1次〜3次ヒッグス場ユニットという、大きく3つの由来の可能性が考えられる。
まず、1次ヒッグス場ユニット(原始ヒッグス場ユニット(PHU))由来の“4角形”(縮みきったバネ)は、却下される。
なぜなら、原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)自体は、重力子の放出源として働き続ける“質量”ではなく、通過点だからである。
原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)自体が、自らそのままの形を保ち、高密度に凝縮し続けることは、不可能なのである。
すなわち、原始ヒッグス場由来(PHU)の“4角形”(縮みきったバネ)が生じるのは、やはり、“重力子の放出源として働き続ける能力、すなわち、質量を持つ他の何か”が存在してのこそである。
したがって、インフレーションを引き起こすエネルギー(インフラントン)を担うものは、“重力子の放出源として働き続ける能力、すなわち、質量を持つ他の何か”の方にあり、それを持たない原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)であると考える方が自然なのである。
よって、インフラトンの候補は、2次ヒッグス場ユニットのプレオン∴ヒッグス場ユニット由来か、3次ヒッグス場ユニット(=eHU、dHU、uHU、νeHU)由来かのどちらかに絞り込まれた。
インフレーションを起こす直前の「ある種のヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)が、とてつもなく高密度に凝縮した状態」は、とてつもなく大きな圧力を持ち、よりコンパクトであるだろうと予想される。 そのような高圧コンパクト状態で原形をとどめやすいのは、3次ヒッグス場ユニット(=eHU、dHU、uHU、νeHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)よりも、2次ヒッグス場ユニットのプレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)であると考えられる。
したがって、次の仮説を立てた。
仮説3.8.2 インフラトンを担う実体は、プレオン∴ヒッグス場ユニット(プレオン∴×4)由来の“4角形”(縮みきったバネ)が高密度に凝縮したものである。
このインフラトンを担う実体、高密度に凝縮した「プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“縮みきったバネ”」が、持っていエネルギーの総和が、インフレーションとともに放出されるエネルギーであり(=ビッグバンのエネルギー源となり)、その後、その高エネルギーを利用することで、第3世代まで各種の素粒子を創発すると考えるとつじつまが合う。
すなわち、この仮説により、様々なことを、無理せず、自然に説明できるようになるのである。
(→結果6『“4つの力の統一”(4つの力の創発の歴史)について』 →EMOES宇宙論)
ビッグバウンス、インフレーション、ビッグバン、“高世代”の創発の過程の、おおよその図を示すと、次のようになる。
※そもそものインフレーションを始めるきっかけ(引き金)は、何であろうか?
その答えに関する有力なヒントは、『高まり続けたエネルギー密度がある臨界点を超えると、 重力が引力から斥力に変わり、ビッグバウンスが起きる』(『量子重力が予言するビッグバウンス宇宙』 日経サイエンス2009年1月号より)という説明にあると思われる。
すなわち、インフレーションの引き金は、単純に、インフラトン(プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“縮みきったバネ”が高密度に凝縮したエネルギーの総和)が、ある閾値(臨界点)を越えることにともなう“ビッグバウンス”であると考えられる。
そして、「高まり続けたエネルギー密度」に臨界点がある理由は、「プレオン∴ヒッグス場ユニットや原始ヒッグス場ユニット」由来の“4角形”(縮みきったバネ)に蓄えられるエネルギーには限界があるからであると考えられる。
高密度に凝縮した「プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“縮みきったバネ”」を、便宜上、次の左のように示した。
便宜上、さらにシンプルにして、下の右側の立方体のように示せることとする。
|
高密度に凝縮した「プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“縮みきったバネ”」
|
|
|
※図は、いずれも、あくまで便宜的なものである。
※「プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)」は、果たして、スピン2だろうか? それとも、スピン0だろうか?
|
スピン2
|
スピン0
|
|
|
|
| プレオン∴ヒッグス場ユニットの“4面体”の半分が転回することによって、トータルのスピンが2になっている。 |
プレオン∴ヒッグス場ユニットの“4面体”をそのままつぶして(圧縮して)できたものに相当する。 |
スピン2なら、グルーオン2つからできていると見なせるので“グルーボール”が関連し、“球”かもしれないという考えもありうるかもしれない。
一方、スピン0なら、“連星の軌道運動”が保たれることになるので、「重力子の放出源として働き続ける」ことを説明しやすいと思われる。
そういう意味では、スピン0の方が、より可能性が高いように思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
いずれにせよ、「プレオン∴×4の“4角形”(縮みきったバネ)」が持っていたその高密度の凝縮が「ビッグバウンス および、インフレーション」の起きている際には、指数関数的に解放されると考えられる。
|
「プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“縮みきったバネ”」が持つ
“高密度の凝縮”の指数関数的な解放
|
|
高度な凝縮した
「プレオン∴×4の
“4角形”(縮みきったバネ)」
を示す“立方体”
|
「高度な凝縮の開放」(×1/8)
|
「高度な凝縮の開放」(×1/82)
|
… |
|
|
|
|
… |
→
|
※ビッグバウンス、インフレーションにともなって、1/8倍、1/8倍…というように、指数関数的に、高密度の凝縮が開放されている様子が示されている。
※これらの図も、あくまで便宜的なものである。 |
このプレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)の凝縮が指数関数的に解放される結果、何が起こるであろうか?
そのことについて、次の仮説を立てた。
仮説3.8.3 インフレーションの過程で、「プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)」の高度な凝縮が指数関数的に開放される結果、その分布において“フラクタルなゆらぎ”が生まれた。 そして、 その“フラクタルな分布のゆらぎ”が、後の銀河、銀河団、超銀河団、ボイド… 等の宇宙の大規模構造を生む元となった。
高度な凝縮が指数関数的に(例えば、1/8倍、その1/8倍、その1/8倍のように)解放されるということは、“4角形”(縮みきったバネ)の密度が、1/8倍、その1/8倍、その1/8倍… と指数関数的に減ると同時に、8倍、その8倍、その8倍… と指数関数的に“分布”が広がる(“分散”が増幅する)ことを意味すると考えられる。 そして、そういった過程によって、“4角形”(縮みきったバネ)の“フラクタルな分布のゆらぎ”が生じると予想される。
そして、それこそが、後に銀河、銀河団、超銀河団…等の宇宙の大規模構造を生む“エネルギー密度のゆらぎ”の原因であると考えるとつじつまが合う。
一方、インフレーションとともに、プレオン∴ヒッグス場ユニットの“4角形”(縮みきったバネ)が“4面体”に変化する過程で、莫大なエネルギーが放出される。
そのエネルギーがビッグバンのエネルギーに他ならない。
そうしてできたプレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“4面体”の一部は、その放出されたビッグバンのエネルギーを利用しながら、少なくとも3世代までのクォークやレプトンを生成すると考えられる。
そして、これらが、非対称性(CP対称性の破れ)に分解することによって物質が反物質を上回ったと考えられる。(→結果5)
3世代までのクォークやレプトンになり損ねた方は、そのままプレオン∴ヒッグス場ユニットの“4面体”として残る。 それがダークマターを構成するものの正体の一部であると考えれば、つじつまがあうと思われる。
(“銀河系の周辺に行くほど、物質の比率が減り、ダークマターの比率が上がる”ことと調和している →EMOES宇宙論)
※こういった過程を経て、各種のヒッグス場(1次〜3次ヒッグス場ユニットの“4面体”の総和)が完成していく。
そうすると、厳密に見れば、「自発的対称性の破れに伴う相転移」によって、完成するヒッグス場は、3次ヒッグス場ユニットで構成されたものだけであると言える。
なぜなら、1次〜2次の方は、その創発過程で、逆に対称性が高まっている((対称性の破れている)秩序が高い状態から、秩序が低い状態へ変化している(エントロピーが増加している))からである。
南部陽一郎は、“超伝導(超電導)”が生じる過程において、「2つの電子からクーパー対が作られる」ことから、ヒントを得て、「自発的対称性の破れ」の概念を生んだ。
クーパー対とは、スピン、運動量がともに逆向きの電子の対である。 そのことは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による「ヒッグス場ユニットの“4面体”の構造」とも調和していると思われる。
なぜなら、例えば、電子ヒッグス場ユニットの“4面体”の中には、確かに、スピン、(軌道)運動量が逆向きのペアが存在しているからである。
しかし、「クーパー対」と、「電子ヒッグス場ユニットの中の電子対」は、似ているところがあるが、大きく違うところもある。
それは、ホーア半径が、a0≒5.29×10-11[m]であるので、電子ヒッグス場ユニットのサイズは、少なくとも、a0≒5.29×10-11[m]以下であると考えられる一方── クーパー対は、<10-7[m]程度であるというように、そのサイズが大きく異なることである。
ただし、“超伝導(超電導)”と“電子の波動性(電子ヒッグス場ユニットとの相互作用)”が何らかの関連を持っていること、すなわち、“クーパー対”と“電子ヒッグス場ユニット”が何らかの相互作用をしていることは、確かだと思われる。 “超伝導(超電導)”がどのようにして生じるか── なぜ、電子ヒッグス場ユニットのびっしりつまった電子ヒッグス場の中を、電場がなくとも(電圧をかけなくとも)進んでいけるようになるのか── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による、詳細な説明は、今後の課題である。
※これまでの“インフレーション”と“ビッグバン”が意味する過程は、例えば、次のように説明されてきた。
『インフレーション・ビッグバン論では、単なる素粒子ではなく宇宙全体が、真空の量子的ゆらぎから一挙に生まれたとしている』
(p.90 『世界の論争・ビッグバンはあったか 決定的な証拠は見当たらない』 近藤陽次 講談社ブルーバックス)
|
これは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明されている、(ビッグバウンスから始まる)“インフレーション”と“ビッグバン”が意味する過程とは、厳密に見れば異なるものである。
また、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の“インフレーション”は、“空間が膨張する過程”ではなく、「その後、空間が膨張できる初期条件を整えるような、“空間が収縮する過程”」であるという点でも、これまでの“インフレーション”とは意味が異なる。(→EMOES宇宙論)
それでも、“ビッグバン”や“インフレーション”という言葉を使い続けるのは、なぜか?
1つは、そもそも、最初に考えられた「ビッグバン(火の玉が宇宙の始まりとする考え)」と、「インフレーション・ビッグバン論(インフレーションが宇宙の始まりで、ビッグバンはその後に起きたとする考え)」におけるビッグバンは、意味が異なっているのに、ビッグバンが使われるのと、同じであろうと思われる。
それは、“ビッグバン”の言葉が持っているイメージ喚起力、その本質的な意味を尊重しているからである。
“ビッグバン”の本質的な意味とは、“非常な高温状態”である。 この本質的な意味(についてのイメージ喚起力)が保持され続けているからこそ、この言葉を続けるのである。
「インフレーション・ビッグバン論」の中のインフレーションと、「ビッグバウンス・インフレーション・ビッグバン論」の中のインフレーションは、厳密に言えば、意味が異なる。
しかし、インフレーションの持っている本質的な意味、すなわち、“急激な(指数関数的な)の分布(密度)の変化”という意味は、保持し続けているので、この言葉を使い続けるのである。
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による「ビッグバウンス・インフレーション・ビッグバン論」には、フラクタルな分布のゆらぎ、すなわち、大規模構造の創発を自然に説明できるというメリットがあるので、これまでの「インフレーション・ビッグバン論」を、より自然(nature)と調和したものにグレードアップしていると言えるかもれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
《階層性問題について》
“階層性問題”というものがある。
これは、プランクエネルギー(約1019GeV) と、ウィークボゾンや陽子などが持つ静止質量エネルギー (それぞれ約80GeV 、約1GeV)の差があまりにも大きすぎるという問題である。
この“階層性問題”を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、どのように説明できるであろうか?
まず、各種の“質量やエネルギー”が、どのように生じ、その大きさがどの程度なのかについて整理する。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── プランクエネルギーEP(=約1019GeV)とは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”の1つが“4角形”(縮みきったバネ)になるときに蓄えるエネルギー(=重力子エネルギーEG)を2π倍したものでもある。
一方、プランクエネルギーEP(=約1019GeV)は、プランク質量MP(≒2×10-8[kg])の“質量エネルギー”に相当するエネルギーである。
このプランク質量MP(≒2×10-8[kg])とは、『“c/2LP”[回/s]の頻度での「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力に相当する“重力子質量MG”』を2π倍したものである。
質量とは、『「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力』のことに他ならないので──
ウィークボゾン(約80GeV)や陽子(約1GeV)、 ニュートリノ(約2.5eV)、電子(約0.5MeV)、クォーク(約3MeV、6MeV)、 プランク質量MP(≒2×10-8[kg]、約1019GeVに相当)は── それぞれの静止質量エネルギー(=内部の運動エネルギー)に見合った頻度で、重力子を放出し続ける。
これまでの説明をまとめると次のようになる。
|
電子ニュートリノ
|
電子
|
クォーク
|
陽子、中性子
|
W−ボソン
|
プランク質量MP
(≒2×10-8[kg])
|
|
静止質量エネルギーを
エネルギー[eV]で表記
|
<約2.5eV
|
<約0.5MeV
(=0.0005GeV)
|
<約3MeV(アップクォーク)
<
約6MeV(ダウンクォーク)
|
約1GeV
|
<約80GeV
|
プランクエネルギーEP
=1.2209×1019[GeV]
|
|
「重力子&“4角形”
(縮みきったバネ)」
を放出する頻度[回/s]
|
<約1.8993×1018
[回/s]
|
<約3.7987×1020
[回/s]
|
(アップクォーク)
<約2.2792×1021[回/s]
(ダウンクォーク)
<約4.5584×1021[回/s]
|
約7.5974×1023
[回/s]
|
<約6.0779×1025
[回/s]
|
“c/2Lp”
=約9.2757×1042
[回/s]
|
|
静止質量エネルギーの起源
|
プレオン∴の外部運動エネルギー
(この軌道運動は、「電子のスピン」も担っている)
|
クォークの静止質量エネルギー
&外部運動エネルギー
|
電子と電子ニュートリノ
の静止質量エネルギー
&外部運動エネルギー
|
「“c/2Lp”[回/s]頻度で重力子の
放出源として働き続ける能力」
≒「原始ヒッグス場ユニット
(PHU)の“4面体”1つを
完全に“4角形”(縮みきったバネ)
まで変形させるのに必要なエネルギー
に等しい質量エネルギーを担う質量
すなわち、重力子質量MG[kg]を、
2π倍したもの」
|
※単純な比例計算で、他の粒子の重力子の放出量が計算できるのだった(→結果1)。
※アップクォークが“〜4.2MeV”なら、〜3.1909×1025[回/s]、ダウンクォークが“〜7.5MeV”なら、〜5.698×1025[回/s]である。 |
以上から、次のことがわかる。
それは、「電子ニュートリノ、電子、クォーク、陽子、中性子、W−ボソン」の“質量エネルギー”と、“プランクエネルギー”は、単位が共通でも、その意味する内容が異なっているということである。 すなわち、前者は、「特定の粒子が持つ重力子の放出源として働き続ける能力」を意味するに対し、後者は、「不特定多数の粒子が持つ重力子の放出源として働き続ける能力の総和」を意味しうる点で、大きく異なっているのである。
|
電子ニュートリノ
|
電子
|
クォーク
|
陽子、中性子
|
W−ボソン
|
プランク質量MP[kg]
(≒2×10-8[kg])
|
|
静止質量エネルギーを
エネルギー[eV]で表記
|
<約2.5eV
|
<約0.5MeV
(=0.0005GeV)
|
<約3MeV(アップクォーク)
< 約6MeV(ダウンクォーク)
|
約1GeV
|
<約80GeV
|
プランクエネルギーEP[J]
=1.2209×1019[GeV]
|
|
「重力子&“4角形”
(縮みきったバネ)」
を放出する頻度[回/s]
|
<約1.8993×1018
[回/s]
|
<約3.7987×1020
[回/s]
|
(アップクォーク)
<約2.2792×1021[回/s]
(ダウンクォーク)
<約4.5584×1021[回/s]
|
約7.5974×1023
[回/s]
|
<約6.0779×1025
[回/s]
|
“c/2Lp”
=約9.2757×1042
[回/s]
|
|
意味
|
「特定の1つの粒子が持つ重力子の放出源として働き続ける能力」
|
「不特定の多数の粒子が持つ重力子の放出源として働き続ける能力の総和」
(or 「プランク質量MP[kg](≒2×10-8[kg])の仮想質点」が持つ重力子の放出源として働き続ける能力)
|
したがって、「 プランク質量MP[kg]」は、陽子だけがおよそ1019個集合してできた物体にも相当しうるし、電子がおよそ1022個集合してできたものに相当しうるのである。
(いずれも、「1秒間にc/2LP[回]」の頻度で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出することに変わりない)
だからこそ、「プランク質量MP[kg]」が「1.2209×1019[GeV]」ものエネルギーを持つのに対して──
最大の「1つの W−ボソン」が持つエネルギーであっても、せいぜい「80GeV」にすぎず、とても、かなわないのである。
そして、以上の説明の中には、実は、階層性問題の答えがある。
すなわち、まさに、「何が 「ウィークボソンの質量エネルギー80GeV〜90GeV」や「陽子&中性子の質量エネルギー1GeV」と、「プランクエネルギーEP[J]=1.2209×1019[GeV]」の違いを生むのか?」という問題に対する答えが、以上の説明にあるのである。
その違いを生んでいる理由は、次のようにまとめられる。
1.質量エネルギー”の意味(内容)が違いうるからである。
すなわち、「ウィークボソンの質量エネルギー80GeV〜90GeV」や「陽子&中性子の質量エネルギー1GeV」が、
「特定の1つの粒子が持つ重力子の放出源として働き続ける能力」に相当するのに対して、「プランクエネルギーEP=1.2209×1019[GeV]」は、“
「不特定の多数の粒子が持つ重力子の放出源として働き続ける能力の総和」に相当しうるからである。
(例えば、「ウィークボソンの質量エネルギー80Gev〜90GeV」や「陽子&中性子の質量エネルギー1GeV」は、「1つの W−ボソン」が持つ質量エネルギーや「1つの陽子or 1つの中性子」が持つ質量エネルギーであるのに対し──
「プランクエネルギーEP[J](1.2209×1019[GeV]」は、「不特定多数の粒子の質量の総和」たりうるプランク質量MP[kg](≒2×10-8[kg]が持つ質量エネルギーMPc2[J]に相当するもので、それは、「陽子だけがおよそ1019個集合してできた物体」や「電子がおよそ1022個集合してできたもの」でもありうるからである)
2.「プランクエネルギーEP[J]=1.2209×1019[GeV]」、すなわち、 「プランク質量MP[kg](≒2×10-8[kg]の質量)を持つ1つの仮想質点」が持つ質量エネルギーMPc2[J](重力子の放出源として働き続ける能力)が、ちょうど、重力子エネルギーEG[J](=MPc2[J])を2π倍したものに相当する。
|
階層性問題は── 「数字や、抽象的な数式」を重視するだけではなく、それらの意味、すなわち、「幾何学的な実体像」の探求をも重視することによって解決できるのである。
|