研究論文
『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
2. 素粒子物理学の標準模型、素粒子の内部構造、電荷&色荷の起原について
素粒子物理学の標準模型は、現代物理学の偉大な成果の1つである。
このぺージでは、主に、(素粒子物理学の標準模型を担う)「電子、クォーク、ニュートリノ、グルーオン、ウィークボソン…」といった素粒子そのものが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で、どのように説明できるかを示す。 (光子や重力子については、結果1で、すでに示した)
それは、自然な世界観(3Steps原理)に基づいて“幾何学的な実体像”(視覚的描像、具体的なイメージ、true picture at Planck scale…)を探究しながら、様々な素粒子の構造や機能を説明していこうとすることであり── それは、素粒子物理学の標準模型に登場する素粒子の“内部構造”を説明していこうとすることに他ならない。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、これまでの素粒子物理学の標準模型の成果を「より深いレベルの階層」から説明しようとするものであり── その自然(nature)と調和している部分を包含するものなのである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、いわば、“究極の量子論”である。
その説明は、必然的に、「電荷や磁極の実体とは何か?(引力と斥力はどのようにして生ずるか? 電子のスピンとは何か?) 色荷の実体とは何か?」と「ゲージ原理とは何か? 局所的な位相回転や弱アイソスピンとは何か?」といった基礎的なテーマにおよぶ。
このページでは、次のようなテーマに沿って説明していく。
《プレオンモデルの予測について》
クォークの電荷が持つ“+2/3、−1/3”という中途半端な数値には、明らかに奇妙さ&違和感がある。
したがって、クォークを、さらにズームインすることで見えてくる、何らかの内部構造があると考えることは、きわめて自然&当然である。
素粒子の内部構造を探究する試みは、過去にもなされており、その成果の1つが、“プレオンモデルの予測”である。
プレオンモデルについて、文献によって、次のことが分かった。
◎プレオンモデルは、「電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)は、それぞれ3つのプレオンから、ウィークボソンは6つのプレオンから、光子は2つのプレオンからできている」と予測している。
◎プレオン理論は、弦理論と共存できる。
◎「質量は閉じ込めのサイズに反比例する」ので、「プレオンから成るクォークは、クォークから成る陽子よりもずっと 大きな質量を持つ」ことになってしまうという問題があり、その解決が望まれている。
(参考 『クォークの中の素粒子 日経サイエン2013年1月号』(D.リンカーン著 日経サイエンス社))
|
さらに他の文献によると、プレオンモデルについて、次のことがわかった。
◎プレオンモデルは、「グルーオンは6つのプレオンからできていること、重力子(グラビトン)は4つのプレオンからできていること」を予測している。
(参考 『A COMPOSITE MODEL OF LEPTONS AND QUARKS. 』Michael A.Shupe in Physics Letters B,Vol.86,No.1,pages87-92;September 10,1979
『A SCHEMTIC MODEL OF QUARKS AND LEPTONS. 』Haim Harari in Physics Letters B,Vol.86,No.1,pages83-86;September 10,1979
『A structual model of quarks and leptons. 』 Clemens HEUSON)
|
プレオンモデルの予測をまとめると次のようになる。
|
光子
|
重力子
|
電子、電子ニュートリノ
アップクォーク、ダウンクォーク
(およびこれらの反粒子)
|
グルーオン
|
ウィークボソン
|
|
プレオンの数
|
2
|
4
|
3
|
6
|
6
|
※これによって、クォークの電荷が持つ“+2/3、−1/3”という中途半端な数値について、矛盾なく説明できるようになる。
このプレオンモデルの予測は── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)を育むための貴重なヒント&よりどころの1つとなった。
《プレオンモデルの予測と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、光子は、素スピノール2つから構成され、重力子は、素スピノール4つから構成されると考えられることは、すでに述べた。
一方、プレオンモデルでは、光子がプレオン2つ、重力子がプレオン4つから構成されることを予測している。
(なお、以下では、プレオンモデル相当の簡略表記として、当面、“プレオン”を○で示す)
よって、次の仮説を立てた。
仮説2.1 「光子や重力子を構成すると予測されているプレオン」の実体は、素スピノールそのものである。
|
重力子(グラビトン)
|
光子
|
|
プレオンモデル相当の
簡略表記
|
○○○○
プレオン4つ
|
○○
プレオン2つ
|
|
素スピノールのネットワーク
(“素スピノールモデル”の表記)
|
|
|
|
簡略表記
|
: :
|
・・
|
|
スピン
|
2
|
1
|
※ここでの軸が示す向き(ブルーの矢印が示す向き)は、“軌道運動の向き”を意味しており── いわるる、「右ねじが進む方向」(“スピンの向き”──上向き、下向き)という意味ではない。
→この「プルーの矢印と、ピンクの矢印の組み合わせ」により、素スピノールが“右巻きか、左巻きか”を区別できる。
|
この仮説により、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、光子や重力子についてのプレオンモデルの予測と調和することになる。
※光子はスピン1、重力子はスピン2である。 このようにスピンが整数であるものが“ボソン”である。
一方、スピンが半整数のものは、“フェルミオン”である。
スピンは、やはり、単純に足し算、引き算できるので── 例えば、素スピノール(スピン1/2)が偶数個集まるとボソン(スピンが整数)になる一方、素スピノール(スピン1/2)が奇数個集まると、フェルミオン(スピンが半整数)となる。
次に、スピンが半整数であるフェルミオンについて説明していく。
例えば、電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)は、いずれも、スピン1/2であるので、フェルミオンである。
プレオンモデルによる予測では、電子やニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)は、プレオン3つから構成されているとのことであった。
|
電子、電子ニュートリノ
アップクォーク、ダウンクォーク
(およびこれらの反粒子)
|
|
プレオンモデル相当の
簡略表記
|
○○○
プレオン3つ
|
電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)が、いずれも、スピン1/2であるので── 1つ1つのプレオン○も、スピン1/2でなければならない。
(1つ1つのプレオンがスピン1等のボソンなら、電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)も、ボソンにならざるをえない)
果たして、光子や重力子と同様に、1つの素スピノールが、プレオン○に相当するのだろうか?
そこで、電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)を構成するプレオン○は、単独で、“1/3の電荷”を持ったり持たなかったりすることを思い出そう。
もし、個々の素スピノールが“1/3の電荷”を持っているならば、中性の電子ニュートリノは、偶数個の素スピノールで構成されていなければならないことになる。(なぜなら、素スピノールは、右巻きか左巻きかの二種類しか存在しないので、例えば、右巻き素スピノールがプラスの電荷、左巻き素スピノールかマイナスの電荷というように決めるしかないからである)
しかし、この「偶数個の素スピノールで構成されている中性の電子ニュートリノ」はボソンに他ならず、電子ニュートリノがフェルミオンであることと矛盾してまう。
したがって、素スピノールがたった1つで、プレオン○を構成しているとは考えにくい。
以上のことを考え合わせて、電子や電子ニュートリノやアップクォークやダウンクォークを構成するプレオン○について、次のものを仮説として提示する。
仮説2.2.1 電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)を構成するプレオン○の実体は── 「スピン1/2の素スピノール3つ」が下図のように組み合わさることで、新しく生まれる“スピン1/2のスピノール”である。
|
プレオン∴
|
|
プレオンモデル相当の
簡略表記
|
○
“電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク
(およびこれらの反粒子)を構成するプレオン”1つ
|
|
素スピノールのネットワーク
(“素スピノールモデル”の表記)
|
|
|
簡略表記
|
∴
|
|
スピン
|
1/2
|
※ここでの軸が示す向きは、“軌道運動の向き”を意味しており、「右ねじが進む方向」(“スピンの向き”──上向き、下向き)という意味ではない。
→この「プルーの矢印と、ピンクの矢印の組み合わせ」により、素スピノールが“右巻きか、左巻きか”を区別できる。
|
このフェルミオンのプレオン○を、(光子や重力子といった)ボソンを構成するプレオン○(すなわち、素スピノール)とはっきり区別するために、「プレオン∴」と表記することとする。
素スピノールが3つ集まることで、±1/3の電荷を持つプレオン∴や中性のプレオン∴を創発し── このプレオン∴が、さらに3つ集まることによって、スピン1/2の電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)を創発すると考えると、プレオンモデルの予測とも、うまく調和している。
※重力子や光子のみならず── プレオン∴も、1つの点ではなく、“広がり”を持って存在していることになる。
※クォークやレプトンの世界を、さらに、ズームインする方向で生まれたものが、クォークやレプトンについての“プレオンモデル”の世界だとすると──
この“プレオンモデル”の世界をさらに、ズームインする方向で生まれたものが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の世界だということができる。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、より「深いレベルの階層」から、“プレオンモデル”の世界をも包含するものであると言える。
※以上で説明している「電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)」とは、第1世代の素粒子に他ならない。
第2世代、第3世代の素粒子については、結果3で説明する。
プレオン∴の大きさについては、次の仮説を立てた。
仮説2.2.2 プレオン∴の大きさは、2プランク長(2LP[m])程度である。
原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”のサイズに近いことになる。
(このサイズは、「面積にも最小単位があり(1平方プランク長=10-66cm2)」という飛び飛びの値しか取らないというループ量子重力理論と調和している。 →考察4)
※プレオン∴は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”から、1つの素スピノールを取り除いたものに相当すると思われる。(詳細な検討は、今後の課題である)
以後、煩雑さを避けるため、プレオン∴の幾何的な実体像について、
※右側は、プレオン∴の幾何的な実体像を簡略化して図示しているものである。
の右側のように簡略化して図示することも可能であることとする。
この簡略表記を利用した上で、「電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)」のみならず、グルーオンやウィークボソンの幾何学的な実体像について、仮説として、次のように提示する。
仮説2.3.1 スピン1のグルーオンは、プレオン∴の2つから創発し、下図のようになっている。
仮説2.3.2 スピン1/2の電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォーク(およびこれらの反粒子)は、プレオン∴の3つから創発し、下図のようになっている。
仮説2.3.3 スピン1のウィークボソンは、(それぞれプレオン∴3つからなる)“電子と反電子ニュートリノ”から創発し、下図のようになっている。
|
グルーオン
|
電子や電子ニュートリノ
アップクォークやダウンクォーク
(およびこれらの反粒子)
|
ウィークボソン
|
|
プレオンモデル相当
の簡略表記
|
○○○○○○
プレオン6つ
(=プレオン∴2つ)
|
○○○
プレオン∴3つ
|
○○○○○○
プレオン∴6つ
|
|
素スピノールのネットワーク
(EMOES表記)
|
|
|
|
|
簡略表記
|
∴ ∴
|
∴
∴ ∴
|
∴ ∴
∴ ∴ ∴ ∴
|
|
スピン
|
1
|
1/2
|
1
|
※この仮説は、付録3スピンネットワークのフラクタルとも調和する。
※ウィークボソンを結びつけるものは、“LP光子の集積したひも”であると考えられる。(→下記説明)
※“LP光子の集積したひも”は、プレオン∴を閉じ込めるので、『「質量は閉じ込めのサイズに反比例する」ので「プレオンから成るクォークは、クォークから成る陽子よりもずっと大きな質量を持つ」ことになってしまう』という問題も生じなくなる。(→下記 《プレオン∴の閉じ込め》)
※グールオンにおけるプレオン○は、素スピノール1つに相当し、クォーク&レプトン、ウィークボソンにおけるプレオン○は、プレオン∴に相当している、というようにプレオン○の意味は異なっていることになる。
以下で、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示す、各素粒子の内部構造──幾何学的な実体像に基づき、様々なテーマについて説明していく。
《電荷の起源について》
電荷とは、「仮想光子の放出源として働き続ける能力」なのであった。 (→結果1)
一方、仮説2.3.2によれば、もし、プレオン∴が電荷、すなわち、「仮想光子の放出源として働き続ける能力」を一切持たなければ、電子や電子ニュートリノ、アップクォークやダウンクォークは、互いに性質の区別がつかないものになってしまう。
さらに、プレオン∴が持つ電荷が正負の区別を持っていなければ、粒子と反粒子の区別もつかなくなってしまう。
したがって、電荷の起源──“「仮想光子の放出源として働き続ける能力」がどのように創発するのか?”“正負の電荷の区別は、どのようにして創発しているか?”についての説明は、とても重要である。
まず、正負の電荷の区別は、どのように創発するのかを考えてみよう。
例えば、ダウンクォークも電子も、3つのプレオン∴からできていて、ダウンクォークは、そのうちの1つだけが「−1/3のマイナス電荷を持つプレオン∴」であり、電子は、3つともが「−1/3のマイナス電荷を持つプレオン∴」であるのだった。
したがって、1つの“プレオン∴”(3つの素スピノールの組み合わせ)の中に、スピン1/2、電荷±1/3[C]の電荷が、何らかの形で創発できると考えられる。
よって、1つのプレオン∴の中で、どのように正負が決まってくるのかに関して、次の仮説を立てた。
仮説2.4 プレオン∴を構成する3つの素スピノールが、“すべてが右巻き”ものが正の電荷を持つプレオン∴であり、“すべてが左巻き”のものが負の電荷を持つプレオン∴である。
この仮説によると、負の電荷を持つプレオン∴3つからなる電子は、すべて左巻きの素スピノールから構成されていることになり、電子は、実質上は、すべて左巻きのものであることを意味する。
このことは、“右巻きの電子”が観測されることと矛盾しない。 なぜなら、“右巻きの電子”は、マクロレベルで(見かけ上、光速を失う結果)観測される“一部の少数派”にすぎないからである。 もし超ミクロのレベルで観測が可能であれば、電子(すなわち、負の電荷を持つプレオン∴×3)を構成する各素スピノールはすべて(少なくとも光速で運動し続けており)左巻きであるので、厳密には、「すべての電子は、実は左巻きである」という結果に至るはずである。
そのことは、“弱い力を受ける電子は、すべて左巻き”であるという事実と調和しているのみなず、 結果5の3での仮説、「仮説5.1 すべての電子と陽子は、弱い力によるベーター崩壊によって、中性子から同時に生じた」とも調和している。
「負の電荷を持つ、“左巻き素スピノール3つ”からなるプレオン∴」を、マイナスプレオンと呼び、「正の電荷を持つ、“右巻き素スピノール3つ”からなるプレオン∴」をプラスプレオンと呼ぶこととする。
(※正負の電荷を持つプレオンは、必然的にフェルミオンのプレオンなので、∴を省くこととした。)
|
|
プラスプレオン
|
マイナスプレオン
|
| 構成 |
“右巻き素スピノール3つ” |
“左巻き素スピノール3つ” |
| 電荷 |
正
+1/3
|
負
−1/3
|
以上により、電荷の正負の区別がどのように創発するかを説明できたことになる。
次に、「仮想光子の放出源として働き続ける能力」がどのように創発するのかを説明する。
例えば、(“左巻き素スピノール3つ”からなる)マイナスプレオンの構造は、次のように図示できる。
※マイナスプレオンを構成する素スピノールは、3つとも左巻きになっている。
※例えば、上図のように赤色の素スピノールが転回している間は、他のブルーの素スピノールのペアの総スピンは0のままであるので── 転回している赤色の素スピノールが、このマイナスプレオン全体のスピンを代表している形になる。 つまり、このマイナスプレオンのスピンは、常に1/2に保たれていることになる。
※このマイナスプレオン(スピン1/2)が3つ組み合わさることによって、電荷−1で、スピン1/2の電子が創発することになる。
|
さて、このような構造を持つマイナスプレオンは、どのようなしくみで、仮想光子を創発するであろうか?
電荷とは、「仮想光子の放出源として働き続ける能力」であり、その「仮想光子の放出源として働き続ける能力」とは、「共転回を生み出す能力」であった。
つまり、マイナスプレオンの中の素スピノールは、少なくとも、何らかの“自ら転回を駆動する能力(原因)”を持っているはずである。
その原因は、何か?
それは、“パウリの排他律”に他ならないと考えられる。
なぜなら、パウリの排他律によると、“スピン1/2のフェルミオンは、同一の物理状態で(同じ方向を向いて)近くに存在し続けることができない”からである。
例えば、下図のマイナスプレオンにおいて、緑の楕円で囲ったペアは、“パウリの排他律”によって、必ず、どちらかが転回しなければならなくなる。
※緑の楕円で囲った、素スピノールのペアは、もし、どちらか一方が転回しなければ、全く同一の物理状態となるので、“パウリの排他律”に反してしまう。
※クォークや&レプトンは、スピン1/2のフェルミオンであるからこそ、“パウリの排他律”にしたがう。
同様に、プレオン∴や、素スピノールも、スピン1/2のフェルミオンであるからこそ、“パウリの排他律”にしたがう。
|
さらに、その転回の後に、下図のような状態になれば── 今度は、緑の中のどちらか一方の素スピノールが、“パウリの排他律”によって、転回しなければならなくなる。
※緑の楕円で囲った、素スピノールのペアは、全く同一の物理状態となっているので、“パウリの排他律”に反している。
つまり、例えば、マイナスプレオン(スピン1/2)は、それを構成する素スピノールが3つとも左巻きであるがために、“パウリの排他律”に駆動(ドライブ)されて、常に、3つの中の1つの素スピノールを自ら転回し続けなければならないのである。
まさに、この「常に、3つの中の1つの素スピノールを自ら転回し続けなければならない」という性質は、電荷の性質にぴったりである。 なぜなら、この性質が、仮想光子の放出源とし働き続ける能力を支えていると考えると、つじつまが合うからである。
※このことは、電荷を持つプレオン∴の中に、右巻きと左巻きの素スピノールが混在していない理由も説明している。
なぜなら、もし混在していたら、下図のように、“パウリの排他律”を満たしているがために、「常に、3つの中の1つの素スピノールを自ら転回し続けなければならない」という性質(原因)が消失するからである。
※左巻きと右巻きの素スピノールが混在しこのように配置している場合、「“パウリの排他律”によって駆動されて自ら転回しなければならない」という必要性がなくなる。 すなわち、これは電荷を持たないものに相当している。
※これが、まさに、“二ュートリノ”等を構成する中性プレオンであると考えられる。
(→詳細は後ほど説明する。 《中性プレオンの起源》)
|
電荷は、仮想光子を放出するだけでなく、それを再吸収しうるのであった。
電子の構成要素である、マイナスプレオンを例にすると、この仮想光子の振る舞いを、次のように整理できる。
※仮想光子が、往復している。
同時に、マイナスプレオンの中の素スピノールの転回と、変形した“4面体”の中の素スピノールの転回が、それぞれ往復している。
※なお、仮想光子が放出されるときのみならず、再吸収される時も、パウリの排他律による、駆動(ドライブ)が存在することがわかる。
|
“パウリの排他律”に駆動(ドライブ)されて生じる共転回の総和── これが、「放出され&再吸収される仮想光子の総和」となり、「原始ヒッグス場ユニットの変形している“4面体”の総和」となり、マクロの静電場となる。
つまり、電荷、すなわち、「仮想光子の放出源として働き続ける能力」は、まさに、「“パウリの排他律”に駆動(ドライブ)されて生じる共転回」によって創発するのである。
そして、「“パウリの排他律”に駆動(ドライブ)されて生じる共転回」は、“たとえ仮想光子が再吸収されなかったとしても”、電荷を持つプレオン∴が存続する限り、ずっと存在し続けると考えられる。
つまり、このモデルは、「電荷(=「仮想光子の放出源として働き続ける能力」)が保存される」という、電荷の性質とも調和している。
※電荷は、加速運動や周期的な振動による“仮想光子の剥ぎ取り”を介して、光子(orその総和である電磁波)を放出しうると同時に、それらの放出された光子(orその総和である電磁波)はエネルギー非保存の所産であると考えられるのだった。(→結果1)
ここまで、負の電荷を持つマイナスプレオンを例にして説明して来たが、以上の説明は、当然、正の電荷を持つプラスプレオンにおいても、同様に成立する。
そして、マイナスプレオンもプラスプレオンも、ともに3つの素スピノールからできているので、そのふるまいは、“決定論的カオス”の状態にあると考えられる。
(なぜなら、それぞれの素スピノールが決定論的にふるまっているとしても、『わずか、三個の自由度を持つ力学系においてすでにカオスが可能』(p.735 『imidas92』 集英社)だからである。 それは、三体の惑星運動がカオスになることとも関連している)
したがって、その、カオス運動にともなって、仮想光子も、3D空間の“あらゆる方向、あらゆる距離に”“あらゆる対タイミングで”放出されるので、「長時間平均をとると、ほぼ均等になる(=エルゴード的になる)」と考えられる。
その結果、「原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primal Higgs(field)Unit)の変形している“4面体”」の分布も均等となり── ガウスの法則や、クーロンの法則を満たすような“静電場”が、その時間&空間平均として、創発されると考えられる。
※結果1で示したように、電荷の間に働くクーロンの法則の“EMOES表記”は、下のようになるのだった。
|
電荷の間に働くクーロンの法則
|
|
元の数式
|
F=kQq/r2=Qq/4πεr2
|
|
“EMOES表記”
|
F=NQ(hc/4LP)×(1/4πn2)×(1/2LP)×Nq
=(aQc2/4πn2)×(1/2LP)×(1/QE)×q
|
※この“EMOES表記”の式は、クーロン力が、電荷Qから放出される仮想光子が作る電場
(=“原始ヒッグス場ユニットの変形している“4面体”の総和”)によって生じていることを、はっきり示しているのだった。
まさに、この「電荷Qから放出される仮想光子が作る電場(=“原始ヒッグス場ユニットの変形している“4面体”の総和”)」が、「パウリの排他律に駆動(ドライブ)された共転回」や「3つの素スピノールが作る決定論的カオス」に支えられて、長時間平均として創発していることになる。
|
※決定論的カオスによって様々方向に仮想光子が生じる際、その「共転回する素スピノールのペアの距離(=電荷を構成している素スピノールと、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形している“4面体”を構成してる素スピノールの間の距離(r=λ/2[m])」と「その変形している“4面体”が蓄えるエネルギー振幅E[J]」は反比例関係にあり、確定している。
(ET=h、cT=λ(=2r)より、Er=hc/2)
※当量電荷QEは、電子の電荷の5.8倍(5.8個分)であるので、マイナスプレオンのおよそ5.8×3=17.4倍(17.4個分)であることになる。
※光子(電磁波)と仮想光子は、やはり、紙一重であると同時に、違いもあることになる。
|
光子(電磁波)
|
仮想光子
|
|
原因
|
“パウリの排他律” &“決定論的なカオス”
+電荷の加速(=運動エネルギー順位Knの増加)
(or正負の電荷の周期的な振動)
|
“パウリの排他律”&“決定論的なカオス”
|
|
発生するしくみ
|
電荷の加速(=運動エネルギー順位Knの増加)
(or正負の電荷の周期的な振動)に伴う
“仮想光子のはぎとり”
(=仮想光子の再吸収され損ない)
によって生じる
|
静止(等速運動)している電荷から生じる
※決定論カオスに基づいて、
様々な方向に仮想光子の放出&再吸収
を繰り返している
|
|
過程の性質
|
一旦生じた原始ヒッグス場ユニットの
“4面体”の変形が、
そのまま規則的に伝播し続ける過程
|
新たな原始ヒッグス場ユニットの
“4面体”の変形の生成&再吸収を
カオス的に繰り返す過程
|
|
エネルギー
|
電荷を加速させる
(=運動エネルギー順位Knを増加させる)
(or正負の電荷を周期的に振動させる)ために
エネルギーが必要。
加速(or周期的な振動)がなれば、
電磁波(光子の集合)を放出しなくなる
※なお、電磁波(光子の集合)そのものは、
エネルギー非保存の所産である。
|
追加のエネルギーは不要。
(電荷のエネルギーは、aQc2[J])
この電荷エネルギーにより、仮想光子
の放出&再吸収を繰り返すことになる。
※なお、電磁場(仮想光子の集合)そのものは、
エネルギー非保存の所産である。
|
| 右巻きor左巻き |
いったん放出された電磁波(光子の集合)は、
右巻きと左巻き両方の素スピノールを利用
|
マイナス電荷は、左巻きのみで構成されているので、共転回の相手は右巻きのみ
プラス電荷は、右巻きのみで構成されているので、共転回の相手は左巻きのみ
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、特殊&一般相対性理論(光速不変、E=mc2、重力場、時空の曲り、アインシュタイン方程式…)やニュートン力学(重力の法則、運動の法則…)、光子、電磁波、電磁場、 電磁気力(の一部)を説明できるのみならず(→結果1)── アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則、電磁気力において引力&斥力が生じるしくみも説明できる。
以下の項目では、アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則、電磁気力において引力&斥力が生じるしくみについて、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明する。
《アンペール−マクスウェルの法則》(“4つのマクスウェル方程式”の中の1つ)──電流が流れると、その回りに磁場ができる(右ねじの方向)
「マクロの磁場」や「マクロの電場」を創発するものは、電磁波を構成する“光子”ではなく、“仮想光子”である。
念のため、仮想光子と光子の比較したものを、下に示す。
|
仮想光子
|
光子
|
|
創発するもの
|
マクロの電場やマクロの磁場
|
電磁波
|
|
進み方
|
電荷から放出されλ/2だけ進み、
λ/2引き返して、電荷に戻る。
|
λの1/2ずつ、
次から次へと遠方へ進み続ける
|
|
速度
|
光速
|
光速
|
|
しくみ
|
電荷の中の素スピノールと
原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))
中の素スピノールのペアにおける
“スピン1”を保った共転回
|
2つの原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))
中の素スピノールのペアにおける
“スピン1”を保った共転回
|
電荷から放出され、電荷に再吸収される“仮想光子”についての仮説を再度示す。
仮説1.7 振動数ν、波長λ(=c/ν)の仮想光子は、電荷の中の素スピノールと、電荷からλ/2の距離だけ離れた「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”」の中の素スピノールのペアが、スピン1を保ちながら、180度共転回することによって進み、もう一度、共転回することによって元に戻るものに相当する。
※仮想光子の場合、ふつうの電磁波の光子と違い、“放出源に戻る”という性質を持つことが図示されている。
※上図のように、電場や磁場のどちらか一方が、前半と後半で逆転することにより、仮想光子の進行方向についても『右ネジの法則』が保たれる。
※上図の左側の「180度の転回&180度の逆転回」によって生じる仮想光子の方が“マクロの電場”の創発で活躍するものであり、右側の「180度の転回×2」によって生じる仮想光子の方が、“マクロの磁場”の創発で活躍するものである。
|
仮説1.7によれば、電子を構成する左巻き素スピノールと、(周囲の、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の中の)“右巻き素スピノール”は、ペアを作って共転回することで、仮想光子を生じる。(電子が左巻き素スピノールのみで構成されていることについての詳細は、すでに述べた。 すなわち、厳密には、「電子は、“左巻き素スピノールから構成されるプレオン∴3つ”から構成される」と考えられるのだった)
この“仮想光子”についての仮説に、“電荷が運動すると仮想光子がどうなるか”の考慮を加えることで、アンペールの法則を説明できる。
仮説1.7.2 電荷が“相対的に優位になる運動の方向”を持たない場合は、仮想光子の共転回が生じる向きに片寄りはないが── 電荷が“相対的に優位になる運動の方向”を持つ場合は、その方向と一致する方向への共転回が、他のどの向きよりも、相対的に優位になる。
それは、次のような意味である。
もし、電荷の決まった方向への運動がなければ、次のように、どの方向への共転回も、等しい頻度で起こりうる
※決まった運動がない場合は、どちらの方向への共転回も等しい頻度で起こりうる。
それによって、ミクロ磁場は、どの方向についても等しい頻度で生じることになる。
なぜなら、電荷によって生じる転回の方向は、本来は、(決定論的なカオスによって)、ランダムである(どの方向も等しい確率で生じる)からである。
その結果、ミクロの磁場は、各方向が互いに打ち消し合うので、マクロの磁場は創発せず── マクロの電場のみが創発することになる。 それが、静電場である。
|
しかし、電荷が、電流などのにように“相対的に優位になる運動の方向”があると状況は一変する。
※図のような、“相対的に優位になる運動の方向”がある場合── 「仮説1.7.2」により、他のどの向きよりも、一番左のような方向への共転回が起こる頻度が、相対的に最も優位になる。
これにともなって、一番左のような“ミクロ磁場”が生じる頻度が最も優位になる。
|
“相対的に優位になる運動の方向”の例は、“電流に伴う運動の方向”に他ならない。
※「電流に伴う運動の方向」は、「素スピノールがミクロレベルで持っていると考えられる、決定論的カオスに従う不規則な運動の方向」と区別される。
※「電流に伴う運動の方向」は、「電流に伴う電子の運動の方向」のことであり、当然、電流の向きとは180度逆向きである。
※例えば、電圧をかけられた電子は、実際は、一直線に電圧に従って進むのではなく、前後を含めジグザグ運動(決定論的カオスに従う不規則な運動)をしながらも、結果的にトータールで見て、“電流に伴う運動の方向”が相対的に優位になる── ということになる。
ある電荷が“相対的に優位になる運動の方向”を持つと、仮説1.7.2により、相対的に、特定のミクロの磁場が優位になる。 その結果、あるマクロの磁場が創発する。
こういった例は、下の図のように示される。
|
|
※導線の中の左巻き素スピノールが電荷の中の素スピノールであり、電線の周囲の右巻き素スピノールが、原始ヒッグス場ユニットの中の素スピノールである。
※電流が下から上へ流れると、電子(左巻き素スピノールで構成される)の運動は、当然、上から下に移動する方向が優位になる。
その結果、仮説1.7.2 により、相対的に、上図のような方向の共転回が優位になる。
その際、無限上方〜無限下方に存在する、「上から下に運動している電子の中の左巻き素スピノール」とペアを作るような、電線の周囲の縁の上の、(原始ヒッグス場の基本構造の中の)右巻き素スピノールが、上図の向きが優位な形で、共転回することになり── 上図のように、アンペールの法則にピッタリ合致した右回りのミクロの磁場が優位になる。 その結果、それらの総和として、アンペールの法則を満たすマクロの磁場が創発することになる。
※共転回する相手の素スピノールの位置に応じて、「立方体の変形」の程度も向きも様々に変化するが、磁場が生じる向きだけは、アンペールの法則に従っている。
なお、電場は、プラスマイナス0になるので両方に矢印を示してある。
|
この考え方によって、マクスウェルが、アンペールの法則を拡張するべく作った式(I=εSdE/dt)が生まれるきっかけとなった、ある現象(後に“変位電流”と名付けられた)をも説明できる。
その現象とは、「コンデンサーに電荷が蓄えられる過程で、電線のないコンデンサーの周囲にも磁場が作られる現象」である。
(参考 『高校数学でわかる マクスウェル方程式』講談社ブルーバックス 竹内淳)
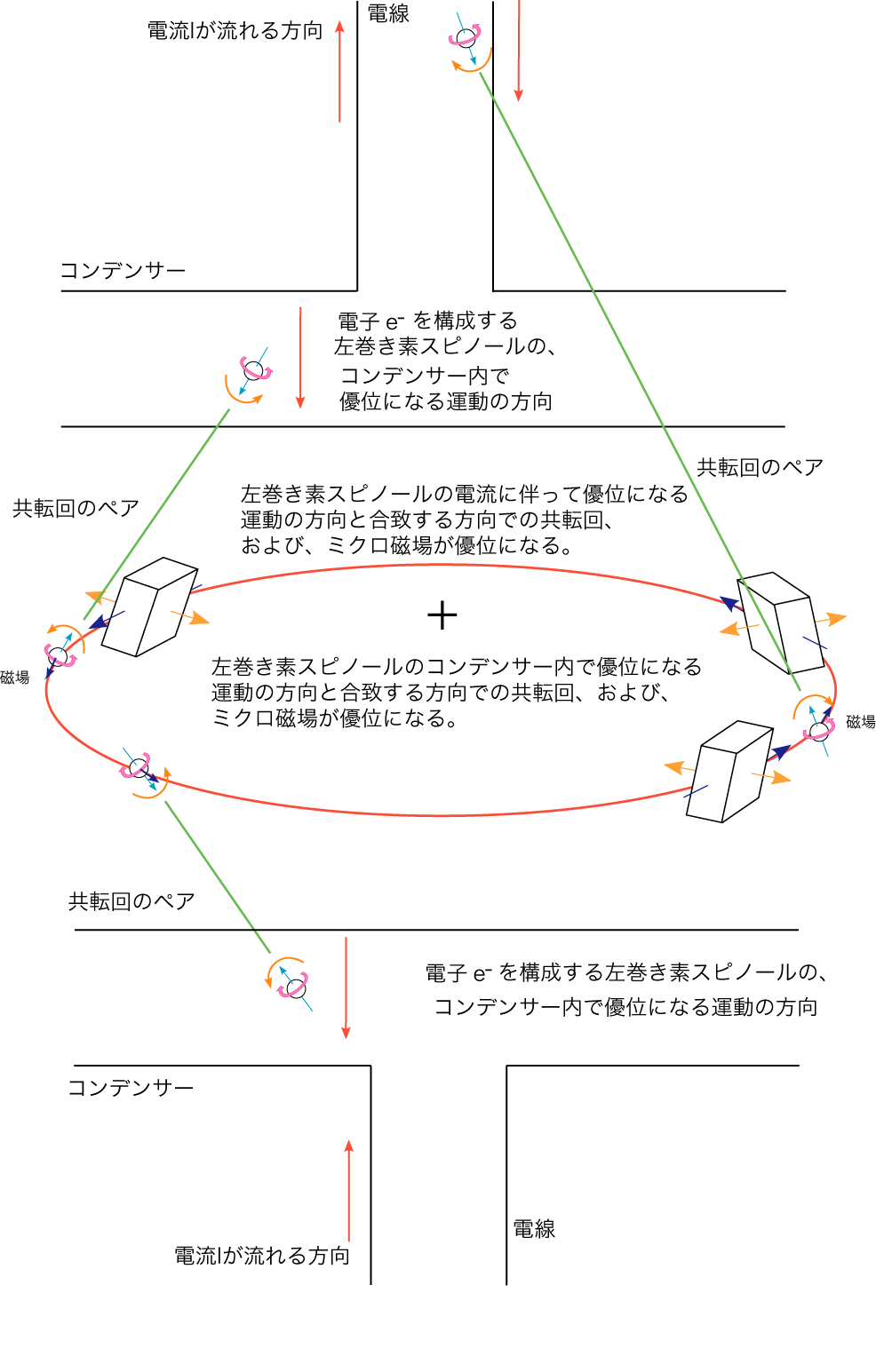 |
|
※電線内で、電子が、相対的に優位になる運動の方向が存在するように、コンデンサー内でも、電子が、相対的に優位になる運動の方向が生じる。
導線内の左巻き素スピノールのみならず、コンデンサー内の左巻き素スピノールによっても、コンデンサー周囲の原始ヒッグス場ユニットの右巻き素スピノールとの共転回、および、ミクロ磁場が、上図の向きが優位な形で生じる。
その結果、それらの総和として、アンペールの法則を満たすマクロの磁場が創発することになる。
※充電中のコンデンサーの周囲に磁場が生じる現象は、わざわざ「変位電流によって磁場が生じる現象」という特別な説明するまでもなく── 「電線およびコンデンサーの中を運動する電子(左巻き素スピノール)によって、磁場が生じる現象」と、統合的に説明できることになる。
|
以上のことは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、ふつうの電流によって生じる磁場と、変位電流によって生じると考えられた磁場が、統合できることを意味する。
つまりは、以上で、4つのマクスウェル方程式の1つ、「アンペール−マクスウェルの法則」を統合的に説明できたことになる。
※マクスウェルは、“電荷の移動”の結果生じた「コンデンサーの間の電場の変化」が、コンデンサーの周囲の磁場を生むという考えを数式計算(ガウスの定理も使用)から求めた。
それに対して、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、“電荷の移動”そのものが、直接コンデンサーの周囲における(相対的に優位な)磁場を生むとシンプルに考える。
※“電荷の運動”(原因)と、“新たに生じる磁場”(結果)を結びつける、共転回する素スピノールのペアは、次々と作られる“仮想光子”に相当し、波長/転回周期(=λ/T)は、光速cに他ならない(λ/T=c)。
このことは、マクスウェルが、数式計算によって、光速を導く過程(電磁波を予想させる波動方程式を導く過程)で、この「アンペール−マクスウェルの法則」も活用したことと調和していると思われる。
※もし、180度の“転回”したのち、180度の“逆転回”したとすると(下図の左側)── すぐにミクロ磁場のN極とS極が逆転してしまうので、マクロの磁場が創発しないことになってしまう。(それは、静電場が創発している状況である)
しかし、180度の“転回”したのち、180度さらに同じ向きに転回をしつつ仮想光子が逆向きに進むとすると(下図の右側)── ミクロの磁場が逆転しないので、マクロの磁場が創発することになる。 それは、マイナス電荷が持つ、相対的に優位になる運動のおかげで、達成されることであると考えられる。
※“マクロの磁場”を創発するのは、右側のタイプの仮想光子である。
アンペール-マクスウェルの法則に従うようなマクロの磁場も、右側のタイプの仮想光子から創発すると考えられる。
※このように、右側の「180度の転回×2」によって生じる仮想光子の方が、“マクロの磁場”の創発で活躍するものであるとすると── 上図の左側の「180度の転回&180度の逆転回」によって生じる仮想光子の方が“マクロの電場”の創発で活躍するものである。
|
※以上の説明は── 電荷とは、やはり、「仮想光子の放出源として働き続ける能力を持つものである」ことと調和している。
※この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、アンペール-マクスウェルの法則を説明するために、“変位電流”を考えることが不要になる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、アンペール-マクスウェルの法則において実在するのは、“変位電流”ではなく── 「電荷が相対的に優位になる運動の方向を持つこと」と、「そのおかけで相対的に優位になって生じる共転回および、ミクロ磁場の総和として創発した、マクロレベルの磁場」であるということになる。
マクスウェルは、電磁波を説明できることを“変位電流”の根拠の1つとした。
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、電磁波についても、変位電流を考えずに説明できるのだった。
したがって、以上のことは── “変位電流”は、実在しないことを示していると思われる。 (詳細な検討は、今後の課題である)
《ファラデーの法則》(“4つのマクスウェル方程式”の中の1つ)(「磁束の変化を打ち消す方向に、誘導起電力が生じる」)
ファラデーの法則が意味する、「磁束の変化を打ち消す方向に、誘導起電力が生じる」現象には、大きく2つのパターンが考えられる。
1つめのパターンは、下図のように、例えば、導線は静止していて、“ある円形の導線”の中を通る磁束が増えると── その変化を打ち消すような向きに、電場(電位勾配)が生じるというものである。
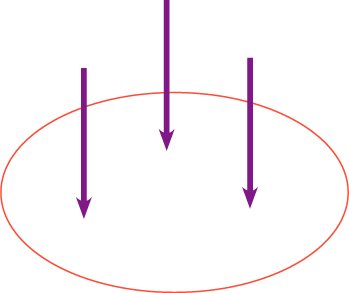 |
→ |
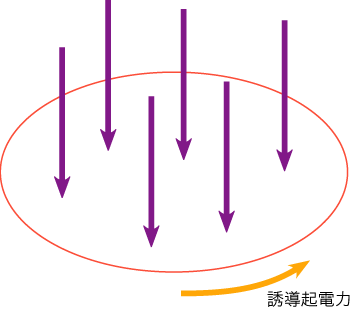 |
& |
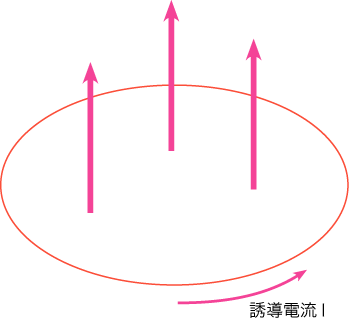 |
| “ある円形の電線”の中を一定の磁束が通っている。 |
|
磁束が変化すると── 電線にそって、電場(電位勾配)=誘導起電力が生じる。 |
|
その誘導起電力=電場(電位勾配)によって、生じた誘導電流が、新たに生み出す磁束は、最初の「磁束の変化」を打ち消そうとする方向(最初の「磁束の変化」と逆向き)である。 |
2つめのパターンは、下図のように、ある一様な磁場があり、そこを導線が運動することによって、誘導起電力=電場(電位勾配)が生じるというものである。
※一様な磁場の中を、導線が運動していくことによって、導線に誘導起電力が生じる。
これは、「一定の磁場の中を電荷が運動することによってローレンツ力が生じる」ということでもある。 |
ファラデーの法則を意味する2つの現象は両方とも、数式上は、共通の式で示される(dφ/dt=誘導起電力 あるいは、マクスウェルの式 rotE=−∂B/∂t)。
これらの2つの現象の根底で(“素スピノール”の挙動レベルで)起きていることは何かを把握するために、ファラデーの法則を、やはり、この2つのパターンに分けて説明することとする。
1.(導線の回路は一定の中)磁場が増加することで、導線の回路に電場(誘導起電力)を生じる。
2.一定の磁場の中を、導線が運動すると、導線の中の電荷にローレンツ力(電場)が作用する。
1.(導線の回路は一定の中)磁場が増加することで、導線の回路に電場(誘導起電力)を生じる。
例えば、永久磁石が運動することによって、磁場が増加する様子は、次のように図示できる。
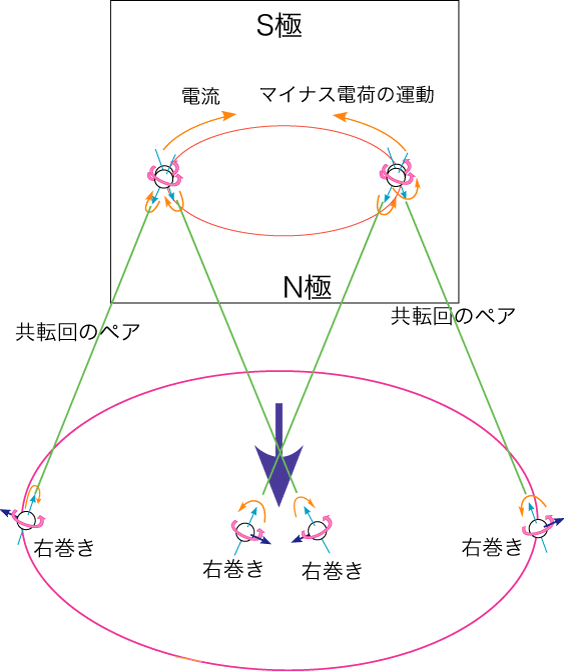 |
→
磁場の増加
|
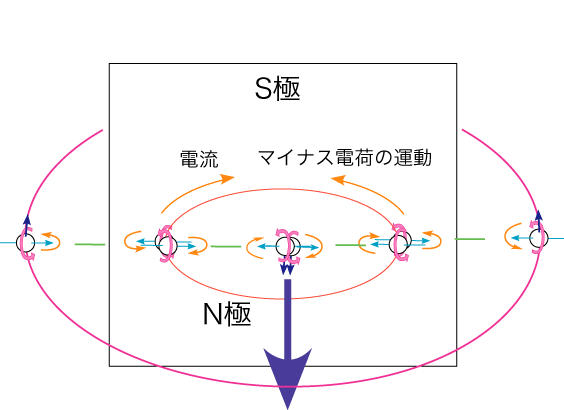 |
|
※永久磁石が、ピンク色の円の中へ向かって運動するとき、ピンク色の円内の磁場が増加する様子を示されている。
※中心部の磁場は、ベクトル和をとることで、はじめて、垂直な磁場となることになる。
それが、紫のベクトルで示されている。
※この場合、ピンク色の円の中心部の磁場は、2つの理由で、増加する。
1. ミクロ磁場の角度が、より垂直になる。
→ベクトル和がより大きくなる。
2.共転回のペアの間の距離rが短くなる。
→転回周期Tが短くなるので、個々のミクロ磁場が大きくなる。
|
※電磁石の場合は、「電磁石の電圧が上がる」ことによって、磁束が増加することになる。
この場合、磁場が増加する理由は、ミクロ磁場の数が増加することである。
図では、数個しか示されていないが、実際は、多数の(無数の)、このような共転回が存在する。
そして、共転回の数だけ、ミクロ電場&ミクロ磁場が創発する。
このミクロ磁場&ミクロ磁場が、ピンク色の円上にどのように創発するかをメインにして、図示すると次のようになる。
※「変形した立方体」を利用して、やや数を増やして図示している。
※複数のミクロ電場が、回路(ピンク色の円)に沿って、1つの方向にそろって創発しうることが読みとれる。 |
この回路(ピンク色の円)に沿って創発する、ミクロ電場の総和が、マクロの誘導起電力と関連していると考えるのは、自然なことであろう。
ただし、上の図は、「180度共転回し始めている間の電場の様子」を示しているにすぎない。
すなわち、仮想光子が放出源に戻る際には、下図のように“ミクロ電場がの向きが180度、逆転する”ことになるのだった。
※2回の共転回により、ミクロ磁場は同じ向きに生じているのに対し、ミクロ電場は逆転している。
このことは、磁場が一定となれば、ミクロ電場は、プラスマイナス0となることを意味する。 |
このことは、もし、磁場が一定になれば、それと同時に、上の仮想光子の振る舞いによって、ミクロ電場がプラスマイナス0となり、マクロの電場、すなわち、誘導起電力が全く生じないことを意味する。
このことは、逆に言えば、磁場が増加し続ける場合には、新たに共転回するペアが、次から次へと供給され続けるので、「(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)ミクロ電場」が相対的に優位になり── その結果、マクロの電場、すなわち、誘導起電力が創発することを意味する。
※磁場が増加し続けるときに限って、この「(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)ミクロ電場」が優位になる。
|
以上のことは、「誘導起電力が生じるのは、磁場が増加する間に限ってのことである」というファラデーの法則が、なぜ、どのようにして成立するのかを説明していることになる。
すなわち、磁場が増加している間に限って、フレッシュな共転回が多くなっているので、下図のような、「(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)ミクロ電場」が相対的に優位になり続けることができ、その結果、誘導起電力が存在し続けることができるのである。
※磁場が増加しているときに限って、図のように、“(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)ミクロ電場”が占める割合が、相対的に優位になり続けることになり── その結果、マクロの電場(誘導起電力)が創発する(存在し続けられる)。
※この創発したマクロの誘導起電力によって電流が流れたとすると、それによって、(アンペールの法則に従い)、新たに生じる磁場は、元々の磁場の増加を打ち消す方向であることがわかる。
※なお、上図は、(永久磁石の運動による誘導起電力よりも)電磁石における「電圧が上がることによって創発する誘導起電力」を理解させてくれやすくすると思われる。電圧が上がっている間、確かに、フレッシュな共転回が供給され続けるからである。
※一方、永久磁石の運動による誘導起電力も、運動による、フレッシュな共転回の供給のみならず、個々のミクロ磁場の増大に比例した“(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)ミクロ電場”の増大があるので、同様に理解できると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
|
当然、導線の中に、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)は、まんべんなく存在するので── 磁場が増加しているときに限って、ほぼ導線全体にわたって、「(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)ミクロ電場」が優位となることになる。
これらの、優位になったミクロ電場の総和が、誘導起電力の実体である。
なお、以上の説明は、やはり、「レンツの法則(磁場の変化を打ち消そうとする方向に誘導起電力が生じる)が、どのようなしくみで成り立つか」をも説明していることになる。
以上で、ファラデーの法則の一部を説明したことになる。
次に、ファラデーの法則の残りの部分、「2.一定の磁場の中を、電荷が運動すると、導線の中の電荷にローレンツ力(電場)が作用する。」ことについて説明する。
2. 一定の磁場の中を、導線が運動すると、導線の中の電荷にローレンツ力(電場)が作用する。
一定の磁場とは、何であろうか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、次の図ように、「とミクロ磁場の総和として創発した、マクロな磁場」として、一定の磁場を、説明する。
※各ミクロ磁場の向きが、そろっている。 この総和である、マクロの磁場が、“一定の磁場”である。
厳密に言えば、各ミクロ磁場は、下図のように振動し続けている。
よって、“一定の方向を向くミクロ磁場の平均”が、マクロ磁場として観測されていることになる。
※2回の共転回により、ミクロ磁場は同じ向きに生じ続けているのに対しミクロ電場は逆転している。
そして、なおかつ、ミクロ電場の向きもバラバラである。 したがって、マクロの電場が観測されることはない。
※4個しか描いていないが、実際は、“(2Lp)3[m3]の体積あたり1つ”を最大限として、びっしりと空間の中に、つまっていることになる。
|
つまり、一定の磁場とは、「ミクロ磁場の向きがそろい、ミクロ電場がそろわないこと」の総和として、創発したものである── とも言える。
※ミクロ磁場においても、N極とともに、S極を示すことができる。
このことは、永久磁石や電磁石の“S極”も、ミクロ磁場の総和として創発すると考えられることと調和している。
|
※原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の中の素スピノールの転回により、ミクロ電場とともに、ミクロ磁場の“N極とS極が同時に生じている”
(→モノポールは、このレベルにおいても、存在していないことになる)
※地球や電子における磁極とも似ている(相似になっている)。
※なお、「永久磁石や電磁石」は、ふつう、「(左巻き素スピノールから構成されている)電子」のふるまいから生まれているので── 「永久磁石や電磁石」が生じるミクロ磁場は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の中の右巻き素スピノールの転回によって生じるもの(上図の右側)であると考えられる。
|
このミクロ磁場がN極とS極の両方を持つという考えは、アンペール-マクスウェルの法則や、これまでのファラデーの法則の説明とも矛盾していない。
(このことは、“モノポール”(単極子)に相当するものは、少なくとも、“原始ヒッグス場ユニット(素スピノール)レベル”においても実在しないことを意味する。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の予測をする。
予測2.0 モノポールは、実在しない。
※なお、この予測は、“磁場のガウスの法則”──「4つのマクスウェルの方程式」の1つとも合致する)
やはり、個々の素スピノールが原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の中で転回するプロセスの中でこそ、“ミクロ電場やミクロ磁場”が生じる。
もし、素スピノールが“一切転回していなければ”、“電場や磁場”は、一切、生じない。
(したがって、個々の素スピノールがN極やS極を持つということもない。
また、だからこそ、“弱い力しか働かない(電荷を持たない)ニュートリノ”が存在できる。 →結果2)
さて、この一定の(一様な)磁場の中を、電子などの荷電粒子が一定の方向に運動すると何が起こるであろうか?
“電荷の流れ”とは、電流に他ならない。 アンペールの法則に従うように、“新たな磁場”が生じるでろあう。
※画面(紙面)に対して垂直な向きで手前から奥へ電子が運動している。
電流は、逆に、奥から手前へ流れていることになる。
したがって、新たに生じるミクロ磁場の総和、すなわち“新たなマクロの磁場”は、アンペールの法則に従っていることがわかる。
※電子の近くに図示した、左巻き素スピノールは、すべて、電子を構成する、左巻き素スピノールである。
原始ヒッグス場ユニットの近くに示した、右巻き素スピノールは、すべて、原始ヒッグス場ユニットを構成する、右巻き素スピノールである。
| ※上図では、示せていないが、実際は |
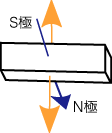 |
のように、ミクロ電場は、プラスマイナス0となっている。 |
|
よって、こういった磁場を生じるような電子が、例えば、下図のような、「元から存在する“一定の磁場”」の中を、運動するとどうなるか?
それは、この一定の磁場に、次のような磁場を重ね合わせることに他ならない。
すると、下図のように、相対的に、(上下方向でも斜め方向でもなく)左右方向において、最も顕著な「ミクロ磁場の数の差」が生まれることになる。
※電子の運動方向に対して、左側で、ミクロ磁場が最も増加するのに対して、右側で最も減少することになる。
| なぜなら、電子の運動方向の左側においては、元からあるマクロ磁場と全く同じ方向にミクロ磁場が生じ増加する一方、 |
|
電子の運動方向の右側においては、
|
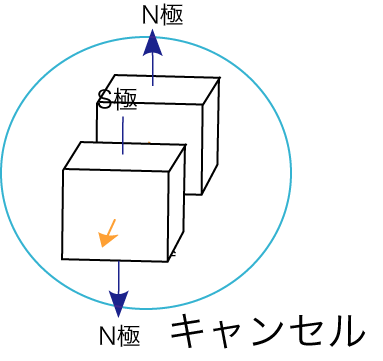 |
のように180度逆向きのミクロ磁場が生じる結果
|
| ミクロの磁場がキャンセルされ、減少すると考えられるからである。 |
|
(なお、キャンセルされるとは、「“4面体”の変形」がキャンセルことであり、エネルギーが最低の、元の“4面体”に近づいていくことを意味する。(→原始ヒッグス場抵抗の増加))
※キャンセルは、いずれのミクロの磁場も、原始ヒッグス場ユニットの中の右巻き素スピノールの転回に伴って生じているからこそ生じる。
電子からの距離が大きくなるのに反比例して、(アンペールの法則にしたがって生じる)ミクロ磁場が小さくなるので、キャンセルの度合いも、それに応じて変化すると考えられる。
一定の磁場を構成するミクロ磁場の大きさも、電子の運動も、本来、任意であるが、元からあるミクロ磁場と、電子の運動によって生じるミクロ磁場の大きさが、ほぼ等しくなるポイントが必ずあると考えられる。 少なくともその部分では、ほぼ100%のキャンセルが実現することになる。
※「ミクロの磁場の増加」が生じるのも、いずれのミクロの磁場も、原始ヒッグス場ユニットの中の右巻き素スピノールの転回に伴って生じているからこそ生じる。(運動する電子も、電磁石も、永久磁石も、その中の左巻き素スピノールが、ミクロ磁場をうむのだった)
|
したがって、電子の運動によって、「電子の進行方向からみて左側の原始ヒッグス場抵抗が小さくなり、右側の原始ヒッグス場抵抗が大きくなる傾向」が創発することになる。
それは、まさに、電子に対して働く力が創発したことに他ならない。
つまり、これが、まさに、ローレンツ力が創発したことに相当する。
当然、実際は、“導体の運動”に伴って、多数の自由電子が運動することになる。
その結果、「電子の進行方向からみて左側の原始ヒッグス場抵抗が小さくなり、右側の原始ヒッグス場抵抗が大きくなる傾向」も、電子数に比例して増加するであろう。
※紫色の矢印は、「電子の運動の向き」を示している。
オレンジ色の大きな矢印は、「(紫色の矢印の向きに運動する)“マイナス電荷を持つ電子”に働く力の向き」である。
オレンジ色矢印の方向に力が生じるのは、「電子の進行方向からみて左側の原始ヒッグス場抵抗が小さくなり、右側の原始ヒッグス場抵抗が大きくなる傾向」が創発しているからである。
この力の向きは、“ローレンツ力の向き”(フレミングの左手の法則)と調和する方向のものである。
(なお、もし、電子(負電荷)のかわりに、陽電子(正電荷)が、同じ方向に運動していたとしたら、ローレンツ力の向き”の方向は、上のオレンジ色の矢印とは逆向きとなるであろう)
|
以上により、「一定の磁場の中を、電荷が運動すると、なぜ、どのようにして、その方向にローレンツ力が生じるのか?」を説明できたことになる。
つまりは、この説明によって、「なぜ、どのようにして、ファラデーの法則が成り立つのか」の残り半分も説明できたことになる。
また、以上より、アンペール・マクスウェルの法則、ファラデーの法則、“磁荷のガウスの法則”(モノポールは存在しない)、電磁波… について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が説明できたことになる。
(残りの1つ(“電荷のガウスの法則”についての式)についての説明は、結果1の《静電場(クーロンの法則)のEMOES表記》にて行った。
したがって、以上により、「4つのマクスウェルの方程式」の4つすべてを説明したことになる)
マクスウェルの方程式で説明されることがら(アンペール・マクスウェルの法則、ファラデーの法則、“磁荷のガウスの法則”(モノポールは存在しない)、“電荷のガウスの法則”、電磁波…)の根底には── 「原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニットの総和)と、仮想光子の創発、すなわち、素スピノール同士の共転回…」という実体があることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示しているのである。
すなわち、こういった実体像を通して、「なぜ、どのようにして、マクスウェルの方程式が成り立つのか?」を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が説明しているのである。
それは、「マクスウェルの方程式」という抽象的な数学の解釈を重視することでもあり、そして、自然(nature)そのものの実体像の探求を、取り戻すことでもあるのである。
※マクスウェルの方程式は、磁場から電場が生まれたり、電場から磁場が生まれたり、「電場と磁場は、紙一重のものである」であることを示している。
そういったことが可能なのは、ミクロ磁場&ミクロ電場の総和として、(観測されるような)マクロの電場やマクロの磁場が生じているからということになる。
※なお、以上の説明が正しければ── 電磁気力は、あくまで、仮想光子の総和が生む“電磁場(電場や磁場)”を介して生じる力であり、ボソンのキャッチボールによって(湯川型の相互作用によって)生じる力ではないことになる。(結果2、結果6)
(しかし、その過程を、“ある電荷が仮想光子を放出し、もう一方の電荷が、その仮想光子を受け取る”というように解釈して計算したとしても、ある程度、つじつまが合うのだと考えられる。 なぜなら、その所産が(成功しているとされる)量子電磁力学(電子&電磁場についての場の量子論)に他ならないからである。
なお、LP光子の方は、グルーオンと同様に、実際に、“吸収される”と言える)
※仮想光子が無限遠方まで届くとしたら、どうやって伝わるか? やはり、“電荷”によって、無限遠方の素スピノールが、ダイレクトに180度転回させられるのであろうか?
しかし、もし仮にそうだすると、転回周期Tが無限大になってしまい、その結果、電荷の中の素スピノールが消費され、電荷が持つ新たに共転回する能力(仮想光子を放出させる能力)が低下することになってしまうのではないだろうか? それは、電荷の低下を意味し、“電荷の保存”と矛盾してしまうことになるのではないだろうか?
もし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が正しければ、このことは、「電磁気力は、無限遠方まで働く」という考え(「4つの力」を比較する際に、頻繁になされる考えである)を見直す必要があることを意味していることになると思われる。(実際には、電磁気力が無限遠方まで働くことを観測することは不可能であるし── 仮に電磁気力が無限遠方まで直接働かなくとも、不都合はないのではないか? 電気磁気力は、“分極する物質”を中継地点として、とびとびで遠くまで伝わるものと考えても矛盾していないのではないか? 各種の“誘電率”は、このあたりの事情を説明してくれているのではないか?) 詳細な検討は、今後の課題である。
※電荷からの距離 r が大きくなればなるほど、仮想光子の転回周期Tも大きくなる(=振動数νが小さくなる&波長λが長くなる)。
仮想光子の転回周期Tは、 T=2r/c で計算できる。(なぜなら、c=νλ=λ/T、r=λ/2だからである)
一方、転回周期Tが大きくなると同時に、仮想光子による180度転回に伴うエネルギー振幅ΔEは、逆に小さくなる。
なぜなら、アインシュタインの式E=hνより、光子のエネルギーE=hν=h/T が成り立つからである。
(それは、不確定性原理の式とも、おおよそ合致するものである→結果4)
これらのことは、仮想光子は、決して、ランダムなエネルギーを持つものではないことを意味している。
すなわち、遠ざかれば遠ざかるほど、E=hc/r に反比例して、仮想光子が生じるエネルギーが小さくなる。
このあたりにも、量子電磁力学(QED)(“電荷&電磁気力”の場の量子論)において、無限大を生じさせないヒントの1つ、“くり込み”を不要にさせるヒントの1つがあると思われる。(もう一つの、無限大を生じさせないヒント、“くり込み”を不要にさせるヒントは、電磁場を原始ヒッグス場ユニットの集合と見る見方(時空に最小の単位があるという見方)である) 詳細な検討は、今後の課題である。
《電荷の間に働く“引力と斥力”について》
電荷の間に働く力──静電力(クーロン力)には、引力と斥力がある。
(それは、重力が引力のみであることと対照的である)
「どのようなしくみで、重力は引力のみとなり、電磁気力には、引力と斥力が存在するのか」については、現代物理学は、説明できていないようである。
(なぜなら、“重力には、反重力があるはずだ”というという説が登場しているほどだからである)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば 「どのようなしくみで、重力は引力のみとなり、電磁気力には、引力と斥力が存在するのか」について、説明できる。
「どのようなしくみで、重力が引力のみとなるか」については、結果1で説明した。
残りの「どのようなしくみで、電磁気力には、引力と斥力が存在するのか」について、を以下に示す。
プラス電荷とマイナス電荷が近くにあると、引力が働く(引き合う方向に力が働く)一方で── プラスどうしの電荷が近くにあると(orマイナスどうしの電荷が近くにあると)斥力が働く。
それは、結局は、プラスプレオンどうし、マイナスプレオンどうしなら斥力、プラスプレオンとマイナスプレオンなら引力が働くからに他ならない。
|
電荷の組み合わせ
|
|
電気力(クーロン力) |
| プラスプレオン&プラスプレオン |
→ |
斥力
|
| マイナスプレオン&マイナスプレオン |
| プラスプレオン&マイナスプレオン |
→ |
引力
|
※これらの総和として、「プラス電荷どうし、マイナス電荷どうしの間に斥力、プラス電荷、マイナス電荷の間に引力が生じる──」という一般的な関係が創発する。
※電子の中の、3つのマイナスプレオンの間に存在する電気力が斥力であるのに、3つのマイナスプレオンが結びついている理由は、それらが、“LP光子の集積したひも”によって閉じ込められているからである。
(→詳細は結果2《プレオン∴どうしを結びつける力》、《プレオン∴の閉じ込め》)
|
したがって、プラス電荷はプラスプレオンから、マイナス電荷はマイナスプレオンから、それぞれ創発しているので──
「どのようなしくみで、プラス電荷どうし、マイナス電荷どうしの間に斥力、プラス電荷マイナス電荷の間に引力が生じるのか?」という問題は、「どのようなしくみで、プラスプレオンどうし、マイナスプレオンどうしの間に斥力、プラスプレオンとマイナスプレオンの間に引力が生じるのか?」という問題と等価であることになる。
以下では、まず、「プラス電荷どうし、マイナス電荷どうしの間に斥力、プラス電荷マイナス電荷の間に引力が生じる」という関係そのものが、どのようにして、生じるのかを説明し── のちに、詳細な仕組みを、荷電プレオンを用いて説明することとする。
例えば、中心にマイナス電荷がある場合を考える。
マイナス電荷は、結局は、すべて左巻き素スピノールのみで構成されているので、周囲にできる電場(=仮想光子による“4面体”の変形)は、すべて、“4面体”の中の右巻き素スピノールが転回することによって生じたものである。
さて、ここに、プラス電荷を持ってくると引力が生じ、マイナス電荷をもってくると斥力が生じるのだった。
中心のマイナス電荷が作る電場は、もともと100%共通であったはずなのに、このようなことが起こるのは、なぜか?
それは、周囲に新たに持ってきた“プラス電荷”あるいは“マイナス電荷”が、元々あった周囲の電場を“引力が生じるように”あるいは“斥力が生じるように”と変化させるからに他ならない。 どのようなしくみで、このような変化を生じさせるであろうか?
1.周囲にプラス電荷を持ってきた場合
下図が、マイナス電荷が中心にあるようすを示すモデルである。
※中心にマイナス電荷があるときのモデルである。
原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形(つぶれ=ピンクの四角で示した部分)が大きいほど、「元の立方体」は、よりつぶれて小さくなっている。 同心円は、厚さ2LPの球殻を示す。
※当然、実際は、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形は、3Dの空間全体にわたってまんべんななく存在する一方で、変形の存続時間も、それぞれの球殻で異なる。
|
ここに、プラス電荷を持ってくると──
↓
※マイナス電荷による“4面体”の変形と、プラス電荷の“4面体”が、共存し続けている。
なぜなら、マイナス電荷(左巻き素スピノールで構成)は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の中の右巻き素スピノールのみを転回させ、プラス電荷(右巻き素スピノールで構成)は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の中の左巻き素スピノールのみを転回させるからである。
※なお、ふつうの仮想光子(静電場)を介する力のみを考えている。
後で説明する、プレオン同士を結びつける力、LP光子を介する作用は、ここでは考えていない。
|
単に、重ね合わせの結果、電荷の間で、“4面体”の変形が共存し、変形が“足し合わさる”(増幅する、増加する…)だけである。
なぜなら、(左巻き素スピノールで構成される)マイナス電荷は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の中の右巻き素スピノールを転回させて電場を作り、
一方、(右巻き素スピノールで構成される)プラス電荷は、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の中の左巻き素スピノールを転回させて電場を作るので、“キャンセル”が一切生じないからである。
周辺のプラス電荷は、結局は── 中心のマイナス電荷が作る「原始ヒッグス場抵抗の減少分」に従って移動するだけのことになる。
つまりは、引力が生じるのである。
これは、ある意味、重力の作用と似た状態である。
すなわち、“周辺に持ってきた質量”が作る重力場は、その質量自身には全く作用しないように── この場合、“周辺に持ってきたプラス電荷”が作る電場は、プラス電荷自身に全く作用していない。
2、周囲にマイナス電荷を持ってきた場合。
下図が、マイナス電荷が中心にあるようすを示すモデルである。(1の最初の条件と全く同じである)
※中心にマイナス電荷があるときのモデルである。
原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”の変形(つぶれ=ピンクの四角で示した部分)が大きいほど、「元の立方体」は、つぶれて小さくなっていることを示す。
|
ここに、マイナス電荷を持ってくると──
↓
※新しく周囲に持ってきたマイナス電荷による“4面体”変形が、もともとのマイナス電荷の周囲の
「原始ヒッグス場抵抗の減少分(つぶれ=ピンクの四角で示した部分)」の大きさの分だけ、キャンセルされている。 キャンセルされた部分が、オレンジで染まった部分として示されている。
すなわち、マイナス電荷が来ることによって、もともとの「原始ヒッグス場抵抗の減少分(つぶれ=ピンクの部分)」が、「原始ヒッグス場抵抗の増加分(=オレンジで染まった部分)」へと変化し、その働きが、100%逆転することになるのである。
※このようなことが起こるのは、マイナス電荷(左巻き素スピノールで構成)は、(中心も周辺も)ともに、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”の右巻きの素スピノールだけを転回させるからである。
すなわち、(左巻き素スピノールで構成される)マイナス電荷が、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の中の右巻き素スピノールを転回させて電場を作る一方、周辺に持ってきた(左巻き素スピノールで構成される)マイナス電荷も、同様に、原始ヒッグス場ユニットの中右巻き素スピノールを転回させて電場を作るので、“競合”および、“キャンセル”が生じるからである。
※なお、ここでは、ふつうの仮想光子(静電場)を介する力のみを考えている。
後で説明する、プレオン同士を結びつける力、LP光子を介する作用は、ここでは考えていない。
|
新たに周辺に配置したマイナス電荷が作る電場(“4面体”の変形)は、元々の中心のマイナス電荷が作る電場が元々もっていた“4面体”の変形の分(=「原始ヒッグス場抵抗の減少分」)だけ、ちょうどピッタリ同じ大きさで、キャンセルされる。
その結果、マイナスの電荷を持ってくると、その「原始ヒッグス場抵抗のキャンセル分」に応じて、斥力が生じる(プラスの電荷を持ってきた時と全く逆方向の力が生じる)と同時に、その“大きさ”は、プラスの電荷を持ってきた場合と、全く同じになる。
つまり、マイナス電荷を周辺に置いた場合── “周辺に持ってきたマイナス電荷”が作る電場が変化することによって生じた「新たな原始ヒッグス場抵抗」の配置に応じて、“斥力”が生じるのである。
それは、「既存のマイナス電荷が作る電場」と「周辺にもってきたマイナス電荷が作る電場」が、重ね合わさることによって、「既存の“原始ヒッグス場抵抗”の向きを100%逆転させた“原始ヒッグス場抵抗”」が創発するということでもある。
つまり、電荷の間に働く力は── それらの電荷が、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)を変形させる際に、転回させる素スピノールが、右巻きと左巻きのどちらであるかが、大きな分岐点となるのである。
すなわち、引力か斥力かは、その相性によって、100%と逆となる。
そのことは、「マイナス電荷が、左巻き素スピノールのみで構成され、プラス電荷が右巻き素スピノールのみで構成されている」、「“4面体”の変形がより大きいほど、その方向へ運動する際の抵抗が減り── その方向へ進みやすくなる」という理由によって、単純に説明できる。
もっと、厳密に見てみよう。
例えば、(電子の中の)マイナスプレオンの周辺に、(陽子(アップクォーク)or 陽電子の中の)プラスプレオンを持ってきた場合── マイナスプレオンによって作られる変形した“4面体”と、プラスプレオンによって作られる変形した“4面体”が、下図のように共存する。
したがって、キャンセルがなく、同じ向きの電場が、単純に足し合わさるだけである。
※キャンセルがなく、共存する場合である。
電場の向きが同じになっている。
※なお、ふつうの仮想光子(静電場)を介する力のみを考えている。
後で説明する、プレオン同士を結びつける力、LP光子を介する作用は、ここでは考えていない。
|
なお、次の図のように、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の変形が増幅する場合も考えられるかもしれない。
※1つの原始ヒッグス場ユニットに作用する、マイナスプレオン(左巻き)とプラスプレオン(右巻き)の電荷が生む仮想光子による変形が増幅している。
このようなことが成立するのは、マイナスプレオンとプラスプレオンの共転回の相手が、右巻きと左巻きというように、別々であるからである。
※上図のように、マイナスプレオンによる変形の幅をa[m]、プラスプレオンによる変形の幅をb[m]とすると、変形幅の合計は、単純に a+b[m]になると考えられる。
※上の図では、遠くはなれた方のマイナスプレオンの転回周期が長く、近くのプラスプレオンの転回周期が短いことも示されている。
このように転回周期が異なっているので、図のような、共転回の開始のタイミングがずれている中での増幅が可能になると考えられる。
※やはり、ふつうの仮想光子(静電場)を介する力のみを考えている。
後で説明する、プレオン同士を結びつける力、LP光子を介する作用は、ここでは考えていない。 |
このように、異種の電荷が近くにある場合は、「個々の“4面体”の変形が増幅する」ことも考えられる。 ただし、電場の線形性によって、実質的には、複数が共存するのと同じ結果になると考えられる。
※もし、正負のプレオンのちょうど中間地点であれば、そこの“4面体”の変形は、2つの仮想光子の作用が、足し合わさることによって、ちょうど2倍になると考えられる。
なお、上では、正負のプレオンの間の原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の変形を示しているが、正負のプレオンの外側にある原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primal Higgs(field)Unit)の変形も、同様に、単純に足し合わさるだけであると考えられる。
次に、同種の電荷──プラスプレオン&プラスプレオン(orマイナスプレオン&マイナスプレオン)──が近くにある場合、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の個々の“4面体”の変形が、キャンセルされることを詳しく図示してみる。
※上図では、左側のマイナスプレオンによる、本来の変形の幅をa1[m](下の左図)、右側のマイナスプレオンによる、本来の変形の幅をa2[m](下の右図)とすると、変形幅の合計は a2−a1[m](「a2>a1」)となることが示されている。
|
|
|
このように「変形幅の合計が a2−a1[m](「a2>a1」)となること」は、もし、右側のマイナスプレオンが単独に存在するならば、変形幅がa2であるところが(上の右図)── 左側のマイナスプレオンによる原始ヒッグス場ユニットの変形が存在することによって(上の左図)、a1の分だけ、“変形できなくなってしまっている”(変形がキャンセルされている)ことを意味する。
|
|
このようなことが成立するのは、マイナスプレオンの両方にとっての共転回の相手が、ともに(同じ原始ヒッグス場ユニットの中の)“右巻き素スピノール”であるからこそである。
※なお、「cT=2r、ET=h」であるので、共転回の間の距離rが短いほど、蓄えられるエネルギーEが大きくなると同時に、原始ヒッグス場ユニットの変形幅も大きくなるので── 「r1>r2」ならば、「a2>a1」と決まる。 これは、もし、2つのマイナスプレオンから等距離にある原始ヒッグス場ユニットならば(「r1=r2」ならば)、「a2=a1」すなわち、100%のキャンセルが生じて、変形幅の合計が、0[m]となることを意味する。
※ふつうの仮想光子(静電場)を介する力のみを考えている。
後で説明する、プレオン同士を結びつける力、LP光子を介する作用は、ここでは考えていない。
|
※なお、これを個々のヒッグス場ユニットの変形の“増幅”によるのではなく── 下図のように、別々のヒッグス場ユニットの変形がバラバラに存在すると考えると、“斥力”が生じる理由を説明できないようである。
| ※ヒッグス場ユニットの変形の、それぞれが、別々に共存する形になっている。 この場合── 斥力が生じる理由を説明できないようである。 |
このように、同種の電荷の場合、斥力を説明できるのは、1つの“4面体”における増幅のみであることは──
異種の電荷の場合は、引力を説明できるのは、1つの“4面体”における増幅と、複数の“4面体”の単純な足し合わせの、両方であることと対照的である。
※もしかしたら、「個々の“4面体”における“増幅かキャンセルか”のみが、引力か斥力かを決める最も重大な分岐点である」「異種の電荷の場合も、実は、個々の“4面体”における増幅による説明のみが正しくて、単純な足し合わせによる説明は、正しくない」ということもあるだうろか? 詳細な検討は、今後の課題である。
いずれにせよ、以上のようなしくみで、電荷の間で、引力や斥力が生じることを説明できることは── 重力との違いを理解する上で重要となる。
|
重力
|
電気力
|
|
引力のみ
|
引力 or 斥力
|
|
質量の間の力
|
電荷の間の力
|
|
電荷の正負に関係なく
引力のみ
|
電荷の正負と関連して
引力か斥力が決まる
|
なぜなら、『例えば、マイナス電荷が中心にあるとき、その周囲に「原始ヒッグス場ユニットの変形(原始ヒッグス場抵抗の減少)」が存在しているからといって、その時点で、重力の場合と同じように、すべての相手に対して引力が生じることない』ことを、はっきり説明できるからである。
すなわち、例えば、マイナス電荷が中心にあるとき、その周辺に、“中性”のもの(中性子、水素原子…)が来たとしても、引力が生じることはない。 なぜなら、例えば、中性子(ダウンクォーク(−1/3の電荷)×2+アップクォーク(+2/3の電荷)×1)や水素(電子+陽子)は、実は、それぞれ、“マイナス電荷+プラス電荷”であるので、「引力+斥力」が働くこととなり、その結果、見かけ上、一切力が働いていない状態(引力が働かない状態)になるからである。
|
相互作用のペア
|
「正の電荷」&「負の電荷」
|
「負の電荷」&「負の電荷」
「正の電荷」&正の電荷」
|
「正負の電荷」&
「(正と負の電荷を含む)
中性の物質」
|
「正負の電荷」&
「(正と負の電荷を含まない)中性の物質」
|
|
具体例
|
電子&陽子
電子&陽電子
…
|
電子&電子
陽子&陽子
…
|
電子&中性子、陽子&中性子
電子&水素原子 …
|
電子&ニュートリノ
陽子&ニュートリノ
…
|
|
重力
|
○引力
|
○引力
|
○引力
|
○引力
|
|
電気力
|
○引力
|
○斥力
|
×引力、×斥力
※実は、ミクロレベルでは、
引力も斥力も存在しているが、
引力と斥力が、ちょうどおなじ大きさで
打ち消し合う結果、見かけ上、
力が働いていないように見える
|
×引力、×斥力
※ミクロレベルでも、
マクロのレベルでも、
引力も斥力も存在しない
|
《磁極の起源、および“電子のスピン”》
上記のマクスウェル-アンペールの法則のところで説明したように、マクロの磁場は、「電荷の運動に伴って相対的に優位になる“素スピノールの共転回”(原始ヒッグス場ユニットの変形)の総和」として創発するのだった。
より単純に書くと、「電荷の運動に伴って優位になる“ミクロ磁場”の総和」として創発するのがマクロの磁場である。
すなわち、マクロの磁場を生む磁極の起源は、電荷の運動に他ならない。
一方、次の記述がある。
『あらゆる物質の磁気モーメントの起源は、次の2つである。
1.物質内部での電荷の運動(電流)
2.素粒子が固有に持つ磁気モーメント』
(ウィキペディア 『磁気モーメント』)
|
磁気モーメントとは、『S極からN極に向うベクトル』と『そのS極とN極の磁極の強さ』の積である。
したがって、モノポールが発見されていない以上、上記の2つの“磁気モーメントの起源”は、“磁極の起源”とほぼ等しい見なすことができる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、この2つ磁極の起源(≒磁気モーメントの起源)は、「電荷の運動に伴って優位になる“ミクロ磁場”の総和」として、マクロの磁場が創発しているという考えで統合することができる。
それを以下に示す。
『1.物質内部での電荷の運動(電流)』については、例えば、次のような電磁石の系が考えられる。
この例においても、「電荷の運動に伴って優位になる“ミクロ磁場”の総和」として、マクロの磁場が創発している。
※電子は、マイナスプレオン3つからできており、それらのマイナスプレオンは、どれも左巻き素スピノール3つから構成されているので、周囲の原始ヒッグス場ユニットの中の“右巻きの素スピノール”のみが共転回している。
※上図では、アンペールの法則を説明する図の、2つだけを組み合わせて示してあるが、実際は、コイルの周辺のすべての領域においてアンペールの法則に従うように「優位となる“ミクロの磁場”および、その総和としてのマクロの磁場」が生じる。
その結果、コイルの中心において、生じる磁場(ミクロ&マクロ)は、どれも同じ方向を向く。
すなわち、ミクロ磁場の総和として、コイルの中心に、図のようなマクロの磁場(N極とS極)が創発することになる。
|
このように、電磁石においては、このマクロの磁場(N極とS極)は、コイル上の電荷の運動の働きの総和として、創発しているものである。
同様に、例えば、水素を構成する電子の軌道運動によって生じる磁気についても、「電荷の運動に伴って優位になる“ミクロ磁場”の総和」として、マクロの磁場が創発している── 説明できるのは明白である。
つまり、『1.物質内部での電荷の運動(電流)』は、「電荷の運動に伴って優位になる“ミクロ磁場”の総和」として、マクロの磁場が創発しているのである。
それでは、もう一方の『2.素粒子が固有に持つ磁気モーメント』(≒素粒子が固有に持つ磁極の起源)の方はどうであろうか?
これまでは、単にその素粒子が持っている“スピン”(固有角運動量)が担っていると考えられてきたと思われる。
一方、この“スピン”(固有角運動量)は、フェルミオンの場合は1/2(厳密にはh/4π[kg・m2/s])の値であり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、 個々の素スピノールも、同じ大きさのスピンを持っているのであった。
しかし、この個々の素スピノールのスピンが、そのまま『2.素粒子が固有に持つ磁気モーメント』(≒素粒子が固有に持つ磁極の起源)も担っているとは考えにくい。
その理由は、少なくとも次の3つである。
1.もし、個々の素スピノールが磁極の起源であるとすると、個々のニュートリノさえもが磁極を 持ってしまうことになり、観測結果と矛盾する。
2.電荷の起源は3つ素スピノールからなる“荷電プレオン”であり、『マクロの磁場は「電荷の運動に伴って相対的に優位になる“素スピノールの共転回”(原始ヒッグス場ユニットの変形)の総和」である』という説明と矛盾する。
3マクスウェル・アンペールの法則、ファラデーの法則と調和する形で磁場の創発を説明できなくなる。 |
この個々の素スピノールの“スピン”(固有角運動量)が、『2.素粒子が固有に持つ磁気モーメント』(≒素粒子が固有に持つ磁極の起源)を担っているのでなければ、何が担っているのであろうか?
それは、「素粒子を構成する荷電プレオン∴の軌道運動」に他ならないと考えられる。
すなわち、この「素粒子を構成する荷電プレオン∴の軌道運動」が『2.素粒子が固有に持つ磁気モーメント』(≒素粒子が固有に持つ磁力)を担っていると考えるとつじつまが合うのである。
電子を例にとってみよう。
個々の電子は、“たとえ軌道運動をしていなくとも磁石である”と考えられている。
この個々の電子の“軌道運動せずに持っている磁極”こそが、「永久磁石」や「強磁性を持つ鉄」… のマクロの磁場(N極とS極)の大部分を担っていると考えられている。
これまでは、個々の電子が磁石であることを、ふつう“電子のスピン(固有角運動量)”によって説明してきた。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、この個々の電子が磁石である理由(個々の電子が軌道運動せずに磁力を持てる理由)を、下図のような、1つの電子を構成する3つのマイナスプレオンの軌道運動によって説明できる。 電子を構成するマイナス電荷を持つ3つのプレオンが「微小回路上を流れている状態(電流を生じている状態)」が、N極やS極を生じると考えるとつじつまが合うのである。
※1つの電子が、軌道運動をしていなくとも磁石になれることを説明する図である。
3つのマイナスプレオン(左巻き素スピノールからなる)が、微小回路を軌道運動することによって、電子が持つ磁場(N極やS極)が、上図の向きに創発する様子を図示している。
なお、「マイナスプレオンが軌道運動する向き」と「微小回路の上を流れる電流の向き」は、逆である。
したがって、この「電子のスピン(3つのマイナスプレオンの微小回路上の軌道運動)」においても、結局、アンペールの法則と調和する向きに磁場(N極やS極)が生じていることがわかる。
このようなしくみによって、マイナスプレオンの電荷は、半永遠的に軌道運動を続けることになる。
そして、「この、半永遠的に続くマイナスプレオンの軌道運動」こそが、まさに、「電子が軌道運動せずに持っている磁極の起源」の幾何的な実体像であることになる。
※なお、左側の図における、紫色の矢印には、「電子のスピンが生じる電磁モーメントのS極からN極へ向かうベクトルの向き」という意味がある。
左側の図のピンク色の矢印は、電流の向きという意味を持つのに対し、右の図における、個々のマイナスプレオンが持っている矢印はマイナスプレオンの軌道運動の方向という意味を持つ。
※なお、常に、マイナスプレオンのうちの2つは、向きが正反対で、角運動量を打ち消し合う形になっている。
|
つまり、個々の“電子のスピン(固有角運動量)”で説明されてきた「電子が軌道運動せずに持っている磁極の起源」は、「電子を構成する3つのマイナスプレオンの軌道運動」によって、説明すしなおすことができるのである。
「電子を構成する3つのマイナスプレオンの軌道角運動量の値」は、いくらだろうか?
求めてみよう。
電子が波動性を持つように、プレオン∴も波動性を持つと考えられる。(→結果4)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、電子の波動性の起源は、電子と電子ヒッグス場ユニット(→結果3)の相互作用である。
同様に、プレオン∴の波動性の起源は、プレオン∴とプレオン∴ヒッグス場ユニット(→結果3)との相互作用であると考えられる。
※プレオン∴ヒッグス場ユニットとは、左巻きマイナスプレオン×2と、右巻きプラスプレオン×2からできているヒッグス場ユニットのことである。(→詳細は、結果3)
「プレオン∴の物質波の実体像」は、「プレオン∴とプレオン∴ヒッグス場ユニットとの相互作用による“プレオン∴の生成と消滅を繰り返す波である”」と考えられる。 このことは、1つの電子が、原子核の周辺を、電子ヒッグス場と相互作用しながら生成と消滅を繰り返す波を形成していると考えられることと相似である。
(詳細は、結果3《「電子の運動エネルギー&電子ヒッグス場ユニット」によって獲得される質量》
結果4の《電子の量子論的な振る舞い──シュレーディンガー方程式》)
電子を構成する1つのマイナスプレオンの運動量をpp∴[kg・m/s]と、マイナスプレオンの物質波の波長λp∴[m]の間には、pp∴=h/λp∴[kg・m/s]の関係がある。
(h:プランク定数[J・s](=[kg・m2/s]) λp∴:マイナスプレオンの物質波の波長[m])
プレオン∴の軌道半径をrp∴[m]とすると、このマイナスプレオンの1つの軌道角運動量は、pp∴rp∴=hrp∴/λp∴[kg・m2/s]となる。
電子を構成する3つのマイナスプレオンのうち2つは、必ず打ち消し合っているので、このpp∴rp∴=hrp∴/λp∴[kg・m2/s]の値が、そのまま電子を構成する3つのマイナスプレオンの軌道角運動量の合計(総和)に他ならない。
一方、次の仮説を立てることとする。
仮説2.5「電子を構成する3つのプレオン∴」と「プレオン∴ヒッグス場ユニット」の間に下図のように、1つのプレオン∴あたり、1つだけのプレオン∴ヒッグス場ユニットが半径rp∴[m]の円周上に配置しており、それぞれ『2πrp∴=λp∴/2 の関係』が成立している。
※なお、マイナスプレオンのうちの2つは、向きが正反対で、角運動量が打ち消し合う形になっている。
※実際には、下図のように3つが一緒に重なっていると考えられる。
|
『2πrp∴=λp∴/2』より『rp∴/λp∴=1/4π』と変形でき、両辺にプランク定数をかけると h/4π=hrp∴/λp∴[kg・m2/s]の関係が得られる。
したがって、『2πrp∴=λp∴/2 の関係』が成立していることは、実は、このマイナスプレオンの1つの軌道角運動量は、pp∴rp∴=hrp∴/λp∴[kg・m2/s]の値が、ぴったり、1/2(厳密にはh/4π[kg・m2/s]に等しいことを意味しているのである。
つまり、仮説2.5が正ければ、「電子を構成する3つのマイナスプレオンの軌道角運動量の値」は、「電子の“スピン”(固有角運動量)の値」や「素スピノールのスピン(固有角運動量)の値」とぴったり等しい1/2(厳密にはh/4π[kg・m2/s])なのである。
このことは、結果的に、「電子のスピン」の実体が、(電子の磁力(磁気モーメント)を担う)「電子を構成する3つのマイナスプレオンの軌道運動」であると見なしても、大きな問題がないことを意味していると思われる。 (厳密には、その実体像は、異なっているが・・・)
※すなわち、“電子のスピン”には、2つあると考えても問題ないと思われる。
1つは、電子の磁力(磁気モーメント)を担う“電子のスピン”(その実体は、「電子を構成する3つのマイナスプレオンの軌道運動」)、
もう1つは、電子の磁力(磁気モーメント)を担わない“電子のスピン”(その実体は、素スピノールのスピン)である。
この1/2(厳密にはh/4π[kg・m2/s])の値は、さらに、「(波長λe[m]&軌道半径re[m]が2πre=λe/2を満たす場合の)電子の軌道角運動量の値」や「マイナスプレオンのスピン(固有角運動量)の値」、「(波長rES・[m]&軌道半径rES・[m]が2πrES・=λES・/2を満たす場合の)素スピノールの軌道角運動量」とも等しいと考えられる。
整理してみると次のようになる。
電子の軌道角運動量
(電子の波長λe[m]&軌道半径re[m]が2πre=λe/2を満たす場合)
→結果4 《ゼロ点エネルギー》) |
1/2(h/4π[kg・m2/s])
|
| 電子のスピン(固有角運動量) |
1/2(h/4π[kg・m2/s])
|
マイナスプレオンの軌道角運動量
(マイナスプレオンの波長rp∴[m]&軌道半径rp∴[m]が2πrp∴=λp∴/2を満たす場合) |
1/2(h/4π[kg・m2/s])
|
| マイナスプレオンのスピン(固有角運動量) |
1/2(h/4π[kg・m2/s])
|
素スピノールの軌道角運動量
(素スピノールの波長rES・[m]、軌道半径rES・[m]が2πrES・=λES・/2を満たす場合) |
1/2(h/4π[kg・m2/s])
|
| 素スピノールのスピン(固有角運動量) |
1/2(h/4π[kg・m2/s])
|
ここには、法則めいたものがあり、仮説2.5を支持しているように思われる。
詳細な検討は、今後の課題である。
※「(波長rES・[m]&軌道半径rES・[m]が2πrES・=λES・/2を満たす場合の)素スピノールの軌道角運動量」とは、1つの素スピノールあたり、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)が半径rES・[m]の円周上に配置しており、『2πrES・=λES・/2 の関係』が成立して相互作用している場合に存在するものであると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※この「1プレオン1プレオン∴ヒッグス場ユニット」方式だと、“構成要素が異なるアップクォークやダウンクォーク”にも応用できる。
(ダウンクォーク=マイナスプレオン×1+反中性プレオン×2、ダウンクォーク=プラスプレオン×2+中性プレオン×1)
※なお、一方で、このマイナスプレオンの運動エネルギー(外部)の総和が、電子の静止質量エネルギーの大部分を担っていると考えられる。 このようにプレオン∴の運動エネルギー(外部)が質量エネルギーを持ちうるということは、ダークマターを考えるヒントとなる。(→EMOES宇宙論3)
※磁気モーメントの単位であるボーア磁子μB、あるいは、g値との関係はどうなっているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
|
以上により、個々の電子にしろ、強磁性をもつ永久磁石にしろ、(コイル中の電流によって生まれる)電磁石にしろ── いずれにせよ、それらによって生じる磁場は、マイナス電荷(すなわち、マイナスプレオンの運動、つまりは、左巻き素スピノール)の軌道運動によって生じた磁場(“ミクロ&マクロ”)として、統一的に説明できることになる。
すなわち、個々の電子、永久磁石、電磁石… を含め、この自然界で磁場を生むのは、結局は、『“マイナス電荷”の中の「左巻き素スピノール」の軌道運動』ということになる。
《磁極の間に働く“引力と斥力”》
以下では、「マイナス電荷(の中の左巻き素スピノール)の軌道運動」によって生じる磁場に話をしぼって、説明していくこととする。
(「プラス電荷(の中の右巻き素スピノール)の軌道運動」によって生じる磁場については省いて説明していく)
磁極の間に働く、磁力にも、電荷の間に働くクーロン力と同様に、引力と斥力がある。
さて、磁力において、引力と斥力が生じる違いは、どのように説明されるであろうか?
次のような仮説を立ててみた。
仮説2.6 異種の磁極──N極とS極が近くにある場合、その間の原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の個々の“4面体”の変形は、増幅する。
同種の磁極──N極&N極(orS極&S極)が近くにある場合、その間の原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の個々の“4面体”の変形は、キャンセルされる。
正しければ、N極とS極は引き合い、N極どうし(S極どうし)は離れ合うことになり、観察結果と合致する。
その詳細を、電荷の時と同様に、単純なモデルを用いて考える。
そのために仮想的な“点磁極”を考える。
※この図は、中心にN極(仮想的な点磁極)があるときのモデルである。
原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”の変形(つぶれ=ピンクの部分)が大きいほど、「元の立方体」は、より小さくなっていることが示されている。
同心円は、厚さ2LPの球殻を示している。
当然、実際、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形は、3Dの空間全体にわたってまんべんなく存在する一方で、変形の存続時間も、それぞれの球殻で異なる。
※ただし、「マクスウェルの4つの方程式」の中の1つによって示されているように、モノポールは、実在しないと考えられるので、“点磁極”は、あくまで仮想的なものである。
なお、例えば、横一列の右半分だけに注目すれば、それは、下のような磁石のN極の先に生じる磁場と、ほぼ等しいとみなすことができる。
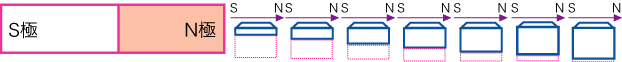
※ふつうの仮想光子を介する力のみを考えている。
後で説明する、プレオン同士を結びつける力、LP光子を介する作用は、ここでは考えていない。
|
ここに、S極の“点磁極”を持ってくると──
↓
※以下、“4面体”とは、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”こととする。
N極とS極の間の時空(緑色の線で囲った領域)では、「N極の“点磁極”による“4面体”の変形(=ミクロ磁場)」と、
「S極の“点磁極”による“4面体”の変形(=ミクロ磁場)」が、同じ方向を向いている。
すなわち、ここには、ミクロ磁場の加算があることになる。
例えば、N極とS極の間にある地点でのN極とS極による“4面体”の変形の幅の長さをそれぞれ、aN[m]、bS[m]とすると、その地点での“4面体”の“変形幅の総和は、aN+bS[m]と計算できる。
※一方、N極とS極の間の反対側にある外側の時空(オレンジ色の線で囲った領域)では、「N極の“点磁極”による“4面体”の変形(=ミクロ磁場)」と、「S極の“点磁極”による“4面体”の変形(=ミクロ磁場)」が、互いに逆を向いている。
よって、ここでは、ミクロ磁場のキャンセルが生じることになる。
例えば、N極とS極の外側のある地点でのN極とS極による“4面体”の変形の幅の長さをそれぞれ、aN[m]、bS[m]と書くと、その地点での“4面体”の変形幅の合計は、│aN−bS│[m]と計算できる。
(なお、aN<bSなので、bS−aN[m]と計算される) |
N極とS極の“点磁極”の間の時空では、“4面体”の変形が“足し合わさる”(増幅する、増加する…)だけであるの対し、“点磁極”の外側の時空では、“4面体”の変形が“キャンセルされる。
この結果、N極とS極の“点磁極”の間には、引力が生じるように観測されるのである。
すなわち、S極とN極は、やはり、それぞれの“点磁極”が作る「原始ヒッグス場抵抗の減少分」(&「原始ヒッグス場抵抗の増加分」)の総和にしたがって、移動するだけにすぎないことになる。
※なお、“点磁極”の場合だけではなく、“棒磁石”の場合であっても、同様に説明できる。
※なお、重力の場合は、2つの質点の、間の時空でも、外側の時空でも、原始ヒッグス場ユニットの変形は、どちらも加算する(足し合わさる)一方である。
2、周囲にN極の“点磁極”を持ってきた場合。
下図が、N極1の仮想的な“点磁極”が中心にあるようすを示すモデルである。(1の場合の最初の条件と全く同じである)
※中心にN極1の仮想的な“点磁極”があるときのモデルである。
原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”の変形(つぶれ=ピンクの部分)が大きいほど、「元の立方体」は、より小さくなっていることが示されている。
|
ここに、N極2の仮想的な“点磁極”を持ってくると──
↓
※以下、“4面体”とは、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”こととする。
N極1と、N極2の間の時空(緑色の線で囲った領域)では、「N極1による“4面体”の変形(=ミクロ磁場)」と、「N極2による“4面体”の変形(=ミクロ磁場)」が、互いに逆を向いている。
よって、ここでは、ミクロ磁場のキャンセルが生じる。
例えば、N極1とN極2の間にある時空における、“4面体”の変形の幅の長さをそれぞれ、aN1[m]、bN2[m]とすると、その地点での“4面体”の変形幅の総和は、│aN1−bN2│[m]と計算できる。
一方、N極1とN極2の間の反対側にある外側の時空(オレンジ色の線で囲った領域)では、「N極1のによる“4面体”の変形(=ミクロ磁場)」と、「N極2による“4面体”の変形(=ミクロ磁場)」が、同じ方向を向いている。
よって、ここに、ミクロ磁場の加算が生じると考えられる。
例えば、N極1とN極2による“4面体”の変形の幅の長さをそれぞれ、aN1[m]、bN2[m]と書くと、その地点での“4面体”の変形幅の総和は、aN1+bN2[m]と計算できる。 |
N極1とN極2の間の時空では、“4面体”の変形が“キャンセルされる”だけであるの対し、N極1とN極2の外側の時空では、“4面体”の変形が“加算する”(足し合わさる、増加する…)。
この結果、N極1とN極2の間には、斥力が生じるように見えるのである。
すなわち、N極1とN極2は、それぞれが作る「原始ヒッグス場抵抗の減少分」(&「原始ヒッグス場抵抗の増加分」)の総和にしたがって、移動しているにすぎないことになる。
※やはり、“点磁極”の場合だけでなく、“棒磁石”の場合であっても、同様に説明できる。
※やはり、重力の場合は、2つの質点の、間の時空でも、外側の時空でも、原始ヒッグス場ユニットの変形は、どちらも加算する(足し合わさる)一方であることと対照的である
※やはり、磁極の間に働く“斥力”も“引力”も、結局は、「原始ヒッグス場抵抗」に従って磁極が移動する結果(=“原始ヒッグス場抵抗”がより小さい方へより小さい方へと移動しやすいという傾向”にしたがって磁極が移動する結果)、そこに生じているように見える力にすぎないことになる。
もし、2つのマイナス電荷が軌道運動せずに、近くに存在していたとしたら、それら2つのマイナス電荷の間には、斥力が生じるだけである。
しかし、2つのマイナス電荷に、“軌道運動”という要素が加わるだけで、斥力のみならず、引力をも生じうるようになる。
(なお、“軌道運動”という要素が加わるだけで、斥力のみならず、引力をも生じうるようになることは── 2つのプラス電荷の間においても同様に成り立つ)
このことから、『N極やS極が「電荷の軌道運動によって」生じている』ということは、磁力の本質であると思われる。
以下で、このことについて、『マイナス電荷の軌道運動』によって生じる磁場にしぼって、より詳しく説明する。
まず、マイナス電荷(の中の左巻き素スピノール)の軌道運動(上から下へ)にともなって、どのように原始ヒッグス場ユニットが変形し、ミクロ磁場が生じるかは、下図のようになる。
※軌道運動の方向は、両方とも“上から下”なのに、原始ヒッグス場ユニットとの位置関係が違うだけで、生じるミクロ磁場は、180度向きが逆になっているのが読みとれる。
|
今度は、逆に、下から上へのマイナス電荷(の中の左巻き素スピノール)の軌道運動にともなって、どのように原始ヒッグス場ユニットが変形し、ミクロ磁場が生じるかは、下図のようになる。
※やはり、軌道運動の方向は、両方とも“下から上”なのに、原始ヒッグス場ユニットとの位置関係が違うだけで、生じるミクロ磁場は、180度向きが逆になっていることが読みとれる。
|
以上の、マイナス電荷の上下方向の軌道運動に伴う、4種類のミクロ磁場の生じ方の要点を整理すると次のようになる。
※マイナス電荷の上下方向の軌道運動に伴って、4種類のミクロ磁場の生じ方がある。
なお、生じるミクロ磁場は、2種類だけであることが読みとれる。
|
ここで、もし、「マイナス電荷の軌道運動」が、ある“回路”の中での運動だとすればどうなるか?
この回路における「マイナス電荷の軌道運動」は、“時計回りと、反時計周り”の2通り考えられる。
まず、1つめとして、下図のような「マイナス電荷の軌道運動」が“反時計周り”の回路の場合(なお、電流は時計回りの場合である)を考える。
※電流の向きと、マイナス電荷の軌道運動の向きは、逆である。
アンペールの法則に従うように、マクロの磁場が創発している。 |
この場合、(共転回のペアが作るベクトルの向きが水平となる)「4つのタイプのミクロ磁場」の生成の中で、相対的に優位なるのは、次の2つのタイプの「ミクロ磁場」の生成(ピンクの○で囲ってある)に他ならない。
※ピンクで囲ってある、優位になるミクロ磁場は── アンペールの法則で説明されるマクロ磁場と、ぴったり合致しているのがわかる。
※「軌道運動による相対的な優位性」が、磁場を生むのだという説明は、特殊相対性理論による説明と、調和していると思われる。
|
次に、2つめとして、下図のような、「マイナス電荷の軌道運動」が“時計周り”の回路(なお、電流は反時計回りである)を考える。
※今回の「電流の向き、マイナス電荷の軌道運動の向き、およびマクロの磁場の向き」は、すべて、前回とは逆になっている。
やはり、アンペールの法則に従うように、マクロの磁場が創発している。 |
この場合、(共転回のペアが作るベクトルの向きが水平となる)「4つのタイプのミクロ磁場」の生成の中で、相対的に優位なるのは、次の2つのタイプの「ミクロ磁場」の生成(ピンクの○で囲ってある)に他ならない。
| ※ピンクで囲ってある、優位になるミクロ磁場は── アンペールの法則で説明されるマクロの磁場と、ぴったり合致している。 |
このように「優位になるミクロ磁場を“どちらか一方に絞り込む”」という意味が、「マイナス電荷が回路を軌道運動する」ということにあることがわかる。
そして、このようなしくみによって、「マイナス電荷の軌道運動」を通じて、マクロの磁場が創発するのである。
以上のしくみが、「同じマイナス電荷が互いに静止していれば、斥力のみが生じるのに、その運動のしかたの違いだけで、斥力のみならず引力が生じるようになる理由」を説明するカギである。
以上をふまえて、次のような、N極とS極がある場合のモデルを、もう一度見つめ直してみよう。
この場合、N極とS極の間の時空(緑色の線で囲った領域)では、(水平な4つのタイプのミクロ磁場生成の中で)「マイナス電荷の運動よって相対的に優位になるミクロ磁場」は、N極によって作られるものも、S極によって作られるものも両方とも、次の「ピンクで囲った2つのタイプ」のものになる。
すなわち、N極とS極の間の時空(緑色の線で囲った領域)では、同じタイプの(共通の)ミクロ磁場が優位なるのだ。
※N極とS極の 間では、N極によって優位になるミクロ磁場と、S極によって優位になるミクロ磁場が、ともにピンクで囲った2つのタイプになる。
このことは、磁場を作るマイナス電荷の軌道運動の向きが同じになるので、「N極による反時計周りの効果」と「S極による反時計回りの効果」が等しくなり、優位になるミクロ磁場が増加(増幅、加算)するのみ、すなわち、“原始ヒッグス場ユニットの変形”も増加するのみになる、ということになる。
一方、N極とS極の外側の時空では── S極の中の“マイナス電荷の運動の向きが逆になることによる効果が生じる”ので、「N極による反時計周りの効果」と「S極による時計回りの効果」が異なるようなり(「S極による時計回りの効果」によって下図の青色で囲ったタイプが優位となり)、“原始ヒッグス場ユニットの変形”のキャンセルが生じることとなる。
※N極とS極の外側の時空では、N極によって優位になるミクロ磁場(ピンク色で囲んだ)と、S極によって優位になるミクロ磁場(ブルーで囲んだ)が、互いに逆向きになるため、磁場のキャンセルが生じる。
※なお、1つの原始ヒッグス場ユニットに対して、同時に変形が生じることによってはじめて、ミクロ磁場のキャンセル、すなわち、「原始ヒッグス場抵抗の増大」が生じると考えられる。
(図から、それが可能であることが読み取れる)。
|
よって、以上より、「磁極の間の加算」と「磁極の外側のキャンセル」の効果がトータルされて生じる「原始ヒッグス場抵抗」に従って磁極が軌道運動する結果、N極とS極の間には引力が生じるように見えるのは、結局は、「マイナス電荷の軌道運動」が原因であることがわかる。
逆に、次のような、N極とN極がある場合のモデルにおいても、同様に、軌道運動を介して、考えることができる。
すなわち、N極1とN極2の間の時空(緑色の線で囲った時空)では── N極2が作る磁場は、“S極の場合と逆向きに軌道運動するマイナス電荷”によって生じるようになるので、“原始ヒッグス場ユニットの変形”のキャンセルが生じることになる。 キャンセルが生じるということは、単に、「相対的に運動していないマイナス電荷同士の間の電磁場の状態」に近づくことをも意味する。 すなわち、このミクロ磁場のキャンセルの効果は、“斥力”が生じる方向に働く。
一方、N極1とN極2の外側の時空(オレンジ色の線で囲った時空)では── “( N極1とN極2を構成する)マイナス電荷の軌道運動の向きが同じになるので”、マイナス電荷の運動によって優位になるミクロ磁場が増加(増幅、加算)するのみとなる。 ミクロ磁場が増加(増幅、加算)するということは、「原始ヒッグス場抵抗」が減ることを意味する。 すなわち、このミクロ磁場が増加(増幅、加算)の効果は、やはり、“斥力”が生じる方向に働く。
つまりは、「磁極の間のキャンセル」と「磁極の外側の加算」の効果がトータルされて生じる「原始ヒッグス場抵抗」に従って磁極が軌道運動する結果、N極とN極の間には斥力が生じるように見えるのは、結局は、「マイナス電荷の軌道運動」が原因であることがわかる。
以上より、磁極の間で引力や斥力が生じる理由は、次の2つに要約できる。
1. N極も、S極も、両方ともに、「左巻き素スピノールのみで構成されたマイナスプレオンの軌道運動によって、相対的に優位になる“4面体”の変形」のおかげで創発している。
2. 原始ヒッグス場ユニット“4面体”の変形がより大きいほど、その方向へ移動する際の抵抗が小さくなるので、その方向へ進みやすくなる。
※なお、以上のモデルは、仮想的な点磁極を想定した説明であった。
しかし、実際は、モノポールは、存在しないと考えられるので、実際は、N極とS極の両方を持つ磁石が、2つ近くに存在する場合を考えなければならい。
N極とS極の両方を持つことは、永久磁石、電子、電磁石どれも、共通する。
例えば、1つの磁石のモデルを図示すると次のようになる。
| ※磁石の場合は、点磁極の場合とは異なり、「“電荷の軌道運動”の逆転」が存在しなくなっている。すなわち、磁石の中のどの場所においても、「“電荷の軌道運動”」の向きが一定となっている。 |
例えば、この磁石が2つ並ぶ場合、どうなるであろうか?
大きく3つのパターンが考えられる。
1.磁石が単純に引き合う場合
※おおよその図である。
磁石中の、どこの場所においても、「“電荷の軌道運動”の方向」は、同じである。
すなわち、「“電荷の軌道運動”の逆転」が存在しない点で、“点磁極”の場合とは異なっていることが読み取れる。
※磁石同士が結びついたものは、「N極とS極の1つのペアを持つ1つの磁石」と見なすことができる。
|
2.磁石が単純に離れ合う場合
※おおよその図である。
やはり、1つ1つの磁石中においては、どこの場所においても、「“電荷の軌道運動”の方向」は、同じである。
しかし、2つの磁石の間では、「“電荷の軌道運動”の方向」が全く逆向きである。
その結果、2つ磁石の間には、斥力が生じ、単純に、互いに離れるよう運動をする。
※厳密に考えれば、「左の磁石のN極と、右の磁石のS極」、および、「左の磁石のS極と、右の磁石のN極」は、引き合う力が働いているはずである。
しかし、これらよりも、「左の磁石のN極と、右の磁石のN極」および「左の磁石のS極と、右の磁石のS極」の間の斥力の合計の方が大きいために、互いに離れる運動となる。
|
3.磁石が回転する場合
※おおよその図である。
例えば、左の磁石を完全に固定し、右の磁石を中心だけを固定して、回転できるようにすると── 磁石は、回転するだろう。
これは、“コンパス(方位磁石)の動き”であり、“磁気モーメント”とも関連する運動である。
この回転運動は、「左の磁石のN極と、右の磁石のS極」、および、「左の磁石のS極と、右の磁石のN極」は、引き合う力が働き、「左の磁石のN極と、右の磁石のN極」および「左の磁石のS極と、右の磁石のS極」の間の斥力が働いているから、こそ生じるものである。
|
これらの説明は、次の仮説と調和している。
仮説2.6 異種の磁極──N極とS極が近くにある場合、その間の原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の個々の“4面体”の変形は、増幅する。
同種の磁極──N極&N極(orS極&S極)が近くにある場合、その間の原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の個々の“4面体”の変形は、キャンセルされる。
そして、以上より、次の結論に至ることができる。
結論2.2 静電気力と磁力の“引力&斥力”も、「仮想光子&変形した“4面体”の総和」として創発する電磁場を介して生じる力、すなわち、「“原始ヒッグス場抵抗”の減少や増加の所産」によって、そこに生じているように見える力として、統一できる。
つまり、電磁気力はすべて、「仮想光子&変形した“4面体”の総和」として創発する電磁場を介する力であり── 結局は、電荷や磁荷を持つ物体が“原始ヒッグス場抵抗”がより小さい方へより小さい方へと進みやすいという傾向”によって、そこに生じているように見える力であることになる。
そして、一方、重力は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として創発する重力場を介する力であり── 結局は、質量を持つ物体が、“原始ヒッグス場抵抗”がより小さい方へより小さい方へと進みやすいという傾向”によって、そこに生じているように見える力であった。
したがって、次の結論を得る。
結論2.3 電磁気力(静電気力&磁気力)と重力は、ともに、「“原始ヒッグス場抵抗”の変化の所産」によって、そこに生じているように見える力として、統一できる。
※なお、数式上は、すでに、電磁気力と重力を統一できることを示した。(→結果1)
今回は、幾何的な実体像をともなったものとして、“引力や斥力”についての説明も含めて、電磁気力と重力を統一できることを示せたということである。
この成果は、アインシュタインが晩年に探究した「電磁気力と重力の両方を幾何で説明する」 という目標の達成のために貢献できるだろうと思われる。
※以上の説明は、アインシュタインの相対性理論における考え方、および、ファラデー&マクスウェルの持っていた考え方、すなわち、場を媒介にして力が伝えられるという考え方とも調和している。
正しければ── 実際には、重力は“重力子の交換”によっては生じていないし、電磁気力も“光子の交換”によっては生じていないことになる。
実際、「重力子や仮想光子を放出して、相手に与える」という“キャッチボール”を、無限遠方の質量や電荷に対して行なうのは、至難の業ではないだろうか?
キャッチボール(湯川型の相互作用)による力の媒介は、あくまで、きわめて狭い範囲でのみ働く力(核力、強い力、弱い力…)限定で行なわれると考えるとすっきりとすると思われる。
詳細な検討は、今後の課題である。 (→下記 《1次的〜3次的な力》)
《中性プレオンの起源》
電荷を持つプレオン∴(マイナスプレオン、プラスプレオン)のみならず、「電荷を持たないプレオン∴」も重要である。
なぜなら、電荷0のニュートリノや、+2/3の電荷を持つアップクォーク、−1/3の電荷を持つダウンクォークが存在できるのは、「電荷を持たないプレオン∴」が存在するからこそだからである。
この「電荷を持たないプレオン∴」のことを、“中性子”の呼び方にならって、“中性プレオン”と呼ぶこととする。
この中性プレオンが“中性”であることの起源は、何か?
それは、3つの素スピノールからなるプレオン∴自身の中に、“自ら共転回を駆動(ドライブ)する原因がない”ことに他ならない。
よって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、次の仮説を立てる。
仮説2.7.1 (電荷を持たない)中性プレオンとは、右巻き素スピノールと、左巻き素スピノールが混在するプレオン∴のことである。
|
中性プレオン
|
|
プラスプレオン
|
マイナスプレオン
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の表記
|
|
|
|
|
素スピノールの構成
|
右巻き左巻きが混在
|
右巻きのみ
|
左巻きのみ
|
|
電荷
|
電荷0
|
+1/3の電荷
|
−1/3の電荷
|
|
「パウリの排他律にもとづいて、
“自ら共転回を駆動(ドライブ)する」
という意味での共転回の原因
|
なし
|
あり
|
あり
|
|
仮想光子の放出源として働く能力
|
ない
|
ある
|
ある
|
|
スピン
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
|
簡略表記
|
0∴
|
+∴
|
−∴
|
|
※ 右巻き左巻きが混在することによって── 「パウリの排他律にもとづいて、“自ら共転回を駆動(ドライブ)する」という意味での共転回の原因が消失している。 これが、中性プレオンの電荷が中性たる所以である。
|
中性プレオンと、その反粒子(反中性プレオン)の違いは、どのように説明されるのだろうか?
まず、考慮すべきは、左巻き素スピノールと右巻き素スピノールが混在するプレオンの構成は、素スピノールの組み合わせが次の2種類のものしか考えられないことである。
すなわち、「左巻き素スピノール2つと、右巻き素スピノール1つ」か、「左巻き素スピノール1つと、右巻き素スピノール2つ」かだけであり、それ以外の組み合わせは存在しないのである。
よって、次の仮説を立てた。
仮説2.7.2 中性プレオンは、左巻き素スピノール2つと、右巻き素スピノール1つからなり、反中性プレオンは、左巻き素スピノール1つと、右巻き素スピノール2つからなる。
中性プレオンと、反中性プレオンの違いを整理すると次のようになる。
|
中性プレオン
|
|
反中性プレオン
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の表記
|
|
|
|
素スピノールの組み合わせ
|
左巻き2つ、右巻き1つ |
左巻き1つ、右巻き2つ |
|
簡略表記
|
0∴
|
_
0∴
|
|
スピン
|
1/2
|
1/2
|
|
トータルで
左巻きか右巻きのどちらか?
|
左巻き
|
右巻き
|
中性プレオンと反中性プレオン関係は、互いに、右巻きと左巻きをすべて逆にしたものであると言える。
※実質的には、中性プレオンか反中性プレオンかは、相対的なものに過ぎないと言える。
すなわち、仮に、中性プレオンが「左巻き1つ、右巻き2つ」からなり、反中性プレオンが「「左巻き2つ、右巻き1つ」からなると決めても、結果的に、つじつまがあうと思われる。
ただし、本論文では、便宜上、上の仮定のように、「中性プレオンは、左巻き素スピノール2つと、右巻き素スピノール1つからなり、反中性プレオンは、左巻き素スピノール1つと、右巻き素スピノール2つからなる」と決めて説明を進めることとした。
(なお、このように決めと、「中性プレオンは、トータルで、左巻き、反中性プレオンは、トータルで右巻き」「左巻き電子ニュートリノは、中性プレオン×2+反中性プレオン×1、右巻き反電子ニュートリノは、中性プレオン×1+反中性プレオン×2」と説明できるので── 「反電子ニュートリノが右巻きしか見つかっていない」ことを比較的スムーズに説明しやすくなる
(→詳細は、のちほど))
※結果5で、詳しく見ていくように、上図の反中性プレオン(右巻きプレオン)は、“中性プレオン(左巻きプレオン)の鏡像”と全く同一である。
((上図にも示した)次の“右巻き反中性プレオン”を──
ぐるりと(コインを裏返すように)回転させると、下記の右側に相当する「“左巻き中性プレオンの鏡像”(=“右巻き中性プレオン”)」と全く同一であることがわかる)
つまり、右巻き中性プレオンと、右巻き反中性プレオンは、全く同一の実体となる。
(この説明は、“マヨナラ粒子”と関連する。 →結果5)
《プレオン∴による、電子やクォークなどの、より正確な表記》
プラスプレオン+∴ マイナスプレオン−∴のみならず、中性プレオン0∴ 反中性プレオン
|
_
0∴
|
を用いることで── |
| 電子やクォークなどの表記を、より具体的に&正確にできるようになる。 |
|
|
|
|
電子
|
陽電子
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
|
|
スピン
|
1/2
|
1/2
|
|
簡略表記
|
−∴
−∴ −∴
|
+∴
+∴ +∴
|
|
電荷
|
−1
|
+1
|
|
|
アップクォーク
|
ダウンクオーク
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
|
|
スピン
|
1/2
|
1/2
|
|
簡略表記
|
0∴
+∴ +∴
|
−∴
_ _
0∴ 0∴
|
|
電荷
|
+2/3
|
−1/3
|
電子ニュートリノも含めて、まとめると、次のようになる。
|
|
電子
|
陽電子
|
アップクォーク
|
ダウンクオーク
|
電子ニュートリノ
|
反電子ニュートリノ
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
|
|
|
|
|
|
スピン
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
|
簡略表記
|
-∴
-∴ -∴
|
+∴
+∴ +∴
|
0∴
+∴ +∴
|
−∴
_ _
0∴ 0∴
|
0∴
0∴ 0∴
|
_
0∴
_ _
0∴ 0∴
|
|
電荷
|
-1
|
+1
|
+2/3
|
-1/3
|
0
|
0
|
|
備考
|
左巻き
|
右巻き
|
右巻き
|
右巻き
|
左巻き
|
右巻き
|
弱い相互作用をもたらすウィークボソンの1例、W-は、おおよそ次のように示すことができる。
|
|
W-ボソン
|
| “EMOES”(素スピノールからの創発モデル) |
|
|
スピン
|
1
|
|
簡略表記
|
_
−∴ 0∴
_ _
−∴ −∴ 0∴ 0∴
|
|
電荷
|
-1
|
※電子と右巻き反電子ニュートリノが結びついている。
他のウィークボソンである、W+やZ0については、後ほど説明する。
(→《ウィークボソンW−、W+、Z0と、弱アイソスピンについて》)
《色荷の起源》
電磁気力を支える電荷や磁荷と同様に、強い力を支える“色荷”も重要である。
この“色荷”は、素粒子物理学の標準模型によると、抽象的な数学(抽象的な数式、郡論、抽象的な幾何(ファインマン図)…)を駆使して生み出された、抽象的な概念に過ぎない。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、この“色荷”の幾何的な実体像を探求することができる。
以下に、その説明をする。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、“1つのクォークが、3つのプレオン∴から構成されるのに対し、グルーオンは、2つのプレオン∴から構成されるのであった。
仮説2.3.1 スピン1のグルーオンは、プレオン∴の2つから創発し、下図のようになってる。
|
クォーク
|
グルーオン
|
|
プレオンモデル相当
の簡略表記
|
○○○
プレオン∴3つ
|
○○○○○○
プレオン6つ
(=プレオン∴2つ)
|
|
素スピノールのネットワーク
(“素スピノールモデル”の表記)
|
|
|
|
簡略表記
|
∴
∴ ∴
|
∴ ∴
|
|
スピン
|
1/2
|
1
|
このことは、クォークの構成要素3つの中の2つ分が、ちょうど1つのグールオン(∴∴)に相当する”ことを意味する。
グルーオンとクォークのおおよその関係を図示すると次のようになる。
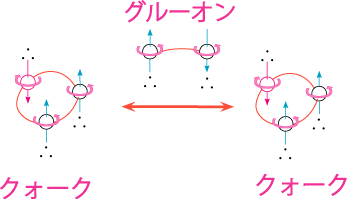 |
= |
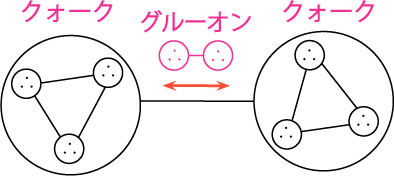 |
このことは、核力を生む“π中間子”と“陽子や中性子”の関係と、ぴったり相似になっていることに気づかれる。
すなわち、「1つの陽子や中性子の構成要素の中の2つ分(クォーク&反クォークの2つ)で、1つのπ中間子に相当すること」が、「クォークの構成要素3つの中の2つ分が、ちょうど1つのグールオン(∴∴)に相当すること”」は、ぴったりフラクタルな関係になっているのである。

※ グルーオン(=∴×2)が、クォーク(=∴×3)を結びつける。
|
|
|
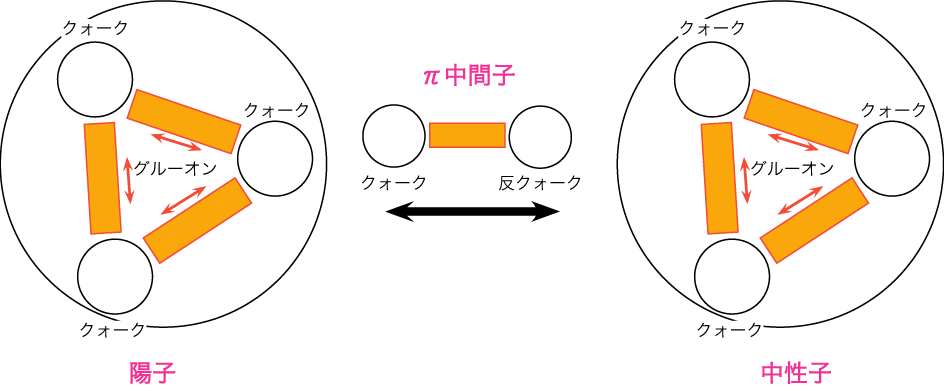 |
※ π中間子(クォーク&反クォークの2つからなる)は、陽子や中性子(それぞれ3つのクォークからなる)を結びつけている。
このことは、まさに、“フラクタル相似の原理”と調和している。
中間子が、「クォークと反クォーク」で構成されていることを参考にすると、さらに、次の仮説を立てることができる。
仮説2.8.0 1つのグルーオンは、“プレオン∴& 反プレオン∴”で構成されている。
この仮説が示すグルーオンの実体像は、先の『仮説2.3.1 スピン1のグルーオンは、プレオン∴の2つから創発し、下図のようになっている』に比べ、より具体的となっている。
※なお、π中間子によって生じる陽子や中性子を結びつける力は、“グルーオンを介する強い力”から生じる“二次的な力”と呼べる。
(“二次的な力”という表現の他にもいろいろ表現がある。 「強い力の1つの見え方」(『図解雑学 素粒子』)、「強い力の作用の間接的な結果」(『クォークとジャガー』)…)
以上をふまえ、色荷の実体像を以下で説明していく。
果たして、色荷とは、何であろうか? “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、どのように色荷を表現できるであろうか?
まず、色荷を、ある“右巻きアップクォーク”を例にして、仮説として、おおよそ次のように定義してみる。
仮説2.8.1
|
“右巻きアップクォーク”の色荷(仮説)
|
|
色荷
|
赤
|
青
|
緑
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
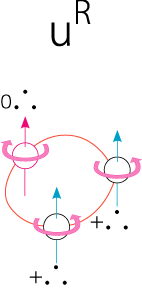 |
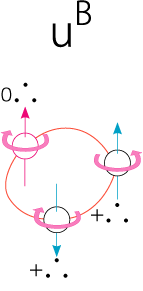 |
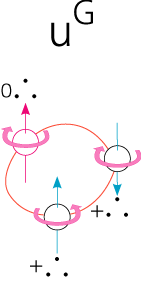 |
|
スピン1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
※プラスプレオンは右巻き、中性プレオンは左巻きであり、トータルのスピンは、すべて1/2になっている。
ピンク色で図示したプレオン∴(右巻きアップクォークuの場合は、中性プレオン)は、“電荷の少数派”であり、「3つのプレオン∴から構成されるアップクォーク」における基準となる。
この“電荷の少数派”であるプレオン∴(ここでは、中性プレオン)を基準として、総スピン1/2を保つような、(他の)2つの右巻きプレオン+∴(プラスプレオン) の配置の仕方を、ちょうど3通り考えられるので、これらを、それぞれ図のように赤、青、緑と定義した。
UR(赤)のみパウリの排他律に反している。
この唯一の「パウリの排他律」に反した赤の色荷が、実は、“色荷の絶え間ない変化”を駆動させる(創発させる)要因になると考えることができる。
電荷の場合は、「パウリの排他律にもとづいて、“自ら共転回を駆動(ドライブ)する」という意味での共転回の原因は、常に持続する(決して消滅しない)のだった。 すなわち、この性質が、電荷の保存を保証するのった。
しかし、色荷の場合は、 UR(赤)のみパウリの排他律に反しているのに対して、残りの2つの、UB(青)とUG(緑)は、パウリの排他律に反していない。
すなわち、『“自ら共転回を駆動(ドライブ)する」という意味での共転回の原因』を持っているのは( パウリの排他律に反している)UR(赤)のみであり── パウリの排他律に反していない、UB(青)とUG(緑)は、『“自ら共転回を駆動(ドライブ)する」という意味での共転回の原因』を持っていないのである。
よって、UR(赤)とUB(青)とUG(緑)の3つが1組となることによって、唯一パウリの排他律に反しているUR(赤)という駆動源をリレーすることによって、“色荷の絶え間ない変化”が創発すると考えられる。 (→詳細は、のちに説明する)
※なお、ダウンクォークにおいても、同様に、仮説として、色荷を定義できる。
仮説2.8.2
|
“右巻きダウンクォーク”の色荷(仮説)
|
|
色荷
|
赤
|
青
|
緑
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
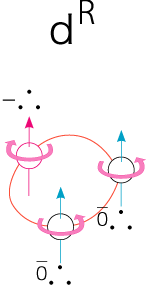 |
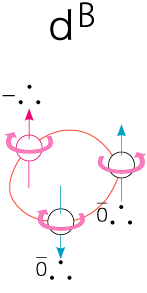 |
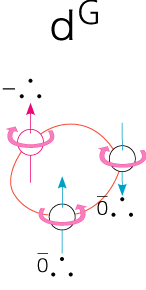 |
|
スピン1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
※右巻きダウンクォークdの場合は、電荷の少数派がマイナスプレオンであり、それがピンクで示されている。
※やはり、dR(赤)のみパウリの排他律に反している。
※マイナスプレオンは左巻き、反中性プレオンは右巻きであり、トータルのスピンは、すべて1/2になっている。
|
以上のように、アップクォークやダウンクォークが上記のような“3つの違った構造”、すなわち、“3つの色荷を持つもの”として区別できるのは、(電子やニュートリノと違い)“少数派の電荷”を持つがゆえのことであることがわかる。
つまり、00− ++0のように、ひとつだけ電荷が異なるからこそ、「3つの“色荷”」を、このように定義できるのである。
※なお、「プラスプレオンは、右巻きである」ことに抵触するような(左巻きのプラスプレオンを考えるような)、次のような定義は、実在しない(却下される)と考えられる。
|
“右巻きアップクォーク”の色荷のモデル(却下されるもの)
|
|
色荷
|
赤
|
青
|
緑
|
| “EMOES”(素スピノールからの創発モデル) |
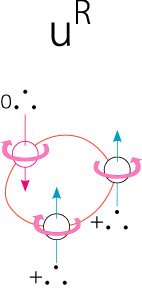 |
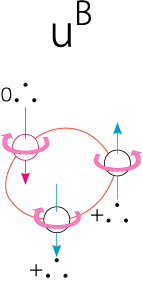 |
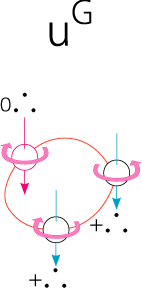 |
※プラスプレオンについて、左巻き、右巻きが混在してしまっており、そもそも「プラスプレオンは右巻き」に抵触している。
※色荷の絶え間ない変化を駆動する、パウリの排他律に反する色荷も、存在していない。
|
つまり、アップクォークにおいても、ダウンクォークにおいても、それらを構成する、3つの“プレオン∴”の“向きの組み合わせ”が、色荷の実体に相当するのである。
そして、パウリの排他律に反する色荷(赤)が、色荷の絶え間ない変化を駆動するのである。
それが、グルーオンを介して、クォークの色が変わり続けることの実体である。
その様子を詳しく説明する。
例えば、下図は、陽子(uud)の中の赤色のアップクォークがグルーオンを放出するとともに、青に変わる様子、
そして、その放出されたグルーオンを受け取った別のアップクォークの色が青から赤に変化する様子を示している。
※図のように、赤色のアップクォークの中の右巻きプラスプレオンと、プレオン∴ヒッグス場ユニットの中の左巻きマイナスプレオンが、パウリの排他律に駆動されて共転回することによって、アップクォークが赤から青に変わっている。 この過程が、グルーオン(左巻き&右巻き(プレオン∴&反プレオン∴)、スピン1)を放出することに相当する。 このとき、クォークは、赤から青へ色荷を変えているので、この放出されたグルーオンは、“赤反青”であることになる。
この際、変形しているプレオン∴ヒッグス場ユニットに、エネルギーが蓄えられる。
そのプレオン∴ヒッグス場ユニットに蓄えられたエネルギーが開放されるのに伴って、プレオン∴ヒッグス場ユニットの中の左巻きマイナスプレオンと、もう一方の青色クォークの中の右巻きプラスプレオンが、共転回することによって、そのクォークの色が青から赤に変わっている。 このことは、“赤反青”のグルーオンをこの受け取ったことを意味する。
なお、この最終段階で、緑(ダウンクォーク)が赤に変わることはない。 なぜなら、もしそうだとすると、陽子の中のクォークが、青が2つ、赤が1つとなってしまい、トータルの色荷が0でなくなってしまうからである。
※プレオン∴ヒッグス場ユニットとは、プレオン∴4つ(右巻き2つ&左巻き2つ)で構成されているヒッグス場ユニットのことである。
原始ヒッグス場ユニットが、素スピノールが4つ(右巻き2つ&左巻き2つ)でできているヒッグス場ユニットであるのと、相似になっている。 ともに“4面体”が基本形で、構成要素の転回により“4面体”のバネが変形するとともにエネルギーを蓄える。
(詳細は、結果3で説明する) |
次は、陽子(uud)の中の赤色のアップクォークがグルーオンを放出するとともに、緑に変わる様子、
そして、その放出されたグルーオンを受け取った別のダウンクォークの色が緑から赤に変化する様子を示している。
※図のように、赤色のアップクォークの中の右巻きプラスプレオンと、プレオン∴ヒッグス場ユニットの中の左巻き中性プレオンが、パウリの排他律に駆動されて共転回することによって、このアップクォークが赤から緑に変わっている。 この過程が、グルーオン(左巻き&右巻き(プレオン∴&反プレオン∴)、スピン1)を放出することに相当する。 このとき、クォークは、赤から緑へ色荷を変えているので、この放出されたグルーオンは、“赤反緑”であることになる。
この際、変形しているプレオン∴ヒッグス場ユニットに、エネルギーが蓄えられる。
そのプレオン∴ヒッグス場ユニットに蓄えられたエネルギーが開放されるのに伴って、プレオン∴ヒッグス場ユニットの中の左巻き中性プレオンと、もう一方の緑色のダウンクォークの中の右巻き反中性プレオンが、共転回することによって、そのクォークの色が緑から赤に変わる。 このことは、“赤反緑”のグルーオンをこの受け取ったことを意味する。
なお、この最終段階で、青(アップクォーク)が赤に変わることはない。 なぜなら、もしそうだとすると、陽子の中のクォークが、緑が2つ、赤が1つとなってしまい、トータルの色荷が0でなくなってしまうからである。。 |
さらに次は、陽子(uud)の中の赤色のダウンクォークがグルーオンを放出するとともに、青に変わる様子、
そして、その放出されたグルーオンを受け取った別のアップクォークの色が緑から赤に変化する過程を示している。
※図のように、赤色のアップクォークの中の右巻き反中性プレオンと、プレオン∴ヒッグス場ユニットの中の左巻きマイナスプレオンが、パウリの排他律に駆動されて共転回することによって、アップクォークが赤から青に変わっている。 この過程が、グルーオン(左巻き&右巻き、スピン1)を放出することに相当する。 このとき、クォークは、赤から青へ色荷を変えているので、この放出されたグルーオンは、“赤反青”であることになる。
この際、変形しているプレオン∴ヒッグス場ユニットに、エネルギーが蓄えられる。
そのプレオン∴ヒッグス場ユニットに蓄えられたエネルギーが開放されるのに伴って、プレオン∴ヒッグス場ユニットの中の左巻きマイナスプレオンと、もう一方の青色のアップクォークの中の右巻きプラスプレオンが、共転回することによって、そのクォークの色が青から赤に変わっている。 このことは、“赤反青”のグルーオンをこの受け取ったことを意味する。
なお、この最終段階で、緑(アップクォーク)が赤に変わることはない。 なぜなら、もしそうだとすると、陽子の中のクォークが、青が2つ、赤が1つとなってしまい、トータルの色荷が0でなくなってしまうからである。
※なお、上記に代わって、陽子(uud)の中の赤色のダウンクォークがグルーオンを放出するとともに、緑に変わり、その放出されたグルーオンを受け取った別の緑のアップクォークの色が緑から赤に変化することも考えられる。 いずれしても、放出されるグルーオンの実体は、同一の「右巻き反中性プレオン+左巻きマイナスプレオン」であることがわかる。 |
以上で、一周してきたことになる。
なお、中性子(ddu)の場合も同様に考えることができる。
すると、考えられるグルーオンは、次の8種類だけであることが、容易にわかる。
|
8種類のグルーオン
|
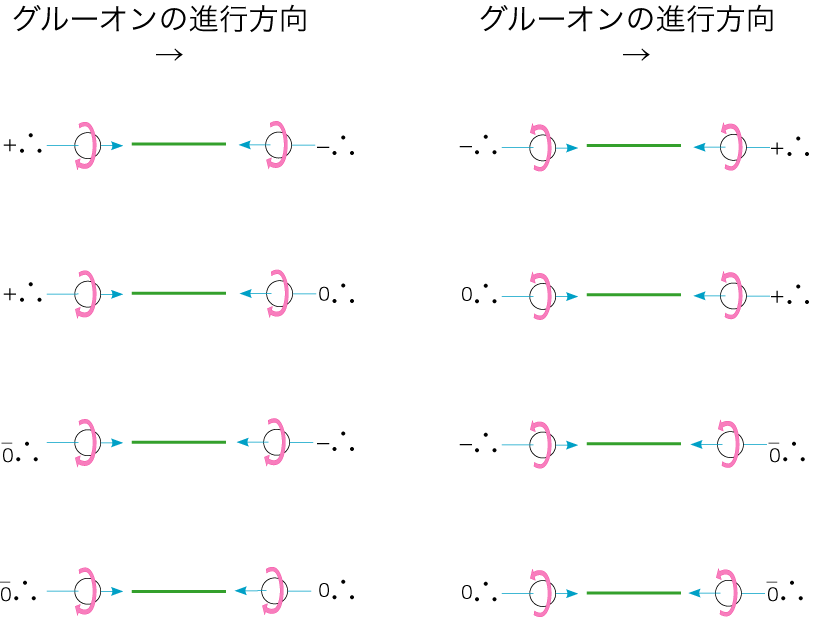 |
※考えられるグルーオンは、この8種類だけである。
※上の8つのグルーオンは、すべて、「プレオン∴&反プレオン∴のペア」になっている。
※なお、共転回は、結局は、それぞれのプレオンの中の「右巻き素スピノールと左巻き素スピノールのペア」が、行なっていると考えられる。
だからこそ、電荷の有無に関係なく、上記のようなペアを組むことができると考えられる。
|
このことは、量子色力学で考えるグルーオンが、8種類であることと、調和している。
量子色力学では、抽象的な数学(ゲージ原理(ケージ理論、局所的なケージ対称性…)、リー群、SU(3)…)によって、この8種類にたどり着いた。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、単純な幾何的な考察から、この8種類に至っている。
このことは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ゲージ原理を含め、抽象的な数学によって探求するしかなかった理論物理学に、新たな手段を提供していることを示していることの一例であると思われる。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ゲージ原理を含む抽象的な数学によって説明されてきた理論物理学の、具体的な意味、すなわち、ミクロレベルの自然(nature)についての幾何的な実体像、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…を提供していることの一例なのだと思われる。
以上の“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)よる説明は、“ゲージ原理”が意味する幾何学的な実体像は、各種のスピノールの“共転回”そのものであることを示していると考えられる。
例えば、電荷から仮想光子が生じるのは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、「電荷の素スピノールと、電磁場(原始ヒッグス場)の素スピノールがペアを作り、一緒に転回すること」によって生じている。 そして、まさに、この“共転回”そのものが、“局所的なゲージ変換を、相殺するかたちでゲージボソンが生じる”ということに相当すると解釈できる。
また、例えば、色荷から生じるグルーオンが生じるのは、プレオン∴の共転回(プレオン∴を構成する素スピノールどうしの共転回)のおかげである。そして、まさに、この“共転回”そのものが、“局所的なゲージ変換を、相殺するかたちでゲージボソンが生じる”ということに相当すると解釈できる。
よって、本来、とても抽象的な数学で示されている“ゲージ原理”について、次の仮説を立てた。
仮説 2.8.3 “ゲージ原理”、すなわち、“局所的なゲージ変換を、相殺するかたちでゲージボソンが生じる”ことは、何らかの“共転回”によって成立している。
※なお、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示す8つのグルーオンの中のどれが「“赤反青”である」などというようには、決まっていない。 すなわち、「“赤反青”も、“赤反緑”
も、その実体は、同じものである」ということがありうる。
また、詳しく調べてみると、上の8種類のグルーオンの実体は、それぞれに── 次のような“色を変える6つのグルーオン”のすべてになりうることが分かる。
|
“色を変える6つのグルーオン”
|
|
赤反青
|
青反緑
|
緑反赤
|
赤反緑 |
緑反青 |
青反赤 |
このことは、何を意味しているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
※中間子を作るグルーオンは、具体的に、どうなっているのだろうか? このことについても、詳細な検討は、今後の課題である。
《プレオン∴どうしを結びつける力》
さらに、どうしても避けられない問題がある。
それは、「そもそも、プレオン∴どうしを結びつける力の正体は何であろうか?」というものである。
例えば、電子を作るためには、−1/3の電荷を持つマイナスプレオン∴どうし“3つ”を結びつける力が必要である。
この力は、同じマイナス電荷どうしを結びつけるので── ふつうの電磁気力ではない。
また、マイナスプレオンは、“グルーオンが作用できるような色荷”を持たないので、“強い力(強い相互作用)”でもない。
当然、(弱すぎるので)重力でもない。
一方で、上の説明でも示した“グルーオンやπ中間子を介する力が持っている、フラクタル相似性”から類推すると、プレオン∴の間に働く力は、素スピノール2つに相当する“・・”のやり取りを介して生じていることが、強く予想された。 なぜなら、“フラクタル相似の原理”と合致するからである。
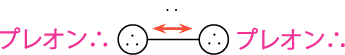
※ ・・が、プレオン(=∴)を結びつける(予想)
|
|
|

※ グルーオン(=プレオン∴+反プレオン∴)が、クォーク(=∴×3)を結びつける。
|
|
|
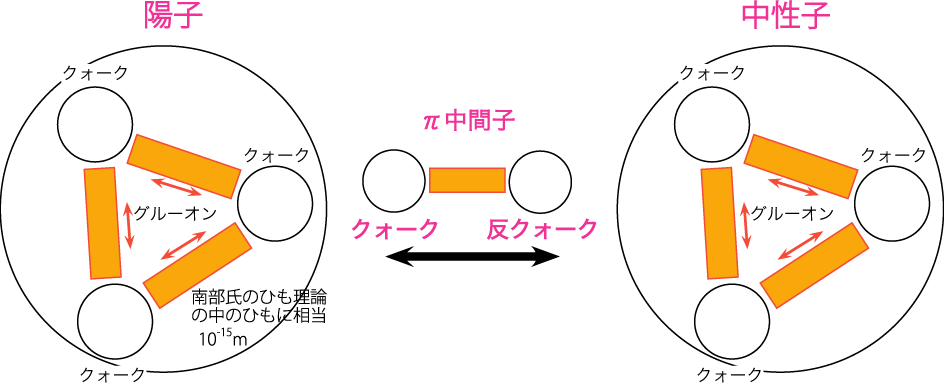
※π中間子(=クォーク+反クォーク)が、陽子や中性子(クォーク×3)を結びつける。
|
よって、次の仮説を立てた。
仮説2.9.1 プレオン∴の間で、距離LPを持つ素スピノール2つ(右巻き&左巻き)をキャッチボールする(湯川型の相互作用をする)ことにより、プレオン∴は、結びつく。
この素スピノール2つ(右巻き&左巻き)は、光子の組成と同じで、サイズがLP[m]なので── これを、便宜上、“LP光子”と呼ぶこととする。
このLP光子は、明らかに、ふつうの仮想光子とは異なる。
なぜなら、もしこれが、ふつうの仮想光子として働くとすれば── マイナスのプレオン∴とマイナスのプレオン∴の電荷の間には、当然、斥力を生じることになってしまうからである。 その結果、例えば、電子が形成されることは決してなくなってしまう。
また、このLP光子は、単なる“波長が短くなった光子”(ふつの電磁波を構成する光子)でもないと予想される。
なぜなら── “光子は波長が短くなり続けると、ある時、重力子エネルギーEGより大きくなってしまう”からである。(→下記、結果1)
こういったLP光子によって生じる力を、便宜上、“原始的な力”と呼ぶこととする。
この“原始的な力”について、先の仮説を、より詳しく書き換える。
仮説2.9.2 (プレオン∴2つからできた)グルーオンという仮想粒子を介して、湯川型の相互作用をすることで、(短い距離限定で)引力が生じたように── 素スピノール2つからできた“LP光子”という仮想粒子を介して、湯川型の相互作用をすることで、(短い距離限定で)引力のみが生じる。
※この場合の、“局所的なゲージ変換を、相殺するかたちで生じるゲージボソン”は、“LP光子”ということになる。 つまり、“ゲージ原理”を満たしていることになる。
“グルーオンやπ中間子を介する力が持っている、フラクタル相似性”から類推すると、グルーオンを介する、強い力(強い相互作用)と、LP光子を介する“原始的な力”は、荷量についても相似であることが予想される。
よって、次の仮説を立てた。
仮説2.9.3 強い力(強い相互作用)が、“グルーオン色荷”を介して働くように── “原始的な力”は、“LP色荷”を介して働く。
※“原始的な力”における色荷を“LP色荷”と呼び、ふつうの色荷(グルーオン色荷)と区別することとした。
例えば、3つの中性プレオンで構成されている左巻きニュートリノを考えてみよう。
左巻きニュートリノは、左巻き中性プレオン2つと、右巻き中性プレオン1つから構成されている。
それぞれに、ふつうの色荷と同様に、仮説として、“LP色荷”を定義できるであろうか?
できる。 確かめてよう。
|
“左巻き中性プレオン”のLP色荷(仮説)
|
|
LP色荷
|
赤
|
青
|
緑
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
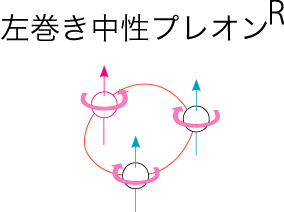 |
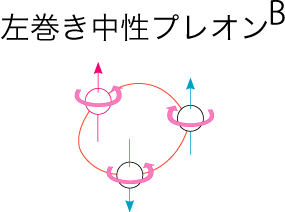 |
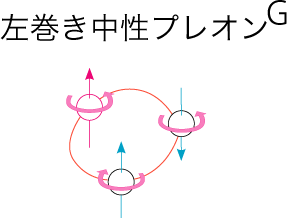 |
|
スピン1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
※少数派が、右巻き素スピノールであり、ピンクで示されている。
多数派が、ブルーの左巻き素スピノールであり、その配置は、3種類考えられる。
※トータルのスピンは、すべて1/2になっている。
※やはり、中性プレオンR(赤)のみパウリの排他律に反している。 |
※なお、右巻き中性プレオンにおいても、同様に、“LP色荷”を定義できるは、容易に確かめられる。
なぜなら、上図において、右巻きと左巻きをすべて交換するだけで定義できるからである。
※このLP色荷を荷量とする“原始的な力”によって、「左巻き中性プレオン3つが結びついて、左巻き電子ニュートリノ」が、そして、「右巻き中性プレオン3つが結びついて、右巻き反電子ニュートリノ」が、それぞれ創発すると考えられる。
(なぜなら、例えば、下図のような、「右巻きダウンクォークと、(アップクォークヒッグス場の中の)左巻き反アップクォークから」から、弱い相互作用により、W−ボソンが生じる過程において、このW−ボソンを構成する反電子ニュートリノが、「右巻き中性プレオン3つが結びついて創発している」からである。
(→《ウィークボソンW−、W+、Z0と、弱アイソスピンについて》)
|
「右巻きダウンクォークと、(アップクォークヒッグス場の中の)左巻き反アップクォークから」
|
|
弱い相互作用により)
W−ボソンに変化
|
|
|
+
|
|
→ |
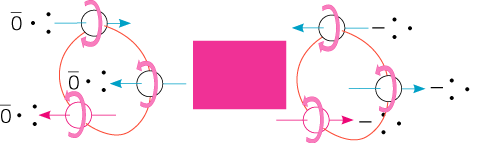 (=
(= 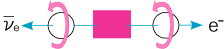 ) )
|
|
右巻きダウンクォーク
|
|
左巻きの反アップクォーク
|
|
W−ボソン
|
※W −ボソンを構成する反電子ニュートリノが、「右巻き中性プレオン3つが結びついて創発している」ことが読み取れる。)
その際、トータルの“LP色荷”は、ふつうの“グルーオン色荷”と同様に、常に、赤青緑がそろって、常に無色になるように保たれる。
このようなLP色荷のしくみがある結果、次のような構造は、パウリの排他律に反していないことになる。
※一見、3つの中性プレオンがすべて左巻き(or 3つの反中性プレオンがすべて右巻き)なので、常に、パウリの排他律に反するペア(緑で囲ってあるようなペア)が存在することになるので、ここにパウリの排他律に駆動される新たな共転回が生じ、新たな電荷のようなものが生まれるかのようにも思われるが、そのようなことは、実際にはない。
なぜなら、3つの中性プレオン(or 反中性プレオン)については、厳密に見れば、すべて“LP色荷”が異なるので(常に、トータルで無色になるように、赤青緑を網羅しているので)、(緑で囲ったようなペアも含め)パウリの排他律に反していないことになるからである。
※パウリの排他律に反しているのは、やはり、中性プレオンR(赤)や反中性プレオンR(赤)の中の“素スピノールのペア”だけである。 それは、この図だけからは読み取れない。 |
※なお、「左巻き中性プレオン2つと、右巻き中性プレオン1つが結びついているもの」や「右巻き中性プレオン2つと、左巻き中性プレオン1つが結びついていもの」は、プレオン∴ヒッグス場ユニットから“1つ”のプレオン∴を取り除いたもの、すなわち、「第二世代のプレオン∴」と呼べるものに相当すると考えられる。
電子の中の、マイナスプレオンにおいても、同様に、LP色荷を定義できる。
確かめてよう。
|
“マイナスプレオン”のLP色荷(仮説)
|
|
LP色荷
|
赤
|
青
|
緑
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
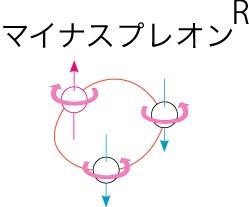 |
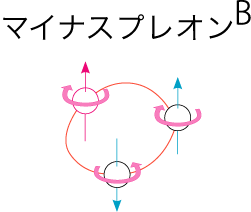 |
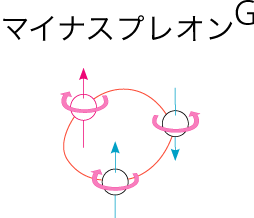 |
|
スピン1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
※マイナスプレオンは、すべて左巻き素スピノールで構成されており、中性プレオンのように、はっきり少数派が確定されることはできないが── 便宜上、形式的に、ある1つの素スピノールを基準にする。(それをピンクで示してある)
それを基準にすると、他の2つの“水色の左巻き素スピノール”の配置を、中性プレオンの場合と同様に、やはり、全部で、3種類考えられる。
※よくみると、マイナスプレオンの赤と青と緑は、どれも同じものである。
(回転させることによって、お互いに同一であることが確かめられる。すなわち、赤青緑の3つとも、パウリの排他律に反している)
しかし、それでも、“中性プレオンの場合と同様に”定義できているのは確かなので── LP色荷を介する“原始的な力”が、マイナスプレオンの間においても、存在できることになる。
すなわち、“中性プレオンの場合と同様に”定義できている以上、電子を構成する3つのマイナスプレオンは、LP色荷を介する“原始的な力”が作用する条件を満たしていることになるのである。
※トータルのスピンは、すべて1/2になっている。
|
電子を構成する、3つのマイナスプレオンの3色に対応するものの構造は、よくみると、3つとも全く同じである。
しかし、LP色荷を、このように“中性プレオンの場合と同様に”定義できる以上── “原始的な力”が作用するのに十分な条件を満たしていることになるのである。
※ただし、ニュートリノの中の“原始的な力”と、電子の中の“原始的な力”の強さは違うということは、あるのかもしれない。(詳細な検討は、今後の課題である)
プラスプレオンについても、同様に、LP色荷を定義できる。
このように中性プレオンも、荷電プレオン(マイナスプレオン&プラスプレオン)も、LP色荷を定義できることは、“原始的な力”は、プレオン∴3つを結びつけて、ニュートリノや電子を作れるのみならず、クォーク(ダウンクォークやアップクォーク)を作れることを意味する。
そして、このことは、“原始的な力”は、プレオン∴2つを結びつけてグルーオンを作ったり、電子と反電子ニュートリノの中のプレオン∴を結びつけてW−ボソンを作ったり、プレオン∴4つを結びつけてプレオン∴ヒッグス場ユニットの“4面体”および、“4角形”(縮みきったバネor四極子)を作ったりすることを支えると考えられる。
このLP光子(およびLP色荷)を介して生ずる“原始的な力”は、湯川型の相互作用の一種である。
そして、この“原始的な力”は、強い力や弱い力のもととなる、グルーオンや、ウィークボソンを生み出す力でもあるので、本当の意味で、“1次的な力”に相当すると言える。
(だからこそ、“原始的な力”という呼び方がふさわしいと思われる)
「仮想光子を介して生じる電磁気力(ふつうの電磁気力)」との関連は、どうだろうか?
ここで、「仮想光子を介して生じる電磁気力(ふつうの電磁気力)」と、「LP光子を介して生じる原始的な力(“原始的な電磁気力”)」の違いを下の表に整理しておく。
|
|
仮想光子を介して生じる電磁気力
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
による説明
|
LP光子を介して生じる原始的な力
|
|
到達距離
|
LP光子が作用する範囲より遠方
〜無限遠(※)
|
近い距離まで
(電子やクォークのサイズほどである。
ウィークボソンのサイズを考えるなら、<10-18[m])
|
|
正負の区別と
力の性質
|
正負を区別する。
引力と斥力がある。
|
正負を区別しない。
引力のみ
|
|
働き
|
クォークやレプトンのサイズ以上の
マクロの電荷どうし、磁荷どうしを
近付けたり、遠ざけたりする
|
プレオン∴どうしを結びつける
プレオン∴を閉じ込める
|
|
生じるもの
|
原子、分子、高分子…
|
電子、ニュートリノ、クォーク… などのフェルミオン
グルーオン(グルーオンの集積したひも)、ウィークボソン(LP光子の集積したひも)、プレオン∴ヒッグス場ユニット… などのボソン
|
|
力を生むしくみ
|
仮想光子の総和が作る電場 or 磁場を
介して、力を伝える。
(原始ヒッグス場抵抗がより小さい方へと
“電荷”や“磁荷”が移動することによって、
そこに生じているように見える力)
|
LP光子のキャッチボールによる
(湯川型の相互作用)
|
両者は、似ているようで、非常に違うことがわかる。 (だからこそ 、“原始的な電磁気力”という呼び方はしないこととした)
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、ふつうの電磁気力や重力は、それぞれ、「仮想光子の総和によってつくられる電磁場」、あるいは、「重力子の総和によって作られる重力場」を介して、力を伝えられているので、「湯川型の相互作用」の所産ではないと見なす。
これは、量子電磁力学(QED)において、電磁気力は、仮想光子のキャッチボールによって生じる(「湯川型の相互作用」の一種である)と見なすのとは、異なる説明である。
量子電磁力学(QED)と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の違いを下に整理しておく。
|
仮想光子を介して生じる電磁気力
|
|
量子電磁力学(QED)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
| 電磁気力が発生するしくみ |
仮想光子のキャッチボールによって生じる
(湯川型の相互作用)
|
仮想光子の総和が作る電場や磁場を
介して力が生じる
(原始ヒッグス場抵抗がより小さい方へと
“電荷”や“磁荷”が移動することによって、
そこに生じているように見える力)
|
|
発散
|
発散する
|
発散しない
|
|
繰り込み
|
繰り込みが必要
|
繰り込みが不要
|
|
到達距離
|
電荷の周囲10-19m※から
無限遠※まで
|
LP光子が作用する範囲より遠方〜無限遠(※)
|
※QEDの適用限界について次のような記述がある。
『マクロのスケールでは地球や木星磁場の存在、銀貨系磁場の存在により、数万光年つまり10+22cmまで適用可能である』
(『素量子物理学の基礎I 』 p.131 朝倉書店)
|
『距離になおすと10-17cmまでQEDが正しく適用できることがわかっている』とある。(『素量子物理学の基礎I 』 p.131 朝倉書店)
なお、一方、LP光子が作用する範囲は、LP=1.616×10-35[m]〜10-18[m](=10-16[cm])である。
このことは、おおよそ、電磁気力と“原始的な力”の分業(すみわけ)が成立していることを意味すると思われる。
※一方、次のような記述もある。
『マクロのスケールでは地球や木星磁場の存在、銀貨系磁場の存在により、数万光年つまり10+22cmまで適用可能である』とある。(『素量子物理学の基礎I 』 p.131 朝倉書店)
|
したがって、厳密には、本当に無限遠方まで適用可能かどうかどうかを確かめることは不可能なのだと思われる。
QEDにおいても、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)においても、本当に無限遠方まで電磁力の影響が及びうるのかどうかは、検討が必要であると思われる。
電磁気力は、ダイレクトで遠方まで作用するのではなく、“電子ヒッグス場ユニット(電子2つ&陽電子2つの計4つからなる)”(→真空の誘電率と関連?)を介して、飛び飛びで作用していることも考えられないだろうか。
詳細な検討は、今後の課題である。
|
《プレオン∴の閉じ込め》
“クォークは閉じ込められている”ので、(ふつうの状態では、陽子、中性子、中間子などから)クォークを単独では取り出すことができない。
“クォークの閉じ込め”が成立する理由は── グルーオンが増幅するために、クォーク同士が遠ざかれば遠ざかるほど、強い力の引力が大きくなる性質、すなわち、「漸近自由の性質」を、強い力が持つことである。
一方、電子やクォークを構成するプレオン∴も、観測されていないので、(現在の宇宙の状態で)“閉じ込められている”と考えられる。
この“プレオン∴の閉じ込め”は、どのようなしくみで起こるのであろうか?
以下で、その説明をする。
まず、LP光子のサイズ(素スピノールの間の距離)が長さLP[m]であるということは、LP光子の波長λが、その2倍の2LP[m]であることを意味する。
まず、プレオン∴同士の距離が短くて、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)を介さない場合は、次のようになる。
|
※例として、左巻きニュートリノの中にある、右巻き中性プレオンと、左巻き中性プレオンの間に生じているLP光子のやり取りを図示している。
原始ヒッグス場ユニット(PHU)を介さずに、ダイレクトに、LP光子が移動している。
※右巻き中性プレオンの、はじめのLP色荷は、赤である。
(パウリの排他律に反するペア(緑で囲ったペア)を持つプレオンの“LP色荷”が、赤であった)
この赤の中性プレオンが、パウリの排他律に反することに駆動されて、図のようなペア(緑で結んだペア)の間に共転回が生じている。
※共転回が終了すると、左巻き中性プレオンが、赤になっている。
(パウリの排他律に反するペア(緑で囲ったペア)を獲得している)
|
1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)を介する場合は、次のようになる。
※プレオンの中のピンクの素スピノールが、少数派の素スピノールである。
最初は、左側の右巻き中性プレオンの、LP色荷が、赤であることがわかる。
その赤のLP色荷が持つ、パウリの排他律に駆動されて、最初の共転回が生じている。
その最初の共転回により、原始ヒッグス場ユニットに、エネルギーが蓄えられる。
次に、そのエネルギーが開放されるともに、新たな共転回が生じ、今度は、右側の中性プレオンのLP色荷が、赤に変化している。
※強い力(グルーオン&色荷あり)の働く過程と、この“原始的な力”(LP光子&LP色荷あり)が働く過程は、相似であることがわかる。
このことは、“フラクタル相似の原理”と調和していることを意味している。
|
ところで── “電磁波を構成する光子は、波長が短くなり続けると、ある時、重力子エネルギーEGを越えてしまう”のだった。
また、結果1の『光子の波、重力子の波』で、次のように説明した。
『重力子1つが持つエネルギーEGを重力子エネルギーと呼ぶこととする。
その意味は、波長2LPの光子2つ分が持つエネルギーch/LPを、(2π)2で割ったものであり── ch/LP−ch/(2π)2LPは、波長2LPの光子2つが、重力子1つになる際に放出する、“結合エネルギー”に相当すると考えられる。
(2π)2≒39.4なので、その結合エネルギーは、1つの重力子が持つエネルギーのおよそ38.4倍であることになる』
このことは、上図のように、波長が2LPの光子1つ分が持つエネルギー(=LP光子のエネルギー)は、重力子エネルギーEGよりも、38.4/2=19.2倍程も大きいことを意味する。
このように、LP光子のエネルギーが、重力子エネルギーよりも19倍ほど以上も大きい場合、何が起きるであろうか?
そこで、次の仮説を立てた。
仮説2.10.1 あるプレオン∴から生じた、LP光子が、原始ヒッグス場ユニットに作用する場合── 下図のように、“4角形”(縮みきったバネ)が次々と作られ続けることによって、増幅し、その過程は、次のプレオン∴に到達するまで続く。
※もう一方のプレオンにたどり着くまで、“4角形”(縮みきったバネ)の変形が増幅し続けている。
※これが、「LP光子の集積したひも」に相当する。
ひもといっても、ふにゃふにゃしておらず、“ピンと張って”いるので、弦(string)と呼ぶこともできる。(→下記♯)
※「LP光子の集積したひも」を構成する“4角形”(縮みきったバネ)は、見た目は、それぞれの構造が、重力子によって生じるものと全く同じである。 中性プレオンと共転回する右はじの“4角形”(縮みきったバネ)は、(新たに共転回する)右巻き中性プレオンとの共転回で解消されるので、重力子を放出しないのは明らかである。 一方、「LP光子の集積したひも」を構成する残りの“4角形”(縮みきったバネ)は、それぞれ1つの重力子を放出するか、(新たに共転回する)右巻き中性プレオンにすべて吸収されるかして、解消されることになると考えられる。(詳細な検討は、今後の課題である)
いずれにしても、「LP光子の集積したひも」は、「重力子の放出源とし働き続ける能力」を持っていない以上、「LP光子の集積したひも」は質量を持っていないことになる。
すなわち、「LP光子の集積したひも」がピンと張りながらまるごと移動するようことは考えられないのである。
※LP光子のサイズが、1プランク長(1LP、約10−35m)に固定されているらこそ、すなわち、原始ヒッグス場ユニット(“4面体”)のサイズに近いからこそ、(グルーオンがグルーオンの増幅を起こすのと同様に)LP光子が“LP光子の増幅”を生じうる。 例えば、もしγ線を構成する光子程度のサイズであれば、原始ヒッグス場ユニットのサイズと比べて大きいので、このような増幅は起こりえない。
※例として、電子ニュートリノを構成する、左巻き中性プレオンについて図示してあるが、電子を構成する左巻きマイナスプレオン、クォークを構成する各プレオンにおいても、同様に図示できる。
※もしかしたら、「LP光子の集積したひも」は、下図のような、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の連星のような構造を考慮した方が、より正確なのかもしれない。詳細な検討は、今後の課題である。
|
この“4角形”(縮みきったバネ)が増幅する過程は、光速で伝わると考えられる。 (なぜなら、共転回の周期の1/2のT/2(=LP/c)の間に、進む距離がLPであるからである)
この増幅の過程は、相手のプレオンにたどり着いて共転回が始まるまで続き、その後は、“4角形”(縮みきったバネ)が、何らかの形で解消されると考えられる。
一部が速やかに重力子を放出することによって解消しされるのか、すべてがプレオン∴に吸収される形で解消されるのかについての、詳細な検討は、今後の課題である。
いずれにせよ、「LP光子の集積したひも」は、重力子の放出源として働き続ける能力を持を持っていないので、「LP光子の集積したひも」は、質量を持っていないことになる。
この「LP光子の集積したひも」は、当然、ニュートリノのみならず、電子やクォークの中にも、存在すると考えられる。
♯『素粒子論はなぜわかりにくいのか』(吉田信夫 技術評論社、p.171)の中に次のような記述がある、
|
『オリジナルなひも理論は、中間子がひも状だと仮定すると高エネルギー実験のデータが説明できることから考案された。「ひも」と言う呼称はそのころから使われているが、ひもの状態を調べたところ、強い張力が作用して常にピンと張っていなければならないことが判明したため、現在では、「弦」と呼ばれる方が多い。
中間子がひもだという見方は、やがて場の量子論に基づく複合粒子のアイデアに取って代わられるが、ひも理論の研究者は、長年扱ってきた理論を見捨てるに忍びず、今度は、電子やクォークなどの素粒子がひもという見方を提案した。』 (下線は、筆者による。)
|
ひも理論(超弦理論)については、別のところで詳しく述べるが(→考察3)、この文章から、有用なヒントを得られる。
すなわち、1つは、『ひもの状態を調べたところ、〜常にピンと張っていなければならないことが判明』という記述は、上記の“LP光子の集積したひも”の説明と調和していることである。
そして、もう1つは、電子やクォークなどが“ひも”だとすると、その電子やクォークなどの“ひも”の実体を担うものは、まさに、“LP光子の集積したひも”であると考えられることである。
さらに、次の仮説を立てた。
仮説2.10.2 プレオン∴間の距離が遠ざかるほど、“LP光子の増幅”が大きくなり「LP光子の集積したひも」のエネルギーが大きくなるので、“原始的な力”は、“漸近自由”の性質を持つことになり、このしくみによって、“原始的な力”は、プレオン∴を、グルーオンやクォーク、そして、レプトン(電子、ニュートリノ…)の中に閉じ込める。
この“プレオン∴の閉じ込め”の仮説は── 現在、なぜ、“電子やクォーク、グルーオンの内部構造”が観測されないのかを説明する。
つまり、少なくとも、これまでの観測結果は、この“プレオン∴の閉じ込め”の説明を支持するものである、ということになる。
※プレオン∴が「LP光子の集積したひも」によって閉じ込められていることは、“グルーオンの集積したひも”によってクォークが閉じ込められていることと相似である。
※この“原始的な力”は、現在も“到達距離が非常に短い”レベルで、活躍し続けていると考えられる。
その活躍の場は、現在の宇宙では、グルーオンやクォーク、レプトンの“中”だけというように限られている。 しかし、 “宇宙の始まり”(ビッグバン)の直後〜グルーオンやクォーク、レプトンが生成されるまでの間には、“原始的な力”は、主役として、広く活躍していたと考えられる。
この仮説2.10.2が正しければ、次のことが予測される。
予測2.1.1 (原始ヒッグス場ユニットの“4面体”が多くを占める)ふつうの状態では(現在の宇宙の状態では)、“LP光子の増幅”が起こるために、
LP光子自体や、および、プレオン∴を、それぞれ単独に、直接的に観測することが困難である。
予測2.1.2 このプレオン∴は、クォーク以上に単独に取り出すことが困難である。
※プレオン∴が観測されにくい、“閉じ込め”以外の理由として、現在の観測手段に限界があることも考えられる。
(なお、現在の観測手段に限界があるという理由によって、例えば、電子やクォークを担う(弦理論の)弦も観測できないと考えられる)
すなわち、仮に“LP光子”や“個々の重力子”自体を観測に使うことが可能だとしても、プレオン∴は、これらの波長と同程度なので、その存在を確かめることは難しいと思われる。しかし、間接的に観測する手段も全くないだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
※LP光子による、プレオン∴を結びつける力が、“漸近自由”の性質を持つと言うことは── プレオン∴どうしの距離が小さければ小さいほど、その所産の質量(例えば、クォークや電子の静止質量エネルギー)が小さくなることを意味する。 それはすなわち、プレオン∴どうしの距離が大きければ大きいほど、(クォークや電子を構成する)プレオン∴の外部運動エネルギーが大きいことを意味し、プレオン∴どうしの距離が小さければ小さいほど、(クォークや電子を構成する)プレオン∴の外部運動エネルギーが小さいことを意味するということである。
この理由により、「プレオン∴から成るクォーク」が十分小さく(=“LP光子の集積したひも”が十分短く)、なおかつ、「クォークから成る陽子」が十分大きければ(=“グルーオンの集積したひも”が十分長ければ)── (最初に挙げた)『「質量は閉じ込めのサイズに反比例する」ので、「プレオンから成るクォークは、クォークから成る陽子よりもずっと大きな質量を持つ」』という問題が生じなくなる、と考えていいと思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
《強い力の漸近自由》
グルーオンによってもたらされる強い力には── 例えば、「クォーク同士が近づくほど、強い力が弱くなる」というような“漸近自由”の性質を持つ。
このことを説明するにあたり、グルーオンと、グルーオン場の“4面体”との相互作用について、次のように仮説を立てた。
仮説2.11.1 あるクォークから生じた1つのグルーオンがプレオン∴ヒッグス場ユニットに作用する場合、下図のように“4角形”(縮みきったバネ)が次々と作られ続けることによって増幅し、その過程は、次のクォークに到達して共転回を始めるまで続く。
※ドミノ倒し(伝言ケーム…)のように、次の色荷(カラーチャージ)を持つ粒子にたどり着くまで、グルーオンが増幅し続けている。
このドミノ倒し(伝言ケーム…)は、結局は、素スピノールの間の共転回によって、形成されていることになので、そのスピードは、光速で進むことになる。
※「グルーオンによって、プレオン∴ヒッグス場ユニットが変形してできた“4角形”(縮みきったバネ)」の構造の1つ1つは── 「 重力子によって、原始ヒッグス場ユニット変形してできた“4角形”(縮みきったバネ)」と、相似になっているのがわかる。
※右はじの“4角形”(縮みきったバネ)は、 緑のアップクォークG(orダウンクォークG)と共転回することによって解消される。
一方、「グルーオンの集積したひも」を構成する残りの“4角形”(縮みきったバネ)は、それぞれ1つの重力子に似たものを放出するか、(新たに共転回する)緑のアップクォークG(orダウンクォークG)にすべて吸収されるかして、解消されることになると考えられる。(詳細な検討は、今後の課題である)
いずれにしても、「グルーオンの集積したひも」は、「重力子の放出源とし働き続ける能力」を持っていない以上、「グルーオンの集積したひも」は質量を持っていないことになる。
すなわち、「グルーオンの集積したひも」がピンと張りながらまるごと移動するようことは考えられないのである。
|
これが、「グルーオンの集積したひも」の実体像である。
この「グルーオンの集積したひも」と「LP光子の集積したひも」は、相似であり── この説明は、“フラクタル相似の原理”と調和している。
この「グルーオンの集積したひも」は、(エネルギーを持っていても)「重力子の放出源として働き続ける能力」である質量を持っていないと考えられる。
(この説明は、個々のグルーオンが(エネルギーを持っていても)質量を持っていないこととも調和している)
この「グルーオンの集積したひも」の質量が、陽子や中性子の98%を担うのではなく、「グルーオンの集積したひも」の両端にあるクォークの外部運動エネルギーが陽子や中性子の98%を担うと考えられる。 そして、クォーク静止質量エネルギー(内部運動エネルギー(=クォークを構成するプレオン∴の外部運動エネルギー))が、残りの2%を担うと考えられる。 (同様に、中間子の質量も説明できる)
※こういった説明は、次の記述についての見直しを迫っているのだった。(結果1《質量の実体像》)
『クォークの質量
このように閉じ込められてはいても、クォークやグルーオンの性質はいろいろわかりつつある。しかし前述したように、クォークの質量は直接に測定することはできない。ハドロンの質量などを考える場合には、クォークの質量にグルーオンの集積したひもの質量を加えたものが実質的な意味をもつ有効質量であると考えられる』
(『物質の究極を探る 現代の統一理論』 p.22 (1序論──素粒子像のあゆみ(大槻昭一郎)) 日本物理学会編 培風館 下線は、筆者による)
|
『
|
|
|
|
〜“mq”はハドロンに閉じ込められたクォークの有効質量(正確には構成質量)、
mqはいわば裸のクォークの質量(正確にはカレント質量)の、それぞれの推定値である』
|
(『物質の究極を探る 現代の統一理論』 p.11の表とその説明から一部抜粋 下線は筆者による)
|
※次のような対応関係にあると考えるとすっきりすると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
『クォークの質量』
『裸のクォークの質量(正確にはカレント質量)』 |
→クォークの静止質量 |
『グルーオンの集積したひもの質量を加えたもの』
『ハドロンに閉じ込められたクォークの有効質量(正確には構成質量)』 |
→クォークの静止質量
+クォークの外部運動エネルギー
|
|
このことは、例えば、『アップクォークとダウンクォークの質量エネルギーがそれぞれ3MeV、6MeVである』と同列に、『電子の質量エネルギーが0.5MeVである』と説明されるときの電子の質量エネルギーとは、「電子の静止質量」に他ならないことと調和していると思われる。
|
さらに、次の仮説を立てた。
仮説2.11.2 クォーク間の距離が遠ざかるほど、“グルーオンの増幅”が大きくなり「グルーオンの集積したひも」のエネルギーも大きくなるので、“強い力”は、“漸近自由”の性質を持つことになり、このしくみによって、“強い力”は、クォークを、陽子や中性、中間子の中に閉じ込める。
正しければ、「グルーオンの集積したひも」が延長する距離が長くなるほど、グルーオンの増幅がより高まってエネルギーが高まると同時に、強い力がより大きくなり、逆に、「グルーオンの集積したひも」の延長する距離が小さければ小さいほど、グルーオンの増幅がより減ってエネルギーが小さくなると同時に、強い力が小さくなることになる。
この説明は、まさに、量子色力学(QCD)による説明と調和している。
例えば、次のような記述とも調和している。
『強い力の場合、二つのクォークが離れるにしたがって、グルーオン場は細いチューブ(あるいはストリング)を形成し、そのためクォークの受ける力は距離に関わらず一定の値にとどまる。エネルギーは力と距離の積であるので、二つのクォークが引き離されると、それらの持つエネルギーは距離に比例して増大していく。そして、さらに二つのクォークが引き離されていくと、単純にそれ以上引き離すよりも、その間の真空から新たにクォークと反クォークの対を生成し2つの“無色”の粒子になる方が、必要なエネルギーが低くなってしまうのである』
(『クォークの閉じ込め』 ウィキペディア 下線は筆者による)
|
『その間の真空から新たにクォークと反クォークの対を生成し』とは、具体的には、「“クォークヒッグス場ユニット”起源で、クォークと反クォークが対生成し」と理解するとつじつまがあう。
一方、次のような記述も考え合わせると──
『2つのクォークの間の「グルーオンゴムひも」の場合も、クォーク同士をさらに引き離せば、やはり切れてしまう。しかしその瞬間に、切れたグルーオンのひもの端に、クォークと反クォークが対で現れる。こうしてクォークは単独で現れることはないのである』(『図解雑学 素粒子』 クォークの閉じ込めについての記述 p184)
『引き延ばされた「グルーオンの集積したひも」のエネルギーを含む全エネルギーが、クォークヒッグス場ユニットからクォークと反クォークの対を生成するエネルギーを含む全エネルギーよりも大きくなる』という条件を満たせば、“切れてしまう”と考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※このようなグルーオンの増幅のしくみは、上記で考えた「LP光子による増幅」のしくみと相似になっていることから類推すると──
『引き延ばされた「LP光子の集積したひも」のエネルギーを含む全エネルギーが、プレオン∴ヒッグス場ユニット(p∴HU(=preon∴ Higgs(field)Unit)からプレオン∴と反プレオン∴の対を生成するエネルギーを含む全エネルギーよりも大きくなる』という条件を満たすとき、“切れてしまう”と予想される。 詳細な検討は、今後の課題である。
なお、たとえ、“切れて”しまったとしても、その“切れた”「LP光子の集積したひも」の端に、プレオン∴と、反プレオン∴が現れるので、結局は、プレオン∴は、閉じ込められたままになると考えられる。 それは、クォークの閉じ込めの場合と同様である。
※「LP光子の集積したひも」と「グルーオンの集積したひも」は、相似になっている。
※“×3”のタイプのフラクタルになっている。
※その相似性は、原始ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)と、プレオン∴ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)が、相似になっていることにもとづいていることがわかる。(→結果3)
|
この「LP光子の集積したひも」と「グルーオンの集積したひも」の相似性は、次の記述を説明するためのヒントとなるかもしれない。
『量子重力理論では、重力は重力子という粒子によって伝えられているが、新しい見方によると、重力子は2つのグルーオンを張り合わせたようなものとみなせる。
この概念は非常に奇妙で、専門家もその意味を完全にはつかめていない。しかし、この2重コピーという性質は、重力が他の既知の力とどのように統合されるべきかについて、新しい視点を与えている。』(p.40)
『重力は重力子という粒子によって媒介されるが、重力子はグルーオンと驚くほどよく似た数学的性質を持っていることがわかった。 重力子は、2つのグルーオンが一緒になって二人三脚のように動いているものとみなすことができるのだ』(p.45)
『これは、例えて言えば、重力相互作用は強い相互作用を2乗することで表せるということだ。 この数学的性質の物理学的意義を明らかにし、どんな状況でもこの性質が成り立つかどうかを確かめるには時間がかかるかもしれない。』(p.46)
(『ファインマンを超えて 新アプローチで探る究極理論』 日経サイエン2012年7月号より 下線は、筆者による)
|
これらの記述する内容は、「重力子(or LP光子×2)によって生じる、原始ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)」と、「グルーオン×2によって生じる、原始ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)」が、下図のように、相似になっていることを反映しているのかもしれない。
|
“4角形”(縮みきったバネ)
|
|
“4角形”の起源からの説明
|
重力子
(光子×2に相当)
|
|
グルーオン×2に相当
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の表記
|
|
∽
|
|
|
簡略表記
|
: :
|
|
∴ ∴
∴ ∴
|
|
スピン
|
2
|
|
2
|
※重力子(=LP光子×2)によって生じる、原始ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)と、
グルーオン×2によって生じる、原始ヒッグス場ユニット由来の“4角形”(縮みきったバネ)は、相似になっている。 |
『重力子は2つのグルーオンを張り合わせたようなものとみなせる。』『驚くほどよく似た数学的性質を持っている』『重力子は、2つのグルーオンが一緒になって二人三脚のように動いているものとみなすことができるのだ』と書かれていることからわかるように── 「重力子(=LP光子×2)」と「グルーオン×2」のふるまいの“数学的性質”が似ているだけであって、決して、重力子とグルーオン2つは、100%同一の実体であるわけでない。
これらの記述は、フラクタル的に相似であることを反映していると解釈すれば、『非常に奇妙で、専門家もその意味を完全にはつかめていない』ことがすっきり解消でき、『この数学的性質の物理学的意義』を理解できるようになるのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
《ウィークボソンW−、W+、Z0と、弱アイソスピンについて》
素粒子物理学の標準模型の中の電弱統一理論(ワインバーグ・サラム理論)が予言し、実際に観測された、ウィークボソンW−、W+、Z0を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)表記するとどのようになるであろうか?
弱い相互作用をもたらすウィークボソンの1例、W−は、おおよそ次のようになることは、すでに示した。
|
|
W−ボソン
|
| “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)表記 |
|
|
スピン
|
1
|
※左巻きの電子と右巻き反電子ニュートリノが結びつくことで、 W −ボソンができている。
このW−ボソンを、その本質を残して、より簡略に表記すると次のようになる。
※簡略化されている。
ただし、左巻きの電子と右巻き反電子ニュートリノが結びつくことで、W−ボソンが生じているという本質は、残っている。 |
このような簡略表記を用いて、ウィークボソンW−、W+、Z0を整理して、図示すると次のようになる。
|
W−ボソン
|
W+ボソン
|
|
|
|
|
電荷−1、 スピン1/2
|
電荷+1、 スピン1/2
|
|
左巻き電子+右巻き反電子ニュートリノ
|
右巻き陽電子+左巻き電子ニュートリノ
|
|
Z0ボソン
|
Z0ボソン
|
Z0ボソン
|
Z0ボソン
|
|
|
|
|
|
|
電荷0、 スピン1/2
|
電荷0、 スピン1/2
|
電荷0、 スピン1/2
|
電荷0、 スピン1/2
|
|
左巻き電子ニュートリノ+右巻き反電子ニュートリノ
|
左巻き電子+右巻き陽電子
|
左巻き反アップクォーク+右巻きアップクォーク
|
左巻き反ダウンクォーク+右巻きダウンクォーク
|
※Z0が4種類あることについては、次の説明を参考にした。
|
電荷
|
プレオン組成
|
粒子
|
|
0
|
|
0 0 0 0 0 0
|
| +++−−− |
| ++−− 0 0 |
| +−0 0 0 0 |
|
Z粒子(4種類ある)
|
(『クォークの中の素粒子 日経サイエン2013年1月号』(D.リンカーン著 日経サイエンス社)のp.38の中の表の一部(下))
|
※なお、便宜上、反粒子をアンダーバーで示していある。
※次の対応関係を見いだせる。 |
|
0 0 0 0 0 0
|
←→ |
「0 0 0」+「 0 0 0」
|
= |
|
| +++−−− |
←→ |
「−−−」+「+++」
|
= |
|
| ++−− 0 0 |
←→ |
「−−0」+「++0」
|
= |
|
| +−0 0 0 0 |
←→ |
「+00」+「− 0 0」
|
= |
|
|
以下では、弱い相互作用の要である、W−ボソンにしぼって、説明を進めることとする。
|
W−ボソン
|
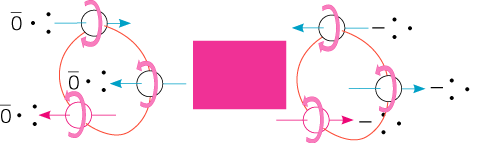 (=
(= 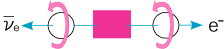 ) )
|
|
電荷−1、 スピン1/2
|
|
左巻き電子+右巻き反電子ニュートリノ
|
W−ボソンは、やはり、電子と反電子ニュートリノが何らかのかたちで結びついてできていると考えられる。
これによって、W−ボソンが速やかに分解されて、電子(∴×3)と、反電子ニュートリノ(∴×3)を生じることをうまく説明できる。
さらには、この幾何的な実体像から、W−の構造が持つ、明らかな時空構造的な非対称性が、左右非対称性を生んでいることが読み取れ── 弱い力が「左巻きの電子、右巻きの反ニュートリノ」のみに働くこと(左右の対称性を破っていること)をうまく説明できる。
それでは、W−の構造の中の電子と反電子ニュートリノを結びつける力とは、いったい何か?
それは、すでに述べたように、ウィークボソンを結びつけるものは、やはり、“LP光子の集積したひも”を介する“原始的な力”に他ならないと考えられる。
これによってはじめて、W−ボソンの質量が、80GeVという大きな質量(「電子1つ(<0.5MeV)と反電子ニュートリノ1つ(<2.5eV)の静止質量の和」よりはるかに大きな質量)を持つことを説明できるのだと思われる。
ただし、“LP光子の集積したひも”自体が質量を担うわけではなく、「電子1つ」と「反電子ニュートリノ1つ」が持つ外部運動エネルギーが、はるかに大きな、80GeVという質量の大部分を担うと考えられる。
すなわち、それは、“LP光子の集積したひも”を切断するためには、それほど大きなエネルギーが必要であるということを意味している。
※この説明は、「グルーオンの集積したひも」自体は質量を担わず、両端のクォークの外部運動エネルギーが、『“裸のクォークの質量(例えば、アップクォーク〜4.2MeV、ダウンクォーク〜7.5MeV)”の和より大きな“陽子や中性子、π中間子の質量(すなわち、「有効質量」(例えば、アップクォーク〜350MeV、ダウンクォーク〜350MeV))”(参考『物質の究極を探る 現代の統一理論』p.11、22)』の大部分を担うという説明と調和していると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
例えば、弱い相互作用の一例、「“ダウンクォークから、アップクォークへ変化し、 W−ボソンが飛び出す”過程」は── “アップクォークヒッグス場ユニット(スピン0、右巻きアップクォーク×2+左巻き反アップクォーク×2)”(→詳細は。結果3)の存在を想定することによって、次のようにピッタリと説明できる。
※「(やってきた)右巻きダウンクォークと、(アップクォークヒッグス場ユニットの中の)左巻き反アップクォーク」から、直接、弱い相互作用により、ウィークボソンになると同時に── 右巻きアップクォークが放出されている。
この過程により、(やってきた)左巻きダウンクォークが、右巻きアップクォークに変化したように見える。
※残りの、右巻きアップクォークと、左巻き反アップクォークは、対消滅する。
|
このように「左巻きダウンクォークが、右巻きアップクォークに変化したように見える」過程で起きていると説明される内容は── “弱アイソスピン”という抽象概念で説明されていたことの幾何的な実体像に相当すると考えられる。
よって、この「右巻きダウンクォークが、アップクォークヒッグス場ユニットと相互作用することによって、右巻きアップクォークに変化するように見える過程」は、単振動的(サインカーブ(正弦波)的)に進むと予想される。 (詳細な検討は、今後の課題である)
なお、「右巻きダウンクォークと、(アップクォークヒッグス場の中の)左巻き反アップクォークから」から、弱い相互作用により、ウィークボソンに変化する過程の詳細は、次のようになる。
|
「右巻きダウンクォークと、(アップクォークヒッグス場の中の)左巻き反アップクォークから」
|
|
弱い相互作用により)
W−ボソンに変化
|
|
|
+
|
|
→ |
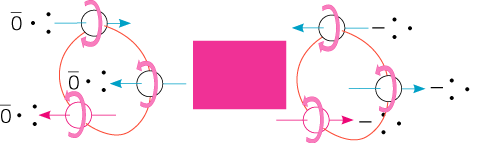 (=
(= 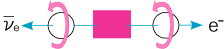 ) )
|
|
右巻きダウンクォーク
|
|
左巻きの反アップクォーク
|
|
W−ボソン
|
※ 右巻きダウンクォークと 左巻きの反アップクォークの組成の合計が、ウィークボソンの組成の合計にぴったり等しいことが読み取れる。
※なお、W−ボソンは、この後、左巻き電子と右巻き反電子ニュートリノに、速やかに分解する。
※なお、次のようにいったん中間子として放出してから、ウィークボゾンに変わっていくということは考えられない。
なぜなら、これだと、(「グルーオンの集積したひも」を介する)“強い力の結合エネルギー”も関わってしまうことになるので、『中性子nとミューオンμの崩壊の結合定数が同じだと言う事実(〜)に抵触する』(『クォーク 第2版』 p.234 南部陽一郎 講談社ブルーバックス)より、一部抜粋)からである。
(なお、中性子nが崩壊して、中性子の中のダウンクォークが、アップクォークに変化し、中性子nが陽子pに変わる過程も、ミューオンμが崩壊する過程も、弱い力を介して起こる)
弱い力(弱い相互作用)は、電子を電子ニュートリノに変えたり、電子ニュートリノを電子に変えたりもできる。
例えば、弱い力(弱い相互作用)が、電子e-を、電子ニュートリノνe- に変える過程は── “ニュートリノヒッグス場ユニット(スピン0、左巻き電子ニュートリノ×2+右巻き反電子ニュートリノ×2)”(→詳細は。結果3)の存在を想定することによって、次のようにピッタリと説明できる。
※「(やってきた)左巻き電子と、(ニュートリノヒッグス場ユニットの中の)右巻き反電子ニュートリノ」から、直接、弱い相互作用により、ウィークボソンになると同時に── 左巻き電子ニュートリノが放出されている。
この過程により、(やってきた)左巻き電子が、左巻き電子ニュートリノに変化したように見える。
※残りの、左巻き電子ニュートリノと、右巻き反電子ニュートリノは、対消滅する。
|
このように「左巻き電子が、左巻き電子ニュートリに変化したように見える」過程で起きていると説明される内容も── “弱アイソスピン”という抽象概念で説明されていたことの幾何的な実体像に相当すると考えられる。
よって、この「左巻き電子が、ニュートリノヒッグス場ユニットと相互作用することによって、左巻き電子ニュートリに変化するように見える過程」は、単振動的(サインカーブ(正弦波)的)に進むと予想される。 (詳細な検討は、今後の課題である)
一方、弱い力(弱い相互作用)が反電子ニュートリノνe- を、陽電子e+に変える過程は── “電子ヒッグス場ユニット(スピン0、左巻き電子×2+右巻き陽電子×2)”(→詳細は。結果3)の存在を想定することによって、次のようにピッタリと説明できる。
※「(やってきた)右巻き反電子ニュートリノと、(電子ヒッグス場ユニットの中の)左巻き電子」から、直接、弱い相互作用により、ウィークボソンが生まれると同時に── 右巻き陽電子が放出されている。
この過程により、(やってきた)右巻き反電子ニュートリノが、右巻き陽電子に変化したように見える。
※残りの、左巻き電子と、右巻き陽電子は、対消滅する。
|
このように「右巻き反電子ニュートリノが、右巻き陽電子に変化したように見える」過程で起きていると説明される内容も── “弱アイソスピン”という抽象概念で説明されていたことの幾何的な実体像に相当すると考えられる。
よって、この「右巻き反電子ニュートリノが、電子ヒッグス場ユニットと相互作用することによって、右巻き陽電子に変化するように見える過程」は、単振動的(サインカーブ(正弦波)的に)、に進むと予想される。 (詳細な検討は、今後の課題である)
つまり、いずれも、弱い力(弱い相互作用)が、素粒子の種類を変える過程は、どれも、適切なヒッグス場ユニットを想定することによって、ぴったり説明できることを示している。
これらは、すべて、“弱アイソスピン”と呼ばれた抽象的な概念、および抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何…)で説明されてきたことについての、幾何的な実体像(具体的な幾何で説明するもの)に相当すると考えられる。
このように、抽象的な概念、抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何…)でしかとりあつかうことができなかった内容を── 具体的な幾何で示すことには大きな意味がある。
なぜなら、それが、ミクロの自然(nature)そのものの“true picture”の探求を支えるからである。
ここに、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の存在意義の1つがあるのである。
※なお、ある粒子が、各種のヒッグス場ユニットとの相互作用することによって、 W-ボソンを放出すると同時に、別の粒子に変化するように見える過程は、単振動的に(サインカーブ(正弦波)的に)進むと予想される。 詳細な検討は、今後の課題である。
※なお、ふつうの“アイソスピン”(陽子←→中性子)についても、同様に、説明できると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※各種のヒッグス場ユニットについては、結果3で詳しく説明する。
《ウィークボソン質量、および、ウィークボソンと中間子の比較》
例えば、W−ボソンは、、1つの電子と1つの反電子ニュートリノが、“LP光子の集積したひも”を介して結びついているものに相当するのであった。
図示すると次のようになる。
※ピンク色の太い線の部分が“LP光子が集積したひも”に相当する。
※「LP光子の集積したひも」の一本一本は、実際は細いと考えられる。(太さ数LP[m]程度)
「LP光子の集積したひも」は、1本だけではなく、複数本の可能性はないと言えるのだろうか?(詳細な検討は、今後の課題である)
|
このW−ボソンは、<80GeVほどの質量を持つ。
一方、W−を構成すると考えられる、1つの電子と1つの反電子ニュートリノの静止質量(電子の質量( <0.5MeV)、反電子ニュートリノの質量(<2.5eV))を足しあわせただけでは、W−の質量( <80Gev)に、とても足りない。
そして、「LP光子の集積したひも」自体が質量を持つとも考えにくい。
(その構造から、「重力子の放出源として働き続ける能力」を説明できないことも理由の1つである)
したがって、この不足分を補うものは、すでに述べたように、1つの電子と1つの反電子ニュートリノの外部運動エネルギーであると考えられる。
「LP光子の集積したひも」を切断するためには、それほど大きな、外部運動エネルギーが必要なのである。
この説明は、次の記述と調和していると思われる。
『じつはW粒子は、それがこの世から消えるときに変化する物質とというかたちでしか目撃されていない。』
(p.268 『なぜE=mc2なのか?』 ブライアン・コックス&ジェフ・フォーショー柴田裕之訳 紀伊国屋書店)
|
そもそも、LP光子を介する“原始的な力”は、クォークやレプトンの中のプレオン∴を閉じ込めるほど強力なものであった。
そして、それほど強力な、LP光子を介する“原始的な力”で結びついてできているはずの、例えば、W−ボソン(W粒子の例)は、“速やかに”分解されて生じる「電子と反電子ニュートリノ」という形でしか観測されないのである。
これは、何を意味しているのだろうか?
もう一度、引用する。
『じつはW粒子は、それがこの世から消えるときに変化する物質とというかたちでしか目撃されていない。』
(p.268 『なぜE=mc2なのか?』 ブライアン・コックス&ジェフ・フォーショー柴田裕之訳 紀伊国屋書店)
|
このことは、「電子と反ニュートリノへと分解されない限り、人類には、W−ボソンを観測できない」ということを意味しているのだ。
すなわち、 「たまたま、速やかに電子と反電子ニュートリノに分解できるほどに“成長したW−ボソン”」だけが、間接的に(分解されて生じた電子と反電子ニュートリノとして)観測されたと見なされていただけの話だったのだ。
この説明は、そもそも「仮想粒子は観測できない」ということとも調和している。 すなわち、仮想粒子の一種であるW−ボソンは、W−ボソンであり続ける限り、決して観測されない── ただそれだけのことであったとも言えると思われる。
つまり、「W−ボソンは、分解されてはじめて観測できるもの」(分解されない限り、観測されないもの)なのだ。
W−ボソンを構成する電子や反電子ニュートリノの運動エネルギーが“およそ80GeV”という閾値をこえるとはじめて、「LP光子の集積したひも」が切れて、W−ボソンは、電子と反電子ニュートリノに分解する。 その分解によって生じた『電子と反電子ニュートリノ』の運動エネルギー(主に外部運動エネルギー)の観測データが、「約80GeVの質量エネルギーをつ持つW−ボソンが観測された」と見なされているに過ぎないのだ。
すなわち、その分解された電子と反電子ニュートリノの観測をもって、「W−ボソンの観測」と見なしているだけであり── そのときの質量エネルギー(主に『電子と反電子ニュートリノ』の外部運動エネルギー)の観測をもって、W−ボソンの質量と見なしているだけのことにすぎないのだ。
この説明により、(超強力な「LP光子を介する“原始的な力”」で支えられて生じている)“弱い力(弱い相互作用)”が、なぜ、かくも“弱い”のか(なぜ、弱いと見なされているのか)を説明できる。
それは、W−ボソンの観測頻度(=分解の発生頻度)が低いからである。
なぜ、観測頻度(=分解の発生頻度)が低いか?
“電子と反電子ニュートリノ”がの運動エネルギーが“およそ80GeV”という閾値をこえて、「LP光子の集積したひも」を切断することが稀だからである。
つまり、「LP光子を介する“原始的な力”」がそれほど強いからこそ、
(切断頻度(分解頻度)が小さくなる結果、)“弱く見える”のだ。
実際は、LP光子を介する“原始的な力”は、(電磁気力よりも)非常に強いものである。
(すなわち、“LP光子の放出頻度”は、(電磁気力を生じる仮想光子の放出頻度よりも)非常に大きい)
そして、“電子と反電子ニュートリノの分解”に達しないような(約80GeVに達しない質量エネルギー(=運動エネルギー)を持つ)、W−ボソンの生成&消滅も、高頻度で起きている。
しかし、それは、まさに、仮想光子であるがゆえに、分解されない限り観測されない。
(すなわち、W−ボソン(仮想粒子)は、W−ボソン(仮想粒子)であり続ける限り観測されない)
したがって、観測されたと見なされるW−ボソンは、80GeVほどの質量エネルギー(=主に『電子と反電子ニュートリノ』の外部運動エネルギー)に達して分解されるほど、成長したものだけである。
つまり、“電子と反電子ニュートリノの分解”に達するような、“成長したW−ボソン”の放出が稀である以上、W−ボソンの観測頻度も小さいものと見なさられざるをえなくなる。
その結果、このW−ボソンを介する“弱い相互作用”は、(実際はとても「強い」力に支えられて生じているのに)「弱い」と見なされてしまうことになってしまうのだ。
しかし、実際は、この現象は、(クォークや電子の中にプレオン∴を閉じ込めるほど)非常に強力な力、すなわち、LP光子を介する“原始的な力”によって生じている。
弱い力(弱い相互作用)は、決して“弱い力”(文字通りの意味の“弱い力”である)によって引き起こされているものではなく── LP光子を介する、非常に強い力(文字通りの意味の“非常に強い力”である)、すなわち、“原始的な力”によって、引き起こされているのである。
こういった事情は、陽子や中性子を結びつける中間子を介する力(相互作用)は、実質的には、グルーオンを介する強い相互作用(すなわち、クォークを閉じ込めるほど“強い力”)によって引き起こされている2次的な力であると見なせることと似ている。
|
1次的な力
|
2次的な力
|
|
グルーオンを介する強い力
|
中間子を介する
陽子や中性子を結びつける力
|
すなわち、“弱い力(弱い相互作用)”は、実質的に、LP光子を介する非常に強い相互作用(すなわち、プレオン∴を閉じ込めるほど“超強力な力”、すなわち、“原始的な力”)によって引き起こされている2次的な力であると見なすことができるのである。
|
1次的な力
|
2次的な力
|
|
“LP光子を介する原始的な力”
|
ウィークボソンを介する 弱い力
|
つまり、中間子と、ウィークボソンには、ともに“二次的な力として生まれている”という意味で、似ているのである。
また、「π+、π−、π0、K+、K0、η…」のような多様な中間子(メソン)を、グルーオンによって統一的に説明できて、「W+、W−、Z0(e+-e−、u+-u−、d+-d−…)」のような多様なウイークボソンをLP光子によって統一的に説明できるという意味でも、似ている。
(このことに気づくと、多様なウィークボソンを、LP光子によって統一的に説明するというのは、とても自然な考えであるように思われてくる)
※なお、中間子とウィークボソンが似ているという考えは、次の記述とも調和していると思われる。
『湯川は、自然における到達距離の短い力が重い粒子の交換で説明できる、と考えた最初の人物である。実のところ、弱い力を伝えるものとして何年かのちにW粒子が提案されたのも、その着想のもととなったのは、湯川の中間子仮説であった』
(『アインシュタインを超える』 p.114 M・カク、J・トレイナー[著] 久志本克己[訳] 広瀬立成〔監修〕 講談社ブルーバックス)
|
※オレンジ色の太い線が、“グルーオン が集積したひも”に相当する。
※ピンク色の太い線が、“「L P光子の集積したひも」”に相当する。
例えば、π−中間子と、W−ボソンは、ともに、ダウンクォークが「アップクォークヒッグス場ユニット」に作用することによって生じることも似ている。
|
π−中間子
|
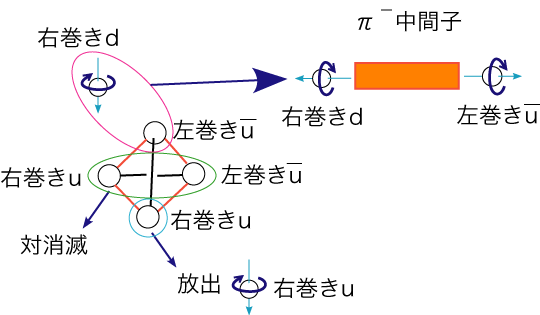 |
|
|
|
W−ボソン
|
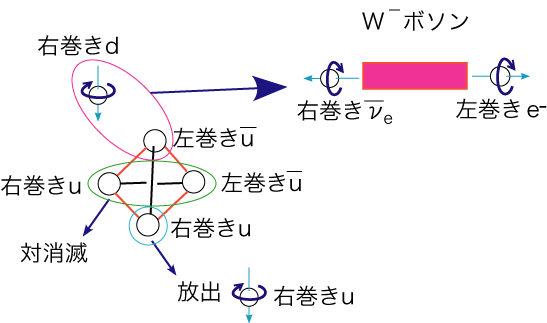 |
|
|
π−中間子
|
|
W−ボソン
|
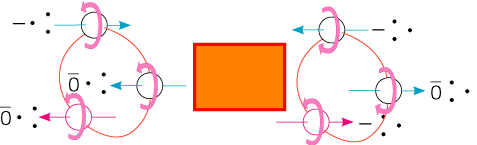 |
|
|
by 「グルーオンの集積したひも」
|
by 「LP光子の集積したひも」
|
※ある意味、マイナスプレオンと反中性プレオンが交換されているだけと言える。
“π−中間子”と“ W−ボソン”は、ともに仮想粒子であり、「観測されるものは、速やかに分解されるものである」ということも似ている。
しかし、違いもある。
それを整理すると次のようになる。
|
|
“π−中間子”
|
W−ボソン
|
|
結びつける力
|
「グルーオンの集積したひも」を介する
“強い力”(強い相互作用)
|
「LP光子の集積したひも」を介する
“原始的な力”
|
|
質量エネルギーの大きさ
|
およそ135MeV
|
およそ80GeV
|
|
質量エネルギーの起源
|
主にクォークの外部運動エネルギー
|
主に『電子や反電子ニュートリノ』
の外部運動エネルギー
|
| ※質量エネルギーが桁違いに異なるのは、結びつける力の大きさ(or切断するのに必要な(構成粒子の)外部運動エネルギー)が桁違いに異なるからに他ならない。 |
なお、先に示したように、「グルーオンの集積したひも」と、「LP光子の集積したひも」は、相似になっている。
以上のことは、“中間子一般”と“ウィークボソン一般”について、言えることである。
よって、以上は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示す、「ウィークボソン」の質量、および、ウィークボソン(弱い相互作用)と中間子(核力)の比較に相当するものである。
これらの具体的な描像によって、「ウィークボソンを介する弱い相互作用は、実質的に、LP光子を介する非常に強い相互作用(“原始的な力”)によって、引き起こされている2次的な力である」ことを無理なく理解できるようになる。
すなわち、そのことは、「中間子を介する核力は、実質的に、グルーオンを介する強い相互作用(強い力)によって、引き起こされている2次的な力である」こととの相似性から理解できるのである。
《1次的〜3次的な力》
以上の、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると──
「陽子や中性子を結びつける核力を生むとされる、π中間子」が、結局、グルーオンを介する強い力の所産であるように、
「弱い力を生むとされる、ウィークボソン(∴×3×2)」は、結局は、“LP光子を介する原始的な力”の所産であると考えられることは、上で述べた。
そして、さらに、グルーオン(∴×2)も、実は、“LP光子を介する原始的な力”の所産であると考えられるのだった。
そうすると──
陽子や中性子を結びつける核力(by π中間子=強い力の所産の例)が、“グルーオンを介する強い力”から生じる2次的な力だと呼べるならば──
同様に、弱い力(by ウィークボソン)や、強い力(by グルーオン)は、実は、この“LP光子を介する原始的な力”から生じた2次的な力と呼べることになると考えるのは、自然なことであることになる。
|
1次的な力
|
2次的な力
|
|
グルーオンを介する強い力
|
π中間子を介する
陽子や中性子を結びつける核力
|

|
1次的な力
|
2次的な力
|
|
“LP光子を介する
原始的な力”
|
グルーオンを介する強い力
ウィークボソンを介する 弱い力
|
これらの関係は、互いに相似の関係にあるので、共通する部分(グルーオンを介する強い力の部分)を介して、両方をまとめ合わせることができる。
すなわち、両方をまとめ合わせると、次のように、π中間子を介する核力は、3次的な力と言えるようになるのだ。
|
1次的な力
|
2次的な力
|
3次的な力
|
|
“LP光子を介する原始的な力”
|
グルーオンを介する強い力
ウィークボソンを介する 弱い力
|
π中間子を介する
陽子や中性子を結びつける核力
|
以上の説明をまとめて図示すると次のようになる。
|
|
|
|
|
|
|
|
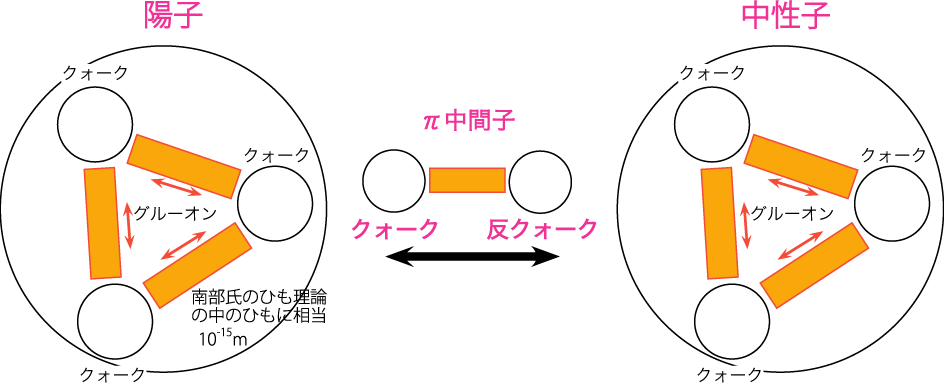 3次的な力
3次的な力
|
※これは、まさに、“フラクタル相似の原理”と調和している。(→付録 その他1)
※なお、弱い力(by ウィークボソン)も、強い力(by グルーオン)も、核力(byπ中間子)も、どれも、ごく短い距離でのみ働くという事実は── これらを根底で支えているだろう“原始的な力”が、ごく短い距離に限り生じるからこそであると理解できる。
このことも、これらのごく短い距離でのみで働く力(湯川型の相互作用による力)は── 無限遠方まで作用できる重力や電磁気力とは、根本的に異なることを示唆していると思われる。
|