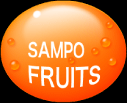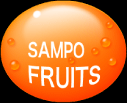|
165
【7番目のパラダイムのフラクタル】
(細胞レベル〜人間レベル2──“自動的に生じる現象”の例)
「細胞レベルと細胞社会レベルの関係に、人間レベルを考え合わせると、さらにおもしろいことに気づくことができるよ」と僕。
「──え、どんなこと?」と彼女。
「うん。やっぱり熱い物に手などがふれたときに思わず引っ込める“反射”を介する過程の例が解りやすいから、それで説明するよ。
それだと、次のようになるんだ。
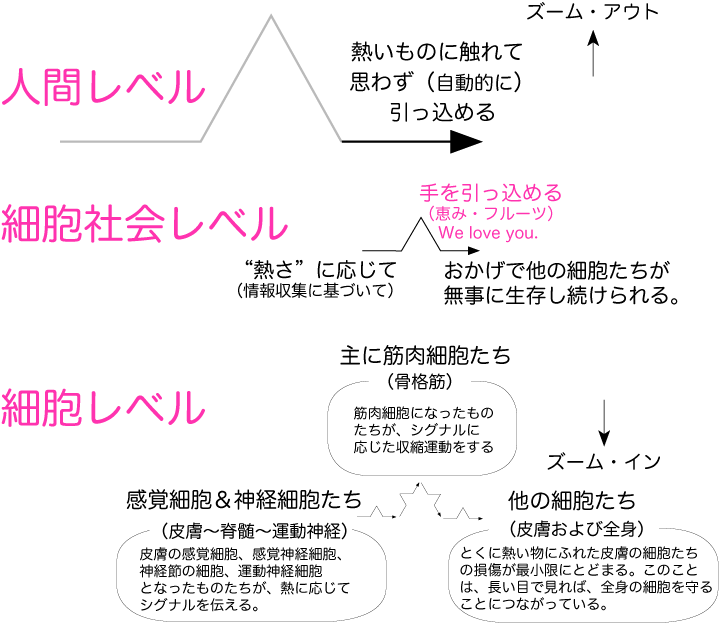
この場合、細胞社会レベルは、個々の細胞レベルからズーム・アウトして見えると同時に、人間レベルの中の3番目の“動かす”のステップからズーム・インしても見える」
「ふーん。そうすると、この“反射”を介する過程においては──
人間レベルでの1番目と2番目のステップ──例えば“認識して、決めて”のステップが省略されてしまっているのね?」
「そうなのさ! このときは、“〜しよう”の意志も“〜したい”の意欲も関係せずに、いわば自動的に運動している」
「すごい! これって、もしかして、ほかの“自動的に生じる現象”も、うまく説明できちゃうってことじゃない?
例えば──
心臓がドキドキ高鳴るとか──
呼吸がハアハァとはずむとか──
心身がリラックスするとか──
“好き”という感情が湧くとか──
“会いたい”という感情が湧くとか──
…」
「そうだね。ほかにも──
あるものを見て、何かのイメージが連想されるのも──
“おなかがすいた”という感覚が生まれて何かを食べたくなるのも──
“のどが乾いた”という感覚が生まれて水分をとりたくなるのも──
緊張してトイレに行きたくなるのも──
暑くて汗をかくのも──
…
どれも、人間レベルの“認識して、決めて”というプロセスが省かれたまま、自動的な“細胞社会レベル”の働きに基づいて生じていると説明できる。
もちろん、会いたい、食べたい、飲みたい、トイレ行きたい… という衝動が自動的に生じたからといって、必ずしも、すぐに実現できるとは限らなくて──」
「そうよね。状況に応じて── 今は会うのをよそう。今は食べるのを我慢しよう。今は水分をとるのをひかえよう。今はトイレ行くのを我慢しよう… と決めて、実現させないことも多々あるわよね」
「そうさ。それが衝動をコントロールする意志の力なのさ」
「そうね。こういった衝動のコントロール力に個人差があるだろうけれど── 動物より人間の方が、そのコントロール力が大きいのは確かよね?」
「ああ、そうだね。その差は、広い視野や長い目を含む『アタマ』の方向の認識力の違いからきているんだよ。このあたりの違いを図で示せば、例えば、次のようになると思うよ」
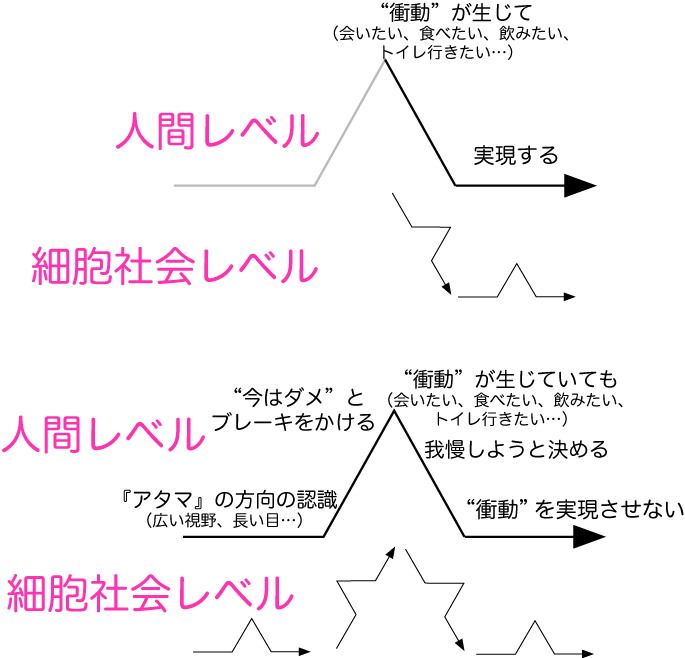
「この例では、衝動的に行動している方において、『アタマ』の方向の認識のステップ──人間レベルでの1番目のステップが省略されているのね?」
「そうさ。まあ、とくに人の場合、1番目のステップが完全に省略されるのは稀で、実際は『カラダ』の方向の認識のステップが関わっていることが多いと思うよ」
「ふーん」
「まあ、いずれにしても、人が衝動と健康的に付き合うために『アタマ』の方向の認識力が重要であるのは変わらないよ」
「そうね」
「それに、衝動の全てを抑制するべきとも限らない。
もし、『アタマ』の方向の十分な認識を経ても、その認識と調和するような“健全な衝動”が自動的に生じ続けているならば、それこそが健全な“やる気”や“意欲”なんだよ。
だから、“〜したい”の意欲が『カラダ』の方向にあるとすれば、“〜しよう”の意志が『アタマ』の方向にあるという話は、本来、『アタマ』の方向の十分な認識と調和している“健全な衝動”の有無を反映していたのさ」
|