研究論文
『一般3Steps理論
&“素スピノール創発モデル”』
2.重力(一般相対性理論)、重力子、質量、光速について
このページでは、次の項目について、一般3Steps理論的、および“素スピノールからの創発モデル”的な説明を試みる。
《光子の波、重力子の波》
まず、光子が、光速で、原始ヒッグス場(電磁場)を移動することについて、“素スピノールからの創発モデル”による説明を試みる。
光子の構造は、次のようであると考えられる。
|
光子
|
|
“素スピノールモデル”の表記
|
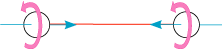 |
|
簡略表記
|
・・
|
|
スピン
|
1
|
※右巻き素スピノールと左巻き素スピノールが結びついている
これが空間内を光速で移動するとは、どういうことであろうか?
次のような考えをヒントにしてみた。
「温度がゼロよりほんの少し高いとどうなるだろうか。この場合も基本はやはりすべてのスピンがそろった状態で、そこにときどきランダムに一個のスピンがひっくりかえることが起きる。そうすると、その隣のスピンがつき合ってやはり逆を向くこともあるだろう。ただ、二つが同時に逆を向くとエネルギーのロスが大きすぎるので、隣が逆を向いたら最初のは元に戻る。次はそのさらに隣が付き合って逆を向く……、という具合にスピンが格子上を伝わって移動していくこともありそうだ。まるで波のようではないか。そう、これは波だ。」(『質量はどのように生まれるのか』 橋本省二 講談社ブルーバックス p160-162 鉄の強磁性に関しての説明文の一部)
この“スピンのひっくりかえりの伝播”が素スピノールのネットワーク上で(原始ヒッグス場で)起きている場合── それがまさに、電磁波の出現に相当しているのではないだろうか?と考えてみた。
よって、次の仮説を立てた。
仮説2.1 光子は、様々な距離にある“原始ヒッグス場”の基本構造をバネ的な足場にして、2つの素スピノールが、ひっくり返りながら進むものに相当する。
光子の流れを簡略に図示すると次のようになる。
以後、素スピノールがひっくり返ることを、“素スピノールが転回する”と表現することとする。
上図のように、“素スピノールの転回(=ひっくり返り)”が、次々と伝わっている。 これが、まさに“光の伝わり方”(光子の移動のし方)の実体に相当することになる。
※このモデルだと、光が持つ“波と粒子の二重性”の性質が生じる理由も、自然に、うまく説明できると思われる。
“原始ヒッグス場”とは、“原始ヒッグス場”の基本構造(“4面体”)がゆるやかに結びつきながら時空を占めている(自由に回転できると同時に固定されている)ものだと考えられる。(→考察3、4)
“原始ヒッグス場”の基本構造の足場とは、次のようなものである。
|
“原始ヒッグス場”の基本構造
(=電磁場の基本構造)
|
|
“素スピノールからの創発モデル”
の表記
|
|
or
|
|
|
構成
|
“右巻き素スピノールのペアと
左巻きの素スピノールのペア”
からなる“4面体”
|
|
スピン
|
0
|
※凝縮のペア(黒い線で結ばれる。右巻きどうし、左巻きどうしのペアである)が2つ組み合わさってできていると言える。
※90度回転させたものも合わせて図示した。 両者は、全く同じである。 |
光子の流れを詳細に図示すると次のようになる。
個々の“原始ヒッグス場”の基本構造の足場にはそれぞれ、必ず、右巻き素スピノール(上に進行、下に進行)、左巻き素スピノール(上に進行、下に進行)の4種類が存在するので、ある波長を持つ光子の進行に必要な素スピノールを、適宜選ぶことが出来る。
※光子は、様々な波長をとることができる。 そのことは、時空をびっしりと占める“原始ヒッグス場”の中で、どの基本構造の足場を選ぶのかによって対応できる。
光子が、近くの足場どうしをまたぐなら短い波長、 遠くの足場どうしをまたぐならば長い波長に、相当すると考えられる。
この光子が、真空中を、光速という一定の速度で伝わるということは──
“転回の頻度”が多いほど(転回するのに要する時間=“転回周期”が短いほど)、“足場”の間の距離が小さくなって(光の波長は短くなって)、
逆に、“転回の頻度”が少ないほど(転回するのに要する時間=“転回周期”が長いほど)、“足場”の間の距離が大きくなる(光の波長は長くなる)ことを意味する。
それは、“転回の頻度”が多いほど光子のエネルギーが大きくなり、“転回の頻度”が少ないほど光子のエネルギーが小さくなることになり、プランクの光が持つエネルギーの式 E=hν と合致する。
※光子の持つエネルギーと、原始ヒッグス場の“4面体”が変形することによって蓄えるエネルギーが等しいと考えられる。
原始ヒッグス場の“4面体”には、速いスピード(短い転回周期)で変形すればするほど大きなエネルギーを蓄えるという性質があることになる。
言い換えれば、E=hν=h/T なので── このエネルギーEの振幅と転回の周期Tは、反比例するということである。
これは、不確定性原理の式── ΔE×Δt ≒h と合致している。
不確定性原理の式は、「原始ヒッグス場の“4面体”がもつ性質」を反映した式と言えるのかもしれない。(→考察6)
※また、真空中で、一回(180度)だけ転回する時間(転回周期)をT180度とし、素スピノールの間の距離をLとすると── 180度転回する間に進む速度は、L/T180度と計算でき、これが、常に光の速度c(約3×108m)に等しいことになる。 L/T180度=c これは、素スピノールの転回周期T=2T180度(つまり、変形に伴って“4面体”が持つエネルギー)が決まると、自動的に、“次の素スピノール”までの距離が決まってしまうことを意味している。
※上記のように「素スピノールの転回が遠方へ伝わる現象(基本スピノーのペア(双極子)が同時に転回する現象)」を、非局所性(エンタングルメント(量子もつれ、絡み合い…))の性質が、支えていると言えるのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
次に、重力子が、波として光速で移動することについて考察する。
重力子は、スピン2である。 次の仮説を立てた。
仮説2.2.0 重力子は、スピン1の光子2つ分に相当し、4つの素スピノールから、次のように構成されている。
|
重力子(グラビトン)
|
|
素スピノールの
ネットワーク
(“素スピノールモデル”の表記)
|
|
|
簡略表記
|
: :
|
|
スピン
|
2
|
この配置によってはじめて、スピン2となるこができる。
さらに次の仮説を立てた。
仮説2.2.1 重力子は、すぐとなりにある“原始ヒッグス場”の基本構造をバネ的な足場として、4つの素スピノールを転回させながら進むものに相当する。
※見やすくするため、原始ヒッグス場の“4面体”の間隔を空けてある。
|
重力子の波は、“2個の光子”が並走するものに相当するものであることが読み取れる。
また、光子が、様々な距離にある“4面体”の足場を移動するのに対して、重力子は、すぐとなりにある“4面体”の足場のみを移動するということは、
重力子の波長は一定であり、非常に短いことを意味する。
(図では、見やすくするため、原始ヒッグス場の“4面体”の間隔を空けてあるが、実際は、間隔が狭まっている)
重力子のサイズは、(重力子の波長)について、次の仮説を立てた。 (→下記の考察《プランク定数、ブランクエネルギーについて》)
仮説2.2.2 重力子のサイズは、1プランク長程度(重力子の波長は、2プランク長(2Lp)程度)と一定となる。
※『アインシュタイン選集2』によれば、アインシュタインは「長い波長の重力子」というものを考えておられたようである。
しかし、もし(物質を中心にして周囲へと放出される)重力子の波長が長くなったとすれば── 1つの重力子は、いずれは複数の原始ヒッグス場にまたがって移動することになってしまうので、1つの重力子のまま存続できず、2つの光子に分裂してしまうと考えられる。 つまり、重力子が“すぐとなりの原始ヒッグス場を足場にして移動すること”には、2つの光子への分裂が生じないという意味があると思われる。 このあたりの詳細な検討は、今後の課題である。
※光子が部分的に“4面体”を途中まで変形させるのと違い── 重力子は、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを100%変形させ、“4角形”にまですることができると考えられる。 この“4角形”は、“縮みきったバネ”と言える。 逆に、重力子は、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを、100%縮みきった“4角形”にすることではじめて、放出されるものである、とも言える。
バネが縮みきってできた“4角形”が持つエネルギーには、大きな意味があると考えられる。 (→下記の考察《プランク定数、ブランクエネルギーについて》)
重力子が、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場の基本構造の集まり)の上を、光速で波として移動するとき、“4角形”(縮みきったバネ)も、一緒に光速で移動していくことになる。 この“4角形”(縮みきったバネ)の動きを、次のように(簡略化して)表記できる。
※縮みきったバネの“4角形”が移動していくことだけが図示されている。
決して、この“4角形”(縮みきったバネ)=重力子というわけではないが── 1つの重力子につき、1つの“4角形”(縮みきったバネ)が近くに生じていることになるので、便宜上、重力子の挙動を近似的に“4角形”(縮みきったバネ)の挙動として代用することも可能かと思われる。
以下では、重力子≒“4角形”(縮みきったバネ)として話を進める。
※なお、上図のようなことが可能になるのは── 1つの原始ヒッグス場の基本構造に注目した場合、“4面体”の状態と“4角形”(縮みきったバネ)の状態を行ったりきたりするプロセスが、下のような簡単な仕組みで達成できるからである。
|
原始ヒッグス場の基本構造由来の
“4角形”(縮みきったバネ)
|
|
原始ヒッグス場の基本構造の
“4面体”
|
|
|
←
→
|
|
|
※例えば、緑で囲ったペアが(放出途中の重力子の働きで)180度転回する(ひっくり返る)と“4面体”の配置に近づくことがわかる。
|
|
※例えば、緑で囲ったペアが(取り込み途中の重力子の働きで)180度転回する(ひっくり返る)と“4角形”(縮みきったバネ)の配置に近づくことがわかる。
|
※素スピノールの数や向きやスピンが、ピッタリ合致している。 このことが基本構造として“4面体”を採用する決め手(理由)の1つとなった。
そして、これこそがバネのような働きをし── 1つの“バネ”の収縮が解消されると同時に、新たな1つの“バネ”が収縮するということを繰り返すおかげで、重力子は、次々と進んでいけると考えられるのである。
|
※重力子の進行とともに、次々と“4角形”(縮みきったバネ)と“4面体”が切り替わっていく様子が読み取れる。
このことは、1つの“バネ”の収縮が解消されると同時に、新たな“バネ”が収縮しているので、重力子が進行する間に、エネルギーの損失はないと考えられる。
※なお、やはり、見やすくするために間隔を空けて図示してある。
重力子の波長は2Lpだと考えられるので、実際は、間隔が狭まっていると考えられる。
|
※“時空の曲がり”(重力場)の変化とは、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の数(密度)の増減によって、もたらされると考えられる。
そういった“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の数(密度)の増減”としての“時空の曲がり”(重力場)の変化も、(重力子1つ1つが光速で進むので)当然、光速で進むと言える。 (→下記の考察)
※なお、個々の重力子そのものを直接に観測することは、やはり非常に困難であると予想される。
なぜなら、実在する重力子のサイズは、波長がプランク長さの2倍程度(2Lp≒2×1.61610-35m=約2.323×10-35m)であると考えられ、なおかつ、1つの重力子の中だけで磁場と電場が完全に打ち消し合っているからである。
個々の重力子そのものと比べれば、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の数(密度)の変化の波は、相対的に観測しやいと思われるが、それは“電磁波”のような波とは、全く異なる波である。
(たとえば、豆電球に与える電圧を周期的に変化させれば、光の強度(光子の数)が増えたり減ったりを繰り返す波と見なせる。 その波は、確かに光速で進む。 しかし、その光の強度の増減の波自体は、決して電磁波ではない。
同様に、エネルギーや質量が周期的に変化することによっても、重力の強度(重力子の数)の増減の波が生じると言える。 その波は、光速で進む。 しかし、その重力の強度(重力子の数)の増減の波自体は、決して、アインシュタインが、電磁波との類推から予言したところの“重力波”ではないと考えられる)
“素スピノールからの創発モデル”は、“電磁波と類推できるような重力波は、あくまで個々の重力子である”ことを示している。
以後、重力波=個々の重力子として、話を進める。
※光子(電磁波)も重力子(重力波)も、原始ヒッグス場の基本構造を、一時的にエネルギーを蓄えるバネのような働きをするものとして活用し、伝わっていく波であると考えられる。 また、光子の波も、重力子の波も、““4面体”のバネが持つエネルギー”を波として伝えるものと見なすこともできると思われる。
以上の考察は、このアプローチによって、“重力場と電磁場の統一”が可能であることを意味していると思われる。
※光子(電磁波)が、電荷を持つ粒子が“身ぶるい”することで生じる波である一方、重力子は、(ミクロレベルで)光速で運動し続ける粒子の“身ぶるい”によって生じると言える。 (→《質量の実体像》)
《質量の実体像》
質量とは何か? “素スピノールからの創発モデル”による説明を試みる。
もともと、あらゆる素粒子は、ミクロのレベルで見ると、常に光速で移動し続けている。
しかし、原始ヒッグス場の基本構造の“4面体”に衝突し、抵抗をうけて“4面体”を変形させる過程で、(マクロレベルでの見かけ上)光速を失うと考えられる。
たとえば、個々の電子、クォーク、陽子… も、周囲の原始ヒッグス場から抵抗を受けることで、(マクロレベルでの見かけ上)光速を失い、質量を獲得すると考えられる。 その際、周囲の原始ヒッグス場を変形させることによって、周囲の時空構造にエネルギーを蓄える。 しかし、電子、クォーク、陽子… は、1回の衝突だけでは、原始ヒッグス場の“4面体”を完全な“4角形”(縮みきったバネ)に変形させて、重力子を放出させることができない。 しかし、時間をかけて、繰り返し衝突することによって、電子、クォーク、陽子… が1つ1つの単独であっても、原始ヒッグス場の“4面体”を完全な“4角形”(縮みきったバネ)に変形させて、重力子を放出させるほどになる。 しかし、それは、プランク質量が放出させる頻度より、ずっと少ない。
一方で、個々の電子、クォーク、陽子… は、それぞれ、電子場由来のヒッグス場、クォーク場由来のヒッグス場、陽子場由来のヒッグス場からも、抵抗を受けることで見かけ上、光速を失う。 (カイラル対称性の破れによる質量獲得に相当)
その過程では、各種のヒッグス場の“4面体”を“4角形”(四極子)に変形させることで、周囲の時空構造にエネルギーを蓄える。
この四極子の“4角形”も、最終的に原始ヒッグス場の“4面体”に何らかの形で作用し、変形させると考えられる。 (この過程の詳細については考察4)
つまり、ある粒子の質量の値は、 原始ヒッグス場を直接、“4角形”(縮みきったバネ)に変形させて、重力子を放出する過程と、それぞれのヒッグス場を介して(カイラル対称性の対称性の破れ)、原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)を変形させ、重力子を放出する過程の合計で決まってくると思われる。
より大きな質量を持っている物体は、より多くの重力子(≒原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ))を一定の頻度で周囲へ放出できるようになっている。
以上の過程全体が、“物体が質量を持っている”ということである考えられる。 以上より、次の仮説を立てた。
仮説2.3.1 ある物体が“質量を持っている”ことは、その物体の中のミクロの粒子(ミクロのレベルで光速で運動し続ける粒子)が、周囲の各種のヒッグス場から抵抗を受ける(周囲の各種のヒッグス場を変形する)過程で、(マクロレベルでの見かけ上)光速を失っている現象の総和である。
※ヒッグス場が相転移することにより── (ミクロレベルで光速で運動し続けている)素粒子は、質量を獲得する。
ふつうは(=ヒッグス場の相転移がすっかり完了している場合は)、質量とは、“重力子&原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)を放出させる能力”であると見なすこともでききる。
※そもそも、物体とは、(ミクロレベルで光速で運動する)素粒子の総和に他ならない。
たとえ、マクロレベルで静止しているように見える物体であっても、ミクロレベルで見れば、光速で運動し続けている素粒子の総和であり、そのエネルギーが、まさに、mc2に相当していると考えられる。
したがって、例えば、太陽も、地球も、人も、自動車も、電車も、自転車も… 含めて、あらゆる大きな物体は、質量を持っている以上、たとえ、マクロレベルで見て静止しているように見えたとしても、ミクロの素粒子レベルで見れば、あらゆる方向に、光速で運動し続けていることになるので、周囲に一定の頻度で、重力子を放出し続けていることになる。
大きな物体は、マクロレベルで見た運動状態にかかわらず(加速していても、等速運動していても、静止していても…)、常に重力子を放出し続けていることになる。
この性質は、後に述べていくように、重力と加速度が等価であるためにも、ニュートンの万有引力の法則に従った形で重力が働くためにも、必要不可欠である。
また、次の仮説を立てた。
仮説2.3.2 物体が持っている質量エネルギー、「その物体を構成するミクロの粒子が、見かけ上光速を失いながら周囲の時空構造へ与える影響(各種のヒッグス場を変形させること)の総和」の影響が、プランクエネルギー(約1.2×1019Gev)を越えると、重力子を一定以上の高い頻度で放出できるようになる。
(→下記の考察《プランク定数、ブランクエネルギーについて》)
また、次の仮説を立てた。
仮説2.3.3 その全質量の大きさは、周囲に、新たに放出させている全重力子の単位時間あたりの数に比例する。
プランク質量(約2×10-8kg)が、単位時間あたりに重力子を放出する頻度をn 個/sとすると、 m kgの質量は、 「m/プランク質量」個の、プランク質量を内在させていることになるので── 全質量mが単位時間当たりに放出する重力子の数= 「m/プランク質量」×n と、単純に計算できることになる。
具体的に、プランクエネルギー(約1019Gev)は、1秒間に何個の重力子を放出するのであろうか?(=nの値はなんであろうか?)
これがわかれば、あらゆる物体について、その全質量がわかるだけで、重力子の放出頻度が計算できることになる。
nの値を確定することは、今後の課題であると思われる。 (→下記の考察によると── n=c/2Lp となる。)
大きな物体が質量を持っている様子を、単純化したモデルで、図示すると次のようになる。
※中心の物体から、重力子(ピンクの四角で示した)と、“4角形”(縮みきったバネ)(紺色の台形で示した)が
放出されている様子を示す。
厳密には“4角形”(縮みきったバネ)=重力子ではないが、1つ“4角形”(縮みきったバネ)には、
必ず1つの重力子が対応しているので、“4角形”(縮みきったバネ)の数=重力子の数として
話を進めることができる。
※単純に図示してあるが、実際は、3D空間のあらゆる方向に、ランダムなタイミングで
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されていると考えられる。
(1つ1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、実際は、光速で無限遠まで進む)
したがって、上図は、ある一定時間内に新たに生じた重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布を
近似的に示していることになる。
※同心円の集まりとして図示してあるが、実際は、およそ“同心球面”の集まりが存在していると考えられる。
以下、これと同様の図は、およそ“同心球面”の集まりを表現しているものとする。
※このあたりのことは、“エルゴード性”と関連させて厳密に考えることができると思われる。
詳細は、今後の課題である。
|
中心部に物体があり── そこから周囲に重力子(≒“4角形”(縮みきったバネ))を、ある一定の頻度で放出している。 この状態が“物体が質量を持っている”(=物体の中のミクロの素粒子が光速を失っている)ことに相当する。
《重力の実体像》
ある物体は、原始ヒッグス場の“4面体”がある方向へ進むためには、わざわざ、“4角形”(縮みきったバネ)に変形しながら、苦労して進む必要がある一方──
すでに“4角形”(縮みきったバネ)となっている方向へ進むためには、その手間が不要となるので、比較的ラクに進むことが可能になると考えられる。
|
原始ヒッグス場の“4面体”があると──
|
= |
運動の際、抵抗を受ける
(ヒッグス場の基本構造の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間がかかる) |
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」があると──
|
= |
(運動の際、抵抗を受けないので)
その方向に運動しやすい
(ヒッグス場の基本構造の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省ける) |
つまり、原始ヒッグス場の“4面体”は、物質の運動に対して抵抗する働きを持っていることになる。
この「原始ヒッグス場の“4面体”が、物体の運動に対して与える抵抗」のことを、単純に“原始ヒッグス場抵抗”と呼ぶこととする。
すると、“原始ヒッグス場抵抗”が大きいほど、原始ヒッグス場の“4面体”が多く(=“4角形”(縮みきったバネ)の密度が小さく)、物体はその中を進みにくくなり── “原始ヒッグス場抵抗”が小さいほど、原始ヒッグス場の“4面体”が少なく(=“4角形”(縮みきったバネ)の密度が大きく)、物体はその中を進みやすいことになる。
|
“原始ヒッグス場抵抗”
|
大きい
|
小さい
|
|
進む物体が受ける抵抗
|
大きい
|
小さい
|
|
運動する物体
|
進みにくい |
進みやすい |
|
“4面体”
|
多い
|
少ない
|
|
「重力子&“4角形”
(縮みきったバネ)」
|
少ない
|
多い
|
例えば、質量Mを持つ物体Pが、次の図のように重力子を放出しているとする。
すると、他の物体Oは、この物体Pに近ければ近い場所にあるほど──
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高い場所にいる(=抵抗をもたらす“4面体”の密度が小さい場所にいる)ことになり、“原始ヒッグス場抵抗”が小さくなるので、他の物体Oは、物体Pに近づく方向にこそ運動しやすく(移動しやすく)なると考えられることになる。
例えば、図のような位置にある、同じ質量を持つ物体O1、O2、O3を考えれば、O1が一番、物体Pの方向へ運動しやすく(移動しやすく)、O3が一番物体Pの方向へ運動しにくい(移動しにくい)ことになる。
すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度がより高ければ高いほど、その方向へ運動する際の抵抗(=“原始ヒッグス場抵抗”)が少なくなっているので── その方向へ進みやすくなると考えられるのである。
まさに、このたりに“重力の実体”があると考えた。 よって次の仮説を立てた。
仮説2.4.1 “原始ヒッグス場抵抗”がより小さい方への(=“4角形”(縮みきったバネ)の密度がより高い方への)運動しやすさ── これが、重力の実体である。
つまり、物体は、ただただ、“原始ヒッグス場抵抗”が、より小さくて、より動きやすい方向に動いている(移動しやすい方向に移動している)だけであり── その過程が、“重力という力によって引っぱられている”と観察されているに過ぎないことになる。
(=つまり、重力は、「“原始ヒッグス場抵抗”が大きい方から、小さい方へ進みやすいという傾向”によって、そこに存在しているように見える力である」に過ぎないと言える)
“4角形”(縮みきったバネ)が増えるほど、“4面体”が減り──、“4角形”(縮みきったバネ)が減るほど、“4面体”が増えるという関係があるので──
「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”の変化量」は、「(重力子とともに放出される)“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」の符号を変えたものに等しいと考えられる。
(つまり、「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”の変化量」=−「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」の関係があると言える)
「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”の変化量」のことを── (電位勾配に習って)“重位勾配”と呼ぶことにする。
すると、(電位勾配が電場、すなわち電気力に等しいように)、この“重位勾配”は、重力場、すなわち重力に等しいことになる。
※重力の実体は、この“重位勾配”、すなわち、「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”の変化量」であるということもできることになる。
※上記のようなしくみで重力が生じるとすると── もし、重力子を一切放出しなければ、重力によって相手の質量を加速させることが一切できないことになる。
重力場を生じるような“質量”の実体とは、「重力子を放出する能力」であるということになる。
※以上の考察は、“量子化された重力”について考える際のよりどころとなると思われる。
この考察をもとにすると、重力や重力ポテンシャルエネルギーを数式でどのように表されるかについては、下記の考察で行なう。(→《量子化された重力の計算》)
例えば、全く同じ質量をもつAとBが2つ近くにあったとしたら、次のようになる。
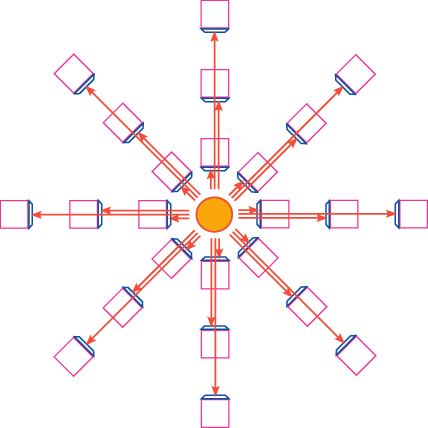 |
+
|
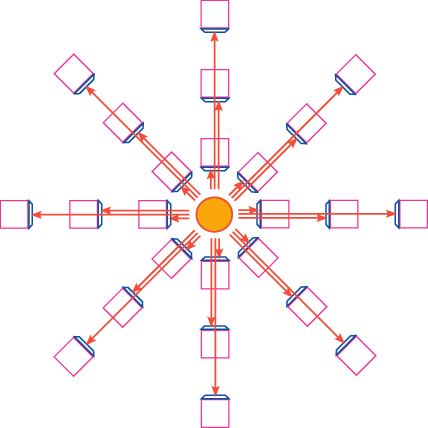 |
|
A
|
|
B
|
|
Aは、Bが作る“重位勾配”(=重力場)にしたがってBの方向へ移動するだろう。
Bは、Aが作る“重位勾配”(=重力場)にしたがってAの方向へ移動するだろう。
その結果、AとBは互いに引き合うように見える形になる。
そして、最終的に1つになる。
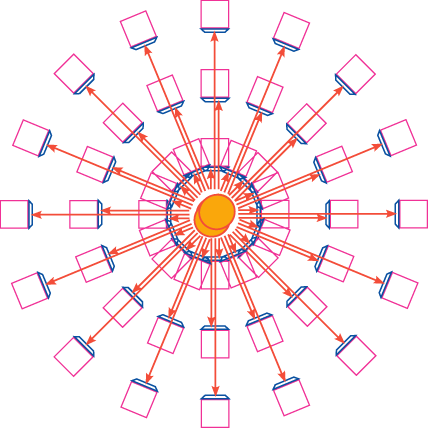 |
|
A&B
|
|
その結果、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化量──“重位勾配”は、(質量欠損がなければ)単に2倍になるであろう。
それは、質量に比例して重力が大きくなるというニュートンの万有引力の法則の数式が示す内容と合致する。
※ある物体の周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度が高いほど(=原始ヒッグス場の“4面体”が少ないほど)── 別の物体にとって“4面体”から“4角形”(縮みきったバネ)へわざわざ変形する手間が省かれる(運動の抵抗が減る)程度が大きくなるので、よりその方向へ移動しやすくなる。
それは、ある物体の周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高いほど、重力が大きくなることを意味している。
つまり、この説明は、“質量が大きいほど重力が大きくなる”というところのニュートンの“万有引力の法則”とも合致する。
※この説明は、ニュートン力学のみならず、重力を“時空の曲がり”の所産としたアインシュタインの説明とも、合致していると思われる。
次に、“時空の曲がり”について、考察する。
《“時空の曲がり”&重力場の実体像》
アインシュタインは、一般相対性理論によって、重力は“時空の曲がり”によって生じる(重力場は“時空の曲がり”である)と説明した。
しかし、“時空の曲がり”という表現は、それだけでは、十分な表現ではない(or 比喩にすぎない)と思われる。
なぜなら、(“2D平面の曲がり”は、確かにイメージできるが)、“3D空間の曲がり”そのものを、直接、はっきりとイメージすることが困難だからである。
“幾何的な実体原理”や“シンブル一様化原理”によると、重力という名の基本的な“自然(nature)”がイメージ不可能な実体からなりたっているとは、考えにくいと思われる。
つまり、このことは、実際に“時空が曲がっている”のではなく、“時空が曲がっている”と解釈できるようななんらかの(イメージ可能な)実体がひそんでいると考えるべきであることを示唆しているのである。
この“時空の曲がり”と解釈できる重力場の実体について、“素スピノールからの創発モデル”は、次のような説明する。
重力場を生じるものの実体とは、「原始ヒッグス場の“4面体”と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和」である。
それは、次のような性質から導かれる説明といえる。
|
原始ヒッグス場の“4面体”があると──
|
= |
運動の際、抵抗を受ける
(ヒッグス場の基本構造の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間がかかる) |
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」があると──
|
= |
(運動の際、抵抗を受けないので)
その方向に運動しやすい
(ヒッグス場の基本構造の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省ける) |
以上をふまえ、もう一度、次の図を見る。
質量が大きいほど、周囲の「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」も大きくなり、重力が大きくなることが読み取れる。
「〜 電場の強さEは、電場の向きの長さ1mあたりの電位差を表していることがわかる。 このことから、電場の強さを電位勾配ということがある」(『新しい高校物理の教科書』講談社ブルーバックス)に習うと──
「重力場の強さは、重力場の向きの長さ1mあたりの“重位差”を表している」ことになる。 また、「この重力場の向きの長さ1mあたりの“重位差”が“重位勾配”である」といえる。 (※“重位”=重力ポテンシャルエネルギーであると考えられる)
そして、この「重力場の向きの長さ1mあたりの“重位差”」=“重位勾配”の実体が、まさに、「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」であると考えられるのである。
|
重力場の強さ(=重力)
|
重力ポテンシャルエネルギー |
|
=「重力場の向きの長さ1mあたりの“重位差”」
=“重位勾配”
=「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」
|
“重位”
|
よって、以上が正しければ、次の結論が得られる。
結論2.1 アインシュタインが“時空の曲がり”と呼んだところの“重力場”の実体とは、「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」である。
したがって、重力場が“時空の曲がり”であるならば── “時空の曲がり”の正体は、「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」であるということになる。
しかし、そもそも、「重力場が“時空の曲がり”である──」 とは、どういうことを意味しているのだろうか?
結論から言うと、下記の考察《等速運動と特殊相対性理論》)説明するように── 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度」が高いほど、「時間の流れが遅くなり、空間は膨張する」ことを意味していると思われる。 つまり、「時間の流れが遅くなり、空間は膨張する」が、“時空の曲がり”が本来、意味していることであると思われる。
つまり、重力場=“重位勾配”の総和の実体が、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和の所産である一方──
“時空の曲がり”=「時間の流れの遅延&空間の膨張」の総和の実体も、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和の所産であることになる。
重力場と“時空の曲がり”の関係を結びつけるミッシングリンク── それが、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和なのである。
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和こそが、重力場も“時空の曲がり”も、両方を説明できる本質的な実体なのである。
この「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和こそが、重力場=“時空の曲がり”というアインシュタインの比喩的な説明を、理解するカギだといえる。
(「重力場とかけて、“時空の曲がり”と解く。 その心は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和である──」ということになる)
※以上の説明が正しければ、“時空の曲がり”&重力場と解釈できるものの実体像を、(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として)3D空間の中においても、比較的しっかりイメージできると思われる。
重力場(=“重位勾配”)の働きのおかげで、地球は、太陽に引き寄せられ続け── 公転し続けていることになる。
一方で、この“時空の曲がり”のおかげで、時間の流れが遅くなり、空間が膨張する。
そして、重力場と“時空の曲がり”は、同一の実体によって担われているので── 「重力場とは、“時空の曲がり”である」という比喩めいた表現も可能となり、間違いではなくなることになる。
しかし、それは、本質を見失わせうる(誤解を招きうる)、曖昧な表現だと言えるかもしれない。
※たとえ、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が大量に通過していたとしても── もし、そこに“勾配”or“密度の変化(密度差)”がなければ、重力場も“時空の曲がり”もなく、重力も生じないことになる。 例えば、人が地球に引っ張られるのは、その方向にのみ“勾配”(“密度の変化(密度差)”)があるからである。 それと直角な方向(水平な方向)には、“勾配”(“密度の変化(密度差)”)がないので── (たとえ重力子が大量に存在していたとしても)力が生じることはない。
そして、以上のもとに、次の仮説を立てた。
仮説2.4.2 アインシュタインの一般相対性理論の数式は、「重力子&原始ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)の挙動」の総和を表現している。
※正しければ、アインシュタインの一般相対性理論が説明する世界は、すべて、「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動の総和」として、解釈できることになる。
※スピノール2つ分で、ベクトルが生まれるように(例…光子(素スピノール2つ)から電場や磁場のベクトルが生まれる)── ベクトル2つ分で、テンソルが生まれるということでいいのだろうか? (例…重力子(光子2つ)から、時空のひずみ“テンソル”が生まれる) 今後の課題である。
《重力場と“重力線”》
重力場=“重位勾配の総和”(「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動の総和」の所産の一例)を、図で表現するために── 電気力線や磁力線に習い、“重力線”を考えることができる。
当然、“重力線”上だけに“重位勾配”があるわけではなく、実際は、(あらゆる方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放射状に放出されているので)あらゆる場所に“重位勾配”が存在していると考えられる。
また、球面の面積は半径の2乗に比例する(球面積S=4πr2)ので、物体から距離が大きくなるほど、距離の2乗に反比例して、“重力線の密度”が減ることになる。
つまり、中心の物質に近づくほど、物体から距離の2乗に反比例して、(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が増えるので)“重位勾配”、つまりは重力が大きくなると考えられる。
この“重力線の密度”&“重位勾配”の性質は── ニュートンの万有引力の法則の式と合致する。
つまりは、“重力線の密度”=“重位勾配”の大きさ=“重力の大きさ”=“重力場の強さ”=「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度=“時空の曲がりの強さ”ということになる。
“重力線の密度”が高いほど、“重位勾配”、重力、“時空の曲がり”… が大きくなることは── 電気力線や磁力線の密度(単位面積あたりの本数)が高いほど、電気力や磁力が大きくなることと同様である。
“等電位面”と同様に── “等重位面”を考えることもできる。
※実際は3次元に放射されているので、 “等重位面”は、実際は球面である
“等重位面”の間隔は、物体に近づくほど狭くなる。 それは、物体に近づくほど、“重位勾配”=重力が大きくなることと合致する。
※“等重位面”とは、重力ポテンシャルエネルギーが等しい面であるとも言える。
※質量が小さいほど“重力”や重力場&“時空の曲がり”が小さくなるように── “重力線の密度”も小さくなる。
逆に、質量が大きいほど“重力”や重力場&“時空の曲がり”が大きくなるように── “重力線の密度”も大きくなる。
※“重力線”の密度が高いほど、物体から放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、高くなる。
もし、同じ質量を持つ物体(天体を含む)の“サイズ(大きさ)”が変化すれば── 物体の周囲の、“重力線”の密度=重力場の大きさ=“重位勾配”の大きさ=“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度=“時空の曲がりの大きさ”も、変化する。
物体(天体を含む)のサイズが小さくなる(コンパクト化する)ほど、物体周囲の“重力線”の密度が高くなり、周辺の重力、“重位勾配”、“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度、時空の曲がり…が大きくなっていることが読み取れる。
なお、上図では、質量の大きさはどれも同じなので、重力子が放出される頻度は、どれも同じである。
しかし、物体がコンパクト化するほど── “重力線”の密度が高い領域が増えることが読み取れる。
※これは、“時空の膨張(宇宙の膨張)”と関連していると考えられる。(→考察3、考察13)
《重力子の働きと慣性》
重力子の働きと“慣性”の関係について考察する。
ニュートン力学と、特殊相対性理論によると──
宇宙空間上で静止している物体に力を加えると、物体は加速運動し、運動エネルギーを増すと同時に、質量エネルギーを増す。 その加速される際、静止していた物体は、もとのように静止し続けようとして抵抗する。 その“抵抗、動かしにくさ…”が慣性である。
そして、いったん加速した物体は、力を加えるのをやめても、等速直線運動を続ける。 その“勢い、はずみ、止めづらさ…”も慣性である。
特殊相対性理論によれば、ある静止している物体が加速運動すると、運動エネルギーを増すと同時に、質量エネルギーを増す。
“素スピノールからの創発モデル”によれば──
静止した物体を動かし始める際の“抵抗、動かしにくさ…”といった“慣性”が生じるのは、まさに、原始ヒッグス場の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形することが必要になるからだと考えられる。 いったん、“4角形”(縮みきったバネ)まで変形されれば、重力子とともに“4角形”(縮みきったバネ)が、光速で運動方向に放出されると考えられる。 そして、まさに、その重力子の放出能力アップが、「運動エネルギーを増すと同時に、質量エネルギーを増す」ことと合致する。
次の仮説を立てた。
仮説2.5.0 静止していた物体が加速しようとすると── 元々の静止質量由来の重力子の放出の他に、運動方向に新たに重力子の放出が始まるようになる。
正しければ、この過程が“動かしにくさ”という意味での“慣性”の実体であると同時に── 特殊相対性理論が説明する、運動エネルギーの増加とともに生じる質量エネルギーの増加の実体であることになる。
そして、物体を加速し、新たに“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させる過程での抵抗力が、慣性力の実体である。
そして、力を加えるのを止めても、いったん加速した物体は、等速直線運動をしている間も、新たに始まった重力子の放出をそのまま保ち続けると考えられる。
ところで、なぜ、等速直線運動が可能になるのまであろうか?
原始ヒッグス場の“4面体”を変形させる必要性は、どこまでもいつまでも続くはずではないのか?
等速直線運動をしている間も、なんらかの方法で、物体の進行方向にある原始ヒッグス場の“4面体”を次から次へと““4角形”(縮みきったバネ)に変形させ続けていることが予想された。
そこで、“とまりにくさ”という意味での慣性の実体像について、次の仮説を立てた。
仮説2.5.1 いったん等速運動を始めた物体は、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を、次から次へと、進行方向へ生じ続けるようになる。
その物体の進行方向と同じ方向に進む重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和は“流れるプール”のような働きを生む。
本当に、そのようなことが可能なのだろうか? 以下で、そのことについて考察する。
プランク質量より大きな質量を持つ物体○が、多数集合して構成される静止した物体(静止質量m0)を考える。
それを、下のような単純化したモデルを使って表記する。
オレンジ色の○が、プランク質量より大きな質量を持つ物体である。
※“4角形”(縮みきったバネ)が放出されている様子を示す。
| ※上図は、64個の |
|
が、1つの物体を構成している様子を示す。 |
※実際は、3Dのランダムな方向に重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を放出する。
「光速で“4つの方向にしか運動できない”ミクロの粒子が想定されている」と考えることが出来る。 |
物体が(マクロレベルで見て)静止しているように観察されたとしても、(○の中に多数存在する)ミクロレベルの素粒子が、光速で運動し続けているので── 物体から重力子が放出される。
それが、上記の物体が持つ、静止質量エネルギーm0c2の実体であると考えられる。
実際は、○の中の素粒子たちが、ミクロのレベルで光速で運動し続けているおかげで重力子が放出されているわけであるが── 大雑把に見て、“○の微小な運動が、原始ヒッグス場の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させて、重力子を、ある頻度で放出している”と解釈することができる。
この物体(静止質量m0)が、(光速よりずっと小さい)速度vで、等速直線運動をしている状態について、次のように仮説を立てた。
仮説2.5.2 ある物体(静止質量m0)が(光速よりずっと小さい)速度vで運動するようになると、(もとからあったm0c2のエネルギーに相当する重力子の他に)新たに“m0v2/2”のエネルギーに相当する、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を運動方向に放出する。
※光速運動と原始ヒッグス場の相互作用により、m0c2のエネルギーに相当する重力子を放出されるのに、
なぜ、単純に速度vの運動と原始ヒッグス場の相互作用により、m0v2のエネルギーに相当する重力子が放出されず、その1/2だけで済むようになるのだろうか?
たしかに、個々の素粒子(質量をm素と表記することとする)が単独で、 速度vで進むならば、m素v2に相当する重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を放出するであろう。
|
|
|
| ※重力子&“4角形”(縮みきったバネ)は、運動方向にのみ放出される。 |
しかし、素粒子の集団が運動する場合は異なることが起こると考えられる。
物体が速度v で運動するとは、その素粒子の集積が、一緒に速度vで運動することに相当する。
m素が単独で進んだ場合、800回重力子を放出する距離をL800とすると──
物体の集合がL800だけ進む際、それぞれの素粒子が何回重力子を放出するかを考えてみる。
|
速度vで、等速直線運動
|
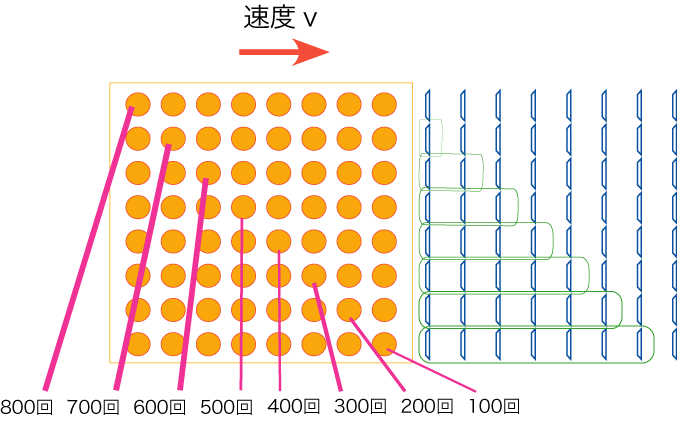 |
※例えば左端の素粒子が800回重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を放出する必要があるのに対し、
例えば、右端の素粒子は、100回の放出で済むようになると考えられる。
なぜなら、後ろから他の素粒子が放出した重力子&“4角形”(縮みきったバネ)が、流れてくるからである。 他の位置にある素粒子も同様である。
※緑で囲った部分は、後ろから流れてくる重力子&“4角形”(縮みきったバネ)に相当する。
|
以上のことをグラフにすると次のようになる。
つまり、この面積は、三角形であるので── “それぞれすべてが800回放出する”と考える場合の、ちょうど1/2だけの重力子が、(素粒子がまとまって運動する場合には)放出されることになる。
つまり──
仮説2.5.2 ある物体(静止質量m0)が速度vで運動するようになると、(もとからあったm0c2のエネルギーに相当する重力子の他に)新たに“m0v2/2”のエネルギーに相当する、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を運動方向に放出する。
と合致する。
一方、下の図から、その運動方向に生じる重力子のエネルギー“m0v2/2”が“時空の流れるプールの効果”に与する様子が詳しく理解できる。
速度vで、等速運動 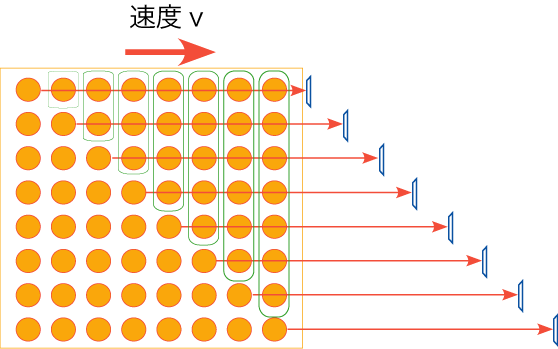 |
※上図の左から1番目の列の列の○が0個の重力子の作用を受けるのに対し、
左から2番目の列の○が1個、左から3番目の列の○が2個、左から4番目の列の○が3個…
というように、一般に右からn番目の列の○がn−1個の重力子の作用を受けることになる。
もし、nがとても大きな数になれば、n番目は、n個の重力子の作用を受ける見なしてよいと
考えられる。 これをグラフにすると次のようになる。
|
このグラフは、その運動方向に生じている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」のエネルギー“1/2m0v2”が、物体のどこに“再投資”されることを意味する。
そして、この再投資される“m0v2/2”と── 物体の“運動エネルギー”m0v2/2は、ぴったり等しい。
まさに、このことによって、等速直線運動が実現していると考えられる。
(つまり、「流れるプール効果の作用」という“再投資”が、等速直線運動を実現させていると考えられる)
そもそも、「流れるプール効果の作用」とは何であろうか?
単純に、すべての重力子が通過する方向に“流れるプール効果”が生じるのではない。 なぜなら、例えば、太陽から放出された重力子は、地球を通過しているが、重力子が進む方向に“流れるプール効果”が生じていないからである。
太陽から放出された重力子は、重力場(“重位勾配”)を形成し、地球を太陽に引っ張る働きをする。
“重位勾配”の実体は、周囲の原始ヒッグス場の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にする手間が省ける程度の差である。 ( 太陽に近い側が大きく、太陽から遠い側が小さい)
“時空の流れるプール効果”が生じるのも、“重位勾配”に基づくのではないかと考えた。
そして、そういう目で、この図を見ると── 右に行くほど、物体が周囲の“4面体”を“4角形”にする手間が省ける程度を示す、負の“重位”が大きくなっていることを示していると解釈できることに気づいた。
ここに生じた“重位勾配”によって、物体が引っ張られることが、“時空の流れるプール効果”の実体に相当するのである。
つまり、“時空の流れるプール効果”がしてくれることは、原始ヒッグス場の中を運動する際の抵抗を0にしてくれることであることになる。
そして、この働きが、等速運動を実現してくれることになる。
つぎのようになる。
いったん、速度vの等速運動を始めると──
『速度vで等速運動
→m0v2/2分の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出
→そのエネルギーが物質の運動へ再投入(「流れるプール効果の作用」の効果が生まれる)
→原始ヒッグス場を進む際の、抵抗が0になる。
→ 『速度vで等速運動
→m0v2/2分の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出
→そのエネルギーが物質の運動へ再投入(「流れるプール効果の作用」の効果が生まれる)
→原始ヒッグス場を進む際の、抵抗が0になる。
→ 『速度vで等速運動
…
を繰り返し続けることになるのだろうか?
いずれにせよ、この「流れるプール効果の作用」が等速直線運動を可能にするしくみ本質であると考えられる。
この「流れるプール効果の作用」のおかげで、原始ヒッグス場の“4面体”の抵抗の中を、一切の力を新たに加えることなく(外から新たなエネルギー投入することなく)、等速直線運動を続けることが可能となる。
これが、“とまりにくさ”に関連した慣性の実体ということになる。
※静止状態に力を加え、いったん、ある速度に達してしまうと、その後は、上記のような“時空の流れるプール効果”の作用のおかげで等速運動し続けるようになる。
この“時空の流れるプール”の働きのおかげもあって、地球は、公転し続けていることになる。
地球が太陽に引き寄せられ続けるのは、“時空の曲がり”(“重位勾配”、重力場)のおかげであり、
地球が太陽の回りを慣性で、進み続けるのは、“時空の流れるプール”のおかげである、と言える。
※いったん、あるスビードを持つに至った── 自動車(や自転車)、スーバーマーケットのカート、カーリングの石… アクセルを踏まなくても、ペダルをこがなくても、手を離しても… ほとんど、そのままの勢いで進み続けることは、この“時空の流れるプール”のおかげであることになる。
※ある質量を持つ物体が減速する際には、運動エネルギーが減ると同時に、“止まりにくさ(勢いor はずみ)”を支えていた“流れるプール効果”が慣性力となる。
※放出される重力子&“4角形”(縮みきったバネ)のエネルギーがm0v2/2となるのは、vが光速cに比べてずっと小さい時にのみ成立すると考えられる。
もし、vが光速cに近くなってくると、それによって生じる重力子のエネルギーは、m0v2/2よりも大きくなり、「m0c2(1−v2/c2)1/2−m0c2」となると考えられる。 すると“流れるプール効果”も、その大きくなる。 等速運動は、やはり同様なしくみで実現すると考えられる
※慣性には、2つの部分がある。 静止している物体の動かしにくさと、一度動き始めた物体の止まりにくさの2つである。
従来のヒッグス場による質量獲得について説明は、(粘つく“納豆やアメ”の比喩ように)“動かしにくさ”の部分だけに焦点があてられていたようである。
“素スピノールからの創発モデル”では、慣性の“動かしにくさ”と“止まりにくさ”の両方を説明する。
“素スピノールからの創発モデル”では── 慣性の“動かしにくさ”とは、ある質量を持つ物体が加速する際に、新たな重力子の“4角形”の放出が追加される過程での“抵抗力”として説明し── 慣性の“止まりにくさ”とは、ある質量を持つ物体が、等速運動している間に、進行方向に生じる重力子の“4角形”による“流れるプール効果”によって説明する。
“動かしにくさ(抵抗力)”のみでなく、“止まりにくさ(勢いor はずみ)”も、説明できるので── “素スピノールからの創発モデル”は、従来のヒッグス場による質量獲得の説明を改善できる可能性があると思われる。
《等価原理》
アインシュタインの等価原理とは、「加速運動と重力が等価である」という原理である。
自由落下する物体を考える。
自由落下する場合には、(アインシュタインの等価原理により)、慣性力(加速運動)と重力は、完全に打ち消し合う。
自由落下する物体が、大きな質量を持つ物体に近づくほど重力──“重位勾配”──が大きくなり続ける。
それは、質量を持つ物体に近づくほど、“重力線”の密度が高くなるからであり、物体から放出される重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度が大きくなるからである。
一方、その物質の方へ自由落下する物体は、加速運動をし続けるので、その運動に伴い“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変換させて、進行方向に重力子を放出させる頻度を増し続けながら落下する。
(物体を加速し、新たに“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させる過程での抵抗力が、慣性力の実体である)
大きな質量を持つ物体から放出される重力子による影響(重力)と、自由落下しながら進行方向に放出される重力子による影響(慣性力)は、ピッタリと打ち消し合う形となる。
(これが、アインシュタインの“等価原理”の実体像であると考えられる)
その結果、落下する物体は、見かけ上、いっさい相手から重力子を受け取りも、放出もしていない状態と同じになる。 それが、“無重力状態”として観測される。
つまり、慣性力(加速運動)と重力が、ともに重力子の放出で説明できることは、アインシュタインの等価原理(この慣性力と重力(重力場)は全く等しい)と合致していると言える。
※ある質量Mの物体が、観測者の方に向かって速度Vで等速運動している系を考える。
前項《重力子の働きと慣性》では、等速運動している物体から、重力子が放出されていることをのべた。
しかし、もし、ある質量Mの物体が、観測者の方に向かって速度Vで等速運動しているときには── “もとの質量M”がもたらす重力より重力が大きくなることはないと考えられる。
(なぜなら、等速運動している限り、その運動によって物体から放出される重力子の総和に、新たに“重位勾配”が生じることはないからである)
逆に、もし、ある質量Mの物体が、観測者の方に向かって加速度aで加速運動しているときには── “もとの質量M”がもたらす重力よりも重力が大きくなると考えられる。
(なぜなら、加速運動によって、新たに物体から放出される重力子の総和には、“重位勾配”が生じていると考えられるからである)
このことも、“加速運動と重力が等価である”ことを示している例であると思われる。
《連星系パルサー》
『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』によると、「アインシュタインは、1915年に発表した一般対性理論の中で加速運度している物体は、重力波の形でエネルギーを放出すると予言した。」とのことである。
重力波の実体は、重力子であると考えれば、この予言は、“素スピノールからの創発モデル”の説明と合致する。
ある物質をミクロのレベルで見れば、素粒子は光速で運動し続けており、その方向転換(加速運動)の際、原始ヒッグス場を変形させるように働きかけている。
素粒子の数が、ある閾値を越えると重力子を放出するようになる。 つまり、ある物質が質量をもっている場合、その物質の中のミクロのレベルの素粒子の“加速運動(方向転換)”の総和が、重力子を放出し続けていると言える。 このことも、「加速運度している物体は、重力波の形でエネルギーを放出するという」アインシュタインの予言と合致していると言える。
(そして、「マクロのレベルで加速運動している物体」のみならず、「マクロのレベルで見かけ上、静止している物体(等速直線運動している物体)」からも、常に重力子が放出されているからこそ、重力も働くし、等価原理が成立すると考えられることは、上に述べた。)
連星パルサーについての「伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいることが発見され、この重力波の存在が間接的に示された」という研究成果(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』)の中では──
「連星系パルサーからの重力放射に必要なエネルギーの源は、軌道運動エネルギーである。だから、重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら、軌道エネルギーはしだいに減少し、このために、パルサーとその伴星が渦巻き状に互いに近づきあい、軌道周期も減少するはずである。」というように、“重力子がエネルギーを持ち去る”という解釈がなされている。
“素スピノールからの創発モデル”によれば、加速していようが、静止していようが関係なく── 重力波(重力子)は、地球からも、太陽からも、人からも、(2×10-5グラム以上の)あらゆる物質から、常に光速で放出され続けている。
“地球、太陽、人…” が、質量を持つと同時に、ある頻度で生じ続けているものが重力子である。
いわば、(大きな物体の)質量とは、“重力子を生じる能力”である。
そして──
もし、運動エネルギーが増せば、“重力子を生じる能力”が増し、重力子を放出する頻度も増すし──
もし、運動エネルギーが減れば、“重力子を生じる能力”が減り、重力子を放出する頻度も減る。
よって、もし、“連星系パルサーの軌道運動エネルギーが減少”するのであれば、“重力子を生じる能力”が減り、放出される重力子の量(頻度)が減るだけである。
“素スピノールからの創発モデル”のパラダイムでは── そこに、“重力子がエネルギーを持ち去る”という現象はどこにも見当たらない。
そもそも、もし、仮に、“重力子がエネルギーを持ち去る”ことが実際に起こるならば── 電子も、クォークも… 含め、あらゆる物体の質量が減りつつけることになってしまい現実と矛盾してしまう。したがって、次の結論に至る。
結論2.2. 重力子が、エネルギーを持ち去るという現象は、実在しない。
一方、観測結果と、計算から求められた予測の数値と、ぴったり一致するのとのことである。
なにかがおかしい。
なぜか?
本当に、軌道運動エネルギーの減少が原因で、“連星系パルサーの軌道周期の減少”しているのだろうか?
逆に、はじめから、重力(ポテンシャル)が原因で(ニュートン力学で説明される、自由落下に似た、ごく単純なしくみで)、“連星系パルサーの軌道周期の減少”し続けているだけであると解釈する方が、自然ではないか?
観測されているものは、あくまで、「公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいること」だけである。
(“連星系パルサーの軌道運動エネルギーが減少”は、解釈にすぎず、決して実際に観測されされたものではない。 この記事にも「重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら」と書かれてある。)
また、次の文献によれば── “連星系パルサーの形成はまれなことであり、超新星系爆発の直後の運動の方向が、たまたま連星系パルサーの形成のためにふさわしい方向のときに限って、形成されるものである”ことがわかる。
「連星中性子星が形成されるためには、2度の超新星爆発を経る必要がある. 超新星爆発では、爆発で放出され質量が大幅に減る。これが連星で起きると、連星が解体する可能性がある.〜. 2つの星が、別々の方向に飛んでいってしまうのである. 〜 爆発が非対称的に起こって、軌道運動とはまったく関係のない方向に新たに誕生した中性子星が飛び出し、運良くもう一方の中性子星の飛んでいった方向に向かえば、連星のまま保たれることもあり得るが、確率は低い. だから、連星中性子性は大変珍しい天体なのである.」(『一般相対論の世界を探る 重力波と数値相対論』 柴田大 著 東京大学出版会 p21-23より一部抜粋)
したがって、「単純に重力によって引き合って(落下しあって)、“連星系パルサーの軌道周期の減少”し続けている」と解釈することは、少なくともナンセンスではなく── むしろ、より単純で、より自然な解釈である思われる。
(正しければ、実際は、重力場を自由落下する物体の運動エネルギーが増すように── 地球より、(地球の内側の)火星や水星の公転速度が速いことから類推できるように── “連星系パルサーの軌道周期の減少”によって、軌道運動エネルギーは、むしろ増すはずであると考えられる)
“素スピノールからの創発モデル”のパラダイムでは、“連星系パルサーの軌道周期の減少”と重力子の関係を、次のように説明する。
連星系パルサーの軌道周期が減少すれば、“質量分布のコンパクト化”が進むので、“重力子の放出量は増える”ように観測される。(考察3)
重力ポテンシャルエネルギーが運動エネルギーに転化するので、連星系パルサーの軌道運動エネルギーが増加するのに伴い、重力子の放出量も増える。
つまり、“連星系パルサーの軌道周期の減少”は、系が重力子を放出する能力を増やす方向に働くことを示している。
理論は、180度、逆である。 しかし、計算された予測数値は、観測とピッタリ一致する。 なぜか?
なぜなら、アインシュタインの一般相対性理論から導いた“四重極公式”によって計算され、持ち去られたと解釈されたエネルギーの減少分と、 運動エネルギーの増加にともない放出される重力子の量(頻度)の増加分が、数字的に等しいからではないだろうか?
連星パルサーの総運動エネルギーをK=(1/2)mv2とし、連星パルサーの総ポテンシャルエネルギーをU=−GmM/rとすると──
連星系パルサーの総エネルギーEは、E=K+U=(1/2)mv2+(−GmM/r)=GmM/2r+(−GmM/r)=−GmM/2r
となる。 (つまり、“総運動エネルギーKと総エネルギーEの和は、0になる”という結論を導く“ビリアル定理”があてはまっている)
つまり、“系の持つ総運動エネルギーK”= −“系の持つ総エネルギーE” である。
“四重極公式”は、連星系パルサーの総エネルギーEの単位時間当たりの変化量dE/dtを、“重力子によって放出される、単位時間あたりのエネルギー量”とイコールで結ぶことによって導かれている。 そして、これが、連星系パルサーの総エネルギーEの単位時間当たりの変化量dE/dtが、“重力波として単位時間当たりに持ちさられるエネルギーの減少分に等しい”という解釈を与えたと思われる。
しかし、ここで、連星系パルサーの総エネルギーEは、連星系パルサーの総運動エネルギーKと、正負の符号が逆で絶対値が等しいことを当てはめる。
連星系パルサーの総運動エネルギーEkの単位時間当たりの変化量dEk/dtと、“重力子によって放出される、単位時間あたりのエネルギー量”を、正負の符号を変えてイコールで結ぶことができることを意味している。 これは、連星系パルサーの総運動エネルギーEkの変化量dEk/dtが、“重力波として放出できるようになったエネルギーの増加分”に等しいと解釈できることを意味すると考えられる。
これは、まさに、運動エネルギーが増す(≒物体が加速する)と、その分、“重力子の放出量が増える”という、これまでの考察と合致する。
“重力波による持ち去りの解釈を生む(総)エネルギーの減少分”、“重力波の放出能力アップの解釈を生む(運動)エネルギーの増加分”── その絶対値が(ビリアル定理によって)たまたま一致しているのである。
確かに、「伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいることが発見され、この重力波の存在が間接的に示された」という結論は変わらないし、この記述自体は、正しいままであることになると思われる。
しかし、その背後で実際に起きていると考えられる2つの現象── “重力波による持ち去り”、“重力波の放出能力アップ”には大きな違いがある。
果たしてどちらだろうか?
むろん、“素スピノールからの創発モデル”のパラダイムでの、これまでの考察は、後者であることを示唆しており、このパラダイムは次の結論を導く。
結論2.3 「伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいる」という観測結果と、アインシュタインの四重曲公式による予測値は── 重力ポテンシャルエネルギーが消費されて、連星の運動エネルギーが増す(≒物体が加速する)ことに伴い、その分、“重力子の放出量が増える”という事実を反映している。
連星パルサーの観測結果および予測数値値は、こういった理論(事実認識、パラダイム…)をサポートする証拠である、と解釈できることになる。
なお、アインシュタイン自身も、“重力波がエネルギーを持ち去る”という解釈とも関連すると思われる、次のような問題意識をもっておられた。
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』 (『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より)
この文章から、「重力子がエネルギーを持ち去り、系のエネルギーが減る」ようなことが起こると考えることは、一般相対性理論の正当性に疑いをもたらすほど、おかしな考え方であると、アインシュタイン自身が考えていたらしいことも読み取れると思われる。
連星系パルサーに関する、このあたりの問題は── もしかしたら、“四重極公式”は、本来、“重力波によって持ち去られるエネルギーの減少量を示す式”ではなく、“重力波の放出能力をアップさせる運動エネルギーの増加量を示す式”だと解釈すれば、解決できる問題に過ぎないのかもしれない。
なお、“重力波の放出能力アップ”は、まさに“質量の増加”を意味していると考えられ、特殊相対性理論の説明と合致していると思われる。
以上の詳しい検討&検証は、今後の課題であると思われる。
《等速運動(慣性系)と特殊相対性理論》
特殊相対性理論に関して、次の仮説を立てた。
仮説2.8.1 アインシュタインの特殊相対性理論の数式が示す世界(光速度不変の原理、相対性原理)も── 時空の素スピノールのネットワークのすべて(原始ヒッグス場、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)…)で説明できる。
特殊相対性理論は、あらゆる慣性系(あらゆる等速直線運動をしている系)で観測する光の速度は一定であること=“光速度不変の原理”を内在させている。
“素スピノールからの創発モデル”では── 光子とは、“原始ヒッグス場”のバネを利用して、素スピノールのペアが、“転回のリレー”を行いながら光速で移動するものであることを示している。
これは、ある種の“新しいエーテル”の存在を認めることになるので、一見、“光速度不変の原理”が破れてしまうことを意味するようにも見える。
しかし、そもそも“原始ヒッグス場”は、時空構造であり、かつての“古いエーテル”が想定していた“物質”とは異なる。
“素スピノールからの創発モデル”&“原始ヒッグス場”でも、なんらかのかたちで、“光速度不変の原理”が成り立っているはずである、という仮説を先に立てた。
以下に、“素スピノールからの創発モデル”&“原始ヒッグス場”の理論で、“光速度不変の原理”がいかにして保たれるかを考察する。
光速c(km/s)=30万km/sであるとして話を進める。
簡単にするため、光源からちょうど30万kmはなれた観測者を考える。
すると、当然、光源から放出された光、つまり、光子は、1秒後に観測者にたどり着くことになる。
かりに、光源も観測者も、ともに“原始ヒッグス場”に対して静止しているとすると── 当然、観測される光速は、秒速30万kmである。
次に、観測者が、速度Vで、光源の方に向けて等速運動しているとする。
すると、自然に考えると── 「1秒間に光が、“原始ヒッグス場”の上で30万km進み、同じ1秒間に観測者は“原始ヒッグス場”の上でVメートル進むのだから、観測者から見て、光は、合わせて1秒間に、30万km+V(m)進むことになる── つまり、光速は、c+Vとなり、観測者にとっての光速は、秒速30万kmを越えてしまうことになる」という結論に至ってしまうかもしれない。
ところが実際は違う。
実際には、観測者は、静止していても、速度Vで運動していたとしても、光速c──「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」──を観測する。
それこそが“光速度不変の原理”である。
※これより、もっと厳密な図示の仕方があるかもしれないが、
おおよその意味は読み取れると思われる。
|
何が起こっているのだろうか?
静止した観測者と、Vで等速運動している観測者の間で何かが決定的に違っているはずである。 何か?
“素スピノールからの創発モデル”のパラダイムは、上記の考察のように、“運動する物体は、前方に重力子を放出していること”が決定的に違うことを示す。
等速運動している間、その運動方向に重力子が放出されていて、それが“慣性”(流れるプール効果)を生んでいると考えられることは前に述べた。 まさにその運動方向へ放出している重力子が、運動方向に存在する時空の性質を変化させている結果、“光速度不変の原理”をもたらしているのではないだろうか?
どのように変化させているか?
「時空を膨張させる方向、時間の流れを遅くさせる方向」に変化させているのである。
これらの変化が作っている効果──「時空を膨張させている効果、時間の流れを遅くさせている効果」は、(原始ヒッグス場の上での)速度Vの運動が持つ、「光源との距離を短縮させている効果、光子が観測者にたどり着くまでの時間を短縮短させている効果」をキャンセルしてしまうと考えられる。 その結果、観測者は、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測する。
つまりは、このようにして、あらゆる慣性系は、それぞれに「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測するようになる。 これが、“光速度不変の原理”の実体ではないだろうか?
だれが、どのような等速運動をしていようが関係なく、その等速運動に伴って重力子が放出されている結果、時空の性質が変わっているので、観測者は、それぞれの時空(それぞれの慣性系)が持つ“時間と長さのものさし”で、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測すると考えられるのである。
※(第三者が外側から観測することによって)運動している物体が収縮しているように見える“ローレンツ収縮”は、運動の進行方向にのみ収縮する。 このことは、重力子が運動方向にのみ放出されることと合致する。
なぜ、等速運動がもたらしている、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の分布の変化が、「時空を膨張させている効果、時間の流れを遅くさせている効果」を生むのか? それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、光子が転回する原始ヒッグス場の“4面体”の足場の比率を減らすことによって── 光子が転回する過程を妨げ、単位時間あたりの、光子が転回する回数を減らすからだと考えられる。 この考えは次の仮説に基づいていると言える。
仮説2.8.2 原始ヒッグス場での、(光子を構成する)素スピノールの“転回そのもの”が、“時の刻み”に相当する。
※正しければ、“運動の進行方向に生じている重力子”のおかげで、運動の進行方向の光子の転回(=時の刻み)が減り、それが原因で、時間の流れが遅くなることになる。
この仮説は、一般相対性理論が示すように、強い重力場であるほど、時間の進み方が遅くなることと合致する。
なぜなら、強い重力場であるほど、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高くなるので、光子にとっての足場──原始ヒッグス場の“4面体”の足場が減り、転回しにくくなるからである。
極端な話、もし、光子が転回できなくなっていれば、そこでは時間の流れが止まっていることになる。
例えば、ブラックホールの中の、原始ヒッグス場の“4面体”の足場が100%消失している場所では、光子は全く転回できなくなっているので、時間の流れが止まっていることになる。 当然、光子は、それ以上先へは進むことができなくなる。 これが、「ブラックホールの外に光が出て行けなくなる」ことの背後に起こっている実体であると考えられる。
観測者の等速運動の速度Vが大きければ大きいほど、原始ヒッグス場の中での「縮みきったバネの“4角形”by重力子」の比率が大きくなるので、それだけ時間の遅れも大きくなると考えられる。
そのことは、その時間の遅れが、特殊相対性理論(ローレンツ変換)から求められる式── t’=(1−(V/c)2)1/2 t
が示す計算結果と合致すると思われる。 (この式もVが大きいほど、時間t’の値が小さくなり、時間の進み方がおそくなることを示している)
一方、空間の膨張は、どう説明できるだろうか?
原始ヒッグス場の中での、「縮みきったバネの“4角形”by重力子」の比率を仮に、a%とする。
※ブルーが基本ヒッグス場の“4面体”、レッドが「縮み切ったバネの“4角形”by重力子」である
すると、「縮みきったバネの“4角形”by重力子」による空間の膨張率は、単純に 100/(100−a) で求められると考えられる。
(これだと、a=0%なら、空間の膨張率は1倍(変化なし)となり、a=33%なら、空間の膨張率は約1.5倍となり、a=50%なら、空間の膨張率は2倍となり、a=100%なら、膨張率は無限大となり、うまく合致する)
なお、空間の膨張率= 100/(100−a)は、光速c、等速直線運動の速度Vを用いて表記すると、空間の膨張率= c/(c−V)と書き換えることができる。
(なぜなら、上図で、観測者による運動によって、1秒後の光源観測者の距離(c-V)を打ち消すように(c-V)が cになるように)空間が膨張するはずだからである。 あるいは、また、単純にa%は、光速c、等速直線運動の速度Vを使うと、a=(V/c)×100%で求められると考えられるからである。 つまり、 100/(100−a)=100/(100−(V/c)×100)=1/(1−(V/c)= c/(c−V)となる。 これは、「光速の何%で、運動しているか?」が、そのまま原始ヒッグス場の中に占める「縮みきったバネの“4角形”by重力子」の比率に相当していることになる。 静止していれば光速の0%で運動しているので空間の膨張率は1で変化せず、光速の50%で運動していたら2倍に空間が膨張し、もし100%で運動していたら無限大に空間が膨張することとなり、うまく合致していると思われる)
つまり、速度の等速直線運動に伴い、「縮みきったバネの“4角形”by重力子」が、放出されていることにより、時空が変化し、
その際、時間は、t’=(1−(V/c)2)1/2 t で遅れ、空間は、 c/(c−V)の割合で膨張するということになる。
以上のことが、特殊相対性理論が示している“光速度不変の原理”の背後で起きていることの実体であると考えられる。
それは、やはり、それぞれの慣性系が、それぞれ独自の“距離&時間”(時空)を持ちうることの実体でもある。
※第三者が、外側から観測すれば、物体が短縮しているように見える(ローレンツ収縮)。
一方で 物体と一緒に運動している本人が、内側から観測すると、何も変わらず、いつもの長さ、いつもの時間の流れで、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測することになる。
(なぜなら、運動によって距離&時間が短縮する分が、(運動に伴って放出される「縮みきったバネの“4角形”by重力子」によって空間が膨張し時間がおそくなるので)、ぴったりとキャンセルされる(打ち消される)からである)
(だからこそ、秒速30kmで太陽のまわりを公転している地球上でも、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測する)
このことは、「運動の内側から観測されることと、運動の外側から観測されることが、違いうる」ことを意味している。
ある時空の構造(=ある「縮みきったバネの“4角形”by重力子」の分布)をもたらしている運動が等速運動であれば── 「縮みきったバネの“4角形”by重力子」の比率は、その運動方向では、どこでも一定となるので、その運動方向に“重位勾配”は、まったく生じない。 しがって、光源となる物体の等速運動による時空構造の変化であろうと、観測者側の等速運動による時空構造の変化であろうと、同様な“時空の変化による効果”がもたらされると考えられる。 このことは、相対性原理と合致する。
以上のように、“素スピノールのネットワーク”は、少なくとも“相対性原理”や“光速不変の原理”と合致している点で、かつて否定されたところの“エーテル”(物質としてのエーテルである。“古いエーテル”と呼ぶこととする)とは異なる実体であることが分かる。
※なお、アインシュタイン選集2 [A10]『エーテルと相対性理論』によると、アインシュタインは、(特殊相対性理論で否定された形になったが、一般相対性理論に基づき)結局は、“エーテル”を必要不可欠と考えていたことが分かる。
『すなわち一般相対性理論によれば、空間は物理的特性を与えられている。それゆえこの意味でエーテルは存在する。 一般相対性理論によればエーテルを伴わない空間を考えることはできないものである。なぜならば、そのような空間では光も伝播することができないし、また空間および時間の基準(すなわち物指と時計)も存在することができない。したがって物理学的に意味のある時間的、空間的距離というものも存在しえないことになる。しかしながらここに考えたエーテルが、質量をもったふつうの物質からできているとか、あるいはまた普通の媒質(水や空気のような)と同じような性質をもっていると考えることはできない。 たとえば、運動というような概念は、われわれのエーテルには適用できない』
このアインシュタインが必要不可欠と考えていたエーテルを“新しいエーテル”と呼ぶこととする。
“素スピノールからの創発モデル”によれば、この“新しいエーテル”の第一候補は、“原始ヒッグス場”である。
なせなら、“原始ヒッグス場”は、「光速度不変の原理」「相対性原理」も満たすからである。
そして、素スピノールおよび原始ヒッグス場は、物質でないし、それ自体は質量をもたない。
したがって、原始ヒッグス場は、上記の“新しいエーテル”が満たすべき条件も満たしている。
次に、光源が速度Vで、観測者の方に向けて等速運動している例について詳しく考える。
※光源が速度Vで運動している場合
※光源が静止している場合
光源が速度Vで運動していても、やはり、それに伴い、重力子が運動方向に放出され、運動方向の時空構造は変化していると考えられる。
その際、やはり、時間は、t’=(1−(v/c)2)1/2 t の割合で遅れていて、空間は、 c/(c−V)の割合で膨張している。
そのおかげで、たとえ光源が速度Vで近づいてきていたとしても、(光源が静止していたときと同様に)観測者は、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測する。(光速度不変の原理)
なお、その際、光のドップラー効果により、(光源が静止していたときと比べて)短い波長を持つ光を観測するであろう。
ところで、光のドップラー効果による振動数νの変化を計算する式は、次のようになっている。(参考 ウィキペディア『ドップラー効果』)
ν’=ν×(1−(V/c)2)1/2/(1−(V/c)cosθ)
光源が、観測者に近づいてくる場合は、θ=0度(cosθ=1)に相当し、上式は、ν’=ν×(1−(V/c)2)1/2/(1−(V/c)) となる。
この式をよく見てみると、“時間の遅れ”を導く式と、“空間の膨張”を導く式の両方がかくれていることがわかる。
なぜなら、ν’=ν×(1−(V/c)2)1/2/(1−(V/c))
=ν×(1−(V/c)2)1/2/((c−V)/c))
=ν×(1−(V/c)2)1/2×(c/(c−V))
と書き換えられるからである。
よって──
ν’=ν×(時間が遅れている割合)×(空間が膨張している割合)
となる。
つまり、光のドップラー効果の現象は、光源の運動にともなって重力子が運動方向に放出されていることに伴い、運動方向の時空が変化している結果、生じている現象であると解釈できることになると考えられる。
※これだと、θ=90度(cosθ=0)のときの、ν’=ν×(1−(V/c)2)1/2の式が説明する、“横ドップラー効果”は、“時間の遅れ”のみが関わって生じていることになり、うまく現実と合致していると思われる。
このことは、重力子が運動方向にのみ放出されるからであると考えられる。 (それは、 やはり、“空間の膨張”や、運動している物体が収縮しているように見える“ローレンツ収縮”は、あくまで運動の進行方向にのみ生じることと合致している)
※光源が近づく場合、一見、時間が遅れている効果によって光の振動数が減るかに思われるが── 空間が膨張している効果がそれを上回っているおかげで、光の振動数が増加しているように観測されると考えられる。
※なお、光源が遠ざかる場合も── その運動方向の時空が変化していると考えられる。 この場合は、逆に、元々放出されていた重力子の数が減ること&「縮みきったバネの“4角形”by重力子」の比率が減ることによって、時間の流れが早くなっていたり、空間が収縮していたりすると考えられる。
(それが、光速度不変の原理を保つための条件である)
すると、例えば、銀河が遠ざかっている場合に観測されるとされる、(光のドップラー効果の一例としての)光の赤方偏移も── (光源が静止している場合に比べて)、時間の流れが早くなっていたり、空間が収縮していたりすることによって生じているはずであることになる。
光源が遠ざかっているはずなのに、その間の空間は、収縮しているのである。 これは、明らかに矛盾している。
なお、速度V(>0)で遠ざかる場合は── ドップラー効果の式ν’=ν×(1−(V/c)2)1/2/(1−(V/c))の中のVの符号がマイナスに変わる。
したがって、遠ざかる場合の光のドップラー効果による振動数νの変化を計算する式は、
ν’=ν×(1−(−V/c)2)1/2/(1−(−V/c))
=ν×(1−(V/c)2)1/2×(c/(c+V))
(=ν×(時間が遅れている割合)×(空間が収縮している割合))
となる。 やはり、空間が収縮していればこそ、振動数νが減るという赤方偏移が生じることを示している。
これらの考察は、「遠くの銀河が赤方偏移を示すのは、宇宙の膨張によって銀河が遠ざかっているためにドップラー効果が生じているから」という説明と、矛盾している。
そして、この考察は、別冊日経サイエンス紙の次の記述と合致している。
「〜厳密には、ドップラー効果による銀河の赤方偏移の理解は正しくない。銀河はそれ自身が高速で後退しているのではないからだ。銀河は静止しているが、その銀河存在する空間自体が膨張するために、後退しているように見えるだけだからだ。波長が長くなるのは、空間が膨張して、その中に存在している光(つまり波)が引き伸されることによる。 この考えに立てば、遠くの銀河からの光は、近くの銀河からの光よりも長い時間、宇宙を旅したため、それだけ長く波が引き伸され、強い赤方偏移を受けるようになったと解釈できる」 (『宇宙膨張は加速している』より──別冊日経サイエンス136『宇宙論の新次元』)
「論点4 銀河の赤方偏移はなぜ起こるのか?
誤解 銀河が空間内を移動し私たちから遠ざかり、ドップラー偏移が起こるから。
正解 空間が膨張し、そこを伝わるすべての光波を引き伸すから。」
「宇宙論的な赤方偏移と通常のドップラー偏移とは別物だ。 天文学者はよくドップラー偏移を引き合いにして出して宇宙論的な赤方偏移を説明するが、学生たちはそのせいでひどい迷惑を被っている。
両者は別々の公式で記述される。ドップラー偏移の式は特殊相対性理論の範疇にあり、空間の膨張が考慮されていないが、宇宙論的赤方偏移の式は、一般相対性理論から導かれ、空間の膨張が考慮されている。」 (『ビッグバンをめぐる6つの誤解』より──別冊日経サイエンス156『宇宙創成期』)
以上は、いずれも、“なぜ遠くの銀河が赤方偏移しているのか”の説明として、“遠ざかる運動に伴うドップラー効果”はふさわしくないことを示している。
※それでは、“なぜ遠くの銀河が赤方偏移している”のであろうか?
その第一候補は、重力場(“重位差”)によって生じる“重力的赤方偏移”であると思われる。
この重力的赤方偏移は、当然、重力場(“重位差”)の規模が大きくなればなるほど、大きくなる。 これは、まさに一般相対性理論と深い関係がある。
(“なぜ遠くの銀河が赤方偏移しているのか”についての、詳しい考察は、考察3で行なう。)
※例えば、ミューオンの質量は、1019Gevより小さいので重力子を放出しないと考えられる。 その“重力子を放出しないミューオン”の寿命が延びることは、どのように説明されるのであろうか? ミューオンの寿命が延びる場合、そこで、なんらかの形での“転回数の低下”が起こっているはずである。 それは、ミューオンに、(重力子を放出している)地球が近づくと解釈することによって、説明できるのだろうか? それとも重力場での加速運動なので、話が違うのだろうか?(地球に近づくほど、重力子の密度が高くなるので、それにともなって“転回数の低下”が起こっているからと考えていいのだろうか?)
一方、重力子を放出しないほど小さな物体どうしの相対運動の場合は、どうなるであろうか? (小さな物体は“観測”をしないので関係ないのだろうか?)
今後の課題である。
《光──光子、電磁波、アンペールの法則、ファラデーの法則》
次に光について、“素スピノール創発モデルによる説明を試みる。
次のような考えをヒントにしてみた。
「温度がゼロよりほんの少し高いとどうなるだろうか。この場合も基本はやはりすべてのスピンがそろった状態で、そこにときどきランダムに一個のスピンがひっくりかえることが起きる。そうすると、その隣のスピンがつき合ってやはり逆を向くこともあるだろう。ただ、二つが同時に逆を向くとエネルギーのロスが大きすぎるので、隣が逆を向いたら最初のは元に戻る。次はそのさらに隣が付き合って逆を向く……、という具合にスピンが格子上を伝わって移動していくこともありそうだ。まるで波のようではないか。そう、これは波だ。」(『質量はどのように生まれるのか』 橋本省二 講談社ブルーバックス p160-162 鉄の強磁性に関しての説明文の一部)
この“スピンの転回(ひっくり返り)の伝播”が素スピノールのネットワーク上で起きている場合── それがまさに、電磁波の出現に相当しているのではないだろうか?と考えてみた。
よって、次の仮説を立てた。
仮説2.7.1 光子は、2つの素スピノールが、転回し(ひっくり返り)ながら進むものに相当する。
図示すると次のようになる。
上図のように、“素スピノールの転回(ひっくり返り)”が、次々と伝わっている。
これが、まさに“光の伝わり方”(光子の移動のし方)の実体に相当することになる。
※光が持つ“波と粒子の二重性”の性質をうまく説明できると思われる。
※これが、真空中を、光速という一定の速度で伝わるということは──
単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”が多いほど、光子の素スピノールの間の距離が小さくなって(光の波長は短くなって)、
逆に、単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”が少ないほど、光子の素スピノールの間の距離が大きく(光の波長は長く)なることを意味する。
※一方、プランクの光のエネルギーの式 E=hν より、単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”(≒光の振動数)が多いほど光子のエネルギーが大きくなり、単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”が少ないほど光子のエネルギーが小さくなることになる。 (このあたりは、不確定性原理とも関連する。考察5)
※このモデルは、“円偏光”についても、うまく説明できると思われる。 転回する方向が、光の進行方向に平行な成分のみなら垂直偏光であるが、もし、光の進行方向と垂直な成分も合わせ持つならば、円偏光となるだろうと考えられる。
一方、電磁波の図をここに重ねてみる。
※電場の向きと垂直な方向に磁場が同時に生じていると考えると、うまく説明できることが読み取れる。
上図は──
下図のように、“右巻きor 左巻きの素スピノールが転回する際に、どちらの方向に電場や磁場が生じるか”という簡単なルールを決めることによって、
電磁波を、“素スピノールからの創発モデル”で、うまく説明できることを示している。
※右巻き素スピノールは、転回の向きに対して、右ねじの方向に磁場が生じている。
※左巻き素スピノールは、転回の向きに対して、左ねじの方向に磁場が生じている。
180度の転回に分けて詳しく図示すると次のようになる。
※素スピノールが1回180度転回する間に、転回&光の進行の方向と平行な面の中で電場を生じ── 同時に、転回&光の進行&電場を含む面と垂直な方向に、磁場が生じることになる。
再び180度転回すると電場と磁場がそれぞれ消滅する。
その際、上図から── 左巻きの素スピノールが、プラスの電界の生成&消滅に対応し、右巻きの素スピノールがマイナスの電界の生成&消滅に対応していることが読み取れる。
(その逆はない。 なぜなら、光については、右ねじの法則が成り立ち、電場→磁場の流れが、右まわりの時にのみ、光は前に進むからである。
(参考『対称性から見た物質・素粒子・宇宙 鏡の不思議から超対称性へ』 広瀬立成 講談社ブルーバックス))
※以上のモデルは、電場と磁場が“直角に存在する”ことを、ピッタリと説明できる。
この電場と磁場が“直角に存在する”ことにより、例えば、アンペールの法則(電流の周りに磁場が生じる)や、ファラデーの法則(磁場の変化に伴い電場が生じる)も、うまく説明できる。
《アンペールの法則》──電流が流れると、その回りに磁場ができる(右ねじの方向)。
1つの仮説を立てることで、アンペールの法則を説明できる。
仮説2.7.2 左巻き電子が近づいてくると── 例えば、その電子の中の“左巻きスピノール”と、(電線上の、原始ヒッグス場の基本構造の中の)これに近づく方向に運動する“右巻き素スピノール”がペアを作り仮想光子となる。 その仮想光子の進行方向にそって“右ねじの法則”に従うような方向に、素スピノールのペアが一緒に転回すると── 遠方の(電線上の)素スピノールが作る個々の磁場が、アンペールの法則に合致するようにそろう。
|
|
電流が下から上へ流れると、電子は、上から下に移動する。
その際、仮に無限遠方の電子の中に存在する考えられる左巻き素スピノールとぺアを作るような(電線上の、原始ヒッグス場の基本構造の中の)右巻素スピノールが転回したとすれば── 上図のように、アンペールの法則にピッタリ合致した右回りの磁場が、素スピノールが作る磁場の総和として形成される。
そして、無限遠方でなくとも、転回のスタート時の角度が斜めになったとしても、同様に、アンペールの法則にピッタリ合致した右回りの磁場が、素スピノールが作る磁場の総和として形成される。
|
|
|
|
電流が上から下へ流れると、電子は、下から上に移動する。
その際、仮に無限遠方の電子の中に存在する考えられる左巻き素スピノールと、ぺアを作るような(電線上の、原始ヒッグス場の基本構造の中の)右巻素スピノールが転回したとすれば── 上図のように、アンペールの法則にピッタリ合致した右回りの磁場が、素スピノールが作る磁場の総和として形成される。
そして、無限遠方でなくとも、転回のスタート時の角度が斜めになったとしても、同様に、アンペールの法則にピッタリ合致した右回りの磁場が、素スピノールが作る磁場の総和として形成される。
|
| 原始ヒッグス場の基本構造とは、上に登場した |
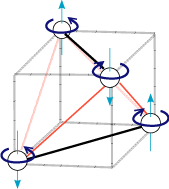 |
のことである。
|
※右巻き電子の場合も同様に考えられる。
今度は、右巻き電子に近づくと── 例えば、右巻き電子の中の右巻き素スピノールと、(電線の中の)電子に近づく方向に運動する左巻き素スピノールのみがペアを作り、決まった方向に(その仮想光子の進行方向にそって“右ねじの法則”に従うような方向に)一緒に転回すると── やはり、磁場がアンペールの法則に一致するように形成されることになる。
※なお、これらは、次々と作られる“仮想光子”に相当すると考えられるので、“180度の転回”のみ、つまり、磁場の生成のプロセスのみを考えればよいと思われる。
(もし、360度転回すれば、磁場の消滅のプロセスも進んでしまう。そして、ふつうの電磁波として、無限遠方へ光子が進んでいってしまうことになり、仮想光子ではなくなる。)
※以上の考察は── 電荷とは、“素スピノールの転回”を含む何かであることを示している。
「電荷の起源とは何か?」(電荷とは何か?)について、大きなヒントが得られる。 「電荷の起源は何か?」(電荷とは何か?)は、考察6にて詳しく考察する。
※また、電子の“幾何的な実体像”──電子の内部構造を考えるヒントの1つを得られる。 (詳細は、考察6の電荷の実体について)
なお、右巻き電子の中に“右巻き素スピノールの転回”のほかに“左巻き素スピノールの転回”も── 左巻き電子の中に“左巻き素スピノールの転回”のほかに“右巻き素スピノールの転回”も、存在すると考えられるので、上記の図はあくまで、“例”であることになる。
《ファラデーの法則》(「磁束の変化を打ち消す方向に、誘導起電力が生じる」)
ファラデーの法則が意味する、「磁束の変化を打ち消す方向に、誘導起電力が生じる」とは、次のようなことである。
下図のように、例えば、“ある円形の電線”の中を通る磁束が増えると── その変化を打ち消すような向きに、電場(電位勾配)が生じるというものである。
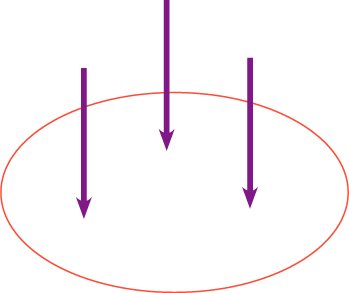 |
→ |
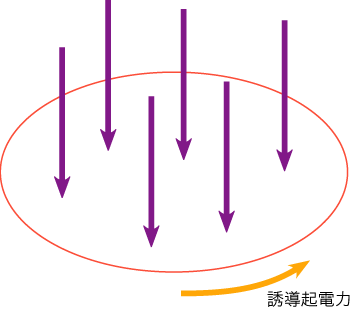 |
& |
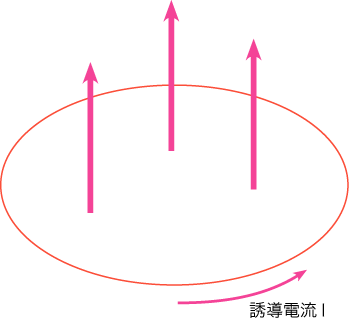 |
| “ある円形の電線”の中を一定の磁束が通っている。 |
|
磁束が変化すると── 電線にそって、電場(電位勾配)=誘導起電力が生じる。 |
|
その誘導起電力=、電場(電位勾配)によって、生じた誘導電流が、新たに生み出す磁束は、最初の「磁束の変化」と逆向きである。 |
その結果、誘導電流が生じ、新たに磁場が生じる。 その向きは、最初の「磁束の変化」を打ち消す方向(逆向き)である。
この現象を“素スピノールからの創発モデル”で説明してみる。
磁束が変化する時に、“素スピノール”の挙動レベルで起きていることは何であろうか。
それは、下図のような向きに、「素スピノールが転回を新たに始める」ということに他ならない。
※数個しか図示していないが、実際は、無数にこのような転回が新たに始まる。
※右巻きの素スピノールが、転回する時は、右ねじの方向に磁場が生じ──
左巻きの素スピノールが、転回する時は、左ねじの方向に磁場が生じている。
新たに生じる磁場の向きが一方向に決まっているということは、左巻き&右巻きの素スピノール、それぞれが転回する方向が、上図のように決まっているということを意味する。
|
この転回を始めた素スピノールは、ただ、それぞれ転回するのではなく、他の素スピノールとペアを作って転回すると考えられる。
それは、光子の場合と同じである。 右巻きと左巻きのペアで、なおかつ、総スピンが1となるようなペアである。(下図の緑で囲ったペアがそれに相当)
例えば、下図のように電線上の素スピノールとペアを作った場合、何が起こるであろうか?
|
|
※この図と下図を見比べてみると、図の矢印の方向に、電場が生じることがわかる。
|
電場が生じるのである。 右巻き素スピノールも、左巻き素スピノールも、同じ向きの電場を作る。
当然、電線の中の素スピノールは、まんべんなく存在するので── 電線全体に、電場が生じる。 これが誘導起電力の実体であると考えられる。
こうして、形成された電場(=誘導起電力)によって、誘導電流が流れる。 それは、最初の「磁場の変化」と逆向きである。
|
|
|
磁束が変化すると── 素スピノールのペアを転回させる。
|
|
| = |
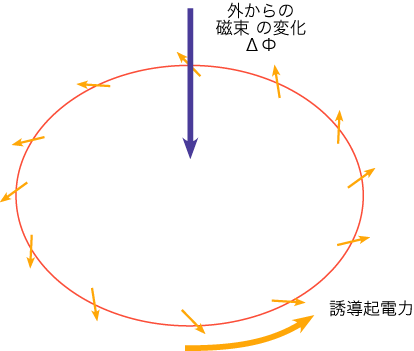 |
& |
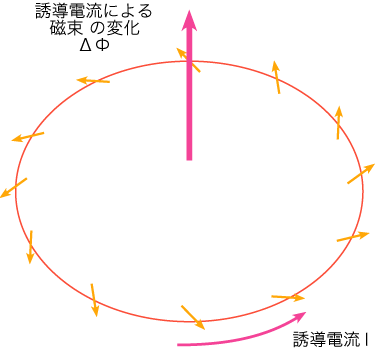 |
|
それは同時に、電線にそって、電場(電位勾配)=誘導起電力が生じることである。 |
|
その誘導起電力=、電場(電位勾配)によって、生じた誘導電流が、新たに生み出す磁束は、最初の「磁束の変化」と逆向きである。 |
つまりは、以上で、ファラデーの法則を説明したことになると思われる。
※なぜ、素スピノールがペアを作って、転回するのであろうか? それは、なぜ、光子がとびとびでペアを作って転回するのかと、本質的に同じであると思われる。
なぜなら、それは、仮想光子に相当すると考えられるからである。
“素スピノールは、そういった性質を持つから”としか言えないのだろうか? この背質は、「量子もつれ」の性質と深いつながりがありそうに思われる。
詳しい考察は、今後の課題である。
※転回の“軸の方向”に磁場が生じることは── 地球の自転の軸の方向、電子の軸に磁場が生じるのと似ている。
例えば、下図のように、光子の素スピノール2つのペアの間で、“磁界が閉じている”とすれば──
|
もし、次のように“磁界が閉じているとしたら──
|
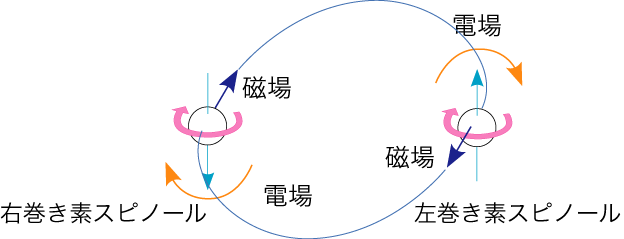 |
素スピノール自体がN極とS極を持つことになる。
これは、“モノポール”(単極子)に相当するものは、素スピノールレベルにおいても実在しないことを意味する。
あるいは、磁力線の実体は、“素スピノールのひっくり返りの軸”の集合であるので、上図のように閉じているとは考えられなく──
素スピノールが、ディラックが予言した“モノポール”(単極子)に相当するものであると言えるのだろうか?
だとすれば、これは、“モノポール”(単極子)が観測しにくい理由は、素スピノールが観測しにくいから── ということになるのだろうか?
詳しい検討は、今後の課題である。
※個々の素スピノールは、転回することによってはじめて、“電場や磁場”を生じることになる。
“転回していない”素スピノールは、“電場や磁場”を持っていないと考えられる。
だからこそ、ファラデーの法則が示すように。磁束が変化するときに限って、誘導起電力が生じるのだと考えられる。
(だからこそ、“弱い力しか働かないニュートリノ”が存在できるだ考えられる。もし、転回していない素スピノールも周囲に電場や磁場をもっていれば、ニュートリノは、電磁場と相互作用をしてしまうだろう。 →考察6)
※光子(or 仮想光子)が生じる際の“180度の転回の仕方”は、次の8通り考えられた。
下図は、→の方向に進む光子のペアである。
|
→
光の進行方向
|
|
|
|
→
光の進行方向
|
|
| 右巻き |
|
左巻き |
|
右巻き |
|
左巻き |
| 右巻き |
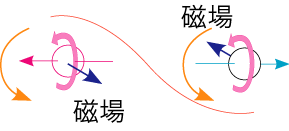 |
左巻き |
|
右巻き |
|
左巻き |
|
上のペア2つ、下のペア2つは、
それぞれ転回の向きが逆転しており、
それに伴って電場の向きが逆転している。
|
|
|
|
上のペア2つ、下のペア2つは、
それぞれ転回の向きが逆転しており、
それに伴って電場の向きが逆転している。
|
|
| 左巻き |
|
右巻き |
|
左巻き |
|
右巻き |
| 左巻き |
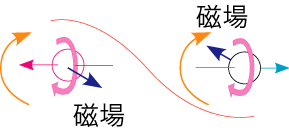 |
右巻き |
|
左巻き |
|
右巻き |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※転回方向を変えると、光りの進む向きは同じだが、その時、電場と磁場の向きが両方、同時に変わる。
※上のリストの、どこかに、電磁気力の正負(プラスとマイナス)を決める違いがあるはずである。
それは、電場の向きの違いが対応していると考えられる。右側が山になっている方がプラスの電場をつくる。逆に、右側が谷になっている方は、マイナスの電場を作ると考えられる。
(誘導起電力の図で、電流を作る電場を生み出す向きと合致する)
※個々の素スピノールの180度の転回には── 原始ヒッグス場を変形させる1回目と、変形を解消する2回目がある。 進行方向の前側(赤い方)が、1回目の原始ヒッグス場の“4面体”を変形させエネルギーを蓄える方で、後側(赤い方)は、2回目の“4面体”の変形を解消し、エネルギーを放出させる方である。
つまり、転回前の図の状態では、赤い素スピノールがエネルギーが大きく、青い素スピノールが小さい。
180度転回すると、今度は、青い素スピノールのエネルギーが高くなる。
※すべて、光の右ねじの法則にしたがっている。
※左の列の4つのペアと、右の列の4つのペアは、素スピノールの運動方向が近づくか遠ざかるかが違っているだけであり、他はすべて同じであることが読み取れる。
※左側の“遠ざかる方の”4つは、実際は、実在しないというようなことがあるのだうか? 今後の課題である。
|
これらが、正電荷由来の仮想光子、負電荷由来の仮想光子のどちらかに、なんらかの形で対応すると考えられる。
“近づくか”“遠ざかるか”の違いは、電場の向きと、無関係ある。よって、“近づくのみ”に絞って考える。
次のようになる。
|
プラスの電場を生む仮想光子
正の電荷由来
|
|
|
|
マイナスの電場を生む仮想光子
負の電荷由来
|
|
| 右巻き |
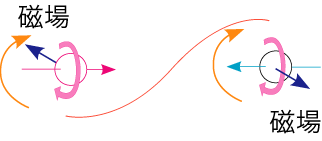 |
左巻き |
※プラスの電場を生むかマイナスの電場を生むかの違いは転回の向きのみである。 |
右巻き |
|
左巻き |
| 左巻き |
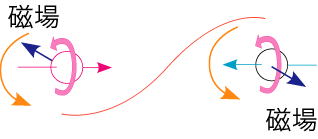 |
右巻き |
左巻き |
|
右巻き |
|
|
→
仮想光子の進行方向
|
|
|
|
→
仮想光子の進行方向
|
|
一方、“電荷”の中においても、転回の仕方(ひっくり返り方)が、4通り考えられる。 (詳細は、考察6プレオンモデル、電荷の起源について)
そして、これらの電荷と光子の中の素スピノールの転回の仕方(ひっくり返り方)の組み合わせが、電磁気力の引力&斥力の区別を生むと考えられる。
(詳細は、考察6プレオンモデル、電荷の起源について)
※仮想光子は、素スピノールを180度だけ1回転回させるだけの光子である。 もし、素スピノールをトータルで360度転回させたとしたら、せっかく生成させた電場をすぐに自ら消滅させてしまうことになってしまうからである。
したがって、仮想光子は、次から次へと伝わっていく、ふつうの電磁波とは異なる性質のものであると考えられる。
※仮想光子として、180度転回した素スピノールは、その後どうなるのであろうか?
→今度は、(電荷によって)180度逆向きに元に戻るように転回させられるので、“同じ向き”の電場が生じ続ける── ということでいいのかもしれない。
(→下記の考察《重力場、エネルギー、質量、非線形性、電磁場の線形性との比較》、 →考察6──電荷の起源)
※以上が正しければ── 電磁気力は、仮想光子の総和が生む電磁場(電場や磁場)を介して生じる力であり、ボソンのキャッチボールによって(湯川型の相互作用によって)生じる力ではないことになる。(考察6、考察11)
なぜなら、仮想光子が、他のものに吸収されるのではなく、実際は、ブーメランのように、仮想光子が(逆向きに進み)、元の電荷に吸収されると考えられるからである。(→考察6──電荷の起源)
(しかし、その過程を、“ある電荷が仮想光子を放出し、もう一方の電荷が、その仮想光子を受け取る”というように解釈して計算したとしても、つじつまが合うのかもしれないと思われる。
なぜなら、その所産が(成功しているとされる)量子電磁気学(電子&電磁場についての場の量子論)に他ならないと考えられるからである。
なお、Δ光子(→考察6)の方は、グルーオンと同様に、実際に、“吸収される”と思われる。)
※無限遠方までどうやって伝わるか? →“電荷”によって、無限遠方の素スピノールが、ダイレクトに180度転回させられると考えられる。
※電荷からの距離 r が大きくなればなるほど、仮想光子の転回周期Tも大きくなる(=振動数νが小さくなる&波長λが長くなる)。 なぜなら、光速cは、一定だからである。
転回周期Tは、 T=r/c で計算できる。
一方、転回周期Tが大きくなると同時に、仮想光子による180度転回に伴うエネルギー振幅ΔEは、逆に小さくなると考えられる。
(プランクの式より、光子のエネルギーE=hν=h/T が成り立つからである。 (それは、不確定性原理の式とも合致する))
(よって、ΔE=E=h/T=hc/r となる。 これをrで微分すれば、dE/dr=−hc/r2
電磁気力(=“電位勾配”、=電場)の式と形が似ている。 つまり、ΔE=E=h/T=hc/r は、電磁ポテンシャルエネルギー(電位)と関連していると考えられる。)
このことは、仮想光子は、決して、ランダムなエネルギーを持つものではないことを意味している。
つまりは、遠ざかれば遠ざかるほど、E=hc/r に従って、仮想光子が生じるエネルギーが小さくなる。
このあたりの考え方にも、量子電磁力学(QED)(“電荷&電磁気力”の場の量子論)において、無限大を生じさせないヒント、“くり込み”を不要させるヒントがあるのかもしれないと思われる。 今後の課題である。
(もう一つの、無限大を生じさせないヒント、“くり込み”を不要させるヒントは、電磁場を基本ヒッグス場の基本構造の集合と見る見方(時空に最小の単位があるという見方)である)
《光子と重力子について》
以上の光子についての考えをふまえ、重力子について再び考察してみる。
※電場&磁場の形成の考え方を当てはめると重力子は、次のようになる。
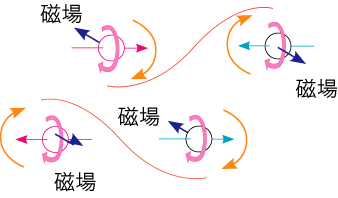 |
→
重力子の進行方向
|
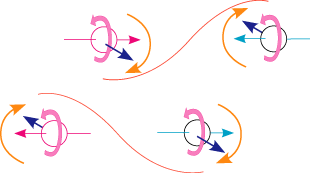 |
1つの重力子の中では、つねに磁場は反発し合っていることになる。
それでも、お互いに離れないのは、原始ヒッグス場の“4面体”の基本構造をもとに重力子が生じているからであると考えられる。
磁場が打ち消し合っているとも解釈でき、磁場の波としては、重力子を観測できないことを意味していると思われる。
ここで、よく、重力子(重力波)が次のように図示されていることを検討してみる。
この図が意味するものは何であろうか?
まず、話を分かりやすくするためにまず、光波の流れを考えてみる。
※光波の中の“ 電場に相当する横波” のそれぞれに、“素スピノールの転回”が対応していることをしている。
(磁場の横波は省いてある)
同様に重力波(波長の短い光波×2)について図示すると、次のようになる。
※重力波の中の“ 電場に相当する横波” のそれぞれに、“素スピノールの転回”が対応していることをしている。
(磁場の横波は、打ち消し合うと考えられる)
この上で示した、電場の横波のこの動きは、単純に下のように表記できる。
まさに、これが、
に相当するのではないだろうか?。
45度傾ければ、次のようになる。
つまり──
とは、電場の横波がお互いに逆向きに振動する様子を示していると解釈できる。 その背後に、素スピノールの挙動(“素スピノールの転回”)が隠れていると理解できる。
重力波の中の磁場の横波は打ち消し合うために観測できないと考えられるので── 重力波が観測されるとしたら、電場の横波の変動としてであることを意味していていると思われる。 しかし、この電場の横波の振幅は、プランク長程度と小さいがために、やはり、直接の観測は、とても困難になると思われる。
※重力が強ければ強いほど、“時空の曲がり”が大きくなり、原始ヒッグス場の足場が減る分、外からは光がゆっくり進むように見える。
しかし、実際には、当の光子は、時空の中を光速で進み続けているつもりになっている(素スピノールのねじれの伝播として光子が移動し続けているつもりになっている)。
なぜなら、“素スピノールのひっくり返り”が時間の流れそのものだからである。
時間の流れが遅くなることの実体は── “時空の曲がり”=重力子による、原始ヒッグス場の足場の消失にともなう、ひっくり返りの頻度の減少であると考えられることは上でも述べた。
※重力が強ければ強いほど、“時空の曲がり”が大きくなり、“4面体”が、薄っぺらな“4角形”(縮みきったバネ)になる分、空間は、膨張しているように見える。
“時空の曲がり”によって、時間の流れが遅くなる(転回周期が長くなる)と同時に、空間が膨張する。
つまり、“光子の転回周期”と、進む距離の比──つまり、光速は、常に一定になる。 つまり、光速不変は、“時空の曲がり”による影響の中でも保たれることになる。
※もし、“重力子の密度”が極端に高まった場合(原始ヒッグス場が存在せず、100%“4角形”(縮みきったバネ)となった場合)── その“時空の曲がり”では、原始ヒッグス場の“4面体”の足場が消失するので、素スピノールの転回が起きなくなり、つまりは、時間が止まる。 その結果、光でさえも、そこを進むことが出来なくなる。
つまり、これは、ブラックホールの中にいることと同じになる。
(これが、ブラックホールの“事象の地平線”に相当すると考えられる)
逆に、もし、原始ヒッグス場の“4面体”が少しでも存在すれば、そこを足場にして、光子が前進していけることになる。 つまり、このことは、原始ヒッグス場には、光子が伝わる足場としての働き── つまり、電磁場としての働きがあることと合致する。意味する。
《プランク定数、ブランクエネルギーについて》
図から読み取れることは、180度の転回を2回繰り返すことで進む距離が、ちょうど1波長分に相当することである。
(180度の転回が1回で、ちょうど半波長分進む。 素スピノールは、半波長ごとに存在する)
結論3.1.0 光子は、素スピノールのペアが、2回180度転回する間に、電磁波の1波長分だけ前進する。
※なお、「ある1つの素スピノール1つが、360度1回転回する間に、1波長分進む」と言い換えることもできる。
次に再び、次の原始ヒッグス場の“4面体”のバネを含めた図をみてみる。
この図からも、光子は、素スピノールのペアが、2回180度転回する間に(=電磁波が1波長分だけ前進する間に)、2回だけ“4面体”は変形することが読み取れる。
1回の光の振動数ν×波長λ=光速cなので──
一般に、振動数νの光子は、一秒間に進む距離cの中で、2ν個の“4面体”を変形させていとることになる。
|
振動数ν=1の1つの光子について
|
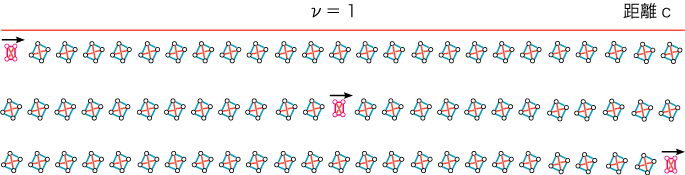 |
※振動数ν=1の場合、波長λ=cである。この光子は、1秒間に2個の原子ヒッグス場の“4面体”バネの変形を利用して、光速で移動していく。
(上の赤い線は、1秒間に進む距離c=30万kmを示している)
|
振動数ν=2の1つの光子について
|
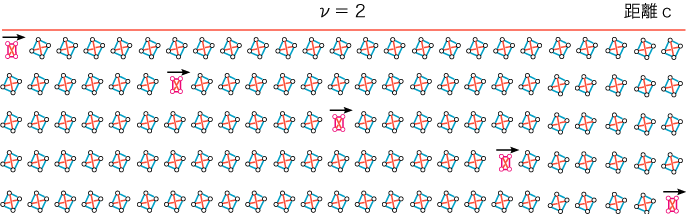 |
※振動数ν=2の場合、波長λ=c/2である。この光子は、 1秒間に4個の原子ヒッグス場の“4面体”のバネの変形を利用して、光速で移動していく。
|
振動数ν=3の1つの光子について
|
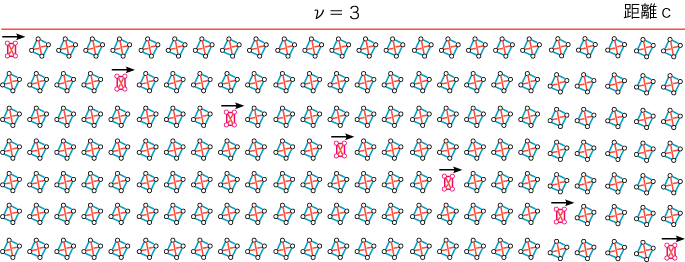 |
※振動数ν=3の場合、波長λ=c/3である。この光子は、 1秒間に6個の原子ヒッグス場の“4面体”のバネの変形を利用して、光速で移動していく。
同様に── もし、ν=100の光子なら、200個の“4面体”のバネの変形を利用して、光速で移動していく。
この「一般に振動数νの光子は、1秒間に2ν個の“4面体”のバネをとびとびで変形させながら、光速で移動すること」は、次のように言い換えることができると思われる。
一般に「振動数νの光子1つは、“1秒間に、2ν個の“4面体”のバネを振動させながら光速で移動する”」と言える。 ・・・(1)
これは、「ある“4面体”の変形したバネのエネルギー」が、増えも減りもしないで、光速で移動していくことを意味している。
「ある“4面体”のバネが変形したエネルギー」とは、なんであろうか?
ここで、アインシュタインの光量子仮説を確認してみる。
「振動数νの光はエネルギーhνをもつ粒子のように振る舞う。 hはプランクの定数である。 このように、粒子のように考えた光を光量子または光子と呼ぶ」
(『基礎教養 物理学 下』 福田義一廣川書店 p344)
つまり、「光子1つが持つエネルギーがE=hν」となる。
そして、この式は、光子の振動数の大きさに応じて、エネルギーの大きさが変化することを意味する。
つまり、“素スピノールからの創発モデル”によれば、光子が持つエネルギーの実体が、「原始ヒッグス場の“4角形”が変形した時に蓄えられるエネルギー」に他ならないという結論が自然に導かれる。
結論3.1.1 「原始ヒッグス場の“4角形”が変形した時に蓄えられるエネルギー」が、光子が持つエネルギーの実体である。
そして、この式は、1/ν=T(周期)であるので、素スピノールの転回周期が、短ければ短いほど── その“4面体”が変形する際に持つエネルギーが大きくなることを意味している。
つまり、「転回によって“4面体”を変形させるスピードが速ければ速いほど── その変形した“4面体”が持つエネルギーは、大きくなる」──
そういった性質を原始ヒッグス場は、持つと言える。
結論3.1.2 転回によって“4面体”を変形させるスピードが速ければ速いほど── その変形した“4面体”が持つエネルギーは、大きくなる。
光子が、1つの原始ヒッグス場の“4面体”のバネを、(1つの素スピノールの転回によって)1回変形するために要するエネルギーをEh1としてみる。
(h1のhは、ヒッグス場のh。1は。1つの素スピノールの転回による変形であることを意味する)
一方、素スピノールが360度転回する周期(転回周期と呼ぶこととする)をTとする。 光のエネルギーE=hνの式より、
(1/Tが、光子の振動数に等しいので) Eh1=h/T となる。
この式は、転回周期が短いほど(波長が短くなるほど)光子のもつエネルギーが大きくなることと合致している。
(また、これは、不確定性原理の式、ΔE×ΔT=hともぴったり合致している。 詳細は考察5)
Eh1=h/T にT=1を代入すると、Eh1=hとなる。
プランク定数hの実体的な意味の1つは、“転回周期1秒で、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを変形させる際のエネルギー振幅”に相当することになる。
(→下記考察)
原始ヒッグス場の基本構造の転回周期が短くなればなるほど、大きなエネルギー振幅で振動するという性質は── 光子の振動数が大きいほど、光子のエネルギーが大きくなるという性質と、本質的に同じであることになる。
※1つの素スピノールが180度転回する間に、時空の基本構造に一時蓄えられるエネルギーは、Eh1=h/Tである。
その素スピノールがもう一度180度転回する間に、時空の基本構造から放出されるエネルギーも、Eh1=h/Tである。
つまり、1つの光子が移動する過程では、エネルギーの増減は生じないことになる。
また、1つの素スピノールが360度転回する間に、時空の基本構造のバネが持つエネルギーの振幅は、h/Tであるということもできる。
以上をふまえた上で、いよいよ、重力子について見てみる。
重力子について、すでに、次の仮説を立てた。
仮説2.2.1 重力子は、すぐとなりにある“原始ヒッグス場”の基本構造をバネ的な足場として、4つの素スピノールを転回させながら進むものに相当する。
仮説2.2.2 重力子のサイズは、1プランク長程度(重力子の波長は、2プランク長(2Lp)程度)の一定となる。
すでに登場した下の図は、まさにこれらのことを表している。
※重力子1つが、1回180度転回する際、1つの“4角形”が“4面体”に戻ると同時に、
1つの“4面体”が“4角形”に変化することが読み取れる。
|
この図からも、重力子とは、光子に相当するものが2つ並走している(2つ光子は、それぞれが発生する電場と磁場を互いに打ち消しあっている)ものであることが読み取れる。
光子が、1つの素スピノールだけを転回させ、1つの原始ヒッグス場の“4面体”を途中まで変形させるのに対し、重力子は、2つの素スピノールを同時に転回させることによって、1つの原始ヒッグス場の“4面体”を完全な“4角形”(縮みきったバネ)まで変形する。
やや簡略化した図が次である。
※1つの“4面体”を“4角形”に変形させるために要するエネルギーの大きさは、1つの“4角形”を“4面体”に戻す際に放出されるエネルギー
に等しいと考えられる。 つまり、1つの重力子が移動する過程においても、エネルギーの増減は生じないことになる。
重力子の波長λが、λ=2Lpであるということは、重力子の振動数νは、ν=c/2Lpであるということになる。
※この図は、すぐとなりの原始ヒッグス場の“4面体”を足場にして進んでいることを示す。
光速cは、およそ秒速30万キロ、プランク距離Lpは、およそ10-35mであるので、
重力子の振動数ν=c/2Lpは、およそ3×108/2×10-35=1.5×1043という、非常に大きな数になる、つまり、この図は当然正確なものではない。
|
重力子の1周期分の転回(2個の素スピノールの360度の転回)の間に(“4面体”が完全な“4角形”になる間に)時空の基本構造のバネが持つエネルギーの振幅Eg(gは、グラビトンのg)は、いくらになるであろうか?
重力子は、光子2個分に相当するものと近似できるという仮定が正しいとすれば、ここで1つの結論を出せる。
結論3.2 重力子1つが1回振動して1波長分進む間に(重力子が2回180度の転回をして、1波長分進む間に)、時空の基本構造のバネが持つエネルギーの振幅の値の近似値は、ちょうど光子2つ分なので、2×hνである。
一方、重力子の一辺の長さの値は── 原始ヒッグス場のサイズ、プランク長(1.616×10-35m)であると考えられる。
したがって、重力子(素スピノールの4つからなるグループ)が2回180度の転回をする過程で進む距離が、1つの波長に相当するので── この重力子の波長も、この重力子に近似できる光子の波長も、ともに、2プランク長(2Lp)──2×プランク長=2×1.616×10-35mであると考えられる。
※この波長は、理論上考えられる最も短い波長に相当すると言えると思われるので── プランク波長λpと呼んでもいいかもしれない。
すると、「1つの重力子が持つエネルギー」(完全な“4角形”=縮みきったバネのエネルギー)の近似値(Eg近似値)は、
Eg近似値≒2×hν=2hc/λ=2hc/2Lp
=2h×3×108/2×1.616×10-35
=6.626×10-34×3×108×1035/1.616
=6.626×3/1.6166×109
=12.296×109
≒1.2296×1010J
と計算できる。
一方、プランク質量が持つエネルギーの大きさ(プランクエネルギー)は、
Ep=1.9561×109J
である。
したがって、プランク質量(プランクエネルギー)と1つの重力子が持つエネルギー(Eg)は、何らかの関係がありそうだと予想された。
そして、その後、上記で計算した“Eg近似値”を2πで割ると、Eg近似値/2π≒1.95796××109Jとなり、プランクエネルギーEp=1.9561×109Jと、極めて近い値になることに気づいた。
よって、次の仮説を立てた。
仮説3.10 Eg近似値(2プランク長(2Lp)の波長を持つ光子2つ分)を2πで割った値──Eg近似値/2π=2hν/2π=hc/πλが、1つの重力子が持つエネルギー(Eg)の正しい求め方であり、それは、ちょうどプランクエネルギーEpに等しい。
※プランクエネルギーとは、1つの重力子が持つエネルギー=「1つの重力子が、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを完全に振動させるのに必要なエネルギー(完全な“4角形”まで変形するエネルギー)」であることになる。
このプランクエネルギーに相当する質量(=プランク質量)をもつ物体があったとする。(E=mc2より、質量2×10-5gである。)
このプランク質量を持つ物体は 1秒間に何個の重力子をすることが出来るであろうか?
かりに、この物体が、ミクロレベルで光速で移動し続けているミクロの粒子だとすると── 原始ヒッグス場の“4面体”は、およそ、プランク長2Lpごとに存在すると言えるので(→考察7)、この物体は、1秒間におよそ、c/2Lp回も“4面体”と衝突できることになる。 そして、衝突するたびに、1つの重力子を放出するであろう(まさに「質量とは、重力子を放出できる能力である」が成り立っている)。
つまり、このプランク質量を持つ物体は、「1秒間にc/2Lp回」も重力子を放出できるということになる。
この物体がかりに、陽子が1019個集まってできた物体だとしても、1つ1つの陽子は、光速で運動し続けているので、「1秒間にc/2Lp回」も重力子を放出することは変わらないであろう。
※重力子の振動数c/2Lpが、ふたたび登場している。 このことからc/2Lpが重要な定数であることがうかがえる。これをプランク振動数νpと呼ぶことがふさわしいかもしれない。以下そのように呼ぶこととする。
すると、νp=c/2Lp=(3×108m/s)/(2×1.616×10-35m)」=0.92×1043 となる。
※陽子1つあたりの1秒間の重力子の放出数をνp/1019で計算できることになる。
(それは、0.92×1024 となる)
一般に、質量mの物体があったとき、それは、1秒間にどのくらいの重力子を放出できるか?
プランク質量mpあたり、νp個の重力子を放出できるので、質量mでは、(m/mp)νp 個の重力子を放出できることになる。
質量mの物体が、速度vで等速運動するとき、どれくらいの重力子を新たに放出するか?
上記の考察《重力子の働きと慣性──等価原理》によれば、mv2のエネルギーに相当する重力子が放出されるのであった(半分は流れるプール効果として使われる)。 mpc2 あたり、νp の重力子 が放出されるので、mv2では、(mv2/mpc2)νp =(m/mp)×(v2/c2)νp 個の重力子を放出するであろう。
v2/c2の値は── かりにvが秒速1mだとすると、1/(3×108)2≒0.11×10-16となるので、かなり小さい。
しかし、m/mpやνp の値がかなり大きいので(例えば、100gの物体なら、m/mp=100/(2×10-5)=0.5×107となる)──
v2/c2の効果が打ち消されて、重力子の放出数は、かなり大きなものとなる。
(100gの物体なら、が秒速1mで進むとした場合── 重力子の放出数≒0.5×107×0.11×10-16×0.92×1043 =0.0506×1034=5.06×1032となる。)
したがって、宇宙空間の中の宇宙船の中で、人でも1本ペンでも等直線運動(慣性運動)が可能であるという観測を説明するのに、重力子の放出による“流れるプール効果”を用いることは、的外れではないことを示していると思われる。
※この考察は、たとえプランク質量に満たない粒子でも、時間をかけて繰り返し原始ヒッグス場の“4面体”に衝突すれば(働きかければ)、重力子を放出できるということを意味すると考えられる。
※ミクロのレベルで、エネルギー保存則が破れていると言える。
周囲のヒッグス場にエネルギーを蓄えても、「ミクロの粒子は光速を保つ」という性質によって、このようなことが可能になっていると言える。
質量とは、重力子を放出する能力であり── 質量とは、そういう性質をものであるということになる。
また、「重力子は、仮想粒子である」から問題ないと言うこともできるかもしれない。
※もし波長が2Lpの光子が存在するとすれば、その光子2つ分が“4面体”←→“4角形”のバネを振動させるエネルギー振幅より、たった1つの重力子がこのバネを振動させるエネルギー振幅がさらに、1/2π≒1/6ほどに小さいということを意味している。
それは、重力子のエネルギー振動がとても効率の良いものである一方、光子によるエネルギー振動が無理のあるものであるともいえる。
(光子の方に無理が出てくるのは、1つの“4面体”を変形させるために、素スピノールの2つを同時に転回させずに、あくまで、1つの素スピノールだけの転回によって、変形させ続けようとするからであると思われる)
Eg近似値と正確なEg、これら2つの間の差は、まさに、「“(無理して存在する)光子の2つ”の“結合エネルギー”に相当する」と解釈できる。
(無理して存在する)光子2つ分が結びついて、新たに1つの重力子が生じる際には、大きなエネルギー(プランクエネルギーの5倍《(2π-1)倍》ほど)が放出されることになる。
その結合エネルギーのおかげでこそ、重力子は、しっかり安定して存在し続けられる。
もし、1つの重力子から、バラバラな光子2つへと分解するためには、多大なエネルギー(プランクエネルギーの5倍ほど)を要する。
したがって、こういった現象は、少なくとも現在の宇宙環境では起こりえないと考えられる。
※この“結合エネルギー”の大きさは── 実際は、波長が“2プランク長の波長の光子”が、ふつうの光子のような電磁波の形で、単独では存在しえないことを意味しているのであろうか? “波長が2Lpの単独の光子(電磁波)”は実在できないが、“波長が2Lpの仮想光子”は実在するということはありうるだろうか?
詳細な検討は、今後の課題である。
1つの重力子が持つエネルギーの物理的な意味について考察してみる。
1つの重力子がつ持つエネルギー=近似式/2π=2hν/2π=2hc/2πλ=(h/π)×c/2Lp(c/2Lp=1秒間の振動数)=hc/2πLp
となる。
重力子の1回の振動(2回の180度の転回)によって、原始ヒッグス場の1つの“4面体”は、1つの“4角形”に変化し、そして再び、“4面体”に戻る。
|
原始ヒッグス場の“4面体”
|
|
原始ヒッグス場の“4角形”
|
|
原始ヒッグス場の“4面体”
|
|
|
→
※エネルギー
E=hc/2πLp
を蓄える
|
|
→
※エネルギー
E=hc/2πLp
を放出
|
|
つまり、1つの重力子が持つエネルギーhc/2πLpとは、原始ヒッグス場の1つの“4面体”を完全な“4角形”に変形するために要するエネルギーであり、“4角形”から“4面体”に戻る際に放出するエネルギーであることを意味する。
1つの重力子が持つエネルギーとは、1秒間に原始ヒッグス場を“4面体”←→“4角形”と振動させるためのエネルギー振幅であることになる。
このエネルギーが波として原始ヒッグス場を光速で、移動していく。
※放出と吸収が等しいので、このエネルギーが光速で移動する際に、トータルでのエネルギーの増減はない。
この1つの重力子が持つエネルギーが、プランクエネルギーに等しい。
これがプランクエネルギーが持つ物理的な意味の1つである。
多くの素粒子は、プラランクエネルギー(1.2×1019Gev)より小さな質量エネルギーをもつ。
しかし、たとえば、個々のクォーク(3Mev、6Mev )、個々の電子(0.5Mev)は、もちろん、個々の陽子(1Gev)さえも、重力子を放出できないということにはならない。
なぜなら、上でも述べたように、プランクエネルギーに満たない粒子であっても、時間をかけ繰り返し“4面体”に働きかけることによって、蓄積されるエネルギーがプランクエネルギーの閾値を越すことができ、これによって重力子を放出できると考えられるからである。
(現実には、プラランクエネルギーをもつ素粒子は存在しないと思われるので── この“エネルギー蓄積”方式が広く実在していると思われる。)
もし、1つの粒子が時間をかけて繰り返し作用したり、一定時間に作用する粒子の数が増したりすれば、蓄積されるエネルギーの合計が、1.2×1019Gevの閾値に達し(=原始ヒッグス場の“4面体”の変形が進み、縮みきったバネの“4面体”に至り)── まさにそのとき、はじめて重力子が放出されるであろう。
※例えば、重力子を、1秒間に、およそ、νp×10-19回=0.92×1024回だけしか重力子を放出できない陽子であっても、トータルでおよそ1.2×1019個集合すれば、νpの頻度で重力子を放出できるようになることになる。
(なお、陽子や中性子の質量は、約1.67×-24gで、プランク質量は、約2×10-5gである。
当然、陽子や中性子の質量の1.2×1019個分の質量≒1.67×-24×1.2×1019=2.004×10-5gとなり、プランク質量2×10-5gと、ほぼ一致する)
※質量が、プランク質量2×10-5グラムより小さな物体も、重力子を放出できると言い換えられる。
※プランクエネルギーは、重力子を放出できるかどうかを決める閾値ということもできる。
個々の電子やクォーク、陽子… は、1回の衝突だけでは重力子を放出できるほど、原始ヒッグス場を変形させることはできないが、それが、蓄積することで、重力子を放出することができる。
これと似た自然現象が、他にもある。
それは、1つ1つの神経伝達物質では、1つの神経細胞が“パルス”を出すことができないが、それが蓄積し、ある閾値を越えて始めて、神経細胞が“パルス”を出すという現象である。
一方、物体の運動にともない、原始ヒッグス場の“4面体”の変形の蓄積が進むことによっても、エネルギーの蓄積が、プランクエネルギーの閾値に達すれば(=縮みきったバネの“4面体”に至れば)、そのときに重力子が放出される。
つまり、様々な原因でエネルギーが蓄積される結果に達するエネルギーの閾値(「縮みきったバネの“4面体”が持つエネルギー」)が、プランクエネルギーが持つ、もう1つの物理的な意味である。
よって、プランクエネルギーには、2つの意味を持たせることが結論づけられる。
結論3.3 プランクエネルギーの物理的な意味は、1つは、“1つの重力子の系が持っているエネルギー”、もう1つは、原始ヒッグス場の“4面体”の変形が様々な原因で蓄積され、それが“4角形”(縮みきったバネ)に達して重力子を放出できるようになるという閾値としてのエネルギー”である。
プランクエネルギー以外の各定数についても、その意味(実体像)をまとめてみた。
まとめると、次のようになる。
|
プランク定数
|
h=6.626×10-34J秒 |
振動数ν=1の光子1つ(=素スピノール2つ分の転回運動)の系が持つエネルギー
周期T=1秒で、原始ヒッグス場の“4面体”の中の1つの素スピノールが転回する際、
その“4面体”が蓄えたり放出したりするエネルギーの大きさ
|
|
プランク距離
|
Lp=1.616×10-35m |
素スピノールのペアの間の最短距離 |
|
プランク時間
|
Tp=5.4×10-44秒 |
素スピノールが1回180度転回するためにかかる最短時間 2Tp=1/νp |
|
プランク振動数
|
νp=0.92×1043 |
素スピノールが1秒間に可能な“360度の転回”の最大数。重力子の振動数に等しい。プランクエネルギーが1秒間に放出する重力子の数に等しい。 νp=1/2Tp |
|
プランクエネルギー
|
Ep=1.9561×109J
=hc/2πLp
1.2×1019Gev |
重力子1つ(=素スピノール4つ分の転回運動)の系が持つエネルギー
1つの原始ヒッグス場の完全な“4角形”が持つエネルギー”
(プランク時間Tpの間に1つの“4面体”の中の2個の素スピノールを180度転回する際、
原始ヒッグス場の“4面体”が蓄えたり放出したりするエネルギーの大きさ)
|
※プランク定数は、“1秒”ときってもきれない定数であることになる。 しかし、1秒は、当然、“地球が自転する時間”から決まってきた時間に過ぎない。(“地球が自転する時間”の24分の1の60分の1の60分の1) 実際は、振動数が1より小さい光子も存在するはずだし(例えば、3秒でやっと1回振動できる光子)、周期T=60秒で振動する原始ヒッグス場の“4面体”も、存在するはずである。 つまり、プランク定数の1/3や1/60というエネルギーも、宇宙には実在するはずである。 したがって、プランク定数自体は、宇宙のエネルギーの最小単位であるとは言えない。 もしかしたら、エネルギーについての普遍的で一定な基準値としては、プランエネルギーEpの方がふさわしいのかもしれない。 あるいは、プランク定数よりプランクエネルギーの方が基礎的な実体であると言えるのかもしれない。
しかし、一方、プランク定数は、時間とエネルギーの関係を身近な“1秒”を使って結びつけられる便利な定数であると言えると思われる。 詳しい考察は、今後の課題である。)
※周期1秒で振動する1つの光子のエネルギーは、hであること── 周期2Lp/c秒で振動する重力子1つがもつエネルギーが、hc/2πLpであること── ともに、
不確定性原理の示す式ΔE×Δt=h の式と関連があると考えられる。 (→考察5)
※プランク距離/プランク時間=Lp/Tpは、光速cに相当する。
最も波長の短い重力子も、2Lp/2Tpで、光速cになる。
一般に光子の波長λが“2nLp”であるとすれば、2nTpの転回周期を持つことになる。(光速が一定なため)
この際、nLpだけ距離の離れた素スピノールが、nTpの時間を費やして、“転回”することを繰り返すことによって、光が光速で進むことになる。
※もう1つのプランクエネルギーを求める式Ep=(hc5/2πG)1/2 と、上記の式Ep=(h/π)×c/2Lp
イコールでつなぐことにより、重力定数Gを計算できると思われた。
hc/2πLp =(hc5/2πG)1/2 より、h2c2/4π2Lp2=hc5/2πG
したがって、 G=2πc3Lp2/h となる。
しかし、これは、もともと、プランク距離を求める式、Lp=(hG/2πc3)1/2から導かれるGと合致するに過ぎない。
ここにあるのは、恒等式の変形にすぎないことになるが── 重力子の振動数や波長の大きさについての仮定(重力子が波長2Lpの光子2つ分が結合エネルギーを放出して結びついているものであるという仮定)が、大きく間違ってはいないことを示していると思われる。
また、重力定数は、プランク距離Lp、光速c、プランク定数hだけから計算できることになるので──
もし、プランク距離Lp、光速c、プランク定数hが一定であるならば、重力定数も一定であることになる。(→考察11)
※各定数のこれまでの表現の中の重力定数Gの代わりに“2πc3Lp2/h”を代入すると、それぞれの定数の意味が、より明確になると思われる。
それは、重力定数Gを Lpで置き換えた表現であると言える。 (cとhは、完全に消えずに残っている)
|
これまでの表現
|
重力定数Gを Lpで置き換えた表現
|
|
プランク距離
|
Lp=(hG/2πc3)1/2 |
Lp
(素スピノールの間の最小距離)
|
|
プランク時間
|
Tp=(hG/2πc5)1/2 |
Lp/c
(素スピノールが180度転回する最小時間)
|
|
プランクエネルギー
|
Ep=(hc5/2πG)1/2 |
hc/2πLp=(h/2π)×(c/2Lp)×2
(波長2Lpの光子2つ分が結合エネルギー
を放出して結びついているもの)
|
(※“これまでの表現”の部分はウィキペディアを参考にした)j
重力も創発されてきただろうというような自然の成り立ちを考え合わせると── 重力定数Gより、「プランク距離Lp──素スピノールの間の距離」の方が、より基礎的な実体であることをうかがわせる。
※さらに、プランク定数hより、プランクエネルギーをEpが基礎的な実体であるかもしれないことを考慮して、プランク定数hをプランクエネルギーEpを用いて置き換えて表すと次のようになる。
|
これまでの表現
|
重力定数Gを Lpで置き換え、
さらにプランク定数hをEpで置き換えた表現
|
|
プランク距離Lp
|
Lp=(hG/2πc3)1/2 |
Lp
(素スピノールの間の最小距離)
|
|
プランク時間Tp
|
Tp=(hG/2πc5)1/2 |
Lp/c
(素スピノールが180度転回する最小時間)
|
|
プランクエネルギーEp
|
Ep=(hc5/2πG)1/2 |
Ep
|
|
プランク定数
|
h
|
2πTpEp
(=2πLpEp/c)
|
|
ディラック定数
|
h/2π
|
TpEp
|
※h=2πTpEpである。 1秒と関係しているはずのhが、プランク時間とプランクエネルギーの積だけからも求められると言うこと。 これは、何を意味しているか?
hは、単に1秒だけでなく── (地球の自転と関係ない)「プランク時間&プランクエネルギーの関係」、そして、一般に「時間とエネルギーの関係」にも関与しているということだと思われる。
やはり、プランク定数には、ものすごく深い意味があるのだ。
例えば、もし、プランク時間を1単位にしている星があれば、そこでの、プランク定数は、H=2πEpになる── ということなのだ。
地球のように、1秒を1単位にしているわが宇宙では、プランク定数Hは、そのままH=hとなる。
もし、われわれにとっての“0.1秒分”を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=10hとなるであろう。
もし、われわれにとっての“3秒分”を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=h/3となるであろう。
もし、われわれにとっての60秒分を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=h/60となるであろう。
そして、どこでも、H=T×Eが成り立つこと── 不確定性原理の式が示すものは、どこの星でも(どのような時間を1単位とする星でも)なりたつ普遍的な原理であるということなのである。
当然、たまたま地球の自転を利用して決めた1秒を単位とした、この星でも、成り立つ──。 そういう普遍的な原理を、不確定性原理の式は表してくれているのである。
(そして、その関係は、原始ヒッグス場の“4面体”がもつ性質として、創発されてきたと考えられるのである。 →考察5)
※光速Cは、ある時間あたりに光が進む距離である。
もし、“3秒分”を1単位といる星があったとしたら、そこでの光速は、C=3c(3秒当たり3c進む)と表記されるであろう。
もし、“1/7秒”を1単位といる星があったとしたら、そこでの光速は、C=c/7(1/7秒当たりc/7進む)と表記されるであろう。
そして、“1秒分”を1単位といる星があるわれわれは、C=c(1秒あたりc進む)と表記している──。 つまり、光速の実体は、どの星でも、かわっていない。
一方、Tp=Lp/Cなので──
もし、“3秒分”を1単位といる星があったとしたら、そこでの、プランク時間は、Tp=Lp/C=Lp/3cと表記されるであろう。
もし、“1/7秒分”を1単位といる星があったとしたら、そこでの、プランク時間は、Tp=Lp/C=7Lp/c と表記されるであろう。
そして。“1秒分”を1単位といる星があるわれわれは、そこでの、プランク時間を、Tp=Lp/c と表記している──。
やはり、表記が変わっているだけで、“プランク時間”の物理的な実体像──“素スピノールが180度転回する最小時間”は、やはり、一切変わっていないと考えられる。
※1つ“4面体”の中の2個の素スピノールが転回する際は、転回周期T×エネルギー振幅E=h/2π となり、これは重力子を説明し──
1つ“4面体”の中の1個の素スピノールが転回する際の式は、転回周期T×エネルギー振幅E=hとなり、これは光子を説明する。
※一方、原始ヒッグス場のある1つの基本構造の“4面体”に注目したとき、もし、1秒間にc/2Lp回の頻度(=νp)で重力子がそこを通過したとすれば── 次から次へと絶え間なくエネルギーが供給され続けることになるので、その“4面体”は、常に“4角形”(縮みきったバネ)のままの状態で存在するようになると考えられる。
この場合、その“ずっと縮みきったバネ”の“4角形”の1つの中には── 1つの重力子がつ持つエネルギー×(c/2Lp回/1秒間)=hc/2πLp×c/2Lp=hc2/4πL2p(=(h/π)×ν2p)のエネルギーが単位時間当たりに存在することを意味すると思われる。
もし、そのようなエネルギー密度をもつ場所がある広い範囲であれば──
つまり、原始ヒッグス場の“4面体”が存在する余地がなくなるほど重力子の密度が高まり、ある“4面体”が、常に“4角形”(ずっと縮みきったバネの“4角形”)であり続けるような性質を持つ“時空の基本構造”が空間に広がっていれば── そこには原始ヒッグス場の“4面体”が存在しないので、“4面体”のバネという足場を失った光子は、そこから先に進めなくなることになる。 つまり、このような性質で満たされた空間は、“ブラックホールの境界線の�、すぐ内側に相当すると考えられる
重力と“3つの力”の決定的な違いは、【素粒子の挙動レベル】の有無である。
重力は、【素粒子の挙動レベル】がなくても存在できる力である。 一方、他の3つの力は、【素粒子の挙動レベル】を介在させてはじめて存在できる力である。
《量子化された重力、重力場の計算》
「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”の変化量」=“重位勾配”=重力は、どのように計算できるであろうか?
その値の大きさは、「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの密度の変化量」に等しいと考えられるので、まず「“4角形”(縮みきったバネ)」の密度を求めることとする。
ある質量Mを持つ物体を中心とする、半径 r の球面を考える。
※図の“4角形”は、半径rの球面上の“4角形”(縮みきったバネ)を表す。
この半径r の球の表面積は、4πr2である。
一方、重力子は、3D空間の360の方向に、ランダムかつムラなく放射されると考えられる。 これまでの仮定により、また重力子は、波長2プランク長(2Lp)であり、すぐとなりの原始ヒッグス場の“4面体”を伝播していくと考えられる。 (原始ヒッグス場の“4面体”の大きさは、2プランク長(2Lp)であると考えられる)
計算を簡単にするため── “4角形”(縮みきったバネ)は、“2Lp刻みの半径rの球面内”にのみ存在すると仮定する。
(したがって、nを整数として r=2nLpと表記できることになる。
たとえ1mでも、r=2nLpの中のnの値は、n=1m/2×(1.616×10-35)m≒0.309×1035と非常に大きなものとなることになる)
半径 r から半径(r+2Lp) に変化する時、球の表面積は、4πr2から4π(r+2Lp)2に変化する。
一方、重力子は、波長2プランク長(2Lp)で、(半径が2Lpだけ大きい球面内の)すぐとなりの原始ヒッグス場を、次々と伝播していくと考えられるので、「半径 r=2nLpの球面に存在する“4角形”(縮みきったバネ)の数」は、nの大きさ(rの大きさ)に関わらず、どこでも一定であると考えられる。
これを定数Nとする。
(実は、N=M/Mpとなると考えられる。→下記の考察)
半径r=2nLpの球面内における「“4角形”(縮みきったバネ)の面密度」は、N/4πr2=N/4π(2nLp)2=N/16πLp2n2 となる。
半径(r+2Lp)=2(n+1)Lpの球面内における「“4角形”(縮みきったバネ)の面密度」は、N/4π(2(n+1)Lp)2=N/16πLp2(n+1)2 となる。
「“4角形”(縮みきったバネ)の面密度」は、N/4πr2 より、1/r2に比例することがわかる。
一方、重力は、ニュートンの万有引力の方程式が示すように、1/r2に比例する。
つまり、“4角形”(縮みきったバネ)が存在する面密度、および重力は、ともに、r2 に反比例することになるので、
この「“4角形”(縮みきったバネ)の面密度」は、そのまま“重力の大きさ”に比例すると考えられる。
※あるいは、「電場の強さは力管の断面積に反比例する」(『基礎教養 物理学 下』p190)という内容から、類推できるからである。 “力管”とは、「電気力線で囲まれた管」のことである。 つまり、この類推によると、“重力子の通り道が、力管に等しい”と考えると球面内の、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の存在しない場所の面積に、重力は、反比例すると考えられ── それは、逆に「「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の存在する場所の面積の比率」=「“4角形”(縮みきったバネ)の面密度」に比例して重力が大きくなることを意味するからである。
※半径rが小さくなるほど、“4角形”(縮みきったバネ)の面密度の大きくなるので(=「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”」が小さくなるので)、重力が大きくなることになる。
比例定数εを使って、半径rの球面の地点の重力場の大きさ(=試験質量に働く重力の大きさ)は、面密度×ε=Nε/16πLp2n2 と書き表せることになる。
※これが、GM/r2=GM/(2nLp)2=GM/4Lp2n2 に等しいと置くと── Nε=4πGM と求まる。
ここで、εを計算してみる。 N=M/Mp(→下記の考察)、Mp=Ep/c2、Ep=hc/2πLp、G=2πc3Lp2/hを代入する結果、ε=4πc2Lp となる。
よって、「“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度」×定数(ε=4πc2Lp)によって、重力場(=“重位勾配”、=“時空の曲がり”)を計算できることになる。
“r=2nLpの地点での重力場”=Nε/16πLp2n2=(M/Mp)×4πc2Lp×(1/16πLp2n2)=Mc2/4MpLpn2=Mc4/4EpLpn2=(Mc4/4Lpn2)×(2πLp/hc)
=(2πc3Lp2/h)×(M/4Lp2n2)=GM/r2
よって、ニュートンの万有引力の法則と合致することが分かる。
一方、重力とは、“重位勾配”、つまり、「単位距離あたりの重力ポテンシャルエネルギーの変化量」(≒重力ポテンシャルエネルギーを微分したもの)に他ならないのであった。
すると、(単位距離あたりではなく)「長さLpあたりの重力ポテンシャルエネルギーの変化量」は、“重位勾配”×2Lpで求められる。
※この傾き(勾配)が重力=“重位勾配”に相当する。
すると、例えば、半径rの球面の地点から、半径(r+2Lp)の球面の地点まで、質量mの物体を移動させる際に必要なエネルギーは、
(Nεm/16πLp2n2) ×2Lp=Nεm/8πLpn2 と求まることになる。
トータルの“重力ポテンシャルエネルギー”は、次の図のように、幅2Lpずつ変化する「重力ポテンシャルエネルギーの変化量」の和であると考えられるので──。
※正確な図ではないが、この図は理解を助けると思われる。
球面の中心から、r=2nLpの地点までの、重力ポテンシャルエネルギーのトータルの変化量の大きさは、2Lpあたりの変化量を、n=1から、n=2… n=r/2Lp まで、ずっと足していけば求まることになる。 (※球面の中心には、いわゆる、大きさのない質点を想定することとする。)
一方、一般に、nが自然数とき、次の不等式が成り立つ。
(参考 『三訂版 高等学校 基礎解析』(昭和63年)の第3章『数列』の中の第2節 数学的帰納法の中の問題13(2) ※数学的な帰納法によって証明できる)
1+1/22+1/32+……+1/n2 ≦ 2−1/n
この不等式を使うと──
r/2Lp
r=2nLpの地点での重力ポテンシャルエネルギー= Σ(Nε/8πLp)×(1/n2) ≦(Nε/8πLp)×(2−1/(r/2Lp))=(Nε/4πLp)×(1−Lp/r)となる。
n=1
※無限遠方のr=∞の地点での、重力ポテンシャルエネルギーの大きさは、((Nε/4πLp)×(1−Lp/r)の中のマイナス項が0に近づくので)、Nε/4πLp となると考えられる。
いわゆる重力ポテンシャルエネルギーの式、−GM/r は、無限遠点を重力ポテンシャルエネルギーを0としたときの、相対的なものであるといえる一方── 先ほど、求めたr=2nLpの地点での、重力ポテンシャルエネルギーの大きさ
|
r/2Lp
Σ(Nε/8πLp)×(1/n2)
n=1
|
≦(Nε/4πLp)×(1−Lp/r) |
|
は、球面の中心の重力ポテンシャルエネルギー0としたときの、絶対的なものであると言える。
−GM/rの大きさは、下に図示してある部分に相当する。
※図の底辺rと高さGM/rの三角形の斜辺の傾きの起きさと、rでのカーブの傾きは等しくなると思われる。
なぜなら、rの地点での“勾配”は、(GM/r)/r=GM/r2と求められ、これがニュートン力学と合致するからである。
|
無限遠方のr=∞の地点での、重力ポテンシャルエネルギーの大きさは、Nε/4πLp となると考えられるので──
Nε/4πLp×(1−Lp/r)の中で、“−GM/r”に、相当する部分は、まさに、この式のマイナス項── (Nε/4πLp)×(−Lp/r)=−Nε/4πr であると言えると思われる。 (実際に、これらは、とても形が似ている。)
“−GM/r”=−Nε/4πr と置き、εを計算してみる。 N=M/Mp、Mp=Ep/c2、Ep=hc/2πLp、G=2πc3Lp2/hを代入する結果、ε=4πc2Lp となる。
(これは、前に求めた式、Nε=4πGM から求めたεの値とも合致する)
よって
r=2nLpの地点での(絶対的な)重力ポテンシャルエネルギー ≦(Nε/4πLp)×(1−Lp/r)
=(Nε/4πLp)×(1−1/2n)=(M/Mp)×4πc2Lp×(1/4πLp)(1−1/2n)=(Mc2/Mp)×(1−1/2n)
=(Mc2×c2/Ep)×(1−1/2n)=(Mc4×2πLp/hc)×(1−1/2n)=(2πc3Lp2/h)×(M/Lp)×(1−1/2n)
=(2πc3MLp/h)×(1−1/2n)=GM×(1/Lp−1/r)
以上より、“素スピノールからの創発モデル”に基づいた量子化された重力場、重力ポテンシャルエネルギーの計算結果──
r=2nLpの地点での重力場=Nε/16πLp2n2 (=πMc3/2hn2=GM/r2)
r=2nLpの地点での(絶対的な)重力ポテンシャルエネルギー ≦(Nε/4πLp)×(1−Lp/r)(=(2πc3MLp/h)×(1−1/2n)=GM×(1/Lp−1/r))
は、ニュートン力学と矛盾していないと考えられる。
|
ニュートン力学
|
“素スピノールからの創発モデル”
に基づいて量子化されたもの
|
|
重力ポテンシャルエネルギー
|
−GM/r
※無限遠方を0としたときの
相対的なもの
|
(2πc3MLp/h)×(1−1/2n)=GM×(1/Lp−1/r)
※物質の取り囲む球面の中心を0
としたときの絶対的なもの
|
|
重力場
|
GM/r2
|
πMc3/2hn2=GM/r2
|
※G=2πc 3L p2/hである
どこでも一定であると考えられる「半径 r=2nLpの球面に存在する“4角形”(縮みきったバネ)の数」は、N=M/Mpとなるのだった。(→下記の考察)
中心から、r離れたある一点までの、重力ポテンシャルエネルギーの変化が、(Nε/4πLp)×(1−Lp/r)以下となると言うことは── ある質点が持つ、重力場のエネルギーの総和── ある質点が周囲に作る、“4角形”(縮みきったバネ)のエネルギーの総和は、
重力場が持つ総エネルギー ≦ GM×(1/Lp−1/r)×N = GM×(1/Lp−1/r)×M/Mp となることを意味する。
つまり、以上のような“素スピノールからの創発モデル”に基づく「重力&重力ポテンシャルエネルギーの量子化」の理論においては、重力の大きさ、重力ポテンシャルエネルギー、重力場が持つ総エネルギーについて、いずれにおいても、無限大は生じず(発散が生じず)、繰り込みが不要になると考えられる。
※仮に、たとえ中心が質点であったとしても、上のように発散が生じないので── 大きさを持つ物体であっても、当然、発散が生じないことになる。
そして、先の考察のように“素スピノールからの創発モデル”に基づいて、アインシュタインの相対性理論に関した現象(光速不変の原理、等価原理…)を説明できるのだった。
以上の考察は、重力の量子化に成功していると言えるのだろうか?
アインシュタインが、難解な数式で求めた“時空の曲がり”を、単純な計算で求めてしまったと言っていいのだろうか?
少なくとも、「“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度」と、重力&重力ポテンシャルエネルギーの間には、深い関係があり── この関係が重力の量子化のためにおおいに役立つことは確かだろうと考えられる。
アインシュタイン方程式との整合性を含め、詳しい検討は、今後の課題である。
※質量Mが1秒間に放出する重力子の総数は、(M/mp)×νpである。…(0)。(νpとは、c/2Lpのことである)
シュバルツシルト半径rsの場所(ブラックホールの事象の地平面)には“4角形”(縮みきったバネ)が100%びっしりとつまっていると考えられるので(→考察7)その球の表面積4πr2sを、“4角形”(縮みきったバネ)の1つの面積(2Lp)2=4Lp2で割ると、球面全体の中に存在する“4角形”(縮みきったバネ)の数が計算できる。
球面全体の中に存在する“4角形”(縮みきったバネ)の数=4πr2s/4Lp2=πr2s/Lp2…(1)
この球面が、(重力子は、すぐとなりの原始ヒッグス場の“4面体”を伝わっていくので)1秒間にνp枚分が放出されると考えることもできる。つまり、(1)×νp が、質量Mが1秒間に放出する重力子の総数のもう1つの求め方になる。
したがって、(0)=(1)×νp つまり、(M/mp)×νp=πr2s/Lp2×νp となり── その結果、(M/πmp)=r2s/Lp2となる。…(2)
この物体の中心からの距離をrとすると、rの場所での球面の中に“4角形”(縮みきったバネ)が何%存在しているか?
それは、rsの地点で100%であるので、rの場所では、単純に(4πr2s/4πr2)×100%=(r2s/r2)×100%存在することになるであろう。
rsの場所での“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度は、(1)を球面積で割って (4πr2s/4Lp2)/4πr2s=1/4Lp2であるので── rの場所での球面の中での“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度は、(1/4Lp2)×(r2s/r2)となる。 ここに(2)を代入すると── rの場所での球面の中での“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度=(1/4Lp2)×(M/πmp)=(1/4πmp)×(M/r2)となる。 …(3)
(つまり、(3)に、定数εをかけることによっても、重力が求められることになる。)
すると、(3)を、N/4πr2に等しいと置くことより、N=M/mpが求まる。 これは、やはり、1つの球面内の重力子の数を意味し── 質量Mが1秒間に放出する重力子の総数の式は、(M/mp)×νpの式は、 「(M/mp)個の重力子を含む球面」を1秒間にνp枚分放出されることを意味していると解釈できることになる。
《重力場、エネルギー、質量、非線形性、電磁場の線形性との比較》
重力子は、それ自体は質量を持たない。 だからこそ、光速で無限遠方まで移動できる。
典型的な重力子は放出源は── 物体の質量を構成する、(ミクロレベルで光速で運動し続ける)素粒子の総和である。
(なお、プレオン∴×4の“4角形”(四極子)も、重力子の放出源になると考えられる。 →考察3)
他に、原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)も、重力子の放出源であると見なすことができるが── やはり、その大元は、物体の質量を構成する素粒子の総和である。
ふつう、重力子は、“素粒子の総和”という質量(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を新たに放出する能力)が原因となって、放出される。
つまり、決して重力子自身が質量を持っているわけではない。(もし、質量を持っていたら、光速で移動できない)
よって重力子が一定の頻度で放出され続けていることは、決して、質量(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を新たに放出する能力)が増え続けることを意味しない。
“素粒子が質量を獲得する”過程とは、(マクロレベルでの見かけ上)光速を失う過程であり、「“4面体”→“4角形”(縮みきったバネ)」のように、原始ヒッグス場の基本構造を変形させる過程そのものと言える。
一定時間内にどれくらいの頻度で、「“4面体”から“4角形”(縮みきったバネ)へ」と原始ヒッグス場の基本構造を変形させることができるかは、質量の大きさに比例する。(まさに質量は、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を新たに放出する能力である)
|
|
|
←生じる“4角形”(縮みきったバネ)の密度が
小さいほど質量が小さい |
生じる“4角形”(縮みきったバネ)の密度が
大きいほど、質量が大きい→
|
|
質量とは、一定時間内に、周囲の原始ヒッグス場の基本構造を「“4面体”→“4角形”(縮みきったバネ)」のように新たに変形させる能力そのものであるとも言える。
素粒子は、もともと、はじめから“重力子を新たに放出できるほどの能力”を持っていたはずなので── そういう意味では、“素粒子が質量を獲得する”という表現より、“素粒子が質量を発揮する”と言う方が、適切なのかもしれない)
その物質が持つ質量によって生み出された重力場は、確かにエネルギーを持つといえる。
しかし、その“重力場が持つエネルギー”は、あくまで、その大元の物質が持つ質量(重力子を新たに放出する能力)によって放出された、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」のエネルギーの総和に過ぎないのであり── その“重力場が持つエネルギー”自身が、新たな重力子の放出源となることは、決してありえないと考えられる。
(したがって、“重力場が持つエネルギー”自体が“新たな質量”になるということもありえない。)
つまり、“エネルギーを持つ重力場”そのものが“質量を持つ”(=重力子を新たに放出する能力を持つ)ということは決して起こらず── 質量(=重力子を新たに放出する能力)を持ち続けるものは、あくまで、大元の物質であると言うことなのである。
一見、重力場がエネルギー(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」)を放出しているように思われるかもしれないが── 大元の物質の質量こそが、“重力場の持つエネルギー”のすべてを供給し続けているのであり── 重力場は、あくまで“エネルギーの通過点”に過ぎないと言うことなのである。
(「たとえ、途中の電線からエネルギーが放出されるように見えても、実際は、すべてのエネルギーが発電所から供給されている── ということと似ていると思われる。 やはり、決して途中の電線から新たにエネルギーが生まれるわけではなく、電線はエネルギーの通過点に過ぎないのである」ということと似ていると思われる。)
つまり、以上のことは、「エネルギーがあっても、質量を持つとは限らない」こと、「質量は、あくまで、エネルギーの1つのあり方にすぎない」ことを示していると思われる。
※質量(=重力子を新たに放出する能力)があれは、必ずエネルギーがあるが──
エネルギーがあるからといって必ず質量(=重力子を新たに放出する能力)があるとは限らない。
(質量→エネルギー○ エネルギー→質量× エネルギーは質量の必要条件であるが十分条件ではない)
※重力子(重力場)の他に、光子(電磁場)も、エネルギーを持つけれども、質量を持たないものの例である。
(※本来、この図は、数学の集合の図にすぎないが── 物質と重力場の関係を表す図とも少し似ている) |
重力場は確かにエネルギーを持つけれども、質量(=重力子を新たに生じる能力)を持たないのであり── 「重力場が、(質量を持つ物体によるもの以外の)新たな重力子を生じる(質量を持つ)」と考えることも、「 重力場のエネルギーそのものを、E=mc2の式にあてはめること」もナンセンスだと言うことになる。
“素スピノールからの創発モデル”によれば── 「重力場(重力子&原始ヒッグス場の総和)そのものが、(“質量を持つ物体”という大元の放出源によるもの以外に)新たに重力子を放出できるようになる(質量を持つ)」ことはないことを、はっきり示している。
重力場は、やはり、大元の波源(質量)から届いてくる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」をリレー(転送)し続けているだけである。
アインシュタインの重力場についての方程式(アインシュタイン方程式)では、
左辺が“時空の曲がり”(曲率)を意味する一方で、右辺には時空を曲げる原因(物質のエネルギー密度(質量密度)や運動量)となるものが入るのであった。
“素スピノールからの創発モデル”に基づく考察によれば── (アインシュタイン方程式)左辺の“時空の曲がり”(曲率)が“重位勾配”(=“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度)に相当し、右辺が“重力子を新たに放出する能力”の密度(=質量密度や運動量)に相当するものが入ると考えられる。
※右辺のTμνには、質量や運動に関したものが入るということは、
マクロの物体の(低速の)運動によって、1/2mv2に相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出され、
ミクロの素粒子の光速の運動によって、mc2に相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」も放出される」と考えられることと、およそ合致すると思われる。
アインシュタイン方程式は、下の図のように、物質の総質量の大きさが同じであっても、その密度が大きくなれば、周囲の“時空の曲がり”=“重位勾配”も、大きくなることを意味していると思われる。
|
|
|
|
※質量の密度は、異なっている。
質量の密度が大きいほど(物体がコンパクト化しているほど)、物質の周囲の、時空の曲がり
=“重位勾配”(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度)は、大きくなっている。
※なお、質量の大きさは、どれも同じであるので──
例えば、共通する図の“2重の緑の間”の部分での時空の曲がり=“重位勾配”は、どれも同じになっている。
|
|
|
以上の中に、「アインシュタインの一般相対性理論の方程式が“非線形である”」と言われていることの意味を見いだすことはできないと思われる。
一方、やはり、「重力場のエネルギーそのものが、(“質量を持つ物体”という大元の重力源からのもの以外に)新たに重力子を生じる(新たに質量を持つ)」ということはないと考えられる。 つまり、「重力場のエネルギー≠質量(≠「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を新たに放出する能力)」であるので── 少なくとも「重力場のエネルギー=質量(=「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する能力)」という意味での非線形性は、自然(nature)の中には、実在しないと考えられる。
つまり、“重力場のエネルギー”そのものを“質量”と見なし、新たな“時空の曲がり”の原因として方程式に代入することはナンセンスであると思われる。
※なぜ、重力は非線形と言われるようになってしまったのだろうか?
その1つの理由は、アインシュタイン選集2(p96〜99)から読み取れる。
その中に、次のような記述がある。
「すなわち、いま一つの完全系(たとえば太陽系)を考えよう。この物理系の全物質量、したがってまたその全重力的作用は、この物理系の全エネルギー、つまり物質によるエネルギーと、重力場のエネルギーの総和に依存する。 この事情は、カ(51)において、重力場のエネルギー成分のt〜 のかわりに、物質および重力場の両方のエネルギー成分の和t〜+T〜を導入することによって表現される。」
この文章には、“物質のエネルギー”(質量や運動量)と“重力場のエネルギー”が、混乱した形で理解され、用いられているという問題──「“重力場のエネルギー”が、新たな質量であるという扱いがなされている」という問題があると思われる。
なぜなら、“素スピノール創発モデル”によれば、物質のエネルギー(=質量)が、その能力に見合った量の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出し、その「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が、“重力場のエネルギー”に相当するからである。
(“素スピノールからの創発モデル”によれば── しかもそれは、収束し、発散しないと考えられる。 by上の考察《量子化された重力、重力場の計算》)
「上で述べたような物質のエネルギー・テンソルの導入の仕方は単に相対性の要請からでは正当化されないということに注意しなければならない。ここでは、われわれは、次のような要求を用いて、上の式を導いた。すなわち重力場のエネルギーは、他のどのような同じ形の、重力的作用をもつべきであるという要請である。」
“物体(質量)から生まれたはずの重力場”が新たな質量になり、そこから、新たな重力場が生まれるという── 非線形的なアイディアの源泉がこの文章にあると思われる。 この文章には、明らかに、「重力場が新たな質量として、新たに重力子を放出するようになる」という非線形性をもたらすような新たな要請を、アインシュタインがしてしまっていることが読み取れる。 しかも、それは、“相対性の要請からは正当化されない”ような要請である。
つまり、「重力場が、新たな質量になる」というアイディアの源は、アインシュタインの心の中にあったと思われる。
※このような考えに至った理由は、アインシュタイン自身が発見した“E=mc2”にあると思われる。
しかし、「エネルギーは、どれも質量なのだ」という考え方は── 必ずしも正しいとは限らず、“E=mc2”の誤用(濫用)であると考えられる。
一方、「質量は、どれもエネルギーなのだ」という考えは常に正しいと思われる。(もしかしたら、mc2=E が、誤用を防ぐ表記と言えるのかも知れない)
E=mc2は、質量をエネルギーに変換できること(質量がエネルギーを持つこと)を示す式にすぎず── 逆にあらゆるエネルギーをすべて質量に変換できることを示す式ではないことになる。 つまり、質量とエネルギーは、厳密には、100%等価ではないことになる。
(「質量とエネルギーは、等価である」という表現は、実は、精確ではないことになる。 “E=mc2”は、条件付きの理論である、ということもできると思われる。 →考察16)
“素スピノールからの創発モデル”によって厳密に表記するならば、「(静止)質量は、“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を新たに放出する能力に相当”するところの、ミクロのレベルで光速で運動し続ける素粒子が持つエネルギーの総和である」となると思われる。
つまり、質量とは、あくまで、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を新たに放出する能力であるので── 「重力場が質量となり、そこから新たな重力子が放出される」という非線形性は、やはり、不要かつナンセンスとなるのだ。
しかし、“時空の曲がり”(曲率)(=“重位勾配”、=“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度)と、質量密度や運動量(=“重力子を新たに放出する能力”の密度)が等しいという本質的な結論はゆるがないと考えられる。
※アインシュタイン選集2、p92〜の「物質が存在しないときの重力場の方程式」の項目に次のように書かれている。
「たとえば1個の質点によって、そのまわりにつくられた重力場を考えてみよう。この重力場はどんな座標系を採用しても、それを消し去ることはできない(訳者注:質点のまわりでは物質は存在しないが、重力場は存在する。〜)」
〜 Bμν=0 とおくことは、きわめて自然な要求であろう。 これらの式は、〜
… … (47)
となる。これが物質が存在しない所での重力場の方程式である。
この方程式を選び出すに際して、任意性のはいることが最小にとどめられたことに注意すべきである。というのは、gμνおよびその微分から構成されており、gμνは2階以上の微分を含まず、2階微係数については線形であるような二階テンソルは、Bμν以外には存在しないからである。
一般相対性の要求から、まったく数学的な方法で導かれたこれらの場の方程式は、一方質点の運動方程式(46)といっしょになって、第一近似ではニュートンの引力の法則を与える。また第二近似まで考えると、ルヴェリエ(Leverrier)によって発見された水星の近日点の移動(他の惑星による摂動に由来する修正を行なったあとに残る移動量)を説明することができる。」 (部分的に、〜として割愛させていただいた。下線は筆者による)
これは、式(47)自体は、線形であることを解釈していいのだろうか?
だとすれば、たとえ、非線形性がなくとも、“水星の近日点の移動”を説明できることになる。
式(47)をもとにして、成立することが示される式(49)については、「この式は、重力場の運動量およびエネルギーの保存則を示すものである」と書かれている。
さらには、式(47)をもとにして、式(47)の“第3の形”──式(51)が導かれる。
そして、式(51)をもとに、上記の「“重力場のエネルギー”が新たな質量となる」という、非線形的な考え方が盛り込まれた上で、式(53)ができていてる。 この式(53)がアインシュタイン方程式の原型である。
このことは、この式自体の中に、どこか間違いがあることを意味しているのだろうか?
それとも、単に、重力場のエネルギー=質量と考えた上での“代入の繰り返し”だけをしなければすむ問題なのだろうか?
それとも、式(47)(49)(51)で十分であるということなのだろうか?
それとも、これまでの考察のどこかに間違いがあるということなのだろうか?
その答えの1つは、“式(47)(49)(51)”の中に、「“時空の曲がり”(曲率)と、“物質のエネルギー”(質量密度や運動量)が等しい」という本質的な結論が内在しているかどうか、あると思われる。 (質点の働きと物質(エネルギーを持つ)の働きは、密度の違いがあるだけで、ある意味、本質的には同じと見なすことができるので、“内在している”と考えていいのだろうか?)
詳細な検討は、今後の課題である。
※すると── 少なくとも、「重力場は非線形であり、 電磁場は線形である」とは、単純に言えないことになる。
重力場と電磁場の違いはなにか?
そこにある大きな違いの1つは、電場や磁場を生むところの光子は、仮想光子であり、決して、ふつうの“電磁波”ではない一方──
重力場を生む重力子は、仮想粒子であると同時に、“重力波”(電磁波×2)である── ということである。
|
場
|
電場&磁場
(電磁場)
|
重力場
|
|
ボソン
|
仮想光子
|
(仮想粒子である)
重力子
|
|
どこへ行くか
|
電荷に再吸収される
|
無限遠方まで進んでいく
|
|
電磁波との関係
|
(無限遠方まで進んでいかないので)
電磁波ではない
|
電磁波×2である
|
もし、電場や磁場を生むとされる仮想光子が、ふつうの電磁波だったらどうなるか?
電場や磁場の正負を逆転し続けるだけになってしまい── 一定の大きさを持つ電場や、一定の大きさを持つ磁場が生じることが決してできなくなってしまうだろうと考えられる。 なぜなら、電磁波であるならば、例えば、生じた電場や磁場は、すぐにその正負を逆転させてしまうからである。(その変化こそが電磁波の波を作る)
しかし、実際には、静止した電荷の周囲には電場、運動する電荷の周囲には磁場ができており、電力線や磁力線を描くことができる。
したがって、電磁場を生む仮想光子と、電磁波は、別物であることがわかる。
※この考察は、電荷の起源── 電荷の幾何学的な実体像を追求するためにも役立つ。(→考察6)
電磁場の世界は線形であるということは、電場や磁場の大きさは、単純な足し算&引き算で求められることを意味する。
それは、素スピノールの転回にともなう“4面体”の変形が単振動であること、すなわち、「仮想光子&原始ヒッグス場の“4面体”←→変形した“4面体”」が“調和振動子”の一例であることを示唆していると思われる。
一方、重力子という名の仮想粒子は、すべて、止まることなく、次から次へと、原始ヒッグス場の基本構造によって、無限遠方までリレーされ続ける。
その過程で、1つ1つの重力子&“4角形”(縮みきったバネ)は、増幅したり減衰したりしないと考えられるので、このあたりにも、非線形性は見あたらないと言える。
ただ単に、中心の質量からの距離の2乗に反比例して、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度が減るだけである。
(決して、重力場そのものから、(“重力子の大元の波源=質量を持つ物体”からの重力子以外に)新たな重力子を生じるようなことは起こらない)
そして、その「距離の2乗に反比例して球面密度が減る」という性質が、ニュートンの万有引力の法則の数式が示す性質を支えていると考えられるのは、いうまでもない。
そして、 「重力場は、重力子&原始ヒッグス場の“4面体”の総和である」と考えられるのは、「重力子&原始ヒッグス場の“4面体”←→“4角形”(縮みきったバネ)」が“調和振動子”の一例だからこそであることに気づくとき── 重力や重力場の世界の中に、やはり、非線形性は見あたらないと思われてくる。
※同様に、電磁場を生む仮想光子の波源(電荷)からの距離の2乗に反比例して電場の大きさ(電気力線の密度)は小さくなる。
(仮想光子は、電磁波ではないので── “電荷”によって、半波長(λ/2)だけ離れた場所にある、素スピノールが、ダイレクトに180度転回させられると考えられる。
(上でも考察したように)光速cは一定なので、電荷からの距離 r =λ/2 が大きくなればなるほど、仮想光子の転回周期Tも大きくなる(=振動数νが小さくなる)。 λ=2rなので、転回周期Tは、T=λ/c=2r/c で計算できる。
プランクの式より、光子のエネルギーE=hν=h/T が成り立つので── 仮想光子の転回に伴うエネルギー振動の振幅Eは、E=h/T=hc/2r と求められる。 これをrで微分すれば、dE/dr=−hc/2r2 となり、電場の大きさ(=“電位勾配”、=電気力の大きさ)を求めるクーロンの法則の式と似たものとなる。)
やはり、重力に非線形性がないからこそ、クローンの法則と同様に、重力は、「距離の2乗に反比例する」のである。
つまり、「実際には、重力場そのものから“新たな重力子が放出される”ことがありえない」おかげで── 重力の大きさを、電磁気力と同様に、比較的、単純に求められるのである。
それは、たとえミクロの量子化された世界でも同様である。(→考察《量子化された重力、重力場の計算》)
※以上の考察は、アインシュタインの一般相対性理論の数式を、本質を失わずに、よりシンプル化できる可能性があることを意味してるのだろうか?
単に、幾何的な実体像を視覚化するプロセスを欠いていたがために、一般相対性理論の数式が複雑難解になってしまっているだけなのだろうか?
上記の考察(《量子化された重力、重力場の計算》)は、よりシンプル化したところの一例なのだろうか? (→ 考察15数学&標準モデルのパラメーターの求め方について))
詳細な検討は、今後の課題である。
※そもそも、ある質量を持つ物体が、エネルギーを持つ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出し続けているなら──
「この世に存在する、エネルギーが増え続けてしまうことになってしまう(新たにエネルギーが生成され続けてしまう)のではないだろうか?」
「これは、エネルギー保存則(熱力学第1法則)の破れを意味するから問題があるのでないだろうか?」という疑問が湧く。
(静止)質量とは、(ミクロレベルで光速を保って運動し続けている素粒子による)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する能力の総和であり── 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の波は、“エネルギーの生成と消滅を繰り返して伝わる(エネルギー保存則を破って生じるところの)仮想粒子の波”である」から問題ない、ということで済むだろうか? (“エネルギー保存則を破って生じる”というのが、仮想粒子の性質そのものである)
あるいは、「ミクロレベルで光速を保って運動し続けている素粒子」ということも大きなポイントであるようにも思われる。
単に、素粒子は、「ミクロレベルで光速を保って運動し続けている」から、エネルギー保存則(熱力学第1法則)の破れておらず問題ない、ということで済むのだろうか? あるいは、「エネルギー保存則(熱力学第1法則)は、条件付きの法則」であるということなのだろうか?(このあたりのことは、“E=mc2”が条件付きの理論であると考えられることとも深い関係がありそうである)
詳細な検討は、今後の課題である。
このあたりのことは、アインシュタイン自身も問題意識を持っておられた。
『アインシュタイン選集2──A8重力波について』によると──
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』 (下線は、筆者による)
※アインシュタインによる「量子論が完成されたときには、〜解決されるのであろう」という予想と、“素スピノールからの創発モデル”に基づく“量子論”についての考察 (→考察3、考察5)、および、“量子論”的な重力についての上記の考察は、うまく合致していると言えるのかもしれない。 詳細な検討は今後の課題である。
※なお、この文章から、アインシュタインは、“量子論がまだ不完全だ”と考えていただけにすぎず(“量子論の不完全さ”について批判していたにすぎず)、決して、量子論のすべてを否定しようとしていたわけではない、ということがうかがえる。
アインシュタインは、“本物の量子論の完成”を強く願っていたのではないだろうか?
|