研究論文
『“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介』
3.超弦理論〈Superstring Theory〉について
“超弦理論”は、マクロの世界が得意な「一般相対性理論(重力)の世界」と、ミクロの世界が得意な「量子論(量子力学、場の量子論)に基づく素粒子物理学の標準模型(3つの力)の世界」とを統合できる理論の最有力候補として、そして、現代物理学界の主流として発展してきた。
そして、しばしば、「一般相対性理論(重力)」と、「量子論(量子力学、場の量子論)に基づく素粒子物理学の標準模型(3つの力)」を統合的に説明することのできる、万物理論(TOE)の“唯一”のものであると説明されてきた。
しかし、これは、“唯一病”の危険な兆候であるおそれがある。
なぜなら、少なくとも、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が存在するからである。
そして、そもそも、その“唯一性”の主張には、本来、大した根拠がなかったことは、次の記述からも読み取れる。
『なぜ、弦が上手く行きなぜ他の理論が駄目なのかは先験的には全く明らかではないが、この理論を展開させて行くにつれて、どのようにうまく行くかは分かるであろう。 おそらく我々は単に想像力のなさで苦労しているだけであり、短距離切断を持つ矛盾のない重力理論は他に多くあるだろう。 しかしながら場の量子論の発散の問題は簡単に解決できそうもないことを経験が示しており、それならばたとえ一つでも解決策が見つかれば我々はそれを非常に真剣に捉えるべきである』
(p5-6 より 『ストリング理論』第1巻 J・ポルチンスキー著 伊藤克司・小竹悟・松尾泰 訳 シュプリンガー・ジャパン ※下線は筆者による。)
|
すなわち、「一般相対性理論(重力)」と、「量子論(量子力学、場の量子論)に基づく素粒子物理学の標準模型(3つの力)」を統合的に説明することのできる理論は、本来は、他にも、ありうるはずなのだ。 たまたま1つの解決策として、“超弦理論”が見つかったので、それを『非常に真剣に捉えるべきである』と主張しているに過ぎなかったのだ。
したがって、もし、その解決策として、新たな理論が見つかれば、それについても、同様に『非常に真剣に捉えるべきである』のは、当然のことである。
※そして、今まさに、「一般相対性理論(重力)」と、「量子論(量子力学、場の量子論)に基づく素粒子物理学の標準模型(3つの力)」を統合的に説明することができるのみならず、『想像力のなさで苦労している』のを助け、『なぜ、弦が上手く行』くのかをも含めて説明できる理論の候補として、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)があるのである。
“超弦理論”が、まだ完全ではないことは、少なくとも、次の記述から読み取れる。
『現在、ひも理論研究者は、等価原理を手にしていないアインシュタインのような立場にいる。 1968年にヴェネツィアーノが示した洞察に満ちた推理以来、発見と革命が繰り返される中で、ひも理論が築かれてきた。 こうした発見を含め、ひも理論の特徴をすべて受け入れる一つの包括的な体系的な枠組み──個々の要素の存在を必然的なものにする枠組み──を構成できるような中心的原理は、いまだに見つかっていない。そうした原理が発見されれば、ひも理論の発展にとって大事件であり、それまで誰も見通せなかった明瞭さで理論内部の仕組みがあらわになるだろう。 もちろん、そのような根本原理が存在する保証はないが、ここ100年の物理学の進化を考えれば、ひも理論研究者はそのような根本原理が存在するという望みを抱くことができる。 ひも理論の次の段階に目を向けるとき、その最優先課題は、理論全体がそこから必然的に生み出されるような根本的な考え、「不可避性の原理」を見つけることなのである。』
(『エレガントな宇宙』 p499 より ※下線は筆者による。) |
『弦理論が構築されることによって、わたしたちが知っているすべての、大まかな輪郭が捉え直されるはずだということはわかっているのだが、まともに使いものになる理論が完成するのを阻む問題点がしつこく残っている。 同時に、弦理論について知れば知るほど、それ以上にわからないことに気づくというありさまだ。 第三次超弦理論革命が必要だと思えるほどである。 だが、第三次超弦理論革命はまだ起こっていない。 弦理論研究者たちは、そんな完全な超弦理論の完成はあきらめて、現在実施されている実験や近い将来実施される実験について、現状で達しているレベルの理解の範囲で弦理論が予測できる断片的な事柄を述べてよしとしようとしている。』
(p5 より 『聞かせて、弦理論 時空・ブレーン・世界の端』 スティーブン・S・ガブサー 吉田三知世訳 ※下線は筆者による。) |
『本書の最初に、デモクリトスの言葉を引用しました。これを超弦理論にあてはめると次のようになるでしょう。
私たちは習慣によって、
重力があったり、
次元があったり、
空間があったりすると思うが、
現実に存在するのは……
本章の最初に、この「……」にあてはめるべき言葉を私たちはまだ知りません。重力や、次元や、空間が幻想であることは確かですが、それが何から現れてきているのかについて、根源的な理解に達していないのです。それを明らかにすることは、これからの大きな課題です。超弦理論はまだまだ発展途上なのです』
(『大栗先生の超弦理論入門』 p.248〜249) |
※そして、今まさに、『まともに使いものになる理論が完成するのを阻む問題点』を解消し、『ひも理論の特徴をすべて受け入れる一つの包括的な体系的な枠組み──個々の要素の存在を必然的なものにする枠組み──を構成できるような中心的原理』や『この「……」にあてはめるべき言葉』、『重力や、次元や、空間』が『何から現れてきているのかについて』の『根源的な理解』を提供する可能性のある理論の候補として、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)があるのである。
“超弦理論”の特徴や現状については、次のような図および記述から、端的に知ることができる。
|
|
|
『図1.4 Lie 群に基づいたゲージ理論が自然の基本的な力を統一してきた様子を示す図. U(1)に基づいたMaxwellの理論は、電気と磁気を統一した. SU(2)×U(1)に基づいたWeinberg-Salam模型は、弱い力と電磁気力を統一した. SU(5), O(10)あるいはより大きな群に基づくGUT理論は、強い力と電弱の力を統一する最良の候補である. 超弦理論は、重力と他の粒子の力を統一するゲージ理論の唯一の候補である』
|
|
| (p11 より 『超弦理論』(『超弦理論とM理論』) ミチオ カク著 太田信義訳 シュプリンガーフェアラーク東京 ※下線は筆者による) |
『超弦理論は、物質の基本的な構成物が点粒子であるであるという仮定だけを捨てるのであるから、今までの物理原理をもっとも損なうことがなく、ゲージ群を複雑で洗練されたものにするという伝統を踏襲するものである. そして、超弦理論は、量子力学のどの法則も破ることはなく、Feynman図の発散を全部ではないとしても、ほとんど除いてくれる. 超弦模型の対称性の群は、物理の歴史で最大のものであり、おそらく、理論を全次数で有限にするほど大きいであろう. もう一度いうと、理論を有限にする根本的な鍵は、量子力学の破れではなく、対称性なのである』
|
| (『超弦理論』(p14 )(『超弦理論とM理論』(p.13-14)) ミチオ カク著 太田信義訳 シュプリンガーフェアラーク東京 ※下線は筆者による) |
『量子力学と相対性理論を結びつけようとすると、多くの落とし穴──アノマリー、発散、タキオン(光より速い粒子)、幽霊(ゴースト、不の確率を持つ粒子)、その他さまざまな病変を集めた本物の地雷源──が出てくるので、それらを抹殺するには膨大な量の対称性が必要なのである。
単純に言うと、超弦モデルが「うまくいく」のは、今までの物理モデルの中で最大の対称性を持っているからである。点ではなく弦に基づいた理論を書き上げると自然に生じるこの対称性の大きな集合は、そのアノマリーや発散を充分に打ち消すことができる』
(『アインシュタインを超える』 p.276-277 M・カク、J・トレイナー[著] 久志本克己[訳] 広瀬立成〔監修〕 講談社ブルーバックス)
|
『多くの落とし穴──アノマリー、発散、タキオン(光より速い粒子)、幽霊(ゴースト、不の確率を持つ粒子)、その他さまざまな病変を集めた本物の地雷源』を解消するために生み出された対称性の1つが、「超対称性」であったことが読み取れる。
そもそも、「不完全な量子物理学」や「不完全な相対性理論」を結びつけようとしたからこそ、これらの問題が生じてしまったのではないだろうか? もし、「完全な量子物理学」や「完全な相対性理論」を結びつけようするのであれば、これらの問題は生じないのではないだろうか?
詳細な検討は、今後の課題である。 |
“超弦理論”は、「物質の基本的な構成物が点粒子であるであるという仮定だけを捨てる」ものであり、既存の物理学(相対性理論、量子論(量子力学、場の量子論)、大統一理論を含む)を最大限に尊重しながら育まれていること── すなわち、抽象的な数学(抽象的な数式(ハイゼンベルクの不確定性原理(不確定性関係))、抽象的な幾何学(ファインマン図…)、ゲージ原理、対称性…)に基づいて、育まれていることがわかる。
※『“超弦理論”が「不完全な量子物理学」や「不完全な相対性理論」を前提にして育まれてしまった以上、“超弦理論”は、不完全にならざるをえない』と言うこともできると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせんとすることは、“超弦理論”を否定することではない。
“超弦理論”が、どのようなしくみで、うまくいき(成功し)、そして、どのようなしくみで、うまくいっていない(失敗している)のかを、説明することである。
自然(nature)と調和している限り、やはり、科学スタイルは、尊重されるべきである。
超弦理論の科学スタイルと“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の科学スタイルの違いを整理すると次のようになる。
|
|
超弦理論
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
Weinberg-Salam模型
についての解釈
|
「弱い力と電磁気力を統一した」
|
抽象的な数式上の統一、
2つの力を理論上同じ枠組みで説明できる
という意味の統一に過ぎない。
弱い力と電磁気力そのものは、
本来、統一できるものではない。
※電磁力学が「光子のチャッチボール」によって生じているという解釈に基づいている時点で自然(nature)からの乖離が始まっている。
|
|
大統一理論
についての解釈
|
「強い力と電弱の力を統一する最良の候補」
超弦理論は、大統一理論を包含していると主張
|
自然(nature)から乖離している
「弱い力&電磁気力」と「強い力」そのものは、
本来は、統一できるものではない。
|
|
ゲージ理論、群
について
|
「ゲージ群を複雑で洗練されたものにする
という伝統を踏襲する」べきである
「素粒子物理学の自然な発展である、
より大きな、より美しい群を仮定する流れ」
と調和しているべきである
|
“幾何的な実体像”としても
説明されるべきもの
例えば、QCDのグルーオン色荷の
幾何的な実体像を示すことができる
“原始的な力”の“LP色荷”を予測
|
|
E=mc2の数式
についての解釈
|
「質量が0になるためには、
エネルギーが0でなければならない」
|
質量は、
エネルギーの一種に過ぎない
(例えば、光子や重力子、電荷は、
エネルギーを持つが、質量は持たない
質量とは「重力子の放出源として
働き続ける能力」に他ならない(→結果1))
|
|
高次元空間
|
「光子の質量が0になるためには、
エネルギーが0でなければならない」
という理由から必要
|
「光子はエネルギーを持っていても、
質量は0である」
ので、高次元空間は、不要
|
|
超対称性
|
「理論を有限にする」ために必要
「ゲージ群を複雑で洗練されたものにする
という伝統を踏襲する」
「超弦模型の対称性の群は、
物理の歴史で最大のもの」
「素粒子物理学の自然な発展である、
より大きな、より美しい群を仮定する流れ」
と調和している
|
自然(nature)から乖離している
(実在しない)
抽象的な数式から導かれた、
(自然(nature)から乖離した)前提の上に
考え出されたもの
|
|
量子力学
|
どの法則も破っていない。
「量子ゆらぎ、不確定性原理…」を
そのまま尊重
|
不完全である
「量子ゆらぎ、不確定性原理…」を
「より深いレベルの階層」から説明し直す
|
|
局所性
|
保たれるべきである
|
保たれていない。非局所性が成り立つ。
(共転回原理、量子もつれ
(エンタングルメント)…が成立している)
弦は、本質的に共転回の所産
(弦も素スピノールの総和として創発する)
|
|
相対性理論
|
完全である
|
不完全である
「時空の曲り、光速不変、エーテル…」を
「より深いレベルの階層」から説明し直す
|
|
時空
|
連続である
「不連続のアプローチは決して否定できないが
素粒子物理学の自然な発展である、
より大きな、より美しい群を仮定する流れ
逆行するように思われる」
|
不連続である
時空は、本来は、微分不可能
(「より大きな、より美しい群」は、
自然(nature)から乖離している)
|
※参考 『超弦理論』(『超弦理論とM理論』)
ミチオ カク著 太田信義訳 シュプリンガーフェアラーク東京 ※下線は筆者による。)
こういった比較によって──
“超弦理論”が、どのようなしくみで、うまくいっていないのか(失敗しているのか)の構図が、浮かびあがってくる。
一言で言えば、「抽象的な数学(抽象的な数式、ゲージ原理、対称性、群論…)」に裏切られているのである。
“超弦理論”は、量子力学、一般相対性理論、素粒子物理学の標準模型(量子電磁力学、ワインバーグサラム理論(電弱統一理論)…)を支える抽象的な数学の伝統を、痛々しいほど尊重している。
しかし、伝統を尊重すればするほど、抽象的な数学(抽象的な数式、ゲージ原理、対称性、群論…)に裏切られて、自然(nature)と乖離してしまっている結果となっているのである。
“超弦理論”は、抽象的な数学(抽象的な数式、ゲージ原理、対称性、群論…)による裏切りの所産である── という構図が浮かび上がるのである。
例えば、アインシュタインのE=mc2という抽象的な数式に裏切られている。
この抽象的な数式から、「質量が0になるためには、エネルギーが0でなければならない」という、自然(nature)と乖離した解釈を導いた。
そして、この「質量が0になるためには、エネルギーが0でなければならない」という自然(nature)から乖離した解釈が前提となり、物理学史上最も大胆なアイデアの1つと言える「26次元時空」が生まれた。
ところが、実際は、「たとえエネルギーを持っていても、質量が0である」ということもありうるのだ。(光子、重力子、電荷…)
したがって、「質量が0になるためには、エネルギーが0なければならない」という理由による、高次元空間の必要性は、全くなくなってしまうのだ。
例えば、量子電磁力学という抽象的な数学(抽象的な数式、ゲージ原理、対称性、群論…)によって育まれた理論にも裏切られている。
量子電磁力学自体は、計算結果が観測結果と一致するという点で、見事に成功している。
しかし、量子電磁力学を支える抽象的な数学は、「電磁気力は、光子のキャッチボールによって生じている」という自然(nature)から乖離した解釈を生んだ。 (→結果6)
そして、この「電磁気力は、光子のキャッチボールによって生じている」という「自然(nature)から乖離した解釈」が前提となり、ワインバーグサラム理論(電弱統一理論)が生まれた。
ワインバーグ-サラム理論(電弱統一理論)自体は、計算結果が観測結果と一致するという点では、見事に成功した。
しかし、こういった「電磁気力は、光子のキャッチボールによって生じている」という前提、および、ワインバーグサラム理論(電弱統一理論)を支える抽象的な数学は、「弱い力と電磁気力が統合された」という「自然(nature)から乖離した解釈」を生む結果となった。
そして、「弱い力と電磁気力が統合された」という「自然(nature)から乖離した解釈」が前提となり── 大統一理論が、育まれた。
大統一理論自体は、計算結果が観測結果と一致しない(予想された陽子崩壊が観測されなかった)という点で、失敗しているのに関わらず、「電弱理論と強い相互作用が統合された」という新たな「自然(nature)から乖離した解釈」を生んだ。
そして、「電弱理論と強い相互作用が統合された」という「自然(nature)から乖離した解釈」が前提となり── 超大統一理論、すなわち、超弦理論が育まれた。
つまりは、抽象的な数学(抽象的な数式、ゲージ原理、対称性、群論…)によって裏切られた結果──
「ワインバーグ-サラム理論(電弱統一理論)→大統一→超大統一」という流れこそが正しいはずだという、「自然(nature)から乖離したビジョン」が生まれてしまったのである。
しかし、そもそも、 量子電磁力学から導かれる「電磁気力は、光子のキャッチボールによって生じている」という解釈(&前提)や、ワインバーグ-サラム理論(電弱統一理論)から導かれる「弱い力と電磁気力そのものが統合された」という解釈の時点で、自然(nature)からの乖離が始まっているのである。
そして、 その「弱い力と電磁気力そのものが統合された」という「自然(nature)から乖離した解釈」を前提として生まれた、大統一理論(「電弱理論と強い相互作用を統合する理論」)が自然(nature)から乖離しているからこそ、予測された陽子崩壊が観測されていないのである。
さらには、この自然(nature)から乖離した「大統一」を前提として育まれている“超大統一(by超対称性)”の理論(「大統一力と重力を統合する理論」)が自然(nature)から乖離しているからこそ、予測された超対称性粒子も、一切観測されていないのである。
“大統一”や“超大統一(by超対称性)”は、ともに、やはり、自然(nature)から乖離した理論なのである。
ともに、自然(nature)から乖離した前提の元に育まれたものなので、当然といえば当然のことである。
抽象的な数学(抽象的な数式、ゲージ原理、対称性、群論…)だけを見て、その美しさにとらわれ続けている限り── 量子電磁力学やワインバーグ-サラム理論の“解釈”の時点で、自然(nature)からの乖離が始まっていること、そして、大統一、超大統一(by超対称性)と発展するにつれて、自然(nature)からの乖離がますます大きくなっていることに気づくことができない。
ここにある自然(nature)からの乖離に気づくためには── 抽象的な数学(抽象的な数式…)を正しく“解釈”すること、すなわち、ミクロの世界の自然(nature)の真の姿、すなわち、“true picture at Planck scale”を正しく思い描こうすることが必要不可欠である。
なぜなら、抽象的な数学(抽象的な数式…)の“解釈”が、新たな前提となるからである。
すなわち、もし抽象的な数学の“解釈”が、自然(nature)から乖離すればするほど、その解釈を前提とする、後に続く理論が、自然(nature)から乖離してしまうからである。
こういった「抽象的な数学」の重視(≒「抽象的な数式の解釈」の軽視)による自然(nature)からの乖離は── 必死に“物理学の伝統”を守ろうとした結果であった。
すなわち、不完全な量子物理学や不完全な相対性理論をそのまま尊重し続けるという“物理学の伝統”の結果── 「抽象的な数式の解釈」の軽視する伝統は、ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)の探求が軽視され、自然(nature)からの乖離が進んだのである。
※なお、「湯川秀樹の中間子理論」は、確かに、「電磁気力は、光子のキャッチボールによって生じている」という描像からの類推のおかげで生まれた。 それが成功したのは、陽子や中性子を結びつける核力が、本当に「中間子のキャッチボールによって生じている」ものだったからである。 この成功は、自然(nature)から乖離していた「抽象的な数学の“解釈”」を前提としていたのにかかわらず、そこから類推して導いた新たな理論が、奇跡的に自然(nature)と調和していたという、きわめて特殊な例であると言える。
厳密には、“大統一”や“超大統一(by超対称性)”にも、同様の奇跡が生じている可能性が残れされていると言えるかもしれない。
しかし、3つの理由で却下される。
1.中間子の方は、「自然(nature)から乖離した前提」を、単に“類推して”導かれたのに対して、“大統一”や“超大統一(by超対称性)”の方は、「自然(nature)から乖離した前提」をベース(土台)にして導かれた。
2.中間子が観測されたのに対し、陽子崩壊も、超対称性粒子も観測されていない。
3.中間子の理論は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和しているのに対し、“大統一”や“超大統一(by超対称性)”そのものが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していない。(→“超対称性”については、下記で、さらに詳しく説明する)
以上の説明は、「観測数値と計算結果が一致しても十分ではない」ことを、はっきり示している。
すなわち、以上の説明は、ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)の探求する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していること(つまりは、3Steps原理と調和していること)も必要であることを、示しているのである。
そして、以上の説明は、“高次元空間”や“超対称性”は、ともに、抽象的な数学に裏切られ続けた結果(すなわち、不完全な量子物理学の伝統を必至に守ろうとし続けた結果)生まれた「自然(nature)から乖離した考え」である可能性が高いことを示唆している。
確かに、自然(nature)と調和している限り、科学スタイルは、尊重されるべきである。
しかし、自然(nature)から乖離している部分については、却下しなければならない。
したがって、自然(nature)から乖離していると判断できる“超対称性”や“高次元空間”については、却下される可能性が高いことがわかる。(詳細は下記で説明する)
よって、以後、原則として、“超弦理論”という言葉は使わず、弦理論(string theory)と表記して話を進めることとする。
そもそも、この弦理論(string theory)とは、いったい何なのだろうか?
弦(string )やブレーン(brane)とは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、どのように説明できるであろうか?
そのことを以下に示す。
南部陽一郎の“ハドロンのひも理論”の中のひも(string、弦)の両端には、結果的に“クォーク”が存在していたのだった。
そして、その“ひも”の実体は、“グルーオンの集積したひも”に他ならないのだった。
よって、その対応関係から類推し、次の仮説を立てた。
仮説D3.1 弦理論(string theory)の弦(string)の両端、および、弦(string)の振動の山や谷の場所には、クォークのみならず、プレオン∴ や、素スピノールが存在する。
仮説D3.2 弦理論(string theory)の弦(string)の実体に相当するものには、少なくとも次の3種類(1次〜3次)がある。
1次弦(primary string) “量子もつれ(=エンタングルメント)”
2次弦(secondary string) “LP光子の集積したひも”
3次弦(tertiary string) “グルーオンの集積したひも”
すなわち、弦理論の中の弦(string)は、大きく3種類あることになる。 整理すると次のようになる。
|
理論
|
弦理論(string theory)
|
|
弦(string)の種類
|
1次弦(primary string)
|
2次弦(secondary string)
|
3次弦(tertiary string)
|
|
弦(string)の実体
|
“量子もつれ
(=エンタングルメント)”
|
“LP光子の集積したひも”
|
“グルーオンの集積したひも”
|
|
両端にあるもの
|
素スピノール・
|
プレオン∴
|
クォーク(∴×3)
|
|
所産
|
光子、重力子
プレオン∴
LP光子
スピンネットワーク
各種の“量子もつれ”の現象
|
クォーク
電子、ニュートリノ
グルーオン
|
陽子、中性子
中間子
|
|
幾何的な実体像
|
|
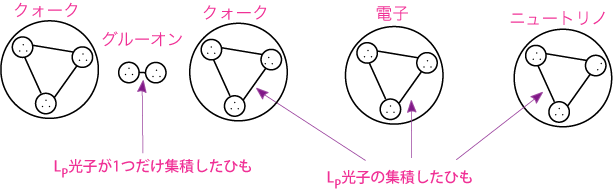 |
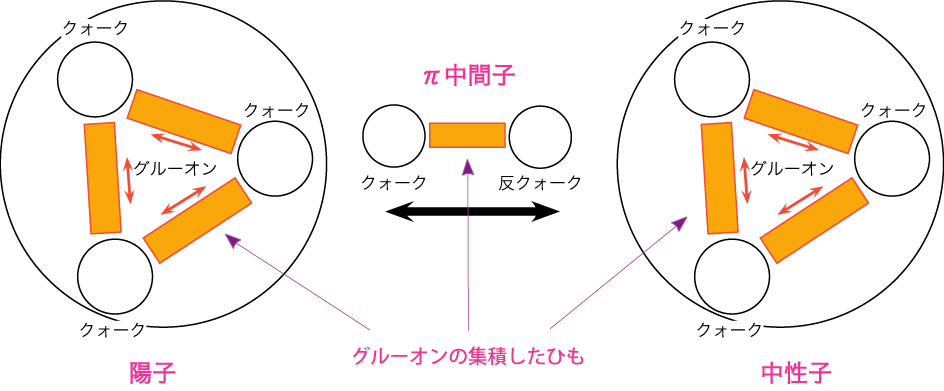 |
※図のサイズは、正確なものでない。
ここにある3種類の弦(string)は、“弦のフラクタル”と言える関係を持っていることがわかる。
(なお、弦のフラクタルは、弦理論(string theory)の1つの特徴である“共形性”とも関連しているかもしれない。(詳細な検討は、今後の課題である))
※素スピノールから創発しているこれら3種類が、それぞれ“弦と見なすことができる”ということは、そこにあるのは、(粗視化による)“弦近似”であると言うことになる。
弦理論(string theory)では、「クォーク&レプトン…」と「光子&重力子…」を、ともに、同一の弦の状態の違いによって説明しようとしているのに対して、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、3種類を区別して、より具体的に説明しようとしている。
※なお、個々のグルーオンは、質量を持たないので、(原始ヒッグス場ユニットを介さずに)プレオン∴をダイレクトに結びつける“LP光子”の所産であることになる。 よって、グルーオンは、“LP光子の集積したひも”の所産の項目に挙げられているが── 厳密には、“LP光子が1つだけ集積したひも”と言うこととになる。
|
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── 弦理論(string theory)の中の弦(string)は、結局はすべて、素スピノールから創発するものなのである。
そして、それらの3種類の弦(string)は、フラクタルをなしている。
※例えば、1次弦(primary string)である、“量子もつれ(エンタングルメント)”を実体とする弦(string)については、具体的には、おおよそ次のような対応関係になっていると考えられる。
|
|
弦理論(string theory)
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
1次弦(primary string)
(光子、重力子、プレオン∴を構成)
|
光子
|
|
|
|
重力子
|
|
|
|
プレオン∴
|
|
|
※便宜上、弦理論で表記されていない“小さな○”も、ともに図示してある。
光子に対応する弦は、素スピノール2つの間の“開いたリンク”に相当し、重力子に対応する弦は、スピノール4つを含む“閉じたリンク”(ループ)に相当し、プレオン∴に対応する弦は、スピノール3つを含む“閉じたリンク”(ループ)に相当していることが読みとれる。
※弦理論(string theory)の弦(string)は、振動すると言われている。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、「1次弦(primary string)の振動」の実体は、素スピノールの“共転回”ということになる。
この素スピノールの“共転回”には、「パウリの排他律、原始ヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギー…」などのはっきりした原因があるのだった。
したがって、“弦(string)が振動する原因”は、“素スピノールの共転回の原因”と同じと見なせるので、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「そもそも、なぜ、どのようなしくみによって、弦(string)が振動するのか?」という基礎的な問題を考えるヒントを与えうることになる。 |
例えば、2次弦(secondary string)である、クォークや電子を構成する弦(string)(「LP光子の集積したひも」)の場合は、次のようになる。
|
弦理論
(string theory)
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
2次弦(secondary string)
(クォーク、電子、ニュートリノ
グルーオを構成)
|
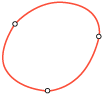
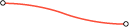
※この図の○は、プレオン∴に相当する
|
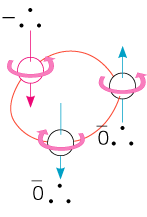 |
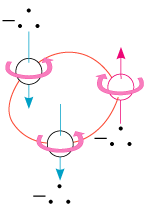 |
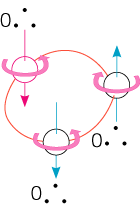 |
|
|
(右巻き)
ダウンクォークd
|
(左巻き)
電子
|
(左巻き)
ニュートリノ
|
グルーオン
|
|
※(右巻き)アップクォークuや、反電子ニュートリノも、同様に示すことができる。
※当然、クォーク、電子、ニュートリノの3種は、実際はサイズが異なる。
なお、そのサイズの違いが質量の差を生む1つの要因であると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※たるんだ“ひも”ではなく、「ピンと張った弦(string)」であることを強調すれば、次のように図示できる。
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
第2世代の弦(string)
(クォーク、電子、ニュートリノを構成)
|
|
|
「LP光子の集積したひも」が“ピンと張っている”様子が図示されている。
|
なお、“ピンと張っている”という描像は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のみならず、次の記述がヒントとなるのだった。
|
『オリジナルなひも理論は、中間子がひも状だと仮定すると高エネルギー実験のデータが説明できることから考案された。「ひも」と言う呼称はそのころから使われているが、ひもの状態を調べたところ、強い張力が作用して常にピンと張っていなければならないことが判明したため、現在では、「弦」と呼ばれる方が多い。
中間子がひもだという見方は、やがて場の量子論に基づく複合粒子のアイデアに取って代わられるが、ひも理論の研究者は、長年扱ってきた理論を見捨てるに忍びず、今度は、電子やクォークなどの素粒子がひもという見方を提案した。』
(『素粒子論はなぜわかりにくいのか』(吉田信夫 技術評論社、p.171) 下線は、筆者による) |
|
|
3次弦(tertiary string)である、陽子&中性子や中間子を構成する「グルーオンの集積したひも」は、下図のようになる。
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
3次弦(tertiary string)
(ハドロン
(バリオン(陽子・中性子)や
メソン(中間子))を構成)
|
|
※「グルーオンの集積したひも」がピンと張っていることが図示されている。
※弦理論(string theory)の表示は省いた。 |
一方、ブレーン(brane)は、どのように説明できるであろうか?
このブレーン(brane)について、次の仮説を立てた。
仮説D3.3.1 弦理論(string theory)のブレーン(brane)の実体に相当するものには、少なくとも次の3種類(1次〜3次)がある。
1次ブレーン(primary brane)=1次ヒッグス場ユニット(primary Higgs field unit)の総和=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和
2次ブレーン(secondary brane)=2次ヒッグス場ユニット(secondary Higgs field unit)の総和=プレオン∴ヒッグス場ユニット(∴HU)の総和”
3次ブレーン(tertiary brane)=3次ヒッグス場ユニット(tertiary Higgs field unit)の総和=
(電子ヒッグス場ユニット(eHU)、クォークヒッグス場ユニット(uHU、dHU)、ニュートリノヒッグス場ユニット(νeHU)の各総和)
※例えば、光子は、原始ヒッグス場に足を固定させ続けているといえるので、この原始ヒッグス場は、『Dプレーン』の一種ということである。
また、3次元であるので、D3ブレーンということになる。
その内容を図示すると、次のようになる。
|
ブレーン(brane)の実体
|
|
1次ブレーン
(primary brane)
|
2次ブレーン
(secondary brane)
|
3次ブレーン(tertiary brane)
|
|
1次ヒッグス場ユニット
の総和
|
2次ヒッグス場ユニット
の総和
|
3次ヒッグス場ユニットの総和
|
|
原始ヒッグス場ユニット
(PHU)の総和
|
プレオン∴ヒッグス場ユニット
(∴HU)の総和
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU)の総和
|
クォークヒッグス場ユニット
(uHU、dHU)の総和
|
電子ニュートリノヒッグス場ユニット
(νeHU)の総和
|
|
|
|
 |
|
|
※これらの3種類(1次〜3次)のブレーン(brane)においても、フラクタルな関係が認められることがわかる。
※いずれも、3次元空間に存在するものなので、D3ブレーン(D3 brane)の一種ということでよいのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
なお、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、(光子のエネルギー&質量を理由に)高次元空間を考える必要がないので、“D3ブレーン”だけであることになる。
※弦理論(string theory)では、5種類のヒッグス場を予想するものがあるとのことである。
「原始ヒッグス場、プレオン∴ヒッグス場、電子ヒッグス場、クォークヒッグス場、ニュートリノヒッグス場」の5種類と関連があるだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
※弦理論(string theory)における、ブレーン(brane)という言葉自体は、3種類(1次〜3次)を区別せず、(ブレーン(brane)という)1つのカテゴリーでくくっている。 したがって、弦理論(string theory)は、「原始ヒッグス場、プレオン∴ヒッグス場、クォークヒッグス場」という言葉を使って、3つの世代を区別する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)よりも、抽象的であると言える。
※弦(string)は、ブレーン(brane)を離れられない。
各ヒッグス場(各ブレーン(brane))が離れられなくする弦(string)は決まっている。 |
|
原始ヒッグス場
(1次ブレーン(primary brane))
|
プレオン∴ヒッグス場
2次ブレーン(secondary brane)
|
電子ヒッグス場
3次ブレーン(tertiary brane)
|
クォークヒッグス場
3次ブレーン(tertiary brane)
|
ニュートリノヒッグス場
3次ブレーン(tertiary brane)
|
|
光子、重力子
(1次弦(primary string))
|
プレオン∴
(1次弦(primary string))
グルーオン
(2次弦(secondary string))
|
電子
(2次弦(secondary string))
|
クォーク
(2次弦(secondary string))
中間子、陽子、中性子
(3次弦(tertiary string))
|
ニュートリノ
(2次弦(secondary string))
|
|
弦理論(string theory)と、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の対応関係を整理すると次のようになる。
|
弦理論
(string theory)
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
弦
(string)
|
1次弦(primary string)──素スピノールの量子もつれ(エンタングルメント)
2次弦(secondary string)──「LP光子の集積したひも」
3次弦(tertiary string)──「グルーオンの集積したひも」
|
|
ブレーン
(brane)
|
1次ブレーン(primary brane)──原始ヒッグス場
2次ブレーン(secondary brane)──プレオン∴ヒッグス場
3次ブレーン(tertiary brane)──電子ヒッグス場、クォークヒッグス場、ニュートリノヒッグス場
|
|
弦(string)が振動すること
|
1次弦(primary string)──素スピノールのペアが共転回すること
2次弦(secondary string)──不明(“ピンと張っている”ので、振動しない?)
3次弦(tertiary string)──不明(“ピンと張っている”ので、振動しない?)
|
|
弦の長さが変化すること
|
素スピノールの間の距離が変化すること
「LP光子の集積したひも」の長さが変化すること
「グルーオンの集積したひも」の長さが変化すること
|
|
閉じた弦(string)
(弦がループを作ること)
|
素スピノールがループを構成→重力子、プレオン∴、
プレオン∴がループを構成→電子、クォーク、ニュートリノ
クォークがループを構成→陽子、中性子
|
|
開いた弦(string)
|
素スピノールが開いた弦(string)を構成→光子
プレオン∴が開いた弦(string)を構成→グルーオン
クォークが開いた弦(string)を構成→中間子
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、弦(string)についての、多くの現象を、素スピノールやプレオン∴(そして、クォーク)から創発したものとして、説明しなおすことが可能になることがわかる。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、あらゆる弦(string)は、「量子もつれ状態にある複数の素スピノール」や、「プレオン∴&LP光子」、「クォーク&グルーオン」の挙動の総和という、「より深いレベルの階層」から創発してきているという見方をしているものであることがわかる。
そのことは、逆に言えば、それらの「より深い階層レベル」を、ひとまりとして近似的に(おおざっぱに、ズームアウト(粗視化)して)とらえ、「弦(string)やブレーン(brane)ととらえている」ものが、弦理論(string theory)であるということに他ならない。
よって、次の結論を得られる。
結論D3.1 弦理論(string theory)は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の近似理論である。
※弦理論(string theory)が近似理論であるということは、弦理論(string theory)が、より抽象的な数学(抽象的な数式…)によって展開されていることを意味する。
そして、より抽象的な数学(抽象的な数式…)によって展開されていることは、自然(nature)から乖離してしまう“裏切り”に気をつけなければならないことを意味する。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、弦理論(string theory)を表記する抽象的な数学(抽象的な数式…)についての、自然(nature)と調和した解釈を提供することによって、その“裏切り”の予防・解消… できるという存在意義があると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
弦理論と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)には、確かに、似ているところがある。
例えば、解決しようとする問題、説明しようとしている対象は、おおよそ同一である。
ともに、「素粒子に“広がり”がある」と考えている。
ともに、一般相対性理論と量子論(量子力学、場の量子論)との統合を説明しようとしている。
ともに、標準モデル(3つの力)のみならず、重力子や重力を説明しようとしている。
ともに、「時空に最小の単位がある」と考えている。
… |
しかし、やはり、違いもある。
弦理論(string theory)のアプローチは、本来、「弦(string)やブレーン(brane)にフォーカスし── 抽象的な、たった1種類の弦(string)の“振動のしかた”の違いによって、そして、抽象的な、高次元まであるブレーン(brane)によって、あらゆる素粒子や場を説明する」という考え方をしている。
一方、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で提案するアプローチは、「“素スピノール”やプレオン∴、クォークにフォーカスし、それらの自己組織化(新たなレベルの3Stepsを生じるような組み合わせ)に伴う“創発”現象として弦(string)やブレーン(brane)(≒ヒッグス場)をとらえ、あらゆる素粒子や場のみならず、時空そのものをも説明する」という考え方をしている。
また、“弦理論”の数学は、とても、抽象的である。
そして、その抽象的な数学(抽象的な幾何、抽象的な数式…)は、非常に難解なものである。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の数学は、とても、具体的である。
そして、その具体的な数学(具体的な幾何、具体的な数式)は、とても、シンプルである。
両者の比較を整理すると次のようになる。
|
“弦理論”
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
見方
|
ズームアウト(粗視化)
|
ズームイン
|
|
(フォーカスする)
対象
|
一種類の弦(string)
高次元まであるブレーン(brane)
|
(1次〜3次)弦(string)を構成する
素スピノールの量子もつれ(エンタングルメント)
「LP光子の集積したひも」
「グルーオンの集積したひも」
(1次〜3次)ブレーン(brane)を構成する
(1次〜3次)ヒッグス場ユニット
|
|
数学
|
抽象的
難解
|
具体的
シンプル
|
|
弦(string)&ブレーン(brane)
(素粒子、ヒッグス場、時空)
|
元からあるもの
|
創発してきたもの
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、弦理論(string theory)を包含するものである。
それが可能なのは、「より深いレベルの階層」から、自然(nature)をとらえているからである。
この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)には、“弦理論”にまさる、大きなメリットが少なくとも、5つある。
1.背景独立性(背景非依存性)が、はっきり得られる。
2.“問題解決能力”が高まる。
3.数式が具体的で、簡単である。
4.高次元空間(余剰次元)、超対称性が不要になる。
5.弦理論(string theory)と、ループ量子重力理論を統合する。(→考察4) |
1.背景独立性(背景非依存性)がはっきり得られる。
背景独立性(背景非依存性)とは、アインシュタインの一般相対性理論と調和する考え方であり、時空が固定された背景ではないという原理である。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、時空が固定された背景ではなく、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニットの総和)における「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として、創発してくるものであることを示している。 一方の“弦理論”は、時空が固定された背景であるという前提を持っており、それは、アインシュタインの相対性理論との調和性が低いことを意味する。
おな、この点に関する超弦理論の現状は、次の記述から読み取れる。
『超弦理論には重力が含まれる. そして重力は時空の理論である. 特殊な平坦な時空の周りでしか理論が定式化されていないということは、重力の理論としては満足できるものではない. 超弦理論は重力を含む整合的な理論であると言ってきたが、これは平坦な時空でのグラビトンの自由度を含むという意味であり、超弦理論での重力の記述が、一般相対論のような幾何的な形で書かれているわけではない. 一般相対論の場合、どのような背景時空をとるかに理論が依存しない. 背景場を考えるということは、時空をあらわすメトリック場を個々の背景場での周りで展開すればよいだけである. これを重力理論の背景非依存性という. これに対して現在の超弦理論の定式化は、背景場にあらわに依存している理論なのである』
(『アインシュタインと21世紀の物理学』 p.238-239 下線は筆者による)
|
2.“問題解決能力”が高まる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「一般相対性理論(重力)」と、「量子論(量子力学、場の量子論)に基づく素粒子物理学の標準模型(3つの力)」を統合的に説明できるのみならず──
「標準モデルの3つの世代とは何か?」
「どのようにして、アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則が成り立つのか?」
「電荷や色荷とは何か」
「どのようにして、慣性系どうしの中で、光速不変となるか?」
「質量や“時空の曲がり”とは何か?」(質量は、どのようなしくみで時空を曲げるのか?)
「どのようにして重力や電磁気力が生じるか?」
「(質量を与える“抵抗”として働くヒッグス場の中で)慣性(等速直線運動)は、どのようにして実現するか?」
「ニュートンの運動方程式F=maは、どのようなしくみで成立するのか?」
「量子ゆらぎ、不確定性関係… は、どのようにして生じるか?」
「コペンハーゲン解釈は、なぜ、うまくいくのか?」
…
などといった、これまで、ほとんど手も足もでなかったような(ときに前提とするしかなかったような)、基礎的な問題についても説明できる。
3. 数式が具体的で、シンプルである。
“弦理論”の数学が抽象的で難解であることは、『ストリング理論』(by J・ポルチンスキー)や『超弦理論』(『超弦理論とM理論』)(byカク・ミチオ)といった教科書の中の数学(数式…)を拝見するとわかる。
その抽象性と難解さは、確かに、とてつもないレベルである。
また、下記のような記述からも、“超弦理論”の数学の難解さがわかる。
『超ひも理論は、このようなやり方で破錠のない形式に作り上げられたが、その代償として、理論に厳しい制限が付け加えられ、数学的にもきわめて難解なものになった。 論文が執筆できる程度にまで超ひも理論を理解するには、世界トップクラスの頭脳を持つ物理学者か何年も専心しなければならないという状況である』
(『素粒子論はなぜわかりにくいのか』 p.172 下線は筆者による)
|
※なお、例えば、“超弦理論”の数式が10500個もの解を持つことからも、その数学が抽象的であることがわかる。
それに対し、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の数学の具体性やシンプルさは、涙が出そうなほどのものである。
ほとんど高校数学レベルを越えるものはない。
(高校数学レベルを越えいるのは、オイラーが証明した「1+1/22+1/32+… の無限級数は、π2/6に収束する」という内容だけであると思われる)
しかし、実は、これが大きなメリットなのである。
習得が楽だからだけではない。
自然な世界観(3Steps原理)の中の、シンプル一様化原理と調和しているからである。
すなわち、数式が具体的でシンプルであることが── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が、ミクロの自然(nature)と、より深く調和していることを証明しているからである。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の数式が単純なのは、ごまかしているからではない。
すなわち、ミクロの自然(nature)そのものが単純であることを反映しているから、数式が単純なのである。
4.高次元空間、超対称性が不要になる。
上でも、すでに、ある程度説明したが、以下で、やや詳しく説明する。
〈高次元空間〉
弦理論において、そもそも、なぜ高次元空間が必要になると考えられるようになったのかは、『大栗先生の超弦理論入門』(p.100〜)を読むとよくわかる。
『大栗先生の超弦理論入門』(p.100〜)を参考にすると、次のように整理できる。
まず、弦理論の場合の空間の次元Dの導出(計算)のための前提は、次のものである。
1.光子は質量を持たない
2.「量子ゆらぎのエネルギー」はゼロでない
(最低エネルギーは、不確定性原理により、ゼロではない)
3.弦全体のエネルギー((量子ゆらぎで生じる)弦の最低エネルギー + 弦の振動エネルギー)が、質量に相当する。
4.光子の最低エネルギーは、(D−1)×(1+2+3+…)となる。
(「空間の次元数をDとすると、弦のゆれる方向のパターン数は、進行方向を差し引いて(D−1)」となる)
5.「1+2+3+4+5+…=−1/12」 である。 オイラーの公式による。
6.「弦が光子に対応する振動を起こすための、振動エネルギー」は、「最初のモードの量子ゆらぎのエネルギー」の2倍である。
7.光子全体のエネルギー((量子ゆらぎで生じる)光子の最低エネルギー+光子の振動エネルギー)は、質量に相当するので、ゼロになる。
これらの前提より、 2+(D−1)×(1+2+3+4+5+…)=2+(D−1)×(−1/12)=0 の方程式が導かれる。
これを解くとD=25 が求まる。
つまり、弦理論の場合、光子の質量が0になるためには、空間は、25次元でなければならない。
なお、“超弦理論”の場合は、さらに、次の前提が加わる。
8.「超弦理論の弦は、普通の空間でD次元の方向に振動するほかに、超空間でグラスマン数の座標の方向にも振動」するので、光子の最低エネルギーは、弦理論の場合の3倍になり、(D−1)×(1+2+3+…)×3となる。
これらの前提より、 2+(D−1)×(1+2+3+4+5+…)×3=2+(D−1)×(−1/4)=0 の方程式が導かれる。
これを解くとD=9 が求まる。 |
| 参考 『大栗先生の超弦理論入門』(p.100〜 「なぜ九次元なのか」) |
弦理論(string theory)による説明と、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明を比較すると次のようになる。
|
|
弦理論(string theory)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
光子のエネルギー
|
光子全体のエネルギーは、
((量子ゆらぎで生じる)光子の最低エネルギー
+光子の振動エネルギー)である
|
光子は0ではないエネルギー“E=hν”を持ち続ける。
(アインシュタインの光量子仮説の式と合致し続ける)
その大きさエネルギーの総和が一定のまま、
素スピノールの共転回によって原始ヒッグス場の上を
次々に、光速で伝わっていく。
|
|
光子の質量
|
光子全体のエネルギー
((量子ゆらぎで生じる)光子の最低エネルギー
+光子の振動エネルギー)は、
質量に相当するので、ゼロになる
|
光子はエネルギーを持つが、
質量(「重力子の放出源として働き続ける能力」)は、持っていない。
(E=mc2は、本来、すべてのエネルギーが
質量を持つことを意味していないので、
光子の質量が0であるために、光子のエネルギーは0でなくてよい)
|
|
量子ゆらぎ
&不確定性原理
|
「量子ゆらぎのエネルギー」はゼロでない
((光子の)最低エネルギーは、
不確定性原理により、ゼロではない) |
光子の単振動の振幅は、確定している。
光子全体のエネルギーは、“光子の振動エネルギー”のみである。
光子においては、(量子ゆらぎ&不確定性原理によって生じる)最低エネルギーは、実在しない。
※そもそも、不確定性原理(不確定性関係)は、人間観測事情を説明する原理に過ぎず、ミクロの自然(nature)の振る舞い方を決める原因になり得ない。
したがって、「最低エネルギーは、不確定性原理により、ゼロではない」「不確定性原理によって量子ゆらぎが生ずる」と説明すること自体、自然(nature)と乖離している。
光子の単振動(素スピノール共転回)の原因は、「パウリの排他律や原始ヒッグス場ユニットに蓄えられたエネルギー…」というミクロの自然(nature)の中にある。
|
この比較より、弦理論(string theory)において、高次元空間が必要になった理由は、“前提”のいくつかが、自然(nature)と乖離していたからであることがわかる。
その「自然(nature)から乖離した“前提”」の起源は、少なくとも、次の「抽象的な数式から導いた“解釈”」に他ならない。
1.アインシュタインの式 E=mc2
2.ハイゼンベルクの不確定性原理の式 ΔE×Δt≧h
1.「(あらゆる)質量は、エネルギーである」という解釈は、自然(nature)と調和しているが、「(あらゆる)エネルギーは、質量である」という解釈は、自然(nature)と乖離している。 なぜなら、質量(エネルギー)は、エネルギーの一種に過ぎないからである。
すなわち、アインシュタインのE=mc2という抽象的な数式から、「エネルギーは、質量である」という自然(nature)と乖離した解釈を導いたからこそ── 「(光子の弦(string))質量が0になるためには、(光子の弦(string))エネルギーが0なければならない」という前提を持つに至ってしまったのである。
質量とは、あくまで、重力子の放出源として働き続ける能力である。
したがって、質量(エネルギー)は、エネルギーの一種に過ぎないのである。
よって、光子や重力子を含め、「エネルギーを持ち続けても、質量が0である」ということが、ありうるのである。
実際、例えば、(電磁波を構成する)光子は、エネルギー(E=hν)を持っているが、質量を持っていない。
だからこそ、光子は、光速で移動できるのである。
2.ここにあるのは、まさに、「“不確定性原理(不確定性関係)”の、ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」である。(→結果4)
不確定性原理(不確定性関係)は、本来は、人間の観測事情を説明する原理に過ぎず、ミクロの自然(nature)の振る舞い方を決める原因になり得ない。
したがって、そもそも「光子の最低エネルギーは、不確定性原理により、ゼロではない」「不確定性原理によって、光子の量子ゆらぎが生ずる」と解釈し、それを前提とすることは、自然(nature)と乖離している。
また、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、スピン1の光子全体のエネルギーは、「2つの原始ヒッグス場ユニットにまたがって蓄えられる、一定のエネルギーhν」という“光子の振動エネルギー”以外に、考えることができない。
したがって、(不確定性原理によって生じる)光子の最低エネルギーは、実在しない。
つまり、弦理論において、「高次元空間が必要になる」という結論は、「抽象的な数式(E=mc2、ΔE×Δt≧h)の解釈」が自然(nature)と乖離したもので、その「自然(nature)と乖離した解釈」を“前提”にしたからこそ生まれたものなのである。
すなわち、空間次元が、弦理論で25次元(超弦理論で9次元)であるという導出(計算)結果は── アインシュタインのE=mc2の式、ハイゼンベルクの不確定性原理の式ΔE×Δt≧h、という抽象的な数式に、裏切られた結果なのである。
前提が自然(nature)と乖離している以上── たとえ数式計算が100%正しいとしても、そこから導かれる「空間次元が、弦理論によると25次元(超弦理論によると9次元)である」という結論は、自然(nature)と乖離している可能性が高いのである。
つまり、物理学史上最も大胆な考えの1つである「26次元時空」は、「(もともと正しいはずの)抽象的な数式の誤解釈」が“前提”となって生まれた根拠の乏しいものに過ぎないのである。
こういったことは、「抽象的な数式」のみを重視し、数式のみをいじくりまわしているだけでは── 気づくことのできないことである。
すなわち、「幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」を重視してはじめて気づくことができるのである。
なぜなら、「抽象的な数式」自体は、あくまで、正しいものだからである。
しかし、「抽象的な数式の解釈」は、自然(nature)と乖離しうるのである。
なぜなら、「抽象的な数式」の意味は、自然(nature)そのものより、広いからである。
「自然(nature)についての幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」を重視する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── 光子のエネルギーは、質量(重力子の放出源とし働き続ける能力)を持ちようがないこと、そして、光子が、不確定性原理によって(不確定性原理が原因となって)、最低エネルギーを持つこともありえないことが、容易にわかる。
したがって、「(光子の弦(string))質量が0になるためには、(光子の弦(string))エネルギーが0なければならない」や「(光子の)最低エネルギーは、不確定性原理により、ゼロではない」という前提が消失している以上、同時に、それらのことが理由による「25次元の高次元空間の必要性」も消失していることになるのである。
つまり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、弦理論(string theory)においては、(そもそも相当無理のある、直観的にも非常に不自然な)「25次元の空間の必要性」は、本来、どこにもなかったのだと言うことができるのだ。
※こういった説明は、実際に、4次元時空(3次元空間および1次元時間)が観測できるという意味で、自然(nature)と調和しているのみならず── 光子、重力子が、いずれも、エネルギーが0でないと同時に質量が0であるという意味においても、自然(nature)と調和している。
※弦理論が「高次元空間が必要である」という結論に至った理由は、『“弦”への注目度が高かったからである』というよりも── 『抽象的な数式の解釈、すなわち、「自然(nature)についての幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」を軽視した結果、抽象的な数式に裏切られたからである』という方が的確であったことになる。
よって、次の結論を得られる。
結論D3.2 空間が高次元でなければならない理由は、本来、弦理論において、どこにも存在しない。
したがって、「高次元空間」が、実際に観測されていないという問題の解決策として、“高次元空間のコンパクト化”、“ヤラビカウ空間の導入”などの新たな考えが導入されたりしたが、そもそも、その必要性も、全くなかったことになる。
そもそも、「自然(nature)についての幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」を重視し、抽象的な数式の解釈を慎重に行いさえすれば、「高次元空間」が不要であることがわかるのである。
すなわち、 「抽象的な数式」の解釈を慎重に行うだけで、「高次元空間」実際に観測されていないという問題などはじめから存在していなかったことがわかるのである。
そのことは、“弦理論”自体は、本来は、そのままで問題がなかったことを意味する。
すなわち、「“高次元空間”を考えなければ理論が破掟してしまう」という問題が、“弦理論”自体の中に、はじめから存在していなかったことを意味するのである。
“アノマリーの問題”は、単に、「抽象的な数式の解釈」を正しく慎重に行いさえすれば解決する問題だったのだ。
弦理論(string theory)自体は、本来は、(“高次元空間”を考えなくとも)そのままで自然(nature)と調和していたのである。
そして、そもそも弦理論(string theory)自体が自然(nature)と調和している理由は──
弦(string)が、素スピノールから創発している幾何的な実体(素スピノールの量子もつれ、プレオン∴&「LP光子の集積したひも」、クォーク&「グルーオンの集積したひも」)についての、近似的な描像(粗視化した描像)だからである。
※なお、厳密に言えば、「自然(nature)と乖離している前提」から導かれた「高次元空間」が、(湯川秀樹による中間子理論の導出の例のように)たまたま、正しい自然(nature)像である可能性は、0ではない。
しかし、超対称性のときと同様に、3つの理由で却下される。
1.中間子の方は、「自然(nature)から乖離した前提」を、単に“類推して”導かれたのに対して、“高次元空間”の方は、「自然(nature)から乖離した前提」をベース(土台)にして導かれた。
2.中間子が観測されたのに対し、高次元空間は、観測されていない。
3.中間子の理論は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和しているのに対し、“高次元空間”そのものが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していない。
高次元空間が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していないことは、次の理由からわかる。
1.“シンプル一様化原理”に反する。
2.スピンネットワークの性質に反する。
1.“シンプル一様化原理”に反する。
例えば、「本来、空間が高次元であり、その中に、3次元空間が生まれる」というような説明、「ズームインすると、高次元空間が見えてくる」という説明は── 「複雑なものから単純なものが生まれる(複雑なものの中に単純なものが生まれる)」、「ズームインするほど複雑になる」ということになってしまい、“シンプル一様化原理”に反するので否定できる。
同様に、以下の考えも“シンプル一様化原理”に反するので、不自然である(自然(nature)から乖離している)と判断できる。
・高次元宇宙の中から、低次元宇宙が生まれたという考え
・大きな高次元の中に浮かぶ3D宇宙という考え(“ブレーン・ワールド”の考え)
・“高次元空間”が普遍的に広く実在し、そこから3次元空間が生まれるという考え
・“高次元空間がコンパクト化”しているために見えないという考え
・プランク距離よりも小さなところに、高次元空間が普遍的に存在するという考え
…
2.スピンネットワークの性質に反する。
なお、“空間は、素スピノールのネットワーク(スピンネットワーク)から生まれる”というこれまでの話、
ペンローズ氏による“スピンネットワークは、3次元空間の角度を生む”という考え、
そして、“(4次元以上の)高次元空間では、すべての“結び目”がほどけてしまう”というトポロジー的な事情からも、「本来、空間が高次元であり、その中に、3次元空間が生まれる」や「ズームインすると、高次元空間が見えてくる」という考えは、否定できる。
よって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデルは、次の予測をする。
予測D3.1 3D空間の周辺にも、中にも(ミクロレベルでもマクロレベルでも)、高次元空間が実在することはない。
なお、この「高次元空間」を否定する予測は、“すべての高次元(余剰次元)”を否定するものではない。
なぜなら、素スピノール(あるいは、原始ヒッグス場ユニット(PHU))がもたらす“新たな自由度”が、“新たな余剰次元”を担うと見なせるからである。
それは、例えば、電子のスピンの自由度が、第4の次元に相当すると見なせることと似ている。
『パウリは、「(個々の電子に四つの自由度を持ち込むことで)ごまかしを想像もされなかった目もくらむような高さに引き上げ、これまでの記録のことごとくを塗り替えてしまった」。 周知のように、電子も宇宙に存在するほかのあらゆるものと同じく三次元の運動をする。 したがって、量子数が三つあれば、完全に十分なはずなのだ』
(p.107 『137』 アーサー・I・ミラー[著] 阪本芳久[訳] 草思社
(太線部は、傍点であった))
|
| ※この記述は、例えば、“電子のスピンの向き”という自由度は、「空間運動の3つの次元」とは異なる、“第4の次元”に相当すると見なせることを意味している。 |
すなわち、例えば、素スピノールの転回の仕方を、“新たな自由度”とみなせば、そこに、新たな次元が存在していると解釈できるということである。
つまり、このような“新たな自由度”が“新たな次元”を担いうるということは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、すべての高次元(余剰次元)は、否定できないことを意味しているのである。
ただし、こういった「“新たな自由度”によってもたらされた“新たな余剰次元”」は、決して“新たな高次元空間”ではない。
これだと、『“新たな空間次元を、わざわざ後からコンパクト化すること”を考えなくてよいのであり── “はじめからコンパクト化している、新たな次元(余剰次元)”を担える、“素スピノールの転回の仕方の自由度”あるいは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の自由度を考えれば十分である』 ということになり便利である。
例えば、カルツァー・クライン理論で、新たに追加された“コンパクトな新たな次元”(5次元目)は、実は、“素スピノール”あるいは、(“原始ヒッグス場ユニット(PHU)”)がもたらす“新たな自由度”が担っていると考えるとつじつまが合うと思われる。 ただし、この考えにおいて、新たに追加された“コンパクトな新たな次元”(5次元目)とは、“新たな高次元空間”とは無縁のものである。
なお、こういった“コンパクトな新たな次元”(5次元目)の説明は、次の記述と調和していると思われる。
『カルツアはすでに五つめの次元は円のように「丸まって」いるから他の四つの次元とはちがうのだと主張していた。宇宙がどう見ても四次元に見える理由を説明するのに、クラインの解答は、この円のサイズがあまりに小さいため直接観測することができないのだ、というものだった。
言い換えると、部屋に放出されたガス分子は確かにあらゆる空間次元を探し出しているのだが、分子は大きすぎるため、円形の第五次元には入っていけないのだ。その結果、ガス分子は五つの次元ではなく、四つの次元にしか充満しないのである。
クラインは第五のサイズがどのくらいになりうるのかも計算している。それはプランク長すなわち10-33センチメートル、言い換えると原子核の100億分のさらに100億分の一の大きさだ。』
(『アインシュタインを超える』 p.226-227 M・カク、J・トレイナー[著] 久志本克己[訳] 広瀬立成〔監修〕 講談社ブルーバックス)
|
| ※クラインによって計算されたサイズも、ほぼぴったりだと思われる。 なお、「プランク長すなわち10-33センチメートル」とは、LP〔m〕≒1.6×10-35〔m〕のことであった。 |
※もしかしたら、あらゆる余剰次元は、得体の知れない“高次元空間”によって説明するのではなく、何かの実体の“自由度”で説明すれば、自然(nature)と調和し続けると言えるのかもしれない。 詳細な検討は、今後の課題である。
※なお、電子のスピンの向きの自由度は、第4の次元であると見なせる一方── 電子のスピンの向きは、結局は、電子の中のプレオン∴の中の素スピノールの向きで説明できるものであった。 電子のスピンの向きの自由度は、この電子の中の“素スピノールの向きの自由度”と本質的に同じものと言ってよいのかもしれない。 (詳細な検討は、今後の課題である)
〈超対称性〉
超対称性は、少なくとも次の3つの理由で却下される。 (“超大統一(by超対称性)”と中間子論との比較は、すでに述べた)
1.超対称性は、「自然(nature)から乖離した前提」をベース(土台)にして導かれた。
2.超対称性粒子が観測されていない。
3.超対称性そのものが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していない。
1.超対称性は、「自然(nature)から乖離した前提」をベース(土台)にして導かれた。
超対称性は、『抽象的な数学』が生んだ「自然(nature)から乖離した前提」を土台にして生まれたものである。
すなわち、「ワインバーグ-サラム理論(電弱統一理論)→大統一→超大統一」という力の統一の流れが正しいはずだという、「自然(nature)から乖離したビジョン」に基づいて生まれたものである。
しかし、そもそも、“4つの力”は、それぞれに異なるしくみで創発している力である(→結果6)ので、“4つの力”そのものを、1つに統一しようとすること自体、自然(nature)から乖離した試みである。
(「“原始的な力”と弱い力」、「強い力と中間子力(核力)」、「電磁気力と重力」は、それぞれ統一できる。
「“原始的な力”&弱い力」と「強い力&中間子力(核力)」は、理論上は、統一できるといえるかもしれない。
しかし、『「“原始的な力”&弱い力」や「強い力&中間子力(核力)」』と『電磁気力&と重力』は、統一できないのだ)
4つの力のすべてを統一できるという「自然(nature)から乖離した前提」をベース(土台)にして、生まれている以上── “超対称性”は、自然(nature)から乖離しているのである。
2.超対称性粒子が観測されていない。
次の記述からもわかるように、“超対称性粒子”は、これまで観測されていない。
『ボソンとフェルミオンを結びつけることで、超対称性は、自然界にあるすべてのボソンに対し、質量や電荷などがまったく同じフェルミオンのパートナーが存在することを要請する。
ところが、われわれの知る世界では明らかにそうなっていない! 通常の素粒子の「超対称性パートナー」と呼ばれるものはいっさい見つかっていないのだ。ボソン型の電子についても、フェルミオン型の光子についても、存在する証拠はない』
(p.195 『超ひも理論を疑う』 ローレンス・M・クラウス 斉藤隆央訳 下線は筆者による)
|
3.超対称性そのものが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と調和していない。
超対称性とは、ボソン(スピンが整数)とフェルミオン(スピンが半整数)の間に、対称性がある(ボソンとフェルミオンを互いに入れ替えることができる)というものである。
この超対称性について、次のような記述もあったのだった。
『ボソンとフェルミオンを結びつけることで、超対称性は、自然界にあるすべてのボソンに対し、質量や電荷などがまったく同じフェルミオンのパートナーが存在することを要請する。』
(p.195 『超ひも理論を疑う』 ローレンス・M・クラウス 斉藤隆央訳 下線は筆者による)
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「自然界にあるすべてのボソンに対し、質量や電荷などがまったく同じフェルミオンのパートナー」というような“超対称性”の存在を、どこにも必要としていない。
いや、それどころか── 「質量や電荷などがまったく同じ」で、スピンだけが異なるパートナーを考えること(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって説明すること)自体、不可能である。(電荷の定義、質量の定義を考えれば、それが無理であることがわかる)
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示す、あらゆる物理概念の“幾何的な実体像”を考えるならば── ボソン(スピンが整数)とフェルミオン(スピンが半整数)が『質量や電荷などがまったく同じ』であるような対称性を持つこと(=“超対称性”が存在すること)は、明らかに、自然(nature)から乖離しているとわかるのである。 ボソン(スピンが整数)とフェルミオン(スピンが半整数)は、創発の仕方も、構造も、性質も、全く異なっているので、当然といえば、当然のことである。
しかし、逆に、抽象的な数学(抽象的な数式…)だけを、いじくりまわし続けている限りは── このことに、全く気づくことができないのである。
※なお、超対称性には、考えられる空間の次元を、25次元から、9次元に減らしてくれるメリットがあると言われてきたが── 上記で示したように、弦理論においては、そもそも高次元空間が不要であし、その実在性も考えにくい以上、そのメリットも消滅している。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると── 弦理論(string theory)において“超対称性”を要する理由(“4つの力(の大きさ)”を統一できるというメリットや次元を減らすというメリット)は消失する。 そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、“超対称性”を説明することは、不可能である。 しかも、実際、“超対称性粒子”は、観測もされていない。
“超対称性”にこだわり続けるべき理由が全くないように思われる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、やはり、次の予測をする。
予測D3.2 超対称性は、実在しない。
やはり、超対称性は、『抽象的な数学』の解釈を軽視した結果、すなわち、「自然(nature)についての幾何学的実体像(視覚的な描像、具体的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」を軽視した結果、生まれてきた、空想上の概念に過ぎないことを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、はっきり示しているのである。
超対称性が存在しないということは、弦理論(string theory)は、やはり、弦理論(string theory)のままであり続けてよいことを意味する。
すなわち、次の結論を導ける。
結論D3.3 弦理論(string theory)は、超弦理論(superstring theory)である必要はなく、弦理論(string theory)であり続けてよい。
5.弦理論(string theory)と、ループ量子重力理論を統合する。
(→考察4)
弦理論(string theory)の弦(string)やブレーン(brane)とは、自然(nature)についての近似的&抽象的な描像である。
すなわち、弦(string)やブレーン(brane)は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が「より深いレベルの階層」から説明している、幾何学的実体像(視覚的な描像、具体的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)の近似である。
したがって、弦理論(string theory)は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって否定されるものではなく── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の近似理論であり、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に包含されるものである。
(それは、ニュートン力学は、アインシュタインの相対性理論にって否定されたものではなく── アインシュタインの相対性理論の近似理論であり、アインシュタインの相対性理論のによって包含されたるということと似ている)
それらを比較すると次のようになる。
|
弦理論(string theory)
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
すべての弦(string)やブレーン(brane)の
“1次〜3次”の違いを区別していないという意味で抽象的
素スピノールから創発した
ミクロの自然(nature)を
弦(string)やブレーン(brane)で近似
|
“弦(string)”や“ブレーン(brane)”の
“1次〜3次”の違いを区別しているという意味で具体的
素スピノールから創発した
ミクロの自然(nature)を
そのまま幾何的な実体像として説明
|
|
ともに自然(nature)と調和している
|
|
ズームアウト(粗視化)
『Out』
|
ズームイン
『In』
|
※弦理論(string theory)における弦が抽象的なものであることは、次の記述からもわかる。
『一七種類の素粒子が「一種類の弦」から現れる
弦理論の大きな利点の一つは、すべての素粒子を一種類の弦で説明できることです。〜。
それまでの素粒子論では、電子、光子などを、それぞれ別の種類の粒子として扱っていました。素粒子の標準模型には一七種類もの基本粒子があります。しかし、それらはみな大きさを持たない点状の粒子なのですから、名札がついているわけでもないのに一七種類に区別されるのは、考えてみると不思議なことです。
ところが弦理論では、すべての素粒子が一種類の弦から現れると考えます。バイオリンの弦がその振動状態によってさまざまな音を奏でるように、素粒子の弦にもさまざまな振動状態があり、それによって電子になったり光子になったりすると考えるからです』
(『大栗先生の超弦理論入門』p.71-72 下線は、筆者による)
『現在の高エネルギー素粒子物理学にも、同じようにたくさんの素粒子がある。光子、重力子、電子、クォーク(クォークは6種類もある!)、グルーオン、ニュートリノなどだ。弦理論は、これらの素粒子の1つひとつを弦の異なる振動モードとして説明することによって統一的な図式を提供することを目指している』
(『きかせて、弦理論』p.115 下線は、筆者による) |
|
※なお、弦理論と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の関係は、「“ハドロンのひも理論”とクォークモデル《標準モデル》」の関係にも似ている。
|
“ハドロンのひも理論”
|
クォークモデル
《素粒子物理学の標準標準》
|
|
単なる“ひも”
|
弦(string)の両端にクォークがある。
弦(string)は、“グルーオンの集積したひも”
(3次の弦(string))
|
|
近似的には、自然(nature)と調和
|
「より深いレベルの階層」からとらえるもので
ミクロの自然(nature)とも調和
|
※ハドロンのひも理論は、クォークモデルの近似であると言える。
“ハドロンのひも理論”は、26次元時空が必要と言われたが── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、高次元空間が不要となるのだった。
よって、本来は、“ハドロンのひも理論”は、クォークモデルによって、否定されたというべきではなく、包含されたというべきである。 |
天動説から、地動説へのシフトは、中心と周辺(すなわち、『In』と『Out』)がひっくり返るほどの、まさに「コペルニクスの転回」と呼べるものである。 (一方だけが、自然(nature)と調和していて、もう一方は、自然(nature)と乖離している)
それに対して、弦理論から、「弦理論」を包含する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)へのシフトは、“「より深いレベルの階層」からの説明”というシフトであり、ズームアウトからズームインへ(『Out』から『In』へ)のシフトに過ぎない。
(ともに、自然(nature)と調和し続けている。 一方が一方の近似であるという関係に過ぎない)
※弦理論は、弦(string)やブレーン(brane)については、1次〜3次を区別していない点で、シンプルである。
しかし、「26次元空間(10次元空間)、カラビ・ヤウ図形、超対称性…」を考慮しなければならなくなる点では、きわめて複雑難解である。
逆に、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、1次〜3次を区別している点では、少し複雑であるが──
「26次元空間(10次元空間)、カラビ・ヤウ図形、超対称性…」を考慮しなくてよい点では、シンプルである。
すなわち、弦理論(string theory)が『弦(string)やブレーン(brane)について1次〜3次を区別しないほどシンプルであるのと引き換えに、 「26次元空間(10次元空間)、カラビ・ヤウ図形、超対称性…」を考慮しなくてはならないほど複雑難解になってしまった』という形で自然(nature)から乖離してしまった原因は、「抽象的な数学(抽象的な数式(E=mc2、ΔE×Δt≧h)、抽象的な幾何、ゲージ理論、群論…)」についての「自然(nature)から乖離した解釈」、すなわち、幾何学的実体像(視覚的な描像、具体的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)の軽視にすぎない。
よって、難解な“超弦理論”から、シンプルな弦理論(string theory)へのシフトは、「抽象的な数学の解釈」の軽視から、「抽象的な数学の解釈」の解釈の重視(=「幾何学的実体像(視覚的な描像、具体的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」の重視)へのシフトであると言えるだろう。
したがって、“弦理論”から、「“弦理論”」を包含する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)への方向転換は、“コペルニクス的転回”とは呼べないが、“コロンブス的な、新たな進路選択”と呼べるものであると思われる。
その本質は、“「より深いレベルの階層」からの説明”へのシフトである。
この“「より深いレベルの階層」からの説明”という“新たな進路選択”は、
「“ハドロンのひも理論”→(そのひも理論を包含する)クォークモデル、標準模型」という“新たな針路選択”が、様々な、発展、成果… をもたらしたように── 様々な、発展、成果… をもたらすと予想される。
この“新たな進路選択”による成果の1つは、“弦理論”が本来目指していた目標(万物の統合)を、より達成しやすくなることである。
すなわち、“新たな進路選択”の先にこそ、“弦理論”が、本来理想としていたはずの、「万物理論を担うほどの“知の探究”(真実の探求)」を、(自然(nature)と調和した形で)存続させていける可能性が大きく広がっているだろう。
また、この“新たな進路選択”により、“弦理論”に、根本的な原理(principle)(=その実体像や本質的な意味)がもたらされ、数学や計算が、より具体的でシンプルになると予想される。
また、この“新たな進路選択”により、“弦理論”が、これまで築いた「貴重なヒント、知の財産…」を、自然(nature)と、より調和的なものにしながら活用し続けていくためにも、役立つと考えられる。
そして、“弦理論”は、本来、シンプルで── 近似的に、自然(nature)と調和しているものであり続けるだろう。
やはり、自然(nature)と調和する限り、様々な科学スタイルは尊重されなければならない。
《M理論ついて》
M理論とは一体何なのか?
M理論とは、“5つの弦理論(string theory)”を統合的に説明できる『方程式の正式な形』の探求を通じて、生まれることが期待された理論である。
『手短に言えば、ひも理論の方程式は複雑すぎて、誰もその正確な形を知らない。物理学者は何とか方程式の近似的な形を述べたに過ぎない。ひも理論の種類によって著しく違うのは、こうした近似的な方程式である。また、五つのひも理論のいずれにおいても、おびただしい数の解、ありあまるほどの宇宙を生み出してしまうのは、こうした近似的な方程式なのだ。
方程式の正確な形はまだ手の届かぬところにあるが、一九九五年(第二次超ひも理論革命の始まり)以来、この正確な形がわかれば、こうした問題が解決するかもしれないという証拠が積み重なってきている。そうなれば、ひも理論が不可避性という特徴を備えるうえでの障害が取り除かれる。実際、方程式の正確な形が理解されれば、五つのひも理論は実は密接に関連していると判明するはずだと、おおかたの物理学者が満足する程度に証明されているのである』
(『エレガントな宇宙』 p.381〜382) |
|
※『五つのひも理論のいずれにおいても、おびただしい数の解、ありあまるほどの宇宙を生み出してしまう』のは、“近似的な方程式”が、まさに、“抽象的な数式”の例だからとも言える。
|
その「5つの弦理論(string theory)」を、統合する試みは、さらに1次元を追加する理論によって、進められた。
『M理論には11個の次元(空間次元が10個、時間次元が1つ)がある。空間次元がもう一つあれば一般相対性理論と電磁気が統合されうることをカルーザが見いだしたように、ひも理論研究者は、こまでの章で論じた九つの空間次元と一つの時間次元に加えて、空間次元がさらにもう一つあれば五つの理論すべてが深く満足の行く形で統合できることを理解している。しかも、この新たな次元は突如どこからともなく現れたわけではない。空間次元が九個、時間次元が一つあるという結論につながった一九七〇年代、八〇年代の推論は近似的なものであった。正確な計算は今なら完成させることができるが、それによれば空間次元が一つ見落とされていたのである。ひも理論研究者はこのことを理解した』
(『エレガントな宇宙』 p.383〜384) |
つまり、5つのひも理論が持つ『方程式の近似的な形』を、プラス1次元することによって統合させることのできる『方程式の正確な形』を持つものがM理論なのである。
すなわち、『M理論が持つだろう“方程式の正確な形”』の各種の極限(近似)が、5つのひも理論が持つ『方程式の近似的な形』になるはずだったのである。
ところが、結局、様々な可能性(不可避性、予測…)を秘めているはずの、『“方程式の正確な形”を持つM理論』が、これまで完成することはなかった。
すなわち、M理論が一体何であるのかについて、結局、分からずじまいになってしまったのである。
『悲しいことに、第二次超弦理論革命は、M理論とはほんとうのところ何なのかについて完全な説明を与えることなく終わってしまった』
(『聞かせて、弦理論』 p.236〜237) |
M理論とは、何だったのだろうか?
いや、M理論とは、何であるべきだったのだろうか?
“M理論の各種の極限(近似)が、各種の弦理論である”という見通しがあった一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の近似が、弦理論(string theory)なのであった。
M理論が、プラス1次元によって、統合的に説明しようとするアプローチであった一方── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が 、弦理論(string theory)を含めた物理学について、“素スピノールの自由度”を追加して統合的に説明するのアプローチなのであった。
M理論と“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)には、重なるところがあるようにも思われた。
よって、M理論とは何か(何であるべきか)について、次の仮説的な定義を立てた。
仮説的な定義D3.1 M理論とは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が説明する「弦(string)やブレーン(brane)に関する、具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」についての、具体的な数学(具体的な数式…)に相当する。
この仮説的な定義によると、M理論は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の一部そのものに相当することになる。
そして、弦(string)やブレーン(brane)に関する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の定式化が、『M理論が持つ“方程式の正確な形”』の完成を意味することになる。
そして、このM理論からは、近似的に(極限として)、「自然(nature)と調和した弦理論(string theory)」だけが、導かれることになる。
したがって、M理論は、『おびただしい数の解、ありあまるほどの宇宙を生み出してしまう』5つの“近似的な数式”の中の多くを淘汰するのである。
すなわち、このM理論は、もはや、『おびただしい数の解、ありあまるほどの宇宙を生み出してしまう』「5つの弦理論(string theory)」を統合的に説明しようとするものではないのである。 (したがって、逆に「5つの弦理論(string theory)」を統合的に説明しようとすることは、自然(nature)から乖離し続けることを意味することになる)
以上の説明は、
『M理論とは一体何なのか──この理論がどんな物理を表現しているのか』
(『エレガントな宇宙』p425) |
に対する回答でもある。
そして、以上の説明は、さらには、次のような記述に対する“答え”でもある。。
『エド(エドワード・ウィッテン)は、われわれに、ひも理論の背後にある核心的な概念──一般相対性理論の核心をなした(重力と加速度との)等価原理に相当するもの──が何もわかっていないが、ひも理論の中心には、時空は表に「現れている」概念であって基本的な概念ではないという概念がある、と重ねて主張した。 つまり、空間の余剰次元がひもの中で何を意味するのかは、明らかではないわけだ。 さらに興味深かったのは、ひもそのものさえ基本的ではなく、これもまたもっと基本的な何かをもとに現れた概念だとわかるのではないか、と彼が言ったことである。』
(p.293-294 『ひも理論を疑う』 (エドワード・ウィッテン)は、筆者による補足) |
『空間の余剰次元がひもの中で何を意味するのか』は、M理論で追加された、新たな1次元については、「素スピノールの自由度」ということになる。
(他の余剰次元については、“不要なもの”であったことは、すでに述べた)
ひも(弦(string)を生み出す『もと』となった『基本的な何か』とは、「素スピノール」に他ならない。
『ひも理論の背後にある核心的な概念──一般相対性理論の核心をなした(重力と加速度との)等価原理に相当するもの』の中心は、“弦(string)が、共転回原理にもとづいて、素スピノールから創発している”という概念だろうと思われる。
そして、さらには、ここには、3Steps原理(特に、“フラクタル相似の原理”“シンプル一様化原理”)も関係していると思われる。
※それらは、
『理論全体がそこから必然的に生み出されるような根本的な考え、「不可避性の原理」』
(『エレガントな宇宙』 p499 より ※下線は筆者による) |
の一部に相当すると思われる。
つまりは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、ひも(=弦(string))とは、「素スピノール」が『もと』になって、フラクタル的に、1次〜3次の弦(string)として、創発したものなのである。
そして、こういった、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)にもとづく、ひも(=弦(string))の具体的な幾何的な実体像を、具体的な数学(数式…)で記述しているものがM理論なのである。
※M理論は、もともとから、弦理論(string theory)ではないのであった。
なぜなら、M理論は、「(10次元を要していた)弦理論」に、さらに“1次元”を追加している理論だからである。
M理論 in“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と、弦理論(string theory)を比較すると次のようになる。
|
弦理論(string theory)
|
M理論
in“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
|
|
ツール、素材
重視するもの
|
抽象的な数学
(抽象的な数式、抽象的な幾何…)
|
具体的な数学
(具体的な幾何、具体的な数式…)
ミクロの自然(nature)の
「 “幾何的な実体像”(視覚的な描像、物理的イメージ、
“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和、フラクタルな相似性…)」
|
|
性質
|
『おびただしい数の解、ありあまるほどの宇宙を生み出してしまう』
|
弦理論(string theory)の
自然(nature)と調和した解釈を導く
『おびただしい数の解、ありあまるほどの宇宙』
を淘汰する。
(5種の弦理論(string theory)も淘汰しうる)
具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何…)
によって表される。
|
|
方向性
|
ズームアウト(粗視化)
『Out』
|
ズームイン
『In』
|
|
自然(nature)
と関係
|
自然(nature)からと乖離しやすい
|
自然(nature)と調和しやすい
|
「自然(nature)が持っている“幾何的な実体像”を重視している“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)」を、仮に、“W理論”と呼ぶこととすると──
(Wには、Mをひっくり返したものという意味のみならず── “world”、“web”、“−^→”(3Steps)、… という意味を持つ)
“M理論”は、“W理論”の一部であったということになる。
そして、目標とされるべきことは、「抽象的な数学(抽象的な幾何、抽象的な数式…)を重視し、『おびただしい数の解、ありあまるほどの宇宙を生み出してしまう』各種の弦理論(string theory)をプラス1次元で統合することを目指していた、かつてのM理論」から、「具体的な数学(具体的な幾何、具体的な数式…)を重視し、プラス1次元(素スピノールの自由度)で、自然(nature)と調和している弦理論(string theory)を探求する、新たなM理論」へと方向転換することである。
そこに生まれるのは、決して、「M理論から“W理論”へのシフト」というものではなく── 「M理論から、M&W理論へという共進化およびシナジー」である。
そういった変化の中で、自然(nature)と調和した形で、『“正確な形の方程式”を持つM理論』が育まれ始めるであろう。
こういった転換が、まさに、ウィッテンの言葉の中の「根本的な転換」に相当すると考えられる。
『M理論とは一体何なのか──この理論がどんな物理を表現しているのか──を理解すれば、過去の科学上の大変動に劣らない根本的な転換が起こる』
(『エレガントな宇宙』 p425) |
すなわち、この『根本的な転換』とは、
「M理論から、“M&W理論への転換”」であり、
やはり、“素スピノールの自由度”の追加という「より深いレベルの階層」からの説明という“新たな進路選択”なのである。
こういった「M&W理論」がより自然(nature)と調和すればするほど、その近似(極限)である「弦理論(string theory)」もより自然(nature)と調和したものになるだろう。
そして、「クォークの間に“グルーオンの集積したひも”がある」という見方が役立ち続けるように── 「素スピノールの間に、共転回(エンタングルメント)という弦がある」、「プレオン∴の間に、“LP光子の集積したひも”がある」という見方も、役立ち続けるだろう。 そして、各種のヒッグス場が、ブレーン(brane)を担うという見方も、役立ち続けるだろう。
つまり、弦理論(string theory)は、自然(nature)と調和している限り、今後とも、役立ち続けるであろう。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)やM理論は、やはり、弦理論(string theory)を否定するものではなく、「弦(string)やブレーン(brane)が、どのようなしくみで、うまくいっている(成功している)のかを説明するのみならず、ときに、どのようなしくみで、うまくいかなくなっているのか(失敗している)のかを説明する」ものである。
一方で、逆に、「偉大な知性によってなしとげられた巨大な“知の財産”」を含む、弦理論(string theory)は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の正当性を、暗黙的に保証してくれるのみならず、ときはに、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の間違いに気づかせてくれることがあるかもしれない。
すなわち、、「“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)やM理論」と、 「弦理論(string theory)」は、それぞれの正当性を保証し合うのみならず、ときに、お互いの進化をうながしうるのである。
つまり、ここにあるのも、シナジーであり、共進化である。
やはり、自然(nature)と調和している限り、多様な科学スタイルは、尊重されるべきである。
すなわち、「自然(nature)は1つ、科学スタイルは多様」という姿勢が、科学にとって、望ましいのだろうと思われる。
確かに、“超弦理論”には、次のような厳しい批判もある。
『失われた世代
聡明な物理学者の中には、二〇年から三〇年を費やして、ひも理論を予測可能な理論にする方法を探し、この理論が理にかなっていて自然界を記述していることを実験的に納得いく形で証明しようとしてきた人がいる。しかし、それほどの年月と才能を費やしておきながら、今ではひも理論は成功しそうにないと考えている。数学に覚えのあるひも理論学者たちは、統一場理論と量子重力を目指す別の道へと、あっさり関心を移していった。
彼ら天才たちは、“失われた世代”の理論物理学者と呼ばれている。過去二〇年間、理論物理学に対する財政支援の大部分はひも理論につぎ込まれてきた。そして、政府交付金や大学の雇用方針によって、物理学はひも理論の発展へと導かれていた。過去何世紀もの科学的取り組みと比べても、無駄になった才能は信じがたいほど大きい。いくつもの大規模なグループがひも理論に全身全霊を捧げたためだ。それに比べて量子力学は、二〇世紀前半の一〇年以上にわたって、アインシュタイン、シュレーディンガー、ボーア、ハイゼンベルク、パウリ、ボルン、ディラック、ジョルダンなど一握りの物理学者の手で発展した。今日では、つねにおそらく一〇〇〇から一五〇〇人の理論物理学者が、ひも理論を研究し、論文を発表している。そして互いの論文を引用することで、文献引用頻度を水増しして、現在ではひも理論学者たちが最も重要な論文を生み出していると見せかけている』
(『重力の再発見』 p.236〜237 ジョン・W・モフゥット 水谷淳訳 早川書房 下線は、筆者による) |
しかし、こういった批判を乗り越えるためには、すなわち、「偉大な知性によってなしとげられた巨大な“知の財産”」が、決して、無駄ではなかったと胸を張っていうためには、幾何的な実体像をも重視し、自然(nature)と調和した弦理論(string theory)として、進化していけばよいことを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示しているのである。
《マルダセナ対応(Ads/CFT対応)およびホログラフィック原理について》
マルダセナ対応(Ads/CTF対応、ゲージ・重力対応、ゲージ・string対応)、およびホログラフィック原理についての自然(nature)との調和性について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、最終的に、どのような判断を下すのだろうか?
マルダセナ対応(Ads/CTF対応)およびホログラフィック原理に関して、次のような記述がある。
『マルダセナの対応は、ホーキングの計算と、ストロミンジャー-バッファの計算の関係を精密に検討することから発見されました。
マルダセナの主張は、九次元空間の超弦理論が、三次元空間の場の量子論と同等であるというものです。「同等である」とは、物理的な現象を説明するために、どちらの理論を使って計算しても、同じ答えが出るということです。これは驚くべきことでしょう。なにしろ前者は重力を含んでいるのに、後者は重力を含んでいません。しかも、次元がまったく違うのです』
(『大栗先生の超弦理論入門』 p.241 下線は筆者による) |
『SBH=kA/4LP2 ここでAは事象の地平面の表面積4πR2 であり、kはボルツマン定数、LP=(Gh/2πc3)1/2は、プランク長である。 この式は、しばしばベッケンシュタイン・ホーキングの公式(Bekenstein-Hawking formula)と呼ばれる。〜 ブラックホールのエントロピーは、事象の地平面の面積Aに比例する。ブラックホールのエントロピーがベッケンシュタイン境界によって得られる最大エントロピーでもある事実とは、ホログラフィック原理を導いた主な要因である』
(『ブラックホールの熱力学』 ウィキペディア。 一部省略、一部表記を変えた。) |
『マルダセナの対応は、ホーキングの計算と、ストロミンジャー-バッファの計算の関係を精密に検討することから発見されました』『ブラックホールのエントロピーがベッケンシュタイン境界によって得られる最大エントロピーでもある事実とは、ホログラフィック原理を導いた主な要因である』ということは──
マルダセナの対応の導出において前提となった、1.「ベッケンスタインとホーキングによるブラックホールのエントロピーの計算」と、2.「ストロミンジャー-バッファによるブラックホールのエントロピーの計算」の自然(nature)との調和性の検討が、重要であることを示していると思われる。
まずは、それぞれを検討してみよう。
1.「ベッケンスタインとホーキングによるブラックホールのエントロピーの計算」
次は、ブラックホールのエントロピーに関する記述である。
『ブラックホールのエントロピーは、「事象の地平面」の面積に比例する。 地平面の面積がプランク面積単位でAの場合、エントロピーはA/4になる(プランク面積は約10-66cm2。 面積の基本的な量子単位で、重力の強さと光速、プランク定数から決まる)。 情報として考えると、エントロピーは事象の地平面に書き込まれており、1ビットのエントロピー(0か1)が4プランク面積に対応する。』
(別冊日経サイエンス149『時空の起源に迫る宇宙論』p.114 『ホログラフィック宇宙』 J.D.ベッケンスタイン) |
『エントロピーは
(エントロピー)=log(同じ巨視的な状態を取る微視的状態の数) (9.6)
として定義される. エントロピーは系の統計的な振る舞いを理解するうえで重要な役割を果たす.
ブラックホールが熱力学的な物体であるならば、エントロピーが定義できるはずである. ブラックホールを熱力学ふうに扱うことで、これは
(ブラックホール・エントロピー)=1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2 (9.7)
で与えられる』
(『アインシュタインと21世紀の物理学』 p.216) |
これらの記述より、ブラックホールの事象の地平面には、“1ピットの情報が、4プランク面積(4Lp2[m2])に相当する何かの実体に詰まっている”と解釈できることが読み取れる。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、ブラックホールの表面では、原始ヒッグス場ユニット(PHU)は、すべて、常に、“4面体”から“4角形”(縮みきったバネ)に切り替わっており、光子が前進するための“足場”が消失してしまっていると考えられる。
原始ヒッグス場ユニット(PHU)が、ホライズン(事象の地平面)に占める面積は、もともと、およそ、4LP2[m2]であると考えられる。
したがって、ホライズン(事象の地平面)の面積4LP2[m2]あたり、1つの“4角形”(縮みきったバネ)が存在することになる。
※事象の地平面にある、すべての原始ヒッグス場ユニット(PHU)が“4角形”(縮みきったバネ)に切り替わっている中で── ブラックホールを中心で縦方向に、2LP[m]の厚さで、輪切りにして示した図である。
便宜上、“4角形”(縮みきったバネ)が生じる向きを交互に90度ずつ変えて図示してあるが、実際は、ランダムに様々な方向に、“4角形”(縮みきったバネ)が生じると考えられる。
いずれにせよ、ホライズン(事象の地平面)の面積4LP2[m2]あたり、1つの“4角形”(縮みきったバネ)が存在することは、変わらない。
|
以上のことは、“原始ヒッグス場ユニット(PHU)由来の“4角形”(縮みきったバネ)(&原始ヒッグス場の“4面体”)と、“4プランク面積に対応する1ビットの情報”は、非常に関連があることを、強く示唆しているように思われた。
よって、次の仮説を立てた。
仮説D3.4 ブラックホールの事象の地平面に存在する、“1ビットの情報(=1ビットのエントロピー(0か1))”を担うものの実体は、「原始ヒッグス場ユニット(PHU)が“4面体”の状態にあるか“4角形”(縮みきったバネ)の状態にあるか」である。
|
原始ヒッグス場ユニット(PHU)が
“4面体”の状態にある
|
←
→ |
原始ヒッグス場ユニット(PHU)が
“4角形”(縮みきったバネ)の状態にある
|
|
|
|
|
0
|
|
1
|
※上図の2つの状態が、1ビット情報(=1ビットのエントロピー(0か1))を担うことになる。
※便宜上、“4角形”(縮みきったバネ)の状態を1と決め、そして、“4面体”の状態を0と決めて、図示してある。 |
※なお、この説明は、次の記述の中の『「レベルX」』が何かを示していることになる
|
『自由度の極限は何だろうか? 原子は電子と原子核でできており、原子核は陽子と中性子の集合体で、陽子や中性子はクォークから成っている。現在の物理学では電子とクォークは励起状態の「超ひも」が最も基本的な実在だと考えられている。しかし、過去1世紀にわたって意外な新事実が次々に明らかになった経緯を考えると、教条的な考え方は禁物だ。宇宙には、現代物理学の想像を超えた階層構造がまだ潜んでいる可能性がある。
一塊の物質にどれだけの情報を詰め込めるかを計算するには、あるいは同じことだが、その物質の本当の熱力学的エントロピーを計算するには、物質を形作る究極の構成要素が何かを知らねば成らない。最も奥深い階層構造を知る必要があるのだ。その階層構造を「レベルX」と呼ぶこととしよう』(別冊日経サイエンス149『時空の起源に迫る宇宙論』p.116 『ホログラフィック宇宙』 J.D.ベッケンスタイン)
|
『「レベルX」が何かはまだ不明』(p117 別冊日経サイエンス149『時空の起源に迫る宇宙論』)ということだが、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、その階層とは、「素スピノール」や「原始ヒッグス場ユニット(PHU)」の階層に他ならないことがただちにわかる。
すなわち、原始ヒッグス場ユニット(PHU)における、“4面体”か“4角形”(縮みきったバネ)かが、“0か1か”という、ブラックホールの表面に存在する自由度に相当することが、ただちに分かるのである。
ベッケンスタインは、数々の仮定を立てながら、抽象的な数式を駆使して、ブラックホールのエントロピーがブラックホールの事象の地平面に比例することを導いた。
そして、ホーキングは、「ブラックホールからの熱放射」の理論からの整合性を保とうとする過程で、比例定数が1/4になることを導いた。
(参考 『ブラックホールの熱力学』(ウィキペイディア) 『Black Holes and Entropy』(Jacob D. Bekenstein)、『Black Hole Entropy and Quantum Gravity』(Parthasarathi Majumdar))
|
『スティーブン・ホーキング(Stephen Hawking)によって証明された定理を根幹として、ヤコブ・ベッケンスタイン(Jacob Bekenstein)は、事象の地平面の面積をプランク面積で割った値にブラックホールのエントロピーは比例するであろうと予想した。ベッケンスタインは、比例定数は(1/2・ln2)/4πとなり、この値に正確に一致しない場合でも、この値に非常に近い値となるであろうと示唆した。翌年、ホーキングはブラックホールが熱的な輻射、ホーキング輻射をしていることを示し、これに対応する特定の温度(ホーキング温度)を持っていることを示した。エネルギーと温度とエントロピーの熱力学の関係を使い、ホーキングは、ベッケンスタインの予想を確かめ、比例定数を1/4と確定することができた。
SBH=kA/4LP2
ここでAは事象の地平面の表面積4πR2 であり、kはボルツマン定数、LP=(Gh/2πc3)1/2は、プランク長である。 この式は、しばしばベッケンシュタイン・ホーキングの公式(Bekenstein-Hawking formula)と呼ばれる』
(『ブラックホールの熱力学』 ウィキペディア 一部表記を変えた。)
|
ベッケンスタインやホーキングにとって、このブラックホールのエントロピーに相当する事象の地平面の面積に比例する量(「1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2」)は、「非常に大きな“乱雑さ”」、「熱」、「熱力学第二法則」(“エントロピーは、増え続ける”という考え)… と結びついたものだった。
それに対して、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2」は、事象の地平面に存在する原始ヒッグス場ユニット(PHU)の個数のみならず、“高度な秩序”を意味するものである。
なぜなら、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、新しいブラックホールの内部〜事象の地平面では、原則として、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”が、すべて“4角形”(縮みきったバネ)に切り替わっているはずだからである。(そのせいで、光子さえも外へ出られないと考えられる)
すなわち、新しいブラックホールの中〜事象の地平面では、“4角形”(縮みきったバネ)か“4面体”かという意味では、“とりうる状態数の数が1”という、最も確率の近い状態になっているのである。(例えて言えば、新しいブラックホールの内部〜事象の地平面では、例えば、「コイン1000枚を投げて、すべてが表になる」というような高い秩序が生じているのである)
つまり、“4面体”か“4角形”(縮みきったバネ)かという意味では── 新しいブラックホールの中は、極めて秩序が高く、エントロピーが限りなく0に近づいていると考えられるのである。
それは、熱力学第二法則に反するので、ありえないのではないか?
決して反していない。
ブラックホールは開放系であり、大量のエントロピーを、大量の重力子として外部へ放出し続けているからである。
それはいわば、「冷凍庫が、熱というエントロピーを、外部へ放出し続けているからこそ、その中に、エントロピーの低い(秩序の高い)氷を生み出せる」のと似た状況である。
ブラックホールの中の物体は、(その強い重力により熱を外部へ放出できないので── その代わりに)重力子というエントロピーを外部に放出するからこそ、その中に、エントロピーの低い(秩序の高い)ブラックホールを生み出せるのである。
ブラックホールの表面積(「事象の地平面」の面積)が意味するものは、“大量の重力子”というエントロピーの放出口の面積、すなわち、エントロピーの放出効率である。
数字もぴったり一致する。
(「事象の地平面」にある原始ヒッグス場ユニット(PHU)の個数は、ブラックホールから放出される重力子の個数そのものである)
以上の説明は、たとえブラックホールの表面積が増え続けていたとしても、そのことによって、ブラックホール自体のエントロピーが増え続けてはいないことをはっきり意味している。
※なお、この説明は、「大量の“物質&そのエントロピー”が、新しいブラッホールを形成する過程を通じて、どうなるか?」の説明において役立つ。 (→詳細は、EMOES宇宙論1)
|
「ベッケンスタイン-ホーキングによる
ブラックホールのエントロピーの計算」
|
“EMOES”
(素スピノールからの創発モデル)
|
|
「1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2」
の導出
|
様々な前提の上で
「抽象的な数式」を駆使して導出
|
幾何から、ただちに導く
|
|
「1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2」
が意味するもの
|
ブラックホールのエントロピー
(エネルギーが最低の)“粒子の数”から導出
とりうる状態数は、2“粒子の数”
すなわち、エントロピーは、“粒子の数”
|
ブラックホールの「事象の地平面」に存在する
“原始ヒッグス場ユニットの数”
“4面体”か“4角形”(縮みきったバネ)か
についてとりうる状態数は、1=20
すなわち、エントロピーは、0
|
|
新しいブラックホールにおける、
エントロピーの増減
|
「事象の地平面」の面積と同様に
たとえ新しいブラックホールでも
エントロピーが
増える一方である
|
そもそもブラックホールは、孤立系ではなく、
大量の重力子を放射し続けるするものである。
新しいブラックホール自身の地平面〜内部での
エントロピーは減る
※ホライズンの面積は重力子の放出能力
(=エントロピーの持ち去り能力)と関係する
|
|
前提
(“抽象的な数式の解釈”を含む)
|
熱力学の第二法則により、
ブラックホールのエントロピーは
なんらかの形で常に増えるべきである。
時空は連続である。
(一般相対性理論がそのまま成立する)
→エネルギー保存則が成り立つべきである
対生成した粒子と反粒子のうち、
“反粒子は負のエネルギーを持つ”
(光子のエネルギーも質量の一種である)
(→「E=mc2についての
自然(nature)から乖離した解釈」に相当)
『不確定性原理によれば“からっぽ”の空間
でさえ仮想光子と仮想粒子の対に満ちている』
(p.204『ホーキング、宇宙を語る』)
(→まさに、「“不確定性原理(不確定性関係)”の
ミクロの自然(nature)の説明手段としての転用」に相当)
|
大量の重力子が、エントロピーを持ち去るので、
熱力学の第二法則は、成立しながら
新しいブラックホールにおいて秩序が生じる
ネーターの定理によると、時空が不連続である場合、
エネルギー保存則、運動量保存則が成り立たない。
→重力子は、エネルギー非保存則の所産である。
ヒッグス場ユニットを構成していた反粒子と粒子は、
ともに正のエネルギーを持つ。
(光子のエネルギーは、質量を持たない)
不確定性原理(不確定性関係)は、人間の観測事情を
示す原理に過ぎず、ミクロの自然(nature)が
どうふるまうかを示す原理ではない。
対生成&対消滅は、ミクロの自然(nature)
における、何らかの原因があって生ずる
|
|
結果
|
ホーキング放射によって、
ブラックホールの質量は減る。
『ブラックホールの質量が減少するに
つれて、事象地平の面積は小さくなるが、
これによるエントロピーの現象は、放出
された放射のエントロピーでお釣りがくるほど
埋め合わされるので、第二法則はけっして
破れていないのである』
(p.144『ホーキング、宇宙を語る』)
|
重力子の放出によって、
ブラックホールの質量は減らない。
(いかなる光子がブラックホールに入っても
ブラックホールの質量は変化しない。
もし、レプトンやクォークの反粒子が
ブラックホールに落ちてきても質量は増える)
“事象の地平面の面積は常に増大するという定理”も、
熱力学の第二法則も保たれて、
数字もぴったり一致する。
|
たとえ、数値は一致しても、そこから導かれるブラックホールのエントロピーに関する結論は、180度異なる。
こういった結論の違いが生じる理由は、結局は、主に“抽象的な数式”に対する解釈の違いにあることがわかる。(→詳細は、EMOES宇宙論1)
|
ハイゼンベルク不確定性原理(不確定性関係)
「ΔX・ΔP≧h/4π ΔE・Δt≧ h/4π」
E=mc2
一般相対性理論
…
|
| ※これらの「抽象的な数式」に裏切られた結果、「1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2」が「ブラックホールのエントロピーである」という解釈が生まれた可能性がある。 |
つまり、 「ベッケンスタインやホーキングによるブラックホールのエントロピーの計算」は、「“抽象的な数式”についての、自然(nature)から乖離した解釈」を前提して導かれたものであるのに関わらず、その「 (エネルギーが最低の)“光子の数”」として計算で求めた数値は、「事象の地平面」にある原始ヒッグス場ユニット(PHU)の個数に奇跡的に等しいものとなったのである。
※べッケンスタインやホーキングが持っていた(前提)と、180度、異なっているにもかかわず、「ブラックホールのエントロピー」と「(事象の地平面にある)原始ヒッグス場ユニット(PHU)の個数」を示す数値が一致するのは、なぜだろうか?
その理由は、おおよそ、次のように説明できると思われる。
ベッケンスタインやホーキングが求めた、『同じ巨視的な状態を取る微視的状態の数』は、「(ブラックホールの中に存在しうる)エネルギーが最低の粒子の数」から、計算で求めたと言うことができる。 (参考 『熱とは何だろう』(竹内薫 講談社ブルーバックス))
このことをヒントにすると、「ベッケンスタインやホーキングが求めたブラックホールのエントロピー」と「(事象の地平面にある)原始ヒッグス場ユニット(PHU)の個数」の数値がおおよそ一致した理由は、次のように考えられる。
質量M[kg]が作るブラックホールを考えて見よう。
このブラックホールの半径は、シュバルツシルト半径Rs=2GM/c2[m]である。
(G[N・m2/kg2]:重力定数、 c[m/s]:光速)
エネルギーが最低の粒子とは「最長の波長λmax[m]を持つ粒子」のことであり、上図のように、半波長(素スピノールの間隔)が、ブラックホールの直径に等しいものである。
この粒子が持つ最低エネルギーEminは、次のように計算できる。
Emin=hc/λmax=hc/4Rs=hc3/8GM[J]=h2/16πLP2M[J]
(λmax/2=2Rs(上図より)、Rs=2GM/c2[m]、「G=2πc3LP2/h」(→結果1)を使用)
(粒子の最低の運動量をpminとすると、pmin=h/λmax となり、この両辺に光速cをかけ合わせると、
Emin=cpmin=hc/λmaxとなる)
ところで、アインシュタインの式によると、全質量エネルギーは、E全質量=Mc2[J]である。
エネルギーが最低の粒子何個分が、この全質量エネルギーに相当するかを計算すると──
E全質量/Emin=Mc2[J]/(h2/16πLP2M)[J]=16πLP2c2M2/h2[個] …(1) となる。
一方、このブラックホールの球の表面積は、4πRs2[m2]である。この表面積の中に、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)のサイズ、すなわち、縦と横が2LP[m]の正方形の面積(4LP2[m2])が、何個あるかを計算すると──
4πRs2[m2]/4LP2[m2]=π(2GM/c2)2/LP2=4πG2M2/c4LP2
=16π3LP2c2M2/h2 [個] …(2)
(1)と(2)は、おおよそ等しい。(π2だけずれているだけである)
(このπ2のずれは、何を意味しているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である)
※なお、この計算は、「最大の波長の粒子」が“光子”であると考えても成り立つ。
(なお、ホーキング放射やブラックホールの蒸発においては、「ブラックホールに取り込まれた光子のエネルギーが、その分だけ、ブラックホールの質量エネルギーを減らす」という考え方がなされている。しかし、光子は質量を持たないので、その説明は、よりいっそう自然(nature)から乖離していると思われる)
|
こういった計算の流れが、“数値の奇跡的な一致”を根底で支えたのだと考えられる。
ベッケンスタインや ホーキングは、“ブラックホールのエントロピー”がA/4LP2(=「1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2」)から求まることを、様々な前提の上で、抽象的な数式を駆使して計算で導いた。
一方、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、このA/4LP2(=「1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2」)の数は、ちょうど、事象の地平面の原始ヒッグス場ユニット(PHU)の数(=(ブラックホールを担う質量から放出されて)事象の地平面をちょうど通過する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数)に等しいことを、その幾何からただちに導く。
このようなことを、「“抽象的な数式”の解釈」、すなわち、「ミクロの自然(nature)についての幾何学的実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」を重視する、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が、はっきり示しているのである。
2.「ストロミンジャー-バッファによるブラックホールのエントロピーの計算」
「ストロミンジャー-バッファによるブラックホールのエントロピーの計算」に関して、次の記述がある。
『巨視的なコップの水は同じように見えても、微視的には水分子はさまざまな微視的な状態を取っている. この微視的状態の可能な数がエントロピーである. 超弦理論によると、ブラックホール・エントロピーもこのようなエントロピーと変わらない. 巨視的な見方であるコップの水に対応するのは、ブラックホールである. 一方微視的な見方、水分子のさまざまな微視的な状態に対応するのが、ストリングのさまざまな状態である. そしてブラックホール・エントロピーは、ブラックホールを作るストリングの微視的状態数だということになる』
(『アインシュタインと21世紀の物理学』 p.217 下線は筆者による) |
『とにかく、相互作用があると結合定数なるものがある。
それで、超ムズカシイと噂の超ひも理論も、ひもどうしの相互作用があるので結合定数がある。その結合定数をgと書くと、ブラックホールと超ひも理論とのあいだには、次のような不思議な関係がある。
不思議な関係 超ひもとD ブレーンの気体の結合定数gを強くするとブラックホールになる。
不思議というより、意味不明だ』
(『熱とはなんだろう』 p.237-238 下線は筆者による) |
『まあ、正直言って、専門家でないと訳がわからない代物ではある。だが、こういう超ひもとDブレーンの配置から、実際に重複度を計算することができて、エントロピーをはじき出すと、驚いたことに、前に発見的な議論によって求めた、ベゲンシュタイン-ホーキングのエントロピーの式(202ページ)と一致するのである!』
(『熱とはなんだろう』 p.237-238 下線は筆者による) |
以上の記述より、下記の仮説を立てた。
仮説D3.5 『超ひもとDブレーンの配置』における、『超ひも』とは、重力子に近いものに相当し、『Dブレーン』とは、原始ヒッグス場(PUF)(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)に近いものに相当し── 『超ひもとD ブレーンの気体の結合定数gを強くするとブラックホールになる』とは、原始ヒッグス場において、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が上昇するとブラックホールになることに相当する。
ストロミンジャー-バッファによる、「ブラックホールのエントロピーの計算」の成果は、『A Class of Five Dimensional External Black Holes』から導いた「A/4=S」という結果と、『Counting of Microscopic BPS States』から導いた「A/4≒S」という結果が一致したことに依存している。
(参考 『Microscopic Origin of the Bekenstein-Hawking Entropy』 ANDREW SROMINGER CUMRUN VAFA)
両者はいずれも、『typeII string theory』『typeIIB string theory』『BPS』『超対称性』… という自然(nature)から乖離した前提に基づく『抽象的な数学(抽象的な数式…)』にもとづいて導かれている。
しかし、自然(nature)から乖離した抽象的な数学から導かれたのにかかわらず── 両者の数字がほぼ一致したのである。
それは、ベッケンスタイン-ホーキングの公式の中の数字が、「事象の地平面にある原始ヒッグス場ユニット(PHU)の個数」と関連したものであったことと──
仮説D3.5の結果、ストロミンジャー-バッファがカウントした『超ひもとDブレーンの配置』の要素の数は、最終的に、事象の地平面に存在する、「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の個数(=「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の個数)」に、等しくなったからだと考えられる。
つまり、両者ともに何らかの形で、「事象の地平面にある原始ヒッグス場ユニット(PHU)の個数」に関連していたからこそ、『超ひもとDブレーンの配置から、実際に重複度を計算することができて、エントロピーをはじき出すと、驚いたことに、前に発見的な議論によって求めた、ベケンシュタイン-ホーキングのエントロピーの式(202ページ)と一致するのである!』ということが、起きたのである。
以上をまとめると次のようになる。
| 1.「ベッケンスタイン-ホーキングによるブラックホールのエントロピーの計算」 |
2.「ストロミンジャー-バッファによるブラックホールのエントロピーの計算」 |
様々な仮定を立てて、自然(nature)から乖離した前提を持つ「抽象的な数式」を駆使して、導いた数字は、事象の地平面に存在する原始ヒッグス場ユニット(PHU)の数に一致した。
|
様々な仮定を立てて、自然(nature)から乖離した前提を持つ「抽象的な数学」を駆使にして導いた数字は、結果的に── 事象の地平面に存在する原始ヒッグス場ユニット(PHU)に一致した。 |
そして、以上のようにして導かれた、1.「ホーキングによるブラックホールのエントロピーの計算」と、2.「ストロミンジャー-バッファによるブラックホールのエントロピーの計算」を前提にして、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」が導かれたのだった。
したがって、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」が「“自然から乖離した前提”から導かれたの2つの理論」を比較して生まれていることは、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)が自然(nature)から乖離している可能性が高いことを示しているように思われる。
しかし、『九次元空間の超弦理論が、三次元空間の場の量子論と同等である』という驚くべきマルダセナの主張自体は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に照らすと、自然(nature)から乖離しているとは言えない。
なぜなら、『九次元空間の超弦理論』の代わりに、『“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の近似としての弦理論(string theory)』と、『三次元空間の場の量子論』と比較すれば、調和しているからである。
すなわち、フラクタル相似の原理があてはまるからである。
このことは、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」が、うまくいくのか(成功するのか?(数字が一致するのか?))を説明している。
すなわち、『“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の近似としての弦理論(string theory)』と、『三次元空間の場の量子論』は、近似的に等しい(フラクタル的に相似である)からこそ、両者による、計算結果が一致する(成功する)ということが起こりうるのだ。
『マルダセナの主張は、九次元空間の超弦理論が、三次元空間の場の量子論と同等であるというものです。「同等である」とは、物理的な現象を説明するために、どちらの理論を使って計算しても、同じ答えが出るということです。これは驚くべきことでしょう。なにしろ前者は重力を含んでいるのに、後者は重力を含んでいません。しかも、次元がまったく違うのです』
(『大栗先生の超弦理論入門』 p.241) |
一方、「“グルーオン×2”と重力子」(「グルーオンの集積したひも」と「LP光子の集積したひも」)の振る舞いには、似た部分があるのであり、互いに、“フラクタル相似の原理”(3Steps原理の1つ)と調和していたのであった。
よって、次の仮説を立てた。
仮説D3.6 「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」における、数字の一致は、“フラクタル相似の原理”を反映している。
※なお、もともと、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」が発表された当初は、マルダセナ自身が、その成果に対して、“ホログラフィック原理”を明確に結びつけていたわけではなく── はじめて、はっきりと結びつけたのは、エド・ウィッテンであったようである。
『私はマルダセナが自分の発見とホログラフィック原理を結びつけたのかどうかは知らない。しかし、エド・ウィッテンはすぐに結びつけた。マルダセナの論文のちょうど2か月後に、ウィッテンはインターネットに自分の論文を掲載して、「反ド・ジッター空間とホログラフィー」というタイトルをつけた』
(『ブラックホール戦争』 レオナルド・サスキンド p.499 日系BP) |
このことから、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」については、必ずしも“ホログラフィック原理”を結びつけなければならないものではないことがわかる。
つまり、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」における成功(数字の一致)は、“ホログラフィック原理”ではなく、“フラクタル相似の原理”を反映していると解釈できるのである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)がせんとすることは、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」を否定することではない。
マルダセナの対応(Ads/CTF対応)が、どういうしくみで、うまくいき(成功し)、どういうしくみでうまくいかなくなっているのかを、より深いレベルの階層から説明することである。 そして、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」についての自然(nature)と調和した解釈を提示することである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」に対する自然(nature)と調和した解釈は、「“フラクタル相似の原理”を反映している」というものである。
すなわち、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」に対する、「“ホログラフィック原理”を反映している」という解釈は、自然(nature)から乖離しているということを示しているのである。
よって、例えば、「3次元空間の事象が幻であり、遠く離れた2次元での事象の投影にすぎない」というようなホログラムは、自然(nature)から乖離していると判断できるのである。
そもそも、“ホログラフィック原理”とは、次のようなものである。
『普段経験している3次元の世界、つまり、銀河、星、惑星、家、巨石、そして人々で満たされた宇宙はホログラムである。すなわち宇宙は、遠く離れた2次元の面にコード化されたものから生じる画像なのだ。この新しい物理学の法則をホログラフィック原理という。それは「空間の内部にある一切のものはその領域の境界面の情報だけで表せる」というものだ』
(『ブラックホール戦争』 レオナルド・サスキンド p.360-361 日系BP) |
『ホログラムは、エッチングされたプラスチックの二次元片で、適切なレーザー光線を当てれば三次元の像を映し出す。一九九〇年代のはじめ、オランダのノーベル賞受賞者ゲラルド・トホーフトとレナード・サスキンド(ひも理論を共同発明した物理学者と同一人物)は、宇宙はホログラムと似た方法で機能しているのではないかという説、《ホログラフィック原理》を提唱した。二人は、三次元の日常の暮らしの中で私たちが目にする出来事は、遠くの二次元表面で起こっている物理過程のホログラフィックな投影かもしれないという、驚くべきアイデアを打ち出したのである。斬新で奇妙な彼らの考えによれば、私たち自身も、私たちが行うことや見ることのすべても、ホログラム像のようなものである。プラトンは、普通の知覚が見せてくれるものは実在の影にすぎないと考えたが、ホログラフィック原理はそれに賛同しつつも、そのメタファーを逆転させる。すなわち、影(低次元の表面上で潰れたように生きるもの)のほうが実在であり、より豊かな構造を持つ高次の存在と思われるもの(私たち自身と、私たちを取り巻く世界)は、その影を投影した儚(はかな)い存在だと言うのだ』
(『宇宙を織りなすもの』 ブライアン・グリーン p.367 草思社 ※(はかな)は、ルビであった。 下線は、筆者による) |
そもそも、このような“ホログラフィック原理”という不思議で奇妙な考えは、次のような単純な論理によって導かれたものであった。
『空間の領域に入る情報のビットの最大の値は、境界の面積につめこむことができるプランクスケールのピクセル数に等しい。これは、空間の領域の内部で起こりうる一切のことに対応した、境界面での記述があることを意味している。境界の面は3次元の内部の2次元のホログラムである』
(『ブラックホール戦争』 レオナルド・サスキンド p.366 日系BP) |
『もしもあらゆる空間領域において、そこに含まれるエントロピーの最大値が、体積ではなく表面積に比例するというのなら、真の基礎的な自由度は(自由度があって無秩序が生じる)、その領域の内部ではなく、その領域の表面に属しているのではないだろうか。ひょっとすると宇宙の真の物理的プロセスは私たちを遠くで取り巻いている薄っぺらな表面の上で起こっているのであって、私たちが見たり経験したりするものはすべて、そのプロセスを投影したものなのではないだろうか。要するに、宇宙はホログラムのようなものかもれないのだ』
(『宇宙を織りなすもの』 ブライアン・グリーン p.367 草思社 ※太線部は、傍点であった) |
つまり、“ホログラフィック原理”は、本質的には、「ブラックホールの自由度が、その体積ではなく、地平面の表面積に等しい」という前提から導かれたのである。
そして、この前提は、まさに、ベッケンスタイン-ホーキングの公式の中の『A/4LP2』という抽象的な数式の“解釈”に他ならない。
『普通に考えれば、ブラックホールのエントロピーも体積に比例しそうだ。
ところが一九七〇年代に、ジェイコブ・ベケンスタインとスティーヴン・ホーキングは、そうではないことを発見したのである。この二人が数学的に解析したところ、ブラックホールのエントロピーは体積ではなく、事象の地平面の面積(大ざっぱに言って、ブラックホールの表面積)に比例することがわかったのだ』
(『宇宙を織りなすもの』 ブライアン・グリーン p.363 草思社) |
しかし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、ベッケンスタイン-ホーキングの公式の『A/4LP2』(=『1(ホライズン面積)/4(プランク長さ)2 』)の部分は、ブラックホールの表面に存在する、「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の数」(あるいは、「ブラックホールの表面から放出される重力子の数」)であると解釈するのだった。
そして、ブラックホールから放出される大量の重力子がエントロピーを持ち去る結果、新しいブラックホールの表面から内部では、秩序が生まれ、エントロピー0に近づくのである。 よって、『A/4LP2』は、ブラックホールが持っているエントロピー(自由度)の大きさではないのだ。
したがって、『空間の領域に入る情報のビットの最大の値は、境界の面積につめこむことができるプランクスケールのピクセル数に等しい』や『真の基礎的な自由度は(自由度があって無秩序が生じる)、その領域の内部ではなく、その領域の表面に属しているのではない』、『ブラックホールのエントロピーは体積ではなく、事象の地平面の面積(大ざっぱに言って、ブラックホールの表面積)に比例する』という、“ホログラフィック原理”の前提の時点で、自然(nature)から乖離しているのである。
したがって、次の結論に至る。
結論D3.4 “ホログラフィック原理”は、自然(nature)から乖離している。
“ホログラフィック原理”は、結局は、「抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何…)」のみを重視し、その解釈、すなわち、「ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」を軽視した結果導かれた、自然(nature)から乖離した考えに過ぎないことを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示しているのである。
よって、“ホログラフィック原理”が自然(nature)から解釈している以上── 「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」の成果は、“ホログラフィック原理”を反映しているという解釈は、自然(nature)から乖離しているのである。
しかし、そのことは、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」が、自然(nature)から乖離していることを意味しない。
なぜなら、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」は、“フラクタル相似の原理”を反映していると解釈できるからである。
『マルダセナはこう主張した。フラットランドのQCDは(3+1)次元の反ド・ジッター宇宙と互いに双対の関係にある。さらにこの3次元の世界では、実際の世界と同じように、物質とエネルギーは重力を働かせる。言いかえれば、QCDは含んでいない重力のない(2+1)次元の世界は、重力のある(3+1)次元の宇宙と同等である』
(『ブラックホール戦争』 レオナルド・サスキンド p.497 日系BP) |
『ひも理論家はずっと原子核に興味をもっていた。ひも理論の初期の時代はハドロン、つまり陽子、中性子、中間子、グルーオンだけを扱っていた。原子核と同じようにこれらの粒子はクォークとグルーオンでできている柔らかな合成物である。しかしプランクスケールの10億倍の10億倍のそのまた100倍の大きなスケールで、自然はまた同じことを繰り返しているようなのだ。ハドロンの物理学の計算はひも理論の計算とほとんど同じことがわかっている。スケールがここまで違うという事実を考えると、それは非常に驚くべきことに思われる。核子は基本ひもに比べて1020倍大きく、1020倍ゆっくり振動する。これらの理論がたとえほんのわずかでも同じということなどありうるのだろうか? ところが、これから明らかになるように、実際にその通りなのだ。そしてもし普通の原子核の中の粒子が基本ひもに似ているなら、核物理学の実験室でひも理論のアイデアを検証すればよいのではないだろうか?
〜
それなら、プランクサイズの粒子を非常に高いエネルギーで衝突させてブラックホールをつくることはできなくとも、それらの拡大バージョン、つまり、グルーボール、中間子、核子を衝突させて、ブラックホールの拡大バージョンをつくることができるかもしれない。〜。数を代入して計算してみると、普通の原子核がリックの中で衝突すると、ちょうどスローモーションしたような状態になって、拡大バージョンのブラックホールをつくれるはずだということがわかった。
リックでブラックホールを作れるというのはどういうことなのか理解するには、ホログラフィック原理とジュアン・マルダセナの発見に戻らなくてはならない。マルダセナはだれも予測しなかったやり方でふたつの異なる数学的な理論が実際には同じであることを発見した。これをひも理論の専門用語では「互いに双対の関係にある」という。一方の理論は重力子とブラックホールのあるひも理論で、(4+1)次元の反ド・ジッター空間(ADS)にある(前の章では、私は視覚化しやすくするために勝手に空間の次元を減らした。本章では減らした次元を元に戻す)。
空間の次元が4個あるというのは核物理学では多すぎるが、ホログラフィック原理を思い出してほしい。ADSの中で起こることはすべて、空間の次元が1個少ない世界でも数学的な理論によって完全に記述できるはずである。 マルダセナは4次元の空間で始めたのだから、ホログラフィックな双対性のもう一方の理論は3次元空間(日常の空間と同じ数)しかない。このホログラフィーの記述は、従来の物理学を記述するために使われる理論のどれかに似ているだろうか?
答えはイエスであることがわかっている。ホログラフィックの双対性の相手は量子色力学(QCD)、つまり、クォーク、ハドロン、原子核に関する理論に数学的にそっくりなのだ。
』 (『ブラックホール戦争』 レオナルド・サスキンド p.505 日系BP) |
※ホログラフィック原理に関連する下線部は、
「ホログラフィック原理」→「フラクタル相似の原理」
「ホログラフィックな双対性」→「フラクタル相似の双対性」
「ホログラフィーの記述」→「フラクタル相似の記述」
のように置き換えることで、自然(nature)と調和するのである。(このように書き換えても、文章の、つじつまが合うことがわかる)
「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」における、“プラス1次元”は、さらなる空間の次元ではなく、“素スピノールの自由度”(or 原始ヒッグス場ユニット(PHU)の自由度)と考えればよい。
(まさに、M理論と弦理論(string theory)の関係に似ている)
※なお、『自然はまた同じことを繰り返しているようなのだ。ハドロンの物理学の計算はひも理論の計算とほとんど同じことがわかっている』の部分は、まさに、“フラクタル相似の原理”で、ぴったり説明できる。 |
つまり、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」は、“フラクタル相似の原理”を反映していると解釈できるのみならず、その解釈こそが自然(nature)と調和しているのである。
よって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の結論を出す。
結論D3.5 マルダセナ対応(Ads/CTF対応、ゲージ・重力対応、ゲージ・string対応)の、自然(nature)と調和している根拠は、“フラクタル相似の原理”である。
すなわち、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」の根拠は、“ホログラフィック原理”であるという説明は、自然(nature)から乖離していることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示しているのである。
『重力は幻なのか? ホログラフィック理論が語る宇宙』(J.マルダセナ 日経サイエンス)を読むと、マルダセナ自身が、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」と“ホログラフィック原理”を結びつけていることがわかる。
しかし、「マルダセナ対応(Ads/CTF対応)」の根拠は、“ホログラフィック原理”ではなく、“フラクタル相似の原理”であると理解することによって── 次の記述のような課題が根底から解消するかもしれないのである。
『私がこうしたホグラフィックな対応を初めて予想したのは、1997年のことだった。この対応が、ある特定の理論(境界面が4次元時空となっていて、単純化した量子色力学をそこに適用した場合)について成り立つであろうと予想したのだ。これは、ひも理論の研究者の間で即座に大きな関心を呼んだ。その後、プリンストン大学のポリャコフとガブザー(Shephen S. Gubser)、クレバノフ(Igor R.Klebanov)のグループ、そしてプリンストン高等研究所のウィッテン(Edward Witten)の研究によって、この予想は定式化され、より明確なものとなった。
以来、多数の研究者が研究に取り組んだ結果、この予想は他の次元や別の量子色力学にも一般化され、予想の正しさを示す多くの証拠が得られた。ただし、これまでのところ、どの例も厳密には証明されていない。数学的に難しすぎるのだ。
〜。
ホログラフィックな対応例はまだ厳密には証明されていない 数学的に難しすぎるのだ
〜。
ホログラフィック理論については、多くの疑問が残っている。特に重要なのは、反ド・ジッター空間についていえることと同じことが、私たちの宇宙でも成り立つのかどうかだ。 反ド・ジッター空間の際立った特徴は、境界面を持っており、そこでの時間がきちんと定義できる点だ。この境界面はずっと存在してきたし、今後も永遠に存在し続ける。これに対し、私たちの宇宙のように、膨張している宇宙はビッグバンから始まったので、きちんと定義できる境界面がない。したがって、私たちの宇宙に対してホログラフィック理論をどう定義したらよいのか、はっきりしない。ホログラムを置くのにふさわしい場所がないのだ』
(『重力は幻なのか? ホログラフィック理論が語る宇宙』 J.マルダセナ 日経サイエンス 下線は、筆者による) |
“ホログラフィック原理”から、“フラクタル相似の原理”へのシフト──
抽象的な数式についての、自然(nature)から乖離した解釈から、自然(nature)と調和した解釈へのシフト──
「境界面と内部の対応関係」から、「ある理論と、それより1つの自由度の多い理論の対応関係」へのシフト──
を達成することで、計算が、具体化&シンプル化することが予想される。
なぜなら、ミクロの自然(nature)そのものが、具体的でシンプルだからである。
すなわち、数式が、抽象的で複雑難解であることは、ミクロの自然(nature)の本質をつかみそこねていることを示している可能性があるからである。
やはり、自然(nature)と調和している限り、多様な科学スタイルは、尊重されるべきである。
しかし、自然(nature)から乖離している部分については、却下しなければならないのである。
もう一度、引用する。
『失われた世代
聡明な物理学者の中には、二〇年から三〇年を費やして、ひも理論を予測可能な理論にする方法を探し、この理論が理にかなっていて自然界を記述していることを実験的に納得いく形で証明しようとしてきた人がいる。しかし、それほどの年月と才能を費やしておきながら、今ではひも理論は成功しそうにないと考えている。数学に覚えのあるひも理論学者たちは、統一場理論と量子重力を目指す別の道へと、あっさり関心を移していった。
彼ら天才たちは、“失われた世代”の理論物理学者と呼ばれている。過去二〇年間、理論物理学に対する財政支援の大部分はひも理論につぎ込まれてきた。そして、政府交付金や大学の雇用方針によって、物理学はひも理論の発展へと導かれていた。過去何世紀もの科学的取り組みと比べても、無駄になった才能は信じがたいほど大きい。いくつもの大規模なグループがひも理論に全身全霊を捧げたためだ。それに比べて量子力学は、二〇世紀前半の一〇年以上にわたって、アインシュタイン、シュレーディンガー、ボーア、ハイゼンベルク、パウリ、ボルン、ディラック、ジョルダンなど一握りの物理学者の手で発展した。今日では、つねにおそらく一〇〇〇から一五〇〇人の理論物理学者が、ひも理論を研究し、論文を発表している。そして互いの論文を引用することで、文献引用頻度を水増しして、現在ではひも理論学者たちが最も重要な論文を生み出していると見せかけている』
(『重力の再発見』 p.236〜237 ジョン・W・モフゥット 水谷淳訳 早川書房 下線は、筆者による) |
こういった批判を乗り越えるためには、そして、「偉大な知性によってなしとげられた巨大な“知の財産”」が、決して、無駄ではなかったと胸を張って言い続けるためには、やはり、抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何…)のみならず── 「ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」をも重視し、自然(nature)と調和した弦理論(string theory)として、進化して行かねばなららないことを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示しているのである。
そして、「抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何…)」のみならず、「ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」をも重視することによってはじめて、次の記述にあるような根本的な課題を乗り越えて行けることを“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、示しているのである。
『本書の最初に、デモクリトスの言葉を引用しました。これを超弦理論にあてはめると次のようになるでしょう。
私たちは習慣によって、
重力があったり、
次元があったり、
空間があったりすると思うが、
現実に存在するのは……
本章の最初に、この「……」にあてはめるべき言葉を私たちはまだ知りません。重力や、次元や、空間が幻想であることは確かですが、それが何から現れてきているのかについて、根源的な理解に達していないのです。それを明らかにすることは、これからの大きな課題です。超弦理論はまだまだ発展途上なのです』
(『大栗先生の超弦理論入門』 p.248〜249) |
すなわち、“超弦理論”(superstring theory)は、「ミクロの自然(nature)の具体的な幾何的な実体像(視覚的な描像、物理的なイメージ、“true picture at Planck scale”、単純な幾何構造の働きの総和…)」をも重視し、「“フラクタル相似の原理”と調和した弦理論(string theory)」へと進化することによって── 『重力や、次元や、空間』が『何から現れてきているのかについて、根源的な理解』を達成でき、完成に近付いていけることを、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示しているのである。
|