研究論文
『一般3Steps理論と
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)について』
2.重力(一般相対性理論)、重力子、質量、光速について
このページでは、次の項目について、一般3Steps理論的、および“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)的な説明を試みる。
《光子の波、重力子の波》
まず、光子が、光速で、原始ヒッグス場(電磁場)を移動することについて、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明を試みる。
光子の構造は、次のようであると考えられる。
|
光子
|
|
“素スピノールモデル”の表記
|
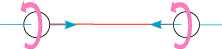 |
|
簡略表記
|
・・
|
|
スピン
|
1
|
※右巻き素スピノールと左巻き素スピノールが結びついている
これが空間内を光速で移動するとは、どういうことであろうか?
次のような考えをヒントにしてみた。
「温度がゼロよりほんの少し高いとどうなるだろうか。この場合も基本はやはりすべてのスピンがそろった状態で、そこにときどきランダムに一個のスピンがひっくりかえることが起きる。そうすると、その隣のスピンがつき合ってやはり逆を向くこともあるだろう。ただ、二つが同時に逆を向くとエネルギーのロスが大きすぎるので、隣が逆を向いたら最初のは元に戻る。次はそのさらに隣が付き合って逆を向く……、という具合にスピンが格子上を伝わって移動していくこともありそうだ。まるで波のようではないか。そう、これは波だ。」(『質量はどのように生まれるのか』 橋本省二 講談社ブルーバックス p160-162 鉄の強磁性に関しての説明文の一部)
この“スピンのひっくりかえりの伝播”が素スピノールのネットワーク上で(原始ヒッグス場で)起きている場合── それがまさに、電磁波の出現に相当しているのではないだろうか?と考えてみた。
よって、次の仮説を立てた。
仮説2.1 光子は、様々な距離にある“原始ヒッグス場”の基本構造をバネ的な足場にして── 「 互いに“近づくor遠ざかる”方向に運動する素スピノールのペア」が、同時に転回する(共転回する)ことを繰り返しながら、進むものに相当する。
光子の流れを簡略に図示すると次のようになる。
※ 「 互いに同じ方向に運動する素スピノールのペア」が、同時に転回している(共転回している)
“素スピノールがひっくり返ること”が、“素スピノールが転回する”ことの意味である。 “素スピノールのペア”が同時に転回することを“共転回する”と呼ぶこととする。
上図のように、“素スピノールの転回(=ひっくり返り)”が、次々と伝わっている。 これが、まさに“光の伝わり方”(光子の移動のし方)の実体に相当することになる。
※このモデルだと、光が持つ“波と粒子の二重性”の性質が生じる理由も、自然に、うまく説明できると思われる。
“原始ヒッグス場”とは、“原始ヒッグス場”の基本構造(“4面体”)がゆるやかに結びつきながら時空を占めている(自由に回転できると同時に固定されている)ものだと考えられる。(→考察3、4)
“原始ヒッグス場”の基本構造の足場とは、次のようなものである。
|
“原始ヒッグス場”の基本構造
(=電磁場の基本構造)
|
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
の表記
|
|
←
→
|
|
|
構成
|
“右巻き素スピノールのペアと
左巻きの素スピノールのペア”
からなる“4面体”
|
|
スピン
|
0
|
※凝縮のペア(黒い線で結ばれる。右巻きどうし、左巻きどうしのペアである)が2つ組み合わさってできていると言える。
※図では止まっているように示されているが、凝縮のペア(黒い線で結ばれた、右巻きどうし、左巻きどうしのペア)は、ふだんは、それぞれに、連星のように、光速で回転運動をしていると考えられる。 この“連星のような動き”(運動量保存則)のおかげで、“場所を移動しない(固定させる)”という重要な性質を獲得すると考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※“連星ような軌道運動”が90度分ずれたものを、おおまかなモデルとして図示した。 交互に変化することになる。 より正確には、次のように連続になっているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
|
|
|
光子の流れを詳細に図示すると次のようになる。
時空をびっしり占める個々の“原始ヒッグス場”の基本構造の足場にはそれぞれ、必ず、右巻き素スピノール(相手に近づく方向に進むもの、遠ざかる方向に進むもの)、左巻き素スピノール(相手に近づく方向に進むもの、遠ざかる方向に進むもの)の4種類が存在するので、ある波長を持つ光子の進行に必要な素スピノールを、適宜選ぶことが出来る。
※光子は、様々な波長をとることができる。 そのことは、時空をびっしりと占める“原始ヒッグス場”の中で、どの基本構造の足場を選ぶのかによって対応できる。
光子が、近くの足場どうしをまたぐなら短い波長、 遠くの足場どうしをまたぐならば長い波長に、相当すると考えられる。
この光子が、真空中を、光速という一定の速度で伝わるということは──
“転回の頻度”が多いほど(転回するのに要する時間=“転回周期”が短いほど)、“足場”の間の距離が小さくなって(光の波長は短くなって)、
逆に、“転回の頻度”が少ないほど(転回するのに要する時間=“転回周期”が長いほど)、“足場”の間の距離が大きくなる(光の波長は長くなる)ことを意味する。
それは、“転回の頻度”が多いほど光子のエネルギーが大きくなり、“転回の頻度”が少ないほど光子のエネルギーが小さくなることになり、アインシュタインの光子が持つエネルギーの式 E=hν と合致する。
※光子が持つエネルギーと、原始ヒッグス場の“4面体”が変形することによって蓄えるエネルギーが等しいと考えられる。
原始ヒッグス場の“4面体”には、速いスピード(短い転回周期)で変形すればするほど大きなエネルギーを蓄えるという性質があることになる。
言い換えれば、E=hν=h/T なので── このエネルギーEの振幅と転回の周期Tは、反比例するということである。
これは、不確定性原理の式── ΔE×Δt ≒h と似ている。(→考察6)
※また、真空中で、一回(180度)だけ転回する時間(転回周期)をT180度とし、光子のペアである素スピノール2つの間の距離をLとすると── 180度転回する間に進む速度は、L/T180度と計算でき、これが、常に光の速度c(約3×108m)に等しいことになる。 L/T180度=c これは、素スピノールの転回周期T=2T180度(つまり、変形に伴って“4面体”が持つエネルギー)が決まると、自動的に、“次の素スピノール”までの距離が決まってしまうことを意味している。
※上記のように「素スピノールの転回が遠方へ伝わる現象(基本スピノールのペアが同時に転回する現象(共転回と呼ぶこととする))」を支えるものと、非局所性(エンタングルメント(量子もつれ、絡み合い…))の現象を支えるものが、本質的に同一のものであると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※このモデルは、「光子は、360度回転すると元に戻る」という考えと合致すると思われる。 なぜなら、180度の共転回を2回繰り返すと、同一の状態になっていることを図から読み取れるからである。
※この電磁場(原始ヒッグス場の“4面体”の総和)は、“光速不変の原理”(なぜ、慣性系で光速一定が観測されるか、なぜ、マイケルソン-モーレーの観測結果が生じるか)を説明できる。(下記の考察《等速運動と特殊相対性理論》)
したがって、「かつて、(古い)“エーテル”が否定されたこと」と矛盾しない。 「原始ヒッグス場の“4面体”の総和」は、いわば、“新しいエーテル”であり、光速不変や電磁場のみならず、重力場を説明できるものである。 アインシュタインが一般相対性理論において、(新しい)エーテルを必要不可欠と考えていたことと合致する。
そもそも転回によって、なぜ、“4面体”が変形するのか? このことについて、次の仮説を立てる。
仮説2.1.2 “4面体”の中で、ある素スピノールが転回する際、その素スピノールのバネの伸縮軸にそった“運動”そのものによって、その運動する方向に、そのままバネが縮んだり伸びたりする形になる。
共転回の時間経過の詳細を図示すると、次のようになる。
共転回する素スピノールが作る角度を次のように定義すると──
光速をcとして、“csinθ” に比例する大きさの速さで、バネを伸縮させることになると考えられる。
kを比例定数、転回周期をTとすると、θ=2πt/T(=ωt)となり、Bの素スピノールを含む“4面体”のバネの伸縮に伴う移動距離xは、x= kc∫sin 2πt/T dt
の積分をすれば求まり── tのときの移動距離は、x=(Tkc/2π)×(1− cos2πt/T) となる。 (最も縮まった時の移動距離は、T/2のときであり、Tkc/πとなる。)
Bを含む“4面体”のバネの伸縮に伴う移動距離 x=(Tkc/2π)×(1− cos2πt/T)をグラフにすると、次のような正弦波となる。
素スピノールAについても、“4面体”の変形による移動距離は、同様な正弦波となると考えられる。
共転回が作る角度θを用いて図示すると次のグラフのように、上(Bを含む“4面体”)のグラフの後半部分と同じになる。
このグラフは、正弦波の対称性により── 共転回にともない、Aの素スピノールを含む変形した“4面体”において解消される“縮みの長さ”と、Bの素スピノールを含む、これから変形する“4面体”に新たに加えられる“縮みの長さ”が、全く同じペースで進むことを意味している。
そして、このことは、もし、「変形した“4面体”に蓄えられるエネルギーが“移動距離(縮み)x”に比例」していれば── Aを含む“4面体”から“開放されるエネルギー”が、Bを含む“4面体”に“蓄えられるエネルギー”と常に等しくなる(エネルギーが常に保存される)ことを意味している。
※本当に、「変形した“4面体”に蓄えられるエネルギーは、“移動距離(縮み)x”に比例」しているのだろうか?
「“移動距離(縮み)”をxとしたとき、蓄えられるエネルギーがkx2/2の式で表される、ふつうのバネ」とは、異なった性質を持つということでいいのだろうか?
それとも、一時的にエネルギー保存則が破れているだけであり、「蓄えられるエネルギーが“移動距離(縮み)x”に比例」しているわけではないということなのだろうか?
詳細な検討は、今後の課題である。
※一方── 共転回が続く間、“4面体”の中で、ペアになっていたもう一方の素スピノールは、どのような動きをしているのであろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
次に、重力子が、波として光速で移動することについて考察する。
重力子は、スピン2である。 次の仮説を立てた。
仮説2.2.0 重力子は、スピン1の光子2つ分に相当し、4つの素スピノールから、次のように構成されている。
|
重力子(グラビトン)
|
|
素スピノールの
ネットワーク
(“素スピノールモデル”の表記)
|
|
|
簡略表記
|
: :
|
|
スピン
|
2
|
この配置によってはじめて、スピン2となることができる。
さらに次の仮説を立てた。
仮説2.2.1 重力子は、“4つの素スピノール”を共転回させながら、すぐとなりにある“原始ヒッグス場”の“4面体”をバネ的な足場として、次々と進む波に相当する。
※見やすくするため、原始ヒッグス場の“4面体”の間隔を空けてある。
|
重力子の波は、“2個の光子”が並走するものに相当するものであることが読み取れる。
重力子は、上図のように、180度の共転回をするたびに、1プランク長(1Lp)進むことになる。 そして、これが、光速で移動することになる。
ふつうの光子が、様々な距離にある“4面体”の足場を移動するのに対して、重力子は、「すぐとなりにある“4面体”の足場のみ」を移動する。 このことは、重力子の波長は一定であり、非常に短いことを意味する。
重力子のサイズ、および゛、重力子の波長について、次の仮説を立てた。 (→下記の考察《プランク定数、ブランクエネルギーについて》)
仮説2.2.2 重力子のサイズは、1プランク長(Lp)程度、重力子の波長は、2プランク長(2Lp)程度と一定となる。
※重力子は、これまで観測されてきている電磁波(光子)──X線やγ線よりも、はるかに波長が短いことになる。 もし、単独の光子がこの波長なら、致命的に大きな影響を与えるのは、必至である。 しかし、重力子は、電場や磁場を100%打ち消すような配置で、2個の光子が並走するものに相当するために、致命的な影響がないと同時に、観測が極めて困難になると考えられる。
※それぞれの素スピノールは、一辺が1プランク長の立方体の空間の中心にあると考えられる(→考察7)。その立方体のサイズを意識するなら、重力子のサイズは、2プランク長(2Lp)であると言えるかもしれない。
※『アインシュタイン選集2』によれば、アインシュタインは「長い波長の重力子」というものを考えておられたようである。
しかし、もし(物質を中心にして周囲へと放出される)重力子の波長が長くなるとすれば── 1つの重力子は、いずれは複数の原始ヒッグス場にまたがって移動し始めてしまい、ついには、1つの重力子としては存続できず、2つの光子に分裂してしまうことになると考えられる。 つまり、重力子が“すぐとなりの原始ヒッグス場を足場にして移動すること”には、2つの光子への分裂を生じさせない、という重要な意味があると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※ふつう光子が部分的に“4面体”を途中まで変形させるのと違い── 重力子は、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを100%変形させ、“4角形”にまですることができると考えられる。 この“4角形”は、“縮みきったバネ”と言える。 一方、物質が何らかの形で、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを、100%縮みきった“4角形”にすることではじめて、重力子が放出されるようになる、と言うこともできる。
バネが縮みきってできた“4角形”が持つエネルギーには、重要な意味があると考えられる。 (→下記の考察《プランク定数、ブランクエネルギーについて》)
※このモデルは、「重力子は、180度回転すると元に戻る」という考えと合致すると思われる。 なぜなら、180度の共転回を1回繰り返すたびに、同一の状態になっていることを図から読み取れるからである。
重力子が、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場の基本構造の集まり)の上を、光速で波として移動するとき、“4角形”(縮みきったバネ)も、一緒に光速で移動していくことになる。 この“4角形”(縮みきったバネ)の動きを、次のように(簡略化して)表記できる。
※縮みきったバネの“4角形”が移動していくことだけが図示されている。
決して、この“4角形”(縮みきったバネ)=重力子というわけではないが── 1つの重力子につき、1つの“4角形”(縮みきったバネ)が近くに生じていることになるので、便宜上、重力子の挙動を近似的に“4角形”(縮みきったバネ)の挙動として代用することも可能かと思われる。
しかし、やはり、重力子も(原始ヒッグス場由来の)“4角形”(縮みきったバネ)も、どちらも大事なので、以下では、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」と表記しながら話を進めることも多くあることになる。
※1つの原始ヒッグス場の基本構造に注目した場合── 「“4面体”の状態←→“4角形”(縮みきったバネ)の状態」と行ったりきたりするプロセスを、下のように説明できる。
|
原始ヒッグス場の基本構造の“4面体”
|
|
原始ヒッグス場の基本構造由来の
“4角形”(縮みきったバネ)
|
|
原始ヒッグス場の基本構造の“4面体”
|
|
|
→
|
|
→ |
|
|
※緑で囲ったペアが(重力子の働きによって)180度転回しながら、“4角形”(縮みきったバネ)の配置に近づく。 その際、右巻きと左巻きの素スピノールの両方が、“4面体”のバネを縮めようとする方向に運動することが図から読み取れる。(「仮説2.1.2」と合致している。) これによって、サンドイッチのように上下からはさむように変形が進むことになる。
|
|
※※重力子がさらに進行するのに伴い、上図の赤い素スピノールのペアのみが転回する。この転回に伴う素スピノールの運動は、“4面体”の変形を維持するような方向(変形が解消されない方向)に向いている。(「仮説2.1.2」と合致している)
|
|
※元の“4面体”の配置に戻る。 |
スピン2の重力子が、スピン0の原始ヒッグス場の“4面体”の上を進行していく過程で、“4面体”は、一時的に、“4角形”(縮みきったバネ)となる。
この“4角形”(縮みきったバネ)こそがバネのような働きをし── 「1つの“バネ”の収縮が解消されると同時に、新たな1つの“バネ”が収縮する」ということを繰り返すおかげで、重力子は、次々と新たな原始ヒッグス場の上を進んでいける。
|
※重力子の進行とともに、次々と“4角形”(縮みきったバネ)と“4面体”が切り替わっていく様子が読み取れる。
このことは、1つの“バネ”の収縮が解消されると同時に、新たな“バネ”が収縮しているので、重力子が進行する間に、エネルギーの損失はないと考えられる。
|
※“時空の曲がり”(重力場)の変化とは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の増減によって、もたらされると考えられる。
そういった“「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の数(密度)の増減”としての“時空の曲がり”(重力場)の変化も、(重力子1つ1つが光速で進むので)当然、光速で進むと言える。
個々の重力子そのものを直接に観測することは、やはり非常に困難である(なぜなら、1つの重力子の中だけで磁場と電場が完全に打ち消し合っているのみならず、実在する重力子のサイズは、波長がプランク長さの2倍程度(2Lp≒2×1.616×10-35m=約3.232×10-35m)と非常に小さいからである)のに比べ──
重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の数(密度)の変化の波は、相対的に観測しやすいと思われる。
しかし、それは“電磁波”のような波とは、全く異なる波である。
(たとえば、豆電球に与える電圧を周期的に変化させれば、光の強度(光子の数)が増えたり減ったりを繰り返す波と見なせる。 その波は、確かに光速で進む。 しかし、その光の強度の増減の波自体は、決して電磁波ではない。
同様に、運動エネルギーや質量が周期的に変化することによっても、重力の強度(重力子の数)の増減の波が生じると言える。 その波は、光速で進む。 しかし、その重力の強度(重力子の数)の増減の波自体は、決して、アインシュタインが電磁波との類推から予言したところの“重力波”ではないと考えられる)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“電磁波と類推できるような重力波は、あくまで個々の重力子である”ことを示している。
以後、重力波=個々の重力子として、話を進める。
※光子(電磁波)も重力子(重力波)も、原始ヒッグス場の基本構造を、一時的にエネルギーを蓄えるバネのような働きをするものとして活用し、伝わっていく波であると考えられる。 また、光子の波も、重力子の波も、両方とも「“4面体”のバネが持つエネルギーを伝えるもの」と見なすこともできると思われる。
以上の考察は、この“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)の方向のアプローチによって、“重力場と電磁場の統一”が可能であることを示唆していると思われる。
※光子(電磁波)が、電荷を持つ素粒子が“身ぶるい”することで生じる波である一方、重力子は、(ミクロレベルで)光速で運動し続ける素粒子の“身ぶるい”によって生じると言える。 (→《質量の実体像》 →考察6)
《質量の実体像》
質量とは何か? “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明を試みる。
もともと、あらゆる素粒子は、ミクロのレベルで見ると、常に光速で移動し続けている。(それは、標準モデルの前提でもある)
しかし、その素粒子は、原始ヒッグス場の基本構造の“4面体”に衝突し、抵抗をうけながら“4面体”を変形させる過程の中で、(マクロレベルでの見かけ上、光速を失うと同時に)重力子を放出させると考えられる。
たとえば、個々の電子、クォーク、陽子… も、周囲の原始ヒッグス場から抵抗を受けながら“4面体”を変形させることによって、重力子を放出させる。 しかし、電子、クォーク、陽子… は、1回の衝突だけでは、原始ヒッグス場の“4面体”を完全な“4角形”(縮みきったバネ)に変形させて、重力子を放出させることができない。 しかし、時間をかけて、繰り返し衝突することによって、電子、クォーク、陽子… が1つ1つの単独であっても、原始ヒッグス場の“4面体”を完全な“4角形”(縮みきったバネ)に変形させるほどになり、重力子を放出させることができる。 しかし、それは、プランク質量が放出させる頻度より、ずっと少ない。
一方で、個々の電子、クォーク、陽子… は、それぞれ、電子場由来のヒッグス場、クォーク場由来のヒッグス場、陽子場由来のヒッグス場から、抵抗を受けることによっても、(見かけ上の光速をさらに失うと同時に)質量をさらに獲得する。 (カイラル対称性の破れによる質量獲得に相当)
その過程では、各種のヒッグス場の“4面体”を“4角形”(四極子)に変形させることで、周囲の時空構造にエネルギーを蓄える。
この四極子の“4角形”も、最終的に原始ヒッグス場の“4面体”に何らかの形で作用し、変形させると考えられる。 (この過程の詳細については考察4)
つまり、ある素粒子の質量は、原始ヒッグス場を直接、“4角形”(縮みきったバネ)に変形させて、重力子を放出する過程と── それぞれのヒッグス場との相互作用を介して(“カイラル対称性の対称性の破れ”を通じて)、最終的に、原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)を変形させて、重力子を放出する過程── この2つの合計で決まってくると考えられる。
素粒子の総和である、より大きな物体は── その素粒子の総数に比例した“より大きな質量”を持っていると同時に、それに比例した“より多くの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ))を周囲へ新たに放出する能力”を持っているはずである。
以上の考察より、“物体が質量を持っている”ということについて、次の仮説を立てた。
仮説2.3.1 ある物体が“質量を持っている”ことは、その物体の中のミクロの素粒子(ミクロのレベルで光速で運動し続ける素粒子)が、完成した“周囲の各種のヒッグス場”を変形させる過程によって、“重力子を放出させている”現象の総和である。
※ヒッグス場が(相転移によって)完成することにより── (ミクロレベルで光速で運動し続けている)素粒子は、重力子を放出させるようになると同時に、質量を獲得する。
つまり、ヒッグス場が相転移が完成する前は、現在のように“重力子を放出させない”と同時に、現在のような質量を持っていないことになる。
よって、ふつうは(=ヒッグス場の相転移がすっかり完了している場合は)、質量とは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を新たに放出させる能力である、と見なすことができきる。
(ヒッグス場の相転移の進展状態に関わらず── “「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を新たに放出させる能力”自体──そのポテンシャル自体は、素粒子が持ち続けていると考えられるので、“ふつうは〜見なすことができる”と書いた。 また、ヒッグス場の相転移の進展状態に関わらず、“カオスによるランダム運動”をする時点で、マクロの光速を失う可能性があると思われたので── 「マクロレベルでの光速を失うことが、質量の獲得である」という定義は、ふさわしくないと考えた)
※物体は、やはり、(ミクロレベルで光速で運動する)素粒子の総和に他ならない。
たとえ、マクロレベルで静止しているように見える物体であっても、ミクロレベルで見れば、光速で運動し続けている素粒子の総和であり、そのエネルギーが、まさに、mc2に相当していると考えられる。 (質量がもつエネルギーE=mc2の中に、なぜ、光速cが登場するかを以上の考察が示唆していると思われる)
したがって、例えば、太陽も、地球も、人も、自動車も、電車も、自転車も… 含めて、あらゆる大きな物体は、質量を持っている以上、たとえ、マクロレベルで見て静止しているように見えたとしても、ミクロの素粒子レベルで見れば、あらゆる方向に、光速で運動し続けていることになるので、周囲に一定の頻度で、重力子を放出し続けていることになる。
大きな物体は、マクロレベルで見た運動状態にかかわらず(加速していても、等速運動していても、静止していても…)、常に重力子を放出し続けていることになる。
この性質は、後に述べていくように、重力と加速度が等価であるためにも、ニュートンの万有引力の法則に従った形で重力が働くためにも、必要不可欠である。
また、次の仮説を立てた。
仮説2.3.2 物体が持っている質量エネルギー、「その物体を構成するミクロの粒子が、見かけ上光速を失いながら周囲の時空構造へ与える影響(各種のヒッグス場を変形させること)の総和」の影響が、プランクエネルギー(約1.2×1019Gev)を越えると、重力子を一定以上の高い頻度で放出できるようになる。
(→下記の考察《プランク定数、ブランクエネルギーについて》)
また、次の仮説を立てた。
仮説2.3.3 物体が、周囲に、新たに放出させている全「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の単位時間あたりの数は、その全質量の大きさに比例する。
これによると、例えば、プランク質量(約2×10-8kg)が、単位時間あたりに重力子を放出する頻度をn 個/sとすると、 m kgの質量は、 「m/プランク質量」個の、プランク質量を内在させていることになるので── 全質量mが単位時間当たりに放出する重力子の数= 「m/プランク質量」×n と、単純に計算できることになる。
具体的に、プランク質量(約2×10-8kg)は、1秒間に何個の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出するのであろうか?(=上述のnの値はなんであろうか?)
これがわかれば、あらゆる物体について、その全質量がわかるだけで、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出頻度が計算できることになる。
nの値を確定することは、今後の課題であると思われる。 (→下記の考察によると── n=c/2Lp となる。)
大きな物体が質量を持っている様子を、単純化したモデルで、図示すると次のようになる。
※中心の物体から、重力子(ピンクの四角で示した)と、“4角形”(縮みきったバネ)(紺色の台形で示した)が
放出されている様子を示す。
厳密には“4角形”(縮みきったバネ)=重力子ではないが、1つ“4角形”(縮みきったバネ)には、
必ず1つの重力子が対応しているので、“4角形”(縮みきったバネ)の数=重力子の数として
話を進めることができる。
※単純に図示してあるが、実際は、(決定論的カオスにしたがったランダムさで)3D空間のあらゆる方向に
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されていると考えられる。
(1つ1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」は、実際は、光速で無限遠まで進む)
したがって、上図は、ある一定時間内に新たに生じた重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布を
近似的に示していることになる。
※同心円の集まりとして図示してあるが、実際は、およそ“同心球面”の集まりが存在していると考えられる。
以下、これと同様の図は、およそ“同心球面”の集まりを表現しているものとする。
※考察1でも触れた「“素スピノール3つでカオス”によるランダムな運動」の作用もおおいに関連していると思われる。
この作用が、ミクロの素粒子による、ランダムな方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出を可能にし、
“長時間で均等にならされる”という“エルゴード性”が生じていると考えれば、つじつまが合う。
|
中心部に物体があり── そこから周囲に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を、ある一定の頻度で放出していると考えられる。
この状態が“物体が質量を持っている”(=物体の中の各“ミクロの素粒子”が、ミクロレベルで光速を保っていると同時に、物体全体がマクロレベルで静止してるように見える)ことに相当する。
※そもそも、各“ミクロの素粒子”が、“抵抗を受けながらも、ミクロレベルで光速を維持し続け、かつランダムな方向に重力子を放出し続ける”
という現象においては、「“作用反作用の法則”(ニュートンの運動の第3法則)」やエネルギー保存則が、(マクロレベルでの現象において成立しているように)普通に成立しているようには見えない。
なぜなら、各“ミクロの素粒子”が、“重力子というエネルギー”を放出し続けているのにかかわらず、
それぞれの素粒子が持っている、“ミクロのレベルの光速度”、質量エネルギー=mc2、 “新たな重力子の放出能力”が保存されるからである。
このことは、単に、「重力子はエネルギー保存則を破って生じる“仮想粒子”である」&「素粒子は、“素スピノール3つでカオス”によるランダムな運動の作用を持っている」&「ある質量を持つ物体から、“質量のない重力子”(だからこそ、光速で進む)が放出されているだけである」という3つのことがあるので問題ない── ということで、済むかと思われる。
詳細な検討は、今後の課題である。 (→下記の次の考察も関連 《連星系パルサー》《重力場、エネルギー、質量、非線形性、電磁場の線形性との比較》)
《重力の実体像》
ある物体は、原始ヒッグス場の“4面体”がある方向へ進むためには、わざわざ、“4角形”(縮みきったバネ)に変形しながら、苦労して進む必要がある一方──
すでに“4角形”(縮みきったバネ)となっている方向へ進むためには、その手間が不要となるので、比較的ラクに進むことが可能になると考えられる。
|
原始ヒッグス場の“4面体”があると──
|
= |
運動の際、抵抗を受ける
(ヒッグス場の基本構造の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間がかかる) |
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」があると──
|
= |
(運動の際、抵抗を受けないので)
その方向に運動しやすい
(ヒッグス場の基本構造の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省ける) |
つまり、原始ヒッグス場の“4面体”は、物質の運動に対して抵抗する働きを持っていることになる。
この「原始ヒッグス場の“4面体”が、物体の運動に対して与える抵抗」のことを、単純に“原始ヒッグス場抵抗”と呼ぶこととする。
すると、“原始ヒッグス場抵抗”が大きいほど、原始ヒッグス場の“4面体”が多く(=“4角形”(縮みきったバネ)の密度が小さく)、物体はその中を進みにくくなり── “原始ヒッグス場抵抗”が小さいほど、原始ヒッグス場の“4面体”が少なく(=“4角形”(縮みきったバネ)の密度が大きく)、物体はその中を進みやすいことになる。
|
“原始ヒッグス場抵抗”
|
大きい
|
小さい
|
|
進む物体が受ける抵抗
|
大きい
|
小さい
|
|
運動する物体
|
進みにくい |
進みやすい |
|
“4面体”
|
多い
|
少ない
|
|
「重力子&“4角形”
(縮みきったバネ)」
|
少ない
|
多い
|
例えば、質量Mを持つ物体Pが、次の図のように重力子を放出しているとする。
すると、他の物体Oは、この物体Pに近ければ近い場所にあるほど──
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高い場所にいる(=抵抗をもたらす“4面体”の密度が小さい場所にいる)ことになり、“原始ヒッグス場抵抗”が小さくなるので、他の物体Oは、物体Pに近づく方向にこそ運動しやすく(移動しやすく)なると考えられることになる。
例えば、図のような位置にある、同じ質量を持つ物体O1、O2、O3を考えれば、O1が一番、物体Pの方向へ運動しやすく(移動しやすく)、O3が一番物体Pの方向へ運動しにくい(移動しにくい)ことになる。
すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度がより高ければ高いほど、その方向へ運動する際の抵抗(=“原始ヒッグス場抵抗”)が少なくなっているので── その方向へ進みやすくなると考えられるのである。
まさに、このたりに“重力の実体像”にせまるヒントがあると思われた。 よって次の仮説を立てた。
仮説2.4.1 “原始ヒッグス場抵抗”がより小さい方への(=“4角形”(縮みきったバネ)の密度がより高い方への)運動しやすさ── これが、重力の実体である。
つまり、物体は、ただただ、“原始ヒッグス場抵抗”が、より小さくて、より動きやすい方向に動いている(移動しやすい方向に移動している)だけであり── その過程が、“重力という力によって引っぱられている”と観察されているに過ぎないことになる。
(=つまり、重力は、「“原始ヒッグス場抵抗”が大きい方から、小さい方へ進みやすいという傾向”によって、そこに存在しているように見える力」に過ぎないと言える)
“原始ヒッグス場抵抗”とは何か? これを次のように定義する。
“原始ヒッグス場抵抗”とは、「原始ヒッグス場の“4面体”を、わざわざ“4角形”(縮みきったバネ)にして進むのに要するのエネルギーの勾配(単位距離当たりの差)」のことである。
すると──
(ある物体が周囲に作る)時空は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高いほど、大きなエネルギーを蓄えていると同時に── (周囲の他の)物体が進むのに要するエネルギーが少なくて済むので、“原始ヒッグス場抵抗”は減っている。
逆に、(ある物体が周囲に作る)時空は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が小さいほど、小さなエネルギーを蓄えていると同時に── (周囲の他の)物体が進むのに要するエネルギーが多く必要になるので、“原始ヒッグス場抵抗”は増えている。
ということになる。
1つの原始ヒッグス場の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にするエネルギーは、仮に、E1とする。
(下記考察《プランク定数、ブランクエネルギーについて》によると、E1=Epである。Epは、プランクエネルギー。 以下、E1=Epとして、話を進める)
質量Mの中心から、r=2nLp離れた所にある、“厚さ2Lpの球殻”を考える。(nは整数、Lpはプランク距離(Lp≒1.616×10-35mである))
2Lpという長さには、原始ヒッグス場の“4面体”や“4角形”(縮みきったバネ)のサイズ、重力子のサイズ、であるという意味がある。
|
ある質量Mを持つ物体を中心とする、半径 r の“厚さ2Lpの球殻”を考える。
※図の“4角形”は、半径rの“厚さ2Lpの球殻”の中の「“4角形”(縮みきったバネ)」を表す。
|
|
※図のように、半径r=2nL pの球面の 外側の幅2L pの球殻を、
“半径r=2nL pの厚さ2L pの球殻”と定義することとする。
|
※たとえ“1cm”でも、r=2nL pの中のnの値は、n≒0.01m/2×( 1.616×10-35) m≒0.309×1033と非常に大きなものとなる。
重力子は、波長2プランク長(2Lp)で、(半径が2Lpだけ大きい球面内の)すぐとなりの原始ヒッグス場を、次々と伝播していくと考えられる。
よって、「質量Mの中心から r=2nLp離れた場所の、厚さ2Lpの球殻の中にある“4角形”(縮みきったバネ)の数NM」は、nの大きさ(rの大きさ)に関わらず、どこでも一定であると考えられる。
(下記の考察《量子化された重力、重力場の計算》によると、NM=2M/Mpである。は、Mは質量、Mpは、プランク質量)
よって、nに関わらず、NM個の“4角形”(縮みきったバネ)があり、その1つが最大Epのエネルギーを持っているので、それぞれの球殻がもつエネルギーは、NMEpとなる。
(より厳密には、しかし、転回している間は(転回周期の時間の中では)エネルギーは一定ではないので、その時間平均のエネルギーを考える必要がある。 その時間平均エネルギーの値は、単純に最大エネルギー振幅を1/2すれば求まり、Ep/2となる。 しかし、一方、各球殻に、“4角形”(縮みきったバネ)だけが存在するのは、特殊な例であり(下の左の図)、共転回の間、“4面体”の変形が、二つの球殻にまたがっているのが大部分である(下の右の図)。
|
※図の“4角形”は、プランク質量Mpから放出された“厚さ2Lpの球殻”の中の「“4角形”(縮みきったバネ)」を表す。
|
|
※実際は、図のように、共転回の状態にあるものがほとんどである。
※なお、共転回のペアが持つエネルギーの和は、一定のE pである。
|
したがって、「エネルギーの平均値がEp/2である“4面体”の変形」は、各球殻に“2NM個”存在するという方が、より正確であり── つまりは、それぞれ球殻が持つエネルギーの時間平均は、Ep/2×2NM=NMEpと計算できることになる。(左の図は、これから変形を開始するエネルギー0の完全な“4面体”とペアを作っている、とみなしてもよいと思われる))
その上で、さらに、半径r=2nLpの厚さ2Lpの球殻が持つエネルギーの球面平均の値を計算してみる。
r=2nLp離れた所にある厚さ2Lpの球殻の全面積は、4πr2=16πn2L2pであり── そのうち、“4角形”(縮みきったバネ)あるいは、変形している“4面体”が占める面積は、およそ、(2Lp)2×2NMである。“4角形”(縮みきったバネ)の部分のエネルギーの時間平均がEp/2であり、それ以外の場所は変形していない“4面体”であり、そのエネルギーは、相対的に0である。
よって、球殻のエネルギーの時間&球面平均の近似値を近似的なE平均と書くことにすると
近似的なE平均={(2Lp)2×2NM×(Ep/2)+ (4πr2−(2Lp)2NM)×0}/4πr2
=NMEp/4πn2
と求まる。
それぞれの“厚さ2Lpの球殻が持つエネルギーの平均値”は、nの値によって異なっており── それをn=1の時の値から順次、足しあわせていくと、およそ、重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)に相当するものになる。 つまり、次の図のように、重力ポテンシャルエネルギーは、中心から遠ざかるにつれ、階段状に増加することになる。
※質量Mの中心からr=2nL pの距離の地点で、n番目の球殻が外側に追加されるごとに、
2L p幅の球殻が持つエネルギーが、時空の中に新たに追加されること、
そして、その総和が、およそ重力ポテンシャルエネルギーに相当することを示している。
球殻は、厚さ2Lpである。
この質量の中心から2Lpだけ遠ざかるごとに、「エネルギーの平均値E平均=NMEp/4πn2 」 の中のnが1増え、その分だけ、(その中心から遠ざかる方向において)周囲の時空のエネルギー=重力ポテンシャルエネルギーが増加(追加)すると考えられる。
(近似的E平均=NMEp/4πn2の値を、1からnまで足し上げると── これは、r=2nLpの地点での重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)に、近似的に等しくなると考えられる。(下図参照、詳細は、下記の考察《量子化された重力、重力場の計算》))
※オレンジの高さの部分が、近似的なE平均=NMEp/4πn2の値であり、それらを1からnの分まで足しあわせると、それがr=2nLpの地点での重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)に、近似的に等しくなると考えられる。
|
今、求めたいのは、力(重力)である。
その力=重力とは、“原始ヒッグス場抵抗”──「原始ヒッグス場の“4面体”を、わざわざ“4角形”(縮みきったバネ)にして進むのに要するのエネルギーの勾配(単位距離当たりの差)」のことである。
飛び飛びの値をとるので、“無限小”を扱う“微分”は使えない。
しかし、“無限小”の代わりに、何を使えば良いだろうか? それが、まさに“2Lp”にほかならないと考えられる。
重力ポテンシャルエネルギーの変化量を、“2Lp”で、エネルギー平均の差を割れば、勾配が求められると思われる。
なぜなら、例えば、もし、次のようなnによらず、重力が一定の重力場が存在する場合── “2Lp”でエネルギー平均の差を割れば、勾配が求まるからである。
また、“重力ポテンシャルエネルギーの変化量”とは、厚さ2Lpの球殻のエネルギーの時間&球面の平均値に他ならないのであった。
よって、r=2nLp の地点での勾配(傾き)=重力は、r=2nLp の厚さ2Lpの球殻が持つエネルギーの近似的な平均値、近似的なE平均=NMEp/4πn2を2Lpで割れば求まることになる。
この重力ポテンシャルエネルギーの勾配(上図のピンクの斜線の傾き)を、(“電位勾配”に習って)“重位勾配”と呼ぶことにする。
この“重位勾配”が、「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”の差」、つまりは、重力場に相当することになる。
“重位勾配”=(NMEp/4πn2)×(1/2Lp) (=NMEp/8πLpn2)
※この“重位勾配”の概念を例えば、全く同じ質量をもつAとBが2つ近くにあった場合にどうなるかを、次のように説明できる。
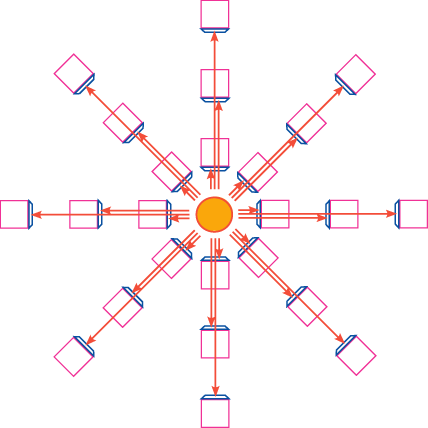 |
+
|
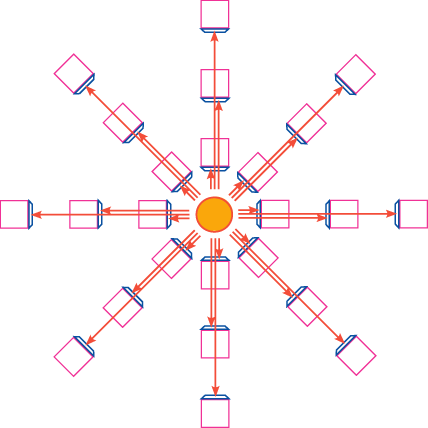 |
|
A
|
|
B
|
|
※より正確には、“4角形”(縮みきったバネ)は、3次元方向に2L pの間隔で放射される。
(その結果、厚さ2L pの球殻を作っているようになる)
Aは、Bが作る“重位勾配”(=重力場)にしたがってBの方向へ移動するだろう。
Bは、Aが作る“重位勾配”(=重力場)にしたがってAの方向へ移動するだろう。
その結果、AとBは互いに引き合うように見える形になる。
そして、最終的に1つになる。
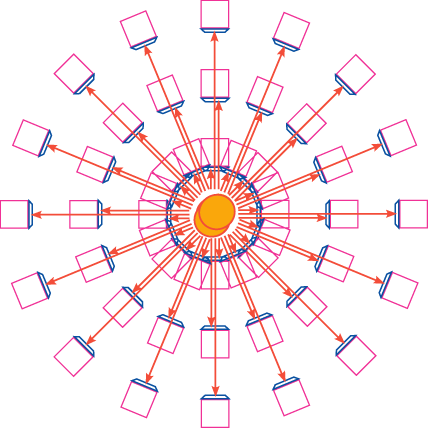 |
|
A&B
|
|
その結果、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度の変化量──“重位勾配”は、(質量欠損がなければ)単に2倍になるだけであろう。
それは、質量に比例して重力が大きくなるというニュートンの万有引力の法則の数式が示す内容と合致する。
※“重位勾配”が大きいほど、別の物体にとって“4面体”から“4角形”(縮みきったバネ)へわざわざ変形する手間が省かれる(運動の抵抗が減る)ので、よりその方向へ移動しやすくなる。
それは、ある物体の周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高ければ高いほど、重力が大きくなることを意味している。
(※「厚さ2Lpの球殻が持つエネルギーの平均値E平均」は、“重力子の面密度”に比例し── “重位勾配”は、“重力子の体積密度”に比例すると言える)
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高いことは、質量が大きく、重力子を新たに放出する能力が高くなっていることを意味しているので── 以上の説明は、“質量が大きいほど重力が大きくなる”というところのニュートンの“万有引力の法則”とも合致する。
EMOESによる“重位勾配”の導き方(重力の発生理由の説明)──“重位勾配”=(NMEp/4πn2)×(1/2Lp)と、ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2の関係は、どのようになっているのだろうか?
重力定数Gは、G=2πc3L2p/h と表記できる。
(プランク定数h、光速c、重力定数Gを使った、プランク距離を求める式、「Lp=(hG/2πc3)1/2」を変形して求まる)
この「G=2πc3L2p/h」と、「r=2nLp」を活用するとニュートンの万有引力の法則の式は、次のように変形できる。
ニュートンの万有引力F
=GMm/r2
=(2πc3L2p/h)×(Mm/4L2pn2)
=(2πcLp/h)×c2Lp×(Mm/4L2pn2)
=(2πcLp/h)×Mc2×(Mm/4Lpn2)
(「プランクエネルギーEp=hc/2πLp」より(詳細は、下記の考察《プランク定数、ブランクエネルギーについて》にて)、
「プランク質量Mp=h/2πcLp」と表記できる。
また、E=Mc2=EpNM(=Ep/2×2NM(=“4面体”のエネルギーの平均ד4面体”の変形の数))である。
これらの「プランク質量Mp=h/2πcLp」と、「Mc2=EpNM」を活用すると、ニュートンの万有引力の法則の式は、さらに次のように変形できる。)
=(1/Mp)×(EpNM)×(m/4Lpn2)
=(EpNM/4Lpn2)×(m/Mp)
=(EpNM/4Lpn2)×(Nm)
(「Nm=m/Mp」である)
ここで、上で求めた「近似的な“重位勾配”=NMEp/8πLpn2」とを比較する。
ニュートンの万有引力F =(質量Mが作る近似的な“重位勾配”)×2π×Nm
となる。
(×Nm)は、 「近似的な“重位勾配”=NMEp/8πLpn2」×2πは、“プランク質量1つ”に対して働く重力であることを意味する。
この2πとは何か?
次元解析上、無次元であるようなので、単純に考えて、『「質量Mが作る近似的な“重位勾配”」を「質量Mが作る正確な“重位勾配”」にするための係数である』ということでいいだろうと思われる。 だとすると、質量Mが作る正確な“重位勾配”が、「NMEp/4Lpn2」であるということであり── ここに2Lpをかけたところの「NMEp/2n2」が、厚さ2Lp球殻が持つ正確な平均のエネルギーであるということになる。 それとも、考察のどこかに、もっと修正すべき点があることを意味しているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
いずれにせよ、ニュートンの万有引力の法則F=GMm/r2は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のパラダイムでは、次のように表記できることになる。
|
“ニュートンの万有引力F”=GMm/r2
=(EpNM/4Lpn2)×Nm
|
※r=2nLpの地点での重力である。
※「Nm=m/Mp」、「NM=M/Mp」である。
それぞれの値は、それぞれの質量が、球殻の中に存在させることの出来る重力子の数であると言える。 |
Mやmをそのまま用いると、次のようになる。
|
“ニュートンの万有引力F”=GMm/r2
=(Mc2/4Lpn2)×(m/Mp)
|
※r=2nL pの地点での重力である
※なお、EpNM=Mc2の関係式、アインシュタインのE=Mc2の意味を教えてくれる式と言うこともできるかもしれない。
つまり、Mc2は、プランクエネルギーEpがNM個分のエネルギー(=重力子NM個分のエネルギー)に相当しているということである。(詳細は、下記にて)
これらを、ニュートンの万有引力Fの“EMOES表記”と呼ぶこととする。
このニュートンの万有引力Fの“EMOES表記”は、「なぜ、重力が存在するか」を説明していると言える。
また、このニュートンの万有引力Fの“EMOES表記”には、連続で微分可能な“距離r”が消失しており、プランク距離Lpとそのn倍(整数倍)だけが長さとして含まれる。
重力を量子化している式の1つであると言えると思われる。
※以上の考察は、“量子化された重力ポテンシャルエネルギー”について考える際のよりどころとなる。
重力ポテンシャルエネルギーを数式でどのように表されるか”についての詳細は、下記の考察で行なう。
(→《量子化された重力の計算》)
ニュートンは、重力の働き方を数式化することに成功したが、「なぜ、重力が働くか?」「重力の正体とは、何か?」については、述べていない。
以上の考察は、これらの基礎的な問いに、答えの1つを提示できる可能性があることを示唆していると思われる。
一方、アインシュタインは、重力を“時空の曲がり”の所産であると説明したしたが、そもそも「なぜ、“時空の曲がり”が生じるか?」「“時空の曲がり”の正体とは何か?」については、述べていない。
次に、“時空の曲がり”について、考察する。
《“時空の曲がり”&重力場の実体像》
アインシュタインは、一般相対性理論によって、重力は“時空の曲がり”によって生じる(重力場は“時空の曲がり”である)と説明した。
しかし、“時空の曲がり”という表現は、それだけでは、十分な表現ではない(or 比喩にすぎない)と思われる。
なぜなら、(“2D平面の曲がり”は、確かにイメージできるが)、“3D空間の曲がり”そのものを、直接、はっきりとイメージすることが困難だからである。
※イメージすることが困難だっだからこそ、リーマン幾何学、リーマン曲率テンソル… という、抽象的な数学(数式)の力を借りて、表記することとなったと思われる。
“幾何的な実体原理”や“シンブル一様化原理”によると、重力という名の基本的な“自然(nature)”がイメージ不可能な実体からなりたっているとは、考えにくい。
つまり、このことは、“時空が曲がり”という表現の背後に、“時空の曲がり”と解釈できるようななんらかの(イメージ可能な)実体がひそんでいると考えるべきであることを示唆しているのである。
この“時空の曲がり”と解釈できる重力場の実体について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次のような説明する。
重力場を生じるものの実体とは、「原始ヒッグス場の“4面体”と「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和」である。
それは、次のような性質から導かれる説明といえる。
|
原始ヒッグス場の“4面体”があると──
|
= |
運動の際、抵抗を受ける
(ヒッグス場の基本構造の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間がかかる) |
|
|
|
|
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」があると──
|
= |
(運動の際、抵抗を受けないので)
その方向に運動しやすい
(ヒッグス場の基本構造の“4面体”を
“4角形”(縮みきったバネ)に変形する手間が省ける) |
以上をふまえ、もう一度、次の図を見る。
質量が大きいほど、周囲の「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」も大きくなり、重力が大きくなることが読み取れる。
「〜 電場の強さEは、電場の向きの長さ1mあたりの電位差を表していることがわかる。 このことから、電場の強さを電位勾配ということがある」(『新しい高校物理の教科書』講談社ブルーバックス)に習うと──
「重力場の強さは、重力場の向きの長さ1mあたりの“重位差”を表している」ことになる。 また、「この重力場の向きの長さ1mあたりの“重位差”が“重位勾配”である」といえる。 (※“重位”=重力ポテンシャルエネルギーであると考えられる)
そして、この「重力場の向きの長さ1mあたりの“重位差”」=“重位勾配”の実体が、まさに、「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」であると考えられるのである。
|
重力場の強さ(=重力)
|
重力ポテンシャルエネルギー |
|
=「重力場の向きの長さ1mあたりの“重位差”」
=“重位勾配”
=「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」
|
“重位”
|
よって、以上が正しければ、次の結論が得られる。
結論2.1 アインシュタインが“時空の曲がり”と呼んだところの“重力場”の実体とは、「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」である。
したがって、重力場が“時空の曲がり”であるならば── “時空の曲がり”の正体は、「“4角形”(縮みきったバネ)の単位距離当たりの球面密度の変化量」であるということになる。
しかし、そもそも、「重力場が“時空の曲がり”である──」 とは、どういうことを意味しているのだろうか?
結論から言うと、下記の考察《等速運動と特殊相対性理論》)説明するように── 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度」が高いほど、「時間の流れが遅くなり、空間は膨張する」ことを意味していると思われる。 つまり、「時間の流れが遅くなり、空間は膨張する」が、“時空の曲がり”が本来、意味していることであると思われる。
つまり、重力場=“重位勾配”の総和の実体が、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和の所産である一方──
“時空の曲がり”=「時間の流れの遅延&空間の膨張」の総和の実体も、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和の所産であることになる。
重力場と“時空の曲がり”の関係を結びつけるミッシングリンク── それが、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和なのである。
「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和こそが、重力場も“時空の曲がり”も、両方を説明できる本質的な実体なのである。
この「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和こそが、重力場=“時空の曲がり”というアインシュタインの比喩的な説明を、理解するカギだといえる。
(「重力場とかけて、“時空の曲がり”と解く。 その心は、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和である──」ということになる)
※以上の説明が正しければ、“時空の曲がり”&重力場と解釈できるものの実体像を、(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和として)3D空間の中においても、比較的しっかりイメージできると思われる。
重力場(=“重位勾配”)の働きのおかげで、地球は、太陽に引き寄せられ続け── 公転し続けていることになる。
一方で、この“時空の曲がり”のおかげで、時間の流れが遅くなり、空間が膨張する。
そして、重力場と“時空の曲がり”は、同一の実体によって担われているので── 「重力場とは、“時空の曲がり”である」という比喩めいた表現も可能となり、間違いではなくなることになる。
しかし、それは、本質を見失わせうる(誤解を招きうる)、曖昧な表現だと言えるかもしれない。
※たとえ、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が大量に通過していたとしても── もし、そこに“勾配”or“密度の変化(密度差)”がなければ、重力場も“時空の曲がり”もなく、重力も生じないことになる。 例えば、人が地球に引っ張られるのは、その方向にのみ“勾配”(“密度の変化(密度差)”)があるからである。 それと直角な方向(水平な方向)には、“勾配”(“密度の変化(密度差)”)がないので── (たとえ重力子が大量に存在していたとしても)力が生じることはない。
そして、以上のもとに、次の仮説を立てた。
仮説2.4.2 アインシュタインの一般相対性理論の数式は、「重力子&原始ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)の挙動」の総和を表現している。
※正しければ、アインシュタインの一般相対性理論が説明する世界は、すべて、「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動の総和」として、解釈できることになる。
※スピノール2つ分で、ベクトルが生まれるように(例…光子(素スピノール2つ)から電場や磁場のベクトルが生まれる)── ベクトル2つ分で、テンソルが生まれるということでいいのだろうか? (例…重力子(光子2つ)から、時空のひずみ“テンソル”が生まれる) 今後の課題である。
《重力場と“重力線”》
重力場=“重位勾配の総和”(「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の挙動の総和」の所産の一例)を、図で表現するために── 電気力線や磁力線に習い、“重力線”を考えることができる。
当然、“重力線”上だけに“重位勾配”があるわけではなく、実際は、(あらゆる方向に「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放射状に放出されているので)あらゆる場所に“重位勾配”が存在していると考えられる。
また、球面の面積は半径の2乗に比例する(球面積S=4πr2)ので、物体から距離が大きくなるほど、距離の2乗に反比例して、“重力線の密度”が減ることになる。
つまり、中心の物質に近づくほど、物体から距離の2乗に反比例して、(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が増えるので)“重位勾配”、つまりは重力が大きくなると考えられる。
この“重力線の密度”&“重位勾配”の性質は── ニュートンの万有引力の法則の式と合致する。
つまりは、“重力線の密度”=“重位勾配”の大きさ=“重力の大きさ”=“重力場の強さ”=「“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の球面密度=“時空の曲がりの強さ”ということになる。
“重力線の密度”が高いほど、“重位勾配”、重力、“時空の曲がり”… が大きくなることは── 電気力線や磁力線の密度(単位面積あたりの本数)が高いほど、電気力や磁力が大きくなることと同様である。
“等電位面”と同様に── “等重位面”を考えることもできる。
※実際は3次元に放射されているので、 “等重位面”は、実際は球面である
“等重位面”の間隔は、物体に近づくほど狭くなる。 それは、物体に近づくほど、“重位勾配”=重力が大きくなることと合致する。
※“等重位面”とは、重力ポテンシャルエネルギーが等しい面であるとも言える。
※質量が小さいほど“重力”や重力場&“時空の曲がり”が小さくなるように── “重力線の密度”も小さくなる。
逆に、質量が大きいほど“重力”や重力場&“時空の曲がり”が大きくなるように── “重力線の密度”も大きくなる。
※“重力線”の密度が高いほど、物体から放出される「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が、高くなる。
もし、同じ質量を持つ物体(天体を含む)の“サイズ(大きさ)”が変化すれば── 物体の周囲の、“重力線”の密度=重力場の大きさ=“重位勾配”の大きさ=“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度=“時空の曲がりの大きさ”も、変化する。
物体(天体を含む)のサイズが小さくなる(コンパクト化する)ほど、物体周囲の“重力線”の密度が高くなり、周辺の重力、“重位勾配”、“4角形”(縮みきったバネ)の球面密度、時空の曲がり…が大きくなっていることが読み取れる。
なお、上図では、質量の大きさはどれも同じなので、重力子が放出される頻度は、どれも同じである。
しかし、物体がコンパクト化するほど── “重力線”の密度が高い領域が増えることが読み取れる。
※これは、“時空の膨張(宇宙の膨張)”と関連していると考えられる。(→考察3、考察13)
《重力子の働きと慣性》
重力子の働きと“慣性”の関係について考察する。
ニュートン力学と、特殊相対性理論によると──
宇宙空間上で静止している物体に力を加えると、物体は加速運動し、運動エネルギーを増すと同時に、質量エネルギーを増す。 その加速される際、静止していた物体は、もとのように静止し続けようとして抵抗する。 その“抵抗、動かしにくさ…”が慣性である。
そして、いったん加速した物体は、力を加えるのをやめても、等速直線運動を続ける。 その“勢い、はずみ、止めづらさ…”も慣性である。
特殊相対性理論によれば、ある静止している物体が加速運動すると、運動エネルギーを増すと同時に、質量エネルギーを増す。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば──
静止した物体を動かし始める際の“抵抗、動かしにくさ…”といった“慣性”が生じるのは、まさに、原始ヒッグス場の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形することが必要になるからだと考えられる。 いったん、“4角形”(縮みきったバネ)まで変形されれば、重力子とともに“4角形”(縮みきったバネ)が、光速で運動方向に放出されると考えられる。 そして、まさに、その重力子の放出能力アップが、「運動エネルギーを増すと同時に、質量エネルギーを増す」ことと合致する。
次の仮説を立てた。
仮説2.5.0 静止していた物体が加速しようとすると── 元々の静止質量由来の重力子の放出の他に、運動方向に新たに重力子の放出が始まるようになる。
正しければ、この過程が“動かしにくさ”という意味での“慣性”の実体であると同時に── 特殊相対性理論が説明する、運動エネルギーの増加とともに生じる質量エネルギーの増加の実体であることになる。
そして、物体を加速し、新たに“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させる過程での抵抗力が、慣性力の実体である。
そして、力を加えるのを止めても、いったん加速した物体は、等速直線運動をしている間も、新たに始まった重力子の放出をそのまま保ち続けると考えられる。
ところで、なぜ、等速直線運動が可能になるのまであろうか?
原始ヒッグス場の“4面体”を変形させる必要性は、どこまでもいつまでも続くはずではないのか?
よって、等速直線運動をしている間も、なんらかの方法で、物体の進行方向にある原始ヒッグス場の“4面体”を次から次へと““4角形”(縮みきったバネ)に変形させ続けるような何らかの“しくみ”が存在することが予想された。
そこで、“とまりにくさ”という意味での慣性を生む“しくみ”の実体像について、次の仮説を立てた。
仮説2.5.1 いったん等速運動を始めた物体は、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を、次から次へと、進行方向へ生じ続けるようになる。
その物体の進行方向と同じ方向に進む重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和は“流れるプール”のような働きを生む。
本当に、そのようなことが可能なのだろうか? 以下で、そのことについて考察する。
(ミクロレベルで光速で運動し続けている)素粒子○が、多数集合して構成される静止した物体(静止質量m0)を考える。
それを、下のような単純化したモデルを使って表記する。
オレンジ色の○が、個々の素粒子である。
※“4角形”(縮みきったバネ)が放出されている様子を示す。
| ※上図は、64個の |
|
が、1つの物体を構成している様子を示す。 |
※実際は、3Dのランダムな方向に重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を放出する。
「光速で“4つの方向にしか運動できない”ミクロの粒子が想定されている」と考えることが出来る。 |
物体が(マクロレベルで見て)静止しているように観察されたとしても、(○の中に多数存在する)ミクロレベルの素粒子が、光速で運動し続けているので── 物体から重力子が放出され続ける。
それが、上記の物体が持つ、静止質量エネルギーm0c2の実体であると考えられる。
実際は、○の中の素粒子たちが、ミクロのレベルで光速で運動し続けているおかげで重力子が放出されているわけであるが── 大雑把に見て、“○の微小な運動が、原始ヒッグス場の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させて、重力子を、ある頻度で放出している”と解釈することができる。
この物体(静止質量m0)が、(光速よりずっと小さい)速度vで、等速直線運動をしている状態について、次のように仮説を立てた。
仮説2.5.2 ある物体(静止質量m0)が(光速よりずっと小さい)速度vで運動するようになると、(もとからあったm0c2のエネルギーに相当する重力子の他に)新たに“m0v2/2”のエネルギーに相当する、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を運動方向に放出できるようになる。
※光速運動と原始ヒッグス場の相互作用により、m0c2のエネルギーに相当する重力子を放出されるのに、
なぜ、単純に速度vの運動と原始ヒッグス場の相互作用により、m0v2のエネルギーに相当する重力子が放出されず、その1/2だけで済むようになるのだろうか?
たしかに、もし、個々の素粒子(質量をm素と表記することとする)が単独で、 速度vで進むならば、m素v2に相当する重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を放出するであろうと予想できる。
|
|
|
※単独の場合。
※m素v2に相当する「(光速で進む)重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、新たに運動方向にのみ放出されると考えられる。 |
しかし、素粒子の集団が運動する場合は異なることが起こると考えられる。
物体が速度v で運動するとは、その素粒子の集積が、一緒に速度vで運動することに相当する。
m素が単独で進んだ場合、800回重力子を放出する距離をL800とすると──
物体の集合がL800だけ進む際、それぞれの素粒子が何回重力子を放出するかを考えてみる。
|
速度vで、等速直線運動
|
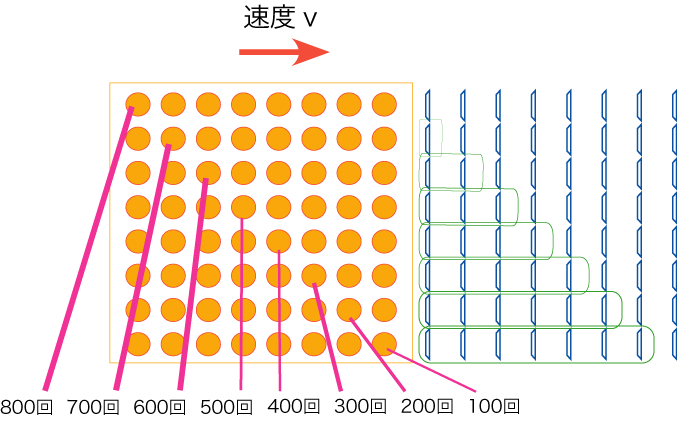 |
※例えば左端の素粒子が800回重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を放出する必要があるのに対し、
例えば、右端の素粒子は、100回の放出で済むようになると考えられる。
なぜなら、後ろから他の素粒子が放出した「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が流れてくるので、その分、わざわざ自分で「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する手間が省けるからである。 他の位置にある素粒子も同様である。
※緑で囲った部分は、後ろから流れてくる重力子&“4角形”(縮みきったバネ)に相当する。
|
以上のことをグラフにすると次のようになる。
つまり、この面積は、三角形であるので── “それぞれすべてが800回放出する”と考える場合の、ちょうど1/2だけの重力子が、(素粒子がまとまって運動する場合には)放出されることになる。
つまり──
仮説2.5.2 ある物体(静止質量m0)が速度vで運動するようになると、(もとからあったm0c2のエネルギーに相当する重力子の他に)新たに“m0v2/2”のエネルギーに相当する、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を運動方向に放出する。
と合致する。
一方、下の図から、その運動方向に生じる重力子のエネルギー“m0v2/2”が“時空の流れるプールの効果”に与する様子が詳しく理解できる。
速度vで、等速運動 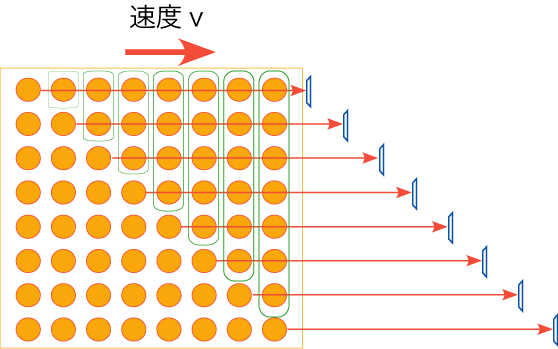 |
※上図の左から1番目の列の列の○が0個の重力子の作用を受けるのに対し、
左から2番目の列の○が1個、左から3番目の列の○が2個、左から4番目の列の○が3個…
というように、一般に右からn番目の列の○がn−1個の重力子の作用を受けることになる。
もし、nがとても大きな数になれば、n番目は、n個の重力子の作用を受ける見なしてよいと
考えられる。 これをグラフにすると次のようになる。
|
このグラフは、その運動方向に生じている「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」のエネルギー“1/2m0v2”が、物体のどこに“再投資”されることを意味する。
そして、この再投資される“m0v2/2”と── 物体の“運動エネルギー”m0v2/2は、ぴったり等しい。
まさに、このことによって、等速直線運動が実現していると考えられる。
(つまり、「流れるプール効果の作用」という“再投資”が、等速直線運動を実現させていると考えられる)
そもそも、「流れるプール効果の作用」とは何であろうか?
単純に、すべての重力子が通過する方向に“流れるプール効果”が生じるのではない。 なぜなら、例えば、太陽から放出された重力子は、地球を通過しているが、重力子が進む方向に“流れるプール効果”が生じていないからである。
太陽から放出された重力子は、重力場(“重位勾配”)を形成し、地球を太陽に引っ張る働きをする。
“重位勾配”の実体は、周囲の原始ヒッグス場の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)にする手間が省ける程度の差である。 ( 太陽に近い側が大きく、太陽から遠い側が小さい)
“時空の流れるプール効果”が生じるのも、“重位勾配”に基づくのではないかと考えた。
そして、そういう目で、この図を見ると── 右に行くほど、物体が周囲の“4面体”を“4角形”にする手間が省ける程度を示す、負の“重位”が大きくなっていることを示していると解釈できることに気づいた。
ここに生じた“重位勾配”によって、物体が引っ張られることが、“時空の流れるプール効果”の実体に相当するのである。
つまり、“時空の流れるプール効果”がしてくれることは、原始ヒッグス場の中を運動する際の抵抗を0にしてくれることであることになる。
そして、この働きが、等速運動を実現してくれることになる。
つぎのようになる。
いったん、速度vの等速運動を始めると──
『速度vで等速運動
→m0v2/2分の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出
→そのエネルギーが物質の運動へ再投入(「流れるプール効果の作用」の効果が生まれる)
→原始ヒッグス場を進む際の、抵抗が0になる。
→ 『速度vで等速運動
→m0v2/2分の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出
→そのエネルギーが物質の運動へ再投入(「流れるプール効果の作用」の効果が生まれる)
→原始ヒッグス場を進む際の、抵抗が0になる。
→ 『速度vで等速運動
…
を繰り返し続けることになると考えられる。
つまり、まさに、この「流れるプール効果の作用」が、等速直線運動を可能にする“しくみ”の本質であると考えられる。
この「流れるプール効果の作用」のおかげで、原始ヒッグス場の“4面体”の抵抗の中を、一切の力を新たに加えることなく(外から新たなエネルギー投入することなく)、等速直線運動を続けることが可能となる。
これが、“とまりにくさ”に関連した慣性を生む“しくみ”の実体ということになる。
※静止状態に力を加え、いったん、ある速度に達してしまうと、その後は、上記のような“時空の流れるプール効果”の作用のおかげで等速運動し続けるようになる。
この“時空の流れるプール”の働きのおかげもあって、地球は、公転し続けていることになる。
地球が太陽に引き寄せられ続けるのは、“時空の曲がり”(“重位勾配”、重力場)のおかげであり、
地球が太陽の回りを慣性で、進み続けるのは、“時空の流れるプール”のおかげである、と言える。
※いったん、あるスビードを持つに至った── 自動車(や自転車)、スーバーマーケットのカート、カーリングの石… アクセルを踏まなくても、ペダルをこがなくても、手を離しても… ほとんど、そのままの勢いで進み続けることは、この“時空の流れるプール”のおかげであることになる。
※ある質量を持つ物体が減速する際には、運動エネルギーが減ると同時に、運動方向への「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出能力が減るので、“止まりにくさ(勢いor はずみ)”を支えていた“流れるプール効果”が低下することになる。
※放出される重力子&“4角形”(縮みきったバネ)のエネルギーがm0v2/2となるのは、vが光速cに比べてずっと小さい時にのみ成立すると考えられる。
もし、vが光速cに近くなってくると、それによって生じる重力子のエネルギーは、m0v2/2よりも大きくなり、「m0c2(1−v2/c2)1/2−m0c2」となると考えられる。 すると“流れるプール効果”も、その大きくなる。 その際も、等速運動は、やはり同様なしくみで実現すると考えられる。
※慣性には、2つの部分がある。 静止している物体の動かしにくさと、一度動き始めた物体の止まりにくさの2つである。
従来のヒッグス場による質量獲得について説明は、(粘つく“納豆やアメ”の比喩ように)“動かしにくさ”の部分だけに焦点があてられていたようである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、慣性の“動かしにくさ”と“止まりにくさ”の両方を説明できる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では── 慣性の“動かしにくさ”とは、ある質量を持つ物体が加速する際に、新たな重力子の“4角形”の放出が追加される過程での“抵抗力”として説明し── 慣性の“止まりにくさ”とは、ある質量を持つ物体が、等速運動している間に、進行方向に生じる重力子の“4角形”による“流れるプール効果”によって説明する。
“動かしにくさ(抵抗力)”のみでなく、“止まりにくさ(勢いor はずみ)”も、説明できるので── “EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、従来のヒッグス場による質量獲得の説明を、より改善できる可能性を持つと思われる。
《ニュートンの運動の第2法則(F=ma)》
上では、慣性──ニュートンの運動の第1法則を“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、説明したことになる。
それでは、ニュートンの運動の第2法則(F=ma)を説明できるであろうか?
質量mの物体に、ある一定の大きさの力Fを加えながら、距離lだけ移動したとする。
この物体に外から加えられたエネルギー(仕事)は、力×距離で、Fl となる。
その結果、物体が速度v、になったとすれると、この物体は、1/2mv2 の運動エネルギーを持つことになる。
なお、この、1/2mv2の運動エネルギーは、上記で述べたように、新たな“重力子の放出能力”
(=新たに、“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形できる能力)に他ならないと考えられる。
この、「新たな“重力子の放出能力”である運動エネルギー」は、「外から加えられたエネルギー(仕事)Fl」に等しいはずである。
つまり、 Fl = 1/2mv2 となる。
これを近似的に時間tで微分できるものとし、両辺を時間で微分してみると── Fv = mv×a となる。
(力Fは一定であり、光速より小さい速度では、質量mは、定数とみなせるので──)
つまり、F=ma となるので、ニュートンの運動の第2法則が導かれたことになる。
よって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によって、ニュートンの運動の第2法則を説明できたことになる。
※これらのことは、ニュートンの運動の第1法則と第2法則が、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)というアプローチによって統合されることを意味しているのかもしれない。詳細な検討は、今後の課題である。
《等価原理》
アインシュタインの等価原理とは、「加速運動と重力が等価である」という原理である。
自由落下する物体を考える。
自由落下する場合には、(アインシュタインの等価原理により)、慣性力(加速運動)と重力は、完全に打ち消し合う。
自由落下する物体が、大きな質量を持つ物体に近づくほど重力──“重位勾配”──が大きくなり続ける。
それは、質量を持つ物体に近づくほど、“重力線”の密度が高くなるからであり、物体から放出される重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度が大きくなるからである。
一方、その物質の方へ自由落下する物体は、加速運動をし続けるので、その運動に伴い“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変換させて、進行方向に重力子を放出させる頻度を増し続けながら落下する。
(物体が加速する際、新たに“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させる過程での抵抗力が、慣性力の実体である)
大きな質量を持つ物体から放出される重力子による影響(重力)と、自由落下しながら進行方向に放出される重力子による影響(慣性力)は、ピッタリと打ち消し合う形となる。
(これが、アインシュタインの“等価原理”の実体像であると考えられる)
その結果、落下する物体は、見かけ上、いっさい相手から重力子を受け取りも、放出もしていない状態と同じになる。 それが、“無重力状態”として観測される。
つまり、慣性力(加速運動)と重力が、ともに重力子の放出で説明できることは、アインシュタインの等価原理(この慣性力と重力(重力場)は全く等しい)と合致していると言える。
※ある質量Mの物体が、観測者の方に向かって速度Vで等速運動している系を考える。
前項《重力子の働きと慣性》では、等速運動している物体から、重力子が放出されていることをのべた。
しかし、もし、ある質量Mの物体が、観測者の方に向かって速度Vで等速運動しているときには── “もとの質量M”がもたらす重力より重力が大きくなることはないと考えられる。
(なぜなら、等速運動している限り、その運動によって物体から放出される重力子の総和に、新たに“重位勾配”が生じることはないからである)
逆に、もし、ある質量Mの物体が、観測者の方に向かって加速度aで加速運動しているときには── “もとの質量M”がもたらす重力よりも重力が大きくなると考えられる。
(なぜなら、加速運動によって、新たに物体から放出される重力子の総和には、“重位勾配”が生じていると考えられるからである)
このことも、“加速運動と重力が等価である”ことを示している例であると思われる。
《連星系パルサー》
『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』によると、「アインシュタインは、1915年に発表した一般対性理論の中で加速運度している物体は、重力波の形でエネルギーを放出すると予言した。」とのことである。
この予言は、重力波の実体が重力子であると考えれば、「加速することによって、新たに重力子が放出されるようになる」と説明する“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)と、おおよそ合致すると思われる。
ただし、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、加速運動している物体のみならず、見かけ上、全く静止している物体からも、重力子が放出され続けていることを示している。 このことは、次のように考えるとつじつまが合うと思われる。
ある物質をミクロのレベルで見れば、素粒子は光速で運動し続けており、その方向転換(加速運動)の際、原始ヒッグス場を変形させるように働きかけている。
素粒子の数が、ある閾値を越えると重力子を放出するようになる。 つまり、ある物質が質量をもっている場合、その物質の中のミクロのレベルの素粒子の“加速運動(方向転換)”の総和が、重力子を放出し続けていると言え── このことも、「加速運度している物体は、重力波の形でエネルギーを放出するという」アインシュタインの予言と合致していることになる。
(そして、「マクロのレベルで加速運動している物体」のみならず、「マクロのレベルで見かけ上、静止している物体(等速直線運動している物体)」からも、常に重力子が放出されているからこそ、重力も働くし、等価原理が成立すると考えられることは上で述べたし、光速不変となると考えられることは下で述べる。)
連星パルサーについての「伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいることが発見され、この重力波の存在が間接的に示された」という研究成果(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』)の中では──
「連星系パルサーからの重力放射に必要なエネルギーの源は、軌道運動エネルギーである。だから、重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら、軌道エネルギーはしだいに減少し、このために、パルサーとその伴星が渦巻き状に互いに近づきあい、軌道周期も減少するはずである。」というように、“重力子がエネルギーを持ち去る”という解釈がなされている。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、加速していようが、静止していようが関係なく── 重力波(重力子)は、地球からも、太陽からも、人からも、自動車からも、鉛筆からも、消しゴムからも… あらゆる物質から、常に光速で放出され続けている。
“地球、太陽、人、自動車、鉛筆、消しゴム…”が質量を持っていると同時に、ある頻度で生じ続けているものが重力子である。
いわば、質量とは、“重力子を生じる能力”である。
そして──
もし、運動エネルギーが増せば、“重力子を生じる能力”が増し、重力子を放出する頻度も増すし──
もし、運動エネルギーが減れば、“重力子を生じる能力”が減り、重力子を放出する頻度も減る。
(参考 《重力子の働きと慣性》)
よって、もし、“連星系パルサーの軌道運動エネルギーが減少”するのであれば、“重力子を生じる能力”が減り、放出される重力子の量(頻度)が減るだけである。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のパラダイムでは── そこに、“重力子がエネルギーを持ち去る”という現象はどこにも見当たらない。
そもそも、もし、仮に、“重力子がエネルギーを持ち去る”ことが実際に起こるならば── 電子も、クォークも… 含め、あらゆる物体の質量が減りつつけることになってしまい現実と矛盾してしまう。 したがって、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の結論に至る。
結論2.2. 重力子が、エネルギーを持ち去るという現象は、実在しない。
一方、観測結果と、計算から求められた予測の数値と、ぴったり一致するのとのことである。
なにかがおかしい。
なぜか?
本当に、軌道運動エネルギーの減少が原因で、“連星系パルサーの軌道周期の減少”しているのだろうか?
逆に、はじめから、重力(ポテンシャル)が原因で(ニュートン力学で説明される、自由落下に似た、ごく単純なしくみで)、“連星系パルサーの軌道周期の減少”し続けているだけであると解釈する方が、自然ではないか?
観測されているものは、あくまで、「公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいること」だけである。
(“連星系パルサーの軌道運動エネルギーが減少”は、解釈にすぎず、決して実際に観測されされたものではない。 この記事にも「重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら」と書かれてある。)
また、次の文献によれば── “連星系パルサーの形成はまれなことであり、超新星系爆発の直後の運動の方向が、たまたま連星系パルサーの形成のためにふさわしい方向のときに限って、形成されるものである”ことがわかる。
「連星中性子星が形成されるためには、2度の超新星爆発を経る必要がある. 超新星爆発では、爆発で放出され質量が大幅に減る。これが連星で起きると、連星が解体する可能性がある.〜. 2つの星が、別々の方向に飛んでいってしまうのである. 〜 爆発が非対称的に起こって、軌道運動とはまったく関係のない方向に新たに誕生した中性子星が飛び出し、運良くもう一方の中性子星の飛んでいった方向に向かえば、連星のまま保たれることもあり得るが、確率は低い. だから、連星中性子性は大変珍しい天体なのである.」(『一般相対論の世界を探る 重力波と数値相対論』 柴田大 著 東京大学出版会 p21-23より一部抜粋)
したがって、「単純に重力によって引き合って(落下しあって)、“連星系パルサーの軌道周期の減少”し続けている」と解釈することは、少なくともナンセンスではなく── むしろ、より単純で、より自然な解釈である思われる。
(正しければ、実際は、重力場を自由落下する物体の運動エネルギーが増すように── 地球より、(地球の内側の)火星や水星の公転速度が速いことから類推できるように── “連星系パルサーの軌道周期の減少”によって、軌道運動エネルギーは、むしろ増すはずであると考えられる)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のパラダイムでは、“連星系パルサーの軌道周期の減少”と重力子の関係を、次のように説明する。
連星系パルサーの軌道周期が減少すれば、“質量分布のコンパクト化”が進むので、“重力子の放出量は増える”ように観測される。(考察3)
重力ポテンシャルエネルギーが運動エネルギーに転化するので、連星系パルサーの軌道運動エネルギーが増加するのに伴い、重力子の放出量も増える。
つまり、“連星系パルサーの軌道周期の減少”は、系が重力子を放出する能力を増やす方向に働くことを示している。
理論は、180度、逆である。 しかし、計算された予測数値は、観測とピッタリ一致する。 なぜか?
なぜなら、アインシュタインの一般相対性理論から導いた“四重極公式”によって計算され、持ち去られたと解釈されたエネルギーの減少分と、 運動エネルギーの増加にともない放出される重力子の量(頻度)の増加分が、数字的に等しいからではないだろうか?
連星パルサーの総運動エネルギーをK=(1/2)mv2とし、連星パルサーの総ポテンシャルエネルギーをU=−GmM/rとすると──
連星系パルサーの総エネルギーEは、E=K+U=(1/2)mv2+(−GmM/r)=GmM/2r+(−GmM/r)=−GmM/2r
となる。 (つまり、“総運動エネルギーKと総エネルギーEの和は、0になる”という結論を導く“ビリアル定理”があてはまっている)
つまり、“系の持つ総運動エネルギーK”= −“系の持つ総エネルギーE” である。
“四重極公式”は、連星系パルサーの総エネルギーEの単位時間当たりの変化量dE/dtを、“重力子によって放出される、単位時間あたりのエネルギー量”とイコールで結ぶことによって導かれている。 そして、これが、連星系パルサーの総エネルギーEの単位時間当たりの変化量dE/dtが、“重力波として単位時間当たりに持ちさられるエネルギーの減少分に等しい”という解釈を与えたと思われる。
しかし、ここで、連星系パルサーの総エネルギーEは、連星系パルサーの総運動エネルギーKと、正負の符号が逆で絶対値が等しいことを当てはめてみる。
すると、連星系パルサーの総運動エネルギーEkの単位時間当たりの変化量dEk/dtと、“重力子によって放出される、単位時間あたりのエネルギー量”を、正負の符号を変えてイコールで結ぶことができるようになる。 これは、連星系パルサーの総運動エネルギーEkの変化量dEk/dtが、“重力波として放出できるようになったエネルギーの増加分”に等しいと解釈できることを意味すると考えられる。
これは、まさに、運動エネルギーが増す(≒物体が加速する)と、その分、“重力子の放出量が増える”という、これまでの考察と合致する。
つまり、“重力波による持ち去りの解釈を生む(総)エネルギーの減少分”、“重力波の放出能力アップの解釈を生む(運動)エネルギーの増加分”── その絶対値が(ビリアル定理によって)たまたま一致しているのである。
確かに、「伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいることが発見され、この重力波の存在が間接的に示された」という結論は変わらないし、この記述自体は、正しいままであることになると思われる。
しかし、その背後で実際に起きていると考えられる2つの現象── “重力波による持ち去り”、“重力波の放出能力アップ”には大きな違いがある。
果たしてどちらだろうか?
むろん、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のパラダイムでの、これまでの考察は、後者であることを示唆しており、このパラダイムは次の結論を導く。
結論2.3 「伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいる」という観測結果と、アインシュタインの四重曲公式による予測値は── 重力ポテンシャルエネルギーが消費されて、連星の運動エネルギーが増す(≒物体が加速する)ことに伴い、その分、“重力子の放出量が増える”という事実を反映している。
連星パルサーの観測結果および予測数値値は、こういった理論(事実認識、パラダイム…)をサポートする証拠である、と解釈できることになる。
なお、アインシュタイン自身も、“重力波がエネルギーを持ち去る”という解釈とも関連すると思われる、次のような問題意識をもっておられた。
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』 (『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より)
この文章から、「重力子がエネルギーを持ち去り、系のエネルギーが減る」ようなことが起こると考えることは、一般相対性理論の正当性に疑いをもたらすほど、おかしな考え方であると、アインシュタイン自身が考えていたらしいことも読み取れると思われる。
連星系パルサーに関する、このあたりの問題は── もしかしたら、“四重極公式”は、本来、“重力波によって持ち去られるエネルギーの減少量を示す式”ではなく、“重力波の放出能力をアップさせる運動エネルギーの増加量を示す式”だと解釈すれば、解決できる問題に過ぎないのかもしれない。
なお、“重力波の放出能力アップ”は、まさに“質量の増加”を意味していると考えられ、特殊相対性理論の説明と合致していると思われる。
以上の詳しい検討&検証は、今後の課題であると思われる。
《等速運動(慣性系)と特殊相対性理論》
特殊相対性理論に関して、次の仮説を立てた。
仮説2.8.1 アインシュタインの特殊相対性理論の数式が示す世界(光速度不変の原理、相対性原理)も── 時空の素スピノールのネットワークのすべて(原始ヒッグス場、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)…)で説明できる。
特殊相対性理論は、あらゆる慣性系(あらゆる等速直線運動をしている系)で観測する光の速度は一定であること=“光速度不変の原理”を内在させている。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では── 光子とは、“原始ヒッグス場”のバネを利用して、素スピノールのペアが、“転回のリレー”を行いながら光速で移動するものであることを示している。
これは、ある種の“新しいエーテル”の存在を認めることになるので、一見、“光速度不変の原理”が破れてしまうことを意味するようにも見える。
しかし、そもそも“原始ヒッグス場”は、時空構造であり、かつての“古いエーテル”が想定していた“物質”とは異なる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)&“原始ヒッグス場”でも、なんらかのかたちで、“光速度不変の原理”が成り立っているはずである、という仮説を先に立てた。
以下に、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)&“原始ヒッグス場”の理論で、“光速度不変の原理”がいかにして保たれるかを考察する。
光速c(km/s)=30万km/sであるとして話を進める。
簡単にするため、光源からちょうど30万kmはなれた観測者を考える。
すると、当然、光源から放出された光、つまり、光子は、1秒後に観測者にたどり着くことになる。
かりに、光源も観測者も、ともに“原始ヒッグス場”に対して静止しているとすると── 当然、観測される光速は、秒速30万kmである。
次に、観測者が、速度vで、光源の方に向けて等速運動しているとする。
すると、自然に考えると── 「1秒間に光が、“原始ヒッグス場”の上で30万km進み、同じ1秒間に観測者は“原始ヒッグス場”の上でvメートル進むのだから、観測者から見て、光は、合わせて1秒間に、30万km+v(m)進むことになる── つまり、光速は、c+vとなり、観測者にとっての光速は、秒速30万kmを越えてしまうことになる」という結論に至ってしまうかもしれない。
ところが実際は違う。
実際には、観測者は、静止していても、速度vで運動していたとしても、光速c──「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」──を観測する。
それこそが“光速度不変の原理”である。
※これより、もっと厳密な図示の仕方があるかもしれないが、
おおよその意味は読み取れると思われる。
※上図が、“静止した観測者の座標系”からみた“30万km”であるのに対し、下図は、“運動している観測者の座標系”からみた30万kmに相当する。
|
何が起こっているのだろうか?
静止した観測者と、vで等速運動している観測者の間で何かが決定的に違っているはずである。 何か?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のパラダイムは、上記の考察のように、“運動する物体は、運動方向に重力子を放出していること”が決定的に違うことを示す。
等速運動している間、その運動方向に重力子が放出されていて、それが“慣性”(流れるプール効果)を生んでいると考えられることは前に述べた。 まさにその運動方向へ放出している重力子が、運動方向に存在する時空の性質を変化させている結果、“光速度不変の原理”をもたらしているのではないだろうか?
どのように変化させているか?
「空間を膨張させる方向、時間の流れを遅くさせる方向」に変化させているのである。
これらの変化が作っている効果──「空間を膨張させている効果、時間の流れを遅くさせている効果」は、(原始ヒッグス場の上での)速度vの運動が持つ、「光源との距離を短縮させている効果、光子が観測者にたどり着くまでの時間を短縮させている効果」をキャンセルしてしまうと考えられる。 その結果、観測者は、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測すると考えられる。
つまりは、だれが、どのような等速運動をしていようが関係なく、その等速運動に伴って重力子が放出されている結果、時空の性質が変わっているので、観測者は、それぞれの時空(それぞれの慣性系)が持つ“時間と長さのものさし”で、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測すると考えられるのである。 これが、“光速度不変の原理”の実体ではないだろうか?
※(第三者が外側から観測することによって)運動している物体が収縮しているように見える“ローレンツ収縮”は、運動の進行方向にのみ収縮する。 このことは、重力子が運動方向にのみ放出されることと合致する。
そして、なぜ“ローレンツ収縮”が(1−(v/c)2)1/2の割合で起こるかと言えば、運動する物体の、“運動方向の時空”が、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で、膨張しているからあると考えられる。
物体と座標の変化
(1)物体が静止している場合、どこにいる観測者にとっても、座標(ものさし)は共通である。
(2)物体が速度vで運動すると、“ローレンツ収縮”が、(1−(v/c)2)1/2の割合で起こる。 このとき、運動方向の空間は、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で膨張している。 このことによって、物体とともに運動している観測者は、(空間の膨張にともなう)新たな座標(ものさし)を持つことになる。
なお、“物体が収縮していること”や“運動方向の空間が膨張していること”を観測できるのは、静止しづつけている観測者である。 物体とともに運動している観測者は、(3)のように、それらを観測できず、(空間の膨張にともなう)新たな座標(ものさし)を持つだけである。
(この新たな座標(ものさし)が、“光速度はcだ”の観測を支えることになる。) |
※光速で運動する物体を、第三者が、外側から観測すれば、物体が短縮しているように見える(ローレンツ収縮)。
一方で 物体と一緒に運動している本人が、内側から観測すると、何も変わらず、いつもの長さ、いつもの時間の流れで、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測することになる。
(なぜなら、運動によって距離&時間が短縮する分が、(運動に伴って放出される「重力子&縮みきったバネの“4角形”」によって空間が膨張し時間がおそくなるので)、ぴったりとキャンセルされる(打ち消される)からであるとも言える)
(だからこそ、秒速30kmで太陽のまわりを公転している地球上でも、「1秒間に光が進む距離は30万kmだ」を観測する)
このことは、「運動の内側から観測されることと、運動の外側から観測されることが、違いうる」ことを意味している。
つまりは、「運動する物体のローレンツ収縮」の影響と、「物体が運動方向への重力子を放出することにともなう物体の周囲(運動方向)の空間の膨張」の影響は、計算上、等価になると言えると思われる。
※そもそも、なぜ、等速運動にともなって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されると、運動方向に空間が膨張するのか?
それは、“4面体”が“4角形”(縮みきったバネ)になると、それだけ、“スペースが広がることになる”からであろうと考えられる。詳細な検討は、今後の課題である。
“光速度はcだ”の観測が成り立つためには、運動にともなって、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で“運動方向の空間が膨張すること”だけでなく、1/(1−(v/c)2)1/2の割合で“運動方向の時間の流れ(時計の歩み)が遅くなること”も必要である。
なぜ、等速運動ともなって「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出されると、「時間の流れを遅くさせている効果」を生まれるのか? それは、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が、光子が転回する原始ヒッグス場の“4面体”の足場の比率を減らすことによって── 光子が転回する過程を妨げ、単位時間あたりの、光子が転回する回数を減らすからだと考えられる。 この考えは次の仮説に基づいていると言える。
仮説2.8.2 原始ヒッグス場での、(光子を構成する)素スピノールの“転回そのもの”が、“時の刻み”に相当する。
※正しければ、“運動の進行方向に生じている重力子”のおかげで、運動の進行方向の光子の転回(=時の刻み)が減り、それが原因で、時間の流れが遅くなることになる。
そして、観測者の等速運動の速度vが大きければ大きいほど、原始ヒッグス場の中での「縮みきったバネの“4角形”by重力子」の比率が大きくなるので、それだけ時間の遅れも大きくなると考えられる。
この仮説は、一般相対性理論が示すように、「強い重力場であるほど、時間の進み方が遅くなること」と合致する。
なぜなら、強い重力場であるほど、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の密度が高くなるので、光子にとっての足場──原始ヒッグス場の“4面体”の足場が減り、転回しにくくなるからである。
極端な話、もし、光子が転回できなくなっていれば、そこでは時間の流れが止まっていることになる。
例えば、ブラックホールの中の、原始ヒッグス場の“4面体”の足場が100%消失している場所では、光子は全く転回できなくなっているので、時間の流れが止まっていることになる。 当然、光子は、それ以上先へは進むことができなくなる。 これが、「ブラックホールの外に光が出て行けなくなる」ことの背後に存在している実体であると考えられる。
※例えば、“地球に高速で降り注ぐミューオン”の寿命が延びることも、やはり、そこでも、高速で運動するミューオン自身が生じさせる“その運動方向に進む重力子”の総和が、“ミューオンの運動方向の時空を変化させる(空間を膨張させると同時に、そこでの時間の流れを遅くする(≒“転回数の低下”を生じる))”ことによって、寿命が延びる── と説明できると思われる。 詳細は、今後の課題である。
※ある時空の構造(=ある「重力子&縮みきったバネの“4角形”」の分布)をもたらしている運動が等速運動であれば── 「重力子&縮みきったバネの“4角形”」の比率は、その運動方向では、どこでも一定となるので、その運動方向に“重位勾配”は、まったく生じない。 しがって、光源となる物体の等速運動による時空構造の変化であろうと、観測者側の等速運動による時空構造の変化であろうと、同様な“時空の変化による効果”がもたらされると考えられる。 このことは、相対性原理と合致する。
以上より、それぞれの慣性系が、それぞれ独自の“空間&時間”(時空)を持ちうることが、特殊相対性理論が示している“光速度不変の原理”を根底で支えていていると言える。
そして、「それぞれの慣性系が、それぞれ独自の“空間&時間”(時空)を持ちうること」を支える実体は、“素スピノールのネットワーク”(特に、原始ヒッグス場)である。
「これは、エーテルではないのか?
エーテルは、かつて否定されたので、矛盾しているのではないか?」という疑問が生じるかもしれない。
しかし、この「“素スピノールのネットワーク”(特に、原始ヒッグス場)」は、少なくとも“光速不変の原理”と合致しているので、かつて否定されたところの“エーテル”(物質としてのエーテル。“古いエーテル”と呼ぶこととする)とは異なる実体であることが分かる。
※さらには、アインシュタイン選集2 [A10]『エーテルと相対性理論』の中の下記の記述から分かるように、アインシュタイン自身が、(特殊相対性理論で否定された形になったが、一般相対性理論に基づき)結局は、“エーテル”を必要不可欠と考えていた。
『すなわち一般相対性理論によれば、空間は物理的特性を与えられている。それゆえこの意味でエーテルは存在する。 一般相対性理論によればエーテルを伴わない空間を考えることはできないものである。なぜならば、そのような空間では光も伝播することができないし、また空間および時間の基準(すなわち物指と時計)も存在することができない。したがって物理学的に意味のある時間的、空間的距離というものも存在しえないことになる。しかしながらここに考えたエーテルが、質量をもったふつうの物質からできているとか、あるいはまた普通の媒質(水や空気のような)と同じような性質をもっていると考えることはできない。 たとえば、運動というような概念は、われわれのエーテルには適用できない』
このアインシュタインが必要不可欠と考えていたエーテルを“新しいエーテル”と呼ぶこととする。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、この“新しいエーテル”の第一候補は、“原始ヒッグス場”である。
この“原始ヒッグス場”は、「光速度不変の原理」をも満たすのみならず── 物質でない(物質未満である)し、それ自体は質量をもたない。
したがって、原始ヒッグス場は、アインシュタインが考えた“新しいエーテル”が満たすべき条件も満たしていると言える。
※有名な「マイケルソン・モーレーの実験」は、“古いエーテル”を否定した。
しかし、この「マイケルソン・モーレーの実験」は、これまでの考察で示したような“新しいエーテル”を否定できない。
なぜなら、“測定機器の運動”によって、「運動方向に重力子が放出されることによって、運動方向に存在する空間が膨張し、そこでの時間の流れが遅くなる」という効果が生じるので、“誤差”を100%観測できなくなると考えられるからである。
いや、そればかりか、マイケルソン・モーレーの実験は、上のような「運動方向に重力子が放出されることによって、運動方向に存在する空間が膨張し、そこでの時間の流れが遅くなる」という性質を持つ、“新しいエーテル”の存在を支持するものであると解釈できると思われる。 (“観測の理論負荷性”の一例である)
《光──光子、電磁波、アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則》
この項目では、光や電磁波、アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則について、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による説明を行なう。
光や電磁波については、上で挙げた、次の仮説で説明できる。
仮説2.1 光子は、様々な距離にある“原始ヒッグス場”の基本構造をバネ的な足場にして── 「 互いに同じ方向に運動する素スピノールのペア」が、同時に転回する(共転回する)ことを繰り返しながら、進むものに相当する。
再度、図示すると次のようになる。
上図のように、“素スピノールの転回(ひっくり返り)”が、次々と伝わっている。
これが、まさに“光の伝わり方”(光子の移動のし方)の実体に相当することになる。
※光が持つ“波と粒子の二重性”の性質をうまく説明できると思われる。
※これが、真空中を、光速という一定の速度で伝わるということは──
単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”が多いほど、光子の素スピノールの間の距離が小さくなって(光の波長は短くなって)、
逆に、単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”が少ないほど、光子の素スピノールの間の距離が大きく(光の波長は長く)なることを意味する。
※一方、プランクの光のエネルギーの式 E=hν より、単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”(≒光の振動数)が多いほど光子のエネルギーが大きくなり、単位時間あたりの“転回の頻度(転回数)”が少ないほど光子のエネルギーが小さくなることになる。 (このあたりは、不確定性原理とも関連する。考察5)
※このモデルは、“円偏光”についても、うまく説明できると思われる。 転回する方向が、光の進行方向に平行な成分のみなら垂直偏光であるが、もし、光の進行方向と垂直な成分も合わせ持つならば、円偏光となるだろうと考えられる。
一方、電磁波の図をここに重ねてみる。
※電場の向きと垂直な方向に磁場が同時に生じていると考えると、おおよそ、うまく説明できることが読み取れる。
上図は──
下図のように、“右巻きor 左巻きの素スピノールが転回する際に、どちらの方向に電場や磁場が生じるか”という簡単なルールを決めることによって、
電磁波を、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で、うまく説明できることを示していると思われる。
※右巻き素スピノールは、転回の向きに対して、右ねじの方向に磁場が生じている。
※左巻き素スピノールは、転回の向きに対して、左ねじの方向に磁場が生じている。
※素スピノールが360度転回する間に、電場のサインカーブは180度分(半分)変化することになる。
これは、「スピノールは720度回ると元に戻る」と言われていることと調和していると思われる。
※この図では、横軸が時間tになっているので、厳密には、電磁波の図とは異なっていることになる。この辺りの詳細については、のちほど考察する。
上図は、電磁波を構成する普通の光子の場合のものである。 “仮想光子”についてのルールは、次のようになると考えられる。
※仮想光子の場合、ふつうの電磁波の光子と違い、“放出源に戻る”という性質を持つと考えられる。
※上図のように、電場や磁場のどちらか一方が、前半と後半で逆転することにより、仮想光子の進行方向についても『右ネジの法則』が保たれる。
『〜光の進行方向を表すベクトルと電気・磁気ベクトルは、たがいに「右ネジの法則」の関係にあることがわかっている。 〜電気ベクトルから磁気ベクトルに向けて右ネジをまわす(時計まわりにする)と、ネジの進む方向が光の進行方向(〜)に一致する。
〜。 〜三つのベクトルの間には、反時計回りの関係(左ネジの関係)はなりたたない。光もまた、右と左の対称性を破っているのである。』
(『対称性から見た物質・素粒子・宇宙 鏡の不思議から超対称性へ』(広瀬立成 講談社ブルーバックス)p69-70より (下線および一部省略は、筆者による)) |
※ミクロのレベルでは、電場と磁場が、常に同時に生じていることになる。 マクロのレベルの電場や磁場は、この「ミクロレベルの“電場と磁場”」が、多数、うまい具合に配置されたときに、創発されると考えられる。 そういう意味で、電場と磁場は、“紙一重である”とも言えるかもしれない。
※以上のモデルは、電場と磁場が“直角に存在する”ことを、ピッタリと説明できる。
この電場と磁場が“直角に存在する”ことにより、例えば、アンペールの法則(電流の周りに磁場が生じる)や、ファラデーの法則(磁場の変化に伴い電場が生じる)も、うまく説明できる。
ここまで電磁波についての考察によると、誤解を招くおそれがあったが──
「ミクロレベルの“電場と磁場”」は、「個々の素スピノール」だけによって生じるわけではない。
実際は、「原始ヒッグス場の“4面体”」の中の、特定の素スピノールが転回することによって生じる「変形した“4面体”」が、「ミクロレベルの“電場と磁場”」を持つのである。
※ミクロレベルの電場と磁場をそれぞれ、ミクロ電場、ミクロ磁場と呼ぶこととする。
なお、実際は、「変形する“4面体”」なのであるが── 直交する磁場と電場が分かりやすくなるので、それぞれ、上図のような「変形した立方体(=直方体)」で図示すると便利である。 例えば、上図の「変形した立方体(=直方体)」の図は、実際は、上図のように時間経過で変化するものを意味することとする。
そして、「マクロレベルの電場や磁場」は、「ミクロ電場&ミクロ磁場の総和」(=「変形する“4面体”」の総和)として、創発されるのである。
そのことを意識して、電磁波について、再度考察する。
※横軸が距離Zになっている。 “4面体”を便宜上□で示した。
この図のポイントの1つは、電磁波の波長に比べ、“光子”を担うとされる「原始ヒッグス場の“4面体”」は、非常に小さいと言うことである。
電磁波の波長には、例えば、10kmに及ぶ長いもの(電波)から、3×10-12mほどの短いもの(γ線)まで、観測されているが── いずれも、2プランク長(2Lp)≒3.232×10-35mよりは、はるかに大きい。
光子は、波長の半分置きに、とびとびに配置された、この小さな中継地点(原始ヒッグス場の“4面体”)を土台にして進むと考えられる。
個々の光子は、原始ヒッグス場の“4面体”を変形するだけである。 従って、個々の光子によって生じる電場や磁場の変化は、実際は、2プランク長(2Lp)程度の非常に狭い範囲に限られて生じていることになる。 (それらが、マイクロ電場、マイクロ磁場に他ならない。)
光子が波として、伝わる様子をやや詳しく図示すると次のようになる。
※緑の○で囲んだ部分は、“共転回”している過程の図に相当する。
マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式の解の1つは──zの正の方向に進む正弦波であらわされる電場は、数式 Ex(z,t)=E0sin(kz−wt)であらわされる。(参考 『物理学スーパーラーニングシリーズ 電磁気学 第2版』 佐川弘幸/本間道雄 著)
k=2π/λであり、求めたいものは、 z=nλの場所での電場の変化である。
電場 Ex(z,t)= E0sin(2πz/λ−wt)=E0sin(2πnλ/λ−wt)=E0sin(2πn−wt)=E0sin(−wt) と単純な正弦波となる。
このことは、これまでの考察と矛盾していないと思われる。
つまり、「とびとびの“4面体”で担われる光子」は、波動方程式を満たしているので、決して、不可能なことではないと考えられる。
(一方、そもそも、光子とは、電磁波を量子化したものである。そういう意味で、むしろ、とびとびの方が自然であると言えるかもしれない)
電場Eの空間が持つエネルギー密度は、ε0E2/2 で、求まる。 よって、
z=nλの場所の原始ヒッグス場の“4面体”を含む立方体の体積((2Lp)3=8L3p)が持つエネルギー密度Eを計算すると── 電場 Ex(z,t)= E0sin(−wt)なので、
エネルギー密度E =ε0E2/2=ε0×( E0sin(−wt))2/2=ε0E20sin2(wt)/2 となる。
一般に、sin2θ=(1−cos2θ)/2 であり、そのグラフは、次のようになる。
そのことは、例えば、次の図ような180度の共転回に伴う電場のエネルギーの変化を考えると── 次の図ように、一方のエネルギーが減る分と、一方のエネルギーが増加する分が、全く等しくなることを意味する。
※エネルギーの減少を意味する緑の縦線が引かれている領域と、エネルギーの増加を意味するピンクの縦線が引かれている領域が、全く等しく推移している。
つまり、共転回する間、ミクロ電場のエネルギーの合計は、一定となり、ぴったり保存されていることになる。
※なお、ミクロ磁場のエネルギーについても、同様に考えることができると思われる。
そして、「左巻き素スピノールがの転回が関与するミクロ電場とミクロ磁場のエネルギー」と「左巻き素スピノールの転回が関与するミクロ電場とマイクロ磁場のエネルギー」の合計は、一定となり── それこそが、1つの光子が持つエネルギーを示す、アインシュタインの式E=hνの値に等しいと考えられる。 詳細な検討は、今後の課題である。
観測結果とは矛盾しないのだろうか?
例えば、アインシュタインの式、E=hνより、光子が持つエネルギーEは、E=hν=hc/λ である。 これは、たとえ、波長3×10-12mほどの高エネルギーのγ線であったとしても、1つの光子が持つエネルギーは、E=hc/λ≒(6.670×10-34×3×108)/3×10-12=6.670×10-14J と非常に小さいことを意味する。(仮に、3×105mの電波だとしたら、1つの光子が持つエネルギーは、E=hc/λ≒(6.670×10-34×3×108)/3×105=6.670×10-31J と、ますます小さいことを意味する) まして、これが光速で移動するのである。
この個々の光子について、とびとびでない、「ひろい場所に広がる滑らかな(連続な)電場や磁場が存在している」か、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が予測するように、とびとびであるか、を「観測によって判断すること」は、不可能なのかもしれない。
そういう意味で、消極的であるが、こまでの観測結果とは矛盾はしていない、と言えると思われる。
また、電磁波を増幅させ(“複数の光子”を使い)、電磁波の腹と節の違いを観測した「レンツの実験」とも、大きく矛盾していることはないように思われる。
詳細な検討は今後の課題である。
※なお、上の「そもそも転回によって、なぜ、“4面体”が変形するのか?」の考察とも、矛盾していないと思われる。 なぜなら、素スピノールの360度の転回の間のエネルギーの変化が同じ形になっているからである。
※なお、静止した電荷が作る(ミクロ)電場の正負は、次のような単純な規則で決まるようである。
|
仮想光子が“4面体”を変形させる際に
転回する素スピノール
|
左巻き素スピノール
|
右巻き素スピノール
|
|
生じる(ミクロ)電場
|
プラス
|
マイナス
|
この規則は、プラスの電荷が右巻き素スピノールのみで構成され、マイナスの電荷が左巻き素スピノールだけで構成されるという後の考察6の内容とぴったり合致する。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、電磁波が「電場→磁場→電場→磁場→…」というような波ではなく── 「「マイクロ“電場&磁場”」(左巻き)→「マイクロ“電場&磁場”」(右巻き)→「マイクロ“電場&磁場”」(左巻き)→「マイクロ“電場&磁場”」(右巻き)→…」というような波であることを示している。 しかし、このことは、決して、4つのマクスウェル方程式と矛盾していない。 そのことを以下の考察で示すことになる。
※なお、現在、“電磁波は「電場→磁場→電場→磁場→…」のようにして伝わる波である”と図示&説明されている本がある一方で──
『電磁波とは何か』(後藤尚久 講談社ブルーバックス p194)のように、電磁波が「電場→磁場→電場→磁場→…」と交互に伝わる波であるという説明について、『〜これは明らかに誤りである。電界と磁界が交互にずれた位置で強くなるのは定在波であり、電磁波は進行しない。
〜電磁波が進むためには〜電界と磁界が同時に強くならなければならないのである。』(下線、省略は筆者による)
と記述された本や、『基礎電磁気学 改訂版』(山口昌一郎 電気学会)のように、進行波が「電場と磁場が同時に強くなっている」ように図示され(p.327)、定在波は「電場と磁場が交互にずれた位置で強くなる」ように図示されている(p.352)本もある。
むろん、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、後者を支持していることになる。
《アンペール−マクスウェルの法則》(“4つのマクスウェル方程式”の中の1つ)──電流が流れると、その回りに磁場ができる(右ねじの方向)
光子(電磁波)については、先に、次のような仮説を立てた。
仮説2.1 光子は、様々な距離にある“原始ヒッグス場”の基本構造をバネ的な足場にして── 「 互いに“近づくor遠ざかる”方向に運動する素スピノールのペア」が、同時に転回する(共転回する)ことを繰り返しながら、進むものに相当する。
電荷から、放出され再吸収されるとされる“仮想光子”について、次の仮説を立てる。
仮説2.7 仮想光子は、様々な距離にある“原始ヒッグス場”の基本構造をバネ的な足場にして── 「 互いに“近づくor遠ざかる”方向に運動する素スピノールのペア」が、同時に転回する(共転回する)ことによって進み、もう一度、光の右ネジの法則に従う方向に転回することによって、元に戻るものに相当する。
※仮想光子の場合、ふつうの電磁波の光子と違い、“放出源に戻る”という性質を持つと考えられる。
※上図のように、電場や磁場のどちらか一方が、前半と後半で逆転することにより、仮想光子の進行方向についても『右ネジの法則』が保たれる。
この“仮想光子”についての仮説を、“電荷が運動すると仮想光子がどうなるか”を考慮し、一部アレンジすることで、アンペールの法則を説明できる。
仮説2.7.2 左巻き素スピノールで構成される電子が運動し、近づいてくると── その電子の中の“左巻き素スピノール”と、(電線上の、原始ヒッグス場の基本構造の中の)“右巻き素スピノール”がペアを作り仮想光子となる。 その際、“共転回が生じるの方向”は、相対的に、“左巻き素スピノール”の“電流に伴う運動の方向”と一致する方向が多くなる。
“電流に伴う運動の方向”とは、“電流に伴う電子の運動の方向”のことであり、電流の向きと逆向きである。
※電子が左巻き素スピノールのみで構成されていることについての詳細は、考察6にて述べる。
※「素スピノールがミクロレベルで持っていると考えられる光速での運動」と区別するため、「電流に伴う運動」を定義した。
この仮説2.7.2の内容を図示すると次のようになる。
|
|
電流が下から上へ流れると、電子(左巻き素スピノールで構成される)は、当然、上から下に移動する。
その結果、仮説2.7.2 により、相対的に、上図のような方向の共転回が優位になる。
その際、無限上方〜無限下方に存在する、「上から下に運動している電子の中の左巻き素スピノール」とぺアを作るような、電線の周囲の縁の上の、(原始ヒッグス場の基本構造の中の)右巻き素スピノールが、上図の向きが優位な形で、共転回することになり── 上図のように、アンペールの法則にピッタリ合致した右回りの磁場が、(右巻き素スピノールの転回の総和によって)創発されることになる。
|
この考え方は、マクスウェルが、アンペールの法則を拡張するべく作った式(I=εSdE/dt)が生まれるきっかけとなった、ある現象(後に“変位電流”と名付けられた)を説明できる。
その現象とは、「コンデンサーに電荷が蓄えられる過程で、電線のないコンデンサーの周囲にも磁場が作られる現象」である。(参考 『高校数学でわかる マクスウェル方程式』講談社ブルーバックス 竹内淳)
|
|
※電線内で電子が運動するように、コンデンサー内でも電子が運動する。
コンデンサー内の左巻き素スピノールのみならず、電線内(無限遠方も含む)の左巻き素スピノールも、コンデンサー周囲の右巻き素スピノールと、共転回をしうる。
わざわざ、充電中のコンデンサーの周囲に磁場が生じる現象は、わざわざ「変位電流によって磁場が生じる現象」という特別な説明するまでもなく── 「電線およびコンデンサーの中を運動する電子(左巻き素スピノール)によって、磁場が生じる現象」と、統合的に説明できると考えられる。
|
以上のことは、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のパラダイムによって、ふつうの電流によって生じる磁場と、変位電流によって生じるとされた磁場が、統合できることを意味する。
つまりは、以上で、4つのマクスウェル方程式の1つ、「アンペール−マクスウェルの法則」を統合的に説明できたことになると考えられる。
※マクスウェルは、“電荷の移動”の結果生じた「コンデンサーの間の電場の変化」が、コンデンサーの周囲の磁場を生むという考えを数式計算(ガウスの定理も使用)から求めた。
それに対して、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、“電荷の移動”そのものが、直接コンデンサーの周囲の磁場を生むとシンプルに考える。
※“電荷の運動”(原因)と、“新たに生じる磁場”(結果)を結びつける、共転回する素スピノールのペアは、次々と作られる“仮想光子”に相当し、波長/転回周期は、光速に相当すると考えられる。(λ/T=c) マクスウェルが、数式計算によって、光速を導く過程で、この「アンペール−マクスウェルの法則」も活用したことと合致すると思われる。
※もし、180度の“転回”したのち、180度の“逆転回”したとすると── 磁場は、すぐにN極とS極が逆転してしまう。
磁場のすぐにN極とS極を逆転させないように、同じ方向に転回を続けさせる、次の図のような共転回もあると思われる。 これだと、磁場が保たれ、観測結果と合致すると思われる。 詳細な検討は今後の課題である。
※電荷によって生じる転回の方向は、本来、(決定論的なカオスによって)、ランダムであると考えられる。 さらには、電圧をかけられた電子は、一直線に電圧に従って進むのではなく、前後を含めジグザグ運動しながら、結果的にトータールで見て電圧に従って、進むことになる。 やはり、電荷の運動があることによって、相対的に、特定の磁場が優位になると言う方が正しいと思われる。
※以上の考察は── 電荷とは、「“素スピノールの転回”を生じる何か」であることを示している。
それは、「電荷の起源とは何か?」(電荷とは何か?)について、大きなヒントとなる。 (「電荷の起源は何か?」(電荷とは何か?)は、考察6にて詳しく考察する)
また、それは、電子の“幾何的な実体像”──電子の内部構造を考えるヒントとなる。 (詳細は、考察6の電荷の実体について)
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば、いわゆる“変位電流”は実在せず── 実在するのは、運動する電荷と、ある方向に共転回する素スピノールが、相対的に優位になって生じたミクロ磁場の総和として創発した、マクロレベルの磁場であると考えられる 。
このパラダイムによれば、“変位電流”が磁場を生じるということも考えられない。
「変位電流が磁場を生じる」と書かれた本がある一方で、「変位電流は磁場を生じない」と書かれた本もある。“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、どちらか言えば後者を支持するが、そもそも、“変位電流”が実在しないと考えているという意味では、どちらとも支持しない。
《ファラデーの法則》(“4つのマクスウェル方程式”の中の1つ)(「磁束の変化を打ち消す方向に、誘導起電力が生じる」)
ファラデーの法則が意味する、「磁束の変化を打ち消す方向に、誘導起電力が生じる」とは、次のようなことである。
下図のように、例えば、“ある円形の電線”の中を通る磁束が増えると── その変化を打ち消すような向きに、電場(電位勾配)が生じるというものである。
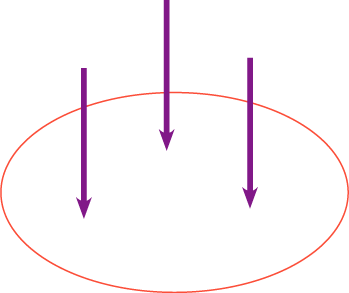 |
→ |
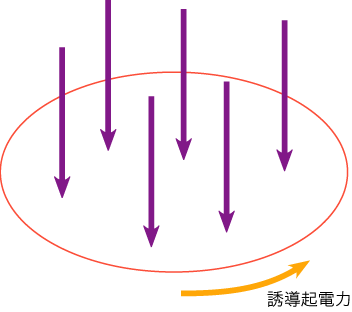 |
& |
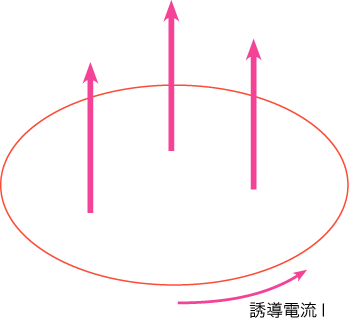 |
| “ある円形の電線”の中を一定の磁束が通っている。 |
|
磁束が変化すると── 電線にそって、電場(電位勾配)=誘導起電力が生じる。 |
|
その誘導起電力=、電場(電位勾配)によって、生じた誘導電流が、新たに生み出す磁束は、最初の「磁束の変化」と逆向きである。 |
その結果、誘導電流が生じ、新たに磁場が生じる。 その向きは、最初の「磁束の変化」を打ち消す方向(逆向き)である。
この現象を“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)で説明してみる。
磁束が変化する時に、“素スピノール”の挙動レベルで起きていることは何であろうか。
ファラデーの法則を継の2つに分けて考察する。
1.磁場が増加することで、任意の閉じた回路に電場(誘導起電力)を生じる。
2.一定の磁場の中を、電荷が運動すると、ローレンツ力が生じる。
1.磁場が増加することで、任意の閉じた回路に電場(誘導起電力)を生じる。
※上部の磁場の源は、永久磁石でも、電磁石であるかを問わない。
なぜなら、ともに、上図のような、マイナス電荷の運動(左巻き素スピノールからなる電荷の運動)によって、作られる点で同じだからである。
磁束が増加するとは、「磁石が下方へ移動する」か、「電磁石の電圧が上がる」ことに相当する。
※中心部の磁場は、ベクタル和をとることで、はじめて、垂直な磁場となることになる。 |
数個しか図示していないが、実際は、無数にこのような転回が存在する。
転回の数だけ、ミクロ電場&ミクロ磁場が存在する。
変形した立方体を利用して、数を増やして表示すると次のようになる。
もし、磁束が一定となり、しばらくたつと、“ミクロ電場がの向きが180度、逆転する”ことになる。 つまり、起電力は、プラスマイナス0で、消失することになる。
なぜなら、磁場が一定であると言うことは、仮想光子の振る舞いによって、ミクロ電場が次のように変化するからである。
逆に、例えば、磁束が増加する間は、新たに共転回が始まるペアが、次から次へと供給され続けることに他ならない。
磁束が増加する間は、フレッシュな共転回が多くなり── 次のようなプロセスにある、ミクロ電場が相対的に増えるからである。
つまり、次の図のように、“一定方向のミクロ電場”が占める割合が、相対的に増えることになり── その結果、マクロの電場(誘導起電力)が強く存在するようになると考えられる。
※確かに、この電場によって生じる電流から生まれる磁場は、磁束の変化を打ち消す方向となっている。
当然、電線の中の素スピノールは、まんべんなく存在するので── ほぼ電線全体に、電場が生じることになる。 これらの総和が誘導起電力の実体であると考えられる。
これが、誘導起電力の創発であると考えられる。
以上の考察は、「レンツの法則が、なぜ成り立つか」をも説明していることになると思われる。
つまりは、以上で、ファラデーの法則の一部を説明したことになる。
次に、ファラデーの法則の残りの部分、「2.一定の(一様な)磁場の中を、電荷が運動すると、ローレンツ力が生じる」ことについて考察する。
一定の(一様な)磁場とは、何であろうか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、次の図ように説明する。
※各ミクロ磁場の向きが、そろっているため、マクロレベルで磁場が観測されるようになる。
一方、各ミクロ電場の向きは、バラバラ(無秩序)であり、なおかつ、360度転回するごとに、向きが完全に逆転している。 よっと、マクロレベルで電場は観測されない。
※4個しか描いていないが、実際は、“(2Lp)3の体積あたり1つ”の割合で、びっしりと空間の中に、つまっていることになる。
|
つまり、一定の(一様な)磁場とは、「ミクロ磁場の向きがそろい、ミクロ電場がそろわないこと」の総和として、創発したものである── と言える。
※N極とともに、S極を示した。
なぜなら、地球や電子と同じように、素スピノールの転回によっても、“N曲とS曲が同時に生じている”と考えるのが自然であると思われるからである。
※素スピノールの転回により、電場とともに、“N曲とS曲が同時に生じている”
この考えは、アンペール-マクスウェルの法則や、これまでのファラデーの法則の説明とも矛盾していない。
(このように、“N曲とS曲が同時に生じている”ということは、“モノポール”(単極子)に相当するものは、“原始ヒッグス場(素スピノール)レベル”においても実在しないことを意味する。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の予測をする。
予測2.0 モノポールは、実在しない。
※なお、この予測は、“磁場のガウスの法則”──「4つのマクスウェルの方程式」の1つ、とも合致する。)
※個々の素スピノールが転回するプロセスの中で、“ミクロ電場やミクロ磁場”を生じることになる。
仮に、素スピノールが“一切転回していなければ”、“電場や磁場”は、存在しないことになると考えられる。
(だからこそ、“弱い力しか働かないニュートリノ”が存在できるだ考えられる。もし、転回していない素スピノールも周囲に電場や磁場をもっていれば、ニュートリノは、電磁場と相互作用をしてしまうだろう。 →考察6)
さて、この一定の(一様な)磁場の中を、電子などの荷電粒子が一定の方向に運動すると何が起こるであろうか?
電荷の流れはとは、電流に他ならない。 アンペールの法則に従うように、“新たな磁場”が生じるでろあう。
※画面(紙面)に対して垂直な向きで手前から奥へ電子が運動している。マイナス電荷なので左回りになっている。
| ※上図では、示せていないが、ミクロ電場は、実際は |
|
のようにプラスマイナス0となっている。 |
元から、存在する「一定の(一様な)磁場」の中を、この電子が運動すると、どうなるであろうか?
相対的に、左右方向について、最も大きな、「ミクロ磁場の数の差」が生まれると考えるのが最も自然であると思われる。
| なぜなら、下の図のように、電子の運動方向の左側においては、元からあるマクロ磁場と全く同じ方向にミクロ磁場が生じ増加する一方、 |
|
電子の運動方向の右側においては、
|
|
のように180度逆向きのミクロ磁場が生じ(キャンセルされる結果)減少すると考えられるからである。 |
(なお、キャンセルされるとは、「“4面体”の変形」がキャンセルことであり、もとのエネルギーの低い“4面体”に戻ることを意味する)
※電子の運動方向に対して、左側で、ミクロ磁場が最も増加するのに対して、右側で最も減少することになる。
※元からある1つのミクロ磁場の大きさと、電子の運動によって生じる1つのミクロ磁場の大きさは、等しいとは限らないので、上図や数は、たまたま等しい場合を図示していることになる。 等しくない場合は、“ミクロ磁場の数”によって釣り合う形でキャンセルされると思われる。詳細な検討は、今後の課題である。 |
その結果、よりマクロレベルで見ると、そこには、マクロレベルの電場が創発されることになる。
※この電場の向きは、“ローレン力の向き”と、合致する方向のものである。
すなわち、創発したマクロレベルの電場、マイナス電荷の電子を電場の方向の逆である右側に運動させることになる。
※なぜ、これが“マクロレベルの電場”となるかについては、下記の考察《静電場(クーロンの法則)のEMOES表記》にで理解できると思われる。
|
以上の考察は、「なぜ、ローレンツ力がその方向に生じるか?」説明していることになる。
そして、それは、「なぜ、一定の(一様な)磁場の中を、電荷が運動すると、ローレンツ力が生じるのか?」を説明していることであり── なぜ、ファラデーの法則が成り立つのかの残り半分を説明していることにもなる。
マクスウェルの方程式が示しているように──
磁場から電場が生まれたり、電場から磁場が生まれたり、やはり、「電波と磁場は、紙一重のものである」であることを思い知らされる。
そういったことが可能なのは、ミクロ磁場&ミクロ電場の総和として、観測されるようなマクロレベルの電場や磁場が生じているからなのである。
マクスウェルの方程式で説明される現象の根底にある、実体像を“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が示している。
すなわち、「なぜ、マクスウェルの方程式が成り立つのか?」を“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)が説明しているのである。
なお、以上の考察では、「4つのマクスウェルの方程式」の中の3つを説明したことになる。
残りの1つ(“電荷のガウスの法則”についての式)についての考察は、下記の《静電場(クーロンの法則)のEMOES表記》にて行なう。
※なお、以上の考察が正しければ── 電磁気力は、仮想光子の総和が生む電磁場(電場や磁場)を介して生じる力であり、ボソンのキャッチボールによって(湯川型の相互作用によって)生じる力ではないことになる。(考察6、考察11)
(しかし、その過程を、“ある電荷が仮想光子を放出し、もう一方の電荷が、その仮想光子を受け取る”というように解釈して計算したとしても、ある程度、つじつまが合うのだろうと思われる。 なぜなら、その所産が(成功しているとされる)量子電磁気学(電子&電磁場についての場の量子論)に他ならないと考えられるからである。
なお、Δ光子(→考察6)の方は、グルーオンと同様に、実際に、“吸収される”と思われる。)
※無限遠方まで仮想光子が届くとしたら、どうやって伝わるか? やはり、“電荷”によって、無限遠方の素スピノールが、ダイレクトに180度転回させられるのであろうか?
しかし、もし仮にそうだすると、転回周期が無限大になってしまい、その結果、電荷の中の素スピノールが消費され、電荷が持つ新たに共転回する能力(仮想光子を放出させる能力)が低下することになってしまうのではないだろうか? それは、電荷の低下を意味し、“電荷の保存”と矛盾してしまうことになる。 このことは、これまでの考察のどこかに間違いがあることを意味しているのだろうか? あるいは、このことは、「電磁気力は、無限遠方まで働く」という考え(「4つの力」を比較する際に、頻繁になされる考えである)を見直す必要があることを意味しているのだろうか?(実際は、電磁気力が無限遠方まで働くことを観測することは不可能であるし── 仮に電磁気力が無限遠方まで直接働かなくとも、不都合はないのではないか? 電気磁気力は、“分極する物質”を中継地点として、とびとびで遠くまで伝わるものと考えても矛盾していないのではないか? 各種の“誘電率”は、このあたりの事情を説明してくれているものなのではないか?) このあたりの詳細な検討は、今後の課題である。
※電荷からの距離 r が大きくなればなるほど、仮想光子の転回周期Tも大きくなる(=振動数νが小さくなる&波長λが長くなる)。 なぜなら、光速cは、一定だからである。
転回周期Tは、 T=r/c で計算できる。
一方、転回周期Tが大きくなると同時に、仮想光子による180度転回に伴うエネルギー振幅ΔEは、逆に小さくなると考えられる。
(アインシュタインの式より、光子のエネルギーE=hν=h/T が成り立つからである。 (それは、不確定性原理の式とも、おおよそ合致する))
これらのことは、仮想光子は、決して、ランダムなエネルギーを持つものではないことを意味している。
つまりは、遠ざかれば遠ざかるほど、E=hc/r に従って、仮想光子が生じるエネルギーが小さくなる。
このあたりの考え方にも、量子電磁力学(QED)(“電荷&電磁気力”の場の量子論)において、無限大を生じさせないヒント、“くり込み”を不要させるヒントがあるのかもしれないと思われる。 今後の課題である。
(もう一つの、無限大を生じさせないヒント、“くり込み”を不要にさせるヒントは、電磁場を基本ヒッグス場の基本構造の集合と見る見方(時空に最小の単位があるという見方)である)
《プランク定数、ブランクエネルギーについて》
図から読み取れることは、180度の転回を2回繰り返すことで進む距離が、ちょうど1波長分に相当することである。
(180度の転回が1回で、ちょうど半波長分進む。 素スピノールは、半波長ごとに存在する)
結論3.1.0 光子は、素スピノールのペアが、2回180度転回する間に、電磁波の1波長分だけ前進する。
※なお、「ある1つの素スピノール1つが、360度1回転回する間に、1波長分進む」と言い換えることもできる。
次に再び、次の原始ヒッグス場の“4面体”のバネを含めた図をみてみる。
この図からも、光子は、素スピノールのペアが、2回180度転回する間に(=電磁波が1波長分だけ前進する間に)、2回だけ“4面体”は変形することが読み取れる。
1回の光の振動数ν×波長λ=光速cなので──
一般に、振動数νの光子は、1秒間に、2ν個の「“4面体”のバネ」を、とびとびで変形させながら(振動させながら)、光速で移動することになる。
この際、先に示した下図が示すように、「1つの光子がもたらす、“4面体”のバネの変形によって蓄えられるエネルギーの総和」は、一定のまま、光速で移動していくことになる。
※「蓄えられたところから放出されるエネルギーの分」と「新たに蓄えられるエネルギーの分」が等しいので、トータルでエネルギーの増減はない。
そして、この一定な「光子1つがもたらす、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを変形によって蓄えられるエネルギーの総和」が、まさに「光子1つが持つエネルギーE=hν」と常に等しいと考えられる。
※「光子1つが持つエネルギーがE=hνである」と考えるのは、アインシュタインの光量子仮説に基づく
「振動数νの光はエネルギーhνをもつ粒子のように振る舞う。 hはプランクの定数である。 このように、粒子のように考えた光を光量子または光子と呼ぶ」
(『基礎教養 物理学 下』 福田義一廣川書店 p344)
※上図の山の最大値がE=hνに等しいと言うことも出来る。また、 E右巻き+E左巻き=hνで一定と言うことも出来る。
※「ある1つの素スピノール1つが、360度1回転回する間に、1波長分進む」ので、光子の振動数ν=1/T(素スピノールの転回周期) ということもできる。
したがって、この式E=hν=h/Tは、素スピノールの転回周期が短ければ短いほど── その“4面体”の変形によって蓄えられるエネルギーの最大値が大きくなることを意味している。
つまり、原始ヒッグス場は、「素スピノールの転回によって“4面体”を変形させるスピードが速ければ速いほど── その変形によって“4面体”に蓄えられるエネルギーの振幅は、より大きくなる」という性質を持つと言える。
※E=h/T にT=1を代入すると、E=hとなる。
プランク定数hの実体的な意味の1つは、“転回周期1秒で、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを変形させる際のエネルギー振幅”に相当することになる。
(→下記考察)
以上をふまえた上で、いよいよ、重力子について見てみる。
重力子について、すでに、次の仮説を立てた。
仮説2.2.1 重力子は、すぐとなりにある“原始ヒッグス場”の基本構造をバネ的な足場として、4つの素スピノールを転回させながら進むものに相当する。
仮説2.2.2 重力子のサイズは、1プランク長(Lp)程度、重力子の波長は、2プランク長(2Lp)程度と一定となる。
すでに登場した下の図は、まさにこれらのことを表している。
※重力子1つが、1回180度の共転回を2回繰り返す度に(1波長(λ=2Lp)進む度に)、1つの“4角形”が“4面体”に戻ると同時に、
となりの新たな“4面体”が“4角形”に変化することが読み取れる。
※光子が、1つの素スピノールだけを転回させ、1つの原始ヒッグス場の“4面体”を途中まで変形させるのに対し、
重力子は、2つの素スピノールを同時に転回させることによって、1つの原始ヒッグス場の“4面体”を完全な“4角形”(縮みきったバネ)まで変形する。
|
この図からも、重力子とは、光子に相当するものが2つ並走している(2つ光子は、それぞれが発生する電場や磁場が互いに打ち消しあっている)ものであることが読み取れる。
よって、光子の場合と同様な理由で、共転回の間、1つの“4面体”を“4角形”に新たに変形させるために要するエネルギーの大きさは、1つの“4角形”を“4面体”に戻す際に放出されるエネルギーに等しいと考えられる。 したがって、共転回の間も含めて、1つの重力子が移動する過程すべてにおいて“エネルギーの総和”は、増減はなくずっと一定であると考えられる。
その「1つの重力子が持つ一定の“エネルギーの総和Eg(gは、グラビトンのg)”」(=“1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が持つエネルギー”)の大きさいくらになるであろうか?
重力子の波長λが、λ=2Lpであるということは、重力子の振動数νは、ν=c/2Lpであるということになる。
※光速cは、およそ秒速30万キロ、プランク距離Lpは、およそ1.6×10-35mであるので、
重力子の振動数ν=c/2Lpは、およそ3×108/3.2×10-35≒1×1043という、非常に大きな数になる。
※この波長2Lpは、理論上考えられる最も短い波長に相当すると言えると思われるので── プランク波長λpと呼んでもいいかもしれない。
|
重力子を、“波長が2プランク長(2Lp)である光子2個分”に相当するものと近似すると、その値Eg近似値は次のように計算できる。
Eg近似値=2×hν=2hc/λ=2hc/2Lp=hc/Lp
プランク長(Lp=1.616×10-35m)、プランク定数h=6.626×10-34J・s、光速c=2.9979×108m/sとして、
Eg近似値=hc/Lp
≒(6.626×10-34J・s)×(2.9979×108m/s)/(1.616×10-35m)
≒1.2292×1010J
と計算できる。
一方、プランク質量が持つエネルギーの大きさ(プランクエネルギー)は、
Ep=1.9561×109J
である。
したがって、プランク質量(プランクエネルギー)と、「1つの重力子が持つ一定の“エネルギーの総和Eg(gは、グラビトンのg)”」(=“1つの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が持つエネルギー”)および、その近似値 、Eg近似値=hc/Lpは、何らかの関係がありそうだと予想された。
ここで、「プランク距離を求める式Lp=(hG/2πc3)1/2」を変形して得られる「G=2πc3Lp2/h」を、もう1つのプランクエネルギーを求める式Ep=(hc5/2πG)1/2 に代入してみると、
Ep=(hc5/2πG)1/2 =(hc5/2πG)1/2=hc/2πLp
となる。 したがって、ぴったり、「Eg近似値/2π=Ep」となる。
※実際、上記で計算した“Eg近似値”を2π=2×3.14159で割ると、Eg近似値/2π≒1.9563××109Jとなり、プランクエネルギーEp=1.9561×109Jと、極めて近い値になる。
よって、次の仮説を立てた。
仮説3.10 ちょうどプランクエネルギーEpに等しい「Eg近似値(2プランク長(2Lp)の波長を持つ光子2つ分)を2πで割った値hc/2π」は、1つの重力子が持つエネルギー(Eg)の正しい求め方である。
※プランクエネルギーとは、「1つの重力子が持つエネルギーの総和」=「1つの重力子が、原始ヒッグス場の“4面体”のバネを、完全に“4角形”(縮みきったバネ)の状態にしたときに蓄えられるエネルギー」であることになる。
※Eg近似値と正確なEg、これら2つの間の差は、まさに、「“(無理して存在する)波長2Lp光子の2つ”の“結合エネルギー”に相当する」と解釈できる。 (詳細は、下記)
このプランクエネルギーに相当する質量(=プランク質量)をもつ物体があったとする。(E=mc2より、質量2×10-5gである。)
このプランク質量を持つ物体は 1秒間に何個の重力子をすることが出来るであろうか?
かりに、この物体が、ミクロレベルで光速で移動し続けているミクロの粒子だとすると── 原始ヒッグス場の“4面体”は、およそ、プランク長2Lpごとに存在すると言えるので(→考察7)、この物体は、1秒間におよそ、c/2Lp回も“4面体”と衝突できることになる。 そして、衝突するたびに、1つの重力子を放出するであろう(まさに「質量とは、重力子を放出できる能力である」が成り立っている)。
つまり、このプランク質量を持つ物体は、「1秒間にc/2Lp個」も重力子を放出できるということになる。
この物体がかりに、陽子が1019個集まってできた物体だとしても、1つ1つの陽子は、光速で運動し続けているので、「1秒間にc/2Lp個」も重力子を放出することに変わりないであろう。
※重力子の振動数c/2Lpが、ふたたび登場している。 このことからc/2Lpが重要な定数であることがうかがえる。これをプランク振動数νpと呼ぶことがふさわしいかもしれない。以下そのように呼ぶこととする。
すると、νp=c/2Lp=(3×108m/s)/(2×1.616×10-35m)」=0.92×1043 となる。
※陽子1つあたりの1秒間の重力子の放出数をνp/1019で計算できることになる。
(それは、0.92×1024 となる)
一般に、質量mの物体があったとき、それは、1秒間にどのくらいの重力子を放出できるか?
プランク質量mpあたり、νp個の重力子を放出できるので、質量mでは、(m/mp)νp 個の重力子を放出できることになる。
質量mの物体が、速度vで等速運動するとき、どれくらいの重力子を新たに放出するか?
上記の考察《重力子の働きと慣性──等価原理》によれば、mv2/2のエネルギーに相当する重力子が放出されるのであった(それは流れるプール効果として使われる)。 mpc2 あたり、νp の重力子 が放出されるので、mv2/2では、(mv2/2mpc2)νp =(m/mp)×(v2/2c2)νp 個の重力子を放出するであろう。
v2/2c2の値は── かりにvが秒速1mだとすると、1/(3×108)2≒0.555×10-17となるので、かなり小さい。
しかし、m/mpやνp の値がかなり大きいので(例えば、100gの物体なら、m/mp=100/(2×10-5)=0.5×107となる)──
v2/c2の効果が打ち消されて、重力子の放出数は、かなり大きなものとなることができる。
(100gの物体なら、が秒速1mで進むとした場合── 重力子の放出数≒0.5×107×0.55×10-17×0.92×1043 =0.0253×1034=2.53×1032となる。)
したがって、このことは、宇宙空間の中の宇宙船の中で、人でも1本ペンでも等直線運動(慣性運動)が可能であるという観測を説明するのに、重力子の放出による“流れるプール効果”を用いることは、的外れではないことを示していると思われる。
※この考察は、たとえプランク質量に満たない粒子でも、時間をかけて繰り返し原始ヒッグス場の“4面体”に衝突すれば(働きかければ)、重力子を放出できるということを意味すると考えられる。
※ミクロのレベルで、エネルギー保存則が破れていると言える。
周囲のヒッグス場にエネルギーを蓄えても、「ミクロの粒子は光速を保つ」という性質によって、このようなことが可能になっていると言える。
質量とは、重力子を放出する能力であり── 質量とは、そういう性質をものであるということになる。 詳細な検討は今後の課題である。
※もし波長が2Lpの光子が存在するとすれば、その光子2つ分が持つエネルギー=“4面体”←→“4角形”のバネが持つエネルギー振幅の最大値の2倍より、たった1つの重力子がこのバネを振動させるエネルギー振幅の最大値が、さらに、1/2π≒1/6ほどに小さいということを意味している。
それは、重力子のエネルギー振動がとても効率の良いものである一方、光子によるエネルギー振動が無理のあるものであるともいえる。
(光子の方に無理が出てくるのは、1つの“4面体”を変形させるために、素スピノールの2つを同時に転回させずに、あくまで、1つの素スピノールだけの転回によって、変形させ続けようとするからであると思われる)
Eg近似値と正確なEg、これら2つの間の差は、まさに、「“(無理して存在する)光子の2つ”の“結合エネルギー”に相当する」と解釈できる。
(無理して存在する)光子2つ分が結びついて、新たに1つの重力子が生じる際には、大きなエネルギー(プランクエネルギーの5倍《(2π-1)倍》ほど)が放出されることになる。
その結合エネルギーのおかげでこそ、重力子は、しっかり安定して存在し続けられる。
もし、1つの重力子から、バラバラな光子2つへと分解するためには、多大なエネルギー(プランクエネルギーの5倍ほど)を要する。
したがって、こういった現象は、少なくとも現在の宇宙環境では起こりえないと考えられる。
※この“結合エネルギー”の大きさは── 実際は、波長が“2プランク長の波長の光子”が、ふつうの光子のような電磁波の形で、単独では存在しえないことを意味しているのであろうか? 仮に、“波長が2Lpの単独の光子(電磁波)”は実在できなくとも、“波長が2Lpの仮想光子”は実在することができるということはあるかもしれない。
詳細な検討は、今後の課題である。
プランクエネルギーの物理的な意味について考察してみる。
1つの物理的な意味は、1つの重力子が持つエネルギー (=hc/2πLp)としての意味、重力子が原始ヒッグス場の“4面体”を““4角形”(縮みきったバネ)にする際に蓄えられるエネルギーとしての意味である。 そのエネルギーは、1つ“4角形”(縮みきったバネ)が、“4面体”に戻る際に放出されるエネルギーでもある。
このエネルギーが波として原始ヒッグス場を光速で移動していくことが、重力子が光速で移動することにほかならない。
※放出と吸収が等しいので、このエネルギーが光速で移動する際に、トータルでのエネルギーの増減はない。
この1つの重力子が持つエネルギー(=hc/2πLp)が、プランクエネルギーに等しい。
これがプランクエネルギーが持つ物理的な意味の1つである。
多くの素粒子は、プラランクエネルギー(1.2×1019Gev)より小さな質量エネルギーをもつ。
しかし、たとえば、個々のクォーク(3Mev、6Mev )、個々の電子(0.5Mev)は、もちろん、個々の陽子(1Gev)さえも、重力子を放出できないということにはならない。
なぜなら、上でも述べたように、プランクエネルギーに満たない粒子であっても、時間をかけて繰り返し“4面体”に働きかけることによって、蓄積されるエネルギーがプランクエネルギーの閾値を越すことができ、これによって重力子を放出できると考えられるからである。
(現実には、そもそもプラランクエネルギーをもつ“単独の素粒子”は存在しないか、存在してもきわめて例外だと思われるので── この“エネルギー蓄積”方式が広く自然界で採用されていると思われる。
これと似たような方式が、自然界で採用されている例が、他にもある。
それは、1つ1つの神経伝達物質では、1つの神経細胞が“パルス”を出すことができないが、それが蓄積し、ある閾値を越えて始めて、神経細胞が“パルス”を出すという現象である。)
もし、1つの粒子が時間をかけて繰り返し作用したり、一定時間に作用する粒子の数が増したりすれば、蓄積されるエネルギーの合計が、1.2×1019Gevの閾値に達し(=原始ヒッグス場の“4面体”の変形が進み、縮みきったバネの“4面体”に至り)── まさにそのとき、はじめて重力子が放出されるであろう。
※例えば、重力子を、1秒間に、およそ、νp×10-19回=0.92×1024回だけしか重力子を放出できない陽子であっても、トータルでおよそ1.2×1019個集合すれば、νpの頻度で重力子を放出できるようになることになる。
(なお、陽子や中性子の質量は、約1.67×-24gで、プランク質量は、約2×10-5gである。
当然、陽子や中性子の質量の1.2×1019個分の質量≒1.67×-24×1.2×1019=2.004×10-5gとなり、プランク質量2×10-5gと、ほぼ一致する)
※以上の考察は、質量が、プランク質量2×10-5グラムより小さな物体も、重力子を放出できると言い換えられる。
つまりは、プランクエネルギーが持つもう1つの物理的な意味は、重力子を放出できるかどうかを決める閾値ととして意味であると言える。
※たとえ、ミクロレベルの1回の衝突だけでは重力子を放出できない個々の電子やクォーク、陽子… であっても、原始ヒッグス場を変形が蓄積し、この“プランクエネルギーの閾値”をこえることで、重力子を放出することができるようになる。
そして、一方で、大きな物体のマクロレベルの運動に伴い、原始ヒッグス場の“4面体”の変形の蓄積が進むことによっても、この“プランクエネルギーの閾値”に達すれば(=縮みきったバネの“4面体”に至れば)、重力子が放出されると考えられる。
つまり、“プランクエネルギーの閾値”に達するための運動には、ミクロレベル、マクロレベルを含めて様々なものがありうることになる。
よって、プランクエネルギーには、2つの意味を持たせることが結論づけられる。
結論3.3 プランクエネルギーの物理的な意味は、1つは、“1つの重力子の系が持っているエネルギー”、もう1つは、原始ヒッグス場の“4面体”の変形が様々な原因で蓄積され、それが“4角形”(縮みきったバネ)に達して重力子を放出できるようになるという閾値としてのエネルギー”である。
プランクエネルギー以外の各定数についても、その意味(実体像)をまとめてみた。
まとめると、次のようになる。
|
プランク定数
|
h=6.626×10-34J秒 |
振動数ν=1の光子1つ(=素スピノール2つ分の転回運動)の系が持つエネルギー
周期T=1秒で、原始ヒッグス場の“4面体”の中の1つの素スピノールが転回する際、
その“4面体”が蓄えたり放出したりするエネルギーの大きさ
|
|
プランク距離
|
Lp=1.616×10-35m |
素スピノールのペアの間の最短距離 |
|
プランク時間
|
Tp=5.4×10-44秒 |
素スピノールが1回180度転回するためにかかる最短時間 2Tp=1/νp |
|
プランク振動数
|
νp=0.92×1043 |
素スピノールが1秒間に可能な“360度の転回”の最大数。重力子の振動数に等しい。プランクエネルギーが1秒間に放出する重力子の数に等しい。 νp=1/2Tp |
|
プランクエネルギー
|
Ep=1.9561×109J
=hc/2πLp
1.2×1019Gev |
重力子1つ(=素スピノール4つ分の転回運動)の系が持つエネルギー
1つの原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)が持つエネルギー”
(プランク時間Tpの間に1つの“4面体”の中の2個の素スピノールを180度転回する際、
原始ヒッグス場の“4面体”が蓄えたり放出したりするエネルギーの大きさ)
|
※プランク定数は、“1秒”ときってもきれない定数であることになる。 しかし、1秒は、当然、“地球が自転する時間”から決まってきた時間に過ぎない。(“地球が自転する時間”の24分の1の60分の1の60分の1) 実際は、振動数が1より小さい光子も存在するはずだし(例えば、3秒でやっと1回振動できる光子)、周期T=60秒で振動する原始ヒッグス場の“4面体”も、存在するはずである。 つまり、プランク定数の1/3や1/60というエネルギーも、宇宙には実在するはずである。 したがって、プランク定数自体は、宇宙のエネルギーの最小単位であるとは言えない。 もしかしたら、エネルギーについての普遍的で一定な基準値としては、プランエネルギーEpの方がふさわしいのかもしれない。 あるいは、プランク定数よりプランクエネルギーの方が基礎的な実体であると言えるのかもしれない。
しかし、一方、プランク定数は、時間とエネルギーの関係を身近な“1秒”を使って結びつけられる便利な定数であると言えると思われる。 詳しい考察は、今後の課題である。)
※周期1秒で振動する1つの光子のエネルギーは、hであること── 周期2Lp/c秒で振動する重力子1つがもつエネルギーが、hc/2πLpであること── ともに、
アインシュタインの光量子仮説の示す式E=hν(=h/T) と関連がある。
そして、時間のエネルギーについての不確定性原理の式とも、ある程度、関連があると考えられる。 (→考察5)
※プランク距離/プランク時間=Lp/Tpは、光速cに相当する。
最も波長の短い重力子も、2Lp/2Tpで、光速cになる。
一般に光子の波長λが“2nLp”であるとすれば、2nTpの転回周期を持つことになる。(光速が一定なため)
この際、nLpだけ距離の離れた素スピノールが、nTpの時間を費やして、“転回”することを繰り返すことによって、光が光速で進むことになる。
※もう1つのプランクエネルギーを求める式Ep=(hc5/2πG)1/2 と、上記の式Ep=(h/π)×c/2Lp
イコールでつなぐことにより、重力定数Gを計算できると思われた。
hc/2πLp =(hc5/2πG)1/2 より、h2c2/4π2Lp2=hc5/2πG
したがって、 G=2πc3Lp2/h となる。
しかし、これは、もともと、プランク距離を求める式、Lp=(hG/2πc3)1/2から導かれるGと合致するに過ぎない。
ここにあるのは、恒等式の変形にすぎないことになるが── 重力子の振動数や波長の大きさについての仮定(重力子が波長2Lpの光子2つ分が結合エネルギーを放出して結びついているものであるという仮定)が、大きく間違ってはいないことを示していると思われる。
また、重力定数は、プランク距離Lp、光速c、プランク定数hだけから計算できることになるので──
もし、プランク距離Lp、光速c、プランク定数hが一定であるならば、重力定数も一定であることになる。(→考察11)
※各定数のこれまでの表現の中の重力定数Gの代わりに“2πc3Lp2/h”を代入すると、それぞれの定数の意味が、より明確になると思われる。
それは、重力定数Gを Lpで置き換えた表現であると言える。 (cとhは、完全に消えずに残っている)
|
これまでの表現
|
“重力定数GをLpで置き換えた表現”
(Gに、G=2πc3Lp2/h を代入した表現)
|
|
プランク距離
|
Lp=(hG/2πc3)1/2 |
Lp
(素スピノールの間の最小距離)
|
|
プランク時間
|
Tp=(hG/2πc5)1/2 |
Lp/c
(素スピノールが180度転回する最小時間)
|
|
プランクエネルギー
|
Ep=(hc5/2πG)1/2 |
hc/2πLp=(h/2π)×(c/2Lp)×2
(波長2Lpの光子2つ分が結合エネルギー
を放出して結びついているもの)
|
(※“これまでの表現”の部分はウィキペディアを参考にした)j
重力も創発されてきただろうというような自然の成り立ちを考え合わせると── 重力定数Gより、「プランク距離Lp──素スピノールの間の距離」の方が、より基礎的な実体であることをうかがわせる。
※さらに、プランク定数hより、プランクエネルギーEpの方が基礎的な実体であるかもしれないことを考慮して、プランク定数hをプランクエネルギーEpを用いて置き換えて表すと次のようになる。
|
これまでの表現
|
重力定数Gを Lpで置き換え、
さらにプランク定数hをEpで置き換えた表現
|
|
プランク距離Lp
|
Lp=(hG/2πc3)1/2 |
Lp
(素スピノールの間の最小距離)
|
|
プランク時間Tp
|
Tp=(hG/2πc5)1/2 |
Lp/c
(素スピノールが180度転回する最小時間)
|
|
プランクエネルギーEp
|
Ep=(hc5/2πG)1/2 |
Ep
|
|
プランク定数
|
h
|
2πTpEp
(=2πLpEp/c)
|
|
ディラック定数
|
h/2π
|
TpEp
|
※h=2πTpEpである。 1秒と関係しているはずのhが、プランク時間とプランクエネルギーの積だけからも求められると言うこと。 これは、何を意味しているか?
hは、単に1秒だけでなく── (地球の自転と関係ない)「プランク時間&プランクエネルギーの関係」、そして、一般に「時間とエネルギーの関係」にも関与しているということだと思われる。
やはり、プランク定数には、ものすごく深い意味があるのだ。
例えば、もし、プランク時間を1単位にしている星があれば、そこでの、プランク定数は、H=2πEp= h/Tpとなる── ということなのだ。
地球上のように、1秒を1単位にしている“われらの宇宙観”では、プランク定数Hは、そのままH=hとなる。
もし、われわれにとっての“0.1秒分”を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=10hとなるであろう。
もし、われわれにとっての“3秒分”を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=h/3となるであろう。
もし、われわれにとっての60秒分を1単位にしている星があったなら、そこでのプランク定数は、H=h/60となるであろう。
つまり、H=T×Eは、どこの星でも(どのような時間を1単位とする星でも)なりたつ普遍的な原理であるということなのである。
当然、たまたま地球の自転を利用して決めた1秒を単位とした、この星でも、成り立つ──。 そういう普遍的な原理を、H=T×Eの式は表してくれているのである。
(そして、その関係は、原始ヒッグス場の“4面体”がもつ性質として、創発されてきたと考えられるのである。 →考察5)
※光速Cは、ある時間あたりに光が進む距離である。
もし、“3秒分”を1単位といる星があったとしたら、そこでの光速は、C=3c(3秒当たり3c進む)と表記されるであろう。
もし、“1/7秒”を1単位といる星があったとしたら、そこでの光速は、C=c/7(1/7秒当たりc/7進む)と表記されるであろう。
そして、“1秒分”を1単位といる星があるわれわれは、C=c(1秒あたりc進む)と表記している──。 つまり、光速の実体は、どの星でも、かわっていない。
一方、Tp=Lp/Cなので──
もし、“3秒分”を1単位といる星があったとしたら、そこでの、プランク時間は、Tp=Lp/C=Lp/3cと表記されるであろう。
もし、“1/7秒分”を1単位といる星があったとしたら、そこでの、プランク時間は、Tp=Lp/C=7Lp/c と表記されるであろう。
そして。“1秒分”を1単位といる星があるわれわれは、そこでの、プランク時間を、Tp=Lp/c と表記している──。
やはり、表記が変わっているだけで、“プランク時間”の物理的な実体像──“素スピノールが180度転回する最小時間”は、やはり、一切変わっていないと考えられる。
※1つの“4面体”の中の2個の素スピノールが転回する際は、転回周期T×エネルギー振幅E=h/2π となり、これは重力子を説明し──
1つの“4面体”の中の1個の素スピノールが転回する際の式は、転回周期T×エネルギー振幅E=hとなり、これは光子を説明することになる。
このことは、h=2πTpEp の式が、重力子と深い関係があることを示唆している。 それは、プランクエネルギーEp が重力子と深い関係あることと合致している。
※一方、原始ヒッグス場のある1つの基本構造の“4面体”に注目したとき、もし、1秒間にc/2Lp回の頻度(=νp)で重力子がそこを通過したとすれば── 次から次へと絶え間なくエネルギーが供給され続けることになるので、その“4面体”は、常に“4角形”(縮みきったバネ)のままの状態で存在するようになると考えられる。
この場合、その“ずっと縮みきったバネ”の“4角形”の1つの中には── 1つの重力子がつ持つエネルギー×(νp)=(hc/2πLp)×(c/2Lp)=hc2/4πL2p(=(h/π)×ν2p)のエネルギーが単位時間当たりに存在することを意味すると思われる。
もし、そのようなエネルギー密度をもつ空間が、ある広範囲で存在すれば──
つまり、原始ヒッグス場の“4面体”が存在する余地がなくなるほど重力子の密度が高まり、ある“4面体”が、常に“4角形”(ずっと縮みきったバネの“4角形”)であり続けるような性質を持つ“時空の基本構造”が、ある空間の中にびっしりと隈無く充満していれば── その空間には原始ヒッグス場の“4面体”が1つも存在しないので、“4面体”のバネという足場を失った光子は、そこから先に進めなくなることになる。 つまり、このような性質で満たされた空間は、“ブラックホールの境界線の�、すぐ内側に相当すると考えられる。
《量子化された重力、重力場の計算》
上の《重力の実体像》で考察したように、「単位距離あたりの“原始ヒッグス場抵抗”の変化量」=“重位勾配”=重力場は、次のように計算できる。
|
“r=2nLpの地点での重力場”
=(Mc2/4πn2)×(1/2Lp)
=(EpNM/4πn2)×(1/2Lp)
|
※プランク質量M pが生む重力場であり、プランク質量M pに対して働く重力に相当する。(→)
球殻の厚さは、2Lpである。
この質量の中心から2Lpだけ遠ざかるごとに、「厚さ2Lpの球殻のエネルギーの平均値E平均=NMEp/4πn2 」 の中のnが1増え、その分だけ、(その中心から遠ざかる方向において)周囲の時空のエネルギー=重力ポテンシャルエネルギーが増加(追加)すると考えられることは、前に述べた。
さて、このE平均=NMEp/4πn2の値を、1からnまで足し上げた値── これは、r=2nLpの地点での重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)を実際に計算してみる。
※オレンジの高さの部分が、E平均=重力場×2nLp=kGNMEp/4πn2… の値であり、それらを1からnの分まで足しあわせると、それがr=2nLpの地点での重力ポテンシャルエネルギー(の絶対値)に、ほぼ等しくなると考えられる。
|
さて、1からnまでの「r=2nLpの地点での重力場”×2Lp」の値を足しあわせてみよう。
当然、(例えば、(Mc2/2LpMp)×(1/n2)の1からnまでを)足しあわせるにあたって、最も大切な計算は、次の級数の計算である。
1+1/22+1/32+1/42+1/52+ … +1/(n−1)2+1/n2
一般に、nが自然数とき、次の不等式が成り立つことが、数学的な帰納法によって、証明できる。
(参考 『三訂版 高等学校 基礎解析』(昭和63年)の第3章『数列』の中の第2節 数学的帰納法の中の問題13(2))
|
1+1/22+1/32+……+1/n2 ≦ 2−1/n
|
この式は、このタイプの無限級数が発散しないという大事なことを示している。
しかし、よく考えると、この不等式の意味することは、「1/x2を積分した面積の方が、横1縦1/n2 の長方形の面積を足しあわせたものより大きい」という、おおざっぱで当たり前なことを意味しているにすぎないとも言える。
※y=1/x2 を1からnまで積分によって求めた面積(下図のピンクの部分の面積)は、「1−1/n」である。
そこに「 1」(一番左側のオレンジの面積)を足しあわせた面積は、明らかに、オレンジの部分の総和より大きい。
|
しかし、この式は、このタイプの無限級数が発散しないという大事なことを示していると言える。
より正確な値を求められないであろうか?
文献を調べると── 「1+1/22+1/32+… の無限級数は、π2/6に収束する」とのことであった。
(この無限級数の問題は、「バーゼル問題」と呼ばれていて、偉大な数学者オイラーが、10年もかけて証明したとのことである。
参考 『なるほど高校数学 数列の物語』p.170 宇野勝博 講談社ブルーバックス)
(2−1/n)において、nを無限大にした際、2に収束してしまうところを── π2/6に収束するように改善すればよいことになる。
つまり、問題の級数は、近似的ではあるが、より正確に次のように計算できることになる。
|
1+1/22+1/32+……+1/n2 ≒ π2/6−1/n
|
※なお、このときの、「1/n」は、y=1/x2 をnから∞までの積分によって求めた面積(下図のピンク面積)に相当すると考えられる。
つまり、「1/n2 を1から∞まで足しあわせた面積π2/6」から、この「y=1/x2 をnから∞までの積分によって求めた面積1/n(ピンクの面積)」を引くことで、近似的に、「1+1/22+1/32+……+1/n2 」の面積(下図のオレンジの面積の総和)を計算していることになる。
※y=1/x2 をnから∞までの積分によって求める面積(ピンクの部分の面積)は、「1/n」である。
|
したがって、厳密には、「1+1/22+1/32+……+1/n2 ≧ π2/6−1/n」ということになる。
(つまり、トータルで 「2−1/n ≧ 1+1/22+1/32+……+1/n2 ≧ π2/6−1/n」ということになる。)
そして、nが大きければ大きいほど誤差が小さくなる「π2/6−1/n」が、近似値として、よりふさわしいと考えられる。
[ 以上より、r=2nLpの場所での、重力ポテンシャルエネルギーは、例えば、
|
n
Σ (kNMEp/4π)×(1/n2)
n=1
|
≒(kNMEp/4π)×(π2/6−1/n)=kπNMEp/24−kNMEp/4πn |
|
というように近似的に計算できることになる。
※たとえ“1cm”でも、r=2nLpの中のnの値は、n=0.01m/2×(1.616×10-35)m≒0.309×1033と非常に大きなものとなるので、少なくとも、われわれの日常的な距離で考えれば、かなり正確な値になっていると考えられる。
※無限遠方のr=∞の地点での、重力ポテンシャルエネルギーの大きさも、簡単に正確に求められることになる。
より── 例えば、
|
∞
Σ (kGNMEp/4π)×(1/n2)
n=1
|
=(kGNMEp/4π)×π2/6=kGπNMEp/24 |
|
というように。
いわゆる重力ポテンシャルエネルギーの式、−GM/r は、無限遠点を重力ポテンシャルエネルギーを0としたときの、相対的なものであるといえる一方── 先ほど、求めたr=2nLpの地点での、重力ポテンシャルエネルギーの大きさ
|
n
Σ (kGNMEp/4π)×(1/n2)
n=1
|
≒(kGNMEp/4π)×(π2/6−1/n)=kGπNMEp/24−kNMEp/4πn |
|
は、質量Mの中心の重力ポテンシャルエネルギー0としたときの、絶対的なものであると言える。
※−GM/rの大きさは、下に図示してある部分に相当する。
※図の底辺rと高さGM/rの三角形の斜辺の傾きの起きさと、rでのカーブの傾きは等しくなると思われる。
なぜなら、rの地点での“勾配”は、(GM/r)/r=GM/r2と求められ、これがニュートン力学と合致するからである。
|
無限遠方のr=∞の地点での、重力ポテンシャルエネルギーの大きさは、kGπNMEp/24 となると考えられるので──
「 kGπNMEp/24−kGNMEp/4πn 」の中で、“−GM/r”に、相当する部分は、まさに、この式のマイナス項── 「 −kGNMEp/4πn 」であると言えると考えられる。
※この関係を使うと── 重力場GM/r2=(GM/r)×(1/2nLp)= kGNMEp/4πn×(1/2nLp)= kGNMEp/4πn2×(1/2Lp) と計算でき、先の重力場の“EMOES表記”と、ぴったり合っている。
以上より、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に基づいた量子化された重力場、重力ポテンシャルエネルギーの計算結果──
r=2nLpの地点での重力場=kGNMEp/4πn2×(1/2Lp)
r=2nLpの地点での(絶対的な)重力ポテンシャルエネルギー =kGπNMEp/24−kGNMEp/4πn
は、ニュートン力学と矛盾していないと考えられる。
|
ニュートン力学
|
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)
に基づいて量子化されたもの
|
|
重力ポテンシャルエネルギー
|
−GM/r
※無限遠方を0としたときの
相対的なもの
|
kGπNMEp/24−kGNMEp/4πn
※物質の取り囲む球面の中心を0
としたときの絶対的なもの
|
|
重力場
|
GM/r2
|
kGNMEp/4πn2×(1/2Lp)
|
以上のような“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に基づく「重力&重力ポテンシャルエネルギーの量子化」の理論においては、重力の大きさ、重力ポテンシャルエネルギー、重力場が持つ総エネルギーについて、いずれにおいても、無限大は生じず(発散が生じず)、繰り込みが不要になっていると考えられる。
そして、なおかつ、先の考察のように“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に基づいて、アインシュタインの相対性理論に関した現象(光速不変の原理、等価原理…)を説明できるのだった。
以上の考察は、重力の量子化に成功していると言えるだろうか?
アインシュタインが、難解な数式で求めた“時空の曲がり”を生じるものの実体を、単純な計算で求めてしまったと言っていいのだろうか?
少なくとも、「“4角形”(縮みきったバネ)の密度(≒時間&空間平均)」と、重力&重力ポテンシャルエネルギーの間には、深い関係があり── この関係が重力の量子化のためにおおいに役立つことは確かだろうと考える。
アインシュタイン方程式との整合性を含め、より詳しい検討は、今後の課題である。
球殻内にある“4角形”(縮みきったバネ)の数 NM=M/Mp で求まることについて。
プランク質量Mpが1秒間に放出する重力子の総数は、νp である。(νpとは、c/2Lpのことである)
よって、質量Mが1秒間に放出する重力子の総数は、(M/Mp)×νpである。…(0)
シュバルツシルト半径rsの場所(ブラックホールの事象の地平面)には“4角形”(縮みきったバネ)が100%びっしりとつまっていると考えられるので(→考察7)その球の表面積4πr2sを、“4角形”(縮みきったバネ)の1つの面積(2Lp)2=4Lp2で割ると、球面全体の中に存在する“4角形”(縮みきったバネ)の数が計算できる。
ブラックホールの表面全体の中に存在する“4角形”(縮みきったバネ)の数=4πr2s/4Lp2=πr2s/Lp2 …(1)
この球面が、(重力子は、すぐとなりの原始ヒッグス場の“4面体”を伝わっていくので)1秒間にνp枚分が放出されると考えることもできる。 つまり、(1)×νp =(πr2s/Lp2)×νp …(2)が、質量Mが1秒間に放出する重力子の総数のもう1つの求め方になる。
したがって、(0)=(2)とすると── (M/Mp)×νp=πr2s/Lp2×νp となり── その結果、(M/πMp)=r2s/Lp2となる。…(3)
一方、この物体の中心からの距離をrとすると、rの場所での球殻の中に“4角形”(縮みきったバネ)が何%存在しているかを考える。
rsの地点で100%存在しており、そのパーセンテージは“球面の面積”に反比例すると考えられるので── rの場所では、単純に(4πr2s/4πr2)×100%=(r2s/r2)×100% …(4)存在することになると考えられる。
rsの場所で球殻内にある“4角形”(縮みきったバネ)の単位面積当たりの数は、(1)を球面積で割って (4πr2s/4Lp2)/4πr2s=1/4Lp2であるので── rの場所での球殻の中での“4角形”(縮みきったバネ)の単位面積当たりの数は、(4)の比率を使い、(1/4Lp2)×(r2s/r2)となる。
ここに(3)より求まる、r2s=(M/πMp)×Lp2を代入すると── rの場所での球面の中での“4角形”(縮みきったバネ)の単位面積当たりの数=(1/4Lp2)×(M/πMp)×Lp2×(1/r2)=(1/4πMp)×(M/r2)=(M/Mp)×(1/4πr2)となる。 …(5)
(※なお、この形から(5)に、なんらかの定数をかけることによっても、重力が求められることになる。)
すると、(5)を、球殻内にある“4角形”(縮みきったバネ)の数NMとすると、その単位面積当たりの数は、NM/4πr2となる。 それが、(5)と等しいので、NM=M/Mpが求まる。
これは、やはり、1つの球殻内の“4角形”(縮みきったバネ)の数を意味し── 質量Mが1秒間に放出する重力子の総数の式、(M/Mp)×νpの式は、 「(M/Mp)個の重力子を含む球面」を1秒間にνp枚分放出されることを意味していると解釈できることになる。
また、あるプランク質量Mpは、厚さ2Lpの球殻のどこかの場所に、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」1つもれなく供給していることを意味していると考えられる。
また、この式により、E=Mc2=NMEPが、ぴったり成り立つことになる。 |
《静電場(クーロンの法則)のEMOES表記》
ニュートンの万有引力の法則の“EMOES表記”は、上の考察で行なった。
ニュートンの万有引力の法則とクーロンの法則の数式は、互いに形が似ているので、クーロンの法則F=kQq/r2=Qq/4πε0r2も“EMOES表記”が可能なはずであると考えた。
電荷の中心からr=2nLp離れた場所で、電荷から放出された仮想光子が作る、1つの「変形した“4面体”」(部分的に縮んだバネ)が持つエネルギーの最大値Eは、(c=νλ、r=λ/2であるので)E=hν=hc/λ=hc/2r=hc/4nLpとなる。
そして、その変形の周期は、転回周期と等しいので、T=h/E=h×(4nLp/hc)=4nLp/cと求まる。
1つの仮想光子がある球殻にもたらす「“4面体”の変形にともなうエネルギーの平均値」は、下図のようにグラフの形から、単純に、「“4面体”の変形に伴うエネルギーの最大値E」×1/2=hc/8nLpと求まる。
※赤い斜線の部分と、オレンジの斜線の部分の部分が全く等しい。
ところで、“力”に寄与する“原始ヒッグス場抵抗”は、「“4面体”が蓄えるエネルギーの時間平均」に等しいはずである。
その「“4面体”が蓄えるエネルギーの時間平均」は、次の式によって求められるはずである。
「“4面体”が蓄えるエネルギーの時間平均」
=「“4面体”の変形にともなうエネルギーの平均値」×「“4面体”が変形している時間(=転回周期)」/(「“4面体”が変形している時間(転回周期)+“4面体”が変形していない時間)
例えば、“ある一定の時間内に、1つの仮想光子が生じる場合の時間平均”を考えると、どれも等しくなることが分かる。
※オレンジの四角は、「“4面体”に蓄えられるエネルギーの“転回中(変形している時間内)”の平均」を表し、最大値の1/2となっとなっている。
それに対し、今求めたい「“4面体”に蓄えられるエネルギーの時間平均」は、「変形していない時間」も考慮しなければならない。
例えば、上図のように、3種類の転回周期を持つ仮想光子による“4面体”の変形を考えると、その時間平均は、どれも等しくなる。
すなわち、例えば、「T=3という時間内での時間平均」は── 3種類とも、一番下のオレンジの四角と同じになる。 |
以上の考察から、 次の結論に至る。
「1つの仮想光子が、r=2nLpある球殻にもたらすエネルギーE」の時間平均は、nの値に関わらず一定の値になる。
一秒間にν個の仮想光子が、r=2nLpある球殻に変形する場合、“4面体”に蓄えられるエネルギーEの時間平均を考える。 それは、次のように計算され、nに関わらず一定となる。
ν×{En/2×Tn+0×(1−Tn)}/1=ν×hc/8nLp×(8nLp/c)=ν×h/2
※ν=3の場合を図示した。
それぞれの1秒間の時間平均を求め、ν倍すれば、全体の時間平均が計算できる。
「変形している時間(Tn)+変形していない時間」=1秒であるので、 それぞれの1秒間の時間平均は、
{En/2×Tn+0×(1−Tn)}/1=(hc/4nLp)/2×(4nLp/c)=h/2 と計算できる。
|
「ある電荷Qの中心からr=2nLp離れた場所にある厚さ2Lpの球殻が持っているエネルギーの総和の、1秒間での時間平均」は、h/2×「その球殻内&1秒間で変形している“4面体”の個数」で求まることになる。
※それは、nに関わらず一定となる。 この性質は、ガウスの法則と調和すると思われる。 そして、このあたりには、「そもそも、なぜ、ガウスの法則が成り立つのか」を説明するヒントがあると言えると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
重力の場合にある質量Mが、プランク質量Mpの何個分かを考えたように── クーロン力の場合にも、ある電荷Qが、ある基本電荷の何個分か考えていく。
ある基本電荷として何がふさわしいか?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、その基本電荷Qpを、「厚さ2Lpの球殻に、一秒間にc/4Lp個の“4面体”の変形をもたらすような電荷である」と定義し、プランク電荷と呼ぶこととする。
プランク電荷は、n=1 の最も内側の球殻に、常に、1つの“4面体”を変形させることのできる電荷であると言える。
(特に、n=1のとき(r=2Lpの場所のとき)、仮想光子は、T=4Lp/cの周期で変形の生成と消滅を繰り返す。(T=2Lp/cの時間で変形を生じ、T=2Lp/cの時間で、変形を消滅させる。 n=1のときのエネルギーが、hc/4Lpが、プランクエネルギー(重力子が持つエネルギー)より大きくなっている。 このことは、この変形が“仮想光子”によるものであり、半波長進み&半波長逆行する形で、再度、元に戻るので問題ないと思われる。 →考察6)
※プランク電荷Qpが、少なくとも“ν=c/4Lp”の頻度で変形できるということは、 ν=c/4Lp≒3×108/4×1.6×10-35≒0.5×1043であるので、これは、とてつもなく大きな頻度であることになる。
(プランク質量Mpは、プランクエネルギーEp=hc/2πLp のエネルギーを持つ“4面体”の変形を、νp=c/2Lp の頻度でできる質量であった。)
一方、この電荷は、当然、他の球殻にも、「変形した“4面体”」を作りうる。
プランク電荷Qpは、その定義より、r=2nLp に対応する球殻にも、一秒間に、c/4Lp個の変形した“4面体”を作る。
よって、「プランク電荷Qpの中心からr=2nLp離れた場所にある厚さ2Lpの球殻が持っているエネルギーの総和の、1秒間での時間平均」は、
h/2×「その球殻内&1秒間で変形している“4面体”の個数」=h/2×ν= hc/8Lp と求まることになる。
※やはり、それは、nに関わらず一定となる。 この性質も、ガウスの法則と調和すると思われる。 そして、このあたりには、「そもそも、なぜ、ガウスの法則が成り立つのか」を説明するヒントがあると言えると思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※ 一般に、NQ個のプランク電荷から構成された電荷は、Q=NQQpと表記でき、厚さ2Lpの球殻内で、1秒間にNQ×(c/4Lp)=個の“4面体”が変化していることになる。
その上で、さらに、プランク電荷Qpの中心からr=2nLp離れた場所にある厚さ2Lpの球殻が持っているエネルギーの空間平均の値を計算してみる。
r=2nLp離れた所にある厚さ2Lpの球殻の全面積は、およそ4πr2=16πn2L2pであり── そのうち、“4角形”(縮みきったバネ)が占める面積は、(2Lp)2×1である。 「変形した“4面体”」の部分のエネルギーの時間平均が「hc/8Lp」であり、それ以外の場所は変形していない“4面体”であり、そのエネルギーは、相対的に0である。
よって、プランク電荷Qpの周囲の厚さ2Lpの球殻のエネルギーの時間&球面平均をE平均と書くことにすると
E平均={(2Lp)2(hc/8Lp)×1 + (4πr2−(2Lp)2×1)×0}/4πr2
=4L2p×(hc/8Lp)×(1/16πn2Lp2)= hc/32πLpn2
となる。
この上で、r=2nLpの場所でのプランク電荷Qpの電場を求める。 エネルギーE平均が“厚さ2Lpの球殻”が持つ“電位差V”に相当すると考えられるので──
E平均を底辺2Lpで割れば、エネルギー勾配、つまり、電場が計算できる。
r=2nLpの場所での基本電荷Qpが作る電場E=E平均/2Lp= (hc/8Lp)×(1/4πn2Lp)×(1/2Lp) …(1)
一方、クローンの法則の式から求まる電場の式を変形してみる。
基本電荷Qpが作る電場E=kQp/r2=Qp/4πε0r2
(1/ε0=c2μ0 であるので──)
=c2μ0Qp/4πr2
(式に1=(2Lp)2 /(2Lp)2 をかけて(=分母と分子の両方に(2Lp)2 をかけて)、r=2nLpを代入して整理すると──)
=(μ0/2Lp)×(Qpc2)×(4L2p/16πn2L2p)×(1/2Lp)
=(μ0/2)×(Qpc2)×(1/4πn2Lp)×(1/2Lp) …(2)
ここで、(1)と(2)を比較してみると──
「Qpc2 ∝ hν(=hc/8Lp)」と考えればつじつまが合うと思われた。(∝は、比例しているという記号) 本当にそのようなことが可能であろうか?
ここで、次元解析を行なう。
右辺の「hν(=hc/8Lp)」の単位は、[J]=[kg・m2/s2]である。
左辺の「Qpc2」の単位は、[C・m2/s2]=[C・m2/s2]となる。
つまりは、クーロンCの単位について、[C]∝[kg]でありさえすれば、つじつまが合うことが予想された。
仮説3.2 クーロンの単位[C]は、[kg]に比例する
※質量も電荷も、両方とも、「原始ヒッグス場の“4面体”を変形させる能力である」という意味で統一できるので、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)のパラダイムで、考えれば、決して無理のある仮説ではない。
果たして、そのようなことが、本当に可能であろうか?
簡単に検証してみる。
|
(1)例えば、「1クーロン=1アンペア×1秒と電気量が決められている。」とのことである。 (参考 『物理学入門』p.133 実教出版株式会社)
つまりは、[C]=[A・s]であり、仮説が3.2が正しければ、[A]=[kg/s]ということになる。
一方、「電流の強さI[A]は、次の式で表される。 I=nqvS 」とのことである。 (参考 『物理学入門』p.156 実教出版株式会社)
右辺の次元は、nqvS [1/m3・C・m/s・m2]=[1/m3・kg・m/s・m2]=[kg/s]となり、矛盾していない。
(2)コンデンサーの電気容量C0[F]は、 C0=1/4πk・S/d=ε0S/d となる。(参考 『物理学入門』p.146 実教出版株式会社)
ε0S/d [C2/N・m2][m2][1/m]=([kg]2/[kg・m/s2・m2])[m2][1/m]=[kg・s2/m2]
一方、1[F]=1[C/V]=1[C][C/J]=1[kg][kg]/[kg・m2/s2]=[kg・s2/m2]となり、
やはり、矛盾していない。
(3)(μ0/2)×(Qpc2)×(1/4πn2Lp)×(1/2Lp) …(2) の単位はどうなるか?
μ0=4π×10-7[N/A2]であるので──
[N/A2][J][1/m]=([N]/[kg2/s2])・[kg・m2/s2][1/m2]=[N][1/kg]=[N/C]=[E](電場)となり、やはり、矛盾していない。
|
クローンの単位[C]と[kg]は比例するという考えは、決して、的外れではないことが分かる。 (比例定数は何か? カギは、共通項の原始ヒッグス場圧である。→下の考察)
「Qpc2 ∝ hν 」の意味、 クーロンの単位[C]が、[kg]に比例することの意味を考えてみる。
それは、「Qpc2 ∝ hν」は、「アインシュタインの式E=mc2 の電荷版である」ということである。
質量mがE=mc2 のエネルギーを持つように、電荷Qには、「E= Qc2 =hν」に比例したエネルギーがつまっているということである。
果たして、係数(比例定数)は何が正しいのか?
(μ0/2)×(Qpc2)×(1/4πn2Lp)×(1/2Lp) …(2)
と、ニュートンの万有引力Fと比較してみる。
|
“ニュートンの万有引力F”=GMm/r2
=(EpNM/4Lpn2)×Nm
=(Mc2/4Lpn2)×(m/Mp)
|
|
ニュートンの万有引力の法則
|
クーロンの法則
|
|
数式
|
F=GMm/r2
|
F=kQq/r2=Qq/4πεr2
|
|
“EMOES表記”
|
F=(EpNM/2n2)×(1/2Lp)×Nm
=(Mc2/2n2)×(1/2Lp)×(1/Mp)×m
|
F=(Qc2)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×(μ0/2Lp)×q
=NQ(ahc/8Lp)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×b(μ0/2Lp)×q
|
|
|
|
※無次元の比例定数をa、bとした。
|
「Qc2=NQQpc2=NQ(ahc/8Lp) 」…(3) となる。
よって、両辺を、NQc2で割って、Qp=ah/8cLp …(4)となる。
ところで、b(μ0/2Lp)とは、何か? 次元解析をすると [N/A2][1/m]=[kg・m/s2][s2/kg2][1/m]=[1/kg]となる。
この次元は、電荷の逆数の次元に等しいものである。 つまり、b(μ0/2Lp)が、プランク電荷の逆数に等しいものとなるようなbを計算で求めることができることを意味している。
よって、 1/Qp=b(μ0/2Lp)となる。 …(5)
(4)と(5)より、 「 ab=16cLp2/hμ0 」(無次元の定数である)が求まる。
b=16cLp2/ahμ0を代入すると── クーロンの法則は、次のように書き換えられる。
F =NQ(ahc/8Lp)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×b(μ0/2Lp)×q
=NQ(ahc/8Lp)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×1/(ah/8cLp)×q …(6)
(仮にa=1とすると──)
=NQ(hc/8Lp)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×1/(h/8cLp)×q
=NQ(hc/8Lp)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×Nq
となった。
ここで、ニュートンの万有引力の法則の式
F=(EpNM/2n2)×(1/2Lp)×Nm
=NM(hc/2πLp)×{1/2n2)×(1/2Lp)×1/(hc/2πcLp)×m
と比較してみると、ニュートンの万有引力の法則の式にも、a/aの定数を想定できる点を含め、非常によい対応関係が認められる。
※重力と同様に、本当に素直に、a=1でいいのだろうか?
実際は、ここまでの数式の上だけでは、a=2でも、a=πでも、矛盾はなさそうである。 ニュートンの万有引力の法則の式の場合は、“プランクエネルギーの理論計算値から、1つに決まるのでこういった問題がなかった。 クーロンの法則の場合は、aの値を絞り込み確定してくれる根拠がどにあるだろうか?
Q[C]の作る電場を二通りで、表記してみる。
1つは、(6)を徹底的に計算を進め、シンプル化したもの。
E[N/C]=NQ(hc/8Lp)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×1/(h/8cLp)
=NQc2/8πLpn2…(7)
もう1つは、再度クーロンの法則から、導いたもの。
E[N/C]=kQ/r2=c2μ0NQQp/4πr2
=NQ(μ0/2)×(Qpc2)×(1/4πn2Lp)×(1/2Lp)…(8)
(7)=(8)とすると、NQc2/8πLpn2=NQ(μ0/2)×(Qpc2)×(1/4πn2Lp)×(1/2Lp)
より、Qp=2Lp/μ0
のように、Qp=の値が求まってしまった。
これは、b=1であることを意味している。
よって、「 ab=16cLp2/hμ0 」(無次元の定)より、「a=16cLp2/hμ0」
求まってしまった。
よって、クーロンの式は、次のようになる。
F=NQ(ahc/8Lp)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×1/(ah/8cLp)×q …(6)
(a=16cLp2/hμ0として──)
=NQ((16cLp2/hμ0)×(hc/8Lp)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×1/((16cLp2/hμ0)×h/8cLp)×q
=NQ(2c2Lp/μ0)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×1/(2Lp/μ0)×q
よって、式(3)の次元をみる。
「Qc2[J]=NQQpc2[J]=NQ(ahc/8Lp)[J]」
a[無次元定数]の意味は、何か?
Qpc2[J]=Qc2[C・m2/s2]である一方
ahc/8Lp[J]=ahc/8Lp[kg・m2/s2]であることからわかる。
※hc/8Lpの次元はは、プランクエネルギーhc/2πLp[kg・m2/s2]と同じ次元である。
つまり、「a=16cLp2/hμ0」[無次元定数]は、「kg」を「クローンC」に変える比例定数であると言える。
ところで、 Mc2=EpNM=(hc/2πLp)×M/Mp より、「Mpc2=(hc/2πLp)」…(9)である。
この(6)と(3)「Qpc2=a(hc/8Lp) 」より、
Qpc2/Mpc2=(ahc/8Lp)/(hc/2πLp)=aπ/4
となる。
よって、 Qp[C]/Mp[kg]=aπ/4 なので、 Qp[C]=(aπ/4)×Mp =a×((π/4)×Mp[kg])となる。
そして、やはり、 Qp[C]=(16cLp2/hμ0)×(π/2)×(h/2πcLp)=2Lp/μ0[C]と、ぴったり一致する。
よって、プランク電荷Qp[C]=2×1.616×10-35/4π×10-7≒1×1.616×10-35/2π×10-7≒2.5719×10-29[C]
(Lp=1.616×10-35m、μ0=4π×10-7 2π=2×3.14159 とした)
という値になる。 電子は、1.60×10-19[C]なので、それに比べて、およそ1010も、小さいことになる。
※このことは、電子の中に内部構造が存在することを示唆しているようにも見える。(→考察6)
※「a=16cLp2/hμ0」=1.5045311×10-21
1Cは、1.0620118×10-4[J]を持つ。
以上より、クーロンの法則の“EMOES表記”は、次のようにシンプルになる。
|
ニュートンの万有引力の法則
|
クーロンの法則
|
|
数式
|
F=GMm/r2
|
F=kQq/r2=Qq/4πεr2
|
|
“EMOES表記”
|
F=(EpNM/2n2)×(1/2Lp)×Nm
=(Mc2/2n2)×(1/2Lp)×(1/Mp)×m
|
F=(NQQpc2/4πn2)×(1/2Lp)×Nq
(=NQ(2c2Lp/μ0)×(1/4πn2)×(1/2Lp)×(μ0/2Lp)×q)
=(Qc2/4πn2)×(1/2Lp)×(1/Qp)×q
|
このクーロンの法則の“EMOES表記”は、クーロン力がなぜ生じるのかを説明している。
やはり、この式は、クーロン力は、Qから放出される仮想光子が作る電場(=“原始ヒッグス場の“4面体”の変形の総和”)によって生じていることを、はっきり示している。
以上のような関係は、かたや、質量mが持つエネルギーがE=mc2[J](=[kg・m2/s2])であるように、電荷Qが持つエネルギーがE=Qc2[J](=[C・m2/s2])であることを示している。
質量とは、「重力子を新たに放出させる能力」なのであり、E=mc2のエネルギーを持つものなのであった。
そして、ミクロの素粒子レベルで光速で運動し続けることが、光速cが登場する理由として考えられるのであった。
一方──
電荷とは、「“仮想光子”を新たに放出させる能力」なのであり、E=Qc2のエネルギーを持つものと言える。
そして、ミクロの“素電荷レベル”で光速で運動し続けることが、光速cが登場する理由として考えられることを示唆しているように思われる。
(電荷の詳細は、考察6電荷の起源)
そして、 ニュートンの万有引力の法則の“EMOES表記”の式&c2を登場させた式は、中心からr=2nLpの距離の厚さ2Lpの球殻が持つエネルギーが、nに関わらず、どこでも同じ、Mc2=EpNM であることを示している。
それは、厚さ2Lpの球殻は、すべての1枚1枚がそれぞれに、Mc2=EpNM のエネルギーが蓄えられていることを意味している。
質量エネルギーMc2が一定で保存される一方── それと全く同じ大きさのエネルギーを持つ「厚さ2Lpの球殻」という“皮”が、周辺の時空に、タマネギの皮のように、何層にも渡って重なって存在していることになる。
厚さ2Lpの球殻の1枚1枚が持つエネルギーは、エネルギー保存則を破って生じる仮想粒子(重力子)の集合が持つエネルギーである。 よって── ここには、“仮想エネルギー保存則”とでも呼んでいいような“保存則”が存在すると言えるのかもしれない。
クーロンの法則の“EMOES表記”の式&c2を登場させた式についても、同様の考察ができる。
電荷Qの中心からr=2nLpの距離の厚さ2Lpの球殻が持つエネルギーが、nに関わらず、(ahc/8Lp)×NQ=Qc2 であることを、式は示している。
それは、厚さ2Lpの球殻は、すべての1枚1枚がそれぞれに、Qc2 という一定のエネルギーを持つということを意味している。
電荷エネルギーが一定で保存される一方── それと同じエネルギーを持つ厚さ2Lpの“皮”(球殻)が、周辺の時空に、タマネギの皮のように、何層にも渡って重なっていることになる。
厚さ2Lpの球殻の1枚1枚が持つエネルギーは、エネルギー保存則を破って生じる仮想光子の集合が持つエネルギーである。 よって── ここにも、“仮想エネルギー保存則”とでも呼んでいいような“保存則”が存在すると言えるのかもしれない。
※この考察は、「なぜ、ガウスの法則が成り立つのか?」について、1つの説明を与えると思われる。
その説明とは、「“仮想エネルギー保存則”が成り立っているからである」というものである。
そして、そもそも、なぜ“仮想エネルギー保存則”が成り立つのかは、やはり、上でも触れたように、「“素電荷”が持つ“決定論的カオスが生むランダムな運動”」と「転回周期Tが仮想光子の滞在時間(寿命)と波長を一定に決める性質」の2つの理由から、自然に(必然的に)、“仮想エネルギー保存則”を生じると考えていいと思われる。 詳細な検討は、今後の課題である。
※以上の考察には、『「点電荷の自己エネルギー」という有名な問題』(参考 p139『これならわかる電磁気学』 遠藤雅守 ナツメ社)を解くカギがあると思われる。 “EMOES”によれば、『電荷の自己エネルギー』においても、無限大は生じず、繰り込みが不要になると考えられる。
※プランクエネルギーEp(=hc/2πLp)=プランク質量Mp(=h/2πcLp)×c2、
EQP(=hc/4Lp)=Qp×c2より── Qp=EQP/c2=h/4cLp=(π/2)×Mp となる。
この式は、電荷Qの単位クーロンC(=A・s)と、質量mの単位kgが、イコールで結ばれることを意味している。 このことは、電荷Q(C=A・s)と質量m(kg)が、統合されうることを示していると思われる。(“EMOES”によれぱ、ともに“周囲の時空を変形させる能力”であると言えるので、それは自然なことである。) そして、もし正しければ、MKSA単位系は、MKS単位系に、シンプル化できることを意味していると思われる。(A・s=kg、より、A=kg・s-1、となる)
そもそも、質量kgも、長さmも、時間sも、クーロンCも、もそもそ人類が恣意的にとり決めた単位だった(実際、貫匁、ポンドという重さ単位、尺寸、ヤード、マイルと言う長さの単位もあったくらいなので…)。 しかし、「プランク質量Mpの何倍か? プランク距離Lpの何倍か? プランク時間Tpの何倍か? プランク電荷Qpの何倍か?」ならば、必然的な単位としてと利用できる。(kg、貫匁、ポンド、メートル、尺寸、ヤード、マイルどれを使っていようが関係なく共有できる単位となる。 すなわち、全宇宙で共有できる) そして、Qp(h/4cLp)は、Mp(h/2πcLp)の(π/2倍)であり、少なくとも単位の上で、統合できそうである。 ただし、Qp=h/4cLpは、MKS単位系のクーロンの数値と言えるものであり、既存のMKSA単位系のクーロンの数値とは、全く異なっている可能性もあると思われた。 それとも、QV=Q×(I/R)の単位は、結局、ジュール J(m2・kg・s-2)なので、既存のクーロンの数値をそのまま使っていいのだろうか?
それとも、あるいは、これまでの考察のどこかに間違いがあることを意味しているのだろうか? 詳細な検討は、今後の課題である。
《重力場、エネルギー、質量、非線形性、電磁場の線形性との比較》
重力子は、それ自体は質量を持たない。 だからこそ、光速で無限遠方まで移動できる。
典型的な重力子は放出源は── 物体の質量を構成する、(ミクロレベルで光速で運動し続ける)素粒子の総和である。
(なお、プレオン∴×4の“4角形”(四極子)も、重力子の放出源になると考えられる。 →考察3)
他に、原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)も、重力子の放出源であると見なすことができるが── やはり、その大元は、物体の質量を構成する素粒子の総和である。
ふつう、重力子は、“素粒子の総和”が持つ質量(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を新たに放出する能力)が原因となって、放出される。
つまり、決して重力子自身が質量を持っているわけではない。(やはり、もし質量を持っていたら、光速で移動できない)
よって重力子が一定の頻度で放出され続けていることは、決して、質量(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を新たに放出する能力)が増え続けることを意味しない。
“素粒子が質量を獲得する”過程とは、重力子を新たに放出できるようになる過程であり、「“4面体”→“4角形”(縮みきったバネ)」のように、原始ヒッグス場の基本構造を変形させられるようになる過程そのものと言える。
一定時間内にどれくらいの頻度で、「“4面体”から“4角形”(縮みきったバネ)へ」と原始ヒッグス場の基本構造を変形させることができるかは、質量の大きさに比例する。(まさに質量は、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を新たに放出する能力である)
|
|
|
←生じる“4角形”(縮みきったバネ)の密度が
小さいほど質量が小さい |
生じる“4角形”(縮みきったバネ)の密度が
大きいほど、質量が大きい→
|
|
質量とは、一定時間内に、周囲の原始ヒッグス場の基本構造を「“4面体”→“4角形”(縮みきったバネ)」のように新たに変形させる能力そのものであるとも言える。
素粒子は、もともと、はじめから“重力子を新たに放出できるほどの能力”を持っていたはずなので── そういう意味では、“素粒子が質量を獲得する”という表現より、“素粒子が質量を発揮する”と言う方が、適切なのかもしれない)
その物質が持つ質量によって生み出された重力場は、確かにエネルギーを持つといえる。
しかし、その“重力場が持つエネルギー”は、あくまで、その大元の物質が持つ質量(重力子を新たに放出する能力)によって放出された、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」のエネルギーの総和に過ぎないのであり── その“重力場が持つエネルギー”自身が、新たな重力子の放出源となることは、決してありえないと考えられる。
(したがって、“重力場が持つエネルギー”自体が“新たな質量”になるということもありえない。)
つまり、“エネルギーを持つ重力場”そのものが“質量を持つ”(=重力子を新たに放出する能力を持つ)ということは決して起こらず── 質量(=重力子を新たに放出する能力)を持ち続けるものは、あくまで、大元の物質であると言うことなのである。
一見、重力場がエネルギー(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」)を放出しているように思われるかもしれないが── 大元の物質の質量こそが、“重力場の持つエネルギー”のすべてを供給し続けているのであり── 重力場は、あくまで“エネルギーの通過点”に過ぎないと言うことなのである。
(「たとえ、途中の電線からエネルギーが放出されるように見えても、実際は、すべてのエネルギーが発電所から供給されている── ということと似ていると思われる。 やはり、決して途中の電線から新たにエネルギーが生まれるわけではなく、電線はエネルギーの通過点に過ぎないのである」ということと似ていると思われる。)
つまり、以上のことは、「エネルギーがあっても、質量を持つとは限らない」こと、「質量は、あくまで、エネルギーの1つのあり方にすぎない」ことを示していると思われる。
※質量(=重力子を新たに放出する能力)があれは、必ずエネルギーがあるが──
エネルギーがあるからといって必ず質量(=重力子を新たに放出する能力)があるとは限らない。
(質量→エネルギー○ エネルギー→質量× エネルギーは質量の必要条件であるが十分条件ではない)
※重力子(重力場)の他に、光子(電磁場)も、エネルギーを持つけれども、質量を持たないものの例である。
(※本来、この図は、数学の集合の図にすぎないが── 物質と重力場の関係を表す図とも少し似ている) |
重力場は確かにエネルギーを持つけれども、質量(=重力子を新たに生じる能力)を持たないのであり── 「重力場が、(質量を持つ物体によるもの以外の)新たな重力子を生じる(質量を持つ)」と考えることも、「 重力場のエネルギーそのものを、E=mc2の式にあてはめて、“重力場の質量”を計算で求めること」もナンセンスだと言うことになる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── 「重力場(重力子&原始ヒッグス場の総和)そのものが、(“質量を持つ物体”という大元の放出源によるもの以外に)新たに重力子を放出できるようになる(質量を持つ)」ことはないことを、はっきり示している。
重力場は、やはり、大元の波源(質量)から届いてくる「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」をリレー(転送)し続けているだけである。
アインシュタインの重力場についての方程式(アインシュタイン方程式)では、
左辺が“時空の曲がり”(曲率)を意味する一方で、右辺には時空を曲げる原因(物質のエネルギー密度(質量密度)や運動量)となるものが入るのであった。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)に基づく考察によれば── (アインシュタイン方程式)左辺の“時空の曲がり”(曲率)が“重位勾配”(=“4角形”(縮みきったバネ)の時間&球面平均を底辺2Lpで割ったもの)に相当し、右辺が“重力子を新たに放出する能力”の密度(=質量密度や運動量)に相当するものが入ると考えられる。
※右辺のTμνには、質量や運動に関したものが入るということは、
マクロの物体の(低速の)運動によって、1/2mv2に相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」が放出され、
ミクロの素粒子の光速の運動によって、mc2に相当する「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」も放出される」と考えられることと、およそ合致すると思われる。
アインシュタイン方程式は、下の図のように、物質の総質量の大きさが同じであっても、その密度が大きくなれば、周囲の“時空の曲がり”=“重位勾配”も、大きくなることを意味していると思われる。
|
|
|
|
※質量の密度は、異なっている。
質量の密度が大きいほど(物体がコンパクト化しているほど)、物質の周囲の、時空の曲がり
=“重位勾配”(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の時間&球面平均を底辺2Lpで割ったもの)は、大きくなっている。
※なお、質量の大きさは、どれも同じであるので──
例えば、共通する図の“2重の緑の間”の部分での時空の曲がり=“重位勾配”は、どれも同じになっている。
|
|
|
以上の中に、「アインシュタインの一般相対性理論の方程式が“非線形である”」と言われていることの意味を見いだすことはできないと思われる。
一方、やはり、「重力場のエネルギーそのものが、(“質量を持つ物体”という大元の重力源からのもの以外に)新たに重力子を生じる(新たに質量を持つ)」ということはないと考えられる。 つまり、「重力場のエネルギー≠質量(=「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を新たに放出する能力)」であるので── 少なくとも「重力場のエネルギー=質量(=「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する能力)」という意味での非線形性は、自然(nature)の中には、実在しないと考えられる。
つまり、“重力場のエネルギー”そのものを“質量”と見なし、新たな“時空の曲がり”の原因として方程式に代入することはナンセンスであると思われる。
※なぜ、重力は非線形と言われるようになってしまったのだろうか?
その1つの理由は、アインシュタイン選集2(p96〜99)から読み取れる。
その中に、次のような記述がある。
「すなわち、いま一つの完全系(たとえば太陽系)を考えよう。この物理系の全物質量、したがってまたその全重力的作用は、この物理系の全エネルギー、つまり物質によるエネルギーと、重力場のエネルギーの総和に依存する。 この事情は、カ(51)において、重力場のエネルギー成分のt〜 のかわりに、物質および重力場の両方のエネルギー成分の和t〜+T〜を導入することによって表現される。」by アインシュタイン (筆者により数式を一部省略)
)
この文章には、“物質によるエネルギー”と“重力場のエネルギー”が、混乱した形で理解され、用いられているという問題──「“重力場のエネルギー”が、新たな質量であるという扱いがなされている」という問題があると思われる。
一方、“素スピノール創発モデル”においては、“物質によるエネルギー”(=質量や運動)と、“物質によるエネルギー”の能力に見合った量だけ放出されたところの「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の総和が持つエネルギー、すなわち、“重力場のエネルギー”をはっきりと区別する。
(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── しかもそれは、収束し、発散しないと考えられる。 by上の考察《量子化された重力、重力場の計算》)
「上で述べたような物質のエネルギー・テンソルの導入の仕方は単に相対性の要請からでは正当化されないということに注意しなければならない。ここでは、われわれは、次のような要求を用いて、上の式を導いた。すなわち重力場のエネルギーは、他のどのような同じ形の、重力的作用をもつべきであるという要請である。」by アインシュタイン (下線は、筆者による)
“物体(質量)から生まれたはずの重力場”が新たな質量になり、そこから、新たな重力場が生まれるという── 非線形的なアイディアの源泉がこの文章にあると思われる。 この文章には、明らかに、「重力場が新たな質量として、新たに重力子を放出するようになる」という非線形性をもたらすような新たな要請を、アインシュタインがしてしまっていることが読み取れる。 しかも、それは、“相対性の要請からは正当化されない”ような要請である。
つまり、「重力場が、新たな質量になる」というアイディアの源は、アインシュタインの心の中にあったと思われる。
※このような考えに至った理由は、アインシュタイン自身が発見した“E=mc2”の利用の仕方にあると思われる。
しかし、「エネルギーは、質量なのだ」という考え方は、正しいとは限らず── 例えば、「重力場が、新たな質量になる」という考えは、“E=mc2”の誤用(濫用)であると考えられる。
(一方、「質量は、エネルギーなのだ」という考えは常に正しいと思われる。 もしかしたら、mc2=E が、誤用を防ぐ表記と言えるのかも知れない)
E=mc2は、質量をエネルギーに変換できること(質量がエネルギーを持つこと)を示す式にすぎず── 逆にあらゆるエネルギーをすべて質量に変換できることを示す式ではないことになる。 つまり、質量とエネルギーは、厳密には、100%等価ではないことになる。
(「質量とエネルギーは、等価である」という表現は、実は、精確ではないことになる。 “E=mc2”は、条件付きの理論である、ということもできると思われる。 →考察16)
“EMOES”(“EMOES”(素スピノールからの創発モデル))によって厳密に表記するならば、「(静止)質量は、“重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を新たに放出する能力に相当”するところの、ミクロのレベルで光速で運動し続ける素粒子が持つエネルギーの総和である」となる。
つまり、質量とは、あくまで、物質(“ミクロのレベルで光速で運動し続ける素粒子”)が、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を新たに放出する能力であるので── 「(「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の通過点に過ぎない)重力場が質量となり、そこから新たな重力子が放出される」という非線形性は、やはり、不要かつナンセンスとなるのだ。
しかし、“時空の曲がり”(曲率)(=“重位勾配”、=重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の時間&球面平均を底辺2Lpで割ったもの)と、質量密度や運動量(=“重力子を新たに放出する能力”の密度)が等しいという本質的な結論はゆるがないと考えられる。
※アインシュタイン選集2、p92〜の「物質が存在しないときの重力場の方程式」の項目に次のように書かれている。
「たとえば1個の質点によって、そのまわりにつくられた重力場を考えてみよう。この重力場はどんな座標系を採用しても、それを消し去ることはできない(訳者注:質点のまわりでは物質は存在しないが、重力場は存在する。〜)」
〜 Bμν=0 とおくことは、きわめて自然な要求であろう。 これらの式は、〜
… … (47)
となる。これが物質が存在しない所での重力場の方程式である。
この方程式を選び出すに際して、任意性のはいることが最小にとどめられたことに注意すべきである。というのは、gμνおよびその微分から構成されており、gμνは2階以上の微分を含まず、2階微係数については線形であるような二階テンソルは、Bμν以外には存在しないからである。
一般相対性の要求から、まったく数学的な方法で導かれたこれらの場の方程式は、一方質点の運動方程式(46)といっしょになって、第一近似ではニュートンの引力の法則を与える。また第二近似まで考えると、ルヴェリエ(Leverrier)によって発見された水星の近日点の移動(他の惑星による摂動に由来する修正を行なったあとに残る移動量)を説明することができる。」 (部分的に、〜として割愛させていただいた。下線は筆者による)
“EMOES”によれば、「1個の質点によって、そのまわりにつくられた重力場」と、“物質が中心に存在したときに周囲にできる重力場”は、同等である。
本質的には、この式(47)だけで、もう十分なのではないだろうか? 現に、それだけで、ニュートンの引力の法則も、水星の近日点移動も説明できている。
さらに、式(47)をもとにして、成立することが示される式(49)については、「この式は、重力場の運動量およびエネルギーの保存則を示すものである」と書かれている。
ところが、式(47)をもとにして導かれた、式(47)の“第3の形”──式(51)をもとに、上記の「“重力場のエネルギー”が新たな質量となる」という、非線形的な考え方が盛り込まれた上で、式(53)ができていている。 この式(53)がアインシュタイン方程式の原型である。
このことは、式(47)(49)(51)までは、線形であると解釈していいのだろうか?
正しければ、たとえ非線形性がなくとも、“ニュートンの万有引力の法則”も、“水星の近日点の移動”も、“エネルギーの保存則”も説明できることになる。
(なお、重力波も、“線形近似”によって導かれている)
だとすれば、「“重力場のエネルギー”が新たな質量となる」という、非線形的な考え方が盛り込まれていない式(47)(49)(51)だけで、やはり十分なのではないだろうか?
以上の考察は、非線形的な考え方が盛り込まれた所産である“アインシュタイン方程式”自体の中に、どこか間違いがあることを意味しているのだろうか?
それとも、単に、重力場のエネルギー=質量と考えた上での“代入の繰り返し”だけをしなければすむ問題なのだろうか?
それとも、これまでの考察のどこかに間違いがあるということなのだろうか?
その答えの1つは、“式(47)(49)(51)”の中に、「“時空の曲がり”(曲率)と、“物質のエネルギー”(質量密度や運動量)が等しい」という本質的な結論が内在しているかどうか、にあると思われる。 (質点の働きと物質(エネルギーを持つ)の働きは、密度の違いがあるだけで、ある意味、本質的には同じと見なすことができるので、“内在している”と考えていいように思われるが──)
詳細な検討は、今後の課題である。
※すると── 少なくとも、「重力場は非線形であり、 電磁場は線形である」とは、単純に言えないことになる。
重力場と電磁場の違いはなにか?
そこにある大きな違いの1つは、電場や磁場を生むところの光子は、仮想光子であり、決して、ふつうの“電磁波”ではない一方──
重力場を生む重力子は、仮想粒子であると同時に、“重力波”(電磁波×2)である── ということである。
|
場
|
電場&磁場
(電磁場)
|
重力場
|
|
ボソン
|
仮想光子
|
(仮想粒子である)
重力子
|
|
どこへ行くか
|
電荷に再吸収される
|
無限遠方まで進んでいく
|
|
電磁波との関係
|
(無限遠方まで進んでいかないので)
電磁波ではない
|
電磁波×2である
|
もし、電場や磁場を生むとされる仮想光子が、ふつうの電磁波だったらどうなるか?
電場や磁場の正負を逆転し続けるだけになってしまい── 一定の大きさを持つ電場や、一定の大きさを持つ磁場が生じることが決してできなくなってしまうだろうと考えられる。 なぜなら、電磁波であるならば、例えば、生じた電場や磁場は、すぐにその正負を逆転させてしまうからである。(その変化こそが電磁波の波を作る)
しかし、実際には、静止した電荷の周囲には電場、運動する電荷の周囲には磁場ができており、電力線や磁力線を描くことができる。
したがって、電磁場を生む仮想光子と、電磁波は、別物であることがわかる。
(この考察は、電荷の起源── 電荷の幾何学的な実体像を追求するためにも役立つ。(→考察6))
電磁場の世界は線形であるということは、電場や磁場の大きさは、単純な足し算&引き算で求められることを意味する。
それは、素スピノールの転回にともなう“4面体”の変形が単振動であること、すなわち、「仮想光子&原始ヒッグス場の“4面体”←→変形した“4面体”」が“調和振動子”の一例であることを示唆していると思われる。
一方、重力子という名の仮想粒子は、すべて、止まることなく、次から次へと、原始ヒッグス場の基本構造によって、無限遠方までリレーされ続ける。
その過程で、1つ1つの重力子&“4角形”(縮みきったバネ)は、増幅したり減衰したりしないと考えられるので、このあたりにも、非線形性は見あたらないと言える。
ただ単に、中心の質量からの距離の2乗に反比例して、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の時間&球面平均を底辺2Lpで割ったもの──すなわち“重位勾配”)が減るだけである。
(決して、重力場そのものから、(“重力子の大元の波源=質量を持つ物体”によって新たに生成させられる重力子以外に)新たな重力子を生じるようなことは起こらない)
そして、その「距離の2乗に反比例して、重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の密度(重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の時間&球面平均を底辺2Lpで割ったもの──すなわち“重位勾配”)が減る」という性質が、ニュートンの万有引力の法則の数式が示す性質を支えていると考えられるのは、いうまでもない。
そして、 「重力場は、重力子&原始ヒッグス場の“4面体”の総和である」と考えられるのは、「重力子&原始ヒッグス場の“4面体”←→“4角形”(縮みきったバネ)」が“調和振動子”の一例だからこそであることに気づくとき── 重力や重力場の世界の中に、やはり、非線形性は見あたらないと思われてくる。
仮想光子が変形する“4面体”(原始ヒッグス場由来)が調和振動子だからこそ、その総和である静電場は、線形であると言えるように── やはり、重力子が変形する“4面体”が調和振動子であるから、その総和である重力場は、線形なのではないだろうか?
だからこそ、質量の大きさに比例して、重力が増加するというニュートンの万有引力の数式も成り立つのだ。
そして、それは、「実際には、(通過点である)重力場そのものから“新たな重力子が放出される”ことがありえない」おかげでもあるのだ。
※以上の考察は、アインシュタインの一般相対性理論の数式を、本質を失わずに、よりシンプル化できる可能性があることを意味してるのだろうか?
単に、幾何的な実体像を視覚化するプロセスを欠いていたがために、一般相対性理論の数式が複雑難解になってしまっているだけなのだろうか?
上記の考察(《量子化された重力、重力場の計算》)は、よりシンプル化したところの一例なのだろうか? (→ 考察15数学&標準モデルのパラメーターの求め方について))
詳細な検討は、今後の課題である。
※そもそも、ある質量を持つ物体が、エネルギーを持つ「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出し続けているなら──
「この世に存在する、エネルギーが増え続けてしまうことになってしまう(新たにエネルギーが生成され続けてしまう)のではないだろうか?」
「これは、エネルギー保存則(熱力学第1法則)の破れを意味するから問題があるのでないだろうか?」という疑問が湧くのも当然である。
しかし── すでに述べたように、(静止)質量とは、(完成したヒッグス場の中で、ミクロレベルで光速を保って運動し続けている素粒子による)「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する能力の総和であり、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の波は、“エネルギーの生成と消滅を繰り返して伝わる(エネルギー保存則を破って生じるところの)仮想粒子の波”である」から問題ない、ということで済むと思われる。
(“エネルギー保存則を破って生じる”というのが、仮想粒子の性質そのものである)
(また、素粒子は、「完成したヒッグス場の中で、ミクロレベルで光速を保って運動し続けている」からこそ、E=mc2が成り立ち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する能力が保存されると考えられる)
つまり、物体の質量が保存されると同時に、物体から放出される“重力子は、質量が0の仮想粒子にすぎない”ので── 質量保存則も、エネルギー保存則(熱力学第1法則)も破れておらず問題ない── ということで済むと思われる。
そして、一方で、“厚さ2Lpの球殻が持つエネルギー”がどこも一定に保たれるという“仮想エネルギー保存則”といえるような保存則が存在すると考えられる。
このあたりのことは、アインシュタイン自身も問題意識を持っておられた。
『アインシュタイン選集2──A8重力波について』によると──
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』 (下線は、筆者による)
※“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、“究極の量子論”を内在させた理論であり── アインシュタインの重力理論を少し修正し、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』を、物体が「(仮想粒子である)重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」を放出する現象として説明しているので、『量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』というアインシュタイン自身による予想と、調和した理論であると言えると思われる。
そして、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、アインシュタインが望んだ「量子論の完成」を強力にサポートする理論であると言えると思われる。 (→考察3、考察5) 詳細な検討は今後の課題である。
※なお、このアインシュタイン自身が紡いだ文章から、アインシュタインは、“量子論がまだ不完全だ”と考えていただけにすぎず(“量子論の不完全さ”について批判していたにすぎず)、決して、量子論のすべてを否定しようとしていたわけではない、ということがうかがえる。
アインシュタインは、量子論をすべて否定しようとしていたのではなく、“本物の量子論の完成”を強く願っていただけだったのではないだろうか?
|