研究論文
『一般3Steps理論
&“素スピノール創発モデル”』
3.エネルギーと時空構造の関係について
エネルギーも、“素スピノールのネットワーク”の自己組織化にもとづく創発現象である。
時空構造、つまり、“素スピノールのネットワーク”は、エネルギーを持ちうると考えられる。
次の仮説を立てた。
仮説3.1 時空構造、つまり、“素スピノールのネットワーク”は、エネルギーを蓄えたり放出したりできる
この時空構造が蓄えるエネルギー── つまりは、素スピノールのネットワークが蓄えるエネルギーを“時空構造ポテンシャルエネルギー”と呼ぶこととする。
(なお、厳密には、“ミクロの素スピノールのネットワーク”の存在は、必ずしも“マクロレベルでの時空構造”の存在を意味するとは限らない。
しかし、マクロの時空構造をともわない“素スピノールのネットワーク”も、ミクロの時空構造をともなうと考え── この“時空構造ポテンシャルエネルギー”と“素スピノールのネットワークが持つエネルギー”は、同等である、として話を進める)
そして、この“素スピノールのネットワークが持つエネルギー”=“時空構造ポテンシャルエネルギー”は、質量エネルギー(mc2)、運動エネルギー(1/2mv2)、熱エネルギー(個々の粒子の運動エネルギー)、重力ポテンシャルエネルギー、電磁ポテンシャルエネルギー(化学エネルギー)、ダークエネルギー、ダークマター、量子ゆらぎのエネルギー … を含め、多くのエネルギーを説明できる可能性があると思われたので、次の仮説を立てた。
仮説3.2 多くのエネルギーが、“時空構造ポテンシャルエネルギー”のもとに、統一できる。
以下、様々なエネルギーについて考察を進める。
《時空の基本構造》
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では── 素スピノールどうしは、ネットワークを作り、素スピノール同士が互いにリンクし合っていると考える。
つまり、素スピノールの1つ1つが、理想気体のように、まったくバラパラに、でたらめなルールで存在しているのではないと考えているのである。
一方、現在の宇宙空間(時空)は、どの方向においても、おおむね性質が均等である(対称性が保たれている)ので、素スピノールが、びっしり整然と結びつき、1つの結晶構造を作っているとも考えにくい。
以上から、次の仮説を立てた。
仮説3.3.1 素スピノールのネットワークは、小さな“基本構造”の単位を持ち、それらがゆるやかに結びついて、より大きなものが構成されている。
※ゆるやかに結びついているとは、その個々の“基本構造”が、その場で回転する自由を持つ一方、全体の中で(原則として)ある場所に固定されていることを意味する。 (→考察4 仮説4.2)
正しいとすれば、現在の宇宙に相当する素スピノールのネットワークは── 少なくとも、“単原子分子を想定する理想気体”や“ダイヤモンドなどの結晶”のようなものではないことになる。 そして、しいて表現するなら、“金属のようにある場所に固定されていると同時に、液体の水の中の水分子のように向きを変えられるようなものということになる。
時空が持ちうる、最も基本的な“分子に似たような基本構造”とは、どのようなものであるのだろうか?
この“基本構造”は、“空間全体を満たす”ので── その構造は、原則として、正多面体構造に近いだろうと推論した。
正多面体構造は、5つある。 正4面体、正6面体(立方体)、正8面体、正12面体、正20面体。
(面の数が多いほど、球に近づき、対称性が高まると同時に、頂点の密度も高まる)
一般的に言えることと同様に── 素スピノールのネットワークの基本構造においても、“密度が高まることで高エネルギー状態になり、逆に密度が下がることで低エネルギー状態になる”と予想される。 よって、これらの、正多面体構造の中では、(もっともシンプルで、もっとも対称性、密度&充填率が低い)正4面体が最もエネルギーが低いと考えられる。
一方、その基本構造は、“素スピノール”の組み合わせからから創発するものである。
そして、素スピノールが単独でバラバラに存在するよりも、“素スピノール2つ分のペア・・”を作って存在した方がエネルギーが小さいことが予想される。
そして、さらに、“素スピノール2つ分のペア・・”どうしは、それぞれ単独でバラバラに存在するよりも、“・・&・・”のペアを作った方がエネルギーが小さいことが予想される。
一方、全く幾何学的なこととして、2つの線分“− −”は、それらをうまく配置させることに◎よって、容易に(線分の両端を頂点とする)“4面体”を作ることが出来る。
よって以上を考えあわせることで、次の結論を得られる。
結論3.1 時空構造ポテンシャルエネルギーは、時空の基本構造が“4面体”である場合に、最も低い。
一方、“4面体”は、変形により、“重力子”を伝えられることを考えた。
(重力子は、スピンは2の閉じたループ。 参照──考察2、考察6)
以上と“シンプル化原理”を考え合わせ、最も基本的な“時空の基本構造”として、次の1つを採用することとした。
|
時空の基本構造の“4面体”
|
|
|
|
※4つの素スピノールからなる。
凝縮のペア(右巻き&右巻き、左巻き&左巻き、黒い線で結ばれる)が、2つ組み合わさってできている。
|
この“4面体”からなるヒッグス場を“原始ヒッグス場”と呼ぶこととする。
原始ヒッグス場の“4面体”の構造は、考察2で述べたように、バネ的な働きをすることで、電磁波(光子)や、重力波(重力子)が創発される。
この“4面体”のバネは、(エネルギーを蓄えながら)最高で“4角形”まで変形できる。 この“バネが縮みきった状態”=“4角形”になるのは、あくまで最高の場合であると考え、次の仮説を立てた。
仮説3.3.2 原始ヒッグス場の“4面体”は、“4角形”(バネが縮みきった状態)まで変形することによって最も大きなエネルギーを蓄えられる一方── 途中までの変形によって、相対的に小さいエネルギーを蓄えることが出来、その変形の度合いが小さければ小さいほど、蓄えられるエネルギーは小さくなる。
それは、縮めば縮むほど、“ふつうのバネ”に蓄えられるエネルギーが大きくなることと同様である。
この原始ヒッグス場の“4面体”の“バネ”のおかげで、電磁波(光子)や、重力波(重力子)が、空間を光速で伝わっていくと考えられるので、この原始ヒッグス場の“4面体”は、電磁場と重力場を作るための土台であると言える。
原始ヒッグス場の“4面体”に蓄えられる“エネルギー振幅”が大きいほど、素スピノールが転回する周期Tが短くなり、より短い波長の光子が創発されると考えられる。 (このことは、プランクの式E=hνのみならず、不確定性原理の式とも合致している。→考察5)
重力子の作用によって、原始ヒッグス場の“4面体”のバネが100%変形する様子を再び図示しておく。
|
重力子によって変形されて生じた
原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)
|
|
原始ヒッグス場の“4面体”
|
|
|
エネルギーを蓄える
←
→
エネルギーを放出する
|
|
|
※例えば、緑で囲ったペアが(放出途中の重力子の働きで)転回する(ひっくり返る)と“4面体”の配置に近づくことがわかる。
※“4面体”に戻る際には、重力子(スピン2)の波を放出する。
|
※このエネルギーの大きさが
“プランクエネルギー”に相当すると考えられる。(←考察2)
|
※緑で囲ったペアが(取り込み途中の重力子の働きで)転回する(ひっくり返る)と“4角形”(縮みきったバネ)の配置に近づくことがわかる。
※素スピノール4つからなる
※凝縮のペア(黒い線で結ばれる。右巻きどうし、左巻きどうしのペアである)が
2つ組み合わさってできている。(スピン0)
|
この原始ヒッグス場の“4面体”は、変形の際に、エネルギーを蓄えたり、放出したりする。
これが、まさに、“時空構造ポテンシャルエネルギー”の実体の一例である。
《時空構造ポテンシャルエネルギー》
原始ヒッグス場の“4面体”以外にも── 様々な“4面体”を考えることが出来る。
※例えば、グルーオン場の“4面体”、ウィークボソン場の“4面体”、
電子場の“4面体”、クォーク場の“4面体”、ニュートリノ場の“4面体”… (→考察4、5) |
そして、いずれにも共通することは── いずれの“4面体”も変形する(“4角形”になる)ことによって、エネルギーを蓄えることができるということである。
つまり、これらの“4面体”の変形の際に蓄えられたエネルギーも、すべて、時空ポテンシャルエネルギーの実体の例であると言える。
しかし、今度の“4角形”は、原始ヒッグス場(重力場)で登場した“4角形”(縮みきったバネ)とは異なる。
それは、四極子としての“4角形”である。
“4角形”(四極子)と“4面体”の関係を、一般化して簡略化して図示すると次のようになる。
|
“4面体”の単位
(tetrahedral unit)
|
|
“4角形”(=四極子)の単位
(quadrupolar unit)
|
|
|
エネルギーの放出
←
→
エネルギーの吸収
|
|
|
※凝縮のペア(黒い線で結ばれる)が
2つ組み合わさってできている。
※最もエネルギーが低い状態に相当する。
|
|
※四極子に相当する。
※各粒子間の距離(黒&赤)を保ちながら、ねじれることで“4面体”に至ることができる。
|
一般に、時空の基本構造が“4面体”である時より、“4角形”(四極子orバネが縮みきった状態)に近い時の方が、時空構造ポテンシャルエネルギーが大きい、ということになる。
しがって、以上より、次の結論を得られる。
結論3.2 時空構造ポテンシャルエネルギーの実体は、時空の基本構造の“4面体”が、変形するときに蓄えられるエネルギーである。
※“4角形”→“4面体”の過程は、ヒッグス機構&自発的対称性の破れとも関連する。 (→考察4、11)
※“四極子”と“バネが縮みきった状態”の関係の概要は、おおよそ次のように図示できる。
この“ワイボトルの底”の形状を示す図は、いわゆる“ヒッグス場の相転移”や“インフラトン”を説明するためによく用いられる図と同じであると思われる。
スピノールを一般化して図示してあるので、素スピノール、プレオン∴のスピノール、電子やクォークのスピノールいずれも、おおよそ、あてはまると思われる。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は── まさしく、この“縮みきったバネ”こそが、未知とされている“インフラトン”の実体である可能性があることを示唆している。
様々な候補の中で、実際に“インフラトン”の実体となりうるものは、プレオン∴×4(グルーオン×2)のヒッグス場由来の“縮みきったバネ”であると考えられる。(→下記の考察、考察6、11)
《対生成&対消滅のエネルギー》
一般に、真空は、エネルギーを得ると、粒子と反粒子のペアを対生成し── 逆に対消滅すると、光子(γ線)としてエネルギーを放出すると言われている。
したがって、真空は、全くの無ではなく── 真空には“何か”があると考えられている。
その“何か”とは何か?
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によると、その“何か”とは、各種の“4面体”に他ならないことが容易にわかる。
なぜなら、“4面体”は、エネルギーが最低の状態であるからである。 (それは、“真空がエネルギー最低の状態である”ことと合致する)
この“粒子と反粒子のペア”の対生成は、“4面体”から“4角形”(四極子)へと変形する過程を経て達成されると考えれば、つじつまが合う。
“4角形”(四極子)←→“4面体”の相互に変化する過程は、対生成や対消滅の過程の一部に相当するのである。
図示すると次のようになる。
|
“4角形”(=四極子)の単位
(quadrupolar unit)
|
|
“4面体”の単位
(tetrahedral unit)
|
|
|
“対生成の過程”
の一部
←
→
“対消滅の過程”
の一部
|
|
|
※もし、“4面体”に変化する際には、
重力子または、光子(γ線)を放出する
※対消滅に至る前の状態でもありうるし、
対生成に近づく途中の状態でもありうる。
|
|
※光子(γ線)などのエネルギーを得ると、励起して“4角形”に近づいていく。
※対消滅の後の状態でもありうるし、
対生成の前の状態でもありうる。
|
※原始ヒッグス場(素スピノール4つからなる“4面体”を基本構造とする。重力場&電磁場を作れる)、グルーオン場、ウィークボソン場、電子場、クォーク場、ニュートリノ場… いずれも共通である。
※“4角形”(四極子)の状態を経て、粒子・反粒子が完全にバラバラになってはじめて対生成が完結すると言えるので、あくまで“過程の一部”であり、対生成、対消滅のすべての過程ではないと言える。
しかし、重力子による“4角形”(縮みきったバネ)の形成とは異なって── ヒッグス場由来の“4角形”(四極子)の形成は、実質的に“対生成”と等価であると考えてもいいのかもしれない。
(原始ヒッグス場における“対生成”に相当するものは、重力子によって原始ヒッグス場由来で生じた“4角形”(縮みきったバネ)の形成ではなく── “Δ光子の対生成”と呼べるものである(Δ光子については、考察5))
※“4角形”(四極子)から“4面体”への変化は、時空の相転移 or “自発的対称性の破れ(カイラル対称性の破れ)”にも相当すると見なすこともできると思われる。 (→考察4)
※“4角形”(四極子)←→“4面体”の変化きは、“量子ゆらぎ”“粒子が持つ波動性”とも関連すると考えられる。 (→考察5)
※量子ゆらぎのエネルギー振幅と、重力子の放出と関連する“4角形”(縮みきったバネ)←→“4面体”の変化とは、何らかの関連があると考えられる。 今後の課題である。(→考察4)
|
《質量エネルギー》
ミクロの世界では(ミクロの目で見る場合)、各素粒子は光速で運動し続けている。
各素粒子は、各種のヒッグス場と衝突し、“4面体”を変形させる過程を繰り返し、行ったり来たりしているので── マクロの目で見ると、光速を失っているように観察される。
その過程が、質量獲得の実体であると考えられる。
1つの素粒子が繰り返し時間かけて作用したり、(たとえ時間をかけなくとも)多くの素粒子が多く集合したりすると── 周囲の時空の基本構造に蓄えられるエネルギーがある閾値(プランクエネルギー)を越え、“重力子”を放出するようになると考えられることは前に述べた。(考察2)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)では、次のように質量を定義した。 (考察2)
仮説2.3.1 ある物体が“質量を持っている”ことは、その物体の中のミクロの素粒子(ミクロのレベルで光速で運動し続ける素粒子)が、周囲の各種のヒッグス場から抵抗を受ける(周囲の各種のヒッグス場を変形する)過程で、(マクロの目での)見かけ上、光速を失い、質量を獲得することの総和である。
仮説2.3.3 その全質量の大きさは、周囲に放出させている全重力子の単位時間あたりの数に比例する。
よって、質量とは、単位時間当たりに生じる重力子&原始ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)の総和(=重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の生成頻度)である、と言うことができる。
つまり、質量エネルギーの実体も、この“素スピノールのネットワーク”が作る“4角形”(縮みきったバネ)、つまり、“時空構造ポテンシャルエネルギー”であることになる。
※アインシュタインのE=mc2の式で示されるような「質量がエネルギーである」という考えと合致する。
質量が大きいほど、周囲に多くの重力子&“4角形”(縮みきったバネ)が作られ、時空にネルギーが蓄えられていることになる。
この重力子によって生じる“4角形”(縮みきったバネ)の総和が“時空の曲がり”の実体の一部に相当すると考えられることは前にも述べた。
(考察2重力(一般相対性理論)、重力子&ヒッグス場ユニット、質量、光速について)
※“4角形”(縮みきったバネ)の密度が高いほど、“時空の曲がり”がより大きいと同時に、より大きなエネルギーを蓄えていると言える。
※ある質量を持つ物体が、重力子(≒エネルギーを持つ“4角形”(縮みきったバネ))を放出し続けていても、ある質量を持つ物体がエネルギーを消失してしまうことにはならない。 “エネルギーが増え続けてしまう”(新たにエネルギーが生成され続けてしまう)ことにもならない。
なぜなら、考察2でも述べたように、重力子(“4面体”からなるヒッグス場の中を伝わる“4角形”(縮みきったバネ)の波)は──、“(エネルギー保存則を破って生じる)仮想粒子の波”だからである。
※重力子によって生じる“4角形”(縮みきったバネ)は、プランクエネルギー(約1.2×1019Gev)と関連すると考えられることは前にも述べた。
(考察2重力(一般相対性理論)、重力子&ヒッグス場ユニット、質量、光速について)
一方、例えば、電子場で生じる“4角形”(四極子)は、電子のが持つ質量エネルギー(0.5Mev)と関連すると考えられる。
このあたりにも、「基本的なエネルギーの間にある、このけたはすはずれの差を説明するという難題」(“階層性問題”)(参考 『究極理論への夢』 S・ワインバーグ P.229)を解く鍵があると思われる。
(→考察9)
《運動エネルギー》
物体の運動に関連して、次の仮説を立てた。
仮説3.5 質量mを持ったある物体が、原始ヒッグス場の中を速度vで等速運動する場合にも、進行方向の原始ヒッグス場の“4面体”が変形し、新たに“4角形”(縮みきったバネ)が生じ、その結果、「m0c2(1−v2/c2)1/2−m0c2」のエネルギーに相当する重力子&“4角形”(縮みきったバネ)が、運動方向に放出される。
※vが、光速よりとても小さいときは、mv2/2、のエネルギーに相当する重力子&“4角形”(縮みきったバネ)が放出されることになる。 つまり、静止質量をm0とすると、運動中の物体の総エネルギー E=mc2≒m0c2+1/2m0vc2 の実体は、すべて、“素スピノールのネットワークにエネルギーを蓄える能力”=“4角形” (縮みきったバネ)を放出する能力であることになる。
※この運動の方向に放出される重力子が“流れるプルール効果”を生み、慣性を生じさせていると考えられることは考察2で述べた。
より速く運動するほど、より多くの頻度で進行方向の原始ヒッグス場の“4面体”を“4角形”(縮みきったバネ)に変形させ、より高頻度で重力子を運動方向へ放出させることになる。
このエネルギーがそのまま“流れるプルール効果”に使われ、慣性運動(等速運動)を実現する。
つまり、“流れるプルール効果”を生むエネルギーこそが運動エネルギーの実体であると言える。
ある物体が持つ運動エネルギーが高いほど、その物体の運動方向へ「m0c2(1−v2/c2)1/2−m0c2」に相当する“4角形”(縮みきったバネ)&重力子の放出能力の高まりという形で、より多くのエネルギーが蓄えられていることになる。
逆に、運動エネルギーが減る際(減速運動の際)── 重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の生成頻度の低下という形で、質量が減ることになる。
※熱は、その実体の一部は、個々の粒子“運動エネルギー”であるので、熱エネルギーの一部についても同様となる。
つまり、運動エネルギー、熱エネルギー(個々の粒子の運動エネルギーの総和としての熱エネルギー)は、ともに、その実体は“4角形”(縮みきったバネ)である。
※静止したように見える粒子が質量を持っている場合、その粒子にも、“4角形”(縮みきったバネ)の放出能力という形で、もともとエネルギーを持っている。
そして、新たに運動が始まると、その運動エネルギーが高まりに応じて“質量が増える”ようにも見える。 これは、特殊相対性理論の世界像と合致している。
(詳細は、考察3重力(一般相対性理論)、重力子&ヒッグス場ユニット、質量、光速について)
※ある物体が静止しているときに比べ、等速運動しているときの方が質量が大きい。
しかし、その物体が、他の物体を引き寄せる重力は、一切、大きくならないと考えられる。 なぜなら、等速運動に達した場合、それによって、運動方向に放出される重力子の集合は、“重位勾配”を全く持たないからである。 一方、もし、物体が、加速運動を続けていたとしたら、他の(運動方向にある)物体を引き寄せる重力は、大きくなると考えられる。 なぜなら、加速運動によって、運動方向に放出される重力子の集合は、“重位勾配”を持つからである。 このことは、等価原理と合致すると思われる。
この予想される現象──
もし、ある質量を持つ物体が加速運動し続ける時は、運動方向の時空に追加され続ける新たな「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」が“重位勾配”を持つので── 加速し続ける間(重力子の放出量を増加させ続けている間、質量が増加し続ける間)は、その新たな“重力子の総和”が、他の「運動方向にある物体のみ」を引き寄せる、新たな重力として働く一方、
いったん、ある質量を持つ物体として、等速運動をし続けるようになると、運動方向に新たに生じた「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の総和」の総和は“重位勾配”を持たないので── その質量増加に伴って追加された、新たな“重力子の総和”は、他の「運動方向にない物体」へはもちろん、「運動方向にある物体」へも、新たな重力として、全く寄与しなくなるという現象は、「運動する物体が運動方向にのみ重力子を放出すること」を検証するための実験モデルの1つとなるかもしれない。
(一方、(運動方向にある)他の物体によって引き寄せられる重力は、(等速運動することによって)増す── ということでいいのだろうか? 今後の課題である)
《重力ポテンシャルエネルギー》
真空中で、2つの質量が互いに引き合う(互いに自由落下をする)ことで、重力ポテンシャルエネルギーは、100%運動エネルギーに変化しうる。
つまり、重力ポテンシャルエネルギーとは、上記で示した運動エネルギーに関連した“4角形”(縮みきったバネ)に変換できる潜在的な(ポンシャルな)エネルギーということになる。
※これは、考察2の“連星パルサー”のところで説明した、“ビリアル定理”と合致する。
“ビリアル定理”は、“総運動エネルギーKと総エネルギーEの和は、0になる”という結論を導く。
《核エネルギー》
離れて存在していた、2つの質量が結合したとき、もし総質量が減ると── 重力子&“4角形”(縮みきったバネ)を放出する能力の総量も減る。
そのようにして、総エネルギーが減る際、光子等、なんらかのかたちで余分なエネルギー(=質量欠損に相当)が外へ放出される。
バラバラに存在していた、2つの質量は、それぞれの周囲に“4角形”(縮みきったバネ)を生み出す能力として、エネルギーを持っている。
2つの質量が結合した際、もし、質量欠損がなければ── それぞれの“4角形”(縮みきったバネ)を生み出す能力の和が、そのまま保存される。
もし、結合する前の“4角形”(縮みきったバネ)の総和より、後者の“4角形”(縮みきったバネ)の方が少なければ── 質量欠損をおこしたのであり── その“4角形”(縮みきったバネ)を生む能力の差が、なんらかの形で、エネルギーとして放出される。
《量子ゆらぎのエネルギー》
エネルギーのゆらぎ──いわゆる“量子ゆらぎ”の効果は、まさに、“4面体”←→“4角形(四極子、縮みきったバネ)or 変形した“4面体”(途中まで縮んだバネ)のゆらぎの総和によってもたらさられると考えると、様々な、つじつまが合うように思われる。(→考察5) よって、次の仮説を立てた。
仮説3.7 “4面体”のエネルギーの放出&吸収こそが、“量子のゆらぎのエネルギー”の実体である。
量子ゆらぎのエネルギーを図示すると次のようになる。
つまり、このエネルギーは、決して、無から生じたものではないことになる。 また、どこからともなくやってきたわけでもないことになる。
より大きなエネルギーが生じているほど、より多くの、より高エネルギーの“4角形”(四極子 or 縮みきったバネ)or 変形した“4面体”(途中まで縮んだバネ)が関与している。
「仮想粒子は、エネルギー保存則を破って生じるものである」と言われるが、全く無秩序なエネルギーを持つのではなく、あくまで、ΔE×Δt ≒ h にしたがうと考えられる。 この変形した“4面体”(途中まで縮んだバネ)が持つエネルギーと、プランク定数hとは、関連があることは考察2でも述べた。
(光子によって(1つの素スピノールによって)1つの原始ヒッグス場由来の“4角形”が蓄えるエネルギーは、hνになる。 例えば、1秒間に1回のスピードで、光子が転回する際のエネルギー振幅は、hとなる。
一方、重力子によって(2つの素スピノールによって)1つの原始ヒッグス場由来の“4角形”が蓄えるエネルギーは、“(h/π)×νp”=“hc/2πLp”になる。 これはプランク質量と一致する)
(詳細は、考察2重力(一般相対性理論)、重力子&ヒッグス場ユニット、質量、光速について))
《電磁ポテンシャルエネルギー(化学エネルギー)》
場の量子論によると、電磁気力は、仮想光子によって生じている。
仮想光子を生じる原因の実体は、《量子ゆらぎのエネルギー》、つまり、ΔE×Δt ≒ h のΔEの実体──変形した“4面体”(途中まで縮んだバネ)であると考えられる。
つまり、電磁ポテンシャルエネルギー(化学エネルギー)が高いほど、仮想光子が多くなり── つまりは、変形した“4面体”(途中まで縮んだバネ)のエネルギーの総量も増えることになる。
※仮想光子による、180度転回によって蓄えられるエネルギーは、そのまま、180度の“逆転回”によって、電荷に戻ってくると考えられるので、エネルギーの損失がなくなると考えられる。(→考察6 電荷の起源)
次に、初期の宇宙と関連したエネルギーについて見ていく。
それは、下図においての左側にある部分である。
|
6面体の単位
(cubic unit)
|
|
4角形の単位
(squarish unit)
|
|
4面体の単位
(tetrahedral unit)
|
|
四極子
|
|
|
エネルギーの吸収
←
→
エネルギーの放出
|
|
エネルギーの吸収
←
→
エネルギーの放出
|
|
エネルギーの吸収
←
→
エネルギーの放出
|
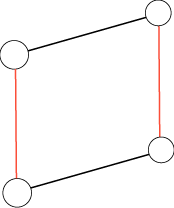 |
“縮みきったバネ”が
集合してできる。
(便宜上6面体としたが、実際は球状かもしれない。
今後の課題である) |
※主に初期の宇宙
(インフレーション)と関連 |
|
※主に、現在の宇宙と関連
※量子ゆらぎと関連 |
※ここで、エネルギーが最低となる。 |
※主に、現在の宇宙と関連
※量子ゆらぎと関連
※自発的対称性の破れとも関連 |
|
《インフレーションをもたらすエネルギー(インフラトン)》
インフレーションをもたらすエネルギー(インフラトン)について、“フェルミオンとは違い、ボソンは同じ物理状態で多数存在できること”を考慮し、次の仮説を立てた。
仮説3.8.1 ある“4角形”(縮みきったバネ)が、とてつもなく高密度に凝縮した状態が、指数関数的に解放されると、エネルギーが放出されると同時に、時空自体も指数関数的に広がる。 この過程が、インフレーションに相当する。
インフレーションを引き起こすエネルギー(インフラントン場)の実体──高密度に凝縮した、ある“4角形”(縮みきったバネ)とは何であろうか?
原始ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)だろうか? 確かに、それもおおいに関係がありそうである。 ただし、原始ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)を生じるのは、やはり、“大きな質量を持つ何か”があってこそである。 重力子が高密度で放出される原因となる何かがあるはずである。 それこそが、インフレーションを起こす“4角形”(縮みきったバネ)の集合であるはずであると考えた。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)による結論から言えば── インフレーションを生む原因の最有力第一候補は、グルーオン×2(プレオン∴×4)に相当する“4角形”(縮みきったバネ)である。
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、その結論を、無理せず、自然に導く。 (詳細は、下のダークマターについて記述、考察6、考察10、考察11)
“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)は、次の仮説を提示する。
仮説3.8.2 プレオン∴ヒッグス場由来の“縮みきったバネ”が高密度に凝縮したものが“インフラトン”の実体である。
※“縮みきったバネ”が持つエネルギーが、インフレーションとともに放出されるエネルギーであり、ファイヤーボール(ビッグバンの元々の呼び方)の熱の源になると考えられる。 インフレーションを始めるきっかけ(引き金)は何であろうか?
その答えと関連する有力なヒントは、「高まり続けたエネルギー密度がある臨界点を超えると、 重力が引力から斥力に変わり、ビッグバウンスが起きる」(量子重力が予言するビッグバウンス宇宙 日経サイエンス2009年1月号より)ということであると思われる。
正しければ、インフレーションの引き金は、単純に、“4角形”(縮みきったバネ)のエネルギーの総和が、ある閾値(臨界点)を越えることにともなうビッグバウンスということになる。
原始ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)に蓄えられるエネルギーには限界があると考えられることは、このような“臨界点”が生まれるという考えと合致していると思われる。
《ダークマター》
インフレーションの際、高度に凝縮した、プレオン∴ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)が指数関数的に(○倍○倍○倍… のように)分散するので、“その“4角形”(縮みきったバネ)のフラクタルな分布のゆらぎ(ムラ)”が生じると考えられる。
(考察9 スピンネットワークのフラクタルについて)
プレオン∴ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)の“フラクタルな分布のゆらぎ”は、“銀河、銀河団、長銀河団、ボイド&グレーとウォール…”という宇宙の大規模構造が持つ“フラクタルな分布のゆらぎ”と、関連していると思われた。
( このゆらぎとともに分布し始めた物質が、重力ポテンシャルエネルギーによって物質がコンパクト化が増幅し続ける結果── “銀河、銀河団、超銀河団、ボイド&グレーとグレートウォール…”という宇宙のフラクタルな大規模構造が生まれてきたと考えるとつじつまが合う)
よって、次の仮説を立てた。
仮説3.9.1 インフレーションの際、高度に凝縮した、プレオン∴ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)が指数関数的に分散する結果生じた“フラクタルな分布のゆらぎ”が、“明るい物質の質量”と“ダークマターの質量”の総和についての“フラクタルな分布のゆらぎ”の起源である。
ところで、上記考察と考察10(3.物質の起原について)によると、プレオン∴の“4角形”(縮みきったバネ)から“4面体”に相転移する際に放出されるエネルギーを放出され(それがビッグバンのエネルギー源であると考えられる)、そのエネルギーを使い、一部のグルーオン×2(=プレオン∴×4)だけが、(少なくとも)3世代のクォークやレプトンに至り、それらが、CP対称性の破れとともに分解される過程で、(反物質より)物質優位の世界ができたと考えられる。
つまり、一部のグルーオン×2(=プレオン∴×4)が、“明るい物質”および、各種のヒッグス場(電子場、クォーク場…)となり── それらの成り損ないとして残ったグルーオン×2(=プレオン∴×4)を材料とする“何か”が、ダークマターに相当すると考えるのが、自然であると思われた。
仮説3.9.2 “明るい物質”および、各種のヒッグス場(電子場、クォーク場…)に成り損いとして残った、グルーオン×2(=プレオン∴×4)を材料とする“何か”が、ダークマターに相当する。
ダークマターとは、具体的に、何に相当するのであろうか?
ところで、観測によれば、銀河の中を運動する速度が、中心から距離によらずほぼ一定である。 それは、次のように銀河の中心からの距離に比例して、その半径の球の質量が大きくなるからであると説明されている。 (そして、このことがダークマターの存在を考え始めるきっかけの1つとなった)
一方、銀河の中の明るい星の分布(電磁波として観測できる物質の分布)は、銀河系の中心部に近づくほど大きい。
上記の総質量分布が正しければ── それを成立させるためには、ダークマターの分布は、銀河の中心部に近づくほど減少し、銀河の周辺部に行くほど増加しなければならないことになる。 つまり、銀河内での、ダークマターと明るい物質、それぞれの密度の分布は、おおよそ、次の図のようになると考えられる。
しかし、この図は、“(電磁波として観測できる)“明るい物資”や各種のヒッグス場(電子場、クォーク場…)への成り損ない(第3世代までへの変化し損ない)が、そのままダークマターである”ことを意味しているわけでない。
なぜなら── 最初の、「プレオン∴の“4角形”(縮みきったバネ)」のムラ(ゆらぎ)の多少に比例して、成り損ないの多少が決まると考えられるからである。 つまり、“明るい物資”が多いほど、“明るい物資”への成り損ないも多いはずだからである。
(もし、現在のダークマターが、単に(電磁波として観測できる)“明るい物質”への成り損ない(3世代のクォークやレプトンへの変化し損ない)ということになれば── 単純に、物質(原子、つりは、クォーク)が多く存在する場所ほど、ダークマターが多く存在することになってしまう)
上図を生んだしくみは何か? 次の仮説を立てた。
仮説3.9.3 上図は、(電磁波として観測できる)“明るい物質”が多く存在するほど、何らかの形でダークマターが消費されて減っていることを示している。
ダークマターが消費されるとは、どういうことか?
次の記述が参考になると思われた。
『物質の究極を探る 現代の統一理論』 日本物理学会 培風館 p22に──
「〜クォークの質量は直接に測定することはできない. ハドロンの質量などを考える場合は、クォークの質量にグルーオンの集積したひもの質量を加えたものが実質的な意味をもつ有効質量であると考えられる. 〜 表3に推定値を示したが、有効質量は裸の質量にひもの質量(質量エネルギーは約350Mev)を加えたものとみることができる.」とある。 (下線は筆者による。 部分的に“〜”により省略してある)
この記述は、例えば、中間子や陽子&中性子の質量が、単なるクォークの質量の和より大きい理由は、“グルーオンの集積したひも”の質量が追加されるからであることを意味している。
つまり、“グルーオンの集積したひも”は、“明るい物質”の質量としてカウントされることになる。
まさに、これが、“ダークマターが消費される”ことに相当するのではないか?
もともと、“クォークやレプトンへの成り損ない”である、グルーオン×2(=プレオン∴×4)(=ダークマターの材料)は、物質の量に比例して、存在していた。
そして、“明るい物資”が物質が凝集することが可能である一方で、グルーオン×2(=プレオン∴×4)(=ダークマターの材料)は物質と一緒に凝集できなかった。 そして、グルーオン×2(=プレオン∴×4)(=ダークマターの材料)の一部は、“グルーオンの集積したひも”として消費され、それは“明るい物質”の質量としてカウントされるようになった。 そのことを上図は意味していると考えられる。
つまり、グルーオン×2(=プレオン∴×4)が、ダークマターであり── 二重の意味で、“明るい物質”の質量の原材料であったと考えるとつじつまが合う。
1つは、物質優位の世界に至るための材料として、もう1つは、グルーオンの集積したひもとして。
ダークマター──グルーオン×2(=プレオン∴×4)とは、具体的にどのような状態になっているのだろうか?
単に“4面体”だろうか? “4角形”(四極子)だろうか? それとも“4角形”(縮みきったバネ)だろうか?
あるいは、これらの集合だろうか?(グルーオン場そのものがダークマターであると言っていいのだろうか?)
詳細な検討は、今後の課題である。
(→考察9素スピノールのネットワークのフラクタル、3つの世代、階層性について(《“4面体”(ヒッグス場の基本構造)のフラクタル》))
《ダークエネルギー》
ハッブルの研究成果──「遠くの銀河から光の赤方偏位」が認められるという観測結果に基づいて、“宇宙は膨張している”という説が生まれた。
また、「超新星から光の赤方偏位と星の明るさ」の観測結果に基づいて、“現在は、ダークエネルギーによって、宇宙膨張は、加速してきている”という説が生まれた。
別冊日経サイエンス紙によれば── 宇宙の膨張、赤方偏移についての、最新で、最も正確な説明は、次のようなものであると思われる。
「〜厳密には、ドップラー効果による銀河の赤方偏移の理解は正しくない。銀河はそれ自身が高速で後退しているのではないからだ。銀河は静止しているが、その銀河が存在する空間自体が膨張するために、後退しているように見えるだけだからだ。 波長が長くなるのは、空間が膨張して、その中に存在している光(つまり波)が引き伸されることによる。 この考えに立てば、遠くの銀河からの光は、近くの銀河からの光よりも長い時間、宇宙を旅したため、それだけ長く波が引き伸され、強い赤方偏移を受けるようになったと解釈できる」 (『宇宙膨張は加速している』より──別冊日経サイエンス136『宇宙論の新次元』)
「論点4 銀河の赤方偏移はなぜ起こるのか?
誤解 銀河が空間内を移動し私たちから遠ざかり、ドップラー偏移が起こるから。
正解 空間が膨張し、そこを伝わるすべての光波を引き伸すから。」(『ビッグバンをめぐる6つの誤解』より──別冊日経サイエンス156『宇宙創成期』)
「宇宙論的な赤方偏移と通常のドップラー偏移とは別物だ。 天文学者はよくドップラー偏移を引き合いにして出して宇宙論的な赤方偏移を説明するが、学生たちはそのせいでひどい迷惑を被っている。
両者は別々の公式で記述される。ドップラー偏移の式は特殊相対性理論の範疇にあり、空間の膨張が考慮されていないが、宇宙論的赤方偏移の式は、一般相対性理論から導かれ、空間の膨張が考慮されている。」 (『ビッグバンをめぐる6つの誤解』より──別冊日経サイエンス156『宇宙創成期』)
ここで、考察2で挙げた、次の仮説を思い出すなら── “宇宙の膨張”の担い手が重力子であると考えるとうまくいくらしいことがうかがえる。
仮説2.4 アインシュタインの一般相対性理論の数式は、重力子(≒原始ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ))の挙動の総和を表現している。
一方── 既存の“大きな重力”によっても光の赤方偏位は起こるとされる。(重力的赤方偏移)
この重力的赤方偏移は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)によれば── 重力子が持つ、光子を構成する素スピノールの転回の頻度を減らし、時間の流れを遅くする作用、そして、空間を膨張させる作用によって起こると説明できる。 このことは、銀河の周囲の“重力子の密度差”が大きければ大きいほど、重力子による“時間の流れを遅くする効果”“空間を膨張させる効果”が大きくなり、同時に、より大きな「遠くの銀河から光の赤方偏位」が観測されることを意味すると考えられる。
“宇宙論的な赤方偏移”と、“重力的赤方偏移”は、ともに“重力子の挙動”で説明できるらしいので、両者が本質的には同じものであるらしいことが、うかがえる。
以上により、“宇宙の膨張”の実体として、次の仮説を立てた。
仮説3.10 “宇宙の膨張”の実体とは── “重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布の増加”(≒“時空の曲がり”の増加 ≒“重位勾配”の増加)による、時間の遅れ&空間の膨張である。
※一時的に加速して、等速運動の速度が増した場合に、運動方向への重力子の放出量が増える。 このことも、宇宙の膨張の一例と言えることになる。
なぜなら、この場合、この1時的な加速によって“重力子の分布の増加”が起きたからである。 この場合、“運動方向のみに宇宙が膨張した”と言える。(これが光速不変の原理を成立させることは、考察2で述べた)。
具体的に銀河の周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布が増加する」のは、どんな時か?
そのひとつは、加速運動をすることである。 (その結果、運動方向に宇宙が膨張する。 運動方向で、重力によって引き寄せる力が増すと考えられ、これが等価原理と合致することは、前に述べた。(考察2))
もう1つは、“物質(&質量)どうしが重力ポテンシャルエネルギーによって集合する”ことにより、“物質(&質量)の分布がコンパクト化する”ことである。
“物質(&質量)の分布がコンパクト化”すればするほど、周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布」が増加し、宇宙は膨張する。
考察2で挙げた次の図は、それをうまく説明している。
例えば── 中心部の物質(&質量)が銀河だとする。
もし、物質(&質量)の凝集が進み、“銀河内の物質(&質量)がコンパクト化”すればするほど── 銀河の周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布」が増加することが、この単純な図によって理解できる。
銀河に限らず一般に── “物質(&質量)の分布がコンパクト化”すればするほど、その周囲の宇宙は膨張すると言えると考えられる。
※アインシュタイン方程式も、中心部の“物質(&質量)分布がコンパクト化”が進むほど、周囲の“時空の曲がり”が大きくなることを示している。
“物質(&質量)の分布がコンパクト化”するプロセスは、様々ある。
そのプロセスの中で、最も激しいもの1つは、新しいブラックホールが形成されつつある段階のものであると考えられる。
なぜなら、新しくブラックホールが形成される間は、ブラックホールが周囲の物質(&質量)を高速で吸い込むとともに── 「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布の増加」が著しく激しく起きていると考えられるからである。
(現に、ブラックホールの境界周辺には、ほとんど光子を外へ出さないほど、高密度の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布」が存在すると考えられる)
銀河は、その中心に巨大なブラックホールを持っていると考えられている。 そして、銀河の中心部以外にもブラックホールはできる。
そこで次の仮説を立てた。
仮説3.11 生まれて間もない“未熟な銀河”であるほど── ブラックホールが新たに形成されることの影響がより大きくなるので、“物質(&質量)の分布がコンパクト化する過程が激しくなる。
光速には限界があるので── 遠くにあるものとして観測される銀河ほど、より過去にさかのぼって存在する若いフレッシュな銀河である。
つまり、宇宙の観測において、遠方にあるとされる銀河ほど“未熟”である。
一方、仮説により、未熟な銀河ほど、ブラックホールの影響が大きくなり、“物質(&質量)分布がコンパクト化”が激しくなるので── まとめると、遠方のものとして観測される銀河ほど、銀河の周囲の宇宙の膨張(銀河の周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布」が増加)も激しくなることになる。
つまりは、“遠くにある銀河ほど、赤方偏移も大きい”という観測結果を、以上の理論によっても、うまく説明できることになる。
※例えば、クエーサーとは、“複数の銀河が合体する”の激しい現象であると考えられている。 (参考 『クエーサーの謎』 講談社ブルーバックス)
この“複数の銀河が合体する過程”では、銀河内の質量密度の分布をコンパクト化が、激しくなる。 つまり、クエーサーの周囲の宇宙の膨張(銀河の周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布」が増加)も激しくなる。 つまり、この考え方は、クエーサーの赤方偏移が、とても大きいという観測結果とも、うまく合致する。
当然、近くの銀河ほど、成熟した銀河である。
したがって、近くの銀河ほど(成熟しているので)、新しいブラックホールの影響も小さくなり、“物質(&質量)のコンパクト化の進み方”が、よりゆるやかになっている。
つまり、近くの銀河ほど、周囲の宇宙の膨張(=周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布」が増加)がゆるやかになり、赤方偏移も小さくなる。
そのことも観測結果と合致している。
一方、たとえ、ブラックホールを介さなくとも、“物質(&質量)の分布のコンパクト化”は、つねに進行していると言える。
なぜなら、例えば、単に、天体同士が重力によって近づく過程(例えば、この天の川銀河と、となりのアンドロメダ銀河が近づく過程)、あるいは、太陽などの恒星で核融合反応が進む過程においても、“物質(&質量)の分布のコンパクト化”は、ゆっくりと進行していると言えるからである。
“ブラックホールが物質(&質量)に作用する”過程のみならず── 銀河どうし、銀河の中の恒星どうし、恒星と惑星… も含め、あらゆる“(重力によって)質量を持つ物質(&質量)が互いに近づく”過程は、“物質(&質量)の分布のコンパクト化”の一例であり、それらの周囲の宇宙を膨張させると考えられる。
自由落下運動が加速することからもわかるように── 重力による“物質(&質量)の分布のコンパクト化”は、一般に加速する。
つまり、“物質(&質量)の分布のコンパクト化”にともなう“宇宙の膨張”は、加速するのが自然なのである。
この考察は、この「重力による“物質(&質量)の分布のコンパクト化」こそが── わざわざ“ダークエネルギー”を持ち出して説明しようとしていた“宇宙の加速膨張”の原因であると解釈できることを意味していると思われる。
正しければ、“宇宙の加速膨張”の原因は、重力ポテンシャルエネルギー(重力によるシンプルな現象──“重力によって物質が加速しながら近づくこと”)に過ぎないことになる。
例えば、ある銀河の「重力による“物質(&質量)の分布のコンパクト化」によっても宇宙の加速膨張が観測される。
一方で、もし、その銀河が重力によって加速して近づいてきていたとしても── 宇宙の膨張が起きているはずである。
(なぜなら、銀河の運動方向への重力子の放出が増えるので、運動方向に宇宙が膨張するからである。
もし、単に等速運動で近づくならば、光のドップラー効果のみが現れる。 しかし、加速運動で近づくならば、“光のドップラー効果”に、“重力的赤方偏移の効果”も追加されると考えられる。 それは、加速時のみに、“重力による引力の増加”が生じることと合致しており、やはり、 “加速運動と重力の働きが等価である”ことと関連していると言えると思われる。
なお、近づいてくる場合、“光のドップラー効果”には、光の波長を短くする効果があり── 加速による“重力的赤方偏移の効果”には、光の波長を長くする効果がある。 単に両者の効果の足しあわせられたもの(打ち消し合わされたもの)が、観測されるということでいいのだろうか? 今後の課題である。)
いずれにせよ、重力の働きによる所産であれば── 近づいてくるような加速運動にせよ、近づいては来ない物質のコンパクト化にせよ、いずれにせよ、“宇宙の膨張”が起きているということができると思われる。
Ωm(物質の密度)+ΩΛ(エネルギー密度)=1 であると考えられている。
Ωm(物質の密度)との和を1に保つΩΛ(エネルギー密度)を担うものがダークエネルギーであるとされている。
(元々は、Ωmが1に近く、ΩΛ増は0に近かった。 ΩΛが増加するとともにΩmは減り、現在、ΩΛが0.73とのことである)
“物質(&質量)の分布のコンパクト化”が進むと、周囲の宇宙が膨張するので── Ωm(物質の密度)は減る。
したがって、ダークエネルギー=ΩΛ(エネルギー密度)は、“物質(&質量)の分布のコンパクト化”にともなって、逆に増加することになる。
ダークエネルギー=ΩΛ(エネルギー密度)の実体とは何であろうか?
(重力ポテンシャルエネルギーは、加速膨張の原因と考えられるが、これがダークエネルギー=ΩΛ(エネルギー密度)というわけではない。 なぜなら、加速膨張するほど、重力ポテンシャルエネルギーは減るはずだからである)
物質(&質量)の分布のコンパクト化”によって、実際に何が起こるかについて、3つの例を挙げる。
〈1〉“物質(&質量)の分布のコンパクト化”が、進めば進むほど── 素粒子の集合のエネルギーが1.2×1019Gevの閾値を越えやすくなるので、より重力子を放出できるようになり、周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布」が増加する。
〈2〉 重力による“物質(&質量)の分布のコンパクト化”が、進めば進むほど── その運動が加速されることによって、周囲の「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)の分布」が増加することも起こる。
〈3〉 さらには、“物質(&質量)の分布のコンパクト化”が、進めば進むほど── 重力子による原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)のキャンセルによって生じていた“4面体”が減り、逆に原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)は増加するということも起こる。
その様子を単純にモデル化して下図に示す。
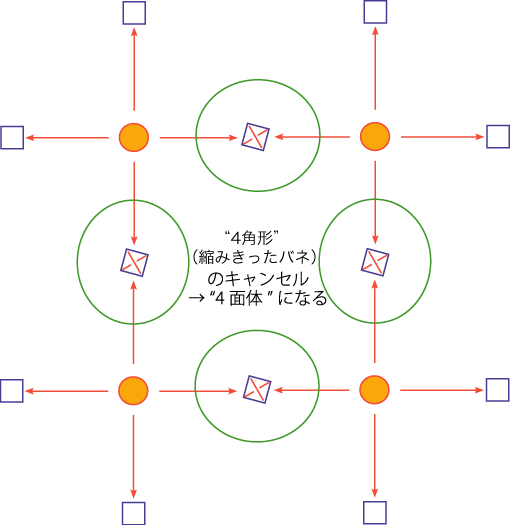 |
→
質量分布の
コンパクト化
|
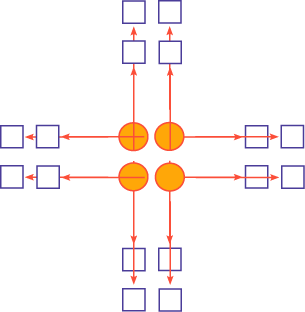 |
また、以上をふまえ下図を見ると、物質(&質量)のコンパクト化が進むほど、(重力子による“4角形”(縮みきったバネ)のキャンセルで生じていた原始ヒッグス場の“4面体”が減るので)、重力子の密度が増加するとともに、周囲の宇宙が膨張すると解釈できる。
以上をふまえて下図を見ると── 例えば、個々の銀河の物質(&質量)の分布のコンパクト化にともない、銀河の周囲に「原始ヒッグス場由来の“4角形”(縮みきったバネ)」が増えるとともに、周囲の宇宙が膨張するために、見かけ上、より遠方に存在するように見えることが読み取れる。
※個々の銀河がそれぞれがコンパクト化する効果が大きいために、このように見える。
(仮に、銀河どうしが重力で近づいていたとしても、その加速運動の方向に宇宙が膨張する効果が現れるので、
単純に近づくようには観測されないと考えられる) |
以上をふまえ、次の仮説を立てた。
仮説3.12 ダークエネルギー=ΩΛ(エネルギー密度)と呼んでいたもの実体は── 原始ヒッグス場由来の(重力子によって生じる)“4角形”(縮みきったバネ)のエネルギーの総和である。
正しければ、質量分布がコンパクト化すればするほど── (重力子の“4角形”(縮みきったバネ)のキャンセルで生じた“4面体”が減るので)原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)が増加し、このダークエネルギーの密度(=ΩΛ)は、増えることになる。
一方で、原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)が増加すればするほど、周囲の宇宙が膨張することになるので── やはり物質の密度(=Ωm)は減る。
つまり、この仮説は、ΩΛが増加するとともにΩmは減ってきているという歴史と、うまく合致している。
※元々は、Ωmが1、ΩΛが0に近かったということは── 元々、(物質がコンパクト化しておらず非常に分散しているがために、一見、物質密度が低いように思えるが、実際は、)原始ヒッグス場の“4角形”(縮みきったバネ)がほとんど存在していなかったがために、宇宙がせまく、小さな物質同士はとても窮屈に存在していたことを意味すると考えられる。 (→考察13《物質&宇宙の歴史》)
以上が正しければ、“重力子の挙動”によって、“宇宙の加速膨張”&ダークエネルギーを説明できたことになる。
※少なくとも“宇宙の加速膨張”と相対性理論の関わりが深いと考えられる以上── 少なくとも“重力子の挙動”と何らかの関わりがあることは間違いないと考えられる。
※ダークエネルギー、ダークマター、明るい物質の関係は、おおよそ次のようにまとめられることになる。
以上のように、様々なエネルギー(質量エネルギー、運動エネルギー(1/2mv2)、熱エネルギー(個々の粒子の運動エネルギー)、重力ポテンシャルエネルギー、電磁ポテンシャルエネルギー(化学エネルギー)、ダークエネルギー、ダークマター、量子ゆらぎのエネルギー、インフレーションを起こすエネルギー…)が、“時空構造ポテンシャルエネルギー”(=重力子&“4角形”〈縮みききったバネ〉およびその集合)によって、説明できる。
よって、次の結論を得た。
結論3.2 時空構造ポテンシャルエネルギーの実体は、時空の基本構造の“4面体”のバネの変形によって蓄えられるエネルギーであり、これにより、多くの種類のエネルギーを統一できる。
|