研究論文
『プランクスケールの自然についての幾何的モデルの探究が生む驚異的な成果』
3《エネルギー保存則(熱力学第一法則)について》
「エネルギーは、新たに生成も消滅もしない」「孤立系の中でエネルギーは一定である」「(この宇宙が孤立系だとすれば)全宇宙でエネルギーは減りも増えもしない」…
これらが、エネルギー保存則が意味してきたことでした。
このエネルギー保存則は、あらゆる物理学の教科書に記載されていることであり、長らく、誰もが、疑おうなどとは思いもよらないような常識となってきました。
すなわち、「エネルギー保存則」という名の科学的な常識は、多くの人々にとって「エネルギー保存則を疑うこと」=「非科学のレッテルを張られること」を意味するほど、あたり前のものとして君臨してきました。
※筆者も、高校時代から物理学を学ぶ中で、その「エネルギー保存則」という名の“科学的な常識”を、何の疑いも持たないままに、身につけてきておりました。
しかし、素スピノル物理学パラダイムを育む中で、『この常識として学んできた“(適用範囲(成立条件)を明確にしない)エネルギー保存則”の方こそが非科学で、自然(nature)から乖離しているのではないか?』という発想が育ち続けました。
その理由の1つは、素スピノル物理学パラダイムを育む過程で、『従来の物理学パラダイムにおいて「エネルギー保存則」が矛盾を生んでいる例があること(エネルギー保存則にこだわらない方が矛盾を減らせること)』に気づいたからです。
その気づきの具体例には、次のものが含まれます。
『時空が不連続であれば、エネルギー保存則が成立しなくなる』
※それは、ネーターの定理がはっきり教えてくださっていることです。
『一般相対性理論を量子化するためには、不連続な時空&エネルギー非保存を前提とする必要がある』
※時空の量子化(一般相対性理論の量子化)と、エネルギー保存則(連続な時空)が矛盾していることに気づきました。
『不連続な時空&エネルギー非保存こそが、「重力波がエネルギーを持ち去り質量を減らす」ことを示す一般相対性理論と「運動エネルギーの増加が質量エネルギーの増加である」ことを示す特殊相対性理論の間にある矛盾を解消できる』
『重力子や光子の生成過程がエネルギー生成過程であることが、さまざまな矛盾を解消する』
『もし1つ1つの重力子がエネルギーを持ち去っていたら、1つの重力子あたりおよそ3マイクログラム(3×10-9[kg])ずつ質量が減り続けることになり、観測結果と矛盾してしまう』
※1つ1つの重力子によって質量が減り続けてしまえば、万有引力の法則にもとづく地球の公転運動さえも成立しないことになってしまいます。
『1つ1つの光子がエネルギーを持ち去らいないと前提の方が、太陽の光度が1億年に1%ずつ増してきていることの説明が容易である』
『また、1つ1つの光子がエネルギーを持ち去らないという前提は、ボーアの原子模型の持っている奇妙さを解消できる』
『量子物理学で登場する「エネルギー保存則を破って生成&消滅するという仮想光子」は、まさに「エネルギーは保存していない」ことの根拠の1つに他ならないと解釈できる』
… |
もう1つの理由は、『自然(nature)の中に、運動エネルギーの一部が、負の仕事によって完全に消滅する例が多々ある』ことに気づいたからです。
「エネルギーの消滅ががどこかで起きているはずだ」という目で、自然(nature)の中を探すと、実際、明らかにエネルギーの一部が100%消滅してしまっている例が、多々、見つかったのです。
次の例には、いずれも、「運動エネルギーの一部の、負の仕事による完全な消滅」が存在します。
「木から落下しはじめたリンゴを優しくキャッチして、静かに地面に下ろす──」
「リンゴを上に放り投げて、静かにキャッチする──」
「その場でジャンプして静かに着地する──」
「エレベータを使って、下に降りる──」
「N極とS極の磁石を手で静かにくっつける──」
「反復横跳びする──」
「手を振る──」
…
|
※例えば、果樹に実っているリンゴを、落下直後に手でキャッチして、そっと地面に下ろす過程でエネルギーが消滅することの説明は、次のようになります。
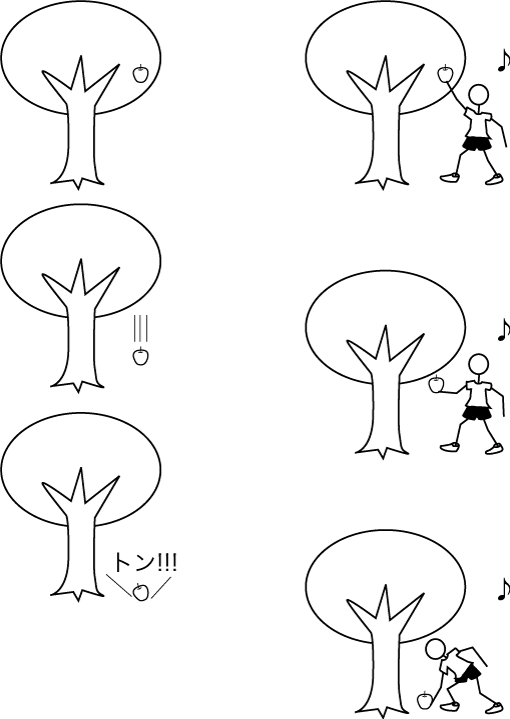 |
※左側は、果樹に実ったリンゴが自由落下する場合です。
最初にリンゴが樹に実っている状態で、このリンゴはすでにポテンシャルエネルギーを持っているのでした。そのポテンシャルエネルギーを計算すると次のようになります。リンゴが地面から高さh[m]の位置に存在し、リンゴの質量がm[kg]であるとするとします。重力速度をg[m/s2]とすると、このリンゴに蓄えられているポテンシャルエネルギー(by地球の重力場)は、mgh[J]です(地面でのポテンシャルエネルギーは0[J]です)。
この静止していたリンゴが落下運動を始めると、このポテンシャルエネルギーを利用して、リンゴは加速して運動エネルギーを蓄えながら地面に向かいます。
このリンゴが地面にぶつかる直前に、リンゴは、mgh[J]=mv2/2[J]の運動エネルギーを持っていることになります。((v[m/s]は、リンゴが地面にぶつかる直線の速さです。空気の摩擦を無視します) 地面に到達すると、その結果、そのリンゴが持っている運動エネルギーmv2/2[J]が、音のエネルギーや熱エネルギー、リンゴを変形するためのエネルギー…に変化します。
※一方、右側は、地面から高さh[m]の位置にある質量m[kg]のリンゴを、落下し始めた直後にキャッチし、そのまま静かに地面に下ろす場合です。
最初に、枝にのリンゴの実がなっている段階で、リンゴがmgh[J]のポテンシャルエネルギーを持っていることは左と全く同じ条件です。
しかし、リンゴが地面に静かに置かれるときにリンゴが持っている運動エネルギーがほぼ0[J]であることが大きく異なっています。
それでは、リンゴが持っていたはずのポテンシャルエネルギーmgh[J](=リンゴの運動エネルギーmv2/2[J]を生み出せるはずの潜在的なエネルギー)の大部分は、どこへ行ってしまったのでしょうか?
完全に消滅したのです。
なぜ消滅したかといえば、少年の運動によってもたらされる「負の仕事」によって、リンゴが本来獲得するはずだった運動エネルギーが、打ち消されてしまったからです。
たった、これだけのことで、エネルギーが完全に消滅してしまうことがあるのです。
※なお、少年は、筋肉の収縮運動によって「負の仕事」をする際、エネルギー(ATPという化学エネルギー)を消費します。
このエネルギー(ATPという化学エネルギー)の一部は熱エネルギー(使えないエネルギー)として散逸しますが、残りのエネルギー(使えるエネルギー=ギブズの自由エネルギーΔG[J])は「負の仕事」をするために使われます。
この「負の仕事」をするために使われるエネルギー(ATPという化学エネルギーの一部)と、リンゴに最初に蓄えられていたポテンシャルエネルギーmgh[J]のほぼすべてが、互いに打ち消し合って(熱にならずに)完全に消滅するのです。
|
他の例も同様です。
たった、それだけの過程で、エネルギーの一部が(熱になるわけでもなく)100%消滅してしまうのです。
つまり、運動エネルギーが消失する際には、必ずしも、すべての運動エネルギーが熱エネルギーとして散逸するとは限らないのです。
たった、これだけのことで、 「エネルギーは、新たに生成も消滅もしない」「孤立系の中でエネルギーは一定である」「(この宇宙が孤立系だとすれば)全宇宙でエネルギーは減りも増えもしない」… という主張するエネルギー保存則が破れていることが、証明(実証)されてしまうことに気づいたのです。
しかも、「運動エネルギーの一部が負の仕事によって完全に消滅すること」は、熱力学第1法則の数式『ΔU=Q+W[J]』からも導けることです。
主に、これら2つの理由から、『この「エネルギー保存則」という“科学的な常識”の方こそが、自然(nature)から乖離しているのではないか?』『“適用範囲を明確にしないエネルギー保存則”の方こそが、非科学のレッテルを張られるべきではないか?』という発想が育ち続けたのです。
さらには、「エネルギー保存則は成立していないはずだ」という目で文献を調べる中で、エネルギー保存則は、決して証明されてきたものではなく、経験法則に過ぎないという認識を深めることができました。
すなわち、エネルギー保存則は、本質的に*、単なる「エネルギーは保存するはずだ」という強い信念に過ぎないという認識を深めることができたのです。
たとえば、次のような記述が参考になります。
|
『取れるエネルギーと必要とした電気を比べるとたかだか同じで、ロスがあるからたいてい損をする。取り出せるエネルギーの方が小さい、というのが熱力学としてまとめられているものの第一法則、第二法則の内容である。これは証明されたことではない。不思議なことに、人間にとって非常に大事な基本的なものは証明されていない。』
(『東京大学公開講座 地球』 p.198 VIII 地球の温暖化 小宮山宏 東京大学出版会) 下線は、筆者によります。
|
| ※『第一法則』は、エネルギー保存則の根拠の1つですので、この記述から、間接的に「エネルギー保存則は、実は証明されたものではない」ことがわかります。 |
『トムソンは公刊された論文の中では神学的な議論を用いていないが、1852年の論文では、「神のみが力学的エネルギーを誕生させたり消滅させたりすることができる、というのはきわめて確実なことであるから」、散逸されたエネルギーが消滅するはずがなくて、転換されるだけである、と述べている。』
(『物理学の誕生─エネルギー・力・物質の概念の発達史─』 p.63 P.M.ハーマン著 杉山滋郎訳 朝倉書店) 下線は筆者によります。 |
※もしエネルギー保存則が証明されていたのなら、このような記述はありえません。この記述から、エネルギー保存則が証明されていなかったことがわかります。
|
|
『この法則は、他の科学の法則と同様、多くの観測と試行から導かれた結論である。検証は十分に広い範囲にわたって尽くされており、一般に受け入れられている。』
(『知っておきたい熱力学の法則と賢いエネルギーの選択』 リチャード・S・スタイン ジョセフ・パワーズ著 安倍明廣 p.9-10(第1章) NTS) 下線は、筆者によります。
|
| ※この『エネルギー保存則』についての記述から、エネルギー保存則が、やはり証明されたものではなく、『多くの観測と試行から導かれた結論』に過ぎないことがわかります。証明されていれば、やはり、『一般に受け入れられている』という説明はありえません。(証明されているピタゴラスの定理について、『ピタゴラスの定理が一般的に受け入れられている』という記述がありえないのと同様です) |
「エネルギー保存則が、決して証明されてきたものではなく、経験法則に過ぎなかった」ということは、論理的に考えてもわかります。
それは、次のように説明できます。
『これまでの観測や実験の結果は、エネルギー保存則が成立するのであれば、当然、起こることが予想されたものだけであった。しかし、決して、エネルギー保存則が成立することを証明するものではなかった。なぜなら、これまでまでの観測や実験は、エネルギー保存則が成立するのであれば、当然、起こることが予想されるものだけであったに過ぎない可能性があるからだ。すなわち、エネルギー保存則が成立しないことが予想されるようなものは無視してきた可能性があるからだ。
つまり、どんなに観測や実験を繰り返して、エネルギー保存則を支持する結果を積み重ねたとしても、エネルギー保存則が成立することを証明することは、原理的に不可能なのだ。
すなわち、観測や実験を繰り返してできることは、反証されないことを確かめること(必要条件を満たすかどうかを確かめること)、および、反証することだけなのだ』 |
※この考えは、『ポパーの反証可能性』と関連しています。
エネルギー保存則は、それが科学である以上、(科学の条件の1つである)反証可能性が存在し続けるので、本来、原理的に証明できないのです。
|
例えば、ジュールによる熱の仕事当量を導く偉大な実験は、確かに、エネルギー保存則が成立する必要条件を満たしていました。すなわち、おもりの力学的エネルギー(運動エネルギー&ポテンシャルエネルギー)が100%熱エネルギーに変換されて「熱の仕事当量が導かれること」は、「エネルギー保存則が成立するのであれば当然そうなるべき帰結」、必要な条件でした。
しかし、ジュールによって、このようにして熱の仕事当量が導かれたとしても、実は、エネルギー保存則が証明されたことにはなっていませんでした。
もし、「エネルギー保存則が証明された」と判断してしまえば、それは「後件肯定の誤謬」だからです。
※エネルギー保存則が成立するのならば、熱の仕事当量が導かれるはずです。
(「エネルギー保存則が成立する」→「熱の仕事当量が導かれる」)
しかし、「熱の仕事当量が導かれる」が確認されたからといって、「エネルギー保存則が成立する」とは本来言えないのです。
それは、『飛行機なら、空を飛びます。(「飛行機である」→「空を飛ぶ」) しかし、空を飛ぶからといって、飛行機であるとは、限りません。』というのと同じ論理です。
つまり、これまでの観測や実験の結果は、エネルギー保存則が成立する必要条件を満たしていても、決して十分条件を満たしていなかったからこそ、エネルギー保存則を証明したことにならなかったのです。
(「エネルギー保存則を証明した」と解釈することは、「後件肯定の誤謬」なのです)
しかも、「樹上のリンゴを地面に静かに下ろす」という、たったこれだけの系で、エネルギーの一部が100%消滅してしまうことが証明(実証)できるのです。
エネルギー保存則が成立しないことを示す観測や実験が実在し、しかも、それが「樹上のリンゴを地面に静かに下ろす」というだけの単純なものなのです。
※当然、「高い所にあるボールを静かに地面に置く」という系でも、実証できます。
高い位置にあるボールを、そのまま手を話せば、ボールは弾み、(最初より減りますが)再びポテンシャルエネルギーを蓄えます。しかし、「高い所にあるボールを静かに地面に置けば」弾みませんので、その再度獲得するはずだったポテンシャルエネルギーの分の“エネルギー”の大部分が消失していることを実証したことになります。
※これらの系は、エネルギー保存則の反証です。
これらの単純で広く存在する系は、これまで、エネルギー保存則を強く信じていたがゆえに、無視してきた観測や実験です。
エネルギーを消滅させることができることを誰もが簡単に実証できるのです。
それにも関わらず、エネルギー保存則は、従来の物理学パラダイムにおいて『最も普遍的な法則』と見なされ続けてきました。
|
『エネルギーのさまざまな形とその間の移り変わりを調べていくと、われわれは物理学の最も普遍的な法則であるエネルギーの保存則に行き着く:
エネルギーは生み出されることも失われることもない。エネルギーは1つの形から他の形へ移り変わることはできるが、エネルギーの総量は決して変わることがない』
(『物理のコンセプト エネルギー』 Paul G.Hewitt John Suchocki Leslie A.Hewitt 著 小出昭一郎監修 黒星瑩一訳 p.13 共立出版株式会社) 下線は、筆者によります。
|
しかも、エネルギー保存則を疑う者が、疑われ(非科学のレッテルが貼られ)続けてきました。
|
『この法則は、他の科学の法則と同様、多くの観測と試行から導かれた結論である。検証は十分に広い範囲にわたって尽くされており、一般に受け入れられている。例外は見つかっておらず、どのような提案であれ、この法則に従わないものは疑わしいとされる。』
(『知っておきたい熱力学の法則と賢いエネルギーの選択』 リチャード・S・スタイン ジョセフ・パワーズ著 安倍明廣 p.9-10(第1章) NTS) 下線は、筆者によります。
|
なぜだったのでしょうか?
理由の一つは、一言で言えば、「エネルギー保存則が成立するはずだ」という思い込み(信念)が強かったからです。
「エネルギー保存則が成立するはずだ」という強い思い込み(信念)は、少なくとも3つの結果をもたらしました。
1.「エネルギー保存則が成立する」ことを支持する証拠だけを集めた。
2.「エネルギー保存則が成立しないはずだ」という発想で、自然(nature)を眺めることができなかった。
3.「エネルギー保存則が成立しないのではないか」(エネルギーの一部は消滅しているのではないか…)という疑いを、徹底的に排除してきた。
1.「エネルギー保存則が成立する」ことを支持する証拠だけを集めた。
※例えば、ネーターの定理を、エネルギー保存則の理論的な根拠と見なしました。しかし、本来、ネーターの定理自体は、「時空が連続ならエネルギー保存則が成立する。時空が不連続ならエネルギー保存則が成立しない」ということを示す中立的なものでした。
※例えば、ジュールの熱の仕事当量の測定を、「エネルギー保存則」の実験的な証拠と見なしました。
しかし、ジュールの偉大な功績である熱の仕事当量の測定が実際に示したことは、運動エネルギーがすべて熱エネルギーに散逸しうるという必要条件が成立することだけでした。
※「エネルギー保存則」に反するように見えた実験結果(例えば、エネルギーの減少)はすべて、(エネルギーの消滅ではなく)「測定誤差」や「熱エネルギー(摩擦熱…)としての散逸によるもの」として解釈したと考えられます。ここにあるのも『観測の理論負荷性』です。
2.「エネルギー保存則が成立しないはずだ」という発想で、自然(nature)を眺めることができなかった。
※例えば、「木から落下しはじめたリンゴを優しくキャッチして、静かに地面に下ろす──」 これだけのことで、エネルギーの一部が100%消滅してしまう事実にさえ気づけなくなってしまいました。
※負の仕事によって運動エネルギーの一部が100%消失する例が多々あるはずだ、という目で自然(nature)を眺められなかったがゆえに、運動エネルギーが減少するように見える現象があっても、(エネルギーの消滅ではなく)「測定誤差」や「熱エネルギーとしての散逸によるもの」として解釈してきたのだと考えられます。
3.「エネルギー保存則が成立しないのではないか」(エネルギーの一部は消滅しているのではないか…)という疑いを、徹底的に排除してきた。
※物理学の専門家の方々は、権威や歴史を持ち出して、「エネルギー保存則」を疑う考えに、「非科学」のレッテルを貼って、徹底的に排除してきました。ここにあるのは、典型的なロックインです。本来の科学の営み(自然(nature)との調和を探究する営み)が、特定の教義を普及するような別の営みにすり替わっています。
※教科書の中に「エネルギー保存則は、実は証明されておらず、“科学者の間の合意”に過ぎない」と明記してきませんでした。そのような教科書によって、知らず知らずにエネルギー保存則を常識として学ばせると同時に、疑う者は非科学のレッテルを張られてしまうという暗黙のプレッシャーを与えてきました。
|
つまり、「エネルギー保存則が成立するはずだ」という思い込み(信念)だけが、エネルギー保存則を『最も普遍的な法則』として君臨させてきた根拠であり、もはや、ここにあるのは、(ガリレオが生み出したところの)本来の自然科学ではなくなっているのです。
このままでは、本来の自然科学の営み(=「自然(nature)との調和を探求する営み」=よく調べて考えて自然(nature)についての『ほんとうのこと。まことの道理』を究める営み(参考 『広辞苑』『科学者』『研究』『真理』→付録『科学について』))が、自然(nature)から乖離した信念(信仰…)を守る営みに変わり果て、自然科学が衰退&絶滅してしまいます。
エネルギー保存則は、少なくとも、次の3つの理由からしっかり見直される必要があります。
1.量子物理学は、エネルギー保存則を破って生じる“仮想粒子”を考慮している。
2.素スピノル物理学パラダイムは、重力子や光子の生成過程が、エネルギーの生成過程であることを示している。(時空が不連続であればエネルギーが保存しないことをネーターの定理が示している)
3.「熱力学第一法則」自身が、たとえ孤立系の中であっても、エネルギーが100%消滅しうることを示している。
|
1.量子物理学は、エネルギー保存則を破って生じる“仮想粒子”を考慮している。
量子物理学(場の量子論、量子電磁力学…)では、仮想光子などの仮想粒子がエネルギー保存則を破って生成&消滅することを考慮して進められています。この値の大きさは、すべてを足し上げると無限大になるほどのものであり、決して無視できないものです。
このことは、従来の物理学パラダイムが根本的な矛盾を抱えていることを意味しています。
少なくとも、このことは、エネルギー保存則の見直しを迫るのに十分な理由の1つに相当しています。
同時に、このことは、エネルギー保存則が、もはや、『物理学の最も普遍的な法則』であるとは言えないことを示しています。すなわち、このとことは、『物理学の最も普遍的な法則であるエネルギーの保存則』という表現が、もはや、現状から乖離していることを示しています。
2.素スピノル物理学パラダイムは、重力子や光子の生成過程が、エネルギーの生成過程であることを示している。(時空が不連続であればエネルギーが保存しないことをネーターの定理が示している)
素スピノル物理学パラダイムでは、成果1で示したように、重力子や光子の生成過程は、エネルギーの生成過程であることを示しています。
すなわち、重力子や光子が、エネルギー非保存の所産である(エネルギーを持ち去らない)ことを示しています。
このことは、素スピノル物理学パラダイムが不連続な時空を前提としていますので、問題ありません。
ネーターの定理と調和しているからです。
これまで、物理学は、「時空は連続である」ことを前提として、さまざまな現象を説明してきました。
この「時空は連続である」という前提は、ニュートンやライプニッツらが“微分”という数学的な手段を発明して以来、これまで物理学界が無意識的に保持してきた前提でした。
なぜなら、“微分”(微分可能であること)は、まさに、「時空が連続である(時空が、どこまでもなめらかである)」という前提の上に成立するものだからです。
そして、まさに、「時空が連続である」という前提の上でこそ、エネルギー保存則が成立するのでした。
そのことを、ネーターの定理が示してくれているのでした。
(なお、厳密には、「時間が連続であるという前提でエネルギー保存則が導かれ、空間が連続という前提で、運動量保存則が導かれる」ことを、ネーターの定理が示してくれています)
一方、ネーターの定理は、「時空が不連続である」のならば、エネルギー保存則が成立しないことを示してくれる定理でもあります。
つまり、「時空が連続であれば、光子や重力子がエネルギーを持ち去る」と「時空が不連続であれば、光子や重力子がエネルギーを持ち去らない」ということの両方を、ネーターの定理は示してします。
したがって、「時空は不連続であること」を前提とし、「光子や重力子に関して、エネルギー保存則が成立していない」ことを示している素スピノル物理学パラダイムには、問題がないことになります。
|
※なお、エネルギー保存則の観測上の正しさは、これまで、せいぜい10−28[s]ほどまでしか確かめられてきませんでした。
『すでに述べたように、エネルギー保存則は時間に対して自然法則が変わらないことの結果であり、これがネーターの定理の核心である。この主張を逆にして、物理法則が変わらないという結果を導くためにエネルギー保存則を用いることもできる。物理法則は、きわめて短い時間スケール、1/10,000,000,000,000,000,000,000,000,000(10−28)秒という短い時間でも、局所的に変化するはずがないことがわかっているのだ。』
( p.110-111 『対称性 レーダーマンが語る量子から宇宙まで』) 下線は、筆者によります。 |
この記述は、10−28[s]までの時間の連続性をややおおげさに提示していますが、一方で10−44[s]での時間の“連続性”は観測で確かめられてこなかったことを露呈しています。このことは、例えば、重力子の生成過程でのエネルギー非保存性は、これまでの観測によって、決して否定されないことを意味しています。
また、空間的並進に対する連続性は、せいぜい10−24[m]ほどまでしか推測されていません。
『(われわれの宇宙の)普通の空間は連続的並進対称性をもっていて、物理法則は空間のどこでも同じである。空間は、並進(平行移動)に対して離散的なステップを持つ結晶格子やチェス盤ではない。つまり、われわれの住んでいる空間には、識別可能な最小距離1/10,000,000,000,000,000,000(10−19)メートルまで短くしても、並進に対して最小のステップ存在しない。間接的な方法を使えば、1,000,000,000,000,000,000,000,000(10−24)メートルという短い距離まで、空間は並進に対して不変であると推測することができる。』
( p.105 『対称性 レーダーマンが語る量子から宇宙まで』 下線は、筆者によります) |
この記述は、10−24[m]までの空間の連続性をややおおげさに提示していますが、一方で10−35[m]での空間の“連続性”は観測で確かめられてこなかったことを露呈しています。このことは、10−35[m]での空間の“不連続性”は、これまでの観測によって、決して否定されていないことを意味しています。
さらに、重力子や光子の生成過程が、エネルギー生成過程であると理解している方が、さまざまな現象を一貫して(統合的に)説明できます。
1.重力子の1つ1つのエネルギーがエネルギー保存則に従わないからこそ、『1つ重力子が放出される度に、重力子エネルギーEG[J]が持ちさられると同時に質量が「プランク質量/2π[kg]」(≒3×10-9[kg])ずつ減ること』がなく、現実の観察(万有引力の法則、慣性の法則、質量保存…)と調和することになります。
2.「連星パルサーにおける公転周期の収縮」や「2つのブラックホールの合体による重力波」の観測は、いずれも重力波(重力子の放出数の変化として創発)がエネルギーを持ち去らない(質量を減らさない)という説明の方が、一貫した説明ができます(「重力波がエネルギーを持ち去って質量を減らす」ことを示す一般相対性理論と「運動エネルギーの増加が質量エネルギーの増加に結びつく」ことを示す特殊相対性理論の間にある矛盾を解消できます)。 また、この説明は、「一般相対性理論の正当性に疑いをもたらすような」問題も解消します。
3.《太陽の光度の変化(『太陽の光度が1億年ごとに1%ずつ増してきていること』)》、《放射冷却》を含む、放射熱に関することを、より一貫して説明しやすくなります。
なお、完全な真空を作ってこれなかった以上、“光子がエネルギーを持ち去らないこと”を反証することは、これまで決してできませんでした。
… |
両者のエネルギーに関することについての説明を比較すると次のようになります。
|
従来の物理学パラダイム
|
素スピノル物理学パラダイム
|
|
時空
|
連続である
(どこまでも)なめらかである
|
不連続である
(プランクスケールで)飛び飛びである
|
|
微分
|
(たとえプランクスケールでも)
可能である
プランクスケールにおいても
微分できる。
|
(“無限小”がない以上、厳密には)
不可能である
時空が連続と見なせるマクロのレベル
においてのみ微分で近似できる。
|
|
エネルギー保存則
|
(重力子や光子のエネルギーも含めて)
常に成立するべきである。
時空が限りなく連続なので
プランクスケールでも成立する。
あらゆる条件で成立する。
|
(重力子や光子のエネルギー等)
ときに成立しない。
例えば、重力子や光子の総和である
重力場(重力波)や電磁場(電磁波)に
ついては、成立していない。
エネルギー保存則の適用範囲(成立条件)を
明確にするべきである。
|
|
光子や重力子
(電子波や重力波)
|
エネルギーを持ち去る
|
エネルギーを持ち去らない
(光子や重力子の生成過程は、
エネルギー生成過程である)
|
|
重力場
|
連続な時空における
抽象的なリーマン幾何学(テンソル)として
時空の曲りを説明
重力場もエネルギー保存則に従う。
|
不連続な時空(原始ヒッグス場)における
「重力子の総和」として
時空の曲りを説明
重力場は、エネルギー非保存の所産である。
|
|
質量エネルギー
|
重力子やその総和である重力波が
エネルギーを持ち去ることによって、
質量エネルギーは減少する。
※この説明は、一般相対性理論の正当性に
疑いを投げかけてしまう理由の1つです。
『物体はその内部の熱運動によってエネルギー
を放出するという結論は、この一般相対性
理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』
(『アインシュタイン選集2──
A8 重力波について』より p.170〜171)
|
重力子(&その総和である重力波)は
エネルギーを持ち去ない。したがって
重力子(&その総和である重力波)の放出に
よって質量エネルギーは減少しない。
※この説明は、一般相対性理論の正当性に疑いを
投げかけてしまう理由の1つを解消しています。
|
|
熱の移動
|
熱伝導、熱対流、熱放射の3つである。
|
熱伝導、熱対流の2つのみである。
※熱放射とよばれた現象は、
熱が移動する現象ではなく
“(新たに生成した)光子が移動先で”
熱エネルギーを生成する現象です。
|
|
計算数値と観測値
|
|
|
ネーターの定理
|
ともに調和している。
※ネーターの定理は、『時空が連続ならエネルギー保存則が成立し、
時空が不連続ならエネルギー保存則が成立しないこと』を示しています。
|
3.熱力学第一法則は、たとえ孤立系の中であっても、エネルギーが完全に消滅しうることを示している。
エネルギー保存則は、量子物理学や素スピノル物理学パラダイムによって見直しを迫られているだけではありません。
実は、孤立系においても、エネルギーが完全に消滅する例(エネルギーが保存しない例)がありうることを、熱力学第一法則自身が示しているのです。熱力学第一法則の抽象的な数式からは、「エネルギーが保存しない例がある」という解釈も導けるのです。
熱力学の第一法則は、ΔU=Q+W[J]で記述できます。
(ΔU[J]:系の内部エネルギーの変化、Q[J]:系に加えられた熱量、W[J]:系に加えられた仕事)
この『ΔU=Q+W[J]』において、Q=0[J]、 W=0[J]ならば、当然、ΔU=0 となります。
このことは、外界と「物質、熱量Q[J]、仕事W[J]」のやりとりが一切ない孤立系の場合、エネルギーの総量が一定となりうることを意味します。
※『孤立系は、外界とものもエネルギーも交換できない系である』
(p.53『アトキンス物理化学要覧』 P.W.ATKINS著 千原秀昭・稲葉章訳)
※なお、「(孤立系としての)宇宙のエネルギーは、増えも減りもせず一定である」ことを、クラウジウスが指摘したのでした。(参考 『物理学天才列伝 上』 クラウジウスの項目 講談社ブルーバックス)
この『ΔU=Q+W[J]』が、エネルギー保存則の根拠となる数式でした。
このエネルギー保存則の根拠となる数式は、エネルギー保存則が孤立系でのみ成立しうることを示しています。
つまり、エネルギー保存則は、熱力学の第一法則(ΔU=Q+W[J])の特殊な条件で成立しうる例に過ぎないのです。
※特殊な条件とは、『ΔU=Q+W[J]』において、(外界と物質やエネルギーのやりとりもなく)Q=0[J] W=0[J] であるという条件です。
したがって、熱力学の第一法則(ΔU=Q+W[J])は、少なくとも孤立系でなければ、エネルギーが増加したり減少したり(消滅したり)しうることをはっきり示しているのです。
例えば、ある系は、(外からの)正の仕事によってエネルギーは増える一方、(外からの)負の仕事によってエネルギーは減る(消滅する)のです。
このことは、やはり、熱力学の第一法則(ΔU=Q+W[J])が、はっきり示していることです。
したがって、「孤立系の設定の仕方」によっては、たとえ孤立系の中であってもエネルギーが消滅することになります。すなわち、例えば、「ある物体の運動エネルギーの負の仕事によって打ち消し」を含むように孤立系が設定されていれば、たとえ、孤立系の中と言えども、エネルギーが消滅するのです。
具体的に『少年とリンゴ』の系をより厳密にした例をもとに説明すると次のようになります。
まずは、『リンゴ、樹、地球、空気』を含む系を孤立系と考えます。
下図のように、この場合、リンゴが自然に落下するので、全力学的なエネルギーがほぼ保存されると考えられます。
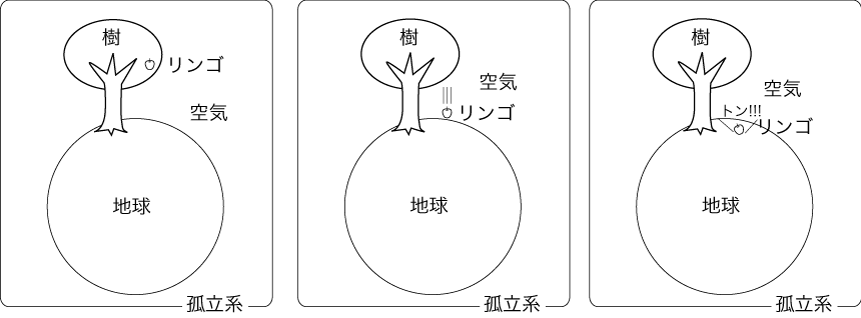
※厳密には、この場合も、一部のエネルギーが消滅している可能性は残されています。
例えば、空気抵抗の摩擦力が、負の仕事として働く結果、(すべてが熱エネルギーとはならずに)一部のエネルギーを消滅してしまう可能性が考えられます。
この孤立系に対して、系外部の『少年』が負の仕事をすることによって、少なくともリンゴに蓄えられていたポテンシャルエネルギーの大部分は完全に消滅します。
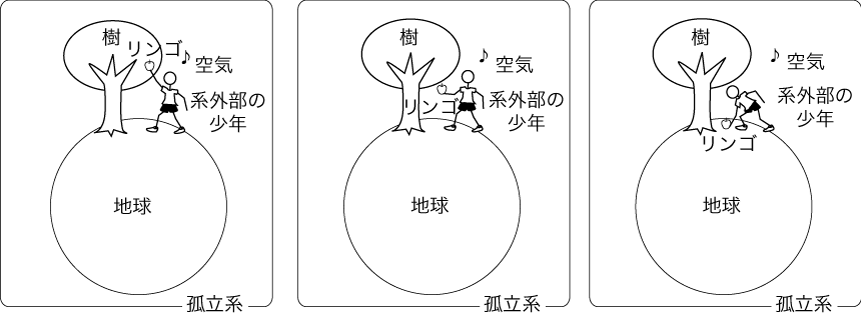
そうなりうることは、熱力学の第一法則(ΔU=Q+W[J])も、はっきり示していることです。
それでは、次に、『リンゴ、樹、地球、空気、少年』を含む系を最初から孤立系と考えたらどうでしょうか?
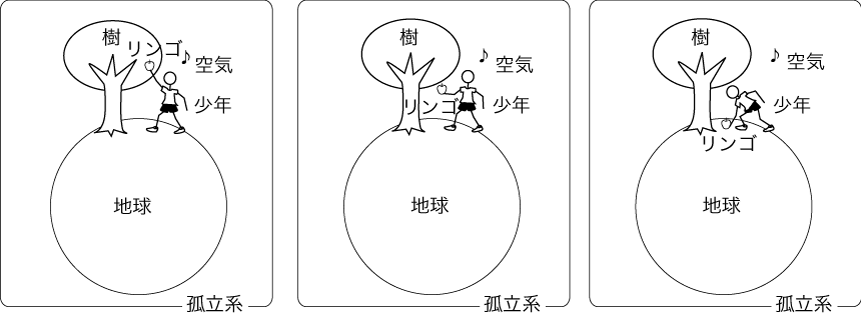
この場合は、孤立系の中であってもエネルギーが減少することになります。
(少なくとも、少なくともリンゴに蓄えられていたポテンシャルエネルギーの大部分と、少年の体内にATPとして蓄えられていた化学エネルギーの一部は、互いに打ち消し合い完全に消滅してしまいます)
少なくとも、この例は、『全宇宙を孤立系と見なした場合』も、同様に(負の仕事によって)エネルギーがいくらでも減りうることを意味しています。
すなわち、現実には、この宇宙の中で、エネルギー保存則が成立しないような(エネルギーの一部が消滅するような)「孤立系の設定の仕方」がいくらでも存在しうるのです。
つまり、エネルギー保存則が成立するのは非常に特殊な例であり、エネルギー保存則はその適用範囲(成立条件)をよく吟味する必要があるのです。
※エネルギー保存則が成立するための必要条件の1つは、「負の仕事によるエネルギーの消滅がない」ということになります。
|
こういったことを、他ならぬ、熱力学の第一法則(ΔU=Q+W[J])自身がはっきり教えてくれるのです。
すなわち、「どの範囲を孤立系に設定するか」によっては、たとえ孤立系の中であってもエネルギーが消滅しうることを「熱力学の第一法則」自身がはっきり示しているのです。
つまり、熱力学第一法則(ΔU=Q+W[J])の抽象的な数式からは、「孤立系としての宇宙のエネルギーの一部は、ときに減る(消滅する)」という解釈も導けるのです。
そういう目で周りを見渡すと、確かに、孤立系の中であってもエネルギーが消滅する例を多々見つけることができます。
《例1》テーブルからh[m]の高さまで持ち上げた、イチゴを盛った皿m[kg]を、ゆっくりとテーブルに戻す場面
例えば、「テーブルからh[m]の高さまで持ち上げた、イチゴを盛った皿m[kg]を、ゆっくりとテーブルに戻す」だけで、一部のエネルギーが消滅してしまいます。
すなわち、「人、イチゴを盛った皿、地球、机、空気」を孤立系であると考えると、孤立系の中であっても、一部のエネルギーが消滅することになります。
まず、テーブルの上のイチゴを盛った皿m[kg]をh[m]の高さまで持ち上げることによって、イチゴを盛った皿m[kg]はmgh[J]の位置エネルギー(重力ポテンシャルエネルギー)を獲得します。(gは重力加速度で、約9.8[m/s2]の値です)
もし、そのとき、手を放せば、イチゴを盛った皿m[kg]は落下し、位置エネルギー(重力ポテンシャルエネルギー)mgh[J]を利用することによって加速し、イチゴを盛った皿m[kg]は、運動エネルギーmv2/2[J](≒mgh[J])を獲得するはずです。
厳密には、このときの空気抵抗等による摩擦熱をQ1[J]とすると、
mgh[J]=mv2/2[J]+Q1[J]となるはずです。
(位置エネルギー(重力ポテンシャルエネルギー)mgh[J]の大部分が運動エネルギーに変化するはずなので、mv2/2[J]>>Q1[J]となります)
それでは、実際に手を放す代わりに、ゆっくりとイチゴを盛った皿m[kg]を下ろし、テーブルに置いてみましょう。
このときの空気抵抗等による摩擦熱をQ2[J]とすると、ゆっくり下ろす方がイチゴを盛った皿m[kg]の速度が遅いですのでQ1[J]>Q2[J]となるはずです。
そして、イチゴを盛った皿m[kg]の最終的な運動エネルギーは、ほぼ0[J]となるはずです。
それをふまえた上で、先ほどの式 『mgh[J]=mv2/2[J]+Q1[J]』を見てみましょう。
すると、位置エネルギー(重力ポテンシャルエネルギー)mgh[J]の中で、少なくとも運動エネルギーmv2/2[J]に転化できたはずの部分が完全に消えてしまったことに気づかれます。
イチゴを盛った皿m[kg]が持っていたはずの位置エネルギー(重力ポテンシャルエネルギー)mgh[J]の大部分(運動エネルギーmv2/2[J]に転化できたはずの部分)は、どこに行ってしまったのでしょうか?
そのイチゴを盛った皿m[kg]が本来獲得できたはずの運動エネルギーmv2/2[J]は、(イチゴを盛った皿m[kg]を下におろす際に)「手&腕、肩の骨格筋」によるイチゴを盛った皿m[kg]に対する“負の仕事”W[J]によって、消滅させられたのです。
※「イチゴを盛った皿、地球、机、空気」を孤立系と考えると、その外部の人による「負の仕事」によって、エネルギーの一部が完全に消滅することになります。そうなることを熱力学第一法則(ΔU=Q+W[J])から導けます。
「手&腕、肩の骨格筋」が“負の仕事”W[J]をする際、ATPという化学エネルギーが消費されます。
その化学エネルギーの一部は熱エネルギー(使えないエネルギー)として散逸しますが、一部の使えるエネルギー(ギブズの自由エネルギーΔG)はやはり、イチゴを盛った皿m[kg]が本来獲得できたはずの運動エネルギーmv2/2[J]を消滅させる“負の仕事”をするために消費されます。
つまり、「手&腕、肩の骨格筋」による“負の仕事”W[J]も、イチゴを盛った皿m[kg]が本来獲得できたはずの運動エネルギーmv2/2[J]も、両方の大部分が、互いに消滅してしまうのです。
※イチゴを盛った皿m[kg]をゆっくりおろす際、ATPが持つ化学エネルギーは、一部(50%〜70%)は、(負の)仕事に変換され、一部(50%〜30%)は、熱として捨てられます。
『骨格筋は、非常に効率よく化学エネルギーを機械的な仕事に変換する。自動車のエンジンはガソリンから得るエネルギーの80%〜90%までも熱にして浪費しているのに、骨格筋では熱にしているものは30〜50%にすぎない。
筋収縮のエネルギーはATPの加水分解によって得られる〜』(『細胞の分子生物学 第2版』 p.618) |
|
※なお、「h[m]の高さからイチゴを盛った皿m[kg]を“ゆっくり”下ろす際の「手&腕、肩の骨格筋」による“負の仕事”W[J]の大きさ」と「イチゴを盛った皿m[kg]をh[m]の高さだけ持ち上げる際の“正の仕事[J]”の大きさ」は、(厳密には、前者が後者より小さくなりますが)おおよそ等しいと考えられます。
※手で下ろす過程で、消滅したイチゴを盛った皿m[kg]の運動エネルギーの大きさをX運動エネルギー[J]、消滅した負の仕事の大きさをX負の仕事[J]、仕事をする際に使った化学エネルギーをEATP[J]、そのときに散逸した熱エネルギーをQ3[J]とすると、次のようになります。
mgh=mv2/2[J]+Q1[J]
mgh=X運動エネルギー[J]+Q2[J]
W[J]=X負の仕事[J]
EATP=W[J]+Q3[J]
よって、消滅したエネルギーの総和X[J]は、次のようになります。
=X運動エネルギー[J]+X負の仕事[J]
=mgh −Q2[J] + EATP(受)−Q3[J]
=mv2/2[J] + (Q1−Q2) +(EATP(受)−Q3)[J] >0
この式は、消滅したかに見えるエネルギーのすべてが、熱エネルギーとして散逸するのではなく、その一部が完全に消滅することを示しています。
※この結果は、「イチゴを盛った皿、地球、机、空気」の孤立系であると考えた場合に熱力学第一法則(ΔU=Q+W[J])が導く、外部の人による「負の仕事」によって、エネルギーの一部が完全に消滅するという結果と調和しています。
この例が示すように、ある運動エネルギーを打ち消すような“負の仕事”(その運動の進行方向と逆向きの力による仕事)は、やはり、エネルギーの一部を完全に消滅させるのです。
※同様に説明できる系として、(すでに説明した)「リンゴの木から落下しはじめたリンゴを優しくキャッチして地面に下ろす」系のみならず、「エレベーターやエスカレーターで下に降りる」、「消防梯子で高いビルから救助される」、「鉛筆を机の上に静かに置く」、「ボールを静かに床に下ろす」、「種を静かに土の中に置く」… といった系も挙げられます。
|
《例2》ミカンを上に放り投げて、それを静かにキャッチする場面
例えば、「ミカンを上に放り投げて、それを静かにキャッチする」だけでも、やはり一部のエネルギーが消滅してしまいます。
すなわち、「人、ミカン、地球、空気」を含む孤立系を考えると、孤立系の中であっても、一部のエネルギーが消滅します。
以下、例1よりも詳しく説明します。
まず、ミカンが上に飛び上がるのは、身体(手、腕…)が、ミカンに対して、仕事をするからです。その仕事は、筋肉の収縮によって行われます。筋肉の収縮のエネルギー源は、ATPが持つ化学エネルギー(ミクロのポテンシャルエネルギー)であり、そのエネルギーは、もとはといえば、太陽光のエネルギーに他なりませんでした。(すなわち、ATPは、光合成を通じて作られたのでした)
ミカンを手で上に放り投げる場合、このATPが持つ化学エネルギーの一部(50%〜70%、使えるエネルギー、キブズの自由エネルギーΔG)は(正の)仕事に変換され、残り(50%〜30%)は、熱エネルギー(使えないエネルギー)として捨てられます(散逸します)。
『骨格筋は、非常に効率よく化学エネルギーを機械的な仕事に変換する。自動車のエンジンはガソリンから得るエネルギーの80%〜90%までも熱にして浪費しているのに、骨格筋では熱にしているものは30〜50%にすぎない。
筋収縮のエネルギーはATPの加水分解によって得られる〜』(『細胞の分子生物学 第2版』 p618) |
|
この場合、ミカンを上に放り投げたあとに何もしなければ、基本的にエネルギーは保存され続けるでしょう。
すなわち、(ATPの化学エネルギーを利用した筋肉の収縮によって仕事されて)運動エネルギーを獲得したミカンは、(運動中、空気の抵抗(摩擦)によってエネルギーを散逸し続けますが)基本的には、力学的エネルギー保存則を満たしながら(重力ポテンシャルエネルギーU+運動エネルギーKを一定とさせながら)運動を続けます。そして、地面に落下する直前に持っていた運動エネルギーは、最終的には、すべて「ミカンを変形するための仕事、音や熱…」に変換されます。(骨格筋の運動に伴って放出された熱も含めて)あらゆる散逸したエネルギーを考え合わせれば、エネルギーの合計は一定となり、(基本的には)エネルギーが保存され続けているでしょう。
(なお、厳密には、この場合も、ミカンの運動エネルギーの一部が消滅している可能性は残されています。
例えば、空気抵抗の摩擦力が、負の仕事として働く結果、(すべてが熱エネルギーとはならずに)一部のエネルギーを消滅してしまう可能性があります)
しかし、ミカンを上に放り投げた位置の近辺で、その落下するミカンを手で優しくキャッチする場合(ミカンに対して負の仕事をする場合)を考えてみましょう。
下に落ちてくるミカンが持っている運動エネルギーは、上に投げるときにミカンに蓄えられる運動エネルギーとほぼ等しいはずです。
(なお、厳密には、ミカンの運動中、空気の抵抗(摩擦)によって、一部のエネルギーが散逸します)
手でキャッチする場合にも、ATPが蓄える化学エネルギーは、一部(50%〜70%、使えるエネルギー、キブズの自由エネルギーΔG)は、(負の)仕事に変換され、一部(50%〜30%)は、熱エネルギー(使えないエネルギー)として捨てられます。
この手でキャッチする過程において、「(ATPのもつ化学エネルギーから)変換された(負の)仕事の大部分」と「落下してくるミカンの運動エネルギーの大部分」はお互いに打ち消し合って消滅します。
(厳密には、負の仕事の一部とミカンの運動エネルギーの一部は、手でキャッチする際に、音、熱… などによって散逸します)
より厳密にするため、式を使って示しましょう。
ミカンを上に放り投げる際に、骨格筋がミカンに加える仕事(ミカンにとって“正の仕事”に相当)を W骨格筋(放)[J] とする。 ミカンを上に放り投げるため骨格筋が運動をする際に、骨格筋が熱として浪費したエネルギーを Q骨格筋(放)[J]とします。
この際に消費されたATPの化学エネルギーを、EATP(放)[J]、空気等の摩擦によって奪われるエネルギーをQ摩擦熱(放)[J]とすれば、
EATP(放)= W骨格筋(放) + Q骨格筋(放) + Q摩擦熱(放)[J] ・・・(6-3.1)
となります。
放り投げられたミカンが、放物線を描き、落下する際、空気の摩擦熱として奪われるエネルギーをQ空気摩擦熱[J]とすると、キャッチされる直前のミカンが持つ運動エネルギーKミカン(受)は、
Kミカン(受) =W骨格筋(放) − Q空気摩擦熱[J] ・・・(6-3.2) となります
ミカンをキャッチする際に骨格筋がミカンに加える仕事(ミカンにとっては“負の仕事”に相当)を W骨格筋(受)[J]とします。ミカンをキャッチするため骨格筋が運動をする際に、骨格筋が熱として浪費したエネルギーを Q骨格筋(受)[J]とします。
この際に消費されたATPの化学エネルギーをEATP受[J]、骨格筋が熱として浪費してエネルギーをQ骨格筋(受)、運動する手から空気の摩擦や音等によって散逸するエネルギーをQ摩擦熱(受)[J]とすれば、
EATP(受)= W骨格筋(受) + Q骨格筋(受) + Q運動摩擦(受)[J] ・・・(6-3.3)
となります。
ミカンをキャッチする際に生じる、ミカンが持っている運動エネルギーから音、摩擦…として散逸する熱をQ音・摩擦擦(受)とすると、
Kミカン(受) =W骨格筋(受) + Q音・摩擦擦(受)[J] ・・・(6-3.4)
となります。
以上の過程で、散逸したエネルギーの総和は、E散逸=Q骨格筋(放) + Q摩擦熱(放) + Q空気摩擦熱+ Q骨格筋(受) + Q運動摩擦(受) + Q音・摩擦擦(受)[J] ・・・(6-3.5)
です。
ミカンの運動エネルギーから消滅した運動エネルギーX運動エネルギー[J]とすると、
Kミカン(受) =X運動エネルギー+Q音・摩擦擦(受)[J] ・・・(6-3.6) となります。
消滅した手による負の仕事(落下するミカンの運動方向と逆向きに働き、落下するミカンの運動エネルギーを減少させるような仕事)の大きさをX負の仕事[J]とすると、
X負の仕事[J]=W骨格筋(受)[J] ・・・(6-3.7)となります。
すべての消失したエネルギーX[J]=X運動エネルギー+X負の仕事[J]は、次のように求まります。
すべての消失したエネルギーX[J]
=X運動エネルギー+X負の仕事[J]
=(Kミカン(受)−Q音・摩擦擦(受))+W骨格筋(受)[J] ((6-3.6)を使用)
=(W骨格筋(放) − Q空気摩擦熱[J]−Q音・摩擦擦(受))+ W骨格筋(受)[J] ((6-3.2)を使用)
=(W骨格筋(放) − Q空気摩擦熱[J])+ (EATP(受)− Q骨格筋(受) − Q運動摩擦(受))[J]
((6-3.3)を使用)
=(EATP(放)− Q骨格筋(放) − Q摩擦熱(放) − Q空気摩擦熱) + (EATP(受)− Q骨格筋(受) − Q運動摩擦(受))[J] ((6-3.1)を使用)
= (EATP(放)+EATP(受)) −E散逸[J] ((6-3.5)を使用)
この式は、骨格筋の運動(放り上げる&受け止める)を引き起こすATPの化学エネルギーから、熱として散逸したすべてのエネルギーを除いた部分が、完全に消滅することを意味しています。
(なお、このE消滅[J]の値が正であることは、容易に確認できます)
すなわち、この式は、「手でキャッチすることによって、ミカンは、結局、元の状態に戻っていても、散逸エネルギー以外のエネルギーが減っている」ことを意味しています。
なぜなら、手や腕(骨格筋)の運動にともなって、ATPの化学エネルギーが減少しており(消費されており)、
「減少した(消費された)ATPの化学エネルギー」>「熱、空気との摩擦、音などの、あらゆる散逸するエネルギー」となっているからです。
ATPの化学エネルギーの起源は、そもそも、太陽光のエネルギー(太陽からの熱放射(0.1〜100μmの波長の電磁波)のエネルギー)でした。
その太陽から得たエネルギーの一部は、熱とはならずに、完全に消滅するのです。
つまり、ミカンを上に放り上げて再びキャッチする過程で、熱、空気との摩擦、音などの、あらゆる散逸するエネルギーを考慮しても、部分的には、エネルギーが完全に消滅するのです。
すなわち、「ミカン、地球、人、空気」を含む「孤立系」において、エネルギーが減少しているのです。
このことは、この「ミカン、地球、人、空気」を含む「孤立系」において、エネルギー保存則は成立し続けていないことを意味しています。
※なお、「ミカン、地球、空気」を“孤立系”と見なし、「人」がミカンに与える仕事を外力とみなせば、熱力学第一法則が成立し続けていると言えます。
※似たような系として、「その場でジャンプして静かに着地する(なわとびする)」、「フライパンのホットケーキをひっくりかえす」、「ジャグリングする」、「踏み台昇降を続ける」、「綱引きで引き分ける」、「同じ位置関係を保ちながら、おしくらまんじゅうを続ける」、「荷物を持ちながら立った姿勢を保つ」… も挙げられます。
|
《例3》(人体(骨格筋…)以外で)摩擦等による熱の散逸が一切生じないという条件で、無重力の宇宙船の中で、m[kg]のメロンをキャッチボールする場面
例えば、「(人体(骨格筋…)以外で)摩擦熱を含めて熱の散逸が一切生じないという条件で、無重力の宇宙船の中で、m[kg]のメロンをキャッチボールする」だけでも、一部のエネルギーが消滅します。
すなわち、「人、メロン、宇宙船」を含む孤立系を考えると、この孤立系の中であっても、一部のエネルギーが消滅します。
二人の宇宙飛行士、AとBは宇宙服を着ており、a[m]離れた宇宙船の座席に固定されて座っています。
この二人がm[kg]のメロンをキャチボールします。
宇宙飛行士Aの骨格筋によるW[J]の正の仕事により、質量m[kg]のメロンをv1[m/s]の速さで投げます。
すると、メロンは運動エネルギーmv12/2[J](=W[J])を獲得したまま等速直線運動をしての宇宙飛行士Bへと向かいます。
(同時に、作用反作用の法則により「宇宙船と宇宙飛行士B」も等しい大きさの運動量を獲得します。すなわちち、「宇宙船と宇宙飛行士A&B」の質量をM[kg]、その速さをv2[m/s]とするとmv1=Mv2[kg・m/s]です。それにともなって「宇宙船と宇宙飛行士A&B」は、運動エネルギーMv22/2(=Mv12(m/M)2/2)[J]を獲得します)
そのメロンを宇宙飛行士Bがキャッチします。
メロンは最終的にBの手の中で静止する過程で運動量が互いに打ち消し合うので、メロンの運動量が再び0[kg・m/s]となると同時に、「宇宙船と宇宙飛行士A&B」の運動量も再び0[kg・m/s]となります。
速さが0[m/s]となると同時に、運動エネルギーもそれぞれ0[J]となります。
人体(骨格筋…)以外で)摩擦熱を含めて熱の散逸が一切生じないという条件であるのに、メロンが持っていたmv12/2[J](=W[J])の運動エネルギー、および、「宇宙船と宇宙飛行士B」が持っていた運動エネルギーMv22/2(=Mv12(m/M)2/2)[J]は、どこへ行ってしまったのでしょうか?
それは、やはり、やはり、メロンの運動エネルギーは、すべてBの骨格筋による“負の仕事”によって消滅し、「宇宙船と宇宙飛行士B」が持っていた運動エネルギーは、メロンによる“負の仕事”によって消滅したのです。
宇宙船という孤立系の中で、このキャッチボールを繰り返すと、二人の宇宙飛行士のATPという化学エネルギーが減り続けることになります。(そして、人体(骨格筋…)から熱エネルギーが散逸するだけです)
この思考実験でわかることは、「(人体(骨格筋…)以外で)摩擦熱を含めて熱の散逸が一切生じないという条件でも、キャッチボールが成立する(運動エネルギーの消滅が実現する)」ということです。そして、「剛体の運動エネルギーは、最終的にすべてが熱エネルギーとして散逸するとは限らない」ということです。
つまり、剛体の運動方向に逆向きに、力(仕事)が加えられることで、運動エネルギーの一部が消滅しうるのです。
※似た系として、「地上で、ふつうに野球のボールのキャッチボールする」、「カートを転がすキャッチボールをする」、「ブランコの触れ幅を力を加えて増幅した後、ブランコの触れ幅を力を加えて減らしていく」… も挙げられます。「空気抵抗、音…」で熱エネルギーとして散逸する部分も確かに存在するでしょうが、一部は、完全に消滅しているはずです。
|
このような例から、たとえ孤立系の中であっても、エネルギーが完全に消滅しうることがわかります。
孤立系の中であっても、ある剛体の運動エネルギーを打ち消すような“負の仕事”が少しでも存在すれば、一部のエネルギーは消滅するのです。
他にも、「孤立系」の中で── 例えば、「反復横跳びをする。手を振る。走って往復する(シャトルランをする)。…」ということがあると、運動エネルギーのすべてが熱エネルギーとして散逸するわけではなく、ある運動エネルギーとそれに対する“負の仕事”の作用によって一部のエネルギーは完全に消滅するのです。
それでは、「走っている自転車をブレーキで止める場面」、「走っている(ハイブリッドでない)自動車をブレーキで止める場面」、「カーリングが、氷の上で少しずつスピードを落とし静止する場面」は、どうでしょうか?
いずれも摩擦力だけによって減速していますので、いかにも運動エネルギーが、すべて熱エネルギーとして散逸しているように見えます。
果たして、本当にすべての運動エネルギーが熱エネルギーとして散逸しているのでしょうか?
“摩擦力”による“負の仕事”は特別であり、負の仕事による運動エネルギーの消滅は一切存在せず、すべての運動エネルギーは熱エネルギーとして散逸できるのでしょうか?
手足の力による“負の仕事”と、“摩擦力”による“負の仕事”は、まったく別物なのでしょうか?
そんなことはないはずです。
“摩擦力”と言えども、運動と逆向きに働く力の一種であって“負の仕事”をする以上、運動エネルギーの一部は、完全に消滅させていると考えるのが自然です。
理論上、摩擦力という負の仕事によっても運動エネルギーの一部が消滅しうる理由が簡単に見つけられます。
例えば、主要な摩擦である「滑り摩擦」は、「凝着→剪断→凝着→剪断…」の繰り返しによって生じています。
(参考 『トライボロジ』 松原清 産業図書株式会社 p.33
『図解 トライボロジー』 村木正芳 日刊工業新聞社 p.39)
「剪断」の際に熱エネルギーが散逸しうる一方で、「凝着」している間は、熱エネルギーが散逸せず、負の仕事によって、エネルギーが消滅すると考えられます。
よって、「滑り摩擦」が生じている間に(特に「凝着」している間を中心として)一部の運動エネルギーが、熱エネルギーとして散逸せずに消滅しているはずであることが予想されます。
|
以上の3つのエネルギー保存則が見直されるべき理由は、互いに支持し合っています。
1.量子物理学は、エネルギー保存則を破って生じる“仮想粒子”を考慮している。
2.素スピノル物理学パラダイムは、重力子や光子の生成過程が、エネルギーの生成過程であることを示している。
3.「熱力学第一法則」自身が、たとえ孤立系の中であっても、エネルギーが100%消滅しうることを示している。
|
なぜなら、いずれも、エネルギーが生成する一方でもなければ、消滅する一方でもないことになっているからです。
(1は、エネルギーの生成と消滅の両方を含んでいます。
2と3は、両者がそろうことで、エネルギーの生成と消滅の両方を含むことになります)
もし、生成するだけで、消滅しないならば、エネルギーが増えすぎて、自然(nature)から乖離してしまいます。
もし、消滅するだけで、生成しないのであれば、エネルギーが減りすぎて、自然(nature)から乖離してしまいます。
つまり、生成と消滅の両者がそろっているおかげで自然(nature)と調和することになるので、3つのエネルギー保存則が見直されるべき理由は、いずれも互いに支持し合っていることになるのです。
「ジュール氏による羽根車の実験」が確かめたことは、「運動エネルギーは、すべて熱エネルギーとして散逸しうる」ことでした。
|
ジュール氏による羽根車の実験とは、『おもりが持っている力学的エネルギー(位置エネルギー)を使って、水中の羽根車を回転させ(位置エネルギーを運動エネルギーに変換して)、その後の羽車の運動エネルギーの消失にともなう水温の変化を観察する』というものでした。人間社会にとって偉大な実験であり、ゆるぎない成果の一つです。
その事情は、次の記述から読み取れます。
『〜摩擦力が働く場合には摩擦力のした負の仕事の分だけ力学エネルギーは減少する。減少した力学的エネルギーは熱になる。発生した熱の量と減少した力学的エネルギーの量が比例することがジュールJouleによって1943年に実験で確かめられ、熱もエネルギーのひとつの形態であることがわかった。摩擦力のある場合も1カロリー(cal)を4.2Jとすると、
『力学的エネルギーと熱エネルギーの和は保存する.』
ことがわかった』
(『物理学通論 I 』 原康夫 学術図書出版社 p91 下線は筆者によります) |
|
|
この実験は、エネルギー保存則が成立するのなら、当然、成り立つ必要条件を満たしていました。
しかし、この実験がどんなに成功しても、「運動エネルギーのすべてが熱エネルギーとして散逸しない系」(一部が完全に消滅する系)も存在しうる以上、原理的に「エネルギー保存則」を証明したことにならないのです。(証明したと思い込むことは、後件肯定の誤謬なのでした)
「運動エネルギーのすべてが熱エネルギーとして散逸しない系」(一部が完全に消滅する系)とは、まさに「負の仕事による剛体の運動エネルギーの消滅」を含むような系です。
したがって、適用条件を考慮したエネルギー保存則は、次のようになります。
『力学的エネルギーと熱エネルギーの和は保存する.
ただし、それは、力学的エネルギーの負の仕事による消滅が一切ない場合に限る.』
そもそも、ジュール氏は、「エネルギーが保存するはずだ」(「エネルギーが不滅であるはずだ」)と深く信じていました。次のジュール氏自身の言葉は、それを裏付けていると思います。
|
『それを用いて私は、約770ポンドを一フィートの高さまで持ち上げることのできる機械的力(フォース)から、水一ポンド当り一度の熱を得た。この結果は、われわれの以前の結論を非常に強く確証するものと認められるであろう。私はただちに、こうした実験を繰り返したり発展させたりするであろう。自然界の重要な諸力(グランド・エイジェンツ)は、創造者の命令により不滅であること、そしてまた機械的 力(フォース)が消費される時にはいつでもそれが厳密に等しい量の熱が得られる、ということを得心しているからである』(『科学の名著 第II期3 近代熱学論集』 p.366 ジュール氏の『磁電気の発熱作用について、および熱の仕事当量について』という論文の補遺の言葉) ( )は、ルビでした。下線は、筆者によります。
|
※『創造者の命令により不滅であること』という記述は、ジュール氏が、「エネルギーが成立するはずだ」(「エネルギーが不滅であるはずだ」)という認識が強い信念であったことを示しています。
※また、この記述は、ジュール氏が、実験結果を「エネルギーが成立するはずだ」(「エネルギーが不滅であるはずだ」)という信念を『非常に強く確証するもの』と見なしていることがわかります。
さらには、その後の新たな実験(有名な羽根車の実験を含む)をする前から、実質的に「エネルギーが成立するはずだ」(「エネルギーが不滅であるはずだ」)という信念を持っていたことを示しています。
|
実質的に「エネルギーが保存するはずだ」(「エネルギーが不滅であるはずだ」)という強い信念こそが、ジュール氏を、羽根車による新たなジュール氏の仕事当量の実験に駆り立てたと考えられます。
ジュール氏は、「エネルギーの保存」(エネルギーの不滅)を支持するような実験をデザインして、その結果を「エネルギーの保存」(エネルギーの不滅)の証拠(『確証』)であると解釈しました。
しかし、実際は、それらのジュール氏の実験結果は、「エネルギーの保存」(エネルギーの不滅)の証明にはなっていないのでした。(証明と見なすことは、やはり、後件肯定の誤謬だったのでした)
すなわち、「運動エネルギーは、すべて熱エネルギーとして散逸しうる」ことは、「エネルギーの保存」(エネルギーの不滅)の必要条件に過ぎないのでした。
さらには、次の記述から(「エネルギー保存則」の)多くの発見者が、先に「何かが保存するはずだ」という信念を持っていたことがわかります。
|
『12人の同時発見者たちは、保存の原理を重要な形で使った最初の人たちではなかった。長年にわたって科学者は何らかの保存の原理に慣れ親しんでいて、それはほとんど直観とでも言えるものだった。理論家は、破壊もされず生成もしない量の発見を、自分たちの最大の偉業として挙げていた。熱素理論の支持者たちは、熱は保存されると仮定していた。18世紀後半にはアントワーヌ=ローラン=ラヴォアジエらが、化学反応において質量が保存されることを証明していた。密閉容器内で化学反応が進行すれば、全体で質量は変化しない。
転換過程を研究する理論家も、当然ながら何らかの保存則をもとに理論を構築しようとした。だが、保存原理を導き出す場合には必ずそうなのだが、入り口からある難しい問題が課せられた。保存されるのはどんな量か? 実はこの問題に対して役に立つ答えを出すには、その保存則そのものに関する知識がなれば不可能に近かった。というのも、その保存量──最終的にエネルギーと特定される──の持つ顕著な特徴は、何よりもそれが保存されることだからだ。保存されるという性質を確かめる上で、質量のように直接観測する術はない。実際に見つかるまで完全には定義できないものを探していたことになる』
(『物理学天才列伝』 p.105 講談社ブルーバックス ウィリアム・H・クロッパー著 水谷淳訳 下線は、筆者によります)
|
※この記述から、「エネルギー保存則」は、自然(nature)の観察から発見されたものではなく、「何かが保存されるはずだ」という信念が先にあって、そこから、頭の中で生み出されたものであることがわかります。
|
すでに挙げた次の記述からトムソン氏も同様の信念を持っていたことがわかります。
『トムソンは公刊された論文の中では神学的な議論を用いていないが、1852年の論文では、「神のみが力学的エネルギーを誕生させたり消滅させたりすることができる、というのはきわめて確実なことであるから」、散逸されたエネルギーが消滅するはずがなくて、転換されるだけである、と述べている。』
(『物理学の誕生─エネルギー・力・物質の概念の発達史─』 p.63 P.M.ハーマン著 杉山滋郎訳 朝倉書店) 下線は筆者によります。 |
少なくとも以上の記述から、「エネルギー保存則」が生み出された当時&育まれた当時、ジュールを氏含めて、多くの方々が「何かが保存するはずだ」という信念をもっていたことがわかります。
多くの方々が「何かが保存するはずだ」という信念を共有していたことは、『力学的エネルギーが減少(消滅)するように見える現象は、すべて「熱エネルギーとしての散逸」にもとづいているということにしましょう。そうすれば、エネルギーが保存することになりますから』というような総意(合意、コンセンサス…)が生まれる土壌になったはずです。
そのことは、エネルギー保存則が、科学者たちの「何かが保存するはずだ」という信念に根ざした総意(合意、コンセンサス…)の所産に過ぎないことを意味しています。
※『エネルギー保存則が、科学者たちの「何かが保存するはずだ」という信念に根ざした総意(合意、コンセンサス…)の所産に過ぎないこと』は、「エネルギー保存の法則」についての、次のような“歯切れの悪い記述”からも読み取れます。
|
『この法則は、他の科学の法則と同様、多くの観測と試行から導かれた結論である。検証は十分に広い範囲にわたって尽くされており、一般に受け入れられている。例外は見つかっておらず、どのような提案であれ、この法則に従わないものは疑わしいとされる。』
(『知っておきたい熱力学の法則と賢いエネルギーの選択』 リチャード・S・スタイン ジョセフ・パワーズ著 安倍明廣 p.9-10(第1章) NTS)下線は、筆者によります。
|
なぜ、これほどまで「エネルギーが保存するはずだ」という思い込みが強かったのでしょうか?
なぜ、エネルギー保存則が成立しなければならなかったのでしょうか?
その理由の1つは、『理論家は、破壊もされず生成もしない量の発見を、自分たちの最大の偉業として挙げていた』からだろうと思います。すなわち、質量保存の法則を含む過去の成功体験にしばられたからだと思います。
もう1つの理由は、『創造者の命令により不滅であること』や『神のみが力学的エネルギーを誕生させたり消滅させたりすることができる』のように、宗教にしばられたからだと思います。
他にも理由があるのかもしれません。
いずれにせよ、「エネルギーが保存するはずだ」「エネルギーは消滅しないはずだ」という信念(思い込み)は、「地球の周囲を太陽が回っているはずだ」という信念(思い込み)のように、自然(nature)から乖離しているのは明らかです。
そのことは、例えば、「リンゴの木から落下するリンゴを優しくキャッチして、地面におろす」というたったこれだけの系でエネルギーの消滅を実証できることが明確に示しています。
※ガリレオは、「地球の周囲を太陽が回っているはずだ」という信念(思い込み)を解消し、「太陽の周囲を地球が回っている」という地動説が正しいと認識してもらうために、天体観測(他の惑星の観測)を含め、さまざまな努力を重ねたのでした。
一方、「エネルギーが保存するはずだ」「エネルギーは消滅しない」という信念(思い込み)を解消し、「エネルギーはときに消滅する」という説明が正しいと認識するためには、だれもが簡単にできる、さまざまな実証実験で事足りるようです。
エネルギーが消滅する例は、探そうと思えばいくらでも見つけられるのです。
「エネルギーが消滅するはずだ」という確信を持って、それを証明する実験をデザインすれば、いくらでも「エネルギーの消滅」を証明する実験や観察が見つかるのです。
摩擦力以外の負の仕事によるエネルギー消滅を厳密に実証できる系については、すでに挙げた通り、簡単にたくさん見つかります。(しかも、熱力学の第一法則(ΔU=Q+W)に従っていますので、理論上も問題ないのでした)
それでは、摩擦力という負の仕事によってウ運動エネルギーの一部が消滅を厳密に実証できる系は、見つけられるでしょうか?
例えば、次のような系が考えられます。
例えば、自動車(≠ハイブリッド)のブレーキによる停車の場面を考えてみましょう。
まず、時速36kmで走る1トン(1000[kg])の乗用車の運動エネルギーを計算してみると次のようになります。
時速36kmの速さは、秒速10m(=10[m/s])です。よって、この乗用車の運動エネルギーK[J]は、mv2/2[J]より、K=1000×102/2=0.5×105[J]と求まります。
1[cal]を約4.18[J]として計算すると、およそ11900[cal]に相当します。
これは、およそ119[g]の0℃の水を100℃まで加熱して沸騰させるのに必要なカロリーに相当します。
鉄の比熱は、水の比熱の約1/10倍です。したがって、この11900[cal]は、119[g]の鉄を1000℃まで加熱するのに必要なカロリーに相当します。
もし、本当に『発生した熱の量と減少した力学的エネルギーの量が等しい』のならば、119[g]の鉄を0℃から1000℃まで加熱させるのに必要なカロリーに相当する運動エネルギー0.5×105[J]を、時速36kmで走る1tの乗用車は、停車するごとに、すべて熱エネルギーとして散逸していることになります。
時速72kmの場合であったら、およそ119[g]の0℃の鉄を4000℃まで加熱させることのできるエネルギーに相当する運動エネルギー2×105[J]を、停車するたびに、すべて熱エネルギーとして散逸していることになります。
時速72kmで走る10tのトラックやバスの場合であったら、119[g]の鉄を40000℃に加熱させるエネルギー相当する運動エネルギー2×106[J]を、停車するたびに、すべて熱エネルギーとして散逸していることになります。
…
本当にそれほどの大きなエネルギーをすべて熱エネルギーとして散逸しているのでしょうか?
自動車のブレーキ(ブレーキディスク)は、それほどの熱量に耐えうるものなのでしょうか?
例えば、ブレーキの部品(ブレーキディスク)が鋼鉄(大部分は鉄)でできているものとし、鉄の融点が1540℃であることを考慮に入れれば──
『時速72kmで走る10tのトラックが、119[g]の鉄を40000℃に加熱させるエネルギー相当する運動エネルギー2×106[J]を、停車するたびに、すべて熱エネルギーとして散逸していれば、鋼鉄(大部分は鉄)でできているブレーキディスクの一部が溶けて焼き付いてしまうはずである。しかし、実際にそのようなブレーキの故障は起きない。したがって、トラックの運動エネルギーのすべてが熱エネルギーとして散逸していることはありえない。
つまり、この系によって、トラックの運動エネルギーの一部はブレーキの負の仕事によって消滅していることが実証されたことになるのである』
のように結論を導くことができるかもしれません。
もちろん、ブレーキの部品(ブレーキディスク)の一部が溶けてしまわないほど、融点が高い素材でできていたり、“放熱効率”が良かったり… という可能性もあるかもしれません。(詳細な検討は、今後の課題です)
しかし、さまざまな可能性を考慮に入れながら「摩擦力による負の仕事が運動エネルギーの一部を完全に消滅させている」と考えざるをえないような実験系をデザインできれば、「摩擦力による負の仕事が運動エネルギーの一部を完全に消滅させている」ことを実証できるだろうと予想されます。
|
このように、摩擦力という負の仕事によっても運動エネルギーの一部が消滅しうることを確かめる実験&観測は、とても重要なものの1つだと思います。
なぜなら、もし確かめられたならば、これまで、「摩擦力による熱エネルギーの散逸」として片付けてきた、さまざまな現象の背後に、(熱エネルギーとして散逸のみならず)「運動エネルギーの負の仕事による消滅」もともなっていたと理解されることなるので、エネルギー問題対策のみならず、気候変動対策にも影響するはずだからです。
|
摩擦力という負の仕事によっても運動エネルギーの一部が消滅しうることが確かめられたのなら、負の仕事による運動エネルギーの消滅は、当然、人や動物が関わらないさまざまな自然現象においても起こりうることになります。
例えば、「風によって木の枝や葉っぱが不規則にゆれる、波によって砂粒等が不規則に往復する、風向きが不規則に変わる、水流が不規則に変わる、乱流、台風…」という自然現象において部分的なエネルギーの消滅が起こりうることになります。
すなわち、このような自然現象においても、すべてのエネルギーが熱エネルギーとして散逸するのではなく、一部の運動エネルギーが「負の仕事」によって消滅することによってトータルのエネルギーが減少することになります。
以上のような「ある運動エネルギーと負の仕事(その運動方向と逆向きに働き、その運動エネルギーを減少させるような仕事)のペアは、互いに消滅する」というしくみは、『高まりすぎた“地球の温度”を下げる効果』をもたらすと考えられます。
このしくみは、それどころか、地球のエネルギーを減らし続けて早々と寒冷化させてしまうことさえも考えられます。しかし、実際は、そうなっていません。
なぜなら、少なくとも、地球は、太陽光を浴びながらエネルギーが供給され続けているからです。
太陽光としてのエネルギーの供給は、当然、『“地球の温度”を高める効果』を持っています。
したがって、先ほどの『高まりすぎた“地球の温度”を下げる効果』は、この『“地球の温度”を高める効果』と協同で、人や動物が関わらないさまざまな自然現象に影響与えていることになります。
この2つの効果は、当然、人や動物が関わらないさまざまな自然現象のみならず、人や動物が関わるさまざまな自然現象にも、直接的に&間接的に影響を与えます。
つまり、運動エネルギーと負の仕事のペアが消滅するしくみは、単に『地球の温度を下げる効果』を説明するのみならず、『(太陽光による)地球の温度を上げる効果』とペアになりながら、「(人間を含む)動物による多彩な運動を含む、さまざまなダイナミックな自然現象」、すなわち、「人間社会を含む地球上の自然(nature)が生む、あらゆるダイナミックでバラエティに富んだ運動、活動…」を支えていることになります。
|
摩擦に与らない負の仕事によるエネルギーの消滅が考慮された場合、あるいは、摩擦力による負の仕事によるエネルギーの消滅が実証された場合、それについての数式上の記述は、少しの修正ですみます。
これまで、単にすべて摩擦熱として片付けていた(解釈していた)失われる熱量Q[J]に、消滅エネルギーX[J]を加えれば、よいだけです。
トータルのエネルギーE1[J]が、摩擦等によって減り、E2[J]となったとします。
従来の物理学のパラダイムでは、その減少分を、すべて摩擦熱等の熱エネルギーQ[J]としての散逸として、処理してきました。
E1[J]=E2[J]+Q[J]
しかし、実際は、すべてが熱エネルギーとして散逸するのではなく、一部のエネルギーが消滅します。その消滅するエネルギーをX[J]とすると、次のようになります。
E1[J]=E2[J]+Q[J]+X[J]
数式上は、これだけの修正で済みます。
この数式は、 すべてのエネルギーは、最終的に、全て熱エネルギーに変化するとは限らないことを意味しています。
すなわち、「エネルギーの減少は、すべて熱エネルギーとしての散逸による」とは限らないことを意味しています。
※なお、この数式は、「熱の仕事当量」や「力学的エネルギーは、摩擦により、熱エネルギーに変化しうること」を否定するものではありません。なぜなら、この数式は、ある運動エネルギーの一部が「負の仕事」によって消滅してしまいうることを反映しているだけだからです。
現段階で、少なくともはっきりしているのは、力学的エネルギーの一部が負の仕事によって完全に消滅しうることです。
そのことは、例えば、「リンゴの木から落ちはじめたリンゴを優しく両手でキャッチして静かに地面に着地させる」だけの系で実証できることです。
たとえ孤立系の中であっても、ある剛体の運動エネルギーを打ち消すような“負の仕事”によってその運動エネルギーの一部は消滅しうるのです。
しかも、そうなりうることを、他ならぬ、熱力学第一法則がはっきり示しています。
つまり、力学的エネルギーの一部が負の仕事によって完全に消滅することは、熱力学第一法則に従っています。
しかし、このことは、エネルギー保存則には、従っていません。
力学的エネルギーの一部が負の仕事によって完全に消滅することは、「適用範囲を考慮しないエネルギー保存則」に対する反例(反証)なのです。
つまり、エネルギー保存則は適用範囲を明確にしなければならないことを、他ならぬ熱力学第一法則がはっきり示しているのです。
以上から、エネルギー保存則について、少なくとも、次の結論に至ります。
結論6-3.1 エネルギー保存則は、光子や重力子の生成過程を考慮せず、なおかつ、“運動エネルギーの負の仕事による消滅”がない限り、成立する。
この結論は、エネルギー保存則の適用範囲(成立条件)を明確にしています。
繰り返しますが、孤立系の中におけるエネルギー消滅の現象が起こりうることは、「熱力学第一法則」自身が示していることです。
つまり、「熱力学第一法則」は正しいままなのです。
しかし、その抽象的な数式の解釈に相当する、「エネルギーは、いついかなる場合でも生成も消滅しないのである」のような「適用範囲(成立条件)を考慮しないエネルギー保存則」は、明らかに自然(nature)から乖離しており、見直す必要があるのです。
※それは、E=mc2という数式の解釈に相当する、「あらゆるエネルギーは、質量である」が、明らかに自然(nature)から乖離しており、見直す必要があることと似ています。
※この説明は、「エネルギー保存則が、証明されていない経験則に過ぎないという事実」や「エネルギー保存則は、科学者の総意(合意、コンセンサス…)に過ぎなかったこと」とも調和しています。
エネルギー保存則は、「証明されていない経験法則」や「合意(コンセンサス)」に過ぎなかったはずなのに、これまで長い間、物理学の根幹を成す、普遍的&絶対的な法則として君臨してきました。
物理学者の多くの方々が、「エネルギー保存則が成立するはずだ」と信じてきました。
「エネルギー保存則」は、マイヤー、ジュール、ヘルムホルツ、クラウジウス… から一貫して信じ続けられたものでした。アインシュタインも信じ続けていました。ホーキングも信じ続けていました。
現在、ほぼすべての物理学者の方々が、ほぼ無意識レベルで、常識的に、エネルギー保存則が正しいと信じています。
高校の物理学で、だれもが、そのように学びます。 (筆者もそのように学びました)
ふつう、誰もが「エネルギー保存則」を疑おうとすることはナンセンスであると反射的に思うようになってしまっています。
ふつう、誰もが「エネルギー保存則」を疑っている理論に対して、反射的に、怪しげで非科学的であるというレッテルをはってしまい、相手にしないように(無視&軽視するように、即座に却下するように…)条件づけられています。
(つい数年前まで、筆者もそのような状態になっておりました)
しかし、「エネルギー保存則」が自然(nature)から乖離していることにはっきり気づきました。
その最大のきっかけは、「(ネーターの定理との調和している)不連続な時空」の前提を含む素スピノル物理学パラダイムの驚異的な成果の数々です。
そして、「エネルギー保存則」が自然(nature)から乖離していることを確信させてくれたのは、「エネルギー保存則は成立しないはずだ」という発想で、自然(nature)を眺めたときに見つかった多くの反例でした。
※「エネルギー保存則は成立しないはずだ」という発想で探せば見つかる反例の多さは、それほど、「エネルギー保存則は成立するはずだ」という信念が強かったことを意味していると思います。
(その反例の1つが、やはり、「高い位置にあるリンゴを優しく静かに地面に着地させる」系で、一部のエネルギーが完全に消滅することです)
やはり、そもそも、なぜ「エネルギー保存則」が信じられるようになったのかをよく調べることも大事だと思います。
例えば、(熱の仕事当量を理論計算によって導いた)マイヤーにとって、それは、まさに思弁的な信念でした。
|
『力は原因である。したがって、原因は結果に等しいという根本原理が完全に適用される。原因cが結果eを持てば、c=eであり、そのeがまた別の結果fの原因ならばe=fであり、という具合にしてc=e=f=・・・=cである。原因と結果の連鎖に置いては、等式の性質からわかるように、一つの項あるいはいくつかの項[だけ]が零になることはできない。あらゆる原因が持つこの第一の属性を、われわれは原因の不滅性と名づける。
〜 さまざまな形態をとりうること、それがあらゆる原因の第二の本質的属性である。2つの属性をまとめて、われわれはこう言う。原因は(量的に)不滅で(質的に)転換可能なものである、と。』
(『科学の名著 第II期3 近代熱学論集』 p.325-326) マイヤー氏の論文中の言葉です。太線は、傍点でした。下線は、筆者によります。
※当時の力とは、今のわれわれにとってのエネルギーに相当しています。上記は、マイヤー流のエネルギー保存則の説明に相当しています。
『活力保存の法則は原因の法則は原因の不滅性という一般法則に基づいていることが判る』
(『科学の名著 第II期3 近代熱学論集』 p.328) マイヤー氏の論文中の言葉です。下線は、筆者によります。
※なお、文中の“活力”は、現在の“運動エネルギー”に相当しています。
|
例えば、(運動エネルギーから熱エネルギーへの変換を実証した)ジュールにとって、それは、まさに宗教的な信念でした。
|
『それを用いて私は、約770ポンドを一フィートの高さまで持ち上げることのできる機械的力(フォース)から、水一ポンド当り一度の熱を得た。この結果は、われわれの以前の結論を非常に強く確証するものと認められるであろう。私はただちに、こうした実験を繰り返したり発展させたりするであろう。自然界の重要な諸力(グランド・エイジェンツ)は、創造者の命令により不滅であること、そしてまた機械的 力(フォース)が消費される時にはいつでもそれが厳密に等しい量の熱が得られる、ということを得心しているからである』(『科学の名著 第II期3 近代熱学論集』 p.366 ) ジュール氏の論文の補遺の言葉です。( )は、ルビでした。下線は、筆者によります。
|
例えば、トムソンにとっても、それは宗教的な信念でした。
『トムソンは公刊された論文の中では神学的な議論を用いていないが、1852年の論文では、「神のみが力学的エネルギーを誕生させたり消滅させたりすることができる、というのはきわめて確実なことであるから」、散逸されたエネルギーが消滅するはずがなくて、転換されるだけである、と述べている。』
(『物理学の誕生─エネルギー・力・物質の概念の発達史─』 p.63 P.M.ハーマン著 杉山滋郎訳 朝倉書店) 下線は筆者によります。 |
例えば、多くの物理学者にとって、それは、直観的な信念でした。
|
『12人の同時発見者たちは、保存の原理を重要な形で使った最初の人たちではなかった。長年にわたって科学者は何らかの保存の原理に慣れ親しんでいて、それはほとんど直観とでも言えるものだった。』
(『物理学天才列伝』 p.105 講談社ブルーバックス ウィリアム・H・クロッパー著 水谷淳訳) 下線は、筆者によります。
|
「エネルギー保存則」が現在まで信念によって支えられてきていることは、「天動説」がかつて信念によって支えられていたことと似ていると思います。
「エネルギー保存則」が現在までゆるぎない常識として君臨していることは、「天動説」がかつてゆるぎない常識として君臨していたことと似ていると思います。
「エネルギー保存則」という思い込みから目を覚ますことが現在まで困難であることは、「天動説」という思い込みから目を覚ますことがかつて困難であったことと似ていると思います。
…
信念に過ぎない「エネルギー保存則」によってもたらされていることの1つは、やはり、(コペルニクス〜ガリレオがせっかく築いた)自然(nature)との調和の探究という本来の科学が、別の営みにすり替わり続けているということです。
別の営みとは、「信念をやみくもに守りぬこうとする営み」です。
科学が「信念をやみくもに守り抜こうとする営み」にすり替わっているという問題には、根深いものがあります。
信念に過ぎなかったはずの「エネルギー保存則」が、いつしか、知らず知らずに物理学者の方々が身に付ける(基礎的な&普遍的な)常識として君臨するようになり、これを疑う考えを反射的に拒絶する(非科学のレッテルを貼って排除する)ようになったからです。
アインシュタインさえも、最後まで信じていました。(だからこそ、一般相対性理論と特殊相対性理論が矛盾し、『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかける』問題が生まれました)
ホーキングも、最後まで信じていました。(だからこそ、ホーキング放射が生み出され、ホーキング自身のかつての成果である面積増大定理と矛盾することになりました)
現在の多くの物理学者の方々も信じています。(一般相対性理論の量子化、時空の量子化が非常に困難な問題となっていることが、それを証明していると思います)
…
その常識化を支えたものが、ヘルムホルツによる、当時の物理学者たちに受け入れられやすい形での「エネルギー保存則」の定式化でした。
そして、さらには、クラウジウスによる、体系的な定式化でした。
※なお、クラウジウスとっても、「エネルギー保存則」は(抽象的な数式を構築するための前提を支える)信念であったろうと考えられます。なぜなら、できあがった抽象的な数式から「(孤立系としての)宇宙のエネルギーは一定である」という解釈を導いたからです。
※なお、ヘルムホルツやクラウジウスの定式化に先立って、ラグランジュが『解析力学』の中で力学的エネルギー保存則を導き出していたこと(参考 p.84 『科学史年表』 小山慶太著 中公新書)も、この常識化を支えたと考えられます。
これらの抽象的な数式による「エネルギー保存則」の定式化は、「エネルギー保存則」が、多くの物理学者の方々にとっての常識となることを決定的にしました。
定式化された「エネルギー保存則」は、あらゆる物理学の教科書にのりました。
アインシュタインやホーキングを含め、多くの物理学者の方々が、常識として学習する内容になりました。
そして、いつしか、従来の物理学パラダイムにおいて『最も普遍的な法則』とさえ見なされるようになりました。
ここにあるのは、いわば、「エネルギー保存則」による封印です。
この「エネルギー保存則」による封印のことを、ボーア-ハイゼンベルクの封印、マクスウェル-アインシュタインの封印に習い、なおかつ、抽象的な数式のみを重視する物理学者への影響の大きさも考慮して、「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」と呼ぶこととします。
この「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」の封印は、アインシュタインやホーキングを含む、ほとんどの科学者の方々に、「エネルギー保存則」に対する“思考停止”をもたらし続けました。
この「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」の影響は大きく、誰もが「エネルギー保存則が成立するはずだ」という前提でものを考え、誰もが自然(nature)を観察することを促しました。
それは、例えば、「木から落ちはじめたリンゴを優しくキャッチして静かに地面に着地させる」だけの過程でエネルギーの一部が完全に消滅している明白な事実を、見落とさせるほどでした。
実際は、「エネルギーが消滅するはずだ」という目で自然(nature)を見渡せば、いくらでも同様な例が見つかるのにです。
しかも、それは、熱力学の第一法則という抽象的な数式から導かれる帰結(解釈)の1つなのにです。
なぜ、これまで、こんなに単純な反例が見過ごされてきたのかといえば、やはり、誰もが、「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」によって思考停止してしまったからです。
すなわち、ほとんどだれもが「エネルギー保存則が成立するはずだ」と信じて(盲信して)、物理学をやってきたからです。
すなわち、これまで、ほとんどだれもが「エネルギー保存則が成立しないはずだ」という目で自然(nature)を見渡してこなかったからです。
そして、これまで、ほとんどだれもが「エネルギー保存則が成立しないはずだ」と疑う人を、反射的に、非科学のレッテルを貼って排除してきたからです。
そもそも、マイヤーによる熱の仕事当量を理論計算によって導いた成果は、実質的に「エネルギー保存則が成立するはずだ」(原因は不滅だ)という非科学的(思弁的な)な信念のもとで生み出されました。そして、その成果の“解釈”も、「エネルギー保存則が成立するはずだ」(原因は不滅だ)という非科学的な(思弁的な)信念を正当化しようとするものでした。(やはり、ここには、「後見肯定の誤謬」があります)
そもそも、ジュールによる熱の仕事当量を実験によって導いた成果は、実質的に「エネルギー保存則が成立するはずだ」という非科学的な(宗教的な)信念のもとに生み出されました。そして、その成果の“解釈”も、「エネルギー保存則が成立するはずだ」という非科学的な(宗教的な)信念を正当化しようとするものでした。
(やはり、ここにも、「後見肯定の誤謬」があります)
そもそも、ヘルムホルツやクラウジウスによる定式化の成果も、実質的に「エネルギー保存則が成立するはずだ」という信念を前提として生み出されました。そして、ヘルムホルツやクラウジウスによる定式化の成果の“解釈”も「エネルギー保存則が成立するはずだ」という信念を正当化しようとするものでした。
(クラウジウスによる『孤立系としての全宇宙のエネルギーは一定である』という数式の解釈は、その一例です)
アインシュタインの一般相対性理論の成果も、実質的に「エネルギー保存則が成立するはずだ」という常識的な(伝統的な)信念を受け継いで生み出されました。(ネーターの定理も、その信念を支持する根拠として活用されました)。そして、一般相対性理論の成果の“解釈”も、「エネルギー保存則が成立するはずだ」という常識的な(伝統的な)信念を正当化しようとするものでした。(その結果、“重力波がエネルギーを持ち去る”という『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかける』解釈がなされたのみならず、一般相対性理論は、「運動エネルギーが増せば質量エネルギーも増加すること」を示す特殊相対性と矛盾してしまうこととなりました)
ホーキングによるホーキング放射の理論も、実質的に「エネルギー保存則が成立するはずだ」という常識的な(伝統的な)信念を受け継いで生み出されました。(その結果、ホーキング放射は、ホーキング自身が生んだ面積増大定理との矛盾を抱えることとなりました)
多くの物理学者の方々にとって、一般相対性理論の量子化、時空の量子化が困難となったのは、「エネルギー保存則が成立するはずだ」という常識的な(伝統的な)信念を受け継いだからこそでした。
…
つまり、「エネルギー保存則」は、やはり、「エネルギー保存則が成立するはずだ」という、単なる信念に過ぎないものでした。
ところが、「エネルギー保存則」は、抽象的な数式化という「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」によって、常識(伝統)に生まれ変わりました。
その常識(伝統)は、「これこそが科学なのだ」というような従来の物理学パラダイムを根底で支える土台のひとつとして君臨し続けてきました。
しかし、もうそろそろ、「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」による思考停止を、解消すべきなのではないでしょうか?
もうそろそろ、「エネルギー保存則」という常識を、科学的に、堂々と疑うべきなのではないでしょうか?
もうそろそろ、「エネルギー保存則」への疑いに対する、反射的な排除を卒業するべきなのではないでしょうか?
「エネルギー保存則が成立しないはずだ」という前提で探すと見つかる多くの反例
(「木から落ちはじめたリンゴを優しくキャッチして静かに地面に着地させる」等)
『量子物理学において考えられている、エネルギー保存則を破って生じる仮想光子』
『素スピノル物理学パラダイムが示している、重力子や光子の生成過程がエネルギー生成過程であること』
『時空が不連続であればエネルギー保存則が成立しないことを、ネーターの定理が示していること』
『たとえ孤立系の中であってもエネルギーが消滅しうることを「熱力学第一法則」の数式自身が示していること』
「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」の弊害…
を念頭に置いて、次の文を読むと、疑うべきなのは、「適用範囲(成立条件)を考慮しないエネルギー保存則」であることがわかります。
|
『エネルギーのさまざまな形とその間の移り変わりを調べていくと、われわれは物理学の最も普遍的な法則であるエネルギーの保存則に行き着く:
エネルギーは生み出されることも失われることもない。エネルギーは1つの形から他の形へ移り変わることはできるが、エネルギーの総量は決して変わることがない』
(『物理のコンセプト エネルギー』 Paul G.Hewitt John Suchocki Leslie A.Hewitt 著 小出昭一郎監修 黒星瑩一訳 p.13 共立出版株式会社) 下線は、筆者によります
|
|
『この法則は、他の科学の法則と同様、多くの観測と試行から導かれた結論である。検証は十分に広い範囲にわたって尽くされており、一般に受け入れられている。例外は見つかっておらず、どのような提案であれ、この法則に従わないものは疑わしいとされる。』
(『知っておきたい熱力学の法則と賢いエネルギーの選択』 リチャード・S・スタイン ジョセフ・パワーズ著 安倍明廣 p.9-10(第1章) NTS) 下線は、筆者によります。
|
|
『科学の法則は、我々が自然の変化をどのように理解しているかを記述したものである。科学者は何百年もかけて科学の法則を検証して、信頼される観測者の唯の一人も法則が成立していない例を発見していないのである。もしも一つでも、法則が破れられている事例があれば、その法則は、修正されるか、捨てられるかである。従って、ほとんどの科学者が、熱力学の法則をエネルギーに関わる提起を評価する基準として採用している。もしもある提案がこれらの法則に違反するものであったら、間違っているのは提案のほうであって、法則のほうではないと判定する。』
(『知っておきたい熱力学の法則と賢いエネルギーの選択』 リチャード・S・スタイン ジョセフ・パワーズ著 安倍明廣 p.36-37(第3章) NTS) 下線は、筆者によります。
|
次のような歯切れの悪い言いまわしも、疑わしさを助長していると思います。
『一般に受け入れられている』
『この法則に従わないものは疑わしいとされる。』
『信頼される観測者の唯の一人も法則が成立していない例を発見していないのである』
『ほとんどの科学者〜 判定する』
エネルギーの保存則の証明は(後件肯定の誤謬に至らざるをえないので)原理的に不可能であるはずなのに「十分な検証」を持ち出している点も、疑わしさを助長していると思います。
『検証は十分に広い範囲にわたって尽くされており』
『エネルギー保存則への疑いは、何を言っても無駄だよ。内容を問わず非科学のレッテルをはられるたけだよ』と言わんばかりの排他性や、数にものを言わせている点も、疑わしさを助長していると思います
『例外は見つかっておらず、どのような提案であれ、この法則に従わないものは疑わしいとされる』
『ほとんどの科学者が、熱力学の法則をエネルギーに関わる提起を評価する基準として採用している』
ここにあるのは、もはや、自然(nature)との調和の探究ではありません。
ここでは、科学が、自然(nature)との調和の探究ではない別の営みにすり替わっています。
このままでは、物理学が、科学が、衰退し、絶滅するおそれがあります。
どう言おうとも、エネルギー保存則が、本来「証明されたわけでない経験法則に過ぎず、信念が起源である合意(コンセンサス)に過ぎない」という事実はゆらぎません。
「エネルギー保存則が成立しないはずだ」という前提で探すと、さまざまな反例が見つかるという事実もゆらぎません。
運動エネルギーが負の仕事によって消滅することを簡単な系で実証できることもゆらぎません。
例えば、高い位置にあるリンゴを静かに地面に下ろすという過程でエネルギーの消滅を実証できることもゆらぎません。
運動エネルギーの負の仕事による消滅が実在しうることを熱力学の第一法則から導けるという事実もゆらぎません。
時空が不連続であればエネルギー保存則が成立しないことを、ネーターの定理が示している事実もゆらぎません。
量子物理学において、エネルギー保存則を破って生成している仮想光子を考えている事実もゆらぎません。
…
それらのことに謙虚に向き合い続けることが、本来、科学者がするべきことなのではないのでしょうか?
やはり、あらゆる科学スタイルの自然(nature)と調和する部分については、尊重され続けるべきです。
素スピノル熱力学は、従来の熱力学パラダイムが生んできた偉大な成果の自然(nature)と調和している部分を包含します。
(したがって、やはり、「エネルギー保存則」に、やみくもに非科学のレッテルを張るのは正しくありません)
熱力学第一法則自体は、(「運動エネルギーの負の仕事による消滅」や「重力子や光子の生成過程」等を考慮しない限り)自然(nature)と調和しています。
しかし、残念ながら、熱力学第一法則という抽象的な数式の解釈の1つである、「エネルギーは、いついかなる場合でも生成も消滅しないのである」のような適用範囲を考慮しないエネルギー保存則は、自然(nature)から乖離しています。
よって、「適用範囲(適用条件)を考慮しないエネルギー保存則」については、自然(nature)から乖離しているという判断を下し、非科学である(単なる信念に過ぎない)と見なさなければならなりません。
エネルギー保存則は、ある条件を満たしたときに限って、成立するのです。
エネルギー保存則は、それとは別の条件を満たしたときは、成立しないのです。
エネルギーは、ときに生成し、ときに消滅するのです。
例えば、エネルギーの生成は、重力子や光子の生成時に起きています。
※重力子や光子の生成過程は、まさに、エネルギーの生成過程です。
例えば、エネルギーの消滅は、ある運動エネルギーに対する負の仕事によって生じています。
※“負の仕事”によって、運動エネルギーの一部が完全に消滅するのです。
よって、すべてのエネルギーが“熱エネルギー”として散逸するとは限らないのでした。
例えば、仮想光子は、生成と消滅を繰り返しながら、エネルギーの生成と消滅を繰り返しています。
※仮想光子を含む仮想粒子は、エネルギー保存則を破って一時的に生成するのでした。
つまり、エネルギーは、増えたり、減ったりを繰り返しているのです。
例えば、「孤立系としての全宇宙」の中でも、エネルギーは、増えたり、減ったりを繰り返しながら、刻々と変化し続けているのです。
エネルギーは、生成&消滅を繰り返しながら、多様でダイナミックな自然(nature)の成立を根底で支えているのです。
すなわち、「重力子や光子の生成過程にともなうエネルギーの生成」や「運動エネルギーに対する負の仕事によるエネルギーの消滅」、および「仮想光子の生成と消滅」などが、この自然(nature)におけるエネルギー現象の多様性を根底で支えているのです。
|