研究論文
『プランクスケールの自然についての幾何的モデルの探究が生む驚異的な成果』
|
成果1
素スピノル重力理論&素スピノル電磁気力理論
|
|
14《連星系パルサーと重力波について》
連星パルサーの研究成果に関連して、次のような記述があります。
『伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいることが発見され、この重力波の存在が間接的に示された』
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』 J.M.ワイズバーグ、J.H.テイラー、L.A.ファウラー)
|
| 『アインシュタインは、1915年に発表した一般対性理論の中で加速運動している物体は、重力波の形でエネルギーを放出すると予言した』 (『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』) |
これらの「間接的な重力波の観測」も「アインシュタインの予言」も、素スピノル物理学パラダイムによる説明、すなわち、『(重力波は「放出される重力子数の変化」として創発する(→下記説明))』という説明や『質量を持つ物体が加速運動する(=物質の運動エネルギーが増す)ことによって、重力子の放出源として働き続ける能力が増す(→上記説明)』という説明と、おおよそ調和しています。
しかし、次の記述は、素スピノル物理学パラダイムの説明とは、180度逆です。
『連星系パルサーからの重力放射に必要なエネルギーの源は、軌道運動エネルギーである。だから、重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら、軌道エネルギーはしだいに減少し、このために、パルサーとその伴星が渦巻き状に互いに近づきあい、軌道周期も減少するはずである』
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』) 下線は、筆者によります。 |
すなわち、この従来の物理学パラダイムにおける“重力波がエネルギーを持ち去る”という説明は、素スピノル物理学パラダイムの説明とは、180度逆です。
なぜなら、素スピノル物理学パラダイムによると、「重力波は“放出される重力子数の変化”であり、重力子の生成過程はエネルギーの生成過程である」ので、“重力波(=「放出される重力子数の変化」)がエネルギーを持ち去らない”のは明白だからです。
※なお、少なくとも次の記述からアインシュタイン自身も“重力波のエネルギーを含めたエネルギー保存則が成り立つこと”を前提として、“重力波がエネルギーを持ち去る”と考えていたことがわかります。
『重力波を放出している物質系は、エネルギーを外に向かって放出するはずである。したがってエネルギー保存則を考えると、この反作用として物質系の運動は減衰することとなる』
(『アインシュタイン選集2』(p.180)) 下線は筆者によります。 |
アインシュタインは、一般相対性理論を、エネルギー保存則(by連続な時空)を前提にして作り上げたので、当然と言えば、当然のことです。
両者を比較すると次のようになります。
|
従来の物理学パラダイム
(『連星系パルサーからの重力波
サイエンス1981年12月号』…)
|
素スピノル物理学パラダイム
|
|
連星系パルサーから放出する
重力波(重力子の総和)による
“エネルギーの持ち去り”
|
ある
|
ない
|
|
重力波
(重力子の総和)
|
エネルギー保存則に従う
|
エネルギー生成過程の所産
|
|
重力波のエネルギーを
含めたエネルギー保存則
|
成り立つ
|
成り立たない
|
|
力学的エネルギーの保存
(運動エネルギーK[J]+
重力ポテンシャルエネルギーU[J]
が一定)
|
成り立たない
(−ΔU/2[J]分が、重力波として
エネルギーを持ち去られる)
|
成り立たない
(−ΔU/2[J]分が、連星の周囲に存在する
空気との摩擦抵抗によって、
エネルギーを持ち去られる。
運動エネルギーの一部が、
熱エネルギーとして散逸する)
|
|
重力と遠心力の関係
|
重力=遠心力
(ゆえに、GMm/r2=mv2/r[N]より、常に
−U/2=K[J]かつ、−ΔU/2=ΔK[J])
|
重力=遠心力
(ゆえに、GMm/r2=mv2/r[N]より、常に
−U/2=K[J]かつ、−ΔU/2=ΔK[J])
|
|
『P =(32GΩ6/5c5)×ε2I 2
回転している質量分布からの
放射パワー』の解釈
|
重力波によってよって持ち去られる
エネルギー
|
「加速運動にともなう“重力子の放出源として
働き続ける能力がアップしている部分”」
=「連星の周囲に存在する空気との摩擦
によって散逸する運動エネルギー」
|
|
P =−dE/dt=dK/dt=−1/2dU/dt
の解釈
|
『P =−dE/dt は、重力波による
“エネルギーの持ち去り”分に相当する』
|
『P =dK/dt は、“重力子の放出源として
働き続ける能力”アップをともなう
放出される重力子数の変動に相当する』
|
※ 『P =(32GΩ6/5c5)×ε2I 2回転している質量分布からの放射パワー』については
『一般相対性理論』(Torsten Flieβbach著 共立出版) を参考にしました。 |
ポイントは、次の所です。
1.連星の運動エネルギーの減少の原因として、従来の物理学パラダイムでは“重力波によるエネルギーの持ち去り”を考えているのに対して、素スピノル物理学パラダイムでは“周囲に存在する空気(気体分子)との摩擦による熱エネルギーとしての散逸”を考えている。
2.「連星の全力学的エネルギーEの減少値ΔEの大きさ」と「連星の運動エネルギーの増加値ΔKの大きさ」は、ぴったり等しい。
|
そもそも、連星系において“エネルギーが持ち去られると考えられた理由”は何だったのでしょうか?
その理由は、『(楕円軌道とならずに)渦巻き状に互いに近づき』合うためには、「重力=遠心力」を保つことが必要であり、そのためには、重力ポテンシャルエネルギーU[J]を消費することによって獲得される(外部)運動エネルギーΔK[J]が、本来の値(力学的エネルギーが保存する場合の値ΔU)の1/2にならなければならないと考えたことです。
|
左図のように、2つの等しい質量m[kg]が軌道1を連星のような円運動をしている系、および、右図のように、同じ軌道1を公転運動(円運動)する質量m[kg]の系を考えてみます。
|
|
|
|
| ※2つの等しい質量m[kg]が、ともに軌道1を通って連星運動をしています。 |
|
※(連星の)重心の位置に存在する、ある質量M[kg]を置くことにより、質量m[kg]が軌道1を公転運動する系を作ることができきます。
このときの質量M[kg]の大きさは、M[kg]=m2/(m+m)2=m/4[kg]と求まります。
(参考『ニ体問題は重心に対する各質点の運動として扱うこともできる.』──『物理入門コース1 力学』 戸田盛和著 岩波書店 p151-153) |
右の系の全エネルギーをE[J]とします。
エネルギーの持ち去りが一切なければ、系の全エネルギーE[J]は、全力学的エネルギーにほかならず、E=K+U[J]が成り立ちます。 (K[J] : 系の全運動エネルギー U[J] : 系の全ポテンシャルエネルギー)
次に、この質量m[kg]が、何らかの原因で、軌道1から軌道2に移る場合を考えてみましょう。
もし、最初の軌道運動に、単に自由落下運動が加わるだけであるならば、質量m[kg]が持っている重力ポテンシャルエネルギーU[J]が消費されて、質量m[kg]の運動エネルギーK[J]が増加します。
すなわち、力学的エネルギー保存則により、E=U+Kが一定なので、 −ΔU[J]=ΔK[J]となります。
|
|
|
|
※単に自由落下が加わるだけなら、質量m[kg]は、軌道1と軌道2の間の重力ポテンシャルエネルギーの減少分の大きさ−ΔU[J]をそのまま100%自身の運動エネルギーの増加分の大きさΔK[J]に使うことになります。
|
|
※その結果、「遠心力>重力」となるので、質量m[kg]は、軌道2をとらずに、勢い余って楕円軌道をとるようになります。 |
しかし、この大きな運動エネルギーのままでは、楕円軌道となってしまいます。
このことは、もし連星様の運動をしていた2つの質量m[kg]においてエネルギーの持ち去りが一切なければ、(軌道を変える際は楕円軌道となってしまうので)『渦巻き状に互いに近づき』合うことができなくなってしまうことを意味します。
楕円軌道とならずに軌道2の円軌道をとるためには(すなわち、『渦巻き状に互いに近づき』合うためには)、あくまで「重力=遠心力」を保ち続ける必要があります。
「重力=遠心力」を保つということは、GMm/r2=mv2/r[N] すなわち、GMm/2r=mv2/2[J]、
つまりは、−U/2=K[J] すなわち、−ΔK=ΔU/2[J]の関係を保ち続けるということに他ななりません。
(M[kg] : 重心の質量 m[kg] : 連星1つの質量 K[J] : 系の全運動エネルギー U[J] : 系の全ポテンシャルエネルギー)
したがって、「重力=遠心力」を保ち続けるためには(軌道をかえても楕円軌道とならないためには)、重力ポテンシャルエネルギーUの差から獲得される運動エネルギーの増加量ΔK(=−ΔU)のちょうど1/2が、何らかの形で持ち去られればよいことがわかります。
以上が、そもそも、連星系において“エネルギーが持ち去られると考えられた理由”です。
|
こういった理由があったからこそ、「余分な運動エネルギーを持ち去っているのは、何なのか?」という疑問が生まれました。
この「何が、余分な運動エネルギーを持ち去っているのか?」について、白羽の矢が当たったのが、まさに重力波でした。
しかも、アインシュタインの重力波のエネルギーの数式から求めた数値と観測値がぴったり一致したので、だれもが、重力波によるエネルギーの持ち去りの説明が正しいと考えました。
そして、連星パルサーの観測結果を、重力波の間接的な証拠と見なしました。
“重力波によるエネルギーの持ち去り”は、従来の物理学パラダイムにおける、常識的な解釈となりました。
しかし、「何が、余分な運動エネルギーを持ち去っているのか?」について他の可能性は本当にないのでしょうか?
次は真空についての重要な記述です。
|
『人工で作り出せる真空状態は、10-11Pa程度である。この圧力下でも1cm3に数千個の気体分子が存在することになる。外宇宙と呼ばれる銀河と銀河の間でも気体分子は存在するとされている。』
(Wikipedia 『真空』) 下線は、筆者によります。
|
銀河と銀河の間の外宇宙にも気体分子が存在するくらいですので、太陽質量の約1.4倍(Wikipedia『PSR B1913+16』)もの質量を持つ2つの連星の周囲にも、気体分子が大量に存在すると考えるのが自然です。
したがって、連星は、周囲の気体分子との衝突、すなわち、摩擦抵抗を受けながら運動エネルギーを低下させ続けている(熱エネルギーとして散逸させ続けている)可能性が考えられます。
この大量の気体分子との衝突によるエネルギーの散逸が、きわめてデリケートな微調整を可能にし、遠心力=重力の維持しながらの公転軌道の収縮を実現するのだとしたら、重力波によるエネルギーの持ち去りは全く不要になります。
※なお、こういった説明の存在は、これまでの“重力波によるエネルギーの持ち去り”による説明が、連星と周囲の気体分子との衝突、すなわち、摩擦抵抗を受けながら運動エネルギーを低下させ続けていること(熱エネルギーとして散逸させ続けていること)を、一切、無視していたという意味で、不完全であったことを意味しています。
つまり、重力波によるエネルギー持ち去りではなく、周囲の気体分子との摩擦抵抗によるエネルギーの持ち去り(熱エネルギーとして散逸)こそが、『“連星系パルサーの軌道運動エネルギーの減少”を引き起こし、これが連星の渦巻き状の近づきあいや、軌道周期の減少を実現している』のならば、重力波によるエネルギーの持ち去りは全く不要になります。
このように、「何が、余分な運動エネルギーを持ち去っているのか?」について、重力波以外の可能性があるのです。
そもそも、観測されているものは、あくまで、「公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいること」だけでした。
(「重力波によるエネルギーの持ち去りによる“連星系パルサーの軌道運動エネルギーの減少”」は、解釈にすぎず、実際に観測されされたものではありません。
現に、この記事にも『重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら』と書かれてあります。)
さらに重要なことは、そのようにして「重力=遠心力」を保ったまま公転軌道を収縮する過程において、連星の運動エネルギーK[J]は増加するということです。
しかも、その運動エネルギーK[J]の増加量の大きさと、総力学的エネルギーE[J]の減少量の大きさは、ぴったり一致します。
※なお、「重力=遠心力」を保ちながらの軌道収縮において、連星の運動エネルギーK[J]は増加するという結論は、エネルギーの持ち去りの原因が何であったとしても変わりません。(仮に重力波であったとしても変わりません)
運動エネルギーの増加は、質量エネルギーの増加に他なりません。したがって、たとえ仮に重力波によってエネルギーが持ち去られていたとしても、「重力=遠心力」を保ちながら軌道収縮する限り、−ΔU/2[J](=ΔK[J])の大きさずつ連星の質量エネルギー(運動エネルギー)は増加し続けるはずなのです。
|
仮に、重力波によってエネルギーが持ち去られて、“連星の質量が減少する”のならば、下の左図のように、2つの等しい質量m[kg]が軌道1を連星のような円運動を続けることはできなくなるはずです。
なぜなら、“連星の質量が減少する”とは、重力ポテンシャルエネルギーによる運動エネルギー(質量エネルギー)の増加分(−ΔU[J])よりも、運動エネルギー(質量エネルギー)の減少が大きいということであり(ΔK<0[J]ということであり)、その結果、「遠心力<重力」となって、連星は、互いに円軌道を維持できなくなり、小さな楕円軌道をとったり、さらには衝突したりすると考えられるからです。
|
|
|
|
※連星の質量が減少するとは、重力波が、軌道1と軌道2の間の重力ポテンシャルエネルギーの減少分の大きさ−ΔU[J]よりも大きな質量エネルギーを、連星の(−ΔU[J]分だけ新たに獲得された運動エネルギーを含めた)質量エネルギーから持ち去ることを意味します。
|
|
※その結果、「遠心力<重力」となるので、連星は、軌道2をとれずに、勢いの低下にともなう小さな楕円軌道をとるようになります。 |
その後も、重力波が質量エネルギーを持ち去り続けるのならば、連星は、互いに“静止にもとづく自由落下に近づく”ということであり、いずれ衝突に至ると考えられます。
つまり、“重力波がエネルギーが持ち去ることによって連星の質量が減少させながら”円軌道を保ちながら軌道収縮することは、不可能なのです。
|
素スピノル物理学パラダイムでは、“連星系パルサーの軌道周期の減少”を、次のように説明します。
『連星パルサーは、互いに、周囲の気体分子との摩擦抵抗によって運動エネルギーの一部を熱エネルギーとして散逸させることによって「重力=遠心力」を保ちながら、系の重心に向かってらせんを描き、公転軌道を収縮しているだけである』
|
素スピノル物理学パラダイムでは、“連星系パルサーの軌道周期の減少”と重力波の関係を、次のように説明します。
“連星系パルサーの軌道周期の減少”にともなって、特定の観測点での、放出される重力子数[個/s]の変化の振幅は、下図のように増加します。
実際は、重力ポテンシャルエネルギーU[J]の1/2を利用して連星は加速を続けるので、(軌道)運動エネルギーが増加し続けます。(それが、上図のように重力波の振幅の増加に反映されます)
もし、“らせん軌道をとりながらの軌道収縮”をする連星の「運動エネルギーの増加に相当する“放出される重力子の変動”」のみを考えるならば、その変化は、次のようになるでしょう。
重力ポテンシャルエネルギーU[J]の1/2を利用した加速によって生じるものには、「(外部)運動エネルギーの増加」(すなわち、速度の増加)だけでなく、軌道収縮にともなう“連星系パルサーの軌道周期の減少”もあります。(それが、下図における、重力波の振動数の増加に反映されています)
そして、その“連星系パルサーの軌道周期の減少”は、「重力波がエネルギーを持ち去る」と前提にしたものとぴったり一致するはずです。
なぜなら、「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提を「周辺の気体分との摩擦抵抗がエネルギーを持ち去る」という前提に置き換えただけだからです。
つまり、「重力波放射によるエネルギーの持ち去り」が、『軌道の減衰に対する唯一の可能な説明』ではないのです。
『軌道の減衰』と『重力波』の説明には、以下に示すように、少なくとも〈1〉従来の物理学パラダイムと〈2〉素スピノル物理学パラダイムの2通りあります。
〈1〉従来の物理学パラダイムでは、重力波がエネルギーを持ち去る結果、軌道収縮ともなって獲得される運動エネルギーは、(重力ポテンシャルエネルギー−ΔU[J]を利用した)本来の運動エネルギーの増加ΔK[J]の1/2になるのでした。
〈2〉一方、素スピノル物理学パラダイムでは、周囲の気体分子との摩擦抵抗が、連星の運動エネルギーの一部を減らす(熱エネルギーとして散逸させる)結果、軌道収縮ともなって獲得される運動エネルギーは、(重力ポテンシャルエネルギー−ΔU[J]を利用した)本来の運動エネルギーの増加ΔK[J]の1/2になります。
いずれにおいても、その結果、重力=遠心力[N]の関係、すなわち、−U/2=K[J]の関係が保たれます。
これらの関係により、全力学的エネルギーE[J]について、E=U+K=−K=U/2[J]の関係が導かれます。
〈1〉従来の物理学パラダイムでは、P=−dE/dt(=dK/dt=−1/2dU/dt)の式を用いて、総力学的エネルギーE[J]減少に相当するものとして、重力波によるエネルギーの持ち去りを説明しました。ある観測地点に到達するエネルギーの周期的な変動の頻度の増加に相当するものとして、重力波の振動数の増加を説明します。
〈2〉一方、素スピノル物理学パラダイムでは、P=dK/dt=(−1/2dU/dt=−dE/dt)の式を用いて、重力波が運動エネルギーの増加ΔKに伴う放出される重力子数の増加に相当するものとして、重力波の振幅の増加を説明します。ある観測地点での放出される重力子数の周期的な変動の頻度の増加に相当するものとして、重力波の振動数の増加を説明します。
※なお、P=−dE/dt=dK/dt ですので、数値は、互いにぴったり等しくなります。
※『巻き込み時間』および“連星系パルサーの軌道周期の減少”についても、いずれも、共通の「−1/2dU/dt=P」の式やケプラー則の式(『T 2∝r 3』)を利用して計算されますので(参考 『一般相対性理論』 p242〜244 Torsten Flieβbach著 共立出版)、互いに、ぴったり一致します。
※このように、“重力波がエネルギーを持ち去る”と前提して導いた数字(計算結果)と“重力波がエネルギーを持ち去らない”と前提して導いた数字(計算結果)は、ぴったり一致することは、「数字の一致は必要条件に過ぎないこと」および「観測の理論負荷性」を示す例だと言えます。
|
〈1〉従来の物理学パラダイム
「重力波放射による運動エネルギーの一部の持ち去り」によって、重力=遠心力を保ちながら、軌道が減衰する。
重力波とは、総力学的エネルギーE[J]が減少した分および、ある観測点での周期的な変動そのものに相当している。
〈2〉素スピノル物理学パラダイム
「周辺の気体分子との摩擦抵抗による運動エネルギーの一部の持ち去り(熱エネルギーとしての散逸)」によって、重力=遠心力を保ちながら、軌道が減衰する。
重力波とは、放出される重力子数の、重力ポテンシャルエネルギーの大きさの1/2(−U/2[J])を利用しての(外部)運動エネルギーK[K]の増加した分(=振幅の増加)および、ある観測点での周期的な変動そのものに相当している。 |
果たして、どちらが、自然(nature)と調和しているでしょうか?
両者の違いを比較すると次のようになります。
|
従来の物理学パラダイム
|
素スピノル物理学パラダイム
|
|
時空
|
連続
|
不連続
|
|
重力波の生成過程
(重力子の生成過程)
|
エネルギー保存則に従っており。
エネルギーを持ち去る
|
エネルギーの生成過程
|
|
エネルギーの持ち去り
|
重力波
|
天体の周囲の気体分子の摩擦抵抗
(熱エネルギーとしての散逸)
|
|
計算式P [J/s]
=−dE/dt
=dK/dt
=−1/2dU/dt
の解釈
|
全力学的エネルギーE[J]の
減少分が重力波によって
持ち去られたエネルギーに相当
P=−dE/dt[J/s]に注目
|
(重力ポテンシャルエネルギーU[J]
の1/2を利用しての)
(外部)運動エネルギーK[K]の
増加分(=振幅の増加)が
重力波の振幅の増加に相当
P=dK/dt(−1/2dU/d)[J/s]に注目
|
|
等速運動(慣性運動)
|
説明できない
(法則である)
|
説明できる
(「時空の砕氷船効果」)
|
|
光速度不変性
|
説明できない
(原理である)
|
説明できる
(運動方法へ放出される重力子の総和
による空間の膨張&
時間の流れのスローダウン)
|
|
アインシュタインの重力場方程式の右辺
|
説明できない
(「粗悪な材木」)
|
説明できる
(「大理石」にグレードアップできる)
|
|
一般相対性理論が持っている矛盾(「エネルギー保存則」と「熱運動による正のエネルギーの放射」の間の矛盾)
|
解消できない
(『量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より p.170〜171)
下線は、筆者によります。)
|
|
|
アインシュタインが一般相対性理論で、エーテルが必要不可欠であると述べたこと
|
説明できない
(エーテルを完全に否定し続けています)
|
説明できる
(物質未満の新しいエーテルの提示)
|
素スピノル物理学パラダイムによれば、ある質量を持つ物体が加速運動をすれば、運動エネルギーが増加して(その運動の方向への)「重力子&縮みきり“4角形”の放出源として働き続ける能力」が増加するとともに、質量が増加します。
ある質量を持つ物体が減速運動をすれば、運動エネルギーが減少して(その運動方向への)「重力子&縮みきり“4角形”の放出源として働き続ける能力」が減少するとともに、質量が減少します。
※この性質が、加速しおわった物体のその後の等速運動(慣性運動)(≒「時空の砕氷船効果」)を支え、運動が光速に近づくほど質量が増加することを支え、光速度不変性を支え(マイケルソンモーレーの実験結果を支え)、そして、アインシュタイン方程式の右辺を支え、一般相対性理論が持っている矛盾(「エネルギー保存則」と「 熱運動による正のエネルギーの放射」の間の矛盾)の解消を支えることは、これまでの説明で述べたとおりです。
このように、自然(nature)を統合的に説明できる能力の高さは、素スピノル物理学パラダイムの自然(nature)との調和性の高さを示していると思います。
この質量の加速運動(や減速運動)にともなう『放出される重力子数の変化』として創発するものが、重力波の振幅です。2つの質量が周期的な振動運動をすることで、ある地点で観測される『放出される重力子数の周期的な変化』として創発するものが、重力波の振動です。
素スピノル物理学パラダイムによれば、時空が不連続なので、重力子の生成過程は、エネルギーの生成過程です。
したがって、「重力子&縮みきり“4角形”」の総和して創発する重力波が、エネルギーを持ち去らないのは明白です。
つまり、重力波(放出される重力子数の変化)の生成過程も、エネルギー生成過程の所産なのです。
そして、重力波(放出される重力子数の変化)が、エネルギー生成過程の所産である以上、エネルギー保存則を根拠に、重力波がエネルギーを持ち去ると説明することは、自然(nature)から乖離していることになります。
そもそも、素スピノル物理学パラダイムによれば、加速していようが、静止していようが関係なく、重力子は、「地球からも、太陽からも、月からも、人からも、りんごからも、自動車からも、鉛筆からも、消しゴムからも、水素からも、電子からも、クォークからも、宇宙船からも、ブラックホールからも…」、あらゆる質量から、常にある頻度で放出され続けており、どの重力子も「エネルギーを持ち去る」ということをしていないのでした。
※ 仮に、もし、“重力子がエネルギーを持ち去る”ことが本当に起こっているならば、電子も、クォークも… 含め、あらゆる物体が持つ質量が、(重力子1つあたりおよそ3.2×10−9[kg]ずつのペースで)減り続けることになってしまうので、今、目の前に存在している自然(nature)の姿とは、全く異なってしまうでしょう。しかも、万有引力の法則さえも成立しなくなってしまうでしょう。
こう言った単純な思考実験も、“重力子がエネルギーを持ち去る”という説明(つまりは、“重力波がエネルギーを持ち去る”という説明)が自然(nature)から乖離性が高いことを示していると思います。
質量が加速運動や減速運動をすれば、ある地点で、 放出される重力子数の変化が観測されます。
もし、運動エネルギー(内部&外部)が増せば、“重力子の放出源として働き続ける能力”が増すので、放出される重力子数も増します。
もし、運動エネルギー(内部&外部)が減れば、“重力子の放出源として働き続ける能力”が減るので、放出される重力子数も減ります。
(参考 5《運動の第1法則(慣性の法則)&第2法則(F=ma)》)
※例えば、2つの質量が周期的な振動運動において、加速が生ずれば、“重力波の振幅の増加”が観測されます。
すなわち、この場合、運動エネルギー(内部&外部)の変化に伴う“ 放出される重力子数の変化”が、重力波の振幅の変化に相当しています。
※例えば、単独の質量が、単純に加速a[m/s 2]で加速したり、減速したりするだけでも、下図のように「 放出される重力子数の変化」が生じます。厳密に見れば、これは、サインカーブではないので(周期的な変化ではないので)本来の「重力波 」ではないことになります。
※図の紫の部分が、加速中の「放出される重力子数の変化」に相当し、ピンクの部分が、減速中の「放出される重力子数の変化」です。
やはり、この場合も、“エネルギーの持ち去り”は、存在しないことがわかります。
※このカーブは、v=at、運動エネルギーK=mv2/2=ma2t2/2より、2次関数(放物線)に相当するカーブであり、サインカーブではありません。したがって、サインカーブでない以上、これを重力波とは呼べません。
※(サインカーブを持つ)重力波とは、単に「重力子の放出源として働き続ける能力の一時的な変動」(「運動エネルギーの一時的な変動」)を反映するものではなく、下記で示すように、「連星パルサー」や「反対向きに単振動する2つの剛体」が持つような周期的な運動を反映するものなのです。
|
2つの質量が周期的な振動運動をしていれば、ある地点で、放出される重力子数の周期的な変化、すなわち、重力波が観測されます。
もし、2つの質量が周期的な振動運動の周期が短くなれば、重力波の振動数が増します。
もし、2つの質量が周期的な振動運動の周期が長くなれば、重力波の振動数が減ります。
つまり、2つの質量の振動運動の周期の変化が、重力波の振動数の変化に相当しています。
重力波は、『周期的に繰り返す振動運動にともなって、ある地点で観測される「放出される重力子数の周期的な変化」の部分に注目してとらえているだけのものに過ぎない』とも言えます。
例えば、2つの同じ質量M[kg]の物体が、互いに反対向きに単振動しているような場合の重力波は、次のように示されます。
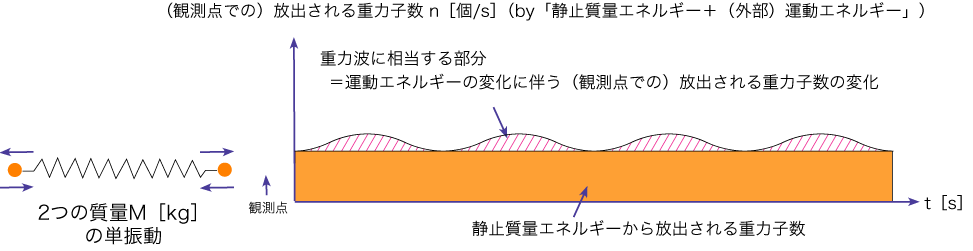 |
※この場合は、図のピンク色の斜線の部分が、運動エネルギーの変化ΔK、すなわち、観測される「放出される重力子数の変化」に相当し、これらが重力波に相当しています。
やはり、この場合でも、重力波による“エネルギーの持ち去り”は、存在しないことがわかります。
※静止質量がM0[kg]の剛体が下図のように速さv[m/s]で運動する場合、この剛体の質量エネルギーMc2[J]は、物体の運動方向へのc/(c−v)に相当する時空の膨張の効果(赤の“→”で表示)、物体の運動と反対の方向へのc/(c+v)に相当する時空の収縮の効果(緑の“←”で表示)が重なる部分において、Mc2=M0c2/(1−v2/c2)1/2≒M0c2+M0v2/2 [J]((c>>v)[m/s])となるのでした。
すなわち、この剛体の質量エネルギーMc2=M0c2/(1−v2/c2)1/2≒M0c2+M0v2/2 [J]((c>>v)[m/s])は、緑の線で示した「放出される重力子数が減る効果」と、赤の線で示した「放出される重力子数が増える効果」が重なった部分についてのものでした。
このことを、互いに、反対向きに単振動する2つの剛体にあてはめると、次の図ようになります。
すると、図で示した観測点では、緑の“→”で示される「重力子の放出が減る効果」と、赤の“→”で示される「重力子の放出が増える効果」が重なることになります。その結果、この観測点での重力子の変動は、『剛体の内部で観測する質量エネルギーMc2[J]に相当する、Mc2=M0c2/(1−v2/c2)1/2≒M0c2+M0v2/2 [J]((c>>v)[m/s])の変動に伴う重力子の変動』と等しくなります。
その結果、上図の運動線上の観測点では、(静止質量エネルギーの分を除いた)ちょうど運動エネルギーK≒M0v2/2[J]の変動だけに相当する「放出される重力子数の変化」、すなわち、重力波を観測することになります。
つまり、上図の観測地点での「(観測される)重力子数の変化(重力波)」は、結局は、「M0v2/2」[J]の変動とぴったり同じになります。
※上図のように、重力波(重力子の放出頻度の変化)が、緑の“→”で示される「重力子の放出が減る効果」と、赤の“→”で示される「重力子の放出が増える効果」が重なるところで観測できるということは、運動する「単独の物体(剛体)」の外部では、運動エネルギーK≒M0v2/2[J]の変動に相当する重力波(放出される重力子数の変化)を観測することができないことを意味します。
|
例えば、連星パルサーの場合も、反対向きに単振動する2つの剛体の場合と同様に考えることができますので、運動エネルギーK≒M0v2/2[J]の変動に相当する重力波(放出される重力子数の周期的な変化)を観測できると考えられます。
やはり、この場合でも、重力波による“エネルギーの持ち去り”は、存在しないことがわかります。
つまり、観測される重力波とは、「(ある観測地点で、観測される)放出される重力子数の周期的な変化」に他ならず、いずれにしても、(個々の重力子の生成過程と同様に、“放出される重力子数の変化”に相当する)重力波の生成過程もエネルギー生成過程であり、“エネルギーの持ち去り”に全く関与しないのです。
連星パルサーの場合、重力ポテンシャルエネルギーの大きさの1/2(−U/2[J])が何らかの形で持ち去られ、残りの1/2(−U/2[J])だけが“連星系パルサーの軌道運動エネルギーの増加”に活用されるのでした。
素スピノル物理学パラダイムでは、重力ポテンシャルエネルギーの大きさの1/2(−U/2[J])の持ち去りは、周囲の気体分子の摩擦抵抗による、熱エネルギーとしての散逸に相当していますので、 連星系パルサーにおいて“重力波(“放出される重力子数の変化”)によるエネルギーの持ち去り”を考えることが不要となります。
それどころか、不連続な時空を前提とする素スピノル物理学パラダイムによれば、では、重力子も重力波も、その生成過程はエネルギーの生成過程ですので、“重力波(“放出される重力子数の変化”)によるエネルギーの持ち去り”を考えることは不可能です。
「重力波がエネルギーを持ち去る」ことに関連して、大きな問題(矛盾)が生ずることに、アインシュタインは気づいていました。
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』 p.170〜171) 下線は、筆者によります。
|
この『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』ほどの、大きな問題(矛盾)を解消しようとアインシュタインは必死でした。
|
『重力波を放出している物質系は、エネルギーを外に向かって放出するはずである。したがってエネルギー保存則を考えると、この反作用として物質系の運動は減衰することとなる。それにもかかわらず、このような減衰のない振動を考えることができる。たとえば、物質系から波が外に向かって放射されるとともに、他方で中心に向かって集まってくる第2の波動場が存在する場合である。しかもこの第2の波は、第1の波によってもち去られたエネルギーと同じ量のエネルギーを、物質系に運び入れる場合である。〜』
(『アインシュタイン選集2──A9重力波について』(p.180-181)) 下線は、筆者によります。
|
なぜ『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』が『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』のかと言えば、その理由は、やはり、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』が、(エネルギー保存則を前提にする場合に限って)「重力波による“エネルギーの持ち去り”によって、系全体の質量が減少する」という奇妙な予測を導くからです。
そこにある大きな問題(矛盾)に、誰よりも一番アインシュタイン自身が気づいていたからこそ、アインシュタインは必死だったのです。
だからこそ、アインシュタインは、『それにもかかわらず、このような減衰のない振動を考えることができる。たとえば、物質系から波が外に向かって放射されるとともに、他方で中心に向かって集まってくる第2の波動場が存在する場合である。しかもこの第2の波は、第1の波によってもち去られたエネルギーと同じ量のエネルギーを、物質系に運び入れる場合である。〜』のような、系全体のエネルギーが減少しなくなるようなしくみを、無理してひねりだしたのです。
(たしかに『考えることができる』かもしれませんが、かなり無理のある(自然(nature)から乖離している可能性が高い)説明であることは明らかです。なぜなら、なにゆえに『第1の波によってもち去られたエネルギーと同じ量のエネルギー』が『物質系に運び入れ』られなければならないのかが全く説明つかないからです)
素スピノル物理学パラダイムによれば、この問題を解決するためにまず何より修正するべきだったのは、「重力波によって“エネルギーが持ち去れる”」という説明、つまりは、その前提であるところの「時空は連続なので、エネルギー保存則が成り立つ」という考えの方だったことになります。
なぜなら、時空が不連続であることを前提とする素スピノル物理学パラダイムによれば、『物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論』には、どこにも問題が生じないからです。
しかし、アインシュタインは、この「連続な時空&エネルギー保存則が成り立つ」という前提を守るべく、必死にもがき続けました。
なぜなら、アインシュタインの偉大な成果──アインシュタインが10年もかけて作り上げた、アインシュタインの重力場方程式(一般相対性理論(byリーマン幾何学))が「連続な時空&エネルギー保存則」(byネーターの定理)を前提に育まれていたからです。
「連続な時空&エネルギー保存則」(byネーターの定理)の前提を守ることは、一般相対性理論(byリーマン幾何学)を守ることそのものだったのです。
したがって、アインシュタインには、「連続な時空&エネルギー保存則」(byネーターの定理)を尊重するしか選択肢がなくなっていたのです。
そのアインシュタインにしてみれば、重力波〈放出される重力子数の変化〉の生成過程が、エネルギーの生成過程であると考えることなど、ナンセンスでしかなかったはずです。
したがって、当然、「負にならない全放射エネルギー、すなわち、重力波が、エネルギーを持ち去る」と考えるしかありませんでした。
その結果、アインシュタインは板挟みにあいました。
アインシュタインは、必死に無理のある考え(『それにもかかわらず、このような減衰のない振動を考えられることができる。〜』)をひねり出すほど追いつめられていたのです。
アインシュタインは、重力波というテーマに至って、「連続な時空&エネルギー保存則を前提とする一般相対性理論」が根本的な矛盾を抱えていることに、はっきり気づいたのです。
(だからこそ、『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』だったのです)
(そして、だからこそ、量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』だったのです)
しかも、その矛盾は、一般相対性理論が「連続な時空&エネルギー保存則を前提とし、微分可能性を前提とするリーマン幾何学に依存していた」以上、アインシュタインにとって、どうしても解消することができないものでした。
素スピノル物理学パラダイムは、この矛盾(板挟み、行き詰まり…)を根底から解消します。
素スピノル物理学パラダイムによると、重力子、重力波、重力場はいずれも、「不連続な時空」&「エネルギー生成の所産(エネルギー非保存の所産)」です。
「どんな方向に対しても負にならない全放射エネルギー」、すなわち、重力波が、「不連続な時空の中で、エネルギー保存則を破って生成する(放出される)重力子数の変化であること」を、素スピノル物理学パラダイムが、はっきり示しています。
(10《重力場、エネルギー、質量》)
しかも、素スピノル物理学パラダイムは、時空の量子化を含むところの、いわば、“究極の量子論”といえるものであり、量子論の完成をも助けるものです。(成果3 素スピノル量子物理学)
すなわち、このことは、次のアインシュタインの期待(予想、望み…)と調和しています。
『量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』 p.170〜171) 下線は、筆者によります。
|
しかも、素スピノル物理学パラダイムは、次のものを「より深い階層のレベル」から説明し、これらの自然(nature)と調和している部分を包含するものです。
◎特殊相対性理論(光速度不変性、ローレンツ収縮、運動エネルギーが増すと質量エネルギーも増加すること(アインシュタインの関係式の1つE=mc2=(m0c2/(1−(v/c)2)1/2[J](m0:静止質量)が示していること)…)
◎一般相対性理論(時空の曲り、重力場が質量を持たないこと、『アインシュタイン方程式の右辺を「高級大理石」とする考え』、『Gが2Gになること』…)
◎ニュートン力学(慣性の法則、F=ma)や万有引力の法則
◎電磁気学(16《静電気力と磁力(電荷と磁極のクーロンの法則)および、重力と電磁気力の統合》)
… |
※逆に「重力波(&重力子)によるエネルギー持ち去り」という考えは、たとえエネルギー保存則と調和していたとしても、特殊相対性理論やニュートン力学とも、矛盾してしまうことを素スピノル物理学パラダイムは示しています。
(例えば、「質量が減少し続ける結果、万有引力法則が成立しなくなる。等速運動が実現しなくなる。…」)
つまり、「連続な時空&エネルギー保存則にしがみついている限り、重力は、量子化することはできない」のです。
すなわち、「連続な時空&エネルギー保存則」と、重力子や「重力の量子化」(「重力場(時空の曲り)の量子化」)は、根本的に矛盾しているのです。
したがって、一般相対性理論の成功をもたらした「連続な時空&エネルギー保存則」の前提そのものが、重力の量子化(「重力場(時空の曲り)の量子化」)を困難にしてきた最大の障壁の1つであったということになります。
※ここにあるのは、言わば、「エネルギー保存則の封印」(「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」)です。
(成果6 3《エネルギー保存則(熱力学第一法則)について》)
アインシュタインは、この「エネルギー保存則の封印」(「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」)によって、板挟みに合い、身動きがとれなくなってしまったことになります。
素スピノル物理学パラダイムは、次の成果を否定するものでありません。
『伴星のまわりを公転するパルサーの軌道がゆっくり縮んでいることが発見され、この重力波の存在が間接的に示された』
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』 J.M.ワイズバーグ、J.H.テイラー、L.A.ファウラー)
|
| 『アインシュタインは、1915年に発表した一般対性理論の中で加速運動している物体は、重力波の形でエネルギーを放出すると予言した』 (『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』) |
しかし、素スピノル物理学パラダイムは、次の記述の中の(重力波が)『エネルギーを持ち去っているとしたら』という前提を否定します。
『連星系パルサーからの重力放射に必要なエネルギーの源は、軌道運動エネルギーである。だから、重力波が存在し、連星からエネルギーを持ち去っているとしたら、軌道エネルギーはしだいに減少し、このために、パルサーとその伴星が渦巻き状に互いに近づきあい、軌道周期も減少するはずである』
(『連星系パルサーからの重力波 サイエンス1981年12月号』) 下線は、筆者によります。 |
すなわち、「重力波がエネルギーが持ち去る」という前提が、自然(nature)から乖離していることを、素スピノル物理学パラダイムがはっきり示しているのです。
素スピノル物理学パラダイムは、連星パルサーと重力波について、次の結論を導きます。
結論1-14.1 連星パルサーから放出される重力波は、エネルギーを持ち去っていない。(重力波の生成過程は、エネルギー生成過程である)。
結論1-14.2 2つの連星が、らせん軌道を描きながら軌道収縮する過程で、(重力ポテンシャルエネルギーの大きさの1/2(−U/2[J])を利用して)運動エネルギーを増加させる(=連星の重力子の放出源として働き続ける能力を増加させる)過程によって、重力波(=放出される重力子数の周期的な変化)の振幅が増加する。
結論1-14.3 重力ポテンシャルエネルギーの大きさの残りの1/2(−U/2[J])の持ち去りは、周囲の気体分子による摩擦抵抗による運動エネルギーの一部の熱エネルギーとしての散逸によって説明するほうが自然である。
重力波とは「(ある地点で観測される)放出された重力子数の周期的な変化」であり、重力波の生成過程は、(重力子と同様に)エネルギー生成過程です。
エネルギーを持ち去るものが、(重力波から)「周囲の気体分子との摩擦抵抗」に置き換わっただけであり、基本的に、軌道周期の減少は、既存の物理学のパラダイムの成果と等しくなります。
“らせん軌道をとりながらの軌道収縮”にともなう運動エネルギーK[J]の増加率の大きさと、総力学的エネルギーE[J]の減少率の大きさはぴったり等しいので、(既存の物理学のパラダイムの成果と同様に)素スピノル物理学パラダイムの成果はアインシュタインの予測と数字的に合致します。
「重力波はエネルギーを持ち去らない」という前提を持つ素スピノル物理学パラダイムは、(2016年2月に最初に発表された)「LIGOが“重力波”を直接、観測した」という偉大な成果と調和しています(矛盾していません)。
しかし、「LIGOによって観測された“重力波”」(LIGOが得た観測データ(重力波の波形))についての“解釈”については、従来の物理学パラダイム(「重力波はエネルギーを持ち去る」という前提)と、素スピノル物理学パラダイム(「重力波はエネルギーを持ち去らない」)のものとの間で、180度の違いがあります。
既存の物理学のパラダイムでは、例えば、『太陽の約35倍と約29倍の質量のブラックホールが、合体後、太陽の約62倍の質量のブラックホールになった結果、太陽の約3倍のエネルギーが重力波として持ち去られた』という“解釈”がなされました。
(参考 『Observasion of Gravitayional Waves from a Binary Black Hole Merger』(PHYSICAL REVIEW LETTERS B.P.Abbot et al.(特に『VI.SOURCE DISCUSSION』の部分)、『重力波とは何か』(p.173-175 講談社ブルーバックス 安東正樹))
※これらの質量の数値は、決して直接観測されたものではなく、LIGOの観測データ(重力波の波形)をもとに、アインシュタインの一般相対性理論(エネルギー保存則(連続な時空)、「重力波によるエネルギーを持ち去り」)を前提とするモデルやシミュレーションを駆使して得られた“見積もり計算”の所産でした。
一方、素スピノル物理学パラダイムの前提(不連続な時空、「重力波はエネルギーを持ち去らない」)によれば、LIGOの観測データ(重力波の波形)から、180度逆の説明を与えます。
それは、次のようなものです。
|
2つのブラックホールが「インスパイラル期、合体、リングダウン期」を経る過程で、重力波の振幅が大きくなったり小さくなったりしている一方で、重力波の振動数だけは一貫して増加し続けています。
このことは、『2つブラックホールが、「インスパイラル期、合体、リングダウン期」のようにコンパクト化し続けるのに伴い、角運動量保存則に従って、回転数がアップし続けていることを意味している』と解釈できます。(アイススケートのスピンにおいて、両腕を縮こませると回転数がアップするの同じ理由です)
2つのブラックホールのコンパクト化に伴い回転数が増加する結果、(角運動量の大きさが一定であるのに対して)運動エネルギーは増加し続けるので、当然、質量エネルギーも増加し続けることになります。
(角運動量の大きさL=mvr=mr2ω(v=rω(ω:角振動数))が一定になる一方、運動エネルギーK=mv2/2=mr2ω2/2は増加し続けます)
合体しコンパクト化が進み球体に近づくほどに連星としての性質(「互いに反対向きに単振動する2つの剛体に相当する性質」)が失われますので、それとともに「重力波(放出される重力子数の周期的な変化)の振幅」は消失していきます。
しかし、その過程で、一貫して、この運動エネルギー増加に伴う質量エネルギーの増加が続くことにより、実際は、「放出され重力子数」は一貫して増え続けます。
つまり、『重力波の振動数が一貫して増加し続けている』という観測結果(重力波の波形)は、この過程で一貫して質量が増加し続けていることを示していると解釈できるのです。
そして、まさに、この解釈(説明)は、重力波がエネルギーが持ち去らないという前提とぴったり調和しています。
この説明は、(インスパイラル期の)連星パルサーにおいて、「(重力ポテンシャルエネルギーの減少分の大きさの1/2(−ΔU/2[J])を利用して)運動エネルギーが増加し続けることにより、連星の質量エネルギーが増加し続けている」こととつじつまが合っています。
※重力波によるエネルギーの持ち去りが質量(質量エネルギー)を減らすという説明は、(インスパイラル期の)連星パルサーにおいて、「(重力ポテンシャルエネルギー減少分の大きさの1/2(−ΔU/2[J])を利用して)運動エネルギーが増加し続けることにより、連星の質量エネルギーが増加し続けている」ことを説明できないのでした。
|
やはり、仮に、重力波によってエネルギーが持ち去られて、“連星の質量が減少する”のならば、下の左図のように、2つの等しい質量m[kg]が軌道1を連星のような円運動を続けることはできなくなるはずです。
|
|
|
|
※連星の質量が減少するとは、重力波が、軌道1と軌道2の間の重力ポテンシャルエネルギーの減少分の大きさ−ΔU[J]よりも大きな質量エネルギーを、連星の(−ΔU[J]分だけ新たに獲得された運動エネルギーを含めた)質量エネルギーから持ち去ることを意味します。
|
|
※その結果、「遠心力<重力」となるので、連星は、軌道2をとれずに、勢いの低下にともなう小さな楕円軌道をとるようになります。 |
つまり、“重力波がエネルギーが持ち去ることによって連星の質量が減少させながら”円軌道を保ちながら軌道収縮することは、不可能なのでした。
|
もし、重力波によるエネルギーの持ち去りが全体の質量(質量エネルギー)までも減らすのであれば、2つのブラックホールが「インスパイラル期、合体、リングダウン期」を経る過程で、運動エネルギーが減り続け、重力波の振動数が一貫して減少するはずであるだけでなく、そもそも「インスパイラル期、合体、リングダウン期」が存在することを説明できなくなる可能性が高いのです。
|
このように、(連星パルサーのときと同様に)「重力波はエネルギーを持ち去らない」という前提による「LIGOによって観測された“重力波”」(LIGOが得た観測データ(重力波の波形))を“解釈”には、一貫性があります。(逆に、「重力波はエネルギーを持ち去る」という前提による「LIGOによって観測された“重力波”」(LIGOが得た観測データ(重力波の波形))を“解釈”には、一貫性がありません)
このことは、「LIGOによって観測された“重力波”」(LIGOが得た観測データ(重力波の波形))は、素スピノル物理学パラダイムを支持する証拠の1つである、と再解釈できることを意味します。(まさに、これは、「観測の理論負荷性」の一例であると言えます)
両者を整理すると次のようになります。
|
|
従来の物理学パラダイム
|
素スピノル物理学パラダイム
|
|
LIGOによって、重力波を直接観測した成果
|
○
|
○
|
|
アインシュタインの一般相対性理論
|
すべて正しい
|
一部(特にエネルギーと関連する部分)は、
修正を要する。
|
|
重力波の生成過程を含むエネルギー保存則
|
○
成立する
(時空は、どこまでも連続)
ゆえに、重力波はエネルギーを
持ち去るはずである。
|
×
成立しない
((プランクスケールで)時空は不連続)
ゆえに、重力波はエネルギーを
持ち去らないはずである。
※重力波の生成過程は、
エネルギーの生成過程です。
|
|
インスパイラル期〜リングダウン期における
2つのブラックホールの質量
|
少なくとも、途中から減るはずである
(※インスパイラル期においては、2つのブラックホールの質量が増えているはずです)
|
一貫して、増えるはずである。
|
|
観測結果(重力波の波形)の解釈
|
『太陽の約35倍と約29倍の質量のブラックホールが、合体後、太陽の約62倍の質量のブラックホールになった結果、太陽の約3倍のエネルギーが重力波として持ち去られた』
|
『(重力波の振幅が大きくなったり小さくなったりしている一方で)重力波の振動数は一貫して増加し続けている』以上、合計の質量は増加し続けている。
|
少なくともインスパイラル期では、“仮にエネルギーが重力波として持ち去られていたとしても”質量は明らかに増加しています。
従来の物理学パラダイムによる説明では、“エネルギーが重力波として持ち去られている”という条件は共通しているはずなのに、インスパイラル期では質量が増え、リングダウン期で質量が減るという不思議なことが起きていることになります。
ここには、根本的な矛盾があります。
「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提にもとづく、『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という一見、もっともに思われる解釈(説明)が持っている根本的な矛盾を詳しく説明すると、次のようになります。
|
ここにある矛盾の1つは、やはり、『たとえ「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提の上であっても、連星ブラックホールの質量が最終的に減るとは考えにくい』ことから生まれるものです。
まず、連星ブラックホールのインスパイラル期について、考えてみましょう。
この説明は、「連星パルサー(連星中性子星)」についての説明の場合と同じです。
「重力波がエネルギーを持ち去る」場合、この重力ポテンシャルエネルギーU[J]の減少分の大きさ(−ΔU/2[J])だけが重力波として持ち去られ、その残りの1/2(−ΔU/2[J])だけが、運動エネルギーの増加(ΔK[J])に使われます。
(すなわち、ΔK=−ΔU/2[J]です。この関係が成立するのは、「遠心力=重力」(「mv2/r=GMm/r2」)の関係が保たれるからです。なお、「ΔU=−ΔK/2」と「全力学的エネルギーE=U+K」より、「ΔE=−ΔK」が導かれるのでした)
つまり、インスパイラル期において、たとえ「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提でも、連星ブラックホールは、その運動エネルギーを増加させる結果、その質量エネルギー(すなわち、質量)を増加させることになるのです。
それは、連星ブラックホールの合体〜リングダウン期についても、基本的に同様に考えて説明するのが自然です。
『連星ブラックホールが合体して球状に至るのは、重力ポテンシャルエネルギーの減少分の大きさ−ΔU[J]が利用されるからです。
「重力波がエネルギーを持ち去る」場合、連星ブラックホールが合体して球状に至る過程においても、重力波として持ち去られるのは、重力ポテンシャルエネルギーの減少分の大きさ−ΔU[J]の一部だけであり、残りは、合体したブラックホールの運動エネルギーの増加、すなわち、質量エネルギーの増加に利用されます。
したがって、たとえ重力ポテンシャルエネルギーの減少分の大きさ−ΔU[J]の100%が重力波として持ち去られるとしても、合体したブラックホールの質量が減らないのが自然です』 |
つまり、インスパイラル期〜合体〜リングダウン期のいずれにおいても、『たとえ「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提の上であっても、連星ブラックホールの質量が減るとは考えにくい』のです。
したがって、『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という一見、もっともに思われる解釈(説明)は、根本的な矛盾を抱えています。
もし、本当に「重力波がエネルギーを持ち去ることによって質量が減るしくみ」があるのならば、これまでの(運動エネルギー=質量エネルギーが増加し続けていることに依存している)連星パルサーについての説明が成立しなくなってしまうのです。
つまり、「LIGOによる重力波を直接観測したことについての説明」と、「M.ワイズバーグ、J.H.テイラー、L.A.ファウラーによる重力波を間接的に観測したことについての説明」は、ともに「重力波がエネルギーを持ち去る」という前提を持っているのに関わらず、互いに矛盾し合っているのです。
その矛盾の本質は、『重力波がエネルギーを持ち去る結果、連星ブラックホールの質量が減る』という解釈(説明)が、『新たに獲得された運動エネルギーが、新たな質量エネルギー(すなわち、質量)になる』という特殊相対性理論の説明と矛盾していることです。
もう1つの矛盾は、100%の真空が存在しないがゆえに、ブブラックホールの周辺にも存在すると考えられる気体分子との関わりの中にあります。
ブラックホールは、周囲の気体分子を吸い込む一方ですので、もはや、『周囲の気体分子による摩擦抵抗による運動エネルギーの一部の熱エネルギーとしての散逸』(参考 結論1-14.3)は、成立しません。
それなのに、公転軌道の収縮が起きるのは、ブラックホールが周囲の気体分子を吸い込む(吸着する)過程が抵抗となり(負の仕事として働き)、ブラックホールの運動エネルギーを減らすからだと考えられます。
すなわち、−ΔU[J]の1/2に相当するブラックホールが獲得する運動エネルギーΔK[J]を「ブラックホールが周囲の気体分子を吸い込む(吸着する)過程の抵抗(負の仕事)」が減らしてくれるおかげで、公転軌道の収縮が起きると考えられます。
※なお、「ブラックホールが周囲の気体分子を吸い込む(吸着する)過程」によって、それぞれのブラックホールが質量を増加させることも、重力>遠心力の方向に働くと考えられます。(重力>遠心力となる条件は、GMm/r2>mv2/r[N]です。この場合、m[kg]がそれぞれのブラックホールの質量で、M[kg]は、重心の質量で、M= m/4[kg]です。よって、GM/r>v2でありさえすれば、すなわち、M=m/4[kg]の大きさ、つまりは、箇々のブラックホールの質量m[kg]が増加しさえすれば、重力>遠心力となることがわかります) この重力>遠心力によって、ブラックホールが獲得する−ΔU[J]の運動エネルギーの1/2を「ブラックホールが周囲の気体分子を吸い込む(吸着する)過程の抵抗(負の仕事)」が減らしてくれると考えられます。この「ブラックホールが周囲の気体分子を吸い込む(吸着する)過程」が生む抵抗(負の仕事)が、ブラックホールの軌道運動の速度が大きければ大きいほど大きくなるからこそ、うまい具合に釣り合いが保たれ(楕円軌道とならずに)公転軌道の収縮が成立するのだと考えられます。詳細な検討は、今後の課題です。
つまり、2つのブラックホールの公転軌道の収縮が、「ブラックホールが周囲の気体分子を吸い込む(吸着する)過程」のおかげ、すなわち、“ブラックホールの質量が増加し続けるおかげ”であることになります。
その意味でも、『重力波がエネルギーを持ち去る結果、連星ブラックホールの質量が減る』という説明は矛盾を抱えていることになります。
※以上を踏まえると、(大きな矛盾を抱えている)「連星ブラックホールの質量が減る」という説明には、「重力波を含めてエネルギー保存則が成り立つはずだ」という前提以外に根拠がどこにもないことがわかります。
つまり、『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という一見、もっともな解釈(説明)は、「重力波を含めてエネルギー保存則が成り立つはずだ」という信念の中で無理してひねり出されたものに過ぎないのです。
ここにあるのも、「エネルギー保存則の封印」(「ヘルムホルツ-クラウジウスの封印」)だと思われます。
(成果6 3《エネルギー保存則(熱力学第一法則)について》)
「リングダウン期には、(インスパイラル期とは異なる)何らかの未知なるしくみがあって、本当に、重力波によるエネルギーの持ち去りによってブラックホールの質量が減るのだ」という可能性を考えることもできるかもしれません。
しかし、「リングダウン期に限って、何らかの未知なるしくみがあって、本当に、重力波によるエネルギーの持ち去りによってブラックホールの質量が減る」と考え続けるのであれば、(アインシュタインがかつて遭遇した)『一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない』ほどの重大な問題に再び直面することになります。
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より p.170〜171 下線は、筆者による) |
すなわち、「リングダウン期に限って、何らかの未知なるしくみがあって、本当に、重力波によるエネルギーの持ち去りによってブラックホールの質量が減る」という解釈(説明)は、結局は、一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるような解釈(説明)なのです。
つまり、「直接観測された重力波(波形)」そのものは、もともと、一般相対性理論を正当化するものであるはずだったのに、その『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という解釈(説明)は、一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるものでもあったのです。
これが、もう1つの矛盾です。
|
素スピノル物理学パラダイムは、(2016年2月に最初に発表された)「LIGOが“重力波”を直接、観測した」という偉大な成果と調和しています(矛盾していません)。
しかし、素スピノル物理学パラダイムは、『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という解釈とは矛盾しています。
そもそも、この『太陽の約36倍と約29倍の質量の連星ブラックホールは、重力波が(太陽の約3倍の)エネルギーを持ち去るので、その分、質虜が減る(太陽の約62倍の質量のブラックホールになる)』という解釈は、(連続な時空&エネルギー保存則を前提とする)一般相対性理論(従来の物理学パラダイム)を忠実に尊重した結果生まれたものでした。
素スピノル物理学パラダイムは、一般相対性理論(従来の物理学パラダイム)について、「重力波がエネルギーを持ち去る(重力波もエネルギー保存則に従う)」→「重力波がエネルギーを持ち去らない(重力波の生成過程は、エネルギー生成過程である)」という修正をせまっています。
※素スピノル物理学パラダイムは、アインシュタインの重力理論に、少なくとも、次の3つの部分的な修正を迫っているのでした。
|
1.時空は連続である
|
→ |
1.時空は不連続である。
|
|
2.重力場は、エネルギー保存則にしたがう。
(重力場のエネルギーを含む全エネルギーは、
エネルギー保存則に従う)
|
→ |
2.重力場は、エネルギー生成過程の所産である。
※重力場は、「重力子&縮みきり“4角形”」の総和として創発するのであり、「重力子&縮みきり“4角形”」の生成過程は、エネルギー生成過程なのでした。
|
|
3.重力場は、非線形である
|
→ |
3.重力場は、線形である。
(重力場のエネルギーそのもそのは、
直接そのまま、質量になりえない)
|
重力波とは、“重力場の波”に他ならないのでした。
したがって、「重力波がエネルギーを持ち去る(重力波もエネルギー保存則に従う)」→「重力波がエネルギーを持ち去らない(重力波はエネルギー非保存の所産である)」という修正は、本質的に、2.の修正と同類であると考えられます。
|