研究論文
『プランクスケールの自然についての幾何的モデルの探究が生む驚異的な成果』
|
成果1
素スピノル重力理論&素スピノル電磁気力理論
|
|
19《アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則》
アンペール-マクスウェルの法則とファラデーの法則は、それぞれ“4つのマクスウェル方程式”の中の1つに相当しているほど重要なものです。
素スピノル物理学パラダイムは、これらのアンペール-マクスウェルの法則とファラデーの法則についても、幾何的モデルを提供します。
(どのようなしくみで、アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則が生じるのかを説明します)
それを以下に示します。
【アンペール−マクスウェルの法則】
アンペール-マクスウェルの法則とは、『電流が流れると、その回りに磁場ができる(右ねじの方向)』というものでした。
「マクロ磁場」や「マクロ電場」を創発するものは、電磁波を構成する“光子”ではなく、“仮想光子”でした。
念のため、仮想光子と光子の比較したものを下に示します。
|
仮想光子
|
光子
|
|
創発するもの
|
(「変形している“4面体”」の総和として)
マクロ電場やマクロ磁場
|
(光子の総和として)
電磁波
|
|
進み方
|
電荷から放出されλ/2[m]だけ進み、
λ/2[m]引き返して、電荷に戻る。
|
λの1/2[m]ずつ、
次から次へと遠方へ進み続ける
|
|
速度
|
光速
|
光速
|
|
しくみ
|
電荷の中の素スピノルと
原始ヒッグス場ユニット(PHU)
中の素スピノルのペアにおける
“スピン1”を保った共転回
(電場のときは後半に逆共転回)
|
2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)
中の素スピノルのペアにおける
“スピン1”を保った共転回
|
電荷から放出され、電荷に再吸収される“仮想光子”についての仮説を再び下に示します。
仮説1-15.1 振動数ν[回/s]、波長λ(=c/ν)[m]の仮想光子は、電荷を構成する素スピノルと、電荷からλ/2[m]の距離だけ離れた「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”」を構成する素スピノルのペアが、スピン1を保ちながら、180度共転回することによって進み、もう一度、共転回することによって元に戻るものに相当する。
仮想光子の場合
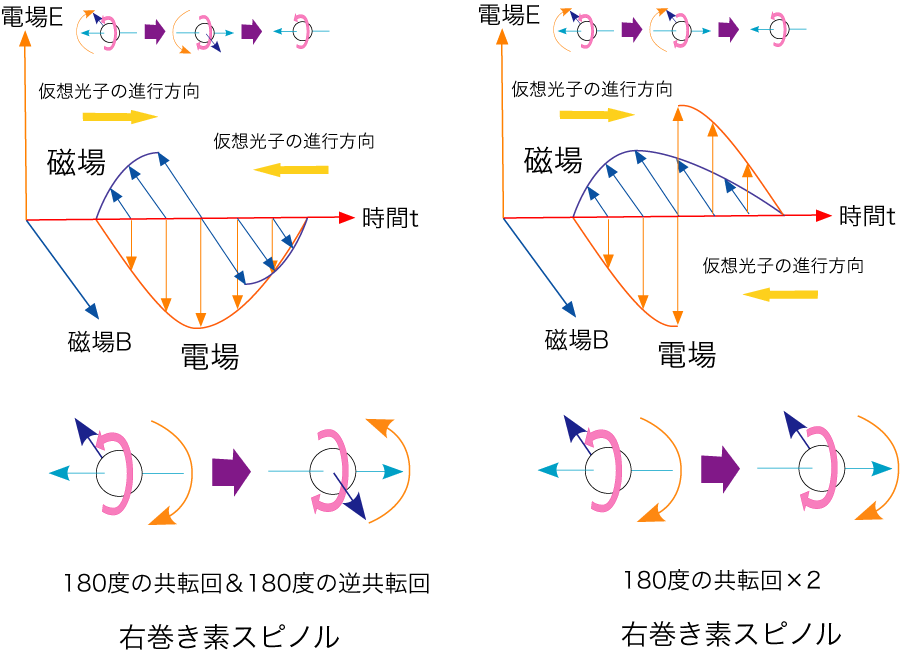
|
※仮想光子の場合、(ふつうの電磁波を構成する光子と違って)“放出源に戻る”という性質を持つことが図示されています。
※上図のように、電場や磁場のどちらか一方が、前半と後半で逆転することにより、仮想光子の進行方向についても『右ネジの法則』が保たれます。
※上図の左側の「180度の共転回&180度の逆共転回」によって生じる仮想光子の方が“マクロ電場”の創発で活躍するものであり、右側の「180度の共転回×2」によって生じる仮想光子の方が、“マクロ磁場”の創発で活躍するものです。
|
仮説1-15.1によれば、電子を構成する左巻き素スピノルと(周囲の、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の中の)“右巻き素スピノル”は、ペアを作って共転回することで、仮想光子を生じます。
(電子が左巻き素スピノルのみで構成されていることについての詳細は、成果2(1《プレオンモデルの予測》 2《電荷の起源》)で述べます。すなわち、厳密には、「電子は、“左巻き素スピノルから構成されるプレオン∴3つ”から構成される」と考えられます)
この“仮想光子”についての仮説に、“電荷が運動すると仮想光子がどのように生ずるか”の考慮を加えるだけで、アンペールの法則を説明できます。
仮説1-19.1 電荷が“相対的に優位になる運動の方向”を持たない場合は、仮想光子の共転回が生じる向きに偏りはないが、電荷が“相対的に優位になる軌道運動の方向”を持つ場合は、その軌道運動の方向と一致する方向への共転回が、他のどの向きよりも、相対的に優位になる。
それは、次のような意味です。
もし、電荷の決まった方向への軌道運動がなければ、下図のように、どの方向への共転回も、等しい頻度で起こりえます。
※決まった方向へ優位となる軌道運動がない場合は、360度の範囲で、どちらの方向への共転回も等しい頻度で起こりえます。
なぜなら、電荷によって生じる共転回の方向は、本来は、(決定論的なカオスによって)、ランダムである(どの方向も等しい確率で生じる)からです。
その結果、プランクスケール磁場は、どの方向についても等しい頻度で生じます。
つまり、プランクスケールの磁場は、各方向が互いに打ち消し合うので、マクロ磁場は創発せず、 マクロ電場のみが創発することになります。 これは、まさに静電場のことです。
|
しかし、電荷が、電流等のように“相対的に優位になる軌道運動の方向”があると状況は一変します。
※上図のように“相対的に優位になる運動の方向”がある場合、「仮説1-17.1」により、360度の中の他のどの向きよりも、紫の長方形で囲った平面の中で図のような方向への共転回が起こる頻度が、相対的に最も優位になります。
詳しく書けば、「“共転回のペア”と“運動のベクトル”を含む平面(紫の長方形で示される平面)の中で、電荷の軌道運動の方向と同じになるような向きの共転回」が、相対的に最も優位になります。
この結果、紫の長方形の中にあるような“プランクスケール磁場”が生じる頻度が最も優位になります。
|
“相対的に優位になる軌道運動の方向”の例は、“電流の逆方向”です。
※「電流の逆方向」とは、「電流に伴う電子の運動の方向」のことであり、当然、電流の向きとは180度逆向きです。
※「電流の逆方向」は、「素スピノルがプランクスケールレベルで持っていると考えられる、決定論的カオスに従う不規則な運動の方向」と区別されます。
※厳密には、電圧をかけられた電子は、一直線に電圧に従って進むのではなく、前後を含めジグザグ運動(決定論的カオスに従う不規則な運動)をしながらも、結果的にトータールで見て、“電流の逆方向”が相対的に優位になります。
ある電荷が“相対的に優位になる軌道運動の方向”が生じると、仮説1-19.1により、相対的に、特定の方向のプランクスケール磁場が優位になります。
そうして優位になったプランクスケール磁場の総和として、マクロ磁場が創発します。
こういった例は、下の図のように示されます。
※導線の中の左巻き素スピノルが電荷を構成する素スピノルであり、電線の周囲の右巻き素スピノルが、原始ヒッグス場ユニットを構成する素スピノルです。
※電流が下から上へ流れると、電子(左巻き素スピノルで構成される)の軌道運動は、当然、上から下に移動する方向が優位になります。
その結果、仮説1-19.1 により、相対的に、上図のような方向の共転回が優位になります。
すなわち、「“共転回のペア”と“運動のベクトル”を含む平面の中で、電荷の軌道運動の方向と同じになるような向きの共転回」が優位になっています。
その際、無限上方〜無限下方に存在する、「上から下に運動している電子の中の左巻き素スピノル」とペアを作るような、電線の周囲の紫の円上に存在する(原始ヒッグス場ユニットの中の)右巻き素スピノルが、上図の向きで優先的に共転回することになり、上図のように、アンペールの法則にピッタリ合致した右回りのプランクスケール磁場が優位になります。
その結果、それらプランクスケール磁場の総和として、アンペールの法則を満たすマクロ磁場が創発することになります。
※共転回する相手の素スピノルの位置に応じて、「立方体の変形」の程度も向きもさまざまに変化しますが、磁場が生じる向きだけは、アンペールの法則に従っています。なお、電場は、プラスマイナス0になるので両方に矢印を示してあります。
|
この考え方によって、マクスウェルが、アンペールの法則を拡張するべく作った式(I=εSdE/dt)が生まれるきっかけとなった現象(後に“変位電流”と名付けられた現象)も説明できます。
その現象とは、「コンデンサーに電荷が蓄えられる過程で、電線のないコンデンサーの周囲にも磁場が作られる現象」です。
(参考 『高校数学でわかる マクスウェル方程式』講談社ブルーバックス 竹内淳)
※電線内で、電子が、相対的に優位になる軌道運動のベクトルが存在するように、コンデンサー内でも、電子が、相対的に優位になる軌道運動のベクトルが生じます。
導線内やコンデンサー内の左巻き素スピノルと、上図の紫の円上に存在する原始ヒッグス場ユニットの右巻き素スピノルとの共転回が、上図の向きで優先的に共転回することによって、上図のような向きのプランクスケール磁場が優位となります。
よって、「“共転回のペア”と“運動のベクトル”を含む平面の中で、電荷の軌道運動の方向と同じになるような向きの共転回」が優位になって生じるプランクスケール磁場の総和として、上図のようなアンペールの法則を満たすマクロ磁場が創発しています。
※充電中のコンデンサーの周囲に磁場が生じる現象は、わざわざ「変位電流によって磁場が生じる現象」という特別な説明するまでもなく、「電線およびコンデンサーの中を運動する電子(左巻き素スピノル)の相対的に優位となる軌道運動によって、磁場が生じる現象」であると、(アンペールの法則のときと同様に)統合的に説明できることになります。
|
以上のことは、素スピノル物理学パラダイムによって、ふつうの電流によって生じる磁場と、変位電流によって生じると考えられた磁場が、統合できることを意味します。
つまりは、以上で、4つのマクスウェル方程式の1つ、「アンペール−マクスウェルの法則」を統合的に説明できたことになります。
※素スピノル物理学パラダイムによれば、アンペール-マクスウェルの法則を説明するために、“変位電流”を考えることが不要になります。
素スピノル物理学パラダイムによれば、アンペール-マクスウェルの法則において実在するのは、“変位電流”ではなく、「電荷が相対的に優位になる軌道運動の方向を持つことのおかげで相対的に優位になって生じるプランクスケール磁場の総和として創発した、マクロ磁場」ということになります。
マクスウェルは、電磁波を説明できることを“変位電流”の根拠の1つとしたのでした。
しかし、電磁波についても、素スピノル物理学パラダイムは、(変位電流を用いずに)共転回の所産として説明できるのでした。
※マクスウェルは、“電荷の移動”の結果生じた「コンデンサーの間の電場の変化」が、コンデンサーの周囲の磁場を生むという考えを数式計算(ガウスの定理も使用)から求めました。
それに対して、素スピノル物理学パラダイムでは、“電荷の移動”そのものが、直接コンデンサーの周囲における(相対的に優位な)磁場を生むとシンプルに考えています。
※“電荷の運動”(原因)と、“新たに生じる磁場”(結果)を結びつける、共転回する素スピノルのペアは、次々と作られる“仮想光子”に相当し、「波長λ[m]/転回周期T[s](=λ/T[m/s])」の値は、光速c[m/s]に他なりません(λ/T=c[m/s])。
このことは、マクスウェルが、数式計算によって、光速を導く過程(電磁波を予想させる波動方程式を導く過程)で、この「アンペール−マクスウェルの法則」も活用したことと調和しています。
※もし、180度の“共転回”が起きたのちに180度の“逆共転回”が起きるとすると(下図の左側)、プランクスケール磁場のN極とS極がすぐに逆転してしまうので、マクロ磁場が創発しないことになってしまいます。(それは、やはり、静電場が創発している状況です)
しかし、180度の“共転回”したのちに180度さらに同じ向きに共転回をしながら仮想光子が逆向きに進むめば(下図の右側)、プランクスケール磁場が逆転しないので、マクロ磁場が創発できることになります。
仮想光子の場合
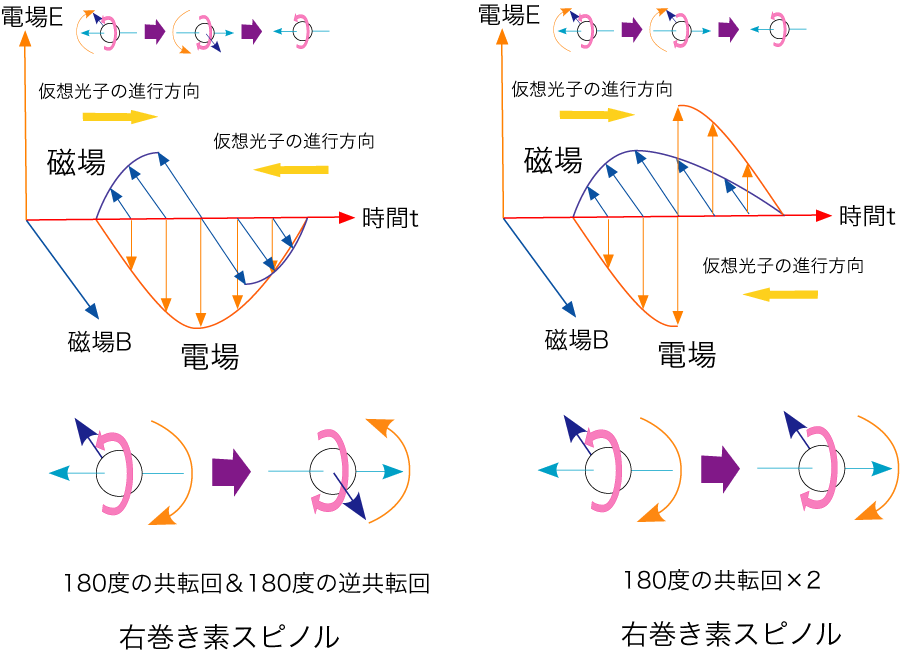
|
※“マクロの磁場”を創発するのは、右側のタイプの仮想光子です。
アンペール-マクスウェルの法則に従うようなマクロの磁場も、右側の「180度の共転回×2」によって生じるタイプの仮想光子によって創発すると考えられます。
※このように、右側の「180度の共転回×2」によって生じる仮想光子の方が“マクロの磁場”の創発で活躍するのに対し、上図の左側の「180度の共転回&180度の逆共転回」によって生じる仮想光子の方が“マクロの電場”の創発で活躍するものです。
|
それでは、静止しているときはプランクスケール磁場が逆転する一方、電荷が軌道運動しているときに限って、プランクスケール磁場が逆転しない原因は、何でしょうか?
その原因は、電荷の軌道運動そのものが、仮想光子を「180度の共転回×2」タイプにするからだと考えられます。
それでは、なぜ、電荷の軌道運動そのものが、仮想光子を「180度の共転回×2」タイプにするのでしょうか?
静止している電荷のそのものが、なぜ、仮想光子を「180度の共転回&180度の逆共転回」タイプにするのでしょうか?
それは、“相対的に決まる”ものに過ぎないのかもしれません。自然(nature)は一つで、見方(観測する座標系)が異なるからなのかもしれません。
なぜなら、たとえある座標系から見て、静止していたとしても、別の座標から見て等速運動していることがありうるからです。
こういった説明は、マクスウェルの方程式が、磁場から電場が生まれたり、電場から磁場が生まれたり、「電場と磁場は、紙一重のものである」と示していることとも調和していると思います。詳細な検討は、今後の課題です。
【ファラデーの法則】
ファラデーの法則とは、『磁束の変化を打ち消す方向に、誘導起電力が生じる』というものです。
このファラデーの法則が意味する「磁束の変化を打ち消す方向に、誘導起電力が生じる」現象には、大きく2つのパターンが考えられます。
1つめのパターンは、下図のように、例えば、導線は静止していて、“ある円形の導線”の中を通る磁束が増えると、その変化を打ち消すような向きに、電場(電位勾配)が生じるというものです。
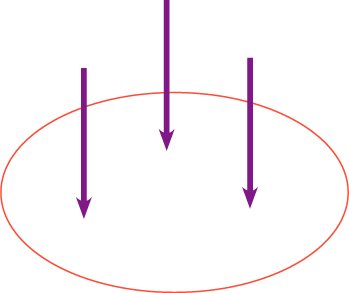 |
→ |
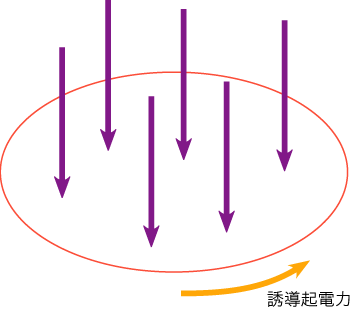 |
& |
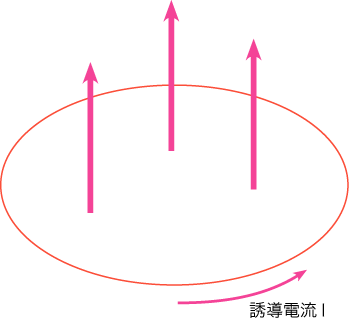 |
| “ある円形の電線”の中を一定の磁束が通っています。 |
|
磁束が変化すると、電線にそって、電場(電位勾配)=誘導起電力が生じます。 |
|
その誘導起電力=電場(電位勾配)によって、生じた誘導電流が、新たに生み出す磁束は、最初の「磁束の変化」を打ち消そうとする方向のものです。 |
2つめのパターンは、下図のように、ある一様な磁場があり、そこを導線が運動することによって、誘導起電力=電場(電位勾配)が生じるというものです。
※一様な磁場の中を、導線が運動していくことによって、導線に誘導起電力が生じます。
これは、「一定の磁場の中を電荷が運動することによってローレンツ力が生じる」ということと等価です。 |
ファラデーの法則を意味する2つの現象は両方とも、数式上は、共通の式で示されます(dφ/dt=誘導起電力 あるいは、マクスウェルの式 rotE=−∂B/∂t)。
これらのファラデーの法則の数式の解釈(幾何的モデル)を示すために、ファラデーの法則を、やはり、この2つのパターンに分けて説明することとします。
1.(導線の回路は一定の中)磁場が増加することで、導線の回路に電場(誘導起電力)を生じる。
2.一定の磁場の中を、導線が運動すると、導線の中の電荷にローレンツ力(電場)が作用する。
|
1.(導線の回路は一定の中)磁場が増加することで、導線の回路に電場(誘導起電力)を生じる。
例えば、永久磁石が運動することによって、磁場が増加する様子は、次のように図示できます。
 |
→
磁場の増加
|
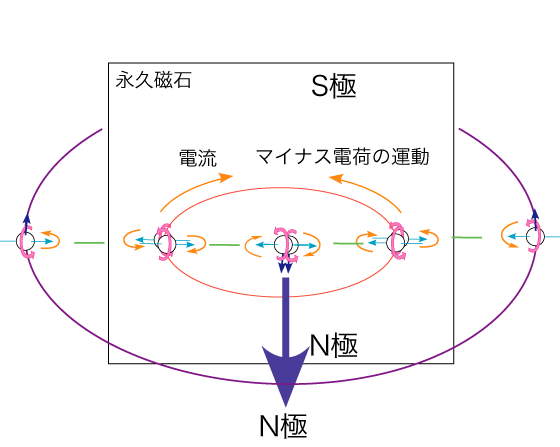 |
|
※永久磁石が、ピンク色の円の中へ向かって運動するとき、ピンク色の円内の磁場が増加する様子を示されています。
※永久磁石の中にはマイナス電荷の軌道円運動(赤色の円上)が存在します。
このマイナス電荷の軌道円運動によって、図のような紫の円上の原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の右巻き素スピノルと、図の向きで優先的に共転回することにより、図のようなプランクスケール磁場が優位になり、その総和としてマクロ磁場が生じています。
※中心部の磁場は、ベクトル和をとることで、はじめて、垂直な磁場となることになります。
それが、紫の大きなベクトルで示されています。
※この場合、紫色の円の中心部の磁場は、2つの理由で、増加します。
1. プランクスケール磁場の角度が、より垂直になる。
→ベクトル和がより大きくなります。
2.共転回のペアの間の距離r[m]が短くなる。
→転回周期Tが短くなるので、個々のプランクスケール磁場が大きくなります。
※もし、永久磁石の代わりに、電磁石を使う場合は、「電磁石の電圧が上がる」ことによって、磁束が増加します。この場合、磁場が増加する理由は、次の理由です。
1.プランクスケール磁場の数が増加する。
|
図では、数個しか示されていませんが、実際は、多数の(無数の)このような共転回が存在します。
そして、その共転回の数だけ、プランクスケール電場やプランクスケール磁場が創発します。
このプランクスケール磁場とプランクスケール磁場が、紫色の円上にどのように創発するかをメインにして、図示すると次のようになる。
※「変形している立方体」を利用して、やや数を増やして図示しています。
※複数のプランクスケール電場が、回路(紫色の円)に沿って、1つの方向にそろって創発しうることが読みとれます。 |
この回路(紫色の円)に沿って創発する、プランクスケール電場の総和が、マクロの誘導起電力と関連していると考えるのは、無理のないことでしょう。
ただし、上の図は、「前半の180度の共転回の間の電場の様子」を示しているにすぎません。
すなわち、もし、磁場が一定になれば(磁石の運動が停止すれば)、仮想光子が放出源に戻る際の、後半の180度の逆共転回の過程が進むことになり、下図のように“プランクスケール電場が打ち消されてしまう”のでした。
| ※2回の共転回により、プランクスケール磁場は同じ向きに生じているのに対し、プランクスケール電場は逆転しています。このことは、磁場が一定となれば(磁石の運動が停止すれば)、プランクスケール電場がプラスマイナス0となることを意味します。 |
このことは、もし、磁場が一定になれば(磁石の運動が停止すれば)、それと同時に、上の仮想光子の振る舞いによって、プランクスケール電場がプラスマイナス0となり、マクロの電場、すなわち、誘導起電力が全く生じなくなってしまうことを意味します。
このことは、逆に言えば、磁場が増加し続けるている場合(磁石の運動が続いている場合)には、新たに共転回するペアが、次から次へと供給され続けるので、「(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)プランクスケール電場」が相対的に優位になり続ける結果、マクロ電場としての誘導起電力が存続できることを意味します。
※磁場が増加し続けるときに限って、この「(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)プランクスケール電場」が優位になり続けます。
|
以上のことは、「誘導起電力が生じるのは、磁場が増加する間に限ってのことである」というファラデーの法則が、なぜ、どのようにして成立するのかを説明しています。
すなわち、磁場が増加している間に限って、フレッシュな共転回が多くなっているので、下図のような、「(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)プランクスケール電場」が相対的に優位になり続けることができ、その総和として、マクロ電場である誘導起電力が存続できるのです。
※磁場が増加しているときに限って、図のように、“(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)プランクスケール電場”が占める割合が、相対的に優位になり続けることになり、その総和として、マクロ電場である誘導起電力が存続できます。
※この存続しているマクロ電場である誘導起電力によって電流が流れたとすると、それによって、(アンペールの法則に従い)新たに生じる磁場は、元々の磁場の増加を打ち消す方向です。
この方向は、「レンツの法則(磁場の変化を打ち消そうとする方向に誘導起電力が生じる)」と調和しています。
|
当然、導線の中に、原始ヒッグス場ユニット(PHU)は、まんべんなく存在しますので、磁場が増加しているときに限って、ほぼ導線全体にわたって、「(誘導起電力を創発しうる、特定の方向の)プランクスケール電場」が優位となりえます。
これらの優位になったプランクスケール電場の総和が、(マクロ磁場に相当する)誘導起電力の実体です。
しかも、この誘導起電力は、「レンツの法則(磁場の変化を打ち消そうとする方向に誘導起電力が生じる)」と調和しています。
以上で、ファラデーの法則の一部(1.(導線の回路は一定の中)磁場が増加することで、導線の回路に電場(誘導起電力)を生じる。)を説明したことになります。
1.(導線の回路は一定の中)磁場が増加することで、導線の回路に電場(誘導起電力)を生じる。
2.一定の磁場の中を、導線が運動すると、導線の中の電荷にローレンツ力(電場)が作用する。
|
次に、ファラデーの法則の残りの部分、「2.一定の磁場の中を、電荷が運動すると、導線の中の電荷にローレンツ力(電場)が作用する。」ことについて説明します。
2. 一定の磁場の中を、導線が運動すると、導線の中の電荷にローレンツ力(電場)が作用する。
一定の磁場とは、何でしょうか?
素スピノル物理学パラダイムでは、次の図ように、「プランクスケール磁場の総和であるマクロ磁場」として、一定の磁場を説明します。
※各プランクスケール磁場の向きが、そろっています。このプランクスケール磁場の総和であるマクロの磁場が“一定の磁場”です。
厳密に言えば、各プランクスケール磁場は、下図のように振動し続けています。
これらの“一定の方向を向くプランクスケール磁場”の総和が、マクロ磁場として観測されていることになります。
※2回の180度の共転回により、プランクスケール磁場は同じ向きに生じ続けているのに対しプランクスケール電場は逆転しています。
そして、なおかつ、プランクスケール電場の向きもバラバラです。したがって、マクロの電場が観測されることはありません。
※4個しか描いていないが、実際は、“(2Lp)3[m3]の体積あたり1つ”を最大限として、びっしりと空間の中に、この「変形している“4面体”」(プランクスケール磁場)が、つまっていることになります。
※永久磁石にせよ、電磁石にせよ、個々の電子にせよ、ふつう、マイナス電荷の運動によって、マクロ磁場が生じています。
(成果2 3《磁極の起源、および“電子のスピン”》)
したがって、このマクロ磁場を構成するプランクスケール磁場(「変形している“4面体”」)は、すべて、原始ヒッグス場の中の右巻き素スピノルが共転回することによって、生じていることになります。
|
つまり、一定の磁場とは、向きがそろったプランクスケール磁場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の右巻き素スピノルの共転回×2によって生じた「変形している“4面体”」)の総和として創発したマクロ磁場なのです。
※なお、プランクスケール磁場においても、N極とともに、S極を示すことができます。
このことは、永久磁石や電磁石の“S極”も、プランクスケール磁場の総和として創発することと調和しています。
|
※原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の素スピノルの転回により、プランクスケール電場とともに、プランクスケール磁場の“N極とS極”が同時に生じています。(→モノポールは、このレベルにおいても、存在していないことになります。なお、素スピノル物理学パラダイムは、モノポールが存在しないことを示しています。→下記)
※地球や電子における磁極とも似ています(相似になっています)。
※なお、「永久磁石や電磁石」は、ふつう、「(左巻き素スピノルから構成されている)電子」のふるまいから生まれていますので、「永久磁石や電磁石」が生じるプランクスケール磁場は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の右巻き素スピノルの共転回によって生じるもの(上図の右側)であると考えられます。
|
このプランクスケール磁場がN極とS極の両方を持つという考えは、アンペール-マクスウェルの法則や、ここまでのファラデーの法則の説明と調和しています。
さて、この一定の(一様な)磁場の中を、電子などの荷電粒子が一定の方向に運動すると何が起こるでしょうかか?
“電荷の流れ”とは、電流に他なりません。
したがって、アンペールの法則に従うように“新たな磁場”が生じます。
※画面(紙面)に対して垂直な向きで手前から奥へ電子が運動しています。
このとき、電流は、逆に、奥から手前へ流れていることになります。
したがって、この図の紫の円上で、新たに生じているプランクスケール磁場の総和(=“新たなマクロ磁場”)が、アンペールの法則に従っていることがわかります。
※電子の近くに図示した、左巻き素スピノルは、すべて、電子を構成する、左巻き素スピノルです。
原始ヒッグス場ユニットの近くに示した、右巻き素スピノルは、すべて、原始ヒッグス場ユニットを構成する、右巻き素スピノルです。
| ※上図では、示せていませんが、実際は |
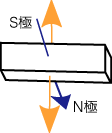 |
のように、プランクスケール電場は、プラスマイナス0となっています。 |
|
よって、こういった磁場を生じるような電子が、例えば、下図のような、「元から存在する“一定の磁場”」の中を、運動するとどうなるでしょうか?
| ※向きがそろったプランクスケール磁場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の右巻き素スピノルの共転回×2によって生じた「変形している“4面体”」)の総和として創発しているマクロ磁場の例です。 |
それは、この一定の磁場に、次のような磁場を重ね合わせることに他なりません。
すると、下図のように、相対的に、(上下方向でも斜め方向でもなく)左右方向において、最も顕著な「プランクスケール磁場の数の差」が生まれることになります。
※電子の運動方向に対して、左側で、プランクスケール磁場が最も増加するのに対して、右側で最も減少することになります。
なぜなら、電子の軌道運動方向の左側においては、元からあるマクロ磁場と全く同じ方向にプランクスケール磁場が生じ増加する一方、電子の軌道運動方向の右側においては、プランクスケール磁場がキャンセルされ、減少すると考えられるからです。
なお、キャンセルされるとは、「“4面体”の変形(by右巻き素スピノル)」が、運動する電子の中の左巻き素スピノルとの共転回によってキャンセルことであり、エネルギーが最低の、元の“4面体”に近づいていくこと(原始ヒッグス場抵抗が増加すること)を意味します。
電子からの距離が小さくなるのに反比例して、(アンペールの法則にしたがって生じる)プランクスケール磁場が大きくなるので、キャンセルの度合いも、それに応じて大きくなると考えられます。
よって、電子の運動(電子に働く力)に影響する“原始ヒッグス場抵抗”の作用は、電子に近いほど大きくなることになります。
※「プランクスケール磁場の増加」が生じるのも「プランクスケール磁場のキャンセル」が生じるのも、いずれのプランクスケール磁場も、原始ヒッグス場ユニットの中の右巻き素スピノルの転回に伴って生じているからこそ生じます。
(なお、運動する電子も、電磁石も、永久磁石も、その中の左巻き素スピノルが、プランクスケール磁場を生じるのでした) |
したがって、電子の運動によって、「電子の進行方向からみて左側の原始ヒッグス場抵抗が小さくなり、右側の原始ヒッグス場抵抗が大きくなる傾向」が創発することになります。
それは、まさに、電子に対して働く力が創発したことに他なりません。
つまり、これが、まさに、ローレンツ力が創発したことに相当しています。
当然、実際は、例えば、下図のような“導線の運動”に伴って、導線の中の多数の自由電子が運動することになります。
※一様な磁場の中を、導線が運動していくことによって、導線に誘導起電力が生じます。
これは、「一定の磁場の中を電荷が運動することによってローレンツ力が生じる」ということと等価です。 |
その結果、「電子の進行方向からみて左側の原始ヒッグス場抵抗が小さくなり、右側の原始ヒッグス場抵抗が大きくなる傾向」も、電子数に比例して増加するでしょう。
 |
※核電子についている紫色の矢印は、「電子の運動の向き」を示しています。
オレンジ色の大きな矢印は、「(紫色の矢印の向きに運動する)“マイナス電荷を持つ電子”に働く力の向き」です。
オレンジ色矢印の方向に力が生じるのは、「電子の進行方向からみて左側の原始ヒッグス場抵抗が小さくなり、右側の原始ヒッグス場抵抗が大きくなる傾向」が創発しているからです。
この力の向きは、“ローレンツ力の向き”(フレミングの左手の法則)と調和する方向のものです。
※この説明は、一定な磁場が「運動するマイナス電荷」によって作られた(準備された)中を、「マイナス電荷」が運動する場合(あるいは、一定な磁場が「運動するプラス電荷」によって作られた(準備された)中を、「プラス電荷」が運動する場合)に限って、成立する説明であるようです。
なぜなら、一定な磁場が「運動するマイナス電荷」によって作られた(準備された)中を、「プラス電荷」が運動する場合(あるいは、一定な磁場が「運動するプラス電荷」によって作られた(準備された)中を、「マイナス電荷」が運動する場合)は、右側も左側も、“4面体”の変形が“増幅”するだけで、“キャンセル”が生じないようだからです。
※例えば、上図が、一定の磁場(マクロ磁場)を担うプランクスケール磁場だとします。
この状況で、運動する電子(左巻き素スピノル)と原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の右巻き素スピノルの共転回が成立すれば、増幅(“原始ヒッグス場抵抗”の減少)やキャンセル(“原始ヒッグス場抵抗”の増加)のどちらともが生じえます。
しかし、この状況で、運動する陽電子(右巻き素スピノル)と原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の左巻き素スピノルとの共転回が成立すれば、増幅(“原始ヒッグス場抵抗”の減少)しか起こらないようです。 |
|
素スピノル物理学パラダイムは、例えば、「もし、上と同じ状況で、電子(負電荷)のかわりに、陽電子(正電荷)が、同じ方向に運動していたとしたら、ローレンツ力の向き”の方向は、上のオレンジ色の矢印とは逆向きとなる」とは限らないこと、「もし、上と同じ状況で、一定の磁場が運動するプラス電荷によって作られていたとしたら、ローレンツ力の向き”の方向は、上のオレンジ色の矢印とは逆向きとなる」とは限らないことを示しているようです。
この系は、検証実験の1つとなりうるのかもしれません。詳細な検討は、今後の課題です。 |
以上により、「一定の磁場の中を、電荷が運動すると、なぜ、どのようにして、その方向にローレンツ力が生じるのか?」を説明できたことになります。
つまりは、この説明によって、「なぜ、どのようにして、ファラデーの法則が成り立つのか」の残り半分も説明できたことになります。
1.(導線の回路は一定の中)磁場が増加することで、導線の回路に電場(誘導起電力)を生じる。
2.一定の磁場の中を、導線が運動すると、導線の中の電荷にローレンツ力(電場)が作用する。
|
以上より、アンペール・マクスウェルの法則、ファラデーの法則、電磁波… について、素スピノル物理学パラダイムによって説明できたことになります。
なお、“電荷のガウスの法則”については、の16《静電気力と磁力(電荷と磁極のクーロンの法則)および、重力と電磁気力の統合》の「どのようなしくみで(なぜ)、(電場の)ガウスの定理が成り立つのか?」にて説明しました。
したがって、以上により、「4つのマクスウェルの方程式」の4つの中の“磁荷のガウスの法則”(モノポールは存在しない)以外をすべてを説明したことになります。
素スピノル物理学パラダイムは、モノポールが存在しないことを示しています。
その理由は、次の4つです。
1.電荷の軌道運動から創発する磁極は、必ず、N極とS極が必ず同時に創発します。
したがって、電荷の軌道運動から創発する磁極は、モノポールでありえません。
2.原始ヒッグス場ユニット(PHU)から生まれるプランクスケール磁場においても、N極とS極が同時に生じますので、モノポールでありえません。
3.単独の素スピノルも、モノボールではありえません。
なぜなら、単独の素スピノルが磁極を持つとすると、マクスウェル・アンペールの法則、ファラデーの法則と調和する形で磁場の創発を説明できなくなるからです。
また、単独の素スピノルがモノポールであれば、ニュートリノが大きな磁極を持つことになり、観測結果と矛盾してしまいます。
4.仮に、例えば、マイナスプレオンを構成する、素スピノルの軌道運動が磁気モーメント(磁極)を生むとしても、やはり、N極とS極が同時に創発することに変わりありません。
|
このことは、“磁場のガウスの法則”(モノポールは存在しない)という、「4つのマクスウェルの方程式」の1つとも調和しています。
マクスウェルの方程式で説明されることがら(アンペール・マクスウェルの法則、ファラデーの法則、“磁荷のガウスの法則”(モノポールは存在しない)、“電荷のガウスの法則”、電磁波…)の解釈として、「仮想光子の創発(素スピノル同士の共転回)と、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形」という幾何的モデルを素スピノル物理学パラダイムが提供しています。
こういった素スピノル物理学パラダイムが提供する幾何的モデルは、「なぜ、どのようにして、マクスウェルの4つの方程式が成り立つのか?」の説明を可能にします。
それは、「マクスウェルの方程式」という抽象的な数学の解釈を重視し、プランクスケールの自然(nature)の幾何的モデルを探求することの重要な成果の1つなのです。
|