15《(クーロンの法則を担う)電場や磁場を創発する仮想光子》
原始ヒッグス場は、重力場のみならず、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」も創発します。
重力場が、原始ヒッグス場の上の「重力子&縮みきり“4角形”」の総和として、創発する一方、電磁場は、原始ヒッグス場の上の「仮想光子&変形している“4面体”」の総和として創発します。
|
(万有引力の法則や一般相対性理論を担う)
重力場
|
(クーロンの法則を担う)
電場と磁場
|
|
どこで創発するか
|
ともに、
「原始ヒッグス場」の上で創発する
|
|
何によって創発するか
|
「重力子&縮みきり“4角形”」
の総和として
|
「仮想光子&変形している“4面体”」
の総和として
|
※「原始ヒッグス場」とは、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和のことです。
原始ヒッグス場の上で、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」を創発するものは、あくまで“仮想光子”の総和であり、“光子”の総和ではありません。 “光子”の総和が創発するものは、電磁波です。
「電磁波を担う“光子”」によって変形される原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する素スピノルが転回する際に生じる「プランクスケールの電場やプランクスケールの磁場」の向きは、下のようなルールに従っているのでした。
光子の場合
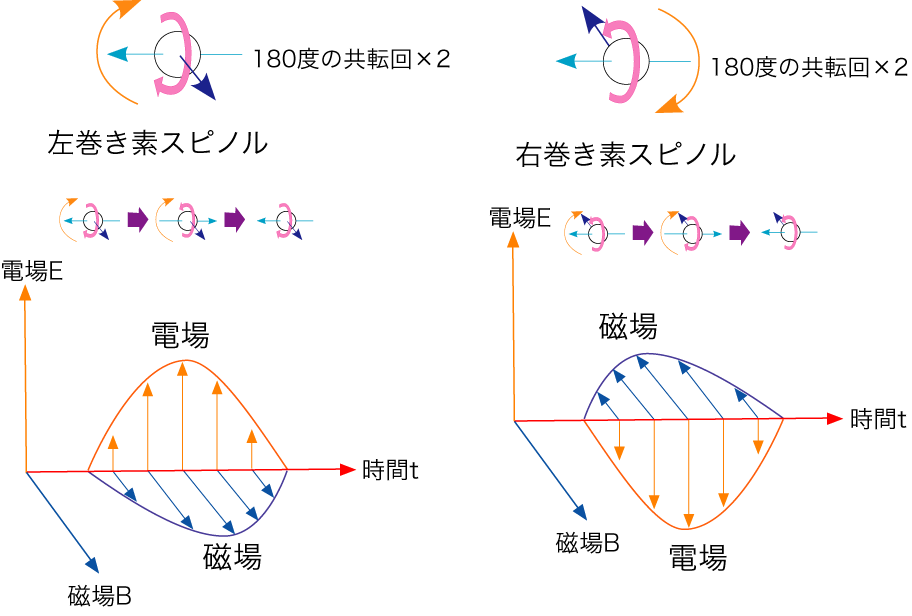
|
ルール1 左巻き素スピノルが転回する向きに対して、左ねじの方向に磁場が生じる。
右巻き素スピノルが転回する向きに対して、右ねじの方向に磁場が生じる。
ルール2 ルール1で決まる磁場に対して、 光子の進行方向について『右ネジの法則』が成立する向きに電場が生じる。
|
上図のような、電磁波を担っている光子が作る「プランクスケールの電場やプランクスケールの磁場」は、クーロンの法則を担っていません。
クーロンの法則を担うのは、光子ではなく、仮想光子です
このクーロンの法則を担う「電場や磁場」の創発を支える1つ1つの“仮想光子”が生じるプランクスケールの電場や、プランクスケールの磁場の振る舞いについては、素スピノル物理学パラダイムは、次のような仮説を立てます。
仮説1-15.1 振動数ν[回/s]、波長λ(=c/ν)[m]の仮想光子は、電荷を構成する素スピノルと、電荷からλ/2[m]の距離だけ離れた「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”」を構成する素スピノルのペアが、スピン1を保ちながら、180度共転回することによって進み、もう一度、共転回することによって元に戻るものに相当する。
(仮想光子によって変形される)原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する素スピノルの挙動を図示すると次のようになります。
仮想光子の場合
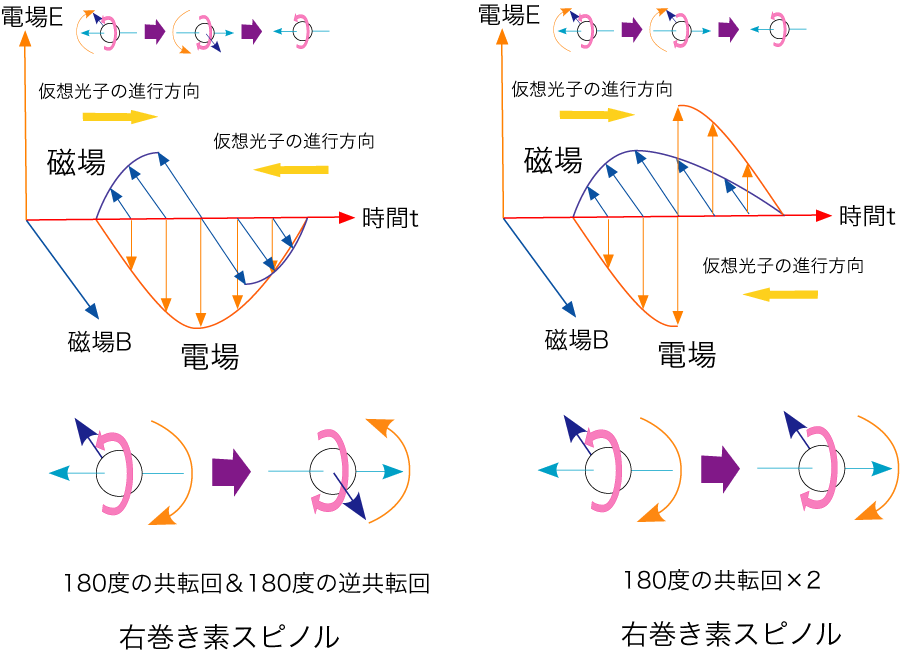
|
※仮想光子は、電磁波を構成する光子と違い、“放出源に戻る”という性質を持ちます。
仮想光子の進行方向が『 → ← 』のように途中で逆転している様子が図示されています。
※上図で示されているように、仮想光子の進行方向が前半と後半で逆転することによって、プランクスケールの電場やプランクスケールの磁場のどちらか一方だけが途中で逆転しています。したがって、プランクスケールの電場やプランクスケールの磁場が逆転していない方、すなわち、「左図の電場」や「右図の磁場」がそれぞれマクロの電場や、マクロの磁場の創発に役立つことになります。
※最初に共転回した方向とは逆方向に共転回することを、逆共転回と呼ぶこととします。
この逆共転回は、上図の左側においてのみ生じています。(右側では、逆共転回はしておらず、仮想光子の進行方向のみが逆転しています。
※プランクスケール電場とプランクスケール磁場は、常に同時に生じています。
この幾何モデルは、電場と磁場が、常に互いに“直角に存在する”ことを、ピッタリと説明できます。
この電場と磁場が“直角に存在する”ことにより、例えば、アンペールの法則(電流の周りに磁場が生じる)や、ファラデーの法則(磁場の変化に伴い電場が生じる)も、うまく説明できます。
(17《アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則》)
※これらのいずれの過程においても、仮想光子の進行方向について『右ネジの法則』が成立しています。
|
|
『〜光の進行方向を表すベクトルと電気・磁気ベクトルは、たがいに「右ネジの法則」の関係にあることがわかっている。 〜電気ベクトルから磁気ベクトルに向けて右ネジをまわす(時計まわりにする)と、ネジの進む方向が光の進行方向(〜)に一致する。』(『対称性から見た物質・素粒子・宇宙 鏡の不思議から超対称性へ』(広瀬立成 講談社ブルーバックス)p69-70より) 下線および一部省略は、筆者によります。
|
以後、このように、光子や仮想光子が原始ヒッグス場ユニット(PHU)を変形することで生ずる「プランクスケールの電場」と「プランクスケールの磁場」のことを、簡単に、プランクスケール電場、プランクスケール磁場と呼ぶこととします。
仮想光子が生むプランクスケール電場やプランクスケール磁場の総和として、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」が創発します。
すなわち、常に同時に生じているはずのプランクスケール電場とプランクスケール磁場が、複数(多数)、うまい具合に配置されたときにはじめて、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」(「マクロの電場」や「マクロの磁場」)が創発することになります。
※(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」(「マクロの電場」や「マクロの磁場」)を、必要に応じて、簡単に、マクロ電場やマクロ磁場と呼ぶこととします。
そういう意味では、マクロ電場が創発するか、マクロ磁場が創発するかは、“紙一重である”とも言えます。
※仮説1-15.1の中の「電荷を構成する素スピノル」という記述は、電荷が複数の素スピノルから創発するものであることにもとづいています。
具体的には、「最も小さい“電荷”」は、(3つの素スピノル(左巻きのみor右巻きのみ)から創発する)荷電プレオン∴です(左巻きのみならマイナス、右巻きのみならプラス)。(成果2 2《電荷の起源》)
例えば、電子は、この荷電プレオン∴(の一種であるマイナスプレオン)3つで構成されています。(成果2 1《プレオンモデルの予測》)
つまり、「電子は、“左巻き素スピノル3つから構成されるマイナスプレオン∴”が、3つ集まっているものである」ということになります。
したがって、仮説1-15.1をより厳密に書けば、「電子を構成する左巻き素スピノルと、(周囲の、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の中の)“右巻き素スピノル”がペアを作って共転回することで仮想光子を生じる」ということになります。
※この素スピノル物理学パラダイムにおける仮想光子の幾何的モデルは、次のような記述で示される状況に対して、1つの答え(解決案)を提供していることになります。
『仮想光子は何らかの計測器で直接検出されることが期待されるが、その概念は定まっておらず、またその存在を証明するのはきわめて困難である。事実、仮想光子は、きわめて抽象的な状態にとどまり、いまだ確かになっていない理論の産物である』(p.127 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』 Eugene Hecht著、尾崎義治・朝倉利光訳 丸善株式会社) 下線は筆者によります。
|
ここで、光子と仮想光子を比較して整理すると、次のようになります。
|
光子
|
仮想光子
|
|
1つ1つが創発するもの
|
(前半と後半でどちらも打ち消されないような)
プランクスケール電場、プランクスケール磁場
|
(前半と後半で一方は打ち消されてしまうような)
プランクスケール電場、プランクスケール磁場
|
|
総和(集合)が創発するもの
|
電磁波
|
マクロ電場やマクロ磁場
|
|
進み方
|
λの1/2[m]ずつ、
次から次へと遠方へ進み続ける
|
電荷から放出されλ/2[m]だけ進み、
λ/2[m]引き返して、電荷に戻る。
|
|
速さ
|
光速
|
|
しくみ
|
(2つの)「原始ヒッグス場ユニットの
中の素スピノル」のペアにおける
スピン1を保った共転回
|
「電荷の中の素スピノル」と
「原始ヒッグス場ユニットの
中の素スピノル」のペアにおける
スピン1を保った共転回(or逆転回)
|
厳密に言えば、プランクスケール電場やプランクスケール磁場は、決して、「個々の素スピノルのペア」だけから生じるわけではありません。
あくまで、「原始ヒッグス場ユニットの“4面体”」の中の、特定の素スピノルが転回することによって生じる「変形している“4面体”」がプランクスケール電場やプランクスケール磁場を生むのです。
※プランクスケール電場やプランクスケール磁場は、原始ヒッグス場ユニットの「変形している“4面体”」として創発します。
したがって、実際は、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”は、変形し続けているので、プランクスケール電場、プランクスケール磁場も変化し続けていることになります。
それらの「変形している“4面体”」を、上図のような「変形中の直方体」で図示することとします。
こうすることで、電場と磁場の関係がわかりやすくなり、便利です。
(プランクスケール電場とプランクスケール磁場が必ず直交するので、このようなことができます)
なお、「変形中の直方体」の図中の電場や磁場のベクトルは、当然、時間tを横軸にした図のような経過で“変化し続けている”ことになります。
だからこそ、 「変形した“4面体”」ではなく、「変形している“4面体”」と記述していることになります。
この「プランクスケール電場&プランクスケール磁場の総和」(=「変形している“4面体”」の総和)として、「マクロ電場やマクロ磁場」が創発します。
|
以上の「変形中の直方体」表示を用いて、仮想光子におけるプランクスケール電場やプランクスケール磁場を図示すると次のようになります。
※「仮想光子の場合は、(電磁波を構成する光子と違い)“放出源に戻る”という性質を持つ」ということを反映している図が示されています。
※上図のように、電場や磁場のどちらか一方が、前半と後半で逆転することにより、仮想光子の進行方向についても『右ネジの法則』が保たれていることが、「仮想光子が持つ“放出源に戻る”という性質」を支えているのでした。
※上図の左側の「180度の転回&180度の逆共転回」の方は、プランクスケール磁場のみが前半と後半で打ち消し合っています。
よって、この「180度の転回&180度の逆共転回」のタイプの「仮想光子&変形している“4面体”」が数的に優位になっている場合、マクロ電場が創発していることになります。
逆に、右側の「180度の転回×2」の方は、プランクスケール電場のみが前半と後半でともに打ち消し合っています。この「180度の転回×2」のタイプの「仮想光子&変形している“4面体”」が数的に優位になっている場合は、マクロ磁場が創発していることになります。 |
こういった仮想光子の所産であるプランクスケール電場やプランクスケール場の幾何的モデルを組み合わせることで、(クーロンの法則を担う)「電場や磁場」を含めて、さまざまな“マクロ電場”や“マクロ磁場”の創発を説明できます。
さらには、電荷が生む“仮想光子”についての仮説に加えて“電荷が運動すると仮想光子がどうなるか”を考慮することで、アンペール-マクスウェルの法則やファラデーの法則を説明できます。(17《アンペール-マクスウェルの法則、ファラデーの法則》)
つまり、あらゆる「マクロ電場やマクロ磁場」は、「プランクスケール電場&プランクスケール場の総和」(=「仮想光子&変形している“4面体”」の総和)として創発すると説明できるのです。
※電荷からの距離 r[m]が大きくなればなるほど、仮想光子の転回周期Tも大きくなります(=振動数ν[回/s]が小さくなり、波長λ[m]が長くなります)。
仮想光子の転回周期T[s]は、 T=2r/c[s]で計算できのでした。(なぜなら、c=νλ=λ/T[m/s]、r=λ/2[m]だからです)
一方、転回周期T[s]が大きくなると同時に、仮想光子による180度転回に伴うエネルギー振幅E[J]は、逆に小さくなります。
なぜなら、アインシュタインの式E=hν[J]より、光子のエネルギーE=hν=h/T[J]、つまり、ET=h[J・s]が成り立つからです。
(それは、不確定性原理の式とも、おおよそ合致するものです。
成果3 10《不確定性原理(不確定性関係)と確定性原理(単振動振幅の確定性関係)》)
これらのことは、仮想光子は、決して、ランダムなエネルギーを持つものではないことを意味しています。
すなわち、遠ざかれば遠ざかるほど、E=hc/r[J]に反比例して、仮想光子が生じるエネルギーが小さくなります。
このあたりには、量子電磁力学(QED)(“電荷&電磁気力”の場の量子論)において、無限大を生じさせないヒントの1つ、“くり込み”を不要にさせるヒントの1つがあると思われます。(もう一つの、無限大を生じさせないヒント、“くり込み”を不要にさせるヒントは、電磁場を原始ヒッグス場ユニットの集合と見る見方(時空に最小の単位があるという見方)です)
|