研究論文
『プランクスケールの自然についての幾何的モデルの探究が生む驚異的な成果』
|
成果1
素スピノル重力理論&素スピノル電磁気力理論
|
|
13《重力場の線形性について(詳細版)》
従来の物理学パラダイム(アインシュタインの一般相対性理論)によると、重力場が非線形であると説明されてきました。
しかし、素スピノル物理学パラダイムによると、重力場が線形であると考えられます。
重力場が線形だと考えられる理由を挙げると、次のようになります。
1.重力場のエネルギーは、通過してくる「重力子&縮みきり“4角形”」のエネルギーの総和にすぎない。
※その結果、“重力場のエネルギー”そのものは、質量(重力子の放出源として働き続ける能力)となりえません。
2.始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)は、調和振動子(単振動する系)の一種であり、重力場は、「重力子&縮みきり“4角形”」の単純な総和(足し算)として創発する。
※その結果、計算は、単純になります。
3.運動エネルギーの増加が、質量エネルギーの増加(重力子の放出源の増加)の実体である。
※その結果、質量エネルギー(運動エネルギー(内部&外部)の総和)と重力場(放出される「重力子&縮みきり“4角形”」の総和)は比例し続けます。
|
よって、素スピノル物理学パラダイムは、次の結論に至ります。
結論1-13.1 重力場は、線形である。
それでは、従来の物理学パラダイム(アインシュタインの一般相対性理論)において、“重力場が非線形である”と考えられてきた次の理由(根拠)は、どのように説明されるのでしょうか?
1.アインシュタイン方程式が、「重力場のエネルギーは、新たな質量、すなわち、新たな重力子の放出源として働き続ける能力(=新たな“時空の曲がり”の原因)である」という考えを用いて導出されている。
2.アインシュタインの重力場方程式の中の曲率そのものが、計量gμνの非線形な式となっている。
3.重力ポテンシャルエネルギーの大きさが、重力が弱い場合、「線形なニュートンの重力理論が示すように、GM/r[J]」となるのに対し、重力が非常に強い場合には「一般相対性理論が示すように2GM/r[J]」になる。
|
※これらの1〜3は、「 重力場が線形だと考えられる理由1〜3」 と、それぞれ関連しています。
以下で、それぞれについて詳しく説明します。
1.アインシュタイン方程式が、「重力場のエネルギーは、新たな質量、すなわち、新たな重力子の放出源として働き続ける能力(=新たな“時空の曲がり”の原因)である」という考えを用いて導出されている。
素スピノル物理学パラダイムは、「重力場のエネルギーが、新たな質量、すなわち、新たな重力子の放出源として働き続ける能力(=新たな“時空の曲がり”の原因)になる」という考えは、自然(nature)から乖離していることを示しています。
すなわち、10《重力場、エネルギー、質量》で示したように、素スピノル物理学パラダイムは、『重力場のエネルギーは、質量を持っていない。』という結論にいたります。
この結論は、“抽象的な数式”の解釈を軽視している限り、絶対にたどり着けない結論と言えるかもしれません。
なぜなら、『「あらゆるエネルギーは質量を持つ」→「重力場は、エネルギーである」→「重力場は、質量である」』という論理の流れ自体は、100%正しくて非の打ち所がないからです。
すなわち、「E=mc2」から導く「あらゆるエネルギーは質量を持つ」という解釈の部分を慎重に吟味しなければ、(それ以降の論理展開自体は100%正しいので)「重力場は、質量である」という考えの中にひそむ、自然(nature)からの乖離性に気づくことができないのです。
しかし、「E=mc2」という数式が持つ本当の意味、すなわち、その数式が意味する具体的な幾何的モデルを重視すれば、「あらゆるエネルギーは質量を持つ」
「重力場がエネルギーを持つので重力場も質量を持つ」「“重力場のエネルギー”そのものを“質量”と見なし、新たな“時空の曲がり”の原因として方程式に代入するべきである」──いずれの説明も、自然(nature)から乖離していること)に明確に気づくことができます。
素スピノル物理学パラダイムによれば、「重力場のエネルギーそのものが、新たに重力子を放出する源として働き続ける能力を持つ(=新たに質量を持つ)」という意味での非線形性は実在しないと、はっきり断言できます。
なぜなら、『重力場のエネルギーと質量が全く別物であること』(=『通過してしてくる「重力子&縮みきり“4角形”」のエネルギーの総和と「重力子&縮みきり“4角形”」の放出源として働き続ける能力、が全く別物であること』)は明白だからです。
つまり、やはり、少なくとも「重力場のエネルギー(通過してくる「重力子&縮みきり“4角形”」のエネルギーの総和)=質量(「重力子&縮みきり“4角形”」の放出源として働き続ける能力)」という意味での非線形性は、自然(nature)の中には、実在しないのです。
※「重力場のエネルギーそのものが質量にならない」ということは、当然、「重力場のエネルギーが質量になり、その質量がさらに新たな重力場を生み、またその新たな重力場のエネルギーそのものが、新たな質量になり… と限りなく繰り返すよう非線形性」もないということです。
※「重力場が、新たな質量になる」「重力場が新たな質量になり、その新たな質量から、さらに新たな重力場が生まれる」という「重力場の非線形性」のアイデアは、他ならぬ、偉大なアインシュタインの心の中から始まったと言えます。
その根本理由は、“E=mc2”という抽象的な数式から、「エネルギーは質量を持つ」という自然(nature)から乖離している、恣意的な解釈を最初に導いたのがアインシュタインだったからです。
「エネルギーは質量を持つ」を前提とすれば、「(エネルギーを持つ)重力場が、新たな質量になるのだ」という考えが、自然(nature)から乖離していることに気づくことができなくなるのは当然です。すなわち、「 E=mc2」という抽象的な数式だけを重視し、その解釈、すなわち、プランクスケールの自然(nature)についての具体的な幾何的モデルを軽視している限り、ここにある自然(nature)からの乖離性に気づくことができなくなるのは当然なのです。
(つまり、抽象的な数式(例えば、“E=mc2”)は、慎重に扱わないと、人を裏切りうるのです)
E=mc2は、本来、決して「あらゆるエネルギーが質量を持っていること」を示す式ではありえません。
実際は、質量とエネルギーは、100%等価ではないのです。
その理由を整理すると、次のようになります。
|
1.エネルギーを持っている「光子や重力子、電磁波や重力波」が光速で移動できることは、エネルギーを持っていても質量を持たないことがある例の1つである。
※そもそも、「あらゆるエネルギーが質量を持っている」という解釈や前提は、アインシュタイン自身が提唱した、光量子仮説の式E=hν[J]と矛盾してしまっています。
2.質量とは、「重力子の放出源として働き続ける能力」であり、質量エネルギーE=mc2とは、「静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー」、すなわち、運動エネルギー(内部&外部)に他ならない。
※つまり、質量と等価なのは、「エネルギー」ではなく、「運動エネルギー(内部&外部)」なのです。
3.エネルギーには、質量エネルギー(=運動エネルギー(内部&外部))のほかに、少なくとも、光子のエネルギー、重力子のエネルギー、電磁波のエネルギー、重力波のエネルギー、電磁場のエネルギー、重力場のエネルギー、電荷のエネルギー、磁極のエネルギーもある。
※これらの質量エネルギー(=運動エネルギー(内部&外部))以外のエネルギーは、いずれも“重力子の放出源として働き続ける能力”を持っていません。
|
このように、「あらゆるエネルギーが質量を持っている」という解釈が自然(nature)と乖離していること示しているものには、単に、素スピノル物理学パラダイムのみならず、「光量子仮説の式E=hν[J]との矛盾」もあるのです。
※そういう意味では、「mc2=E」、あるいは、「Em=mc2」が、「誤解釈、誤用、濫用…」を予防する表記と言えるのかも知れません。
※なお、例えば、光子によって、電子や陽電子のペアが対生成したり、原子が(外部)運動エネルギーを獲得して熱を持ったりする過程は、新たな質量の生成を意味するので、光子のエネルギーが“質量に変換される”ということはありえます。
また、例えば、ある物体が、その物体に蓄えられた重力ポテンシャルエネルギー(重力場のエネルギー)を利用して、(外部)運動エネルギーを獲得した場合も、新たな質量の生成を意味するので、ある物体に蓄えられた重力ポテンシャルエネルギーが“質量に変換される”ということもありえます。
(質量エネルギーとは、静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギーの和でした)
しかし、だからといって、光子や重力場自体が質量(重力子の放出源として働き続ける能力)を持っているわけではありません。あくまで新たに獲得された(外部)運動エネルギーが質量(重力子の放出源として働き続ける能力)を持っているのです。
それでは、「重力場のエネルギーが質量となるという」考えを盛り込んで導出されたアインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)は、間違いなのでしょうか?
いよいよ、そのことを検討してみましょう。
『アインシュタイン選集2』の「物質が存在しないときの重力場の方程式」(p92〜)の項目に次のように書かれています。
|
『たとえば1個の質点によって、そのまわりにつくられた重力場を考えてみよう。この重力場はどんな座標系を採用しても、それを消し去ることはできない。すなわち、gμνを質点のまわりで至る所, 定数のgμνに変換することはできない(訳者注:質点のまわりでは物質は存在しないが、重力場は存在する。 〜)。
そこで、物質が不在の場合の重力場の方程式として、テンソルBσμστから導かれた対象テンソルBμνを0とおくことは、きわめて自然な要求であろう。こうして、10個の量gμνに対して10個の方程式が得られたわけである。 これらの式は、Bσμστがすべて0のときには、もちろん満足される。これらの式は、われわれに好都合な座標系では、(44)を考慮に入れて
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =0
|
(47)
|
| (−g)1/2=1 |
となる。 これが物質が存在しない所での重力場の方程式である。
〜
一般相対性の要求から、まったく数学的な方法で導かれたこれらの場の方程式は、一方質点の運動方程式(46)といっしょになって、第一近似ではニュートンの引力の法則を与える。また第二近似まで考えると、ルヴェリエ(Leverrier)によって発見された水星の近日点の移動(他の惑星による摂動に由来する修正を行なったあとに残る移動量)を説明することができる。これらの事実は、ここに展開された理論が物理的に正当である証拠であると見なしてよいと思う』
(p.93〜94 『アインシュタイン選集2』) 一部省略しました。下線は筆者によります。数式は、入力の都合上、表記法を変えてありますが、その内容は元の数式と同等のものです。
|
この「物質が存在しないときの重力場の方程式」は、下の一番左の図のものに相当すると見なせます。
|
|
|
|
※一番左の図は、「物質が存在しないときの重力場の方程式」、すなわち、「1個の仮想的な質点によって、そのまわりにつくられた重力場」に相当すると見なせます。
それに対して、右側の2つは、物質が存在するときの重力場を表していると見なせます。
仮想質点と物質の“重力子の放出源として働き続ける能力”が全く等しいので、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、3つとも、全く等しくなっているのでした。
|
|
このことは、「物質がないときの重力場」(=「1個の仮想的な質点によって、そのまわりにつくられた重力場」)と「物質があるときの重力場」は、“密度の違い”があるだけで、重力場を作る能力は、本質的には同じだと見なせることを意味します。
つまり、このことは、「物質が存在しないときの重力場の方程式」、すなわち、「(物質が存在せず)質点のみがあるとときの重力場の方程式」として、考え出された(47)の式だけで、本質的には、もう十分であることを示しているのです。
現に、それだけで、少なくとも、ニュートンの引力の法則も、水星の近日点移動も説明できています。
ところが、物質が存在しない所での重力場の方程式である式(47)──
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =0
|
(47)
|
| (−g)1/2=1 |
をもとにして導かれた、式(47)の“第3の形”── 式(51)
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
をもとに、上記の「“重力場のエネルギー”が新たな質量となる」という意味の、非線形的な考え方が盛り込まれた上で、アインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)の原型であるところの、式(53)ができています。
|
『そこで一般相対性理論でも、物質のエネルギー・テンソルTσμ を考えよう。 〜。
このエネルギー・テンソル(これはポアッソン方程式のρに対応する)が重力場の方程式のなかにどんな具合に挿入されなければならないかは、(51)式が教えてくれる。すなわち、いま一つの完全な系(たとえば太陽系)を考えよう。この物理系の全質量、したがってまたその全重力的作用は、この物理系の全エネルギー、つまり物質によるエネルギーと、重力場のエネルギーの総和に依存する。この事情は、(51)において、重力場のエネルギー成分tσμのかわりに、物質および重力場の両方のエネルギー成分の和tσμ+Tσμ を導入することによって表現される。したがって、(51)のかわりにテンソル式
(gσβΓαβμ),α =−κ[(tσμ+Tσμ)−δσμ(t+T)/2]
|
(52)
|
| (−g)1/2=1 |
が求められる。T =Tμμである(ラウエのスカラー)。これはわれわれが求めていた一般の場合(すなわち、物質が存在するときに)における重力場の方程式の混合テンソル形式に書かれたものである。この式から逆に(47)に対応して
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
が出てくる。』 (アインシュタイン選集2(p97)) 一部省略しています。下線は、筆者によります。
|
「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場は、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当し、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場が、「物質があるときの重力場」に相当しています。
ここで、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)と「物質があるときの重力場」は、“密度の違い”があるだけで、重力場を作る能力は、部分的には、本質的には同じと見なせることを思い出しましょう。
|
|
|
|
※一番左が、「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場、すなわち、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当していて、
右側の2つは、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場、すなわち、物質が存在するときの重力場に相当していると見なせます。
やはり、仮想質点と物質の“重力子の放出源として働く能力”が全く等しいので、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、3つとも全く等しくなっています。
|
|
|
「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場と、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場が、部分的に同等であると見なせるということは、何を意味するのでしょうか?
それは、アインシュタイン方程式の原形(53)の左辺は、『「重力場のエネルギー成分tσμ」+「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場(時空の曲り)から、「重力場のエネルギー成分tσμ」がつくる重力場(時空の曲り)を引いたものであること、すなわち、アインシュタイン方程式の原形(53)の左辺は、単に、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場(時空の曲り)を表記する式に、相当することを意味するのです。
(gσβΓαβμ),α =−κ[(tσμ+Tσμ)−δσμ(t+T)/2]
|
(52)
|
|
(−g)1/2=1
|
『「重力場のエネルギー成分tσμ」+「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場
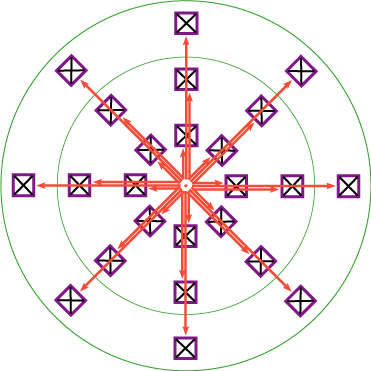 |
+ |
 |
|
− |
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
|
(−g)1/2=1
|
「重力場のエネルギー成分tσμ」がつくる重力場
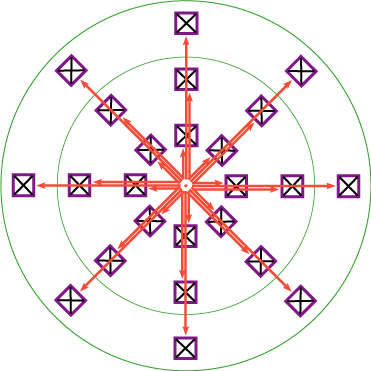
|
|
|
| = |
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ−gμνT/2]
|
(53)
|
|
(−g)1/2=1
|
「物質のエネルギー・テンソルTσμ」』が作る重力場
|

|
このようにして、アインシュタイン方程式自体は、「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形的な考え方が盛り込まれた上で導出されていますが、その最終的には、「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形性を持っていない式となっているのです。
すなわち、アインシュタイン方程式は、右辺も左辺も、質量エネルギー(静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))によって生じる重力場(時空の曲り)を意味しているだけであり、 「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形性は式から消えてしまっているのです。
つまり、「重力場のエネルギーが質量となる」という自然(nature)から乖離した考えを用いて導出されたのに関わらず、アインシュタイン方程式(アインシュタインの重力場の方程式)自体は、結果的に自然(nature)と調和したもの(「重力場のエネルギーが質量となる」という考えが反映されていない式)となっているのです。
よって、次の結論に至ることができます。
結論1-15.2 アインシュタイン方程式が、「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形的な考え方を用いて導出されていることは、重力場が非線形であるという根拠にならない。
※整理すると、次のようになります。
物質が存在しない所での重力場の方程式
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =0
|
(47)
|
| (−g)1/2=1 |
や
(gσβΓαβμ),α =−κ(tσμ−δσμt/2)
|
(51)
|
| (−g)1/2=1 |
が、意味するもの
|
物質が存在する所での重力場の方程式
Γαμν,α+ΓαμβΓβνα =−κ[Tσμ)−gμνT/2]
|
(53)
|
| (−g)1/2=1 |
が意味するもの
|
|
|
|
※左が、「重力場のエネルギー成分tσμ」が作る重力場、すなわち、「物質がないときの重力場」(仮想的な質点が作る重力場)に相当し、
右は、「物質のエネルギー・テンソルTσμ」が作る重力場、すなわち、物質が存在するときの重力場を表しています。
|
|
|
この対応関係は、式(47)も式(53)も、本質的には、部分的には、同等なものであることを意味します。
現に、少なくとも、どちらも「ニュートンの引力の法則」や「水星の近日点移動」を説明できるのでした。
※例えば、太陽系を考えてみます。全体の重心に仮想的な質点を考え、太陽系のあらゆる重力子の放出源としての働きを、この仮想的な質点1だけが担うと仮定してみます。
すなわち、“仮想的質点M”は、太陽系に含まれる「物質のエネルギー・テンソルTσμ 」が持つ重力子の放出源としての働き続ける能力をそのままにしながら、想像上、重心点まで圧縮したものです。
すると、 「この仮想質点の、重力子の放出源として働き続ける能力」は、「太陽系のすべての天体の総和の、重力子の放出源として働き続ける能力」であると定義されることになります。
(ここには、(重力子の通過点である)重力場が持っているエネルギーが、「重力子の放出源として働き続ける能力」、すなわち、質量になるという考えがどこにも入り込んでいません)
このことは、仮想的質点の質量をM仮として、太陽系に存在する各天体の質量エネルギー(静止質量エネルギー+(外部)運動エネルギー=運動エネルギー(内部&外部))をMc2とすると(その静止質量をM0、速度をvとすると)、
M仮c2 =ΣMc2(=ΣM0c2(1−v2/c2)−1/2)
と表記できることを意味します。
すると、太陽系のまわりの重力場は、結局、「この仮想質点のみがあるときの重力場の方程式」(=「物質が存在しないときの重力場の方程式」)の一部分(例えば、下の2重の緑で囲まれた所)で表現されることになります。
|
|
|
|
※左が、「仮想的質点と、そのまわりにつくられた重力場」であり、右は、太陽系のすべての物質を取り囲む球面と、そのまわりの重力場を表しているとします。
その、定義により、仮想的質点と太陽系の全物質の、“重力子の放出能力”が全く等しいので、例えば、2重の緑線で囲まれた部分の重力場は、両方とも、全く等しくなります。 |
|
だからこそ、 アインシュタイン方程式の右辺(8πG/c4)Tμνの成分の近似値≒(NM/4πn)×(1/r2)には、この緑の部分であることを示すための項(1/nr2)を含んでいると理解することができます。
2.アインシュタインの重力場方程式の中の曲率そのものが、計量gμνの非線形な式として表記されている。
アインシュタインの重力場方程式の中には、リッチ曲率テンソルRμνが含まれています。
リッチ曲率テンソルRμνとは、『Γαμν,α−Γαμα,ν+ΓαμρΓρνα−ΓαμνΓρνρ』のことです。
例えば、「物質が存在していない場合の重力場の方程式」は、次のようになり、この式は「リッチ曲率テンソルRμν=0」を意味しています。
| Γαμν,α−Γαμα,ν+ΓαμρΓρνα−ΓαμνΓρνρ=0 |
|
| (−g)1/2≠1 |
※アインシュタイン選集2 p.98の訳者注を参考にしました。
|
そして、この「リッチ曲率テンソルRμν=0」、すなわち、『Γαμν,α−Γαμα,ν+ΓαμρΓρνα−ΓαμνΓρνρ=0』という数式は、“計量gμνの非線形な式”に相当しています。
果たして、このことは、重力場そのもそのが非線形であることの根拠になるでしょうか?
そのことに関連して、やはり、次の記述が参考になります。
『(アシュテカは)アインシュタインの重力場の方程式を解く巧妙な方法を思いつき、方程式を書き直すことで最悪の非線形性の大半を消して、一般相対性理論をはるかに単純に見えるようにした。』
(p.268『パーフェクト・セオリー 一般相対性理論に挑む天才たちの100年』(ペドロ・G・フェレイラ 高橋則明 訳 NHK出版) 下線は、筆者によります。(アシュテカは)は、筆者による補足です。 |
『以上で導いた、Einstein理論に対する新たな正準理論はAshtekar 理論と呼ばれる. Ashtekar 理論はいくつかの優れた特徴を持っている. その第1は、理論に現れる諸式が基本変数の簡単な微分多項式となっていることである. 第6章で展開した計量を基礎とする正準理論(ADM理論)では拘束関数が計量の複雑な非線形式(実は分数式)となっていたことを思い起こすと,これは大幅な進歩である.』
(『岩波講座 現代の物理学6 一般相対性理論』 p.215 佐藤文隆・児玉英雄著 岩波書店) 下線は、筆者によります。 |
つまり、一般相対性理論(アインシュタインの重力場方程式)の意味内容を損なわずに、数式上の非線形性(計量gμνに関する非線形性)の大半を消すことに、アシュテカが成功したのです。
このことは、一般相対性理論の数式が持っている非線形性は、必ずしも重力場の非線形性の根拠としては非常に脆弱であることを意味しています。
しかも、素スピノル物理学パラダイムによれば、重力場は、始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)という調和振動子(単振動する系)から生まれた「重力子&縮みきり“4角形”」の単純な総和(足し算)として、単純に計算できるものです。
以上より、素スピノル物理学パラダイムは、次の結論に至ります。
結論1-15.3 アインシュタインの重力場方程式の中に、(計量gμνに関する)非線形性があることは、“重力場が非線形である”ということの根拠になりえない。
3.重力ポテンシャルエネルギーの大きさが、重力が弱い場合、「線形なニュートンの重力理論が示すように、GM/r[J]」となるのに対し、重力が非常に強い場合には「一般相対性理論が示すように2GM/r[J]」になる。
このことに関連して、次のような記述があります。
『この非線形的な補足は、実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”と考えることができる(〜)。収縮が進むにつれて、質量は増加して行くようにみえる。そして最終的には、よく用いる方程式のなかで以前説明したおなじみのGという因子が、あたかも2Gになってしまったかのようになるのである。
〜
同様にして、重力の強さが弱いところで物体を取り扱う場合には、重力ポテンシャルφに対する方程式は、Φ=GM/Rであるが、重力の強さが非常に強い場合、物体は、あたかも、Φ=2GM/Rであるかのようにふるまう。』
(p.224-226 『新しい重力理論 ニュートンから重力波まで』 アーサー・クライン著 竹内均訳 講談社ブルーバックス) 下線は、筆者によります。
|
この記述内容を単純に言い換えれば、「質量M[kg]の物体が、自己の重力(重力ポテンシャルエネルギー)によって、コンパクト化していく場合、重力が弱い場合は、ニュートン力学にしたがい、質量M[kg]のままなのに対し、重力が非常に強い場合には、一般相対性理論により、質量2M[kg]であるかのように振る舞う」ということになります。
たかが2倍といっても、あなどることはできません。なぜなら、質量M[kg]が2倍になるということは、同時に、質量エネルギーMc2[J]や重力場(時空の曲り)も2倍になるということだからです。
|
重力が弱い場合
(byニュートン力学)
|
重力が非常に強い場合
(byアインシュタインの一般相対性理論)
|
|
重力ポテンシャルエネルギー
U[J]
|
U=−GM/R[J]
|
U=−2GM/R[J]
|
|
質量M[kg]
|
M[kg]
|
2M[kg]
|
|
質量エネルギーMc2[J]
|
Mc2[J]
|
2Mc2[J]
|
|
重力場[N/kg]
|
F=GM/R2[N/kg]
|
F=2GM/R2[N/kg]
|
|
時空の曲り[1/m2]
|
(NM/4πn)×(1/r2))[1/m2])
|
(2NM/4πn)×(1/r2)[1/m2])
|
| ※なお、重力が非常に強い場合に、時空の曲りが2倍になるのは、(重力ポテンシャルエネルギーのカーブに比例する時空の曲り、すなわち、自由落下で消せる方の時空の曲りが2倍になるからです。 |
これまでは、「Gという値が、重力が非常に強い場合に、2倍になる(2Gになる)」ことは、一般相対性理論(重力場)が非線形であることの根拠の1つであると見なされてきました。なぜなら、Gが2Gになることは、上記のように、『実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”』が生じること、すなわち、「重力場が、新たな質量になる」という考えによって説明されてきたからです。
それでは、素スピノル物理学パラダイムによれば、「Gという値が、重力が非常に強い場合に、2倍になる(2Gになる)」ということは、どのように説明されるでしょうか?
それは、質量が2倍に増えるからです。
その大筋は、次のように説明できます。
物体がシュバルツシルト半径RS[m]まで、コンパクト化するまでに獲得する(外部)運動エネルギーが新たな質量エネルギーとしてカウントされます。
その新たに獲得される質量エネルギー((外部)運動エネルギーK[J])は、ぴったりそこまで利用された重力ポテンシャルエネルギーの大きさGM/Rs[J]に等しくなります。
そして、物体表面での重力場が2倍になるのは、この新たに獲得された質量エネルギー((外部)運動エネルギーK[J])(=利用された重力ポテンシャルエネルギーの大きさGM/R[J])が質量を2倍にするからです。
|
物体がシュバルツシルト半径RS[m]まで、コンパクト化することによって、本当に質量が2倍になるのでしょうか?
そのことについて、くわしく説明すると次のようになります。
トータルの質量がM[kg]のN個の粒子が、無限遠方から重力によってコンパクト化する系を考えます。
その系を、ある1つの粒子の質量m[kg][<<M[kg]]と、(残りN−1個の)合計の質量M[kg](厳密には、M−m[kg]ですが、m[kg]<<M[kg]なので、そのように考えます)にわけて考えることにします。
まず、(残りN−1個の)合計の質量M[kg]が、はじめからシュバルツシルト半径RS[m]に存在していると仮定した場合に、ある1つの粒子の質量m[kg]の質量がどのように変化するかを考えます。

| ※シュバルツシルト半径RSに質量M[kg](厳密には、M−m[kg])がすでにあるとして、無限遠方にある質量m[kg]が自由落下する系を考えています。オレンジの円は、球殻を意味しています。 |
|
この場合、質量m[kg]は、シュバルツシルト半径RS=2GM/c2[m]に至るまでに、質量が何倍になるでしょうか?
質量m[kg]が、無限遠方にあるときの質量エネルギーは、mc2=NmEG[J]です。
質量m[kg]が無限遠方からr=2nLP[m]の地点に来るまでに、重力ポテンシャルエネルギーを利用して蓄えられる運動エネルギー(質量エネルギー)は、一般に、NMNmEG/4πn[J]でした。 (9《量子化された重力、重力場の計算》)
さて、r=2nLP=シュバルツシルト半径RS(=2GM/c2)[m]のときのnの値は、次のように求まります。
RS=2GM/c2=2nLP[m]より、
n=GM/LPc2
=(c2LP/2πMG)M/LPc2 (G=c2LP/2πMGを利用 4《重力の幾何的モデル》)
=(M/2πMG)
=NM/2π
このシュバルツシルト半径RS=2GM/c2[m]のときのnの値NM/2πをNMNmEG/4πn[J]に代入すると次のようになります。
NMNmEG/4πn[J]=NmEG/2[J]
このNmEG/2[J]が、質量m[kg]がシュバルツシルト半径RS=2GM/c2[m]に至るまで獲得する質量エネルギーということになります。
もとの質量エネルギーがmc2=NmEG[J]ですので、これでは、2倍には足りません。
どこか考え足りない所はないでしょうか?
あります。
それは、本来、合計の質量M[kg]も、無限遠方からシュバルツシルト半径RS[m]に達する際に、運動エネルギーを獲得して質量エネルギーを増加させるということです。
仮に、合計の質量M[kg]がシュバルツシルト半径RS[m]に達していた際に、合計の質量M[kg]が2倍に増加しているならば、無限遠方の質量m[kg]が新たに獲得する質量エネルギーが、(2NM)NmEG/4πn=NmEG[J](n=NM/2πを使用)と、先ほどの計算値の2倍となり、これは、もとの質量エネルギーNmEG[J]のぴったり2倍に相当するようになり、つじつまが合います。
一方、合計の質量M[kg]がシュバルツシルト半径RS[m]に達していた際に、“2倍以外”になると、つつじつまが合わなくなります。
|
無限遠方の質量M[kg]が
元の何倍になるか
|
無限遠方の質量m[kg]が
新たに獲得する質量エネルギー
|
無限遠方の質量m[kg]が
元の何倍になるか
|
|
…
|
…
|
…
|
|
1.2倍
|
(1.2NM)NmEG/4πn=0.6NmEG[J] |
1.6倍
|
|
1.5倍
|
(1.5NM)NmEG/4πn=0.75NmEG[J]
|
1.75倍
|
|
2倍
|
(2NM)NmEG/4πn=NmEG[J]
|
2倍
|
|
3倍
|
(3NM)NmEG/4πn=1.5NmEG[J]
|
2.5倍
|
|
4倍
|
(4NM)NmEG/4πn=2NmEG[J]
|
3倍
|
|
…
|
…
|
…
|
|
このように“2倍以外”にシュバルツシルト半径RS[m]に達した合計の質量M[kg]が増加すると、質量m[kg]の増加立と、全体の質量の増加率が異なってしまい、つじつまが合わなくなります。
したがって、シュバルツシルト半径RS[m]に達した合計の質量M[kg]は、運動エネルギーの増加によって、“2倍に増える”はずであることがわかります。
このような説明は、N個の質量m0、m1、m2、m3、… mN−2、mN−1、mN それぞれについて同様にあてはめて考えることができます。よって、トータルの質量Mtotal(=m0、m1、m2、m3、… mN−2、mN−1、mN)[kg]は、シュバルツシルト半径RS[m]まで、コンパクト化することによって、質量が2倍になることがわかります。
以上より、無限遠方からN個の粒子が重力によってコンパクト化する系で、シュバルツシルト半径Rs=2GM/c2[m]に至る
までに、質量が2倍になるしくみが説明できたことになります。
|
つまり、シュバルツシルト半径RS[m]までコンパクト化する際に、物体が獲得する運動エネルギーをカウントされて質量(エネルギー)が2倍となる結果、それが、あたかも、重力が弱い場合のGが、重力が非常に強い場合に、2倍の2Gとなるように見えるだけなのです。
以上より、下表のすべてを説明できたことになります。
|
重力が弱い場合
(byニュートン力学)
|
重力が非常に強い場合
(byアインシュタインの一般相対性理論)
|
|
重力ポテンシャルエネルギー
U[J]
|
U=−GM/R[J]
|
U=−2GM/R[J]
|
|
質量M[kg]
|
M[kg]
|
2M[kg]
|
|
質量エネルギーMc2[J]
|
Mc2[J]
|
2Mc2[J]
|
|
重力場[N/kg]
|
F=GM/R2[N/kg]
|
F=2GM/R2[N/kg]
|
|
時空の曲り[1/m2]
|
(NM/4πn)×(1/r2))[1/m2])
|
(2NM/4πn)×(1/r2)[1/m2])
|
※すべて、質量が2倍に増加することで説明できます。
質量が2倍に増加することが、Gが2Gに増加するように見えさせていることがわかります。
|
素スピノル物理学パラダイムは、新たな質量になりうるのは、重力場のエネルギーではなく、運動エネルギー(内部&外部)であることをはっきり示しています。
すなわち、『実際の質量の横にある一種の“幽霊質量”』と考えられていたものは、「重力場のエネルギー」ではなく、実際は、『重力ポテンシャルエネルギーを利用して増加した(外部)運動エネルギーに相当する質量』であることを素スピノル物理学パラダイムが、はっきり示しているのです。
このように「物体によって、重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得された(外部)運動エネルギー」が、新たな質量となるからこそ、Gという値が2倍になるようにみえるのです。
このことは、ある天体が自身の重力によってコンパクト化すると、弱い重力でのGという値が、非常に強い重力(シュバルツシルト半径RS[m])で、2倍になる(2Gになる)のは、重力場が非線形であるからではないことを意味しています。
つまり、「質量の大きさ(「重力子&縮みきり“4角形”」の放出源として働き続ける能力)に比例した大きさの重力場が創発する」ことに変わりがないので、重力場そのものは、線形であるという説明は、ゆるがないことになるのです。
※そのように線形となるのは、「重力子&縮みきり“4角形”」の総和(単純な合計)が重力場に相当し続けるからです。もし、「重力子&縮みきり“4角形”」の総和(単純な合計)以上が、重力場となるならば、非線形と言えますが実際はそうではありません。
素スピノル物理学パラダイムは、次の結論に至ります。
結論1-15.4 (線形な)ニュートンの重力理論での、Gという値が、2倍の2Gになることは、“重力場が非線形である”ということの根拠にはなりえない。
※これまで、従来の物理学パラダイムで、弱い重力でのGという値が、非常に強い重力(シュバルツシルト半径RS[m])で、2倍になる(2Gになる)ことは、重力場が非線形であるとみなされてきましたが、それは誤解であったことになります。
※なお、「重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した(外部)運動エネルギーのみが新たな質量になる」という説明は、アインシュタインの重力場方程式の右辺が、質量エネルギー(「静止質量エネルキー&(外部)運動エネルギー」(=運動エネルギー(内部&外部)))であるという説明とも調和しています。
(このことは、この「アインシュタインの右辺が、質量エネルギー(「静止質量エネルキー&(外部)運動エネルギー」(=運動エネルギー(内部&外部)))であるという説明」が、アインシュタインの重力場方程式の右辺を「粗悪な材木」から、強固な「高級大理石」に、アップグレードしうるという考えを支持するものだと思います。
※以上の説明のような、「物質が重力によって収縮する(コンパクト化する)際に、物体(質量)が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して、運動エネルギーを獲得し、それが新たな重力子の放出源になること」を考慮すると、下図の説明について補足する必要が生まれることがわかります。
下図は、やはり、あくまで「物体の静止質量エネルギー&運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件のもとで、その中心(重心)に向けて、その全体積 Vだけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを説明しているものに過ぎません。すなわち、その全体積 V[m3]だけをどんどん小さく変化させるとどうなるかを説明しているものに過ぎません。この場合は、全体積V[m3]が小さくなると、それに反比例して、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)の密度」が大きくなるだけです。
|
|
|
|
※この図は、「物体の質量エネルギー&運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件つきの図です。
この条件がついてはじめて、グリーンの部分の時空が、すべて同じになることができます。
※結果的に、“ニュートンの重力理論”に相当するものになっています。
|
|
|
しかし、「物体の静止質量エネルギー&(外部)運動エネルギーの総量(=運動エネルギー(内部&外部)の総量)を一定にしたまま」という条件は、実は、現実的な条件ではなかったことになります。
ふつうは、物質自身の質量が生じる重力によって収縮する(コンパクト化する)ので、「物質が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して運動エネルギーを獲得し、それが新たな重力子の放出源になること」を考慮する方が現実的です。それを考慮して図示すると、次のようになります。
|
物体が、(物質自身が持つ)重力によって収縮する(コンパクト化する)場合
|
|
|
→
|
|
※「物体が重力によって収縮する(コンパクト化する)際に、物質が、重力ポテンシャルエネルギーを利用して獲得した運動エネルギーが
新たな重力子の放出源になること」を考慮した図です。
※なお、2倍になるのは、無限遠方からシュバルツシルト半径RS[m]まで、コンパクト化させた場合だけです。
しがって、上図のように、例えば、「途中から」コンパクトしただけでは、2倍には至りません。
|
|
|
以上の3つの結論、すなわち、
結論1-15.2 アインシュタイン方程式が、「“重力場のエネルギー”そのものが、そのままで新たな質量となる」という意味の非線形的な考え方を用いて導出されていることは、重力場が非線形であるという根拠にならない。
結論1-15.3 アインシュタインの重力場方程式の中に、(計量gμνに関する)非線形性があることは、“重力場が非線形である”ということの根拠になりえない。
結論1-15.4 (線形な)ニュートンの重力理論での、Gという値が、2倍の2Gになることは、“重力場が非線形である”ということの根拠にはなりえない。
は、いずれも、少なくとも、物体のコンパクト化が、シュバルツシルト半径に至るまでは、「結論1-13.1 重力場は、線形である」が成立することを支持するものです。
なお、シュバルツシルト半径(ブラックホール)に至ってから以降については、さらなる説明が必要なのは確かです。
なぜなら、「(無限遠方にある)質量が(シュバルツシルト半径RS[m]までコンパクト化すると)2倍になる」という関係が、もはや成立しないからです。
すなわち、ある質量M[kg]は、ブラックホールになることによって、2倍どころか、その質量が『NM/π』倍に増加する必要があるからです。
この事情について、下のテーブル内で説明します。
シュバルツシルト半径Rsに対応する事象の地平面の面積Sは、S=4πRs2[m2]です。
一方、シュバルツシルト半径Rs=2GM/c2=(2M/c2)×(c2LP/2πMG)=(M/MG)×(LP/π)です。
(G=c2LP/2πMGを使用 4《重力の幾何的モデル》)
よって、S=4πRs2={(M/MG)2/π}×4LP2[m2]となります。
つまり、重力(4《重力の幾何的モデル》)を説明してきた『(M/MG)×4LP2』だけでは、事象の地平面のすべてを縮みきり“4角形”にするためには、とても足りないのです。(当然、その2倍でも足りません)
『(M/MG)×4LP2』とは、(ニュートンの重力理論やアインシュタイン重力理論の一部を説明できた)厚さ2LP[m]の球殻において、質量M[kg]が生じる「縮みきり“4角形”」が占める面積でした。
一方、質量M[kg]の物体がブラックホールになる際は、事象の地平面において、すべての原始ヒッグス場ユニット(PHU)が縮みきり“4角形”になると考えられます(そのことにより、光子がブラックホールの内部から外部へ進めなくなると考えられます)。したがって、物体がブラックホールになる場合、その事象の地平面において縮みきり“4角形”が占める面積は、『{(M/MG)2/π}×4LP2[m2]』となるはずです。
つまり、厚さ2LP[m]の球殻において『M/MG=NM[個]』の原始ヒッグス場ユニット(PHU)を縮みきり“4角形”に変形していた、質量M[kg]が、ブラックホールになることによって、『(M/MG)2/π=NM2/π)[個]』の原始ヒッグス場ユニット(PHU)を縮みきり“4角形”に変形できるようになるはずであることがわかります。
このことは、ある質量M[kg]は、ブラックホールになることによって、その質量が、トータルで少なくとも『NM/π』倍に増加するはずであることを意味します。(これは、“2倍”になるどころの話ではありません)
|
ある質量M[kg]は、ブラックホールになることで(シュバルツシルト半径RS[m]の中で、さらにコンパクト化することで)、本当に、その質量が少なくとも『NM/π』倍に増加するのでしょうか?
ことについて、以下で説明します。
やはり、トータルの質量がM[kg]のN個の粒子が、無限遠方から重力によってコンパクト化する系を考えます。
その系のM[kg]とm[kg]の質量は、シュバルツシルト半径RS[m]までコンパクト化されるまでに、2倍の2M[kg]と2m[kg]の質量に至るのでした。(G→2Gの変化に相当)

| ※オレンジの円は、球殻を表しています。M[kg]も、m[kg]mも質量が2倍になっています。 |
|
質量が『NM/π』倍に増加するかどうかを確かめるには、ここから先の続きが大事になります。
ここから先は、トータルの質量が2M[kg]のN個の粒子が、シュバルツシルト半径RS[m]から重力によってコンパクト化する系を考えます。
その系を、例によって、ある1つの粒子の質量2m[kg][<<2M[kg]]と、すでにr=2LP[m](r=2nLPにおいて、n=1)の地点までに達した(残りN−1個の)合計の質量2M[kg](厳密には、2M−2m[kg]ですが、2m[kg]<<2M[kg]なので、そのように考えます)にわけて考えてみます。

| ※中心の円は、半径r=2LP[m]の球を表しています。 |
|
2m[kg]の質量が、r=RS[m](r=2nLPにおいて、n=NM/2π)の地点から、r=2LP[m](r=2nLPにおいて、n=1)の地点まで、さらに落下することによって、重力ポテンシャルエネルギーを利用して蓄える運動エネルギー(質量エネルギー)は、次のように計算できます。
n=NM/2πとして──
(2NM)(2Nm)EG/4π{(1/(n−1)−1/n)+(1/(n−2)−1/(n−1)+(1/(n−3)−1/(n−2)+… (1/3−1/4)+(1/2−1/3)+(1−1/2)}
=NMNmEG/π{1−1/n}
=NMNmEG/π−2NmEG (実際に、n=NM/2πを代入)
=(NmEG)NM/π −2NmEG [J]
2NmEG [J]とは、無限遠方にあった質量m[kg]が、r=RS[m]の地点にたどり着いた時に持っている質量エネルギーでした。
したがって、この式「(NmEG)NM/π −2NmEG [J]」は、無限遠方に存在する、質量m[kg]が、半径r=2LP[m]の地点まで落下することによって、トータルで、ぴったりNM/π倍になることを示す式そのものであると解釈できるものであることがわかります。
※無限遠方にあった質量m[kg](質虜エネルギーNmEG[J])は、r=RS[m]の地点にたどり着いた時に、質量2m[kg](質虜エネルギー2NmEG[J])になります。
『r=RS[m]の質量2m[kg](質虜エネルギー2NmEG[J])は、r=2LP[m]の地点にたどり着くまでに蓄える重力ポテンシャルエネルギーを利用して蓄える運動エネルギー(質量エネルギー)』が、『(NmEG)NM/π −2NmEG [J]』です。
したがって、r=RS[m]の質量2m[kg](質虜エネルギー2NmEG[J])は、r=2LP[m]の地点にたどり着いた時に、(NmEG)NM/π[J]になります。
つまり、無限遠方にあった質量m[kg](質虜エネルギーNmEG[J])は、r=2LP[m]の地点にたどり着くまでに、トータルで、NM/π[J]倍になります。
N個の質量m0、m1、m2、m3、m4、m5、… mN−2、mN−1、mN は、それぞれ非常に小さく、等しい大きさであるとします。
※なお、素スピノル物理学パラダイムによると、あらゆるクォークやレプトンといった剛体は、シュバルツシルト半径RS[m]に至るまでにプレオン∴(=プレオン∴(成果2))まで分解されます。
(5素スピノル宇宙論 2《新しいブラックホールの中で起こること概論》)
すると、同様な説明を、N個の質量m0、m1、m2、m3、m4、m5、… mN−2、mN−1、mN それぞれについてあてはめて考えれば、それぞれがNM/π倍になることになります。
したがって、トータルの質量M(=m0+m1+m2+m3+m4+m5+…+mN−2+mN−1+mN)[kg]は、半径r=2LP[m]までコンパクト化することによって、質量が少なくともNM/π倍になることがわかります。
以上により、一般に、質量M[kg]は、半径r=2LP[m]まで、コンパクト化されるまでに、少なくともNM/π倍になるしくみが説明できたことになります。
※“少なくとも”です。
「シュバルツシルト半径RS[m]に至るまで質量が2倍になる過程」で考えた効果(質量M[kg]も増える結果、獲得する運動エネルギーも増加するという効果)を考慮すれば、もっと増加することが考えられるからです。上の説明では、その効果を全く考慮していません。
なお、「シュバルツシルト半径RS[m]に至るまで質量が2倍になる過程」と「シュバルツシルト半径RS[m]に至ってから、半径r=2LP[m]まで、コンパクト化されるまで質量がNM/π倍になる過程」の間には、質量エネルギー獲得のしくみに微妙な違いがあると考えられます。
なぜなら、もし100%同じであれば(=「シュバルツシルト半径RS[m]に至るまで質量が2倍になる過程」の説明法(論法)を100%同じように使い続けられるのであれば)、質量M[kg]が半径r=2LP[m]の球までコンパクトされるまでにNM/π倍になることによって、質量m[kg]が(NM/π)2倍になってしまい、つじつまが合わなくなってしまうからです。
かといって、『質量M[kg]も増える結果、獲得する運動エネルギーも増加するという効果』が全くなく、単にぴったりNM/π倍となるのも不自然です。
よって、実際の倍率は、NM/π倍と(NM/π)2倍の間のどこかの値であると考えられます。それを比例定数α(1<α<NM/π)を用いて、αNM/π倍と表記してみます。
すると、「シュバルツシルト半径RS[m]に至るまでの過程」と「半径r=2LP[m]まで、コンパクト化されるまでの過程」は、次のように整理できます。
|
無限遠方の質量M[kg]が
元の何倍になるか
|
無限遠方の質量m[kg]
(質量エネルギーNmEG[J])が
達する質量(質量エネルギー)
|
無限遠方の質量m[kg]が
元の何倍になるか
|
|
r=RSまで
|
2倍
|
2m[kg]
(2NmEG[J])
|
2倍
|
|
r=2LPまで
|
αNM/π倍
|
αmNM/π[kg]
(α(NmEG)NM/π[J])
|
αNM/π倍
|
|
「半径r=2LP[m]まで、コンパクト化されるまでの過程」で働く仕組みとして、次のものが挙げられます。
1.シュバルツシルト半径に至るまでに2倍に増えた質量をぴったり帳消しにしつつ、質量M[kg]と質量m[kg]が互いに等しい倍率で増加できる倍率が“αNM/π倍”となる。(その増えた質量は、ブラックホールの事象の地平面の原始ヒッグス場ユニットを100%「縮みきり“四角形”」にする必要な質量にぴったり等しくなる)
※シュバルツシルト半径(ブラックホールのサイズ)がRS[m]=(M/MG)×(LP/π)のように質量M[kg]に比例している一方で、質量M[kg]に比例して重力子が放出されることによって周囲の時空は質量M[kg]に比例して膨張します。その結果、ブラックホールの外部からの観測上のサイズが質量M[kg]に反比例して収縮します。つまり、ブラックホールを外部から観測する際のサイズは、単にNM/π倍であっても、αNM/π倍であっても、等しくなると考えられます。なお、この性質は、新しいブラックホール生成過程における、各種のヒッグス場ユニット(電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット…)によって質量が増加する効果も、外部からの観測上帳消しにしていまうと考えられます。
2.シュバルツシルト半径RS[m]までコンパクト化が進んだ、トータル2M[kg]の質量を持つ物体は、もはやクォークやレプトンによる構成が維持されず、プレオン∴(=プレオン∴(成果2))に分解されてしまう。
3.ここで、プレオン∴(=プレオン∴(成果2))は、プレオン∴×4の「縮みきり“四角形”(スピン0)」(成果2 18《“インフラトン”の起源》)などのような形で既存の上限の運動エネルギーを内部運動エネルギーに転換する形で、新たな外部運動エネルギー(重力子の放出源として働き続ける能力)を、互いに同時に蓄える。
|
|
まだ、課題が残っていますが、いずれにせよ、重力場は、結局、獲得する運動エネルギーに比例して創発していること、すなわち、ここにも「重力場そのもののエネルギーが、そのまま新たな質量になる」という意味の非線形性は見いだせないことは変わらないので、「重力場は線形である」という結論は、ゆらがないことになります。
※仮に、「NM/π倍」以上に運動エネルギーを増加しうるポテンシャルがあり、互い等しい倍率でさらに増加したとしても、その質量の総和に比例して、ブラックホールの事象の地平面の原始ヒッグス場ユニットを100%「縮みきり“四角形”」にするだけです。
|
つまり、ある質量M[kg]は、新しいブラックホールになることで(シュバルツシルト半径RS[m]の中で、さらにコンパクト化することで)、本当に、とタールで、少なくとも『NM/π』倍に増加するのです。
しかも、このように質量が少なくとも『NM/π』倍になる過程についても、『結論1-13.1 重力場は、線形である』という結論は、ゆらいでいません。
※素スピノル物理学パラダイムによれば、重力場は、結局、「(“デュアルLP光子”からなる)重力子&縮みきり“4角形”」の総和(単純な合計)、すなわち、“個々の原始ヒッグス場ユニットの単振動(調和振動子)の総和(単純な合計)”に過ぎないのだから、“当然といえば当然のことだ”ということになります。
もう一度、『結論1-13.1 重力場は、線形である』という結論に至る理由を挙げます。
1.重力場のエネルギーは、通過してくる「重力子&縮みきり“4角形”」のエネルギーの総和にすぎない。
※その結果、“重力場のエネルギー”そのものは、質量(重力子の放出源として働き続ける能力)となりえません。
2.始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)は、調和振動子(単振動する系)の一種であり、重力場は、「重力子&縮みきり“4角形”」の単純な総和(足し算)として創発する。
※その結果、計算は、単純になります。
3.運動エネルギーの増加が、質量エネルギーの増加(重力子の放出源の増加)の実体である。
※その結果、質量エネルギー(運動エネルギー(内部&外部)の総和)と重力場(放出される「重力子&縮みきり“4角形”」の総和)は比例し続けます。
|
つまり、素スピノル物理学パラダイムは、たとえブラックホールに至り、コンパクト化が、半径r=2LP[m]まで進んでも、『結論1-13.1 重力場は、線形である』が正しいことを示しています。
素スピノル物理学パラダイムによれば、(重力子の通過点である)重力場そのものから、いきなり、新たな重力子を生じるようなことは起こりえないので、少なくとも、“重力場が質量になる”というような非線形性が決して生じえないのは確かです。
そして、だからこそ、静止質量の大きさに比例して、重力が増加するというニュートンの万有引力の数式も成り立つのです。
また、だからこそ、「静止質量エネルギーと(外部)運動エネルギー」の総和(=運動エネルギー(内部&外部)の総和)、すなわち、“重力子の放出源として働き続ける能力”に比例して重力が増加するというアインシュタインの重力場方程式も成立するのです。
これらは、「(重力子のエネルギーの通過点に過ぎない)重力場そのものが、いきなり、“新たな重力子の放出源として働く能力”、すなわち、新たな質量を獲得することがありえない」おかげでもあるのです。
※なお、電磁場も線形です。
(15《仮想光子による電場や磁場の創発》、16《静電気力と磁力(電荷と磁極のクーロンの法則)および、重力と電磁気力の統合》)
つまり、「重力場も 電磁場も、ともに線形」なのです。
このように電磁場の世界も、重力場の世界も、ともに線形であるということは、電場や磁場の大きさ、重力場の大きさは、ともに単純な足し算&引き算で求められることを意味しています。
そして、そのことは、素スピノルの転回にともなう原始ヒッグス場ユニットの“4面体”の変形が単振動であること、すなわち、「仮想光子&変形している“4面体”」も「重力子&縮みきり“4角形”」も“調和振動子”であることを考えれば、やはり当然のことです。
すなわち、仮想光子や重力子が変形させている原始ヒッグス場ユニットの“4面体”が調和振動子であるからこそ、その総和である電子場も重力場も、ともに線形なのです。
|