研究論文
『プランクスケールの自然についての幾何的モデルの探究が生む驚異的な成果』
2《新しいブラックホールの中で起こること概論》
アインシュタインの一般相対性理論は、宇宙を語るためになくてはならない重要な理論です。
しかし、それは、宇宙を説明するための十分&完全な理論ではないのは明らかです。
なぜなら、次の記述にもあるように、アインシュタインの一般相対性理論は、「新しいブラックホールの中で何が起こるのか、ビッグバンの瞬間に何があったのか」を説明することが十分にできないからです。
『一般相対性理論はブラックホールの存在やビッグバンを予測したが、ブラックホールの中心で何が起きるか、あるいは、ビッグバンの瞬間に何があったのか、物理学者に教えてくれないということだ。 そのような極微の規模では、理論全体が成り立たなくなる。半世紀以上にもわたり、物理学者は一般相対性理論を修正して、量子のレベルでもうまくやれるようにしようとしてきた』
(p.283〜 『世界を数式で想像できれば アインシュタインが憧れた人々』 下線は筆者によります) |
そして、偉大なアインシュタイン自身が、一般相対性理論が不完全であることを自覚していたからです。
|
『一九二一年までには、著名な人物のなかでこの理論にまだ不満を抱いているのはアインシュタイン本人だけとなっていた。この理論全体が一貫して対称性を持つようにと望んでいた彼の厳しい目からすれば、この方程式の左辺については、これは時空の幾何学によって表現されており、堅固なものと言ってよかったが、右辺のほうは、そうとはいえなかったのだ。彼は、この方程式のことを、お粗末に設計された建物になぞらえて、半分は「高級大理石」でできているのに、もう半分は「粗悪な材木」でできているようなものだとけなしたことまであった。不満を抱えた彼は、残りの生涯のほとんどを、この建物を修繕するという無駄な努力に費やす。三〇年以上かけてこの修繕作業を続けたのに関わらず、彼はそれに成功することはなかった。』
(『世界でもっとも美しい10の物理方程式』p.329 下線は、筆者によります)
|
|
『放射されるエネルギーの流れの密度はどんな方向に対しても負にならないことは(27)から容易にわかる。したがって、全放射エネルギーも負にならない。すでに以前の論文で強調されたように、以上のような考察の最終結論、つまり、物体はその内部の熱運動によってエネルギーを放出するという結論は、この一般相対性理論の正当性に疑いを投げかけるに違いない。量子論が完成されたときには、多分、重力理論をも修正しなければならないであろう(このような修正が行なわれたのちにはじめてすぐ上に述べた疑問は解決されるのであろう)』
(『アインシュタイン選集2──A8重力波について』より p.170〜171 下線は、筆者によります)
|
素スピノル物理学パラダイムがせんとするとことは、アインシュタインの一般相対性理論を否定することではありません。
それが、どのようなしくみでうまくいっているかを説明することです。そして、それが、どのような理由でうまくいっていないのかを説明することです。
素スピノル物理学パラダイムは、より深いレベルの階層から、アインシュタインの一般相対性理論を(その適用条件を含めて)包含的に説明するものです。
素スピノル物理学パラダイムによれば、アインシュタインの一般相対性理論が「新しいブラックホールの中で何が起こるのか、ビッグバンの瞬間に何があったのか」を説明できない理由は、次のように要約できます。
『一般相対性理論の数式が、“時空が連続である(微分可能である)ことを前提としている近似的で抽象的な数式”だからである。
すなわち、それは、“時空が不連続であることを前提とするような(「より深いレベルの階層」から説明するような)プランクスケールの自然(nature)についての具体的な幾何的モデルの探求が欠けている”からである』
|
素スピノル物理学パラダイムは、「新しいブラックホールの中で何が起こるのか、ビッグバンの瞬間に何があったのか」について説明できます。
すなわち、次の疑問に対する答えを提起します。
新しいブラックホール(新しくできたばかりのブラックホール)の内部で何が起こるのか? (本ページ)
新しいブラックホールが作られるとき、エントロピーや情報、質量は、どうなるのか?”
(3《新しいブラックホールとエントロピー》 4《新しいブラックホールと質量や情報》 および本ページ)
素スピノル物理学パラダイムに限らず、新しいブラックホールが作られる際のことを説明するために、次の2つを前提とするのとはもっともなことだと考えられます。
1. 可能な限りコンパクト化する。
2. 質量が増加する一方である。
1.可能な限りコンパクト化する。
この前提は、ホーキング-ペンローズの特異点定理、および、「ブラックホールは、少なくとも“クォーク星”より小さい」という事実を根拠とします。
ただし、「ホーキング-ペンローズの特異点定理」は、(一般相対性理論と同様に)時空が連続で微分可能であることを前提として導かれた定理であり、新しいブラックホールの中のあらゆるものが、その強い重力によって(大きさのない)“一点”まで収束する、ということを主張するものです。その結果、“無限大”が登場してしまいます。
『一九六五年から七〇年にかけて、ロジャー・ペンローズと私が行った研究によれば、一般相対論にしたがうかぎり、ブラックホールの中には無限大の密度と無限大の時空湾曲率をもつ特異点が存在するはずである。この特異点は時間のはじまりにおけるビックバンにかなり似ている』
(『ホーキング、宇宙を語る ビッグバンからブラックホールまで』 p.122
S・W・ホーキング 林一訳 早川書房 下線は、筆者によります) |
この特異点定理および、「ブラックホールは、“クォーク星”より小さい」という事実により、少なくとも、クォークや電子、ニュートリノが存続できない(プレオン∴まで分解する)ほどの、とてつもなく強い重力が、新しいブラックホールの中心部で生じており、そのコンパクト化が可能な限り進むことが予想されます。
※なお、それほど強い重力なので、当然、クォークヒッグス場ユニットや電子ヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニットも、存続できなくなると考えられます。
※なお、素粒子物理学の標準モデルの第2世代や第3世代も、当然、存続できません。
※また、ダークマター(プレオン∴ヒッグス場ユニットの総和)(11《ダークマター》)も中心部へ移動すると考えられます。
2.質量(重力子の放出源として働き続ける能力)が増加する一方である。
「質量が増加する一方である」ということは、ブラックホールの中心部で、質量エネルギー(「重力子&「縮みきり“4角形”」」の放出源として働き続ける能力)が、増加する一方であることを意味します。
保存されるのではなく増加すると考えられるのは、(重力ポテンシャルエネルギーを利用して)獲得された運動エネルギーが、新たな質量エネルギーになるはずだからです。
例えば、シュバルツシルト半径RS[m]の球までコンパクト化するまでにおいては、重力ポテンシャルエネルギーによって、物質の“運動エネルギー”が増加する分、質量エネルギー、すなわち、「重力子&“4角形”(縮みきったバネ)」の放出源として働き続ける能力が増加する結果、「Gが2Gになる」(「質量が2倍になる」)と考えられるのでした。(成果1 13《重力場の線形性について(詳細版)》)
さらに、中性子星→クォーク星→ブラックホールとコンパクト化が進む過程では、重力ポテンシャルエネルギーが利用され続けて、質量(“運動エネルギー”)がさらに増加し続けるのみならず、[物質の10億倍に相当する対消滅のペア(電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット…)由来の質量や、ダークマター(プレオン∴ヒッグス場ユニットの総和)(11《ダークマター》)由来の質量による加勢を考えずとも]半径r=2LP[m]の球までコンパクト化することによって、もとの質量M[kg]からの増加は、トータルで(“2倍”をはるかに越え)“NM/π倍”(NM=M/MG)に至るのでした。(成果1 13《重力場の線形性について(詳細版)》)
一方、ブラックホールの形成過程で、クォークやレプトンが分解して生じたプレオン∴は、原則としては、素スピノルまでは分解されないと考えられます。
なぜなら、単独の素スピノルは、重力子の放出源として働き続ける能力を持たないからです。
すなわち、もし素スピノルまで分解してしまうのであれば、質量が減ってしまうことになるからです。
※「単独の素スピノル」と「原始ヒッグス場ユニット(PHU)」との相互作用は、「電子」と「電子ヒッグス場ユニット(eHU)」との相互作用と似たものと考えられます。したがって、その振る舞いの全体を通じて、重力子を放出できる理由を見いだせないことになります。
つまり、「大きさのない“特異点”」には至らず、特異点の代わりに、「プレオン∴の集合」に至るのです。
そして、その「プレオン∴の集合」は、「重力子&「縮みきり“4角形”」」の放出源として働き続けるしくみを、なんらか形で持ち続けると考えられます。
この“プレオン∴の集合”は、どのように配置するでしょうか?
それらの“プレオン∴の集合”は、やはり、可能な限りコンパクト化すると考えられるので、プレオン∴まで分解して生じた、“粒子と反粒子のペア”──マイナスプレオンとプラスプレオンのペア(=“−∴と+∴のペア”)と中性プレオンと反中性プレオンのペア(=“0∴と0∴のペア”)を作ってボゾンとなり、フェルミ圧を減少させながら、凝縮していると予想されます。(なお、粒子と反粒子の数は、ぴったり一致します。 成果2 19《物質の起源──10億対“10億+1”の割合での反物質に対する物質の優位性》)
つまり、この“ボソン化によるフェルミ圧の消失”が、“可能な限りのコンパクト化”を実現してくれるのです。
※フェルミオンと違い、ボソンは、同一の物理状態で同位置を占めることができるのでした。
そのペアは、どのような状態で凝縮しているのでしょうか?
ペアのままの状態で凝縮するのでしょうか? それとも、四極子の状態で凝縮するのでしょうか? それとも「縮みきり“4角形”」の状態で凝縮するのでしょうか?
ここで、「質量がコンパクト化すればするほど、中心部のエネルギー密度が大きくなる」ことを思い出してみます。
すると、もし、ペアの状態、四極子の状態であったならば、エネルギー密度の大きい(高いエネルギーを持つ)中心部で“バラバラに分解してしまう”ことになってしまいます。それは、ブラックホールの中心部で、「可能な限りコンパクト化が進む」と予想されることと矛盾しています。
| ※この図より、ペアの状態や四極子であれば、高エネルギー状態で分解してしまうことがわかります。また、「縮みきり“4角形”」であれば、高エネルギー状態で分解しないこともわかります。 |
一方、「プレオン∴の集合」が「縮みきり“4角形”」を構成して凝縮するのであれば、中心部においてエネルギーが高まっていたとしても、「縮みきり“4角形”」の状態を維持でき、なおかつ、“フェルミ圧の消失”を達成し続けて同一の物理状態のボソンとしてほとんど1カ所に凝縮できます。それは、ブラックホールの中心部で、「可能な限りコンパクト化が進む」と予想されることと調和しています。
この「縮みきり“4角形”」を構成するプレオン∴は、外部運動エネルギー(「重力子&「縮みきり“4角形”」」の放出源として働く能力」)を獲得するのでした。
したがって、この場合の「縮みきり“4角形”」は、スピン2ではなく、スピン0であることが予想されます。
|
スピン2の
「縮みきり“4角形”」
|
スピン0の
「縮みきり“4角形”」
|
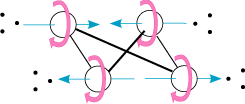 |
|
なぜなら、スピン0であることは、下記のようにダイナミックに運動し続けられることを意味しているからです。
すなわち、スピン0の「縮みきり“4角形”」であることによって、より大きな運動エネルギー(「重力子&「縮みきり“4角形”」」の放出源として働き続ける能力」)を獲得できると考えられるからです。
※この連星のような軌道運動によって、プレオン∴は、より大きな外部運動エネルギー(重力子の放出源として働き続ける能力)を獲得すると考えられます。
※このように、(“プレオン∴の集合”由来の)「スピン0の「縮みきり“4角形”」」が「重力子の放出源として働き続ける能力」を持つと考えられることは、「スピン0の原始ヒッグス場ユニットの“4面体”」も、「重力子の放出源として働き続ける能力」を持ち、それがダークマターの一種であると考えられることと調和しています。(→11《ダークマター》)
ともに、連星のような軌道運動によって、外部運動エネルギーを保持して、重力子を放出し続けると考えられます。
※ スピン0の「縮みきり“4角形”」である結果、グルーオンとは関係ないことになります。
|
以上より、素スピノル物理学パラダイムは、次の結論に至ります。
結論5-2.1 新しいブラックホールの中では、クォークやレプトン(物質由来&ヒッグス場ユニット由来)がプレオン∴まで分解され、それらのプレオン∴は、
|
スピン0の
「縮みきり“4角形”」
|
 |
−∴ +∴
+∴ −∴ |
or |
0∴ 0∴
0∴ 0∴
|
|
のような構造を持って、中心部に凝縮する。その際、重力ポテンシャルエネルギーを利用することによって、大きな外部運動エネルギーを獲得し続ける。
このようなプレオン∴×4の「縮みきり“4角形”」(スピン0)の形で「2.質量(重力子の放出源として働き続ける能力)が増加する一方である」ことに加え、「1.可能な限りコンパクト化する」ことを考え合わせると、新しいブラックホールの生成過程で、多数のプレオン∴×4の「縮みきり“4角形”」(スピン0)がボソンとして同じ状態をとって凝縮しながら、ほとんど1カ所に集合するので、「取りうる状態数」が減り、エントロピーが小さくなると考えられます。
ここまでの説明をまとめると、次のようになります。
とてつもない大きな重力によってクォークやレプトンが存続できないために、(10億対1で優位になってできた)物質と(10億対の対消滅してできた)ヒッグス場ユニットの両方が、プレオン∴まで分解し、プレオン∴ヒッグス場ユニットの「縮みきり“4角形”」として凝縮する。一方、ダークマターも、「縮みきり“4角形”」として、凝縮する。
新しいブラックホールの中心部では、(大きさのない)『ブラックホールの中には無限大の密度と無限大の時空湾曲率をもつ特異点』まで収縮する代わりに、(大きさを持つ)プレオン∴ヒッグス場ユニットの「縮みきり“4角形”」というボソンの同じ状態を取った凝縮となるのである。
プレオン∴ヒッグス場ユニットの「縮みきり“4角形”」は、スピン0であり、構成するプレオン∴は、重力ポテンシャルエネルギーを利用して、より大きな外部運動エネルギー(重力子の放出源として働き続ける能力)を獲得する。
一方これらは、可能な限りコンパクト化(集中)するので、(ボソンの同じ状態を取った凝縮をともなって)「取りうる状態数」の低下させながら、系のエントロピーを減らします。
|
※ブラックホールの事象の境界面で、すべての原始ヒッグス場ユニットが、「縮みきり“4角形”」になっているということは、その内側に行くほど、なんらかの形で重力子の密度の増加を支えなければならないことを意味してます。
それは、重力子が(「2LP[m]の間隔」を空けずに)さらにせばまって連続して存在できるだけでは解決しない一方、“多重共転回”のようなしくみが存在すれば、問題が解決しそうです。詳細な検討は、今後の課題です。
|