1《光子の波》
光子とは、従来の物理学パラダイムで、次のように説明されてきているものです。
|
『1905年、Einsteinは、振動数νの光はhνのエネルギーをもった粒子の流れのように振る舞うとする光量子仮説を唱えた. 〜 このような粒子は、後に光子(photon)と呼ばれるようになった』
(p.4 『8朝倉現代物理学講座 量子光学』 櫛田孝司著 朝倉書店) 下線は、筆者によります。
|
|
『アインシュタイン(1879〜1955、アメリカ)は、光を振動数ν[Hz]に比例するエネルギーhν[J]をもった粒子(光子または光量子という)の流れと見なし、光子1個が電子とぶつかって、そのエネルギー全部を電子に与えて消えてしまうと考えれば、光電効果が説明できることを示した(1905年)』
(p.236-237 『物理学入門』 実教出版) 下線は、筆者によります。
|
|
『光の振動数をν[Hz]で表すことにする。 光は
E=hν[J] h=6.63×10−34Js ……(5)
というエネルギーをもった多数の粒子の流れである。 この粒子を光子(光量子)という』
(p.308 『新しい物理学の教科書』 講談社ブルーバックス) 下線は、筆者によります。
|
|
『振動数νの光はエネルギーhνをもつ粒子のように振る舞う
hはプランク定数である。このように考えた光を光量子または光子という』
(p.344 『基礎教養 物理学』 廣川書店) 下線は、筆者によります。
|
|
『光子 光の粒子で、エネルギーをE=hνと、運動量p=h/λをもつ。ここで、νはその電磁放射の振動数、λは波長である』
(p.490 『量子革命』 用語集)
『電磁放射 電磁波には、運ぶエネルギーの大きさに応じてさまざまなタイプがある。 電磁波によって運ばれるエネルギーのことを電磁放射と言う。 振動数の低い波(たとえば電波)は、振動数の高い波(たとえばガンマ線)よりも電磁放射は少ない』
(p.493 『量子革命』 用語集) 下線は、筆者によります。
|
いずれの記述からも、“光子”について、ある程度の(ぼんやりとした)イメージを得ることができます。
そして、以上から、少なくとも『振動数ν[回/s]の電磁波(光、電波、ガンマ線…)が「“E=hν[J]のエネルギー”を持つ光子」の総和として創発している』ことがわかります。
しかし、いずれの説明からも、「光子は、いったいどういうしくみで流れる(移動する)のか?」、「どういうしくみでエネルギーを運ぶのか?」、「光子は、どういうしくみで、hν[J]に相当するエネルギーをもつのか?」といったこと、すなわち、「光子とは、いったい何なのか?」についての「具体的なイメージ」を見出すことは、困難です。
※その困難さに、しっかり気づいていたのはアインシュタインです。そのことは、次の記述から読み取れます。
|
『“すべての物理学者は光子が何であるか知っていると思っている”とアインシュタインは書き、さらに“私は光子とは何であるのかの問題に答を見いだすのに一生を費やしたが、いまだにわからない”と続けている』
(p.10 『ヘクト光学 I ─基礎と幾何光学─ OPTICS,4th edition』) 下線は、筆者によります。
|
|
『二〇世紀の始めから一九五五年にこの世を去るときまで、彼の念頭を離れなかったのがこの量子の問題だった。「量子問題については、私は一般相対論の一〇〇倍ぐらい頭を使っているよ」と彼は言っているが、そんなに考え続けても、どうにもらちがあかなかったのである。晩年になっても最初考えはじめたころと比べて少しの進歩もないどころか、いよいよもってわからなくなってきた感さえあった。「もう五〇年もの間必死で考え続けているというのに、いっこうに『光量子(クオンタ)とは何なのか?』という問題の解決に近づいてはしないのだ」とアインシュタインはぼやいている。「このごろは猫も杓子もこの答えがわかったなんぞと思っているらしいが、それは大まちがいというものだよ。」』
(p.60 『アインシュタインの部屋──[上]』 エド・レジス著 大貫昌子訳 工作社) 下線は、筆者によります。『(クオンタ)』はルビでした。
|
素スピノル物理学パラダイムは、まさに、この困難さ(疑問)を解消するような答え、「具体的な幾何的モデル」を提供します。
それは、抽象的な数学(抽象的な数式、抽象的な幾何)によってではなく、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何)によってなされます。
すなわち、素スピノル物理学パラダイムは、まさに、「光子は、いったいどういうしくみで流れる(移動する)のか?」、「どういうしくみでエネルギーを運ぶのか?」、「光子は、どういうしくみで、hν[J]に相当するエネルギーをもつのか?」について、具体的な数学(具体的な数式、具体的な幾何)を用いながら、「具体的な幾何的モデル」を提供します。
素スピノル物理学パラダイムでは、1つ1つの“光子”の幾何的モデルを、次のような仮説として提供します。
仮説1-1.1 光子は、下図のように、素スピノル2つから成り、スピン1を保ち続けるものである。
|
光子
|
|
素スピノル物理学パラダイム
の表記
|
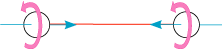 |
|
簡略表記
|
・・
|
|
スピン
|
1
|
| ※“スピン1/2の左巻き素スピノル”と“スピン1/2の右巻き素スピノル”が結びついて、スピン1の光子ができています。
※この光子の説明は、弦理論において、「光子は、スピン1を持つ開いた弦である」と説明されていることと調和しています。
|
このような光子が、空間(電磁場)を光速で移動するとは、どういうことでしょうか?
次のような記述をヒントにしてみました。
|
『温度がゼロよりほんの少し高いとどうなるだろうか。この場合も基本はやはりすべてのスピンがそろった状態で、そこにときどきランダムに一個のスピンがひっくりかえることが起きる。そうすると、その隣のスピンがつき合ってやはり逆を向くこともあるだろう。ただ、二つが同時に逆を向くとエネルギーのロスが大きすぎるので、隣が逆を向いたら最初のは元に戻る。次はそのさらに隣が付き合って逆を向く……、という具合にスピンが格子上を伝わって移動していくこともありそうだ。まるで波のようではないか。そう、これは波だ。』 (『質量はどのように生まれるのか』 橋本省二 講談社ブルーバックス p160-162 鉄の強磁性に関しての説明文の一部)
|
この“スピンのひっくりかえりの伝播”が電磁場の上で(素スピノルのネットワーク上で)起きている場合、それがまさに、光子の創発に相当しているだろうと考えてみました。
よって、次の仮説を立てました。
仮説1-1.2 振動数ν[回/s]、波長λ[m](=c/ν[m])の電磁波を構成する光子は、間隔r[m]が波長λ[m]の1/2であるような「素スピノルのペア」がスピン1を保ちながら、180度、同時に転回する(共転回する)ことを、下図のように次々と繰り返しながら進むものに相当する。
※“素スピノルのペア”が、スピン1を保ちながら、同時に転回することを“共転回する”と呼ぶのでした。
(なお、1つの素スピノルが“ひっくり返る”ことを、“転回する”と呼ぶのでした)
この共転回の繰り返しの過程は、まさに、『隣が逆を向いたら最初のは元に戻る』ことの繰り返しの過程に相当していることが図から読み取れます。
※素スピノルのペアの間隔r[m]が、波長λ[m]の1/2に相当するということは、光子は、180度の共転回を2回繰り返すことによって、1波長分の距離を進むことを意味します。
|
光子は、“素スピノルのペア”が“共転回”するからこそ、スピン1を保ち続けられることが、下図からわかります。
※素スピノルのペアが、共転回している最中の様子を示している図です。
このように、Aがθだけ転回すると同時に、Bも同じθだけ転回するからこそ、総スピン1を保つことができることがわかります。
|
この仮説は、「このように、180度の共転回の繰り返しによって、スピンの1の光子が、次々と伝わっていくこと」こそが、“光子の伝わり方”(光子の移動のし方)を示す幾何的モデルであることを示しています。
これが、真空中を、光速という一定の速度で伝わるということは、「c=νλ=2νr[m/s]」の関係が成立することを意味します。
(c[m/s]:光速 ν[回/s]:光子の振動数 λ[m]:波長 r[m]:素スピノルのペアの間の距離)
よって、「c=νλ=2νr[m/s]」の式から、単位時間あたりの光子振動数ν[回/s]が大きくなるほど、それに反比例して、光子の波長λ[m](=2r[m])は短くなって、逆に、単位時間あたりの光子振動数ν[回/s]が少ないほど、それに反比例して、光子の波長λ[m](=2r[m])は長くなることがわかります。
つまり、光子は、振動数ν[回/s]に反比例した波長λ[m]を持つと同時に、「180度の共転回の振動数2ν[回/s]」に反比例した「素スピノルの間の距離r[m]」を持つことになります。
一方、アインシュタインの光量子仮説の式「E=hν[J]」により、光子のエネルギーE[J]と、光子の振動数ν[回/s]のみならず、単位時間あたりの“180度の共転回の頻度(共転回数)(=2ν[回/s])”も比例することがわかります。
「E=hν」[J]の式は、ν=1/T[回/s](T[s]:周期)より、「ET=h[J・s]」と変形することもできます。
この式は、共転回が短時間で済むほど(速いスピードで共転回するほど)、光子のエネルギーが大きいことを意味しています。
※この「ET=h[J・s]」の式は、不確定性原理(不確定性関係)とも関連します。(成果3 10《不確定性原理(不確定性関係)と確定性原理(単振動振幅の確定性関係)》)
※この周期T[s]は、「“180度の共転回”の周期の2倍」に相当するのみならず、「1つの素スピノル360度の転回周期」にも相当します。
また、「E=hν[J]」 であるということは、(ν=c/λ[1/s] より)「E=hν=ch/λ(=ch/2r)[J]」が成立することを意味します。
したがって、光子の運動量p=E/c=h/λ(=h/2r)[J・s/m]、すなわち、pλ=h[J・s]の関係が得られます。
この式は、共転回をする素スピノルの間隔がせまいほど、光子の運動量(共転回する素スピノルの勢い)が大きいことを意味しています。
※この「pλ=h[J・s]」の式は、不確定性原理(不確定性関係)とも関連します。(成果3 10《不確定性原理(不確定性関係)と確定性原理(単振動振幅の確定性関係)》)
※なお、このモデルは、“円偏光”についても、うまく説明できます。すなわち、転回する方向が、光の進行方向に平行な成分のみなら垂直偏光であるが、もし、光の進行方向と垂直な成分も合わせ持つならば、円偏光となると説明できます。
光子の幾何的モデルについてまとめると次のようになります。
◎180度の共転回を1回繰り返すことによって、光子は、1/2波長分(r=λ/2[m](r [m]: 素スピノルのペアの間の距離)だけ進む。(すなわち、180度の共転回を2回繰り返すことによって、光子は、1波長分(λ=2r [m](r [m]: 素スピノルのペアの間の距離))だけ進む)
このように「c=νλ=2νr[m/s]」の関係が成立させながら、光子は、光速c[m/s]で移動する。
◎180度の共転回を2回繰り返すこと(=共転回360度分)が、「光子が1回振動すること」、「光子の1周期T[s]だけ時間が経過すること」、「光子が1波長λ[m]分だけ進むこと」に相当する。
◎光子のエネルギーをE[J]、光子の運動量をp[J・s/m]とすると、ET=h[J・s]、pλ=[J・s]の関係がある。 |
こういった光子の幾何的モデルを、先に述べた『振動数ν[回/s]の電磁波(光、電波、ガンマ線…)は、「E=hν[J]のエネルギーを持つ光子」の総和として創発している』に加味することによって、次の結論に至ります。
結論1-1.1 振動数ν[回/s]&波長λ[m]の電磁波は、「E=hν[J]のエネルギーのみならず、波の性質(振動数ν[回/s]や波長λ[m])も持つ光子」の総和として創発している。
先の『振動数ν[回/s]の電磁波(光、電波、ガンマ線…)は、「E=hν[J]のエネルギーを持つ光子」の総和として創発しているものであるらしい』では、個々の光子が、振動数ν[回/s]や波長λ[m]を持つかどうかについては、全く触れられていなかったので、この結論1-1.1には、「個々の光子が振動数ν[回/s]や波長λ[m]を持つ」という新しい意味(情報)が加わっています。
それぞれ1つ1つが「“E=hν[J]のエネルギー”のみならず、振動数ν[回/s]や波長λ[m]を持つ」光子は、いわば、“光子の波”と呼べるものです。
以後、素スピノル物理学パラダイムで、光子と言う場合── 「“E=hν[J]のエネルギー”のみならず、振動数ν[回/s]や波長λ[m]を持つ光子」、すなわち、“光子の波”(=光の量子波)を意味しているものとします。
※この「光子の波」の幾何的モデルにより、光が持つとされる“波と粒子の二重性”が生じる理由も、自然にうまく説明できます。
(成果3 14《粒子と波の二重性──相補性原理》)
※また、この「光子の波」の幾何的モデルにより、光電効果やコンプトン効果も説明できます。
(成果3 19《コンプトン効果》)
こういった幾何的モデルで示される光子、すなわち、“光子の波”は、「とびとびの波、デジタルな波、不連続な波…」であり、まさに“量子波”(quantum wave)とも呼べるものです。
こういった“光の量子波”の集合、すなわち、“振動数ν[回/s]、波長λ[m]の光子の集まりの流れ”は、どのようにして、“振動数ν[回/s]、波長λ[m](=c/ν[m])の電磁波”を創発するのでしょうか?
まず、“1つの光子の波”の幾何的モデルの図に、電磁波の図を重ねてみます。
※「素スピノルのペア」の間隔r[m]は、常に波長λ[m]の1/2になっていますので、図のように、おおよそ、電磁波の山や谷の部分に素スピノルが配置していると考えると、少なくとも振動数ν[回/s]と波長λ[m]の対応関係が説明できることが読み取れます。
※また、電場の向きと垂直な方向に、(同時に)磁場が生じていると考えると、うまく説明できそうであることも読み取れます
|
上図をふまえると、下図のように“右巻きor 左巻きの素スピノルが転回する際に、どちらの方向に、どのような時間経過で電場や磁場が生じるか”というような簡単なルールを決めることによって、光子の総和として、電磁波に一致する電場や磁場が創発することを、うまく説明できることがわかります。
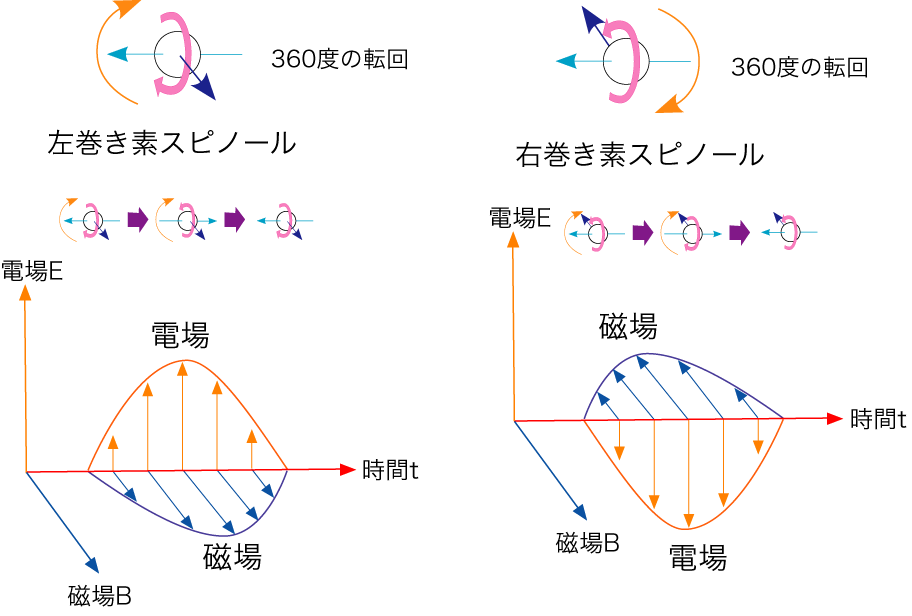 |
ルール1 左巻き素スピノルが転回する向きに対して、左ねじの方向に磁場が生じる。
右巻き素スピノルが転回する向きに対して、右ねじの方向に磁場が生じる。
ルール2 ルール1で決まる磁場に対して、 光子の進行方向について『右ネジの法則』が成立する向きに電場が生じる。
|
※1つの素スピノルが360度転回する間に、電場や磁場のサインカーブは180度分しか変化しないことになります。
※このサインカーブ自体は、横軸が時間tになっていますので、当然、電磁波のサインカーブとは異なるものです。
すなわち、これは、光子1つが(ある場所で)生じる電磁場の時間変化を示しているに過ぎません。
しかし、こういった性質を持つことは、マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式の解を満たすことがわかります。
マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式の解の1つである 「zの正の方向に進行する正弦波であらわされる電場や磁場」は、次の式で表されるるのでした。
|
Ex(z,t)=E0sin(2πz/λ−wt)
By(z,t)=(E0/v)sin(2πz/λ−wt)
(参考p.186 『物理学スーパーラーニングシリーズ 電磁気学 第2版』 佐川弘幸/本間道雄 著)
|
そこで、 z=nλ/2での場所での電場や磁場の変化を求めてみるために、z=nλ/2を代入すると──
電場 Ex(z,t)= E0sin(2πz/λ−wt)=E0sin(πnλ/λ−wt)=E0sin(πn−wt)=±E0sin(wt)
磁場 By(z,t)=(E0/v)sin(2πz/λ−wt)=(E0/v)sin(πnλ/λ−wt)=(E0/v)sin(πn−wt)=±(E0/v)sin(wt)
のように、ともに単純な正弦波となることがわかります。
このことは、「光子を構成する、とびとびの“素スピノル”」の1つ1つが単純な正弦波となる“電場や磁場の変化”を担いさえすれば、マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式を満たすことを意味します。
※光子を構成する素スピノルは、「プランクスケールの“電場&磁場”」(左巻き)→「プランクスケールの“電場&磁場”」(右巻き)→「プランクスケールの“電場&磁場”」(左巻き)→…」のように、電場と磁場を両方同時に生じていることになります。
このことは、そもそも、(マクスウェルの方程式から導かれる波動方程式の解の1つである、 「zの正の方向に進行する正弦波であらわされる電場や磁場」に相当する)上式からも導かれることです。
しかし、このことは、“電磁波は、「電場→磁場→電場→磁場→…」のようにして伝わる波である”という下図のような図示&説明とは異なります。
この図は、「オリジナルは、ノーベル物理学賞者のボルンによって描かれたため、その後、多くの著者に取り上げられた」(『電磁波とは何か』 p194 講談社ブルーバックス)とのことです。
しかし、この「電場→磁場→電場→磁場→…」と交互に伝わる波は、実際は、定在波に過ぎず、進行する電磁波ではありません。そのことは、次の記述からもわかります。
『電界と磁界が交互にずれた位置で強くなるのは定在波であり、電磁波は進行しない。
〜電磁波が進むためには〜電界と磁界が同時に強くならなければならないのである』
(『電磁波とは何か』(後藤尚久 講談社ブルーバックス p194) 下線、省略は筆者によります。 |
進行波が「電場と磁場が同時に強くなっている」ように図示され(p.327)、定在波は「電場と磁場が交互にずれた位置で強くなる」ように図示されている(p.352)文献があります。
(『基礎電磁気学 改訂版』(山口昌一郎 電気学会) |
『これは定在波を表していることに注意しなければならない』と記述され、『誤りの例』として、上のような図を提示している文献もあります。
(『入門 電波応用 [第2版]』(藤本恭兵 共立出版 p.17) 下線は筆者によります。 |
|
したがって、下図のように、電場と磁場が両方同時に生じる性質は、「進行する電磁波」を生み出すために必要なことなのです。
※『右ネジの法則』については、次の記述が参考になります。
|
『〜光の進行方向を表すベクトルと電気・磁気ベクトルは、たがいに「右ネジの法則」の関係にあることがわかっている。 〜電気ベクトルから磁気ベクトルに向けて右ネジをまわす(時計まわりにする)と、ネジの進む方向が光の進行方向(〜)に一致する。』
(『対称性から見た物質・素粒子・宇宙 鏡の不思議から超対称性へ』(広瀬立成 講談社ブルーバックス)p69-70より)
下線および一部省略は、筆者によります。
|
|
こういった個々の光子が複数集まると、どうなるでしょうか?
このことに関連して、次のような重要な記述があります。
|
『光子数の多い極限では、コヒーレント状態は振幅、位相ともに決まった波で表される古典的な状態と実質的に同じになる』
(p.163 『8朝倉現代物理学講座 量子光学』 櫛田孝司著 朝倉書店)
|
※コヒーレント状態とは、「位相がそろった状態」という意味です。
この記述は、同じ振動数ν[回/s]を持つ光子(光の“量子波”)が多数、位相がそろった状態(=コヒーレント状態)で生み出されれば、古典的な電磁波の波(上図のサインカーブのような波)を創発しうることを意味しています。
この説明は、「個々の光子がマクスウェルの方程式から導かれた波動方程式を満たす」ことからも、無理のないことがわかります。
また、こういった、とびとびの光子(光の量子波)の総和として創発するものが電磁波であるという描像は、『コヒーレントな光子の集団の典型的な例である、レーザー』(成果3 18《ボーアの原子模型》)はもちろん、『電磁波の腹と節の違いを観測したことに相当する「ヘルツの実験」』や『電気双極子の振動によって生じる電磁波』(成果1 20《電気双極子の振動に伴う放射について》)も説明できます。
すなわち、これらの既存の光に関する現象や観測結果は、光子の波(光の量子波)の総和として創発するものとして、再解釈できるのです。
こういった光子および、そのエネルギーを伝える媒体は、どのようなものでしょうか?
これまでの従来の物理学パラダイムにおいて、電磁波は、「電磁場の上を伝わる」と説明されています。
(なお、マクスウェルは、エーテルの存在を前提として定式化したのでした。そして、エーテルは、マイケルソン-モーレーの実験、アインシュタインの特殊相対性理論によって否定されたと言われているのでした)
したがって、電磁波を構成する光子も、電磁場を媒体にし、その上を波として進むと考えるのが自然でしょう。
それでは、“電磁場”の幾何的モデルは、どのようなものでしょうか?
素スピノル物理学パラダイムでは、次のような仮説を立てて説明します。
仮説1-1.3.1 下図のような、右巻き素スピノルのペアと左巻きの素スピノルのペア”が対消滅してできている、“原始ヒッグス場ユニット”(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))の挙動の総和として、電磁場が創発する。
|
“原始ヒッグス場ユニット”
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))
(=原始ヒッグス場の基本構造)
|
|
素スピノルのネットワーク
(素スピノル物理学の表記)
|
|
←
→
|
|
|
構成
|
“左巻き素スピノルのペアと
右巻きの素スピノルのペア”
対消滅してできている
|
|
構造
|
“4面体”
|
|
エネルギー
|
“正4面体”のとき、
蓄えているエネルギーが最も小さい
|
|
スピン
|
0
|
光子は、この“原始ヒッグス場ユニット”(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))の“4面体”をバネ的な足場にして、光速で移動することになります。
この“原始ヒッグス場ユニット”(PHU)が多数びっしりと占めている総和として創発するのが、原始ヒッグス場です。
電磁場は、この原始ヒッグス場の上で創発すると考えられます。
※なぜ、電磁場ユニット((EU(=electromagnetic(field)Unit)))ではなく、わざわざ、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))と表記するのでしょうか?
それは、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニットの総和)が電磁場のみならず「重力場、質量を与えるヒッグス場、四次元時空連続体、時空の曲り、“新しいエーテル(非物質的エーテル)”…」も担うからです。
なぜ、ヒッグス場(ユニット)ではなく、原始ヒッグス場(ユニット)と表記するのでしょうか?
それは、ヒッグス場には、原始ヒッグス場以外にも、電子ヒッグス場、クォークヒッグス場、ニュートリノヒッグス場など、他のヒッグス場も存在するからです。(成果2 16《ヒッグス場と各種の場》)
※びっしりと占めている原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和として「電磁場、重力場、質量を与えるヒッグス場、四次元時空連続体、時空の曲り、新しいエーテル(非物質的エーテル)…」が創発するということは、これらが不連続であることを意味します。
原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する、凝縮のペア(黒い線で結ばれた、右巻きどうしのペア&左巻きどうしのペア)は、ふだんは、それぞれに、連星のように、連続して、高速の軌道円運動をしていると考えられます。
この“連星のような(連続)軌道円運動”の幾何的モデルを図示すると、下図のようになります。
|
原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する素スピノルの“連星のような(連続)軌道円運動”
|
|
|
※この“連星のような動き”こそが、“場所を移動させない(位置を固定させる)”という重要な性質を創発すると考えられます。(“原始ヒッグス場ユニット”の1つ1つは、特定の場所を占めている(自由に回転できると同時に場所を固定している)と考えられます)
※なお、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する個々の素スピノルについては(連続な)回転対称性が成立するので(ネーターの定理によって)「素スピノルの角運動量保存則」が成立すると考えられます。
※“高速”の軌道円運動と書きましたが、この素スピノルの軌道円運動の速さは、“光速に等しくなければならない”理由はないようです。なぜなら、仮に、この素スピノルの軌道運動の速さが光速を越えていたとしても、“光速不変性”は保たれ、特殊相対性理論と矛盾しないからです。
“光速不変性”が成立する理由(光速不変が、どのようなしくみで創発するか)については、後で説明します。
(成果1 7《光速度不変性とローレンツ収縮》)
※素スピノルの(連続)軌道円運動の“速度の大きさ”は、“場所を移動させない(位置を固定させる)”という重要な性質を創発することとも関連していると思います。この“速度の大きさ”は、具体的にいくらになるのが自然(nature)と調和するのでしょうか? 詳細な検討は、今後の課題です。
※ファインマンによると、粒子と反粒子は、時間の流れが逆なのだと解釈できるのでした。したがって、「右巻き素スピノルのペア」と「左巻き素スピノルのペア」が同じ方向に(連星のような)回転運動しているということは、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の中の素スピノルについては、単に(連星のような)軌道円運動している間は「トータルで時間が流れていないことになる」と考えられます。一方、例えば、光子を構成している素スピノルとして、原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成している素スピノルが共転回している間は、「右巻き素スピノルのペア」と「左巻き素スピノルのペア」の軌道円運動に差が生まれるからこそ、「時間が流れる」(時間が創発する)という説明も成立すると考えられます。詳細な検討は、今後の課題です。
|
1つの光子について、ET=h[J・s]の関係が成立するのでした。
この「ET=h[J・s]」の式は、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)の振る舞いを示していると解釈することもできます。
すなわち、この場合は、周期T[s]は「1つの素スピノル360度の転回周期」に相当し、エネルギーE[J]は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの最大の振幅に相当すると解釈します。
したがって、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の“4面体”は、変形することによって一時的にエネルギーを蓄え、 光子が持つエネルギー(E=hν)が大きいほど、それに比例して、“4面体”に蓄えられるエネルギーの振幅も大きくなると考えられます。
※この解釈は、共転回が短時間で済むほど(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)を構成する素スピノルが、速いスピードで転回するほど)、光子のエネルギー、および、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーが大きくなることを意味しています。
以上より、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)の総和の上で“光子の流れ”が生ずる様子を示す幾何的モデルは、次のようになります。
※この幾何的モデルは、光子が、「原始ヒッグス場ユニット(PHU)のバネに一時的に蓄えられるエネルギーを、とびとびに伝えながら光速で進んでいる様子を示しています。
※1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))の中の1つの素スピノルが、光子を構成するそれぞれの素スピノルに相当しています。
※「バネのようにエネルギーを蓄えている、1つの“4面体”の変形」が解消されるとともに、新たな“4面体”の変形が生じている様子も図示されています。
この図より、光子(素スピノルのペア)の移動とともに、エネルギーが移動することがわかります。
それは、共転回する素スピノルのペアの中で、ピンク色で示している素スピノルを含む“4面体”の方が、より大きなエネルギーを蓄えており、その後、その“4面体”の変形が解消されるとともに、そのエネルギーを次の“4面体”に新たに蓄えることを繰り返すことによって、エネルギーが光速で移動することを意味しています。
なお、振動数νを持つ光子のエネルギー(2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの合計)は、常にぴったりE=hν[J]となります。(下で説明)
※びっしり占める個々の“原始ヒッグス場ユニット(PHU)”の足場にはそれぞれ、必ず、右巻き素スピノル(相手に近づく方向に進むもの、遠ざかる方向に進むもの)、左巻き素スピノル(相手に近づく方向に進むもの、遠ざかる方向に進むもの)の4種類が存在するので、ある波長を持つ光子の進行に必要な素スピノルを、適宜選ぶことが可能となります。
|
光子は、その振動数ν[回/s]の違いに応じて、さまざまな大きさのエネルギー(E=hν[J])を持つことができます。
その光子の持つエネルギーの起源は、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)に蓄えられるエネルギーの合計です。
光子によって原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの起源は、その原始ヒッグス場ユニットで生じるプランクスケールの電場、プランクスケールの磁場のエネルギーの合計です。
※光子を構成する素スピノルは、「プランクスケールの“電場&磁場”」(左巻き)→「プランクスケールの“電場&磁場”」(右巻き)→「プランクスケールの“電場&磁場”」(左巻き)→…」のように、電場と磁場を両方同時に生じているのでした。
振動数ν[回/s]を持つ光子(光の量子波)のエネルギーの総和(原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの総和)は、常に一定のE=hν[J]となります。
そのことは、次のように説明できます。
原始ヒッグス場ユニット(PHU)上の光子の幾何的モデルが示すように、1つの光子(2つの素スピノル)が1回だけ180度の共転回する間に、一方の「変形している“4面体”」が、(蓄えた)エネルギーを放出するのと同時に、もう一方の“4面体”がエネルギーを新たに蓄えるように変化します。
その共転回の際の「原始ヒッグス場ユニット(PHU)の変形」と「プランクスケールの電場の変化」の様子を、詳しく示すと次の図ようになります。
※上図の、上段の左側にあるピンクの素スピノルの転回は、蓄えたエネルギーをこれから放出する過程を担い、右側にあるブルーの素スピノルの転回は、エネルギーをこれから新たに蓄える過程を担うことになります。
※下段の左側にあるブルーの素スピノルは、蓄えていたエネルギーを放出し終えた状態を示し、右側のピンクの素スピノルは、エネルギーを蓄え終えており、これからその蓄えたエネルギーを放出する(他へ伝える)過程を担うことになります。
|
上図のように、変形している原始ヒッグス場ユニット(PHU)の場所における「プランクスケールの電場の変化」が単純な正弦波となることで、マクスウェル方程式から導かれる波動方程式を満たすようになるのでした。
この正弦波は、z=nλ/2の場所に存在する「変形している原始ヒッグス場ユニット(PHU)」が生じる「プランクスケールの電場の変化」、すなわち、電場 Ex(z,t)=±E0sin(wt)という単純な正弦波に相当するのでした。
※位相がそろった(コヒーレントな)光子の集合が、トータルで古典的な電場となるので、光子1つによるプランクスケールの電場の変化をE光子sin(wt) とし、その場所での、光子の個数をn光子とすると、z=nλ/2の場所でのプランクスケールの電場の変化は、単純に、電場 Ex(z,t)=±E0sin(wt)=±n光子E光子sin(wt) となります。
一方、一般に、電場Eの空間が持つエネルギー密度は、ε0E2/2[J/m3]で求まるのでした。
よって、 z=nλ/2[m]の場所にある1つの原始ヒッグス場ユニットにおけるエネルギー密度EPHU[J/m3]を計算すると、1つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)が作るプランクスケールの電場 は、±E光子sin(wt)なので、エネルギー密度EPHU=ε0×(±E光子sin(wt))2/2=(ε0E光子2sin2wt)/2[J/m3]となります。
ところで、 共転回している間の、原始ヒッグス場ユニット(PHU)が蓄えているエネルギー密度の変化は、エネルギーを放出する分と、エネルギーを吸収する分との間で、位相が常にちょうどπ/2(90度)ずれていることが図からわかります。
よって、共転回を担っている2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるのエネルギー密度の合計は、
ε0E光子2sin2wt+ε0E光子2sin2(wt±π/2)
=ε0E光子2sin2wt+ε0E光子2cos2wt
=ε0E光子2
を1/2倍したもの、すなわち、一定の値として決まります。
つまり、光子を構成する2つの素スピノルが共転回する間、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に、プランクスケールの電場のエネルギーとして蓄えられるエネルギーの合計は、ぴったり一定となっているのです。
なお、プランクスケールの磁場のエネルギーについても、全く同様に考えることができます。
すなわち、光子を構成する2つの素スピノルが共転回する間、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に、プランクスケールの磁場のエネルギーとして蓄えられるエネルギーの合計が、ぴったり一定となっていることを確かめることができます。
※磁場のエネルギー密度は、μ0H2/2で求まる一方で、原始ヒッグス場ユニット(PHU)が作るプランクスケールの磁場も、sin(wt)に比例します。
(z=nλ/2での場所でのプランクスケールの磁場の変化は、磁場 Ey(z,t)=(E0/v)sin(2πz/λ−wt)=±(E0/v)sin(wt)と単純な正弦波となるのでした) よって、プランクスケールの磁場のエネルギー密度は、 sin2wtに比例することになり、なおかつ、エネルギーを放出する分と、エネルギーを吸収する分との間で、位相が常にπ/2(90度)ずれていますので、電場の場合と同様にして、共転回の間、磁場のエルギー密度の総和も一定となることが確かめられます。
以上より、「左巻き素スピノルの転回が関与する“プランクスケールの電場とプランクスケールの磁場”のエネルギー」と「右巻き素スピノルの転回が関与する“プランクスケールの電場とプランクスケールの磁場”のエネルギー」の合計は、常に一定となることがわかります。
よって、「共転回に関わる2つの原始ヒッグス場ユニットの“4面体”に蓄えられるエネルギーの合計」は、ずっと一定のままに、1つの光子が光速で移動していくことになります。
この一定の値、すなわち、1つの光子がもたらす「共転回に関わる2つの原始ヒッグス場ユニットの“4面体”に蓄えられるエネルギーの合計」の値が、まさにアインシュタインの光量子仮説の式E=hν[J]の値、すなわち、「光子1つが持つエネルギーの値」に相当すると考えるとつじつまが合います。
このようにして、振動数ν[回/s]を持つ光子(光の量子波)のエネルギーの総和(原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの総和)は、常に一定のE=hν[J]となることを説明できるのです。
よって、次の結論に至ります。
結論1-1.2 光子を構成する2つの素スピノルを含む、2つの原始ヒッグス場ユニット(PHU)に蓄えられるエネルギーの合計は、常に、一定であり、その値がE=hν[J]である。
※エネルギーの合計が常に一定となるのは、「スピン1を保ちながら、同時に素スピノルのペアが転回できるから(共転回できるから)」に他ならなりません。よって、共転回は、アインシュタインの光量子仮説も根底で支えていることになります。
※例えば、アインシュタインの光量子仮説の式、すなわち、光子が持つエネルギーE=hν[J]から、「素スピノルの転回周期(=原始ヒッグス場ユニットが変形する周期)」をT[s]として、ET=h[J・s]という式を導くことができるのでした。
この「ET=h[J・s]」の式は、(光子を構成する)素スピノルの360度の転回の周期Tが短ければ短いほど、それに反比例して、その“4面体”の変形によって蓄えられるエネルギーの最大値(振幅)が大きくなることを意味していると解釈できるのでした。
そのような性質を原始ヒッグス場ユニット(PHU)が持つからこそ、ET=h[J・s]やE=hν[J]の式が成立すると考えられます。
また、この「ET=h[J・s]」の式は、ハイゼンベルグの不確定性原理の式「ΔE×Δt≧h」と似たものとなっていますが、ハイゼンベルグの不確定性原理(不確定性関係)とは、根本的に異なる内容を意味しています。
なぜなら、「ET=h[J・s]」の式の方は、「光子の持つエネルギー」や「素スピノルの転回周期(=原始ヒッグス場ユニットが変形する周期)」が確定していることを意味しているからです。
この「ET=h[J・s]」の式が、プランクスケールの自然(nature)そのものがどのようにふるまうかを示す式であるのに対し、ハイゼンベルグの不確定性原理の式「ΔE×Δt≧h」は、本来、人間の観測事情(プランクスケールとマクロの相互作用が持っている自然(nature))を示してくれる式であり、プランクスケールの自然(nature)そのものがどのようにふるまうかを示す式ではありません。
(成果3 10《不確定性原理(不確定性関係)と確定性原理(単振動振幅の確定性関係)》)
※E=h/T にT=1を代入すると、E=h[J]となります。
プランク定数hの値の大きさの実体的な意味の1つは、“転回周期1秒で、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”のバネを変形させる際のエネルギー振幅である”ということになります。
(成果3 21《プランク定数、プランクエネルギー、プランク自然定数》)
1つの“光子の量子波”と電磁波の関係について、やや詳しく図示すると次のようになります。
※上が電磁波(複数の光子の総和として創発)であり、下が電磁波を構成する“1つの光子”が生むプランクスケール電場やプランクスケール磁場を示しています。
※下の中の「右巻き」と「左巻き」とは、原始ヒッグス場ユニット“4面体”の中で転回する素スピノルについてのものです。
※“変形している立方体”で簡略表示していますが、厳密には、「“変形している、原始ヒッグス場ユニットの“4面体”」です。 |
この図のポイントの1つは、電磁波の波長に比べて、“光子”を担うとされる「原始ヒッグス場の“4面体”」は、非常に小さい(せいぜい2プランク長(2LP[m])程度である)ことです。
電磁波の波長には、例えば、10[km]に及ぶ長いもの(電波)から、3×10-12[m]ほどの短いもの(γ線)まで、観測されていますが、いずれも、原始ヒッグス場ユニット(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit)のサイズである、およそ2プランク長(2LP[m])≒3.232×10-35[m]よりは、はるかに大きいです。(なお、(電磁波を創発しない)LP光子は、ここで考えていません)
1つ1つの光子は、波長の半分(λ/2[m])の距離ずつ、とびとびに配置された、この小さな中継地点(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”)を土台にして進みます。
個々の光子は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”を変形するだけですので、個々の光子によって生じる電場や磁場の変化は、実際は、2プランク長(2LP[m])程度の非常に狭い範囲に限られて生じていることになります。(それらが、まさにプランクスケールの電場&プランクスケールの磁場に他なりません)
光子の波(=光の量子波)が伝わる様子を、時間経過をやや厳密にして図示すると次のようになります。
※緑の○で囲んだ部分は、“共転回”している最中のものに相当します。
※1つの光子が、とびとびに配置された、この小さな中継地点(原始ヒッグス場ユニット(PHU)の“4面体”)を土台にして進んでいく様子が読み取れます。
※この光子を伝えるとびとびの原始ヒッグス場ユニット(PHU)は、光子の波長の半分(λ/2[m])の距離ずつ離れて配置しています。 |
このように説明できる、たった1つの光子は、まさに、一定のエネルギーを光速で運ぶものであり、“量子波(quantum wave)”という言葉にふさわしいものです。
ここまで、主に、“光子のエネルギー”について説明してきましたが、それでは、“光子の運動量”とは、どのように説明されるのでしょうか?
それを簡単に示すと次のようになります。
共転回の時間経過の詳細を図示すると、次のようになります。
この図の中の、共転回のペアの右側のブルーの素スピノルの動きに注目すると、“4面体”の中の、ある素スピノルが転回する際の、その素スピノルの(小さな)軌道円運動”そのもののおかげで、その運動する方向に、そのまま“4面体”の変形が進むことが読み取れます。
この素スピノルの(小さな)軌道円運動の中に、“光子の運動量”を見いだすことができます。その説明は、下図のようになります。
この光子の運動量の説明は、コンプトン効果を説明するために役立ちます。 (成果3 19《コンプトン効果》)
以上のような、素スピノル物理学パラダイムによる電磁場の幾何的モデルの提案、すなわち、「光子の媒体となる“電磁場”は、原始ヒッグス場(=原始ヒッグス場ユニット(PHU)の総和)の挙動として創発している」という提案は、“エーテルの復活”を意味し、既存の物理学と矛盾しているように思われる方もおられるかもしれません。
しかし、追々詳しく説明していくように、ここに矛盾はありません。(むしろ、逆に矛盾を解消するものです)
ここで簡単に理由を挙げると、次のようになります。
|
1.原始ヒッグス場は、電磁場のみならず、質量(3《質量》)、等速直線運動(5《「重力子&「縮みきり“4角形”」」の働きと運動の第1法則(慣性の法則)&第2法則(F=ma)》)、重力場(時空の曲り)(4《重力の幾何的モデル》、8《“時空の曲がり”と重力場の幾何的モデル》)、電磁気力と重力の統合(11《静電気力と磁力(電荷と磁極のクーロンの法則)および、重力と電磁気力の統合》)、四次元時空連続体… も含めて、統合的に説明できるものである。
※「原始ヒッグス場」という幾何的モデルは、統合的な説明を可能にします)
2.原始ヒッグス場は、“光速度不変性”がなぜ生じるのか(なぜ慣性系で光速度不変性が観測されるか、どのうようにしてマイケルソン-モーレーの観測結果が生じるか)も説明できる。(7《光速度不変性とローレンツ収縮》)
3.原始ヒッグス場は、「マイケルソン-モーレーの観測結果」と矛盾していないのみならず、他ならぬアインシュタインが一般相対性理論(『アインシュタイン選集2』 A10 エーテルと相対性理論)において、(特殊相対性理論で否定されたはずの)エーテルが必要不可欠と考えていた矛盾を解消している。
※アインシュタインは、あくまで“非物質的な新しいエーテル”を考えていました。
原始ヒッグス場は、物質ではない(物質未満の実体である)ので、この“非物質的な新しいエーテル”に相当しうるものです。 つまり、「電磁場や重力場の創発を説明できる原始ヒッグス場」という幾何的モデルには単に矛盾がないだけでなく、特殊相対性理論で「古いエーテル(物質的なエーテル)”が否定されたこと」と、一般相対性理論で「新しいエーテル(非物質的なエーテル)が必要不可欠であると考えられていること」を調和的に説明するものです。
|
|