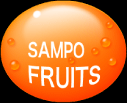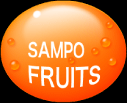2010年12月28日 さんぽフルーツ1.77
となりのコンパス
◎12何も指し示していないということじゃ。→指し示しているとはかぎらないということじゃ。
◎15プチ・マップの作り方── それは、コンパス・オーナー様のお好みでございますぅ〜♪→プチ・マップの作り方は、コンパス・オーナーのお好みでございますぅ〜♪
◎15図示 プチ・マップの作り方は、コンパス・オーナーのお好み
◎19 とその時、 ──あっ! ひらめいた!?→ それから、しばらくすると── ある考えがひらめいた。 ──あっ! もしかして!?
◎19追加 「それから、例えば、頭の中で会話するが『アタマ』の方向にあるとすれば、ちゃんと声帯をふるわせて、声を出して会話するが『カラダ』の方向にあるよ」 図『カラダ アタマ』(頭の中で会話する 声を出して会話する(ちゃんと声帯をふるわせて)) 「ほぃほぃほぃー♪」
◎19その後も、→それをきっかけに、眠気も吹き飛び──
◎19こっちまで眠たくなってきたよ。 ──。 ──ん?→こっちまで眠たくなってきたよ。(一行空ける) ──。 ・・・ ──ん?
◎19頭と体、両方と関連しているんだな──。→『アタマ』の方向と『カラダ』の方向、両方と関連しているんだな──。
◎20一緒に海辺に来ていた僕は── →一緒に海辺に来ていた僕は、
◎20雲だと言葉にする人生が『コトバ』の方向にあるってことかぁ──→雲だと言葉にする人生が『コトバ』の方向にあるってことかぁ
◎20初めて見つけたんだっけ──→初めて見つけたんだっけ
◎21ランピーのぬくもりが手から伝わってくる──。→ランピーのぬくもりが手に伝わってくるのが感じられた。
◎21これらはすべて、言葉にする人生が『コトバ』の方向にあるとすれば── 言葉にする前の様々な感じを、ただただ感じるままの人生が『カタチ』の方向にある── そう言えるんだよ→これらはすべて、“言葉にする人生が『コトバ』の方向にあるとすれば、言葉にする前の様々な感じをただただ感じるままの人生が『カタチ』の方向にある──” そう言えるものたちなんだよ
◎22 余裕のある人生にしよう→彩り豊かな人生にしよう。
◎22 ささやかな人生にしよう→フルーツフルな人生にしよう
ヒストリー
◎2003 そして、自由自在に曲げたりできることにして、→自由自在に曲げたりできることを説明することで
◎2002→2003 (【物語3.02】39の中の“ちょっと曲っちまったけど── まぁ、いいかぁ。”には、そのような意味を込めていました)
◎2003 おかけで→おかげで
7つのコンパス
サンプル 創造する
◎追加
以上は、人生レベルの創造すると言えるものです。〜つまりは、創造し合いの上に、誕生しているようにも思われてきます。
◎2008-2009→2008-2010
サンプル『In Out』
◎追加
近づく 遠ざかる、離れる
近い 遠い
そばにいる、近くにいる 離れている
◎修正
プチ・マップを広げて見る 人生をそのまま見る→人生をそのまま見る プチ・マップを広げて見る
遠くに光る“キラリ”を、カシャ! 近づいて、おじいさんの笑顔を、カシャ!→近づいて、おじいさんの笑顔を、カシャ! 遠くに光る“キラリ”を、カシャ!
サンプル『On Off』
◎削除 近づく、
◎削除 遠ざかる、
◎修正 誰か →誰からしく
◎重複のため下部で削除 (場所が)下 (場所が)上
◎これ/this あれ/that→これ/this それ/it あれ/that
◎下部で削除 これ それ あれ
2010年10月2日 さんぽフルーツ1.76
音楽
◎曲の追加 Joy(Joy of SAMPO)
◎3曲ほど、ささやかな作品をアップしています。
Love.MP3 MDCT.MP3 Sampo's kanon.MP3 ずっと前に作曲したものです。 木岬さんぽ
→4曲ほど、ささやかな作品をアップしています。 木岬さんぽ
Joy(Joy of Sampo).MP3 Love.MP3 MDCT.MP3 Sampo's kanon.MP3
2010年9月6日 さんぽフルーツ1.75
7つのコンパス
物語3.02
◎7追加 そして、口の中のイチゴを味わい、ほとんどすべてを飲み込んだ僕は、ようやく口を開いた。
◎13忘れないように一応書き留めておくかぁ。→一応、忘れないように書き留めておくかぁ。
◎14「コンバンハでございますぅ〜♪」 ──!!!
→「コンバンハでございますぅ〜♪」
「──」 ──!!!
◎14夢ではないでございますぅ〜♪→「──」 夢ではないでございますぅ〜♪
◎14 本当ですぅ〜♪→ 「──」 本当ですぅ〜♪
◎14 ──!!!→ 「──」 ──!!!
◎16床から数10センチの空中に、ペーパーコンパスがフワフワと浮かんでいたのだ。→そこには、床から数10センチの空中にフワフワと浮かんでいるペーパーコンパスの姿があった。
◎17地図で見るのと同じで──→地図で見ていたのと同じで──
◎17僕の目は、大きく見開かれたんだ。→僕は、目を大きく見開いたんだ。
◎18 スーっと→スーッと
◎18 両腕がジワジワと疲れてきた──→両腕がジワジワと疲れてきた。◎18 ──ゴトッ。の前の改行を増やす。
◎19「あれ、わかったかもしれない。
プチ・マップの作り方──」
→「あれ、わかったかもしれない。 新たなプチ・マップの作り方──」◎19 「あ、ごめん、ごめん。 そうだったんだね──。→「あ、そうだったんだね。 ごめん、ごめん。
◎19 じゃあ、また、のちほどゆっくり。 おやすみ」
「──ふわあぁぁ〜♪ ゴメンナサイですぅ〜♪ シツレイですぅ〜♪」
→じゃあ、また、のちほどゆっくり」
「ふわあぁぁ〜♪ ゴメンナサイですぅ〜♪ シツレイですぅ〜♪」
「あぁ、おやすみ」
◎19 「ふわあぁぁ〜。 なんだか、こっちまで眠たくなってきたよ」→「ふわあぁぁ〜」 なんだか、こっちまで眠たくなってきたよ。(黒→青)
◎19 黒→青 コンパスの気持ちを、こちらの体をふるわせてキャッチする、感情移入の人生が『カラダ』の方向にあるとすれば── コンパスの気持ちを頭の中で思い描く、想像の人生は、相対的に『アタマ』の方向にあるんじゃないか?
◎20 駆けまわっていた── →駆けまわっていた。
◎20 心地いい波の音──。→心地いい波の音が聞こえた。
◎20 水平線の上に→水平線の上には、
◎20 「そう。 つまり── まとめれば、次のようになる──」
→「うん。 そうすると── これらは、1つの地図にまとめることができるよ」
◎21の図中で ゴンピーのおなか→ランピーのおなか
◎21 シュークリームにそっくりな形をした雲が、上空に浮かんでいることに気づいた。→ふと見上げると、上空に、ある白い雲が浮かんでいて、その形がシュークリームにそっくりであることに気付いた。
◎21 完璧にシュークリー厶だなぁ。 あぁ、うまそう。
──あぁ、はら減ったー。 食いてぇ──。
──。 ──あっ、そうだ! 新しいこと、ひらめいた!」
→完璧にシュークリー厶だね。 あぁ、うまそう」 ──あぁ、はら減ってきたー。 ・・・ ──。 「──あっ、そうだ! 新しいこと、ひらめいた!」
◎21 「そうすると── それは、おいしい、眠い、心地いい、波の音、座っている … どれも同じなのさ。 これらのように、言葉にする人生が『コトバ』の方向にあるとすれば── 言葉にする前の様々な感じを、ただただ感じるままの人生── それらが『カタチ』の方向にあるんだよ。 ※図 そして、それは── 白いやぬくもりについても同じことで── つまり── “ふつうの形”を見たりふれたりして感じるままの人生だけでなく、色、温度、味、音、匂い、体の中の感覚、感情、情動 … を感じるままの人生も『カタチ』の方向にありうるってことなんだ──」
→「そういう意味で── おいしい、眠い、気持ちいい、心地いい波の音、座っている、ぬくもりがある、白い雲が見える … どれも、きっと同じなのさ。これらはすべて、言葉にする人生が『コトバ』の方向にあるとすれば── 言葉にする前の様々な感じを、ただただ感じるままの人生が『カタチ』の方向にある── そう言えるんだよ」 ※図
◎適宜、空白の調節あり。
サプリ
◎1番目のコンパス 『カタチ コトバ』
“色、ぬくもり、空腹感・・・”と言葉にされる前のもの── →“色彩、温度、味、音、匂い、体の中の感覚、感情、情動 … ”について、言葉で表現される前のもの──
◎1番目のコンパス 『カタチ コトバ』 言葉の反対の方向の意味を持つものとしての『カタチ』です。→言葉の反対の方向の意味を持つものとしての『カタチ』──広義の『カタチ』です。
サンプル
◎4番目のコンパスにおいて追加
近づいて〜♪ 近づかないで〜♪
◎6番目のコンパスにおいて削除
近づいて〜♪ 近づかないで〜♪
サンプル
◎心 不可能です。 きっと、どんなに科学が進歩しても──。 (間接的にたどり着く技術には、至っているようですが…)→難しいと思います。
◎心 自分自身の感動や行動の心としての一面です。→例えば、自分自身で心の動きとして認識するところの、感動や行動です。
◎心 外から捉えうる、『アタマ』〈Brain〉に相当するもの→外から捉えうる、『アタマ』〈Head〉の方向のもの
◎心 図削除 『On Off』 心がある 心がある
◎心 追加 社会に心があるのでしょうか?──
◎心 追加 (想像することはできますが── 例えば、ある人生がここまで豊かな心を持っていることを個々の細胞が知り得ないように、個々の人には知りえないことではないかと思います)
◎心 心をみようとしてきました。→心を見ようとしてきました。
さんぽフルーツトップページ、ロゴのページ
◎SAMPO All→SAMPO,All
2010年7月8日 さんぽフルーツ1.74
物語3.02
◎6 ぐうー・・・ お腹が鳴った。
→なんで、よりによってイチゴなの? 女子じゃあるまいし── ぐうー・・・ お腹が鳴った。
◎7において追加
──。 こんなにおいしいイチゴ、生まれて初めてかも──。
◎11今、自分は、どの方向にいるのか── どの方向に向かおうとしているのか──→今、自分は、どの方向にいるのか、どの方向に向かおうとしているのか
◎11「──。 うん──」→「──。 ウン──」
◎11道しるべ──→ミチシルベ──
◎11図追加 人生のあらゆる状況に合わせて、役立つ地図を作ることができる
◎12どの方向へ進むのがいいか→どの方向へ進むのがいいのか
◎12図追加 それら自体は、本来、“どこへ向かうべきか、どの方向へ進むのがいいのか”を、何も指し示していない
◎13とっさに地図を放り投げると、→とっさに地図を放り投げ、
◎14 書き入れてくださる方── 所有してくださる方のことですぅ〜♪→書き入れてくださっている方── 所有してくださっている方のことですぅ〜♪
◎17そして、しばらくすると、→しばらくすると
◎17 「〜見る見る遠ざかっていくのがわかった。」と「しばらくすると、〜」の文の間を1行空ける。
◎17「〜、静止した。」と「そこは、地元全体を〜」の文の間を1行空ける。
◎17その海岸線は、地図で見るのと同じ形で→その海岸線の形は、地図で見るのと同じで
175
◎変化次第じゃないかなぁ。→選択次第じゃないかなぁ。
◎方向転換できるような人生であれば── “Against Life”から、ほど遠くなることが可能なんだよ→方向転換するような人生を選択するならば── “Against Life”からほど遠くなり、“For Life”に近づくことが可能なんだよ
◎ちょっと違うような…→ちょっと違くない? …
更新履歴
◎13書きもれの追加
まぁ、どうでもいいけど、忘れないように一応書き留めておくかぁ。
7つのコンパス サンプル
◎3番目のコンパスにおいて追加 ミランコビッチサイクル
◎4番目のコンパスにおいて追加 ためになっている ためなっていない
◎5番目のコンパスにおいて追加 害になっている ためなっている
◎6番目のコンパスにおいて追加 「「ために」という言葉や思いからやっていることが、本当に相手のためになっている。(→ありがたい) 「ために」という言葉や思いからやっていることと、本当に相手のためになることが、ズレている。
◎6番目のコンパスにおいて追加 ためにと、おかげがかみ合っている。(→「喜んでくれてよかった」「おかげ様で助かった」という互いの満足) ためにと、おかげがずれている。(→「せっかく、あなたのためにやったのに」という恩の押しつけ)
研究1.06→1.07
エコ分野での応用例──
◎今、少なくとも4つ挙げられる。
1.温度を調節するために、水も効果的に使う。(H2Oの循環の強化、多重的な対策) (by生態系と生体の類推──)
生体は、何かある目的を達成するために(例えば、血糖値の下がり過ぎを防ぐ、体温の上がり過ぎを防ぐ、血圧の下がり過ぎを防ぐ …といった目的)、多くの場合、同時に何重にも対策を重ねている。 そうすることで、より安全に、より安定的に(確実に)、その目的を達成している。
例えば、“体温が上がりすぎないようにするため”に、人を含む、多くの生体(特に恒温動物)は、運動を減らす(代謝を低下させる)、水を用いて涼しくする(発汗、湖水浴、水風呂、水シャワ…)、血管の拡張させる、日陰に移動する、移住する 等々、様々な方法をとっている。
これらのことは、生態系の温暖化対策のために、二酸化炭素の排出を減らすこと、単独の方法に頼るべきではないことを示していると思われる。
特に、“発汗”のシステムが長い進化の歴史を経て採用されてること──とりわけ恒温動物にとって、その活動を維持しながら温度を下げることのできるしくみであることに着目すれば、 “生態系の温度が上がりすぎを防ぐ”ためには、二酸化炭素の排出を減らす(大気中の二酸化炭素を削減する)ことにプラスして── “水を活用する”ことを同時に進めていくことも、大切であることが類推される。
その際、例えば、人工降雨、打ち水、海水を濾過して真水にする技術 … が活用できると思われる。
その中で、“発汗”に近いという意味で、打ち水に着目すると── さらなる効果的な“打ち水”効果を利用できるシステムの開発も有効であると思われる。(例えば、道路から一斉に放水して潤す等の技術 … ) そのためにも、水不足の問題を抱えた地域をも念頭においた、すぐれた水循環を開発し、構築することが重要である。 乾燥地帯を含めて、どこへでも効率的に水を届けられるような、“水のパイプライン網”等を作るために、生体の血管網から学び──何十億年もの進化の歴史のつまった“生体”を、多いに模倣して──創造していくことも有効であると考えられる。 (当然、水が確保できれば、植物の生存の可能性も高まり── 植物が生育することができれば、大気中の二酸化炭素の削減へとつながるというメリットも生ずる) また、人工降雨などの“大気中の水の移動をコントロールし活用する”技術は、パイプライン同様、打ち水効果を利用するという意味においても有効であると考えられる。
このように、水を上手に循環させて、過剰な温暖化を予防する技術が開発できれば、同時に、過剰な寒冷化を予防することも可能になると考えられる。
二酸化炭素の削減に加えて、類い稀な比熱を持つ“水”の活用も同時に重ねて進めることが、生態系の温度をコントロールする(気温の上がり過ぎ、下がり過ぎの両方の予防していくこと)ために、より確実(安定的)で、迅速・安全で、合理的・効率的である。
2.生体の持つエネルギー産生を模倣した(ヒントにした)エネルギーシステムの開発も進める。 (多重的な対策) (by生態系と生体の類推──)
生体は、時には既存のものをフルに活用し、時には必要なものを自分で作り出して利用することで生存してきている。 また、時には、一見、脅威にみえる要素を恩恵に変えるように進化することによっても、生存してきている。(例、酸素を脅威から恩恵に変える)
太陽光や二酸化炭素を活用してエネルギー等を蓄える植物たち、そのエネルギー等を消費して二酸化炭素を供給する動物たち、これらの両者の営みが、うまくバランスがとれていたことが、長い生態系の歴史の礎であった。
もし、エネルギー等を消費する人間たちがいて、それらに釣り合うエネルギー等を、太陽エネルギーから合成することができれば、これからの長い生態系の歴史も築いていけると考えられる。 その際、何十億年もの進化の歴史がつまった生体が持っている、非常に効率的な仕組みを、おおいにヒントにしたり、模倣したりしていくことも有効であると考えられる。
(1)太陽光発電は、理にかなっている。
※生体が光合成する目的は、エネルギーの確保のみならず、生体の材料の確保にもある。
エネルギー収支の優れた太陽光発電によって、太陽光エネルギーから直接電気を作るのは、とても効率的である。
(日照時間の多い)砂漠地帯等への設置が、脅威を恩恵に変えるという意味でも、よいと考えられる。
(2)光合成の所産は、原則として、食料や材料として活用し、燃料としての活用は、非常時のみにする。 ※生体が光合成する目的は、エネルギーの確保のみならず、生体の材料の確保にもある。 そうした所産を燃料だけのために利用するのは、非効率的であり、非常にもったいない。 そういう意味で、何かの材料としても活用できる石油を、燃料のためだけに使うことも、もったいないと言える。 (そういう意味で、“低炭素社会”が目指す方向性は、よいと考えられる。 しかし、食料── 炭水化物(ブドウ糖)、タンパク質(アミノ酸)、脂肪(脂肪酸)… の主要な骨格が“炭素”であることも考慮に入れれば、“低炭素社会”よりも“低炭素燃料社会”の方がより適切な表現であると言えるのかもしれない)
(3)太陽光を利用できない時などの非常時のために、枯渇エネルギー(核燃料等)は、できる限り、確保しておこうとする。 ※生体は、飢餓状態などの非常時にのみに、タンパク質や脂肪をエネルギー源にする。
(4)“二酸化炭素の吸収”を伴う光合成をヒントにして(or模倣して)、“メタンの吸収”をともなう合成の仕組みを見つけ出す(or 作り出す)
※生体(葉緑体)は、二酸化炭素(CO2)を吸収し、カルビン・ベンソン回路によって、“少しずつのステップを積み重ねる回路”を頻回繰り返すことで、エネルギーや生体の材料となる炭水化物を生み出している。 このカルビン・ベンソン回路を適宜ヒントにし(模倣し)、もし、メタン(CH4、これ自体も燃料にもなる。メタン菌※1 等の活用が理想)を吸収し、“少しずつのステップを積み重ねる回路”を頻回繰り返すことで、ナフサ等の石油の一部を合成するような技術(油母経由でなく、直接各種アルカンを生み出す技術)を開発する。 なお、その所産は、原則として“材料”として活用し、燃料としての活用は非常時のみにする。 (メタン菌※1 各種ある中で、特に“二酸化炭素と水素を材料としてメタンを生成する”メタン菌)
・・・
当然、エネルギー確保に関しても、多重的な取り組みが重要となることが類推される。
3.温室効果ガス(二酸化炭素やメタン…)を有効活用することで減らしたりする(上手に循環させることでコントロール)技術の開発もめざす。(CO2,CH4 …の循環の強化、多重的な対策)
かつて地球上に生存していた多くの生物にとって脅威であった酸素が増加したことで、結果的には、それを有効活用できる種類の生物(現在多くを占める植物&動物)が繁栄することとなった。 一見、脅威である二酸化炭素(メタン)が増えていることは、それを有効活用できる生物(orメタン活用のシステム)が繁栄するチャンスでもある。
高濃度の二酸化炭素は、光合成を進める植物やメタン菌等にとって、貴重な恩恵である。 二酸化炭素を資源(恩恵)とできる生物に二酸化炭素を大いに吸収してもらい減らしていこうとすることは合理的である。 その意味でも植林は、とても重要であろう。 また、2の(4)で述べた、メタン(温室効果は、二酸化炭素の21倍)を活用できる技術を開発することも、過剰な温室効果ガスをコントロールする意味においても重要となると考えられる。
もし温暖化の抑制を目指す際ならば、温室効果ガスの排出を減らすことにプラスして、温室効果ガスの有効活用を同時に進めていくこと── こうした多重的な取り組みが、より確実であり、合理的であることが類推できる。
(おな、水蒸気も温室効果ガスの一種である。 その意味においても、1で述べた水の循環の重要性が認められる)
4. 生態系やエネルギーをしかっりモニターした上で予測し、最適な方向を選択できるシステムを開発する。
生体には、原則として、一方通行はない。 体温が上がりすぎないように下がりすぎないように── 二酸化炭素が増えすぎないように減りすぎないように── ブドウ糖(エネルギー源)が増えすぎないように減りすぎないように── … 両方を調節するような能力を獲得することで、生存し続けている。
生態系も同様であろう。
気温が上がりすぎないように、下がりすぎないように── 二酸化炭素も増えすぎないように、減りすぎないように── エネルギーが過剰にならないように枯渇(不足)しないように── … 各種要素の両方を調節できるシステムを育むことが大切になると考えられる。
温度について見れは、温暖化のみでなく、寒冷化(氷河期)も含めた、両方の予防を目指し── 二酸化炭素であれば、その過剰だけでなく、過少も含めた両方の予防を目指し── エネルギーであれば、枯渇だけでなく、その過剰も含めた両方の予防を目指す── ということである。
つまり、狭い&広い両方の視野で見すえ、短い&長い両方の目で見すえ── その都度、具体的な、めざすべき最適な状態や方向を設定し── 予防的に余裕をもって対応していけるようなシステムを作ることが重要であることが類推できる。
この的確な予測対応システムの構築は、非常に困難を伴うものになると思われる。 しかし、そうした困難を乗り越えて出来上がるシステムでなければ本物ではない。
あらゆる分野の知見、知恵、体験 … を総動員して、社会全体で、このシステムを創造し、進化させ続けていくことが必要であると思われる。
→
生体は、何かある目的──例えば、血糖値の下がり過ぎを防ぐ、体温の上がり過ぎを防ぐ、血圧の下がり過ぎを防ぐ … といった目的──を達成するために、多くの場合、同時に何重にも対策を重ねている。 そうすることで、より安全に、より安定的に、より確実に、その目的を達成している。
例えば、“体温が上がりすぎないようにするため”に、人を含む、多くの生体(特に恒温動物)は、運動を減らす(代謝を低下させる)、血管の拡張させる、すずしい風にあたり放熱する、日陰に移動する、移住する、水を用いて涼しくする(発汗、湖水浴、水風呂、水シャワ…) 等々、様々な方法をとっている。
これらのことは、“生態系の温度の上がりすぎを防ぐためには、二酸化炭素の排出を減らせばよい”というように、単独の方法に頼るべきではないことを示していると思われる。
生態系と生体の間に、次のようなパラレルな関係がある。
|
生態系
|
生体
|
|
海流、河川の流れ
対流圏での水の流れ〈降雨、降雪、蒸発…〉
|
血流(循環)
|
|
大気から宇宙への放熱
(水蒸気→水滴→雨、雪)
〈水蒸気が放熱することで、水滴──雨、雪となる〉
|
皮膚からの放熱
〈風があたることで、空気が、熱を吸収して持ち去る〉
|
|
-
|
発汗〈皮膚〉
(汗→水蒸気)
〈蒸発することで、汗が熱を吸収する
〈体表面から熱を持ち去る〉〉
|
|
大気のバリア
〈対流圏(温室効果ガスの層…)、
成層圏(オゾン層…) …〉
|
皮膚のバリア
|
|
雲、エアロゾル … による太陽光の反射
|
日陰に避難〈木陰、屋根の下…〉
衣類、帽子で、太陽光を遮蔽
|
|
雲、積雪、… による太陽光の反射
|
日焼け止め … よる太陽光の反射
|
|
光合成の所産を消費することで、
大気中にCO2が溜まる
|
代謝することで、体内にCO2が溜まる
|
|
光合成することで大気中のCO2が減る
|
息を吐くことで体内からCO2を排出する
|
太陽光エネルギー
地熱
地球の核のエネルギー
→空気の移動(風、対流)、河川、潮の流れ、
海流、大陸の移動 …
|
食糧につまったエネルギー
植物につまったエネルギー
(光合成の所産)
→血流(循環)、呼吸、消化、運動、思考…
|
|
太陽光発電→電気
風力、水力、潮力→電気
核燃料→電気
地熱→電気
|
食糧→仕事+カロリー or 生体の材料
化石燃料→電気 or 物作りの材料
|
|
…
|
以上のことをふまえ、何十億年もの進化の歴史のつまった“生体”も多いにヒントにして、温暖化に向けた対応策を、いろいろ創造していくことが有効であると考えられる。
1.生体の持つ温度維持のしくみを模倣した、生態系における最適な温度維持システムの開発も進める。 (by生態系と生体の類推──)
それは、いわば、“生態系の恒温化”を目指す営みである。
もし温暖化の抑制を目指す際であれば、温室効果ガスの排出を減らす対策──生体では、代謝を低下させることに対応──にプラスして、温室効果ガスの有効活用を同時に進めていくなどの多重的な取り組みが、より確実で合理的である。
少なくとも2つの追加手段が考えられる。
(1)“呼気”に相当する、“温室効果ガス(二酸化炭素やメタン…)を生態系から排出するシステム”を、より効果的なものにする。
(2)“発汗”に相当する、“効果的&一時的に温度を下げるシステム”を確立する。
・効率的な生態系放熱システムを開発する。
・効果的な“日陰”システムを開発する。(エネルギー確保を維持しながら)
(1)“呼気”に相当する、“温室効果ガス(二酸化炭素やメタン…)を生態系から排出するシステム”を、より効果的なものにする。
かつて地球上に生存していた多くの生物にとって脅威であった“酸素”が増加したことで、結果的には、それを有効活用できる種類の生物(現在多くを占める、好気的な植物&動物)が繁栄することとなった。 一見、脅威である二酸化炭素(or メタン)が増えていることは、それを有効活用できる生物(or メタン活用のシステム)が繁栄するチャンスでもある。
高濃度の二酸化炭素は、光合成を進める植物やメタン菌等にとっては、貴重な恩恵の1つである。 二酸化炭素やメタンを資源として活用できる生物やシステムに二酸化炭素を大いに吸収してもらい減らしていこうとすることは合理的である。
1つは、新しい植林を通じて、フレッシュな木を育てることが重要であり、とても理にかなっていると思われる。
“成熟しきった森”は、カーボンニュートラルなので、“新しい森”の方が、二酸化炭素の吸収の能力が高い。 したがって、場合によっては、“既存の森の一部を伐採し、物作りの材料としてそのまま活用すると同時に、すぐに植林する──つまり、計画的に伐採して、計画的に植林する”を繰り返すという営みも効果的であろう。
伐採した木材は、燃料として燃やさず、木工製品、紙製品 … などの各種、製品として長期間活用するならば、それらは、二酸化炭素を蓄えてくれる貴重なCO2の貯蔵タンクとなりうる。
また、稲作で生じたワラ、い草 … を活用した製品も同様に、CO2の貯蔵タンクとなりうる。
もし、乾燥地帯への水の供給する技術が開発出来るのであれば、植物を新たに生育させることができるので、これも、新たな二酸化炭素の貯蔵タンクを増やすことにつながる。
(その際は、人工降雨などで“大気中の水の移動をコントロールし活用する”技術、海水を濾過して真水にする技術、水道の技術 … が役立つと考えられる)
一方、“二酸化炭素の吸収”を伴う光合成を模倣して、“メタンの吸収”をともなう合成の仕組みを開発できれば、とても有効であると考えられる。
生体の中の葉緑体は、二酸化炭素を吸収し、カルビン・ベンソン回路──“少しずつのステップを積み重ねる回路”──を頻回繰り返すことで、エネルギーや生体の材料となる炭水化物を生み出している。 このカルビン・ベンソン回路を適宜ヒントにし、メタン※1 を吸収し、“少しずつのステップを積み重ねる回路”を頻回繰り返すことで、ナフサ等の石油の一部を合成するような技術(つまり、油母経由でなく直接各種アルカンを生み出せる技術)を開発できれば、温室効果ガスの効率的な削減のコントロールの可能性が高まることを意味する。 なお、こうしてできる所産は、できるだけプラスチックやゴム等の物作りの“材料”として活用すれば、メタンの貯蔵タンクとなりうる。
(※1 メタンCH4、これ自体も燃料にもなる。 もし、大気中のメタンが減少し、原料不足となるならば、(メタンの貯蔵の意味では逆行するが)海底のメタンやメタン菌等を活用することも1つの手段であろう。 なお、この際のメタン菌は、各種あるのメタン菌の中で、特に“二酸化炭素と水素を材料としてメタンを生成する”メタン菌が有効であると思われる)
もし、寒冷化に際し、CO2濃度等を高める必要がでてくれば、木材、紙、プラスチック、ゴム、ナフサ等を、燃料として転用し、二酸化炭素を大気中に供給すればよいことになる。
二酸化炭素やメタンを有効活用しつつ、何かに吸収させて貯蔵し減らす技術は、“下がりすぎたら逆に上げられる”という柔軟性を持つかどうかが重要なポイントの1つであると思われる。
(2)“発汗”に相当する、一時的に効率的に熱を下げられるシステムも開発する。
特に恒温動物である生体においては、体温がある程度上がると汗を出す。 その汗が気化する際に多くの熱を吸収することを利用することで、生体は、大量の熱を効率的に放出する。
生態系の恒温化においても、このような一時的に効率的に体温を下げる仕組みが、生態系にもあってもおかしくないことが類推できる。
(海面や地面からの水の蒸発は、発汗とパラレルではない。 水蒸気は、大気中にとどまり、温室効果ガスの一部として熱を蓄えうる。 水蒸気、そして、雲は、生態系の一部そのものであり続けている。 また、水蒸気が、再び、水や氷に相転移する際、宇宙空間への放熱することも、“発熱”とは、パラレルではない。 これとパラレルなのは、風にあたることで熱を放熱することである)
温室効果ガスとは、ビニールハウス効果ガスである。
例えば、“ビニールハウス”の中で、蒸し暑くて蒸し暑くてどうしようもなくなれば、どうするか?
1つは、ビニールの一部を一時的に開放することで、風通しをよくすることが考えられる。
ビニールに相当する、温室効果ガスの層を、なんらかの手段で部分的に解放して、対流圏と成層圏の間の風通しをよくするこはできないだろうか? もし、オゾンホールならぬ、“温室効果ガスホール”のようなものを形成したり消滅させたりを、安全に自由自在にできるようになれば、それは、生態系の温度維持のために効果的に役立つと思われる。
もう1つは、ビニールハウスの外面に、何かの日陰を設けることが考えられる。
実際は、温室効果ガスの層であるので、そこより上部に、太陽光を反射する日陰を作れば良いことになる。
例えば、次の条件を満たす、何かの理想的な浮遊物(エアロゾル …)を開発できればいいのかもしれない。
あるいは、いっそうのこと、ビニールハウスの屋根を一時的におおえるような太陽光発電パネルがあればいいのかもしれない。 これは、エネルギー確保を維持しながらクールダウンもできる“理想的な日陰”になりうる。
2.生体の持つエネルギー産生を模倣したエネルギーシステムの開発も進める。 (by生態系と生体の類推──)
生体は、時には既存のものをフルに活用し、時には必要なものを自分で作り出して利用することで生存してきている。 また、時には、一見、脅威にみえる要素を恩恵に変えるように進化することによっても、生存してきている。(例、酸素を脅威から恩恵に変える)
太陽光や二酸化炭素を活用してエネルギーや酸素などを蓄える植物たち、そのエネルギーや酸素を活用し、二酸化炭素などを再び供給する動物たち、これらの両者の営みが、うまくバランスがとれていたことが、これまでの長い生態系の歴史の礎であった。
もし、エネルギー等を消費する人間たちがいて、それらに釣り合うエネルギー等を、太陽光などから十分確保することができれば、人間たちのいる生態系も、長い歴史を築いていけると考えられる。 その際、何十億年もの進化の歴史がつまった生体が持っている、非常に効率的な仕組みを、おおいにヒントにしていくことも有効であると考えられる。
(1)太陽光発電は、理にかなっている。
※生体が光合成する目的は、エネルギーの確保のみならず、生体づくりの材料の確保にもある。
エネルギー収支の優れた太陽光発電によって、太陽光エネルギーから直接電気を作るのは、ムダが少なく、とても効率的である。
どうしても植物を育てられないような(日照時間の多い)砂漠地帯等で太陽光発電機を設置することは、脅威を恩恵に変えるという意味で、よいと考えられる。 あるいは、広大な海面に浮かべるタイプや、日陰を作り出しうる空中(時に宇宙空間?)に浮かべるタイプも、有効なのかもしれない。
(2)光合成の所産は、原則として、食料or物作りの材料として活用し、燃料としての活用は、非常時のみにする。
※生体が光合成する目的は、エネルギーの確保のみならず、生体づくりの材料の確保にもある。
そうした所産を燃料だけのために利用するのは、非効率的であり、非常にもったいない。
したがって、何かの材料としても活用できる石油を、燃料のためだけに使うことも、もったいないと言える。
(そういう意味で、“低炭素社会”が目指す方向性は、よいと考えられる。 しかし、食料── 炭水化物(ブドウ糖)、タンパク質(アミノ酸)、脂肪(脂肪酸)… の主要な骨格が“炭素”であることも考慮に入れれば、“低炭素社会”よりも“低炭素燃料社会”の方がより的を得た表現であると言えるのかもしれない)
(3)太陽光を利用できない時などの非常時のために、枯渇エネルギー(核燃料、化石燃料等)は、できる限り温存しておこうとする。
※生体は、飢餓状態などの非常時にのみに、タンパク質や脂肪をエネルギー源にする。
(4)“水の特性を活用することで、エネルギーを節約する。
※類い稀な比熱を持つ水は、すでに、生態系においても十分活躍してきている。
実際、生態系において、水は、特に液体(海 …)という形で、保温剤、保冷剤両方の働きをしている。(なお、極端に寒くなり固体(雪、氷)として存在すれば、日光を反射し、ますます寒い環境を維持する保冷剤としてのみ働き、極端に暑くなり気体(水蒸気)として存在すれば、温室効果ガスという名の保温剤としてのみ働く)
例えば、個々の家庭での温度調節のために、水を活用するのは、理にかなっていると思われる。 打ち水・霧吹き、水風呂、雪室 … が活用でき、エアコン等の使用量が減れば、エネルギーの節約につながり、場合によっては二酸化炭素の排出の抑制へとつながる。
・・・
当然、エネルギー確保に関しても、多重的な取り組みが重要となる。
3. 生態系の温度やエネルギーの状態をしかっりモニターした上で、予測し、最適な方向を選択できるシステムを開発する。
生体には、原則として、一方通行はない。 体温が上がりすぎないように下がりすぎないように、二酸化炭素が増えすぎないように減りすぎないように、ブドウ糖(エネルギー源)が増えすぎないように減りすぎないように … 両方を調節するような能力を獲得することで、生存し続けている。
生態系においても同様に──
気温が上がりすぎないように下がりすぎないように、二酸化炭素も増えすぎないように減りすぎないように、エネルギーが過剰にならないように枯渇(不足)しないように … 各種要素の両方を調節できるシステムを育むことが大切になると考えられる。
例えば、温度について見れは、温暖化のみでなく寒冷化(氷河期)も含めた両方の予防を目指すことが大切になるということである。
その際、例えば、二酸化炭素濃度が空気中に適量存在することは、過剰な温暖化、過剰な寒冷化のどちらにも、かたむいていないことを示す大切な指標の1つとなるであろう。
また、水が大量に凍りもせず、大量に蒸発もせず── 水が、液体として、ほどよい量で、良好に循環し続けているということも、そのことを示す重要な指標の1つとなるであろう。
もちろん、既存の指標以外にも、新たな指標を開拓して行こうとするとことも大切になると思われる。
日々、月々、年々の状況や変化を、広い&長い視野で見すえ、その都度、具体的な、めざすべき最適な状態や方向を設定し── 早め早めに余裕をもって予防対策をしていけるようなシステムを作ることが重要となる。
この的確な予測対応システムの構築は、非常に困難を伴うと同時に、日々進化し続けていくべきものであると思われる。
あらゆる分野の知見、知恵、体験 … を総動員して、社会全体で、このシステムを創造し、進化させ続けていくことが必要であると思われる。
2010年5月20日 さんぽフルーツ1.73
研究トップ
◎ネルギー保存則→エネルギー保存則
◎4つの力→4つの力〈弱い力、強い力、電磁気力、重力〉
3Steps理論とその応用についてトップ
◎4つの力→4つの力〈弱い力、強い力、電磁気力、重力〉
トップページとロゴのページにおいて
◎音楽と7つのコンパスの間を空ける。
7つのコンパス
トップページ
◎細胞、細胞の社会(健康)、人間社会、生態系(エコシステム) … のためのもの→日常生活、人間社会(経済…)、細胞&細胞の社会(健康、生命…)、生態系(エコシステム) … のためのもの
サプリ 『カタチ コトバ カラダ アタマ』
◎そこに登場する“形”は、“頭の中に思い描く夢を現実のものにする”という意味でしょう。→そこに登場している“形”は、現実という意味でしょう。
◎見なします→見なしています。
◎つまり、ここにある“形”とは、“言葉”の反対の方向の意味を持つものとしての“形”です。→つまり、ここにある『カタチ』とは、“言葉”の反対の方向の意味を持つものとしての『カタチ』です。
◎もう1つは、“色、ぬくもり、空腹感・・・”と言葉にされる前のもの── それらも、すべて『カタチ』の方向にあると見なします。 つまり、ここにある『カタチ』は、『コトバ』の反対の方向としての『カタチ』です。
もちろん、そのような意味は、まだ一般的ではありません。 しかし、それは、ぜひとも表現する価値のある、もののとらえ方だと思います。 そして、その願いがつまった表現がアウトラインの括弧付きの『カタチ』── そして、『コトバ』です。
このように、『コトバ』と『カタチ』は、お互いに反対の方向にあるととらえる結果、応用範囲がとても広がります。→そして、もう1つは、“色、ぬくもり、空腹感・・・”と言葉にされる前のもの── それらも、すべて『カタチ』の方向にあると見なしています。 つまり、ここにある『カタチ』とは、“言葉”の反対の方向の意味を持つものとしての『カタチ』です。 もちろん、そのような意味は、まだ一般的ではありませんが、それは、表現する価値のある、もののとらえ方であると思います。 アウトラインの括弧付きの『カタチ』と『コトバ』は、そのような意味を持っています。 その意味で使う結果、『カタチ』と『コトバ』は、応用範囲がとても広がります。
◎改行の修正あり
物語3.02
◎0しばし、それまでのいきさつが、走馬灯のように頭の中を流れた──。→それまでのいきさつが、しばし、走馬灯のように頭の中を流れた。
◎1見つけたことだった──。 ん?→見つけたことだった。 ──ん?
◎1近づいてみると、それは、→ 近づいてみると、
◎1ビンの中から取り出して広げてみると、→ビンの中から、それを取り出して広げてみると、
◎1愛犬のゴンピー→愛犬のランピー
(以下のゴンピーについて、ゴンピー→ランピー)
◎1 決めたんだ──。→決めたんだ。
◎2頭をこちら側に向けて横になっていた──。→頭をこちら側に向けて横になっていた。
◎2ゴ、ゴンピーの散歩?→ラ、ランピーの散歩?
◎2 僕はなぜか→なぜか僕は
◎2秘密にすることにした──。→秘密にすることにした。
◎3余分な部分の削除 ちょっくら穴でも掘ってやろうかなと、だったから──、
◎3追加 「ほう、そうか──」
◎3 「ん? どうした?」→「──ん? どうした?」
◎3 なんか、ビビって足が動かない→なんか緊張しすぎて足が動かない
◎3 ──どうなってんだ?→どうなったんだ?
◎3アッハッハッ!!→アッハッハッ!
◎4おじいさんから少し離れた場所に→おじいさんとランピーから少し離れた場所に
◎4水平線が広がっているのが見えた──。→水平線が広がっているのが見えた。
◎4一致していたんだ──。→一致していたんだ。
◎5やはり、なんの反応もない。→やはり、なんの反応もなかった。
◎5声を大きくして言ってみた。→声を大きくしてみた。
◎5うんともすんとも言わない。→うんともすんとも言わないおじいさん。
◎5びっくりさせないでくれよ→驚かさないでくれよ
◎5くれ── いただけませんか? ──お願い→くれ、下さりませんか? ──お願いします
◎5両手を合わせて頼んだ。→思わず両手を合わせて頼んだ。
◎5おじいちゃんは断った。→ おじいちゃんはあっさり断った。
◎6のぞき込んでいるだけであった。→のぞき込んでいるだけだった。
◎7ミカン色に輝かせている──。→ミカン色に輝かせていた。
◎7──うっめえ!→──うっめえ〜!
◎7さらにもう1つ、ほおばる僕──。→さらにイチゴをほおばる僕──。
◎7でも──→でも、
◎8移動してるような── ないような──→移動してるような、ないような──
◎8じっと眺めた──。→じっと眺めた。
◎8追いかけることにした──。→追いかけることにした。
◎8向きを変えるおじいさん──。→向きを変えるおじいさん。
◎9どの方向に、向かおうとしているのか→どの方向に向かおうとしているのか
◎10作っていくといいかもしれん──→作っていくといいかもしれん
◎10東西南北の土台の中に→東西南北の土台の上に
◎10地図が完成する──。→ちょっとした地図が完成する──。
◎10西に砂浜があり、東に家があるということなら、次のような地図ができるという具合にじゃ──→西に砂浜があり、東に家があるという具合にのぉ──
◎10「──。 ──あぁ。 そうだね」→「──。 ──あぁ」
◎10『カタチ コトバ カラダ アタマ』の土台の中に→『カタチ コトバ カラダ アタマ』の土台の上に
◎10こっちの『コトバ』の方向にのせる とすれば── 見るままの人生は、こっちの『カタチ』の方向にのせることができる──→こっちの『コトバ』の方向にのせるとすれば── 見るままの人生は、こっちの『カタチ』の方向にのせることができる。
◎10「──ふーん」 ・・・→「──」 ・・・
◎11じゃが、地図というのは、便利じゃ。→プチといえども、地図というのは、やっぱり便利じゃ。 なぜなら、
◎11地図がてきてしまえば→地図ができてしまえば
◎11同じことじゃな。 アッハッハッ→同じことじゃな。 アッハッハッ!
◎11その土地の方に道を教えてもらったりできれば→その土地に住んでいる方に道を尋ねることができたりすれば
◎11たどり着けることもあるじゃろう──。→たどり着けることもあるじゃろう。
◎11じゃがのお→じゃがのぉ
◎11十分ありうる。→多々ありうる。
◎11未だ地図のない前人未到の地を進んでいこうとする時── 未知の領域を開拓していこうとする時── 未完成なものを完成させていこうとする時── 未熟なものを成熟させていこうとする時── 未来を切り開いていこうとする時── 未だ誰も経験していない自分にピッタリの人生を築いていこうとする時── … そのような時は── とりわけ、このコンパスが大いに役立つじゃろう」 「──コンパスが?」→未だ地図のない前人未到の地を進んでいこうとする時や、未知の領域を開拓していこうとする時── あるいは、未来を切り開いていこうとする時や、未だ誰も経験していない自分にピッタリの人生を築いていこうとする時── … そのような時は、とりわけ、このコンパスが大いに役立つじゃろう」 「──。 コンパス──」
◎11じゃからのお──→じゃからのぉ
◎11そのおかけで、人生のあらゆる状況に合わせて、役立つ地図を作ることができるはずじャ──→そのおかげで、人生のあらゆる状況に合わせて、役立つ地図を作ることができるはずじゃ──
◎11貴重な道しるべになってくれるじゃろう── アッハッハッ!→貴重な道しるべになってくれるじゃろう
◎12アッハッハッ! はやる気持ちは、わからんでもない。→うん。 はやる気持ちも、わからんではない。
◎13宝探しをしたかったなぁ──。 ──残念だよ。→宝探ししたかったなぁ。 ──ガッカリだよ。
◎13ある意味、どうでもよかったけれど── 少しもったいなかったようにも感じられて── ゆっくり思い返してみた──。→ある意味、どうでもよかったけれど── 少しもったいなくも感じられたので、ゆっくり思い返してみることにした
13まぁ、どうでもいいけど── 一応、忘れないように書き留めておくかぁ。→まぁ、どうでもいいけど、忘れないように一応書き留めておくかぁ。
◎52じゃがのお→じゃがのぉ
◎92じゃがのお→じゃがのぉ
◎92身につけられるのじゃからのお──。→身につけられるのじゃからのぉ──。
7つのコンパス
◎あとがきのページのタイトル 7つのコンパス【3.01】 あとがき→7つのコンパス【物語3.02】 あとがき
◎あとがきのページ内の上部のタイトル せかいのコンパス3.02→7つのコンパス【物語3.02】──あとがき──
◎あとがき ──あとがき──を、本文のセルの外側の上部から、本文のセルの内側の上部にも追加する。
◎あとがき “参考文献2” を、あとがき〈補足〉として別のページにうつす。
◎あとがき〈補足〉 参考文献2において、
そして、本以外にも、映画、音楽、テレビやラジオの番組、ウェブサイト、広告、経済、学問(学業)、仕事、友人や家族を含む様々な出会い、自分自身 … そのどれもが、“参考文献2”となりうることに気付く時── 新たな“コンパスマスター”が誕生していることになるのかもしれませんね。→そして、本などの作品を含む様々な人生の所産── 産業、経済、学問、メディアを含む様々な人類(人間社会)の所産── 人類を含む、様々な生態系の所産── … そのどれもが、“参考文献2”となりうることを実感する時── 新たな“コンパスマスター”が誕生していることになるのかもしれませんね。
2010年3月29日 さんぽフルーツ1.72
【物語3.02】
◎35において追加(挿入) エネルギーを蓄えさせてくれるような──
◎69 初恋のきざしを→初恋のきざしのときめきを
◎166 それぞれのレベルにおいて── それぞれのレベルの営みをコントロールする“かなめ”のような部分→それぞれのレベルにおいて、それぞれの営みをコントロールするような“かなめ”の部分──
◎166『アタマ』──『Brain』の部分→『アタマ』──“Head”の方向のもの
◎166削除 『カラダ アタマ』が『Body Brain』であると思うと分かりやすいと思うよ──
◎166表中 大脳新皮質〈前頭葉〉→脳〈Brain〉
◎166表中 自律神経系 内分泌系、小脳 大脳新皮質〈側頭葉…〉… →“神経回路”(or“内分泌回路”)
◎166表中 人生の主体→体
◎166表中 細胞の集合体 〈個体、人体〉→細胞の集合体
◎166 『Brain』→“Head”の方向のかなめ
◎166 ここで、『Brain』→ここで、“Head”の方向のかなめ
◎166生体機能分子の社会レベルの『Brain』→生体機能分子の社会レベルの“Head”の方向のかなめ
◎166分子構造体のかなめの部分なんだよ。 →分子構造体の働きの中心部分で、
◎166 どれこれ、どこここ、かまわなく、→どれこれどこここ関係なく
◎166アロステリックってのは、条件に応じて、タンパク質の構造を変え、同時に働きを変えるしくみなんだ──。 もし、この働きを持つ“かなめ”の分子がなければ、ある化学反応は制御されずに、ある特定の物質だけが作り出される一方── そんな状態に陥ってしまう──。→アロステリックってのは、ある条件に応じてタンパク質の構造と機能を同時に変えるようなしくみなんだ。 もし、このしくみを持つ“かなめ”の分子がなければ、ある化学反応が制御されないせいで、ある特定の物質だけが過剰に作り出される一方── そんな状態に陥ってしまう。
◎166 細胞レベル『Brain』→細胞レベルの“Head”の方向のかなめ
◎166もし、この“かなめ”がなければ── 細胞は細胞として正しく制御されなくなり、適切な分化も、適切な分裂も不可能になり── →もし、この“かなめ”の部分がなければ── 細胞は細胞として正しく制御されなくなり、適切な分化も分裂も維持できなくなり──
◎166 細胞の社会レベルの『Brain』のいい例は、自律神経系や内分泌系さ。 もし、これらがなければ、細胞の社会は、うまく制御されなくなり── それぞれの細胞たちが、勝手気ままに働いたり、成長したりしてしまう。→細胞の社会レベルの“Head”の方向のかなめのいい例は、自律神経系を担う“神経回路”さ。もし、これが存在しなければ、細胞の社会における器官や組織は、うまく制御されなくなり── それぞれが、勝手気ままに働いたり、休んだりしてしまう。
◎遠ざかってしまい── 人体、そして、個体の生存も危ぶまれてしまうことになる──」→遠ざかり、人体の生存が危ぶまれてしまうことになる
◎166 「人生のレベルの『Brain』にあたるものは、わかるよね」 「アハッ。 これは、はっきはり、わかるような気がする」 「うん。 この『Brain』──頭脳が、→ 人生のレベルの“Head”の方向のかなめは、脳──“Brain”さ。 これが
◎166 どうすれば食糧を得られるか── どうすれば危険を回避できるか── … を思考することができ── つまりは、生きてこれたってことなんだよ。 もちろん、それは、すぐれたアイディアや有効なものを創造していく際の“かなめ”でもあり── ある人生は、頭脳があったからこそ、一生という限られた時間の中で、人生を含め様々なものを効率よく育てることができたと言える。 言い換えれば、もし、感情や情動や本能だけで、いきあたりばったりで生きていれば、一生の間に達成できる、成長やパフォーマンスは、とても制限されてしまう── ってことさ」 「トラブルを予防するためだけでなく── よりよく生きていくためにも、大切な“かなめ”なのね」→感情や情動や本能を抱くことができ── どうすれば食糧を得られるか、どうすれば危険を回避できるかを思考することができ── 体温や呼吸をうまくコントロールでき── … つまりは、生きてこれたってことなんだよ。 もちろん、それは、すぐれたアイディアや有効なツールをタイムリーに創造していく際の“かなめ”でもある」 「単に生きのびていくためだけでなく── よりよく生きていくためにも、大切な“かなめ”なのね」
◎166 次の社会レベルの『Brain』は?→次の社会レベルの“Head”の方向のかなめは?
◎166 サポートしてくれたりもする。 つまり、メディアは、“律速酵素”に相当する存在として、様々な社会現象を、減速したり、加速したりする力を持っているんだ──。 だから、そのメディアが健全に働いてくれたおかげで── 人間社会は、よりよく営まれるようになったし── このスピードで、ここまで進歩してこれたとも言えるんだよ→サポートしてくれたりもする
◎166 「つまり、そういう意味で、“かなめ”の存在なのね──」→ 「つまり、社会が存続したり、よりよい社会に向かったりするための“かなめ”として、メディアは大切な存在なのね」
◎166 時には、加速したり、時には、減速したりするような── コントロールの“かなめ”のような部分──『Brain』の部分があるってこと。
→時に応じて加速したり減速したりするようなコントロールの“かなめ”の部分──“Head”の方向のものがあるってこと。
◎166 その“Head”の方向のものは、それぞれのレベルが、生存を維持したり→それらは、それぞれのレベルが維持されたり
◎166 働いていってくれるってことなんだ──→働いていってくれるってことなんだ
◎172 人類は、生態系の『Brain』→人類は、“Head”の方向のかなめ──いわば“生態系のBrain”
◎172 生態系の『Brain』── →生態系の“Brain”──
◎172 砂漠化した地域に植物が生えるようにするとか、気候変動をモニターして上手にコントロールするとか、隕石の衝突を予防したりするとか … も、人類の役割なのかもしれないってことさ───→植林したりすることで森を守るとか、気温の変化をモニターし上手に対処することで程よい気候変動を維持するとか、隕石の衝突を予測し上手に対処することで生態系を守るとか … も、人類の役割なのかもしれないってことさ
◎172 ことなんだ──。 “一部そのもの”→ことなんだ。 ──“一部そのもの”
◎175違うような── →違うような…
◎176“恩返し社会”が、でき上がっているんだよね──。→“恩返し社会”が出来上がっているんだよね。
◎179 人類の営みのよさを演繹的に説明してくれるツールです」 「──」 「はぁ──。 →人類の営みがよいものかどうかを演繹的に説明してくれるツールです」 「──。 はぁ──。
◎あとがき
学問、学校→学問(学業)
木岬さんぽを上部から下部へ移動。
音楽
◎アンドレギャニオンのめぐり逢い を削除
さんぽフルーツトップページ
◎右側部分の文字のサイズ-1を解除
◎2008-2010
該当する図の部分
◎『アタマ』〈Brain〉→『アタマ』〈Head〉
◎サンプルとサプリのThe 1st CompassのAltテキストを入れる
サンプルとサプリの該当部分
◎The 1st Comapssのように“The”を挿入
サプリ
◎1st 『Body Brain Form Word』となるでしょうか──。→『Body Head Form Word』となるでしょうか──。
◎1st あるとらえる結果、応用範囲が、とても広がります。→あるととらえる結果、応用範囲がとても広がります。
◎1st 物質現象レベルから、生態系レベルまで。→物質現象レベルから生態系レベルまで──。
◎1st より、ご理解頂けるかと思います。→より深くご理解頂けるかと思います。
◎1st それらの、辞書にのっていたり、一般的に使われる意味と、『カタチ』と意味あいの違いは、なんでしようか?→それらの“辞書にのっていたり、一般的に使われていたりする”意味と『カタチ』の持つ意味の違いは、なんでしょうか?
◎1st その意味の立場では、→1つは、
◎1st 存在すると理解します。→存在すると見なします。
◎1st それらも『カタチ』にあると見ます。 ここにある『カタチ』は、『コトバ』の反対の方向としての『カタチ』です。 つまり、“色、ぬくもり、空腹感・・・”と言葉にされる前のもの── それらは、すべて『カタチ』の方向にあると見ます。→もう1つは、“色、ぬくもり、空腹感・・・”と言葉にされる前のもの── それらも、すべて『カタチ』の方向にあると見なします。 つまり、ここにある『カタチ』は、『コトバ』の反対の方向としての『カタチ』です。
◎1st 心と体、こころとからだ、ココロとカラダの関係は、実は、『In Out』で表現できてしまうことに気づいたので、→一方、心と体、こころとからだ、ココロとカラダの関係は、実は、『In Out』で表現できてしまうことに気づきました。 以上のことから、
◎1st “ココロ、心、こころ”、どれでも同じですが── 心には、少なくとも『アタマ』心と『カラダ』心があると言えます。→心には、少なくとも『アタマ』の方向の心と『カラダ』の方向の心があると言えます。
◎1stにおいて削除
「『カラダ アタマ』も『In Out』で、説明出来るのではないか」と思われるかもしれません。 もっともです。 なぜなら、事実、『カラダ アタマ』は、『In Out』の一例なのですから。(『Brain』──Bra『In』とは、よくいったものです) しかし、『カラダ』の“中”──『In』に該当するものには、肺や心臓、腸や胃、骨もあります。 つまり、『カラダ』が『Out』の方向にあるとすれば、『In』の方向にあるものは、『アタマ』のみならず、肺や心臓、胃腸や、骨格…も、挙げられてしまうのです。 すると、あくまで、それは、頭──『Brain』──『アタマ』でなければならない、ということを想うとき、やはり、『カラダ アタマ』には、存在する意味があると思います。 つまり、『カラダ アタマ』は、『In Out』の1例── それ以上の意味を持っていると言えるでしょう。→ 一方、想像、思考、記憶、感情、情動、ストレス・・・ どれも、脳〈Brain〉の働きが関係していると言えます。 ですので、脳にも、少なくとも『アタマ』の方向の脳と、『カラダ』の方向の脳があると言えるようです。 (最も『アタマ』脳の方向にある脳は、前頭葉をはじめとする新皮質であり、『カラダ』の方向に進むに従って、大脳辺縁系、視床、小脳、脳幹 … とうつっていくと言えます。 もちろん、心臓、肺、胃腸 …に比べれば、すべて『アタマ』の方向にあると言えるのですが──)
◎1st そのことは、→この『カラダ アタマ』〈Body Head〉の土台は、
◎1st 応用することで、より明確になります。→応用することができます。
◎1st表中 細胞→細胞体
◎1st表中 細胞の集まり→細胞の集合体
◎1st表中 神経系、内分泌系…→“神経回路”(or“内分泌回路”)
◎1st表中 頭(脳)→脳〈Brain〉
◎1st表中 メデイア→メディア
◎1st表中 人類→人類?
◎1st 人類は、生態系のブレインたる存在なのかもしれません。→人類は、生態系のコントロールする『アタマ』の方向のかなめなになれるのかもしれません。
◎生態系のブレーン、リーダーとして→生態系における“脳〈Brain〉”として
◎1st 人類の、生態系に対する責任の重大さを、より深く感じます。→生態系に対する人類の責任の重大さをより強く感じます。
該当部分
◎余分な読点の削除あり。改行の修正あり。
2009年12月29日 さんぽフルーツ1.71
音楽
◎Pti-Music→Petit Music
【サプリ】
◎7 Backのリンクの修正(Sample→Supli)
該当するページの見出し、タイトル、リンクについて
◎1st Compass → The 1st Compass
◎1st compass → The 1st Compass
◎2nd Compass → The 2nd Compass
◎2nd compass → The 2nd Compass
◎3rd Compass → The 3rd Compass
◎3rd compass → The 3rd Compass
◎4th Compass → The 4th Compass
◎4th compass → The 4th Compass
◎5th Compass → The 5th Compass
◎5th compass → The 5th Compass
◎6th Compass → The 6th Compass
◎6th compass → The 6th Compass
◎7th Compass → The 7th Compass
◎7th compass → The 7th Compass
【物語3.02】
上部のテーブルの幅微調整(間隔をあける)
【サンプル】
◎4 テーブル幅修正
◎感ずる 考える ページトップへのリンクもれを改善
【ヒストリー】
◎上部の年数のリンク集について 文字を大きく、幅をもたせる。
◎2004について
タイトルをテーブルで区切って改行
2009年11月15日 さんぽフルーツ1.70
研究1.05→1.06
エコ分野での応用例──
1.
◎とりわけ、“発汗”のシステムが、長い進化の歴史を経て採用されてることに着目すれば、 →特に、“発汗”のシステムが長い進化の歴史を経て採用されてること──とりわけ恒温動物にとって、その活動を維持しながら温度を下げることのできるしくみであることに着目すれば、
◎追加 その際、例えば、人工降雨、打ち水、海水を濾過して真水にする技術 … が活用できると思われる。
◎そうした意味においても、打ち水も、とても理にかなった方法の1つであろう。 そして、さらなる効果的な、“打ち水”効果を利用できるシステムの開発も有効であると思われる。(例えば、道路から一斉に放水して潤す等の技術 … ) そのためにも、水不足の問題を抱えた地域をも念頭においた、すぐれた水循環を開発し、構築することが重要である。 乾燥地帯を含めて、どこへでも効率的に水を届けられるような、“水のパイプライン網”等を作るために、生体の血管網から学び──何十億年もの進化の歴史のつまった“生体”を、多いに模倣して──創造していくことも有効であると考えられる。 (当然、水が確保できれば、植物の生存の可能性も高まり── 植物が生育することができれば、大気中の二酸化炭素の削減へとつながるというメリットも生ずる。 パイプライン以外にも、“大気中の水の移動をコントロールし活用する”技術も、有効であると考えられる)→(その中で、“発汗”に近いという意味で、打ち水に着目すると── さらなる効果的な“打ち水”効果を利用できるシステムの開発も有効であると思われる。(例えば、道路から一斉に放水して潤す等の技術 … ) そのためにも、水不足の問題を抱えた地域をも念頭においた、すぐれた水循環を開発し、構築することが重要である。 乾燥地帯を含めて、どこへでも効率的に水を届けられるような、“水のパイプライン網”等を作るために、生体の血管網から学び──何十億年もの進化の歴史のつまった“生体”を、多いに模倣して──創造していくことも有効であると考えられる。 (当然、水が確保できれば、植物の生存の可能性も高まり── 植物が生育することができれば、大気中の二酸化炭素の削減へとつながるというメリットも生ずる) また、人工降雨などの“大気中の水の移動をコントロールし活用する”技術は、パイプライン同様、打ち水効果を利用するという意味においても有効であると考えられる)
◎また、→このように、
※改行追加あり
2.
◎1.→(1) 2.→(2) 3.→(3) 4.→(4)
◎(2)エネルギーとしての活用は、→燃料としての活用は、
◎(2)そうした所産をエネルギーだけのために利用するのは、→そうした所産を燃料だけのために利用するのは、
◎(2)エネルギーのためだけに使うことも、→燃料のためだけに使うことも、
◎(2)において追加 (そういう意味で、“低炭素社会”が目指す方向性は、よいと考えられる。 しかし、食料── 炭水化物(ブドウ糖)、タンパク質(アミノ酸)、脂肪(脂肪酸)… の主要な骨格が“炭素”であることも考慮に入れれば、“低炭素社会”よりも“低炭素燃料社会”の方がより適切な表現であると言えるのかもしれない)
3.
◎2の4で述べた→2の(4)で述べた
【物語3.02】
◎99にて文追加 ──キャハハ♪ 彼女のお姉さんも妊娠中なんだって。 楽しいね。
あとがき
◎私→僕
◎-1pt 実際に、〜・・・
◎実際に、犬を飼っていたこと→実際に、犬を飼い、毎日のように散歩につれていっていたこと
◎“参考文献2”なりうることに気付く時→“参考文献2”となりうること
に気付く時
2009年9月18日 さんぽフルーツ1.69
さんぽフルーツロゴページ
◎さんぽフルーツの、このロゴマーク── ビタミンC→この、さんぽフルーツのロゴマーク── ビタミンC
※改行の調整あり
ウェブサイトのページ
◎トップページ以外の楕円形のSAMPO FRUITS のロゴをクリックするとトップページに戻ります。→『さんぽフルーツ』のトップページ以外の楕円形のSAMPO FRUITS のロゴ(上部にあることが多いです)をクリックすると『さんぽフルーツ』のトップページに戻ります。
【物語3.02】トップページ
◎思い浮かべるようにして、読まれると→思い浮かべるようにして読まれると
研究トップページ
◎科学者(研究者)向けです。→研究者(専門家)向けです。(理系・文系を問いません)
該当ページ
◎下部ロゴのAlt テキストについて SAMPO FRUITS シンプルロゴ(ページのトップへ)→To Page Top
さんぽフルーツトップページ&ウェブサイトについてのページ
◎メールアドレスの変更
7つのコンパス【サンプル】
『カタチ コトバ』
◎(場所が)左 (場所が)右
◎左脳 右脳
『過去 現在 未来』
◎後ろを振り返る - 前を見る
『In Out』
◎(場所が)下 (場所が)上
◎これ、それ、あれ。
◎時間外 out of time 時間内 in time
『On Off』
◎視線を合わせる 視線をそらす、はずす
7つのコンパス【物語3.02】
トップページ
◎テーブルの幅の微調整
表紙のページ(となりのコンパス、ふたりのコンパス、せかいのコンパス)
◎テーブルの微調整
◎3つの表紙の画像について altテキストを追加
106
◎追加 ♪太陽がキスして地球が頬を染めている♪ あい・フィール・ハッピー♪ ゆー・フィール・ハッピー♪ そー・うぃー・フィール・ハッピー♪ ピピッピーピー♪
あとがき
◎しかし、もちろん、作品をここまで→そして、もちろん、作品をここまで
◎ここに挙げさせていただき→ここに挙げさせて頂き
◎みわたせば→見渡せば
◎句読点、サイズの修正あり。
リンクについてのページ
◎そのものを削除
該当ページ(さんぽフルーツトップページ、サイトマップ、アップ履歴、アップ履歴2008、ウェブサイトについて)
◎“リンクについて”のリンクを削除
2009年8月22日 さんぽフルーツ1.68
さんぽフルーツトップページ
◎追加〈さんぽフルーツ〉
◎木岬 さんぽ→by 木岬 さんぽ
◎メールロゴ改行
◎-2pt→-1pt Copyright©2008-2009 KIMISAKI SAMPO All Rights Reserved.
さんぽフルーツロゴページ
◎木岬 さんぽ 中央→左寄り
◎-2pt→-1pt Copyright©2008-2009 KIMISAKI SAMPO All Rights Reserved.
7つのコンパストップページ
◎R12(小卒以上推奨)→推奨 12歳以上(or小卒以上)
◎R15(中卒以上推奨)→推奨 15歳以上(or中卒以上)
◎R17→推奨 17歳以上
7つのコンパストップページ上部
◎木岬 さんぽ→by木岬 さんぽ
音楽トップページ
◎木岬 さんぽ→by木岬 さんぽ
◎by SAMPO→Pti-Music by SAMPO
◎アップさせて頂きます。→アップしています。
◎-3pt→-1pt ©2008 KIMISAKI SAMPO All Rights Reserved.
ネイチャー写真トップぺージ
◎木岬 さんぽ→by木岬 さんぽ
◎by SAMPO→Nature Photos by SAMPO
◎-3pt→-1pt ©2008 KIMISAKI SAMPO All Rights Reserved.
研究1.04→1.05
◎木岬 さんぽ→by木岬 さんぽ
本文
◎挿入 エコ分野での応用例
◎“生態系〈ecosystem〉の維持、エネルギー枯渇の回避のためにどうしたらよいのか──。” の本文を、別ページに移動し、リンクする。
エコ分野での応用例のページ
◎とても理にかなった方法の1つである。→とても理にかなった方法の1つであろう。
◎有効であろう→有効であると思われる
◎また、エネルギー確保に関しても→当然、エネルギー確保に関しても
◎かつて、一見、脅威だった酸素が増えたことで、それを有効活用できる生物(動物)が繁栄した。→かつて地球上に生存していた多くの生物にとって脅威であった酸素が増加したことで、結果的には、それを有効活用できる種類の生物(現在多くを占める植物&動物)が繁栄することとなった。
◎それを有効活用できる生物(植物)(orメタン活用のシステム)→それを有効活用できる生物(orメタン活用のシステム)
◎資源とする→資源(恩恵)とできる
◎吸収してもらい減らしていくことは→大いに吸収してもらい減らしていこうとすることは
◎その意味でも植林は、とても重要である。→その意味でも植林は、とても重要であろう。
◎過剰な温室効果ガスをコントロールする意味においても重要となる→過剰な温室効果ガスをコントロールする意味においても重要となると考えられる
◎こうした多重的な取り組みが、より確実であり、合理的である。→こうした多重的な取り組みが、より確実であり、合理的であることが類推できる。
◎-1pt (おな、水蒸気も温室効果ガスの一種である。 その意味においても、1で述べた水の循環の重要性が認められる)
◎予防的に余裕をもって対応していけるようなシステムを作ることが重要である。→予防的に余裕をもって対応していけるようなシステムを作ることが重要であることが類推できる。
7つのコンパス
【物語3.02】
◎152 笑顔がこぼれた。→笑みがこぼれた。
【サプリ】7th『-^→』
なお、ニュートン力学で、ベクトルという形で表現されている“力”の背後には、7番目のコンパスがあると理解することできます。 なぜなら、質量と距離から、引力が決定されるので。 つまり、“この時は、こうなる”という決まった流れの一例だからです。 本当に、土のように、目立たないものですね。
生物学や化学で登場する活性化エネルギーの図と似ていると見ていいと思います。この化学反応も、この時は、こうなるという流れです。
なお、量子力学では、粒子を波として、あつかいますが、この波の性質、量子としての粒子の挙動も、7番目のコンパスで、説明できる、一例であるのかもしれません。→なお、物語編では、ミクロの生物学や化学で登場する活性化エネルギーの図のレベル(=エネルギーレベル)〜マクロの生態系レベルまでが扱われていますが、さんぽフルーツの研究のページでは、ミクロの方向に、さらに2つのレベル(──4つの力レベル、超ひも理論レベル)がプラスされて、扱われています。
7つのコンパス
【サンプル】
5番目のコンパス
◎追加 休むのは良い。休むのは好き
◎やっては、まずい→やってはまずい。〜してはまずい やっていい。〜していい。
◎してはダメ!!→してはダメ するとよい
7番目のコンパス
◎NEXTのリンク先 アップダウン→サンプルトップ
サプリ、サンプルの該当ページ
◎下部の線の位置 BACK NEXTの下→To Page Topの下
サプリ
◎7番目のコンパスの下部のNEXTリンク先 トップページ→サプリトップページ
該当ページ
◎キーワード削除
該当ページ
※ソース上の余分な文字列削除あり
該当ページ
◎下部のリンク集の削除
◎下部のSAMPO FRUITSのスイッチ→TO PGAGE TOPのページへ
(リンク先の変更 さんぽフルーツトップページ→そのページの先頭)
サイトマップ
◎トップページのロゴ2つ→1つ
◎順序変更 7つのコンパス ネイチャー写真 音楽→ネイチャー写真 音楽 7つのコンパス
ウェブについて
◎順序変更 7つのコンパス ネイチャー写真 音楽→ネイチャー写真 音楽
該当ページ
◎リンク集の順番の変更
・7つのコンパス ネイチャー写真 音楽→ネイチャー写真 音楽 7つのコンパス
・7つのコンパス 物語3.02 サプリ サンプル ヒストリー ネイチャー写真 音楽→ネイチャー写真 音楽 7つのコンパス 物語3.02 サプリ サンプル ヒストリー
2009年7月23日 さんぽフルーツ1.67
さんぽフルーツトップページ
◎最新アップ日→木岬 さんぽ作品集 最新アップ日
◎バージョン数の表示の変更(一桁減らして表示することに。これまでの、1.066等は、1.66と同等のものにあたることとした。例)1.066=1.66 …)
◎SAMPO FRUITの文字の大きさを-1ptに
該当するすべてのページにおいて
◎更新履歴→アップ履歴
【サンプル】
4th Compass『In Out』
◎追加 『In』勉強中、遊び中、休憩中、仕事中、考え中、昼寝中… 『Out』-
◎追加 『In』これ/this 『Out』あれ/that
6th Compass『On Off』
◎追加
『On』! 『Off』-
『On』あっ!! 『Off』あっ
7th Compass
◎追加 本をいろいろ手に取ってみる “これを買おう”と決める 実際に買う
【物語3.02】
◎トップページ
また、“──”は、“時間経過”or“間”を表しています。 “あー”等の中の“ー”ように、発声を伸ばしてるという意味は持っていません。
◎42配置訂正 左寄り→中央
◎116 スヤスヤ眠っている赤ちゃん── → いつの間にか、スヤスヤ眠っている赤ちゃん──
◎171〜181【ライフ自身が示している知恵】→【ライフ〈Life〉自身が示している知恵】
◎175
ほど遠くなることも可能なんだよ→ほど遠くなることが可能なんだよ
◎175「あぁ──」→「──。 あぁ──」
◎175 なければないに越したことはないけれど──→なくてすむなら、それに越したことはないけれど── たとえあっても、
ロゴ
◎このロゴマークは、→このロゴマーク──
ウェブサイト
◎メールの画像のリンクの修正
その他(該当するページ)
◎キーワードの修正、ロゴのAltテキストの修正あり
◎Reserved→Reserved.
◎ 2008 KIMISAKI SAMPO→©2008-2009 KIMISAKI SAMPO
2008 KIMISAKI SAMPO→©2008-2009 KIMISAKI SAMPO
◎ 2008 KIMISAKI SAMPO→©2008 KIMISAKI SAMPO
2008 KIMISAKI SAMPO→©2008 KIMISAKI SAMPO
◎ 2008KIMISAKI SAMPO→©2008 KIMISAKI SAMPO
2008KIMISAKI SAMPO→©2008 KIMISAKI SAMPO
◎ 2004-2008 KIMISAKI SAMPO→©2004-2009 KIMISAKI SAMPO
2004-2008 KIMISAKI SAMPO→©2004-2009 KIMISAKI SAMPO
◎ 2008-2009 KIMISAKI SAMPO→©2008-2009 KIMISAKI SAMPO
2008-2009 KIMISAKI SAMPO→©2008-2009 KIMISAKI SAMPO
◎copyright 2008 KIMISAKI SAMPO→©2008-2009 KIMISAKI SAMPO
◎ソース上の余計な“間違い文字列”の削除あり
2009年6月21日 さんぽフルーツ1.066
さんぽフルーツロゴのページ
◎さんぽフルーツの、このロゴマークの見本は、ビタミンCたっぷりのみかんです。→◎さんぽフルーツの、このロゴマークは、ビタミンCたっぷりのみかんをイメージして作りました。
7つのコンパス
【ヒストリー】
◎2001 身近なものにしたかったので→身近なものにもしたかったので
【物語3.02】
◎トップページ バージョン3.02にあたるので→最新のバージョン3.02にあたるので
◎12「そうそう。それから、“コンパス・フォー・ライフ”は、全部で7つある」とおじいさん。→ 「それらが、“道しるべ”であるということが、何を意味しているか、わかるかい?」とおじいさん。
「──さぁ。 わからないよ。 何?」と僕。
「うん。 それは── こうしてできる地図も、元々のコンパスも、それら自体は、本来、“どこへ向かうべきか、どの方向へ進むのがいいか”を、何も指し示していないということじゃ。 まあ、それは、普通の地図やコンパスと同じことじゃな。 アッハッハッ!」
「──え? じゃあ、何が、指し示すの?」
「それは──」
「それは?」
「それは──」
「それは?」
「──。 7つのコンパス──ザ・セブン・コンパセズ・フォー・ライフ(The 7 Compasses For Life)自身の中に、その答えがある── らしい。 アッハッハッ!」
「──わけわからないよ。 それに、7つって、どういうこと?」
「うん。 “コンパス・フォー・ライフ”は、実は、全部で7つあるんじゃ」
◎26生きている証じゃからのぉ。→生きている証の1つの形なのじゃからのぉ。
◎58 あいつら、異星人のような存在じゃないか?→あいつら── それこそ、異星人のような存在じゃないか?
◎116 「──ねぇ、見て見て♪」と彼女。
「ん?」
「こうやると、笑うんだよ。 高い高い高い──、 ──バァー♪ ほらほら! わかるでしょ? アハハッ♪」 得意気な彼女──。
赤ちゃんは、たしかに、ニコニコと笑みを浮かべていた──。
→ 「あっ」 突然、彼女が、小さくさけんだ
「え? どうしたの?」
「うん。 笑ったの── この子が。 あ、また♪ ──アハッ。 かわいいね」
赤ちゃんの笑顔と、彼女の笑顔── ふたつの笑顔が、向かい合って、そこにあった──。
得意気に、赤ちゃんのほっぺたをピョンピョンとつついたりする彼女──。
※空白の調整あり。
◎171〜181【コンパスが示してくれる知恵】→【ライフ〈Life〉自身が示している知恵】
◎171 人類は、生態系の『Brain』として活躍できるかもしれないからってこと──。 例えば、環境に負荷をかけずに安全にエネルギーを生み出せる技術を開発したり、植林を実施したり … 生態系が生きていくのを助けていくために、ある程度の、時間や資源の投資が不可欠になるからってことだよ── → 例えば、環境に負荷をかけずに安全にエネルギーを生み出せる技術を開発したり、植林を実施したり … 生態系が生きていくのを助けていくために、ある程度の、時間や資源の投資が不可欠になるからってことだよ──。 別の見方をして言い換えれば── 人類は、生態系の『Brain』として活躍できるかもしれないってことなんだけどね
◎171生命40億年の歴史も教えてくれるんだよ→生命40億年の歴史自身が教えてくれることでもあるんだよ
◎172 (生命40億年の歴史も教えてくれる知恵)→(生命40億年の歴史自身も示している知恵)
◎174 「“For Life”──。
ねぇ、私たちが前に話した、
→ 「“For Life”──。 すてきね」
「ああ。 しかも、それは── “コンパスや地図”自身が示している方向ではなくて── ライフ自身が示している方向だから、なおさら──」
「うん。
ねぇ、私たちが前に話した、
◎174 そんなライフスタイルたちを『For』ライフと呼んだのと、→そんなライフスタイルたちを呼んだところの『For』ライフと
◎174 “For Life”につながりやすいから──。
→ある意味、“For Life”につながりやすいと言えるから──。
◎174 改行 例えば、“今、心地よくてハッピー”であれば、
◎175(『Against』ライフ → ?)→ (『Against』ライフ →“For Life”)
◎175 「ねえ。 逆に── 今、自分自身の『For』ライフを育めなければどうなるかしら?」と彼女。
「うん。 やっぱり、“For Life”も危うくなるよ──。
なぜって、1つは、自分が悲しんでいたり、怒っていたりしてれば── リラックスできずにストレスがたまってしまうってことで、“心も、頭と体も健康を損ないやすい”ってこと── つまり、“細胞の社会が生きていけない”ってことにつながりやすいだろ?」と僕。
「そうね──。 それに、自分自身が、過剰にストレスをためていたり、イライラしていたりすれば── “自分自身や誰かが生きていくため”にも働きにくくなり── つまりは“人間社会が生きていくため ”にもなりにくくなっちゃうかもね?──」
「そうさ。 そして、その結果── 景気も悪くなり、生活も苦しくなり── … 『For』ライフが、いっそう、程遠いものになってしまう」
「──うん。 さらには、そのせいで、“生態系が生きていくため── 長い将来にわたって生きていくため──”どころじゃない── そんなことにもなりかねないのね。 悲しいけれど──。 ──。 ・・・」
「ああ──。 そうだね──」
「──あ、そうだ!
→ 「ねえ。 すると、逆に── 『Against』ライフに陥ってしまったならば── やっぱり、“For Life”も危うくなるのかしら?」と彼女。
「うーん──。 それは、結局── その後にどんな方向に向かって行くか次第── つまり、その後の、変化次第じゃないかなあ」と僕。
「変化?」
「そう。 そりゃあ、『For』ライフに比べれば、『Against』ライフの方が、リスクが大きくなるよ。
だって、例えば── もし悲しみやつらさをためこみ、長くくすぶらせ続けてしまえば── ストレスが蓄積して健康を害することになったり、何かを傷つけてしまうことになったり… “Against Life”の方向に進む可能性が高まるのは確かだから──。
でもだよ── たとえ、悲しみやつらさ… に遭遇しても── 上手に対処して、心底さっぱりした上で、次の目標、楽しみ … を見つめていこうって具合に、方向転換できるような人生であれば── “Against Life”から、ほど遠くなることも可能なんだよ」
「うん」
「そして、さらには、“For Life”に向かっていくために役立つ、一時的な『Against』ライフってのも、きっと、あるはずなんだよ。
例えば── おじいさんが、心を鬼にして、親身になって僕を叱ってくれた時の、僕やおじいさんの心の痛み── 休養の大切さを教えてくれた、スランプの時のつらさ── ペース配分の大切さに気付かせてくれた、山登りの際のしんどさ── … とか?」
「アハッ。 そうね── 子供が歩き方を身につけていく時の、転倒の際の痛み── 免疫力を高めるための、予防接種の際の注射針の痛み── 私に優しさを伝えてくれた、レジに来てくれた時の、あなたの心の痛み── … 痛み、悲しみ … そういった『Against』ライフも、時に、“For Life”に向かって行くために役立つことがあるんだね」
「あぁ──」 3つめの例は、ちょっと違うような── って、まぁ、いいかぁ。 「だから── 悲しみ、つらさ、痛み… は、なければないに越したことはないけれど── それを上手に乗り越えたり活用したりすることができれば、新たな気持ちで、“For Life”に向かって行けるってことで── そのような人生にとっては、それは、貴重なプロセスだと言えるのさ──」と僕。
「プロセス──」
「そう。 そのブロセスでの分岐点は何かというと── その『Against』ライフを経験した後に、“For Life”に向かっていけるのか、向かっていけないのか、ってことなんだよ」
「うん。 そうね──。 ・・・ ──あ、そうだ!
◎176 「つまり──
自分自身の『For』ライフを育めれば、“For Life”を達成しやすくなって── 『Aainst』ライフに陥ってしまうと、長い目で見て、“For Life”からほど遠くなってしまうってことね?」と彼女。
「ああ、そうだね。
──そして、こんなことも、言える。
自分自身の『For』ライフを育めれば、“For Life”を達成しやすくなって── “For Life”を達成できれば、おかげで、よりいっそう『For』ライフを、味わえる──ってことも」
→ 「つまり──
自分自身の『For』ライフを育めれば、“For Life”を達成しやすくなるけど── たとえ『Aainst』ライフに陥ってしまったとしても、上手に対応することで、“For Life”の方向に向かっていけるってことね?」と彼女。
「そうさ。 そして、さらには── 『For』ライフであろうと、『Against』ライフであろうと── “For Life”を貫いて行こうとすることが大切だよってことを、他ならぬ、ライフ自身が示しているってことなんだ。
『For』ライフが“For Life”につながりやすいって話も、あくまで“つながりやすい”ってだけの話でしかなくて── 下手すりゃ、たとえ『For』ライフであったとしても“Agaist Life”の方向に向かっていってしまうことだって、十分ありうるのだから──」
「うん」
「──そして、こんなことも、言える。
自分自身が“For Life”を育めれば、おかげで、全体も“For Life”を達成しやすくなって── 全体が“For Life”を達成できれば、おかげで、よりいっそう自分自身が“For Life”を育める── ってことも」 自分自身が“For Life”を育めれば、おかげで、全体も“For Life”を達成しやすくなって── 全体が“For Life”を達成できれば、おかげで、よりいっそう自分自身が“For Life”を育める── ってことも」
2009年5月25日 さんぽフルーツ1.065
アップ履歴
◎2009年5月18日分について “7つのコンパス【物語3.02】”の言葉を追加
7つのコンパス【物語3.02】
◎トップページ
なお、 ──手紙? などの色付の表記は、→ なお、原則として ──手紙? などの青色の表記が、
◎11道先案内人に出会えない場面も→道先案内人に出会えなかったりする場面も
◎11ましてや、前人未到の地を進んでいこうとする時── 誰の真似でもない自分にピッタリの人生を築いて行こうとする時── … そんな時は、地図はもちろん── このコンパスも、ますます役立つじゃろう 「──コンパスも?」 「そうじゃとも。 なぜなら、このコンパスを利用すれば、プチ・マップを、限りなくたくさん作っていくことができるのじゃからのお──」 「限りなく?──」 「そうじゃ。 そのおかけで、人生の、あらゆる状況に合わせて、役立つ地図を作ることができるはずじャ──」 →ましてや、未だ地図のない前人未到の地を進んでいこうとする時── 未知の領域を開拓していこうとする時── 未完成なものを完成させていこうとする時── 未熟なものを成熟させていこうとする時── 未来を切り開いていこうとする時── 未だ誰も経験していない自分にピッタリの人生を築いていこうとする時── … そのような時は── とりわけ、このコンパスが、大いに役立つじゃろう」 「──コンパスが?」 「そうじゃとも。 なぜなら、このコンパスを利用すれば、プチ・マップを、限りなくたくさん作っていくことができるのじゃからのお──」 「限りなく?──」 「そうじゃ。 そのおかけで、人生のあらゆる状況に合わせて、役立つ地図を作ることができるはずじャ──」
◎26 ちょろいもんよ!」 →ちょろいもんよ」
◎28 思いますですぅ〜♪→思いますぅ〜♪
◎28 グレードアップしているんだね!→グレードアップしているんだね
7つのコンパス【ヒストリー】
◎トップページの2004の部分について 【物語】《書籍版》→【物語1.0】《書籍版》
2009年5月18日 さんぽフルーツ1.064
7つのコンパス【物語3.02】
◎2──うん。 ゴンピー、行くよ。→ ──行くよ、ゴンピー。
◎2宝の地図のことだけは秘密にした──。→宝の地図のことだけは秘密にすることにした──。
◎「知らないよ」 ヤバい! このおじいさん、あやしすぎ!! →「え? 知らないよ」 ヤバい。 このおじいさん、明らかにあやしすぎ──。
◎5僕は、おじいさんの体をゆすった。→僕は、おじいさんの体を揺り動かした。
◎5おじいさんは、ふと、身をおこし、ゆっくり立ち上がったんだ。 ──ん!?→おじいさんは、ふと、身をおこし── そのまま、ゆっくり立ち上がったんだ。 ──ん!? 思わず身構える僕。 しかし、そんな僕の姿を、気にも留めずに──
◎5おじいさんは、そう言うと── →おじいさんは、そう言いつつ──
◎6 その後、僕は、宝を掘り当てるべく、穴掘りに燃えた。 そうして、ついに、穴は、僕の体をまるまる隠すくらいまでほどになった──。 でも── 宝物が見つかる気配は全くなくて── 身をかがめて穴をのぞき込んでいるゴンピーの姿があった── →その後、僕は、宝を掘り当てるべく、穴掘りに燃えたんだ。 でも── たとえ、穴が、僕の体をまるまる隠すくらいまでほどになったとしても── 宝物が見つかる気配は全くなくて── ゴンピーは、ただ、身をかがめて穴をのぞき込んでいるだけであった。
◎7さらにもう一つ、→さらにもう1つ、
◎8 おじさんの後を、走って追いかけた──→ おじさんの後を、走って追いかけることにした──。
◎8──な、なんとなく」 「──うん。→ ──な、なんとなく?」 「──。 ──うん。
◎9ふつうの羅針盤の場合には、→ふつうのコンパスの場合には、
◎9 「まずは── 人生の方向だと思ってみてごらん」 「方向?」 「そうじゃとも。 人生の方向── 人が生きていく際の方向じゃな」 「ホウコウ──」 「そうじゃ。 “人生のためになるコンパス”は、いろんな人生の方向──人が生きていく際の、様々な方向を教えてくれるんじゃ」→「まずは── 人生における“方向”だと思ってみてごらん」 「ホウコウ?」 「そうじゃとも。 人生における“方向”── 人が生きていく際の“方向”じゃな」 「方向──」 「そうじゃ。 例えば、今、自分が、どんな方向にいるのか── 今、自分は、どの方向に、向かおうとしているのか── … そういった、人が生きていく際の様々な“方向”を、このコンパスは、教えてくれるんじゃ」
「──」
◎9図中の文 “人生のためになるコンパス”は、いろんな人生の方向──人が生きていく際の、様々な方向を教えてくれる→人が生きていく際の様々な“方向”を、このコンパスは、教えてくれる
◎10改行の修正あり
◎10「──うん。 まぁ、コンパスを利用すると、地図を作ることができる── そう思うと理解しやすいかもしれん」とおじいさん。→ 「──うん。 じゃから、まずは、コンパスを利用して、どんどん、地図を作っていくといいかもしれん──」とおじいさん。
◎10次のような地図ができる──」「──。 ──あぁ、そうだね」→次のような地図ができるという具合にじゃ──」「──。 ──あぁ。 そうだね」
◎10 図削除 コンパスを利用すると地図を作れる
◎11 「そうじゃ。 そして、7つのコンパスを利用すれば、このプチ・マップは、限りなくたくさん作っていくことができる──」 「限りなく?──」 「そうじゃ。 そのおかけで、人生の、あらゆる状況に合わせて、役立つ地図を作ることができるはずじャ──」「──。 うん──」 「そして、これらの出来上がったプチ・マップたちは、生きていく際の、貴重なヒントになってくれるじゃろう── アッハッハッ!」 「ヒント──」 → 「じゃが、地図というのは、便利じゃ。 いったん、しっかりした地図がてきてしまえば── たとえコンパスがなくとも、“今、自分は、どの方向にいるのか── どの方向に向かおうとしているのか──”が、一目瞭然となるからのぉ。 ──まあ。 それは、ふつうの地図の場合と同じことじゃな。 アッハッハッ」 「──」 「もちろん、もし、道路の案内標識や看板などの目印が充実しておったり、その土地の方に道を教えてもらったりできれば── たとえ地図がなくとも、道に迷わずに目的地にたどり着けることもあるじゃろう──。 じゃがのお、長い人生── そういった、目印がなかったり、道先案内人に出会えない場面も、十分ありうる。 そんな時は、地図は、とっても便利じゃ。 ましてや、前人未到の地を進んでいこうとする時── 誰の真似でもない自分にピッタリの人生を築いて行こうとする時── … そんな時は、地図はもちろん── このコンパスも、ますます役立つじゃろう」 「──コンパスも?」 「そうじゃとも。 なぜなら、このコンパスを利用すれば、プチ・マップを、限りなくたくさん作っていくことができるのじゃからのお──」 「限りなく?──」 「そうじゃ。 そのおかけで、人生の、あらゆる状況に合わせて、役立つ地図を作ることができるはずじャ──」「──。 うん──」 「そして、これらの出来上がったプチ・マップたちは、生きていく際の、貴重な道しるべになってくれるじゃろう── アッハッハッ!」 「道しるべ──」
さんぽフルーツロゴについてページ
◎この、さんぽフルーツのロゴマークの見本は、→さんぽフルーツの、このロゴマークの見本は、
◎テーブルや改行についての設定若干変更
リンクについて
◎テーブルの設定若干変更
2009年4月29日 さんぽフルーツ1.063
追加ページ
◎SAMPO FRUITSロゴの説明のページを追加。(トップページのロゴからリンクされています)
◎ウェブサイトについて
※楕円形のSAMPO FRUITS のロゴをクリックするとトップページに戻ります。→※トップページ以外の楕円形のSAMPO FRUITS のロゴをクリックするとトップページに戻ります。
◎サイトマップにおいて追加 SAMPO FRUITS ロゴについて
全ページについて
◎SAMPO FRUITSの水滴付きロゴの丸みをアップする。
トップページ以外の全ページについて
◎SAMPO FRUITSの水滴付きロゴのALTテキスト修正 木岬 さんぽ作品集 SAMPO FRUITS→SAMPO FRUITS logo to top page
トップページ
◎SAMPO FRUITSの水滴付きロゴのALTテキスト修正 木岬 さんぽ作品集 SAMPO FRUITS→SAMPO FRUITS logo at top page
◎上部プレート ALTテキスト修正 木岬さんぽ作品集 さんぽフルーツ→さんぽフルーツトップページプレート
◎下部プレート ALTテキスト修正 木岬さんぽ作品集 SAMPO FRUITS→SAMPO FRUITS top page plate
該当する全ページについて
◎白い部分を持つテーブル(幅96%)において、そのテーブルの幅をせまく設定する(幅96%→幅77%)
◎“7つのコンパス 物語3.02 サプリ サンプル ヒストリー”のテーブルリンク集をすべて、トップページのものと全く同じにする。 (これによって、外枠が形成され、物語3.02 サプリ サンプル ヒストリーのプレートの高さが増した。)
◎SAMPO FRUITSロゴの説明のページを追加。(トップページのロゴからリンクされています)
◎ウェブサイトについて
※楕円形のSAMPO FRUITS のロゴをクリックするとトップページに戻ります。→※トップページ以外の楕円形のSAMPO FRUITS のロゴをクリックするとトップページに戻ります。
◎サイトマップにおいて追加 SAMPO FRUITS ロゴについて
ネイチャー写真
◎もみじ中のコメント 部分的に紅葉していますね。→部分的に、紅葉し始めていますね。
7つのコンパス【物語3.02】
◎72 きっと莫大な財産をもたらしてくれるじゃろう──。→きっと莫大な人生の財産をもたらしてくれるじゃろう──。
◎102 プチマップ追加 何かをする 何もしない。(『In Out』)
研究
3Steps理論 結果&考察 医療分野での応用例のページ
◎(1)腫瘍細胞側の遺伝情報を書き換える(or 組み換える)方向の研究→ (1) 腫瘍細胞側の遺伝情報(or生体機能分子の連携プレーの流れ)を書き換える方向の研究
◎以上のことは── 腫瘍細胞側の遺伝情報を書き換え、いわば“再進化”を進めることによって治療していく、という方向の研究が重要であることを示唆している。→以上のことは── 腫瘍細胞側の遺伝情報(or生体機能分子の連携プレーの流れ)を書き換え、いわば“再進化”を進めることによって治療していく、という方向の研究が重要であることを示唆している。
◎この、病巣側の遺伝情報を書き換えるという方向性は── ワクチン療法の持つ、個体側の遺伝情報を書き換える(特に免疫系において)という方向性と対照的である。→この、病巣側を書き換えるという方向性は── ワクチン療法の持つ、個体側を書き換える(特に免疫系において)という方向性と対照的である。
◎(なお、病的な細胞の遺伝情報を書き換えようとする方向性は、ほかの難病の治療においても役立っていくであろう)→ (なお、病的な細胞を書き換えようとする方向性は、ほかの難病の治療においても役立っていくであろう)
2009年3月31日 さんぽフルーツ1.062
【物語3.02】
◎52まずは、それをしっかり受け入れる──。→そのことを、まずは十分に受け入れる──。
【ヒストリー】
◎『7つの地図、The Seven Maps』(2000 10/27)
ついにここまで、来ました。→ついに、ここまで来ました。
【サンプル】
◎4番目のコンパスにおいて追加 関係ある、関係ない
◎4番目のコンパスにおいて追加
見て創造する 見ないで創造する
見て愛する 見ないで愛する( 盲目的に愛する)
見ている 見ていない(無視している)
座っている 座っていない (立っている、寝ている、歩いている…)
向き合っている 向き合っていない
飛び込んている 飛び込んでいない
何かをしている 何もしていない
創造している 創造していない
笑っている 笑っていない
喜んでいる 喜んでいない
している していない
I'm walking. I'm not walking.
I'm sitting. I'm not sitting.
※現在進行形ing が、『In』の方向にあり、not -ingが、『Out』の方向にあるというのは── ingと『In』 notと『Out』が、それぞれ似ていて、面白いですね。 日本語においても、“〜している最中だ”の“中”が『In』と重なります。 そういう意味で、“現在進行形”という表現より、“現在最中形”という表現の方がぴったりなのかもしれませんね。 (走っている、歩いている… と同様に、座っている、止っている… も、“最中形”なら、うまくかみ合います)
- not
- without doing anyting.
I am doing something. I am not doing anything./ I am doing nothing.
There is something. There is nothing. There is not anything.
Yes No
※ Don't you have anything to write with? (何か、筆記用具持っていないですか?) No, I don't. (はい、持っていません)
こうした、英語と日本語とのズレが理解できます。
日本語の“はい、いいえ”は、『On Off』の意味での違い(“その通り、違う”という意味)を持っているのに対し、英語のYes,No は、あくまで、『In Out』の意味での違いを持っているようてす。
『In』←『Out』手に入れる、貯める/蓄える、収入をえる、入れる、食べる…
『In』→『Out』捨てる、消費する/使う、支出する、出す…
『In』←『Out』入る、飛び込む、何かをする…
『In』→『Out』出る、飛び出る、何かをやめる…
遊ぶの/遊びなさい/遊ぶのがよい 遊ばないの/遊ばないようにしなさい/遊ばないのがよい
休むの/休みなさい/休むのがよい
休まないの/休まないようにしなさい/休まないのがよい
動かすの/動かしなさい/動かすのがよい 動かさないの/動かさないようにしなさい/動かさないのがよい
支持するの/支持しなさい/支持するのがよい 支持しないの/支持しないようにしなさい/支持しないのがよい
反対するの/反対しなさい/反対するのがよい 反対しないの/反対しないようにしなさい/反対しないのがよい
見るの/見なさい/見るのがよい 見ないの/見ないようにしなさい/見ないのがよい
決めるの/決めなさい/決めるのがよい 決めないの/決めないようにしなさい/決めないのがよい
笑うの/笑いなさい/笑うのがよい 笑わないの/笑わないようにしなさい/笑わないのがよい
〜するの/するのがよい/しなさい/しなさいな/しなさいよ… 〜しないの/しないのがよい/しなさんな/しなさんなよ…
〜して下さい 〜してくれ 〜しないで下さい 〜しないでくれ
〜しますように 〜するように 〜しませんように 〜しないように
◎第3のコンパスにおいて 守備でのプレーの流れ→守備での連携プレーの流れ。
◎第3のコンパスにおいて追加 攻撃でのプレーのつながり(例…ヒット→送りバント→タイムリーヒット)
工場での物作り(流れ作業──自動車の組み立て…) 農作物の収穫までの流れ
スキー、スケートでの滑り、ジャンプ、回転… の動き
水泳での飛び込み、泳ぎ、ターン… の動き
陸上競技での走り、ジャンプ、投てき … の動き
マラソンコースの進み方 …
リレーでの流れ(陸上、水泳、スキー…)
ネイチャー写真
◎オオイヌノフグリ 毎年、これが咲き始めると、「ああ、春だなあ」と思います。→桜と同様に── 毎年、これが咲き始めると、「ああ、春だなあ」と思います。
2009年3月22日 さんぽフルーツ1.061
研究
『3Steps 理論とその応用について』ver.1.02→1.03
◎結果&考察にページ追加 医療分野での応用例 腫瘍細胞に対して、どう向き合っていけばいいのか。(治療法の開発におけるプラスαの方向性) (本文の上記文から、追加ページへリンク)
◎結果&考察 提示してみる。→いくつか提示してみる。
◎結果&考察 光合成の所産は、原則として、食料や素材として活用→光合成の所産は、原則として、食料や材料として活用
◎結果&考察 できるだけ確保しておく。→できる限り、確保しておこうとする。
◎結果&考察 そういう意味で、何かの材料としても活用できる石油を、エネルギーのためだけに使うことも、もったいないと言える。
◎結果&考察 燃料合成の仕組みを見つけ出す→合成の仕組みを見つけ出す
◎結果&考察 直接ガソリンやナフサ等(燃料と原料両方)を合成するような技術→ナフサ等の石油の一部を合成するような技術
◎結果&考察 を開発できれば、より効率的に各種燃料や各種材料を確保できると思われる。→を開発する。なお、その所産は、原則として“材料”として活用し、燃料としての活用は非常時のみにする。
◎結論 医学の発展→医学&医療の発展
【ヒストリー】
◎ヒストリーのすべてのページ リンクの色を、青から濃いピンクに変更◎ヒストリーのトップページ以外のページ 7つのコンパス、物語3.0、サプリ、サンプル、ヒストリーのリンク集をすべてgifにする。(物語3.0→物語3.02)
【サンプル】
◎3番目のコンパスにおいて、追加
話の流れ 会話の流れ
音の伝わり、音圧の変化 電子の流れ、電圧の変化
手順(物作り、料理、掃除、将棋…)
受精してから、器官が形成されていく流れ(発生の流れ)
出産の流れ(第1期→第2期→第3期)
赤ちゃんの発達の流れ(首がすわる→寝返り→お坐り→ハイハイ→ …)
ボールの動き(野球ボール、サッカーボール、バレーボール…)
投球フォームの流れ、配球の流れ バッティグフォームの流れ 走塁(一塁→二塁→三塁→ホーム)守備でのプレーの流れ(例…ダブルプレー)
サッカーでの、ボールのパス回しの流れ(例…センターリング→シュート)バレーでのプレーの流れ(例…レシーブ→トス→スパイク)
2009年3月21日 さんぽフルーツ1.060
さんぽフルーツトップページ
◎もみじの写真のgif中の木岬 さんぽの間隔を調整する。
◎物語3.01(3.02)、サプリ、サンプル、ヒストリーのリンク集のgifのグラデーションを微調整(他のグラデーションと統一ぎみにする)
※なお、他のページにある同じリンク集も、同様に変更。
◎【物語3.01】→【物語3.02】 アップ履歴以外の、ほぼすべてのページで表示を変更
【物語3.02(3.01)】
◎10本文中の数字 半角→全角 これで1枚の地図が完成
◎16本文中の数字 半角→全角 数10センチの空中
◎16本文中の数字 半角→全角 2階の窓から外へと
◎24本文中の数字 半角→全角 2番目のコンパス
◎26本文中の数字 半角→全角 1艘の船 この1年で感じたこと
◎27本文中の数字 半角→全角 本文中の数字 半角→全角2番目のコンパス
◎28本文中の数字 半角→全角 2番目の“コンパス・フォー・ライフ”
◎28本文中の数字 半角→全角 2番目のコンパス(2カ所)
◎30本文中の数字 半角→全角 3枚いて 全部で5枚
◎35本文中の数字 半角→全角 任期は、3年 3番目のコンパス 中学3年 この1年で考えたこと
◎37本文中の数字 半角→全角 3番目のコンパス
◎38本文中の数字 半角→全角 ほんの1例
◎38本文中の数字 半角→全角 3番目の“コンパス・フォー・ライフ” 3番目のコンパスのすごさ
◎39本文中の数字 半角→全角 3番目のコンパスってさぁ
◎40本文中の数字 半角→全角 3番目のプチ・マップ作り
◎41本文中の数字 半角→全角 本文中の数字 半角→全角3番目のコンパスの意味、1日1回、年に1度
◎41 CO2、O2の中の2を半角のままで小さく。
◎42本文中の数字 半角→全角 3番目のコンパス
◎56宇宙人の1種であるというとに他ならん──→宇宙人の1種であるということに他ならん──
◎68本文中の数字 半角→全角 もう1つのレジ
◎70本文中の数字 半角→全角 1枚の葉っぱを見るか、1本の木を見るか、1つの森を見るか
◎71本文中の数字 半角→全角 1つの“生きていく際の方向”
◎72本文中の数字 半角→全角 5番目のコンパス
◎76本文中の数字 半角→全角 1時間目(2カ所)
◎81本文中の数字 半角→全角 5番目のコンパス
◎84彼を知っているの!?」 「──ええ!?」 !!!→彼を知っているの!?」 「──え? っていうか、そういう笑い方するヤツは、他にもいっぱいいるんじゃないの? そっちの世界では」 「いいえ、いないわよ。 彼以外には── キャハハッ?♪」 「──ええ!?」 !!!
◎102本文中の数字 半角→全角 それら1つ1つは
◎105数字半角→全角 これら1つ1つも立派な
◎106本文中の数字 半角→全角 0からすべてを 0から作り出されては
◎117本文中の数字 半角→全角 1年なんて
◎119本文中の数字 半角→全角 この3年間
◎123本文中の数字 半角→全角 7番目のコンパス
◎126本文中の数字 半角→全角 7番目のコンパス
◎129本文中の数字 半角→全角 3%未満
◎130本文中の数字 半角→全角 1. 2. 3. 1日1回
◎132本文中の数字 半角→全角 7番目のコンパス(2カ所)
◎134本文中の数字 半角→全角 7番目のコンパス
◎135本文中の数字 半角→全角 4番目から6番目
◎136 橙色の 見方、決め方 をそれぞれ太く
◎137本文中の数字 半角→全角 1番目のコンパス
◎138ねぇ、登り坂と下り坂、どっちが好き?」と彼女。 「え? ──そりゃぁ、下り坂」と僕。→ ねぇ、登り坂と下り坂、どっちがラク?」と彼女。 「え? ──そりゃぁ、下り坂」と僕。 「でしょ? で── 登り坂と下り坂、どっちが好き?」 「──下り坂」と僕。
◎138だから、“下り坂が『For』”とかって意味づけができるであろう7番目のコンパスは→だから、“下り坂の部分が『For』”とかって意味づけができるであろう7番目のコンパスは
◎147本文中の数字 半角→全角 1本のビン
◎154本文中の数字 半角→全角 7番目のコンパス
◎156〜162 168〜170 本文中の数字 半角→全角 7番目のコンパスのフラクタル
◎158図 熱いものに触れて思わず(反射的に、自動的に)→熱いものに触れて思わず(自動的に)
◎158図 3カ所、テキストの背面、白く塗りつぶす
◎166本文中の数字 半角→全角 もう1つのライフの本質 本質の1つなのね?
【サンプル】
◎創造する 文追加
(※“生体を模倣して創造する、生体と異なるように創造する”は、その例)
◎創造する 文&プチマップ追加 他をみて創造する『Out』クリエイションもあれば、自分自身をみて、創造する『In』クリエイションもある。
◎創造する 文&プチマップ追加 見て、創造する『In』クリエイションもあれば、、見ないで創造する『Out』クリエイションもある。
◎アップ履歴2008 2008年5月25日 【物語3.0】→【物語3.0(1)】
◎アップ履歴2008 2008年5月20日以前の【物語3.01】の表示を【物語3.0】に修正
アップ履歴 2009年3月17の中の次を削除 ◎158図 熱いものに触れて思わず(反射的に、自動的に)→熱いものに触れて思わず(自動的に)
アップ履歴 2009年3月17の中の次を削除 ◎158図 3カ所、テキストの背面、白く塗りつぶす
2009年3月17日 さんぽフルーツ1.059
◎ネイチャー写真 とんび ☆→☆☆
◎ネイチャー写真 どんぐり ☆→☆☆
7つのコンパス
◎トップページ 1番目のコンパスの図 数字を真ん中に(windows用)
【サンプル】
◎創造する 1の袋→1つの袋
◎4番目のコンパスにて追加 古い(過去に存在する) 新しい(過去に存在しない)
【物語3.01】
◎52
「うん──。 ──あ、でも、今は、もう大丈夫さ」 「──うん」 → 「うん──。 ──あ、でも、今は、もう大丈夫さ」 「──うん」 「──」 ・・・ ふと、悲しげな表情をした僕に気付いたからか── おじいさんは、続けて語り始めた。 「まぁ──。 動物にしろ、人間にしろ、いずれしぬ。 いつか、しぬ。 じゃがのお、そこで── ただ、悲嘆にくれたり、おびえたり、おそれたり … するだけでは── つまらん結果をまねいてしまうことになるじゃろう──」「──」「いつかしぬこと── まずは、それをしっかり受け入れる──。 じゃが、決して、その認識だけで終わるのではないぞ──。 “だから、どうしたらいいのか──。 だから、どう生きたらいいのか──” そういったことこそをしっかり見つめていくんじゃ」 「──。 どう生きたらいいのか──」「あぁ、そうじゃとも──。 もちろん── “だから、どう生きたいのか。 だから、ほかの人たちと、どう接していきたいのか。 だから、誰に何を伝えていきたいのか──。 何を残していきたいのか──。 …”も含めて── じゃ。 そんなふうにして生きていけば── 人生、より実り多きものなるじゃろう──」 おじいさんは、僕を見て、ほほ笑んだ。 「──」「より充実させようとして生きること── よりよく生きようとすること── … それらも、とっても、すてきなことじゃ──。 わしは、それを、生への執着とは呼ばん──。 それは、生きることそのもの── かけかげえのない生の一部そのものなのじゃからのぉ──」 「──あぁ。 そうだね──。 ・・・ ──ありがとう」 どれくらいの時間がたったのだろう。 僕とおじいさんは、しばらく水平線を眺めていた──。
(1行空ける)
◎56地球人は、宇宙人の1種じゃ──→地球は、宇宙の一部じゃ。 ということは、地球人は、宇宙人の1種であるというとに他ならん──
◎56“もしかしたら、〜 を繰り返しているのかもしれん──”→もしかしたら、〜 を繰り返しているのかもしれん──。
◎59このあたりはな── →このあたりの岬はな──
◎59キスした場所なんじゃ。→キスした場所でもあるんじゃ。
◎91 3年 数字を半角→全角
◎158本文
いわば、反射的に、自動的に … ──つまり、無意識に運動しているとも言える→いわば、動的に … ──つまり、無意識に運動しているとも言える
◎158図 熱いものに触れて思わず(反射的に、自動的に)→熱いものに触れて思わず(自動的に)
◎158図 3カ所、テキストの背面、白く塗りつぶす
◎181 この46億年の→この、46億年もの
◎181絶妙な生態系から、恩恵を受けとる一方──→絶妙な生態系から、赤ちゃんのように恩恵を受けとる一方──
◎181そのプロセスに、この研究成果が、→そのフルーツ育てのプロセスに、この研究成果が──
2009年2月28日 さんぽフルーツ1.058
さんぽフルーツ
◎トップページ 最新更新日→最新アップ日 (0→-1pt)
7つのコンパス
◎トップページ
◎コンパスと○数字の間隔をテーブルで区切り、高さの間隔を調整。
◎トップページ表中 R13→R12(小卒以上推奨)
◎トップページ表中 R16→R15( 中卒以上推奨)
◎トップページ表 左寄り→中央
【物語3.01】
◎トップページ コンパスのテーブルの幅を調整(余白を作る)
◎コンパスと○数字の間隔をテーブルで区切り、高さの間隔を調整。
【物語3.01】
◎12半角→全角 1年で最も美しくなるんじゃ。
◎12──2番目のコンパスについては、来年、話そう→2番目のコンパスについては── 来年、話そう
◎23人生は、果実作りだ→人生は、フルーツ育てだ
7つのコンパストップページ、【物語3.01】トップページ
◎48 必死に、もがいた。 しにものぐるいで、もがいた。 ──んにゃろう! しんでたまるか! やりたいことがいっぱいあるんだ! やらなきゃならないことがあるんだ! あれも── これも── それも── … → 「ごぼっ」 ──う、うそだろう。 ・・・ 「うごっ」 ──こ、こんなことがあっていいのか ・・・ 「おごっ」 やってみたいことが、いっぱいあるはずなのに── ・・・ あれとか── 「あがっ」 ・・・ これとか── 「ごぼぼっ」 ・・・ それとか── 「おごごっ」 ・・・
◎86 「クスクスッ。 その調子、その調子!」「ただ── 勉強への意欲が湧いてきたのはいいけれど── → 「クスクスッ。 その調子、その調子! ──ノーベル賞、もらちゃったりしてね。 アハッ」 「そうそう。 ノーベル賞、ノーベル賞。 アハハッ。 ・・・ ──。 ただ── 勉強への意欲が湧いてきたのはいいけれど──
◎107 だから、少なくともその理由から、→だから、そういう意味では── 少なくともその理由から、
◎108追加 ある意味、何かの賞とかも、いいのかもしれないけれど── それよりはるかに大事なものが── 僕には、あるはずだ。
【ヒストリー】
◎2004『カラダ ココロ』は、『In Out』の一例であることに気づいたこともあり── →『カラダ ココロ』は、本質的に『In Out』のコンパスだけで説明できることに気づいたこともあり──
◎2005(遠回りしましたが、結局、95年当時のものと同じ表現に舞い戻りました)→(遠回りしましたが、結果的に、95年当時のものと同じ表現に舞い戻った形となりました)
【サンプル】
◎『カラダ アタマ』追加 体でキャッチできる言葉にする
◎テーフルの余計な空白を削除──。
◎各テーブルの下部に…の行を加える
◎各テーブルの最下部に薄いブール色のセルにし、『In Out』『On Off』等を加え、各サンプルを統一して表示
2009年2月20日 さんぽフルーツ1.057
サイト全体
◎さんぽフルーツのロゴ、全体的に修正
Altテキスト 木岬さんぽ作品集 SAMPO FRUITSに統一
円形の黒て囲む→長方形の黒でかこむ。
さんぽフルーツトップページ
◎上部のリンク集を大きなテーブルから出す。
◎研究、写真の中のもみじ等の若干の位置変更
◎もみじの写真を含む画像jpeg→gif
7つのコンパストップページ&【物語3.01】トップページ
◎7つのコンパスの図、すべて、SVGを介さず直接、gifの画像ファィルを作成
【物語3.01】トップページ、となりののコンパス、ふたりののコンパス、せかいのコンパス各トップページ
◎表紙 PDF経由て、web用にgifの画像ファイルを作成
◎せかいのコンパス表紙 色をやや明るく
研究 1.01→1.02
結果&考察
◎(H2Oの循環の強化)→(H2Oの循環の強化、多重的な対策)
◎(by生態系と個体の類推──)→(by生態系と生体の類推──)
◎“温度が上がりすぎないようにするため”に、人を含む、多くの恒温動物が(長い進化の歴史を経て)採用している方法は、代謝を低下させること(二酸化炭素の排出を減らすこと、運動を減らすこと)と、汗をかくことであった。 代謝を低下させることに比べ、汗を用いて温度を下げるというのは、とても合理的・効率的であり、安全である。 一方、代謝を下げることは、温度の下げ過ぎを含めて、生存の危機を招くリスクがある。
“生態系の温度が上がりすぎないようにする”ためには、水を使うことも有効であるであると考えられる。 温度の下がり過ぎや社会システムの危機のリスクも低い。
その意味においても、打ち水は、とても理にかなった方法である。 そして、さらなる効果的な、打ち水効果を利用できるシステムの開発が重要であると思われる。(例えば、道路から一斉に放水して潤す等の技術 … ) そのためにも、水不足の問題を抱えた地域をも念頭においた、すぐれた水循環を開発し、構築することが大切であろう。 乾燥地帯を含めて、どこへでも効率的に水を届けられるような、“水のパイプライン網”等を作るために、生体の血管網から学び──何十億年もの進化の歴史のつまった“生体”を、多いに模倣して──創造していくことも有効であると考えられる。
また、水を上手に循環させて、熱の上昇をコントロールする技術が開発できれば、同時に、寒冷化を予防することも可能になると思われる。
二酸化炭素(温室効果は、メタンの21分の1)のみならず、類い稀な比熱を持つ“水”にも注目して気温をコントロールしようとすること(気温の上がり過ぎ、下がり過ぎの両方の予防していくこと)が、最も確実・迅速・安全で、合理的・効率的であると考えられる。
→ 生体は、何かある目的を達成するために(例えば、血糖値の下がり過ぎを防ぐ、体温の上がり過ぎを防ぐ、血圧の下がり過ぎを防ぐ …といった目的)、多くの場合、同時に何重にも対策を重ねている。 そうすることで、より安全に、より安定的に(確実に)、その目的を達成している。 例えば、“体温が上がりすぎないようにするため”に、人を含む、多くの生体(特に恒温動物)は、運動を減らす(代謝を低下させる)、水を用いて涼しくする(発汗、湖水浴、水風呂、水シャワ…)、血管の拡張させる、日陰に移動する、移住する 等々、様々な方法をとっている。 これらのことは、生態系の温暖化対策のために、二酸化炭素の排出を減らすこと、単独の方法に頼るべきではないことを示していると思われる。 とりわけ、“発汗”のシステムが、長い進化の歴史を経て採用されてることに着目すれば、 “生態系の温度が上がりすぎを防ぐ”ためには、二酸化炭素の排出を減らす(大気中の二酸化炭素を削減する)ことにプラスして── “水を活用する”ことを同時に進めていくことも、大切であることが類推される。 そうした意味においても、打ち水も、とても理にかなった方法の1つである。 そして、さらなる効果的な、“打ち水”効果を利用できるシステムの開発も有効であろう。(例えば、道路から一斉に放水して潤す等の技術 … ) そのためにも、水不足の問題を抱えた地域をも念頭においた、すぐれた水循環を開発し、構築することが重要である。 乾燥地帯を含めて、どこへでも効率的に水を届けられるような、“水のパイプライン網”等を作るために、生体の血管網から学び──何十億年もの進化の歴史のつまった“生体”を、多いに模倣して──創造していくことも有効であると考えられる。 (当然、水が確保できれば、植物の生存の可能性も高まり── 植物が生育することができれば、大気中の二酸化炭素の削減へとつながるというメリットも生ずる。 パイプライン以外にも、“大気中の水の移動をコントロールし活用する”技術も、有効であると考えられる) また、水を上手に循環させて、過剰な温暖化を予防する技術が開発できれば、同時に、過剰な寒冷化を予防することも可能になると考えられる。 二酸化炭素の削減に加えて、類い稀な比熱を持つ“水”の活用も同時に重ねて進めることが、生態系の温度をコントロールする(気温の上がり過ぎ、下がり過ぎの両方の予防していくこと)ために、より確実(安定的)で、迅速・安全で、合理的・効率的である。
◎エネルギーシステムの開発も進める。 →エネルギーシステムの開発も進める。 (多重的な対策)
◎追加 また、エネルギー確保に関しても、多重的な取り組みが重要となることが類推される。
◎過剰な温室効果ガス(二酸化炭素やメタン)を有効活用させることで→温室効果ガス(二酸化炭素やメタン…)を有効活用することで
◎追加 (CO2,CH4 …の循環の強化、多重的な対策)
◎メタン→メタン(温室効果は、二酸化炭素の21倍)
◎追加 もし温暖化の抑制を目指す際ならば、温室効果ガスの排出を減らすことにプラスして、温室効果ガスの有効活用を同時に進めていくこと── こうした多重的な取り組みが、より確実であり、合理的である。(おな、水蒸気も温室効果ガスの一種である。 その意味においても、1でのべた水の循環の重要性が認められる)
【サンプル】
◎創造する メロロディー→メロディー
【物語3.01】
◎となりのコンパストップページ ロゴを小さくして、ほかと同じ大きさに
◎152笑っていたりしていても、免疫の働きって、よくなるんでしょ?→クヨクヨしていたりするより、笑っている時の方が、免疫の働きって、ずっと、よくなるんでしょ?
◎152数字半角→全角 年に10回くらい
2009年2月10日 さんぽフルーツ1.056
◎ウェブサイトについて メールのリンク切れ修復 かつ、Altテキスト追加
◎さんぽフルーツトップページ メールを再び戻す。かつ、Altテキスト追加
7つのコンパス【サンプル】
◎6→4(ここに)いる (ここに)いない
◎6これは、いつもの自分だ これは、いつもの自分でない→これは、いつもの自分だ これは、いつもの自分と違う
◎6これは自分だ これは自分ではない→これは自分と同じだ、これは自分と違う
◎6これは、自分のことだ これは、自分のことではない→ これは、自分のことと同じだ これは、自分のことと違う
◎4追加
これは、いつもの自分だ これは、いつもの自分でない
これは自分だ これは自分ではない
これは、自分のことだ これは、自分のことではない
◎6いつもの自分をなくし続けている→いつもの自分を失い続けている
◎6 なくしている、失っている、欠けている(欠いている)→失っている、欠けている(欠いている)
◎6手に入れる なくす→手に入れる 手放す
◎4追加 手に入れる 手に入れない
◎4追加 手放す 手放さない
◎4追加 覚えている 覚えていない
◎4追加 忘れる 忘れない
◎6(頭の中からなくす…)→(頭の中から消す…)
◎4追加 知っている(頭の中にある…) 知らない(頭の中にない…)
◎6釣り合っていない→釣り合いがくずれている
◎4追加 釣り合っている 釣り合っていない
◎6→4合う 合わない
(間に合う …) (間に合わない …) 似合う 似合わない
※◎4→6似てる 似てない 図も移動。
◎6ピッタリ ユルユル→ちょうどである、ピッタリ(服が…) きつい、ゆるい(服が…)
◎6(『コトバ』と『カタチ』が不一致)→(『コトバ』と『カタチ』がずれている)
◎6追加 課題と能力が釣り合っている 課題と能力がずれている
◎6→4できる(可能) できない(不可能)
◎6思いのままに叶う(自由自在) 思いが叶わない(不自由)
→自由自在 思いと現実がずれている
◎4追加 思いのままに叶う(自由自在) 思いが叶わない(不自由)
◎6削除 合格する 不合格になる。
◎6“しよう”と“したい”が不一致 『アタマ』と『カラダ』が不一致
→“しよう”と“したい”がずれている 『アタマ』と『カラダ』がずれている
◎4→6ある(目的がある、意味がある、 価値がある …) ない(目的がない、意味がない 、価値がない …) 存在する 存在しない
〜する 〜しない
◎6 (組み合わせたり、組み分けたリを繰り返して、創造される)→(組み合わせたり、組み分けたリを繰り返して、新しいものにたどり着く)
◎6図追加 組み合わせる←→組み分ける
◎4 追加 見る 見ない 決める 決めない 動かす 動かさない 支持する 支持しない 反対する 反対しない 賛成する 賛成しない 愛する 愛さない 創造する 創造しない … …
【物語3.01】
◎98図 手に入れる なくす→手に入れる 手放す
◎98図 削除(ここに)いる (ここに)いない
◎98図 いつもの自分をなくし続けている→いつもの自分を失い続けている
◎98図 これは自分だ これは自分ではない→これは自分と同じだ、これは自分と違う
◎98図(頭の中からなくす…)→(頭の中から消す…)
◎98図 削除 知っている(頭の中にある…) 知らない(頭の中にない…)
◎98図 釣り合っていない→釣り合いがくずれている
◎98図 削除 合う 合わない(間に合う …) (間に合わない …) 似合う 似合わない
◎98図において追加 きつい ちょうどである、ピッタリ(服が…) きつい、ゆるい(服が…)
◎98図において削除 できる(可能) できない(不可能)
◎98図において追加 課題と能力が釣り合っている 課題と能力がずれている
◎98図において 思いのまま(自由自在) 思いが叶わない(不自由)→思いのままに叶う(自由自在) 思いと現実がずれている
◎98図において削除 合格する 不合格になる。
◎98図において (『コトバ』と『カタチ』が不一致)→(『コトバ』と『カタチ』がずれている)
◎98図において “しよう”と“したい”が不一致 『アタマ』と『カラダ』が不一致→“しよう”と“したい”がずれている 『アタマ』と『カラダ』がずれている
◎98図において 削除 ある(目的がある、意味がある、 価値がある …) ない(目的がない、意味がない 、価値がない …) 存在する 存在しない
〜する 〜しない
◎98図において追加 組み合わせる 組み分ける
◎101文 今、ひらめいたんだけど、“似てる‐似てない→今、ひらめいたんだけど、“似てる‐異なっている
◎101図 似てる 似てない→似てる 異なっている
2009年1月16日 さんぽフルーツ1.055
【物語3.01】
◎107 創造すること──“新しく何かを生み出す”ことの本質の1つなのかもね→創造することの本質の1つなのかもね
【サンプル】
◎創造する テキスト&テキスト中の3つの図 追加
【物語3.01】の中では、“組み合わせたり、組み分けたりを繰り返すことが、創造する際の、本質の1つである──”といった内容のことが述べられています。〜
〜創造する営みは、好きやよいも含めて──『For』を保証してくれます。 そして── 『For』ライフや“For Life”をも根底で支えてくれます。
2009年1月14日 さんぽフルーツ1.054
研究『3Steps理論とその応用』1.00→1.01
◎結果&考察 今、少なくとも3つ挙げられる。→今、少なくとも4つ挙げられる。
◎結果&考察 水を効果的に使う。→水も効果的に使う。
◎結果&考察 水を使うことが有効であるであると考えられる。→水を使うことも有効であるであると考えられる。
◎結果&考察 代謝を低下させること(二酸化炭素の排出を減らすこと)ではなく、汗をかくことであった。→代謝を低下させること(二酸化炭素の排出を減らすこと、運動を減らすこと)と、汗をかくことであった。
◎結果&考察 “水”こそに→“水”にも
◎結果&考察 二酸化炭素(温室効果は、メタンの21分の1)ではなく、→二酸化炭素(温室効果は、メタンの21分の1)のみならず、
◎結果&考察 追加3.過剰な温室効果ガス(二酸化炭素やメタン)を有効活用させることで減らしたりする(上手に循環させることでコントロール)技術の開発もめざす
かつて、一見、脅威だった酸素が増えたことで、それを有効活用できる生物(動物)が繁栄した。 一見、脅威である二酸化炭素(メタン)が増えていることは、それを有効活用できる生物(植物)(orメタン活用のシステム)が繁栄するチャンスでもある。高濃度の二酸化炭素は、光合成を進める植物やメタン菌等にとって、貴重な恩恵である。 二酸化炭素を資源とする生物に二酸化炭素を吸収してもらい減らしていくことは合理的である。 その意味でも植林は、とても重要である。 また、2の4で述べた、メタンを活用できる技術を開発することも、過剰な温室効果ガスをコントロールする意味においても重要となる。
◎結果&考察 3生態系やエネルギーをしかっりモニターした上で〜→4生態系やエネルギーをしかっりモニターした上で〜
◎2008→2008-2009
アップ履歴 下記 2008年年1月10日 さんぽフルーツ1.053→2009年1月10日 さんぽフルーツ1.053
2008年1月10日 さんぽフルーツ1.053
さんぽフルーツトップページ
◎Altテキストの修復 木岬 さんぽ作品集 さんぽフルーツ、木岬 さんぽ作品集 SAMPO FRUITS
◎Altテキスト追加 研究
◎2008→2008-2009
2009年1月7日 さんぽフルーツ1.052
◎アップ履歴 2008年の部分を別ページに分けてリンクをはる(アップ履歴2008)。
7つのコンパストップページ
◎生態系→生態系(エコシステム)
【物語3.01】
◎55
「大丈夫大丈夫──。 じゃが、もうちょっとで、おぼれそうになるとこだったわい。 アッハッハッ!」→「あぁ、大丈夫大丈夫──。 ──じゃが、もうちょっとで、おぼれそうになるとこだったわい。 ゴホッ」
◎55泳ぎの名手だったんじゃよ。 ゴホッ→泳ぎの名手だったんじゃよ。
◎55 3本 数字について半角→全角
◎56
繰り返しているのかもしれない──”→繰り返しているのかもしれん──”
◎56削除 “もしかしたら、地球人が、今現在、生存している唯一の宇宙人なのかもしれない──” そんな気持ちさえも持って、生きのびていこうとする努力を真剣にしていなければ── 他の宇宙人と出会うことなども、当然、夢また夢じゃろう──。 → ・・・
◎111
自分の実体験や実感から、見いだした、自分にピッタリの言葉たちであった──。→自分の実体験や実感から見いだした、自分にピッタリの言葉たち── そして、何回か書き直した上で出来上がった言葉たちであった──。
◎149「──37度8分。 ──ピークは、過ぎたようね。 一安心ね」→「──36度8分。 ──ピークは、過ぎたようね。 ──まずは、一安心ね」
◎149「いや、まだまだ、けっこう高いよ。 もう少し、様子みていかないと──」→「うん。 でも、まだ、もう少し様子みていかないと──」
◎149「──うん。 でもね──。→「──うん、そうね。 でもね──。
◎151追加 もちろん、上がりすぎるのは、よくないけれど──
◎154 自己、ソウジセイ──。→自己、相似性──。
【サンプル】
◎心 (間接的にたどり着く技術には、至っているようですが…)
【ヒストリー】
◎2002で追加 (【物語3.01】39の中の“ちょっと曲っちまったけど── まぁ、いいかぁ。”には、そのような意味を込めていました)
研究
◎3Steps理論とその応用について 概要図の中の物質生成レベルでの修正
(電磁気力のエネルギー保存で、化学反応が進んだりする、超流動、トンネル効果…) → (化学反応が進んだりする…)