研究論文
『プランクスケールの自然についての幾何的モデルの探究が生む驚異的な成果』
14《「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)との相互作用》
電子の質量エネルギーは、静止質量エネルギーと運動エネルギーの和であり、ともに「重力子の放出源として働き続ける能力」を持っています。
この電子の質量エネルギーと深い関わりがあるのが、原始ヒッグス場ユニット(PHU)です。
それに対して、電子の軌道運動と深い関わりがあるのが、電子ヒッグス場ユニット(eHU)です。(16《ヒッグス場と各種の場》)
原始ヒッグス場ユニットと電子ヒッグス場ユニットの幾何的モデルを比較して示すと下のようになります。
|
原始ヒッグス場ユニット
(PHU(=Primordial Higgs(field)Unit))
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU=electron Higgs(field)Unit)
|
|
ヒッグス場ユニットの構造
|
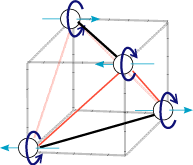
「左巻き素スピノル2つ」のペア
&「右巻き素スピノル2つ」のペア
|
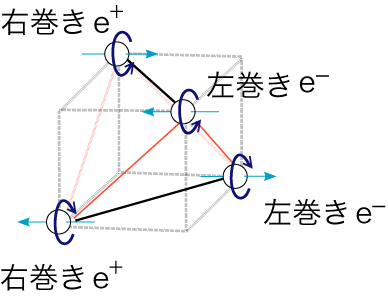
「左巻き電子と右巻き陽電子」のペア×2
|
|
基本構造の
おおよそのサイズ
|
2プランク立方((2LP)3[m3])
(2LP=3.232×10-35[m])
|
<10-10[m]
※少なくとも水素原子の大きさより
小さいと考えられます。
(詳細な検討は、今後の課題です)
|
電子の軌道運動は、原始ヒッグス場ユニット(PHU)に作用すると、それらを直接「縮みきり“四角形”」まで変形させることによって重力子を放出させ続けます。 まさに、その能力が、質量エネルギー(=運動エネルギー)に相当するものです。
一方、電子の軌道運動は、電子ヒッグス場ユニット(eHU)に作用すると、電子の消滅と生成の波を創発します。
まさに、この波は、電子の物質波に相当するものです。(成果3 2《電子の波動性と波動関数ψ──シュレーディンガー方程式》)
「電子の物資波(消滅と生成の波)」についての概要を示すと次のようになります。
電子が消滅と生成を繰り返す様子を示す幾何的モデルを簡単に図示すると次のようになります。
左巻き電子が運動してきて、電子ヒッグス場ユニットに近づく。
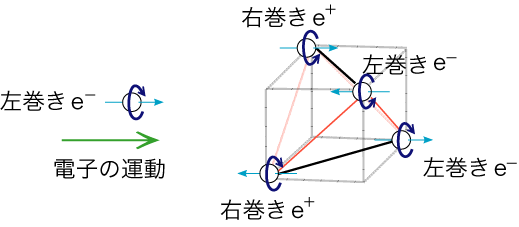
|
→ |
左巻き電子がで電子ヒッグス場ユニット(eHU)の中の
右巻き陽電子と結びつくことによって消滅する。
と同時に、新たな四極子が生成する。
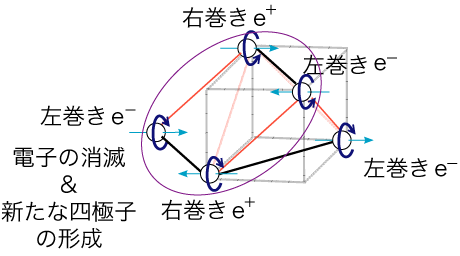
※紫の楕円で囲んだ4つが新たな四極子です。
|
|
↑
|
|
↓
|
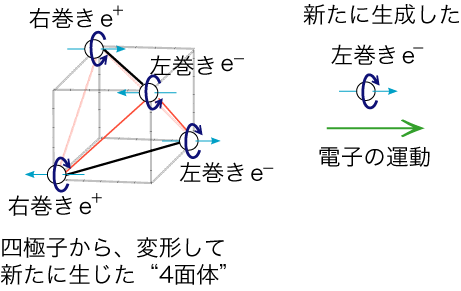
| ※四極子が“4面体”に変形する過程で、新たな電子が生成します。 |
|
定常状態(速さ一定)において、電子は、決まった波長λe[m]を持ちます。
この波長λe[m]を持つ、定常状態(速さ一定)の電子は、λe/2[m]の間隔の電子ヒッグス場ユニットの相互作用しながら、軌道運動をします。
この電子の“定常状態”において、電子に作用する、「電子ヒッグス場ユニットが生じるポテンシャルエネルギー」は、次のようになると考えられます。 (成果3 3《電子の定常状態と電子軌道》)
※各電子ヒッグス場ユニットが生じるポテンシャルエネルギーが、色別に示してあります。
運動している電子には、常に、“2つのポテンシャルエネルギー”が作用していることが読み取れます。
これらの“2つのポテンシャルエネルギー”が作用することによって生まれる力は、合計が常に0になることが図から読み取れます。
なぜなら、“2つのポテンシャルエネルギー”は、上下逆転している同じ形で、“傾き(勾配)”の大きさが等しいからです。(なお、電子に作用するポテンシャルエネルギーの“傾き(勾配)”が、電子に作用する“力”に相当するのでした)
※また、一方のポテンシャルエネルギーの減少分が、もう一方のポテンシャルエネルギーの増加分に常に等しいことが読み取れます。すなわち、ポテンシャルエネルギーの合計が常に一定であることが読み取れます。 |
このようなしくみにより、定常状態の電子は、一定の速度ve[m/s]と一定の波長λe[m] を保ち続けることになります。
(この場合、電子は、加速or減速しないので、光子を放出しないことになります。 参考 成果3 18《ボーアの原子模型》)
以上をまとめて、電子と電子ヒッグス場ユニットの相互作用の詳細を示すと、次のようになります。
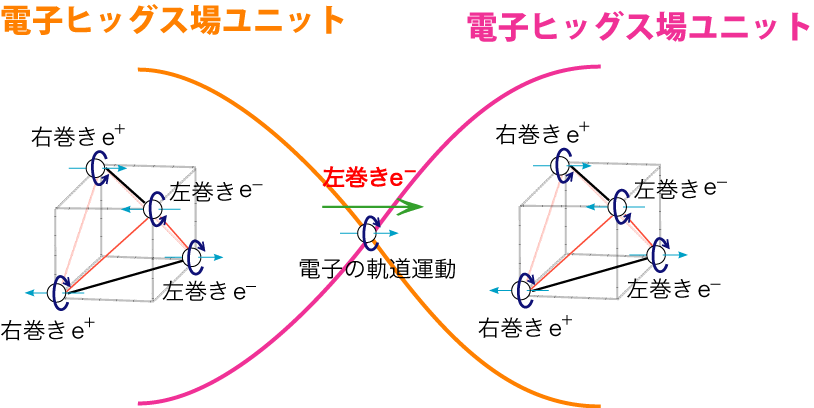
※左巻き電子が軌道運動し、ある電子ヒッグス場ユニットから離れると同時に、別の電子ヒッグス場ユニットに近づいていることが示されています。
※“定常状態(速さ一定)で軌道運動している電子”は、この図からわかるように、常に「離れている1つの電子ヒッグス場ユニット」と、「近づいている1つの電子ヒッグス場ユニット」の両方から、同時に、力を受けています。
このように電子に働いている力の合計は、定常状態(速さ一定)の場合、常に0になります。
(“ポテンシャルエネルギーの傾き(勾配)”に相当する、2つの力の大きさが互いに等しくて、その向きが逆だからです) そのおかげで、定常状態(速さ一定)の電子は、電子ヒッグス場ユニット(eHU)と相互作用しながらも、等速運動を実現しているのです。
(なお、原始ヒッグス場ユニット(PHU)と相互作用しながらも、等速運動を実現しているしくみについては、5《運動の第1法則(慣性の法則)&第2法則(F=ma)》で示しました)
※したがって、このことは、「どのようなしくみで電子の定常状態が生じるか、どうして電子の定常状態において光子が放出されないのか」の理由の一部を説明していることになります。(ボーアが仮定(前提)とするしかなかったことの一部を説明していることになります)(成果3 18《ボーアの原子模型》) |
|
|
↓
|
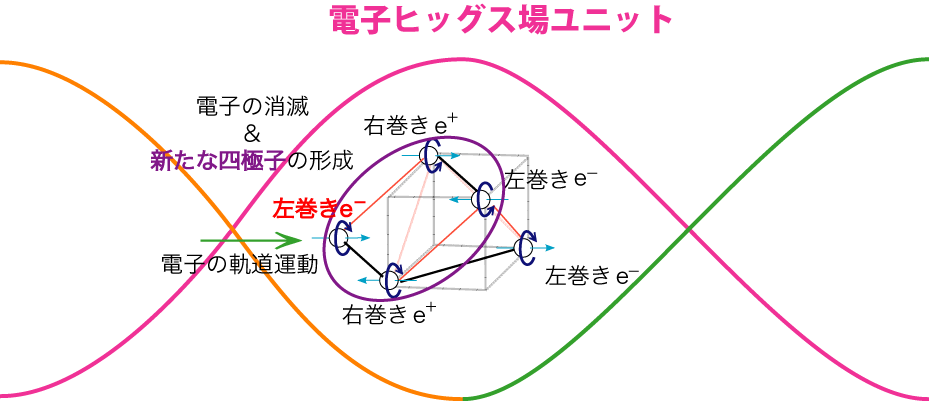
※軌道運動してきている左巻き電子が、原始ヒッグス場ユニットの中の右巻き陽電子と結びつくことによって“消滅”すると同時に、新たな四極子が生成しています。
この電子ヒッグス場ユニットは、かつて「電子ヒッグス場ユニットが生んだ“ポテンシャルエネルギー”」に等しい大きさのエネルギーを蓄えることになります。
※この過程で、左巻き電子は、一定の速さv[m/s]で運動し続けているのに関わらず、消滅もしています。
この消滅(=静止質量m0の消失)の度合いに比例して、運動エネルギー(m0v2/2)は、減少することになります。
この電子の「静止質量エネルギー&運動エネルギー」が減少する変化は、サインカーブになると考えられます。
(10《ウィークボソンW−、W+、Z0と、弱アイソスピン》)
そのカーブは、下図の紫で示したサインカーブ(特に◯で示した部分)になると考えられます。
この紫のサインカーブの波長は、ポテンシャルエネルギーのサインカーブの波長の1/2になっています。
|
|
|
↓
|
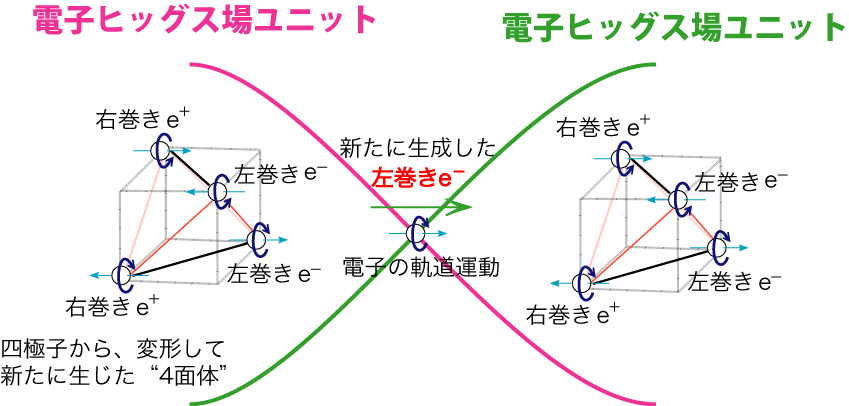
※電子ヒッグス場ユニットが生ずるポテンシャルエネルギーを利用して、「四極子を構成していなかった残りの左巻き電子」が新たに放出されています。
この過程で、電子ヒッグス場ユニットの中の四極子が消滅すると同時に、元の“4面体”に戻ります。
この新たに生じた左巻き電子の起源が、「電子ヒッグス場ユニットを構成していて、四極子になり損ねた左巻き電子」であるということは、新たに生じた左巻き電子は、元の左巻き電子とは、厳密には異なることを意味します。しかし、両者は、全く区別がつきません。
(電子には、原子における同位体のような多様性がないからです。このことは、シンプル一様化原理と調和しています)
※電子ヒッグス場ユニットが生ずるポテンシャルエネルギーが解消されていると同時に、電子ヒッグス場ユニットがポテンシャルエネルギーを生じています。
やはり、電子ヒッグス場ユニットが生ずるポテンシャルエネルギーに由来する力と電子ヒッグス場ユニットが生ずるポテンシャルエネルギーに由来する力は、ぴったり打ち消しあっています。
つまり、この新たに左巻き電子が放出される過程においても、やはり、“左巻き電子の加速”は生じていません(等速運動を続けています)。よって、新たに左巻き電子が放出される過程においても、光子は放出されません。
※この過程で、「電子の速さv[m/s]」や「2つの電子ヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギーの合計」は、それぞれ常に一定となります。
※この生成(=静止質量m0の生成)の度合いに比例して、運動エネルギー(m0v2/2)は、増加することになります。
この電子の「静止質量エネルギー&運動エネルギー」が増加する変化も、サインカーブになると考えられます。
(10《ウィークボソンW−、W+、Z0と、弱アイソスピン》)
そのカーブは、下図の紫で示したサインカーブ(特に◯で示した部分)になると考えられます。
この紫のサインカーブの波長は、やはり、ポテンシャルエネルギーのサインカーブの波長の1/2になっています。
|
|
|
↓
…
|
つまり、このような電子と電子ヒッグス場ユニットの相互作用において、下図の紫のサインカーブのように、電子の「静止質量エネルギー&運動エネルギー」は、変化します。
※しかも、この紫のサインカーブは、電子の存在度(存在確率)に相当するものになっています。
(成果3 2《電子の波動性と波動関数ψ──シュレーディンガー方程式》)
この全過程における、紫のサインカーブで示している、電子の「静止質量エネルギー&運動エネルギー」の変化は、まさに、“波”と見なすことができるものです。
これが“電子の波動性”、すなわち、“電子の物質波”を説明する幾何的モデルです。
それは、電子ヒッグス場ユニットの“4面体”を、いわば(ポテンシャルエネルギーを蓄える)“バネ”として利用しながら、電子が速さv[m/s]一定のまま、電子ヒッグス場の中を、その質量エネルギー(静止質量エネルギー+運動エネルギー)を周期的に変動させながら、波動的に移動していることに相当しています。
しかも、この幾何的モデルは、“電子の物質波”は、「電子が、消滅と生成を繰り返すところの波」、すなわち、「“電子の存在度”が周期的に変化する波」であることを示しています。
(なお、「“電子の存在度”の周期的な変化」のサインカーブの波長は、上記の「電子ヒッグス場ユニットのポテンシャルエネルギーの変化」のサインカーブの波長の1/2となっています)
※この“電子の存在度”の変動の波は、まさに、“電子の存在確率”の変動の波と関連あるものです。
つまり、いわゆる“電子の存在確率”(=波動関数の絶対値の二乗ψ*ψが意味するもの)は、この“電子の存在度”の変化の波に相当していると考えると、ぴったりつじつま合います。(成果3 2《電子の波動性と波動関数ψ──シュレーディンガー方程式》))
「電子の質量エネルギー(運動エネルギー+静止質量エネルギー)」と「電子ヒッグス場ユニットの質量エネルギー」の和は、常に一定となります。
つまり、電子の定常状態における全過程で、トータルの質量エネルギーの増減は生じず、保存されています。
※したがって、電子の定常状態(速さ一定)において、
「電子ヒッグス場ユニットの質量エネルギーの最大値」=「電子の運動エネルギーの最大値」+「電子ヒッグス場ユニットの質量エネルギーの最小値」
の関係があることになります。
電子ヒッグス場ユニットのみならず、プレオン∴ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット、ニュートリノヒッグス場ユニットも、その本質は、プレオン∴、電子、クォーク、ニュートリノの“存在度を変動させる”だけであり、新たに質量を生み出すということはありません。
なぜなら、 「各種の粒子の質量エネルギー(運動エネルギー+静止質量エネルギー)」と「各種ヒッグス場ユニットの質量エネルギー」が、互いに転化しているだけだからです。
したがって、この各種の粒子と、各種の「ヒッグス場ユニット」の間の相互作用においては、“質量獲得”は、存在しないことになります。
つまり、素スピノル物理学パラダイムは、次の結論に至ります。
結論2-14.1 各種の粒子に“質量を与える”働きを持つヒッグス場は、原始ヒッグス場(原始ヒッグス場ユニットの総和)だけである。
※このことは、いわゆる、「カイラル対称性の破れにともなう質量獲得」の説明についての見直しを迫っています。
「カイラル対称性の破れにともなう質量獲得」とは、例えば、電子は、「左巻き電子→右巻き電子→左巻き電子→右巻き電子…」と変化することを繰り返す過程によって、(マクロレベルでの見かけ上の)光速を失い、質量を獲得することです。
(参考 『質量はどのように生まれるのか 素粒子物理最大のミステリーに迫る』(橋本省二 講談社ブルーバックス))
しかし、素スピノル物理学パラダイムは、このような「カイラル対称性の破れにともなう質量獲得」というしくみは、自然界に実在しないことを示しています。
1つの理由は、電子は、本質的に、左巻きであるからです。すなわち、“右巻き電子”は、「電子が光速を失うことにより、観測しうるもの」にすぎず、本来、右巻き電子と左巻き電子は、対称的に存在するものではないからです。(実際、観測される量は、左巻き電子>>右巻き電子となっています)
つまり、カイラル対称性は、「電子は、本質的に、左巻きである」という意味で、元々から破れているのです。
そこで、実在するとすれば、「左巻き電子→右巻き陽電子→左巻き電子→右巻き陽電子…」 のようなしくみです。
しかし、このしくみを含む(内在している)と見なせる、定常状態の電子と電子ヒッグス場ユニットの相互作用においては、「質量エネルギー(運動エネルギー+静止質量エネルギー)」と「電子ヒッグス場ユニットに蓄えられるエネルギー」が、互いに転化しているだけであり、“質量の新たな獲得”はどこにも存在していません。
質量獲得は、単に電子ヒッグス場ユニットと相互作用するだけでは達成されず、やはり、「原始ヒッグス場」との相互作用があってはじめて、達成されるのです。
つまり、素スピノル物理学パラダイムは、少なくとも、『例えば、電子は、左巻き電子→右巻き電子→左巻き電子→右巻き電子… と変化することを繰り返す過程によって、(マクロレベルでの見かけ上の)光速を失い、質量を獲得する』という意味での「カイラル対称性の破れにともなう質量獲得」は、実在しないことを示しており、その見直しを迫っているのです。
|
※連星のような軌道運動にともなって獲得される質量エネルギーは、電磁場のポテンシャルエネルギーを利用して獲得される外部運動エネルギーに相当する分だけ生じると考えられます。
|
電子ヒッグス場ユニット
(eHU=electron Higgs(field)Unit)
|
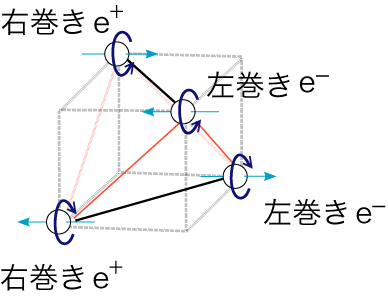
「左巻き電子と右巻き陽電子」のペア×2
|
※電子と陽電子がペアを組んで連星のような軌道運動をしているのは、それが、電磁場のポテンシャルエネルギーを利用して獲得される外部運動エネルギーにもとづいて生じているからである。
対照的に、プレオン∴ヒッグス場ユニットが、マイナスプレオンどうし、プラスプレオンどうしがペアを組んで連星のような軌道運動しているのは、それが、重力場のポテンシャルエネルギーを利用して獲得される外部運動エネルギーをもとづいて生じているからである。
|
それは、電子ヒッグス場ユニットのみならず、クォークヒッグス場ユニットについても同様に考えられます。
つまり、素スピノル物理学パラダイムは、対消滅した状態、すなわち、例えば、電子ヒッグス場ユニットやクォークヒッグス場ユニットの“正4面体”が形成されている状態でも、重力子の放出がなくならないことを示しています。
だからといって、1対10億の比率で物質が優位になり、残りの物質と反物質のペアが対消滅した所産が各種のヒッグス場ユニット(電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット…)と考えられることと、実際、ダークマターの比率は、せいぜい物質数%に対して、ダークマターが数十%の比率であることは、必ずしも矛盾しません。(すなわち、もし、例えば、電子ヒッグス場ユニットやクォークヒッグス場ユニットの“正4面体”が質量を持ち続け、重力子の放出を続けているのならば、ダークマターの比率は、物質数%に対して、ダークマターが数億%になってしまうという問題は生じません)
なぜなら、「物質と反物質のペアが対消滅した所産が各種のヒッグス場ユニット(電子ヒッグス場ユニット、クォークヒッグス場ユニット…)」の分布が、宇宙空間に均等にまんべんなく分布していれば、質量として観測されないことになる、という説明が成立するからです。
(一方、ダークマターは、分布が不均等でムラがある結果、質量として観測されていることになります)
この説明は、次のこととも調和しています。
1.(電子2つと陽電子1つで構成されていると考えられる)ミューオンが、1つの電子よりはるかに大きな質量を持っている。
2.新しいブラックホールができる際に生ずると考えられる(マイナスプレオン2つとプラスプレオン2つで構成されている、スピン0の)「縮みきり“4角形”」が、重力子を放出し続けると考えられる。(→素スピノル宇宙論)
3.(マイナスプレオン2つとプラスプレオン2つで構成されている)プレオン∴ヒッグス場ユニットが質量を持ち続け、それがダークマターであると考えられる。(→素スピノル宇宙論)
|
|