研究論文
『プランクスケールの自然についての幾何的モデルの探究が生む驚異的な成果』
2《電子の波動性と波動関数ψ──シュレーディンガー方程式》
《電子の波動性と波動関数ψ──シュレーディンガー方程式》
そもそも、シュレーディンガー方程式は、「ド・ブロイの物質波」の理論を取り入れて生まれたものでした。
すなわち、波動関数ψは、本来、「空間を伝わる電子波」を表すはずのものでした。
量子は空間を伝わるときには波動として伝わり, 物質と衝突するときには粒子として振舞う. 空間を伝わる電子波を表す, 時刻t と座標x, y, zの関数ψ(x, y, z, t)を波動関数と呼ぶ. … 電子波の伝わり方を表す法則, すなわち, 波動関数を決める方程式は、1926年にシュレーディンガーが発見したシュレーディンガー方程式である.
(p.40 裳華房テキストシリーズ-物理学 『現代物理学』 原康夫著 裳華房) 下線は筆者によります。
|
しかし、シュレーディンガー自身も、出来上がったシュレーディンガー方程式の解、波動関数ψについての解釈に苦労しました。
|
虚数 i を含む複素数がそこに入ってくることにシュレーディンガーは気づいた。彼は、自分の波動理論に複素数が出てくるのに頭を痛め、なんとか排除しようとがんばった。しかし、そうはできなかった。彼が頭を痛めたのは、複素数には二つの部分──実部と虚部──があり、虚部があるということは、波動関数には、直接観察できない位相があるということを意味していたからだ。位相とは、アナログ時計の針の角度のように周期的に変化する量で、位相に虚部があるということは、そこには直接測定できない部分があるということだった。位相の虚部は、時間の経過に従って振動しているのに、外部からはそれを見ることができない、つまり、それを「リアリティー」として見ることはできないということだった。シュレーディンガー方程式は、多次元の「配位空間」の中で「波打って」いる何かを描いているのだった。
(p356 『世界でもっも美しい10の物理方程式』 ロバート・P・クリス 吉田三知世・訳 日経BP) 下線は筆者によります
|
そして、シュレーディンガー自身によるシュレーディンガー方程式についての解釈(「波動一元論」&波束…)は、失敗に終わりました。(参考 p.85〜90『光の場、電子の海 量子場理論への道』新潮社)
|
…電子が示す粒子としての振舞いは、あらゆる場所で値を持つ波動関数ψを使って果たして説明できるものなのか。
この問題について、シュレーディンガーは、別個に「プランクスケールの力学からマクロの力学への連続的移行」という論文を書き下ろした。そこでは、1つの振動パターンではなく多数の振動パターンを重ね合わせた「波束」を考えることによって、粒子描像と対応づけられることが示唆されている。
…この波の塊(波束)は、そのままの形を保ちながら、ニュートン力学に従う振動子と同じように振動を続けることになる。これはまさに、波動関数を使って古典的な粒子の姿を再現したものではないか。遂にシュレーディンガーは、波動力学を使って粒子のように振舞う電子を作り出すことに成功した──かのように見えた。
波動力学の崩壊
シュレーディンガーの快進撃は1年にわたって続く。だが、1926年の終わり頃から、次第にほころびが目につくようになる。
特に問題とされたのが、本当に波束が凝集した状態を安定的に維持できるのかという点である。1927年、ハイゼンベルクは、凝集する波としてシュレーディンガーが具体的に示した波動関数は、波束が崩れないきわめて例外的なケースであることを示した。ほとんどの場合も、どこかで波束を凝集させても、次第に崩れていってしまうのである。
凝集させた波が崩れていくことは、波の一般的性質である。…シュレーディンガーの議論には明らかに致命的な欠陥がある。…
さらに数学的な形式の面でもすっきりしないところがある。…
(p.86〜88『光の場、電子の海 量子場理論への道』新潮社 吉田伸夫) 下線は筆者によります。
|
その結果、従来の物理学パラダイムでは、以下に示すように、「波動関数ψは、実在する物理的な何かに対応するのではなく、ψの絶対値の2乗(ψ2)が存在確率を意味する」と解釈するのが主流となっています。
|
時刻tに場所(x, y, z)電子を検出しようとする場合に, 電子を発見する確率は │ψ(x, y, z, t)│2に比例する。
(p.40 裳華房テキストシリーズ-物理学 『現代物理学』 原康夫著 裳華房)
現在では、波動方程式の解となるψそのものが物理的に存在していると考える物理学者はほとんどいない。ψは確かに何かを表しているのだが、それが何なのかを確信することができないのだ。
波動関数ψについての最も実用的な解釈は、1926年にマックス・ボルン(1882〜1970)によって与えられた。それによると、ψの波形を持った何かが実在するのではない。ψはある事象が起きる確率を表すというのである。〜 この解釈は、「電子とは何か」といった根源的な謎を不問に付しているものの、実際に波動関数を使って計算する際には最も便利で破錠のない解釈なので、現在でも通用している。
(p.89『光の場、電子の海 量子場理論への道』新潮社)一部省略しました。太線の下線部は、原文では傍点でした。他の下線は、筆者によります
その二、三ヶ月後、こんどはヴォルフガング・パウリが、波動方程式の解釈を一歩進めた。〜 ボルンはψを状態の確率と解釈したが、ここにきてパウリは、ψは粒子の確率だと主張した。つまり、ψ2は、一個の電子がある位置に存在する確率を表していると言うのだ。パウリのこの立場は、ψ関数からリアリティーを完全に剥ぎ取ったものであり、したがってシュレーディンガーの解釈からは一層遠く離れたものだった。
(『世界でもっとも美しい10の物理方程式』 ロバート・P・クリース 吉田三知世・訳 日系BP) 下線は、筆者によります。
…
|
つまり、従来の物理学パラダイムでは、波動関数ψそのものは、何かの“物理的な実体”に対応していると解釈するのではなく、 「ψの絶対値の2乗(ψ2)」が“存在確率”を表すと解釈するのです。
以上のような状況について、素スピノル物理学パラダイムは、何か貢献できることがあるでしょうか?
あります。それは、次の3点です。
1.『波動関数ψそのそものが、何なのか? 波動関数ψが意味する、幾何学的な実体像(物理的な実体)とは、どのようなものか?』をはっきり示す。
2.『どうして、「波動関数ψの絶対値の2乗(ψ2)」が存在確率を表すと解釈できるのか?』を説明する。
3. シュレーディンガー方程式の価値を取り戻す。
|
1. 波動関数ψそのそものが、何なのか?
波動関数ψが意味する、幾何学的な実体像(物理的な実体)とは、どのようなものか?
素スピノル物理学パラダイムは、次のように説明します。
『電子は、電子ヒッグス場(電子ヒッグス場ユニットの総和)の中を進む際に、消滅と生成を交互に繰り返す。
この「電子の消滅と生成の繰り返し」は、波に相当する。
すなわち、“電子ヒッグス場(=電子ヒッグス場ユニットの総和)”と電子の相互作用が、電子の波としての振る舞いを創発する』(→成果2 14《「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)との相互作用》) |
素スピノル物理学パラダイムは、この「電子ヒッグス場(電子ヒッグス場ユニットの総和)の中で生じる、電子の“消滅と生成の繰り返し”の波」と、波動関数ψが関連していると解釈します。
※この波が創発する過程は、電子が質量を獲得する過程ではないことは、前に述べました。
すなわち、電子の運動エネルギー(質量エネルギー)も、電子ヒッグス場ユニットに蓄える質量エネルギーの和は、常に一定となるのでした。
(→成果2 14《「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)との相互作用》)
電子が消滅と生成を繰り返す様子を示す幾何的モデルを簡単に図示すると次のようになります。
左巻き電子が運動してきて、電子ヒッグス場ユニットに近づく。
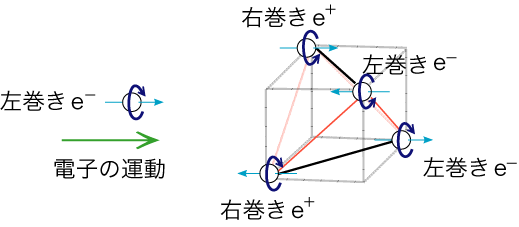
|
→ |
左巻き電子がで電子ヒッグス場ユニット(eHU)の中の
右巻き陽電子と結びつくことによって消滅する。
と同時に、新たな四極子が生成する。
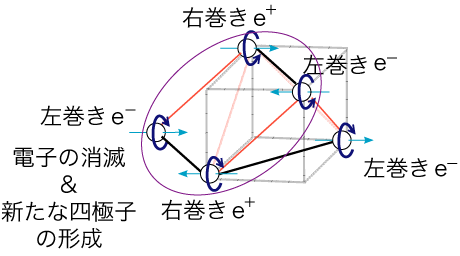
※紫の楕円で囲んだ4つが新たな四極子です
|
|
↑
|
|
↓
|
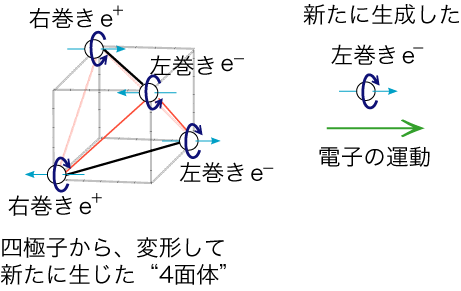
| ※四極子が“4面体”に変形する過程で、新たな電子が生成します。 |
|
※成果2で、『電子ヒッグス場ユニットと電子の相互作用の詳細』を説明する際に示した図を簡略化したものです。
『ある運動エネルギーを持つ電子が、ある電子ヒッグス粒子ユニットの中の陽電子とペアを作り消滅する一方で、新たな電子が生成する。
その新たに生成した電子が別の電子ヒッグス場ユニットの中の陽電子とペアを作り消滅する一方で、再び、新たな電子が生成する。
その新たな電子が同様にして消滅する一方で、また新たな電子が生成する。…』 |
このようにして、電子は、消滅と生成を繰り返しながら、運動を続けることになります。
この電子ヒッグス場の中での「電子の消滅と生成の繰り返し」の全過程は、まさに、“波”と見なすことができるものです。
このような「電子の消滅と生成の繰り返しの波」こそが、(ド・ブロイが考えた)“電子の物質波”(電子の波動性)の幾何的モデルです。
この「電子の消滅と生成の繰り返しの波」の幾何的モデルが「ド・ブロイの物質波」の理論を取り入れて生まれたシュレーディンガー方程式の解である波動関数ψと関連していると、素スピノル物理学パラダイムは解釈するのです。
※上記のような「複数の電子が協力してできる“消滅と生成の波”の創発」は、どの電子も100%同じであることに依存しています。「どの電子も100%同じであること」は、「電子については、各種の原子における“同位体”のような多様性がないこと」を意味しています。(このことは、シンプル一様化原理と合致しています)
このような「“消滅と生成の波”の創発」を支えるしくみ、すなわち、「どの電子も100%同じであること」は、「トンネル効果」や「量子テレポーテーション」の説明にも役立つと考えられます。(詳細な検討は、今後の課題です)
※なお、このように「電子の消滅と生成の繰り返しの波」にともなって電子の存在度が変化したとしても、「1つの電子ヒッグス場ユニット+1つの電子」の質量(重力子の放出源として働き続ける能力)は周期的に変化しません。
すなわち、質量の和、「1つの電子ヒッグス場ユニット+1つの電子」は、ずっと一定となっているのです。
※紫のサインカーブが電子の質量の変動を示し、ピンクのサインカープが電子ヒッグス場ユニットの質量の変動を示しています。両者の和は、一定となっています。
|
※なお、定常状態の場合、1つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)に蓄えられるエネルギーは、もう1つの電子ヒッグス場ユニット(eHU)から開放されたエネルギーに等しく、このしくみにより、軌道運動する1つの電子には、軌道運動の方向に働く力が0[N]になり(=電子は、軌道運動の方向に、加速や減速が生じなくなり)等速で運動し続けられるのでした。
※ここで、黄色、ピンク、グリーン、青のサインカーブは、それぞれの電子ヒッグス場ユニットに蓄えられるポテンシャルエネルギーを意味しています。
|
※なお、シュレーディンガー方程式の解である波動関数ψと(「電子の消滅と生成の繰り返しの波」に相当する)上図の紫のサインカーブ(14《「電子と電子ヒッグス場ユニット(eHU)との相互作用》)は、等しくありません。
すなわち、素スピノル物理学パラダイムによれぱ、「「波打って」いる何か」とは、確かに「(電子等の)「消滅と生成」の繰り返しの波」に他なりませんが、シュレーディンガー方程式の解である波動関数ψは、「(電子等の)「消滅と生成」の繰り返しの波」(上図の紫のサインカーブ)そのものではありまぜん。
波動関数ψとは、生成波と消滅波の和なのです。(→下記2.)
2.どうして、「波動関数ψの絶対値の2乗(ψ2)」が存在確率を表すと解釈できるのか?
以下では、「電子と電子ヒッグス場ユニットの相互作用が生む電子の生成と消滅の繰り返し」にしぼって話を進めます。
この「電子の消滅と生成の繰り返しの波」と、シュレーディンガー方程式の解の典型的な例である波動関数ψ=cosθ+isinθは、相性がよいようです。
なぜなら、次の図のように、「電子の生成と消滅の繰り返しの波」を、複素平面(ガウス平面)での回転として理解できるからです。
※例えば、波動関数ψの中の実数部分(実数軸x=cosθ)が観測できる部分、すなわち、“生成度”を意味し、虚数部分(虚数軸y=sinθ)が観測できない部分、すなわち、“消滅度”を意味すると考えことができます。
この場合、生成度を示す「実数軸のx=cosθ」を生成波と呼び、消滅度を示す「虚数軸のy=sinθ」を消滅波と呼ぶことができます。すると、「波動関数ψ=cosθ+isinθ」は、実質的には、「生成波と消滅波の和である」と解釈できます。
※この場合、波動関数ψの中の実数部分(実数軸x=cosθ)が観測できる部分(=“生成度”)を意味し、虚数部分(虚数軸y=sinθ)は、観測できない部分(=“消滅度”)を意味すると考えていることになり、位相θの変化に伴って、オレンジ色で示した円上を、波動関数ψの複素数に対応する点が移動する様子は、消滅と生成の繰り返しを意味していることになります。
位相がπ/2変化するごとに、消滅→生成→消滅→生成… が繰り返されていることもわかります。
※複素平面(ガウス平面)とは次のようなものでした。
実数x を数直線(x軸)上の点と1対1対応させられるように、複素数z=x+iyをxy平面上の点と1対1対応させられる(図…). この平面を複素平面あるいはガウス平面という. 極座標r、θを導入すると、複素数の実数部xと虚数部yは
x=r cosθ y=i r sinθ (2.25) と表される.
(p.29『岩波基礎物理シリーズ5 量子力学』 原康夫 岩波書店) 下線は筆者によります。
|
|
|
速さ一定の自由電子の“物質波”を例にして、図示すると次のようになります。
※この場合、グリーンのsinθの波が、“消滅度”を意味する消滅波です。また、オレンジのcosθの波が、“生成度”を意味する生成波です。
※電子が電子ヒッグス場ユニット(eHU)から離れているほど(電子ヒッグス場ユニット(eHU)の間隔の中央に近いほど)、オレンジのcosθの波、すなわち、生成波の山や谷が大きいことが読み取れます。
逆に電子が電子ヒッグス場ユニット(eHU)に近づいているほど(電子ヒッグス場ユニット(eHU)の地点に近いほど)、グリーンのsinθの波、すなわち、消滅波の山や谷が大きいことが読み取れます。
すなわち、電子ヒッグス場ユニット(eHU)の間隔の中央が、最も電子の生成度が高いことを、オレンジで示したcosカーブが示していることが読み取れます。一方、電子ヒッグス場ユニット(eHU)の場所そのものが、最も“消滅度”が高いこと、グリーンで示したsinカーブが示していることが読み取れます。
※生成波と消滅波は、互いに位相がπ/2だけずれています。
(だからこそ、位相がπ/2ごとに、生成と消滅を繰り返すことになります)
※生成波は、“プラスの存在度”を意味する存在波と呼べるものです。
消滅波は、“マイナスの存在度”を意味する非存在波と呼べるものです。
※速さが一定だということは、電子の物質波の波長が一定であることを意味しています。
なお、電子ヒッグス場ユニットと電子ヒッグス場ユニットの間の間隔は、電子の物質波の波長の半分(λe/2[m])です。
|
上図は、“自由電子”(ポテンシャルエネルギーV=0)の片道の物質波に相当する波動関数ψ=cosθ+isinθを説明する幾何的モデルに相当しています。
※このような自由な電子の場合は、波動関数の絶対値の2乗を計算すると、ψ*ψ=(cosθ+isinθ)×(cosθ−isinθ)=cos2θ+sin2θ=1 となり、“電子が一様に(濃淡なく)”空間に存在することになります。
例えば、次のような、深い井戸型ポテンシャルのn=3の場合に相当している定常状態(定在波の状態)を考えることができます。
※これは、深い井戸型ポテンシャルのn=3の場合に相当しています。
電子の物質波の“節”にあたる部分が、電子ヒッグス場ユニット(eHU)が存在する部分になっています。
|
この図から、定常状態(定在波の状態)の場合、電子の存在度(存在確率)を考慮する際には、(“節”にピークを迎える消滅波(図のグリーンのサインカーブ(sinθに相当))を無視して)節と節の間の中心にピークを迎える生成波(上図のオレンジのコサインカーブ(cosθに相当))だけを考えればよいことがわかります。
一方、深い井戸型ポテンシャルのn=3の場合は、シュレーディンガー方程式を解くことで、波動関数ψ=cosθと求まります。(このcosθは、まさに電子の生成波の部分に相当していることが図からわかります)
この波動関数ψ=cosθの絶対値の2乗は、ψ*ψ=(cosθ)×(cosθ)=cos2θとなります。
図で考えることと計算結果が調和していることがわかります。
例えば、次のような深い井戸型ポテンシャルのn=2の場合に相当している、定常状態(定在波の状態)を考えることができます。
※これは、深い井戸型ポテンシャルのn=2の場合に相当しています。
電子の物質波の“節”にあたる部分が、電子ヒッグス場ユニット(eHU)が存在する部分になっています。
※この場合、オレンジのサインカーブ(sinθに相当)が生成波、グリーンのコサインカーブ(cosθに相当)が消滅波になっています。
|
この図から、定常状態(定在波の状態)の場合、電子の存在度(存在確率)を考慮する際には、(“節”にピークを迎える消滅波(図のグリーンのサインカーブ(cosθに相当))を無視して)節と節の間の中心にピークを迎える生成波(上図のオレンジのコサインカーブ(sinθに相当))だけを考えればよいことがわかります。
一方、深い井戸型ポテンシャルのn=2の場合は、シュレーディンガー方程式を解くことで、波動関数ψ=i sinθと求まります。(この i sinθは、まさに電子の生成波の部分に相当していることが図からわかります)
この波動関数ψ=i sinθの絶対値の2乗は、ψ*ψ=(−i sinθ)×(i sinθ)=sin2θとなります。
図で考えることと計算結果が調和していることがわかります。
※なお、この場合は、下図のように奇数軸が生成波、実数軸が消滅波を意味しているというように、逆転していることになります。
※「調和振動子、水素原子…」といった定常状態(定在波の状態)についても、基本的に、井戸型ポテンシャルの場合と同様に示すことができると考えられます。すなわち、物質の定在波の“節”に当たる部分(電子が存在しない部分)が、電子ヒッグス場ユニット(eHU)に存在しており、物質波の“波”に当たる部分(電子が存在する部分)が、電子ヒッグス場ユニット(eHU)の間に存在している形になると考えられます。
このことは、定常状態(定在波の状態)においてシュレーディンガー方程式から計算で求まる波動関数ψが“生成波”に相当するように(各種の境界条件によって)決まるがゆえに、「波動関数ψの絶対値の2乗(ψ2)」が“存在確率”に比例する量になることを意味します。
(合計が1になるように、計算によって“規格化”すれば、それは存在確率に相当すると見なせることになります)
素スピノル物理学パラダイムによれば、電子は、“消滅と生成”を繰り返しながら、電子ヒッグス場(=電子ヒッグス場ユニット(eHU)の総和)の中を移動し続けています。
その電子の「“消滅と生成”を繰り返し」、すなわち、「“電子の存在度”が変化する様子」をシュレーディンガーの波動方程式が表記しています。
定常状態(定在波の状態、エネルギー状態(固有状態)が一定)の場合、波動関数ψは、(各種の境界条件によって)生成波の部分のみで構成されるように決まるので、その2乗は、存在度、すなわち、「ある場所に電子が存在する確率」ときってきれないものとなるのです。
以上は、ボルンの確率解釈が、どのようなしくみで成立するかの説明に相当しています。
このことからも、素スピノル物理学パラダイムによる、シュレーディンガーの波動方程式の中の虚数 i が示唆する“観測できない部分を含む波動”、すなわち、波動関数ψの正体についての定義、『定義3-2.1 波動関数ψの実体は、(電子等の)ヒッグス場ユニットとの相互作用で生じる(電子等の)「消滅と生成」の繰り返しの波である。』は、的外れではないことがわかります。
※非定常状態の場合(自由電子…)に、「波動関数の絶対値の2乗」が「ψ*ψ=(cosθ+isinθ)×(cosθ−isinθ)=cos2θ+sin2θ=1」と位相に関わらず一定値となるのは、電子が空間に一様に(メリハリなく均等に)存在することを意味しています。
この理由は、波動関数ψの中に消滅波の成分が残り続けており、単純に「生成波の2乗に相当する“存在確率”(“存在度”)」に比例する量ではなくなるからです。
よって、定常状態(定在波の状態)であることと、波動関数の2乗が「生成波の2乗に相当する“存在確率”(“存在度”)」に比例する量になることには、きってもきれない関係があることになります。すなわち、波動関数ψの2乗が「生成波の2乗に相当する“存在確率”(“存在度”)」に比例する量になるための必要条件の1つが、「定常状態である」ということなのだと考えられます。
※自由電子の場合、存在確率に比例すると考えられるcos2θの変化と“消滅確率(非存在確率)”に比例すると考えられるsin2θの変化の2つを一緒に図示すると次のようになります。
※波動関数の絶対値2乗ψ*ψの中のcos2θ、sin2θの変化のグラフを一緒に合わせて図示しています。
なお、別の座標の取り方をすれば、sinθが生成波、cosθが消滅波となりえます。
※cos2θ、sin2θは、ともに2乗なので、常に正の値になっています。
また、cos2θとsin2θの合計は、常に一定となっています。
※なお、この図は、“ニュートリノ振動”における、例えば、電子ニュートリノの割合と、ミューニュートリノの割合の関係を示す図と相似なものとなっています。
このことは、大きな2つのことを示唆しているのかもしれません。
1つは、『「電子の生成←→電子の消滅」の波は、実は、「電子の生成←→ミューオンの生成」の波と、本質的に、同じものであると見なすことができるものかもしれない』ということです。
なぜなら、電子ヒッグス場ユニットの中の陽電子と電子が、対消滅したあとの“残り”は、ミューオンの組成と同じものに他ならないからです。
もし、電子のエネルギーが十分に大きければ(高エネルギーの電子の場合)、「電子←→ミューオン」のように振動すると予想されます。 しかし、p=h/λ により、電子のエネルギーが大きいほど、電子波の波長は、短くなります。したがって、「電子←→ミューオン」となるような高エネルギーの電子波の波長は、水素原子の最内殻の電子の波長よりも短いものでしょう。この辺りが「電子←→ミューオン」の波の観測を難しくしているのかもしれません。(詳細な検討は、今後の課題です)
(正しければ、“電子の消滅”は、実は、“ミューオンの生成”に他ならなかったということになります)
もう1つは、『ニュートリノの振動の実体は、ニュートリノと、ニュートリノヒッグス場ユニット(νeHU)の相互作用である』ことを示唆している可能性があるということです。確かに、(抽象的な数学を駆使して予想され、実際に観測された)“ニュートリノ振動”の幾何的モデルは、『ニュートリノとニュートリノヒッグス場ユニット(νeHU)の相互作用である』と考えるとつじつまが合います。
なお、「電子ニュートリノ←→ミューニュートリノ」の振動は、「電子←→ミューオン」の振動よりも、低いエネルギーで生じるからこそ、比較的観測しやすいのだと考えられます。 (詳細な検討は、今後の課題です)
|
※定常状態である場合、エネルギー状態(固有状態)が一定である一方、非定常状態である場合、さまさまなエネルギー状態(固有状態)をとります。
それは、非定常状態が、波の重ね合わせで生じる波束(および不確定性原理&コペンハーゲン解釈)と関連していることを意味しています。
非定常状態における確率が波の重ね合わせで生じる波束(および不確定性原理&コペンハーゲン解釈)と関連しているところの『収束の確率』(参考『コペンハーゲン解釈』ウィキペディア)である一方、定常状態での「波動関数ψの絶対値の2乗」で求まる確率は『存在確率』です。
両者は、異なる次元ものです。
|
非定常状態における『収束の確率』
|
定常状態における「波動関数ψの絶対値の2乗」
で示される『存在確率』
|
|
さまざまな固有状態(エネルギー状態)が
重ね合わさったときに、ある固有状態が起こる確率
|
ある一定のエネルギー状態(定常状態)における、
電子の存在確率
|
|
重ね合わせの状態Ψ=c1ψ1+c2ψ2+c3ψ3+…+cnψn
において、固有状態ψnで存在する確率は|cn|2
(参考『量子力学がわかる』伊東正人 技術評論社)
|
シュレーディンガー方程式の解である波動関数ψが
境界条件により、生成波に相当するようになる。
「生成波の絶対値の2乗に相当する“存在確率”」
|
|
波の重ね合わせで生じる波束
(および不確定性原理&コペンハーゲン解釈)と関連
|
ボルンの確率解釈、「生成波(存在度)」と関連
|
詳細は、4《コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&波動関数の収縮)について》のページで説明します。
3. シュレーディンガー方程式の価値を取り戻す。
以上のような説明を可能にするという意味からも、シュレーディンガー方程式は、(ハイゼンベルグの行列力学にはない)非常に高い価値を持っていることがわかります。
確かに、シュレーディンガー方程式と、ハイゼンベルグの行列力学は、数学的には、等価であると言えるのかもしれません。
しかし、そのイメージ喚起性、すなわち、「ダイナミックな生き生きとした電子の振る舞いを示してくれる」ことを含め、物理的には、等価ではないのです。
シュレーディンガー方程式についてのシュレーディンガー自身による解釈は、失敗してしまいましたが、そのことは、“シュレーディンガー方程式”自体の価値を低める理由であってはなりません。
素スピノル物理学パラダイムは、シュレーディンガー方程式が「“電子ヒッグス場(=電子ヒッグス場ユニット(eHU)の総和)”と電子の相互作用」というプランクスケールの自然(nature)の本質を、ダイナミックに生き生きと&厳密に示してくれる式であることを示しています。
素スピノル物理学パラダイムは、このシュレーディンガー方程式が示してくれている豊かなプランクスケールの自然像を幾何的モデルとして提示しているのです。
|