研究論文
『プランクスケールの自然についての幾何的モデルの探究が生む驚異的な成果』
9《電子や光子の二重スリット実験の説明》
次のような「電子や光子の二重スリット実験」は、「量子の奇妙に見える振る舞い」を示すものの典型例でした。
| 『“二重スリットを、電子や光子を1つずつ通過させて、ある1点を発光させる”という過程を繰り返すと── 1つ1つの電子や光子が時間をずらして投入されているのに関わらず、なぜか波の干渉が起きて、スクリーンに縞模様ができる』 |
こういった奇妙さは、これまで、「同時に存在している各状態の重ね合わせ(同時多状態)」によって説明されてきました。
すなわち、こういった奇妙さこそが、「(分割しないはずの)1つの電子が、確率の波として両方のスリットを通過して干渉するのだ(byコペンハーゲン解釈)、多世界解釈…」等々を含む、大胆な解釈が正当化されてきた理由の1つとなってきました。
素スピノル物理学パラダイムは、この奇妙さ(「量子の奇妙に見える振る舞い」)を自然に説明できます。
すなわち、次の仮説を応用して説明できます。(参考 8《非局所性(量子もつれ)と重ね合わせの原理》)
仮説3-8.2 「同時に存在している各状態の重ね合わせ(同時多状態)」によって説明されてきた現象はすべて、「“時間差”を持って存在している各状態(一時一状態)の総和」として創発している。
例えば、「電子の二重スリット実験」によって観察される“電子の奇妙に見える振る舞い”の素スピノル物理学パラダイムによる説明は、次のようになります。
素スピノル物理学パラダイムによれば、電子は、(v1=2πke2/h≒2.2×106[m/s]以下の速度で軌道運動する場合)消滅と生成を繰り返す波を創発しています。(→4《コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&波動関数の収縮)について》)
スクリーンに到着したとき、ちょうど消滅のタイミング(位相)だったら発光しませんし、ちょうど生成しているタイミング(位相)だったら発光します。
1つ1つの電子の物質波の波長λeは(投入される電子の運動エネルギーおよび“運動量の大きさ”が一定である限り)どれもほぼ一定であり、(決定論的カオスに基づく微妙な方向転換はありうるとはいえども)スリット通過後の短い距離では電子の軌道は“おおよそ直線”に近くなるはずなので、「軌道運動する電子」も「相互作用する電子ヒッグス場ユニット」も、おおよそ、同心半円の上に分布すると考えられます。
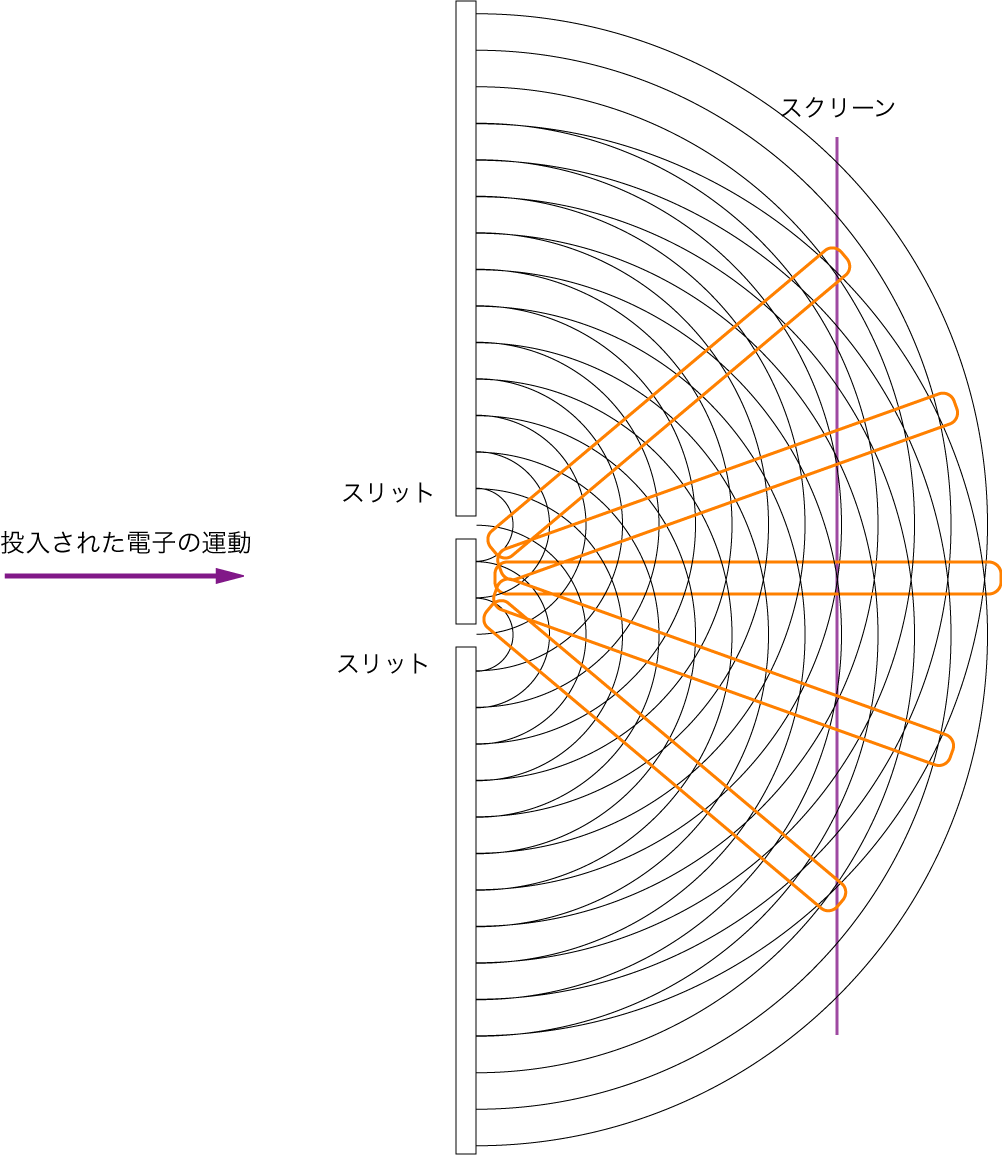
この図においては、半円を描く線上の部分が「(生成度が最大の)電子」が分布するところに相当し、半円と半円の間の中央の部分が「電子と相互作用する電子ヒッグス場ユニット((消滅度が最大の)電子)」が分布するところに相当しています。(その様子を詳しい図で下に示しました)
さて、次の図に戻りますと──
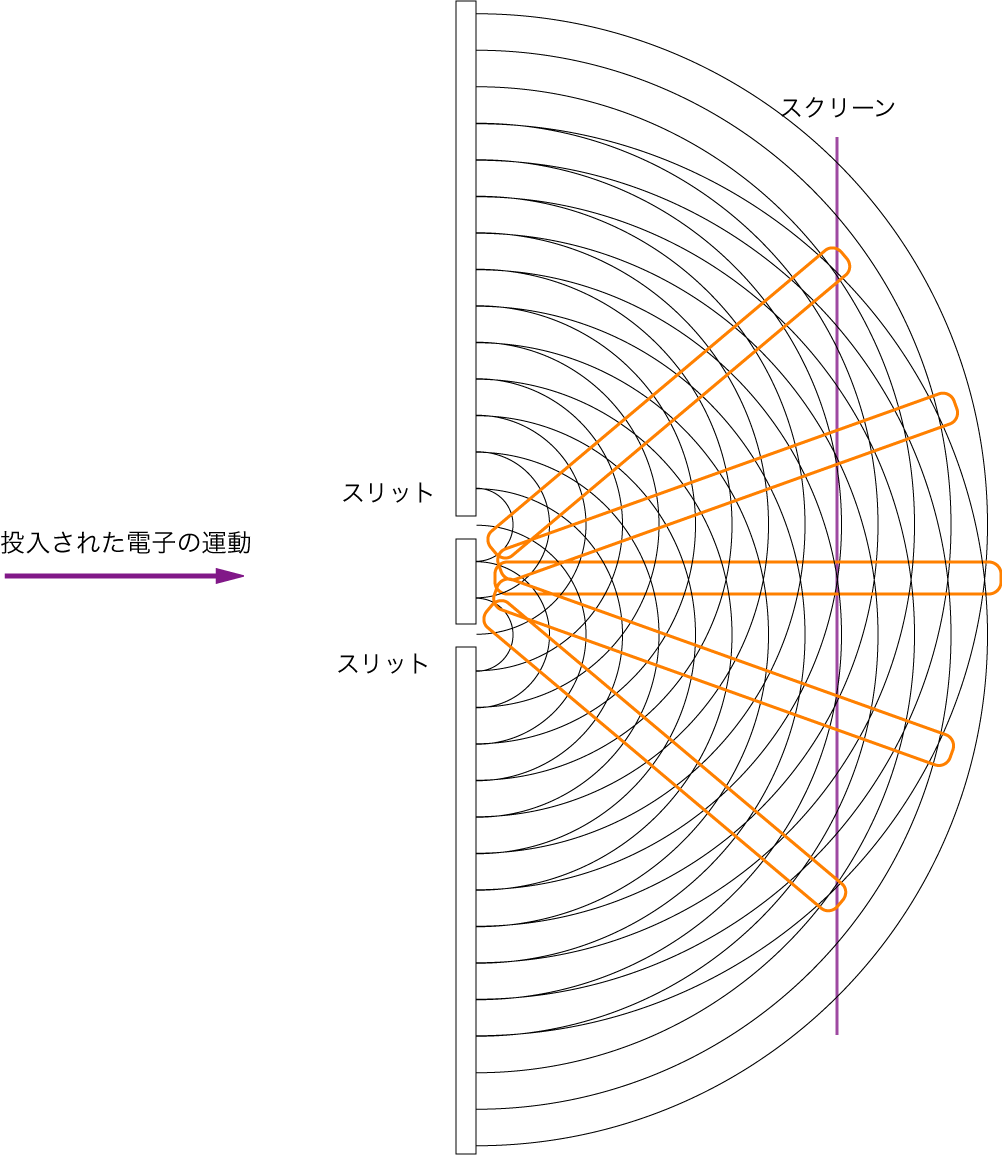
この同心半円が、二つ重なるところ(オレンジで囲ってある所)は、ともに、電子の生成度が最大になっている場所です。
ちょうどスクリーン上で、ちょうどこの同心半円が重なる場所では電子による発光が最も大きくなり、周辺の重ならない場所では、相対的に電子による発光が小さくなります。このことが、結果として、“縞模様”として観測されると考えられます。
『量子力学を見る 電子線ホログラフィーの挑戦』(外村彰 著 岩波科学ライブラリー28)には、
大変不思議な結果が得られました。一個一個の電子を送ったのにもかかわらず、干渉縞が観測されたのです。
(『量子力学を見る 電子線ホログラフィーの挑戦』(外村彰 著 岩波科学ライブラリー28) p.56) 下線は筆者によります。 |
という記述と、その観測結果を示す美しい写真(p.54-55)が載っています。
この写真をよくみると“電子の存在数のピークの間にも、けっこうな数の電子が存在する”のがわかります。このことは、素スピノル物理学パラダイムによる上のような説明と調和していると思います。
素スピノル物理学パラダイムによる説明の最大のメリットの1つは、「たとえ、1つ1つの電子が、時間をずらして投入されても、スクリーンに縞模様ができる」ことを自然に説明できることです。
すなわち、1つ1つの電子は、どちらか一方のスリットを通ってスクリーンに到達しているだけです。ただし、それぞれの電子は、生成と消滅の波を形成しながら、おおよその直線軌道を通り、スクリーンに到達します。それを繰り返すと、スリット上で、生成度の高い電子が多数やって来る場所もできれば、少数しか来ない場所(電子が電子ヒッグス場ユニット(eHU)と相互作用して消滅していることの多い場所)もできます。
つまり、ただ、1回1回の投入を繰り返すだけで、電子の数が相対的に多い場所と、少ない場所の濃淡、すなわち、“縞模様”できるのです。
※したがって、厳密に言えば、ここにあるのは、“干渉縞”ではなく、ただの“縞模様”に過ぎないということになります。
なぜなら、もし“干渉”であるなら“強め合い”のみならず、“打ち消し合い”があるはずですが、素スピノル物理学パラダイムによる説明においては、“打ち消し合い”が存在しないからです。
「縞模様が観測された(スクリーンに、単に縞模様ができた)」と「干渉縞が観測された(波の干渉が起きて、スクリーンに縞模様ができた」の間にある違いは、「観察の理論負荷性」の反映に他なりません。
素スピノル物理学パラダイムの単純な説明には、 「(分割しないはずの)1つの電子が、確率の波として同時に2つのスリットを通過して、干渉するのだ」という、“きわめて奇妙な説明”(“きわめて不自然で無理のある説明”)が不要になるという大きなメリットがあります。
もしかしたら、「たとえ1つ1つの電子が、時間をずらして別々に投入されたとしても、スクリーンに縞模様ができる」という実験結果は、「干渉によって縞模様が生じる」という説明に対する反証であると解釈できるのかもしれません。
そして、「“電子の消滅と生成の波”が実在し、それらの合計が縞模様を生んでいる」という単純な説明を支持するもの(反証しないもの)であると解釈できるのかもしれません。 (やはり、ここにあるのも“観測の理論負荷性”の一種であると思われます)
※なお、スリットを1つにしてみると次のようになるでしょう。
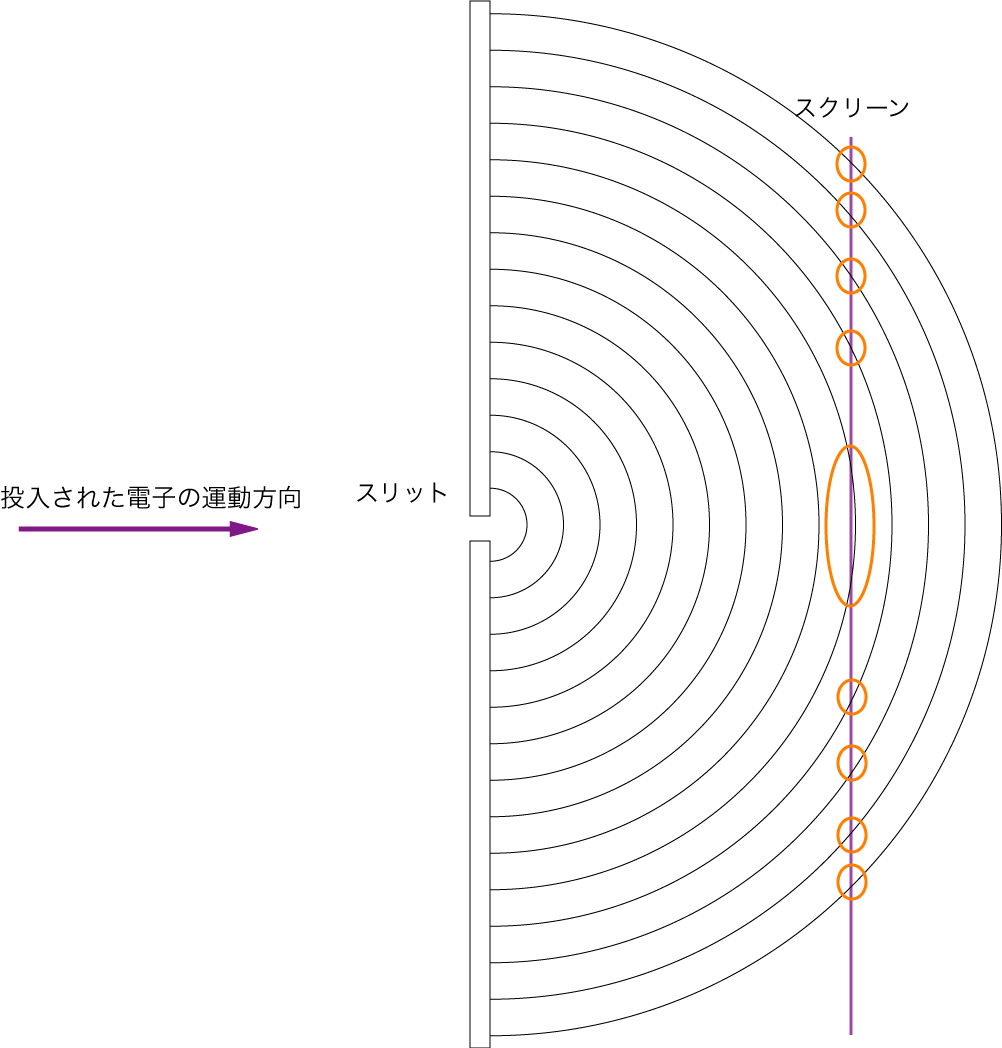
図のオレンジで囲った部分で、(相対的に生成度の高い電子が多くなるので)、電子による発光数が多くなると考えられます。これは、“電子による回折縞”が生じる理由を説明していると思われます。すなわち、『スリットが1つの場合に、電子によって回折縞が現れる』という観測結果についても、素スピノル物理学パラダイムは、説明できることになると思われます。詳細な検討は、今後の課題です。
|
したがって、素スピノル物理学パラダイムにおいては、「1つの電子から生じた“両方のスリットを同時に通る、確率の波”が干渉しあって…」という、無理のある(奇妙な、不思議な…)説明が不要となるのです。
1つ1つの(実在する)電子は、やはり、それぞれ、たった1つの軌道を、因果律に従って、進んでいるだけです。
これらの電子の到着ポイントを、複数(ある時間差の中で)足し合わせてみると、電子が多く到達する部分、少ししか到達しない部分の濃淡、すなわち、縞模様が現れてきます。この“縞模様”は、因果律に従う“実在する電子”の軌道運動を集計した結果、すなわち、“統計的な分布”に過ぎません。
この“電子の生成度”を集計したものは、「電子の“存在度”の分布」、あるいは、「電子の存在確率」であると見なしても、つじつまが合うでしょう。 (すなわち、観測結果は、コペンハーゲン解釈で求めた計算結果とおおよそ一致するでしょう)
この素スピノル物理学パラダイムによる説明は、(奇妙な)「両方のスリットを同時に通るような、確率の波の干渉」が不要になるというメリットがある点で、コペンハーゲン解釈による説明とは大きく異なります。
素スピノル物理学パラダイムは、次の結論に至ります。
結論3-9.1 「1つの電子が、両方のスリットを同時に通る」ことによって生じる“波の干渉”は、実在しない。
電子の場合と同様にして、光子の場合の“2重スリットの実験”を説明できます。
すなわち、「“光子を1つずつ、二重スリットを通過させて、ある1点を発光させる”という過程を繰り返すと、1つ1つの光子は、時間をずらして投入されているのに関わらず、スクリーンに縞模様ができる」ということも同様に説明できます。
そして、光子の場合においても、電子の場合と同様に、“1つの光子が、同時に両方のスリットを通過する結果生じる、波の干渉”によって「スクリーン上に縞模様ができる」という奇妙な説明は、不要となることがわかります。
その説明は、次のようになります。
したがって、素スピノル物理学パラダイムにおいては、光子についても、「1つの光子から生まれ“両方のスリットを同時に通る、確率の波”が干渉しあって…」という、無理のある(奇妙な、不思議な…)説明が不要となるのです。
1つ1つの(実在する)光子は、やはり、それぞれ、たった1つの進路を、因果律に従って、進んでいるだけです。
これらの量子の到着ポイントを、複数(ある時間差の中で)足し合わせてみると、多く存在する部分、少ししか存在しない部分の濃淡、すなわち、縞模様が現れてきます。この“縞模様”は、因果律に従う“実在する光子”の到達を集計した結果、すなわち、“統計的な分布”に過ぎません。
そして、この“光子の到達”を集計したものは、「光子の“存在度”の分布」、あるいは、「光子の存在確率」と解釈しても、つじつまが合うでしょう。(すなわち、観測結果は、コペンハーゲン解釈で求めた計算結果とおおよそ一致するでしょう)
この素スピノル物理学による説明には、(奇妙な)「両方のスリットを同時に通るような、確率の波の干渉」が不要になるというメリットがある点で、コペンハーゲン解釈による説明とは大きく異なります。
素スピノル物理学パラダイムは、次の結論に至ります。
結論3-9.2 「1つの光子が、両方のスリットを同時に通る」ことによって生じる波の干渉は、実在しない。
素スピノル物理学パラダイムは、「二重スリットの実験結果」について、『 1つ1つの(実在する)電子や光子は、因果律に従うたった1つの軌道・ルートを進んでいるだけであり、それらの量子の振る舞いの総和によって、スクリーンに縞模様が創発するのである』というように説明します。
このように素スピノル物理学パラダイムは、「電子や光子を1つずつ投入したとしても、スクリーンに縞模様ができる」ということを、無理せず、自然に説明できるのです。
素スピノル物理学パラダイムの説明は、「たとえ、1つ1つの光子や電子が、時間をずらして投入されても、スクリーンに縞模様ができる」ことが観測された時点で、『この縞模様は、「ふつうの波の干渉」とは、全く異なったしくみで生じている。この縞模様は、そもそも干渉縞ではないのかもしれない』と考えるべきであったことを示しています。
すなわち、素スピノル物理学パラダイムは、「たとえ1つ1つの電子や光子が、時間をずらして別々に投入されたとしても、スクリーンに縞模様ができる」という実験結果は、そもそも「干渉によって縞模様が生じる」という説明に対する反証かもしれないと解釈すべきであったことを示しています。
素スピノル物理学パラダイムによって二重スリットで生じる縞模様を、無理せず単純に説明できるのは、“量子波”の実体を 「滑らかに進む連続な古典的な波」と考えず、「デジタルな量子的な(とびとびの)波」と考えたおかげです。(逆に“古典的な連続な波”のイメージにとらわれたからこそ、「同時に両方のスリットを通っているのだ」という、強引できわめて奇妙な説明が生まれたとも考えられます)
このことは、プランクスケールの自然(nature)における波、すなわち、量子波は、「滑らかに進む連続な古典的な波」ではなく、「デジタルな(とびとびの)波」であると説明することは、決して突拍子もないことではなく、むしろもっともな発想であることを示していると思われます。
つまり、電子&光子の「二重スリットの実験」の観測結果は、こういった素スピノル物理学パラダイムによる説明を支持するもの(反証しないもの)であると解釈しなおすことが可能なのです。 (やはり、「観察の理論負荷性」の一例です)
※なお、コペンハーゲン解釈(重ね合わせの原理&確率解釈)にもとづく計算は、今後とも、実用上(観測値の確率的な予想&説明のために)役立ち続けるでしょう。なぜなら、「観測上の限界(人間の観測事情)」、および、「決定論的カオス」が存在するからです。
※素スピノル物理学パラダイムによれば、少なくとも「二重スリットの実験」を説明するために「1つの量子が、不思議なしくみで同時に両方のスリットを通っているのだ」という奇妙な説明が不要になる以上、無理のある“多世界解釈”も不要となるようです。詳細な検討は、今後の課題です。
※ところで、つぎのような記述があります。
|
量子力学は, 粒子と波動の両方の性質をもつ電子のしたがう力学である. 原子核, 陽子, 中性子なども量子力学にしたがう。
(p.40 裳華房テキストシリーズ-物理学 『現代物理学』 原康夫著 裳華房)
|
『原子核, 陽子, 中性子なども量子力学にしたがう』ことは、「中性子ヒッグス場ユニット」や「陽子ヒッグス場ユニット」が、存在することを示唆しているでしょうか? それとも、アップクォークヒッグス場ユニット(uHU)、ダウンクォークヒッグス場ユニット(dHU)だけで、 “原子核, 陽子, 中性子”の波動性が生じているのでしょうか?
ここで、『C60の分子さえも縞模様を作る』(参考 『量子コンピュータ』 竹内繁樹 講談社ブルーバックス)ことを思い出してみます。
この『C60の分子さえも縞模様を作る』事実は、(さすがに、「C60ヒッグス場ユニット」は実在しないはずですので)「中性子ヒッグス場ユニット」や「陽子ヒッグス場ユニット」は実在せず(不要であり)、アップクォークヒッグス場ユニット(uHU)、ダウンクォークヒッグス場ユニット(dHU)だけで、“原子核, 陽子, 中性子(およびC60の分子)”の波動性が生じうることを示しているように思われます。詳細な検討は、今後の課題です。
※「“連続な波の干渉”によるのではなく、あくまで、個々の光子や電子の“デジタルな(とびとびの)量子波の集計”によって、縞模様が生じていること」を、はっきりと検証するために、例えば、電子や光子を1つ1つ投入する二重スリットの実験で、スリットを通らないで(orスリットを通ったあとに) 壁を跳ね返ってくる電子や光子をもしっかりカウントするような「実験&観測」のデザインも役立つのかもしれません。詳細な検討は、今後の課題です。
|